要約 目的:春季カタル重症例に対するトリアムシノロンアセトニド(TA)の眼瞼への皮下注射の効果の報告。対象と方法:本研究は62か月の間2施設で行われた。春季カタル重症例20例28眼にTAの皮下注射を1回だけ行った。年齢は7~34歳(平均15歳)である。対象として春季カタル重症例8例8眼にプレドニゾロンを経口的に継続投与した。年齢は8~28歳(平均15歳)である。症例はすべて男性であった。臨床診断基準による臨床スコアで効果を判定した。結果:両群とも投与から2週後に病状が改善した。皮下注射群では投与開始から24週後の時点で,内服群に比べ有意な再発抑制効果があった(p<0.01)。眼圧上昇は皆無であった。結論:TAの眼瞼への皮下注射は,速やかな消炎効果と再発抑制効果があり,春季カタル重症例での症状を改善させる。
雑誌目次
臨床眼科61巻5号
2007年05月発行
雑誌目次
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
原著
眼脂培養による細菌検査とレボフロキサシン耐性菌の検討
著者: 村田和彦
ページ範囲:P.745 - P.749
要約 目的:眼脂から培養された細菌と,レボフロキサシンに対する耐性菌の報告。対象と方法:過去21か月間に病院と老人施設の入居者151眼と外来患者136眼から採取した眼脂を培養し,レボフロキサシンに対する耐性菌を検索した。結果:病院と老人施設の入居者から147株,外来患者から126株が分離された。147株中82株(56%)と126株中36株(29%)がレボフロキサシン耐性であった。147株中30株(20%)と136株中7株(6%)がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)であった.Coagulase陰性ブドウ球菌のレボフロキサシン耐性率は,外来患者よりも病院と老人施設の入居者で高かった。結論:点眼液として使われる抗生物質での第1選択であるレボフロキサシンに対する耐性化は,外来患者よりも病院と老人施設の入居者で高い。
若年で発症し5年の間隔をあけ僚眼に発症したと考えられた単純ヘルペスウイルスによる急性網膜壊死
著者: 柞山健一 , 渋谷悦子 , 椎野めぐみ , 竹内聡 , 三上武則 , 遠藤要子 , 伊藤典彦 , 石原麻美 , 中村聡 , 林清文 , 水木信久 , 矢吹和郎 , 佐藤真美 , 野村英一 , 栗田正幸
ページ範囲:P.751 - P.755
要約 目的:単純ヘルペスウイルスによる急性網膜壊死が5年前に僚眼にも発症していたと推定される若年例の報告。症例:19歳女性が左眼の充血と眼痛で受診した。5年前に網膜剝離があり,硝子体手術を受けていた。矯正視力は右50cm手動弁,左(1.2)であった。右眼にはシリコーンオイルが充填され,虹彩後癒着が全周にあった。左眼には虹彩炎,硝子体混濁,眼底下方に黄白色滲出斑があった。経過:前房水のPCR検査で単純ヘルペスウイルスが検出され,これによる急性網膜壊死と診断した。即日入院のうえ,アシクロビル点滴と副腎皮質ステロイドの全身投与を行った。左眼視力は(0.1)に低下したが,3週後に(0.9),1年後の現在(1.2)に回復し,再発はない。結論:急性網膜壊死が疑われる症例では,房水のPCR検査などによる早期の診断と治療が望まれる。
経毛様体扁平部水晶体切除を併用し硝子体手術を施行した若年者増殖糖尿病網膜症の手術成績
著者: 外尾恒一 , 近藤寛之 , 尾崎弘明 , 林英之 , 内尾英一 , 大里正彦 , 大島健司
ページ範囲:P.757 - P.760
要約 目的:若年者の増殖糖尿病網膜症に対する経毛様体扁平部水晶体切除を併用した硝子体手術の結果の報告。対象と方法:過去6年間に増殖糖尿病網膜症に対して経毛様体扁平部水晶体切除併用の硝子体手術を行った24例38眼を対象とした。年齢は18~38歳(平均31歳)であり,術後6か月以上の経過が観察できた症例に限った。黄斑浮腫のみ,または血管新生緑内障がある症例は除外した。手術の成績は術後の最終視力で評価した。結果:最終視力は,0.1以上が28眼(74%),0.5以上が21眼(55%)であった。最終視力が0.1未満の10眼では,30歳未満,網膜剝離,網膜下増殖の3項目が有意な術前因子であった(p<0.05)。結論:経毛様体扁平部水晶体切除を併用した硝子体手術は,若年者の増殖糖尿病網膜症に対する選択肢の1つである。
井上眼科病院におけるフルオレセイン蛍光眼底造影での副作用
著者: 河田直樹 , 山川曜 , 冨樫真紀子 , 宮石美幸 , 井上賢治 , 岡山良子 , 若倉雅登 , 井上治郎
ページ範囲:P.761 - P.765
要約 目的:井上眼科病院でフルオレセイン蛍光眼底造影で副作用が生じた症例と,蛍光眼底造影を控えた症例の報告。対象:過去2年間に蛍光眼底造影を予定した3,562例を対象とした。結果:3,497例に蛍光眼底造影が実際に行われた。造影剤によると思われる副作用が53件(1.53%)で起こった。これら症例には,性別と年齢については特異性がなく,6月と9月に副作用が多く発生した。蛍光眼底造影を控えた65例(1.82%)については,その理由として,心臓,腎臓または肝臓の障害と高血圧が多かった。結論:フルオレセイン蛍光眼底造影を行うときには,患者に十分な説明を行い,検者は季節変動にも配慮して副作用に留意する必要がある。
長期間経過後に両眼にみられた網膜色素上皮裂孔を伴う胞状網膜剝離の1例
著者: 加藤健 , 青木真祐 , 橋本加奈 , 牧野伸二 , 茨木信博
ページ範囲:P.769 - P.772
要約 目的:網膜色素上皮裂孔を伴う胞状網膜剝離が14年後に他眼にも発症した症例の報告。症例:46歳男性が左眼視力低下で受診した。矯正視力は右1.2,左0.3で,左眼眼底に網膜色素上皮裂孔を伴う胞状網膜剝離があった。フルオレセイン蛍光眼底造影で色素上皮裂孔に一致して過蛍光があり,光凝固を行ったが剝離は改善せず,通院を中断した。61歳になった14年後に右眼にほとんど同様の病変が生じた。矯正視力は右0.4,左0であった。副腎皮質ステロイドの内服と光凝固を行い,眼底病変は鎮静化したが,夕焼け状眼底になった。結論:網膜色素上皮裂孔を伴う胞状網膜剝離が長期の間隔をおいて両眼に発症した症例は少なく,稀有な1例である。
網膜血管病変に合併した加齢黄斑変性の臨床像
著者: 荻野哲男 , 竹田宗泰 , 今泉寛子 , 奥芝詩子
ページ範囲:P.773 - P.778
要約 目的:網膜血管病変に併発した滲出型加齢黄斑変性の頻度と臨床像の報告。対象と方法:2005年までの3年間の診療録を検索し,この期間に経験した網膜血管病変と滲出型加齢黄斑変性が併発した71例76眼を検討した。年齢が50歳以下,強度近視,脈絡膜炎などは除外した。結果:76眼の内訳は,糖尿病網膜症59眼,網膜静脈分枝閉塞症15眼,その他2眼であった。年齢は58~92歳(平均72歳)であり,男性50眼,女性26眼であった。50眼(62%)が狭義の加齢黄斑変性,24眼(32%)がポリープ状脈絡膜血管症,2眼(3%)が網膜内血管腫様増殖であり,これらの頻度は,同期間に経験した網膜血管病変を伴わない加齢黄斑変性969眼のそれと有意差がなかった。結論:糖尿病網膜症や網膜静脈分枝閉塞症などの網膜血管病変には高頻度で滲出型加齢黄斑変性が併発し,その臨床像は血管病変に併発しないそれと同様である。
視力良好な滲出型加齢黄斑変性に対するトリアムシノロンアセトニド後部テノン囊下注入
著者: 高橋牧 , 佐藤拓 , 堀内康史 , 渡辺五郎 , 森本雅裕 , 松本英孝 , 野田聡実 , 徳倉美智子 , 岸章治
ページ範囲:P.779 - P.784
要約 目的:視力がよい加齢黄斑変性にトリアムシノロンアセトニド(TA)をテノン囊下に注入した結果の報告。対象と方法:矯正視力が0.6以上の滲出型加齢黄斑変性31眼を対象とした。TA20または40mgをテノン囊下に注入し,6か月以上の経過を観察した。TA投与後の視力が0.5以下になるか,光線力学的療法(PDT)を必要とした症例をKaplan-Meier法での死亡と定義した。結果:TA投与の1年後で15眼(48%)が生存と判定された。漿液性網膜剝離は17眼(55%)で消失した。10眼にPDTが行われたが,それまでの期間は平均6.4か月であった。視力の急性低下は皆無であった。結論:視力が良好な加齢黄斑変性に対し,TA投与は初回治療として価値がある方法である。
早期硝子体手術が奏効した肝膿瘍原発の転移性細菌性眼内炎の1例
著者: 三村真士 , 前野貴俊 , 吉岡由利子 , 佐藤孝樹 , 石崎英介 , 小嶌祥太 , 南政宏 , 池田恒彦
ページ範囲:P.785 - P.790
要約 目的:早期の硝子体手術が奏効した肝膿瘍原発の転移性細菌性眼内炎の1例の報告。症例:65歳女性に発熱と意識障害などが突発し,肝膿瘍と診断された。抗菌薬による治療開始から4日後に右眼に眼痛と視力低下が生じた。矯正視力は右指数弁,左0.5で,右眼に前房蓄膿,硝子体混濁,網膜出血があり,内因性眼内炎と診断した。経過:即日眼科に入院のうえ,水晶体と硝子体を全切除した。耳側赤道部より周辺には網膜壊死があった。術中に採取した硝子体液から
抗加齢QOL共通問診票を用いたLASIK手術前後における生活の質の検討
著者: 山田瑞環子 , 谷原理香 , 染谷元子 , 塚脇智映 , 高橋洋子 , 米井嘉一 , 高橋現一郎
ページ範囲:P.791 - P.795
要約 目的:LASIK術前後の生活の質の変化の報告。対象と方法:近視または近視性乱視に対してLASIKを行った196名を対象とした。男性80例,女性116例で,年齢は18~62歳(平均35歳)であった。抗加齢QOL共通問診票を使い,術前後の身体の症状と心の症状の変化を5段階評価で比較した。結果:全体のスコアの平均は,術前2.0,術後1.7であり,有意に改善していた(p<0.05)。項目別では,「目がかすむ」以外の全項目(筋肉痛・こり,肩がこる,目がつかれる,めまい,息切れ,自信を失った,怒りっぽい,緊張感)で改善があった。結論:LASIK後では,眼科的症候以外でも生活の質が改善する。
ステロイドパルス療法でも再発を繰り返した原田病の1例
著者: 正木究岳 , 高島保之 , 奥平晃久
ページ範囲:P.797 - P.800
要約 目的:副腎皮質ステロイドのパルス療法で治療し,再発を繰り返した原田病症例の報告。症例と経過:24歳男性が2日前からの両眼の変視症で受診した。矯正視力は右0.8,左1.2で,両眼の後極部に漿液性網膜剝離があり,蛍光眼底造影所見と合わせ原田病と診断した。1日200mgのプレドニゾロンを投与したが,3日後に投与量を漸減すると直ちに漿液性網膜剝離が再発した。1日1gのメチルプレドニゾロンによるパルス療法に切り替えたが,維持量にすると再発し,これを3回繰り返した。1日200mgのシクロスポリンによる併用を開始し,3日後に網膜剝離は消失した。発症から1年後の現在まで再発はない。結論:副腎皮質ステロイドのパルス療法で再発を繰り返す原田病には,ステロイドとシクロスポリンの併用投与が奏効することがある。
未熟児網膜症の統計学的検討
著者: 山田義久 , 宮村紀毅 , 隈上武志 , 三島一晃 , 北岡隆 , 黒木明子 , 林田裕彦 , 森内浩幸 , 田川正人 , 青木幹弘 , 角至一郎 , 木下史子 , 光武伸祐
ページ範囲:P.801 - P.805
要約 目的:長崎県下での未熟児網膜症の現状の報告。対象と方法:2004年までの3年間に,長崎県の4施設の眼科に紹介された出生体重1,500g以下の未熟児236例471眼を対象とした。網膜症の重症化因子を統計学的に検討した。結果:未熟児網膜症は141例289眼(61%)に発症し,77眼に治療が行われた。重症例は,在胎期間が25~28週,出生体重が750~1,000g未満に多かった。重症化因子として,出生体重,在胎週数,輸血歴に有意差があった。結論:輸血により未熟児網膜症が悪化する可能性がある。
放射線治療が著効した転移性虹彩腫瘍の1例
著者: 富長岳史 , 堅野比呂子 , 佐々木勇二 , 井上幸次 , 河合公子
ページ範囲:P.807 - P.810
要約 目的:放射線治療が著効した転移性虹彩腫瘍の報告。症例と経過:肺腺癌に対し,2年前から化学療法を断続的に受けていた68歳男性が右眼の充血と視力低下で受診した。矯正視力は右0.3,左1.2,眼圧は右50mmHg,左15mmHgであった。右眼に虹彩毛様炎と虹彩の下鼻側に白色隆起性病変があり,転移性虹彩腫瘍と診断した。眼圧下降治療には反応しなかった。疼痛の訴えが強かったが,眼球温存を考慮し,眼球摘出ではなく放射線治療を選択した。6MeVのX線による三門照射で1日量3Gyを連日行い,総量42Gyとした。照射開始後,虹彩の腫瘍は次第に小さくなり,4か月後には完全に消失した。眼圧は下降し,疼痛はなくなった。結論:転移性虹彩腫瘍に対し,放射線治療は有用な選択肢の1つである。
糖尿病黄斑浮腫に対するトリアムシノロンアセトニド後部テノン囊下注入の効果と合併症
著者: 孫鳳銘 , 上本理世 , 水木信久
ページ範囲:P.811 - P.813
要約 目的:糖尿病黄斑浮腫に対してトリアムシノロンアセトニドを後部テノン囊下に注入した結果の報告。対象と方法:糖尿病黄斑浮腫がある6例9眼にトリアムシノロンアセトニド20mgを後部テノン囊下に1回注入し,5~11か月(平均8か月)の経過を追った。男性3眼,女性6眼で,年齢は平均65歳であった。視力はIogMARで評価し,0.2以上変化したものを改善または悪化とした。結果:視力は4眼が改善,5眼が不変であり,悪化はなかった。視力が改善した4眼中1眼では,注入後284日で元の視力に戻った。合併症として高眼圧が1眼,眼瞼下垂が2眼にあった。感染または血糖値上昇はなかった。結論:トリアムシノロンアセトニドの後部テノン囊下注入は,糖尿病黄斑浮腫で視力を改善させる。高眼圧と眼瞼下垂などの合併症については,事前に説明することが望ましい。
糖尿病黄斑浮腫に対するトリアムシノロン後部テノン囊下注入後黄斑部光凝固の長期経過
著者: 木村忠貴 , 林寿子 , 田村和寛 , 梅基光良 , 植田良樹
ページ範囲:P.815 - P.818
要約 目的:糖尿病黄斑浮腫に対するテノン囊下ステロイド投与と光凝固による併用治療の長期経過の報告。対象と方法:糖尿病黄斑浮腫17例19眼を対象とした。男性4眼,女性15眼であり,年齢は53~74歳(平均64歳)であった。全例を6か月以上,13眼は13か月まで経過を観察した。トリアムシノロンアセトニド(TCA)20mgをテノン囊下に注入し,その2または4週後に赤色レーザーによる光凝固を疎な格子状に置いた。HbA1C値が7.0mg/dl以下の8眼を血糖コントロール良好,これを超える11眼を不良と定義した。視力と光干渉断層計(OCT)所見から算出した黄斑部網膜体積を指標として効果を判定した。結果:血糖コントロール良好群では治療後の黄斑浮腫が有意に改善持続し,視力にも改善傾向があった。不良群では黄斑浮腫の改善は一過性で,1~3か月間のみであった。結論:糖尿病黄斑浮腫に対するTCAのテノン囊下投与と光凝固による効果は,血糖コントロールが良好な症例で長期間持続した。
原因不明の弱視として長期間観察された黄斑低形成症の1例
著者: 山村陽 , 中島伸子 , 深尾隆三 , 稗田牧
ページ範囲:P.819 - P.822
要約 目的:当初は弱視とされていた黄斑低形成症の1症例の報告。症例:5歳男児が右眼視力低下で受診した。矯正視力は右0.5,左1.0であった。間欠性外斜視があり,両眼視機能では同時視のみがあった。経過:弱視と診断し,左眼遮閉を行った。右眼視力は2か月後に0.9,2年後に0.9,6年後に0.4になった。眼底の精査で,両眼に中心窩反射と輪状反射がなく,蛍光眼底造影で中心窩の無血管領域がなく,光干渉断層計(OCT)による検査で生理的陥凹がない平坦な黄斑であった。これらの所見から両眼の黄斑低形成症と診断した。結論:弱視が疑われる小児では,黄斑低形成症などの器質的疾患である可能性があるので,眼底を精査することが必要である。
新生児集中治療室を明室から暗室に転換した前後の未熟児網膜症の動向
著者: 伊藤彰 , 西山香織
ページ範囲:P.823 - P.826
要約 目的:新生児集中治療室を明室から半暗室に変えた前後での未熟児網膜症の頻度の変化の報告。対象と方法:新生児集中治療室で管理した出生時の体重が1,500g以下の極小低出生体重児130例を検索の対象とした。65例は集中治療室が明室であり,65例はこれを半暗室とした時期に入室した。結果:無呼吸発作の発現率は,明室群では52%,暗室群では32%であり,有意差があった(p<0.05)。人工換気を必要とした期間の平均はそれぞれ14日と11日であり,有意差がなかった。酸素投与を必要とした期間はそれぞれ32日と31日であり,有意差がなかった。未熟児網膜症の発現率は,明室群では70%,暗室群では50%であり,有意差があった。光凝固などの治療はそれぞれ23%と12%で行われ,有意差がなかった。結論:新生児集中治療室を明室から半暗室に変えた後には,無呼吸発作と未熟児網膜症の発現率が低下した。
アカントアメーバ角膜炎3例の治療経験
著者: 森紀和子 , 太田浩一 , 杉本知子 , 永野咲子 , 渋木宏人 , 村田敏規
ページ範囲:P.827 - P.832
要約 目的:ソフトコンタクトレンズ(SCL)装用中に発症したアカントアメーバ角膜炎3症例の報告。症例と経過:3症例とも女性で,年齢は32,33,44歳であった。それぞれ毎日装用使い捨てSCL,連続装用使い捨てSCL,連続装用非含水性SCLを使用していた。連続装用をしていた2例は,SCLを水道水で洗浄していた。いずれも片眼に発症し,2例では放射状角膜神経炎,1例には偽樹枝状病変があった。2例では角膜擦過標本にアカントアメーバが検出された。全例に抗真菌薬の局所投与と角膜搔爬を行い,2例にはクロルヘキシジンを点眼した。抗真菌薬と角膜搔爬が奏効しない1例にはpolyhexamethylene biguanide(PHMB)点眼を追加し,急速な消炎を得た。結論:SCL長期装用に伴うアカントアメーバ角膜炎では早期診断と早期治療が望ましい。抗真菌薬と角膜搔爬が無効な難治例にはPHMB点眼が奏効することがある。
正常眼圧緑内障におけるレボブノロール点眼の長期効果
著者: 比嘉利沙子 , 井上賢治 , 若倉雅登 , 井上治郎 , 富田剛司
ページ範囲:P.835 - P.839
要約 目的:正常眼圧緑内障に対するレボブノロール点眼の眼圧と視野に及ぼす影響の報告。症例と方法:レボブノロール点眼を単剤として2年以上使用している正常眼圧緑内障29例29眼を対象とした。男性17例,女性12例であり,年齢は25~79歳(平均50歳)であった。眼圧は3か月毎,ハンフリー視野計による視野は12か月毎に評価した。結果:点眼開始前の眼圧は16.5±2.1mmHgであり,点眼開始1年後,2年後,3年後の値はいずれも有意に低かった(p<0.05)。点眼前後の視野は,mean deviation(MD)とpattern standard deviation(PSD)のいずれについても変化がなかった。結論:正常眼圧緑内障に対するレボブノロールの2年以上の長期点眼で,眼圧は有意に下降し,視野は変化しない。
硝子体ポケット後壁が検眼鏡的に観察できた囊胞様黄斑浮腫の1例
著者: 白戸勝 , 武田憲夫 , 八代成子 , 植村明弘 , 西桂 , 水野嘉信
ページ範囲:P.841 - P.844
要約 目的:後部硝子体ポケットの後壁が検眼鏡で観察できた囊胞様黄斑浮腫症例の報告。症例:55歳男性に6年前から右眼の霧視があった。矯正視力は右0.07,左1.2であり,右眼の乳頭から黄斑部にかけて楕円形の膜があり,蛍光眼底造影と光干渉断層計で囊胞様黄斑浮腫(CME)があった。経過:黄斑浮腫に対し硝子体手術を実施した。楕円形の膜が後部硝子体ポケットの後壁であることが術中所見として確認できた。囊胞様黄斑浮腫は改善したが,術後5か月後の右眼視力は0.09であった。結論:囊胞様黄斑浮腫の発症に後部硝子体ポケットが関与した可能性がある。
ステロイドの大量療法が無効であった全身性エリテマトーデスに伴う漿液性網膜剝離の1例
著者: 山田浩喜 , 酒井淳 , 三島一晃 , 岩永希 , 本多絵美 , 北岡隆
ページ範囲:P.847 - P.851
要約 目的:漿液性網膜剝離に対して副腎皮質ステロイドの大量投与が無効であった全身性エリテマトーデス(SLE)症例の報告。症例:51歳女性が左眼の比較中心暗点で受診した。8年前に関節痛と発熱を契機としてSLEと診断され加療中であった。所見と経過:矯正視力は右1.5,左0.5であった。漿液性網膜剝離が右眼の鼻側と左眼の黄斑部にあり,網膜血管炎が併発していた。SLEに続発した網膜症として,それまで内服中であったプレドニゾロンを増量した。2週後に網膜剝離は軽快したが,その3週後に再発したので,ステロイド大量療法を行ったが無効であり,胞状網膜剝離になった。網膜光凝固で軽快し,初診から10か月後の現在まで再発はない。結論:SLE患者に生じた漿液性網膜剝離では,ステロイドの大量全身投与は慎重に行うべきであり,早期の網膜光凝固が奏効することがある。
日本人の角膜鉄線発生率
著者: 松原稔
ページ範囲:P.853 - P.858
要約 目的:Hudson-Staehli's lineで代表される角膜鉄線の日本人での頻度の報告。対象と方法:外来の初診患者3,008名を検索した。内訳は男性1,395名,女性1,613名である。細隙灯顕微鏡(ZEISS SL130)付属のCCDカメラで角膜を動画として撮影した。結果:典型的なHudson-Staehli's lineは男性36名と女性26名,角膜片雲の影響を受けたその亜型は男性49名と女性11名,Stocker's lineは男性4名と女性2名,Fleischer's ringは男性3名の総計131名(4.4%)にあった。発生率は加齢とともに増加した。結論:日本人の角膜鉄線の頻度は4.4%であった。従来の海外の報告と比較し,頻度がずっと低いこと,年齢とともに増加すること,男女差があることで大きく異なる。
結膜炎と結膜潰瘍を認めたBehçet病疑いの1例
著者: 牧野昌子 , 安東えい子 , 後藤正隆
ページ範囲:P.859 - P.863
要約 目的:結膜炎と結膜潰瘍があり,全身所見からBehçet病が疑われた症例の報告。症例:44歳女性が2年前からある両眼の眼瞼腫瘤と左眼の眼痛で受診した。両眼の上眼瞼に出血しやすい巨大乳頭結膜炎と,左眼の球結膜に潰瘍があった。以前から腰痛と微熱があり,整形外科で両側仙腸関節炎と診断された。皮膚科では口腔内アフタと毛囊炎様の皮疹が頸部と前胸部にあり,Behçet病の疑いと診断された。球結膜の生検で,結膜上皮内と間質の血管周囲に炎症細胞の浸潤があった。眼症状は副腎皮質ステロイドの局所投与で軽快した。結論:結膜炎と結膜潰瘍はBehçet病の眼症状である可能性がある。
黄斑円孔の自然閉鎖例に対する硝子体手術症例
著者: 木村育子 , 永田浩章 , 竹尾悟 , 成田理会子 , 鈴木美砂 , 渡邉洋一郎 , 門之園一明
ページ範囲:P.865 - P.867
要約 目的:特発性黄斑円孔が自然閉鎖した眼に硝子体手術を行った症例の報告。症例:45歳男性が右眼の視力低下と変視症で受診した。矯正視力は右0.4,左1.5であった。右眼に黄斑円孔があり,光干渉断層計では円孔の大きさは1/7乳頭径であった。右眼を特発性黄斑円孔の第3期と診断した。経過:10週後に黄斑円孔は閉鎖し,視力は0.5になった。視力と自覚症状の改善が乏しいために硝子体手術で内境界膜を剝離し,SF6ガスを注入した。視力は手術の9日後に1.0,13日後に1.5になった。光干渉断層計では黄斑は正常の形態であった。結論:自然閉鎖した黄斑円孔に硝子体手術を行うことで,早期に視力と自覚症状の改善が得られることがある。
全身性エリテマトーデスの加療中に両眼性胞状網膜剝離を生じた1例
著者: 金子優 , 笠木靖夫 , 山下英俊
ページ範囲:P.869 - P.873
要約 目的:重症全身性エリテマトーデス(SLE)に対する副腎皮質ステロイド薬を投与中に胞状網膜剝離が生じ,SLEが寛解するとともに網膜剝離が軽快した症例の報告。症例:59歳女性が関節痛と発熱を契機としてSLEと診断され,プレドニゾロンなどの全身投与を受けていた。第22病日に両眼の視力が低下した。矯正視力は右0.6,左0.5であり,滲出斑を伴わない胞状網膜剝離が両眼の後極部にあった。蛍光眼底造影と臨床所見とから,多発性後極部色素上皮症が疑われた。免疫吸着療法によりSLEの活動性が低下し,胞状網膜剝離と視力が改善した。結論:SLEによる脈絡膜血管炎にステロイド薬で網膜色素上皮症が誘発されたことで,胞状網膜剝離が発症した可能性がある。
連載 今月の話題
眼内レンズ―最近の進歩
著者: 松島博之
ページ範囲:P.697 - P.704
白内障手術療法の進歩とともに眼内レンズに付随する付加機能の進歩が著しい。着色IOL,非球面IOL,多焦点IOLなどさまざまなIOLが開発され,話題に上るが,実際の機能や利点がわかりにくいものが多い。今回IOLに付随する付加機能を改めてできるだけわかりやすく解説することを試みた。
日常みる角膜疾患・50
コンタクトレンズのケア用品による角膜傷害
著者: 柳井亮二 , 西田輝夫
ページ範囲:P.706 - P.710
症例
患者:37歳,女性
主訴:コンタクトレンズの定期検査
現病歴:近視矯正目的のソフトコンタクトレンズ(soft contact lens:以下,SCL)装用中で,現在,自覚症状はない。
コンタクトレンズ装用歴:従来型のSCLを20年前から使用しており,現在は2週間頻回交換SCLを終日装用していた。現在のケア用品は多目的用剤(multi-purpose solution:以下,MPS)を使用し,ケア方法を遵守していた。
既往歴・家族歴:特記すべきことはない。アトピー素因なし。
初診時所見:視力は右(1.2×SCL),左(1.2×SCL)であった。細隙灯顕微鏡検査において,SCLのフィッティングは良好であったが,両眼に軽度の充血がみられた(図1a)。SCLをはずしてフルオレセイン染色を行うと,両眼にA3D2の点状表層角膜症(superficial punctate keratopathy:以下,SPK)を認めた(図1b)。両眼の眼瞼結膜に充血,濾胞や乳頭の形成はみられなかった。涙液検査は,シルマー試験では両眼とも正常で,マイボーム腺の閉塞はみられなかったが,涙液破綻時間は3秒に短縮していた。
経過:SCLはFDA分類(表1)でグループⅠ(低含水,非イオン性)の素材で,レンズケア用剤は塩酸ポリヘキサニド(以下,PHMB)を消毒成分としたMPSであった。MPSによる角膜障害が疑われたためSCL装用を中止し,抗菌点眼薬の点眼を行った。SCL装用中止後4日目に両眼の充血は軽減し,点状表層角膜症は治癒していた(図1c,d)。以後,SCLの装用を再開に当たって,ポビドンヨード製剤のケア用剤に変更し,現在までSPKの再発はみられていない。
公開講座・炎症性眼疾患の診療・2
特発性視神経炎
著者: 新田卓也 , 北市伸義 , 大野重昭
ページ範囲:P.712 - P.718
はじめに
網膜神経節細胞からの神経線維は,網膜内では無髄神経だが眼球から出て眼窩内に入る際に有髄神経線維となる。約100万本あるとされる神経線維はひとまとめとなって視神経管を通って頭蓋内に入り,視交叉で視神経線維の約半数は交叉し,外側膝状体などに終止する。この眼球から視交叉までの神経線維の束を視神経と呼び,神経線維が集合して眼球を貫く部位は視神経乳頭と呼ばれる。
視神経に何らかの炎症性の機序が働き,視機能障害をきたした状態を視神経炎と呼ぶ。炎症以外の機序による視神経障害は視神経症と呼ばれる。細菌やウイルスなどの感染が視神経炎の直接の原因となることもあるが,ここでは視神経炎の大多数を占め,脱髄が機序として推測される特発性視神経炎について解説する。また,特発性視神経炎と所見は酷似するが,その病態,予後が異なると考えられる疾患として自己免疫性視神経症(炎)があり,特発性視神経炎の治療を考えるうえで理解が必要となるため,今回一緒に取り上げた。
網膜硝子体手術手技・5
黄斑円孔
著者: 浅見哲 , 寺崎浩子
ページ範囲:P.720 - P.725
はじめに
黄斑円孔に対し1991年にKellyら1)により硝子体手術が行われるようになってから,閉鎖率を上げるためにさまざまな治療法が試みられてきた。網膜色素上皮を擦過したり,生体糊を使用したりという工夫がされたが,内境界膜剝離が円孔閉鎖率を格段に向上させることが1995年にBrooks2)により報告されてからは,内境界膜剝離が一般的な手技になった。
本稿では内境界膜剝離の手術手技を中心に基本的な術中の注意点についても述べたい。
眼科医のための遺伝カウンセリング技術・7
遺伝確率に関する情報提供とカウンセリング技法―確率をどのように伝えるか
著者: 千代豪昭
ページ範囲:P.727 - P.737
はじめに
遺伝カウンセリングでは「遺伝病が発病したり,再発する可能性をクライエントに伝える」という過程がある。「カウンセラーから知らされた遺伝医学情報をもとに,クライエントが自らの意志で罹病による不利益を回避するために行動決定する」のが遺伝カウンセリングの1つの流れである。遺伝カウンセリングが医療行為に準じるというのも,この過程がクライエントの精神・身体の健康に深く関わるからである。
さて,科学性を重視する遺伝カウンセリングでは,遺伝性疾患の発病や再発の可能性を「確率」という数字で説明することが多い。確率を読み取り未来を予測することが難しいのは天気予報の降水確率を例にとっても明らかであるが,遺伝現象の確率的な表現の伝達が難しい理由として,いくつかの問題が指摘できる。
眼科医のための救急教室・5
高齢者救急
著者: 和田崇文 , 箕輪良行
ページ範囲:P.876 - P.878
はじめに
2006年の総務省統計局の発表によれば,わが国の高齢者人口は総人口の20.7%となり,国民5人に対し1人を占めています。そして「65歳以上74歳以下」の前期高齢者よりも「75歳以上」の後期高齢者の増加が著しく,また地域に老人介護施設も増加した結果,医療現場に高齢者が急増したと推察されます。以前から「小児は大人の小型ではない」といわれますが,「老人は成人の延長ではない」1)ことも熟知する必要があると思います。そこで今回は周術期管理を中心に高齢者救急の注意点を解説します。
高齢者の身体的・生理的変化
高齢者診療の注意点は岩田2)の「12の教訓」(表1)および総論が詳しいので以下に引用し,そのなかの重要ポイントを解説します。
臨床報告
視力,視野障害を伴った視神経乳頭上色素性腫瘍の1例
著者: 鈴木茂揮 , 星合繁 , 福島孝弘 , 関根新 , 越野崇 , 折原唯史 , 眞舘幸子 , 栗原秀行
ページ範囲:P.891 - P.895
要約 目的:視神経乳頭上色素性腫瘍に視力と視野障害が併発した症例の報告。症例:48歳女性が健康診断で眼底異常を指摘された。矯正視力は右1.2,左0.9であった。左眼の視神経乳頭前に1.5乳頭径の黒褐色の隆起性病変があった。同様な病変は8年前にも当院で確認されていた。ゴールドマン視野検査で左眼の鼻下側に狭窄があった。経過中に左眼視力が0.9と1.2の間を変動した。眼底所見から良性の黒色細胞腫が強く疑われたが,本症例では視力が変動し,視野異常があることが特異的であった。結論:視神経乳頭の黒色細胞腫で視力と視野障害が生じたのは,腫瘍による視神経線維の圧迫または視神経内血管の循環障害による可能性がある。
エピケラトームを用いて角膜混濁除去を行った1例
著者: 柴田優子 , 宮井尊史 , 子島良平 , 刑部安弘 , 宮田和典 , 天野史郎
ページ範囲:P.897 - P.901
要約 目的:エピケラトームを併用して角膜の混濁除去を行った症例の報告。症例:20歳の女性が3歳のときに両眼の顆粒状角膜ジストロフィと診断された。混濁が強くなり,角膜擦過術を複数回受けた。4年前に当科を受診した。矯正視力は右0.1,左0.7であり,レーザーによる角膜切除術(PTK)で視力が右1.0,左0.9に改善した。さらに電気分解術を2回右眼に行ったが角膜混濁が進行した。視力が右0.6,左0.7に低下したので,エピケラトームによる上皮剝離除去と電気分解術を施行した。4日後に角膜上皮欠損がなくなり,7日後に視力は右0.6,左0.6になった。術前の角膜厚は右515μm,左487μmであり,術後は右480μm,左490μmになった。エピケラトームを使うことで角膜混濁の電気分解を短時間で行うことができた。結論:再発を繰り返した角膜混濁を電気分解で除去する際にエピケラトームを使い,治療時間が短縮化できた。
カラー臨床報告
水晶体核落下に対するoptical fiber-free intravitreal surgery system(OFFISS)を用いた硝子体腔内双手超音波乳化吸引術
著者: 山田英機 , 堀尾直市 , 谷川篤宏 , 堀口正之
ページ範囲:P.885 - P.890
要約 目的:硝子体腔内に落下した水晶体を,ライトガイドなしで眼内を観察する硝子体手術で摘出した2症例の報告。症例と方法:1例は眼球への鈍性外傷で水晶体が硝子体腔に落下した69歳女性,1例は白内障手術中に水晶体核が硝子体腔に落下した59歳男性である。ライトガイドを用いずに眼内を観察できる硝子体手術(optical fiber-free intravitreal surgery system)で,落下した水晶体を双手超音波乳化吸引術により摘出した。結果:この方法により,水晶体核片を安定した状態で保持しながら処理することができた。術中または術後の合併症はなく,それぞれ0.3と1.0の視力を得た。結論:硝子体腔内双手超音波乳化吸引術は,硝子体腔に落下した水晶体またはその核片の処理に,安全で有効な方法である。
今月の表紙
小口病
著者: 山本素士 , 中澤満
ページ範囲:P.705 - P.705
患者は24歳女性。結膜炎で近医を受診した際に夜盲を訴え,眼底異常を認めたため精査目的で当院を紹介され受診した。既往歴は,5歳より多発性硬化症がある。家族歴に特記すべきことはなく,近親婚は確認できていない。眼底検査で“はげかかった金箔様”眼底を認めたが,長時間暗順応後の眼底検査では正常眼底となった(水尾-中村現象)。20分暗順応flash ERGでa波の低下,b波の消失,律動様小波は正常で長時間暗順応flash ERGでa波,b波の改善を認めた。視野,色覚,中心フリッカ値は正常であった。以上より小口病と診断した。
小口病は先天停止性夜盲の一種で,原因として常染色体劣性遺伝でアレスチン遺伝子1147delA変異,またはロドプシンカイネース遺伝子の異常が報告されている。日本人の場合は,前者が多いとされている。
べらどんな
自由と独創
著者:
ページ範囲:P.719 - P.719
どこも悪くないのだが,ときどき病院に通っている。「いざ」というときに,あらかじめコネをつけておこうという下心からである。
頭部の磁気共鳴画像検査(MRI)をしてもらった。CTと違ってとても騒々しい機械だが,できた画像を見てびっくりした。血管造影をしないのに頭蓋内の動脈がはっきり出ているのだ。
戦後の10年
著者:
ページ範囲:P.738 - P.738
ドイツは第一次世界大戦で破れた。休戦協定が結ばれたのが1918年11月11日,そして講和条約がベルサイユで批准されたのがその翌年の6月28日である。
連合軍,とくにフランスはドイツに対して苛酷であった。天文学的な額の賠償金を要求された。旧1マルクが1兆マルクになるなどの超インフレになり,経済が破滅してしまった。
やさしい目で きびしい目で・89
熱く思うこと (2)薬害
著者: 島川眞知子
ページ範囲:P.875 - P.875
コーヒーを注文すると一緒に出てくる,小さなカップ入りミルク“コーヒーフレッシュ”が実は牛乳成分は1滴も含まれず,植物油と水を混ぜ,添加物で白濁させ,香料を加えてミルク風に仕立てたものだってご存じですか。マーケットで売られているカット野菜,コンビニのパックサラダが長時間パリッとしているのは,刻んだ野菜を殺菌剤入りのプールに何度もつけて処理されているからだって驚きません?(安部司:食品の裏側.東洋経済新報社,2005)これは食品添加物の危険性を指摘した本で,読み進むうちに,知らないうちに口にした添加物から実は多くの疾病が作り出されているのだろうと危惧せざるを得ない。
これと同様に私は以前から,薬害というのが潜在的に多発しさまざまな疾病を引き起こしているに違いない,と確信している。以下は私の経験例である。
ことば・ことば・ことば
失言
ページ範囲:P.879 - P.879
不注意で「ものを言い違えること」がときにあります。これをlapsus linguaeと言い,ラテン語の表現ですが,英語でもそのまま使われます。前半の意味は「滑ること」で,硝子体脱出vitreous prolapseにもこれが入っています。後半は「舌」のことです。
無知が原因である場合はこれとは別です。ある大国の副大統領が中南米の国々を訪問することになりました。中南米はラテンアメリカが別名です。ほとんどの国でスペイン語かポルトガル語,すなわちラテン語の方言が公用語だからです。
--------------------
あとがき フリーアクセス
著者: 中澤満
ページ範囲:P.912 - P.912
「臨床眼科」 5月号をお送りいたします。早いもので,2007年もあと1か月少々で折り返しとなります。日々の仕事に追われて,いつの間にか時間が過ぎてしまうことが多くなってしまいますが,眼科の専門分野といえども自分で意識して常に知識の整理を行っていないと,あっという間に取り残されてしまいます。「臨床眼科」が少しでも読者の知識のリニューアルにお役に立てばと願ってやみません。
そのひとつの助けとなるべく今月も連載が順調に進んでいます。千代豪昭氏による「眼科医のための遺伝カウンセリング技術」は,今回で第7回目となります。以前から「眼は遺伝病の宝庫」というあまりありがたくない言葉がありますが,それだけに外来診療の場で遺伝性疾患の説明や遺伝カウンセリングをわれわれ眼科医が担当することもよくあることで,そのときの心構えの基本を教えられる非常に有益な連載です。
基本情報
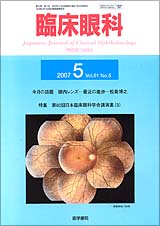
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
