要約 目的:往診した眼科患者を在宅者と有料老人ホーム入居者とに分け,眼疾患と全身状態について検討した結果の報告。対象と方法:過去31か月間に往診した40症例を解析した。在宅者13例,老人ホーム入居者27例で,男性13例,女性27例であり,年齢は63~104歳(平均86歳)であった。結果:全身状態についての診療情報は,在宅者では8例(62%),ホーム入居者では25例(93%)から提供された。視力低下はそれぞれ11例(85%)と22例(81%),両眼とも視力0.5以下はそれぞれ9例(69%)と13例(48%),外眼部疾患はそれぞれ5例(38%)と7例(26%),脳または神経疾患はそれぞれ6例(46%)と15例(56%),整形外科疾患はそれぞれ3例(23%)と7例(26%)にあった。年齢については両群間に有意差がなかった。結論:往診の依頼は,脳または精神疾患があることが多く,在宅者では外眼疾患が多い。全体を通じ,全身疾患のために来院が困難なことが往診を依頼する主要な原因であった。
雑誌目次
臨床眼科62巻4号
2008年04月発行
雑誌目次
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
原著
緑内障手術の視機能への影響
著者: 豊川紀子 , 宮田三菜子 , 木村英也 , 黒田真一郎 , 永田誠
ページ範囲:P.461 - P.465
要約 目的:緑内障手術後の視機能の検討。対象と方法:深部強膜切除およびシュレム管外壁開放術(サイヌソトミー)併用線維柱帯切開術単独(LOT)群43例54眼,線維柱帯切除術単独(LEC)群37例40眼の術後の視力,惹起乱視,高次収差,コントラスト感度,涙液層について検討した。結果:LOT群のほうがLEC群よりも視力回復が有意に早かった(p<0.05)。高次収差(瞳孔径4mm)はLOT群0.28±0.2,LEC群0.47±0.3でLEC群のほうが有意に大きく(p<0.05),惹起乱視もLEC群で有意に増加していた(p<0.01)。両群とも,術後視力は良好でMD≧-12Dでもコントラスト感度が低下している症例があった。LEC群では涙液油層分布が不整になる傾向があり,それらの症例では高次収差が大きい傾向があった。結論:緑内障術後では視力良好な症例でも視機能が低下している可能性がある。
菌塊を形成した涙小管感染症の細菌学的検討
著者: 石川和郎 , 児玉俊夫 , 島村一郎 , 鄭暁東 , 金子明生 , 西谷元宏 , 石川明邦 , 大城由美
ページ範囲:P.467 - P.472
要約 目的:菌塊を形成した涙小管炎7例の起炎菌微生物の報告。対象と方法:手術により菌塊を摘出した涙小管炎7例を対象とした。年齢は60~83歳(平均70歳)で,男性1例,女性6例である。膿性分泌物または摘出した菌塊は嫌気培養または塗抹標本と病理組織標本のグラム染色を行った。結果:膿性分泌物の嫌気培養で2例が放線菌と同定され,塗抹標本のグラム染色で5例が放線菌と同定され,1例では病理組織から真菌感染が疑われた。放線菌の6例では,表皮ブドウ球菌や口腔連鎖球菌の混合感染があった。結論:菌塊を形成した涙小管炎では,嫌気培養だけでは放線菌の検出は困難で,塗抹または病理標本のグラム染色が起炎微生物の同定に有用である。
エタンブトール視神経症の耳側感度低下
著者: 比嘉利沙子 , 塩川美菜子 , 深作貞文 , 若倉雅登 , 井上治郎
ページ範囲:P.473 - P.478
要約 目的:エタンブトール視神経症の病型による視野障害の特徴がHumphrey視野で明確になるか検討した報告。対象と方法:エタンブトール視神経症連続5症例の視力および視野の経過を1年以上追跡した。結果:中心暗点型4例のGoldmann視野では,中心,傍中心暗点を認め,Humphrey視野では両眼の耳側感度低下を認めた。回復期でもHumphrey視野の耳側と鼻側の感度差は明らかであった。結論:中心暗点型エタンブトール視神経症のHumphrey視野は,過去の動物実験における視交叉の変性所見とよく符合した。エタンブトール視神経症では,視交叉が一次的に障害されやすい部位と考えられ,その検出にはHumphrey視野が適している。
再発下垂体腫瘍へのガンマナイフ治療後に視神経炎を生じた1例
著者: 細田淳英 , 水野谷智 , 阿部秀樹 , 金井秀仁 , 池田和敏 , 木田橋久明 , 鈴木雅信
ページ範囲:P.479 - P.482
要約 目的:下垂体腫瘍の再発に対するガンマナイフ治療後に視神経炎が生じた症例の報告。症例:41歳女性が5日前からの両眼視力低下で受診した。5年前に下垂体腫瘍に対し脳外科で手術を受け,50日前にその再発に対してガンマナイフ照射を受けた。矯正視力は右0.5,左0.6で,中心フリッカ値が低下し,色覚異常があった。眼底に異常はなかった。両眼視野に盲点の拡大と上方の感度低下があり,磁気共鳴画像検査(MRI)で視神経髄鞘が高信号であった。これらの所見から視神経炎と診断した。副腎皮質ステロイド薬のパルス療法で視力は両眼とも1.2に改善した。以後18か月後の現在まで経過は良好である。結論:下垂体腫瘍に対するガンマナイフ治療では,視神経炎が併発する可能性があり,副腎皮質ステロイド薬のパルス療法が奏効することがある。
増殖糖尿病網膜症に対する術前ベバシズマブ硝子体内注入の検討
著者: 米田愛 , 宇野木良孝 , 松本牧子 , 岸川泰宏 , 山田浩喜 , 宮村紀毅 , 隈上武志 , 三島一晃 , 北岡隆
ページ範囲:P.483 - P.487
要約 目的:増殖糖尿病網膜症に対する硝子体手術の術前処置としてのベバシズマブ硝子体注入の検討。対象と方法:増殖糖尿病網膜症13例16眼を対象とした。男性11眼,女性5眼で,年齢は平均56歳であり,15眼にはすでに光凝固が行われていた。8眼に網膜新生血管,10眼に虹彩ルベオーシス,6眼に牽引性網膜剝離があった。硝子体手術の3または4日前にベバシズマブ1.25mgを硝子体に注入した。同様な糖尿病網膜症があり,硝子体手術を受けた23例28眼を対照とした。視力はlogMARとして評価した。結果:ベバシズマブ注入後に網膜と乳頭の新生血管は退縮し,新生血管を処理するときの出血は対照群よりも少量であった。平均視力は注入群では術前の0.74が術後0.46に,対照群では術前の1.22が術後0.85に改善した。ベバシズマブ投与による合併症はなかった。結論:増殖糖尿病網膜症に対するベバシズマブ硝子体注入は新生血管を退縮させ,その後の硝子体手術が安全になる。
抗ウイルス治療に抵抗し両眼網膜剝離を生じた進行性網膜外層壊死の1例
著者: 宮岡佳美 , 鈴木潤 , 山内康行 , 後藤浩
ページ範囲:P.489 - P.492
要約 目的:治療に抵抗したヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症に伴う進行性網膜外層壊死(PORN)の1例の報告。症例:47歳男性が3日前からの右眼視野狭窄で受診した。5か月前に急激な体重減少があり,HIV抗体が陽性であった。以後水痘・帯状疱疹,ウイルス性髄膜炎,トキソプラズマ脳症,水痘を発症し,highly active antiretrovirus therapy(HAART)を受けていた。矯正視力は右0.8,左1.2で,右眼には眼底全周に黄白色の病巣と一部に網膜剝離があり,左眼には周辺部に白色の点状病巣があった。前房水から水痘・帯状疱疹ウイルスのDNAが検出され,PORNと診断した。アシクロビルなど抗ウイルス薬の全身投与は奏効せず,初診から16日目に右眼は全網膜剝離になった。3か月後に左眼に黄白色病巣が出現し拡大した。ガンシクロビルなどを投与したが網膜壊死部の円孔から網膜剝離が生じた。硝子体切除術などで網膜は復位した。以後6か月後の現在まで安定し,0.8の視力を維持している。結論:PORNが発症するときには免疫不全状態にあることが多く,抗ウイルス療法や外科的治療が困難なことがあり,予後不良である可能性がある。
高齢者に発症した原田病の2例と臨床的特徴
著者: 市頭教克 , 小沢昌彦 , 野田美登利 , 村田浩司 , 林英之 , 内尾英一
ページ範囲:P.493 - P.497
要約 背景:原田病の好発年齢は20~40歳代とされている。高齢で本症が発症すると,原田病に特有な皮膚などの眼外症状と加齢による変化との鑑別が困難である。ステロイドの大量投与で全身状態が悪化し,副作用が生じることがある。目的:2例の高齢者に発症した原田病の報告。症例:83歳女性と60歳男性を原田病と診断した。1例には数週間前から難聴と耳痛があり,4日前に眼痛と霧視を自覚した。矯正視力は右0.6,左0.4であった。左眼に虹彩炎,両眼に乳頭の発赤腫脹と乳頭黄斑間の網膜剝離があり,髄液に細胞増加があった。他の1例は両眼の霧視発症から2週間後に受診した。視力は右0.15,左0.2であり,両眼に角膜後面沈着物,乳頭の発赤浮腫,乳頭と黄斑間の網膜剝離があった。髄液に細胞増加があった。両症例ともHLA型がDR4陽性であった。両症例にステロイドパルス療法を行い,軽快した。症例1では打撲による頸椎骨折,症例2では炎症が再発した。結論:今回の2症例では,注意深いステロイドの全身投与が奏効し,髄液検査とHLAタイピングが診断に有効であった。
容易に睫毛抜去できる睫毛鑷子の作製とその有効性
著者: 小林茂樹 , 小林守治
ページ範囲:P.499 - P.502
要約 目的:新規に考案した睫毛鑷子の紹介とその評価。方法:従来の睫毛鑷子の把持面を粗面加工することで睫毛を確実に挟めるようにした。症例:85歳女性に流涙があり,脂漏が多く,睫毛が細かった。今回考案した睫毛鑷子で睫毛をしっかり保持し,抜去することができた。69歳女性の両眼の下眼瞼に細く短い睫毛があった。今回考案した睫毛鑷子でスムーズに抜去することができた。結論:今回改良した睫毛鑷子は,短時間で容易かつ確実に睫毛を抜去することができる臨床的に有効な器具である。
心因性視覚障害―世代別にみた傾向と特異性
著者: 一色佳彦 , 木村徹 , 木村亘 , 横山光伸 , 武田哲郎 , 松永次郎 , 正化圭介
ページ範囲:P.503 - P.508
要約 目的:心因性視覚障害と診断した患者につき,世代別の病態の特徴,診断の根拠,推定心因などについての報告。対象:過去12年間に心因性視覚障害と診断した180症例を診療録に基づいて検索した。男性51例,女性129例で,年齢別の内訳は,13歳未満の小児66例,20歳までの思春期41例,60歳までの成人56例,高齢者17例である。結果:推定心因は,小児と思春期では学校や家庭に関するストレスが上位を占め,成人では仕事や家庭など生活に関するストレス,高齢者では孤独,経済問題,疾病に関するストレスが多かった。病態の特徴として,小児と思春期では心因が単純で治療しやすい症例が多く,成人と高齢者では心因が複雑で治癒しにくい傾向があった。結論:心因性視覚障害は全年齢層にあり,成人と高齢者では,小児や思春期とは異なり難治例が多い。
両眼の急激な視力障害で発症した自己免疫性視神経症の1例
著者: 小島照夫 , 鷲尾紀章 , 若栗隆志 , 上田至亮 , 石田政弘 , 西川真平
ページ範囲:P.509 - P.512
要約 目的:視力障害で発症した自己免疫性視神経症の症例の報告。症例と経過:45歳女性に両眼の視力障害が突発して受診した。Basedow病と特発性血小板減少性紫斑病の既往があり,13日前から咽頭痛と熱発があり服薬中であった。視力は左右眼とも指数弁で,対光反射が減弱していた。2日後に両眼とも視力0となった。両眼に軽い乳頭浮腫があり,磁気共鳴断層検査(MRI)で両眼の視神経炎が推定された。血液検査で抗核抗体,抗サイログロブリン抗体,抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体が高値であり,自己免疫性視神経症と診断した。ステロイドパルス療法を行い,6か月後に矯正視力は右0.1,左0.04に回復した。結論:自己免疫性が疑われる視神経症では,早期であればステロイドの大量全身投与が奏効することがある。
チオテパ点眼を用いた翼状片手術成績
著者: 二階堂寛俊
ページ範囲:P.513 - P.515
要約 目的:術後にチオテパ点眼を用いた翼状片手術の報告。対象と方法:過去6年間に行った翼状片手術のうち,術後1年以上経過を追えた143例160眼を対象とした。術式として,結膜下組織の広範な切除を伴う単純切除を行った。術後,抗菌薬とステロイド点眼とともに,チオテパを1日4回点眼し,平均20.2日使用した。輪部を越えて角膜に血管を伴う組織が侵入したものを再発とした。結果:再発が4眼(2.5%)にあり,うち1眼は再手術を必要とした。チオテパ点眼による副作用はなく,術後の瘢痕形成や充血はなく,美容的にもほとんど問題がなかった。結論:翼状片の単純切除後にチオテパを点眼することにより,再発をほとんど防ぐことができた。
日本人角膜鉄線の形と分布―動画を応用した角膜鉄線撮影法
著者: 松原稔
ページ範囲:P.517 - P.522
要約 目的:角膜鉄線の全容を写真撮影し,その形と位置を数値化して解析した日本人の角膜鉄線の報告。対象と方法:初診患者4,043名を対象とした。内訳は男性1,927名,女性2,116名である。細隙灯顕微鏡に装着したCCDカメラで動画を撮影し,パノラマ写真として印画紙に焼付けた。角膜鉄線の両端と中間点の位置と全長を数値化して検索した。結果:Hudson-Stähli線は92名(2.3%),翼状片などの疾病に伴う鉄線は17名(0.4%),角膜片雲に併発する鉄線は69名(1.7%)にあった。鉄線には成長または減衰を示す例があった。結論:角膜鉄線を写真と数値で記録することで,統計学的かつ時系列的に解析することができる。生理的な鉄線と病的な鉄線があり,成長または減衰することがある。
血清IgE値とLASIK合併症との関連
著者: 安岡恵子 , 福島敦樹 , 角環 , 上野脩幸
ページ範囲:P.523 - P.526
要約 目的:血清のIgE値とLASIK術後合併症との関連の報告。対象と方法:過去6年間にLASIKを行った症例のうち,250例250眼を対象とした。血清IgE値が170IU/ml以上の96眼とこれ未満の154眼の2群についてのLASIK合併症の頻度を検索した。合併症は,びまん性層間角膜炎,角膜フラップのストリエ,角膜上皮迷入の3種に分けた。結果:びまん性層間角膜炎は250眼中7眼(2.8%)に生じ,IgE高値群では6眼(6.3%),低値群では1眼(0.7%)であり,有意差があった(p=0.0139)。ストリエは250眼中6眼(2.4%)に生じ,IgE高値群では4眼(4.2%),低値群では2眼(1.3%)であり,有意差はなかった(p=0.208)。角膜上皮迷入はなかった。結論:血清IgE値は,LASIK後のびまん性層間角膜炎の発症に関連がある可能性と,LASIK後の合併症の予測に有用である可能性がある。
Purtscher網膜症の網膜断層像の経過
著者: 細貝真弓 , 秋山英雄 , 岸章治
ページ範囲:P.527 - P.532
要約 目的:光干渉断層計(OCT)で経過を追ったPurtscher網膜症の1例の報告。症例:70歳男性が自動車を運転中に電柱に衝突し,多発性肋骨骨折を生じ,その翌日に受診した。矯正視力は右0.2,左0.02で,両眼の乳頭周囲に綿花様白斑があり,左眼は乳頭黄斑間に網膜の白濁があった。OCTで両眼に漿液性網膜剝離と左眼網膜内層に高反射があった。漿液性網膜剝離は1か月後に消失した。受傷から3か月後に矯正視力は右1.0,左0.7になったが,白濁部では網膜内層が菲薄化し,視細胞の内節と外節の接合部が消失し中心暗点が生じた。結論:Purtscher網膜症の急性期では網膜の白濁と綿花様白斑が混在し,漿液性網膜剝離があった。陳旧期では網膜内層が菲薄化し,視細胞の内節と外節の接合部が消失し,中心暗点の原因になった。
網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫に対するベバシズマブ硝子体内投与の短期成績
著者: 元村憲文 , 三浦雅博 , 岩﨑琢也
ページ範囲:P.533 - P.536
要約 目的:網膜静脈閉塞症に対するベバシズマブ硝子体内投与の短期成績の報告。症例と方法:黄斑浮腫がある網膜静脈分枝閉塞8眼と網膜中心静脈閉塞7眼を対象とした。ベバシズマブ1.25mgを硝子体に注入し,注入前と注入1か月後の所見を光干渉断層計(OCT)で比較した。結果:網膜静脈分枝閉塞症では8眼中6眼(75%),網膜中心静脈閉塞症では7眼中4眼(57%)で黄斑浮腫が改善した。ベバシズマブ硝子体内投与による副作用はなかった。結論:ベバシズマブ硝子体内投与は,網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫を軽減させる。
網膜静脈閉塞による遷延性類囊胞状黄斑浮腫に対する硝子体ベバシズマブ投与の短期効果
著者: 梅基光良 , 山口泰孝 , 木村忠貴 , 植田良樹
ページ範囲:P.537 - P.541
要約 目的:遷延性黄斑浮腫を伴う網膜静脈閉塞症に対するベバシズマブ硝子体内投与の結果の報告。症例:各種治療に抵抗し,10か月以上遷延する類囊胞状黄斑浮腫を伴う網膜静脈閉塞6例6眼を対象とした。年齢は41~87歳(平均69歳)であり,網膜静脈分枝閉塞症3例と網膜中心静脈閉塞症3例であった。ベバシズマブを硝子体内に投与し,視力,黄斑部の網膜厚,黄斑部の体積を3か月後まで測定した。視力はlogMARで評価した。結果:視力,網膜厚,網膜容積は全例で1週間後に有意に改善した。黄斑浮腫は5眼で1か月後に再発した。浮腫が改善したが,視力が改善しない1眼には網膜色素上皮萎縮があった。結論:遷延性の黄斑浮腫でもベバシズマブの硝子体内投与により,一過性の浮腫と視力の改善が得られるが,高頻度に再発する。
光線力学療法施行後早期に著明な視力低下をきたした加齢黄斑変性症例の検討
著者: 新井純 , 新井郷子 , 吉田紀子 , 福井えみ , 中村さち子
ページ範囲:P.543 - P.547
要約 目的:光線力学療法(PDT)を行った後,早期に顕著な視力低下が起こった症例の検討。対象:PDTを行った加齢黄斑変性(AMD)患者のうち,術前の矯正視力が0.4~0.6の48例48眼を対象とした。男性36例,女性12例であり,年齢は47~87歳(平均72歳)であった。AMDの内訳は,狭義のAMD 15眼,ポリープ状脈絡膜血管症(PCV)28眼,網膜血管腫様増殖5眼であった。結果:PDTから6か月後の視力は,10眼で改善,26眼で不変,12眼で悪化した。7眼(15%)では0.2未満に低下した。この7眼中,2眼がPCV,3眼が脈絡膜新生血管を伴うPCVであった。視力低下の原因は,脈絡膜新生血管の拡大が2眼,瘢痕化が3眼,網膜色素上皮の萎縮が3眼であった。結論:脈絡膜新生血管を伴うPCVでは,PDTを行う際に注意が必要である。
Torsional phacoを用いた落下水晶体に対する硝子体腔内超音波乳化吸引術
著者: 塙本宰 , 菊地琢也 , 今井正之 , 小沢忠彦
ページ範囲:P.549 - P.553
要約 目的:落下水晶体を毛様体扁平部からtorsional phaco(OzilTM)を用い,硝子体腔内超音波乳化吸引を行い除去した症例を報告する。対象と方法:対象は白内障手術中の核落下2例と虹彩・脈絡膜コロボーマに水晶体落下を伴う1例である。3ポート硝子体手術を行い,ポート周辺の周辺部硝子体切除を十分に行った。その後,torsional phacoを用いて毛様体扁平部から落下水晶体の乳化吸引を行った。結果:乳化吸引時に核のはじき返しが少なく,水晶体を何度も落下することがなかった。全例で経過は良好で併発症はない。結論:毛様体扁平部からtorsional phacoを用いると核片が散らばらずに効率のよい核処理ができ,侵襲の小さい手術が行うことができる。
25ゲージ硝子体手術でのインフュージョン位置置換
著者: 松下新悟 , 内藤毅 , 香留崇 , 竹林優 , 佐藤寛之 , 塩田洋
ページ範囲:P.555 - P.557
要約 目的:25ゲージ硝子体手術の際,通常は外下方のカニューラに留置しているインフュージョンを外上方のカニューラに移動させ,外下方のカニューラから眼内器具を挿入して上方周辺部を処理した。その有用性を報告する。対象と方法:過去6か月間に行った25ゲージ硝子体手術で,周辺部の処理を必要とした連続15眼を対象とした。内訳は,糖尿病網膜症11眼と裂孔原性網膜剝離4眼である。上述の方法でインフュージョンの位置を変換し,周辺部処理の有用性を検討した。結果:インフュージョンの位置を変換することで,周辺部を安全に処理することが全例ででき,術創への負担が軽減できたために術後の術創の閉鎖が良好であり,術後の低眼圧を予防できた。結論:硝子体手術の際,インフュージョンの位置を変換することで,安全に周辺部を処理することができる。
経結膜硝子体手術に併施する小切開白内障手術の切開径についての検討
著者: 椋野洋和 , 木村大作 , 服部昌子 , 糸井恭子 , 楠原仙太郎 , 大音壮太郎 , 宮本紀子 , 秋元正行 , 高木均
ページ範囲:P.559 - P.561
要約 目的:経結膜硝子体手術と同時に行う小切開白内障手術での最適な切開の大きさについての報告。対象と方法:過去7か月間に23ゲージ経結膜硝子体手術併用の小切開白内障手術を行った72例72眼を対象とした。42眼では眼内レンズを非wound-assisted法で,30眼ではwound-assisted法で挿入した。これらについてhydrationなしに硝子体手術が可能である白内障手術の切開径を検索した。結果:Hydrationなしで硝子体手術が可能な症例は,2.65mmの切開創による非wound-assisted法で18眼中16眼(89%),2.2mmの切開創によるwound-assisted法で16眼中9眼(56%)であった。結論:経結膜硝子体手術と併用する小切開白内障手術では,非wound-assisted法では2.65mm, wound-assisted法では2.2mmの大きさの角膜切開が適している。
特発性網膜動脈分枝閉塞症の1例
著者: 森紀和子 , 宮原照良 , 太田浩一 , 村田敏規
ページ範囲:P.563 - P.566
要約 目的:若年者の両眼に発症した網膜動脈分枝閉塞症の報告。症例:27歳男性が右眼の視野欠損を自覚し,同日受診した。矯正視力は右1.2,左1.5であり,右眼には上鼻側,左眼には網膜動脈分枝の閉塞と網膜の白色化があった。網膜動脈炎による網膜動脈閉塞が疑われた。血液検査,心電図,全身の磁気共鳴断層検査(MRI),脳血管造影検査では異常がなかった。ウロキナーゼの全身投与と高圧酸素療法で網膜閉塞部の再疎通は得られなかった。プレドニゾロンとアスピリンなどの内服で視野が改善し,網膜動脈閉塞部の拡大が停止した。プレドニゾロンの減量で網膜動脈閉塞と視野欠損が悪化したので,ステロイドパルス療法を行った。視野変化はほぼ停止し,18か月後の現在まで病状は安定している。結論:両眼性の網膜動脈分枝閉塞症の本症例は,原因不明であり,抗凝固薬と副腎皮質ステロイドに反応せず,ステロイドパルス療法に抵抗した。
17年間経過観察しているLeber粟粒血管腫症の1例
著者: 野村昌弘 , 小森景子 , 山田恭子 , 尾関直毅 , 細田進悟
ページ範囲:P.567 - P.570
要約 目的:17年間経過を追ったLeber粟粒血管腫症の症例の報告。症例と経過:36歳男性が4年前からの右眼視力低下で受診した。前医ではCoats病といわれていた。矯正視力は右0.2,左2.0であった。右眼に黄斑から下耳側にかけて輪状の滲出斑と網膜血管瘤があった。粟粒血管腫症と診断し,網膜血管瘤に対し光凝固を行った。黄斑にかかる輪状網膜症は消退し,視力は改善した。以後17年11か月の間,同一医師が治療と経過観察をしている。新しい部位に血管瘤が出現し,現在まで23回669発の光凝固を行ってきた。現在の右眼矯正視力は1.0である。結論:Leber粟粒血管腫症では網膜血管瘤への光凝固が奏効し,滲出斑の消退が期待できる。本症例が示すように血管瘤の新規発症があり,短期間に完治しない可能性がある。
血管れん縮視神経網膜症の1例
著者: 土屋櫻 , 古賀規貴 , 村上晶
ページ範囲:P.571 - P.575
要約 目的:血管れん縮視神経網膜症の症例の報告。症例:53歳男性が呼吸困難の悪化でうっ血性心不全と診断され,緊急入院した。血圧は257/158mmHgであった。治療により血圧は正常化し,心不全と呼吸困難は改善した。入院から8日後に一過性の両眼視力障害があり,その3日後に眼科を受診した。矯正視力は右0.8,左1.2で,両眼とも乳頭が境界不鮮明で発赤・腫脹し,その周囲に軟性白斑と出血斑があった。黄斑部にかけて浮腫と星状斑があり,網膜動脈が狭細化していた。視野では両眼のMariotte盲点が拡大し,左眼の下鼻側に欠損があった。加療により全身状態が改善し,7週間後に退院した。網膜出血,白斑,乳頭から黄斑部にかけての浮腫は消退した。入院から7か月後の時点で,視力は左右とも1.2であり,Mariotte盲点の拡大はなくなったが左眼下鼻側の視野欠損は残った。結論:本症例は血管れん縮網膜症の重症型である血管れん縮視神経網膜症と診断される。これに対し,降圧治療は奏効したが,視野欠損は残存した。
専門別研究会
オキュラーサーフェス(ドライアイ研究会)
著者: 横井則彦 , 後藤英樹
ページ範囲:P.577 - P.579
本年度のドライアイ研究会では,ドライアイに精通している人なら誰でもその存在を知っており,しばしば治療に難渋するBUT(breakup time:涙液層破壊時間)短縮型ドライアイ(以下,short BUTドライアイ)がテーマとして取り上げられた。このドライアイの1型,疑い,あるいは亜型(角結膜上皮障害がみられない例も多く,そのような例ではドライアイの診断基準を満たさない)の典型例は,①極端に短いBUT,②角結膜上皮障害はないかあってもきわめて軽微,③強い眼不快感を訴える(乾燥感が強く目を開けていられない),④涙液貯留量や反射性涙液分泌量(SchirmerⅠ法)は正常,⑤点眼治療で効果のある例は少なく,しばしば上,下の涙点プラグ挿入が行われ,流涙があっても強い乾燥感よりはましということで経過観察されている,といった特徴がある。
興味あることに本疾患は,わが国では非常に注目されているが,世界的にその疾患概念が認められているわけではない。それは,わが国ではドライアイの中心メカニズムとして涙液の安定性(フルオレセインの破綻という目で見える指標)が重視されているのに対し,欧米では浸透圧上昇と炎症が重視されてきているというスタンスの違いによるものかも知れない。いずれにしても,ドライアイの専門家が最も苦戦を強いられる疾患の1つである本疾患が初めて研究会の舞台に取り上げられたことは喜ばしいことである。戸田郁子先生らが最初に報告された当初は,本疾患とアレルギー性結膜炎との関連が議論されたが(Toda I et al:Ophthalmology 102,1995),はたして今回,どんな知見が得られたのであろうか。
色覚異常
著者: 市川一夫
ページ範囲:P.580 - P.581
本研究会は,10月11日,京都国際会館Room B-1で開催された。演題は先天異常2題,後天異常5題の計7題で,そのうち2題は指定演題であった。
1.先天色覚異常の色誤認(指定演題) 中村かおる・他
中村らは,先天色覚異常の色誤認を色名呼称検査で正常者41名,先天色覚異常者209名に実施し,その結果をまとめ報告している。先天色覚異常者の内訳は,1型2色覚36名,1型3色覚30名,2型2色覚88名,2型3色覚55名であった。検査条件は,照明:D65を使用し200~500 lx,距離50cm,色票30mm×30mmサイズの12色相4色調および5段階の無彩色を順不同で提示し,赤・オレンジ・黄・茶・緑・青・紫・ピンク・白・灰色・黒の11語に限定して呼称させた。評価方法は,正常者の5%以上が答えた色名を正答,それ以外の答えを誤答としていた。
結果について,全色票の誤答率は1型・2型ともに2色覚>3色覚>正常色覚の順であった。正常者の色名呼称は色相により明確に区分され,ほとんどの色票で1~2個の色名に集中した。2色覚では,高彩度で青緑→灰色(1型2色覚)・紫(2型2色覚),黄緑→オレンジ,紫→青の色名呼称間違いが認められた。その他の色調では,青-紫,緑-茶の混同頻度が高かった。全色相にわたり,高明度をピンク・灰色・白,低明度を緑・茶・赤,低彩度を緑・茶・赤・ピンクなどばらばらの誤答であった。無彩色では,低明度→緑・茶・紫,高明度→ピンクに誤る傾向にあった。異常3色覚では,高彩度では正常色覚とほぼ同等の呼称が得られた。その他の色調では,2色覚と類似の誤答がみられた。異常3色覚では,2色覚に比べ程度が軽かったと報告していた。
地域予防眼科
著者: 平塚義宗 , 小野浩一 , 村上晶
ページ範囲:P.582 - P.584
はじめに
第27回専門別研究会「地域予防眼科」は2007年10月11日に開催された。長年本研究会の世話人を務められた赤松恒彦先生が4月に逝去された。赤松先生は地域予防眼科研究会の立ち上げから長きにわたって世話人を務められ,日本におけるロービジョンケア,視覚障害者のリハビリテーションや地域医療,国際医療協力の分野において多大な貢献をされた。この場をお借りして赤松先生の失明予防に対するご業績とご遺徳を偲び,心よりご冥福をお祈り申し上げます。
本年の演題は地域予防眼科の名にふさわしく,公衆衛生と関連したさまざまな分野から計6題(国際保健2題,ロービジョン関連2題,医療経済1題,ヘルスシステム関連1題)となった。当日は木曜日にもかかわらず,日本全国から地域医療学に関心のある多くの先生方が参加され,活発な質疑応答がなされた。座長は増田寛次郎先生(日本失明予防協会)が務めた。
連載 今月の話題
眼底自発蛍光
著者: 三田村佳典 , 山本修一
ページ範囲:P.433 - P.439
眼底自発蛍光検査は非侵襲的に網膜色素上皮におけるリポフスチンの分布を描出することができる。リポフスチンは視細胞外節の生理的な貪食に伴う代謝産物であり,眼底自発蛍光は網膜色素上皮の代謝機能を反映しているといえる。本稿では眼底自発蛍光検査における各疾患の特徴的な所見や視機能との関連について概説したい。
日常みる角膜疾患・61
穿孔性角膜外傷
著者: 能美典正 , 近間泰一郎 , 西田輝夫
ページ範囲:P.440 - P.442
症 例
患者:13歳,女性
主訴:左眼眼痛
現病歴:2005年11月12日,屋外でバドミントンをしていて,シャトルを拾おうとしゃがんだときに枯れ枝で左眼を受傷した。近医を受診し,角膜異物,角膜裂傷の診断で同日当科を紹介され受診した。当科初診時,視力は右1.0(1.0),左0.06(矯正不能)であった。左眼角膜に実質浅層に及ぶ幾筋もの擦過創と角膜瞳孔領下縁に前房に達する木片を認めた(図1)。虹彩は正円で穿孔創や出血は認めず,水晶体にも明らかな混濁はなかった。眼底は透見不能であったが,頭部X線写真,CT上は眼内に異物所見は認めなかった。
公開講座・炎症性眼疾患の診療・13
サルコイドーシス
著者: 北市伸義 , 合田千穂 , 宮崎晶子 , 大野重昭
ページ範囲:P.444 - P.449
はじめに
サルコイドーシスは全身,特に肺門部リンパ節に非乾酪性肉芽腫を形成する疾患であり,病変は肺,眼,皮膚に好発する1)。あらゆる民族・人種でみられ,好発年齢は男女の20~30歳代と女性の50~60歳代である2)。病因は不明であるが,外来要因として樹木花粉やコピー機のトナー粒子などの無機粒子,粉塵なども指摘されている。ニューヨーク同時多発テロのレスキュー隊員に発症者が多いとの報告もある(図1)。
現在わが国では内眼炎(ぶどう膜炎)の原因疾患として最も頻度の高い疾患であるが(図2),なかには全身所見を伴っていないものの,眼所見からサルコイドーシスが強く疑われる場合もある。近年患者数が増加しており,内科や皮膚科との連携が重要な疾患である。厚生労働省の特定疾患に指定されている。
網膜硝子体手術手技・16
開放性眼外傷(1)分類と病態
著者: 浅見哲 , 寺崎浩子
ページ範囲:P.450 - P.455
はじめに
開放性眼外傷は,時間を問わずやってくる緊急疾患であり,常日頃から対処法に関するイメージをもっておくことは必要である。病態が多彩であり傷害部位の把握が困難で,手術を行ってみたら思わぬ場所にまで傷害が及んでいるということも多い。受傷原因,眼組織の状態によっては時間的余裕がなく,非常に限られた時間のなかで眼組織の状態を診断し,治療に結びつけていかなければならない。
近年の網膜硝子体手術の手技,器具,手術補助剤などの進歩により,重症な眼外傷でも解剖学的,かつ視機能的によい結果が残せるようになってきた。本号からは開放性眼外傷の病態,診断,具体的な治療法について述べることとする。
今回は開放性眼外傷の分類とそれぞれの病態の違いについて解説する。
もっと医療コミュニケーション・4
コミュニケーションツールとしてのEBM
著者: 綾木雅彦
ページ範囲:P.586 - P.589
EBMという医療の方法論
「患者のための医療」という雑誌が2002年に篠原出版新社から発刊されました。言われてみれば当たり前のことなのですが,この頃から世間では大きく扱われるようになってきました。『患者は何でも知っている―EBM時代の医師と患者』(斉尾武郎(監訳),中山書店)という,ドキッとするような題名の本が2004年に出版されました。英語の題名は“The Resourceful Patient”,つまり非常に情報源がいま多いということです。そこで考えてみますに,いま期待されている医師のひとつの雛形は,エビデンスが活用できて,患者のための医療を心がけている医師であるといってもよいのではないでしょうか。
臨床報告
糖尿病網膜症に対して観血的治療を施行したPrader-Willi症候群の1例
著者: 坂本真季 , 坂本英久 , 久保田敏昭 , 石橋達朗
ページ範囲:P.597 - P.602
要約
目的:糖尿病網膜症に対して手術を行ったPrader-Willi症候群症例の報告。症例:23歳男性が両眼の視力低下で受診した。3歳のときに肥満や特異な顔貌からPrader-Willi症候群が疑われ,4歳のときに15番染色体長腕の部分欠失があり,本症候群の診断が確定した。10歳で糖尿病と診断され,9か月前に左右とも1.0の視力があった。所見と経過:身長151cm,体重97kgで,左右眼とも矯正視力は0.04,眼軸長は約21mmで,角膜屈折力は左右眼ともほぼ47Dであった。眼底に増殖糖尿病網膜症があり,右眼には網膜中心静脈閉塞症,左眼には硝子体出血が併発していた。右眼に汎網膜光凝固を行った後,左右眼に硝子体手術と水晶体乳化吸引術を行い,硝子体腔をシリコーンオイルで充填した。右0.05,左0.2の最終視力が得られた。結論:Prader-Willi症候群に併発した糖尿病網膜症に対して硝子体手術が奏効したが,精神発達遅延などが関係する術前・術後の管理に問題があった。早期発見と早期治療が望まれる。
Acute macular neuroretinopathyの1例
著者: 久保寛之 , 林敏信 , 月花環 , 大熊康弘 , 小川智一郎 , 水野かほり , 常岡寛
ページ範囲:P.603 - P.607
要約 目的:急性黄斑部神経網膜症(acute macular neuroretinopathy:AMNR)の症例の報告。症例:39歳女性が7週間前に突発した左眼の視力低下で受診した。矯正視力は右1.5,左0.4であり,左眼の黄斑部に円形の赤色斑があった。走査レーザー顕微鏡で赤色斑に一致する低反射があった。Amslerチャートの中央部が光って見え,視野検査で中心感度の低下が検出された。多局所網膜電図では左眼の中心部に応答低下があった。光干渉断層計では異常所見がなく,磁気共鳴画像検査(MRI)では頭蓋内と視神経に異常はなかった。以上の所見から,左眼のAMNRと診断した。以後3か月間,左眼の所見に変化はない。結論:AMNRの診断には,走査レーザー顕微鏡と多局所網膜電図が有効なことがある。
べらどんな
めくばせ
著者:
ページ範囲:P.439 - P.439
豚はときどき諺に登場する。「豚もおだてりゃ木に登る」は日本の例だし,英語には“pigs will fly”というのがある。直訳すると「豚が空を飛ぶであろう」だが,「(そんなことが)あるはずがない,まず不可能」が実際の意味である。
豚の目は小さい感じがする。英語のpig-eyedという表現は,「くぼんだ小さな目をしている」というときに使われる。
今月の表紙
格子状角膜ジストロフィ
著者: 寺内渉 , 西田輝夫
ページ範囲:P.443 - P.443
患者は44歳男性,2006年10月に近医を受診し,格子状角膜ジストロフィと診断され,治療的レーザー角膜切除術または角膜表層移植手術目的で当院を紹介され受診した。初診時所見では,視力は右0.08(0.4P),左0.08(0.5),グレアテストは右25.0%,左12.5%であった。両眼とも角膜深層と表層に淡い混濁を伴っていた。11月20日に角膜表層の淡い混濁を切除するため,右眼に治療的レーザー角膜切除術を施行した。切除量は角膜上皮45μm,角膜実質81μmで,術後視力は(1.2×HCL)であった。
写真は初診時の徹照法写真である。撮影のポイントは反帰光が最大の明るさになる視神経乳頭の反射の位置に固視を誘導して撮影することである。また,スリット光を瞳孔縁までシフトし,スリット長・幅を病変の邪魔にならないようにカットすることもポイントの1つである。具体的にはスリット長3mm,スリット幅8mm程度で撮影するのが望ましい。強膜散乱法や細いスリットまたは太いスリットの直接照明法,拡散照明法を併用することで病変の全体像を捉えることができる。
書評
がん医療におけるコミュニケーション・スキル―悪い知らせをどう伝えるか[DVD付] フリーアクセス
著者: 西條長宏
ページ範囲:P.553 - P.553
医師が患者とよくコミュニケーションをとり,適切に病状と治療の方向性などを説明し患者の理解と同意を得たうえで,検査や治療を行うことはがん医療の基本である。また,医師と患者のコミュニケーションは人対人のものであり,そこには個人の性格や考え方が反映されることは当然である。患者とのコミュニケーションのなかでも「悪い知らせの伝え方」についてはさまざまな研究がなされており,欧米では確立された理論に基づくトレーニングが行われている。
一方,わが国ではそのような教育や訓練を受けたことのある医師はほとんどなく,約半数が「悪い知らせを伝えている医師に立ち合った」程度の“教育”しか受けていない。すなわち,患者とのコミュニケーションは経験に基づくものという考え方が中心になってきていた。しかし,それではやっていることが正しいか否か誰も自信がもてないとともに,いたずらに患者の不安感をあおったり,逆に過度の希望を抱かせたりしていることも多いと推定される。というのは,医師が自信のない場合は,患者にとって好ましくない情報についての議論を避けたり,根拠のない楽観論をせざるをえないことによる。結果的に医師は疲弊し,ますますストレスを感じる状態に陥ってしまう。
標準眼科学 第10版 フリーアクセス
著者: 石橋達朗
ページ範囲:P.584 - P.584
本教科書は1981年に初版が出版された。私はこの年,ちょうど大学院を卒業した。臨床に戻る私にとって,最新の,しかも標準的な眼科学を改めてざっと復習するのに,本書は最適の教科書であった。
それから現在までの26年もの間に,この書は9回も改訂を重ねている。より新しい眼科学の知見を常に取り入れていく,という姿勢には脱帽である。特に今回の第10版は編者が「記念すべき第10版」と記しているように,かなり綿密な吟味のもと,改訂がなされている。
やさしい目で きびしい目で・100
女は損?
著者: 目時友美
ページ範囲:P.585 - P.585
女性なら誰しもが少なくとも一度は,女として生まれてきたことに対してどうしようもない思いをしたことがあるのではないでしょうか。
私には弟がいますが,そのためか,家では小さな頃から男女の違いをはっきりさせて育てられた気がします。食事の準備や後片付けなど「女の子なら手伝いなさい」と言われ,男ならゆっくりテレビを見ていてもいいのかと疑問を持ちながら生活していました。
ことば・ことば・ことば
黒
ページ範囲:P.593 - P.593
ある国際学会で,腫瘍学の専門家による特別講演がありました。「眼科医にもっと常識を」という主催者の趣向でした。
目新しい話題がいくつもあったなかに,「転移をする癌としない癌がある」のが印象的でした。中枢神経の腫瘍はまず転移をしないし,脈絡膜の悪性黒色腫も同じだそうです。したがって,黒色腫がある眼を早期摘出しても,生命予後には無関係だということになります。
--------------------
あとがき フリーアクセス
著者: 西田輝夫
ページ範囲:P.626 - P.626
Asia Corneal Societyが結成され,第1回の集まりがシンガポールで開かれました。米国を中心とする招待講演者に加え,中国とインドという人口の多い国はもちろん,韓国,台湾やタイ,インドネシア,ベトナム,フィリピンなどから約400人の参加者がありました。また今年の6月にはWorld Ophthalmology Congressが香港で開催されます。いままでのヨーロッパとアメリカを中心とする眼科に加え,アジアの諸国が大きく発展して世界の眼科学に貢献し始めてきていることを熱い思いとともに実感しました。海外での学会に出席して感じるのは,共通のプラットフォームとして英語が用いられていることで,英国やアメリカの言語としての英語というよりも,世界共通語としての英語という位置づけが急速に拡がっているように思います。
今月号も,第61回日本臨床眼科学会で発表された研究の原著と専門別研究会の報告を中心にお届けします。日本臨床眼科学会は,眼科学全体を見渡す幅広いシンポジウム,教育講演やインストラクションコースなどに加え,多くの一般演題が報告され,わが国での臨床眼科の発展に大きく貢献しています。急速に展開していく新しい治療法や手術術式あるいは診断技術などの最前線の講演に加え,稀有な眼疾患などの経験について報告され,討議されます。これらの報告が,原著として雑誌「臨床眼科」に掲載され記録されることで,将来にわたり参照することができ,同じような症例を経験されるであろう眼科医の診断や治療法の選択に将来大いに参考になります。世界での眼科学の進歩を知ることと同時に,わが国の自然・社会環境や医療制度のなかでの眼科医療の共有という観点で,雑誌「臨床眼科」がお役に立つものと信じます。
基本情報
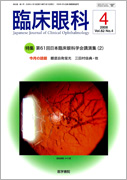
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
