2011年,「眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識」という増刊号を刊行した。そこでは,発刊以前の5年間に,臨床眼科分野において変化した内容のみを選択的に記述した。読者が習得すべき重要な内容を明らかにするだけでなく,その量を最小限にするためである。想定した読者は中堅眼科医であり,多忙な彼らが,日常業務の合間に短時間で知識のアップデートを可能にすることを狙ったものであった。おかげで,多くの中堅医師のみならず,研修医からも好評を博することができたが,このことはこういう種類の情報が求められていることを,我々に深く認識させてくれた。
さて,先の刊行から7年が過ぎ,新たなものが必要であるという声が寄せられるようになってきた。その理由は3つに分けられる。
雑誌目次
臨床眼科72巻11号
2018年10月発行
雑誌目次
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.5 - P.5
序文 フリーアクセス
著者: 坂本泰二
ページ範囲:P.7 - P.7
1.屈折/調節の異常・白内障
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.13 - P.13
1)検査
視力検査:コントラスト感度・コントラスト視力検査
著者: 南雲幹
ページ範囲:P.14 - P.19
ここが変わった!
以前の常識
●日常臨床の視力検査では白黒の高コントラストのランドルト環視標を用い,視力を評価するが基本である。
現在の常識
●われわれの日常生活においてはさまざまなコントラストのものを見ており,日常視での視覚の質(QOV)が問われる現在,従来の視力検査による評価では限界があり,精密に視機能を判定するためコントラスト感度検査のニーズはさらに高まっている。
●2018年4月に診療報酬が改定され,空間周波数特性(MTF)を用いたコントラスト感度検査の算定が可能となった。ただし算定は「水晶体混濁があるにもかかわらず矯正視力が良好な白内障患者で水晶体再建術の手術適応の判断に必要な場合に,当該手術の前後においてそれぞれ1回に限る」とされている。
学童近視
著者: 長谷部聡
ページ範囲:P.20 - P.24
ここが変わった!
以前の常識
●学度近視の進行予防は夢物語である。
●近視も乱視も眼鏡は低矯正とすべきである。
●累進屈折力レンズは老視矯正に処方する。
現在の常識
●学度近視の進行は予防できる。強力な効果と安全性を備える予防治療は確立されていない。
●近視も乱視も完全矯正にはメリットがある。
●累進屈折力レンズは,近見内斜位を示す小児で良い適応である。
2)屈折異常の治療
コンタクトレンズ処方
著者: 植田喜一
ページ範囲:P.25 - P.29
ここが変わった!
以前の常識
●オルソケラトロジーレンズの対象年齢は20歳以上とする(小児には処方すべきではない)。
●カラーコンタクトレンズ(CL)はトラブルが多いので処方しない。
現在の常識
●オルソケラトロジーの対象年齢は原則として20歳以上とし,未成年者には慎重処方とする。
●酸素透過性の高い素材で色素をサンドウィッチ状に挟んだ構造のカラーCLが開発されたので,透明なCLと同様に処方できるカラーCLがある。
近視矯正手術
著者: 山村陽
ページ範囲:P.30 - P.33
ここが変わった!
以前の常識
●LASIKのフラップ作製には,マイクロケラトームと呼ばれる金属ブレードが用いられていたが,フラップの大きさや厚みの精度が低かった。
●LASIKではフラップ作製後にエキシマレーザーで近視矯正を行う。
現在の常識
●フェムトセカンドレーザーを用いると,高い精度のフラップが作製できるようになった。
●フェムトセカンドレーザーだけで近視矯正ができるような術式が登場した。
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2023年10月)。
白内障手術の考え方
著者: 黒坂大次郎 , 五日市そら
ページ範囲:P.34 - P.37
ここが変わった!
以前の常識
●すでに白内障手術の安全性・確実性はかなり高いレベルに到達した。
●乳幼児の白内障手術では,視機能獲得のためには眼内レンズのほうがコンタクトレンズ矯正よりも有利である。
●性能が向上した高機能眼内レンズが登場し広く普及する。
現在の常識
●眼内圧をコントロールできる白内障手術機器,水晶体囊拡張リング(CTR)の普及などで,難症例でも安全性・確実性がさらに高まるとともに,一部眼内レンズで前眼部毒性症候群(TASS)などが大規模に生じ危険性も明らかになった。
●乳幼児の白内障手術では,眼内レンズ,コンタクトレンズ矯正による視力予後に差はなく,眼内レンズ挿入すると再手術が多くなり,コンタクトレンズ矯正のほうが望ましい。
●多焦点眼内レンズは,トーリック型も登場するなど一定の成績を収めたものの,近見負荷度数やさまざまな設計デザインのものへと改良が続けられ,いろいろな選択肢が増えるとともに患者のライフスタイルと合わせることがさらに重要となった。
単焦点眼内レンズ
著者: 松島博之
ページ範囲:P.38 - P.42
ここが変わった!
以前の常識
●白内障手術時の単焦点IOLは,3ピースと1ピースが混在していた。
●カートリッジにセットアップするタイプのインジェクターを使用していた。
●水晶体囊破損時はIOL縫着が主流であった。
現在の常識
●単焦点IOLは1ピースが主流となった。
●IOLがインジェクターにセットアップされているプリロードタイプの製品が増加し,販売数を伸ばしている。
●水晶体囊破損時の新しい固定方法として強膜内固定法が開発され,増加傾向である。
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2023年10月)。
老視に対する外科的治療
著者: 戸田郁子
ページ範囲:P.43 - P.49
ここが変わった!
以前の常識
●角膜や強膜に対する老視の外科的治療は過去にさまざま試みられ,一定の効果があると報告されていた。
●多焦点IOLは,副次作用のため適応は限定的であった。
現在の常識
●角膜や強膜に対する治療は効果が不十分であることがわかった。
●白内障眼に対しては,水晶体に対する外科治療(多焦点IOL,EDOF IOL)の改良が進み,適応選択と術前説明を適切に行えば,第一選択となりうる。
●非白内障眼では術前シミュレーションで良好であれば,レーシックによるモノビジョンが外科的治療ではほぼ唯一の選択肢である。
Special Lecture
有水晶体眼内レンズの最新動向
著者: 神谷和孝
ページ範囲:P.50 - P.52
はじめに
有水晶体眼内レンズは,レンズの固定位置によって前房型(隅角支持型,虹彩支持型)と後房型(毛様溝固定型)に分類されるが,2015年の日本白内障屈折矯正手術学会による多施設共同研究の結果では,後房型有水晶体眼内レンズ〔implantable collamer lens(ICL)またはphakic IOL〕(Visian ICL:STAAR Surgical社)の使用がすでに96%となっており,現在ではほぼ後房型に移行している1)。2010年2月2日に厚生労働省より正式に認可を受けた。レーシックに比較して,安全性・有効性が高いだけでなく術後視機能の優位性が報告されている2)。その一方,ICLの問題点として術後白内障の発症や瞳孔ブロック予防を目的とした術前レーザー虹彩切除の必要性があった。
これらの問題を解決すべく,清水らは世界に先駆けてレンズ中央部に直径0.36mmの貫通孔を有する有水晶体眼内レンズ(hole ICL,KS-AP)を開発し,今や同レンズが市場を席捲しつつある。本稿では,最新世代の有水晶体眼内レンズであるhole ICLの臨床成績,適応拡大へ向けた取り組みや今後の展開について紹介したい。
心療眼科の重要性
著者: 若倉雅登
ページ範囲:P.53 - P.55
はじめに
眼科は「視覚」という高度に発達した感覚器を扱った診療科と位置づけることができる。眼球や視覚に関する身体科である。20世紀後半から劇的な進歩を遂げたヒトの大脳生理学は,脳への情報入力の90%近くが視覚からであることを明らかにした。
一方,自分自身が生きるのに精一杯で,国のセイフティネットはほとんど働かない後発開発途上国では,ある人が何らかの原因で失明すると1年以内に死亡する確率は80%以上だといわれる。
このことは,視覚が人の一生にきわめて重大な役割を担っていることの証左で,その視覚系に障害をきたしたり,視覚情報の一次的受容器である眼球や,その周辺に何らかの理由で不都合が生じたりすると,生活視機能(臨床で計測される視機能とは異なり,質的,時間的要素も含めた人の生活上で用いられる実践的視機能を意味する筆者の造語)は明らかに低下する。それは,視機能そのものの問題にとどまらず,2次的障害,すなわち失明恐怖,経済的不安はもとより,自尊心が踏みにじられ,生活意欲も低下するなど心的問題に結びつきやすい。
また,種々の精神的問題が非器質的,もしくは心因性などと形容される視覚障害や視器の頑固な不快感を惹き起こされることを臨床上で経験することも稀ではない。
人々の社会生活にこれほど本質的な意味をもつ視覚が障害され,あるいは障害に瀕した個人が,その状態に適応することは容易ではない。にもかかわらず,従来の眼科医療ではそこまで斟酌した対応は,ほとんどなされてこなかった。つまり,従来の眼科臨床においては,必要だとわかってはいても,実際には心身医学的対応が行われてこなかったと考えられる。
ただし,ロービジョンにおいては心理臨床の必要性が多少は語られてはきた1,2)。しかし,ロービジョンに限らず,視覚にかかわる広範囲の眼科臨床領域において,また,精神医学的な疾患やそこで使用される神経用薬の影響において,「視覚の心身医学」の照明を当てる必要性を筆者らは感じている。ここに,「心療眼科」を標榜し,あるいは「心療眼科研究会」を発足させ3),その重要性を語ろうとする動機づけがある。
そして,時代の要請や時代の変化も関連してか,こうした問題意識が次第に無視できない大きさになっており,心療眼科に関心を寄せる眼科医が増加していることは確かである。本稿は,筆者自身が行っている心療眼科の実際の外来を描写しながら,心療眼科の重要性,必需性を認識していただくことを目的として記述する。
2.眼表面・角膜疾患
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.57 - P.57
1)検査
前眼部3次元画像解析
著者: 上野勇太
ページ範囲:P.58 - P.61
ここが変わった!
以前の常識
●前眼部診察の際には細隙灯顕微鏡で観察し,前眼部写真を撮影することで記録に残していた。写真は平面的な病変の広がりや色調を評価するのに適しているが,角膜厚や病変の深さなど前後方向の情報を記録しづらいという欠点があった。
現在の常識
●OCTの技術が前眼部検査に応用された。前眼部OCTを用いることで,非接触式かつ短時間での撮影により,混濁組織であっても高解像度の断面像を取得可能となった。
●前眼部OCTは角膜パーツ移植の術後経過観察において不可欠な検査であり,その他の前眼部疾患においても非常に有用な情報が得られる。
前眼部画像解析による角膜疾患の新知見
著者: 山口剛史
ページ範囲:P.62 - P.69
ここが変わった!
以前の常識
●多くの角膜混濁疾患は,混濁で視力が低下すると思われていた。
●角膜混濁眼や角膜移植後など不正乱視が非常に強い眼では,高次収差解析はできなかった。
現在の常識
●角膜混濁眼では,疾患ごとに特徴的な不正乱視パターンがあることがわかった。
●角膜混濁眼では高次収差が増えていて,角膜混濁と高次収差の両方で視力が低下する。
●角膜混濁眼の一部で,ハードコンタクトレンズなどで高次収差を低減することで劇的に視力が改善する症例がある。
●高次収差を考慮しなければ,角膜移植後に視力の改善が得られないことがある。
2)診断・治療
アレルギー性結膜疾患の診断と治療
著者: 岸本達真 , 福田憲
ページ範囲:P.70 - P.73
ここが変わった!
以前の常識
●アレルギー性結膜炎の治療の効果判定や,薬剤選択に有用な自覚症状の評価法が存在しなかった。
●アレルギー性結膜疾患の診断において,眼局所のⅠ型アレルギーを証明するために結膜の好酸球を同定する必要があった。
●春季カタルの治療はステロイド点眼薬を中心に用いられてきたが,眼圧上昇の副作用があった。
●アレルギー性結膜炎の治療は,対症療法が主であった。
現在の常識
●アレルギー性結膜疾患QOL調査票が開発された。
●眼局所のⅠ型アレルギーを証明する方法として,涙液総IgE迅速検査キットが用いられるようになった。
●アレルギー性結膜疾患のガイドラインが改訂され,春季カタルの治療に免疫抑制点眼薬が用いられるようになった。
●スギ花粉症の治療法に抗原特異的免疫療法が加わった。
マイボーム腺機能不全の診断と治療
著者: 有田玲子
ページ範囲:P.74 - P.78
ここが変わった!
以前の常識
●マイボーム腺機能不全(MGD)の診断は眼瞼縁の所見,マイボーム腺分泌脂(meibum)の色や粘度など,検者の主観や熟練に頼るものが多く,検者によるばらつきが大きかった。
●MGDの治療はステロイド眼軟膏,抗菌薬眼軟膏,人工涙液点眼など対症療法が中心に処方されてきたが,長期的に効果を実感できるものがほとんどなく,患者の満足を得られないことが多かった。
現在の常識
●MGDの診断はマイボグラフィ(マイボーム腺の形態観察),インターフェロメトリー(涙液油層観察)の出現により客観的に再現性高く診断することができ,検者によるばらつきが減少した。治療効果のモニタリングも可能となった。
●MGDの治療は温罨法やリッドハイジーンの有効性を示すエビデンスが次々と示され,“脂が足りないタイプ”のドライアイをターゲットにした治療法が次々とリリースされ,根治を目指すものとなっている。
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2023年10月)。
ドライアイに対するTear Film Oriented Diagnosis
著者: 横井則彦
ページ範囲:P.79 - P.83
ここが変わった!
以前の常識
●2006年の診断基準では,ドライアイは,自覚症状,涙液異常〔涙液層破壊時間(BUT)異常(5秒以下),または,シルマーテスト1法異常(5mm以下)〕,上皮障害で診断されていた。そのため検査結果から,涙液減少型とBUT短縮型のドライアイを区別することが可能であった。
現在の常識
●2016年の診断基準では,ドライアイは,自覚症状,BUT異常(5秒以下)で診断されるようになったが,ドライアイのサブタイプを分類することができない。
●眼表面の層別診断(TFOD)は,涙液層の破壊パターンに基づいて,①その破壊をもたらす眼表面の不足成分の看破,②ドライアイのサブタイプ分類,③破壊を防ぐことでドライアイを治療しうる眼表面の層別治療(TFOT)の提案の3つを可能にする方法である。
眼表面摩擦関連疾患の診断と治療
著者: 山口昌彦
ページ範囲:P.84 - P.90
ここが変わった!
以前の常識
●以前,ドライアイの病態として「眼表面摩擦」という概念は一般臨床において広く浸透していなかった。
現在の常識
●現在,ドライアイの病態の1つとして,瞬目に伴う「眼表面摩擦」亢進が注目されるようになってきた。
●眼表面摩擦関連疾患の病態は複合的で,上輪部角結膜炎(SLK),リッドワイパー結膜上皮症(LWE),糸状角膜炎などがあり,治療には,ドライアイ治療薬のレバミピド点眼薬(ムコスタ®点眼薬)やジクアホソル点眼薬(ジクアス®点眼薬)が有効である。
円錐角膜の診断と治療
著者: 前田直之
ページ範囲:P.91 - P.96
ここが変わった!
以前の常識
●円錐角膜は非炎症性疾患で,その進行は自然に止まるのを待っていた。
●角膜生体力学特性を測定できなかった。
●ハードコンタクトレンズが装用できなければ角膜移植しか治療法はなかった。
現在の常識
●円錐角膜は炎症性疾患で進行を抑制するために,目を擦る癖を止めさせアレルギー疾患を治療する。それでも進行する場合は角膜クロスリンキングの適応となる。
●角膜生体力学特性は測定できる。
●ハードコンタクトレンズと角膜移植の間に角膜リング,有水晶体眼内レンズ,特殊コンタクトレンズなど,治療のモダリティが多彩になりつつある。
眼表面疾患の再生医療
著者: 大家義則
ページ範囲:P.97 - P.100
ここが変わった!
以前の常識
●難治性疾患である角膜上皮幹細胞疲弊症に対する一般医療としては,他家角膜輪部移植が最も一般的である。
●角膜上皮幹細胞疲弊症に対して臨床研究として培養角膜,もしくは口腔粘膜上皮細胞シート移植を行うことができる。
現在の常識
●自家培養上皮細胞シートを用いた治験が終了し,その成果をもとに再生医療製品として承認される可能性がある。
●iPS細胞由来上皮細胞シート移植の臨床応用開始が予定されている。
角膜パーツ移植
著者: 稲富勉
ページ範囲:P.101 - P.108
ここが変わった!
以前の常識
●角膜移植は全層角膜移植が主体であった。
●角膜混濁や水疱性角膜症にも全層角膜移植術が第一選択であった。
●トレパンによる角膜切開が標準手技であった。
●角膜上皮移植には輪部移植や角膜上皮形成術が唯一の方法であった。
現在の常識
●病的部位のみを置換するパーツ移植が発展している。
●水疱性角膜症にはDSAEKやDMEKなどの角膜内皮移植が第一選択である。
●エキシマレーザー,マイクロケラトーム,フェムトセカンドレーザーなどが角膜移植に応用されている。
●培養角膜上皮移植や培養口腔粘膜上皮移植などの再生医療が実現している。
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2023年10月)。
フェムトセカンドレーザーによる角膜移植
著者: 妹尾正
ページ範囲:P.109 - P.115
ここが変わった!
以前の常識
●角膜移植とは角膜全層移植とはほぼ同義語であった。
現在の常識
●トレパンブレードを用いた角膜移植が50年以上用いられていたが,FSLによる角膜移植によって切開形状をカスタマイズできるようになった。
●これまで角膜移植では最低でも16〜32針行っていた縫合が,0〜16針で行えるようになった。
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2023年10月)。
羊膜移植術
著者: 石垣理穂 , 中村隆宏
ページ範囲:P.116 - P.119
ここが変わった!
以前の常識
●先進医療として行われ,自施設で採取した羊膜を移植治療に用いることができる。
●採取を行えない施設では,羊膜移植術を実施できない。
現在の常識
●眼表面疾患に対して,日本眼科学会の羊膜移植術者認定を受けた眼科専門医が,地方厚生局に羊膜移植実施施設として届け出た施設で,日本組織移植学会認定羊膜バンクから斡旋を受けた羊膜を用いて行う保険診療である。
Special Lecture
微生物学からみた感染性角膜炎
著者: 鈴木崇
ページ範囲:P.120 - P.121
はじめに
感染性角膜炎は,透明組織である角膜に微生物が増殖し,免疫反応を引き起こし,炎症を生じた状況である.重篤な症例では,角膜混濁,角膜穿孔,角膜高度乱視を引き起こし,視力が低下する。治療は,原因微生物を検出し,その原因微生物を死滅させる抗微生物薬の投与が必要となる。
最新の微生物学の進歩により,感染症の病態が少しずつ明らかになりつつあり,最新の微生物検出方法や新規治療法の開発が行われている。感染性角膜炎においても研究が行われており,最新の情報が明らかになっている。本稿では,感染性角膜炎の最新の情報について感染性角膜炎の病態,微生物検出方法,治療法に分けて解説する。
3.緑内障
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.123 - P.123
1)検査
前眼部の診察法
著者: 藤代貴志
ページ範囲:P.124 - P.128
ここが変わった!
以前の常識
●隅角,濾過胞の観察は,細隙灯検査が一般的である。
●UBM検査を用いての濾過胞の検査は,感染リスクからやりにくい。
現在の常識
●AS-OCTの進化で,隅角,濾過胞の検査が正確に非侵襲的かつ短時間で可能になる。
視野の解析法
著者: 内藤知子
ページ範囲:P.129 - P.132
ここが変わった!
以前の常識
●自動静的視野検査では中心30°ないしは24°以内を検査対象として,グレースケールの濃淡で評価することが多かった。
現在の常識
●初期緑内障性視野障害の判定基準としてAnderson-Pattelaの分類を参考にし,特にパターン偏差の連続する異常と眼底との相応性に注目し判断を行う。
●今後,増加が予想される近視眼緑内障においては中心10°以内の評価が重要である。また,OCTの急速な普及により「前視野緑内障」の発見が増加しているが,その場合にも検査のプログラム選択に注意が必要である。
●視野検査のトピックスとして,ヘッドマウント型視野計アイモが上市された。頭にヘルメットのように装着できる視野計で,従来,測定困難であった症例での使用が期待される。
緑内障とOCT
著者: 齋藤瞳
ページ範囲:P.133 - P.137
ここが変わった!
以前の常識
●OCTは黄斑部疾患診断用の機器であり,緑内障分野ではあまり役に立たないと考えられていた。
●緑内障性変化は乳頭形状や乳頭周囲網膜神経線維層変化のみで判断していた。
現在の常識
●TD-OCTからSD-OCTへと進化したことにより,OCTは緑内障診断(特に早期緑内障において)にも必須の補助診断機器と位置づけられている。
●乳頭周囲のみならず,黄斑部の解析も重要と考えられている。
2)診断
前視野緑内障の診断
著者: 中西秀雄
ページ範囲:P.138 - P.143
ここが変わった!
以前の常識
●緑内障の診断においては,視野障害(機能的異常)と視神経障害(構造的異常)を一対として扱い,この両者が存在することおよび両者の障害位置の整合性を確認したうえで,診断を下すことが必要と考えられていた。
現在の常識
●通常の視野検査で緑内障性視野障害を認めない場合でも,眼底検査で緑内障性構造障害が確認されれば,「前視野緑内障」(PPG)と診断して管理するようになった。
●緑内障性構造障害の補助診断に用いられる眼底3次元画像解析装置は,OCTが最も一般的となった。
●「通常の視野検査」で緑内障性視野障害を認めない場合に取りうる「特殊視野検査(機能選択的視野検査)」の選択肢が広がった。
●黄斑部に構造障害を伴う症例では,ハンフリー自動視野計10-2プログラムに代表されるような,「精密中心視野検査」の追加を考慮するべきである。
緑内障性視神経症の画像診断
著者: 東出朋巳
ページ範囲:P.144 - P.150
ここが変わった!
以前の常識
●緑内障性視神経症の画像診断のターゲットは,視神経乳頭形状と乳頭周囲網膜神経線維層厚であった。
現在の常識
●緑内障性視神経症(GON)の画像診断の主要ターゲットは乳頭周囲網膜神経線維層厚と黄斑部網膜内層厚であり,視神経乳頭深部構造,視神経乳頭部血流などが新たに加わった。
眼圧の動態
著者: 坂田礼
ページ範囲:P.153 - P.157
ここが変わった!
以前の常識
●生活習慣に基づいた眼圧測定(日中は座位,夜間は仰臥位)で,眼圧日内変動パターンを把握することが主流であった。
●仰臥位でも眼圧を測定できる代表的な機器としては,トノペン,パーキンス,PTGであり,使用経験が浅いと測定誤差が大きく出た。また,それぞれ点眼麻酔が必要であった。
●緑内障点眼薬のなかで,主経路に作用する薬剤はピロカルピン塩酸塩のみであった。
●毛様体光凝固術は,眼球癆になるリスクがあった。
現在の常識
●2012年頃からコンタクトレンズセンサーに関する論文が出始め,眼圧日内変動パターンを連続的に把握できるようになってきている。ただし,わが国では未承認であり,従来方式の眼圧日内変動検査は行われている。
●2012年に点眼麻酔が不要のアイケアPRO手持眼圧計(TA03,ICARE FINLAND社)が登場したことで,仰臥位でも簡便に眼圧測定を行うことができるようになった。
●2011年以降で新規に販売された緑内障点眼薬(配合剤は除く)としては,α2刺激薬,ROCK阻害薬があり,特に後者は主経路からの房水排出にかかわる薬剤として注目を集めている。
●2017年からマイクロパルスレーザー(Cyclo G6)を用いる毛様体光凝固術が可能となり,これは眼球癆にならないと考えられている。
緑内障診断に近視が与える影響
著者: 山下高明
ページ範囲:P.158 - P.162
ここが変わった!
以前の常識
●OCTは緑内障の診断精度が高く,誤判定は眼底写真より少ない。
現在の常識
●近視眼では,OCTによって緑内障と誤判定されるケースが少なくない。
●眼底の近視性変化は多岐にわたり,それぞれ異なる偽陽性所見を呈する。
●近視の増加で緑内障病型ごとの有病率が変化している。
3)治療
原発閉塞隅角緑内障の治療
著者: 酒井寛
ページ範囲:P.163 - P.168
ここが変わった!
以前の常識
●POAGと比べると,PACGは稀であるので疾患としての重要性も低い。
●急性原発閉塞隅角症やPACGの治療はレーザー虹彩切開術を行う。白内障手術は主要な選択肢ではない。
●わが国において,アルゴンレーザー虹彩切開術後の合併症として水疱性角膜症が注目されている。
●エビデンスレベルの高いランダム化比較試験により,急性発作眼に対してはレーザー虹彩切開術と比べて水晶体再建術のほうが優れていることが示されていたが,その他の病型においての研究はない。
現在の常識
●有病率は低いが,PACGの失明率はPOAGの数倍あるので,失明者数はほぼ同数であり,予防可能な疾患であることを加味すると重要性はより高い。
●各国のガイドラインにおいて,レーザー虹彩切開術は現在でも急性原発閉塞隅角症やPACGの治療の基本とされているが,水晶体再建術も併記されている。
●欧州のガイドラインでは,Nd-YAGレーザー虹彩切開術が推奨されており,わが国のガイドラインでもアルゴンレーザーを併用するNd-YAGレーザー虹彩切開術が提案されている。
●ランダム化比較試験により,急性発作眼に加えて慢性の原発閉塞隅角症およびPACGにおいても,レーザー虹彩切開術と比べて水晶体再建術のほうが優れていることが示された。
緑内障治療薬
著者: 本庄恵
ページ範囲:P.169 - P.173
ここが変わった!
以前の常識
●原発開放隅角緑内障の目標眼圧は,緑内障病期に応じて設定することが多かった。
●主流出路房水流出促進薬を日常診療で使用することは少なかった。
●多剤併用療法では単剤併用が基本であった。
●緑内障点眼で眼表面,眼瞼などの副作用はある程度はやむをえず,基本的には休薬,もしくは観血的治療の検討などが対処法であった。
現在の常識
●個別化医療の選択という考えが進み,目標眼圧は病期を含めた緑内障の進行にかかわる危険因子の評価から総合的に設定されることが提唱されるようになっている。
●主流出路房水流出促進薬など新規機序の緑内障治療薬が増えた。
●配合剤の種類が増え,患者負担の軽減,アドヒアランスの維持などの面からも積極的な処方が勧められる。
●防腐剤,添加剤の異なる薬物,後発品など緑内障治療薬の選択肢が増えたため,治療上の大きなポイントである副作用に回避について,まずは薬剤変更が検討できるようになった。
緑内障に対するレーザー治療
著者: 溝上志朗
ページ範囲:P.174 - P.177
ここが変わった!
以前の常識
●選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)は,アルゴンレーザー線維柱帯形成術(ALT)と同様,手術に踏み切る前の最後の手段。
現在の常識
●SLTにより,最大耐容薬剤使用中の患者の手術を回避することは難しい。
●ステロイド緑内障は,手術に踏み切る前にSLTを試みる価値がある。
●点眼アドヒアランスに問題がある患者に対してSLTは有力な選択肢である。
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2023年10月)。
線維柱帯切除術の適応と手術手技,術後処置
著者: 丸山勝彦
ページ範囲:P.178 - P.182
ここが変わった!
以前の常識
●緑内障の手術といえば,レクトミーとロトミーの二者択一である。
●手術手技のこだわりをアピール。
●術後,結膜の上から縫うのは度胸が必要である。
現在の常識
●術式が多様化し,いろいろな術式のなかから選択が可能となった。
●手術手技のこだわりは人それぞれである。
●術後,結膜の上から縫う技量が必要である。
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2023年10月)。
線維柱帯切開術の基本手技とその術後管理
著者: 結城賢弥
ページ範囲:P.183 - P.187
ここが変わった!
以前の常識
●線維柱帯は強膜弁を作製し,シュレム管を同定したのち金属のロトームや糸を挿入して行う。
現在の常識
●線維柱帯は隅角鏡を用いて直視し,角膜切開創から挿入した器具や糸を用いて切開する。
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2023年10月)。
小児緑内障の治療
著者: 池田華子
ページ範囲:P.188 - P.191
ここが変わった!
以前の常識
●原発先天緑内障に対しては,術者の経験に応じて線維柱帯切開術または隅角切開術を行う。
現在の常識
●原発先天緑内障に対しては,術者の経験に応じて線維柱帯切開術または隅角切開術を行う。
●360°線維柱帯切開術は,従来法と比べて眼圧予後が良好な可能性がある。
●照明付きカテーテルを用いる360°線維柱帯切開術は,比較的実施が容易である。
Special Lecture
緑内障のロービジョンケア
著者: 佐藤佑二 , 奈良井章人 , 木内良明
ページ範囲:P.192 - P.194
はじめに
当院では「見えにくくて困っている」「このまま見えなくなるのか,将来が不安でしょうがない」という患者の声から眼科として対応の必要性を感じ,2009年9月にロービジョン外来が開設された。開設から2017年10月までに95名の方が受診し,年々受診希望者は増えている。
緑内障は視覚障害の原因疾患の1位であり,日本緑内障学会から報告された多治見スタディでは40歳以上の約5%が緑内障である。また,高齢化に伴い,緑内障の発症リスクは高くなる1)ため,緑内障患者の絶対数は増加傾向にある。一方,緑内障は自覚症状に乏しい疾患であり,緑内障であると気づいていない人も多い。そして自覚のないまま徐々に症状が悪化して最終的にロービジョン外来を受診される方もいる。
当院のロービジョン外来受診者の原因疾患は緑内障が最も多く(図1),年々緑内障のロービジョンケアの需要は高まっている。
緑内障と自動車運転
著者: 国松志保
ページ範囲:P.195 - P.198
はじめに
都市部では,バス・地下鉄・電車などの公共交通機関が充実しているため,視野の狭い患者本人が,実際に自転車を運転をすることは少ないが,地方では自動車以外の移動手段がなく,患者本人が自動車の運転に頼らざるをえない。2007年度の旅客輸送機関分担率調査(国土交通省)では,47都道府県のうち34県で,府県内の移動の90%以上が自動車に依存しているという結果であった。そのため,地方では中心視力だけに頼って車の運転をしている視野狭窄患者は非常に多いと予想される。しかし,実際には信号機などの道路標識の認識,右折・左折時の歩行者や自転車の確認のためには,中心視力だけでなく十分な視野が必要であり,自動車運転を続けている末期緑内障患者では,視野障害による安全確認の不足が原因の交通事故を引き起こしうる1)。
4.網膜・硝子体疾患
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.199 - P.199
1)検査
スウェプトソースOCT
著者: 秋山英雄
ページ範囲:P.200 - P.203
ここが変わった!
以前の常識
●EDI-OCTの手法を用いることで黄斑部疾患の脈絡膜構造を解析していた。
現在の常識
●SS-OCTの登場で脈絡膜,硝子体がより明瞭に観察できるようになった。
●画角が広く,また3次元画像構築が容易である。
網膜電図(ERG)
著者: 近藤峰生
ページ範囲:P.204 - P.208
ここが変わった!
以前の常識
●ERGの記録の前には,必ず散瞳しなければいけなかった。
●ERGを記録するときには,点眼麻酔後にコンタクトレンズ電極を挿入しなければいけなかった。
現在の常識
●散瞳しなくてもERGの記録が可能になった。
●皮膚電極ERGでも信頼性の高いERGが記録できるようになった。
OCTアンギオグラフィ
著者: 間瀬智子 , 石羽澤明弘
ページ範囲:P.209 - P.217
ここが変わった!
以前の常識
●網脈絡膜の微小循環障害を詳細に捉えるには蛍光眼底造影検査(FA・IA)が必須である。
●造影剤の動態(流入遅延や蛍光漏出,蛍光貯留など)から,無灌流領域や新生血管などの診断を定性的に行う。
現在の常識
●OCTAは,無灌流領域や異常血管の有無を非侵襲的に毛細血管レベルで捉えることができ,定量的評価も可能である。
●OCTAは層別解析を可能とし,血管の描出される深さや形態から性状を判断する。
広角眼底撮影
著者: 鈴木哲章 , 國方彦志
ページ範囲:P.219 - P.223
ここが変わった!
以前の常識
●眼底全体の記録には,複数枚の写真を重ね合わせて合成するパノラマ写真が一般的であった。
●特に蛍光眼底造影では,多象限にわたる病変の正確な経時的変化の同時評価が困難であった。
現在の常識
●一度の走査で網膜周辺部を含め広範囲を記録できる。
●複数のメーカーから広角眼底撮影装置が発売されており,それぞれに特徴がある。
2)診断・治療
病的近視眼の画像診断
著者: 大野京子
ページ範囲:P.225 - P.229
ここが変わった!
以前の常識
●後部ぶどう腫は眼底検査で判断される主観的な病変であった。
●球後視神経やくも膜下腔,眼窩組織など深部組織は病的近視眼でも可視化できなかった。
●CNVの診断には蛍光眼底造影が必須であった。
現在の常識
●後部ぶどう腫の全貌を画像で可視化でき,客観的かつ定量的な診断が可能となった。
●症例により,眼窩の血管や結合組織,球後の視神経の描出が可能となった。
●活動性の評価は今後の課題であるが,OCTAにより非侵襲的診断が可能となった。
PDTの適応
著者: 小椋有貴 , 五味文
ページ範囲:P.230 - P.233
ここが変わった!
以前の常識
●滲出型AMD治療に対するベルテポルフィンを用いたPDTは2000年頃に開始された。
●抗VEGF薬の登場により,その良好な治療成績が広く認識され,治療の第一選択となった。
現在の常識
●抗VEGF薬のデメリットは頻回投与が必要となることと,薬価が高額であることである。
●滲出型AMDの長期的な管理に抗VEGF薬とPDTの併用の選択肢も検討されている。
ポリープ状脈絡膜血管症の診断と治療
著者: 古泉英貴
ページ範囲:P.234 - P.237
ここが変わった!
以前の常識
●OCTは網膜断層像の評価が主であった。
●治療の主流はPDTであった。
現在の常識
●OCTでの脈絡膜断層像が注目されるようになった。
●Pachychoroidとの関連が示されるようになった。
●OCTAの診断的価値が模索されている。
●抗VEGF薬の役割が大きくなった。
黄斑浮腫に対する治療
著者: 志村雅彦
ページ範囲:P.238 - P.242
ここが変わった!
以前の常識
●VEGF阻害薬は黄斑浮腫に対し保険適用を受けていなかった。
●光凝固が標準治療であった。
●網膜血管の詳細は把握されていなかった。
現在の常識
●VEGF阻害薬が黄斑浮腫に対し保険適用を受け,広く普及した。
●光凝固の有用性が否定されつつある。
●OCTAの登場により網膜血管の詳細が把握され,病態との関連性が研究されている。
抗VEGF療法
著者: 丸子一朗
ページ範囲:P.243 - P.249
ここが変わった!
以前の常識
●AMD:抗VEGF薬のPRN投与
●mCNV:治療法なし(保険適用外の抗VEGF療法)
●DME・RVOによる黄斑浮腫:レーザー治療,ステロイド治療,硝子体手術
現在の常識
●AMD:抗VEGF薬のTAEまたはPRN投与
●mCNV:保険適用の抗VEGF療法
●DME・RVOによる黄斑浮腫:抗VEGF療法が第一選択
乳頭ピット黄斑症候群の診断と治療
著者: 平形明人
ページ範囲:P.250 - P.255
ここが変わった!
以前の常識
●TD-OCTとSD-OCTで分離と剝離を検出して診断していた。
●乳頭ピットの程度について,あまり情報がなかった。
●黄斑剝離の治療に乳頭縁にレーザー治療をしていた。
●硝子体手術の難治例に対する治療法が難しかった。
現在の常識
●SD-OCTとSS-OCTの進歩で,乳頭ピットや網膜層構造の変化や硝子体の関与が観察できるようになった。
●乳頭ピットの形態は多様であり,くも膜下腔や硝子体線維の関与の程度が幅広いことがわかった。
●OCTで自然復位例や網膜層構造の障害程度も観察しやすくなり,硝子体手術の治療適応の検討がしやすくなった。
●硝子体手術の難治例に対し,新たな治療法が検討されてきている。
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2023年10月)。
3)手術手技
黄斑円孔手術
著者: 森實祐基
ページ範囲:P.256 - P.261
ここが変わった!
以前の常識
●黄斑円孔に対する手術は20Gもしくは23G硝子体手術が主流である。
●ILMの染色にはICGを用いる。
●眼内にガスが入っていると,黄斑を観察することは難しい。
●巨大黄斑円孔に対する有効な治療法はない。
現在の常識
●黄斑円孔に対する手術は25Gもしくは27G硝子体手術が主流である。
●ILMの染色にはBBGを用いる。DAVSの登場により,低濃度の染色,低照明でのILM処理が可能である。
●SS-OCTを用いることによって,ガス下の黄斑形態を観察することが可能である。
●巨大黄斑円孔をはじめとした難治性黄斑円孔に対してILM翻転やILM移植が有効である。
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2023年10月)。
バックリング手術
著者: 厚東隆志
ページ範囲:P.263 - P.266
ここが変わった!
以前の常識
●下方のRRDはバックルが第一選択であった。
●倒像鏡+20Dレンズで眼底を観察しながら手術をしていた。
●網膜下液排出時の脈絡膜穿刺は針で施行していた。
現在の常識
●下方弁状裂孔のRRDに対しては硝子体手術を積極的に選択するようになった。
●広角観察システム+シャンデリア照明でバックリング手術を行うようになった。
●脈絡膜穿刺にレーザーを用いるようになった。
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2023年10月)。
レーザー網膜光凝固
著者: 野崎実穂
ページ範囲:P.269 - P.274
ここが変わった!
以前の常識
●毛細血管瘤に対する局所凝固は,造影結果を見ながら凝固するので,技術と経験が必要である。
●閾値下凝固は特殊な装置がないとできず,見えない凝固斑を密に打つ名人でないとできない手技である。
●無灌流領域には,必ずレーザー網膜光凝固を行う。
現在の常識
●ナビゲーション機能搭載レーザー網膜光凝固装置により,造影結果などをもとに,正確な局所凝固が誰でもできるようになった。
●網膜レーザー光凝固装置に,閾値下凝固ができるソフトウェアが搭載され,パターンで凝固できるため,特殊な装置や名人芸は必要なくなった。
●VEGF阻害薬の登場で,無灌流領域に対するレーザー網膜光凝固は必須ではなくなった。
Special Lecture
網膜血管内治療
著者: 門之園一明
ページ範囲:P.276 - P.279
はじめに
血管内治療は,さまざまな分野で臨床応用されており,一般的な治療となって久しい。特に心臓血管外科,脳外科での進歩は目覚ましく,血管内視鏡の開発まで進んでいる。一方,眼科での血管内治療はいまだに実現していない。網膜には多くの血管閉塞疾患が存在するにもかかわらず,なぜ血管内治療の開発が進まないのであろうか? その理由は網膜血管の大きさによる。網膜内の血管の最大径は約100μmである。冠動脈のそれが2〜4mm程度であり,1/20以下の細い管を対象にすることになる。このため,網膜血管内治療は今までいくつかの臨床応用研究がされてきたものの,実現に至らなかった。筆者らは,10年前より血管内治療の開発を進めており,2017年よりようやく臨床応用が可能となり,良好な治療成績を収めることができるようになった1)。そこで,本稿では,網膜中心動脈閉塞症(central retinal artery occlusion:CRAO)に関する治療の概略を述べる。
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2023年10月)。
iPS細胞を用いた眼科治療の進捗
著者: 万代道子
ページ範囲:P.280 - P.281
はじめに
山中伸弥教授のノーベル賞受賞により「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」という言葉が急速に知られるようになり,社会全体として再生医療への期待が高まっている。iPS細胞によって何が可能になったのか。また,どのような治療が期待できるのか。臨床現場でも,いざ患者の期待を目の前にすると,どう説明すべきか迷う状況もあるかもしれない。ここでは,iPS細胞の意義,その臨床応用,将来的な展望をまとめてみたい。
黄斑円孔手術後にうつむきは必要か?
著者: 山下敏史
ページ範囲:P.282 - P.285
はじめに
黄斑円孔は,中心窩に円孔を生じる疾患であり,中心暗点(視野異常),視力低下や歪視・変視といった症状を起こす。そのほとんどが特発性であり,50〜70歳台に好発し,女性にやや多いとされている。その原因は,網膜硝子体界面の変化による硝子体牽引であることが明らかとなっているが1,2),それは生理的な現象であり,予防法は存在しない。また黄斑円孔には,特発性のほかに強度近視が原因のもの,炎症などが原因で起こる続発性黄斑円孔や眼打撲が原因で起こる外傷性黄斑円孔もある。
5.ぶどう膜炎・強膜炎・感染症
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.289 - P.289
1)ぶどう膜炎・強膜炎
生物学的製剤の使い方
著者: 慶野博
ページ範囲:P.290 - P.294
ここが変わった!
以前の常識
●眼炎症領域で承認されている生物学的製剤はインフリキシマブのみであり,適応疾患はBehçet病難治性網膜ぶどう膜炎に限定されていた。
現在の常識
●2016年9月にTNF阻害薬であるアダリムマブが非感染性の中間部,後部,または汎ぶどう膜炎に対して承認され,従来の治療で効果不十分な症例に対してTNF阻害薬の使用が可能となった。
●「非感染性ぶどう膜炎に対するTNF阻害薬使用指針および安全対策マニュアル」を参考に抗TNF療法を行う。
非感染性ぶどう膜炎の治療戦略
著者: 蕪城俊克
ページ範囲:P.295 - P.298
ここが変わった!
以前の常識
●トリアムシノロンアセトニドのテノン囊下注射には,ケナコルト-A®注をオフラベルで用いていた。
●ステロイド内服を行っても再燃を繰り返すBehçet病以外の難治性非感染性ぶどう膜炎に対しては,ステロイド内服を再燃しないぎりぎりの量で続けるか,保険適用のないケナコルト-A®注をオフラベルで使い続けるしかなかった。
現在の常識
●非感染性ぶどう膜炎に伴う黄斑浮腫に対してトリアムシノロンアセトニド(マキュエイド®)のテノン囊下投与が保険適用となり,ケナコルト-A®注をオフラベルで用いる必要がなくなった。
●ステロイド内服で再燃を繰り返すBehçet病以外の難治性の非感染性ぶどう膜炎に対して,シクロスポリン(ネオーラル®),アダリムマブ(ヒュミラ®)が保険適用となり,ステロイド離脱のための治療が可能となった。
ステロイド製剤の局所での使い方
著者: 楠原仙太郎
ページ範囲:P.299 - P.302
ここが変わった!
以前の常識
●前部ぶどう膜炎・強膜炎ではベタメタゾン点眼で治療するが,重症例ではステロイド結膜下注射を考慮する。
●中間部または後部ぶどう膜炎および後部強膜炎に対しては,トリアムシノロンテノン囊下注射/硝子体注射を保険適応外で使用する。
現在の常識
●前部ぶどう膜炎・強膜炎の治療方針に変化はないが,エビデンスが蓄積されてきた。
●後眼部炎症を伴う非感性ぶどう膜炎に対するトリアムシノロンテノン囊下投与が保険適用となった。
●国外ではジフルプレドナート懸濁液点眼や徐放性ステロイド硝子体内インプラントなど,わが国とは異なる治療が可能になっている。
免疫抑制薬の使い方
著者: 中井慶
ページ範囲:P.303 - P.305
ここが変わった!
以前の常識
●ステロイドの増減だけで,何とかぶどう膜炎の眼炎症はコントロールできる。
現在の常識
●ステロイドに積極的に免疫抑制薬を併用することで,副作用を抑えて,ぶどう膜炎の眼炎症をコントロールする。
眼内悪性リンパ腫の診断と治療
著者: 武田篤信
ページ範囲:P.306 - P.310
ここが変わった!
以前の常識
●眼内悪性リンパ腫の診断において,細胞診での悪性細胞の検出率は半分以下であるため難しい。
●眼内悪性リンパ腫の治療は,眼病変に対する局所放射線療法が第一選択である。
現在の常識
●眼内悪性リンパ腫の診断は細胞診だけでなく,サイトカインIL-10測定などの補助診断を併せて用いることで確定診断に至る症例が増えている。
●眼病変に対しては,局所放射線療法よりも局所化学療法が第一選択である。
●生命予後に直結するCNS悪性リンパ腫の発症予防のために,年齢,全身状態にもよるが,全身化学療法または全身化学療法後に放射線療法(全脳照射)を併用することがある。
ぶどう膜炎による続発緑内障への対処法
著者: 竹内大
ページ範囲:P.311 - P.315
ここが変わった!
以前の常識
●点眼加療はβ阻害薬,炭酸脱水酵素阻害薬が主に用いられていた。
●内科的治療が奏効しない症例に対する緑内障チューブインプラント手術の有効性を示すエビデンスは,症例報告,小規模スタディに限られていた。
現在の常識
●UGに対してもPG関連薬が有効である。
●Rock阻害作用を有する点眼薬の有効性も知られている。
●国外では緑内障チューブインプラント手術の中・長期的な有効性,安全性が多症例での検討で報告されている。
Special Lecture
小児のぶどう膜炎
著者: 後藤浩
ページ範囲:P.316 - P.317
はじめに
小児のぶどう膜炎は多施設調査などのデータが存在しないため,その実態は不明な点も多いが,成人では主要疾患として位置づけられるサルコイドーシス,Vogt-小柳-原田病,Behçet病などは一般に稀である。自施設における小児ぶどう膜炎(15歳以下)の統計を表1に示す。全118症例の平均年齢は11.2±3.7歳で,性別は男児39例(33%),女児79例(67%)と女児が男児の約2倍を占めている。分類可能なぶどう膜炎としてはiridocyclitis in young girlsのほか,川崎病や若年性特発性関節炎(juvenile idiopathic arthritis:JIA),腎尿細管間質性腎炎に伴うぶどう膜炎などが代表的な疾患であるが,全体の6割近くは同定不能であり,この点は以前と比較しても大きな変化はないと考えられる。
2)感染症
結核の診断と治療
著者: 高瀬博
ページ範囲:P.318 - P.320
ここが変わった!
以前の常識
●眼外臓器に結核病変が検出されない患者に結核性ぶどう膜炎を疑う際の診断は,典型的臨床像に加え,ツベルクリン皮内反応を参考に診断を行う。
現在の常識
●ツベルクリン皮内反応に加え,インターフェロン遊離試験(クォンティフェロンTbゴールドまたはTスポット. TB)を行う。
サイトメガロウイルスの診断と治療
著者: 臼井嘉彦
ページ範囲:P.321 - P.325
ここが変わった!
以前の常識
●定性PCRは,CMVによる虹彩毛様体炎や網膜炎の診断に有用である。
●Posner-Schlossman症候群やFuchs虹彩異色性虹彩毛様体炎は,非感染性ぶどう膜炎である。
●CMVの診断は,網羅的PCR検査により行われるが,研究として行う。
●CMV網膜炎の原因としては,AIDSによる発症頻度が高い。
現在の常識
●定量PCRはCMVによる虹彩毛様体炎や網膜炎の診断のみならず,CMVウイルスコピー数と病像に相関があると報告されているため,治療効果の判定にも有用である。
●非感染性ぶどう膜炎として分類されていたPosner-Schlossman症候群やFuchs虹彩異色性虹彩毛様体炎のなかに,CMV-DNAが検出される症例がある。
●CMVの診断は,先進医療として,網羅的PCR検査により行われる。それに伴いCMV角膜内皮炎・虹彩毛様体炎は増加傾向である。
●非HIV患者に生じ,慢性的な経過をとるCMV網膜炎は,慢性網膜壊死(chronic retinal necrosis)と称する新たな疾患概念が提唱されている。
6.神経・外眼部・腫瘍などの疾患
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.327 - P.327
1)神経
視神経炎における抗MOG抗体の取り扱い
著者: 毛塚剛司
ページ範囲:P.328 - P.331
ここが変わった!
以前の常識
●視神経炎には,視神経脊髄型多発性硬化症を伴うタイプのほかに,抗AQP 4抗体陽性の視神経炎があり,脊髄炎を伴うことが多い。
●抗AQP 4抗体陽性の視神経炎は,多くのケースにおいて副腎皮質ステロイドの投与に加えて,血漿交換療法が有効である。
現在の常識
●特異抗体陽性視神経炎には,抗AQP 4抗体陽性視神経炎のほかに,抗MOG抗体陽性視神経炎が存在する。
●抗AQP 4抗体陽性視神経炎は,視神経炎の10%前後であり,女性に多く,ステロイドに対して抵抗性である。一方,抗MOG抗体陽性視神経炎は,視神経炎の10%前後であり,性差はないか男性にやや多く,視神経乳頭腫脹が強く,眼痛も強い。また,ステロイドによく反応するが,再発しやすい傾向にある。
●特異抗体陽性視神経炎において,ステロイドパルス療法が無効の場合は血漿交換療法を行うほかに,IVIg大量療法も有効である。
神経眼科でのOCTの活用
著者: 後藤克聡 , 三木淳司
ページ範囲:P.332 - P.340
ここが変わった!
以前の常識
●神経眼科領域におけるOCT検査は,主に視神経疾患をターゲットとして,cpRNFL厚の評価が行われてきた。
●乳頭腫脹を伴う視神経疾患の急性期では,乳頭腫脹によるcpRNFL厚の増加やセグメンテーションのエラーが生じるためRGC萎縮の評価ができなかった。
現在の常識
●GCC厚などの黄斑部網膜内層解析により,乳頭腫脹を伴う視神経疾患でも急性期におけるRGCの評価ができる。
●視路の障害部位に応じた網膜内層の形態変化をきたすため,OCT測定によって視路の障害部位の予測や視路疾患の有無の診断の一助として有用である。
●OCTAの出現により,視神経萎縮に伴う放射状乳頭周囲毛細血管の欠損を観察することが可能となった。
斜視のボツリヌス毒素治療
著者: 三村治
ページ範囲:P.342 - P.346
ここが変わった!
以前の常識
●斜視への治験以外は,個人輸入で購入したボツリヌス毒素製剤を倫理委員会の承認を受けたうえでしか使用できなかった。
●筋電図や電極兼用注射針も国産のものがなく,すべて海外から輸入した高価なものを使う必要があった。
●上記の理由から,国内では斜視へのボツリヌス毒素治療は実際の臨床では行われていなかった。
現在の常識
●2015年に斜視への適応拡大が認められ,国産の比較的安価で使いやすい筋電計や電極兼用注射針も開発されたが,施注には講習会受講と眼科専門医の資格が必要である。
●水平斜視だけでなく上下斜視や麻痺性斜視にも広く注射できるようになったが,12歳未満の小児は非適応である。
●ボツリヌス毒素治療は手術の困難な症例でも適応があり,斜視治療の選択肢の増加につながるものである。
2)外眼部疾患
眼瞼下垂手術
著者: 小久保健一
ページ範囲:P.348 - P.351
ここが変わった!
以前の常識
●日本では,後天性の眼瞼下垂に対して挙筋腱膜をターゲットとした前転法が主流であった。
●創傷治癒の観点からメス,スプリング剪刀,キルナー,バイポーラなどを用いた組織を損傷しない手術が好まれていた。
現在の常識
●挙筋腱膜前転法は現在も主流であることには違いないが,日本独自の術式である経皮ミュラー筋タックが広まってきている。
●ボリュームサージャンを中心に炭酸ガスレーザーや高周波メスなどのデバイスが普及してきた。
睫毛内反手術
著者: 上笹貫太郎
ページ範囲:P.352 - P.357
ここが変わった!
以前の常識
●先天睫毛内反症は,皮膚穿通枝の脆弱により前葉(皮膚,眼輪筋)の乗り上げが原因で起こるとされていた。
●Hotz変法に代表される皮膚切開法が主流となり,再発率の高い埋没法は症例を選んで行う。
現在の常識
●先天睫毛内反症のなかには,睫毛乱生を伴うものや後葉の引き込みによって前葉の乗り上がりが強調されている症例も存在する。
●睫毛乱生の程度や後葉の引き込みを認める症例では,皮膚切開法でも再発の可能性があり,睫毛の外反を補助するlid margin splitや後葉の位置を是正するLERs切離などを併施する。
IgG4関連Mikulicz病からIgG4関連眼疾患への変遷
著者: 高比良雅之
ページ範囲:P.358 - P.361
ここが変わった!
以前の常識
●IgG4関連疾患の眼症状は,古来よりMikulicz病と称される対称性涙腺腫大が主であり,重篤な視機能障害を呈する病態は知られていなかった。
●IgG4関連涙腺炎からリンパ腫が発症した症例報告が散見されたが,眼窩リンパ増殖性疾患に占めるIgG4関連疾患の割合など,その頻度は不明であった。
現在の常識
●IgG4関連疾患の眼症状には涙腺腫大のほかにも三叉神経腫大,外眼筋腫大がしばしばみられ,これらはIgG4関連眼疾患の3大病変である。また,視神経症による重篤な視機能障害をきたす症例もある。
●日本での多施設調査では,IgG4染色陽性MALTリンパ腫の症例数はIgG4関連眼疾患のおよそ1/5であり,治療に際して両者の鑑別は重要である。
3)腫瘍
乳児血管腫の治療
著者: 尾山徳秀
ページ範囲:P.362 - P.367
ここが変わった!
以前の常識
●ステロイドの全身投与や局所療法,インターフェロンα療法,抗癌剤のビンクリスチンやシクロホスファミド,手術加療,色素レーザーなどの治療法は劇的に改善することは少なく,それらを使用することによる副作用の懸念も常に存在した。
●治療が遅れたり,治療の反応が悪い場合は,40〜60%の確率で不同視弱視などの屈折異常弱視が発生した。
現在の常識
●早期に非選択的β遮断薬を使用することで,導入直後から劇的な改善を認めることが多く,屈折異常弱視の発生率も下がる。重篤な副作用の頻度も少ない。
●非選択的β遮断薬は点滴や内服があるが,最近ではシロップ剤も存在し,眼科領域で使用する点眼の塗布でも効果が認められる。
網膜芽細胞腫
著者: 鈴木茂伸
ページ範囲:P.368 - P.371
ここが変わった!
以前の常識
●局所化学療法は難治例に対する実験的治療である。
●国内で
現在の常識
●局所化学療法は治療の主軸であり,初期治療として行う場合もあるが,適応は施設ごとに異なる。
●発病者の
画像誘導放射線治療
著者: 牧島弘和 , 辻比呂志
ページ範囲:P.372 - P.375
ここが変わった!
以前の常識
●患者の皮膚に書いた目印などで位置を照合していた。位置誤差は1〜2cm以上見積もる必要があった。画像での確認は多くて週1回程度で2次元情報であった。
現在の常識
●X線写真を複数方向から撮影,もしくはCTやMRIを用いて位置を毎回3次元で照合する。位置誤差は部位によっては1mm未満まで抑えられる。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.8 - P.11
基本情報
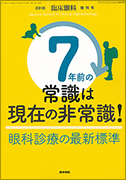
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
