要約 目的:偽落屑症候群(PE)を有する高度散瞳不良例に対し計画的フェムトセカンドレーザー白内障手術(FLACS)を施行し,術前虹彩切開後のCCC径が2.6mmであったにもかかわらず無事に水晶体再建術を遂行できた症例の報告。
対象と方法:患者は96歳,女性。両眼の視力低下を主訴に受診した。両眼にPEあり,前房はやや浅め,白内障核硬化度はエメリー・リトル分類grade 3〜4で,両眼とも散瞳不良であった。チン小帯脆弱の可能性を説明したところFLACSを希望された。
結果:FLACS施行日の約2か月前に虹彩切開術を施行し,虹彩に数か所の切れ込みを入れた。FLACS当日の瞳孔径は3.7mmで,FLACSによるCCC径2.6mm通りにCCCを施行した。フェムトセカンドレーザーで核を8分割にマンゴーカット後,型どおり水晶体を処理し眼内レンズを挿入した。
結論:高度散瞳不良例に対するFLACS施行時には,術前にあらかじめ虹彩切開をしておくオプションがある。
雑誌目次
臨床眼科74巻10号
2020年10月発行
雑誌目次
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
原著
計画的虹彩切開術にもかかわらず散瞳不良であったフェムトセカンドレーザー白内障手術
著者: 井上貴久彦 , 岩西宏樹 , 雑賀司珠也
ページ範囲:P.1235 - P.1239
ポリープ状脈絡膜血管症に対する光線力学的療法併用抗血管内皮増殖因子治療後短期における治療成績と再発予測因子
著者: 永吉美月 , 塩瀬聡美 , 和田伊織 , 狩野久美子 , 石川桂二郎 , 秋山雅人 , 森賢一郎 , 納富昭司 , 中尾新太郎 , 久冨智朗 , 園田康平
ページ範囲:P.1241 - P.1249
要約 目的:ポリープ状脈絡膜血管症(PCV)に対する光線力学的療法(PDT)併用抗血管内皮増殖因子(VEGF)治療後短期における治療成績と再発予測因子の検討。
対象と方法:対象は2017年8月〜2018年8月に九州大学病院眼科で未治療PCVに初回からPDTと抗VEGF薬導入期3回投与を施行し,12か月以上経過観察できた14例14眼。新たな眼底出血,および光干渉断層計で確認された滲出性変化を再発と定義した。PDT併用治療開始から12か月後の時点における治療効果を視力,中心窩網膜厚(CRT),中心窩脈絡膜厚(CCT)に基づいて評価し,再発予測因子を同定するため治療前因子〔既往歴,喫煙歴,ポリープの種類,視力,CRT,CCT,病巣最大径,自発蛍光(FAF)における低蛍光領域〕と再発との関連について検討した。
結果:治療12か月後すべての症例で視力の維持がみられ,CRT,CCTは減少していた。4眼(29%)は治療後12か月以内に再発した。既往歴,喫煙歴,ポリープの種類,視力,CRT,病巣最大径は再発と関連がなかったが,再発群では非再発群に比べて有意に治療前の平均CCTが薄く(非再発群で279±59μm,再発群で196±50μm,p<0.05),FAFにおける平均低蛍光領域は広かった(非再発群で3.2±1.9μm2,再発群で9.1±5.3μm2,p<0.05)
結論:PCVに対して初回PDT併用抗VEGF治療を行い,治療開始12か月後すべての症例で視力を維持し,滲出が改善していた。治療前のCCTとFAFでの蛍光領域の広さが,治療後早期の再発予測に有用である可能性が示唆された。
滲出型加齢黄斑変性に対するVEGF阻害薬硝子体注射後に進行した白内障に対する手術の予後
著者: 廣瀬尊郎 , 若林美宏 , 馬詰和比古 , 川上摂子 , 山本香織 , 阿川毅 , 渡邉陽子 , 村松大弐 , 馬場良 , 清水広之 , 後藤浩
ページ範囲:P.1251 - P.1257
要約 目的:滲出型加齢黄斑変性(滲出型AMD)に対する血管内皮細胞増殖因子(VEGF)阻害療法の治療経過中に白内障が進行し,手術治療を施行した症例の予後を検討する。
対象と方法:対象は2010年10月〜2016年10月に東京医科大学病院眼科で滲出型AMDに対しVEGF阻害薬硝子体注射が開始され,その後の治療経過中に白内障が進行したため手術を施行した26例27眼である。手術時の年齢の中央値は82.8歳(分布:69〜93歳),術後の経過観察期間の中央値は19.9か月(6.2〜72.9か月)である。視力とVEGF阻害薬硝子体注射の回数を手術前後で比較し,白内障手術の効果と影響を検討した。
結果:注射開始から白内障手術までの期間と注射回数の中央値(分布)は,それぞれ45.5か月(7.9〜85.8か月),16回(5〜46回)であった。手術前後12か月間の注射回数の中央値(分布)は,それぞれ5回(0〜9回),5回(0〜10回)と術前後で有意差はなかった(n=20)。logMAR視力の中央値(分布)は,白内障術前の0.70(0〜1.70)から術後1か月後には0.22(0.18〜1.30)と有意に上昇した(p<0.001)。視力は術後12か月の時点では19眼(95%)で維持されていたが,滲出型AMDの悪化により1眼(5%)で低下した。他の1眼(5%)では術後2か月目に黄斑出血が再発した。
結論:滲出型AMDに対するVEGF阻害薬硝子体注射後に進行した白内障に対する手術療法では視機能の向上が期待できる。ただし,術後に滲出型AMDが増悪する症例もあることに留意する必要がある。
アフリベルセプト治療抵抗性の加齢黄斑変性に対するレスキューPDT併用療法の12か月成績
著者: 河崎勇貴 , 上田浩平 , 東惠子 , 井上達也 , 小畑亮
ページ範囲:P.1259 - P.1264
要約 目的:アフリベルセプト治療抵抗性の滲出型加齢黄斑変性(AMD)に対して光線力学療法(PDT)併用治療を行った12か月成績を検討した。
対象と方法:対象症例は,アフリベルセプト硝子体内投与(IVA)を行い治療効果が乏しいと判断したAMDに対してPDT療法を併用し,12か月間経過観察した滲出型AMDの連続症例22例22眼(平均年齢74.7±7.1歳)。ベースラインおよび12か月後の矯正視力,中心窩網膜厚(CFT),および中心窩脈絡膜厚(CCT),さらに12か月後の滲出性変化消退率,12か月間の硝子体注射投与回数について検討した。
結果:平均logMAR視力はベースライン0.29±0.28,12か月後0.24±0.35(p=0.259)であり,有意な変化はなかった。CFTおよびCCTは有意に減少した。12か月後の滲出性変化消退率は72.7%であった。12か月間の硝子体注射追加投与回数は平均3.6±3.4回,PDTは1回(2眼)または0回(20眼)であった。
結論:アフリベルセプト治療抵抗性のAMDに対するPDT併用療法の12か月後に視力は維持され,滲出性変化は約7割で消退した。
春季カタルに対するトリアムシノロンアセトニド眼瞼皮下注射の治療成績
著者: 藤田皓 , 佐伯有祐 , 原田一宏 , 内尾英一
ページ範囲:P.1265 - P.1272
要約 目的:春季カタル(VKC)は小児に発症し長期の治療を必要とする。ステロイド点眼薬の長期使用により眼圧上昇などの合併症が危惧されるため,その代替治療として行っているトリアムシノロンアセトニド(TA)眼瞼皮下注射の長期間の臨床経過を検討した。
対象と方法:対象は2009年1月〜2018年12月の10年間に福岡大学病院でVKCに対しTA眼瞼皮下注射を受けた41例64眼。平均観察期間は35.7±32.5月(0〜119月)。診療録をもとに,性別,年齢分布,季節性,注射回数,複数回注射を必要とした患者の初診時年齢および投与間隔,注射前後の点眼薬,合併症について後ろ向きに検討した。
結果:男性35例,女性6例,年齢は4〜32歳で平均11.4±6.18歳。TA眼瞼皮下注射は合計で139回施行され,うち23回(16.5%)は7月,21回(15.1%)は3月に施行された。1眼当たりの注射回数は1〜13回で,平均3.39±3.40回であった。複数回の注射を必要としたものは男性14例,女性4例であった。その平均年齢は9.17±3.99歳(4〜19歳),平均投与間隔は11.0±6.07月(1〜35月)であった。合併症は3例に眼圧上昇,1例に麦粒腫,1例に睫毛伸長が認められ,眼圧上昇がみられたものは男性1例,女性2例であった。
結論:難治性のVKCに対するTA眼瞼皮下注射は,TA眼瞼結膜下注射やステロイド内服でしばしばみられる眼圧上昇をきたすことが少ない。手技が簡便で投与間隔が比較的長いことから,安全な治療法であることが示唆された。
線維柱帯切除術による眼圧変化と視神経乳頭周囲の網膜視神経線維層微小循環の変化
著者: 森春樹 , 妹尾正 , 原岳 , 橋本尚子 , 本山祐大 , 大河原百合子 , 成田正弥 , 伊野田悟
ページ範囲:P.1273 - P.1278
要約 目的:線維柱帯切除術による眼圧変化が視神経乳頭周囲の網膜視神経線維層(RNFL)の微小循環に与える影響を検討する。
対象と方法:原眼科病院で線維柱帯切除術を行った41眼で,年齢は70.0±10.1歳。視神経乳頭周囲のRNFL内微小循環は,ZEISS社のCirrus-HD OCTのAngioplex for ONHで測定したcapillary perfusion値(P値,毛細血管密度)とcapillary flux index値(F値,血管血流速度)(ともに上方,耳側,下方,鼻側,INDEX)を使用し,術前1か月以内と術後2週間前後の各値を対応のあるt検定で比較した。また,術前と術後の耳側のP値とF値の変化量を多変量解析した。いずれも有意水準をp<0.05とした。
結果:術前の平均眼圧は21.8mmHg,術後は12.3mmHgであった。P値は耳側が41.4±2.8%から42.9±3.8%,P INDEXが37.8±2.7%から38.5±2.6%と有意に上昇していた。F値は耳側が0.32±0.043から0.301±0.040,下方が0.312±0.039から0.298±0.038,鼻側が0.318±0.044から0.302±0.040,F INDEXが0.316±0.040から0.300±0.037と有意に減少していた。術前と術後の耳側のP値とF値の変化量を多変量解析した結果,P値,F値の変化量と眼圧差との有意な相関はなく,F値の変化量は術前F値が高いほど減少していた。
結論:線維柱帯切除術後の眼圧下降により,P値は増加しF値は低下する傾向があった。P値,F値の変化量は眼圧変化と相関せず,一時的な眼圧の急激な変化には強く影響されないことが示された。術前F値が高いほどF値の変化量は減少していたが,眼圧下降により血管面積が増え,それに伴いF値が減り,血流量全体としては術前後で大きく変化してない可能性がある。
白内障術後10年以上経過観察できたぶどう膜炎併発強皮症の1例
著者: 中山馨 , 上甲覚
ページ範囲:P.1279 - P.1285
要約 目的:両眼にぶどう膜炎,続発緑内障,そして角膜混濁を併発した強皮症患者に行った,超音波白内障手術を行った術後10年の経過報告。
症例:70歳で強皮症と診断された89歳女性。
所見と経過:77歳の初診時に,両眼にぶどう膜炎,続発緑内障,角膜混濁,白内障が認められた。右眼は病的近視もあった。ぶどう膜炎と緑内障は点眼により沈静化した。術前矯正視力は,右0.01,左0.2であった。78歳時に両眼に超音波水晶体乳化吸引術(PEA)と眼内レンズ(IOL)挿入術を施行した。両眼とも術中合併症はなかった。術後最高矯正視力は,右0.04,左0.9であった。角膜上皮障害により視力低下することがあった。術後9年目から主に後発白内障のため左眼は徐々に視力は低下し,最終矯正視力は0.5であった。ぶどう膜炎の再燃はなく,眼圧は安定していた。
結論:ぶどう膜炎と緑内障が併発した強皮症患者の両眼にPEAとIOL挿入術を行い,10年間の経過は良好であった。
OCTOPUS 900視野計を用いた静的視野によるVisual Field Score,Functional Field Score,Functional Vision Scoreの測定
著者: 原田亮 , 加茂純子
ページ範囲:P.1286 - P.1295
要約 目的:Visual Field Score(VFS),Functional Field Score(FFS),Functional Vision Score(FVS)について,OCTOPUS 900視野計(OP)で測定した値と,ゴールドマン視野計(GP)で測定した値の比較を行う。OPによるVFSの測定時間と疲労度を調べる。
対象と方法:対象は同意を得た140名の患者(男性79名,女性61名,平均年齢71.0±11.8歳)。GP Ⅲ/4e視標で動的視野を測定後,Colenbrander-Kamoエクセルシートに手入力でVFS,FFS,FVSを算出した。OPのカスタムプログラム,Colenbrander grid test(CGT)で静的視野によるVFSを測定後,表計算エクセルのマクロを使用してFFS,FVSを自動計算した。CGTは偽陽性,偽陰性がそれぞれ33%未満を信頼性良好群,それ以上を信頼性不良群とした。OPとGP,それぞれの結果から得たスコアの相関について,統計解析を行った。FFSクラス,FVSクラスの比較を行った。CGTの測定時間と疲労の有無について集計した。
結果:信頼性良好群のOPによるVFSは82.5±20.1,GPによるVFSは86.6±17.4であった(r=0.77,p<0.001)。OPによるFFSは90.1±15.8,GPによるFFSは91.7±12.6であった(r=0.73,p<0.001)。OPによるFVSは87.9±19.6,GPによるFVSは89.1±17.1であった(r=0.88,p<0.001)。信頼性良好群のFFSクラスは75%,FVSクラスは78%がOPとGPで同じクラスであった。信頼性不良群のFFSクラスは63%,FVSクラスは75%がOPとGPで同じクラスであった。症例全体で,CGTの測定時間は片眼230.5±48.9秒で,疲労なしが81%であった。
結論:FFS,FVSは,OPとGPでほぼ同等だったと考えられた。CGTの測定時間は両眼で平均8分程度であり,ほとんどの人が疲労なしに検査終了した。
血漿交換療法を要した抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎の1例
著者: 西田(濱田)舞 , 山川百李子 , 上田真衣 , 吉田裕一 , 室山絵美子 , 宮原晋介 , 近藤誉之 , 田邉晶代
ページ範囲:P.1296 - P.1303
要約 目的:視交叉視索炎として発症した抗アクアポリン4(AQP4)抗体陽性視神経炎に対し,早期血漿交換療法により視機能の回復を認めたので報告する。
症例:65歳,女性。2018年4月より原因不明の吃逆,嘔吐が持続し6月中旬に自然治癒した。7月下旬より急激な両眼視力低下を自覚し当科を紹介され受診となった。初診時,視力は右(0.1),左(0.09),中心フリッカ(CFF)値は右35Hz,左25Hz,視神経乳頭に異常はなく,動的視野検査にて両耳側暗点と左眼鼻下側の視野狭窄を認めた。MRIにて両側視交叉および左視索に造影効果,および第4脳室周囲にFLAIRで高信号を認めた。視交叉視索炎に対してステロイドパルスを1クール施行するも,CFF値の低下と視野の悪化を認めたためステロイド内服併用血漿交換療法(PE)に切り替えた。入院中に抗AQP4抗体陽性が確認され,抗AQP4抗体陽性視交叉視索炎と診断した。2回目のPE後から視野とCFF値の改善,4回目のPE後には視力の改善を認めた。計7回のPEの後,ステロイド内服単独療法へ移行し,以後視神経炎の再燃はない。
結語:急性期治療としてのステロイドパルスへの反応が乏しく,臨床症状およびMRI所見から抗AQP4抗体陽性が強く疑われる視神経炎においては早期に血漿交換療法への移行を検討することが望ましい。
最終的に眼内レンズ縫着術が奏効した外傷性毛様体解離による低眼圧黄斑症の1例
著者: 中村ゆい , 廣瀬浩士 , 鬼頭勲
ページ範囲:P.1304 - P.1308
要約 目的:広範囲の外傷性毛様体解離に伴う低眼圧黄斑症が遷延し,種々の手術で軽快せず,最終的に眼内レンズ縫着術が奏効した1例の報告。
症例:56歳の男性が3か月前に左眼を殴打され,前房出血,広範囲の毛様体解離,低眼圧が生じた。前房出血が消退した後,眼圧は8mmHg以下になり,低眼圧黄斑症が生じたため,当科を紹介され受診した。
所見と経過:矯正視力は右1.2,左0.5で,眼圧は右17mmHg,左8mmHgであった。左眼は浅前房で,外傷性白内障と低眼圧黄斑症があった。前眼部OCTで270°にわたる毛様体解離があった。薬物療法は無効で,受傷14か月後に経強膜毛様体縫合術,水晶体切除,硝子体手術と20%SF6によるガスタンポナーデを行った。低眼圧黄斑症が続いたため,受傷17か月後に毛様体解離部の冷凍凝固と強膜輪状締結術を行った。低眼圧黄斑症が続いたため,その2か月後に眼内レンズ縫着術を行った。1週間後に眼圧は43mmHgになり,低眼圧黄斑症は消退した。以後,眼圧と眼底は安定し,1.5の最終視力を得ている。
結論:遷延する毛様体解離に伴う低眼圧黄斑症は,受傷から長期間を経ても,手術療法が奏効し,本症例では人工水晶体が有効であった。
線維柱帯切開術既往眼に対する眼内内視鏡下スーチャートラベクロトミーの長期成績
著者: 玉垣瑛 , 宮原晋介 , 新井江里子 , 田中大輔 , 藤﨑竜也 , 森哲
ページ範囲:P.1309 - P.1313
要約 目的:眼外からの線維柱帯切開術が有効であった緑内障で,数年後に眼圧が再上昇した症例における,眼内内視鏡下スーチャートラベクロトミーの有効性について検討した。
対象と方法(症例):10人10眼(男性6例,女性4例)。初回手術時の年齢は,75.4±11.1歳であった。疾患の内訳は,落屑緑内障9眼,原発開放隅角緑内障1眼であった。初回手術として8時方向から線維柱帯切開術を行い眼圧下降が得られたものの,数年後に眼圧再上昇を認め,眼内内視鏡下にスーチャートラベクロトミーを初回手術以外の部位に追加施行した緑内障眼を対象とした。線維柱帯切開術以外の眼科手術歴のないものが1眼,白内障手術の既往があるものが4眼,初回手術時に白内障手術を併施したものが4眼,スーチャートラベクロトミーに白内障手術を併施したものが1眼で,いずれもレーザー治療の既往はなかった。角膜混濁を1眼に認めた。
結果:線維柱帯切開術が有効であったものの,平均で約3年後に眼圧再上昇をきたした10例10眼において,眼内内視鏡下スーチャートラベクロトミーを追加施行したところ,術前24.6±4.3mmHgから術後半年で11.1±5.5mmHgに眼圧が再下降した。
結論:眼内内視鏡下スーチャートラベクロトミーは,線維柱帯切開術後の再手術として有効であった。
視覚障害者の就労支援マニュアルの開発—支援ツールの開発
著者: 高橋広 , 氏間和仁 , 岩井克之 , 村上美紀 , 山田信也 , 山田敏夫 , 吉田治 , 近藤寛之
ページ範囲:P.1314 - P.1319
要約 目的:視覚障害者の就労支援を目的とするマニュアル制作研究の際に,視覚障害者のなかでも特に視野障害が支援者に理解されにくいがために,支援の支障となっていることが明らかとなった。そこで,タブレット端末で視野障害の状況を共有できるツールを開発したのでその有用性を紹介する。
対象と方法:北九州総合療育センター眼科を2019年2〜4月に受診した視野障害者の支援者15名に対し,ゴールドマン視野表の説明,冊子「みる 見る 診る」と開発したタブレット端末の支援ツール試作版を見せ,見え方がイメージできたかどうかを質問し,イメージできた人数を比較した。
結果:視野表の説明のみで,「少しイメージできた」者が5名で,他の10名は全くイメージができなかった。また,「みる 見る 診る」でイメージできた者は,10名であった。一方,支援ツール試作版では15名全員が視野障害のイメージができた。
結論:タブレット端末により視野障害をイメージすることが容易になり,眼疾患の理解を深めることができた。就労場面において,多くの支援者と共通の認識に立つこともできる可能性が示唆された。
連載 今月の話題
新型コロナウイルスに生じる結膜炎の臨床所見—既報のまとめ
著者: 佐々木香る
ページ範囲:P.1187 - P.1199
2020年,水様性眼脂の結膜炎患者が来院するたびに新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の可能性を考えなければならなくなった。無症候でさえ感染予防が必要だといわれる。身近では誰もが知らず,成書にも載っていない疾患である。ともかく,イメージを得るために既報から写真で学びたいと思う。本稿では,COVID-19患者に生じた眼所見に関する論文のうち,症例写真が掲載されたものを,その論文要旨とともにレビューする。
国際スタンダードを理解しよう! 近視診療の最前線・1【新連載】
—小児の近視をみたらどうすればよいか?—小児の近視は増えているか?
著者: 藤本聡子 , 川崎良
ページ範囲:P.1200 - P.1206
◆小児の近視有病率には人種差があり,日本を含めた東アジアは世界の中でも近視の有病率が高く,今後も増加すると予想されている。
◆学童の近視は年齢とともに増加傾向であるが,特に発症の低年齢化が報告されている。
◆発症年齢が低いほど,最終的な近視度数は強くなる。
Clinical Challenge・7
視神経乳頭発赤・腫脹から考える鑑別診断
著者: 石川均 , 龍井苑子
ページ範囲:P.1182 - P.1185
症例
患者:14歳,男児
主訴:両眼の視力低下
既往歴:外傷含め特記すべき事項なし
家族歴:血縁のある親族に視覚障害者なし
現病歴:1か月前から見えにくくなってきた。入学試験が近づくにつれ,症状は徐々に進行してきた。
眼炎症外来の事件簿・Case26
白内障手術後に硝子体混濁をきたした症例
著者: 原田陽介
ページ範囲:P.1208 - P.1212
患者:77歳,男性
主訴:左眼視力低下
既往歴:関節リウマチでプレドニゾロン,およびメトトレキサートを内服中であった。また,前立腺肥大,右三叉神経第1枝帯状疱疹,右眼正常眼圧緑内障の既往があった。さらに右眼網膜分枝静脈閉塞症(branch retinal vein occlusion:BRVO)による硝子体出血のため8年前に白内障手術併用硝子体手術を施行されていた。
現病歴:もともと両眼にドライアイがあり,10年以上前から近医眼科に定期的に通院していた。右眼は8年前にBRVOによる硝子体出血をきたし,硝子体手術(白内障手術併用)を施行されている。1年前に左眼白内障による視力低下があり,近医で白内障手術が施行された。術後左眼矯正視力は(0.6)から(1.0)に改善するも,前房内炎症は遷延し術後1週間で左眼硝子体混濁が出現した。その後も硝子体混濁は改善せず,白内障手術後7か月で蛍光眼底造影検査をしたところ網膜血管炎も疑われたため,プレドニゾロン30mg内服を開始した。しかし,前房内炎症および硝子体混濁は改善しなかった。左眼白内障手術から9か月後,左眼の精査加療目的で広島大学病院眼科(以下,当科)に紹介され受診した。
臨床報告
両眼性脈絡膜皺襞に伴う後天性遠視化の1例
著者: 矢田奈々 , 安川力 , 久保田敏信 , 篠島亜里 , 小椋祐一郎
ページ範囲:P.1216 - P.1220
要約 目的:両眼性に脈絡膜皺襞を認め,遠視化を伴った1例を報告する。
症例:61歳,男性。元来,近視用の眼鏡を装用していたが,最近,急に遠視寄りになり,眼鏡が不要になったため,原因精査希望で近医を受診した。
所見:両眼の遠視化と眼底後極部に水平方向に走る脈絡膜皺襞を認めた。低眼圧を認めず,他院にてCT・MRIを施行したが眼窩に腫瘤性および炎症性病変を認めなかった。頭蓋内,副鼻腔にも脳血管障害その他の占拠性病変を認めず,原因不明にて当院にさらなる精査目的で紹介された。当院初診時の視力は右0.9(1.2),左1.0(1.5),等価球面度数で右+0.25D,左−0.50D,眼軸長右22.8mm,左23.2mmであった。Bモードで眼球後壁の平坦化と視神経周囲のくも膜下腔の拡大を認めた。フルオレセイン蛍光眼底造影では皺襞に一致した淡い過蛍光のほか,インドシアニングリーン蛍光眼底造影にて視神経乳頭周囲に放射状に伸びる低蛍光の線条を認め,それに沿って眼底自発蛍光の斑状過蛍光を認めた。眼症状は固定し,頭痛その他の全身症状もなく,CT・MRIで頭蓋内病変を認めないため,髄液検査は希望されず脳脊髄圧亢進の有無は不明である。
結論:原因疾患を認めない両眼性の脈絡膜皺襞に伴う遠視化の1症例を経験した。両眼性の特発性脈絡膜皺襞による後天性遠視化の報告は海外に数十例あり,良性とされているが,発症メカニズムが不明で経過もまちまちなため,注意して経過観察する必要がある。
異なる被覆材料による緑内障チューブシャント手術中期成績の比較
著者: 植木麻理 , 小嶌祥太 , 根元栄美佳 , 前田美智子 , 河本良輔 , 杉山哲也 , 池田恒彦
ページ範囲:P.1221 - P.1227
要約 目的:緑内障チューブシャント手術における異なる被覆材料による中期成績を比較する。
方法:対象は2012年4月〜2016年3月に大阪医科大学にて同一術者がチューブシャント手術を施行し,2年以上経過観察ができた80例84眼のうちストレートタイプを挿入した29例30眼(アーメド緑内障バルブ20眼,バルベルト緑内障インプラント10眼)。チューブ被覆は自己強膜弁(F群)が13眼,保存強膜(G群)が17眼であった。術前の年齢,内眼手術既往数,緑内障手術既往数,術前眼圧に両群間の差はなかった。術後3か月,6か月,12か月,18か月,24か月の眼圧と,術後1年と2年での被覆材料下のチューブの見え方をスコア化(確認できない:1点,うっすらと見える:2点,はっきりと見える:3点,チューブ部分が隆起している:4点)し,比較検討した。
結果:眼圧は術後24か月では両群間に有意差はなかったが,6か月,12か月では有意にG群で高かった。被覆下のチューブはG群では術後1年,2年とも確認できなかったが,F群では1年で2.3±1.0,2年で3.0±1.2とG群よりも確認しやすく,経年で有意に被覆材料下のチューブ透見が進行していた。
結論:保存強膜によるチューブ被覆は自己強膜弁よりも眼圧下降効果はやや小さかったが,経年的菲薄化が少なく,チューブが露出しにくい可能性が示された。
眼内レンズ強膜内固定術の術後成績
著者: 難波倫江 , 加藤睦子 , 中山正 , 木下悠十
ページ範囲:P.1228 - P.1234
要約 目的:当院におけるT-fixation techniqueによる眼内レンズ(IOL)強膜内固定術の術後成績を後ろ向きに検討し,通常の囊内固定と成績を比較検討する。
対象と方法:岡山赤十字病院において,T-fixation techniqueでIOL強膜内固定術を行った22症例25眼を検討した。また,その僚眼に通常のIOL囊内固定が行うことができた13眼を比較対象とした。手術方法は,IOL支持部を25 G硝子体鑷子を用いて眼外へ抜き出し,強膜トンネル内に挿入した。
結果:視力は全例で改善し,logMAR視力平均0.59±0.56から0.22±0.39と有意であった(p<0.05)。屈折誤差は−0.64±1.36であった。IOL傾斜は強膜内固定術で平均6.8±4.4°,囊内固定4.4±2.1°で有意差はなかったが(p=0.09),IOL偏心は強膜内固定術で平均0.60±0.50mm,囊内固定は0.29±0.21mmと強膜内固定で有意に大きかった(p<0.05)。術後合併症として,5眼(20%)に硝子体出血,3眼(12%)に低眼圧,1眼(4%)に一時的な高眼圧,1眼(4%)にIOL支持部の結膜下脱出がみられた。
結論:IOL強膜内固定術は僚眼のIOL囊内固定と比較して,IOL傾斜は有意差はなかったが,IOL偏心が有意に大きかった。今後は,屈折誤差や傾斜および偏心をさらに最小限にするべく,手術手技や固定位置の工夫などをしていくことが重要である。
今月の表紙
眼内炎
著者: 佐藤信之介 , 坂本泰二
ページ範囲:P.1186 - P.1186
症例は78歳,女性。近医にて白内障手術施行した後,右眼の視力低下を自覚した。術後眼内炎となり当院を紹介され受診となった。初診時の視力は右0.07(矯正不能),左0.07(0.2×+3.00D()cyl−1.00D 65°)。右眼の前房内に炎症細胞およびフィブリンがみられ前房蓄膿を認めた。眼底は,硝子体混濁のため透見困難であった。右眼に25G経毛様体扁平部硝子体切除とIOL抜去術を行い,術後も炎症細胞,硝子体混濁はみられたが1か月後には消失した。2か月後にはIOL挿入術を行い,右眼の視力は(1.0×+0.50D()cyl−1.75D 120°)まで改善した。
撮影はTOPCON社製スリットランプSL-D7にNikon社製デジタルカメラD300を取り付けた装置で行った。スリットの縦幅は最大で,横幅は約2mmと広げ,撮影光量を上げた。前房内の炎症細胞を強調するために背景を消し,スリット光の角度を,約70°と大きくつけた。
海外留学 不安とFUN・第57回
ボストン・マサチューセッツへ行く!・1
著者: 中川迅
ページ範囲:P.1214 - P.1215
2019年4月より米国マサチューセッツ州ボストンにあるSchepens Eye Research Instituteに留学する機会に恵まれ,大変貴重な経験を積ませていただいております。これからの海外留学を検討されている方への一助となれば,と私の留学記を書かせていただきます。
Book Review
がん診療レジデントマニュアル 第8版 フリーアクセス
著者: 南博信
ページ範囲:P.1250 - P.1250
『がん診療レジデントマニュアル』が改訂され第8版が出版された。初版が世に出されたのが1997年だから22年にもわたって利用されていることになる。本マニュアルは疫学・診断から治療までを要領よく網羅しコンパクトサイズにまとめているため,白衣のポケットに入れてベッドサイドで知識を確認するために便利に活用できる。国立がん研究センターの若手内科医が書いているので,治療それも薬物療法が中心にまとめられている。がん薬物療法に携わっている内科医がよく利用しているのも理解できる。
目を通してもらうとわかるが,本マニュアルの薬物療法の記載にはすべて根拠論文が示されている。患者さんは一人として同じ人はいないのだから,マニュアルだけでは実際の治療はできない。必ず根拠論文をあたって,その治療をどのような患者さんのどのような状況でどのように使うべきか,その効果の大きさと副作用の程度からどのくらいの有用性が期待できるのかを把握してから治療に当たる必要がある。今は病棟や外来でも簡単にインターネットにアクセスできる時代である。この根拠論文は必ず役に立つはずである。逆に言えば,必ず根拠論文をあたってから治療に臨まねばならない。治療の根拠論文にすぐたどり着けるという意味でも,本マニュアルは非常に便利な一冊である。
Dr.セザキング直伝! 最強の医学英語学習メソッド[Web動画付] フリーアクセス
著者: 清澤宝
ページ範囲:P.1258 - P.1258
“USMLE”と聞いて,憧れをもちつつも,ハードルが高いように感じて挑戦するに至らなかった学生も少なくないはず。「そもそもUSMLEって何から手をつけるの?」「英語力はどれくらい必要なの?」「自分でも合格できる可能性はあるの?」といったさまざまな疑問によって,やがては「やっぱりやめときますわ!」に落ち着いてしまう。そんな学生にとって,本書は必読の書籍ではないかと感じた。まさに英語力ゼロに近い状態からUSMLE最高得点を叩き出したDr.セザキングの医学英語学習メソッドは,英語に苦手意識を持つ学生に夢や希望を与える。
第1章から第4章では「なぜ英語力に乏しかったDr.セザキングがUSMLEに合格できたか?」「USMLE合格という目的を達成するために,どのように英語を勉強するべきか?」ということが具体的に書かれており,USMLEをゼロから勉強するための事前準備が明確になるであろう。また医学英語を勉強する上で非常に役立つ知識や考え方がユーモアたっぷりに書かれているので,USMLEを受験しない医学生にとっても医学英語を勉強するきっかけになるに違いない。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1178 - P.1179
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1180 - P.1181
べらどんな Hans Goldmann
著者:
ページ範囲:P.1240 - P.1240
眼科の外来から“ゴールドマン”の名がついた器械が一斉に消えたら,さぞスッキリし,広く感じられるだろうかと思う。細隙灯顕微鏡や視野計がなくなるのである。
Hans Goldmann(1899〜1991)は,チェコのプラハに生まれた。当時は,オーストリア帝国の一部である。1924年にスイスのベルン大学眼科に移った。
学会・研究会 ご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1320 - P.1321
アンケート用紙
ページ範囲:P.1326 - P.1326
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1327 - P.1327
あとがき フリーアクセス
著者: 稲谷大
ページ範囲:P.1328 - P.1328
前回,私が「あとがき」を執筆したのは4月号でしたが,振り返って読み返してみると,ARVOに参加しようかどうか,呑気なことを書いていました。その後,ARVOが開催中止となり,次々と国際学会の中止延期が続いています。ついに,第74回臨床眼科学会も現地開催は見送りWEB開催となりました。
自粛の長期化で,日本のGDPが年率27.8%減少という戦後最悪の落ち込みを記録しています。新型コロナウイルスが今後消滅することは考えにくく,インフルエンザウイルスのように新々型コロナも登場するかもしれません。どこかで見切りをつけないといけないのですが,このままズルズルいきそうな社会の空気になってしまっています。社会の空気を変えることは難しく,むしろこのウィズコロナを乗り切るためには,対面形式ではなくWEBでの学会発表や会議,授業に慣れていく必要があります。今までなんとなく苦手でお断りしていたのですが,私もウィズコロナの5G時代に対応すべく,積極的にWEB発表を引き受けることにしました。なんだかユーチューバーかラジオのDJになったみたいで,慣れてしまえば結構楽しいものです。
基本情報
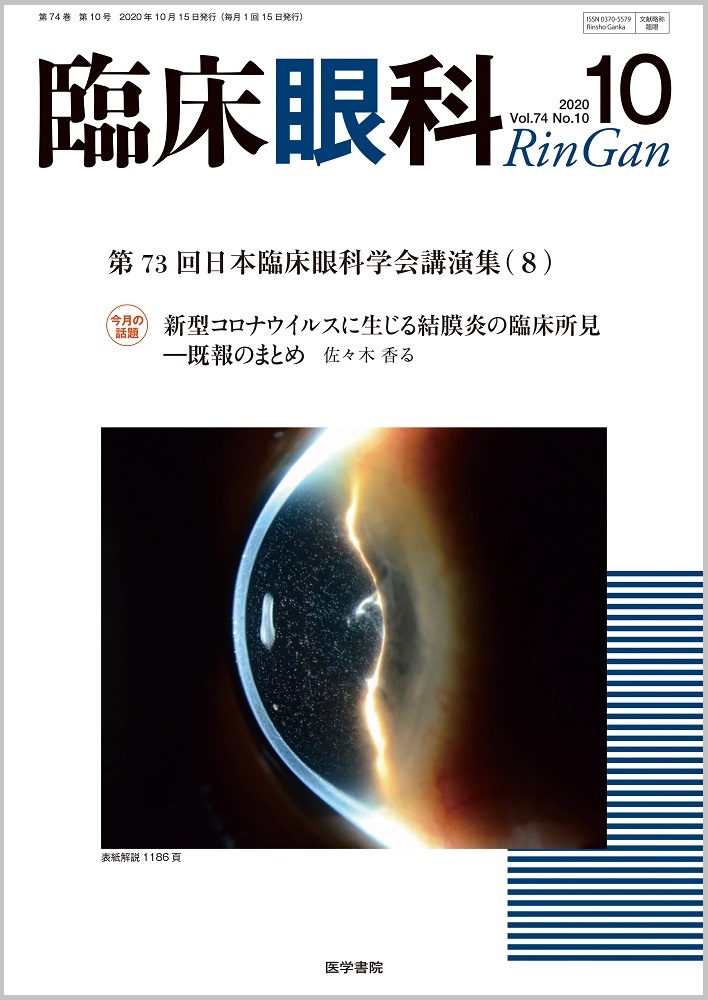
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
