皆さんは,患者への検査や手術の同意説明はどのようにされておられますか? 医療法第1条の4第2項には,「医療を提供するに当たり,適切な説明を行い,医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」と明記されています。したがって,私たち医師は患者に十分な説明を行う義務を負っているといえます。
十分な説明を行うために,DVDなどの資材を活用されている先生も多いと思いますが,やはり説明文書として書面記録を残しておくことは大変重要です。しかしながら,その説明文書は各施設で独自に工夫して作成されていることが多く,場合によっては,自分が勤めていた前の施設の同意書を流用して加工したり,気がついたらもう10年ぐらい改訂してなかったりしているのではないでしょうか? また,新しい術式を導入したときに,一から文書を作成するのも大変な作業ですし,重要な説明が漏れたりしていないか気になるところです。
雑誌目次
臨床眼科74巻11号
2020年10月発行
雑誌目次
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
序文 フリーアクセス
著者: 稲谷大
ページ範囲:P.5 - P.5
1 眼瞼
眼瞼内反症手術
著者: 木下慎介
ページ範囲:P.12 - P.13
手術・治療の概要
眼瞼内反症は,加齢による変化や瘢痕などのさまざまな原因により眼瞼が内反した状態であり,その原因を正確に診断して外科的介入を行うことで根治が得られる疾患である。
加齢性眼瞼内反症は,眼瞼水平方向,およびcapsulopalpebral fascia(CPF)の瞼板枝や皮膚穿通枝が弛緩することで瞼板が回転しやすくなり,さらに眼輪筋前隔膜部が眼輪筋前瞼板部に乗り上げやすい状態になることで下眼瞼の内反が生じる1)。一方,瘢痕性眼瞼内反症は,眼瞼結膜側の拘縮が主たる原因である2)。このような違いから,それぞれに対する外科的介入の方針は大きく異なっており,両者の鑑別が非常に重要である。
睫毛内反症手術—切開法
著者: 太田優
ページ範囲:P.14 - P.15
手術・治療の概要
睫毛内反症とは,余剰皮膚などの眼瞼前葉の過剰により,睫毛が内反し,眼表面に接触し角膜上皮障害などを起こす状態を指す(図1)。多くは先天的なものであり小児によくみられる。充血,流涙,角膜びらんによる羞明,不正乱視,睫毛の角膜への接触が高度であると角膜混濁による視力低下を起こすこともある。
手術は一般的に年齢に応じて,小児であれば全身麻酔,成人であれば局所麻酔で行う。
睫毛内反症手術—内眥形成術
著者: 石嶋漢
ページ範囲:P.16 - P.18
手術・検査の概要
上眼瞼の先天性睫毛内反症は,眼瞼の前葉(皮膚,筋肉など瞼の表面側の組織)の相対的な多さや,いわゆる二重瞼でないため皮膚が目側に移動しやすいことにより,睫毛が角膜に触れさまざまな症状を生じる。目の内側にある皮膚が眼瞼皮膚を牽引し,内反症の原因になっている場合がある(図1)1)。
睫毛が目に当たると痛みや違和感があり,重症化すると角膜潰瘍,弱視の原因となる。視力発達の原因と考えられる場合は手術を早期に行う。そのため,眼科にて視力検査,角膜に傷ができていないかを確認する必要がある2)。
皮膚弛緩症手術
著者: 田中波
ページ範囲:P.19 - P.21
病態
皮膚弛緩症は,加齢により皮膚が瞼縁を越えて下垂することで視野障害を生じたり,押し下げられた睫毛が角膜に接触することで点状表層角膜炎を生じるなど,さまざまな症状をきたす疾患であり(図1),同時に,患者は眼瞼の重さを高率に訴える。偽眼瞼下垂の1つで,加齢により瞼縁が下垂する眼瞼下垂症と区別されるが,両者はともに退行性変化であるため合併することも多い1)。垂れ下がった皮膚を持ち上げると瞳孔領が確認できる。
眼瞼下垂症手術—挙筋短縮術
著者: 松田弘道
ページ範囲:P.22 - P.23
手術・治療の概要
退行性眼瞼下垂は,上眼瞼挙筋腱膜の瞼板からの離断や上眼瞼挙筋の筋力低下などの原因で発症する1)。初期症状には開瞼時の負荷の自覚があり,下垂の進行に伴い上方視野が狭くなってくる。また,顔貌の変化(上眼瞼溝の深化,重瞼線・眉毛高の上昇)や頭痛,肩こり,眼精疲労といった訴えも多い。眼瞼下垂の重症度はmargin reflex distance-1(第一眼位でペンライトを正面から当てた際,角膜上の反射光と上眼瞼縁までの距離)と挙筋機能(眉毛部を指で押さえた状態で下方視から上方視における上眼瞼縁の移動距離)で表される。挙筋短縮術は径皮膚もしくは径結膜アプローチから上眼瞼挙筋群(上眼瞼挙筋腱膜・Müller筋)を前転させる術式であり,挙筋機能が比較的保たれている症例に対してよい適応となる。
眼瞼下垂症手術—吊り上げ術
著者: 松田弘道
ページ範囲:P.24 - P.25
手術・治療の概要
前頭筋吊り上げ術は,上眼瞼と眉毛部を吊り上げ材で連結し,前頭筋の収縮力を利用して瞼を挙上させる方法である。挙筋機能不良の眼瞼下垂に対して適応となり,主な対象疾患には先天性眼瞼下垂,外眼筋ミオパチー,先天性外眼筋線維症,動眼神経麻痺,重症筋無力症がある。自覚症状は,下垂の重症度に応じた上方視野障害,整容上の不利益(顎上げ頭位,眉毛高の上昇,重瞼線の左右差)であり,小児の場合には視性刺激遮断弱視や屈折異常弱視といった視機能発達の面でも注意する必要がある。使用される吊り上げ材は自家組織として大腿筋膜や側頭筋膜,長掌筋腱など,人工素材としてゴアテックス®やシリコーンチューブ,ナイロン糸などがある1)。各材料の特徴やそれに伴う合併症をよく理解したうえで選択することが重要である。
睫毛乱生症手術
著者: 國正茜
ページ範囲:P.26 - P.26
手術・治療の概要
睫毛乱生とは,睫毛の生えている方向や配列の乱れにより,眼瞼内反がないにもかかわらず睫毛が角膜や結膜に当たっている状態である。原因としては特発性のものがほとんどであるが,毛根周囲の炎症による配列の変化で生じることもある(例えば,外傷・術後,結膜炎による結膜瘢痕など)。その他,睫毛重生も原因として挙げられる。
診断には臨床的に行い,フルオレセイン染色にて角膜の状態を確認する。治療方法としては,睫毛抜去,レーザー毛根破壊術,睫毛電気分解,Lid splitting,毛根切除などが挙げられる。
霰粒腫摘出術
著者: 濱岡祥子
ページ範囲:P.27 - P.29
手術・治療の概要
霰粒腫とは,マイボーム腺に生じる慢性肉芽腫性炎症であり,瞼板内に限局しているものと,進行して瞼板前面を破壊し眼瞼前葉にまで炎症が及ぶものに大別される1)。
見た目が脂腺癌と類似しているため,特に脂腺癌の好発年齢の患者(図1)においては鑑別は重要である。霰粒腫と脂腺癌の例を図2に示す。このように,前眼部所見から霰粒腫と脂腺癌を鑑別するのは専門家でも困難な場合があり,少しでも疑わしい場合は生検して病理を確認する必要がある。
眼瞼腫瘍切除術
著者: 飯田知子
ページ範囲:P.30 - P.31
手術・治療の概要
眼瞼腫瘍は,本人ではなく医師が気づいて指摘することが多いというのが筆者の印象である。腫脹そのものには気がついていても,単なる“いぼ”だと思って放置し,初診時にはかなり成長してしまっているものもみられる。大きくなってから切除すると,切除範囲も広くなり傷痕や引き攣れを残しやすくなる。悪性である場合も考えると,早期に発見し手術を勧めるべきだと考えている。
眼瞼腫瘍で最も気になるのは,悪性か良性かという点であると思われる。まずはしっかりと腫瘍を細隙灯顕微鏡などで観察することが大切である。次に形状・大きさ・色・場所・出血・潰瘍の有無などを観察する。写真撮影による記録は後から見直すこともできるので極力撮っておく。また,問診により成長スピードや再発の有無,年齢などさまざなな鑑別診断の材料を集める。もちろん確定診断は病理組織検査であり,筆者は良性と思われる腫瘍であっても患者の了承が得られれば全例に病理組織検査を行っている。
眼瞼痙攣のボトックス注射
著者: 木村亜紀子
ページ範囲:P.32 - P.33
治療法の概要
眼瞼痙攣の患者が「瞼がピクピクする」と訴えることはまずない。「瞼を閉じていたほうが楽」「まぶしくてしょぼしょぼする」「瞼がいったん閉じてしまうと開かない」という訴えが多い。軽症例ではドライアイとほぼ主訴が同じであることから,ドライアイ治療に抵抗する,あるいは無効例には眼瞼痙攣を疑い瞬目テストを行うとよい。重症例では機能的失明状態となり診断は容易である(図1)。
眼瞼痙攣の診断には瞬目テストが簡便で有用である。瞬目テストには「軽瞬テスト」「速瞬テスト」「強瞬テスト」があるが,臨床的には「速瞬テスト」がわかりやすい。「できるだけ早く瞬きをしてください」と指示し,速い瞬目をさせる。途中でリズミカルな瞬目ができなくなり強く閉瞼したり,開瞼ができなくなったりすれば陽性と判断する。軽症例も見逃すことのない有用な検査で,30秒程度行えば十分判断できる1)。
2 涙道
涙管チューブ挿入術
著者: 後藤聡
ページ範囲:P.36 - P.37
手術・治療の概要
涙道閉塞は,涙点から鼻涙管開口部までの涙道のあらゆる部分が閉塞することにより,流涙や眼脂・涙囊炎を引き起こす疾患である。その原因は諸説あるが,詳しくはわかっていない。治療法は外科的治療法しかなく,涙管チューブ挿入術と涙囊鼻腔吻合術(DCR)に大別される。DCRは閉塞部位を迂回して新たな流出経路を作製することを目的とするが,基本的には鼻涙管閉塞に対する治療である。涙管チューブ挿入術は,チューブを閉塞部位に挿入し,癒着を防止することで鼻涙管の閉塞部位を元の状態にすることが目的で,適応範囲は涙道のあらゆる部分である。DCRのほうが侵襲は大きくなるが,再閉塞が少ないとされている。
涙管チューブ挿入術の手術適応は,涙点から鼻涙管開口部のあらゆる涙道閉塞に起因する流涙や涙囊炎である。涙管チューブ挿入術とDCRのどちらを治療法として選択するかは術者によってさまざまである。侵襲の小ささから,涙管チューブ挿入術での治療が可能であれば,そちらを第一選択とすべきである。近年,涙管チューブ挿入術の際に涙道内視鏡を併用することができるようになり,また涙道内視鏡を利用したさまざまな手技も開発されてきたため1,2),従来の盲目的な挿入に比べ手術成績や再現性は向上した。しかし,涙囊炎合併鼻涙管閉塞では,DCRを第一選択にしたほうがよい場合がある3)。
涙囊鼻腔吻合術—鼻内法
著者: 三村真士
ページ範囲:P.38 - P.40
手術・治療の概要
涙囊鼻腔吻合術(dacryocystorhinostomy:DCR)は,鼻涙管閉塞症の治療に用いられる術式で,閉塞している鼻涙管を回避して新しく鼻内と涙囊の吻合部を作製する方法である(図1)。かつては,皮膚を切開して涙囊にアプローチする鼻外法がスタンダードであったが,より低侵襲な硬性鼻内視鏡を使用して経鼻的にアプローチする鼻内法(図2)が発展し,現在ではスタンダードとなっている施設が多い。
鼻涙管閉塞のもう1つの治療法として,涙管チューブ挿入術を用いた涙道再建術(図3)があるが,両者にはそれぞれメリット・デメリットがあるため,手術適応を決める際には両者の比較を説明する必要がある(後述)。現時点では両者の適応を決める明確なガイドラインはなく,海外では涙管チューブ挿入術では再発率が高いため,涙管チューブ挿入術は,機能性流涙症もしくは涙道狭窄症,DCRは涙道閉塞症を適応するが1),わが国では涙管チューブ挿入術の治療成績が海外に比して良好であるため,上記および患者の社会的背景を鑑みて術式を選択する。
涙囊鼻腔吻合術—鼻外法
著者: 中山知倫 , 渡辺彰英
ページ範囲:P.41 - P.43
手術・治療の概要
鼻涙管閉塞症は,鼻涙管が閉塞することにより,流涙症や涙囊炎を引き起こす疾患である。炎症に伴う涙道上皮のバリア機能の破綻が一因となっている可能性がある1)が,まだ完全には原因究明がされていない。
現在のところ,根治的な治療法は外科的治療法しかない。外科的治療法は,涙管チューブ挿入術と涙囊鼻腔吻合術(DCR)に大別される。涙管チューブ挿入術は,チューブを閉塞部位に挿入し,そのステント効果で,鼻涙管の閉塞部位を元の状態にすることが目的であるのに対して,DCRは閉塞部位を迂回して新たな流出経路を作製することを目的とする(図1)。報告により実際の治療成績はさまざまではあるが,この治療コンセプトの違いから,涙管チューブ挿入術よりもDCRのほうが侵襲は大きくなるが,涙道再建としての効果が大きいとされている。DCRの流涙改善の治療成績は術者の経験により異なるため,報告によっても異なるが,80〜99%程度2)とされる。
涙小管形成手術
著者: 松山浩子
ページ範囲:P.44 - P.45
手術・治療の概要
涙小管断裂は,外傷による涙道損傷のなかで最も頻度が高く,鈍的外傷,鋭的外傷により眼瞼裂傷が生じている症例に合併していることがある。多発外傷であることも多いため,眼球打撲,眼窩骨骨折などのその他の眼外傷の有無や全身,特に頭頸部外傷の併発の有無に注意して診察する。受傷を疑う部位のCT検査を行い,必要に応じて他科へコンサルトして緊急度の高い順に治療を進めていく。
涙点プラグ挿入術
著者: 北口善之
ページ範囲:P.46 - P.48
手術・治療の概要
近年ムチン層に働きかける点眼薬の登場により点眼治療により病状をコントロールできる症例が増えているが,点眼治療を行っても所見の改善が得られない症例はまだまだ存在する。
涙点プラグの挿入を考えるのは,点眼治療では所見や自覚症状が改善しないときである。糸状角膜炎を伴うドライアイ,涙液分泌減少型のSjögren症候群や,移植片対宿主病(graft-versus-host disease:GVHD),Stevens-Johnson症候群に伴うドライアイなどがよい適応となることが多い。角膜上皮障害がAD分類(area,densityのスコア)でA2D2以上のままで残存していることを目安とするが,角膜上皮障害が軽微な涙液層破壊時間(tear break up time:BUT)短縮型ドライアイや,ドライアイの関連疾患である上輪部結膜炎,結膜弛緩症などにおいても,自覚症状を改善する例を多数経験する。そのため,点眼療法で十分な効果が得られないときには適応としてもよい1)。一方,感染や薬剤性の角膜障害に対しては原疾患の治療をまず行う必要がある。
3 眼外傷
結膜・角膜・強膜縫合術
著者: 渡邉智子 , 妹尾正
ページ範囲:P.50 - P.51
手術・治療の概要
外傷による縫合術が必要となるのは,鈍的外力によって生じる眼球破裂や鋭的外力によって生じる穿孔性眼外傷である。眼球破裂は眼球壁が比較的薄い角膜輪部,外直筋の付着部,内眼手術歴があれば術創に関連した部位が多い。一方,穿孔性眼外傷は穿孔創が角膜など前眼部に位置することが多く,鉄片・ガラス片・コンクリート片などが飛入した場合には,眼内に残留している可能性を留意しなければならない。いずれの場合においても難治性であることが多く,複数回手術を行っても視機能を維持することが困難な場合が少なくない。
問診をとることが難しい場合もあるが,労災などとのかかわりもあり,受傷場所,日時,受傷転機,異物の飛入の可能性などできるだけ短時間に詳しく問診し,必ずカルテに記載しておく。
毛様体縫合術/虹彩整復術/瞳孔形成術
著者: 秋元正行
ページ範囲:P.52 - P.54
手術・治療の概要
毛様体縫合術は,毛様体解離に対して行われる。当院では,解離した毛様体を縫着する方法で実施している。結膜を輪部で切開して強膜を露出し,輪部より後方5mm程度から輪部後方2mmに向かって強膜半層フラップを作製する。フラップ下強膜床に輪部と平行に切開を加えて毛様体を露出する。切開部に毛様体を縫着しながら閉創し,強膜フラップを縫合したうえで結膜を縫合する。毛様体解離の範囲が狭い場合は,強膜フラップを作製せず,隅角を観察しながら,長尺針を前房から穿刺する方法で行う場合もある。
毛様体解離の存在は,長期間の低眼圧から疑われ,隅角検査によって確認されることが多い。超音波生体顕微鏡(UBM),前眼部OCT,Bモードエコーなどで毛様体上腔の存在を確認することもできる。画像を示すことで,患者さんの理解を得られやすい。術後も撮影して提示する。
眼内異物除去術
著者: 小菅正太郎
ページ範囲:P.55 - P.57
手術・治療の概要
眼内異物とは,異物が角膜または結膜・強膜を穿孔して眼内にとどまっている状態であり,失明や視機能に大きな影響を与える恐れのある眼科救急疾患である。眼内異物には前房内異物,水晶体異物,硝子体網脈絡膜異物がある。異物の種類,飛入部位,到達部位により,白内障,硝子体出血,網膜剝離,眼内炎などを合併している症例も多い。そのため,角・強膜創の縫合術,白内障や硝子体手術などについて,患者に説明する必要がある。
発症原因は青壮年,男性の作業中の受傷がほとんどで,異物は金属片が多く,その他に木片やガラス片などがある。症状は無症状から,充血,眼痛,霧視,高度な視力低下などさまざまである。異物が小さく,高速で飛入した場合には症状が乏しいこともあるので,初診時の詳細な問診(いつ・どこで・誰が・何をしていて受傷したか)は眼内異物の診断にとても重要である。
眼球摘出術
著者: 中林征吾
ページ範囲:P.58 - P.60
手術・治療の概要
眼外傷による損傷の程度はさまざまであり,前房出血,外傷性白内障,外傷性硝子体出血,角膜破裂や強膜破裂などがある。穿孔創がある場合,虹彩や硝子体,脈絡膜,網膜が眼外へ脱出することがある(図1)。
診察時には,光覚弁,手動弁,指数弁などの大まかな視力評価は必ず行っておく。眼瞼腫脹や結膜下出血,前房出血,硝子体出血のために,強膜や眼内の状態を正しく把握できない場合も多い。超音波Bモードで外傷性の硝子体出血や網膜剝離の有無,CT検査にて眼球の形状が維持できているか,眼周囲の骨折や眼内異物がないかなどを判断する。高度眼外傷の手術における麻酔は球後麻酔でも可能ではあるものの,外傷後の患者は精神的に不安定なことが多く,患者の心理を考えると全身麻酔が望ましい。全身麻酔に必要な採血,胸部写真,心電図などの検査も行う。
4 眼窩
眼窩腫瘍摘出術
著者: 馬詰和比古
ページ範囲:P.62 - P.64
手術・治療の概要
眼窩腫瘍は,眼科の日常診療では比較的稀な疾患であるが,なかには急速に進行し生命にも影響を及ぼす悪性腫瘍もあることから,迅速な検査,診断が必要となる。眼科診療の基本は細隙灯顕微鏡検査であるが,眼窩腫瘍の診断においてはCT検査およびMRI検査を用いて患者に説明をすることになる(図1)。また,多くの患者は眼瞼下垂,眼球突出などの主訴で来院することも多く,顔面写真を撮像して,画像検査と合わせて腫瘍の位置などを理解してもらう(図2)。実際の腫瘍摘出術は,診断目的に腫瘍の一部を摘出する組織生検目的と,根治目的のための腫瘍全摘出の2つに分けられる。眼科手術の多くは局所麻酔で対応が可能であるが,眼窩腫瘍摘出術の場合は,骨切り術を併用することもあるため,全身麻酔を施行することも多い。
眼窩底骨折整復術
著者: 恩田秀寿
ページ範囲:P.65 - P.67
手術・治療の概要
・眼球,視神経,外眼筋,脂肪を収めている眼窩は7つの骨(前頭骨,頰骨,上顎骨,篩骨,涙骨,口蓋骨,蝶形骨)から構成されている。そのうち上顎骨と頰骨で構成される眼窩下壁〔眼窩底(orbital floor)〕と篩骨で構成される眼窩内壁に骨折が生じやすい。
・骨折の有無は眼窩CT検査で診断し,眼窩の骨折形態から閉鎖型骨折(図1)と開放型骨折(図2)の2つに大別される1)。閉鎖型とは骨折はあるものの眼窩の形状が保たれているものであり,開放型とは明らかな骨折があり,眼窩の形状が保たれていないものをいう。閉鎖型では筋絞扼型と脂肪絞扼型で分類し,筋絞扼型では“missing rectusサイン”を認める。また術中所見から,骨折が扉(ドア)のような形状で脂肪などが隙間に挟まっていた場合をトラップドア型骨折と呼ぶ。一方,骨折が大きく落とし穴のような状態を呈し,そこに脂肪などが嵌頓していた場合を骨欠損型骨折と呼ぶ。骨折部位が亀裂のみで脂肪などの嵌頓が少ない場合を線状型骨折と呼ぶ2)。
5 神経眼科
視神経炎に対するステロイドパルス治療
著者: 辻隆宏
ページ範囲:P.70 - P.71
治療法の概要
視神経炎は,検眼鏡的に視神経乳頭浮腫がある乳頭炎型と球後型に分類される。視神経炎は,通常,特発性視神経炎を指し,予後も良好である。しかし,抗アクアポリン4(AQP4)抗体陽性視神経炎や多発性硬化症の一部として発症することもあり,再発やステロイド抵抗性のことがある。
治療は,第一にステロイドパルス療法になる。副作用の予防のため,治療前に必ず,B型肝炎,ヘルペス,梅毒などの感染症を含む末梢血検査,胸部写真や心電図検査を行う必要がある。難治性の視神経炎を想定して,治療前に,抗AQP4抗体の測定を行う。特に,感染症については十分に注意を払う必要がある。
甲状腺眼症に対するステロイドパルス治療
著者: 神前あい
ページ範囲:P.72 - P.74
治療法の概要
甲状腺眼症は,甲状腺自己抗体による自己免疫性炎症性疾患で,外眼筋,涙腺,脂肪織に炎症性の腫大が起こる。そのために,複視,眼瞼腫脹,眼球突出などの眼症状が出現する。主に甲状腺機能亢進症のBasedow病に併発するが,甲状腺機能が正常のBasedow病(euthyroid Graves' disease)や橋本病でも甲状腺自己抗体が陽性であれば,眼症状が出現することがある。Basedow病などの甲状腺疾患の発症前後3か月〜1年以内に眼症状が発症することが多いが,アイソトープ治療後や甲状腺全摘出後であっても自己抗体が上昇する症例では眼症状が出現する可能性があり,眼科での精査加療が必要になる。眼症状が軽症の場合は経過観察となるが,中等症以上の眼症状が出現した場合は,基礎疾患の治療と並行して,眼症状の治療が必要になる。
球後に炎症のある活動期の治療としてステロイドパルス治療があり,投与方法としてはソル・メドロール® 500mg×3日を3クール投与するdaily法と,週に1回500mg×6回+250mg×6回投与するweekly法が行われている。甲状腺自己抗体のうち,甲状腺刺激抗体(TSAb)が最も眼症状と相関するので1),TSAbの推移に留意しながら経過をみる必要がある。球後病変の精査はMRIにて行うことが望ましい(図1)。T1強調画像による外眼筋肥大や脂肪織の腫大と併せて,脂肪抑制のT2強調画像を撮影することで外眼筋の炎症を評価できるため,活動期や治療効果の判定が容易となる。
甲状腺眼症に対する放射線治療
著者: 渡邉志穂 , 淡河恵津世 , 廣松雄治
ページ範囲:P.75 - P.77
治療法の概要
はじめに
・Basedow病とは,甲状腺に対する自己免疫により甲状腺機能が亢進し,甲状腺腫や眼症,thyroid heart(不整脈・心不全),中毒症状(四肢麻痺),甲状腺クリーゼなどを起こす。甲状腺眼症とは,甲状腺機能異常に関連して起こる眼瞼眼窩内組織に対する自己免疫疾患で,外眼筋の(甲状腺刺激レセプター抗体などによる)炎症症状である。
・球後組織内に浸潤した活性化Tリンパ球が線維芽細胞を活性化し,グリコサミノグリカンの産生が亢進した結果,組織の浮腫や外眼筋の肥厚が引き起こされ,眼球突出などが起きる。放射線療法は,この眼窩に浸潤した活性化Tリンパ球を抑制する。
・眼症は活動期と非活動期に分けられ,活動期でも重症度により治療法が異なるので,その評価が大切である。また,甲状腺機能が良好でも眼症は進行・再発することがあり,経過観察が重要である。
・治療は禁煙し甲状腺機能の正常を保ちつつ,消炎治療を行うが,その第一選択はパルス療法である。一般的には,パルス治療の効果不十分時・治療後再炎時に放射線治療が用いられるが,併用することで効果が増強する。また,ステロイド投与総量を抑制できるという報告もある1)。
6 斜視弱視
小児のアトロピン点眼
著者: 杉原友佳
ページ範囲:P.80 - P.81
検査の概要
小児の弱視治療において,調節麻痺薬を使用して正確な屈折検査を行うことは必要不可欠である。現在,調節麻痺薬として効果が強い順に,アトロピン硫酸塩水和物点眼液(以下,アトロピン),シクロペントラート塩酸塩(以下,サイプレジン),トロピカミド点眼液,スチグミンメチル硫酸塩が使用されている。上記の点眼は,アセチルコリンと拮抗することによって副交感神経を遮断し調節麻痺作用を引き起こす。このうち調節麻痺薬として最もよく用いられているのはアトロピンとサイプレジンであるが,使用の際,アトロピンは顔面紅潮や発熱など,サイプレジンは眠気や運動失調,幻覚などの副作用を起こす可能性があることが知られている。
アトロピンの致死量は成人100mg,小児10mgで,1%アトロピン点眼液1本5mLには50mgのアトロピンが含まれているため1),点眼処方の際には患者とその家族に対して十分な説明が必要である。散瞳作用は点眼後数分で始まり,30〜40分で最大となる。作用は7〜10日間持続する2)。添付文書では幼児・小児においては0.25%に希釈して使用することが望ましいと記載されているが,最近の調査では医師の判断のもと1%または0.5%アトロピン点眼液を処方する施設も多く,点眼回数については2回/日×7日間または2回/日×5日間で実施している施設が半数以上を占めているようである3)。実際,決められた点眼方法を厳守することで6歳以下の小児においても問題なく1%アトロピン点眼液を使用することが可能であるとの報告もある4)。
斜視手術—筋弱化術
著者: 岡本真奈
ページ範囲:P.82 - P.84
手術・治療の概要
斜視とは両眼の外眼筋のバランスが崩れ,両眼の視線が合わなくなることをいい,小児では両眼視機能の発育が阻害され,成人では複視や眼精疲労が生じ,斜視角が大きい場合は整容面でも問題となる。斜視の手術には,筋弱化術,筋強化術,斜筋手術,筋移動術などがあるが,本稿では筋弱化術について解説する。
筋弱化術には,後転術,切腱術,hang back法,Faden法などがある(図1)。手技的に難易度が高いわけではないが,術量の決定が眼位予後を左右するため,術前検査は重要である。当院では,小児の場合は,調節麻痺薬による屈折検査をルーチンで行い,屈折異常があれば屈折矯正を行い,そのうえで,交代プリズム遮閉試験で斜視角を測定する。麻痺性斜視の場合はHess赤緑試験や大型弱視鏡検査なども追加する。両眼視機能検査として,Titmus Stereo Testなどの立体視検査や網膜対応検査なども行い,最終的にはプリズム順応試験を行い,小児では術後正位を狙い,成人では術後複視をきたさないように術式を決定する。乳幼児の場合にはKrimsky法や眼位写真なども参考にしている。
斜視手術—筋強化術
著者: 西村香澄
ページ範囲:P.85 - P.87
手術・治療の概要
一般的に“前後転術”といわれる術式の“前”にあたるのが筋肉の強化術である。筋肉の長さを短くして静止張力を増加させたり,筋肉を元の付着部よりも角膜側に縫着したりすることで,回転張力を増加させて眼位を矯正する方法である。
筋肉の強化術は,短縮術(resection),前転術,折りたたみ術(plication)に分類される(図1〜3)。
斜視手術—下斜筋手術
著者: 清水ふき , 宇田川さち子
ページ範囲:P.88 - P.90
手術・治療の概要
斜筋異常では上下斜視,回旋斜視が生じ,多くは代償性異常頭位を呈している。通常,広い融像幅をもち,代償頭位をとることによって良好な眼位を保っているため,斜視弱視の発生は少なく,両眼視機能も良好なことが多いとされている。そのため,主として検査に信頼性・再現性があると考えられる就学前後で手術を行うが,上下偏位が高度な症例などでは低年齢で手術に踏み切る場合もある。下斜筋過動症に対しては下斜筋弱化手術が適応となるが,上斜筋麻痺に対しても拮抗筋である下斜筋の弱化手術で対応することが多い。また,交代性上斜位に対して下斜筋前方移動術が選択されることもある。
代表的な術前検査として,以下が挙げられる。
斜視手術—筋移動術
著者: 根岸貴志
ページ範囲:P.91 - P.93
手術・治療の概要
筋移動術は,通常の筋収縮による作用ベクトルとは異なる方向に眼球を牽引できるよう,外眼筋の作用点の位置を変更する手術である。主に外転神経麻痺・動眼神経麻痺に対して行われ,Hummelsheim法(1907)1)(図1)やJensen法(1964)2)(図2)が代表的である。他に固定内斜視に対する横山法(図3)3)や,外転神経麻痺に対する西田法4)などがある。滑車神経麻痺に対する下直筋後転鼻側移動は,単に下直筋自体の外旋作用の減弱術であることから今回は含めない。
斜視手術—調節糸法
著者: 古森美和
ページ範囲:P.94 - P.95
手術・治療の概要
調節糸法は,手術後の眼位に応じて再度術量を変化させる斜視手術法である。本法を用いることで,より正確な眼位矯正が可能となる。全身麻酔で斜視手術を行い,調節糸を設置して覚醒後に局所麻酔で調整を行う方法と,局所麻酔で斜視手術を行いながら,術中に調整を行う方法がある。
適応となるのは,斜視手術のなかでも術後効果の予想が難しい場合(再手術症例,甲状腺眼症,大角度の斜視角を有する症例,眼窩壁骨折や筋断裂などの外傷後の症例など)や,通常よりも正確な矯正が必要な場合(微小角斜視,上下斜視,回旋斜視や,融像幅が小さい症例,複視を訴える症例など)である。局所麻酔での調整ができない小児や精神発達遅滞,先端恐怖症や閉所恐怖症,痛みに耐えられないなどの症例は適応外となる。調節糸法を予定する場合は,術前に詳細な問診や説明を行い,適応を判断する必要がある。
ボツリヌス毒素注射併用斜視手術
著者: 宇井牧子
ページ範囲:P.96 - P.97
手術・治療の概要
斜視に対するA型ボツリヌス毒素(botulinum toxin type A:BTX-A)治療は,わが国では2015年6月に保険適用となり,12歳以上のすべての斜視に使用できるようになった。BTX-Aは,運動神経末端でアセチルコリン放出を抑制し,神経筋伝達を阻害する。BTX-A注射によって筋の麻痺・収縮抑制を起こすこととなる。大角度の斜視に対して術中に後転術とBTX-Aを併用することで,後転術による筋の弱化効果が増強され,通常の後転術より大きな眼位矯正量を得ることができる。
BTX-A注射併用斜視手術の良い適応は,大角度の麻痺性斜視,甲状腺眼症,大角度の共同性斜視である1)。本来,BTX-A療法は注射後3〜4か月で神経末端より別の発芽が生じて筋収縮力が回復するが,筋線維の細い外眼筋では注射部位に恒久的な萎縮と線維化が生じるとの報告もある2)。BTX-A注射併用後転術を短縮術と組み合わせたり両眼後転術に加えることで,中等度以上の麻痺性斜視に対しても筋移動術を行わずに正面視で正位が得られることがあり,筋移動術による上下斜視や前眼部虚血のリスクを抑えることができる3)。
未熟児網膜症に対するレーザー治療
著者: 野々部典枝
ページ範囲:P.98 - P.99
手術・治療の概要
未熟児網膜症(retinopathy of prematurity:ROP)は,早産児に起きる血管増殖性疾患であり,現在でも小児の失明の主要因となっている。出生時の網膜血管の発育が不十分で,無血管領域より血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)などのサイトカインが発生し,網膜新生血管を生じて網膜剝離へと進行する。ROPに対するレーザー光凝固治療は,わが国では1967年から行われており,最も確立した治療である。網膜無血管領域を凝固することでVEGFの産生を抑制し,ROPの活動性を低下させることが目的である(図1)。しかし,レーザー光凝固は周辺部網膜を破壊する治療であるため,特にzone Ⅰやzone Ⅱ posteriorのような血管の伸長の短い例では凝固斑が黄斑部に及んでしまい,中心窩の形態が異常となったり,周辺視野狭窄,近視化など多くの課題を有している1)。
近年,BEAT-ROP study2)やRAINBOW study3)などの多施設前向き研究の結果,ROPに対する抗VEGF薬硝子体注射の有効性が示され,2019年にラニビズマブがROPに対する適用承認を得た。今後,ROP治療は大きな治療方針の変化が起きることが予想されるが,決してレーザー光凝固が不要となるわけではなく,抗VEGF薬単独では鎮静化できない例や,退院後頻回に通院できない例に対してレーザー光凝固と抗VEGF薬の併用が行われるなど,両者の長所を生かした効果的な治療方法が模索されている。
7 屈折矯正
オルソケラトロジー
著者: 中井義典
ページ範囲:P.102 - P.103
治療法の概要
オルソケラトロジーは,特殊なカーブをもつハードコンタクトレンズにより角膜前面のカーブを平坦に変形させ,一時的に近視の矯正を行う方法である。夜間就寝中にコンタクトレンズを装用し,日中は裸眼で生活できることを目標としている(図1)。−1.0Dから,最大−8.0D程度の近視を矯正することが可能とされている。装用を中止することで角膜は元の状態に戻るので,可逆的な屈折矯正方法であることがメリットである。最近では学童の近視進行を抑制する効果が確認され,20歳未満の症例も適応となったことにより,処方が拡大している1〜3)。
PRK
著者: 福岡秀記
ページ範囲:P.104 - P.105
手術・治療の概要
角膜は,約43D(ジオプター)程度の屈折力をもつ透明組織である。PRK(photorefractive keratectomy)は,その角膜前面をレーザーで切除して曲率を変えることで屈折力を変化させ,近視,乱視,遠視を矯正する手術である(図1)。PRKは,術後の疼痛や早期の視力改善で勝るLASIK(laser
LASIK
著者: 福井正樹
ページ範囲:P.106 - P.109
手術・治療の概要
LASIK(laser
LASIKの適応については「屈折矯正手術のガイドライン(第7版)」1)を参考にするとよい。簡単にまとめると以下のとおりである。
SMILE
著者: 小島隆司
ページ範囲:P.110 - P.111
手術・治療の概要
SMILE(small incision lenticule extraction)は,レーザー角膜屈折矯正手術に分類される屈折矯正手術である。レーザー角膜屈折矯正手術のなかで代表的なものはLASIKで,執筆時点でも世界でも最も数多く行われている屈折矯正手術である。LASIKは軽度〜中等度近視,乱視の矯正において有効かつ安全な治療法として確立しているが,いくつか欠点もある。その1つがフラップ関連の合併症である。フラップ関連の合併症には,上皮迷入,外傷によるフラップのずれ,フラップの皺などがある。また角膜神経をほぼ全周にわたって切断するため,術後にドライアイを惹起しやすいという特徴がある。
SMILEは,フェムトセカンドレーザーで角膜実質内にレンチクル(lenticule)と呼ばれる屈折矯正分に相当する角膜切除を行い(図1),2〜4mmの角膜切開から,そのレンチクルを抜き取る。このため,LASIKのようなフラップ関連合併症がほとんどないのがメリットである。ドライアイに関しては角膜知覚の低下がLASIKより少なく1),術後ドライアイの面ではLASIKよりも有利であると思われる。
ICL(通常型)
著者: 常廣俊太郎
ページ範囲:P.112 - P.113
手術・治療の概要
ICL(implantable Contact/Collamer Lens,STAAR surgical社)は,有水晶体眼に挿入する屈折矯正を目的とした眼内レンズ(IOL)である。EUで1997年に承認され,国内では2010年に厚生労働省の認可を取得した。現在ではより安全性の向上したHole ICL(ICL KS-AquaPORT,STAAR surgical社)が開発され,世界およそ75か国で使用されている。
ICLの特徴として以下の点が挙げられる。
8 角膜
全層角膜移植
著者: 山口剛史
ページ範囲:P.116 - P.118
手術・治療の概要
全層角膜移植は,角膜の病変部を切除して全層ドナー角膜組織と置換する術式で,光学的(角膜を透明にする)と治療的(穿孔部を補強する)移植がある。代表的な適応疾患は,角膜実質混濁と角膜内皮機能不全,角膜穿孔などである。今は,角膜内皮疾患は主に角膜内皮移植で治療されるが,実質混濁や瘢痕のある症例では全層角膜移植が適応となる。全層角膜移植は1900年代初頭から始まった最も歴史のある組織移植の1つで,1950年代にステロイド点眼,1970年代の近代顕微鏡手術・縫合糸・角膜組織保存法が臨床応用され,予後が改善し普及した。
全層角膜移植は,経過が良ければ視力が改善し患者に喜んでもらえるが,重篤な術中・術後合併症が起きると,術前よりも視力が低下し,「こんなはずじゃなかった」と患者を不幸にすることもある。全層角膜移植では,他の角膜移植の術式と比較して,①適応疾患が広く術前状態が患者によって異なる,②手術中にオープンスカイとなるため,水晶体・眼内レンズ(IOL)の脱臼や脱出,駆逐性出血など重篤な術中合併症があること,③拒絶反応や緑内障,感染症など術後の合併症の頻度が高いことが挙げられる。これらの説明は,患者との信頼関係の構築だけでなく,患者の病気への理解を深めることで術後合併症の予防や早期受診・早期発見につながるためにも重要である。
角膜上皮形成術/輪部移植術
著者: 冨田大輔
ページ範囲:P.119 - P.121
手術・治療の概要
角結膜の表面は「上皮細胞」で覆われており,上皮に障害が生じた場合,角膜輪部にある角膜上皮細胞のもととなる細胞(幹細胞)が増殖・移動して上皮障害が修復される。しかし,輪部機能が低下すると,角膜上皮が供給できなくなり,上皮障害が改善しない,あるいは角膜上皮の結膜化といった不具合が生じる。その結果,角膜混濁をきたし,視力障害が起こるだけでなく,遷延性上皮欠損や感染性角膜潰瘍により角膜の菲薄化・角膜穿孔を起こし,難治であることも多い。こういった症例を治療する場合,角結膜上皮と涙液をまとめて1つのユニット(オキュラーサーフェス)として扱う考え方が重要である。輪部機能不全に陥った場合,正常な輪部組織を移植するしか輪部機能を回復する方法はないわけであるが,移植後の予後は,オキュラーサーフェスが正常に保たれるかどうかが大きく左右する。
輪部機能不全をきたす原因は,Stevens-Johnson症候群,眼類天疱瘡,無虹彩症などの疾患だけでなく,重症な熱傷,化学傷などの外傷,薬剤性やビタミンA欠乏症などが挙げられる。
表層角膜移植術
著者: 谷口紫
ページ範囲:P.122 - P.124
手術・治療の概要
表層角膜移植術は,光学的角膜移植と治療的角膜移植に分けられる。光学的角膜移植は視力の向上を目的とし,比較的表層に限局する実質混濁や内皮障害を伴わない実質の変形が適応となる。疾患としては,角膜炎や感染後の瘢痕や円錐角膜などである。一方で,治療的角膜移植は,角膜形状の維持や病巣の除去を目的とし,適応は角膜穿孔眼(切迫穿孔も含む),菲薄化した角膜潰瘍,輪部デルモイドである。
治療的角膜移植を施行する場合は,眼球形態の維持や病巣除去を目的とするため緊急的に手術を決定することがあるが,保存角膜での手術も可能である。輪部デルモイドや周辺部角膜潰瘍などに対する移植では,むしろ保存角膜の使用が拒絶反応を避けるうえで有利といえる。
DALK
著者: 福井正樹
ページ範囲:P.125 - P.127
手術・治療の概要
深層層状角膜移植(DALK)とは,角膜パーツ移植の1つであり,角膜実質の病変をターゲットとして実質を移植する術式である1)。代表的な対象疾患としては,実質混濁を起こす角膜ジストロフィ,角膜実質炎・感染後の角膜混濁,実質の菲薄を伴う円錐角膜(図1)などがある。
実際の診療で注意すべき点は,内皮障害が起きていないかの判断である。スペキュラーマイクロスコープで角膜内皮細胞密度,形状を確認することが必須である(図1b)が,時として角膜実質混濁のため内皮細胞密度・形状の判定が困難であり,内皮炎を伴う病態で角膜内皮障害があると判断されるときにはDALKではなく,全層角膜移植(PKP)を選択する必要がある。
DSAEK
著者: 縣千聖 , 吉田絢子 , 宮井尊史
ページ範囲:P.128 - P.130
手術・治療の概要
角膜内皮移植術(Descemet's stripping automated endothelial keratoplasty:DSAEK)とは,角膜内皮機能不全眼に対し行われる角膜移植で,角膜内皮と深層実質の一部を移植するものである。適応疾患は,Fuchs角膜内皮ジストロフィ,偽水晶体性水疱性角膜症,レーザー虹彩切開術後の水疱性角膜症などである。
全層角膜移植(penetrating keratoplasty:PKP)に対するDSAEKの利点としては,術後乱視が少ないこと,拒絶反応のリスクが低いこと,術中open skyになることによる駆逐性出血のリスクが低いこと,創強度が高く外傷時の破裂のリスクが低いことなどが挙げられる。そのため,内皮機能不全に対する治療法として,DSAEKはPKPに替わり第一選択となっている。必要な検査としては,細隙灯顕微鏡検査(図1),スペキュラマイクロスコープ,OCT(図2),パキメータ,さらに緑内障を合併している場合は視野検査などがある。角膜混濁が進むと内皮細胞密度の計測ができなくなるので,角膜厚を中心にフォローアップする。
DMEK
著者: 親川格 , 林孝彦
ページ範囲:P.131 - P.133
手術・治療の概要
Descemet膜角膜内皮移植術(Descemet membrane endothelial keratoplasty:DMEK)は,角膜内皮機能不全眼に対する外科的治療法としてMellesらが報告1)して以降,欧米を中心に多くの施設で行われている。その対象疾患も,近年では原因疾患を問わず水疱性角膜症(bullous keratopathy:BK)眼全体に拡大されており,良好な視機能,早期からの高視力,低い拒絶反応率を獲得していることが報告されている。また,近年の前眼部におけるOCTの発達に伴い,診断および周術期・術後における評価に重用されている。術前に前眼部の写真やOCT像(図1)を患者へ供覧することで個々の現状に対する理解が深まり,治療法の提案に対して良好な医師患者関係を取りやすくなった。また,周術期においては移植片接着状態を前眼部OCTによって細部にわたる評価が可能であり,術後においても前眼部の写真やOCT像(図2)を患者へ供覧することで治療効果の実感をしてもらいやすくなった。
角膜表層切除
著者: 柿栖康二
ページ範囲:P.134 - P.135
手術・治療の概要
角膜表層切除にはエキシマレーザーを用いた表層切除(PTK)が含まれるが,本稿ではゴルフ刀などを用いて,マニュアルで表層に限局した角膜混濁や角膜感染症病巣部を除去する方法について解説する。適応となる角膜混濁疾患として,カルシウム塩が上皮下に沈着する帯状角膜変性症(図1a),隆起性病変を呈する角膜アミロイドーシスやSalzmann結節変性,眼表面扁平上皮新生物(ocular surface squamous neoplasia:OSSN)などがある。術前および術後検査として,細隙灯顕微鏡検査だけではなく,前眼部OCTで切除範囲の確認や角膜形状解析装置で角膜乱視成分の評価を行うことは重要である。
手技の実際であるが,すべての疾患に共通していることはゴルフ刀やスプリング剪刀で角膜上皮の剝離や隆起性病変を除去すること,術後はバンデージ効果による上皮化促進および疼痛予防目的にて治療用ソフトコンタクトレンズ(SCL)を装用することである。特に帯状角膜変性症では角膜上皮下にカルシウム塩が沈着しているため,まずゴルフ刀で角膜上皮を剝離した後,キレート剤であるエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(EDTA-Na2)を十分に含ませたMQA(medical quick absorber)を数分間塗布し,カルシウム塩を除去する必要がある(図1b)1)。
PTK
著者: 福本光樹
ページ範囲:P.136 - P.138
手術・治療の概要
治療的レーザー角膜切除術(phototherapeutic keratectomy:PTK)とは,エキシマレーザーで角膜表層の混濁を除去する手術手技である。エキシマレーザーはフッ化アルゴンから生じる193nmの紫外線レーザーで,熱を発せずにμm単位での平滑で正確な切除(蒸散)が可能である(図1)。また,照射周辺組織への影響がほとんどない。
手術適応は角膜表層の混濁や沈着物の除去で,さらに深い中層や深層の混濁や沈着物は不適応となる(表1)。角膜ジストロフィや帯状角膜変性が代表的な疾患である。再発性上皮びらんに対して,実質浅層を切除することにより角膜上皮基底膜の再生を促し,角膜上皮と実質の接着強化目的でPTKを施行する場合がある。
翼状片切除術
著者: 土至田宏
ページ範囲:P.139 - P.141
手術・治療の概要
翼状片は,血管を伴う結膜由来の増殖組織が主に角膜の鼻側から侵入する疾患1)である。薬物治療には反応しないため,外科的切除が治療の基本となる。翼状片頭部の先端が瞳孔領に達し,現に視力低下をきたしている場合や,そこまで到達していなくても角膜形状に変化をもたらしている場合もあるため,角膜形状解析装置による形状変化をマップ(図1)で示すと手術の必要性に関する患者の理解が深まりやすい。特に白内障に翼状片が合併している症例では,白内障のみが原因で見づらいと思っている患者も少なくないため,角膜形状変化を示すことで,角膜乱視の存在と先に翼状片手術を要する理由を説明しやすくなる。
羊膜移植
著者: 松村健大
ページ範囲:P.142 - P.143
手術・治療の概要
羊膜は眼表面手術における補助材料としての有用性が確立されており1〜3),2014年には羊膜移植術が保険収載された。羊膜移植は組織移植の1つとして位置づけられており,羊膜移植を行うためには,事前に手続きを行い,ガイドラインを遵守しての実施が不可欠である。詳細は,日本角膜学会のホームページを参照されたい。
羊膜を用いた眼表面手術には,以下の3つの方法があり,それぞれ期待する機序と適応疾患が異なる。
結膜腫瘍切除術
著者: 西野翼 , 横川英明 , 小林顕
ページ範囲:P.144 - P.145
手術・治療の概要
結膜腫瘍は球結膜,瞼結膜いずれにも,数多くの種類が発生しうる。眼腫瘍は,眼科臨床全般のなかでも馴染みにくい疾患,領域の1つとなりうるが,その原因として疾患が多岐にわたり,一般眼科臨床と関連が薄い用語が数多く存在することが挙げられる。眼科臨床医がすべての眼腫瘍を理解することは現実には困難であるが,頻度の高い腫瘍については,臨床的特徴やおおよその治療方針を理解しておく必要がある。特に悪性腫瘍については,診断の遅れが生命予後にも影響を及ぼす可能性があり,眼腫瘍専門医でなくとも診療にかかわる眼科医の責任は重い。幸い,結膜は薄く透明なため,多くの場合は腫瘍が露出ないしは透見しているため,おおかたの組織の由来を推定することができる。
病歴の聴取,視診,硝子棒などを用いての触診,細隙灯顕微鏡写真の撮影(図1,2),超音波生体顕微鏡(UBM),AS-OCT,必要に応じて採血やMRIなどの診察,検査を行う。結膜上皮下は非常に粗な組織で,腫瘍細胞が散布しやすいと考えられるため,悪性の可能性がある結膜腫瘍を切開生検・部分切除する際には,結膜腫瘍はできるだけ角膜輪部に近い部位を生検し,円蓋部結膜下に腫瘍が散布しないよう心がける。球結膜の悪性腫瘍が疑われる場合には,安全領域を1〜3mm程度とる。初回から安全域をとった全切除を行うか,生検+悪性時拡大切除を行うかなどの予定を決めるのが最も重要である。正確な臨床診断が,適切な手術プランにつながる1)。
結膜弛緩症手術
著者: 横川英明 , 小林顕
ページ範囲:P.146 - P.148
手術・治療の概要
結膜弛緩症(conjunctivochalasis)とは,球結膜がたるんだ状態であり,たるんだ結膜が下眼瞼縁に乗って認められる(図1a,b)。結膜弛緩症の詳細な原因は不明であるが,結膜の加齢変化や機械的な摩擦,炎症,涙液の不安定性などが関与すると考えられている1)。フルオレセイン染色下で観察すると,軽度の弛緩症でも指摘可能であり,随伴する涙液メニスカスの障害や角結膜上皮障害の有無も判定可能である。結膜弛緩症の大部分は無症状であるが,眼不快感(異物感,流涙,反復する結膜出血など)を生じることがある。また,結膜弛緩症に涙液減少型ドライアイやMeibom腺機能不全などの他の眼表面疾患を合併している場合がある。
結膜弛緩症が原因で眼不快感が生じている場合に治療対象となる。治療の第一選択は薬物療法であり,ドライアイ点眼や低濃度ステロイド点眼などが使用される。眼外にこぼれ出るような重症の結膜弛緩症で,薬物で自覚症状の改善が不十分な場合に手術が行われる。手術の目的は,余剰な結膜(たるみ)を減少させることでスムーズな球結膜面を再建し,涙液メニスカスを修復して自覚症状の改善を図ることである。外科的治療として,焼灼法と切除縫合法が多く行われている。
結膜囊形成術
著者: 平山雅敏
ページ範囲:P.149 - P.151
手術・治療の概要
結膜は粘膜の一種であり,血管,リンパ管に富む薄く透明な膜構造である1)。結膜は解剖学的に眼瞼結膜と眼球結膜に分かれており,結膜全体を囊状体とみなして結膜囊と呼ぶ。結膜囊は,涙液の貯留場所(リザーバー)となり,眼表面の涙液安定性の維持などの眼の生理上重要な役割を果たしている。
結膜囊形成術は,結膜囊を再建する手術である。広義には結膜弛緩症に対する手術を含むが(「結膜弛緩症手術」参照のこと),本稿では,Stevens-Johnson症候群や化学傷などの重症瘢痕性眼表面疾患や外眼手術後などの瞼球癒着などの疾患に対する手術を対象疾患とする(図1)。
角膜内リング
著者: 小島隆司
ページ範囲:P.152 - P.153
手術・治療の概要
角膜内リング(intracorneal ring segment)挿入術は,角膜内にポリメチルメタクリレート(PMMA)製のリングを埋植して屈折矯正を行う手術である。歴史は古く,もともとは通常の近視および乱視矯正手術として登場したが,エキシマレーザーの登場により,レーザー角膜屈折矯正手術にとって代わられた。しかしその後,円錐角膜の屈折矯正方法として脚光を浴び,現在は円錐角膜の治療として行われることがほとんどである。角膜内リングはarc-shortening effect(図1)によって角膜を平坦化する手術で,挿入するリングが厚くなると平坦化の度合いが強くなる。
この効果を利用して,角膜内リング挿入手術は球面,乱視度数を軽減させることが可能であり,また主に非対称成分を中心とした不正乱視成分も軽減が可能である1)。
角膜クロスリンキング
著者: 愛新覚羅維
ページ範囲:P.154 - P.156
手術・治療の概要
角膜クロスリンキング(corneal crosslinking:CXL)は,2003年にドイツのドレスデン工科大学医学部のWollensak,Seilerらにより開発された治療法で,370nmの長波長紫外線(UVA)に対するリボフラビンの感受性を利用し,角膜実質コラーゲン線維の架橋を強め,剛性を高める方法である(図1)1)。CXLは円錐角膜の進行を人工的に停止させるという新しいコンセプトの治療として,すでに有効性と安全性が確立されている。
CXLの術式は大きく標準法と改良法に分かれ,それぞれについて詳しく述べる。
9 ぶどう膜炎
アダリムマブ(ヒュミラ®)
著者: 眞下永
ページ範囲:P.158 - P.160
治療法の概要
アダリムマブ(ヒュミラ®)は腫瘍壊死因子(TNF)阻害薬の1つで,完全ヒト型抗ヒトTNF-αモノクローナル抗体である。2008年に関節リウマチに対して保険適用となり,その後も多種の自己免疫疾患に適用となり,広く使用されている。2016年に「既存治療で効果不十分な非感染性の中間部,後部又は汎ぶどう膜炎」(適正使用ガイド)に対して保険適用となった。すでにBehçet病による難治性網膜ぶどう膜炎に保険適用となっていたインフリキシマブ(レミケード®)が点滴注射製剤であるのに対し,ヒュミラ®はBehçet病以外の非感染性のぶどう膜炎にも使用できる皮下注射製剤である。初回は80mgを投与後1週間後から40mgを2週ごとに皮下注射するが,数回の指導を経れば自己注射が可能である。
ヒュミラ®の使用時に大切なことは,『非感染性ぶどう膜炎に対するTNF阻害薬使用指針および安全対策マニュアル(2019年度)』1)を順守することである。
インフリキシマブ(レミケード®)
著者: 竹内正樹 , 桐野洋平
ページ範囲:P.161 - P.163
治療法の概要
インフリキシマブ(レミケード®)は,アダリムマブ(ヒュミラ®)とともに眼科領域で用いられる生物学的製剤である。生物学的製剤とは,バイオテクノロジーを応用して生成された生体の分子を標的とする治療薬である。レミケード®はキメラ型抗腫瘍壊死因子(TNF)抗体であり,マウス由来のFab領域とヒト由来のFc領域からなる。わが国では,2007年にBehçet病による難治性網膜ぶどう膜炎の治療薬として承認された。
Behçet病は口腔内潰瘍,ぶどう膜炎,皮膚病変,外陰部潰瘍を4主症状とする原因不明の炎症性疾患であり,その他にも関節炎,消化器症状,中枢神経病変,血管炎など全身の諸臓器に炎症を引き起こす。眼症状としては,発作性に漿液性のぶどう膜炎を呈し,典型例では前房蓄膿がみられる。たび重なる眼炎症発作により不可逆的な傷害となり,患者の視機能は徐々に低下し,重症例では失明に至る。レミケード®が用いられる以前には,眼炎症発作のコントロールに難渋する症例も多く,発症10年後の最高矯正視力は平均0.1程度まで低下していた1)。
ステロイドパルス治療
著者: 青木朋恵
ページ範囲:P.164 - P.165
治療法の概要
ステロイドパルス治療とは,大量のステロイド薬を短期的かつ集中的に投与する治療法であり,強力な抗炎症作用および免疫抑制作用を期待して,通常のステロイド投与量では治療できない重篤な病態に用いられている。
眼科においてはVogt-小柳-原田病や交感性眼炎,視神経炎などでステロイドパルス治療が行われる。その場合は通常,入院のうえメチルプレドニゾロン(ソル・メドロール®)1000mg/日を3日間点滴投与し,その後プレドニゾロン換算で40〜60mg/日から内服漸減する。視神経炎に対する治療では,ステロイドパルス治療後3〜4日経過しても視機能の改善を認めなければ,再度ステロイドパルス治療を行う1)。30mg/日以下に減量できれば感染のリスクが減少するといわれているので,外来診療に切り替える場合が多い。ステロイド薬を漸減した後は眼病変の再発に注意が必要である。
10 白内障
Nd:YAGレーザー
著者: 後沢誠
ページ範囲:P.168 - P.169
手術・治療の概要
Nd:YAG(neodymium-doped:yttrium-aluminumgarnet)レーザーは,後発白内障および前囊収縮に対するスタンダードな治療である1)。安全かつ短時間で終わる治療法であるが,網膜剝離,囊胞様黄斑浮腫などの視機能に影響するような合併症も,頻度は少ないながら報告されているため,適切なインフォームドコンセントを行うことが重要である。
フェムトセカンドレーザー白内障手術
著者: 三田村麻里
ページ範囲:P.170 - P.172
手術・治療の概要
白内障手術は水晶体超音波乳化吸引術(PEA),continuous curvilinear capsulorrhexis(CCC)が考案され,現在では確立した術式となっている。フェムトセカンドレーザー白内障手術(FLACS)は2009年に初めて報告され,その後日本でも開始された。FLACSは通常の白内障手術を行う前に,専用のレーザー機器を使用して角膜切開,前囊切開,核分割を事前に計画された通りに行うものである(図1)。
術後視力や合併症率など手術成績は研究によってまちまちであるが,最新のメタ解析1)では,FLACSは通常の白内障手術方法と比較し,前囊切開不全や亀裂の発生が高く,黄斑や角膜浮腫,術後眼圧上昇も高いと結論づけられ,Zinn小帯損傷や後囊破損,硝子体ロスといった比較的重い合併症には差がないと報告されている。加えてコストもかかるFLACSではあるが,正確な前囊切開は術者の精神的および技術的負担を軽減でき,核の軟化や正確な位置での角膜切開(強主経線切開,limbal relaxing incisionsやintrastromal astigmatic keratotomy),その再現性の高さなど,FLACSでなければ行うことができない部分もある。白内障を治すだけでなく,より良い視機能と多様性を求められる近年では,手術の選択肢の1つとして呈示されることが望ましい。
トーリック眼内レンズ
著者: 長谷川優実
ページ範囲:P.174 - P.176
手術・治療の概要
トーリック眼内レンズ(IOL)とは,白内障手術時に乱視矯正も同時に行うことができるIOLである。現在日本で承認されているトーリックIOLは,多焦点IOLも合わせて表1の通りである。術前の角膜乱視に,手術による惹起乱視を加えて,術後の残余乱視を予測し,それに合わせたトーリックモデルと固定軸をカリキュレーターで計算して決定する。カリキュレーターには,各社が公開しているウェブカリキュレーターや,眼軸長測定装置に内蔵されているカリキュレーター,CASIA(TOMEY)などの前眼部解析装置に内蔵されているカリキュレーターなどがある。近年は,角膜後面に平均で0.3Dの倒乱視が存在すること1,2)が報告され,乱視矯正の精度を向上させるために,角膜後面乱視の予測値を加えた計算式や,角膜後面乱視を実測して計算に用いる方法などが考案されている。
水晶体再建術
著者: 柴田奈央子
ページ範囲:P.178 - P.179
手術・治療の概要
現在行われている水晶体再建術の多くは,水晶体超音波乳化吸引術(PEA)および眼内レンズ(IOL)挿入術であるが,状況に応じて水晶体囊外摘出術(extracapsular cataract extraction:ECCE),水晶体囊内摘出術(intracapsular cataract extraction:ICCE)が適応される。
手術適応の判断,術後屈折値の決定,IOL種類の選択,IOL度数計算のため,以下の術前検査が必要である。散瞳での細隙灯顕微鏡検査,屈折検査,角膜曲率半径計測,遠見・近見視力検査,全距離視力,コントラスト感度検査,眼軸長測定,角膜内皮細胞顕微鏡検査,瞳孔径測定,角膜形状解析検査,OCTによる黄斑の評価などである。両眼手術例における2眼目の屈折値は,Fellow Eye Self Tuning法(FEST法)1)により決定する。
小児白内障手術
著者: 松野裕樹
ページ範囲:P.180 - P.181
手術・治療の概要
小児の白内障には,出生時より水晶体混濁が認められる狭義の先天白内障,生後早期に外傷などの要因がなく発生する発達白内障,外傷などの要因で生じる続発白内障がある。乳幼児期に発症した外傷などの要因がない白内障を先天白内障と,外傷例も含めた小児期の白内障も含めて小児白内障と呼ぶこともある1)。
検査では視機能評価,眼位,細隙灯顕微鏡,超音波検査などを行う。視機能評価とは固視反射や視力検査であるが,困難な場合には選択視法(preferential looking:PL)や視覚誘発電位(visual evoked potential:VEP)も有用である。眼位検査では斜視,交代視,眼振の有無を確認する。細隙灯顕微鏡で白内障の評価をするが,必ず散瞳を行ったうえで混濁の部位や程度,虹彩後癒着の有無なども確認する。白内障による混濁が強い場合,超音波Bモードによる後眼部の評価も併せて行う。
眼内レンズ摘出
著者: 芳賀彰
ページ範囲:P.182 - P.183
手術・治療の概要
白内障手術時に挿入された眼内レンズ(IOL)に術後偏位,脱臼,混濁,屈折度数ずれなどが生じた場合にはIOLを眼外へと摘出する必要が生じる場合がある。また,近年では多焦点IOL挿入後にコントラスト感度の低下やハローなどが生じ,IOLが摘出される症例も報告されている1)。
現在のIOLはアクリル製フォールダブルレンズが主流となっており,術中に眼内にて剪刀を用いて光学部を切断することが可能であるが,ポリメチルメタクリレート(PMMA)製の光学部を有するIOLでは剪刀で切断することできず,光学部に合わせて創口を作成する必要があるため(図1),可能であれば挿入されているIOLの情報を術前に得ておくことが望ましい。
眼内レンズ強膜内固定術
著者: 田中慎
ページ範囲:P.184 - P.185
手術・治療の概要
眼内レンズ(IOL)強膜内固定術とは,IOLの支持部を強膜内に固定する術式である。本稿では,当院で行われているフランジ法のIOL強膜内固定術について解説する1,2)。IOL強膜内固定術は縫合糸を用いずにIOLを強膜へ固定するため手術操作が少なく手術時間が短縮できること,縫合糸の露出といった合併症がないことが利点としてあり,近年多くの施設で行われるようになっている。
眼内レンズ縫着術
著者: 市川浩平
ページ範囲:P.186 - P.188
手術・治療の概要
眼内レンズ(IOL)縫着術は,種々の理由によりIOLを固定するための囊が存在しない症例に対し,縫着糸を用いてIOL支持部を主に毛様溝に固定する術式である。適応として,術後無水晶体眼やZinn小帯脆弱による水晶体亜脱臼・脱臼例,IOL亜脱臼・脱臼例,白内障術中の後囊破損例などがある。
縫着術の問題点として,一般の白内障手術と異なり,IOL偏位・傾斜,硝子体出血,虹彩捕獲,囊胞様黄斑浮腫(cystoid macular edema:CME),網膜剝離,感染性眼内炎などの合併症を発症しやすいこと,IOL固定位置が通常の囊内固定と異なるために挿入IOL度数の補正が必要であること1),初回手術の影響により術前に角膜内皮細胞密度が著明に減少している症例を少なからず認めること,縫着術に適したIOLを使用する必要があること2)などがある。特に術後に発症する合併症のために術後矯正視力が術前矯正視力よりも低下する可能性があるため,術前に患者に合併症のリスクについて十分に説明を行っておく必要がある。水晶体やIOLの偏位・落下の手術説明においては,スリット写真や眼底写真を用いて行うと患者も理解しやすい。
11 緑内障
レーザー虹彩切開術
著者: 有村尚悟
ページ範囲:P.190 - P.191
手術・治療の概要
レーザー虹彩切開術は,瞳孔ブロックを引き起こす病態,すなわち閉塞隅角症・原発閉塞隅角緑内障などの狭隅角眼,水晶体膨隆・脱臼,虹彩後癒着,プラトー虹彩,小眼球などが適応となる。そのなかでもレーザー虹彩切開術の良い適応である急性緑内障発作は,放置すると失明の危険性が高く,可及的速やかに対応する。診断時は,AS-OCTが診断の助けになることも多い(図1)。発作の際は,できるかぎり早期に介入することで,ダメージを受けた視力・視野は回復する可能性がある。適応があっても安全に施行できない場合,例えば角膜混濁による視認性の低下や,施行病院における器具が不十分であるというような問題,認知症などの全身状態に問題がある場合は,観血的に水晶体再建術や周辺虹彩切除術なども考慮に入れるべきである。アルゴンレーザー虹彩切開術後は角膜内皮細胞面積の増加,あるいは角膜内皮細胞密度の減少を経験する場合があり,緑内障発作眼,滴状角膜やジストロフィなど角膜内皮に問題がある症例は,術後短期的・長期的に水疱性角膜症をきたす可能性があるので,アルゴンレーザーを使用せず,Nd:YAGレーザーのみを用いて行うことも考える。
手術原理としては,虹彩周辺部をレーザーにより穿孔し,前後房間の交通を作成する。その後,虹彩を膨隆させていた後房の房水が前房に導かれることによって,瞳孔ブロックを解除する。したがって,隅角線維柱帯以降の房水流出機能が障害されている症例では眼圧下降が得られない。
レーザー線維柱帯形成術
著者: 小島祥
ページ範囲:P.192 - P.193
手術・治療の概要
レーザー線維柱帯形成術は,線維柱帯へのレーザー照射により房水流出率を改善するものとされており,正常眼圧緑内障を含む広義の原発開放隅角緑内障,落屑緑内障,高眼圧症,ステロイド緑内障,色素緑内障などが適応となる1)。最近は,線維柱帯のメラニン色素含有細胞のみをターゲットとするQスイッチ半波長Nd-YAGレーザーを使用した選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)が主流となっている。アルゴンレーザーを用いたレーザー線維柱帯形成術と比較して低侵襲で,合併症の発症率も少ない。眼圧下降効果は20〜30%程度で2),眼圧日内変動の低減も期待できる3)。点眼治療と比較した利点として,アドヒアランス不良や点眼薬による副作用の回避が挙げられる。効果減弱時に再照射することも可能である。合併症は,一過性眼圧上昇,虹彩炎,周辺虹彩前癒着などがある。また,ノンレスポンダーが30%程度存在することには注意が必要である4)。
レーザー毛様体破壊術
著者: 小島祥
ページ範囲:P.194 - P.195
手術・治療の概要
レーザー照射による光凝固で毛様体を破壊し,房水産生を抑制することで眼圧下降を図る治療法である1)。本稿では経強膜的毛様体光凝固術の同意書をもとにした解説を行うが,レーザー毛様体光凝固術には照射方法の違いから,経強膜法,経瞳孔法,眼内法がある。定量性に乏しく,眼球癆といった重篤な副作用もある治療法で2),すでに視機能が失われていて高眼圧による疼痛を生じている症例や,複数回の濾過手術を行ってもなお眼圧コントロールが不良な症例などが適応となる。近年,マイクロパルス波による経強膜毛様体光凝固術が普及している3)。また,海外では眼内毛様体光凝固術が一般的になってきている。ともに従来の毛様体光凝固術と比較してより安全性が高いとされている。
周辺虹彩切除術
著者: 愛知高明 , 力石洋平
ページ範囲:P.196 - P.197
手術・治療の概要
周辺虹彩切除術は,原発閉塞隅角症(primary angle closure:PAC)・原発閉塞隅角緑内障(primary angle closure glaucoma:PACG)など相対的瞳孔ブロックが原因の閉塞隅角眼に対して,周辺部虹彩を切除することで前後房間の圧差を解消する術式である。
緑内障診療ガイドライン(第4版)によると,PAC・PACGの治療としては,相対的瞳孔ブロック機序のある場合はレーザー虹彩切開術(LI)または水晶体摘出術を施行し,LIが不可能な場合に周辺虹彩切除術を選択すると示されている。また,急性原発閉塞隅角症(acute PAC:APAC)・急性原発閉塞隅角緑内障(acute PACG:APACG)の治療においても,薬物治療後の瞳孔ブロックの解除目的に行うとしている1)。現在,LIの普及により周辺虹彩切除術を行うことは少なくなっている。しかし,LIによる閉塞隅角の悪化や,水疱性角膜症が発症する症例も報告されている2,3)。近年,周辺虹彩切除術よりも水晶体摘出術のほうが効果的であるとの報告もある4)。また,水晶体摘出術がLIより費用対効果も高く,予後も良いことが証明されており5),PAC・PACGやAPAC・APACGの症例に対して水晶体摘出術を選択する機会が今後多くなるであろうと予測される。しかしながら,すべての施設で水晶体摘出術が行えるわけではない。
Cyclo G6
著者: 藤代貴志
ページ範囲:P.198 - P.199
手術・治療の概要
レーザー毛様体光凝固術(Cyclo G6)は,房水を産生している毛様体にレーザー照射をすることで房水の産生の低下や流出を促進させ,眼圧の下降を目指す治療方法である。治療方法の流れとしては,①麻酔をかける,②レーザープローブを眼球に押し付ける,③レーザーを照射する,④眼帯して終了,がおおまかなものである。
①は,痛みを抑えるために,球後麻酔を行ってからレーザー治療を行う。2%キシロカインを3〜5mL程度使用している。
エクスプレス濾過手術
著者: 新田耕治
ページ範囲:P.201 - P.203
手術・治療の概要
25G V-ランスメスなどを使用して強膜弁下グレーゾーンの強膜寄りで虹彩と平行するような刺入角度で,強膜岬の直上に相当する部位で切開を施行する。強膜弁を把持しながらエクスプレス本体を回しながら挿入し,抵抗が軽くなったらエクスプレスの突出部(返しの部分)が完全に眼内に挿入されているので,デリバリーシステムのボタンを強く押し,エクスプレス本体をリリースする。
トラベクレクトミー
著者: 瀧原祐史
ページ範囲:P.204 - P.205
手術・治療の概要
緑内障の病態は十分解明されたとはいえないが,眼圧による視神経乳頭での網膜神経節細胞の軸索絞扼により,その細胞死と視野障害が生じると考えられている。トラベクレクトミーを検討するタイミングとして,可能な限り薬物治療を強化しても,視野障害が進行している,あるいは明らかな高眼圧が継続している場合などが考えられる。現在の視野障害と進行のペース,年齢,眼圧,視力1),患者の自覚症状と理解,社会的要素などを総合的に捉え,適応を慎重に検討する必要がある。視野障害進行に対しては,今一度,網膜,視神経乳頭より後方の病変など,緑内障以外の疾患が発生している可能性を除外し,緑内障の進行をみていることを確かめる。眼圧上昇に対しては,薬物治療のアドヒアランスに変化がないかも確認する。
トラベクレクトミーでは,眼内から眼外の濾過胞への房水のバイパスをつくる(図1)ことにより,眼圧下降効果が期待される。長期の眼圧下降効果を目指して,マイトマイシンCを併用する。術前評価として,強膜弁と濾過胞をどこに作成するのかを考えながら,白内障手術,硝子体手術創の有無,結膜の可動性が良好な部位を確認する2)。
トラベクロトミー眼外法/マイクロフックトラベクロトミー
著者: 髙井保幸
ページ範囲:P.206 - P.209
手術・治療の概要
わが国では,眼圧下降を図る代表的な手術方法として,濾過手術と流出路再建術が行われてきた。トラベクロトミーは線維柱帯・Schlemm管内壁を切開することで,房水流出抵抗を減少させ,眼圧下降を期待する手術で,古くから施行されてきた流出路再建術である。濾過手術と比較し,眼圧下降効果は劣るが,濾過胞を形成しないため,濾過胞に関連する合併症(感染や漏出),過剰濾過による浅前房,低眼圧黄斑症,脈絡膜剝離などの視力に影響を及ぼす合併症が少ない。
これまでのメタルプローブ(トラべクロトーム)を使用したトラベクロトミーの術式は,いずれも眼外法で結膜と強膜を切開する必要があった。近年の流出路再建術は,将来の濾過手術のための結膜温存の観点や,一般的に眼外法に比較し手術難度が低いことから,さまざまなデバイス(ナイロン糸,トラベクトーム,マイクロフック,Kahookデュアルブレードなど)を使用して眼内から線維柱帯・Schlemm管内壁を切開・除去する眼内法に移行しつつある。マイクロフックトラベクロトミーの利点は,隅角鏡を通して直視下に線維柱帯・Schlemm管内壁を切開することができるため,確実性と安全性が高いことや結膜,強膜を温存でき,低侵襲に加え,白内障手術と同時に短時間で簡便に施行できることである。
デュアルブレードを用いた流出路再建術
著者: 岡橋英里香 , 三木篤也
ページ範囲:P.210 - P.211
手術・治療の概要
緑内障とは,視神経変化,特徴的視野変化を有し,眼圧下降により進行を抑制できる疾患と定義されており,緑内障の治療は眼圧を下げることを基本としている。眼圧を下げる方法として薬物療法,レーザー治療,手術などがある。緑内障では,房水流出路の閉塞もしくは機能不全を生じると眼圧が上昇する。流出路再建術とは,線維柱帯を切開して再建することにより眼圧下降を図る手術である。
近年,低侵襲緑内障手術(MIGS)と呼ばれる従来の緑内障手術よりも侵襲の小さい手術が登場した。Kahookデュアルブレードを用いた流出路再建術はMIGSの一種である。Kahookデュアルブレードは先端の2枚のブレードにより線維柱帯を帯状に切除することができる(図1,2)。角膜に小さな創を作り,そこからデュアルブレードを挿入し,線維柱帯を切開する。白内障手術と同時に行われることが多い。
スーチャートラベクロトミー
著者: 小野岳志
ページ範囲:P.212 - P.214
手術・治療の概要
緑内障手術は大きく分けると,トラベクレクトミー(LEC)を代表とする濾過手術とトラベクロトミー(LOT)を代表とする流出路再建術がある。LOTは房水流出抵抗の存在する傍Schlemm管内皮網組織を標的とし,Schlemm管内壁と線維柱帯を120°切開することで,眼圧を下降させる術式である。
LOTの1つであるスーチャートラベクロトミー(S-LOT)は,線維柱帯の切開範囲を360°に拡大した術式で,LOTと同様に強膜弁を作製し眼の外から線維柱帯にアプローチする眼外法(図1)と,隅角鏡で線維柱帯を実際に観察しながら前房側からアプローチする眼内法(図2)がある。どちらも,先端を丸く加工した5-0ナイロン糸をSchlemm管内に挿入し,1周通糸後に糸を引っ張りながら360°線維柱帯を切開する。単独手術の術後眼圧は,LOTでは15〜20mmHg,S-LOTでは13〜15mmHgにコントロールされることが多く,S-LOTのほうがより低い眼圧を達成できると考えられている1〜4)。現在では,低侵襲緑内障手術(MIGS)の広がりで,低侵襲で将来の濾過手術に備えて結膜が温存でき,短時間で行うことができる眼内法を選択することが多い。
白内障手術併用眼内ドレーン
著者: 石田恭子
ページ範囲:P.215 - P.217
手術・治療の概要
販売名iStentトラベキュラーマイクロバイパスステントシステム(iStent)は,水晶体再建術と同時に行う,白内障手術併用眼内ドレーンである。近年提唱されている低侵襲緑内障手術(MIGS)の一種であるが,水晶体再建術と同時に行うことで保険適用となることと,日本眼科学会から出されている基準を満たす患者にのみ施行できることが,他の緑内障術式と大きく異なる点である。適応基準および選択基準を表1に,除外基準を表2にまとめる1)。
術前に,白内障手術併用眼内ドレーンの適応基準に一致するか,除外基準に該当しないかをあらかじめ検査する必要がある。つまり,眼圧測定,視野検査による病期判定,隅角鏡検査での隅角開放度と癒着の有無,スペキュラーマイクロスコープでの角膜内皮検査,また通常の水晶体再建術に準じた術前検査を行い,安全な水晶体再建術が可能か判定する。Zinn小帯脆断裂例では,iStentに硝子体が嵌頓する可能性があるため,非適応である。
アーメド緑内障バルブ/バルベルト緑内障インプラント
著者: 岩﨑健太郎
ページ範囲:P.218 - P.219
手術・治療の概要
バルベルト緑内障インプラントは,シリコーン製のチューブとプレートからなるフィルトレーションデバイスであり,房水を眼内からチューブに通してプレートに流出させ,プレート周囲に形成される結合織の被膜を通して周囲組織に房水吸収させることで眼圧下降を得る(図1)。
アーメド緑内障バルブは,シリコーン製のチューブと調圧弁をもつプレートからなるフィルトレーションデバイスである。眼圧下降の機序はバルベルトと同様であるが,一番の大きな違いは調圧弁が付いていることである。調圧弁は,理論上眼圧が6〜8mmHg以下では弁が閉じて房水が流れなくなっているため,術直後の低眼圧が起こりにくいという特徴がある(図2)。
前房洗浄術
著者: 小野岳志
ページ範囲:P.220 - P.221
手術・治療の概要
前房洗浄術は,外傷後の前房出血による高眼圧の場合以外はほとんどが術後合併症に対して行うために,(準)緊急的な手術となることが多い。前房洗浄術の具体例としては,白内障手術後に前房内に残存した水晶体皮質の除去や,前房内に残留した粘弾性物質により高眼圧をきたしている場合に,その粘弾性物質の除去などがある。緑内障手術〔トラベクロトミー(LOT)などの流出路再建術〕後に生じた前房出血により高眼圧をきたしている場合に,その出血の除去などがある。シリコーンオイルを使用した網膜硝子体手術後に乳化したシリコーンオイルにより高眼圧をきたしている場合に,その除去などがある。
本稿では,緑内障手術後の前房出血に対する前房洗浄術に関して解説する。LOTの術中に前房圧が低下し,上強膜静脈から前房内に逆流性の出血がほぼ全例で生じ,術後に前房出血を合併するが,ほとんどは術後1〜2週間で消退する。前房出血と高眼圧を同時に合併している症例も多く,前房出血が軽度で高眼圧を認める場合は,抗緑内障点眼薬の再開や追加,炭酸脱水酵素阻害薬(アセタゾラミド錠)の内服,高張浸透圧薬(D-マンニトールやグリセリン)の点滴などを高眼圧の程度に応じて段階的に行い,眼圧下降を図る。しかし,多量の前房出血(瞳孔領以上)により30mmHg以上の高眼圧が持続している場合(図1)は,急速な視野障害の進行や角膜染血症などの危険性もあるため,前房洗浄術を検討する1〜3)。
12 網膜硝子体
硝子体手術—硝子体出血
著者: 平林一貴
ページ範囲:P.224 - P.225
手術・治療の概要
硝子体出血の年間発症率は,10万人当たり7人と報告されている1)。硝子体出血の原因には増殖糖尿病網膜症,外傷,網膜裂孔,網膜剝離,網膜静脈閉塞症,後部硝子体剝離や加齢黄斑変性などがある。視力予後は原疾患によって異なるため,硝子体出血の原因を特定することが重要である。視力予後は網膜裂孔,後部硝子体剝離,網膜静脈閉塞症は比較的予後良好であるのに対して,網膜剝離や増殖糖尿病網膜症,加齢黄斑変性に続発するものは予後不良とされている2)。
眼底の透見不良な硝子体出血の場合,超音波Bモード検査にて網膜剝離や網膜裂孔の有無を確認する必要がある。早期の硝子体手術を受けた患者は,受けなかった患者と比較して視力予後が良好であったとの報告もあり3),当院においては,糖尿病や加齢黄斑変性などの硝子体出血の原因疾患が明らかでない眼底透見不良の患者に対しては早期の硝子体手術を施行している。
硝子体手術—増殖糖尿病網膜症
著者: 清水啓史
ページ範囲:P.226 - P.228
手術・治療の概要
糖尿病網膜症に対する手術は,増殖性糖尿病網膜症(proliferative diabetic retinopathy:PDR),黄斑浮腫(diabetic macular edema:DME)に対して行う場合に分けられる。
PDRの病態は,糖尿病による細小血管障害により無灌流領域が出現し,同部に新生血管が生じる。新生血管が破綻すると硝子体出血をきたす。新生血管が線維性血管増殖(fibrovascular proliferation:FVP)を形成し,硝子体とともに網膜を牽引することにより牽引性網膜剝離(traction retinal detachment:TRD)をきたす。時にはTRDに網膜裂孔を併発し,裂孔原性網膜剝離となり,増殖性硝子体網膜症に至ることもある。
硝子体手術—裂孔原性網膜剝離
著者: 佐藤智人
ページ範囲:P.230 - P.232
手術・治療の概要
裂孔原性網膜剝離(以下,網膜剝離)とは,網膜に発生した孔から硝子体液が神経網膜層と網膜色素上皮(RPE)層の間に貯留し,その結果,視細胞が変性して不可逆的な視機能障害を生じる疾患である。
網膜剝離に対する術法は,硝子体手術とバックリング手術(p.248-250参照)に大きく分けられる。硝子体手術を術法として選択すべきは,①巨大裂孔,②渦静脈膨大部より深い裂孔,③2象限以上にまたがり,かつ深さの異なる多発裂孔,④硝子体出血などによる硝子体混濁,⑤裂孔不明の症例が挙げられる。
硝子体手術—黄斑上膜
著者: 盛岡正和
ページ範囲:P.233 - P.235
手術・治療の概要
黄斑上膜(epiretinal membrane:ERM)とは,黄斑部に生じた膜様組織によって視力低下や変視症,不等像視などをきたす疾患である。近年のOCTの発達により,容易に診断されるようになり,またその画像を示すことにより患者に対する説明もしやすくなった(図1)。多くは特発性であるが,糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症などに続発して生じることもある。硝子体手術で膜様組織を剝離除去することにより黄斑形状の改善を得ることができる。変視症の検査としてアムスラーチャートやM-CHARTS(図2)などが用いられている。特にM-CHARTSは変視量として定量化できるため,手術適応の判断や術前後での変化を捉えるのに有用である1)。
硝子体手術—黄斑円孔
著者: 芳賀彰
ページ範囲:P.236 - P.238
手術・治療の概要
黄斑円孔は,特発性もしくは外傷などによって黄斑部網膜に円孔が生じ,中心視力の低下や歪視を生じる疾患である。1988年にGass1)が黄斑円孔の病態と進展に関して言及し,1991年にKellyとWendell2)が硝子体手術とガスタンポナーデで円孔を閉鎖しうることを報告したことで黄斑円孔は治療可能な疾患となった。さらに,近年のOCTの進歩によって網膜硝子体界面異常を詳細に捉えることが可能となり,黄斑円孔の病態生理に関する理解が進んでいる。
黄斑円孔に対する硝子体手術においては網膜内境界膜(ILM)の剝離によって閉鎖率は向上し3),近年では大型や陳旧性の円孔に対して円孔周囲のILMを翻転し円孔上に被覆するinverted ILM flap technique4)を行うことで,これまで円孔閉鎖が難しかった症例に対しても良好な初回円孔閉鎖率を得ることが可能となってきている。
硝子体手術—ぶどう膜炎
著者: 永田健児
ページ範囲:P.242 - P.244
手術・治療の概要
ぶどう膜炎で硝子体手術を行う目的は大きく2つに分けられる。1つは視機能の改善が目的で,もう1つは硝子体解析による検査である。ぶどう膜炎では慢性炎症により黄斑上膜が形成されることが多く,硝子体手術の適応となることがある。また,ステロイド抵抗性の硝子体混濁や黄斑浮腫でも手術が有効なことがある。一般的な黄斑上膜や黄斑浮腫と同様にOCTでの評価は重要であり,患者への説明にも有用である。眼内炎症を評価する検査機器としてフレアメータがあるが,主には血管透過性の状態を表す指標であることを理解しておく必要がある。
硝子体手術で採取した硝子体の解析は診断に有用である1)。細胞診やフローサイトメトリ解析により硝子体に浸潤した細胞の種類や悪性度を解析することができる。また,インターロイキン(IL)-10とIL-6の比は眼内リンパ腫の鑑別に有用である2)。サイトカインを解析する際には,灌流液を含まない検体を使用する必要がある。高齢者でステロイド抵抗性のぶどう膜炎をみたら眼内リンパ腫の鑑別が必要であり,硝子体生検が有用である(図1)。
硝子体手術—水晶体核落下
著者: 小南太郎
ページ範囲:P.246 - P.247
手術・治療の概要
水晶体核落下は,主に白内障手術の合併症として発生する。対処する際には,さらなる合併症を起こさないように細心の注意を払う必要がある。今回は自施設にて白内障手術執刀時に生じた場合ではなく,他院で生じた水晶体核落下に対して二次的に手術を行う場合についての対応を想定したものとする。
落下した核が非常に小さく炎症所見もあまりない症例では自然吸収される場合もあり経過観察してもよいが,たいていの場合眼圧が上昇し炎症も起こるので硝子体手術が必要となる1)。前医での白内障手術から1日でも時間が経過していると核が軟らかくなっていることが多いため,まずはカッターで処理してみる。核が固い場合には20Gで毛様体扁平部に新たに創を作製しフラグマトームを用いるか,パーフルオロカーボンを注入し落下核を前房まで上昇させて超音波水晶体乳化吸引術にて処理する。
バックリング手術
著者: 佐藤智人
ページ範囲:P.248 - P.250
手術・治療の概要
裂孔原性網膜剝離(以下,網膜剝離)に対する手術法は,バックリング手術と硝子体手術に大きく分けられる。術式の選択は術者の術法に対する慣れにもよるがバックリング手術を選択すべきは,後部硝子体剝離を伴わない格子状変性内の萎縮性円孔を原因とする若年者(特にアトピー性皮膚炎患者)の症例である〔硝子体手術を選択すべき症例は,「硝子体手術—裂孔原性網膜剝離」の項(p.230〜232)を参照のこと〕。
バックリング手術の特徴は原則,眼内操作を行わないことである。利点として,①水晶体損傷がないため術前の調節力を維持できる,②手術孔を作製しないため不測の外傷に強い(眼球破裂時における眼内容物脱出の危険性が低い)が挙げられる。そのため,スポーツを趣味(職業)としている患者では本術式の適応を考慮する。
網膜剝離に対する気体注入
著者: 安達功武 , 齋藤昌晃
ページ範囲:P.252 - P.253
手術・治療の概要
裂孔原性網膜剝離(rhegmatogenous retinal detachment:r-RD)に対する気体注入(pneumatic retinopexy:PnR)は,Hiltonら1)や恵美ら2)によって有効性が報告され,1980年代後半〜1990年代においてわが国でも盛んに行われた治療法である。しかし併発症の問題や3),低侵襲硝子体手術(MIVS)が主流となった現在において,PnRを積極的に選択すべき症例は限定的であると考えられる。近年,米国でPIVOT試験4)が報告され,硝子体手術に対する優位性を示していることから,症例の選択やそのマネジメントを再確認することは意義があると考えられる。
詳細な術式は報告により細かな相違はあるものの,目的は硝子体内に気体注入を行い,体位により網膜裂孔を気体で一時的に閉鎖させて網膜の復位を得て,そのうえで網膜光凝固術や冷凍凝固術を用いて網膜裂孔の永久閉鎖(網膜裂孔の瘢痕閉鎖)を行うというものである。
網膜裂孔に対する光凝固術/汎網膜光凝固術
著者: 山田雄貴
ページ範囲:P.254 - P.255
治療法の概要
網膜へのレーザーを用いた光凝固術は,種々の網膜疾患に欠かせない重要な治療手段の1つである1)。眼科におけるレーザー治療の適応は網膜にとどまらず,角膜疾患,屈折矯正,緑内障など多岐にわたるが,ここでは主に網膜へのレーザー治療として網膜裂孔に対する光凝固術と汎網膜光凝固術について触れる。
近年のレーザー照射機器の進歩は目覚ましい。従来のマルチカラーレーザーに加え,短波長高出力を実現し患者の痛み軽減と光凝固に要する時間を短縮したPASCALや,アイトラッキング機能により治療箇所への正確性が上昇したNavilasなどが現在臨床利用されている。レーザー機器の進歩は患者とわれわれ眼科医両者の負担を軽減していることは疑いようもないが,そもそも網膜光凝固術という治療自体が侵襲的な治療であり,個々の症例に応じた説明と同意が重要であることを忘れてはならない。
トリアムシノロンアセトニド(マキュエイド®)テノン囊下注射
著者: 小島祥
ページ範囲:P.256 - P.257
治療法の概要
糖尿病黄斑浮腫,網膜静脈閉塞症および非感染性ぶどう膜炎に伴う黄斑浮腫に対する治療としてトリアムシノロンアセトニド(マキュエイド®)のテノン囊下注射(sub-Tenon's triamcinolone acetonide injection:STTA)がある。マキュエイド®は長期作用型の副腎皮質ステロイドで,その消炎作用が黄斑浮腫を軽減させるといわれている。2017年にテノン囊下注射が保険適用となった。
マキュエイド®は白色結晶性の粉末で,テノン囊下注射の場合は1バイアルに1.0mLの生理食塩水または眼灌流液を注入してトリアムシノロンアセトニド濃度が40mg/mLになるように用時懸濁し,20mg/0.5mLをテノン囊下に注入する。
トリアムシノロンアセトニド(マキュエイド®)硝子体内注射
著者: 一尾享史
ページ範囲:P.258 - P.259
治療法の概要
トリアムシノロンアセトニド(マキュエイド®)は,糖尿病黄斑症(diabetic macular edema:DME)の治療薬として硝子体内投与で2010年より保険適用となっている。DMEの原因においては種々の要因があるとされているが,いまだ特定には至っていない。
DMEの治療法としては,一般的には抗血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)薬の硝子体内投与が多く行われている1)。しかし,その一方で抗VEGF薬に対して抵抗を示す症例も見受けられる。以前より抗VEGF薬の硝子体内投与で改善がなく,テノン囊下にステロイドを注射することでDMEの鎮静化がみられる症例があったが,そのような抵抗症例に対してマキュエイド®の硝子体内注射はテノン囊下注射より効果があると考えられる。ただ,ステロイドを硝子体内注射することで有水晶体眼は高率に白内障を引き起こすために,適応には注意を払う必要がある。また,40mgの投与のためには0.1mLの投与かつ,懸濁液が注射針内で詰まらないよう27G針での投与が必要である。そして0.1mL投与するため,眼圧上昇を解消するために注射前後いずれかで前房穿刺を行う。
13 AMD
PDT
著者: 中井駿一朗 , 三木明子
ページ範囲:P.262 - P.263
治療法の概要
光線力学的療法(photodynamic therapy:PDT)はベルテポルフィンという光感受性物質を静脈内投与し,光感受性物質が集積した部位に非発熱性レーザーを照射することで,光化学反応を惹起し,脈絡膜新生血管(choroidal neovascularization:CNV)を閉塞させる治療法である(図1)。近年における加齢黄斑変性(age-related macular degeneration:AMD)治療の第一選択は抗血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)薬の硝子体内注射である。しかし,抗VEGF薬硝子体内注射に抵抗性を示す症例や治療効果が減弱もしくは消失した耐性症例,ポリープ状脈絡膜血管症(polypoidal choroidal vasculopathy:PCV)に対して,抗VEGF薬硝子体内注射およびPDTの併用治療の有効性が示されてきており,PDTが再評価されてきている。併用治療の有効性の機序は,PDT後に発生するVEGFを抑制することでPDT後の網膜下出血や治療後早期に生じる滲出性変化が抑えられること,および抗VEGF薬自体のCNVへの効果である。
抗VEGF薬療法が主流の現在においては,PDTを施行する際には抗VEGF薬硝子体内注射を併用することが一般的である。しかしながら,注射に対する心理的抵抗が強い場合や全身的な問題がある場合には,PDT単独治療も選択肢となりうる。
抗VEGF薬硝子体内注射
著者: 柿本宙志
ページ範囲:P.264 - P.266
治療法の概要
加齢黄斑変性症(age-related macular degeneration:AMD)とは,加齢性変化に伴い黄斑部網膜に滲出性または萎縮性の変化をきたす疾患である。わが国では滲出性の変化をきたす滲出型AMDが圧倒的に多く,基本的には脈絡膜新生血管(choroidal neovascularization:CNV)の発生に伴い,網膜浮腫,網膜剝離,出血などの滲出性変化が生じることで視機能の低下をきたす。CNVの発生および伸展には血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)が重要な役割を担っており,治療の第一選択は抗VEGF療法である。眼科で承認されている抗VEGF薬は,ペガプタニブナトリウム(マクジェン®:2020年2月販売中止),ラニビズマブ(ルセンティス®),アフリベルセプト(アイリーア®)の3剤であり,滲出型AMDに対してはすべて使用可能である。
蛍光眼底造影検査
著者: 平山公美子
ページ範囲:P.267 - P.269
検査の概要
加齢黄斑変性とは,黄斑部の網膜色素上皮,Bruch膜,脈絡膜毛細血管板の加齢変化が原因で起こる疾患である。滲出型と萎縮型に分けられ,中心視力の低下や歪視の原因となる。萎縮型は治療法はないが,滲出型は黄斑の網膜下や色素上皮下に脈絡膜から新生血管が伸展し出血や滲出性変化を起こし,治療適応となるため的確な診断と鑑別が重要である(図1)。OCTの普及とともに早期発見が可能となり,以前よりも視力が良好な段階で診断し,治療を開始することが可能となってきている。その一方で,中心性漿液性網脈絡膜症や網膜静脈閉塞症といった黄斑に滲出性変化をきたす他の疾患と混同されることも多く,病状の診断・治療の評価には蛍光眼底造影検査が有用である。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.6 - P.10
基本情報
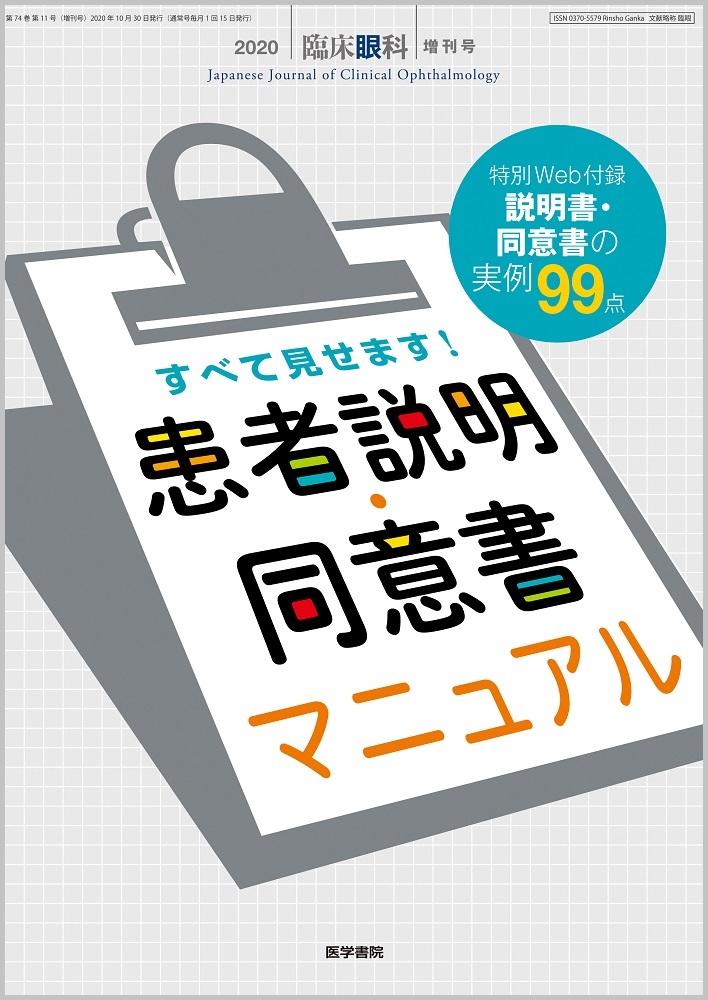
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
