最近,総合診療医が重要視されるようになってきていることは皆さんご存知だと思います.なぜそういうことになってきたかというと,医学・医療があまりに高度になってきたために一人のドクターが診られる範囲がどんどん狭くなってきて,専門家ばかりになってきたことで,病気を診ることはできても,患者を診ることができないような状況が生まれてきたことが大きいといえます.しかし,間違ってはいけないのは,総合診療医やかかりつけ医は決して患者の病気すべてがわかるわけではありません.適切にそれぞれの専門医に委ねるポイントをよく知っていることが大切です.眼科においても,このことは同じで,患者のことをよくわかっている眼科かかりつけ医の存在は重要ですが,適切な時期に適切なドクターに紹介できてこそ眼科かかりつけ医としての使命が果たされます.そういう意味で「病診連携」の重要性はとみに高まってきており,これからますます高まっていくといってよいでしょう.
もう一つの「病診連携」の側面として,コミュニケーションがあります.コミュニケーションエラーが起きると,折角の高度な医学の成果は生かされず,医療としてお粗末なものになってしまいます.我々医療者と患者の間のコミュニケーションエラー,つまりインフォームドコンセントが不十分なことが,どれだけ多くの医療事故・医療過誤を生んできたかを考えていただくとよくわかると思います.そして,実は「病診連携」というのはクリニックと病院との間のコミュニケーションに他なりません.これがうまくいくかどうかが,安全で有効な質の高い眼科医療を患者に提供できるかどうかの要になってくるのです.そしてまた,「病診連携」が全体としてうまくいくかどうかには,現在,そして今後ますます重要になってくる医師の働き方改革の成否がかかっているのです.
雑誌目次
臨床眼科75巻11号
2021年10月発行
雑誌目次
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
序文 フリーアクセス
著者: 井上幸次
ページ範囲:P.5 - P.5
1 眼瞼・結膜
細菌性結膜炎
著者: 稲田紀子
ページ範囲:P.10 - P.14
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
・発熱,眼瞼腫脹を伴う急性発症小児例は,涙道疾患,眼窩蜂巣炎に伴う結膜炎などを疑い,抗菌薬を局所投与したうえで改善しないようなら病院に紹介する.
・強い結膜充血,膿性眼脂,あるいは角膜潰瘍を伴う急性発症成人例は,淋菌感染症を疑い早急に病院に紹介する.
・眼脂および結膜充血が遷延化,寛解・増悪を繰り返す亜急性〜慢性の成人例は,クラミジア結膜炎を疑い抗菌薬を変更するか病院に紹介する.
病院で診るとき
・重症例および遷延化例では,原因菌の検索および結膜炎以外の感染巣の有無を確認する.
・原因細菌の薬剤感受性試験結果を踏まえた抗菌薬の投与を行う.
・抗菌薬全身投与のタイミングや,他科(小児科,皮膚科など)との連携を考慮する.
流行性角結膜炎
著者: 川村朋子 , 佐伯有祐
ページ範囲:P.16 - P.22
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るときのポイント
・流行性角結膜炎を疑ったら積極的にイムノクロマト法による確定診断を行う.
・角膜に非典型的な所見(広範な角膜びらんや混合感染を疑う角膜浸潤)を認めた場合は,高次医療機関へ紹介する.
病院で診るときのポイント
・大きな病院では,クリニックのように診療導線を分離することが構造上不可能なことが多いため,感染予防には特に注意する.
・見かけ上の臨床症状が重篤であっても,その原因は,ウイルスによる直接的な傷害だけではなく,患者の年齢,アトピー性皮膚炎の有無,全身,局所の免疫状態など,宿主側の免疫状態により修飾されていることに留意する.発症日から日数がどれくらい経過しているかが感染対策の助けになる.
アレルギー性結膜炎・春季カタル・アトピー性角結膜炎
著者: 海老原伸行
ページ範囲:P.23 - P.27
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・抗アレルギー薬点眼液,ステロイド点眼液,免疫抑制薬点眼液で改善しないとき.
・小児でステロイド点眼液により著明な眼圧上昇を認めるとき.
・細菌性角膜炎や角膜ヘルペスなどの角膜感染症の合併が強く疑われるとき.
・シールド潰瘍の潰瘍底の細胞残渣や角膜プラークを除去するとき.
・小児で角膜混濁や不正乱視のため視機能訓練をしないと弱視になる可能性があるとき.
・顔面や眼瞼のアトピー性皮膚炎のため眼搔破・眼叩打行動が強く認められるとき.
・舌下免疫療法を希望されたとき.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・季節性・通年性アレルギー性結膜炎で抗アレルギー薬点眼液のみで症状がコントロールできるとき.
・春季カタル・アトピー性角結膜炎で角膜上皮障害がない,または軽度のとき.
・学校・仕事の都合で待ち時間の長い大学病院への通院を希望しないとき.
眼瞼結膜腫瘤
著者: 古田実
ページ範囲:P.29 - P.32
クリニック・病院で診るときのポイント
診察する施設の規模を問わず注意すべきポイント
・眼瞼皮膚,瞼板,結膜,角膜に生じた隆起性病変もしくは炎症性病変は,腫瘍との鑑別が必要である.
・通常の点眼治療などの局所治療で改善しない病変は,診断を再確認する(腫瘍の可能性を考える).
・腫瘤や腫脹による重篤な視機能障害や痛みに対して,原因への効果的治療ができない場合,基幹施設や専門施設の医師に直接連絡して対応を決定する.
・外眼部の腫瘍性疾患を診療できる施設や医師との連携を日頃から確立しておく.
眼瞼・結膜色素沈着
著者: 兒玉達夫
ページ範囲:P.34 - P.39
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
眼腫瘍の経験が少ない一般クリニックでは,前眼部色素性病変に正確な診断をつけるのは困難なことが多い.眼腫瘍の専門家でも臨床診断を間違うことがある.大切なことは眼腫瘍を疑い,悪性腫瘍を見落とさない観察眼である.球結膜や上下眼瞼の皮膚面だけでなく,上眼瞼も翻転して瞼結膜面,涙丘部も観察する.必ず両眼を診察する.経過観察を行う場合,前眼部病変を同じ条件で画像を記録する.
クリニックから病院へ紹介するとき
・良性腫瘍と思われても増大の訴えがあるとき,経過観察で増大傾向を示すとき.
・悪性腫瘍が疑われるとき(良性・悪性の区別がつかない場合も含む).
・眼腫瘍の治療経験がないとき,治療に自信がないとき.
・良性腫瘍と思い切除したが悪性であったとき→クリニックで腫瘍切除をする場合,必ず検体を病理組織検査に提出する.病院紹介時には必ず術前の前眼部写真も添える.病理検査と術前写真も記録できないクリニックでは腫瘍切除をする資格はない.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・良性腫瘍は根治切除後.
・悪性腫瘍は加療後,再発・転移の可能性がほぼなくなったとき.
外反症・内反症・眼瞼下垂
著者: 大山泰司 , 渡辺彰英
ページ範囲:P.40 - P.46
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
《外反症》
・急性発症であれば眉毛の高さを見て顔面神経麻痺の鑑別を行う.ただし,中枢性の顔面神経麻痺であれば眉毛の位置は正常のため,可能であれば感染症に配慮しつつマスクを外してもらい口角の高さに左右差がないかも確認するほうが望ましい.
《内反症》
・年齢にかかわらず,不可逆性の角膜障害を生じる前に治療を行う.
・小児では角膜所見を確認するとともに乱視の増悪による視力低下,弱視の併発に十分注意をする.
・小児は自覚の訴えが難しいこともあり保護者からの聞き取りも参考にする.
《眼瞼下垂》
・小児の先天性眼瞼下垂では,顎上げや眉毛挙上などをしているか,瞳孔反射が得られるかを確認する.
・動脈瘤の圧迫による動眼神経麻痺鑑別のため,瞳孔の左右差や急性発症でないか必ず確認をする.
・散瞳と完全動眼神経麻痺があれば直ちに動脈瘤を疑う.
病院で診るとき
《外反症》
・原因が弛緩によるものなのか,もしくは眼瞼前葉の萎縮(皮膚瘢痕,拘縮)や後葉の過剰(瞼結膜の膨隆)によるものなのか外眼部診察を行う.
・顔面神経麻痺が疑われる場合にはその他の神経症状についても問診を行い,症状があれば頭蓋内疾患を疑い画像検索を行う.
・顔面神経麻痺で頭蓋内疾患が否定されれば,後日耳鼻咽喉科などの当該科へ対診依頼をする.
《内反症》
・眼瞼の前葉,後葉いずれが原因となっているのか診察時に確認をする.
・内反症と涙道通過障害が併存している流涙症の患者に涙道治療を先に行った場合,角膜所見が増悪することがあるので留意しておく必要がある.
《眼瞼下垂》
・日内変動や瞳孔左右差,眼球運動について評価を行う.
・急性発症で散瞳を伴った眼瞼下垂では脳動脈瘤を疑い,その日のうちに脳神経外科など当該科へ対診の依頼をする.
・片眼性の場合,僚眼の過開大(眼瞼後退)がないか評価をする.
・先天性眼瞼下垂では瞳孔反射や追視の有無をみて形態遮断覚弱視に注意する.
兎眼
著者: 鄭暁東
ページ範囲:P.47 - P.52
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・初診時すでに重症の場合.
① 角膜感染併発,穿孔の場合は早急に紹介する.
② 高度な充血,角膜上皮障害がみられた場合は,点眼,軟膏塗布治療を開始してから紹介する.
・軽症や中等症とみられても,点眼,軟膏塗布など保存的加療で改善しない場合も紹介する.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・兎眼に対して眼形成手術を行い,眼瞼形態の正常化が得られたとき.
・兎眼による眼表面の炎症が鎮静化し,上皮障害の治癒が得られたとき.
眼瞼縁炎
著者: 鈴木智
ページ範囲:P.53 - P.58
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・初診時すでに重症の場合.
① その日のうちに紹介可能→薬処方をせず紹介.
② その日のうちに紹介不可能→点眼や眼軟膏などの局所薬剤の使用歴を確認し,接触性眼瞼縁炎を疑う場合には休薬を指示,感染性眼瞼縁炎を疑う場合には(できれば眼瞼縁を擦過し培養に供してから)抗菌薬点眼,抗菌薬眼軟膏を開始して紹介.
・初診時は軽症や中等症で原因薬剤の休薬や局所抗菌薬で治らない場合→治療を変更せずに紹介.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・感染性であれば,感染が十分抑制でき,起炎菌(確定しない場合には想定でもよいが)の情報をつけて今後の抗菌薬選択の情報を提示できるようになったとき.
・薬剤アレルギーによるものであった場合には,炎症を消退させ,原因薬剤を確定し使用禁忌(あるいは要注意)薬として連絡が可能になったとき.
翼状片
著者: 上松聖典
ページ範囲:P.59 - P.62
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・通常の翼状片の場合は基本的にクリニックでの診療で問題ない.クリニックに手術設備があれば,必要に応じて手術を行う.しかし,下記の場合は病院や角膜専門施設に紹介する.
① 他の角結膜疾患に伴う結膜組織の侵入(偽翼状片)の場合,原疾患に対する治療が必要である.このような症例では術後角膜や強膜の菲薄化,時に角膜穿孔を生じることがある.
② 再発翼状片に対しては,専門施設での羊膜移植術併用の翼状片切除術1)も検討する(図1).羊膜移植ができる術者と施設は現時点では限定されており2),事前に確認が必要である.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・通常の翼状片.
・角膜への結膜侵入をきたす疾患が落ち着いたとき.
・術後,症状が落ち着いたとき.
結膜弛緩症
著者: 横井則彦
ページ範囲:P.63 - P.67
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・初診時に症状が重症(強い眼痛など)の場合.
① すぐに紹介する場合→治療を行わずに紹介.
② 治療を試みて紹介する場合→治療を開始し,改善がない場合に治療を変えずに紹介.
・初診時の症状は中等症までで,点眼治療を開始したが改善が得られない場合→治療を変えずに紹介.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・病院の点眼治療で改善が得られ,クリニックで同じ点眼治療で経過観察する場合.
・病院の外科治療で改善が得られ,クリニックで点眼治療で経過観察する場合.
2 角膜
感染性角膜炎
著者: 井上幸次
ページ範囲:P.70 - P.74
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・初診時ですでに重症の場合
① その日のうちに紹介可能→抗菌点眼薬を処方せず紹介.
② その日のうちに紹介不可能→角膜病巣を擦過して培養に供してから抗菌点眼薬を開始して紹介.
・初診時は軽症や中等症で抗菌薬や抗真菌薬を開始したが治らない場合→治療を変更せずに紹介.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・病巣の瘢痕化と前房炎症消失が完全に得られたとき.
・上皮修復したとき.
眼部帯状疱疹・角膜ヘルペス—再発性角膜上皮びらんを含む
著者: 篠崎和美
ページ範囲:P.75 - P.82
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
《眼部帯状疱疹》
・急性期で全身への抗ウイルス薬が未投与/不十分,または眼合併症や脳神経症状がみられる場合,できる限り当日中に紹介する.当日に紹介できない場合は,抗ウイルス薬内服を処方する.
・皮疹消退期で眼合併症が重症,または1週間で改善の兆しがない場合,治療は変更せずできるだけ翌日までに紹介する.眼圧上昇がある場合は対処する.
《角膜ヘルペス》
・初診時に広範囲の上皮障害や角膜潰瘍を伴う場合,加療せず当日中に紹介する.当日の紹介が困難な場合は紹介先に対応を相談する.当日に紹介も相談も困難な場合,前眼部写真撮影,角膜病巣部の擦過物の塗抹・細菌/真菌培養を行う(付着物や眼脂だけでも提出).散瞳薬で瞳孔管理,消炎を図る.
・初診時に明らかな視力障害や高度の浸潤・混濁を伴う角膜実質の炎症の場合も基本的な対応は同じだが,当日に紹介も相談もできない場合,瞳孔や眼圧管理のみ行い紹介する.
・治療開始後悪化もしくは1週間経ても改善の兆しがない場合,ステロイド薬を開始すべきか増量すべきか迷った場合は,治療を変更せず紹介する.
《再発性角膜上皮びらん》
・2〜3日しても改善がない場合,視力低下が著明な場合,頻回に繰り返す場合はできるだけ早く紹介する.
クリニックから病院へ逆紹介するとき
・いずれも沈静化が明らかになったとき.
コンタクトレンズ障害
著者: 重安千花
ページ範囲:P.83 - P.86
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・感染性角膜炎〔別稿(p.70-74)参照〕→特にコンタクトレンズ(CL)装用者では重症化しやすい緑膿菌,真菌,アカントアメーバによる角膜炎も多く,注意を要する.
・無菌性角膜浸潤・多発性角膜浸潤→感染要素が否定できず,治療効果がみられない場合.
・その他の非感染性眼障害→CLを中止し,点眼加療をしてもなお症状が改善されない場合.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・感染がコントロールされ,瘢痕化を得たとき.
・炎症が沈静化したとき.
・自覚・他覚症状が改善したとき.
・CLの調整を要するとき.
周辺部角膜浸潤・潰瘍
著者: 稲垣絵海 , 羽藤晋
ページ範囲:P.87 - P.92
クリニック・病院で診るときのポイント・クリニックから病院へ紹介するときのポイント
病院で診るとき
・鑑別診断と治療方針の選択が重要である.
① 関節リウマチなどとの鑑別と,他科との連携
② 治療方針の決定:保存的治療,Brown手術,ドナー角膜を用いた手術(角膜上皮形成術,表層角膜移植術など)
クリニックから病院へ紹介するとき
・周辺部角膜浸潤を伴う疾患のうち,保存的治療で対処可能か,穿孔するリスクが高いかの見極めが重要である.以下は,Mooren潰瘍を示唆する高リスクな所見である.
① 急性発症
② 輪部に沿って生じる円弧状潰瘍
a)細胞浸潤を伴う,b)潰瘍は急峻な掘れ込みを伴う,c)透明帯を伴わない
③ 輪部に並行して潰瘍が進展
④ 毛様充血
以上の所見があった場合は急激に進行する場合があるので,可能であればその日のうちに病院に紹介する.その日のうちに紹介不可能な場合は,ベタメタゾンリン酸エステルナトリウムの1時間ごとの頻回点眼を処方し,状況に応じて紹介を行う.
角膜形状異常—円錐角膜・ペルーシド角膜変性
著者: 高静花
ページ範囲:P.93 - P.98
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院に紹介するとき
・細隙灯顕微鏡検査では異常はないが,角膜形状異常が疑われる場合.
① 矯正視力良好,自覚症状なし,ただし乱視が強い.
② 急に眼鏡やコンタクトレンズが合わなくなった(特に若年者).
③ 若年者で,斜乱視や倒乱視あるいは乱視の度数や軸に左右差を認める.
・角膜形状異常が認められ,精査および治療が必要な場合.
① 円錐角膜の重症度の把握が必要.
② 角膜不正乱視に対する屈折矯正や治療が必要.
③ 白内障術前検査で見つかった場合は詳細な術前検査が必要.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・病院で今後の定期的な診察が不要.
・病院で今後も定期的に経過観察するが,その間での診察が必要.
角膜ジストロフィ・変性
著者: 近間泰一郎
ページ範囲:P.99 - P.105
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・初診時すでに視力低下がある場合→視力低下にジストロフィがどの程度影響しているかが明らかでなく,白内障の先行治療の可否や角膜の治療適応の有無について判断に迷うとき.
・患者がジストロフィの臨床診断,または遺伝子相談を希望する場合.
・角膜混濁の原因がはっきりせず,精査を希望する場合.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・ジストロフィの診断が臨床的に確定し,視機能が保たれているとき.
・角膜の治療(角膜表層切除や角膜移植など)が終了し,視力が安定しているとき.
・手術などの積極的治療より経過観察を患者が希望するとき.
(いずれも,視機能の低下が進行した際には再度紹介受診が必要となることもある)
角膜内皮障害
著者: 吉永優 , 相馬剛至
ページ範囲:P.106 - P.112
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・原因不明の角膜内皮障害を認めた場合.
・角膜内皮細胞密度が低く,白内障手術後に内皮障害が生じるリスクが高い場合.
・角膜移植の適応,もしくはそれに準ずる程度の角膜内皮障害を有する場合.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・原疾患が非進行性である,もしくは原疾患に対する治療により病状が落ち着いた場合.
・白内障手術後に,角膜内皮機能が維持された,もしくは回復した場合.
・角膜移植後の逆紹介は難しいが,移植医との間で緊密な病診連携が可能である場合.
ドライアイ
著者: 内野裕一
ページ範囲:P.113 - P.118
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・一般的なドライアイ点眼薬にて他覚的所見/自覚的な症状が改善しない.
・クリニックでは涙点プラグを使用できない.
・重症な涙液分泌減少型ドライアイを認めるものの,Sjögren症候群などの全身疾患の精査ができない.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・既存の処方点眼薬や人工涙液のみで,改善した自覚症状や他覚所見の維持が見込める.
・改善した自覚症状に患者自身が満足しており,定期的な診察は2〜3か月おきとなっている.
角膜化学腐食・熱腐食
著者: 大家義則
ページ範囲:P.119 - P.124
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
・角膜上皮および輪部障害の程度を観察する.
・化学腐食の場合はpHを測定する.
・pHが中性ではない場合,できれば流水で十分洗眼を行ってから紹介.
病院で診るとき
・角膜上皮および輪部障害,pH測定については同様.
・pHが中性ではない場合,流水で十分洗眼を行う.
・急性期は炎症,感染症,遷延性上皮欠損に注意が必要.
・慢性期は角膜上皮幹細胞疲弊症に対する治療を検討.
3 涙道
鼻涙管閉塞
著者: 三谷亜里沙 , 白石敦
ページ範囲:P.126 - P.130
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
《急性涙囊炎の場合》
・当日紹介が可能であれば,CT精査が可能な眼科病院に紹介する.
・当日紹介が困難な場合は,眼脂培養を提出しておき,広域抗菌薬を処方する.
・急性涙囊炎から眼窩蜂巣炎,眼窩内膿瘍など視機能障害を及ぼすものや,化膿性髄膜炎など生命にかかわる病態に進展する場合があるため,抗菌薬投与後も厳重な経過観察を短期間に行う必要がある.
《慢性涙囊炎の場合》
・基本的には根治的治療のため,涙道手術が可能な施設に紹介する.内眼手術を控えている場合,術後眼内炎のリスクを下げる意味でも内眼手術前の治療介入が望ましい.
・抗菌薬の投与を漫然と続けるべきではない.
・涙道閉塞に伴う角膜障害を合併している場合や腫瘍などの涙道外病変に伴う涙道閉塞が疑われる場合は早めに紹介する.
・先天鼻涙管閉塞の場合,1歳以降で眼脂,流涙症状の改善傾向を認めない症例は紹介を検討する.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・涙道内視鏡下涙管チューブ挿入術もしくは涙道鼻腔吻合術を施行し,術後経過に問題がないとき.
・角膜病変合併例では角膜上皮障害の改善を認めたとき.
抗がん剤による涙道障害
著者: 鎌尾知行
ページ範囲:P.131 - P.135
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・初診時ですでに涙点閉鎖または涙小管閉塞を認めるとき→可能な限り早期に病院へ紹介.
・初診時で涙点閉鎖または涙小管閉塞を認めないとき.
① 流涙症状があるときは早期に病院へ紹介.
② 流涙症状がないときは人工涙液の頻回点眼で経過観察.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・涙道再建が得られたとき.
・抗がん剤終了後.
涙囊炎・涙小管炎
著者: 宮崎千歌
ページ範囲:P.136 - P.140
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・初診時にすでに重症の場合.
① その日のうちに紹介可能→抗菌薬を投与せず紹介.
② その日のうちに紹介不可能→急性涙囊炎の場合には,眼脂培養をし,抗菌薬を点眼,必要に応じて内服,点滴をし,症状が治まらなくても早めに紹介.慢性涙囊炎,涙小管炎の場合には,眼脂培養をして,投薬せずに紹介.
・初診時は軽症や中等症で抗菌薬や抗真菌薬を開始したが治らない場合→治療を変更せずに紹介.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・根治手術が終了し,症状が消失したとき.
・根治手術がすぐに予定できず,手術までの間の保存的治療依頼のため.
4 白内障
ぶどう膜炎を併発した白内障
著者: 眞下永 , 大黒伸行
ページ範囲:P.142 - P.146
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・炎症がコントロールできていないぶどう膜炎を伴う場合:基本的にはできるだけ早期に紹介(特に小児ぶどう膜炎・強膜炎・診断のついていないぶどう膜炎に伴う症例).
① 慢性炎症で数日以内に紹介可能な場合→できれば副腎皮質ステロイド薬(ステロイド)などによる消炎を行う前に紹介.
② 急性炎症,または数日以内に紹介不能の場合→無治療時の所見を詳細に記録し,ステロイド点眼・注射治療などを開始して紹介.
・消炎が得られていても白内障手術の術中合併症リスクが高いと判断される場合:虹彩後癒着・強膜の菲薄化・高度の帯状角膜変性・水晶体動揺・続発緑内障を伴っている白内障症例→成熟白内障に至る前に紹介.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・ぶどう膜炎に対する治療方針が決まり,白内障術後3か月以上経て,点眼や局所注射のみで炎症・眼圧のコントロールが可能となったとき.
水晶体脱臼・亜脱臼
著者: 嘉村由美
ページ範囲:P.147 - P.152
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
・水晶体偏位(脱臼・亜脱臼)の原因について十分に問診して判断する.
・視力低下を自覚していない場合にはクリニックでの経過観察が可能.
・経過観察では屈折値,眼圧の変化などに注意.
手術可能な病院で診るとき
・先天性で調節力が残存している場合は,どの時点で手術を行うか十分な説明と同意が必要.
・先天性では,全身合併症について検索が必要.
・浅前房,毛様体解離の有無と範囲,眼圧などに注意して手術方針を決める.
眼内レンズ偏位・落下
著者: 市川浩平 , 太田俊彦
ページ範囲:P.153 - P.158
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・眼内レンズ(IOL)落下例は手術の適応となるため直ちに病院へ紹介.
・IOL偏位例や明らかなIOL振盪例は,視力障害,単眼複視,グレアなどの自覚症状を認めることが多く,放置すると落下のリスクがあるため直ちに病院へ紹介.
・軽度のIOL振盪を認めても,視力障害,単眼複視,グレアなどの自覚症状を認めない場合は経過観察.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・視力の回復とともに眼内の炎症がほとんど消失して,一過性高眼圧,低眼圧,硝子体出血,囊胞状黄斑浮腫,網膜剝離,術後眼内炎などの合併症を認めないとき.
眼内レンズ交換
著者: 鳥居秀成
ページ範囲:P.159 - P.166
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
眼内レンズ(IOL)交換が必要となるのは,大きく分けて次の2つの状況があり,①IOL混濁を伴う場合,②IOL混濁を伴わない場合,に大別される.①はIOL混濁によって視機能が低下している場合,②は患者がIOLの種類や度数変更を希望している場合などが該当する.以下の項目でもこの分け方で解説する.
クリニックから病院に紹介するとき
・IOL混濁を伴う場合:視機能低下がIOL混濁により生じている可能性が高く,患者がIOL交換手術を強く希望している場合.
・IOL混濁を伴わない場合:白内障手術後1か月程度経過しても,患者がIOLの種類や度数変更などによる交換手術を強く希望している場合.IOL交換に伴う合併症について患者が理解しており,それでも交換を希望しているとさらによい.
病院からクリニックに逆紹介するとき
・IOL混濁を伴う場合:IOL交換が問題なく終了し,IOLが囊内に固定できた場合.
・IOL混濁を伴わない場合:患者が希望する種類のIOLが挿入され,希望の見え方になった場合.
白内障術後眼内炎
著者: 井上真
ページ範囲:P.168 - P.172
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・初診時すでに重症.
① その日のうちに紹介可能な場合→紹介先には電話連絡を行い,入院での緊急手術が必要であることを説明してから紹介.
② その日のうちに紹介不可能な場合→起因菌が強毒菌である場合には短時間で急変するおそれがあるため,当日に対応してくれる施設を探す.
・初診時は軽症か中等症の場合→すぐに紹介する必要はない.非感染性を疑っても感染性の可能性も考慮して治療プランを立てる.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・眼内炎症が完全に消失されたとき.
・再発の可能性がきわめて低いとき.
5 緑内障
白内障合併の緑内障
著者: 庄司信行
ページ範囲:P.174 - P.179
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニック(緑内障手術を行っていない施設)で診るとき
・病型の確定もしくは推測.落屑や虹彩炎の確認.
・視力障害は白内障のため? それとも進行した緑内障のため?
① 乳頭周囲の網膜神経線維層と後極の神経節細胞層の評価.黄斑疾患の除外.
② 視野検査は中心30°だけでなく,時に10°内の評価と中心窩閾値測定を行う.
・可能な限り,複数回の眼圧測定と信頼できる視野検査の結果をもとに治療を開始する.
病院(緑内障手術も可能な施設)で診るとき
・病型の確定.
① ベースライン(無治療時)情報の確認.経過中の眼圧変動や前房内炎症の有無を確認.
② 隅角の確認.
・介入した治療の評価.
① 現在の眼圧で緑内障の進行が止まっているかどうかの確認.
② 点眼の追加・変更による眼圧下降の有無と視野進行速度の変化の確認.
・観血的治療が必要かどうか? 白内障単独でよいのか,緑内障手術の併用が必要なのかを判断するための視野進行の評価.
小児の緑内障
著者: 川瀬和秀 , 野々部典枝 , 冨田遼
ページ範囲:P.181 - P.186
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
《原発先天緑内障》
・出生前または新生児期(0〜1か月):出生直後から角膜混濁,角膜径増大(11mm以上),眼軸長の伸長などを認め,アイケアなどによる眼圧測定で高眼圧を認める場合,および先天眼形成異常や先天全身疾患に関連した緑内障などの眼圧上昇の可能性がある疾患.
・乳児期(1〜24か月):生後数か月から流涙,羞明,眼瞼痙攣などの角膜浮腫による刺激症状がある場合,眼圧測定,眼底検査,超音波Bモード検査などにより角膜混濁,角膜径増大(12mm以上),眼圧上昇,眼軸長の伸長を確認した場合.
・遅発性(2歳以上):2歳以上で流涙,羞明,眼瞼痙攣などの角膜浮腫による刺激症状がある場合,細隙灯顕微鏡検査,圧平眼圧測定,眼底検査,超音波Bモード検査などにより角膜混濁,角膜径増大(13mm以上),眼圧上昇,眼軸長の伸長や近視化を確認した場合.
《若年開放隅角緑内障》
・4歳以降では,眼球拡大や角膜浮腫などの刺激症状を伴わないことも多い.細隙灯顕微鏡検査,圧平眼圧測定,超音波Bモード検査,屈折検査,眼底検査などにより角膜混濁,角膜径増大,眼圧上昇,眼軸長の伸長や近視化,視神経乳頭陥凹拡大などを確認した場合.
・小学生以上では,細隙灯顕微鏡検査,圧平眼圧測定,眼底検査に加え,OCTや視野検査により緑内障が疑われる場合.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・幼児や小児の臨床検査や視能訓練ができる施設は限られているため,逆紹介する前に確認する.
・緑内障治療とともに視能訓練も大切である.
・術後眼圧が落ち着いていても数か月〜半年に1回の診察継続が必要.
・4歳以上では,視力,眼圧測定,小学生以上では,視野検査や眼底写真,OCTの練習が必要.
前視野緑内障
著者: 庄司拓平
ページ範囲:P.187 - P.192
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・前視野緑内障は緊急疾患ではないため,OCT検査や視野検査を行った後に紹介.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・治療方針が決まったとき.
眼圧が下がらない緑内障
著者: 佐野一矢 , 谷戸正樹
ページ範囲:P.193 - P.198
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
《紹介するべき症例》
・複数の点眼(3剤以上)を使用しても眼圧が下がらない症例.
・喘息やアレルギーで十分な点眼処方ができず眼圧が高いままの症例.
※なお,炭酸脱水酵素阻害薬内服で眼圧が落ち着いている症例とは,すなわち「内服を止めれば再上昇する症例」である.長期的な内服は腎機能にも影響を与えるため推奨されない.
上記は,手術適応となりうるため,自院で対応不可であれば速やかに紹介すべきである.
《紹介前に確認すること》
・薬剤アドヒアランスを確認する.
・ステロイド使用の有無を再度確認する.
・緑内障病型を再度見直す(自院で手術対応可能かどうかを考える).
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・眼圧が下がり,かつその眼圧で落ち着いている症例.
※線維柱帯切開術後は眼圧が一度下降した後,リバウンドで再上昇することがあるので注意する.
・手術に伴う合併症がない症例(あってもすでに治っている症例).
・緑内障の背景疾患が落ち着いた症例(ぶどう膜炎・糖尿病など).
・その眼圧で視野進行スピードが十分低下したことを確認できた状態.
視野障害が進む正常眼圧緑内障
著者: 溝上志朗
ページ範囲:P.200 - P.205
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
・中心10°の視野も積極的にチェック.
・他の緑内障病型の合併に注意.
・緑内障とは異なる視野・OCTパターンに注意.
病院で診るとき
・濾過手術後の合併症に注意.
・中心視野障害が高度に進行しているケースに注意.
末期緑内障
著者: 本庄恵
ページ範囲:P.206 - P.212
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
《初診時,すでに視野障害が進行》
・著明な高眼圧の場合はすぐに薬物療法を開始,正常眼圧〜25mmHg以下ならベースライン眼圧を確認してから薬物療法を開始,点眼加療のみで良好な眼圧コントロールが得られた→中心視野検査,30-2/24-2視野検査を継続し眼圧コントロール下での進行を確認,進行傾向なら紹介を検討.
・高眼圧を認め,点眼加療では眼圧コントロールが得られず,内服加療追加である程度眼圧コントロールが得られた→可能なら中心視野検査も施行のうえ紹介を検討.
・高眼圧を認め,点眼加療,内服加療追加でも眼圧コントロールが得られない→可能なら中心視野検査も施行のうえ紹介.
・正常眼圧であるが緑内障性変化か頭蓋内病変などかが不明→自院で精査困難であれば紹介.
・隅角閉塞病態の場合→原則的には外科的治療が必要なため薬物治療が奏効していても紹介を検討.
《薬物治療を継続しているが視野障害に進行がみられる》
・眼圧下降は十分得られており,眼圧コントロールは良好,薬物治療は行えているが進行→30-2/24-2視野,中心視野,眼圧経過のデータとともに紹介.
・眼圧下降が不十分,点眼はfull medication→点眼内容は変えず,眼圧が高すぎる場合は内服を追加し,データとともに紹介.
・眼圧下降が不十分,点眼アレルギーなどで点眼加療が十分に行えない→使用可能な点眼,必要なら内服を追加し,データとともに紹介.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・点眼変更,整理などで安定し,観血的手術の必要はないと判断.
・レーザー治療,低侵襲緑内障手術,流出路再建術,隅角癒着解離術,水晶体再建術など観血的治療のうえ,点眼併用で眼圧が安定.
・濾過手術,チューブシャント手術などを施行,術後の経過は安定.
ぶどう膜炎続発緑内障
著者: 丸山和一
ページ範囲:P.213 - P.218
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・初診時にすでに重症の場合.
① その日のうちに紹介可能→抗炎症治療せず(眼圧下降目的の治療のみ施行)に紹介.
② その日のうちに紹介不可能→可能であれば眼圧上昇時のスリット写真を撮影.眼圧下降だけを目的にして,マンニトールを点滴し,ダイアモックスを投与して眼圧をなるべく下げておく(基礎疾患の有無は口頭でもよいので確認しておく).
・初診時は軽症や中等症で,眼圧下降薬など眼圧を下げる処置をしても改善しない場合→治療は継続して,早めに紹介.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・眼圧下降が継続的に得られ,眼圧上昇発作が3か月以上抑制できているとき.
・炎症も3か月以上抑制できているとき.
血管新生緑内障
著者: 東出朋巳
ページ範囲:P.219 - P.223
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
① 血管新生緑内障(NVG)のハイリスク症例(眼科または内科が無治療あるいはコントロール不良の糖尿病,内眼手術後の糖尿病網膜症,虚血型網膜中心静脈閉塞症,眼虚血症候群など)では,散瞳する前に前眼部診察と隅角検査を行い,ルベオーシスの有無を確認する.
② 高眼圧症例(角膜浮腫,充血あるいは前房出血を伴う場合)には,NVGを疑って糖尿病などの病歴を聴取し,ルベオーシスの有無や虚血性網膜疾患の有無を念頭に置いて診察する.
③ 眼圧のみでなく,視力,視野も測定して視機能を評価する.
病院で診るとき
上記①〜③に加えて,下記のポイントが挙げられる.
① 糖尿病や高血圧など病歴に応じて専門の内科にコンサルトする.眼虚血症候群疑いの場合,画像検査と脳神経外科へのコンサルトを行う.
② 網膜光凝固および抗血管内皮増殖因子薬の硝子体内注射の適応の有無と施行時期を検討する.中間透光体混濁によって経瞳孔的網膜光凝固が難しい場合には,白内障手術や硝子体手術を考慮する.一方,薬物治療による眼圧下降が不十分である場合には,緑内障手術を考慮する.
原発閉塞隅角緑内障
著者: 栗本康夫
ページ範囲:P.224 - P.228
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
《閉塞隅角があるかどうかの緑内障病型判定》
・閉塞隅角を疑わせる所見がないかどうか,細隙灯顕微鏡検査で必ずvan Herick法で周辺前房の深さを確認する.van Herick法で前房深度/角膜厚比が1/4以下(できれば1/3以下)であれば閉塞隅角の存在を疑う(図1).さらに,隅角鏡検査に習熟していれば同検査を行って原発閉塞隅角症疑い(表1)に該当するかどうかを判定する.
《重症度の評価:どのくらい緊急性があるか》
・緑内障視神経症がどのくらい進行しているか,視野検査および視神経乳頭所見により評価する.
・眼圧はどれくらいか測定を行い,亜急性緑内障発作を疑わせる既往がないか聴取する.
病院で診るとき
《治療適応の判定》
・本緑内障病型は原則として外科的治療が第一選択になるので,治療適応の有無の判定が重要.
《隅角閉塞メカニズムの判定》
・その症例に無効な治療を選択しないようにするためには,隅角閉塞メカニズムの判定が重要.
《最適な治療術式の決定》
・術式のメリットとデメリットを症例ごとによく吟味して,それぞれの症例に最適な術式を決定する.
6 ぶどう膜炎
原田病
著者: 岩田大樹 , 南場研一
ページ範囲:P.230 - P.235
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
・Vogt-小柳-原田病(原田病)の初期には前眼部炎症がみられないこともある.前房炎症がみられるときだけではなく,みられないときでも視力低下,霧視や飛蚊症などの症状があれば必ず眼底を確認する.
・漿液性網膜剝離を伴わない視神経乳頭浮腫型では診断に苦慮することがある.疑わしいときにはこまめな診察を行い,紹介の必要性を判断する.
病院で診るとき
・紹介を受けた病院では,原田病の遷延型への移行を防ぐためにも早期診断・早期治療を心がける.
・眼科画像検査として,眼底造影検査,OCT,レーザースペックルフローグラフィなどが有用である.ただし原田病は全身疾患であり,特に診断に苦慮する場合には髄液検査,感音性難聴などの全身検索も行う.
Behçet病
著者: 園田康平
ページ範囲:P.236 - P.240
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
・連携病院と発作時の対応について事前によく打ち合わせをしておく.
病院で診るとき
・Behçet病眼症は基本的に急性発作である.眼発作を認めたときには,その程度をBOS24スコアによって判定・記録する.発作頻度も活動性判定に重要なので,発作時期をきちんと記録する.
・眼炎症発作とともに,全身状態に気を配る.
・コルヒチン,シクロスポリン,抗腫瘍壊死因子(TNF)治療を行っている症例では,定期的に肝腎機能をチェックし,感染症などの副作用に留意する.
サルコイドーシス
著者: 石原麻美
ページ範囲:P.241 - P.245
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
・点眼薬だけでは治療困難で,副腎皮質ステロイド薬の全身投与が必要と考えられる場合,クリニックでは投与せずに病院へ紹介する.
・ステロイド点眼薬を開始しても,治療への反応が悪い,また病状の進行が速いなど,サルコイドーシス以外の疾患を疑った場合には速やかに病院へ紹介する.
・紹介状には初診時(点眼治療開始前)の眼所見,治療内容,経過中の眼所見の変化などをわかりやすく記載する.
病院で診るとき
・クリニックでの治療が病像を修飾している可能性があることを念頭に置いて診察する.
・サルコイドーシス疑いで紹介された症例では,診断に必要な全身検査を行うが,同時に鑑別診断を考えて検査をオーダーする.
・他科(内科,皮膚科など)と連携を取りながら診断,治療にあたり,十分に消炎してからクリニックに逆紹介する.
原因不明のぶどう膜炎
著者: 蕪城俊克
ページ範囲:P.246 - P.250
クリニックで診るときのポイント
ぶどう膜炎は発症当初は全例が原因不明である.眼科施設を受診し,眼所見や全身症状,検査所見を踏まえて診断基準などにより原因病名がつけられていく.ぶどう膜炎は大きく内因性(非感染性),感染性,腫瘍性(仮面症候群),特発性に分類される(表1)1).内因性ぶどう膜炎にはBehçet病,Vogt-小柳-原田病,サルコイドーシスなどが含まれ,感染性ぶどう膜炎にはヘルペス性虹彩炎や細菌性眼内炎などが含まれる.特発性ぶどう膜炎とは,ぶどう膜炎の原因精査を行ってもぶどう膜炎を起こした原因病名が決められない症例を指す.感染性ぶどう膜炎では消炎治療に加え,抗菌薬(抗ウイルス薬)の投与が必要であり,腫瘍性では抗がん剤や放射線治療が必要となる.ぶどう膜炎は原因疾患によって治療はかなり異なるため,クリニックにおいても初診時に十分な問診,診察,検査を行って,診断病名をつける努力をすることが大切である.
ぶどう膜炎の鑑別診断では,眼内の炎症所見に加え,ぶどう膜炎に関連する全身疾患の有無や画像検査,血液検査などの結果から診断基準などに基づいて診断病名を特定する.ぶどう膜炎の鑑別に際しては,4つのチェックポイント〔①炎症の解剖学的局在(前部,後部,汎ぶどう膜炎),②両眼性・片眼性,③炎症の性状(肉芽腫性・非肉芽腫性),④急性・慢性〕に注目して原因疾患を絞り込むとわかりやすい1).主なぶどう膜炎疾患の診断法は,日本眼炎症学会が作成した「ぶどう膜炎診療ガイドライン」に記載されており,日本眼科学会のホームページからダウンロード可能である2).
クリニックでできるぶどう膜炎の鑑別診断のやり方を表2に示す.Behçet病は4つの主症状(口腔内アフタ,皮膚病変,陰部潰瘍,眼病変),5つの副症状(関節症状,血管症状,消化器症状,神経症状,副睾丸炎)から診断する疾患であり2),特別な検査は必要ない.しかし,ぶどう膜炎が急性・再発性であることや,非発作時にも蛍光眼底造影でシダ状蛍光漏出をみることが多いなど,Behçet病ぶどう膜炎として矛盾しないことを確認しておきたい.診断病名が確定すれば,その疾患で推奨されている治療を行う.主なぶどう膜炎疾患の治療法もぶどう膜炎診療ガイドライン2)に記載されているので,参照していただきたい.
強膜炎
著者: 山﨑将志 , 堀純子
ページ範囲:P.251 - P.255
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・初診時すでに重症の場合.
① その日のうちに紹介可能→点眼薬処方や処置などをせずに紹介.
② その日のうちに紹介不可能→感染性を除外できればステロイド点眼を開始し,可能な限り早めに病院受診を指示.
・初診時は軽症や中等症で抗菌薬やステロイドの点眼を開始したが治らない場合→治療を変更せずに紹介.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・強膜の炎症が鎮静化したとき.
・随伴する全身性炎症疾患の病勢が落ち着いているとき.
7 網膜硝子体
先天性眼底疾患・網膜芽細胞腫
著者: 近藤寛之
ページ範囲:P.258 - P.262
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
《先天性眼底疾患》
・出生早期に異常を認めた場合には,まず基幹病院に紹介する.
・網膜剝離性疾患では浅前房による緑内障を見逃さないようにする.
《網膜芽細胞腫》
・3歳までは再発の有無の確認のために基幹病院への受診を促す.
病院で診るとき
《先天性眼底疾患》
・網膜剝離性疾患では乳児期に病変の活動性が残っていないかを確認する.
・網膜ジストロフィでは屈折矯正が適切であるかを確認する.
《網膜芽細胞腫》
・家族性の場合には眼球外への転移がないか慎重にフォローする.
糖尿病網膜症
著者: 志村雅彦
ページ範囲:P.263 - P.268
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・蛍光眼底造影を施行し,介入治療を要するとき→無灌流領域や新生血管が出現している場合.
・蛍光眼底造影ができないとき→眼底に出血がほとんどみられなくても無灌流領域が広がっていることもある.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・網膜症の活動性が鎮静化し,少なくとも3か月以上病態が安定している場合.
・新たな介入治療の必要性がなくなった場合.
加齢黄斑変性
著者: 山本有貴 , 五味文
ページ範囲:P.269 - P.274
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・脈絡膜新生血管(CNV)からの出血を伴っていたり,黄斑部に出血が及んでいる場合はできるだけ早めに紹介する.
・Type 1 CNVで網膜下液を少し伴うものなどはやや待機可能.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・基本的には専門施設で経過観察.抗血管内皮増殖因子(VEGF)薬注射の間隔が延長できるようになってきた場合は,クリニックと病診連携し,クリニックで1〜2か月に一度,専門病院は3〜4か月に一度の定期検査となる場合もある.長期にわたり,抗VEGF薬投与なしで滲出性変化が抑えられている場合は患者本人に再燃の可能性を説明し,クリニックへ逆紹介する.
中心性漿液性脈絡網膜症
著者: 和泉雄彦 , 飯田知弘
ページ範囲:P.275 - P.280
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・罹病期間,危険因子(特に副腎皮質ステロイド薬使用の有無)の確認.
・網膜障害の程度を確認.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・長期的に脈絡膜新生血管の発症に注意.
・僚眼の状態にも注意.
網膜血管閉塞症
著者: 馬場高志
ページ範囲:P.281 - P.285
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・病型の診断が眼底所見からでは困難な場合.
《網膜静脈閉塞症》
・自施設で治療困難な場合は,数日以内に紹介.治療に抵抗し,治療が困難な場合は,次の治療スケジュール前に紹介.
《網膜動脈閉塞症》
・発症が早期で,診断時に自施設で治療が可能であれば,すぐに治療.治療困難な場合はすぐに紹介.
《眼虚血症候群》
・緊急性が高く,原因精査に限界があるため,治療困難な場合は早急に紹介.
病院からクリニックへ逆紹介するとき(下記条件をともに満たす状態)
・十分な原因の精査が終わり,全身疾患が定期的な内科医による管理下にある状態.
・定期的な治療,もしくは治療なしで活動が停止した状態.
黄斑円孔・黄斑上膜
著者: 的場亮 , 森實祐基
ページ範囲:P.286 - P.291
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
・黄斑円孔(MH)は,Gass分類ステージ1B以降で病院への紹介を検討する.
・黄斑上膜(ERM)は,歪視の自覚(アムスラーチャートでの歪視の検出)があり,矯正視力が1.0未満の場合に,病院への紹介を検討する.
病院で診るとき
・MHは円孔径,経過,併発疾患などから難治性MHかどうかを判断し,術式を決定する.
・ERMは視力だけでなく,歪視などの随伴症状も参考にして手術適応を決定する.
・MH,ERMともに,術後は視力だけでなく,網膜層構造や歪視の改善を確認してからクリニックへの逆紹介を検討する.
近視性黄斑症
著者: 中尾紀子 , 五十嵐多恵 , 大野京子
ページ範囲:P.293 - P.298
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
《成人の場合》
・びまん性萎縮以上の近視性黄斑症が疑われ視力低下を伴う場合.
・黄斑部新生血管の発症を疑う場合.
《小児の場合》
・乳頭周囲びまん性網脈絡膜萎縮を疑う場合.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
《成人の場合》
・近視性網脈絡膜萎縮の他に明らかな合併症を認めず,一定期間著変がない場合.
・黄斑部新生血管の治療後,一定期間再発なく経過した場合.
脈絡膜腫瘍
著者: 辻英貴
ページ範囲:P.300 - P.304
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
・脈絡膜腫瘍は,腫瘍を直接見ることはできない.そのため悪性黒色腫であっても,黒色調を呈するのは腫瘍の一部分のみが多い(図1).網膜下に明らかな隆起が観察される場合には,腫瘍専門施設へ紹介する.
・隆起に乏しい症例の場合には,経過観察が可能である.高さ(厚み)がない,境界鮮明,網膜剝離などの所見がない,などの場合には,母斑(図2)や網膜色素上皮過形成などの良性疾患が含まれる.
・母斑は悪性黒色腫の母地となりうるものであり,病変の拡大や多発などがあれば専門医に紹介する.
病院で診るとき
・腫瘍は良性か悪性かは,活動性があるかないかが大切で,その根拠となるのはフルオレセイン蛍光眼底造影検査(FA)/インドシアニングリーン蛍光眼底造影検査(IA)と,腫瘍のサイズの増大があるか否かである.
・FAでは腫瘍による網膜色素上皮の破壊があるかが大切で,腫瘍の高さについてはBモードエコーにて経時的に測定していくのがよい.
・母斑はメラノーマの発生母地であるが,腫瘍の厚みで3mm程度がその境界と考えてよい.悪性黒色腫の場合には,Bモードエコー(図3)とMRI(図4)が診断の補助となる.大きさの変化,特に厚みが2〜3mmを超え,さらなる増大傾向のある場合には,悪性黒色腫に進行している可能性を示唆する.
8 神経眼科
視神経炎
著者: 中馬秀樹
ページ範囲:P.306 - P.311
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・0.1以下の視力低下の強い視神経炎が疑われたら当日のうちに紹介する.
・その他は可及的速やかに紹介する.
・再発した抗アクアポリン(AQP)4抗体陽性視神経炎は当日のうちに再紹介する.
・視神経炎は,中途半端にステロイド内服などをさせずに,なるべく早く神経眼科医へ紹介する.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・視機能が回復,安定したとき.
・視機能の回復が限局的でも悪いなりに安定したとき.
眼科から脳神経内科へ紹介するとき
・典型的視神経炎で,全身神経症状がみられるとき.
・典型的視神経炎で,脳内の脱髄病変が蓄積されていくとき.
・抗AQP4抗体陽性や抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白抗体陽性視神経炎で脳から脊髄に脱髄病変がみられるとき.
眼瞼痙攣
著者: 木村亜紀子
ページ範囲:P.312 - P.316
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
《明らかな眼瞼痙攣の場合》
・ボツリヌス治療の適応である.自施設で施行,もしくはボツリヌス治療を行っている施設へ紹介.
《眼瞼痙攣が疑わしい場合》
・ボツリヌス治療は行わず,大学病院などのボツリヌス外来(もしくは担当医師)へ紹介.
病院で診るとき
・問診と瞬目テストで診断をつけ,診断がつけばボツリヌス治療に進む.
眼球運動障害
著者: 林孝雄
ページ範囲:P.317 - P.321
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
《急性》
・急激な複視を自覚しており,眼球運動障害がみられた場合.
① その日のうちに紹介可能→脳動脈瘤など緊急を要する場合は,すぐに紹介.
② その日のうちに紹介不可能→なるべく早めの受診を促す.
《亜急性》
・最近複視を自覚し始めたと訴え,眼球運動障害がみられた場合→早めの受診を促す.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
《複視の自覚が軽減した場合》
・症状が固定し,複視は残っていても日常生活に支障をきたすことがなくなっており,紹介元や近医への通院を希望すれば,クリニックへ逆紹介する.
《眼球運動障害が改善した場合》
・複視もなく,紹介元や近医への通院を希望すれば,クリニックへ逆紹介する.
視野障害
著者: 中村誠
ページ範囲:P.322 - P.327
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・急性発症の視野障害があるにもかかわらず細隙灯顕微鏡検査・眼底検査で異常がみられないとき.
① 片眼性かつ相対的瞳孔求心路障害(RAPD)陽性→その日のうちに病院へ紹介.
② 片眼性かつRAPD陰性→予約をとって病院へ紹介.
③ 両眼性の場合→可能な限り早く病院へ紹介.
・緑内障で治療中だが,進行が早い,ないし非典型的な視野変化が現れた場合→予約をとって病院へ紹介.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・原疾患が完治したとき.
・原疾患の加療がこれ以上望めず,病院までの通院が困難になったとき.
眼窩腫瘤性疾患
著者: 田邉美香
ページ範囲:P.328 - P.332
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
《問診で重要なポイント》
・症状の発症時期はいつか?→数日前,数週間前から発症して,増悪しているようなら即日紹介する.
・増悪のスピードは年単位か,月単位か,週単位か,日単位か?→日単位,週単位に増悪している症例は即日紹介する.
・複視があるか?→複視がある場合は画像検査が必須.早急にCT/MRIを手配する.
・痛みがあるか? また,その性状(眼球運動時痛,眼窩深部痛)は?→痛みがある場合,炎症性疾患の可能性が高く,進行が速いことが多い.
・体位による眼球突出の変化→静脈奇形などの血管性病変では,頭を下げると眼球突出が増悪する.
・全身状態や既往歴(悪性腫瘍の治療歴,糖尿病の有無,手術歴など)→悪性腫瘍(特に肺癌,乳癌)の治療歴があれば転移性腫瘍も念頭に置く.糖尿病では,感染性疾患の除外が重要.副鼻腔手術歴があれば,その関連を疑う.
《診察上,注意して診るポイント》
・片側性か両側性か?→両側性であれば炎症性疾患の可能性が高いが,悪性リンパ腫や転移性腫瘍も鑑別に挙がる.
・眼球突出の程度→高度な眼球突出によって,画像上,眼球後方が鋭角になるほど圧迫されているような状態では視機能障害が出るリスクが高く,早急な治療介入が必要である.
・眼瞼腫脹・発赤の範囲→炎症性疾患で発赤・腫脹が強い.眼窩内腫瘍が触れることがあり,触診も重要である.
・結膜・強膜所見→結膜炎や強膜炎を認める場合は炎症性疾患の可能性が高い.
・斜視,眼球運動障害の有無などについて確認を行い,鑑別を進める→斜視,眼球運動障害がある場合は画像検査が必須.早急にCT/MRIを手配する.手配できなければ,早急に紹介する.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・炎症性疾患であれば,一定期間十分な消炎が得られたとき.
・腫瘍性疾患であれば,積極的治療が終了し,経過をフォローするのみとなったとき.
心因性視覚障害
著者: 清澤源弘 , 小町祐子
ページ範囲:P.333 - P.337
クリニック・病院で診るときのポイント・紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックで診るとき
《心因性(機能性)視覚障害の疑い方》
・視力低下を説明しうるだけの器質的所見がみられない.
・他覚的屈折値に対して裸眼視力値が不良,矯正視力が(1.0)に届かない,トリック法で健常視力が得られる,といった特徴的な所見がみられる.
・発症前に心因となりそうな精神的ストレスとなるエピソードが存在する.
クリニックから病院へ紹介するとき
・器質的病変をより確実に否定するために視覚誘発電位などの精密検査を必要とする場合.
・患者の心因を探り,取り除いていく目的で,小児科や精神科領域病院への紹介が必要.ただし,治療効果の確認のために,必ず眼科の併診を継続.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・心因要素が取り除かれる,または軽減して視覚障害が改善されたとき.
・心理支援の結果,心的ストレスが解消されることにより受診自体を必要としなくなるケースもある.
9 弱視斜視
小児内斜視
著者: 長谷部聡
ページ範囲:P.340 - P.344
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院に紹介するとき
《斜視診療を専門としないクリニック》
・次の3つの要件を1つでも満たさない場合は,内斜視があると判断された時点で早めに病院(専門医)を紹介.
① 調節麻痺下の屈折検査ができる.
② 低年齢児の視力評価ができる.
③ 遮閉試験に精通した医師または視能訓練士がいる.
《斜視診療も専門とするクリニック》
・保護者に両眼視機能の仕組みや将来予想されるハンディキャップなどについて十分に説明したうえで,必要に応じて屈折矯正や弱視治療を行いつつ斜視手術に踏み切るタイミングを検討する.スムーズな病診連携を図るには,日頃から病院(術者)との情報交換も必要である.
病院からクリニックに逆紹介するとき
・逆紹介の時期も紹介時期と同様,紹介元が斜視診療にどの程度,重点を置いているかどうかで異なる.術後経過が良ければ術後3〜12か月で紹介元に返すことも多い.
近視を伴う内斜視
著者: 佐藤美保
ページ範囲:P.345 - P.349
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・遠視のない小児.
・外転制限があるとき.
・複視の自覚があるとき.
・患者が治療を希望するとき.
病院からクリニックに逆紹介するとき
・治療後病状が安定しているとき.
・継続的に眼位,視力のフォローが必要と思われるとき.
外斜視
著者: 下條裕史
ページ範囲:P.350 - P.355
クリニック・病院で診るときのポイント
クリニックで診るとき
・緊急紹介が必要な場合.
① 急性の斜視は基本的に病院へ紹介が望ましい.
② 脳動脈瘤による動眼神経麻痺による急性の外斜視が疑われる場合は超緊急!
・それ以外は基本的に急を要する場合は少ないが……
① 共同性かそうでないかはきちんと鑑別する.
② 共同性なら恒常化,複視の自覚,眼精疲労が強くなってきたら病院への紹介時期.
病院で診るとき
・クリニックの項目にもあるように脳動脈瘤による急性外斜視が疑われる場合は脳外科に緊急紹介.
・紹介状に情報が全く書いていない場合も多々あるので特にいつから発症したかはきちんと聴取すること.
・感覚性外斜視を否定するために,1回は散瞳して眼底疾患がないかどうかをきちんと診ること.
・経過をみていくうちに両眼視機能,特に立体視が悪化してきていないか注目.
弱視
著者: 清水ふき , 杉山能子
ページ範囲:P.356 - P.361
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・弱視の確定診断が困難な場合.
① 視力検査ができない.
② 屈折検査ができない.
・治療を行っているが,視力が改善してこない場合.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・検査が上手にできるようになった.
・視力が改善・安定した.
10 ロービジョンケア
若年者のロービジョンケア
著者: 守本典子
ページ範囲:P.364 - P.369
クリニック・病院で診るときのポイント
・視機能の発達時期にある乳幼児に対して,器質的異常があっても屈折異常を眼鏡矯正して弱視を防ぐことはクリニックでも病院でも同じである.
・先天無虹彩や白皮症など羞明をきたしていることが明らかな例では,虹彩付きソフトコンタクトレンズ1)か遮光眼鏡の装用を試みる.遮光眼鏡のトライアルを備えていない場合は最寄りのロービジョン・視覚リハビリテーション外来(以下,LV外来)へ紹介する.
・視力や視野の障害が予想される場合,当該の検査ができなくても器質的異常と視反応や行動の観察から身体障害者手帳の診断書を発行できる.視機能の発達が見込まれれば再認定の時期を記しておくとよい.
・これと同時に,LV外来のある眼科か各県に1校はある視覚特別支援学校(以下,盲学校)へ紹介し,早めに療育・教育の支援体制を整える.
・学齢期には授業や屋外活動に支障が生じる可能性が高いため,拡大・遮光など視覚補助具の選定や学校生活上のアドバイスが必要になる.中高生では受験対策とそれを見越した在学中の試験の受け方も重要である.自院で難しい場合はLV外来へ.
・近年,情報通信技術の進歩で視覚障害児の学習環境は改善してきている.また,最近はCOVID-19感染拡大の影響で対面交流が難しくなっている反面,オンラインでの交流が全国規模で広がっている.リモートワークへの移行も視覚障害者には有利に働いているので,そのようなプラスの情報をぜひとも患者や家族に知らせていただきたい.
成人のロービジョンケア
著者: 藤田京子
ページ範囲:P.370 - P.374
クリニック・病院から紹介/逆紹介するときのポイント
クリニックから病院へ紹介するとき
・治療が一段落した,もしくは有効な治療法がなく完治が望めない状況で日常生活に支障がでている場合.
・患者が必要とするケアの内容によっては病院での対応が難しい場合があるため,紹介先の病院で対応が可能かどうかを事前に問い合わせておく必要がある.
病院からクリニックへ逆紹介するとき
・基本的に普段の経過観察や治療は紹介元のクリニックで継続される.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.6 - P.8
基本情報
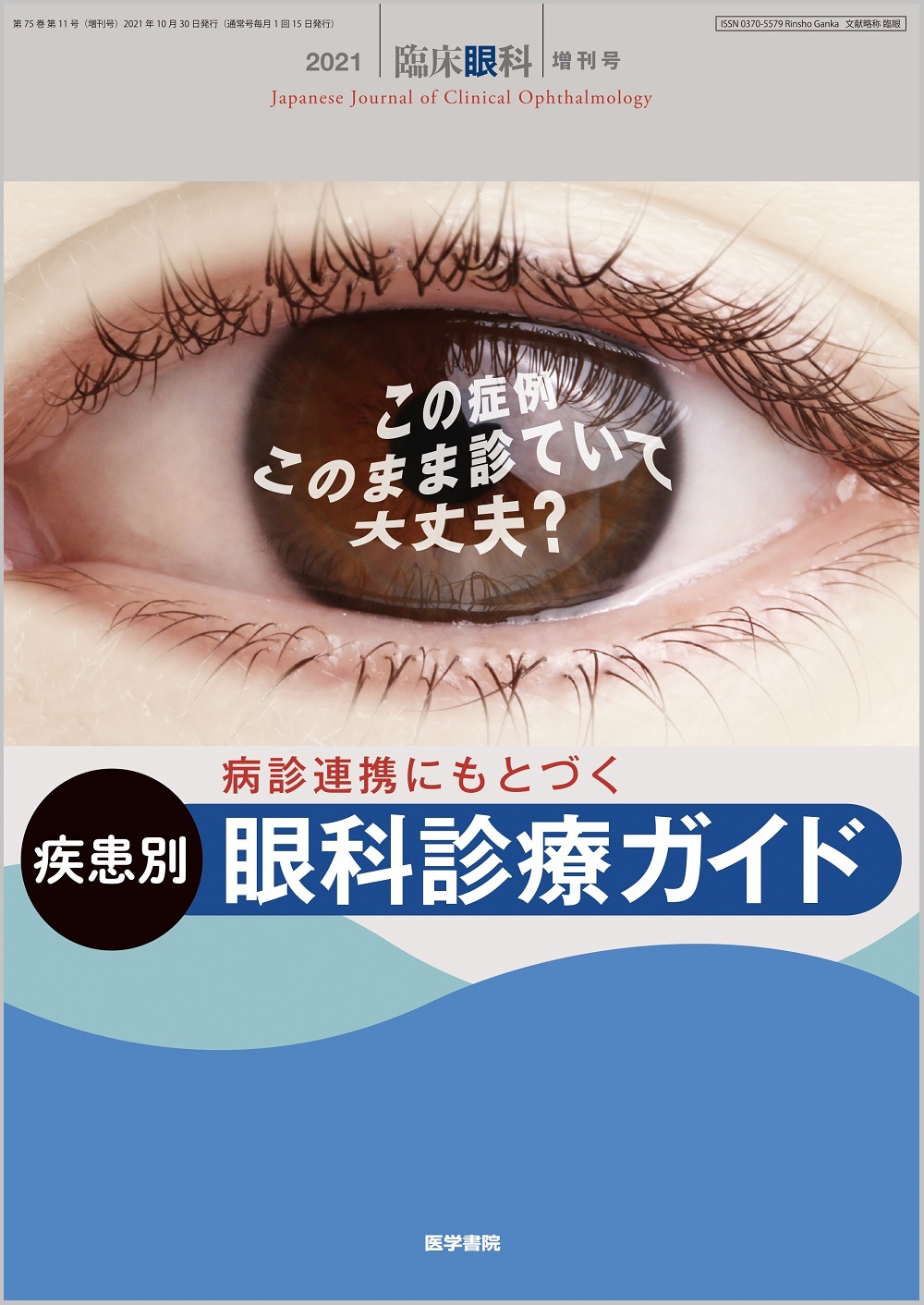
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
