現在,世界中で非常に多くの眼科臨床研究が行われており,それらを全分野についてフォローしていくことは容易なことではありません.しかしながら,エビデンスに基づいた診療を行うためには,しっかりとしたプロトコールに基づいて行われた臨床研究を参考にしながら診療を行うことが求められていますし,実際にそれに答えるように現在ではさまざまな情報やツールが利用できるようになっています.日本眼科学会,American Academy of Ophthalmology,Europe Society of Ophthalmologyなどは多くの教育ページを提供していますし,ガイドラインやPreferred Practice Patternを定期的に更新してくれています.加えてThe Cochrane Libraryもありますし,雑誌についても以前からあるSurvey of Ophthalmologyや各雑誌のreview articleに加え,Progress in Retinal and Eye ResearchやAnnual Review of Vision Science,Current Opinion in Ophthalmologyなどの多くのreview雑誌において各分野における最新の研究成果がまとめられています.さらに近年,医療関係者や学生の間でよく使われるようになってきているUpToDateなどのオンラインツールを使えば,よりストレートに最新の臨床研究の成果を知ることもできます.
とはいえ正直なところ,日本眼科学会のホームページに掲載されているわが国のガイドラインにキャッチアップするだけでも困難を感じていらっしゃる先生も少なくないと思われます.さらに多くのガイドラインがありながらも,それでもそれぞれのガイドラインがカバーする領域はかなり広く,それらの内容の元となった研究や論文の詳細を知ることはガイドラインを読んだだけではできません.そうはいっても1つひとつ引用されている原著論文にまで当たるのはさらに大変です.
雑誌目次
臨床眼科76巻11号
2022年10月発行
雑誌目次
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
序文 フリーアクセス
著者: 鈴木康之
ページ範囲:P.5 - P.5
1 緑内障
日本の緑内障疫学研究で得られた重要な知見を教えてください
著者: 岩瀬愛子
ページ範囲:P.12 - P.15
多治見スタディでは調査時までの緑内障の未発見患者の多さが指摘されましたが,久米島スタディの結果も同様で,世界の調査のなかで比較しても日本では未発見患者が多いことがわかりました.そして,PACGよりPOAGのほうが発見されにくいことがわかりました.
緑内障患者の経過観察で視野検査,眼底検査,OCT検査などの適切な検査間隔について教えてください
著者: 山下高明
ページ範囲:P.16 - P.19
緑内障は主に進行速度で受診間隔が決まるため,病型と病期から進行速度を予測して適切な受診間隔を決定します.
早期の原発開放隅角緑内障に対する眼圧下降治療の効果についてエビデンスはありますか?
著者: 竹本大輔 , 東出朋巳
ページ範囲:P.20 - P.23
早期の開放隅角緑内障における点眼治療による視野障害進行抑制効果は,エビデンスレベルが最も高い試験デザインに基づく臨床研究によって証明されています.
進行した原発開放隅角緑内障に対してどの程度の眼圧下降治療が必要ですか?
著者: 中元兼二
ページ範囲:P.24 - P.27
目標眼圧を平均で14mmHg未満,眼圧上限を18mmHg未満とします.眼圧が低い症例ほど眼圧長期変動にも留意して,低く安定した眼圧を目指します.
高眼圧症患者が原発開放隅角緑内障を発症することを予防するために眼圧下降治療は有効ですか? また,どのような症例に治療を行うべきですか?
著者: 大久保真司
ページ範囲:P.28 - P.31
高眼圧症患者に対する眼圧下降治療は,原発開放隅角緑内障の発症を予防するために有効です.高齢,垂直C/D比が大きい,高眼圧,PSDが大きい,中心角膜厚が薄い,視神経乳頭出血の出現などの危険因子を有する症例では治療開始が推奨されています.
進行している正常眼圧緑内障の治療ではどの程度眼圧を下げたらよいですか?
著者: 山本哲也
ページ範囲:P.32 - P.35
薬物療法と手術療法を組み合わせて,可能であれば眼圧が10mmHgを超えない程度に(下降率として20%以上)下降させることを目指します.
患者にきちんと点眼してもらうにはどのようなことに気をつけたらよいですか?
著者: 内藤知子
ページ範囲:P.36 - P.38
緑内障で視機能障害が進行したり,加齢により後屈姿勢が困難になると適切な点眼操作ができなくなります.点眼が上手にできない患者には繰り返し点眼指導を行い,高齢者には仰臥位での点眼を勧めることも有効です.
交感神経α2受容体刺激薬には神経保護効果があると考えてよいですか?
著者: 横山悠
ページ範囲:P.39 - P.43
眼圧下降療法のようなエビデンスは確立されているとはいえませんが,いくつかの基礎研究,臨床研究で神経保護に関する有望な成果が報告されています.
どのようなときにレーザー線維柱帯形成術を施行するのがよいですか?
著者: 丸山勝彦
ページ範囲:P.44 - P.47
最大耐用量の薬物療法でも十分な眼圧下降が得られない場合に行います.副作用やアドヒアランスを加味すると,症例によっては「最大耐用量」は1剤や0剤のこともあります.
有水晶体眼の原発開放隅角緑内障に対して線維柱帯切除術を施行するとき,白内障手術はいつ行うのがよいでしょうか?
著者: 井上俊洋
ページ範囲:P.48 - P.51
白内障手術は線維柱帯切除術後1年以上経過してから行うと,眼圧コントロールに最も影響が少ないと思われますが,白内障手術が視機能改善に有益と考えられる場合は同時手術も選択肢となります.
濾過手術後の濾過胞感染の危険性や,それを予防するための工夫について教えてください
著者: 大鳥安正
ページ範囲:P.52 - P.55
濾過手術では,円蓋部基底結膜切開とテノン囊の前転により可能な限り囊胞状,無血管濾過胞を作らないことが濾過胞感染の予防になりえます.
プレートのある緑内障チューブシャント手術の適応と注意すべきことは何でしょうか?
著者: 石田恭子
ページ範囲:P.56 - P.63
通常の線維柱帯切除術(TLE)が不成功に終わった症例,結膜瘢痕が高度な症例,TLEの成功が見込めない症例,TLEが技術的に困難な症例が適応となります.目標眼圧,病型,手術既往を含めた術野の状態,リスク因子に応じて,バルベルトかアーメドを選択します.両者は術式や管理方法が異なるため,事前に習熟して手術に臨む必要があります.
急性原発閉塞隅角緑内障予防に対してレーザー周辺虹彩切開術はどの程度有用ですか?
著者: 酒井寛
ページ範囲:P.64 - P.68
急性原発閉塞隅角症(APAC)を引き起こしやすいことが知られているAPACの反対眼,眼圧上昇や周辺虹彩前癒着をすでにきたしている原発閉塞隅角症(PAC)眼,緑内障性視神経症をきたしている原発閉塞隅角緑内障,小発作の症状のある原発閉塞隅角症疑い(PACS)眼などに対する薬物療法の予後は非常に不良なので,原則としてレーザー周辺虹彩切開術(LPI)を含む手術加療が必要です.最近発表された2つのランダム化比較試験の結果では,LPIには症状のないPACSからPACへの進行予防効果があることが示されました.一方,PACSからAPACへの進行予防効果は示されませんでした.
原発閉塞隅角病に対して白内障手術とレーザー周辺虹彩切開術とでは,いずれがより有効ですか?
著者: 澤田明
ページ範囲:P.69 - P.73
多くの症例においては,白内障手術がより有効です.しかし,病態をしっかり把握したうえで,眼科的所見や手術合併症(術者の手技レベルを含む),患者サイドの要因として生活状況などを総合的に判断し治療方針を考慮すべきです.
2 白内障・視覚矯正
小児の近視進行予防は,どれくらいの効果があるのでしょうか?
著者: 小川護 , 四倉絵里沙 , 鳥居秀成
ページ範囲:P.76 - P.82
小児の近視進行予防法のうち,国内で承認された治療法はいまだありませんが,近視進行抑制効果が1つ以上のランダム化比較試験で認められている方法として,屋外活動,低濃度アトロピン点眼液,オルソケラトロジー,多焦点コンタクトレンズ,特殊眼鏡,サプリメントなどが挙げられます.単独治療,もしくはこれらの組み合わせで近視進行予防治療を行います.
3焦点眼内レンズは,2焦点眼内レンズと比べて,どのように優れているのでしょうか?
著者: 林研
ページ範囲:P.90 - P.94
3焦点眼内レンズ挿入眼は,2焦点眼内レンズ挿入眼に比べ中間距離視力が有意に良好ですが,遠見と近見視力には大きな差はありません.
白内障の眼内レンズ度数計算式はどれを使えばよいでしょうか?
著者: 須藤史子
ページ範囲:P.95 - P.99
従来からのSRK/T式やHaigis式よりも,術後屈折誤差予測の精度が異常眼軸長眼にも良いとされるBarrett Universal Ⅱ式や新しい人工知能を用いた式に注目が集まっています1).
LASIK後の眼内レンズ度数計算式はどれを使えばよいでしょうか?
著者: 後藤聡
ページ範囲:P.100 - P.104
米国白内障屈折矯正手術学会(ASCRS)のウェブサイトを活用し,複数の計算式の結果を平均した値を用いることが推奨されます.
白内障術後の残余屈折異常に対しては,どのように対処すればよいでしょうか?
著者: 神谷和孝
ページ範囲:P.105 - P.110
角膜表面などに他の眼合併症があれば,その治療を優先します.角膜面における外科的矯正としてLASIK,PRK,LRIなどがあり,矯正量が少ない症例に適しています.IOL面における矯正としてIOL交換やピギーバックIOLなどがあり,矯正量が大きい症例に適しています.屈折誤差,角膜厚,眼合併症,患者の意向を総合的に勘案して,追加矯正を考慮すべきでしょう.
Zinn小帯脆弱症例では,眼内レンズ固定はどのようにすればよいでしょうか?
著者: 松島博之
ページ範囲:P.111 - P.114
Zinn小帯脆弱症例でも,手術中にZinn小帯脆弱を確認した時点でCTRを活用することで,IOL囊内固定が可能です.
眼内レンズの強膜内固定の現状はどうなっているのでしょうか?
著者: 太田俊彦
ページ範囲:P.115 - P.122
眼内レンズ(IOL)支持部を鑷子で抜き出して強膜トンネル内に固定する当初の術式よりも,最近ではより簡便なダブルニードル法併用フランジ固定を選択する術者が増えています.しかし,術後のIOL傾斜やフランジ脱出による術後眼内炎などの問題点があります.
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月)。
着色眼内レンズは,本当に黄斑保護に役立っているのでしょうか?
著者: 市川一夫
ページ範囲:P.123 - P.125
役立つとした報告とそうともいえない報告が混在しており,今後の研究が待たれる状態です.
小児の白内障手術では,眼内レンズを入れるべきでしょうか? 避けるべきでしょうか?
著者: 小早川信一郎
ページ範囲:P.126 - P.128
手術時の年齢によります.1歳未満であれば避けるべきです.1歳以上なら挿入を検討します.わが国の標準的な適応は2歳以上です.
LASIKと有水晶体眼内レンズは,どのように使い分ければよいでしょうか?
著者: 稗田牧
ページ範囲:P.129 - P.132
軽度〜中等度の近視で角膜が正常であれば,LASIKが第一選択です.LASIKの適応外やかなりの強度近視では,有水晶体眼内レンズが適応になります.
3 ぶどう膜炎
どのような非感染性ぶどう膜炎に対してTNF阻害薬を使うべきですか?
著者: 臼井嘉彦
ページ範囲:P.134 - P.137
既存治療(ステロイド全身投与やシクロスポリン投与)で効果不十分な非感染性の中間部,後部または汎ぶどう膜炎に使うべきです.
非感染性ぶどう膜炎に対するTNF阻害薬治療を中止する適切なタイミングを教えてください
著者: 高瀬博
ページ範囲:P.138 - P.141
明確なコンセンサスはいまだありませんが,眼内および全身の炎症が長期間完全に抑制されていれば,TNF阻害薬から他の免疫抑制薬に切り替えられる可能性があります.
非感染性ぶどう膜炎でTNF阻害薬を使えばステロイド内服をやめられますか?
著者: 蕪城俊克
ページ範囲:P.142 - P.145
非感染性ぶどう膜炎に対しステロイド内服量を減量する目的でTNF阻害薬(アダリムマブ)が用いられます.国際臨床試験の結果では,アダリムマブ開始により最終的にステロイド離脱して非活動状態を達成したのは,試験開始時点で活動性であったぶどう膜炎症例の54%(66/123例),および同時点で非活動性であった症例の89%(51/57例)でした.
免疫チェックポイント阻害薬の副作用によるぶどう膜炎の頻度と対処法を教えてください
著者: 岩田大樹
ページ範囲:P.146 - P.150
免疫チェックポイント阻害薬で治療された患者の3.6%で眼障害の副作用が報告されています.基本的な対処として,原因薬剤の休止,炎症の程度に応じたステロイド薬の点眼や全身投与,免疫抑制療法を検討します.
感染性ぶどう膜炎におけるPCR検査はどのくらい信頼できますか?
著者: 杉田直
ページ範囲:P.151 - P.154
適切な,かつ炎症の活動性のある眼局所検体を用いたリアルタイムPCR手法ならば,ヘルペスウイルス感染症の結果はほぼ100%近く信頼できます.しかし,結核などPCRだけでは診断できない疾患群があります.
小児を含むわが国でのぶどう膜炎の頻度を教えてください
著者: 長谷川英一
ページ範囲:P.155 - P.157
2016年度のわが国における全国疫学調査では,年間の新規ぶどう膜炎患者数は眼科新規患者の3.2%であり,そのうち小児の割合は5.6%でした.
4 神経眼科・弱視・斜視
Leber遺伝性視神経症の日本における頻度と最新の情報を教えてください
著者: 上田香織
ページ範囲:P.160 - P.163
最新の疫学調査として,2019年に全国調査が行われました.年間新規発症者は69人(男性62人,女性7人),総患者数は約2500人,有病率は1:50000程度と推計されました.
外傷性視神経症に対して手術療法は意味があるのでしょうか?
著者: 恩田秀寿
ページ範囲:P.164 - P.167
視神経管骨折がはっきりしない外傷性視神経症の治療方針に,有力なエビデンスは見いだせていません.しかし,個々の症例をみると薬物治療や外科的治療が奏効する場合があります.
難治性視神経炎の急性期治療においてどのようなときにIVIGを使えばよいですか?
著者: 植木智志
ページ範囲:P.168 - P.170
難治性視神経炎の代表疾患である抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎などが疑われる症例では,まずステロイドパルス療法を行います.ステロイドパルス療法を行っても視力改善がみられなければ,IVIGを検討します.
Sagging eye syndromeとは何ですか?
著者: 國見敬子 , 後関利明
ページ範囲:P.171 - P.175
眼窩pulleyをはじめとする眼窩周囲の結合織の加齢性変化による開散麻痺様遠見内斜視および微小上下斜視疾患です.
スマートフォンで内斜視になりやすいのはどんな人ですか?
著者: 飯森宏仁
ページ範囲:P.176 - P.179
近視や長時間使用の背景のある若年者が多いですが,詳細については不明な部分が多く現在全国調査が行われています.
どのような斜視に対してボツリヌス毒素療法が有効ですか?
著者: 宇井牧子
ページ範囲:P.180 - P.184
後天内斜視,急性期外転神経麻痺,甲状腺眼症に有効で,ボツリヌス毒素療法の良い適応です.大角度の斜視に対する後転術との併用療法も有効です.海外では乳児内斜視への有効性が明らかにされていますが,わが国では12歳以上の症例にのみ保険適用です.
斜視手術でplication術を使うのはどんなときですか?
著者: 櫻井藍子 , 後関利明
ページ範囲:P.185 - P.188
切筋の必要がないplication術は,切筋を要する前転術と同等の効果があります.前眼部虚血を回避でき,lost muscleを生じず,術後早期であれば修正可能であり,術後屈折に影響を与えない,前転術より低侵襲の術式です.前転術の適応となる症例はplication術の適応です.
5 網膜硝子体
滲出型加齢黄斑変性の治療にはどのようなエビデンスがありますか?
著者: 柳靖雄
ページ範囲:P.190 - P.192
視力を維持するという点で抗VEGF薬(ベバシズマブ,ラニビズマブ,アフリベルセプト,ブロルシズマブ,ファリシマブ)の有効性が示されています.これまでの臨床研究によると,未治療の中心窩黄斑部新生血管を伴う加齢黄斑変性患者に対する視力改善の程度については,薬剤による違いは認めていません.ファリシマブは最大で16週間隔の投与が可能ですが,どの薬剤が最も治療間隔を延長し患者の治療負担軽減につながるかは明らかとなっていません.臨床試験のサンプルサイズでは,稀な安全性転帰の違いや忍容性を推定するのに十分ではないかもしれません.
ポリープ状脈絡膜血管症に対して光線力学療法を併用した抗VEGF療法を導入期治療として考えてもよいですか?
著者: 小畑亮
ページ範囲:P.193 - P.196
はい.治療初回からPDTを併用した抗VEGF療法は,ポリープ閉塞率を上げ,視力予後を改善し,治療回数を少なくするために有効です.
早期加齢黄斑変性の患者にはどのステージでどのようなサプリメントを勧めるのがよいですか?
著者: 柳靖雄
ページ範囲:P.197 - P.200
早期加齢黄斑変性(AMD)のなかでも進行の可能性の高い(中等度AMD)患者は,抗酸化ビタミンとミネラルのマルチビタミンサプリメントを服用すると進行を抑制できる可能性があります.一方でルテインとゼアキサンチンを含むサプリメントは,AMDの進行にはほとんど影響しない可能性があります.また,高濃度のβ-カロテンを含むサプリメントは,全身性の副作用が高い可能性があります.
近視性新生血管黄斑症に対する抗VEGF薬の使い方について教えてください
著者: 大西由花
ページ範囲:P.201 - P.205
抗VEGF薬を単回投与し,その後は,活動性の持続もしくは再燃が確認された場合に再投与を行う
糖尿病網膜症に対する抗VEGF薬と網膜光凝固術の使い分けについて教えてください
著者: 加藤喜大 , 吉田茂生 , 春田雅俊
ページ範囲:P.206 - P.209
治療方針決定には,患者のコンプライアンス,糖尿病黄斑浮腫の種類や網膜の状態を総合的に考慮する必要があります.
増殖糖尿病網膜症に対する抗VEGF療法の効果は?
著者: 津田祐希 , 中尾新太郎
ページ範囲:P.210 - P.213
わが国では保険適用外ですが,短期的な視力予後に関しては汎網膜光凝固(PRP)に劣りません.PRPと比較して視野感度を保ち,硝子体手術の必要性を低下させる可能性があります.しかし,経済的側面や来院回数の課題もあり,長期的な評価が求められます.
網膜静脈分枝閉塞症に対する抗VEGF療法の使い方は? レーザー治療との併用は?
著者: 瓶井資弘
ページ範囲:P.214 - P.217
1+PRN投与で治療するのが主流です.レーザーは少なくとも1年は併用することはありません.
全身副作用の発現頻度は抗VEGF薬の種類によって異なりますか?
著者: 片岡恵子
ページ範囲:P.218 - P.220
急性心筋梗塞や脳血管障害などの全身副作用の発現頻度を,ベバシズマブ(適応外使用),ラニビズマブ,アフリベルセプトの3剤で比較した場合,薬剤の種類による明らかな差はありません.
中心性漿液性脈絡網膜症の治療法とその予後について教えてください
著者: 山本有貴 , 五味文
ページ範囲:P.221 - P.224
治療法は,漏出点に対する直接光凝固,漏出点が黄斑近傍にある場合は光線力学療法(PDT)を施行します(CSCに対するPDTは保険適用外).慢性化した場合は脈絡膜新生血管を伴うことがあり,視力低下に注意が必要です.
網膜中心動脈閉塞症に対する適切な治療法を教えてください
著者: 村上祐介
ページ範囲:P.225 - P.228
発症4.5時間以内の経静脈的血栓溶解治療の有効性が示唆されましたが,ランダム化比較試験での検証はなく,現在のところわが国での承認薬はありません.また,RAOは心血管病の併発リスクが高く,二次予防のために診療科間・施設間の連携診療が重要です.
難治性黄斑円孔に対する手術法は何が適切ですか?
著者: 塩出雄亮 , 森實祐基
ページ範囲:P.229 - P.233
「難治性黄斑円孔」は,標準的な手術法(硝子体切除+ILM剝離+ガスタンポナーデ)では円孔の閉鎖を得ることが難しい黄斑円孔の総称です.近年報告されたメタアナリシスの結果からは,円孔径の大きな黄斑円孔(円孔径>400μm)や高度近視に伴う黄斑円孔では,内境界膜を剝離するよりも翻転したほうが円孔の閉鎖率が高いといえます.
裂孔原性網膜剝離には強膜バックリング術と硝子体手術のどちらを勧めますか?
著者: 出田隆一
ページ範囲:P.234 - P.237
最新のメタアナリシスの結果によると,初回復位率,最終復位率ともに強膜バックリング術と硝子体手術の間に差はありません.視力予後にも実質的には差がなく,臨床的には個々の症例の病態によって判断するべきです.
裂孔原性網膜剝離に対する硝子体手術成績に関連する因子は何ですか?
著者: 船津諒
ページ範囲:P.238 - P.242
増殖性硝子体網膜症(グレードB以上),巨大裂孔,脈絡膜剝離,低眼圧を伴うcomplex型裂孔原性網膜剝離(RRD)は網膜復位率と関連します.Non-complex型RRDかつ50歳未満の有水晶体眼または多発裂孔を呈するとき,経毛様体扁平部硝子体切除術を選択すると再手術率を高める可能性があります.
6 角結膜・感染症
アレルギー性結膜炎に免疫療法は効果があるのでしょうか?
著者: 中島勇魚 , 福田憲
ページ範囲:P.244 - P.247
アレルゲン免疫療法はアレルギー性結膜炎の症状の緩和に効果があることが臨床治験で証明されています.
円錐角膜は遺伝性のものですか? それとも後天性のものですか?
著者: 臼井智彦
ページ範囲:P.251 - P.254
円錐角膜は,異なる複数の病因が存在している可能性があります.遺伝性か後天性かについて結論は出ておらず,遺伝的なものもあれば,眼をこすることや,睡眠時の眼球圧迫などによる外傷が必須条件である,との考え方もあります.
角膜クロスリンキングの適応と効果について教えてください
著者: 吉田絢子
ページ範囲:P.255 - P.259
角膜クロスリンキングは進行性の角膜拡張性疾患に対して実施され,主な適応疾患は円錐角膜です.リボフラビンと紫外線照射の効果で角膜実質の強度が上がり,角膜拡張の進行が抑制されます.
デスメ膜を剝離しただけで水疱性角膜症が治るって本当ですか?
著者: 家室怜 , 相馬剛至
ページ範囲:P.260 - P.263
Fuchs角膜内皮ジストロフィによる角膜浮腫に対して,角膜中央部のデスメ膜を剝離することで角膜浮腫を消退させた報告が複数あります.適応症例の研究が進めば治療の選択肢として普及するかもしれません.
培養ヒト角膜内皮細胞移植(前房内注入)の成績はどうでしょうか?
著者: 沼幸作
ページ範囲:P.264 - P.269
ヒト初回投与試験である臨床研究11例における手術後5年の臨床成績は,従来型角膜内皮移植術と同等あるいは優れるという結果を示しています.
日本における感染性角膜炎の起炎菌について教えてください
著者: 戸所大輔
ページ範囲:P.270 - P.274
細菌が8〜9割を占め,グラム陽性球菌では黄色ブドウ球菌や肺炎球菌,グラム陰性桿菌では緑膿菌やモラクセラが代表的です.ただし,コンタクトレンズ装用者では緑膿菌とアカントアメーバが多くみられます.
眼類天疱瘡の結膜生検のコツについて教えてください
著者: 田聖花
ページ範囲:P.275 - P.277
確定診断は,瞼結膜生検の直接蛍光抗体法による組織検査で行いますが,陽性率は低いため,臨床的所見による診断が重要です.生検による病状進行のリスクがあり,慎重に行う必要があります.
7 腫瘍・涙器涙道
ぶどう膜悪性黒色腫の眼球温存治療は可能でしょうか? また,どのような方法があるのでしょうか?
著者: 鈴木茂伸
ページ範囲:P.280 - P.283
放射線治療により,90%程度の眼球を温存できるようになっています.ただ,視力低下は避けられず,血管新生緑内障を高率に生じます.放射線治療には,小線源治療,粒子線治療,定位放射線治療などがあります.
ぶどう膜悪性黒色腫の全身転移の予測や早期発見は可能でしょうか? また,転移が発見されたときはどうしたらよいですか?
著者: 鈴木茂伸
ページ範囲:P.284 - P.288
ぶどう膜悪性黒色腫の転移は肝臓に生じることが多く,肝臓の画像検査が有用です.転移の予測因子はTNM分類,組織型,腫瘍組織の遺伝子発現などがあります.転移の治療は,肝臓だけの治療,あるいは免疫療法が行われます.
網膜芽細胞腫の眼球摘出後の管理ではどのようなことに注意すべきでしょうか?
著者: 鈴木茂伸
ページ範囲:P.289 - P.293
①術後創管理および義眼調整,②摘出眼球の病理検査および後療法の適応,③眼窩再発のチェック,④片側性の場合の他眼発症,⑤遺伝,⑥二次がんなどに注意する必要があります.
眼内リンパ腫の眼病変の治療はどのように行うのがよいでしょうか?
著者: 蕪城俊克
ページ範囲:P.294 - P.297
原発性悪性リンパ腫に対する治療には,①放射線治療,②メトトレキサート硝子体注射(保険適用外),③大量メトトレキサートを中心とした全身化学療法があり,症例の状態に応じて単独あるいは組み合わせた治療法が行われています.
無色素性の脈絡膜腫瘍はどのようなものがあるでしょうか? また,どのような検査を行って診断すべきでしょうか?
著者: 加瀬諭
ページ範囲:P.298 - P.299
無色素性脈絡膜腫瘍は転移性脈絡膜腫瘍,無色素性悪性黒色腫との鑑別が重要で,検査としてはOCT,蛍光眼底造影,超音波Bモード,MRI,123I-IMP SPECTが有用です.
脈絡膜転移がんに対して,どのような治療を行うとよいでしょうか?
著者: 鈴木茂伸
ページ範囲:P.300 - P.304
原発腫瘍に対する全身の薬物治療,放射線治療,レーザーなどの局所治療があります.予測される生命予後,眼球の状態,他眼の状態,患者の希望から,最適な治療方針を決め,遅滞なく実施することが重要です.
眼付属器MALTリンパ腫の発症にウイルスは関与しているでしょうか?
著者: 加瀬諭
ページ範囲:P.306 - P.307
眼付属器MALTリンパ腫の発症に対するウイルスの関与は否定的ですが,人種によっては関連があるかもしれません.
眼付属器MALTリンパ腫の治療選択はどのように行うべきでしょうか?
著者: 加瀬諭
ページ範囲:P.308 - P.309
総線量30Gyによる放射線照射は,その寛解率は高いですが,白内障の発症に注意が必要です.無治療での経過観察を選択する場合には長期の通院・画像検査による評価が必要です.
どのような場合にIgG4関連眼疾患を疑い,どのような検査を行って診断すべきでしょうか?
著者: 高比良雅之
ページ範囲:P.310 - P.314
IgG4関連眼疾患で最も多い涙腺腫大はしばしば左右対称性です.両側の眼瞼腫脹がみられる場合には,眼窩部MRIと血清IgG4測定を行い,涙腺生検による病理検査の適応を考慮すべきでしょう.
先天鼻涙管閉塞に対する適切な治療時期,方法はどのように考えるべきでしょうか?
著者: 松村望
ページ範囲:P.315 - P.317
生後6か月頃までは経過観察を行い,自然治癒しなければプロービングを行います.1歳未満に局所麻酔で行うか,1歳以降に全身麻酔で行うかは,どちらでもよいです.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.6 - P.9
基本情報
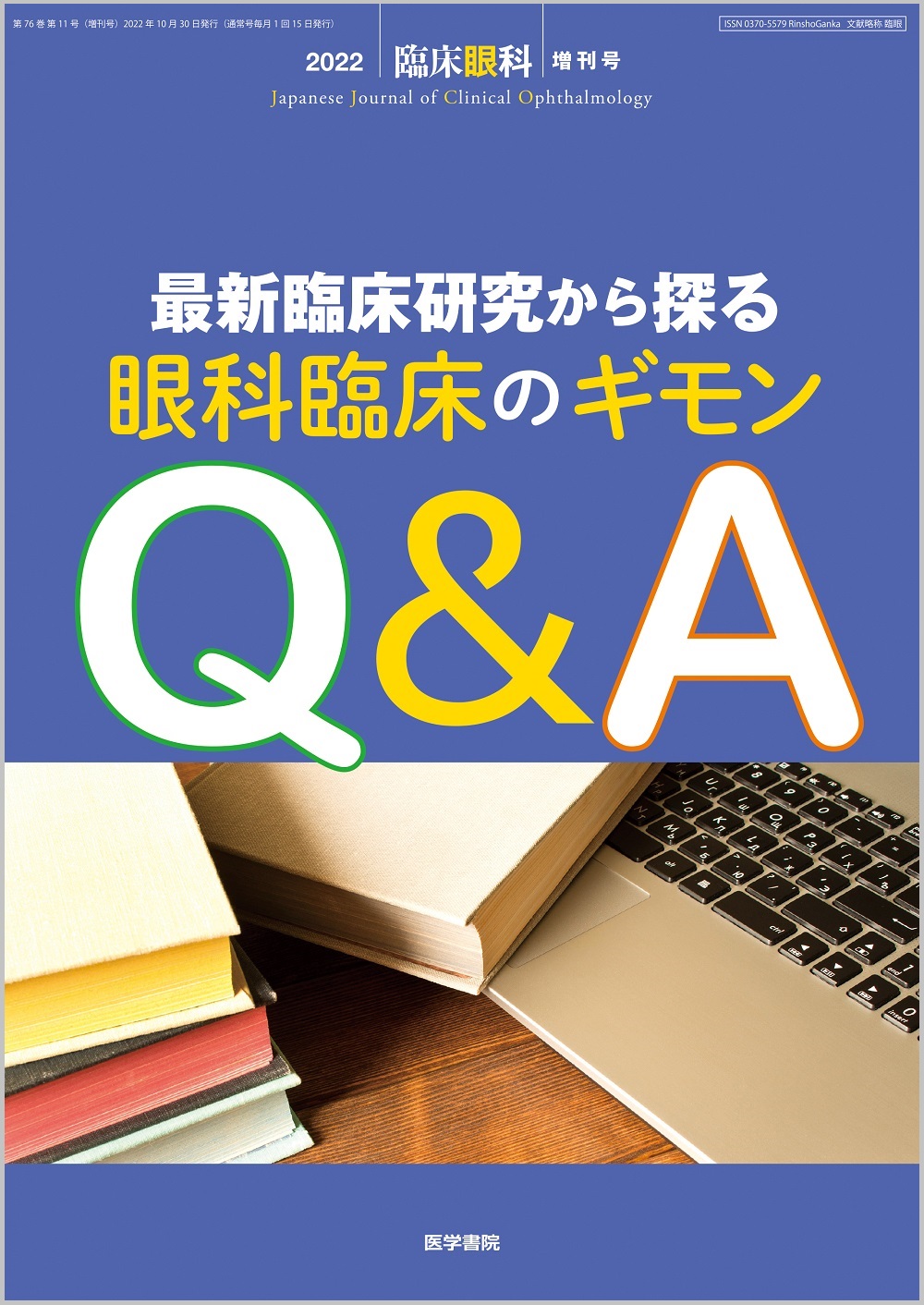
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
