近年,眼科領域も細分化が進み,ますます専門性に特化していく傾向にあります.各分野の発展は目覚ましく,新しい検査機器の登場による診断技術の進歩や,革新的な手術機器の登場,さらにはますます進化する術式や新薬の開発など,国内外の学会ではわくわくするような情報が目白押しです.
しかしながら,日々の臨床においては,最先端の治療をもってしか治せない患者さんばかりが受診されるわけではなく,一般的な疾患の患者さんも多く受診されますし,自分の専門や得意な疾患だけを診察すればよいというわけでもありません.また,緊急疾患はいつでもやってくる可能性がありますし,「私,やったことがなくて,それ苦手だから診ません」ということも通用しません.とはいっても,あまり経験のない疾患や,昔,大学で上級医と一度だけやったことがあるような処置を,クリニックや病院において1人で対応するのはやはり不安を抱きます.
雑誌目次
臨床眼科77巻11号
2023年10月発行
雑誌目次
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
序文 フリーアクセス
著者: 堀裕一
ページ範囲:P.5 - P.5
1.外眼部(眼瞼・眼窩・涙道)
霰粒腫と麦粒腫への対応
著者: 石嶋漢
ページ範囲:P.10 - P.16
●治療の基本方針:内科的治療→外科的治療
点眼,軟膏,抗菌薬内服などの内科的治療は,外科的治療を行う・行わないにかかわらず行ってよい.疼痛など症状が強い場合は切開を考慮する
●麻酔方法:局所麻酔か全身麻酔か
成人は局所麻酔をためらうことはほぼないが,小児は可能な限り全身麻酔下で行いたい.施設により状況が異なるので,小児への局所麻酔にも慣れておく
●切開方法:皮膚切開か結膜切開(瞼板切開)か
病巣へのアプローチは,近いほうから切ると病変を逃がしにくい.皮膚を切るのをためらって遠い結膜側から切開し「何も出なかった」ということにならないよう,切開を決めたらためらわず病巣に近い方向からアプローチする
眼瞼腫瘍への対応
著者: 大湊絢
ページ範囲:P.17 - P.22
●良性腫瘍か悪性腫瘍かを問診と視診から見きわめる
●腫瘍の治療の原則は全切除(母斑は例外)
●良性腫瘍は安全域なしで切除可能,悪性腫瘍は安全域を含めて切除する
●切除後の創部,眼瞼の形,眼表面への影響を十分考慮する
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
睫毛乱生への対応
著者: 加藤桂子
ページ範囲:P.23 - P.28
●睫毛電気分解は電極針を睫毛と平行に挿入する
●睫毛電気分解は電極針を無理に押し進めない
●睫毛根切除術はすべての毛根を切除できるようにできるだけ皮下組織を切除する
●睫毛根切除はバイポーラで焼灼することで残存した毛根を破壊できる
眼瞼への麻酔・切開・縫合
著者: 清水英幸 , 上田幸典
ページ範囲:P.29 - P.35
●麻酔のポイント
なるべく細い針を用いて,ゆっくり眼瞼の耳側から順に三叉神経の走行に沿って注入する
麻酔薬は筋層からの出血を予防するために,皮下から眼輪筋浅層に注入する
眼瞼後葉から結膜下に手術操作が及ぶ場合には結膜下麻酔も行う
全身麻酔下でも局所麻酔を併用して手術を行う
●切開のポイント
予定切開線の皮膚に十分な緊張を水平・垂直方向にかけながら切開する
皮膚面に対して垂直にメス刃を立て,メス刃の腹で切開する
一刀で深く切り込まずに皮膚,眼輪筋と順に切開する
●縫合のポイント
組織学的に各層が連続するように縫合する
創円に十分な血流が供給されるように縫合する
瘢痕収縮を予想した縫合をする
下眼瞼内反症の外科的治療
著者: 林憲吾
ページ範囲:P.36 - P.41
●切開法(Jones変法など)は再発率が低くいが,手技が煩雑で時間がかかる
●埋没法は出血が少なく,手技が簡便かつ短時間施行可能であり,低侵襲である
●水平方向の弛緩をpinch testで確認する
●水平方向の弛緩の有無により,2種類の埋没法を使い分ける
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
眼瞼裂傷および涙小管断裂への対応
著者: 三村真士
ページ範囲:P.47 - P.50
●受傷機転を十分に把握し,眼瞼を層別に再建する
●原形をとどめていなかったとしても残存する組織にむだな部分はないはずであり,組織を切除することは極力避ける
●涙小管断裂の有無はかならずチェックし,通過障害がある場合は再建する
●術後瘢痕予防のための工夫をする
涙小管炎
著者: 高橋靖弘
ページ範囲:P.51 - P.53
●涙小管炎に対する点眼内服治療は,発症早期にのみ有効である
●大多数の涙小管炎症例には手術が必要である
●涙小管内の涙石および肉芽組織を,鋭匙を用いて確実に除去する
●すべての涙石および肉芽組織が除去できているかを涙道内視鏡を用いて確認する
涙道内視鏡手術
著者: 鎌尾知行
ページ範囲:P.54 - P.59
●涙道内視鏡はベントタイプの彎曲を利用して涙道の生理的屈曲部位を越える
●滑車下神経麻酔は12mm(1/2インチ)短針を使用する
●数種類の涙点拡張針を用いて涙点を十分に拡張する
●閉塞部の凹み(dimple)や白色線維化領域からアプローチする
●粘膜裂孔を形成し,強い痛みや眼瞼浮腫を認めれば中止する
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
2.角結膜
春季カタルに対する外科的治療
著者: 内尾英一
ページ範囲:P.62 - P.65
●春季カタルの治療の基本は免疫抑制点眼薬による薬物治療である
●薬物治療でも抑制できない急性増悪に対して外科的治療が適応になる
●トリアムシノロンアセトニド(TA)眼瞼皮下注射は,瞼板上の一側に20mgを原則的に注射する
●TA眼瞼皮下注射による薬物皮下結節がわずかにみられるが,眼圧上昇は稀である
●乳頭切除は再発を防ぐために,術後には必ず免疫抑制点眼薬を投与する
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
眼窩脂肪ヘルニア
著者: 加瀬諭
ページ範囲:P.66 - P.69
●眼窩脂肪ヘルニアは,病理組織学的に毛細血管の豊富な組織であるため,術中の出血に対する用意が必要である
●脱出した脂肪組織の摘出の際にはモスキート鉗子でクランプして切除する
●切除後速やかにクランプを外すと出血するリスクがあるため,クランプを外さずにまずは切除縁を凝固する
結膜弛緩症手術
著者: 田聖花
ページ範囲:P.70 - P.73
●異物感以外にドライアイも生じるため,より再発の少ない術式を選択する
●焼灼法は比較的簡便だが,術後の結膜上皮欠損に注意する
●強膜縫着法では,強膜通糸時の強膜穿孔に注意する
●切除縫合法は,より根治に近い術式である
●切除縫合法では,切除量過多にならないよう注意する
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
翼状片手術
著者: 難波広幸
ページ範囲:P.74 - P.80
●翼状片頭部は鈍的に剝離する
●結膜弁での再建かマイトマイシンCの使用,もしくはその両方を行う
●縫合時は通糸・結紮で弁に牽引がかからないように留意する
●再発時の手術では組織の癒着が強く,直筋の確保が重要である
角膜穿孔への対応
著者: 家室怜 , 相馬剛至
ページ範囲:P.81 - P.86
●角膜穿孔の原因・部位・サイズを把握し,病態に応じた対応を行う
●小径の穿孔ではソフトコンタクトレンズ装用を行う
●外傷による線状の穿孔創には角膜縫合が適している
●角膜移植では移植片接合部や縫合糸が視軸にかからないように移植片をデザインする
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
角膜化学外傷時の対応
著者: 冨田大輔
ページ範囲:P.87 - P.91
●受傷直後は,まずは原因物質の除去と局所の洗浄を行う
●結膜囊までしっかり洗浄し,pHの中性化を確認する
●局所および全身へのステロイド投与による消炎を行う
●広範囲な角膜上皮欠損に対しては治療用ソフトコンタクトレンズの装用や羊膜被覆術を検討する
鉄片異物
著者: 子島良平
ページ範囲:P.92 - P.95
●鉄片異物はサンダーなどの使用が契機となり,充血や異物感,流涙などを主訴とする
●異物が角膜表面に限局している場合は細隙灯顕微鏡下で除去する
●異物が角膜深層に達し穿孔の可能性がある場合は手術室で治療する
●鉄片異物を繰り返す患者にはゴーグル装用を勧める
●角結膜に異物が見当たらないときは眼内異物を疑い精査を行う
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
涙点プラグ挿入術
著者: 加藤弘明
ページ範囲:P.96 - P.99
●術前に必ず涙点のサイズを測定し,そのサイズに合ったプラグを選択する
●挿入する涙点プラグの種類は,プラグの特徴を踏まえたうえで症例に合わせて選択する
●術中合併症として,涙点プラグの迷入が挙げられる
●術後合併症として,肉芽形成,プラグ脱落とそれに伴う涙点拡大,白色塊形成が挙げられる
IPL
著者: 有田玲子
ページ範囲:P.101 - P.105
●ライドガイド(ハンドピースの先端部分)と皮膚が平行になるように施術する
●ライドガイドは皮膚に押し付けない
●ジェルは薄めの塗布でよい
●IPLのあとにMeibom腺圧出を行うほうが効果的である
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
角膜クロスリンキング
著者: 福本光樹
ページ範囲:P.107 - P.111
●円錐角膜の早期発見が重要である
●円錐角膜の進行を見逃さないように,特に若年者の定期検査は必須である
●円錐角膜に対する進行予防が目的であり,現時点では唯一の標準的な治療方法である
●術後の合併症として特に感染予防が重要である
3.白内障・屈折矯正
ICL手術
著者: 神谷和孝
ページ範囲:P.114 - P.117
●国内における手術需要は大幅に増加しており,屈折矯正手術の中心となりつつある
●最新のホールICLでは,術後白内障や眼圧上昇といった合併症リスクが軽減している
●強度近視だけでなく,中等度近視や非進行性軽度円錐角膜に対しても適応が拡大している
●白内障手術に手技が近く,白内障手術の経験を活かしやすい
●レンズのアップサイドダウンに対しては,一度眼外に摘出した後に再挿入する
術後眼内炎
著者: 薄井紀夫
ページ範囲:P.118 - P.122
●重篤な医原性感染症であるが,適切な対応で救える疾患
●最も確実な治療方法は,抗菌薬添加灌流液を用いた前房洗浄+硝子体手術
●手術時の灌流液には,バンコマイシン塩酸塩とセフタジジム水和物を添加
●強力な抗炎症療法(ステロイド薬の全身投与・点眼)も必須
トーリックIOL術後回旋
著者: 安田健作 , 西村栄一
ページ範囲:P.123 - P.128
●乱視矯正効果を発揮させるには,的確な位置へのIOLの固定が重要である
●術後IOL回旋の危険因子を意識し,できる限りの予防をする
●軸ずれの修正は,精度の高い軸ずれの定量を行い,正確な軸の修正を行う
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
前囊収縮・後発白内障
著者: 永田万由美
ページ範囲:P.129 - P.133
●前囊収縮と後発白内障は進行しやすい時期が異なる
●前囊収縮・後発白内障ともにNd:YAGレーザーによる切開術を施行する
●レーザーパワーは低めに設定のうえ開始し,切開が困難な場合は少しずつパワーを上げていく
●レーザー誤照射によるcrackやpitに注意する
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
4.緑内障
急性緑内障発作への対応
著者: 吉水聡
ページ範囲:P.136 - P.141
●急性緑内障発作は直ちに治療を施行しなければ急速に失明へと至る救急疾患であるため,早急に適切な診断・治療を行う必要がある
●薬物治療で一時的な眼圧下降が得られても再発作をきたしやすく,外科的治療が必要である
●僚眼も発作リスクが高く,治療介入が推奨される
レーザー線維柱帯形成術—SLT・PSLT
著者: 野崎実穂
ページ範囲:P.142 - P.146
●レーザー治療開始前に,治療効果の限界や一過性眼圧上昇のリスクについて十分説明する
●アプラクロニジン塩酸塩をレーザー照射30〜60分前および照射直後に点眼し,一過性眼圧上昇を避ける
●レーザー照射30〜60分後に眼圧を測定する
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
レーザー切糸
著者: 奥道秀明
ページ範囲:P.147 - P.149
●トラベクレクトミー術後,翌日〜1か月の間に行う
●前もって隅角を確認して,虹彩や硝子体の嵌頓がないかを確認する
●眼圧が自然と下降傾向のときは切糸を行わず,原則として1日1本までとする
●円蓋部基底の結膜切開であれば,後方から行う
●可能であれば侵襲の少ないMandelkornレンズを用いる
過剰濾過への対応
著者: 西尾侑祐 , 白鳥宙 , 中元兼二
ページ範囲:P.150 - P.153
●線維柱帯切除術後の1〜18%に過剰濾過をきたす
●経結膜強膜弁縫合は簡便かつ低侵襲な方法である
●最も根治的な処置は,結膜弁を開放し直視下で行う強膜弁再縫合であるが,やや侵襲性が高い
●Compression sutureは確実性に乏しいが,濾過胞上からのタンポナーデ効果による間接的濾過量抑制効果を期待して行う
濾過胞からの房水漏出時の対応
著者: 飯川龍
ページ範囲:P.154 - P.159
●まずはフローレス試験紙を直接漏出が疑われるところに付けて,漏出の程度と部位を判定する
●術後早期の漏出は,早急な対応を要する
●術後晩期の漏出は,濾過胞の形態により術式を選択する
ブレブニードリング
著者: 杉原佳恵
ページ範囲:P.160 - P.166
●細隙灯検査と前眼部OCTで術前の濾過胞の形態を評価する
●手術室で行う
●マイトマイシンCを結膜下注射する時に注入部位が広がりすぎないようにコントロールする
●針での切開後,ブレブナイフへ持ちかえ,針で切開した層と同じ層で濾過胞壁を切開するようにする
●前房が浅くなる場合は,術終了時に前房内へ粘弾性物質を注入する
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
トラベクレクトミー(MMC併用)
著者: 浪口孝治
ページ範囲:P.171 - P.175
●トラベクレクトミーはさまざまな緑内障病型に対応できる術式である
●房水漏出させないために,結膜およびテノンの取り扱いが重要である
●低眼圧や前房出血などの合併症も多いため,術後管理も重要である
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
iStent
著者: 杉原一暢
ページ範囲:P.177 - P.183
●白内障手術併用眼内ドレーンの使用要件基準に準拠する
●低侵襲緑内障手術であり,合併症は少ないが,眼圧下降効果は弱め
●術後の眼圧やQOLなどを考慮して術式選択を行う
●少ない点眼薬で,あまり進行のみられない緑内障患者に良い適応
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
低侵襲緑内障手術(MIGS)
著者: 安田健作 , 三浦瑛子 , 齋藤雄太
ページ範囲:P.184 - P.190
●隅角所見・解剖を確認し,隅角鏡の扱いに慣れておく
●術後の眼圧は15mmHg前後で,緑内障初期〜中期に良い適応となる
●手術成功のコツは,良い視認性を保つことにある
●濾過手術の前段階の位置づけであり,本手術の適応と限界を理解する
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
バルブ付き緑内障チューブシャント手術
著者: 松尾将人
ページ範囲:P.191 - P.197
●症例ごとに最適な手術をプランニングする
●非吸収糸を用いて2直筋間の直近付着部後方にプレートを固定する
●チューブ先端と角膜内皮との距離を確保する
●チューブを自己強膜または保存強膜で被覆し,結膜縫合を行う
●プレート上にトリアムシノロンアセトニドのテノン囊下注射を行う
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
マイクロシャント—プリザーフロマイクロシャント
著者: 森和彦
ページ範囲:P.198 - P.203
●マイクロシャントは濾過系MIGS(低侵襲緑内障手術)の1つ
●線維柱帯切除術と同様に前房と結膜下組織の間に新たな房水流出路を作製
●チューブ先端が前房内に位置するため角膜内皮障害に注意
●濾過手術の1つであり,術後には濾過胞の維持管理が必要
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
5.ぶどう膜炎
硝子体生検
著者: 楠原仙太郎
ページ範囲:P.206 - P.210
●硝子体中の細胞を採取する際にはカッティングレートを低く設定する
●無灌流下での強膜圧迫ではカニューラの向きに注意
●最周辺部硝子体の十分な郭清は必須
●生検の目的に合わせたサンプル管理が重要
●三方活栓部位での気泡のトラップがないことを事前に確認
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
眼感染症多項目PCR検査—ぶどう膜炎前房水スクリーニング検査
著者: 中野聡子
ページ範囲:P.211 - P.215
●房水ピペットは安全かつ簡便に前房水採取が可能である
●炎症の主座から,病原体・炎症に富む治療前検体を採取する
●眼内液は計画的にPCR,サイトカイン,培養などに振り分ける
●感染性ぶどう膜炎,眼内炎,角結膜炎のPCRキットがある
●先進医療費用は患者負担で,特約付医療保険で給付される
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
ぶどう膜炎に対するSTTA
著者: 蕪城俊克
ページ範囲:P.216 - P.219
●点眼麻酔,洗眼を行う
●鼻下側の結膜に小切開を加え,強膜が露出するのを確認する
●ビスコ針を眼球のカーブに沿って曲げ,強膜に沿って針の根元まで結膜下に挿入する
●薬液が入っていかないときは,ビスコ針の先端を少し引いてから注入する
●感染予防のため,注射前に結膜消毒,注射後には抗菌薬点眼を行う
ウイルス性網膜炎に対する硝子体手術
著者: 臼井嘉彦
ページ範囲:P.220 - P.226
●定量PCRによるウイルスコピー数の測定は,ウイルス性網膜炎(急性網膜壊死やサイトメガロウイルス)の診断のみならず治療方針の決定にも有用である
●薬物療法や硝子体手術が進歩した今日でも,ウイルス性網膜炎の視力予後は不良な場合が多いため,硝子体手術に踏み切る場合は,患者との十分なインフォームドコンセントが必要である
●ウイルス性網膜炎の硝子体手術の施行にあたっては,施行時期や手術手技,術後合併症および視力予後に関する十分な理解が必要である
●硝子体手術により発症早期に眼内のウイルス量や過剰なサイトカイン量を低減できる
6.網膜硝子体
硝子体注射
著者: 片岡恵子
ページ範囲:P.228 - P.232
●起こりうる合併症についてあらかじめ熟知し,対応策を考えておく
●硝子体注射前の消毒により注射後の細菌性眼内炎のリスクを減らす
●硝子体注射は硝子体腔の中心に向かって針を挿入する
●水晶体や網膜の損傷などの重篤な合併症に注意する
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
光線力学的療法(PDT)
著者: 湧川空子 , 古泉英貴
ページ範囲:P.234 - P.242
●PDT施行中のトラブルを防ぐための事前準備が重要である
●症例に応じて適切な照射範囲の決定が必要である
●ベルテポルフィンの血管外漏出が起こった際は直ちに投与を中止し,適切な対応を行う
汎網膜光凝固術
著者: 村上智昭
ページ範囲:P.243 - P.249
●対象疾患とその重症度を確認し,治療適応を決定する
●中間透光体の混濁が強いときは,長波長のレーザー光を選択する
●凝固斑が出やすい中間周辺部で試し打ちを行い,凝固条件を最適化する
●疼痛が強い場合は,短波長・短時間照射に設定する
網膜裂孔へのレーザー光凝固
著者: 石龍鉄樹
ページ範囲:P.250 - P.253
●弁状裂孔の場合は,弁状裂孔の付け根の周辺側を十分に凝固する
●格子状変性萎縮円孔の場合は,格子状変性を囲み,円孔は個別に凝固斑で囲む
●部分的剝離がある例は,可能であれば観血的治療を検討する
●直径250〜400μmの大きめの凝固で,凝固斑辺縁が接するように取り囲む
●凝固斑中心部が過凝固にならないように,レーザーパワーを調整する
●円蓋(オペルクルム)を形成している円孔は,必ずしも凝固しなくてもよい
網膜硝子体手術時の麻酔
著者: 丸子一朗
ページ範囲:P.254 - P.259
●テノン囊麻酔は手技の簡便さ・確実性から最も用いられている手技である
●球後麻酔は知覚および疼痛抑制だけでなく眼球運動も制御可能で,硝子体手術に相性が良く習熟すべき手技である
●静脈麻酔は鎮静を目的とし,確実に効果が期待できる
●笑気麻酔は笑気自体の鎮静作用の有用性から,使用施設が増えている
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
ヘッズアップサージャリー導入時に知っておくべきこと
著者: 坂西良仁
ページ範囲:P.260 - P.264
●見え方が鏡筒での手術とどう違うかを知る
●照明は鏡筒の手術のときより照度を下げる
●手術室の照明は消したほうが見やすい
●慣れるまでは画質設定はあまりいじらない
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
眼球破裂時の対応
著者: 小嶋健太郎
ページ範囲:P.265 - P.270
●疑わしい病歴を有する眼外傷患者を診察する際には,眼球破裂が生じている可能性を常に念頭に置いて診察を行う
●眼球破裂を示唆する診察時の所見とCT画像検査での評価を駆使して診断する
●しばしば難治性で視力予後は不良であり,患者および家族に適切なインフォームドコンセントを行いつつ,個々の症例の状況に応じて知識と技術を総動員し視力予後の改善に努める
術後合併症
著者: 岡本史樹
ページ範囲:P.271 - P.275
●術後早期の眼圧上昇には複数の原因があり,それぞれの原因を解決するような治療法が必要
●硝子体手術後では虹彩後癒着が起こりやすく,瞳孔ブロックを防ぐような対処が必要
●術後脈絡膜剝離は網膜剝離と見間違うことがあり,特に鑑別が必要
眼内炎
著者: 井手山碧 , 大音壮太郎
ページ範囲:P.277 - P.281
●眼内炎を引き起こすと視力予後が悪く,予防および早期発見・早期治療が重要となる
●診断には前房水や硝子体液を採取し,塗抹・培養で起因菌を検出することが重要となる
●後眼部に炎症を認めるなど感染性眼内炎が疑われる場合は,抗菌薬の硝子体注射および硝子体手術が必要である
7.神経眼科
ボトックス治療
著者: 増田明子
ページ範囲:P.284 - P.287
●ボトックス治療は眼瞼痙攣に対して唯一保険適用となっている治療法である
●注射時は皮膚の皺をしっかり伸ばして注射したほうが痛みや内出血の軽減になる
●出血した際は,出血部位を圧迫止血する
●注射当日は注射部位を擦らない,投与後1時間は石鹸での洗顔は避けるように指導する
●投与箇所および単位を顔のスケッチに記録しておくと次回以降の参考になる
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
瞳孔薬物負荷テスト
著者: 森本壮
ページ範囲:P.288 - P.291
●瞳孔不同をきたす疾患を鑑別し,診断を確定するために瞳孔薬物負荷テストを行うかどうか適切に判断する
●徐神経性過敏について理解し,検査を行う
●使用する点眼薬の作用(縮瞳か散瞳)および副作用について理解し,検査を行う
上方注視負荷試験,アイステスト,エドロホニウム(テンシロン)テスト
著者: 松本直
ページ範囲:P.292 - P.296
●重症筋無力症の初発症状は眼瞼下垂と複視が多い
●上方注視負荷試験,アイステストは眼科外来で簡便に行える
●試験前後の記録を画像に残しておくと診断が容易となる
●エドロホニウムテストは副作用のリスクがあり,全身管理下に行う
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
8.小児眼科・斜視
小児の検査処置時の鎮静
著者: 藤本智子 , 四宮加容
ページ範囲:P.298 - P.301
●小児に検査・処置を行う場合,薬剤を用いた鎮静が必要となることがある
●鎮静前の経口摂取を「2-4-6ルール」に則り制限する
●鎮静中および鎮静後の全身状態確認を怠らない
小児の睫毛内反への対応
著者: 太田優
ページ範囲:P.302 - P.304
●睫毛内反症は,眼瞼前葉の余剰や,下眼瞼牽引筋群の皮膚穿通枝の脆弱性により起こる
●術式は切開法と通糸(埋没)法がある
●切開法であるHotz変法が確実性の高い術式であり,小児には全身麻酔を繰り返さないためにも初回からこちらを選択したほうがよい
●内眼角贅皮が著明な場合は,内眼角形成術(内田法,Z形成など)を併施する必要がある
先天鼻涙管閉塞・先天涙囊瘤(先天涙囊ヘルニア)
著者: 大野智子 , 松村望
ページ範囲:P.305 - P.309
先天鼻涙管閉塞
●片側性の場合は,生後6〜9か月頃を目途にプロービング(ブジー)を行う
●プロービングの際は介助者にしっかり患児の顔と体を制御してもらう
●プロービングは無理な力を入れない,押し進めない
●ブジー不成功時は同じことを繰り返さない
先天涙囊瘤(先天涙囊ヘルニア)
●自然治癒が多い
●一方で,急性涙囊炎や蜂窩織炎を生じることがある
●両側性の場合は呼吸困難をきたす可能性がある
●経鼻的造瘻術による治療が奏効する
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
外眼筋牽引試験
著者: 根岸貴志
ページ範囲:P.310 - P.312
●事前に表層角膜びらんや結膜下出血の説明をしておく
●検査はリラックスした状態で行う
●鑷子などで角膜を傷つけないようにする
●眼球の回旋中心を意識して三次元的に牽引する
斜視に対するボトックス治療
著者: 宇井牧子
ページ範囲:P.314 - P.318
●ボツリヌス毒素を外眼筋に注射すると,斜視手術における後転術に似た効果が得られる
●後天発症の斜視では,半数以上で反復注射や手術なくして治癒に至る
●良い適応は,急性後天共同性内斜視,甲状腺眼症,急性期外転神経麻痺である
●手術加療と比べ,発症早期に治療介入でき,侵襲が少なく,簡便に行える
●効果にばらつきがあり,一過性眼瞼下垂や一過性上斜視の合併症が起こりうる
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2028年10月).
未熟児網膜症に対する治療
著者: 松下五佳
ページ範囲:P.319 - P.323
●未熟児網膜症の治療の目的は網膜剝離への進行を予防することである
●レーザー光凝固,抗VEGF療法の適応の区別は明確でなく,症例ごとに検討する
●レーザー光凝固は眼球の向きの制御など,効率よく照射を行うための手技の習熟を要する
●抗VEGF療法では硝子体注射の手技に伴う水晶体や網膜の損傷に注意を要する
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.6 - P.8
基本情報
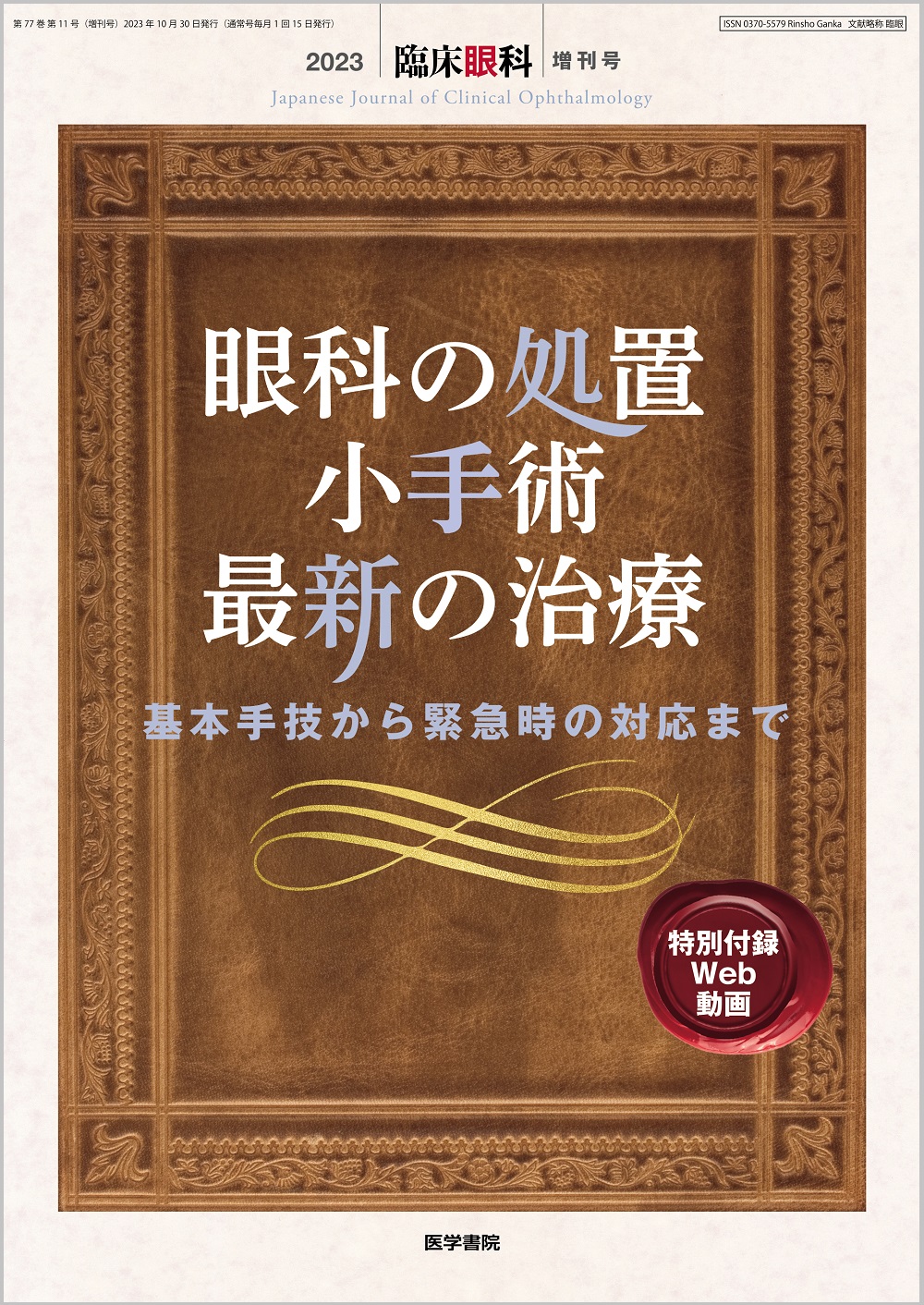
バックナンバー
78巻13号(2024年12月発行)
特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。
78巻12号(2024年11月発行)
特集 ザ・脈絡膜。
78巻11号(2024年10月発行)
増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ
78巻10号(2024年10月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]
78巻9号(2024年9月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]
78巻8号(2024年8月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]
78巻7号(2024年7月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]
78巻6号(2024年6月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]
78巻5号(2024年5月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]
78巻4号(2024年4月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]
78巻3号(2024年3月発行)
特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]
78巻2号(2024年2月発行)
特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療
78巻1号(2024年1月発行)
特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!
77巻13号(2023年12月発行)
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
77巻12号(2023年11月発行)
特集 意外と知らない小児の視力低下
77巻11号(2023年10月発行)
増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕
77巻10号(2023年10月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]
77巻9号(2023年9月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]
77巻8号(2023年8月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]
77巻7号(2023年7月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]
77巻6号(2023年6月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]
77巻5号(2023年5月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]
77巻4号(2023年4月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]
77巻3号(2023年3月発行)
特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]
77巻2号(2023年2月発行)
特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで
77巻1号(2023年1月発行)
特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?
76巻13号(2022年12月発行)
特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか
76巻12号(2022年11月発行)
特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る
76巻11号(2022年10月発行)
増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A
76巻10号(2022年10月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]
76巻9号(2022年9月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]
76巻8号(2022年8月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]
76巻7号(2022年7月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]
76巻6号(2022年6月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]
76巻5号(2022年5月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]
76巻4号(2022年4月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]
76巻3号(2022年3月発行)
特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]
76巻2号(2022年2月発行)
特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療
76巻1号(2022年1月発行)
特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ
75巻13号(2021年12月発行)
特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略
75巻12号(2021年11月発行)
特集 網膜色素変性のアップデート
75巻11号(2021年10月発行)
増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド
75巻10号(2021年10月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]
75巻9号(2021年9月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]
75巻8号(2021年8月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]
75巻7号(2021年7月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]
75巻6号(2021年6月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]
75巻5号(2021年5月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]
75巻4号(2021年4月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]
75巻3号(2021年3月発行)
特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]
75巻2号(2021年2月発行)
特集 前眼部検査のコツ教えます。
75巻1号(2021年1月発行)
特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます
74巻13号(2020年12月発行)
特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!
74巻12号(2020年11月発行)
特集 ドライアイを極める!
74巻11号(2020年10月発行)
増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点
74巻10号(2020年10月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]
74巻9号(2020年9月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]
74巻8号(2020年8月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]
74巻7号(2020年7月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]
74巻6号(2020年6月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]
74巻5号(2020年5月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]
74巻4号(2020年4月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]
74巻3号(2020年3月発行)
特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]
74巻2号(2020年2月発行)
特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ
74巻1号(2020年1月発行)
特集 画像が開く新しい眼科手術
73巻13号(2019年12月発行)
特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?
73巻12号(2019年11月発行)
特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!
73巻11号(2019年10月発行)
増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート
73巻10号(2019年10月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]
73巻9号(2019年9月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]
73巻8号(2019年8月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]
73巻7号(2019年7月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]
73巻6号(2019年6月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]
73巻5号(2019年5月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]
73巻4号(2019年4月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]
73巻3号(2019年3月発行)
特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]
73巻2号(2019年2月発行)
特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版
73巻1号(2019年1月発行)
特集 今が旬! アレルギー性結膜炎
72巻13号(2018年12月発行)
特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴
72巻12号(2018年11月発行)
特集 涙器涙道手術の最近の動向
72巻11号(2018年10月発行)
増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準
72巻10号(2018年10月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]
72巻9号(2018年9月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]
72巻8号(2018年8月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]
72巻7号(2018年7月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]
72巻6号(2018年6月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]
72巻5号(2018年5月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]
72巻4号(2018年4月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]
72巻3号(2018年3月発行)
特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]
72巻2号(2018年2月発行)
特集 眼窩疾患の最近の動向
72巻1号(2018年1月発行)
特集 黄斑円孔の最新レビュー
71巻13号(2017年12月発行)
特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル
71巻12号(2017年11月発行)
特集 視神経炎最前線
71巻11号(2017年10月発行)
増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる
71巻10号(2017年10月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]
71巻9号(2017年9月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]
71巻8号(2017年8月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]
71巻7号(2017年7月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]
71巻6号(2017年6月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]
71巻5号(2017年5月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]
71巻4号(2017年4月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]
71巻3号(2017年3月発行)
特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]
71巻2号(2017年2月発行)
特集 前眼部診療の最新トピックス
71巻1号(2017年1月発行)
特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?
70巻13号(2016年12月発行)
特集 脈絡膜から考える網膜疾患
70巻12号(2016年11月発行)
特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ
70巻11号(2016年10月発行)
増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル
70巻10号(2016年10月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]
70巻9号(2016年9月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]
70巻8号(2016年8月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]
70巻7号(2016年7月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]
70巻6号(2016年6月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]
70巻5号(2016年5月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]
70巻4号(2016年4月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]
70巻3号(2016年3月発行)
特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]
70巻2号(2016年2月発行)
特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
70巻1号(2016年1月発行)
特集 眼内レンズアップデート
69巻13号(2015年12月発行)
特集 これからの眼底血管評価法
69巻12号(2015年11月発行)
特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア
69巻11号(2015年10月発行)
増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!
69巻10号(2015年10月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)
69巻9号(2015年9月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)
69巻8号(2015年8月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)
69巻7号(2015年7月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)
69巻6号(2015年6月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)
69巻5号(2015年5月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)
69巻4号(2015年4月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)
69巻3号(2015年3月発行)
特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)
69巻2号(2015年2月発行)
特集2 近年のコンタクトレンズ事情
69巻1号(2015年1月発行)
特集2 硝子体手術の功罪
68巻13号(2014年12月発行)
特集 新しい術式を評価する
68巻12号(2014年11月発行)
特集 網膜静脈閉塞の最新治療
68巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで
68巻10号(2014年10月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)
68巻9号(2014年9月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)
68巻8号(2014年8月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)
68巻7号(2014年7月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)
68巻6号(2014年6月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)
68巻5号(2014年5月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)
68巻4号(2014年4月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)
68巻3号(2014年3月発行)
特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)
68巻2号(2014年2月発行)
特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう
68巻1号(2014年1月発行)
特集 眼底疾患と悪性腫瘍
67巻13号(2013年12月発行)
特集 新しい角膜パーツ移植
67巻12号(2013年11月発行)
特集 抗VEGF薬をどう使う?
67巻11号(2013年10月発行)
特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理
67巻10号(2013年10月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)
67巻9号(2013年9月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)
67巻8号(2013年8月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)
67巻7号(2013年7月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)
67巻6号(2013年6月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)
67巻5号(2013年5月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)
67巻4号(2013年4月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)
67巻3号(2013年3月発行)
特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)
67巻2号(2013年2月発行)
特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療
67巻1号(2013年1月発行)
特集 新しい緑内障手術
66巻13号(2012年12月発行)
66巻12号(2012年11月発行)
特集 災害,震災時の眼科医療
66巻11号(2012年10月発行)
特集 オキュラーサーフェス診療アップデート
66巻10号(2012年10月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)
66巻9号(2012年9月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)
66巻8号(2012年8月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)
66巻7号(2012年7月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)
66巻6号(2012年6月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)
66巻5号(2012年5月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)
66巻4号(2012年4月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)
66巻3号(2012年3月発行)
特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)
66巻2号(2012年2月発行)
特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開
66巻1号(2012年1月発行)
65巻13号(2011年12月発行)
65巻12号(2011年11月発行)
特集 脈絡膜の画像診断
65巻11号(2011年10月発行)
特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!
65巻10号(2011年10月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)
65巻9号(2011年9月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)
65巻8号(2011年8月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)
65巻7号(2011年7月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)
65巻6号(2011年6月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)
65巻5号(2011年5月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)
65巻4号(2011年4月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)
65巻3号(2011年3月発行)
特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)
65巻2号(2011年2月発行)
特集 新しい手術手技の現状と今後の展望
65巻1号(2011年1月発行)
64巻13号(2010年12月発行)
特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ
64巻12号(2010年11月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)
64巻11号(2010年10月発行)
特集 新しい時代の白内障手術
64巻10号(2010年10月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)
64巻9号(2010年9月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)
64巻8号(2010年8月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)
64巻7号(2010年7月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)
64巻6号(2010年6月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)
64巻5号(2010年5月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)
64巻4号(2010年4月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)
64巻3号(2010年3月発行)
特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)
64巻2号(2010年2月発行)
特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか
64巻1号(2010年1月発行)
63巻13号(2009年12月発行)
63巻12号(2009年11月発行)
特集 黄斑手術の基本手技
63巻11号(2009年10月発行)
特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて
63巻10号(2009年10月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)
63巻9号(2009年9月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)
63巻8号(2009年8月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)
63巻7号(2009年7月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)
63巻6号(2009年6月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)
63巻5号(2009年5月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)
63巻4号(2009年4月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)
63巻3号(2009年3月発行)
特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)
63巻2号(2009年2月発行)
特集 未熟児網膜症診療の最前線
63巻1号(2009年1月発行)
62巻13号(2008年12月発行)
62巻12号(2008年11月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)
62巻11号(2008年10月発行)
特集 網膜硝子体診療update
62巻10号(2008年10月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)
62巻9号(2008年9月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)
62巻8号(2008年8月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)
62巻7号(2008年7月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)
62巻6号(2008年6月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)
62巻5号(2008年5月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)
62巻4号(2008年4月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)
62巻3号(2008年3月発行)
特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)
62巻2号(2008年2月発行)
特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見
62巻1号(2008年1月発行)
61巻13号(2007年12月発行)
61巻12号(2007年11月発行)
61巻11号(2007年10月発行)
特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて
61巻10号(2007年10月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)
61巻9号(2007年9月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)
61巻8号(2007年8月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)
61巻7号(2007年7月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)
61巻6号(2007年6月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)
61巻5号(2007年5月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)
61巻4号(2007年4月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)
61巻3号(2007年3月発行)
特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)
61巻2号(2007年2月発行)
特集 緑内障診療の新しい展開
61巻1号(2007年1月発行)
60巻13号(2006年12月発行)
60巻12号(2006年11月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)
60巻11号(2006年10月発行)
特集 手術のタイミングとポイント
60巻10号(2006年10月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)
60巻9号(2006年9月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)
60巻8号(2006年8月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)
60巻7号(2006年7月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)
60巻6号(2006年6月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)
60巻5号(2006年5月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)
60巻4号(2006年4月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)
60巻3号(2006年3月発行)
特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)
60巻2号(2006年2月発行)
特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療
60巻1号(2006年1月発行)
59巻13号(2005年12月発行)
59巻12号(2005年11月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)
59巻11号(2005年10月発行)
特集 眼科における最新医工学
59巻10号(2005年10月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)
59巻9号(2005年9月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)
59巻8号(2005年8月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)
59巻7号(2005年7月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)
59巻6号(2005年6月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)
59巻5号(2005年5月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)
59巻4号(2005年4月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)
59巻3号(2005年3月発行)
特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)
59巻2号(2005年2月発行)
特集 結膜アレルギーの病態と対策
59巻1号(2005年1月発行)
58巻13号(2004年12月発行)
特集 コンタクトレンズ2004
58巻12号(2004年11月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)
58巻11号(2004年10月発行)
特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例
58巻10号(2004年10月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)
58巻9号(2004年9月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)
58巻8号(2004年8月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)
58巻7号(2004年7月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)
58巻6号(2004年6月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)
58巻5号(2004年5月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)
58巻4号(2004年4月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)
58巻3号(2004年3月発行)
特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)
58巻2号(2004年2月発行)
58巻1号(2004年1月発行)
57巻13号(2003年12月発行)
57巻12号(2003年11月発行)
57巻11号(2003年10月発行)
特集 眼感染症診療ガイド
57巻10号(2003年10月発行)
特集 網膜色素変性症の最前線
57巻9号(2003年9月発行)
57巻8号(2003年8月発行)
特集 ベーチェット病研究の最近の進歩
57巻7号(2003年7月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)
57巻6号(2003年6月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)
57巻5号(2003年5月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)
57巻4号(2003年4月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)
57巻3号(2003年3月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)
57巻2号(2003年2月発行)
特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)
57巻1号(2003年1月発行)
56巻13号(2002年12月発行)
56巻12号(2002年11月発行)
特集 眼窩腫瘍
56巻11号(2002年10月発行)
56巻10号(2002年9月発行)
56巻9号(2002年9月発行)
特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略
56巻8号(2002年8月発行)
56巻7号(2002年7月発行)
特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に
56巻6号(2002年6月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)
56巻5号(2002年5月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)
56巻4号(2002年4月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)
56巻3号(2002年3月発行)
特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)
56巻2号(2002年2月発行)
56巻1号(2002年1月発行)
55巻13号(2001年12月発行)
55巻12号(2001年11月発行)
55巻11号(2001年10月発行)
55巻10号(2001年9月発行)
特集 EBM確立に向けての治療ガイド
55巻9号(2001年9月発行)
55巻8号(2001年8月発行)
特集 眼疾患の季節変動
55巻7号(2001年7月発行)
55巻6号(2001年6月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)
55巻5号(2001年5月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)
55巻4号(2001年4月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)
55巻3号(2001年3月発行)
特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)
55巻2号(2001年2月発行)
55巻1号(2001年1月発行)
特集 眼外傷の救急治療
54巻13号(2000年12月発行)
54巻12号(2000年11月発行)
54巻11号(2000年10月発行)
特集 眼科基本診療Update—私はこうしている
54巻10号(2000年10月発行)
54巻9号(2000年9月発行)
54巻8号(2000年8月発行)
54巻7号(2000年7月発行)
54巻6号(2000年6月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)
54巻5号(2000年5月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)
54巻4号(2000年4月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)
54巻3号(2000年3月発行)
特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)
54巻2号(2000年2月発行)
特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム
54巻1号(2000年1月発行)
53巻13号(1999年12月発行)
53巻12号(1999年11月発行)
53巻11号(1999年10月発行)
53巻10号(1999年9月発行)
特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
53巻9号(1999年9月発行)
53巻8号(1999年8月発行)
53巻7号(1999年7月発行)
53巻6号(1999年6月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)
53巻5号(1999年5月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)
53巻4号(1999年4月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)
53巻3号(1999年3月発行)
特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)
53巻2号(1999年2月発行)
53巻1号(1999年1月発行)
52巻13号(1998年12月発行)
52巻12号(1998年11月発行)
52巻11号(1998年10月発行)
特集 眼科検査法を検証する
52巻10号(1998年10月発行)
52巻9号(1998年9月発行)
特集 OCT
52巻8号(1998年8月発行)
52巻7号(1998年7月発行)
52巻6号(1998年6月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)
52巻5号(1998年5月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)
52巻4号(1998年4月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)
52巻3号(1998年3月発行)
特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)
52巻2号(1998年2月発行)
52巻1号(1998年1月発行)
51巻13号(1997年12月発行)
51巻12号(1997年11月発行)
51巻11号(1997年10月発行)
特集 オキュラーサーフェスToday
51巻10号(1997年10月発行)
51巻9号(1997年9月発行)
51巻8号(1997年8月発行)
51巻7号(1997年7月発行)
51巻6号(1997年6月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)
51巻5号(1997年5月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)
51巻4号(1997年4月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)
51巻3号(1997年3月発行)
特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)
51巻2号(1997年2月発行)
51巻1号(1997年1月発行)
50巻13号(1996年12月発行)
50巻12号(1996年11月発行)
50巻11号(1996年10月発行)
特集 緑内障Today
50巻10号(1996年10月発行)
50巻9号(1996年9月発行)
50巻8号(1996年8月発行)
50巻7号(1996年7月発行)
50巻6号(1996年6月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)
50巻5号(1996年5月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)
50巻4号(1996年4月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)
50巻3号(1996年3月発行)
特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)
50巻2号(1996年2月発行)
50巻1号(1996年1月発行)
49巻13号(1995年12月発行)
49巻12号(1995年11月発行)
49巻11号(1995年10月発行)
特集 眼科診療に役立つ基本データ
49巻10号(1995年10月発行)
49巻9号(1995年9月発行)
49巻8号(1995年8月発行)
49巻7号(1995年7月発行)
49巻6号(1995年6月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)
49巻5号(1995年5月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)
49巻4号(1995年4月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)
49巻3号(1995年3月発行)
特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)
49巻2号(1995年2月発行)
49巻1号(1995年1月発行)
特集 ICG螢光造影
48巻13号(1994年12月発行)
48巻12号(1994年11月発行)
48巻11号(1994年10月発行)
特集 高齢患者の眼科手術
48巻10号(1994年10月発行)
48巻9号(1994年9月発行)
48巻8号(1994年8月発行)
48巻7号(1994年7月発行)
48巻6号(1994年6月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)
48巻5号(1994年5月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)
48巻4号(1994年4月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)
48巻3号(1994年3月発行)
特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)
48巻2号(1994年2月発行)
48巻1号(1994年1月発行)
47巻13号(1993年12月発行)
47巻12号(1993年11月発行)
47巻11号(1993年10月発行)
特集 白内障手術 Controversy '93
47巻10号(1993年10月発行)
47巻9号(1993年9月発行)
47巻8号(1993年8月発行)
47巻7号(1993年7月発行)
47巻6号(1993年6月発行)
47巻5号(1993年5月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京
47巻4号(1993年4月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京
47巻3号(1993年3月発行)
特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京
47巻2号(1993年2月発行)
47巻1号(1993年1月発行)
46巻13号(1992年12月発行)
46巻12号(1992年11月発行)
46巻11号(1992年10月発行)
特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋
46巻10号(1992年10月発行)
46巻9号(1992年9月発行)
46巻8号(1992年8月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島
46巻7号(1992年7月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島
46巻6号(1992年6月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島
46巻5号(1992年5月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島
46巻4号(1992年4月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島
46巻3号(1992年3月発行)
特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島
46巻2号(1992年2月発行)
46巻1号(1992年1月発行)
45巻13号(1991年12月発行)
45巻12号(1991年11月発行)
45巻11号(1991年10月発行)
特集 眼科基本診療—私はこうしている
45巻10号(1991年10月発行)
45巻9号(1991年9月発行)
45巻8号(1991年8月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京
45巻7号(1991年7月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京
45巻6号(1991年6月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京
45巻5号(1991年5月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京
45巻4号(1991年4月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京
45巻3号(1991年3月発行)
特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京
45巻2号(1991年2月発行)
45巻1号(1991年1月発行)
44巻13号(1990年12月発行)
44巻12号(1990年11月発行)
44巻11号(1990年10月発行)
44巻10号(1990年9月発行)
特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている
44巻9号(1990年9月発行)
44巻8号(1990年8月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋
44巻7号(1990年7月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋
44巻6号(1990年6月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋
44巻5号(1990年5月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋
44巻4号(1990年4月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋
44巻3号(1990年3月発行)
特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋
44巻2号(1990年2月発行)
44巻1号(1990年1月発行)
43巻13号(1989年12月発行)
43巻12号(1989年11月発行)
43巻11号(1989年10月発行)
43巻10号(1989年9月発行)
特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている
43巻9号(1989年9月発行)
43巻8号(1989年8月発行)
43巻7号(1989年7月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京
43巻6号(1989年6月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京
43巻5号(1989年5月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京
43巻4号(1989年4月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京
43巻3号(1989年3月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京
43巻2号(1989年2月発行)
特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京
43巻1号(1989年1月発行)
42巻12号(1988年12月発行)
42巻11号(1988年11月発行)
42巻10号(1988年10月発行)
42巻9号(1988年9月発行)
42巻8号(1988年8月発行)
42巻7号(1988年7月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)
42巻6号(1988年6月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)
42巻5号(1988年5月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)
42巻4号(1988年4月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)
42巻3号(1988年3月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)
42巻2号(1988年2月発行)
特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)
42巻1号(1988年1月発行)
41巻12号(1987年12月発行)
41巻11号(1987年11月発行)
41巻10号(1987年10月発行)
41巻9号(1987年9月発行)
41巻8号(1987年8月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)
41巻7号(1987年7月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)
41巻6号(1987年6月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)
41巻5号(1987年5月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)
41巻4号(1987年4月発行)
特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)
41巻3号(1987年3月発行)
41巻2号(1987年2月発行)
41巻1号(1987年1月発行)
40巻12号(1986年12月発行)
40巻11号(1986年11月発行)
40巻10号(1986年10月発行)
40巻9号(1986年9月発行)
40巻8号(1986年8月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)
40巻7号(1986年7月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)
40巻6号(1986年6月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)
40巻5号(1986年5月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)
40巻4号(1986年4月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)
40巻3号(1986年3月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)
40巻2号(1986年2月発行)
特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)
40巻1号(1986年1月発行)
39巻12号(1985年12月発行)
39巻11号(1985年11月発行)
39巻10号(1985年10月発行)
39巻9号(1985年9月発行)
39巻8号(1985年8月発行)
39巻7号(1985年7月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
39巻6号(1985年6月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
39巻5号(1985年5月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
39巻4号(1985年4月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
39巻3号(1985年3月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
39巻2号(1985年2月発行)
特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
39巻1号(1985年1月発行)
38巻12号(1984年12月発行)
38巻11号(1984年11月発行)
特集 第7回日本眼科手術学会
38巻10号(1984年10月発行)
38巻9号(1984年9月発行)
38巻8号(1984年8月発行)
38巻7号(1984年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
38巻6号(1984年6月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
38巻5号(1984年5月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
38巻4号(1984年4月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
38巻3号(1984年3月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
38巻2号(1984年2月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
38巻1号(1984年1月発行)
37巻12号(1983年12月発行)
37巻11号(1983年11月発行)
37巻10号(1983年10月発行)
37巻9号(1983年9月発行)
37巻8号(1983年8月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
37巻7号(1983年7月発行)
特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
37巻6号(1983年6月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
37巻5号(1983年5月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
37巻4号(1983年4月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
37巻3号(1983年3月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
37巻2号(1983年2月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
37巻1号(1983年1月発行)
特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻12号(1982年12月発行)
36巻11号(1982年11月発行)
36巻10号(1982年10月発行)
36巻9号(1982年9月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
36巻8号(1982年8月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
36巻7号(1982年7月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
36巻6号(1982年6月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
36巻5号(1982年5月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
36巻4号(1982年4月発行)
特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
36巻3号(1982年3月発行)
36巻2号(1982年2月発行)
36巻1号(1982年1月発行)
35巻12号(1981年12月発行)
35巻11号(1981年11月発行)
35巻10号(1981年10月発行)
35巻9号(1981年9月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)
35巻8号(1981年8月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)
35巻7号(1981年7月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)
35巻6号(1981年6月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
35巻5号(1981年5月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
35巻4号(1981年4月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
35巻3号(1981年3月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
35巻2号(1981年2月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)
35巻1号(1981年1月発行)
特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻12号(1980年12月発行)
34巻11号(1980年11月発行)
34巻10号(1980年10月発行)
34巻9号(1980年9月発行)
34巻8号(1980年8月発行)
34巻7号(1980年7月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
34巻6号(1980年6月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
34巻5号(1980年5月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
34巻4号(1980年4月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
34巻3号(1980年3月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
34巻2号(1980年2月発行)
特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
34巻1号(1980年1月発行)
33巻12号(1979年12月発行)
33巻11号(1979年11月発行)
33巻10号(1979年10月発行)
33巻9号(1979年9月発行)
33巻8号(1979年8月発行)
33巻7号(1979年7月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
33巻6号(1979年6月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
33巻5号(1979年5月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
33巻4号(1979年4月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)
33巻3号(1979年3月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
33巻2号(1979年2月発行)
特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
33巻1号(1979年1月発行)
32巻12号(1978年12月発行)
32巻11号(1978年11月発行)
32巻10号(1978年10月発行)
32巻9号(1978年9月発行)
32巻8号(1978年8月発行)
32巻7号(1978年7月発行)
32巻6号(1978年6月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
32巻5号(1978年5月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
32巻4号(1978年4月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
32巻3号(1978年3月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
32巻2号(1978年2月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
32巻1号(1978年1月発行)
特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
31巻12号(1977年12月発行)
31巻11号(1977年11月発行)
31巻10号(1977年10月発行)
31巻9号(1977年9月発行)
31巻8号(1977年8月発行)
31巻7号(1977年7月発行)
31巻6号(1977年6月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
31巻5号(1977年5月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
31巻4号(1977年4月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
31巻3号(1977年3月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)
31巻2号(1977年2月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
31巻1号(1977年1月発行)
特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
30巻12号(1976年12月発行)
30巻11号(1976年11月発行)
30巻10号(1976年10月発行)
30巻9号(1976年9月発行)
30巻8号(1976年8月発行)
30巻7号(1976年7月発行)
30巻6号(1976年6月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
30巻5号(1976年5月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
30巻4号(1976年4月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)
30巻3号(1976年3月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
30巻2号(1976年2月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
30巻1号(1976年1月発行)
特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
29巻12号(1975年12月発行)
29巻11号(1975年11月発行)
29巻10号(1975年10月発行)
29巻9号(1975年9月発行)
29巻8号(1975年8月発行)
29巻7号(1975年7月発行)
29巻6号(1975年6月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)
29巻5号(1975年5月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)
29巻4号(1975年4月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)
29巻3号(1975年3月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)
29巻2号(1975年2月発行)
特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)
29巻1号(1975年1月発行)
28巻12号(1974年12月発行)
28巻11号(1974年11月発行)
28巻10号(1974年10月発行)
28巻9号(1974年9月発行)
28巻7号(1974年8月発行)
28巻6号(1974年6月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)
28巻5号(1974年5月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
28巻4号(1974年4月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
28巻3号(1974年3月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
28巻2号(1974年2月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
28巻1号(1974年1月発行)
特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
27巻12号(1973年12月発行)
27巻11号(1973年11月発行)
27巻10号(1973年10月発行)
27巻9号(1973年9月発行)
27巻8号(1973年8月発行)
27巻7号(1973年7月発行)
27巻6号(1973年6月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)
27巻5号(1973年5月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)
27巻4号(1973年4月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)
27巻3号(1973年3月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)
27巻2号(1973年2月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)
27巻1号(1973年1月発行)
特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻12号(1972年12月発行)
26巻11号(1972年11月発行)
26巻10号(1972年10月発行)
26巻9号(1972年9月発行)
26巻8号(1972年8月発行)
26巻7号(1972年7月発行)
26巻6号(1972年6月発行)
26巻5号(1972年5月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻4号(1972年4月発行)
第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION
26巻3号(1972年3月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)
26巻2号(1972年2月発行)
特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)
26巻1号(1972年1月発行)
25巻12号(1971年12月発行)
25巻11号(1971年11月発行)
25巻10号(1971年10月発行)
25巻9号(1971年9月発行)
25巻8号(1971年8月発行)
25巻7号(1971年7月発行)
25巻6号(1971年6月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻5号(1971年5月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻4号(1971年4月発行)
第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion
25巻3号(1971年3月発行)
25巻2号(1971年2月発行)
25巻1号(1971年1月発行)
特集 網膜と視路の電気生理
24巻12号(1970年12月発行)
特集 緑内障
24巻11号(1970年11月発行)
特集 小児眼科
24巻10号(1970年10月発行)
24巻9号(1970年9月発行)
24巻8号(1970年8月発行)
24巻7号(1970年7月発行)
24巻6号(1970年6月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)
24巻5号(1970年5月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)
24巻4号(1970年4月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
24巻3号(1970年3月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
24巻2号(1970年2月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
24巻1号(1970年1月発行)
特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
23巻12号(1969年12月発行)
23巻11号(1969年11月発行)
23巻10号(1969年10月発行)
23巻9号(1969年9月発行)
23巻8号(1969年8月発行)
23巻7号(1969年7月発行)
23巻6号(1969年6月発行)
23巻5号(1969年5月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)
23巻4号(1969年4月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
23巻3号(1969年3月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
23巻2号(1969年2月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
23巻1号(1969年1月発行)
特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
22巻12号(1968年12月発行)
22巻11号(1968年11月発行)
22巻10号(1968年10月発行)
22巻9号(1968年9月発行)
22巻8号(1968年8月発行)
22巻7号(1968年7月発行)
22巻6号(1968年6月発行)
22巻5号(1968年5月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)
22巻4号(1968年4月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)
22巻3号(1968年3月発行)
特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
22巻2号(1968年2月発行)
特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)
22巻1号(1968年1月発行)
21巻12号(1967年12月発行)
21巻11号(1967年11月発行)
21巻10号(1967年10月発行)
21巻9号(1967年9月発行)
21巻8号(1967年8月発行)
21巻7号(1967年7月発行)
21巻6号(1967年6月発行)
21巻5号(1967年5月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)
21巻4号(1967年4月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
21巻3号(1967年3月発行)
特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
21巻2号(1967年2月発行)
特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)
21巻1号(1967年1月発行)
20巻12号(1966年12月発行)
創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩
20巻11号(1966年11月発行)
20巻10号(1966年10月発行)
20巻9号(1966年9月発行)
20巻8号(1966年8月発行)
20巻7号(1966年7月発行)
20巻6号(1966年6月発行)
20巻5号(1966年5月発行)
特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)
20巻4号(1966年4月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)
20巻3号(1966年3月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)
20巻2号(1966年2月発行)
特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
20巻1号(1966年1月発行)
19巻12号(1965年12月発行)
19巻11号(1965年11月発行)
19巻10号(1965年10月発行)
19巻9号(1965年9月発行)
19巻8号(1965年8月発行)
19巻7号(1965年7月発行)
19巻6号(1965年6月発行)
19巻5号(1965年5月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)
19巻4号(1965年4月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)
19巻3号(1965年3月発行)
特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)
19巻2号(1965年2月発行)
特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)
19巻1号(1965年1月発行)
18巻12号(1964年12月発行)
特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例
18巻11号(1964年11月発行)
18巻10号(1964年10月発行)
18巻9号(1964年9月発行)
18巻8号(1964年8月発行)
18巻7号(1964年7月発行)
18巻6号(1964年6月発行)
18巻5号(1964年5月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)
18巻4号(1964年4月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)
18巻3号(1964年3月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)
18巻2号(1964年2月発行)
特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)
18巻1号(1964年1月発行)
17巻12号(1963年12月発行)
特集 眼科検査法(3)
17巻11号(1963年11月発行)
特集 眼科検査法(2)
17巻10号(1963年10月発行)
特集 眼科検査法(1)
17巻9号(1963年9月発行)
17巻8号(1963年8月発行)
17巻7号(1963年7月発行)
17巻6号(1963年6月発行)
17巻5号(1963年5月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)
17巻4号(1963年4月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)
17巻3号(1963年3月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)
17巻2号(1963年2月発行)
特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)
17巻1号(1963年1月発行)
16巻12号(1962年12月発行)
16巻11号(1962年11月発行)
16巻10号(1962年10月発行)
16巻9号(1962年9月発行)
16巻8号(1962年8月発行)
16巻7号(1962年7月発行)
16巻6号(1962年6月発行)
16巻5号(1962年5月発行)
16巻4号(1962年4月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(3)
16巻3号(1962年3月発行)
特集 第15回臨床眼科学会号(2)
16巻2号(1962年2月発行)
特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)
16巻1号(1962年1月発行)
15巻12号(1961年12月発行)
15巻11号(1961年11月発行)
15巻10号(1961年10月発行)
15巻9号(1961年9月発行)
15巻8号(1961年8月発行)
15巻7号(1961年7月発行)
15巻6号(1961年6月発行)
15巻5号(1961年5月発行)
15巻4号(1961年4月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(3)
15巻3号(1961年3月発行)
特集 第14回臨床眼科学会号(2)
15巻2号(1961年2月発行)
特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)
15巻1号(1961年1月発行)
14巻12号(1960年12月発行)
14巻11号(1960年11月発行)
特集 故佐藤勉教授追悼号
14巻10号(1960年10月発行)
14巻9号(1960年9月発行)
14巻8号(1960年8月発行)
14巻7号(1960年7月発行)
14巻6号(1960年6月発行)
14巻5号(1960年5月発行)
14巻4号(1960年4月発行)
14巻3号(1960年3月発行)
特集
14巻2号(1960年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
14巻1号(1960年1月発行)
13巻12号(1959年12月発行)
13巻11号(1959年11月発行)
13巻10号(1959年10月発行)
13巻9号(1959年9月発行)
13巻8号(1959年8月発行)
13巻7号(1959年7月発行)
13巻6号(1959年6月発行)
13巻5号(1959年5月発行)
13巻4号(1959年4月発行)
13巻3号(1959年3月発行)
13巻2号(1959年2月発行)
特集 第13回臨床眼科学会号
13巻1号(1959年1月発行)
12巻13号(1958年12月発行)
12巻11号(1958年11月発行)
特集 手術
12巻12号(1958年11月発行)
12巻10号(1958年10月発行)
12巻9号(1958年9月発行)
12巻8号(1958年8月発行)
12巻7号(1958年7月発行)
12巻6号(1958年6月発行)
12巻5号(1958年5月発行)
12巻4号(1958年4月発行)
12巻3号(1958年3月発行)
特集 第11回臨床眼科学会号
12巻2号(1958年2月発行)
12巻1号(1958年1月発行)
11巻13号(1957年12月発行)
特集 トラコーマ
11巻12号(1957年12月発行)
11巻11号(1957年11月発行)
11巻10号(1957年10月発行)
11巻9号(1957年9月発行)
11巻8号(1957年8月発行)
11巻7号(1957年7月発行)
11巻6号(1957年6月発行)
11巻5号(1957年5月発行)
11巻4号(1957年4月発行)
11巻3号(1957年3月発行)
11巻2号(1957年2月発行)
特集 第10回臨床眼科学会号
11巻1号(1957年1月発行)
10巻13号(1956年12月発行)
特集 トラコーマ
10巻12号(1956年12月発行)
10巻11号(1956年11月発行)
10巻10号(1956年10月発行)
10巻9号(1956年9月発行)
10巻8号(1956年8月発行)
10巻7号(1956年7月発行)
10巻6号(1956年6月発行)
10巻5号(1956年5月発行)
10巻4号(1956年4月発行)
特集 第9回日本臨床眼科学会号
10巻3号(1956年3月発行)
10巻2号(1956年2月発行)
特集 第9回臨床眼科学会号
10巻1号(1956年1月発行)
9巻12号(1955年12月発行)
9巻11号(1955年11月発行)
9巻10号(1955年10月発行)
9巻9号(1955年9月発行)
9巻8号(1955年8月発行)
9巻7号(1955年7月発行)
9巻6号(1955年6月発行)
9巻5号(1955年5月発行)
9巻4号(1955年4月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅲ
9巻3号(1955年3月発行)
9巻2号(1955年2月発行)
特集 第8回日本臨床眼科学会
9巻1号(1955年1月発行)
8巻12号(1954年12月発行)
8巻11号(1954年11月発行)
8巻10号(1954年10月発行)
8巻9号(1954年9月発行)
8巻8号(1954年8月発行)
8巻7号(1954年7月発行)
8巻6号(1954年6月発行)
8巻5号(1954年5月発行)
8巻4号(1954年4月発行)
8巻3号(1954年3月発行)
8巻2号(1954年2月発行)
特集 第7回臨床眼科学會
8巻1号(1954年1月発行)
7巻13号(1953年12月発行)
7巻12号(1953年11月発行)
7巻11号(1953年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅱ
7巻10号(1953年10月発行)
7巻9号(1953年9月発行)
7巻8号(1953年8月発行)
7巻7号(1953年7月発行)
7巻6号(1953年6月発行)
7巻5号(1953年5月発行)
7巻4号(1953年4月発行)
7巻3号(1953年3月発行)
7巻2号(1953年2月発行)
特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)
7巻1号(1953年1月発行)
6巻13号(1952年12月発行)
6巻11号(1952年11月発行)
特集 眼科臨床の進歩Ⅰ
6巻12号(1952年11月発行)
6巻10号(1952年10月発行)
6巻9号(1952年9月発行)
6巻8号(1952年8月発行)
6巻7号(1952年7月発行)
6巻6号(1952年6月発行)
6巻5号(1952年5月発行)
6巻4号(1952年4月発行)
6巻3号(1952年3月発行)
6巻2号(1952年2月発行)
特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會
6巻1号(1952年1月発行)
5巻12号(1951年12月発行)
5巻11号(1951年11月発行)
5巻10号(1951年10月発行)
5巻9号(1951年9月発行)
5巻8号(1951年8月発行)
5巻7号(1951年7月発行)
5巻6号(1951年6月発行)
5巻5号(1951年5月発行)
5巻4号(1951年4月発行)
5巻3号(1951年3月発行)
5巻2号(1951年2月発行)
5巻1号(1951年1月発行)
4巻12号(1950年12月発行)
4巻11号(1950年11月発行)
4巻10号(1950年10月発行)
4巻9号(1950年9月発行)
4巻8号(1950年8月発行)
4巻7号(1950年7月発行)
4巻6号(1950年6月発行)
4巻5号(1950年5月発行)
4巻4号(1950年4月発行)
4巻3号(1950年3月発行)
4巻2号(1950年2月発行)
4巻1号(1950年1月発行)
