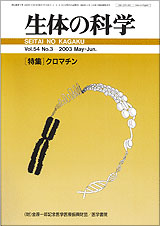文献詳細
実験講座
エバネッセンス顕微鏡
著者: 寺川進1 櫻井孝司1 坪井貴司1 菊田敏輝1 若園佳彦1 山本清二1
所属機関: 1浜松医科大学光量子医学研究センター
ページ範囲:P.245 - P.253
文献概要
屈折率の違う物質の界面に光を入射させると,全反射を起こすような入射角度の範囲があり,全反射が起きると界面上の低屈折率側にエバネッセント光が生ずることは,古くから知られていた。1970年代後半にD. Axelrodらはこのエバネッセント光を使って生物標本の励起をしてその蛍光像を得るのに成功し1),初めてエバネッセント光を生物顕微鏡の照明に応用する道を拓いた。この方法は,コントラストのよい蛍光法として使われていたが,あまり一般的には広がらなかった。その後,船津らは同じ方法を一分子の蛍光励起に使用し,一分子がリアルタイムの動画像として捉えられることを示してから2),同法が大きな注目を集めることとなった。この時点では,光源の適切な状態を得るにはかなりの技術と苦労が要り,医学生物学に携わる誰にでも使えるものではなかった。
参考文献
掲載誌情報