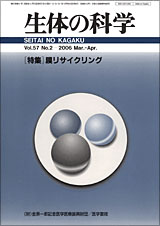文献詳細
特集 膜リサイクリング
文献概要
動物の様々な組織,とくに物理的負荷が多くかかる組織において,細胞膜には日常的に損傷が起きている1)。もしこの細胞膜の損傷が修復されなければ,それはその細胞の死を意味するが,通常は細胞膜の損傷は修復され,細胞は生き延びていることが明らかにされている1)。この膜修復という現象は長く省みられることがなかった。このことの一つの理由は,修復の仕組みが脂質二重膜の性質にのみ帰結され,細胞膜は細胞それ自身の関与なしに単に自発的にあるいは受動的に修復すると考えられてきたことにあるであろう。ところが,細胞膜損傷の修復が実際には損傷箇所から流入するCa2+に対する細胞の応答であることが,古くChambersやHeilbrunnによって示されていた(“surface precipitation reaction”)2)。1990年代に入り,直径1μm程度の微小な細胞膜損傷の修復には損傷箇所から流入するCa2+が誘起するエキソサイトーシスが必須であることが見出された3)。さらに細胞は,もっと大きな,たとえば10μm2程度以上の損傷を修復する能力も有していることが知られている。すなわち,そのような大きな損傷ができたとき,損傷箇所直下にある小胞同士が融合してできる大きな膜構造が,ちょうどパンクしたタイヤを修理するように膜損傷を修復するのである。それについては別の総説に詳しい4)。本稿では,細胞膜が微小な損傷を受けた場合の修復機構について,特にエキソサイトーシスの関与に重点を置いて,最近の研究を紹介する。
参考文献
19:697-731, 2003
419:295-301, 1930
263:390-393, 1994
6:499-505, 2005
359:733-736, 1992
15:2826-2838, 1995
15:689-696, 1995
271:17751-17754, 1996
15:3787-3791, 1996
131:1737-1745, 1995
112:719-731, 1999
159:625-635, 2002
162:543-549, 2003
2:E233, 2004
6:898, 2005)
6:843-847, 2005
14:93-106, 2003
(Bethesda) 20:239-251, 2005
13:1131-1142, 1994
89:83-94, 1995
8:138-141, 1998
4:E236-E242, 2002
15:688-695, 2004
110:847-859, 1997
1147:89-104, 1993
11:4339-4346, 2000
279:44996-45003, 2004
436:925, 2005
436:1025-1029, 2005
掲載誌情報