わが国には,小脳に関する研究の長い伝統があり,また,わが国の多くの研究者が,世界の小脳研究をけん引し,その発展に貢献してきた。とりわけ,伊藤正男先生と佐々木和夫先生は,1960年代に,当時の先端的電気生理学的解析法を駆使して,小脳の神経回路の解明に取り組んだ。伊藤先生は,小脳のプルキンエ細胞が抑制性ニューロンであることを明らかにした。当時,プルキンエ細胞のような大型の投射ニューロンはすべて興奮性であると広く考えられていたが,伊藤先生の発見はこのドグマを否定し,大きなブレークスルーとなった。佐々木先生はJohn Carew Eccles教授のもとで,小脳皮質の神経回路の解析に取り組み,多くを明らかにした。伊藤先生,佐々木先生たちの研究によって,小脳の神経回路の大枠が解明され,その略図は現在の教科書に記載されている。1970年代以降,伊藤先生は前庭動眼反射の適応をモデルとして小脳による運動制御と運動学習のメカニズム解明に取り組んだ。Marr-Albus-伊藤の理論として知られる小脳運動学習理論を確立し,小脳の運動学習の基盤と考えられる長期抑圧の発見とその分子機構の解明に取り組んだ。佐々木先生は大脳と小脳の間の神経回路とその機能に関する研究を進めた。このように,世界の神経科学の発展に多大な貢献をされた両先生であるが,多変残念なことに,佐々木和夫先生は2017年7月に,伊藤正男先生は2018年12月にご逝去された。
伊藤先生は,本誌『生体の科学』の創刊時から深く編集に関わり,育ててこられた。そこで,伊藤先生が生涯研究対象とされ,世界的にその業績が広く認知されている小脳について,特集することが肝要と考えた次第である。大学院生として,伊藤先生に直接指導を受けた最後の世代である狩野と,2光子顕微鏡を駆使した計測で小脳研究に新風を吹き込んだ喜多村の2名が編集を担当することとなった。
雑誌目次
生体の科学72巻1号
2021年02月発行
雑誌目次
特集 小脳研究の未来
特集「小脳研究の未来」によせて フリーアクセス
著者: 狩野方伸 , 喜多村和郎
ページ範囲:P.2 - P.2
Ⅰ.発生発達
ゼブラフィッシュ小脳神経回路の発生と機能
著者: 清水貴史 , 日比正彦
ページ範囲:P.3 - P.8
小脳は協調的な運動や運動学習の制御だけでなく,古典的恐怖条件づけや学習における報酬期待などの認知・情動機能にも関与している1)。小脳の発生と機能は主に哺乳類を用いて研究されてきたが,近年ゼブラフィッシュを用いた研究も発展してきた。ゼブラフィッシュは体外で発生し,初期仔魚期の体は透明であり(色素を含まない突然変異体も利用可能である),発生が早い。また,ゼブラフィッシュの脳は哺乳類の脳よりも小さく単純であるが,構造や機能が保存されており,脊椎動物の脳の発生と機能を研究するための汎用性の高いモデルになりつつある。更に,ゼブラフィッシュを用いた脳の発生と機能を研究するための様々なツールや手法が発展してきた。これらには,外来の遺伝子を持つトランスジェニックゼブラフィッシュや,脳の発生や機能に関係ある遺伝子の変異体がある。また,CRISPR/Cas9システムを用いたゲノム編集により,興味のある遺伝子を破壊したり,改変することも容易である。神経回路機能の研究には,Ca2+インジケーターや電圧センサーを用いたニューロン活動のライブイメージングや光遺伝学ツールによる機能操作が可能である。仔魚期においては,脳の小ささを生かした全脳イメージングも可能であり,興味のある神経領域のみならず他の領域との関連性を調べることができる。
このように,ゼブラフィッシュを用いた研究は,他の脊椎動物では得られない重要な情報を得られる可能性がある。本稿では,ゼブラフィッシュの小脳発生と機能について哺乳類との比較を交えて概観する。
小脳出力の新フレームワークとしての小脳縦縞構築
著者: 藤田啓史
ページ範囲:P.9 - P.12
小脳は歴史的に運動機能においてよく調べられてきた。一方で,小脳は自律神経機能や大脳の非運動機能など,多彩な機能に関与することが知られている1,2)。近年では,幅広い神経精神症状に関与することも知られている3)。例えば,小脳のプルキンエ細胞のみに異常を持たせた遺伝子改変マウスは,自閉スペクトラム障害様の行動異常を示す4)。更に,自閉スペクトラム障害モデルマウスにおいて小脳を刺激すると,刺激した部位に応じて特定の自閉症様の行動異常が改善される5)。臨床的には,小脳の刺激が統合失調症の陰性症状を改善する6)。これからの小脳研究には,運動機能に限らず,多彩な小脳機能を研究するための小脳神経回路の新たなフレームワークが求められている。
発達期小脳のシナプス刈り込み
著者: 上阪直史
ページ範囲:P.13 - P.17
動物の発達期に脳の神経回路が正確に形成されることで,動物が環境を知覚する,行動する,知性を持つことなどの脳機能が備わる。脳機能の基になる神経回路がどのように形成されるか,その原理を解明することは興味深いテーマであり,発達障害の病態解明・治療法開発ならびに人工知能の開発に貢献する。生まれたばかりの動物の神経回路は未熟であり,動物の機能もほとんど備わっていない。生後発達期に脳の神経回路は精緻化され,脳機能が発現する。この細胞レベルでの変化として,“シナプス刈り込み”と呼ばれる現象がある。シナプス刈り込みにおいて,一部のシナプス(神経細胞同士の結合)が強められて残存し,残りの余剰シナプスは弱められて最終的に除去される1)。この過程は未熟な神経回路を機能的な成熟した神経回路に変化させるために重要であると考えられている2,3)。
発達期小脳の登上線維-プルキンエ細胞シナプスはシナプス刈り込みを研究するのに適したモデルである4)。成体におけるプルキンエ細胞は平行線維と登上線維の2つの異なる興奮性シナプス入力を受ける5,6)。平行線維は小脳顆粒細胞の軸索で,各平行線維は1つまたは2つのシナプスをプルキンエ細胞樹状突起のスパイン上に形成している。個々のシナプスの入力は弱いが,約10万本以上の平行線維が個々のプルキンエ細胞にシナプス結合している。対照的に,成体のほとんどのプルキンエ細胞は,単一の登上線維から強いシナプス入力を受けている(単一支配)(図1)。各登上線維はプルキンエ細胞の近位樹状突起上に数百個の機能的に強いシナプスを形成している。しかし,生まれてしばらくは,すべてのプルキンエ細胞は複数の登上線維からのシナプス入力を受ける(多重支配)。
Ⅱ.シナプス・神経回路
小脳への感覚信号の伝達経路
著者: 久保怜香 , 橋本浩一
ページ範囲:P.18 - P.22
体性感覚刺激が延髄下オリーブ核を介して小脳のプルキンエ細胞に伝達されることはよく知られている。しかし,その伝達経路についてはいまだ不明な点が多い。本稿では,マウス口辺ヒゲ領域から小脳Crus Ⅱプルキンエ細胞への下オリーブ核を介した感覚情報伝達に着目し,その伝達経路について最近の筆者らの研究を含め概説する。
小脳皮質からの主要な出力を担うプルキンエ細胞には,顆粒細胞から平行線維を介する入力と,延髄下オリーブ核から登上線維を介する入力の2種類の主要な興奮性入力がある。このなかで下オリーブ核から登上線維を介する入力は,ほとんどの場合1個のプルキンエ細胞に対し1本しか入力していないが,プルキンエ細胞の近位樹状突起に絡みつくように多数のシナプスを形成するため,1回の活動で非常に大きな興奮性シナプス後電位を発生する。このため通常の状態では,登上線維のシナプス伝達により,必ずプルキンエ細胞に最初の活動電位に引き続き複数の小さな活動電位が連なるcomplex spike(CS)と呼ばれる活動電位が発生する(図1A,D)。このシナプス伝達は,同時に電位依存性Ca2+チャネルを活性化して樹状突起全体に細胞内Ca2+上昇を引き起こし,長期抑圧などのシナプス可塑性の誘導に関与する。
小脳LTD/LTP—小脳学習を支えるシナプス可塑性
著者: 掛川渉 , 柚﨑通介
ページ範囲:P.23 - P.29
小脳神経回路の要衝を担う顆粒細胞軸索平行線維-プルキンエ細胞間シナプス(平行線維シナプス;図1A)は,神経活動に応じてその形態や機能を柔軟に変化させる。この現象は“シナプス可塑性(synaptic plasticity)”と呼ばれ,Marr,Albus,伊藤らによる小脳学習理論(Marr-Albus-Ito理論)が提唱された1970年代以降,運動記憶・学習の分子基盤として世界中で注目されてきた1)。その間,培養神経細胞標本や急性脳切片を用いた電気生理学的手法と遺伝子改変動物作製技術の飛躍的な進歩により,シナプス可塑性を担う数多くの分子が同定された。本稿では,平行線維シナプスで生じる2つの代表的なシナプス可塑性:長期抑圧(long-term depression;小脳LTD)および長期増強(long-term potentiation;小脳LTP)の分子機構と生理的役割について,筆者らの最近の研究成果を含めて概説する。
プルキンエ細胞興奮性の可塑性
著者: 大槻元 , 山脇優輝 , 谷垣宏亮
ページ範囲:P.30 - P.35
可塑性は,刺激や活動に対して応答が変化する脳・神経系の特性である。神経細胞の可塑性は,脳・神経系のあらゆる部位で発現し得る。シナプス伝達効率やシナプス構造の変化にとどまらず,神経細胞の活動電位発火や樹状突起での膜興奮性,電気シナプスなど,活動依存的な神経細胞の応答様式変化の発見は数多ある。本稿では,小脳皮質での神経細胞の膜興奮特性の可塑性に関する研究を中心に紹介する。小脳における興奮性の可塑性の発見,誘導機序と双方向性,樹状突起の興奮性変化,そして,シナプス電流伝導の選択的制御など,21世紀に入って見いだされた新しい小脳可塑性の役割を紹介したい。
小脳神経回路のシナプス特性
著者: 川口真也
ページ範囲:P.36 - P.40
神経細胞の軸索起始部で発生した活動電位は,終末に至るとCa2+を流入させて伝達物質を放出させ,別の細胞と接続するシナプスで情報が伝達される。活動電位が高速で軸索を伝導することと,活動電位の到達からわずか1msで伝達物質を放出できることが,神経系の高い情報処理能力の基礎となる。シナプス伝達のしくみについて,様々な標本でパッチクランプ法を用いた機能解析により知見が蓄積してきた。一方で,こうした理解は多くの場合,シナプス後部の応答から推定されたもので,軸索から終末に至る活動電位の伝導やシナプス前部での開口放出の動態などについて,不明点も多く残っている。これは,シナプスが通常1μm程度しかない微小構造であるため,シナプスの高速動態を直接実験的に記録することが難しいことに起因する。ところが,近年の計測技術の発達により,軸索終末からのパッチクランプ記録や蛍光イメージングによるシナプス小胞動態の直接的な解析が可能になってきた。特に小脳神経回路については構成するシナプスのほとんどから直接記録が報告され,シナプスの機能を規定するパラメータの詳細がわかりつつある。
本稿では,その小脳神経回路シナプスに焦点を当てて最近の知見を概説し,動物の運動を調節する小脳回路での情報の流れとシナプスの機能設計の合目的性について考察したい。
Ⅲ.システム・運動制御
大脳小脳連関と運動制御
著者: 田中康裕
ページ範囲:P.41 - P.45
小脳は神経回路の概要が早くからわかり,原理を当てはめて機能を慮り,それを実証する発見がなされるなど理想的ともいえる研究が展開された1-5)。本稿では筆者らの最近の研究6)に触れつつ,大脳小脳連関および大脳基底核と小脳の皮質下での連関をまとめ,運動制御における小脳内部モデルの働きなどを概説する。また,運動開始時にみられる大脳皮質の準備活動に小脳が重要であるという近年の齧歯類研究を取り上げる。最後に,脳にみられるモジュール性と関連づけて,多領域多細胞の神経活動と多次元の動物行動から探る神経科学の必要性を説きたい。なお,筆者らの最近の研究6)に関しては,本誌既刊の解説7)もあるため,参考にしていただきたい。
小脳と時間的差分(TD)学習
著者: 大前彰吾 , 大前景子
ページ範囲:P.46 - P.51
[概要]小脳のプルキンエ細胞への登上線維(climbing fiber;CF)からの入力信号は,小脳の学習を引き起こす教師信号である。筆者らは,瞬目条件づけの前後でマウスのCF信号に含まれる情報を調べた。従来の通説どおり,CF信号は思わぬ嫌悪刺激に対する事後の予測誤差を伝えていた。加えて,マウスが嫌悪刺激の予測を学習し終えたとき,嫌悪刺激の到来を事前に警告する信号がCFで伝えられるという驚くべき発見をした。この信号パターンは,ドーパミン信号と同様に,時間的差分学習(temporal difference learning;TD学習)における学習信号の特性を備えており,小脳がTD学習をできる可能性を示した。更に,この事前の警告信号を生成している回路を探索し,それに小脳自体が関与していることを明らかにした。これは,小脳への教師信号の生成を小脳自身が担っているという大変興味深い事実を示唆している。
小脳の縞状構造と高次機能
著者: 堤新一郎
ページ範囲:P.52 - P.56
小脳は従来精密な運動制御に関わっていると考えられていたが,近年,運動準備やタイミング予測,報酬情報処理などの高次機能における役割に注目が集まっている。小脳の神経回路は,大脳と比して少ない細胞種による均一な繰り返し構造を特徴とするが,集団としての機能は頭尾方向の縦縞上に構造化されていることが知られている。この小脳縞状構造の研究の歴史と,近年注目されている高次機能との関連についてまとめる。
サッケード適応と小脳
著者: 小島奉子
ページ範囲:P.57 - P.61
サッケードは視線を見たいものに移す眼球運動である。普段の生活で自分が目を動かしていることを意識することは滅多にないが,サッケードは霊長類が日々行う運動のなかで,最も多く速く正確な運動である。この正確な運動を,脳はどのように制御し維持しているのか。それには,伊藤正男先生によって証明された小脳の理論が重要な役割を果たしていることがわかってきた。本稿では,その神経メカニズムを解説する。
Ⅳ.病態
脊髄小脳変性症の病態生理
著者: 石川欽也
ページ範囲:P.62 - P.68
脊髄小脳変性症とは,小脳と,それに関係する脳の系統が緩徐に障害される神経疾患の総称である。小脳の機能とその破綻を俯瞰する本特集のなかで,本稿では特に頻度が高く,病態がわかってきた幾つかの疾患について概説する。
遺伝子改変疾患マウスと小脳異常
著者: 細井延武 , 平井宏和
ページ範囲:P.69 - P.73
医学研究において,疾患の状態を作り出すことはたいへん重要であり,実験動物(例えばマウス)を用いて研究を開始する際の最初の実験操作となる。その最初の操作には,圧迫,損傷,熱操作(高温・低温への曝露)などの機械的・物理的な操作や,薬物の投与などの化学物質による操作などが挙げられるが,近年では,生命の設計図である遺伝子を直接操作して,生体内に異常な状態を作り出し疾患を引き起こすことで,その疾患の原因と詳細なメカニズムを探る研究手法が一般的となっている。研究対象としたい疾患の原因となる遺伝子の変異が既にわかっている場合には,研究開始時にどのような遺伝子操作をするべきかが明確であるが,その疾患の遺伝的原因やメカニズムが全く不明な場合,ある遺伝子操作によって“偶然”疾患の状態になった場合をその研究の出発点とするしかない。
当研究室では,今まで遺伝子改変技術による疾患マウスを用いてその疾患のメカニズムを明らかにする研究を行ってきた。本稿では,ある遺伝子改変によって期せずして“偶然”作出できた疾患マウスを詳細に調べることにより,振戦(体の震え)のメカニズムに迫ることができた研究成果の例1)と,遺伝的原因が同定されているものの,生体内での機能的異常が不明であった指定難病の小脳失調疾患の細胞内メカニズムを解明し,既承認薬を用いた新規治療法の可能性を指摘できた研究例2)について,研究現場の率直でリアルな視点から紹介したい。
自閉スペクトラム症と小脳
著者: 石田綾
ページ範囲:P.74 - P.77
自閉スペクトラム症(autism spectrum disorder;ASD)は,コミュニケーションの障害,繰り返す行動と,限定的な興味を特徴とする発達障害である。ASDには遺伝的要因が強く関係し,多くの関連遺伝子が同定されている。各遺伝子の機能解析が進む一方で,脳のどの領域のどのような異常がASDの中核症状につながるのかについては,未解明な点が多い。このなかで,運動制御を担う小脳がASDにも関与する可能性が報告され,注目を集めている。また,近年は小脳が高次機能にも関与することが認知され,小脳がASDのみでなく様々な精神神経疾患に関与する可能性も議論されている。本稿では,小脳が高次機能に及ぼす影響について概説し,ASDと小脳の関係についてモデルマウスを用いた最近の研究動向をまとめる。
小脳を知る・守る・創るの融合から見える内部モデル仮説の先
著者: 本多武尊
ページ範囲:P.78 - P.83
伊藤正男博士は,脳科学研究推進計画のなかで,脳を“知る”,“守る”,“創る”をテーマに脳科学総合研究センターをつくり,日本における脳科学のフロンティアの場として未来への発展を描いた1)。その未来へのトピックスは“こころ”であった。今なお未開拓なフロンティアであるが,1963年にノーベル生理学・医学賞を授与されたJohn Carew Ecclesの墓参りに伊藤博士と同行した際に,Helena Eccles夫人とPiergiorgio Starata博士,伊藤博士による,現在の脳科学よりも熱い“こころと脳の議論”を目にすることができたことは良い機会であった2)。脳科学を牽引してきた小脳研究は“知る”,“守る”,“創る”を発展させ,未来に向かって“こころ”に迫れるのかについて挑戦する。
仮説と戦略
哺乳類における中枢性の老化・寿命制御機序—健康寿命の延伸と病のない余生を考える フリーアクセス
著者: 佐藤亜希子
ページ範囲:P.84 - P.90
日本は,1970年に高齢化社会[人口に占める高齢者(65歳以上の人)の割合が7%を超えている状態]となり,1994年からは高齢社会(人口に占める高齢者の割合が14%),そして2007年からは,ついに超高齢社会(人口に占める高齢者の割合が21%)となっている。老化現象は一見複雑ではあるが,細胞から個体レベルまでを系統立てて老化・寿命制御機序を明らかにしていくことで,老化疾患に対する新規の予防,治療,そして診断法の創出につながり,人々へより健やかな生活をもたらしてくれることが期待される。
本稿ではまず,寿命推移から日本の超高齢社会とそのなかで挙げられる課題について述べる。次に,老化の遺伝的素因となり得る老化・寿命制御因子を紹介し,更に,これまでの報告から,哺乳類の老化・寿命を制御するうえで,脳,特に視床下部が持つ機能的重要性をまとめ,最後に,老化の予防と治療を目指した介入法について考察したい。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1 - P.1
次号予告/財団だより フリーアクセス
ページ範囲:P.91 - P.91
あとがき フリーアクセス
著者: 岡本仁
ページ範囲:P.92 - P.92
本誌『生体の科学』の生みの親である伊藤正男先生が逝去されてから2年になる。それから遡ること半世紀の1967年に伊藤先生は,John Eccles,János Szentágothaiと共著で,“The Cerebellum as a Neuronal Machine(神経機械としての小脳)”を出版され,小脳の神経回路が高度に秩序立っており,計算機としての機能を持っているに違いないと唱えられた。その後,実験的生理学と計算論を総動員した脳科学を実践する道を歩まれ,世界の研究者を先導された。本特集号では,狩野先生と喜多村先生のご尽力によって,伊藤先生の蒔かれた小脳研究の種が,その後多様性に富む豊かな森へと発展した様を,新進気鋭の研究者として世界中の第一線で活躍されている方々を執筆者にお招きすることによって,お伝えできた。更に「仮説と戦略」では,最近急速に発展している中枢性の老化・寿命制御機序の研究の現状を,佐藤先生が極めて簡潔・明瞭にまとめてくださり,今後の研究への指針を示していただいた。執筆者の諸先生方には深く感謝いたします。
基本情報
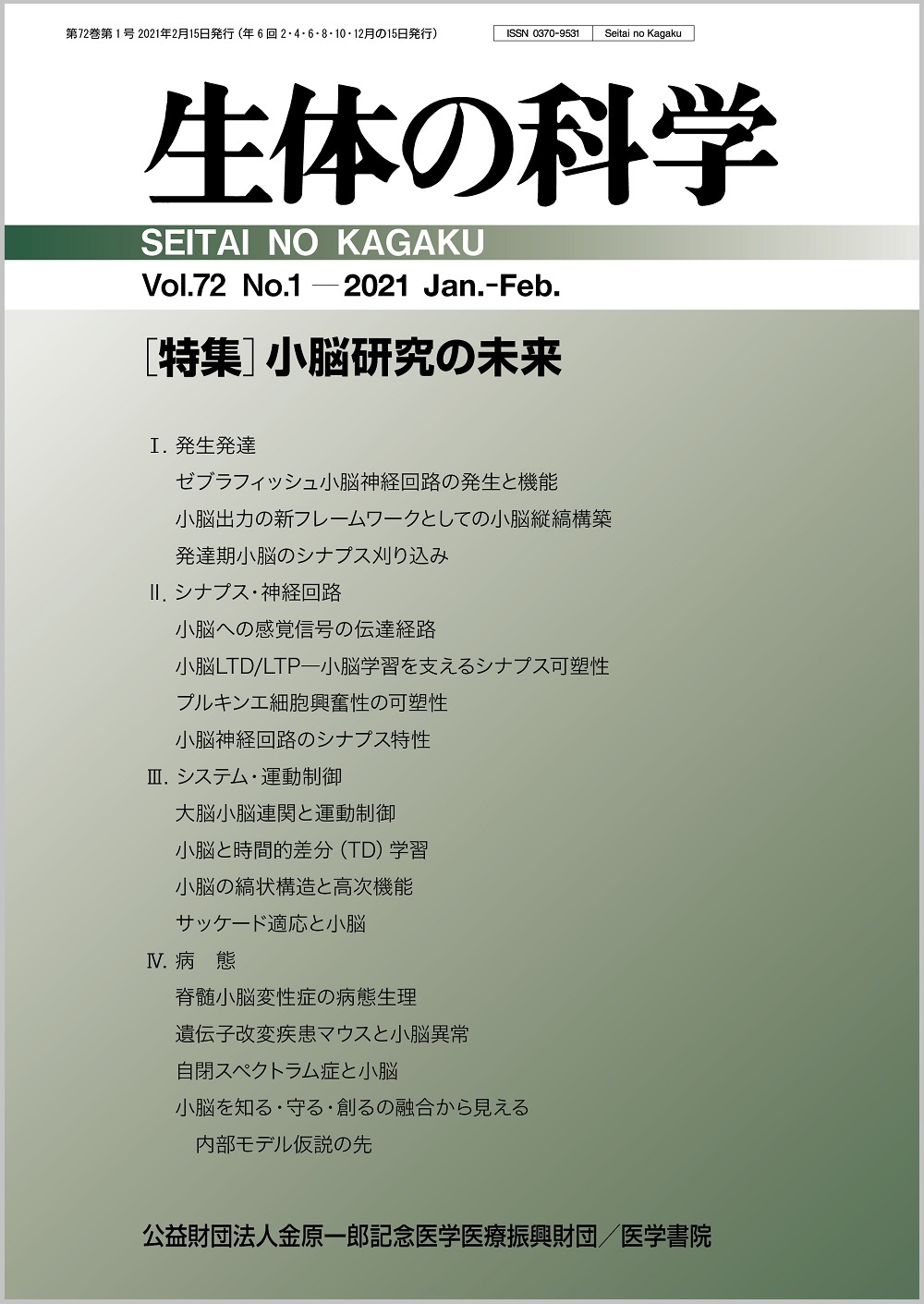
バックナンバー
75巻6号(2024年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅤ:脂肪
75巻5号(2024年10月発行)
増大特集 学術研究支援の最先端
75巻4号(2024年8月発行)
特集 シングルセルオミクス
75巻3号(2024年6月発行)
特集 高速分子動画:動的構造からタンパク質分子制御へ
75巻2号(2024年4月発行)
特集 生命現象を駆動する生体内金属動態の理解と展開
75巻1号(2024年2月発行)
特集 脳と個性
74巻6号(2023年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅣ:骨・軟骨
74巻5号(2023年10月発行)
増大特集 代謝
74巻4号(2023年8月発行)
特集 がん遺伝子の発見は現代医療を進歩させたか
74巻3号(2023年6月発行)
特集 クロマチンによる転写制御機構の最前線
74巻2号(2023年4月発行)
特集 未病の科学
74巻1号(2023年2月発行)
特集 シナプス
73巻6号(2022年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅢ:血管とリンパ管
73巻5号(2022年10月発行)
増大特集 革新脳と関連プロジェクトから見えてきた新しい脳科学
73巻4号(2022年8月発行)
特集 形態形成の統合的理解
73巻3号(2022年6月発行)
特集 リソソーム研究の新展開
73巻2号(2022年4月発行)
特集 DNA修復による生体恒常性の維持
73巻1号(2022年2月発行)
特集 意識
72巻6号(2021年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅡ:骨格筋—今後の研究の発展に向けて
72巻5号(2021年10月発行)
増大特集 脳とからだ
72巻4号(2021年8月発行)
特集 グローバル時代の新興再興感染症への科学的アプローチ
72巻3号(2021年6月発行)
特集 生物物理学の進歩—生命現象の定量的理解へ向けて
72巻2号(2021年4月発行)
特集 組織幹細胞の共通性と特殊性
72巻1号(2021年2月発行)
特集 小脳研究の未来
71巻6号(2020年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅠ:最新の皮膚科学
71巻5号(2020年10月発行)
増大特集 難病研究の進歩
71巻4号(2020年8月発行)
特集 細胞機能の構造生物学
71巻3号(2020年6月発行)
特集 スポーツ科学—2020オリンピック・パラリンピックによせて
71巻2号(2020年4月発行)
特集 ビッグデータ時代のゲノム医学
71巻1号(2020年2月発行)
特集 睡眠の制御と機能
70巻6号(2019年12月発行)
特集 科学と芸術の接点
70巻5号(2019年10月発行)
増大特集 現代医学・生物学の先駆者たち
70巻4号(2019年8月発行)
特集 メカノバイオロジー
70巻3号(2019年6月発行)
特集 免疫チェックポイント分子による生体機能制御
70巻2号(2019年4月発行)
特集 免疫系を介したシステム連関:恒常性の維持と破綻
70巻1号(2019年2月発行)
特集 脳神経回路のダイナミクスから探る脳の発達・疾患・老化
69巻6号(2018年12月発行)
特集 細胞高次機能をつかさどるオルガネラコミュニケーション
69巻5号(2018年10月発行)
増大特集 タンパク質・核酸の分子修飾
69巻4号(2018年8月発行)
特集 いかに創薬を進めるか
69巻3号(2018年6月発行)
特集 生体膜のバイオロジー
69巻2号(2018年4月発行)
特集 宇宙の極限環境から生命体の可塑性をさぐる
69巻1号(2018年2月発行)
特集 社会性と脳
68巻6号(2017年12月発行)
特集 心臓の発生・再生・創生
68巻5号(2017年10月発行)
増大特集 細胞多様性解明に資する光技術─見て,動かす
68巻4号(2017年8月発行)
特集 血管制御系と疾患
68巻3号(2017年6月発行)
特集 核内イベントの時空間制御
68巻2号(2017年4月発行)
特集 細菌叢解析の光と影
68巻1号(2017年2月発行)
特集 大脳皮質—成り立ちから機能へ
67巻6号(2016年12月発行)
特集 時間生物学の新展開
67巻5号(2016年10月発行)
増大特集 病態バイオマーカーの“いま”
67巻4号(2016年8月発行)
特集 認知症・神経変性疾患の克服への挑戦
67巻3号(2016年6月発行)
特集 脂質ワールド
67巻2号(2016年4月発行)
特集 細胞の社会学─細胞間で繰り広げられる協調と競争
67巻1号(2016年2月発行)
特集 記憶ふたたび
66巻6号(2015年12月発行)
特集 グリア研究の最先端
66巻5号(2015年10月発行)
増大特集 細胞シグナル操作法
66巻4号(2015年8月発行)
特集 新興・再興感染症と感染症対策
66巻3号(2015年6月発行)
特集 進化と発生からみた生命科学
66巻2号(2015年4月発行)
特集 使える最新ケミカルバイオロジー
66巻1号(2015年2月発行)
特集 脳と心の謎はどこまで解けたか
65巻6号(2014年12月発行)
特集 エピジェネティクスの今
65巻5号(2014年10月発行)
増大特集 生命動態システム科学
65巻4号(2014年8月発行)
特集 古典的代謝経路の新しい側面
65巻3号(2014年6月発行)
特集 器官の発生と再生の基礎
65巻2号(2014年4月発行)
特集 細胞の少数性と多様性に挑む―シングルセルアナリシス
65巻1号(2014年2月発行)
特集 精神疾患の病理機構
64巻6号(2013年12月発行)
特集 顕微鏡で物を見ることの新しい動き
64巻5号(2013年10月発行)
増大特集 細胞表面受容体
64巻4号(2013年8月発行)
特集 予測と意思決定の神経科学
64巻3号(2013年6月発行)
特集 細胞接着の制御
64巻2号(2013年4月発行)
特集 特殊な幹細胞としての骨格筋サテライト細胞
64巻1号(2013年2月発行)
特集 神経回路の計測と操作
63巻6号(2012年12月発行)
特集 リンパ管
63巻5号(2012年10月発行)
特集 細胞の分子構造と機能―核以外の細胞小器官
63巻4号(2012年8月発行)
特集 質感脳情報学への展望
63巻3号(2012年6月発行)
特集 細胞極性の制御
63巻2号(2012年4月発行)
特集 RNA干渉の実現化に向けて
63巻1号(2012年2月発行)
特集 小脳研究の課題(2)
62巻6号(2011年12月発行)
特集 コピー数変異
62巻5号(2011年10月発行)
特集 細胞核―構造と機能
62巻4号(2011年8月発行)
特集 小脳研究の課題
62巻3号(2011年6月発行)
特集 インフラマソーム
62巻2号(2011年4月発行)
特集 筋ジストロフィーの分子病態から治療へ
62巻1号(2011年2月発行)
特集 摂食制御の分子過程
61巻6号(2010年12月発行)
特集 細胞死か腫瘍化かの選択
61巻5号(2010年10月発行)
特集 シナプスをめぐるシグナリング
61巻4号(2010年8月発行)
特集 miRNA研究の最近の進歩
61巻3号(2010年6月発行)
特集 SNARE複合体-膜融合の機構
61巻2号(2010年4月発行)
特集 糖鎖のかかわる病気:発症機構,診断,治療に向けて
61巻1号(2010年2月発行)
特集 脳科学のモデル実験動物
60巻6号(2009年12月発行)
特集 ユビキチン化による生体機能の調節
60巻5号(2009年10月発行)
特集 伝達物質と受容体
60巻4号(2009年8月発行)
特集 睡眠と脳回路の可塑性
60巻3号(2009年6月発行)
特集 脳と糖脂質
60巻2号(2009年4月発行)
特集 感染症の現代的課題
60巻1号(2009年2月発行)
特集 遺伝子-脳回路-行動
59巻6号(2008年12月発行)
特集 mTORをめぐるシグナルタンパク
59巻5号(2008年10月発行)
特集 現代医学・生物学の仮説・学説2008
59巻4号(2008年8月発行)
特集 免疫学の最近の動向
59巻3号(2008年6月発行)
特集 アディポゲネシス
59巻2号(2008年4月発行)
特集 細胞外基質-研究の新たな展開
59巻1号(2008年2月発行)
特集 コンピュータと脳
58巻6号(2007年12月発行)
特集 グリケーション(糖化)
58巻5号(2007年10月発行)
特集 タンパク質間相互作用
58巻4号(2007年8月発行)
特集 嗅覚受容の分子メカニズム
58巻3号(2007年6月発行)
特集 骨の形成と破壊
58巻2号(2007年4月発行)
特集 シナプス後部構造の形成・機構と制御
58巻1号(2007年2月発行)
特集 意識―脳科学からのアプローチ
57巻6号(2006年12月発行)
特集 血管壁
57巻5号(2006年10月発行)
特集 生物進化の分子マップ
57巻4号(2006年8月発行)
特集 脳科学が求める先端技術
57巻3号(2006年6月発行)
特集 ミエリン化の機構とその異常
57巻2号(2006年4月発行)
特集 膜リサイクリング
57巻1号(2006年2月発行)
特集 こころと脳:とらえがたいものを科学する
56巻6号(2005年12月発行)
特集 構造生物学の現在と今後の展開
56巻5号(2005年10月発行)
特集 タンパク・遺伝子からみた分子病―新しく解明されたメカニズム
56巻4号(2005年8月発行)
特集 脳の遺伝子―どこでどのように働いているのか
56巻3号(2005年6月発行)
特集 Naチャネル
56巻2号(2005年4月発行)
特集 味覚のメカニズムに迫る
56巻1号(2005年2月発行)
特集 情動―喜びと恐れの脳の仕組み
55巻6号(2004年12月発行)
特集 脳の深部を探る
55巻5号(2004年10月発行)
特集 生命科学のNew Key Word
55巻4号(2004年8月発行)
特集 心筋研究の最前線
55巻3号(2004年6月発行)
特集 分子進化学の現在
55巻2号(2004年4月発行)
特集 アダプタータンパク
55巻1号(2004年2月発行)
特集 ニューロンと脳
54巻6号(2003年12月発行)
特集 オートファジー
54巻5号(2003年10月発行)
特集 創薬ゲノミクス・創薬プロテオミクス・創薬インフォマティクス
54巻4号(2003年8月発行)
特集 ラフトと細胞機能
54巻3号(2003年6月発行)
特集 クロマチン
54巻2号(2003年4月発行)
特集 樹状突起
54巻1号(2003年2月発行)
53巻6号(2002年12月発行)
特集 ゲノム全解読とポストゲノムの問題点
53巻5号(2002年10月発行)
特集 加齢の克服―21世紀の課題
53巻4号(2002年8月発行)
特集 一価イオンチャネル
53巻3号(2002年6月発行)
特集 細胞質分裂
53巻2号(2002年4月発行)
特集 RNA
53巻1号(2002年2月発行)
連続座談会 脳とこころ―21世紀の課題
52巻6号(2001年12月発行)
特集 血液脳関門研究の最近の進歩
52巻5号(2001年10月発行)
特集 モチーフ・ドメインリスト
52巻4号(2001年8月発行)
特集 骨格筋研究の新展開
52巻3号(2001年6月発行)
特集 脳の発達に関与する分子機構
52巻2号(2001年4月発行)
特集 情報伝達物質としてのATP
52巻1号(2001年2月発行)
連続座談会 脳を育む
51巻6号(2000年12月発行)
特集 機械的刺激受容の分子機構と細胞応答
51巻5号(2000年10月発行)
特集 ノックアウトマウスリスト
51巻4号(2000年8月発行)
特集 臓器(組織)とアポトーシス
51巻3号(2000年6月発行)
特集 自然免疫における異物認識と排除の分子機構
51巻2号(2000年4月発行)
特集 細胞極性の形成機序
51巻1号(2000年2月発行)
特集 脳を守る21世紀生命科学の展望
50巻6号(1999年12月発行)
特集 細胞内輸送
50巻5号(1999年10月発行)
特集 病気の分子細胞生物学
50巻4号(1999年8月発行)
特集 トランスポーターの構造と機能協関
50巻3号(1999年6月発行)
特集 時間生物学の新たな展開
50巻2号(1999年4月発行)
特集 リソソーム:最近の研究
50巻1号(1999年2月発行)
連続座談会 脳を守る
49巻6号(1998年12月発行)
特集 発生・分化とホメオボックス遺伝子
49巻5号(1998年10月発行)
特集 神経系に作用する薬物マニュアル1998
49巻4号(1998年8月発行)
特集 プロテインキナーゼCの多様な機能
49巻3号(1998年6月発行)
特集 幹細胞研究の新展開
49巻2号(1998年4月発行)
特集 血管―新しい観点から
49巻1号(1998年2月発行)
特集 言語の脳科学
48巻6号(1997年12月発行)
特集 軸索誘導
48巻5号(1997年10月発行)
特集 受容体1997
48巻4号(1997年8月発行)
特集 マトリックス生物学の最前線
48巻3号(1997年6月発行)
特集 開口分泌のメカニズムにおける新しい展開
48巻2号(1997年4月発行)
特集 最近のMAPキナーゼ系
48巻1号(1997年2月発行)
特集 21世紀の脳科学
47巻6号(1996年12月発行)
特集 老化
47巻5号(1996年10月発行)
特集 器官―その新しい視点
47巻4号(1996年8月発行)
特集 エンドサイトーシス
47巻3号(1996年6月発行)
特集 細胞分化
47巻2号(1996年4月発行)
特集 カルシウム動態と細胞機能
47巻1号(1996年2月発行)
特集 神経科学の最前線
46巻6号(1995年12月発行)
特集 病態を変えたよく効く医薬
46巻5号(1995年10月発行)
特集 遺伝子・タンパク質のファミリー・スーパーファミリー
46巻4号(1995年8月発行)
特集 ストレス蛋白質
46巻3号(1995年6月発行)
特集 ライソゾーム
46巻2号(1995年4月発行)
特集 プロテインホスファターゼ―最近の進歩
46巻1号(1995年2月発行)
特集 神経科学の謎
45巻6号(1994年12月発行)
特集 ミトコンドリア
45巻5号(1994年10月発行)
特集 動物の行動機能テスト―個体レベルと分子レベルを結ぶ
45巻4号(1994年8月発行)
特集 造血の機構
45巻3号(1994年6月発行)
特集 染色体
45巻2号(1994年4月発行)
特集 脳と分子生物学
45巻1号(1994年2月発行)
特集 グルコーストランスポーター
44巻6号(1993年12月発行)
特集 滑面小胞体をめぐる諸問題
44巻5号(1993年10月発行)
特集 現代医学・生物学の仮説・学説
44巻4号(1993年8月発行)
特集 細胞接着
44巻3号(1993年6月発行)
特集 カルシウムイオンを介した調節機構の新しい問題点
44巻2号(1993年4月発行)
特集 蛋白質の細胞内転送とその異常
44巻1号(1993年2月発行)
座談会 脳と遺伝子
43巻6号(1992年12月発行)
特集 成長因子受容体/最近の進歩
43巻5号(1992年10月発行)
特集 〈研究室で役に立つ細胞株〉
43巻4号(1992年8月発行)
特集 細胞機能とリン酸化
43巻3号(1992年6月発行)
特集 血管新生
43巻2号(1992年4月発行)
特集 大脳皮質発達の化学的側面
43巻1号(1992年2月発行)
特集 意識と脳
42巻6号(1991年12月発行)
特集 細胞活動の日周リズム
42巻5号(1991年10月発行)
特集 神経系に作用する薬物マニュアル
42巻4号(1991年8月発行)
特集 開口分泌の細胞内過程
42巻3号(1991年6月発行)
特集 ペルオキシソーム/最近の進歩
42巻2号(1991年4月発行)
特集 脳の移植と再生
42巻1号(1991年2月発行)
特集 脳と免疫
41巻6号(1990年12月発行)
特集 注目の実験モデル動物
41巻5号(1990年10月発行)
特集 LTPとLTD:その分子機構
41巻4号(1990年8月発行)
特集 New proteins
41巻3号(1990年6月発行)
特集 シナプスの形成と動態
41巻2号(1990年4月発行)
特集 細胞接着
41巻1号(1990年2月発行)
特集 発がんのメカニズム/最近の知見
40巻6号(1989年12月発行)
特集 ギャップ結合
40巻5号(1989年10月発行)
特集 核内蛋白質
40巻4号(1989年8月発行)
特集 研究室で役に立つ新しい試薬
40巻3号(1989年6月発行)
特集 細胞骨格異常
40巻2号(1989年4月発行)
特集 大脳/神経科学からのアプローチ
40巻1号(1989年2月発行)
特集 分子進化
39巻6号(1988年12月発行)
特集 細胞内における蛋白質局在化機構
39巻5号(1988年10月発行)
特集 細胞測定法マニュアル
39巻4号(1988年8月発行)
特集 細胞外マトリックス
39巻3号(1988年6月発行)
特集 肺の微細構造と機能
39巻2号(1988年4月発行)
特集 生体運動の分子機構/研究の発展
39巻1号(1988年2月発行)
特集 遺伝子疾患解析の発展
38巻6号(1987年12月発行)
-チャンネルの最近の動向
38巻5号(1987年10月発行)
特集 細胞生物学における免疫実験マニュアル
38巻4号(1987年8月発行)
特集 視覚初期過程の分子機構
38巻3号(1987年6月発行)
特集 人間の脳
38巻2号(1987年4月発行)
特集 体液カルシウムのホメオスタシス
38巻1号(1987年2月発行)
特集 医学におけるブレイクスルー/基礎研究からの挑戦
37巻6号(1986年12月発行)
特集 神経活性物質受容体と情報伝達
37巻5号(1986年10月発行)
特集 中間径フィラメント
37巻4号(1986年8月発行)
特集 細胞生物学実験マニュアル
37巻3号(1986年6月発行)
特集 脳の化学的トポグラフィー
37巻2号(1986年4月発行)
特集 血小板凝集
37巻1号(1986年2月発行)
特集 脳のモデル
36巻6号(1985年12月発行)
特集 脂肪組織
36巻5号(1985年10月発行)
特集 細胞分裂をめぐって
36巻4号(1985年8月発行)
特集 神経科学実験マニュアル
36巻3号(1985年6月発行)
特集 血管内皮細胞と微小循環
36巻2号(1985年4月発行)
特集 肝細胞と胆汁酸分泌
36巻1号(1985年2月発行)
特集 Transmembrane Control
35巻6号(1984年12月発行)
特集 細胞毒マニュアル—実験に用いられる細胞毒の知識
35巻5号(1984年10月発行)
特集 中枢神経系の再構築
35巻4号(1984年8月発行)
特集 ゲノムの構造
35巻3号(1984年6月発行)
特集 神経科学の仮説
35巻2号(1984年4月発行)
特集 哺乳類の初期発生
35巻1号(1984年2月発行)
特集 細胞生物学の現状と展望
34巻6号(1983年12月発行)
特集 蛋白質の代謝回転
34巻5号(1983年10月発行)
特集 受容・応答の膜分子論
34巻4号(1983年8月発行)
特集 コンピュータによる生物現象の再構成
34巻3号(1983年6月発行)
特集 細胞の極性
34巻2号(1983年4月発行)
特集 モノアミン系
34巻1号(1983年2月発行)
特集 腸管の吸収機構
33巻6号(1982年12月発行)
特集 低栄養と生体機能
33巻5号(1982年10月発行)
特集 成長因子
33巻4号(1982年8月発行)
特集 リン酸化
33巻3号(1982年6月発行)
特集 神経発生の基礎
33巻2号(1982年4月発行)
特集 細胞の寿命と老化
33巻1号(1982年2月発行)
特集 細胞核
32巻6号(1981年12月発行)
特集 筋小胞体研究の進歩
32巻5号(1981年10月発行)
特集 ペプチド作働性シナプス
32巻4号(1981年8月発行)
特集 膜の転送
32巻3号(1981年6月発行)
特集 リポプロテイン
32巻2号(1981年4月発行)
特集 チャネルの概念と実体
32巻1号(1981年2月発行)
特集 細胞骨格
31巻6号(1980年12月発行)
特集 大脳の機能局在
31巻5号(1980年10月発行)
特集 カルシウムイオン受容タンパク
31巻4号(1980年8月発行)
特集 化学浸透共役仮説
31巻3号(1980年6月発行)
特集 赤血球膜の分子構築
31巻2号(1980年4月発行)
特集 免疫系の情報識別
31巻1号(1980年2月発行)
特集 ゴルジ装置
30巻6号(1979年12月発行)
特集 細胞間コミニケーション
30巻5号(1979年10月発行)
特集 In vitro運動系
30巻4号(1979年8月発行)
輸送系の調節
30巻3号(1979年6月発行)
特集 網膜の構造と機能
30巻2号(1979年4月発行)
特集 神経伝達物質の同定
30巻1号(1979年2月発行)
特集 生物物理学の進歩—第6回国際生物物理学会議より
29巻6号(1978年12月発行)
特集 最近の神経科学から
29巻5号(1978年10月発行)
特集 下垂体:前葉
29巻4号(1978年8月発行)
特集 中枢のペプチド
29巻3号(1978年6月発行)
特集 心臓のリズム発生
29巻2号(1978年4月発行)
特集 腎機能
29巻1号(1978年2月発行)
特集 膜脂質の再検討
28巻6号(1977年12月発行)
特集 青斑核
28巻5号(1977年10月発行)
特集 小胞体
28巻4号(1977年8月発行)
特集 微小管の構造と機能
28巻3号(1977年6月発行)
特集 神経回路網と脳機能
28巻2号(1977年4月発行)
特集 生体の修復
28巻1号(1977年2月発行)
特集 生体の科学の現状と動向
27巻6号(1976年12月発行)
特集 松果体
27巻5号(1976年10月発行)
特集 遺伝マウス・ラット
27巻4号(1976年8月発行)
特集 形質発現における制御
27巻3号(1976年6月発行)
特集 生体と化学的環境
27巻2号(1976年4月発行)
特集 分泌腺
27巻1号(1976年2月発行)
特集 光受容
26巻6号(1975年12月発行)
特集 自律神経と平滑筋の再検討
26巻5号(1975年10月発行)
特集 脳のプログラミング
26巻4号(1975年8月発行)
特集 受精機構をめぐつて
26巻3号(1975年6月発行)
特集 細胞表面と免疫
26巻2号(1975年4月発行)
特集 感覚有毛細胞
26巻1号(1975年2月発行)
特集 体内のセンサー
25巻5号(1974年12月発行)
特集 生体膜—その基本的課題
25巻4号(1974年8月発行)
特集 伝達物質と受容物質
25巻3号(1974年6月発行)
特集 脳の高次機能へのアプローチ
25巻2号(1974年4月発行)
特集 筋細胞の分化
25巻1号(1974年2月発行)
特集 生体の科学 展望と夢
24巻6号(1973年12月発行)
24巻5号(1973年10月発行)
24巻4号(1973年8月発行)
24巻3号(1973年6月発行)
24巻2号(1973年4月発行)
24巻1号(1973年2月発行)
23巻6号(1972年12月発行)
23巻5号(1972年10月発行)
23巻4号(1972年8月発行)
23巻3号(1972年6月発行)
23巻2号(1972年4月発行)
23巻1号(1972年2月発行)
22巻6号(1971年12月発行)
22巻5号(1971年10月発行)
22巻4号(1971年8月発行)
22巻3号(1971年6月発行)
22巻2号(1971年4月発行)
22巻1号(1971年2月発行)
21巻7号(1970年12月発行)
21巻6号(1970年10月発行)
21巻4号(1970年8月発行)
特集 代謝と機能
21巻5号(1970年8月発行)
21巻3号(1970年6月発行)
21巻2号(1970年4月発行)
21巻1号(1970年2月発行)
20巻6号(1969年12月発行)
20巻5号(1969年10月発行)
20巻4号(1969年8月発行)
20巻3号(1969年6月発行)
20巻2号(1969年4月発行)
20巻1号(1969年2月発行)
19巻6号(1968年12月発行)
19巻5号(1968年10月発行)
19巻4号(1968年8月発行)
19巻3号(1968年6月発行)
19巻2号(1968年4月発行)
19巻1号(1968年2月発行)
18巻6号(1967年12月発行)
18巻5号(1967年10月発行)
18巻4号(1967年8月発行)
18巻3号(1967年6月発行)
18巻2号(1967年4月発行)
18巻1号(1967年2月発行)
17巻6号(1966年12月発行)
17巻5号(1966年10月発行)
17巻4号(1966年8月発行)
17巻3号(1966年6月発行)
17巻2号(1966年4月発行)
17巻1号(1966年2月発行)
16巻6号(1965年12月発行)
16巻5号(1965年10月発行)
16巻4号(1965年8月発行)
16巻3号(1965年6月発行)
16巻2号(1965年4月発行)
16巻1号(1965年2月発行)
15巻6号(1964年12月発行)
特集 生体膜その3
15巻5号(1964年10月発行)
特集 生体膜その2
15巻4号(1964年8月発行)
特集 生体膜その1
15巻3号(1964年6月発行)
特集 第13回日本生理科学連合シンポジウム
15巻2号(1964年4月発行)
15巻1号(1964年2月発行)
14巻6号(1963年12月発行)
特集 興奮收縮伝関
14巻5号(1963年10月発行)
14巻4号(1963年8月発行)
14巻3号(1963年6月発行)
14巻1号(1963年2月発行)
特集 第9回中枢神経系の生理学シンポジウム
14巻2号(1963年2月発行)
13巻6号(1962年12月発行)
13巻5号(1962年10月発行)
特集 生物々理—生理学生物々理若手グループ第1回ミーティングから
13巻4号(1962年8月発行)
13巻3号(1962年6月発行)
13巻2号(1962年4月発行)
Symposium on Permeability of Biological Membranes
13巻1号(1962年2月発行)
12巻6号(1961年12月発行)
12巻5号(1961年10月発行)
12巻4号(1961年8月発行)
12巻3号(1961年6月発行)
12巻2号(1961年4月発行)
12巻1号(1961年2月発行)
11巻6号(1960年12月発行)
Symposium On Active Transport
11巻5号(1960年10月発行)
11巻4号(1960年8月発行)
11巻3号(1960年6月発行)
11巻2号(1960年4月発行)
11巻1号(1960年2月発行)
10巻6号(1959年12月発行)
10巻5号(1959年10月発行)
10巻4号(1959年8月発行)
10巻3号(1959年6月発行)
10巻2号(1959年4月発行)
10巻1号(1959年2月発行)
8巻6号(1957年12月発行)
8巻5号(1957年10月発行)
特集 酵素と生物
8巻4号(1957年8月発行)
8巻3号(1957年6月発行)
8巻2号(1957年4月発行)
8巻1号(1957年2月発行)
