幹細胞という言葉が科学史上に現れたのは,1968年ドイツの発生生物学者Ernst Haeckelが“Stammzelle”の語を用いたときといわれている。20世紀初め,“幹細胞性”の研究は,主として造血細胞と奇形腫(テラトーマ)を用いて行われた。そして,幹細胞が多分化能と自己複製能を持つ細胞と定義されたのは,1961年のことである。カナダ トロント大学のMcCulloch博士は血液の研究者,Till博士は物理の研究者,この二人がある日,リトリート(研究室を離れての研究者同士の集まり,避難と同時に静養の意味あり)でお互いの仕事の話をしたことから,共同研究が進んだといわれている。研究者は自分の研究に忙しく,あまり他人の仕事に関心を示さないもので,時に隣あって話をする機会は大事なことだ。全身に放射線をかけたマウスに骨髄細胞を移植したところ,マウスは造血を回復した。そのとき,彼らは脾臓に小さな瘤が幾つかできているのを見つけた。この瘤は赤血球や白血球からできており,1つの母細胞が分裂してできた集団だということがわかった。幹細胞を直接見ることはできないものの,増えた何百万個の子孫を見て,母なる細胞を想像し,彼らは謙虚に細胞とは呼ばずに,脾コロニーユニットと呼んだ。のちに,多くの人がこのユニットの実体=幹細胞を見ようと努め,スタンフォード大学のWeissmanのグループは,Herzenbergと協力してFACSによる幹細胞の同定を試みた。造血幹細胞研究に続いて,神経や消化管上皮などで多くの組織幹細胞研究が誕生した。
一方,3胚葉に分化するテラトーマの研究は,始原生殖細胞や内部細胞塊の研究に展開し,1981年にはEvansらによってES細胞が樹立され,2006年には山中伸弥らによってiPS細胞が作製された。これらは組織幹細胞に対して,多能性幹細胞といわれる。現在では,胎児,胎盤の両方に分化し得る全能性幹細胞の研究にまで進展している。
雑誌目次
生体の科学72巻2号
2021年04月発行
雑誌目次
特集 組織幹細胞の共通性と特殊性
特集「組織幹細胞の共通性と特殊性」によせて—幹細胞は,どのように使われているのか? フリーアクセス
著者: 須田年生
ページ範囲:P.94 - P.94
Ⅰ.幹細胞の自律性とニッチ依存性:Q.幹細胞の自己複製能とは何か?
造血幹細胞の自己複製とその制御機構
著者: 森嶋達也 , 滝澤仁
ページ範囲:P.95 - P.99
血液細胞は体内において浮遊細胞として存在し,その幹細胞である造血幹細胞を含む骨髄液も,容易に体外に取り出し分離解析が可能であるという臓器特性により,造血幹細胞は骨髄移植をはじめとした再生医療に古くから用いられて,研究が進んでいる体性幹細胞である。本稿では,前半では造血幹細胞の定常状態における恒常性維持のメカニズムについて最新の知見を紹介しつつ概説する。また,後半ではストレス造血,特に感染などの炎症ストレス下の造血幹細胞の振る舞いについての研究の進歩について紹介する。
精子幹細胞のランダムな挙動からニッチの役割を考える
著者: 吉田松生
ページ範囲:P.100 - P.104
哺乳類の精子形成は幹細胞によって支えられている。本稿では精巣におけるニッチの構築と,そこで繰り広げられる精子幹細胞の振る舞いを概観する。浮かび上がってきたのは,特別なニッチで厳密に非対称分裂を繰り返すという従来のイメージとは違って,精巣の中で気まま(ランダム)に振る舞う幹細胞の姿であった。
上皮幹細胞システムの共通性と特殊性—幹細胞性はどのように規定されるか?
著者: 佐田亜衣子
ページ範囲:P.105 - P.108
われわれの身体の表面を覆う上皮は,外的刺激や感染から生体を守るバリアとして働くほか,水分量や体温の調節,知覚など,生体機能に必須の役割を果たす。上皮は,細胞の入れ替わりがはやく,損傷に対する高度な再生能を持つ組織の一つとして知られ,上皮幹細胞により新たな細胞の産生や損傷修復が担われている。皮膚においては,毛包,毛包間表皮のそれぞれの上皮コンパートメントが固有の性質を持つ幹細胞集団によって維持されている。
本稿では,実態が明らかにされはじめた上皮幹細胞システムの共通性と特殊性について,最新の知見を交えて解説する。
消化管幹細胞の寛容性とニッチによるホメオスタシスの維持
著者: 安田忠仁 , 馬場秀夫 , 石本崇胤
ページ範囲:P.109 - P.112
正常組織幹細胞は自己複製能と多系統の分化細胞への多分化能を有しており,組織・臓器の恒常性は幹細胞を頂点とする階層構造によって維持されている。幹細胞研究の系譜は,造血幹細胞を中心に進展を遂げ,近年それを追随する形で固形臓器,なかでも消化管における幹細胞研究が盛んに行われるようになった。その端緒は,消化管における幹細胞を同定するマーカーとして,Lgr5が報告されたことに由来する。このLgr5陽性細胞は小腸および大腸の陰窩底部に発現し,幹細胞の特徴である多分化能を有した組織の恒常性維持に必須の細胞であることが示唆された。更に,オルガノイド技術の発達を背景として,Lgr5陽性幹細胞を取り巻くニッチの実態解明が進んでいる。特に,間葉系細胞を中心とした微小環境とLgr5陽性幹細胞との相互作用が大きな注目を集めている。
本稿では,消化管幹細胞研究の変遷をたどりながら,各消化管臓器における幹細胞とニッチに関する最新の知見について概説したい。
多能性の遷移とエピジェネティクス
著者: 遠藤充浩 , 丹羽仁史
ページ範囲:P.113 - P.118
初期胚から樹立される胚性幹(ES)細胞は,一定の培養条件下で,分化多能性を保ちつつほぼ無限に自己複製することができる。多能性は,一般的には三胚葉すべてに分化できる能力として規定される。近年,多能性の状態には幅があることがわかり,エピブラスト幹細胞,フォーマティブ幹細胞など,異なる発生段階に相当する多能性幹細胞を樹立・維持することが可能になった。また,次世代シークエンス技術を用いた網羅的な遺伝子発現解析やDNA修飾,ヒストン修飾,クロマチン構造解析の精度が上がったことにより,少数細胞から成る初期胚における解析が広く行われるようになり,これまでに樹立されてきた様々な多能性幹細胞が,胚のどの細胞に相当するかについての知見が蓄積されるようになった。それに伴い,多能性の形質と遺伝子発現・エピゲノム修飾との因果関係についての理解も深まりつつある。
本稿では,多能性状態の遷移とエピジェネティクスの関係について,DNAメチル化とポリコーム群を中心に最近の知見を概説する。
Ⅱ.幹細胞による組織・臓器構築:Q.発生学における幹細胞の位置づけとは?
肝臓における幹細胞システムの特殊性とリプログラミング
著者: 鈴木淳史
ページ範囲:P.119 - P.124
高い再生能を有する肝臓には,古くから幹細胞(肝幹細胞)が存在すると考えられていた。実際,肝臓の発生過程では,自己複製能と多分化能(肝臓を構成する上皮細胞である肝細胞と胆管上皮細胞への二分化能)という幹細胞に特徴的な性質を有する“肝芽細胞”が存在する。また,成体の肝臓においても,慢性的な肝障害によって幹細胞の性質を有する細胞が出現し,肝再生に寄与することがわかっている。しかし,肝幹細胞は造血幹細胞や腸上皮幹細胞などとは異なり,恒常的な組織の維持には関与しないという認識が現在では一般的である。したがって,肝臓において幹細胞の性質を有する細胞は,肝臓の発生過程と慢性的な肝障害による再生過程で一時的に機能する細胞と考えられる。このことから,肝臓には,血液や皮膚,腸管など,幹細胞によって組織恒常性が維持される典型的な幹細胞システムが存在する組織とは一線を画する,肝臓特異的な幹細胞システムが存在するといえる。それゆえ,肝臓において幹細胞の性質を有する細胞については,幹細胞と呼ぶよりもむしろ前駆細胞と呼ぶほうが適切ではないかと考えられ,筆者らも“肝前駆細胞”として扱うこととする。
本稿では,肝臓の発生過程でその組織形成を担う肝前駆細胞について筆者らの研究成果を中心に概説すると共に,肝前駆細胞の運命決定因子の同定と,他種細胞から肝前駆細胞への運命転換誘導に関する研究成果も紹介する。
脳の進化をつかさどる神経幹細胞
著者: 今泉研人 , 岡野栄之
ページ範囲:P.125 - P.129
中枢神経系を構成する細胞は神経幹細胞という単一の幹細胞から発生し,その分化制御のメカニズム研究は,神経発生学や神経再生研究における中心的なテーマの一つである。また,神経幹細胞は,成体におけるニューロン新生に関与することが明らかになってからは,神経機能研究,精神疾患の基盤の理解という観点から研究対象を広げてきた。更にその一方で,脳の進化において神経幹細胞が担う役割が大きく注目され始めている。脳,特に大脳皮質は,進化の過程で霊長類出現以降に大きく増大し,ヒト特異的な高い知能に寄与してきた。この現象は,ゲノム情報の変化に基づく神経幹細胞の種特異的な特性の獲得によることが明らかになりつつある。
本稿では,神経幹細胞の役割を脳進化の側面から考察し,特にヒト特異的な神経幹細胞制御機構を通しての脳進化のメカニズム研究について紹介する。また,従来の動物モデルではアプローチ困難であるヒト特異的神経発生機構の研究の,今後の展開について考察する。
心臓幹細胞—その発生と臨床応用について
著者: 貞廣威太郎 , 家田真樹
ページ範囲:P.130 - P.134
心臓における幹細胞研究は,基礎研究手法の発展により大きなパラダイムシフトを迎えた。系統追跡技術の進歩により,発生過程において多様な細胞集団が時間・空間的に複雑な分化を繰り返し,心臓が形成されることが明らかとなり,シングルセル解析によって,その細胞集団の全貌が解明されはじめている。一方で,これらの技術の進歩は,組織幹細胞としての心臓幹細胞の存在を覆し,基礎研究で得られた知見が,なぜ有効な臨床応用に結びつかなかったかを明らかにした。本稿では,その変遷を幅広い視点から述べていくこととする。
細胞系譜特異的な前駆細胞に基づく腎臓の再構成
著者: 小林明雄 , 西中村隆一
ページ範囲:P.135 - P.140
腎臓は,血液の浄化や生体のイオンバランスの維持に必須な臓器である。腎臓は様々な組織から成り,主にネフロン,集合管,間質から構成される(図1)。腎臓の機能単位であるネフロンは血管と相互作用することで,血液中の老廃物を濾過して取り除き,水分やイオンの受け渡しを行う。ネフロンで産生された血液老廃物や水分・イオンは尿となり,集合管を通じて膀胱へ移動し,更には体外へと排出される。これらネフロンや集合管などの上皮組織は,間質によって囲まれている(図1)。
ヒトの腎臓には約100万個のネフロンが存在しており,ネフロン数と腎機能の間には正なる相関があることが知られている1)。哺乳類において,ネフロンは発生期にのみ産生され,成体で新しくネフロンが作られることはない。よって腎臓内のネフロン数は,生後増加することなく次第に減少し,一定数を下回ると慢性腎臓病(CKD)となる。現在の腎臓病の治療には,主に透析と腎移植が用いられている。しかし,腎臓病患者は生涯にわたり頻繁に透析を受け続けなくてはならず,また,腎移植のための腎臓の提供は極めて限られている。現在,これらの問題の解決策として再生医療が注目されており,多能性幹細胞由来の腎臓オルガノイド作製など様々な研究が行われている。
Ⅲ.多様性を示す幹細胞:Q.分化決定と可変性の関係とは?
既存の血管に存在する血管内皮幹細胞の同定とその生物学的意義
著者: 高倉伸幸
ページ範囲:P.141 - P.145
既存の血管の中には,臓器特異的な血管構造や血管機能を維持し,障害を受けた際には速やかに血管を再構築する血管内皮幹細胞が存在することが判明してきた。血管内皮幹細胞の発生,自己複製,加齢性変化,ニッチなどまだ不明の点が多いが,これらが明らかになることで,血管の再生,アンジオクライン機構を利用した臓器再生など,医学的応用に大いに貢献が期待される細胞であると考えられる。
神経堤—“第4の胚葉”の分化多様性は如何にして獲得されたか?
著者: 栗原裕基
ページ範囲:P.146 - P.150
神経堤(あるいは神経冠)(neural crest)は,脊椎動物の胚発生において神経外胚葉と表皮外胚葉の境界に生ずる幹細胞集団である1)。神経堤細胞は,神経板から神経管が形成される過程で,その辺縁から上皮間葉転換(epithelial to mesenchymal transition;EMT)を経て遊走し,知覚および交感神経細胞やグリア細胞,副腎髄質細胞,色素細胞のほか,頭部では骨,軟骨,歯牙,血管平滑筋など間葉系組織の構成細胞に分化する。神経堤は間葉系細胞への分化の有無により,前後(頭尾)軸に沿って頭部(cranial)神経堤と体幹部(trunk)神経堤の2つの領域に大きく分けられる。ニワトリ胚ではその境界は第3-4体節間に相当する。この境界前後(第1-7体節)と最後尾(第28体節以降)の領域からは腸管神経叢を形成する迷走神経が派生し,それぞれ迷走(vagal)・仙骨(sacral)神経堤として区別されることもある(図1)。神経堤の発生異常は,頭部顔面形成異常やヒルシュスプルング病,先天性中枢性低換気症候群などの先天性疾患を来すことが知られており,神経堤細胞に起源を有する神経芽腫や神経線維腫症などの腫瘍性疾患も含めて,神経堤症(neurocristopathy)と総称されている2)。
間葉系幹細胞の基礎研究と臨床応用
著者: 八尾尚幸 , 新井文用
ページ範囲:P.151 - P.154
1960年代後半に,Friedensteinらにより骨髄中に線維芽細胞様の間葉系前駆細胞が存在することが初めて報告された1)。それらの細胞が骨細胞,軟骨細胞,脂肪細胞などに分化する多分化能を持ち,自己複製することから組織幹細胞であると認識された。この細胞は,その後,Caplanらにより間葉系幹細胞(mesenchymal stem cell;MSC)という呼称が提唱された2)。MSCは間葉系組織のあるすべての臓器に存在していると考えられており,MSCはサイトカインやケモカインなどの液性因子,また,コラーゲンやフィブロネクチンなどの細胞外マトリックスを分泌し,組織内の細胞保護や組織修復,更には組織内の炎症や免疫の制御など様々な役割を持ち,組織の恒常性を維持していると考えられている。MSCは治療に有効な様々な作用を有していることに加え,生体組織から採取可能であるため,受精卵から作製する胚性幹細胞(embryonic stem cell;ES cell)のような倫理的な問題は少なく,遺伝子導入して人工的に作製する人工多能性幹細胞(induced pluripotent stem cell;iPS cell)と比較してがん化の危険性が低く,安全性が高いと考えられている。近年では,MSCを利用した細胞治療が盛んに行われている。本稿ではMSCの生体内での役割,更にMSCを利用した細胞治療について概説する。
ヒト胎盤発生と幹細胞
著者: 柴田峻 , 岡江寛明 , 有馬隆博
ページ範囲:P.155 - P.159
哺乳類において,正常な胎児の発生と発育には機能的な胎盤が必須である。胎盤は,胎児の“呼吸器”“消化器”“内分泌器”として多彩な機能を発揮する臓器である。また,その異常は,流産,胎児発育不全,妊娠高血圧症をはじめとする妊娠合併症を引き起こす原因となる。
本稿では,ヒト胎盤の発生機序について概説し,ヒト胎盤幹(TS)細胞の未分化維持と細胞分化について,最新の知見を基に紹介する。
Ⅳ.幹細胞のクローン性増殖とAging:Q.幹細胞のLife Cycle
クローン解析で見えてきた造血幹細胞の加齢性変化
著者: 山下真幸 , 岩間厚志
ページ範囲:P.160 - P.165
造血幹細胞は自己複製と多分化能を併せ持ち,すべての系統の血液細胞を長期にわたって産生することのできる造血系で唯一の細胞集団である。しかし,造血幹細胞の自己複製には限界があり,加齢と共に造血幹細胞の機能が失われる結果,貧血や免疫異常など,血液ホメオスタシス破綻を生じてしまう。したがって,造血老化を食い止めるためには,造血幹細胞の加齢性変化を理解し,それに基づいて造血幹細胞の機能低下を防止することが重要となる。最近のクローン解析技術の進歩により,発生過程で生じた個々の造血幹細胞クローンは機能的に不均一であることが明らかとなり,機能の偏った造血幹細胞のクローン拡大が造血老化の本質と考えられるようになってきた。ヒトにおいては,加齢と共にゲノム異常を持った白血球が末梢で長期間にわたって検出される,いわゆるクローン性造血の存在が明らかにされ,白血病などの造血器腫瘍が発症する素地として,また心筋梗塞や脳卒中といった心血管系疾患の重要なリスク因子として注目されている。
そこで本稿では,発生期から老年期に至るまでの造血幹細胞のクローン性変化に着目し,加齢に伴って生じる造血幹細胞の機能低下とクローン性造血発生のメカニズムについて最新の動向を交えながら考察する。
幹細胞競合と皮膚の再生老化
著者: 松村寛行 , 劉楠 , 西村栄美
ページ範囲:P.166 - P.171
臓器の老化のメカニズムについては,古くから諸説提唱されてきた1-3)。皮膚においては加齢に加えて,紫外線やタバコなどの環境因子の関与が大きいことが知られていることに加え,活性酸素,代謝,ゲノム不安定性,エピゲノム変化など“hallmarks of aging”として知られる因子や現象が老化全般に関わるとされている3)。しかし,損傷やストレスを受けた細胞が生体内でどのような運命や動態を示すのか,多くの組織や臓器においていまだほとんど明らかにされていない。老人性の白毛症(白髪)や脱毛症は加齢と共に発症する典型的な老化形質である。筆者らはこれまでに哺乳類の毛包が老化するしくみを研究し,ステムセルエイジング(幹細胞老化)が毛包という小器官の老化を決定的なものとしていることを明らかにしている。マウスやヒトにおいて,加齢または種々のストレス負荷によって,色素幹細胞の枯渇から色素細胞が不足し白髪を発症すること4)に加え,毛包幹細胞の枯渇によって毛包が矮小化(ミニチュア化)して毛髪が細く短く疎になることも明らかにしてきた5)。つまり,器官再生の要である組織幹細胞が老化においても鍵を握っており,ステムセルエイジングが器官老化の決め手となり得ることを明らかにした。一方,皮膚は個体と外界との境界に位置し,外界からの様々なストレスや損傷などに曝されているが,その活発な新陳代謝によってあらたに生まれ変わり続けており,個体を外界から守っている。生涯にわたって表皮幹細胞の疲弊を防いでいることが想定されるが,個々の幹細胞の運命や動態についてはほとんど明らかにされていなかった。
“細胞競合”とは,適応度の異なる同種細胞が近接した際に,適応度の高い細胞が低い細胞を排除する現象をいう。1975年にMorataらによってショウジョウバエの発生期の翅において,野生型細胞とリボソームタンパク質遺伝子の変異細胞が混在した際にのみ変異細胞が排除される現象が報告され,その基本的な概念が提唱された(図1A)6,7)。近年,哺乳類のイヌの上皮細胞(MDCK細胞)8)やマウスの腸管細胞9)などにおいても観察され,遺伝子変異を獲得したがん前駆細胞を排除するなど,細胞集団を最適化する機構としても注目を集め始めている。皮膚や腸管など上皮系の組織幹細胞システムにおいても,造血幹細胞と類似して上皮系幹細胞クローンのサイズの増大とクローン数の減少が知られるようになった。当時は確率論的に引き起こされるとしてニュートラルな(中立的)幹細胞競合であろうとみなされ,そこに適応度の違いに基づく細胞競合が起こっているかどうかは明らかではなかった(図1B)10,11)。一方,Toressらは,マウスの初期胚のエピブラストにおいて,MYCの発現量の高いエピブラストがより低いエピブラストと隣接した際にアポトーシスを誘導して排除していることを明らかにし,初期胚において細胞競合が生理的に起こっていることを報告した(図1C)12)。また,発生初期のマウス表皮においてはMYCNを低発現する細胞は周囲の細胞によってアポトーシスで排除され,更に重層化してくると細胞分化により排除していることが最近報告されている(図1D)13)。つまり,発生中の組織においても細胞競合が生理的に重要な役割を担っていることが考えられる。しかしながら,発生後の上皮系組織や臓器において組織幹細胞が隣接する幹細胞との間で“細胞競合”を引き起こしているのかどうか,またその生理的な意義については不明であった14)。
腸上皮の老化に関わるストレス応答の2方向性
著者: 小笠原暢彦 , 油井史郎 , 渡辺守
ページ範囲:P.172 - P.176
体内で最も早いターンオーバーを示す腸上皮の恒常性を維持するのが上皮幹細胞である。恒常状態で静的細胞動態を示す血液幹細胞などの多くの組織と同じ静的な特性を示す一群の細胞1)という考え方だけでなく,細胞周期が高回転する増殖性細胞という考え方もあり2),活発な議論の絶えない実に興味深い研究領域となっている。
近年腸幹細胞に関して,加齢・炎症などのストレス反応を通じた老化の詳細が明らかになり,幹細胞機能の低下によるバリア機能・再生能の低下が大腸がんなどの疾患リスクにつながることがわかってきた3)。この過程には代謝動態の変化,epigeneticsの変化,細胞外基質をはじめとする微小環境の変化などの様々な因子が密接に関与している。本稿では,前半で腸上皮幹細胞の特性とその老化の概要に関する最近の知見を概説し,後半では微小環境,特に細胞外基質の変化が幹細胞に与える影響が,単に老化という概念だけでは理解しきれず,上皮細胞の幼若化・胎児化という新しい考え方が有用であることを示した筆者らの報告4)を紹介する。
活性酸素種による組織幹細胞の老化と長寿・老化耐性齧歯類ハダカデバネズミの抗老化戦略
著者: 大岩祐基 , 岡香織 , 河村佳見 , 三浦恭子
ページ範囲:P.177 - P.180
近年,老化に関する様々な知見が蓄積され,老化制御に重要な因子が少しずつわかってきた。本稿では,特に活性酸素種(reactive oxygen species;ROS)に着目して,老化と組織幹細胞についての近年の知見の概略を示す。また,筆者らの研究対象である,長寿・老化耐性齧歯類ハダカデバネズミを紹介する。更に,ROSに対するハダカデバネズミの抗老化戦略を紹介し,老化研究の今後の課題について考察する。
仮説と戦略
人間は冬眠できるのか? フリーアクセス
著者: 砂川玄志郎
ページ範囲:P.181 - P.186
一部の哺乳類は自らの代謝を低下させることで,少ないエネルギー消費量で生命活動を維持できる。このような省エネ状態は休眠と呼ばれ,数か月の休眠を冬眠,数時間の休眠を日内休眠と呼ぶ。自然界ですべての哺乳類が休眠を行うわけではなく,人間も休眠はできないと考えられている。一方で,休眠のような長期間にわたる省エネ状態を人間で安全に実現できると,臨床において生命が危機的状況にあるときに,積極的に代謝を下げることで生命予後の劇的な向上が期待できる。筆者らは人間を安全に冬眠させるための研究開発を行っているが,はたして人間を冬眠させることはできるのであろうか?
本稿では,これまでに得られてきた知見をもとに,人間が冬眠できるかどうか,そして,人工冬眠実現のために必要な研究開発の展望について概説する。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.93 - P.93
財団だより フリーアクセス
ページ範囲:P.129 - P.129
財団だより フリーアクセス
ページ範囲:P.187 - P.187
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.134 - P.134
お知らせ フリーアクセス
ページ範囲:P.154 - P.154
あとがき フリーアクセス
著者: 栗原裕基
ページ範囲:P.188 - P.188
今回は須田年生先生をゲストエディターにお招きし,幹細胞の特集を企画していただきました。須田先生は長年にわたってわが国の幹細胞学・血液学を牽引してこられた先生で,昨年米国血液学会で最も栄誉あるE. Donnall Thomas Prizeを日本人として初めて受賞されました。先生がなぜ幹細胞に魅せられ,40年以上の間一貫して取り組んでこられたのか,その面白さ,奥深さがこの特集から伝わってくるように思います。
「組織幹細胞は,組織を長期にわたって維持するという能力を有するものの,その使われ方は,各組織によって違うようです。細胞回転の速い組織に限っても,造血幹細胞,腸管幹細胞,表皮幹細胞,精子幹細胞で,それぞれ異なります。この特集を通読し,その違いについて,考察するのもおもしろいと思われます。ゆえに,各研究者にメールアドレスを併記していただきました。」〜須田先生より
基本情報
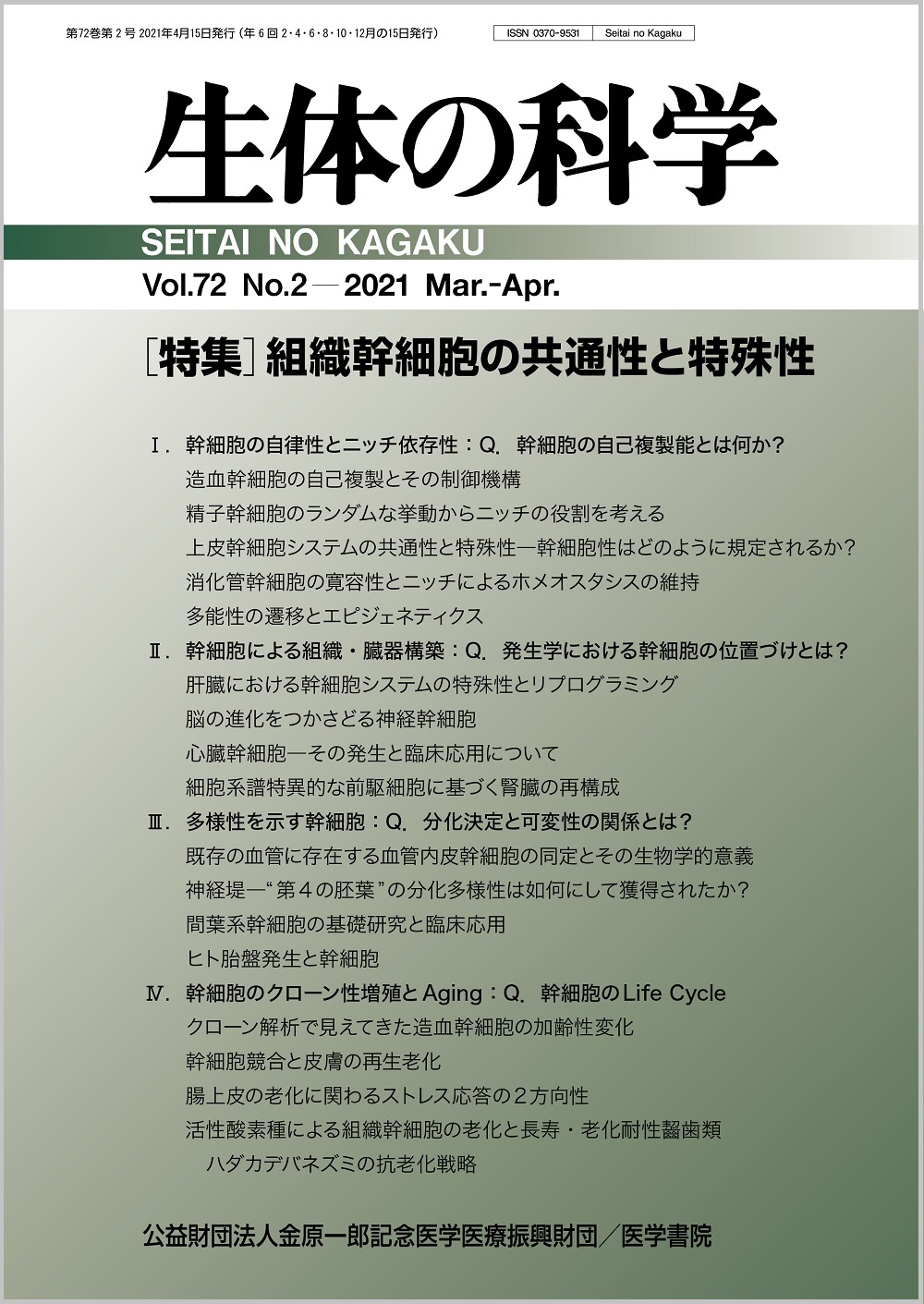
バックナンバー
75巻6号(2024年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅤ:脂肪
75巻5号(2024年10月発行)
増大特集 学術研究支援の最先端
75巻4号(2024年8月発行)
特集 シングルセルオミクス
75巻3号(2024年6月発行)
特集 高速分子動画:動的構造からタンパク質分子制御へ
75巻2号(2024年4月発行)
特集 生命現象を駆動する生体内金属動態の理解と展開
75巻1号(2024年2月発行)
特集 脳と個性
74巻6号(2023年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅣ:骨・軟骨
74巻5号(2023年10月発行)
増大特集 代謝
74巻4号(2023年8月発行)
特集 がん遺伝子の発見は現代医療を進歩させたか
74巻3号(2023年6月発行)
特集 クロマチンによる転写制御機構の最前線
74巻2号(2023年4月発行)
特集 未病の科学
74巻1号(2023年2月発行)
特集 シナプス
73巻6号(2022年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅢ:血管とリンパ管
73巻5号(2022年10月発行)
増大特集 革新脳と関連プロジェクトから見えてきた新しい脳科学
73巻4号(2022年8月発行)
特集 形態形成の統合的理解
73巻3号(2022年6月発行)
特集 リソソーム研究の新展開
73巻2号(2022年4月発行)
特集 DNA修復による生体恒常性の維持
73巻1号(2022年2月発行)
特集 意識
72巻6号(2021年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅡ:骨格筋—今後の研究の発展に向けて
72巻5号(2021年10月発行)
増大特集 脳とからだ
72巻4号(2021年8月発行)
特集 グローバル時代の新興再興感染症への科学的アプローチ
72巻3号(2021年6月発行)
特集 生物物理学の進歩—生命現象の定量的理解へ向けて
72巻2号(2021年4月発行)
特集 組織幹細胞の共通性と特殊性
72巻1号(2021年2月発行)
特集 小脳研究の未来
71巻6号(2020年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅠ:最新の皮膚科学
71巻5号(2020年10月発行)
増大特集 難病研究の進歩
71巻4号(2020年8月発行)
特集 細胞機能の構造生物学
71巻3号(2020年6月発行)
特集 スポーツ科学—2020オリンピック・パラリンピックによせて
71巻2号(2020年4月発行)
特集 ビッグデータ時代のゲノム医学
71巻1号(2020年2月発行)
特集 睡眠の制御と機能
70巻6号(2019年12月発行)
特集 科学と芸術の接点
70巻5号(2019年10月発行)
増大特集 現代医学・生物学の先駆者たち
70巻4号(2019年8月発行)
特集 メカノバイオロジー
70巻3号(2019年6月発行)
特集 免疫チェックポイント分子による生体機能制御
70巻2号(2019年4月発行)
特集 免疫系を介したシステム連関:恒常性の維持と破綻
70巻1号(2019年2月発行)
特集 脳神経回路のダイナミクスから探る脳の発達・疾患・老化
69巻6号(2018年12月発行)
特集 細胞高次機能をつかさどるオルガネラコミュニケーション
69巻5号(2018年10月発行)
増大特集 タンパク質・核酸の分子修飾
69巻4号(2018年8月発行)
特集 いかに創薬を進めるか
69巻3号(2018年6月発行)
特集 生体膜のバイオロジー
69巻2号(2018年4月発行)
特集 宇宙の極限環境から生命体の可塑性をさぐる
69巻1号(2018年2月発行)
特集 社会性と脳
68巻6号(2017年12月発行)
特集 心臓の発生・再生・創生
68巻5号(2017年10月発行)
増大特集 細胞多様性解明に資する光技術─見て,動かす
68巻4号(2017年8月発行)
特集 血管制御系と疾患
68巻3号(2017年6月発行)
特集 核内イベントの時空間制御
68巻2号(2017年4月発行)
特集 細菌叢解析の光と影
68巻1号(2017年2月発行)
特集 大脳皮質—成り立ちから機能へ
67巻6号(2016年12月発行)
特集 時間生物学の新展開
67巻5号(2016年10月発行)
増大特集 病態バイオマーカーの“いま”
67巻4号(2016年8月発行)
特集 認知症・神経変性疾患の克服への挑戦
67巻3号(2016年6月発行)
特集 脂質ワールド
67巻2号(2016年4月発行)
特集 細胞の社会学─細胞間で繰り広げられる協調と競争
67巻1号(2016年2月発行)
特集 記憶ふたたび
66巻6号(2015年12月発行)
特集 グリア研究の最先端
66巻5号(2015年10月発行)
増大特集 細胞シグナル操作法
66巻4号(2015年8月発行)
特集 新興・再興感染症と感染症対策
66巻3号(2015年6月発行)
特集 進化と発生からみた生命科学
66巻2号(2015年4月発行)
特集 使える最新ケミカルバイオロジー
66巻1号(2015年2月発行)
特集 脳と心の謎はどこまで解けたか
65巻6号(2014年12月発行)
特集 エピジェネティクスの今
65巻5号(2014年10月発行)
増大特集 生命動態システム科学
65巻4号(2014年8月発行)
特集 古典的代謝経路の新しい側面
65巻3号(2014年6月発行)
特集 器官の発生と再生の基礎
65巻2号(2014年4月発行)
特集 細胞の少数性と多様性に挑む―シングルセルアナリシス
65巻1号(2014年2月発行)
特集 精神疾患の病理機構
64巻6号(2013年12月発行)
特集 顕微鏡で物を見ることの新しい動き
64巻5号(2013年10月発行)
増大特集 細胞表面受容体
64巻4号(2013年8月発行)
特集 予測と意思決定の神経科学
64巻3号(2013年6月発行)
特集 細胞接着の制御
64巻2号(2013年4月発行)
特集 特殊な幹細胞としての骨格筋サテライト細胞
64巻1号(2013年2月発行)
特集 神経回路の計測と操作
63巻6号(2012年12月発行)
特集 リンパ管
63巻5号(2012年10月発行)
特集 細胞の分子構造と機能―核以外の細胞小器官
63巻4号(2012年8月発行)
特集 質感脳情報学への展望
63巻3号(2012年6月発行)
特集 細胞極性の制御
63巻2号(2012年4月発行)
特集 RNA干渉の実現化に向けて
63巻1号(2012年2月発行)
特集 小脳研究の課題(2)
62巻6号(2011年12月発行)
特集 コピー数変異
62巻5号(2011年10月発行)
特集 細胞核―構造と機能
62巻4号(2011年8月発行)
特集 小脳研究の課題
62巻3号(2011年6月発行)
特集 インフラマソーム
62巻2号(2011年4月発行)
特集 筋ジストロフィーの分子病態から治療へ
62巻1号(2011年2月発行)
特集 摂食制御の分子過程
61巻6号(2010年12月発行)
特集 細胞死か腫瘍化かの選択
61巻5号(2010年10月発行)
特集 シナプスをめぐるシグナリング
61巻4号(2010年8月発行)
特集 miRNA研究の最近の進歩
61巻3号(2010年6月発行)
特集 SNARE複合体-膜融合の機構
61巻2号(2010年4月発行)
特集 糖鎖のかかわる病気:発症機構,診断,治療に向けて
61巻1号(2010年2月発行)
特集 脳科学のモデル実験動物
60巻6号(2009年12月発行)
特集 ユビキチン化による生体機能の調節
60巻5号(2009年10月発行)
特集 伝達物質と受容体
60巻4号(2009年8月発行)
特集 睡眠と脳回路の可塑性
60巻3号(2009年6月発行)
特集 脳と糖脂質
60巻2号(2009年4月発行)
特集 感染症の現代的課題
60巻1号(2009年2月発行)
特集 遺伝子-脳回路-行動
59巻6号(2008年12月発行)
特集 mTORをめぐるシグナルタンパク
59巻5号(2008年10月発行)
特集 現代医学・生物学の仮説・学説2008
59巻4号(2008年8月発行)
特集 免疫学の最近の動向
59巻3号(2008年6月発行)
特集 アディポゲネシス
59巻2号(2008年4月発行)
特集 細胞外基質-研究の新たな展開
59巻1号(2008年2月発行)
特集 コンピュータと脳
58巻6号(2007年12月発行)
特集 グリケーション(糖化)
58巻5号(2007年10月発行)
特集 タンパク質間相互作用
58巻4号(2007年8月発行)
特集 嗅覚受容の分子メカニズム
58巻3号(2007年6月発行)
特集 骨の形成と破壊
58巻2号(2007年4月発行)
特集 シナプス後部構造の形成・機構と制御
58巻1号(2007年2月発行)
特集 意識―脳科学からのアプローチ
57巻6号(2006年12月発行)
特集 血管壁
57巻5号(2006年10月発行)
特集 生物進化の分子マップ
57巻4号(2006年8月発行)
特集 脳科学が求める先端技術
57巻3号(2006年6月発行)
特集 ミエリン化の機構とその異常
57巻2号(2006年4月発行)
特集 膜リサイクリング
57巻1号(2006年2月発行)
特集 こころと脳:とらえがたいものを科学する
56巻6号(2005年12月発行)
特集 構造生物学の現在と今後の展開
56巻5号(2005年10月発行)
特集 タンパク・遺伝子からみた分子病―新しく解明されたメカニズム
56巻4号(2005年8月発行)
特集 脳の遺伝子―どこでどのように働いているのか
56巻3号(2005年6月発行)
特集 Naチャネル
56巻2号(2005年4月発行)
特集 味覚のメカニズムに迫る
56巻1号(2005年2月発行)
特集 情動―喜びと恐れの脳の仕組み
55巻6号(2004年12月発行)
特集 脳の深部を探る
55巻5号(2004年10月発行)
特集 生命科学のNew Key Word
55巻4号(2004年8月発行)
特集 心筋研究の最前線
55巻3号(2004年6月発行)
特集 分子進化学の現在
55巻2号(2004年4月発行)
特集 アダプタータンパク
55巻1号(2004年2月発行)
特集 ニューロンと脳
54巻6号(2003年12月発行)
特集 オートファジー
54巻5号(2003年10月発行)
特集 創薬ゲノミクス・創薬プロテオミクス・創薬インフォマティクス
54巻4号(2003年8月発行)
特集 ラフトと細胞機能
54巻3号(2003年6月発行)
特集 クロマチン
54巻2号(2003年4月発行)
特集 樹状突起
54巻1号(2003年2月発行)
53巻6号(2002年12月発行)
特集 ゲノム全解読とポストゲノムの問題点
53巻5号(2002年10月発行)
特集 加齢の克服―21世紀の課題
53巻4号(2002年8月発行)
特集 一価イオンチャネル
53巻3号(2002年6月発行)
特集 細胞質分裂
53巻2号(2002年4月発行)
特集 RNA
53巻1号(2002年2月発行)
連続座談会 脳とこころ―21世紀の課題
52巻6号(2001年12月発行)
特集 血液脳関門研究の最近の進歩
52巻5号(2001年10月発行)
特集 モチーフ・ドメインリスト
52巻4号(2001年8月発行)
特集 骨格筋研究の新展開
52巻3号(2001年6月発行)
特集 脳の発達に関与する分子機構
52巻2号(2001年4月発行)
特集 情報伝達物質としてのATP
52巻1号(2001年2月発行)
連続座談会 脳を育む
51巻6号(2000年12月発行)
特集 機械的刺激受容の分子機構と細胞応答
51巻5号(2000年10月発行)
特集 ノックアウトマウスリスト
51巻4号(2000年8月発行)
特集 臓器(組織)とアポトーシス
51巻3号(2000年6月発行)
特集 自然免疫における異物認識と排除の分子機構
51巻2号(2000年4月発行)
特集 細胞極性の形成機序
51巻1号(2000年2月発行)
特集 脳を守る21世紀生命科学の展望
50巻6号(1999年12月発行)
特集 細胞内輸送
50巻5号(1999年10月発行)
特集 病気の分子細胞生物学
50巻4号(1999年8月発行)
特集 トランスポーターの構造と機能協関
50巻3号(1999年6月発行)
特集 時間生物学の新たな展開
50巻2号(1999年4月発行)
特集 リソソーム:最近の研究
50巻1号(1999年2月発行)
連続座談会 脳を守る
49巻6号(1998年12月発行)
特集 発生・分化とホメオボックス遺伝子
49巻5号(1998年10月発行)
特集 神経系に作用する薬物マニュアル1998
49巻4号(1998年8月発行)
特集 プロテインキナーゼCの多様な機能
49巻3号(1998年6月発行)
特集 幹細胞研究の新展開
49巻2号(1998年4月発行)
特集 血管―新しい観点から
49巻1号(1998年2月発行)
特集 言語の脳科学
48巻6号(1997年12月発行)
特集 軸索誘導
48巻5号(1997年10月発行)
特集 受容体1997
48巻4号(1997年8月発行)
特集 マトリックス生物学の最前線
48巻3号(1997年6月発行)
特集 開口分泌のメカニズムにおける新しい展開
48巻2号(1997年4月発行)
特集 最近のMAPキナーゼ系
48巻1号(1997年2月発行)
特集 21世紀の脳科学
47巻6号(1996年12月発行)
特集 老化
47巻5号(1996年10月発行)
特集 器官―その新しい視点
47巻4号(1996年8月発行)
特集 エンドサイトーシス
47巻3号(1996年6月発行)
特集 細胞分化
47巻2号(1996年4月発行)
特集 カルシウム動態と細胞機能
47巻1号(1996年2月発行)
特集 神経科学の最前線
46巻6号(1995年12月発行)
特集 病態を変えたよく効く医薬
46巻5号(1995年10月発行)
特集 遺伝子・タンパク質のファミリー・スーパーファミリー
46巻4号(1995年8月発行)
特集 ストレス蛋白質
46巻3号(1995年6月発行)
特集 ライソゾーム
46巻2号(1995年4月発行)
特集 プロテインホスファターゼ―最近の進歩
46巻1号(1995年2月発行)
特集 神経科学の謎
45巻6号(1994年12月発行)
特集 ミトコンドリア
45巻5号(1994年10月発行)
特集 動物の行動機能テスト―個体レベルと分子レベルを結ぶ
45巻4号(1994年8月発行)
特集 造血の機構
45巻3号(1994年6月発行)
特集 染色体
45巻2号(1994年4月発行)
特集 脳と分子生物学
45巻1号(1994年2月発行)
特集 グルコーストランスポーター
44巻6号(1993年12月発行)
特集 滑面小胞体をめぐる諸問題
44巻5号(1993年10月発行)
特集 現代医学・生物学の仮説・学説
44巻4号(1993年8月発行)
特集 細胞接着
44巻3号(1993年6月発行)
特集 カルシウムイオンを介した調節機構の新しい問題点
44巻2号(1993年4月発行)
特集 蛋白質の細胞内転送とその異常
44巻1号(1993年2月発行)
座談会 脳と遺伝子
43巻6号(1992年12月発行)
特集 成長因子受容体/最近の進歩
43巻5号(1992年10月発行)
特集 〈研究室で役に立つ細胞株〉
43巻4号(1992年8月発行)
特集 細胞機能とリン酸化
43巻3号(1992年6月発行)
特集 血管新生
43巻2号(1992年4月発行)
特集 大脳皮質発達の化学的側面
43巻1号(1992年2月発行)
特集 意識と脳
42巻6号(1991年12月発行)
特集 細胞活動の日周リズム
42巻5号(1991年10月発行)
特集 神経系に作用する薬物マニュアル
42巻4号(1991年8月発行)
特集 開口分泌の細胞内過程
42巻3号(1991年6月発行)
特集 ペルオキシソーム/最近の進歩
42巻2号(1991年4月発行)
特集 脳の移植と再生
42巻1号(1991年2月発行)
特集 脳と免疫
41巻6号(1990年12月発行)
特集 注目の実験モデル動物
41巻5号(1990年10月発行)
特集 LTPとLTD:その分子機構
41巻4号(1990年8月発行)
特集 New proteins
41巻3号(1990年6月発行)
特集 シナプスの形成と動態
41巻2号(1990年4月発行)
特集 細胞接着
41巻1号(1990年2月発行)
特集 発がんのメカニズム/最近の知見
40巻6号(1989年12月発行)
特集 ギャップ結合
40巻5号(1989年10月発行)
特集 核内蛋白質
40巻4号(1989年8月発行)
特集 研究室で役に立つ新しい試薬
40巻3号(1989年6月発行)
特集 細胞骨格異常
40巻2号(1989年4月発行)
特集 大脳/神経科学からのアプローチ
40巻1号(1989年2月発行)
特集 分子進化
39巻6号(1988年12月発行)
特集 細胞内における蛋白質局在化機構
39巻5号(1988年10月発行)
特集 細胞測定法マニュアル
39巻4号(1988年8月発行)
特集 細胞外マトリックス
39巻3号(1988年6月発行)
特集 肺の微細構造と機能
39巻2号(1988年4月発行)
特集 生体運動の分子機構/研究の発展
39巻1号(1988年2月発行)
特集 遺伝子疾患解析の発展
38巻6号(1987年12月発行)
-チャンネルの最近の動向
38巻5号(1987年10月発行)
特集 細胞生物学における免疫実験マニュアル
38巻4号(1987年8月発行)
特集 視覚初期過程の分子機構
38巻3号(1987年6月発行)
特集 人間の脳
38巻2号(1987年4月発行)
特集 体液カルシウムのホメオスタシス
38巻1号(1987年2月発行)
特集 医学におけるブレイクスルー/基礎研究からの挑戦
37巻6号(1986年12月発行)
特集 神経活性物質受容体と情報伝達
37巻5号(1986年10月発行)
特集 中間径フィラメント
37巻4号(1986年8月発行)
特集 細胞生物学実験マニュアル
37巻3号(1986年6月発行)
特集 脳の化学的トポグラフィー
37巻2号(1986年4月発行)
特集 血小板凝集
37巻1号(1986年2月発行)
特集 脳のモデル
36巻6号(1985年12月発行)
特集 脂肪組織
36巻5号(1985年10月発行)
特集 細胞分裂をめぐって
36巻4号(1985年8月発行)
特集 神経科学実験マニュアル
36巻3号(1985年6月発行)
特集 血管内皮細胞と微小循環
36巻2号(1985年4月発行)
特集 肝細胞と胆汁酸分泌
36巻1号(1985年2月発行)
特集 Transmembrane Control
35巻6号(1984年12月発行)
特集 細胞毒マニュアル—実験に用いられる細胞毒の知識
35巻5号(1984年10月発行)
特集 中枢神経系の再構築
35巻4号(1984年8月発行)
特集 ゲノムの構造
35巻3号(1984年6月発行)
特集 神経科学の仮説
35巻2号(1984年4月発行)
特集 哺乳類の初期発生
35巻1号(1984年2月発行)
特集 細胞生物学の現状と展望
34巻6号(1983年12月発行)
特集 蛋白質の代謝回転
34巻5号(1983年10月発行)
特集 受容・応答の膜分子論
34巻4号(1983年8月発行)
特集 コンピュータによる生物現象の再構成
34巻3号(1983年6月発行)
特集 細胞の極性
34巻2号(1983年4月発行)
特集 モノアミン系
34巻1号(1983年2月発行)
特集 腸管の吸収機構
33巻6号(1982年12月発行)
特集 低栄養と生体機能
33巻5号(1982年10月発行)
特集 成長因子
33巻4号(1982年8月発行)
特集 リン酸化
33巻3号(1982年6月発行)
特集 神経発生の基礎
33巻2号(1982年4月発行)
特集 細胞の寿命と老化
33巻1号(1982年2月発行)
特集 細胞核
32巻6号(1981年12月発行)
特集 筋小胞体研究の進歩
32巻5号(1981年10月発行)
特集 ペプチド作働性シナプス
32巻4号(1981年8月発行)
特集 膜の転送
32巻3号(1981年6月発行)
特集 リポプロテイン
32巻2号(1981年4月発行)
特集 チャネルの概念と実体
32巻1号(1981年2月発行)
特集 細胞骨格
31巻6号(1980年12月発行)
特集 大脳の機能局在
31巻5号(1980年10月発行)
特集 カルシウムイオン受容タンパク
31巻4号(1980年8月発行)
特集 化学浸透共役仮説
31巻3号(1980年6月発行)
特集 赤血球膜の分子構築
31巻2号(1980年4月発行)
特集 免疫系の情報識別
31巻1号(1980年2月発行)
特集 ゴルジ装置
30巻6号(1979年12月発行)
特集 細胞間コミニケーション
30巻5号(1979年10月発行)
特集 In vitro運動系
30巻4号(1979年8月発行)
輸送系の調節
30巻3号(1979年6月発行)
特集 網膜の構造と機能
30巻2号(1979年4月発行)
特集 神経伝達物質の同定
30巻1号(1979年2月発行)
特集 生物物理学の進歩—第6回国際生物物理学会議より
29巻6号(1978年12月発行)
特集 最近の神経科学から
29巻5号(1978年10月発行)
特集 下垂体:前葉
29巻4号(1978年8月発行)
特集 中枢のペプチド
29巻3号(1978年6月発行)
特集 心臓のリズム発生
29巻2号(1978年4月発行)
特集 腎機能
29巻1号(1978年2月発行)
特集 膜脂質の再検討
28巻6号(1977年12月発行)
特集 青斑核
28巻5号(1977年10月発行)
特集 小胞体
28巻4号(1977年8月発行)
特集 微小管の構造と機能
28巻3号(1977年6月発行)
特集 神経回路網と脳機能
28巻2号(1977年4月発行)
特集 生体の修復
28巻1号(1977年2月発行)
特集 生体の科学の現状と動向
27巻6号(1976年12月発行)
特集 松果体
27巻5号(1976年10月発行)
特集 遺伝マウス・ラット
27巻4号(1976年8月発行)
特集 形質発現における制御
27巻3号(1976年6月発行)
特集 生体と化学的環境
27巻2号(1976年4月発行)
特集 分泌腺
27巻1号(1976年2月発行)
特集 光受容
26巻6号(1975年12月発行)
特集 自律神経と平滑筋の再検討
26巻5号(1975年10月発行)
特集 脳のプログラミング
26巻4号(1975年8月発行)
特集 受精機構をめぐつて
26巻3号(1975年6月発行)
特集 細胞表面と免疫
26巻2号(1975年4月発行)
特集 感覚有毛細胞
26巻1号(1975年2月発行)
特集 体内のセンサー
25巻5号(1974年12月発行)
特集 生体膜—その基本的課題
25巻4号(1974年8月発行)
特集 伝達物質と受容物質
25巻3号(1974年6月発行)
特集 脳の高次機能へのアプローチ
25巻2号(1974年4月発行)
特集 筋細胞の分化
25巻1号(1974年2月発行)
特集 生体の科学 展望と夢
24巻6号(1973年12月発行)
24巻5号(1973年10月発行)
24巻4号(1973年8月発行)
24巻3号(1973年6月発行)
24巻2号(1973年4月発行)
24巻1号(1973年2月発行)
23巻6号(1972年12月発行)
23巻5号(1972年10月発行)
23巻4号(1972年8月発行)
23巻3号(1972年6月発行)
23巻2号(1972年4月発行)
23巻1号(1972年2月発行)
22巻6号(1971年12月発行)
22巻5号(1971年10月発行)
22巻4号(1971年8月発行)
22巻3号(1971年6月発行)
22巻2号(1971年4月発行)
22巻1号(1971年2月発行)
21巻7号(1970年12月発行)
21巻6号(1970年10月発行)
21巻4号(1970年8月発行)
特集 代謝と機能
21巻5号(1970年8月発行)
21巻3号(1970年6月発行)
21巻2号(1970年4月発行)
21巻1号(1970年2月発行)
20巻6号(1969年12月発行)
20巻5号(1969年10月発行)
20巻4号(1969年8月発行)
20巻3号(1969年6月発行)
20巻2号(1969年4月発行)
20巻1号(1969年2月発行)
19巻6号(1968年12月発行)
19巻5号(1968年10月発行)
19巻4号(1968年8月発行)
19巻3号(1968年6月発行)
19巻2号(1968年4月発行)
19巻1号(1968年2月発行)
18巻6号(1967年12月発行)
18巻5号(1967年10月発行)
18巻4号(1967年8月発行)
18巻3号(1967年6月発行)
18巻2号(1967年4月発行)
18巻1号(1967年2月発行)
17巻6号(1966年12月発行)
17巻5号(1966年10月発行)
17巻4号(1966年8月発行)
17巻3号(1966年6月発行)
17巻2号(1966年4月発行)
17巻1号(1966年2月発行)
16巻6号(1965年12月発行)
16巻5号(1965年10月発行)
16巻4号(1965年8月発行)
16巻3号(1965年6月発行)
16巻2号(1965年4月発行)
16巻1号(1965年2月発行)
15巻6号(1964年12月発行)
特集 生体膜その3
15巻5号(1964年10月発行)
特集 生体膜その2
15巻4号(1964年8月発行)
特集 生体膜その1
15巻3号(1964年6月発行)
特集 第13回日本生理科学連合シンポジウム
15巻2号(1964年4月発行)
15巻1号(1964年2月発行)
14巻6号(1963年12月発行)
特集 興奮收縮伝関
14巻5号(1963年10月発行)
14巻4号(1963年8月発行)
14巻3号(1963年6月発行)
14巻1号(1963年2月発行)
特集 第9回中枢神経系の生理学シンポジウム
14巻2号(1963年2月発行)
13巻6号(1962年12月発行)
13巻5号(1962年10月発行)
特集 生物々理—生理学生物々理若手グループ第1回ミーティングから
13巻4号(1962年8月発行)
13巻3号(1962年6月発行)
13巻2号(1962年4月発行)
Symposium on Permeability of Biological Membranes
13巻1号(1962年2月発行)
12巻6号(1961年12月発行)
12巻5号(1961年10月発行)
12巻4号(1961年8月発行)
12巻3号(1961年6月発行)
12巻2号(1961年4月発行)
12巻1号(1961年2月発行)
11巻6号(1960年12月発行)
Symposium On Active Transport
11巻5号(1960年10月発行)
11巻4号(1960年8月発行)
11巻3号(1960年6月発行)
11巻2号(1960年4月発行)
11巻1号(1960年2月発行)
10巻6号(1959年12月発行)
10巻5号(1959年10月発行)
10巻4号(1959年8月発行)
10巻3号(1959年6月発行)
10巻2号(1959年4月発行)
10巻1号(1959年2月発行)
8巻6号(1957年12月発行)
8巻5号(1957年10月発行)
特集 酵素と生物
8巻4号(1957年8月発行)
8巻3号(1957年6月発行)
8巻2号(1957年4月発行)
8巻1号(1957年2月発行)
