脳が体内の様々な情報を集約し生体の恒常性を保つための制御シグナルを発することは,内分泌系や自律神経系において古くから研究されてきました。近年,このような脳と体の相互作用には,腸管内の細菌叢やそれと反応する免疫系など,より多くの因子が関わり,単に代謝系の恒常性維持などだけでなく,“こころ”を含む脳の機能維持に深く関わることが明らかになってきました。『生体の科学』ではこの度,この分野の発展に大きく貢献されている研究者の皆様にご協力をいただき,「脳とからだ」という題で,この分野の発展を鳥瞰できる特集を編集しました。
第Ⅰ章の「腸,免疫系,脳の相互作用」では,多発性硬化症に代表される免疫性神経疾患の発症や進行へ及ぼす腸内細菌叢の影響,T細胞活性化による不安の亢進,さらには自律神経系が及ぼす免疫系細胞の動態や炎症反応への影響など,神経と免疫の幅広い相互作用について論じられています。
雑誌目次
生体の科学72巻5号
2021年10月発行
雑誌目次
増大特集 脳とからだ
特集「脳とからだ」によせて フリーアクセス
著者: 『生体の科学』編集委員一同
ページ範囲:P.370 - P.370
Ⅰ.腸,免疫系,脳の相互作用
腸内環境と神経疾患
著者: 三宅幸子
ページ範囲:P.371 - P.374
神経疾患では,多発性硬化症のような免疫疾患ばかりでなく,パーキンソン病などに代表される変性疾患においても,炎症反応などの免疫応答が病態形成に関与することがわかってきた。一方,生体の半数以上のリンパ球が存在し,腸内細菌叢と相互作用する免疫組織として腸管が注目されている。多発性硬化症やパーキンソン病では炎症の促進につながるdysbiosisがみられ,病態への関与が示唆されている。
腸内細菌と中枢神経系炎症
著者: 宮内栄治 , 大野博司
ページ範囲:P.375 - P.377
次世代シーケンサーの普及により,多発性硬化症患者が健常人とは異なる腸内細菌叢を有することが明らかになってきた。また,患者糞便を疾患モデルマウスに移植することにより,腸内細菌叢の変化が中枢神経系の炎症や脱髄に影響することも示さている。本稿では,多発性硬化症患者の腸内細菌叢の特徴とその宿主への作用機序,更には腸内細菌を起点とした予防・治療の可能性について述べる。
免疫活性化と不安
著者: 宮島倫生 ,
ページ範囲:P.378 - P.381
免疫系と脳神経系は複雑に相互作用していることが明らかになってきている。本稿では,免疫系と脳神経系との相互作用のなかでも,末梢の免疫細胞,特にT細胞の活性化が不安を亢進させるメカニズムに焦点を当てる。具体的には,近年明らかにされてきた“母体免疫活性化に起因する不安様行動の亢進”“恒常的T細胞活性化に起因する不安様行動の亢進”“ストレスに起因する亢進した不安様行動におけるT細胞の役割”という3点のトピックを紹介する。
神経免疫システムと多発性硬化症
著者: 河野資 , 井上誠
ページ範囲:P.382 - P.385
免疫機能による神経系制御や神経機能による免疫系制御に関する知見が,この10数年の間に多数報告されている1)。この免疫機能と神経機能を相互理解することが,自己免疫性,神経障害性および感染性疾患の解明に必須となりつつある。多発性硬化症は神経免疫システムが大きく関わる代表的疾患である。また,様々な環境要因による神経免疫システムの変調が,その病態発症や再発,並びに,病型や薬物感受性に大きく影響する。本稿ではこれらに関する最近の知見と今後の展望について述べる。
腸内細菌によるストレス応答・行動特性の制御
著者: 須藤信行
ページ範囲:P.386 - P.388
近年,腸内細菌は宿主のストレス反応や行動特性に影響することが明らかにされている。筆者らの人工菌叢マウスを用いた検討では,無菌マウスは通常のspecific pathogen free環境下で飼育されたマウスと比較し,ストレス応答が有意に増強していた。また,無菌マウスは,通常の腸内細菌を有するマウスと比較し,多動で不安レベルが高かった。以上の結果は,腸内細菌は成長後のストレス反応や行動特性にも影響することを示している。
ストレスによる炎症応答のメカニズムとその役割
著者: 谷口将之 , 北岡志保 , 古屋敷智之
ページ範囲:P.389 - P.392
社会や環境から受けるストレスは抑うつなど情動変化を引き起こし,うつ病などの精神疾患のリスク因子となる。近年,ストレスによる情動変容における炎症応答の重要性が確立され,ストレスにおける末梢および中枢の免疫細胞の役割の研究が進められている。反復ストレスは内分泌系や自律神経系の活性化を引き起こし,単球や好中球などミエロイド系細胞の動員とその活性化を引き起こす。更に,内側前頭前皮質などの特定の脳領域においてミクログリア活性化を誘導し,神経細胞の樹状突起の退縮を伴った情動変容を促す。また,これらの炎症メカニズムに転写・エピゲノム制御の関与が推測される。これらの知見はストレス応答がエピゲノム変化として記憶され,炎症応答を修飾して情動変容を引き起こすことを示唆し,ストレスによる炎症応答を対象とした新たな創薬標的となる可能性が期待される。
交感神経系による骨髄の制御
著者: 粟生智香 , 菊田順一 , 石井優
ページ範囲:P.393 - P.396
交感神経系は生体が恒常性を維持するうえで重要なシステムであり,以前から研究が進められてきた。最近の研究によって,より多様な臓器で機能を持つことが明らかになりつつあり,骨髄も注目を集める臓器の一つである。交感神経系は骨髄において,造血幹細胞の維持に関わり,骨髄細胞の移動も制御している。一方,骨代謝の側面からみると,交感神経系は骨芽細胞の分化および骨形成を抑制する。本稿ではこれらの最新の知見に加え,筆者らが生体イメージングの系を用いて明らかにした,急性炎症初期の好中球の動態に対する機能の研究を紹介する。更に,生体イメージングを利用した交感神経系の機能の探索における課題と,今後の展望についても述べる。
交感神経によるリンパ球の体内動態の制御
著者: 鈴木一博
ページ範囲:P.397 - P.400
神経系が免疫系に多大な影響を及ぼしていることは古くから指摘されてきたが,そのメカニズムは長らく不明であった。しかし近年,神経系と免疫系の相互作用のメカニズムが急速に明らかになりつつある。とりわけ,自律神経系が多様な分子機構を介して免疫応答を制御していることが明らかになった。ここでは,交感神経によるリンパ球動態の制御に焦点を当て,その分子機構を解説すると共に,その生理的意義と治療応用の可能性について考察する。
迷走神経を介した新しい炎症抑制メカニズム
著者: 寺谷俊昭 , 三上洋平 , 金井隆典
ページ範囲:P.401 - P.404
腸管内の免疫細胞は,環境に応じて分化や機能を変化させる。腸管免疫を変化させる主要な環境因子の一つとして,神経が近年着目されている。免疫調節に関わる様々な神経機能が矢継ぎ早に報告されているが,腸管恒常性に最も大事とされる制御性T細胞に関わる神経の存在については不明瞭なままであった。そこで筆者らは,制御性T細胞の分化・機能に関わる神経の同定を試みた。本稿では,当教室で実施した研究成果について紹介する1)。
ゲートウェイ反射による血液脳関門への免疫細胞ゲート形成制御と病態の誘導
著者: 田中勇希 , 村上正晃
ページ範囲:P.405 - P.408
これまでに筆者らは,局所神経活性化が固有の血管に免疫細胞の中枢への侵入口を形成するゲートウェイ反射を報告してきた。本稿では,これまでに報告してきたゲートウェイ反射を介した血液脳関門の制御と,組織特異的な病態誘導との関係について論じる。
中枢神経の障害がもたらす免疫系の変容と病態
著者: 上野将紀
ページ範囲:P.409 - P.411
脳血管障害や外傷など脳や脊髄の障害は,感染症のリスクを高める。その機序として,自律神経や視床下部-下垂体-副腎系など,免疫を制御する神経経路の破綻による免疫能の低下が指摘されている。本稿では,中枢神経の障害において,脳と免疫系をつなぐ神経の変化が,免疫機能へおよぼす影響とその病態について,最近の研究動向を概説する。免疫を制御する神経基盤とその病態の理解は,新たな治療戦略へつながると期待される。
Ⅱ.グリアと脳の相互作用
甲状腺ホルモンによるグリア細胞の制御
著者: 野田百美
ページ範囲:P.412 - P.415
甲状腺ホルモンは,脳の発達・成長の段階で必須なホルモンであるだけでなく,成熟した脳でも重要な機能があり,亢進症・低下症は様々な精神症状を引き起こし,高齢では認知症・アルツハイマー病のリスクファクターとなっている。甲状腺機能異常の発症には顕著な性差があるが,そのメカニズムは不明である。本稿では,細胞レベル,および甲状腺機能異常症のモデルマウスを用いた組織レベルで,グリア細胞と神経突起のスパインに対する甲状腺ホルモンの作用とその性差・週齢差について示し,認知症を含む様々な精神神経症状のメカニズム解明,有効な予防法の確立に向けた今後の展望を述べる。
中枢神経炎症制御とNG2グリア
著者: 片岡洋祐 , 田村泰久
ページ範囲:P.416 - P.418
うつ病や認知症の発症・進展,慢性疲労症候群や感染症での疲労感の誘発など,様々な病態に中枢神経炎症が深く関わることが明らかになってきた。神経炎症はミクログリアやアストロサイトの活性化により誘発されることはよく知られている。一方,神経炎症を抑制・制御する脳内の細胞についてはよくわかっていない。最近,NG2を発現するグリア前駆細胞がミクログリアの活性化を制御し,神経炎症の抑制に寄与する可能性を見いだした。
グリア細胞が作り出す神経機能異常による痛みや痒み
著者: 津田誠
ページ範囲:P.419 - P.422
末梢神経の損傷や機能不全,あるいは皮膚の炎症などにより,慢性的な痛みや痒みが生じる。動物モデルでの基礎研究から,神経障害や炎症によってグリア細胞が形態や遺伝子発現変化を伴い活性化状態となり,周囲の神経活動に異常を生じさせることがわかってきた。本稿では,脊髄後角や脳のミクログリアとアストロサイトによって作り出される神経の機能異常と痛みや痒みのメカニズムについて概説する。
母体免疫活性化と自閉症スペクトラム障害
著者: 吉田文明 , 富田泰輔
ページ範囲:P.423 - P.425
自閉症スペクトラム障害(ASD)は免疫系の異常に伴う疾患であることが示唆されつつある。疫学的な調査から,妊娠時の感染に伴う母体免疫活性化がASD発症リスクを高めるとする報告がなされていた。近年確立された母体免疫活性化を模した動物モデルにおいてもこの関連性が再現され,母体免疫活性化とASD発症の相関に注目が集まりつつある。そこで,本稿では母体免疫活性化とASD発症リスクの相関についての知見を簡潔にまとめる。
ミクログリアによるシナプスの形成・刈り込みと自閉スペクトラム症
著者: 内野茂夫
ページ範囲:P.426 - P.429
ミクログリアは,胎生初期の卵黄囊に存在する前駆細胞を起源とする脳内の免疫担当細胞である。正常時は,神経回路の形成・再構築や神経活動の制御など,脳内の恒常性の維持に寄与している。一方,病態時は,異物や死細胞の除去に加え,脳の損傷や機能障害部位を感知し,神経細胞の保護や修復も行う。本稿では,正常脳での発達過程におけるミクログリアの役割を概説すると共に,自閉スペクトラム症の病態脳におけるミクログリアの関与について,最近の知見を紹介する。
ミクログリアと情動制御
著者: 澤田誠
ページ範囲:P.430 - P.433
これまでの研究から想定されてきたミクログリアによる情動制御の可能性について,遺伝子操作技術やライブイメージング技術の応用によって直接的に関与していることを示す結果が得られるようになってきた。高精度なオミックス技術によって単一細胞レベルでの分子分析も可能となってきているため,今後は脳内での位置関係の情報を保ったまま細胞の微細領域を分取することにより制御メカニズムを明らかにしていく必要がある。
統合失調症の神経活動異常と神経免疫異常
著者: 平野羊嗣 , 加藤隆弘
ページ範囲:P.434 - P.437
統合失調症は,その高い生涯有病率にもかかわらずいまだに原因不明で,病態解明と病態生理に基づくバイオマーカーの確立および治療法開発が急務である。近年,統合失調症患者の脳内のE/Iバランス異常や神経免疫異常が示唆されており,ガンマオシレーションや免疫マーカーの測定が有用なバイオマーカーとして注目されている。本稿では,統合失調症の神経活動異常と神経免疫異常および両者の関連に関する知見と今後の展望を概説する。
アストロサイトによる情動制御
著者: 繁冨英治 , 小泉修一
ページ範囲:P.438 - P.441
情動に関連する神経回路の機能は,グリア細胞活動により調節される。アストロサイトは,ニューロンとニューロン間のシナプス伝達とは異なる様式で,周囲のニューロンの興奮性,シナプス伝達を制御して,情動に関連する神経回路を調節する。このことから,アストロサイトの機能を理解することは,情動が生じるメカニズムおよびうつ病などの情動の障害を伴う精神疾患の病態解明において鍵となる。
ミクログリアによる社会的意思決定の制御—ミクログリアは無意識由来行動をつかさどる?
著者: 加藤隆弘
ページ範囲:P.442 - P.445
脳内免疫細胞ミクログリアの活動が人間の普段の行動や社会活動に及ぼす影響はほとんど解明されていない。本稿では,健常成人男性を対象としてミクログリア活性化抑制作用を有するミノサイクリン内服による信頼ゲームを実施した経験から,ミクログリアが脳内力動に限らず無意識に左右される精神力動の主役として人間の社会的意思決定に重要な役割を果たす可能性に言及し,意識・無意識と神経系・ミクログリアとの関係を展望する。
治療戦略から考えるアルツハイマー病の神経炎症
著者: 関谷倫子 , 飯島浩一
ページ範囲:P.446 - P.449
アルツハイマー病と神経炎症の関わりは古く,初めて症例が報告された1906年には,肥大化したグリア細胞がアミロイド斑の周囲に集積する様子が観察されていた。近年のゲノム解析により,多くのミクログリア遺伝子がアルツハイマー病の発症リスクと関連づけられ,神経炎症が病理形成の主要因子として働くことが示された。本稿では,神経炎症を標的としたアルツハイマー病の治療戦略の現状を概説する。
グリアの生理機能喪失による疾患と治療戦略
著者: 𠮷田賢治 , 杉尾翔太 , 加藤大輔 , 和氣弘明
ページ範囲:P.450 - P.453
中枢神経系を構成する細胞の半数以上はグリア細胞によって占められている。グリア細胞はアストロサイト(星状膠細胞),オリゴデンドロサイト(希突起膠細胞),ミクログリア(小膠細胞),NG2細胞に分類され,それぞれ異なる生理機能を有している。これらグリア細胞が神経細胞と相互に機能的連携をとることで高次脳機能の発現に寄与することが明らかになるにつれ,精神・神経疾患の病態へのグリア細胞の関与が着目されてきている。本稿ではグリア細胞のなかでも特に,髄鞘形成を担うオリゴデンドロサイトとその前駆細胞の生理機能に関する最近のトピックスを紹介し,その機能喪失による精神・神経疾患への関与について述べ,オリゴデンドロサイトを標的とする治療戦略の可能性について考察する。
Ⅲ.中枢と末梢の相互作用
主観的感情と内受容感覚の神経メカニズム
著者: 梅田聡
ページ範囲:P.454 - P.456
主観的感情は,内受容感覚の中枢である島皮質,および自律神経活動が介する身体の活動を同時に検討することにより,科学的に扱うことができるようになった。島皮質前部と帯状回前部から成るセイリエンスネットワークは,身体の状態がホメオスタシスから逸脱しているかをモニターし,それを回復の方向に導く役割を持つ。身体状態の逸脱の認識と,自らが置かれた状況の理解が統合されることにより,主観的感情が生み出される。
内受容感覚と感情認識—基礎的概念から臨床研究への展開
著者: 寺澤悠理
ページ範囲:P.457 - P.460
主観的な感情の認識に,身体内部で生じた変化の感じ方は大きな影響を及ぼしている。内受容感覚とは,身体内部環境に関する感覚であり,その認知神経科学的基盤を探ることは,感情認識のメカニズムに関する基礎的な理解を深めるだけでなく,感情に関連した疾患の機序や治療方法を考えるためにも重要である。近年では,脳の予測的符号化理論に基づいて,内受容感覚を理解しようとする立場も台頭し,身体と脳,そしてこころの関係性を検討するための重要な手がかりが提示されている。
覚醒下手術による感情認識に関わる島皮質機能の解明—脳とこころの脳神経外科学・認知神経科学の融合型研究
著者: 本村和也 , 寺澤悠理 , 梅田聡
ページ範囲:P.461 - P.463
島皮質に関わる脳腫瘍患者に対して,表情認識課題[顔写真から表情を認識する課題(怒り,喜び,悲しみ,嫌悪,感情なし)]を用いながら実際に覚醒下手術中に島皮質を直接刺激することで,感情認識に関わる脳機能ネットワーク解析を行った。表情が表す感情の種類,強さの識別に対して検討した。島皮質が,身体内部からの情報である内受容感覚に基づく覚醒度の神経基盤として,怒りや悲しみなどの感情認識の変化に関わることを示唆する。
脳身連関の神経機構:分界条床核の役割
著者: 南雅文
ページ範囲:P.464 - P.466
消化管への伸展刺激が,分界条床核においてノルアドレナリン遊離を促進した。筆者らは,分界条床核内ノルアドレナリン神経伝達亢進が不安・嫌悪を惹起することを報告しており,消化管刺激が分界条床核内ノルアドレナリン神経伝達亢進を介して不安・嫌悪を惹起することが考えられる。一方,分界条床核へのβアドレナリン作動薬投与が,胃の運動を抑制し,大腸の運動は促進した。不安やストレスが分界条床核内ノルアドレナリン神経伝達を亢進して,胃もたれや下痢などの消化管機能障害を惹起することが考えられる。
ELKSによる脳-末梢分泌システムの制御機構
著者: 濱田駿 , 大塚稔久
ページ範囲:P.467 - P.470
ELKSは,生体にユビキタスに発現する全体がコイルドコイル領域から成るタンパク質である。元々,ある種の甲状腺がんで転座している分子として同定されていたが,その後の研究によって様々な細胞機能に関与していることが明らかになってきた。特に,中枢神経のシナプス小胞の分泌や,末梢臓器の内分泌機構(インスリン放出)にも関与することが明らかになっている。本稿では,ELKSによる脳-末梢分泌システムの制御に関する最近の話題と今後の展望について述べる。
Ⅳ.内分泌系と脳の相互作用
脳・消化管ペプチドからみたヒト行動調節
著者: 乾明夫 , 宇都(鮫島)ななみ , 榊弥香
ページ範囲:P.471 - P.474
脳・消化管ペプチドは脳と消化管の双方に存在するペプチドであり,消化管機能,食欲・エネルギー代謝調節や情動,学習,社会行動などに深く関わっている。脳・消化管ペプチドの作用には内因性ペプチドレベルに加え,受容体シグナリングやペプチド作用を修飾する自己抗体,食品由来ペプチドなどが関与している。脳・消化管ペプチドは,心身のストレスとそのレジリエンスにも関わるものと考えられる。
オレキシンと情動
著者: 山中章弘
ページ範囲:P.475 - P.477
睡眠障害の一つである“ナルコレプシー”は,オレキシン神経の特異的脱落によって発症することが知られている。ナルコレプシーの症状は,日中の耐えがたい眠気,睡眠麻痺,入眠時幻覚,情動脱力発作などがある。それらの症状のうち,情動脱力発作は,笑ったり,嬉しかったりしたときなどのポジティブな情動によって発動され,筋の脱力が生じる発作である。本稿では,オレキシンと情動脱力発作について最新の研究成果を含めて紹介する。
うつと糖尿病の悪循環を防止するオレキシン系を介した睡眠・覚醒調節機構
著者: 笹岡利安 , 恒枝宏史
ページ範囲:P.478 - P.480
生活習慣や社会構造が急速に変化した現代社会では,うつ病と肥満・2型糖尿病患者が増加しており,しかもこれらの疾患の発症と進展は連関している1)。インスリン抵抗性や2型糖尿病ではうつの発症と進展は増大し,うつや不眠を伴うと糖尿病は増悪する。しかし,うつとインスリン抵抗性や2型糖尿病を結びつける因子は未知な点が多い。視床下部神経ペプチドのオレキシンは,睡眠・覚醒を制御してエネルギー・糖代謝の恒常性維持に重要な役割を担う。オレキシン神経系の活動は,喜びや怒りなどの情動の感情や社会的活動により高まる一方,うつ状態では低下し,うつ患者の脳脊髄液中オレキシン濃度は低下していることが知られている。本稿では,糖尿病とうつを結ぶ因子としてオレキシンに着目し,オレキシンによる糖代謝調節や,通常およびストレス下におけるインスリン抵抗性防御効果について,筆者らの知見を中心に概説する。
ペプチドによる摂食・エネルギー代謝調節研究の新たな展開
著者: 中里雅光
ページ範囲:P.481 - P.484
ペプチドは内分泌,神経,免疫による生体制御をつかさどる物質である。新規のペプチドの発見は今まで未知であった生体制御系の解明に直結すると共に,病態の理解や新たな創薬にもつながる。近年の研究技術の進歩は,ペプチドの発見や既知のペプチドの新たな役割の解明をもたらしてきた。ペプチド研究は,糖尿病や脂質異常症,肥満症などの病態理解や治療薬開発に大きく貢献している。
食欲制御のコンダクター:グレリン
著者: 佐藤貴弘 , 椎村祐樹 , 梶谷宇 , 岩田想 , 児島将康
ページ範囲:P.485 - P.488
グレリンは胃や十二指腸から分泌されて血液中を循環するホルモンであり,全身に広く分布するグレリン受容体に結合して多彩な生理作用を示す。このような生理作用の多くは脳機能の調節を介して発現すると考えられているが,詳細なメカニズムは未知の部分も多い。本稿では,末梢から分泌されて血液中を循環するグレリンと,中枢から分泌されて神経内分泌因子として作用するグレリンに着目し,グレリンが食欲制御のコンダクターとして機能するメカニズムを中心に概説する。
“やる気”の神経制御機構
著者: 内田俊太郎 , 櫻井武
ページ範囲:P.489 - P.492
やる気・動機付け(motivation)とは,行動を一定の方向に向けて発動させ,維持する過程である。ヒトでは,やる気は意志力といわれることもあり,目標に向かって努力・行動する精神機能のことを指す。本稿では実行機能,報酬系,覚醒という3つのシステムから,行動を支える神経基盤について概説する。
意志力の障害と脳病態
著者: 尾内康臣
ページ範囲:P.493 - P.496
意志力は欲したいという意欲と異なり,実行を伴う欲動的・能動的能力を表し,脳内制御も純粋な意欲の機構と異なると考えられている。脳内には意欲に関連する脳領域は多く報告されているが,共通項はあるものの意志力の脳内機構には未知の部分も多い。本稿では,意欲低下の代表疾患のうつ病と病態を異にする摂食障害や多動性障害の患者脳において,神経炎症とモノアミン神経に着目することで意志力障害の脳病態を考察する。
慢性ストレス負荷と抗うつ剤による脳内モノアミン神経活動のバランス制御
著者: 那波宏之 , 鬼川真紀 , 難波寿明 , 外山英和
ページ範囲:P.497 - P.500
動物個体の精神ストレス感受性や抵抗性(レジリエンス)には,3種モノアミン神経伝達が包括的な影響を及ぼす。精神ストレスが負荷されるとドパミン神経,セロトニン神経,ノルアドレナリン神経はその自律発火頻度を一斉に上昇させ,扁桃体や前頭前野,視床下部などを介して,下垂体や交感神経系などを興奮させることで,覚醒・思考レベルを高め,不安感を惹起し,注意力を亢進させると共に,血圧上昇や心拍数を上げることで,全生体防御システムを駆動させる。
このように,脳内モノアミン神経系はストレス感受性や抵抗性の調節司令塔の役割を担う。一見合理的な生体防御システムに思えるが,過度の精神ストレスや長期にわたるストレス刺激は,逆に意識レベルを下げ,注意力とやる気を低下させ,漫然と恐怖・不安をあおり,血圧上昇や心拍数の調節を不安定化させ,いわゆる“うつ症状”を惹起する。従来の抗うつ剤の薬理学から,セロトニンやノルアドレナリン神経伝達がストレス調節において重要視されているが,最近の研究結果との矛盾も多い。そこで筆者らは,中脳延髄にある各モノアミン神経細胞の自律発火がどのように相互に影響・干渉しているかを探求した。その結果,安静時のドパミン神経活動が最も下流に位置して,ストレス感受性に直接的に影響している可能性が判明した。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.369 - P.369
財団だより フリーアクセス
ページ範囲:P.501 - P.501
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.502 - P.502
基本情報
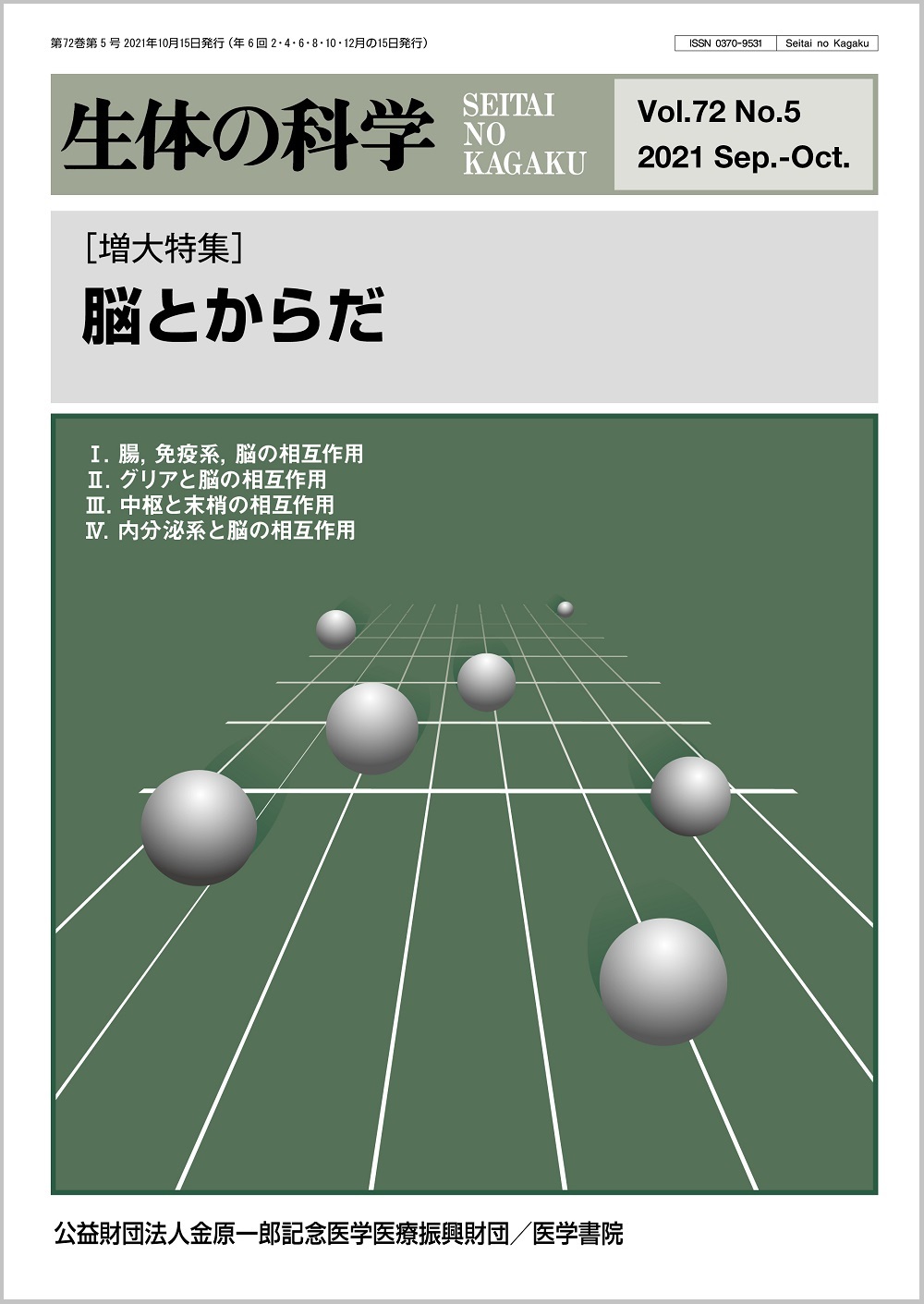
バックナンバー
75巻6号(2024年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅤ:脂肪
75巻5号(2024年10月発行)
増大特集 学術研究支援の最先端
75巻4号(2024年8月発行)
特集 シングルセルオミクス
75巻3号(2024年6月発行)
特集 高速分子動画:動的構造からタンパク質分子制御へ
75巻2号(2024年4月発行)
特集 生命現象を駆動する生体内金属動態の理解と展開
75巻1号(2024年2月発行)
特集 脳と個性
74巻6号(2023年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅣ:骨・軟骨
74巻5号(2023年10月発行)
増大特集 代謝
74巻4号(2023年8月発行)
特集 がん遺伝子の発見は現代医療を進歩させたか
74巻3号(2023年6月発行)
特集 クロマチンによる転写制御機構の最前線
74巻2号(2023年4月発行)
特集 未病の科学
74巻1号(2023年2月発行)
特集 シナプス
73巻6号(2022年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅢ:血管とリンパ管
73巻5号(2022年10月発行)
増大特集 革新脳と関連プロジェクトから見えてきた新しい脳科学
73巻4号(2022年8月発行)
特集 形態形成の統合的理解
73巻3号(2022年6月発行)
特集 リソソーム研究の新展開
73巻2号(2022年4月発行)
特集 DNA修復による生体恒常性の維持
73巻1号(2022年2月発行)
特集 意識
72巻6号(2021年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅡ:骨格筋—今後の研究の発展に向けて
72巻5号(2021年10月発行)
増大特集 脳とからだ
72巻4号(2021年8月発行)
特集 グローバル時代の新興再興感染症への科学的アプローチ
72巻3号(2021年6月発行)
特集 生物物理学の進歩—生命現象の定量的理解へ向けて
72巻2号(2021年4月発行)
特集 組織幹細胞の共通性と特殊性
72巻1号(2021年2月発行)
特集 小脳研究の未来
71巻6号(2020年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅠ:最新の皮膚科学
71巻5号(2020年10月発行)
増大特集 難病研究の進歩
71巻4号(2020年8月発行)
特集 細胞機能の構造生物学
71巻3号(2020年6月発行)
特集 スポーツ科学—2020オリンピック・パラリンピックによせて
71巻2号(2020年4月発行)
特集 ビッグデータ時代のゲノム医学
71巻1号(2020年2月発行)
特集 睡眠の制御と機能
70巻6号(2019年12月発行)
特集 科学と芸術の接点
70巻5号(2019年10月発行)
増大特集 現代医学・生物学の先駆者たち
70巻4号(2019年8月発行)
特集 メカノバイオロジー
70巻3号(2019年6月発行)
特集 免疫チェックポイント分子による生体機能制御
70巻2号(2019年4月発行)
特集 免疫系を介したシステム連関:恒常性の維持と破綻
70巻1号(2019年2月発行)
特集 脳神経回路のダイナミクスから探る脳の発達・疾患・老化
69巻6号(2018年12月発行)
特集 細胞高次機能をつかさどるオルガネラコミュニケーション
69巻5号(2018年10月発行)
増大特集 タンパク質・核酸の分子修飾
69巻4号(2018年8月発行)
特集 いかに創薬を進めるか
69巻3号(2018年6月発行)
特集 生体膜のバイオロジー
69巻2号(2018年4月発行)
特集 宇宙の極限環境から生命体の可塑性をさぐる
69巻1号(2018年2月発行)
特集 社会性と脳
68巻6号(2017年12月発行)
特集 心臓の発生・再生・創生
68巻5号(2017年10月発行)
増大特集 細胞多様性解明に資する光技術─見て,動かす
68巻4号(2017年8月発行)
特集 血管制御系と疾患
68巻3号(2017年6月発行)
特集 核内イベントの時空間制御
68巻2号(2017年4月発行)
特集 細菌叢解析の光と影
68巻1号(2017年2月発行)
特集 大脳皮質—成り立ちから機能へ
67巻6号(2016年12月発行)
特集 時間生物学の新展開
67巻5号(2016年10月発行)
増大特集 病態バイオマーカーの“いま”
67巻4号(2016年8月発行)
特集 認知症・神経変性疾患の克服への挑戦
67巻3号(2016年6月発行)
特集 脂質ワールド
67巻2号(2016年4月発行)
特集 細胞の社会学─細胞間で繰り広げられる協調と競争
67巻1号(2016年2月発行)
特集 記憶ふたたび
66巻6号(2015年12月発行)
特集 グリア研究の最先端
66巻5号(2015年10月発行)
増大特集 細胞シグナル操作法
66巻4号(2015年8月発行)
特集 新興・再興感染症と感染症対策
66巻3号(2015年6月発行)
特集 進化と発生からみた生命科学
66巻2号(2015年4月発行)
特集 使える最新ケミカルバイオロジー
66巻1号(2015年2月発行)
特集 脳と心の謎はどこまで解けたか
65巻6号(2014年12月発行)
特集 エピジェネティクスの今
65巻5号(2014年10月発行)
増大特集 生命動態システム科学
65巻4号(2014年8月発行)
特集 古典的代謝経路の新しい側面
65巻3号(2014年6月発行)
特集 器官の発生と再生の基礎
65巻2号(2014年4月発行)
特集 細胞の少数性と多様性に挑む―シングルセルアナリシス
65巻1号(2014年2月発行)
特集 精神疾患の病理機構
64巻6号(2013年12月発行)
特集 顕微鏡で物を見ることの新しい動き
64巻5号(2013年10月発行)
増大特集 細胞表面受容体
64巻4号(2013年8月発行)
特集 予測と意思決定の神経科学
64巻3号(2013年6月発行)
特集 細胞接着の制御
64巻2号(2013年4月発行)
特集 特殊な幹細胞としての骨格筋サテライト細胞
64巻1号(2013年2月発行)
特集 神経回路の計測と操作
63巻6号(2012年12月発行)
特集 リンパ管
63巻5号(2012年10月発行)
特集 細胞の分子構造と機能―核以外の細胞小器官
63巻4号(2012年8月発行)
特集 質感脳情報学への展望
63巻3号(2012年6月発行)
特集 細胞極性の制御
63巻2号(2012年4月発行)
特集 RNA干渉の実現化に向けて
63巻1号(2012年2月発行)
特集 小脳研究の課題(2)
62巻6号(2011年12月発行)
特集 コピー数変異
62巻5号(2011年10月発行)
特集 細胞核―構造と機能
62巻4号(2011年8月発行)
特集 小脳研究の課題
62巻3号(2011年6月発行)
特集 インフラマソーム
62巻2号(2011年4月発行)
特集 筋ジストロフィーの分子病態から治療へ
62巻1号(2011年2月発行)
特集 摂食制御の分子過程
61巻6号(2010年12月発行)
特集 細胞死か腫瘍化かの選択
61巻5号(2010年10月発行)
特集 シナプスをめぐるシグナリング
61巻4号(2010年8月発行)
特集 miRNA研究の最近の進歩
61巻3号(2010年6月発行)
特集 SNARE複合体-膜融合の機構
61巻2号(2010年4月発行)
特集 糖鎖のかかわる病気:発症機構,診断,治療に向けて
61巻1号(2010年2月発行)
特集 脳科学のモデル実験動物
60巻6号(2009年12月発行)
特集 ユビキチン化による生体機能の調節
60巻5号(2009年10月発行)
特集 伝達物質と受容体
60巻4号(2009年8月発行)
特集 睡眠と脳回路の可塑性
60巻3号(2009年6月発行)
特集 脳と糖脂質
60巻2号(2009年4月発行)
特集 感染症の現代的課題
60巻1号(2009年2月発行)
特集 遺伝子-脳回路-行動
59巻6号(2008年12月発行)
特集 mTORをめぐるシグナルタンパク
59巻5号(2008年10月発行)
特集 現代医学・生物学の仮説・学説2008
59巻4号(2008年8月発行)
特集 免疫学の最近の動向
59巻3号(2008年6月発行)
特集 アディポゲネシス
59巻2号(2008年4月発行)
特集 細胞外基質-研究の新たな展開
59巻1号(2008年2月発行)
特集 コンピュータと脳
58巻6号(2007年12月発行)
特集 グリケーション(糖化)
58巻5号(2007年10月発行)
特集 タンパク質間相互作用
58巻4号(2007年8月発行)
特集 嗅覚受容の分子メカニズム
58巻3号(2007年6月発行)
特集 骨の形成と破壊
58巻2号(2007年4月発行)
特集 シナプス後部構造の形成・機構と制御
58巻1号(2007年2月発行)
特集 意識―脳科学からのアプローチ
57巻6号(2006年12月発行)
特集 血管壁
57巻5号(2006年10月発行)
特集 生物進化の分子マップ
57巻4号(2006年8月発行)
特集 脳科学が求める先端技術
57巻3号(2006年6月発行)
特集 ミエリン化の機構とその異常
57巻2号(2006年4月発行)
特集 膜リサイクリング
57巻1号(2006年2月発行)
特集 こころと脳:とらえがたいものを科学する
56巻6号(2005年12月発行)
特集 構造生物学の現在と今後の展開
56巻5号(2005年10月発行)
特集 タンパク・遺伝子からみた分子病―新しく解明されたメカニズム
56巻4号(2005年8月発行)
特集 脳の遺伝子―どこでどのように働いているのか
56巻3号(2005年6月発行)
特集 Naチャネル
56巻2号(2005年4月発行)
特集 味覚のメカニズムに迫る
56巻1号(2005年2月発行)
特集 情動―喜びと恐れの脳の仕組み
55巻6号(2004年12月発行)
特集 脳の深部を探る
55巻5号(2004年10月発行)
特集 生命科学のNew Key Word
55巻4号(2004年8月発行)
特集 心筋研究の最前線
55巻3号(2004年6月発行)
特集 分子進化学の現在
55巻2号(2004年4月発行)
特集 アダプタータンパク
55巻1号(2004年2月発行)
特集 ニューロンと脳
54巻6号(2003年12月発行)
特集 オートファジー
54巻5号(2003年10月発行)
特集 創薬ゲノミクス・創薬プロテオミクス・創薬インフォマティクス
54巻4号(2003年8月発行)
特集 ラフトと細胞機能
54巻3号(2003年6月発行)
特集 クロマチン
54巻2号(2003年4月発行)
特集 樹状突起
54巻1号(2003年2月発行)
53巻6号(2002年12月発行)
特集 ゲノム全解読とポストゲノムの問題点
53巻5号(2002年10月発行)
特集 加齢の克服―21世紀の課題
53巻4号(2002年8月発行)
特集 一価イオンチャネル
53巻3号(2002年6月発行)
特集 細胞質分裂
53巻2号(2002年4月発行)
特集 RNA
53巻1号(2002年2月発行)
連続座談会 脳とこころ―21世紀の課題
52巻6号(2001年12月発行)
特集 血液脳関門研究の最近の進歩
52巻5号(2001年10月発行)
特集 モチーフ・ドメインリスト
52巻4号(2001年8月発行)
特集 骨格筋研究の新展開
52巻3号(2001年6月発行)
特集 脳の発達に関与する分子機構
52巻2号(2001年4月発行)
特集 情報伝達物質としてのATP
52巻1号(2001年2月発行)
連続座談会 脳を育む
51巻6号(2000年12月発行)
特集 機械的刺激受容の分子機構と細胞応答
51巻5号(2000年10月発行)
特集 ノックアウトマウスリスト
51巻4号(2000年8月発行)
特集 臓器(組織)とアポトーシス
51巻3号(2000年6月発行)
特集 自然免疫における異物認識と排除の分子機構
51巻2号(2000年4月発行)
特集 細胞極性の形成機序
51巻1号(2000年2月発行)
特集 脳を守る21世紀生命科学の展望
50巻6号(1999年12月発行)
特集 細胞内輸送
50巻5号(1999年10月発行)
特集 病気の分子細胞生物学
50巻4号(1999年8月発行)
特集 トランスポーターの構造と機能協関
50巻3号(1999年6月発行)
特集 時間生物学の新たな展開
50巻2号(1999年4月発行)
特集 リソソーム:最近の研究
50巻1号(1999年2月発行)
連続座談会 脳を守る
49巻6号(1998年12月発行)
特集 発生・分化とホメオボックス遺伝子
49巻5号(1998年10月発行)
特集 神経系に作用する薬物マニュアル1998
49巻4号(1998年8月発行)
特集 プロテインキナーゼCの多様な機能
49巻3号(1998年6月発行)
特集 幹細胞研究の新展開
49巻2号(1998年4月発行)
特集 血管―新しい観点から
49巻1号(1998年2月発行)
特集 言語の脳科学
48巻6号(1997年12月発行)
特集 軸索誘導
48巻5号(1997年10月発行)
特集 受容体1997
48巻4号(1997年8月発行)
特集 マトリックス生物学の最前線
48巻3号(1997年6月発行)
特集 開口分泌のメカニズムにおける新しい展開
48巻2号(1997年4月発行)
特集 最近のMAPキナーゼ系
48巻1号(1997年2月発行)
特集 21世紀の脳科学
47巻6号(1996年12月発行)
特集 老化
47巻5号(1996年10月発行)
特集 器官―その新しい視点
47巻4号(1996年8月発行)
特集 エンドサイトーシス
47巻3号(1996年6月発行)
特集 細胞分化
47巻2号(1996年4月発行)
特集 カルシウム動態と細胞機能
47巻1号(1996年2月発行)
特集 神経科学の最前線
46巻6号(1995年12月発行)
特集 病態を変えたよく効く医薬
46巻5号(1995年10月発行)
特集 遺伝子・タンパク質のファミリー・スーパーファミリー
46巻4号(1995年8月発行)
特集 ストレス蛋白質
46巻3号(1995年6月発行)
特集 ライソゾーム
46巻2号(1995年4月発行)
特集 プロテインホスファターゼ―最近の進歩
46巻1号(1995年2月発行)
特集 神経科学の謎
45巻6号(1994年12月発行)
特集 ミトコンドリア
45巻5号(1994年10月発行)
特集 動物の行動機能テスト―個体レベルと分子レベルを結ぶ
45巻4号(1994年8月発行)
特集 造血の機構
45巻3号(1994年6月発行)
特集 染色体
45巻2号(1994年4月発行)
特集 脳と分子生物学
45巻1号(1994年2月発行)
特集 グルコーストランスポーター
44巻6号(1993年12月発行)
特集 滑面小胞体をめぐる諸問題
44巻5号(1993年10月発行)
特集 現代医学・生物学の仮説・学説
44巻4号(1993年8月発行)
特集 細胞接着
44巻3号(1993年6月発行)
特集 カルシウムイオンを介した調節機構の新しい問題点
44巻2号(1993年4月発行)
特集 蛋白質の細胞内転送とその異常
44巻1号(1993年2月発行)
座談会 脳と遺伝子
43巻6号(1992年12月発行)
特集 成長因子受容体/最近の進歩
43巻5号(1992年10月発行)
特集 〈研究室で役に立つ細胞株〉
43巻4号(1992年8月発行)
特集 細胞機能とリン酸化
43巻3号(1992年6月発行)
特集 血管新生
43巻2号(1992年4月発行)
特集 大脳皮質発達の化学的側面
43巻1号(1992年2月発行)
特集 意識と脳
42巻6号(1991年12月発行)
特集 細胞活動の日周リズム
42巻5号(1991年10月発行)
特集 神経系に作用する薬物マニュアル
42巻4号(1991年8月発行)
特集 開口分泌の細胞内過程
42巻3号(1991年6月発行)
特集 ペルオキシソーム/最近の進歩
42巻2号(1991年4月発行)
特集 脳の移植と再生
42巻1号(1991年2月発行)
特集 脳と免疫
41巻6号(1990年12月発行)
特集 注目の実験モデル動物
41巻5号(1990年10月発行)
特集 LTPとLTD:その分子機構
41巻4号(1990年8月発行)
特集 New proteins
41巻3号(1990年6月発行)
特集 シナプスの形成と動態
41巻2号(1990年4月発行)
特集 細胞接着
41巻1号(1990年2月発行)
特集 発がんのメカニズム/最近の知見
40巻6号(1989年12月発行)
特集 ギャップ結合
40巻5号(1989年10月発行)
特集 核内蛋白質
40巻4号(1989年8月発行)
特集 研究室で役に立つ新しい試薬
40巻3号(1989年6月発行)
特集 細胞骨格異常
40巻2号(1989年4月発行)
特集 大脳/神経科学からのアプローチ
40巻1号(1989年2月発行)
特集 分子進化
39巻6号(1988年12月発行)
特集 細胞内における蛋白質局在化機構
39巻5号(1988年10月発行)
特集 細胞測定法マニュアル
39巻4号(1988年8月発行)
特集 細胞外マトリックス
39巻3号(1988年6月発行)
特集 肺の微細構造と機能
39巻2号(1988年4月発行)
特集 生体運動の分子機構/研究の発展
39巻1号(1988年2月発行)
特集 遺伝子疾患解析の発展
38巻6号(1987年12月発行)
-チャンネルの最近の動向
38巻5号(1987年10月発行)
特集 細胞生物学における免疫実験マニュアル
38巻4号(1987年8月発行)
特集 視覚初期過程の分子機構
38巻3号(1987年6月発行)
特集 人間の脳
38巻2号(1987年4月発行)
特集 体液カルシウムのホメオスタシス
38巻1号(1987年2月発行)
特集 医学におけるブレイクスルー/基礎研究からの挑戦
37巻6号(1986年12月発行)
特集 神経活性物質受容体と情報伝達
37巻5号(1986年10月発行)
特集 中間径フィラメント
37巻4号(1986年8月発行)
特集 細胞生物学実験マニュアル
37巻3号(1986年6月発行)
特集 脳の化学的トポグラフィー
37巻2号(1986年4月発行)
特集 血小板凝集
37巻1号(1986年2月発行)
特集 脳のモデル
36巻6号(1985年12月発行)
特集 脂肪組織
36巻5号(1985年10月発行)
特集 細胞分裂をめぐって
36巻4号(1985年8月発行)
特集 神経科学実験マニュアル
36巻3号(1985年6月発行)
特集 血管内皮細胞と微小循環
36巻2号(1985年4月発行)
特集 肝細胞と胆汁酸分泌
36巻1号(1985年2月発行)
特集 Transmembrane Control
35巻6号(1984年12月発行)
特集 細胞毒マニュアル—実験に用いられる細胞毒の知識
35巻5号(1984年10月発行)
特集 中枢神経系の再構築
35巻4号(1984年8月発行)
特集 ゲノムの構造
35巻3号(1984年6月発行)
特集 神経科学の仮説
35巻2号(1984年4月発行)
特集 哺乳類の初期発生
35巻1号(1984年2月発行)
特集 細胞生物学の現状と展望
34巻6号(1983年12月発行)
特集 蛋白質の代謝回転
34巻5号(1983年10月発行)
特集 受容・応答の膜分子論
34巻4号(1983年8月発行)
特集 コンピュータによる生物現象の再構成
34巻3号(1983年6月発行)
特集 細胞の極性
34巻2号(1983年4月発行)
特集 モノアミン系
34巻1号(1983年2月発行)
特集 腸管の吸収機構
33巻6号(1982年12月発行)
特集 低栄養と生体機能
33巻5号(1982年10月発行)
特集 成長因子
33巻4号(1982年8月発行)
特集 リン酸化
33巻3号(1982年6月発行)
特集 神経発生の基礎
33巻2号(1982年4月発行)
特集 細胞の寿命と老化
33巻1号(1982年2月発行)
特集 細胞核
32巻6号(1981年12月発行)
特集 筋小胞体研究の進歩
32巻5号(1981年10月発行)
特集 ペプチド作働性シナプス
32巻4号(1981年8月発行)
特集 膜の転送
32巻3号(1981年6月発行)
特集 リポプロテイン
32巻2号(1981年4月発行)
特集 チャネルの概念と実体
32巻1号(1981年2月発行)
特集 細胞骨格
31巻6号(1980年12月発行)
特集 大脳の機能局在
31巻5号(1980年10月発行)
特集 カルシウムイオン受容タンパク
31巻4号(1980年8月発行)
特集 化学浸透共役仮説
31巻3号(1980年6月発行)
特集 赤血球膜の分子構築
31巻2号(1980年4月発行)
特集 免疫系の情報識別
31巻1号(1980年2月発行)
特集 ゴルジ装置
30巻6号(1979年12月発行)
特集 細胞間コミニケーション
30巻5号(1979年10月発行)
特集 In vitro運動系
30巻4号(1979年8月発行)
輸送系の調節
30巻3号(1979年6月発行)
特集 網膜の構造と機能
30巻2号(1979年4月発行)
特集 神経伝達物質の同定
30巻1号(1979年2月発行)
特集 生物物理学の進歩—第6回国際生物物理学会議より
29巻6号(1978年12月発行)
特集 最近の神経科学から
29巻5号(1978年10月発行)
特集 下垂体:前葉
29巻4号(1978年8月発行)
特集 中枢のペプチド
29巻3号(1978年6月発行)
特集 心臓のリズム発生
29巻2号(1978年4月発行)
特集 腎機能
29巻1号(1978年2月発行)
特集 膜脂質の再検討
28巻6号(1977年12月発行)
特集 青斑核
28巻5号(1977年10月発行)
特集 小胞体
28巻4号(1977年8月発行)
特集 微小管の構造と機能
28巻3号(1977年6月発行)
特集 神経回路網と脳機能
28巻2号(1977年4月発行)
特集 生体の修復
28巻1号(1977年2月発行)
特集 生体の科学の現状と動向
27巻6号(1976年12月発行)
特集 松果体
27巻5号(1976年10月発行)
特集 遺伝マウス・ラット
27巻4号(1976年8月発行)
特集 形質発現における制御
27巻3号(1976年6月発行)
特集 生体と化学的環境
27巻2号(1976年4月発行)
特集 分泌腺
27巻1号(1976年2月発行)
特集 光受容
26巻6号(1975年12月発行)
特集 自律神経と平滑筋の再検討
26巻5号(1975年10月発行)
特集 脳のプログラミング
26巻4号(1975年8月発行)
特集 受精機構をめぐつて
26巻3号(1975年6月発行)
特集 細胞表面と免疫
26巻2号(1975年4月発行)
特集 感覚有毛細胞
26巻1号(1975年2月発行)
特集 体内のセンサー
25巻5号(1974年12月発行)
特集 生体膜—その基本的課題
25巻4号(1974年8月発行)
特集 伝達物質と受容物質
25巻3号(1974年6月発行)
特集 脳の高次機能へのアプローチ
25巻2号(1974年4月発行)
特集 筋細胞の分化
25巻1号(1974年2月発行)
特集 生体の科学 展望と夢
24巻6号(1973年12月発行)
24巻5号(1973年10月発行)
24巻4号(1973年8月発行)
24巻3号(1973年6月発行)
24巻2号(1973年4月発行)
24巻1号(1973年2月発行)
23巻6号(1972年12月発行)
23巻5号(1972年10月発行)
23巻4号(1972年8月発行)
23巻3号(1972年6月発行)
23巻2号(1972年4月発行)
23巻1号(1972年2月発行)
22巻6号(1971年12月発行)
22巻5号(1971年10月発行)
22巻4号(1971年8月発行)
22巻3号(1971年6月発行)
22巻2号(1971年4月発行)
22巻1号(1971年2月発行)
21巻7号(1970年12月発行)
21巻6号(1970年10月発行)
21巻4号(1970年8月発行)
特集 代謝と機能
21巻5号(1970年8月発行)
21巻3号(1970年6月発行)
21巻2号(1970年4月発行)
21巻1号(1970年2月発行)
20巻6号(1969年12月発行)
20巻5号(1969年10月発行)
20巻4号(1969年8月発行)
20巻3号(1969年6月発行)
20巻2号(1969年4月発行)
20巻1号(1969年2月発行)
19巻6号(1968年12月発行)
19巻5号(1968年10月発行)
19巻4号(1968年8月発行)
19巻3号(1968年6月発行)
19巻2号(1968年4月発行)
19巻1号(1968年2月発行)
18巻6号(1967年12月発行)
18巻5号(1967年10月発行)
18巻4号(1967年8月発行)
18巻3号(1967年6月発行)
18巻2号(1967年4月発行)
18巻1号(1967年2月発行)
17巻6号(1966年12月発行)
17巻5号(1966年10月発行)
17巻4号(1966年8月発行)
17巻3号(1966年6月発行)
17巻2号(1966年4月発行)
17巻1号(1966年2月発行)
16巻6号(1965年12月発行)
16巻5号(1965年10月発行)
16巻4号(1965年8月発行)
16巻3号(1965年6月発行)
16巻2号(1965年4月発行)
16巻1号(1965年2月発行)
15巻6号(1964年12月発行)
特集 生体膜その3
15巻5号(1964年10月発行)
特集 生体膜その2
15巻4号(1964年8月発行)
特集 生体膜その1
15巻3号(1964年6月発行)
特集 第13回日本生理科学連合シンポジウム
15巻2号(1964年4月発行)
15巻1号(1964年2月発行)
14巻6号(1963年12月発行)
特集 興奮收縮伝関
14巻5号(1963年10月発行)
14巻4号(1963年8月発行)
14巻3号(1963年6月発行)
14巻1号(1963年2月発行)
特集 第9回中枢神経系の生理学シンポジウム
14巻2号(1963年2月発行)
13巻6号(1962年12月発行)
13巻5号(1962年10月発行)
特集 生物々理—生理学生物々理若手グループ第1回ミーティングから
13巻4号(1962年8月発行)
13巻3号(1962年6月発行)
13巻2号(1962年4月発行)
Symposium on Permeability of Biological Membranes
13巻1号(1962年2月発行)
12巻6号(1961年12月発行)
12巻5号(1961年10月発行)
12巻4号(1961年8月発行)
12巻3号(1961年6月発行)
12巻2号(1961年4月発行)
12巻1号(1961年2月発行)
11巻6号(1960年12月発行)
Symposium On Active Transport
11巻5号(1960年10月発行)
11巻4号(1960年8月発行)
11巻3号(1960年6月発行)
11巻2号(1960年4月発行)
11巻1号(1960年2月発行)
10巻6号(1959年12月発行)
10巻5号(1959年10月発行)
10巻4号(1959年8月発行)
10巻3号(1959年6月発行)
10巻2号(1959年4月発行)
10巻1号(1959年2月発行)
8巻6号(1957年12月発行)
8巻5号(1957年10月発行)
特集 酵素と生物
8巻4号(1957年8月発行)
8巻3号(1957年6月発行)
8巻2号(1957年4月発行)
8巻1号(1957年2月発行)
