75巻6号(2024年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅤ:脂肪
75巻5号(2024年10月発行)
増大特集 学術研究支援の最先端
75巻4号(2024年8月発行)
特集 シングルセルオミクス
75巻3号(2024年6月発行)
特集 高速分子動画:動的構造からタンパク質分子制御へ
75巻2号(2024年4月発行)
特集 生命現象を駆動する生体内金属動態の理解と展開
75巻1号(2024年2月発行)
特集 脳と個性
生体の科学72巻6号
2021年12月発行
雑誌目次
特集 新組織学シリーズⅡ:骨格筋—今後の研究の発展に向けて
特集「新組織学シリーズⅡ:骨格筋—今後の研究の発展に向けて」によせて フリーアクセス
著者: 武田伸一
ページ範囲:P.504 - P.504
Ⅰ.骨格筋収縮研究の多様な側面
筋小胞体カルシウムポンプの構造とイオン輸送機構
著者: 豊島近
ページ範囲:P.505 - P.509
人工ナノ筋肉を用いた筋収縮原理の解明
著者: 岩城光宏 , 柳田敏雄
ページ範囲:P.510 - P.514
昆虫の筋肉が教えていること
著者: 岩本裕之
ページ範囲:P.515 - P.518
Ⅱ.骨格筋組織を支える細胞の役割・応答
筋サテライト細胞の適応
著者: 中村彩紗 , 深田宗一朗
ページ範囲:P.519 - P.521
間質の間葉系前駆細胞とサルコペニア
著者: 上住円 , 上住聡芳
ページ範囲:P.522 - P.526
神経筋接合部(NMJ)の形成・維持メカニズム—NMJを標的とした治療技術の開発を目指して
著者: 江口貴大 , 山梨裕司
ページ範囲:P.527 - P.531
骨格筋のメカノバイオロジー
著者: 平野航太郎 , 鈴木美希 , 原雄二
ページ範囲:P.532 - P.536
Ⅲ.骨格筋を障害する疾患の注目すべき病態
糖尿病とサルコペニア
著者: 平田悠 , 小川渉
ページ範囲:P.537 - P.541
自己免疫性筋炎—新たな疾患概念と分類
著者: 西森裕佳子 , 西野一三
ページ範囲:P.542 - P.548
鏡-緒方症候群の筋発生異常の原因となる真獣類特異的遺伝子
著者: 石野史敏 , 北澤萌恵 , 金児-石野知子
ページ範囲:P.549 - P.554
筋チャネル病の新たな病態
著者: 久保田智哉 , 髙橋正紀
ページ範囲:P.555 - P.559
CGGリピートと筋疾患
著者: 石浦浩之
ページ範囲:P.560 - P.564
デュシェンヌ型筋ジストロフィーの中枢神経障害
著者: 橋本泰昌 , 青木吉嗣
ページ範囲:P.565 - P.568
ベッカー型筋ジストロフィーと中枢神経障害
著者: 森まどか
ページ範囲:P.569 - P.572
Ⅳ.遺伝性筋疾患研究を起点とした治療原理の進展
糖鎖の新たな理解をもとにした筋ジストロフィー治療法の開発
著者: 金川基
ページ範囲:P.573 - P.576
RNA制御機構の解析で明らかとなるRNA病の病態解明と新規治療法開発
著者: 細川元靖 , 萩原正敏
ページ範囲:P.577 - P.581
治療法の開発を見据えた筋強直性ジストロフィーの新たな病態の解明
著者: 中森雅之
ページ範囲:P.582 - P.585
アンチセンス核酸医薬の発展とデリバリー手法の開発
著者: 丸山理香 , 横田俊文
ページ範囲:P.586 - P.590
連載講座 ヒトを知るモデル動物としてのゼブラフィッシュ-2
トランスポゾンを用いたゼブラフィッシュの遺伝学—遺伝子トラップ法〜Gal4-UAS法 フリーアクセス
著者: 川上浩一
ページ範囲:P.591 - P.595
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.531 - P.531
財団だより フリーアクセス
ページ範囲:P.548 - P.548
あとがき フリーアクセス
著者: 編集者一同
ページ範囲:P.596 - P.596
生体の科学 第72巻 総目次 フリーアクセス
ページ範囲:P. - P.
基本情報
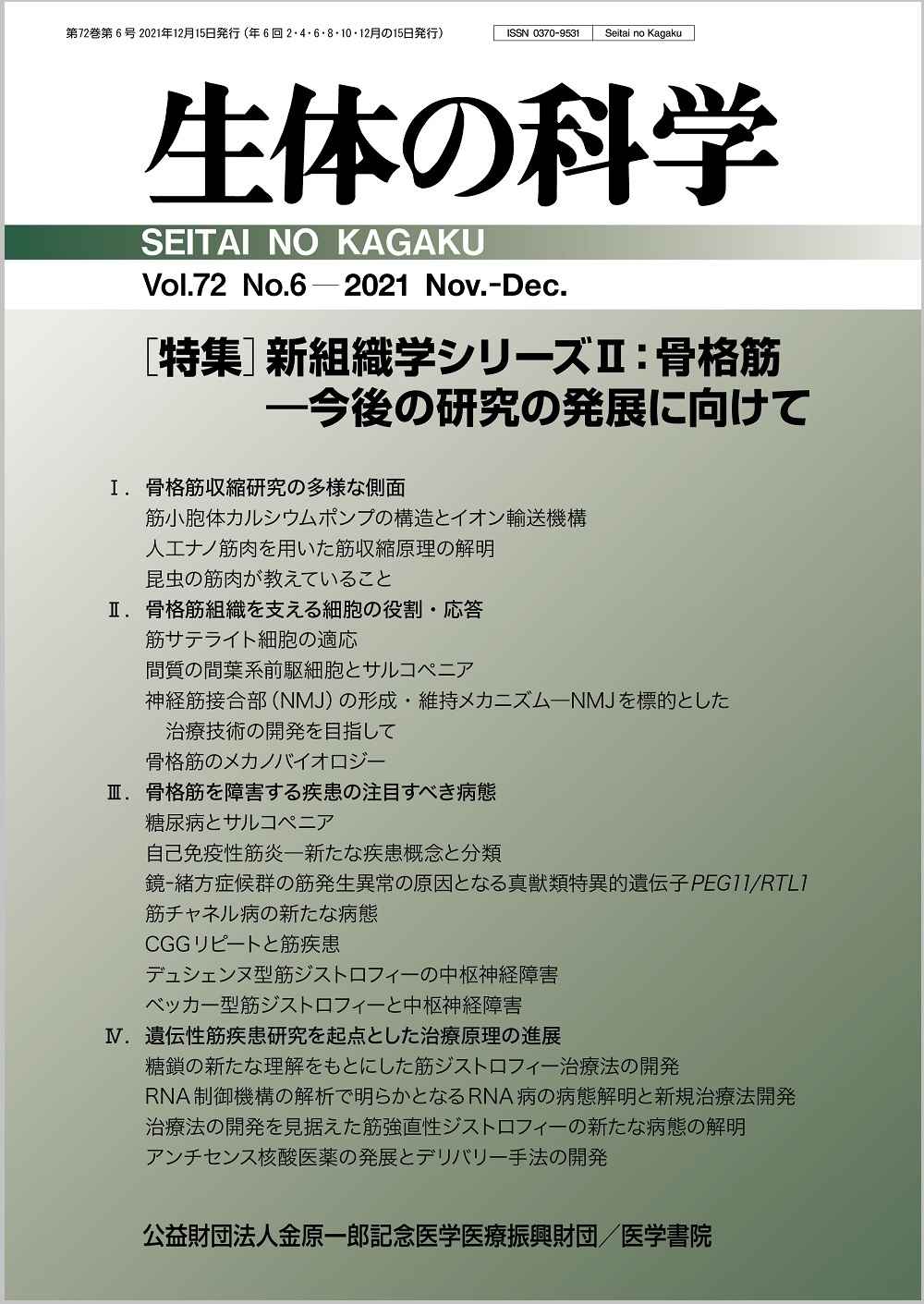
バックナンバー
75巻6号(2024年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅤ:脂肪
75巻5号(2024年10月発行)
増大特集 学術研究支援の最先端
75巻4号(2024年8月発行)
特集 シングルセルオミクス
75巻3号(2024年6月発行)
特集 高速分子動画:動的構造からタンパク質分子制御へ
75巻2号(2024年4月発行)
特集 生命現象を駆動する生体内金属動態の理解と展開
75巻1号(2024年2月発行)
特集 脳と個性
74巻6号(2023年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅣ:骨・軟骨
74巻5号(2023年10月発行)
増大特集 代謝
74巻4号(2023年8月発行)
特集 がん遺伝子の発見は現代医療を進歩させたか
74巻3号(2023年6月発行)
特集 クロマチンによる転写制御機構の最前線
74巻2号(2023年4月発行)
特集 未病の科学
74巻1号(2023年2月発行)
特集 シナプス
73巻6号(2022年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅢ:血管とリンパ管
73巻5号(2022年10月発行)
増大特集 革新脳と関連プロジェクトから見えてきた新しい脳科学
73巻4号(2022年8月発行)
特集 形態形成の統合的理解
73巻3号(2022年6月発行)
特集 リソソーム研究の新展開
73巻2号(2022年4月発行)
特集 DNA修復による生体恒常性の維持
73巻1号(2022年2月発行)
特集 意識
72巻6号(2021年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅡ:骨格筋—今後の研究の発展に向けて
72巻5号(2021年10月発行)
増大特集 脳とからだ
72巻4号(2021年8月発行)
特集 グローバル時代の新興再興感染症への科学的アプローチ
72巻3号(2021年6月発行)
特集 生物物理学の進歩—生命現象の定量的理解へ向けて
72巻2号(2021年4月発行)
特集 組織幹細胞の共通性と特殊性
72巻1号(2021年2月発行)
特集 小脳研究の未来
71巻6号(2020年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅠ:最新の皮膚科学
71巻5号(2020年10月発行)
増大特集 難病研究の進歩
71巻4号(2020年8月発行)
特集 細胞機能の構造生物学
71巻3号(2020年6月発行)
特集 スポーツ科学—2020オリンピック・パラリンピックによせて
71巻2号(2020年4月発行)
特集 ビッグデータ時代のゲノム医学
71巻1号(2020年2月発行)
特集 睡眠の制御と機能
70巻6号(2019年12月発行)
特集 科学と芸術の接点
70巻5号(2019年10月発行)
増大特集 現代医学・生物学の先駆者たち
70巻4号(2019年8月発行)
特集 メカノバイオロジー
70巻3号(2019年6月発行)
特集 免疫チェックポイント分子による生体機能制御
70巻2号(2019年4月発行)
特集 免疫系を介したシステム連関:恒常性の維持と破綻
70巻1号(2019年2月発行)
特集 脳神経回路のダイナミクスから探る脳の発達・疾患・老化
69巻6号(2018年12月発行)
特集 細胞高次機能をつかさどるオルガネラコミュニケーション
69巻5号(2018年10月発行)
増大特集 タンパク質・核酸の分子修飾
69巻4号(2018年8月発行)
特集 いかに創薬を進めるか
69巻3号(2018年6月発行)
特集 生体膜のバイオロジー
69巻2号(2018年4月発行)
特集 宇宙の極限環境から生命体の可塑性をさぐる
69巻1号(2018年2月発行)
特集 社会性と脳
68巻6号(2017年12月発行)
特集 心臓の発生・再生・創生
68巻5号(2017年10月発行)
増大特集 細胞多様性解明に資する光技術─見て,動かす
68巻4号(2017年8月発行)
特集 血管制御系と疾患
68巻3号(2017年6月発行)
特集 核内イベントの時空間制御
68巻2号(2017年4月発行)
特集 細菌叢解析の光と影
68巻1号(2017年2月発行)
特集 大脳皮質—成り立ちから機能へ
67巻6号(2016年12月発行)
特集 時間生物学の新展開
67巻5号(2016年10月発行)
増大特集 病態バイオマーカーの“いま”
67巻4号(2016年8月発行)
特集 認知症・神経変性疾患の克服への挑戦
67巻3号(2016年6月発行)
特集 脂質ワールド
67巻2号(2016年4月発行)
特集 細胞の社会学─細胞間で繰り広げられる協調と競争
67巻1号(2016年2月発行)
特集 記憶ふたたび
66巻6号(2015年12月発行)
特集 グリア研究の最先端
66巻5号(2015年10月発行)
増大特集 細胞シグナル操作法
66巻4号(2015年8月発行)
特集 新興・再興感染症と感染症対策
66巻3号(2015年6月発行)
特集 進化と発生からみた生命科学
66巻2号(2015年4月発行)
特集 使える最新ケミカルバイオロジー
66巻1号(2015年2月発行)
特集 脳と心の謎はどこまで解けたか
65巻6号(2014年12月発行)
特集 エピジェネティクスの今
65巻5号(2014年10月発行)
増大特集 生命動態システム科学
65巻4号(2014年8月発行)
特集 古典的代謝経路の新しい側面
65巻3号(2014年6月発行)
特集 器官の発生と再生の基礎
65巻2号(2014年4月発行)
特集 細胞の少数性と多様性に挑む―シングルセルアナリシス
65巻1号(2014年2月発行)
特集 精神疾患の病理機構
64巻6号(2013年12月発行)
特集 顕微鏡で物を見ることの新しい動き
64巻5号(2013年10月発行)
増大特集 細胞表面受容体
64巻4号(2013年8月発行)
特集 予測と意思決定の神経科学
64巻3号(2013年6月発行)
特集 細胞接着の制御
64巻2号(2013年4月発行)
特集 特殊な幹細胞としての骨格筋サテライト細胞
64巻1号(2013年2月発行)
特集 神経回路の計測と操作
63巻6号(2012年12月発行)
特集 リンパ管
63巻5号(2012年10月発行)
特集 細胞の分子構造と機能―核以外の細胞小器官
63巻4号(2012年8月発行)
特集 質感脳情報学への展望
63巻3号(2012年6月発行)
特集 細胞極性の制御
63巻2号(2012年4月発行)
特集 RNA干渉の実現化に向けて
63巻1号(2012年2月発行)
特集 小脳研究の課題(2)
62巻6号(2011年12月発行)
特集 コピー数変異
62巻5号(2011年10月発行)
特集 細胞核―構造と機能
62巻4号(2011年8月発行)
特集 小脳研究の課題
62巻3号(2011年6月発行)
特集 インフラマソーム
62巻2号(2011年4月発行)
特集 筋ジストロフィーの分子病態から治療へ
62巻1号(2011年2月発行)
特集 摂食制御の分子過程
61巻6号(2010年12月発行)
特集 細胞死か腫瘍化かの選択
61巻5号(2010年10月発行)
特集 シナプスをめぐるシグナリング
61巻4号(2010年8月発行)
特集 miRNA研究の最近の進歩
61巻3号(2010年6月発行)
特集 SNARE複合体-膜融合の機構
61巻2号(2010年4月発行)
特集 糖鎖のかかわる病気:発症機構,診断,治療に向けて
61巻1号(2010年2月発行)
特集 脳科学のモデル実験動物
60巻6号(2009年12月発行)
特集 ユビキチン化による生体機能の調節
60巻5号(2009年10月発行)
特集 伝達物質と受容体
60巻4号(2009年8月発行)
特集 睡眠と脳回路の可塑性
60巻3号(2009年6月発行)
特集 脳と糖脂質
60巻2号(2009年4月発行)
特集 感染症の現代的課題
60巻1号(2009年2月発行)
特集 遺伝子-脳回路-行動
59巻6号(2008年12月発行)
特集 mTORをめぐるシグナルタンパク
59巻5号(2008年10月発行)
特集 現代医学・生物学の仮説・学説2008
59巻4号(2008年8月発行)
特集 免疫学の最近の動向
59巻3号(2008年6月発行)
特集 アディポゲネシス
59巻2号(2008年4月発行)
特集 細胞外基質-研究の新たな展開
59巻1号(2008年2月発行)
特集 コンピュータと脳
58巻6号(2007年12月発行)
特集 グリケーション(糖化)
58巻5号(2007年10月発行)
特集 タンパク質間相互作用
58巻4号(2007年8月発行)
特集 嗅覚受容の分子メカニズム
58巻3号(2007年6月発行)
特集 骨の形成と破壊
58巻2号(2007年4月発行)
特集 シナプス後部構造の形成・機構と制御
58巻1号(2007年2月発行)
特集 意識―脳科学からのアプローチ
57巻6号(2006年12月発行)
特集 血管壁
57巻5号(2006年10月発行)
特集 生物進化の分子マップ
57巻4号(2006年8月発行)
特集 脳科学が求める先端技術
57巻3号(2006年6月発行)
特集 ミエリン化の機構とその異常
57巻2号(2006年4月発行)
特集 膜リサイクリング
57巻1号(2006年2月発行)
特集 こころと脳:とらえがたいものを科学する
56巻6号(2005年12月発行)
特集 構造生物学の現在と今後の展開
56巻5号(2005年10月発行)
特集 タンパク・遺伝子からみた分子病―新しく解明されたメカニズム
56巻4号(2005年8月発行)
特集 脳の遺伝子―どこでどのように働いているのか
56巻3号(2005年6月発行)
特集 Naチャネル
56巻2号(2005年4月発行)
特集 味覚のメカニズムに迫る
56巻1号(2005年2月発行)
特集 情動―喜びと恐れの脳の仕組み
55巻6号(2004年12月発行)
特集 脳の深部を探る
55巻5号(2004年10月発行)
特集 生命科学のNew Key Word
55巻4号(2004年8月発行)
特集 心筋研究の最前線
55巻3号(2004年6月発行)
特集 分子進化学の現在
55巻2号(2004年4月発行)
特集 アダプタータンパク
55巻1号(2004年2月発行)
特集 ニューロンと脳
54巻6号(2003年12月発行)
特集 オートファジー
54巻5号(2003年10月発行)
特集 創薬ゲノミクス・創薬プロテオミクス・創薬インフォマティクス
54巻4号(2003年8月発行)
特集 ラフトと細胞機能
54巻3号(2003年6月発行)
特集 クロマチン
54巻2号(2003年4月発行)
特集 樹状突起
54巻1号(2003年2月発行)
53巻6号(2002年12月発行)
特集 ゲノム全解読とポストゲノムの問題点
53巻5号(2002年10月発行)
特集 加齢の克服―21世紀の課題
53巻4号(2002年8月発行)
特集 一価イオンチャネル
53巻3号(2002年6月発行)
特集 細胞質分裂
53巻2号(2002年4月発行)
特集 RNA
53巻1号(2002年2月発行)
連続座談会 脳とこころ―21世紀の課題
52巻6号(2001年12月発行)
特集 血液脳関門研究の最近の進歩
52巻5号(2001年10月発行)
特集 モチーフ・ドメインリスト
52巻4号(2001年8月発行)
特集 骨格筋研究の新展開
52巻3号(2001年6月発行)
特集 脳の発達に関与する分子機構
52巻2号(2001年4月発行)
特集 情報伝達物質としてのATP
52巻1号(2001年2月発行)
連続座談会 脳を育む
51巻6号(2000年12月発行)
特集 機械的刺激受容の分子機構と細胞応答
51巻5号(2000年10月発行)
特集 ノックアウトマウスリスト
51巻4号(2000年8月発行)
特集 臓器(組織)とアポトーシス
51巻3号(2000年6月発行)
特集 自然免疫における異物認識と排除の分子機構
51巻2号(2000年4月発行)
特集 細胞極性の形成機序
51巻1号(2000年2月発行)
特集 脳を守る21世紀生命科学の展望
50巻6号(1999年12月発行)
特集 細胞内輸送
50巻5号(1999年10月発行)
特集 病気の分子細胞生物学
50巻4号(1999年8月発行)
特集 トランスポーターの構造と機能協関
50巻3号(1999年6月発行)
特集 時間生物学の新たな展開
50巻2号(1999年4月発行)
特集 リソソーム:最近の研究
50巻1号(1999年2月発行)
連続座談会 脳を守る
49巻6号(1998年12月発行)
特集 発生・分化とホメオボックス遺伝子
49巻5号(1998年10月発行)
特集 神経系に作用する薬物マニュアル1998
49巻4号(1998年8月発行)
特集 プロテインキナーゼCの多様な機能
49巻3号(1998年6月発行)
特集 幹細胞研究の新展開
49巻2号(1998年4月発行)
特集 血管―新しい観点から
49巻1号(1998年2月発行)
特集 言語の脳科学
48巻6号(1997年12月発行)
特集 軸索誘導
48巻5号(1997年10月発行)
特集 受容体1997
48巻4号(1997年8月発行)
特集 マトリックス生物学の最前線
48巻3号(1997年6月発行)
特集 開口分泌のメカニズムにおける新しい展開
48巻2号(1997年4月発行)
特集 最近のMAPキナーゼ系
48巻1号(1997年2月発行)
特集 21世紀の脳科学
47巻6号(1996年12月発行)
特集 老化
47巻5号(1996年10月発行)
特集 器官―その新しい視点
47巻4号(1996年8月発行)
特集 エンドサイトーシス
47巻3号(1996年6月発行)
特集 細胞分化
47巻2号(1996年4月発行)
特集 カルシウム動態と細胞機能
47巻1号(1996年2月発行)
特集 神経科学の最前線
46巻6号(1995年12月発行)
特集 病態を変えたよく効く医薬
46巻5号(1995年10月発行)
特集 遺伝子・タンパク質のファミリー・スーパーファミリー
46巻4号(1995年8月発行)
特集 ストレス蛋白質
46巻3号(1995年6月発行)
特集 ライソゾーム
46巻2号(1995年4月発行)
特集 プロテインホスファターゼ―最近の進歩
46巻1号(1995年2月発行)
特集 神経科学の謎
45巻6号(1994年12月発行)
特集 ミトコンドリア
45巻5号(1994年10月発行)
特集 動物の行動機能テスト―個体レベルと分子レベルを結ぶ
45巻4号(1994年8月発行)
特集 造血の機構
45巻3号(1994年6月発行)
特集 染色体
45巻2号(1994年4月発行)
特集 脳と分子生物学
45巻1号(1994年2月発行)
特集 グルコーストランスポーター
44巻6号(1993年12月発行)
特集 滑面小胞体をめぐる諸問題
44巻5号(1993年10月発行)
特集 現代医学・生物学の仮説・学説
44巻4号(1993年8月発行)
特集 細胞接着
44巻3号(1993年6月発行)
特集 カルシウムイオンを介した調節機構の新しい問題点
44巻2号(1993年4月発行)
特集 蛋白質の細胞内転送とその異常
44巻1号(1993年2月発行)
座談会 脳と遺伝子
43巻6号(1992年12月発行)
特集 成長因子受容体/最近の進歩
43巻5号(1992年10月発行)
特集 〈研究室で役に立つ細胞株〉
43巻4号(1992年8月発行)
特集 細胞機能とリン酸化
43巻3号(1992年6月発行)
特集 血管新生
43巻2号(1992年4月発行)
特集 大脳皮質発達の化学的側面
43巻1号(1992年2月発行)
特集 意識と脳
42巻6号(1991年12月発行)
特集 細胞活動の日周リズム
42巻5号(1991年10月発行)
特集 神経系に作用する薬物マニュアル
42巻4号(1991年8月発行)
特集 開口分泌の細胞内過程
42巻3号(1991年6月発行)
特集 ペルオキシソーム/最近の進歩
42巻2号(1991年4月発行)
特集 脳の移植と再生
42巻1号(1991年2月発行)
特集 脳と免疫
41巻6号(1990年12月発行)
特集 注目の実験モデル動物
41巻5号(1990年10月発行)
特集 LTPとLTD:その分子機構
41巻4号(1990年8月発行)
特集 New proteins
41巻3号(1990年6月発行)
特集 シナプスの形成と動態
41巻2号(1990年4月発行)
特集 細胞接着
41巻1号(1990年2月発行)
特集 発がんのメカニズム/最近の知見
40巻6号(1989年12月発行)
特集 ギャップ結合
40巻5号(1989年10月発行)
特集 核内蛋白質
40巻4号(1989年8月発行)
特集 研究室で役に立つ新しい試薬
40巻3号(1989年6月発行)
特集 細胞骨格異常
40巻2号(1989年4月発行)
特集 大脳/神経科学からのアプローチ
40巻1号(1989年2月発行)
特集 分子進化
39巻6号(1988年12月発行)
特集 細胞内における蛋白質局在化機構
39巻5号(1988年10月発行)
特集 細胞測定法マニュアル
39巻4号(1988年8月発行)
特集 細胞外マトリックス
39巻3号(1988年6月発行)
特集 肺の微細構造と機能
39巻2号(1988年4月発行)
特集 生体運動の分子機構/研究の発展
39巻1号(1988年2月発行)
特集 遺伝子疾患解析の発展
38巻6号(1987年12月発行)
-チャンネルの最近の動向
38巻5号(1987年10月発行)
特集 細胞生物学における免疫実験マニュアル
38巻4号(1987年8月発行)
特集 視覚初期過程の分子機構
38巻3号(1987年6月発行)
特集 人間の脳
38巻2号(1987年4月発行)
特集 体液カルシウムのホメオスタシス
38巻1号(1987年2月発行)
特集 医学におけるブレイクスルー/基礎研究からの挑戦
37巻6号(1986年12月発行)
特集 神経活性物質受容体と情報伝達
37巻5号(1986年10月発行)
特集 中間径フィラメント
37巻4号(1986年8月発行)
特集 細胞生物学実験マニュアル
37巻3号(1986年6月発行)
特集 脳の化学的トポグラフィー
37巻2号(1986年4月発行)
特集 血小板凝集
37巻1号(1986年2月発行)
特集 脳のモデル
36巻6号(1985年12月発行)
特集 脂肪組織
36巻5号(1985年10月発行)
特集 細胞分裂をめぐって
36巻4号(1985年8月発行)
特集 神経科学実験マニュアル
36巻3号(1985年6月発行)
特集 血管内皮細胞と微小循環
36巻2号(1985年4月発行)
特集 肝細胞と胆汁酸分泌
36巻1号(1985年2月発行)
特集 Transmembrane Control
35巻6号(1984年12月発行)
特集 細胞毒マニュアル—実験に用いられる細胞毒の知識
35巻5号(1984年10月発行)
特集 中枢神経系の再構築
35巻4号(1984年8月発行)
特集 ゲノムの構造
35巻3号(1984年6月発行)
特集 神経科学の仮説
35巻2号(1984年4月発行)
特集 哺乳類の初期発生
35巻1号(1984年2月発行)
特集 細胞生物学の現状と展望
34巻6号(1983年12月発行)
特集 蛋白質の代謝回転
34巻5号(1983年10月発行)
特集 受容・応答の膜分子論
34巻4号(1983年8月発行)
特集 コンピュータによる生物現象の再構成
34巻3号(1983年6月発行)
特集 細胞の極性
34巻2号(1983年4月発行)
特集 モノアミン系
34巻1号(1983年2月発行)
特集 腸管の吸収機構
33巻6号(1982年12月発行)
特集 低栄養と生体機能
33巻5号(1982年10月発行)
特集 成長因子
33巻4号(1982年8月発行)
特集 リン酸化
33巻3号(1982年6月発行)
特集 神経発生の基礎
33巻2号(1982年4月発行)
特集 細胞の寿命と老化
33巻1号(1982年2月発行)
特集 細胞核
32巻6号(1981年12月発行)
特集 筋小胞体研究の進歩
32巻5号(1981年10月発行)
特集 ペプチド作働性シナプス
32巻4号(1981年8月発行)
特集 膜の転送
32巻3号(1981年6月発行)
特集 リポプロテイン
32巻2号(1981年4月発行)
特集 チャネルの概念と実体
32巻1号(1981年2月発行)
特集 細胞骨格
31巻6号(1980年12月発行)
特集 大脳の機能局在
31巻5号(1980年10月発行)
特集 カルシウムイオン受容タンパク
31巻4号(1980年8月発行)
特集 化学浸透共役仮説
31巻3号(1980年6月発行)
特集 赤血球膜の分子構築
31巻2号(1980年4月発行)
特集 免疫系の情報識別
31巻1号(1980年2月発行)
特集 ゴルジ装置
30巻6号(1979年12月発行)
特集 細胞間コミニケーション
30巻5号(1979年10月発行)
特集 In vitro運動系
30巻4号(1979年8月発行)
輸送系の調節
30巻3号(1979年6月発行)
特集 網膜の構造と機能
30巻2号(1979年4月発行)
特集 神経伝達物質の同定
30巻1号(1979年2月発行)
特集 生物物理学の進歩—第6回国際生物物理学会議より
29巻6号(1978年12月発行)
特集 最近の神経科学から
29巻5号(1978年10月発行)
特集 下垂体:前葉
29巻4号(1978年8月発行)
特集 中枢のペプチド
29巻3号(1978年6月発行)
特集 心臓のリズム発生
29巻2号(1978年4月発行)
特集 腎機能
29巻1号(1978年2月発行)
特集 膜脂質の再検討
28巻6号(1977年12月発行)
特集 青斑核
28巻5号(1977年10月発行)
特集 小胞体
28巻4号(1977年8月発行)
特集 微小管の構造と機能
28巻3号(1977年6月発行)
特集 神経回路網と脳機能
28巻2号(1977年4月発行)
特集 生体の修復
28巻1号(1977年2月発行)
特集 生体の科学の現状と動向
27巻6号(1976年12月発行)
特集 松果体
27巻5号(1976年10月発行)
特集 遺伝マウス・ラット
27巻4号(1976年8月発行)
特集 形質発現における制御
27巻3号(1976年6月発行)
特集 生体と化学的環境
27巻2号(1976年4月発行)
特集 分泌腺
27巻1号(1976年2月発行)
特集 光受容
26巻6号(1975年12月発行)
特集 自律神経と平滑筋の再検討
26巻5号(1975年10月発行)
特集 脳のプログラミング
26巻4号(1975年8月発行)
特集 受精機構をめぐつて
26巻3号(1975年6月発行)
特集 細胞表面と免疫
26巻2号(1975年4月発行)
特集 感覚有毛細胞
26巻1号(1975年2月発行)
特集 体内のセンサー
25巻5号(1974年12月発行)
特集 生体膜—その基本的課題
25巻4号(1974年8月発行)
特集 伝達物質と受容物質
25巻3号(1974年6月発行)
特集 脳の高次機能へのアプローチ
25巻2号(1974年4月発行)
特集 筋細胞の分化
25巻1号(1974年2月発行)
特集 生体の科学 展望と夢
24巻6号(1973年12月発行)
24巻5号(1973年10月発行)
24巻4号(1973年8月発行)
24巻3号(1973年6月発行)
24巻2号(1973年4月発行)
24巻1号(1973年2月発行)
23巻6号(1972年12月発行)
23巻5号(1972年10月発行)
23巻4号(1972年8月発行)
23巻3号(1972年6月発行)
23巻2号(1972年4月発行)
23巻1号(1972年2月発行)
22巻6号(1971年12月発行)
22巻5号(1971年10月発行)
22巻4号(1971年8月発行)
22巻3号(1971年6月発行)
22巻2号(1971年4月発行)
22巻1号(1971年2月発行)
21巻7号(1970年12月発行)
21巻6号(1970年10月発行)
21巻4号(1970年8月発行)
特集 代謝と機能
21巻5号(1970年8月発行)
21巻3号(1970年6月発行)
21巻2号(1970年4月発行)
21巻1号(1970年2月発行)
20巻6号(1969年12月発行)
20巻5号(1969年10月発行)
20巻4号(1969年8月発行)
20巻3号(1969年6月発行)
20巻2号(1969年4月発行)
20巻1号(1969年2月発行)
19巻6号(1968年12月発行)
19巻5号(1968年10月発行)
19巻4号(1968年8月発行)
19巻3号(1968年6月発行)
19巻2号(1968年4月発行)
19巻1号(1968年2月発行)
18巻6号(1967年12月発行)
18巻5号(1967年10月発行)
18巻4号(1967年8月発行)
18巻3号(1967年6月発行)
18巻2号(1967年4月発行)
18巻1号(1967年2月発行)
17巻6号(1966年12月発行)
17巻5号(1966年10月発行)
17巻4号(1966年8月発行)
17巻3号(1966年6月発行)
17巻2号(1966年4月発行)
17巻1号(1966年2月発行)
16巻6号(1965年12月発行)
16巻5号(1965年10月発行)
16巻4号(1965年8月発行)
16巻3号(1965年6月発行)
16巻2号(1965年4月発行)
16巻1号(1965年2月発行)
15巻6号(1964年12月発行)
特集 生体膜その3
15巻5号(1964年10月発行)
特集 生体膜その2
15巻4号(1964年8月発行)
特集 生体膜その1
15巻3号(1964年6月発行)
特集 第13回日本生理科学連合シンポジウム
15巻2号(1964年4月発行)
15巻1号(1964年2月発行)
14巻6号(1963年12月発行)
特集 興奮收縮伝関
14巻5号(1963年10月発行)
14巻4号(1963年8月発行)
14巻3号(1963年6月発行)
14巻1号(1963年2月発行)
特集 第9回中枢神経系の生理学シンポジウム
14巻2号(1963年2月発行)
13巻6号(1962年12月発行)
13巻5号(1962年10月発行)
特集 生物々理—生理学生物々理若手グループ第1回ミーティングから
13巻4号(1962年8月発行)
13巻3号(1962年6月発行)
13巻2号(1962年4月発行)
Symposium on Permeability of Biological Membranes
13巻1号(1962年2月発行)
12巻6号(1961年12月発行)
12巻5号(1961年10月発行)
12巻4号(1961年8月発行)
12巻3号(1961年6月発行)
12巻2号(1961年4月発行)
12巻1号(1961年2月発行)
11巻6号(1960年12月発行)
Symposium On Active Transport
11巻5号(1960年10月発行)
11巻4号(1960年8月発行)
11巻3号(1960年6月発行)
11巻2号(1960年4月発行)
11巻1号(1960年2月発行)
10巻6号(1959年12月発行)
10巻5号(1959年10月発行)
10巻4号(1959年8月発行)
10巻3号(1959年6月発行)
10巻2号(1959年4月発行)
10巻1号(1959年2月発行)
8巻6号(1957年12月発行)
8巻5号(1957年10月発行)
特集 酵素と生物
8巻4号(1957年8月発行)
8巻3号(1957年6月発行)
8巻2号(1957年4月発行)
8巻1号(1957年2月発行)
本サービスは医療関係者に向けた情報提供を目的としております。
一般の方に対する情報提供を目的としたものではない事をご了承ください。
また,本サービスのご利用にあたっては,利用規約およびプライバシーポリシーへの同意が必要です。
※本サービスを使わずにご契約中の電子商品をご利用したい場合はこちら