生き物の複雑で多様な形態がどのようにしてつくられるのか。そのしくみを理解することは,古くから続く生物学の大きな目標の一つと言えます。1917年に出版されたD'Arcy Wentworth Thompsonの名著“On Growth and Form”を皮切りに,形態形成に対する機械論的な知見は数多く積み上げられてきました。また,形づくりの設計図とも言えるゲノム配列の解読が進み,遺伝子工学の発展により,働く分子の実体解明も進められてきました。コトとモノの両面でうまく研究が進められてもなお,発生や成長の過程で複雑さを増していく形態形成は謎に満ちた現象で,そのしくみの理解を目指す研究には色褪せない魅力があります。
本特集では全体を4つの章に分け,研究の第一線で活躍されている先生方に最新の知見についてご執筆いただきました。
雑誌目次
生体の科学73巻4号
2022年08月発行
雑誌目次
特集 形態形成の統合的理解
特集「形態形成の統合的理解」によせて フリーアクセス
著者: 平島剛志
ページ範囲:P.286 - P.286
Ⅰ.形態の要素をつくるしくみ
細胞とオルガネラのサイズ決定のしくみ
著者: 原裕貴 , 山本一男
ページ範囲:P.287 - P.290
多細胞生物は,様々な大きさ(サイズ)の細胞により構成される。また,細胞内部の機能を担うオルガネラのサイズも多様である。生物は,発生・分化や環境の変化に応じて細胞やオルガネラのサイズを適切に制御することで,生理的機能を調節する。では,生物は適切なサイズをどうやって知るのだろうか。本稿では,生物が細胞とオルガネラのサイズを適切に制御するしくみとその生理的意義について,最新の研究成果も交えながら考察したい。
細胞の非対称パターン化をつかさどる力学機構
著者: 茂木文夫
ページ範囲:P.291 - P.294
生物の複雑な形態と機能は,それぞれの細胞が細胞質や細胞膜近傍において確立する分子や生化学反応の空間的非対称性“極性パターン”に依存する。この細胞が示す極性パターンは,細胞内で起こる“流れ”の動的変化が特定分子を特定の目的地へ輸送する物理的プロセスに依存していることが,近年の研究から明らかにされた。本稿では,動物細胞の極性化に焦点を当て,細胞内における流体の生成とパターン形成への寄与に関する最近の進歩を概説する。
胚発生における細胞骨格と細胞集団の協調的な運動
著者: 進藤麻子
ページ範囲:P.295 - P.299
動物胚の体内組織の“形”は,それぞれの組織を構成する細胞が集団となって動くことでつくられる。このとき,細胞たちは勝手気ままに動くのではなく,隣の細胞や離れた細胞の動きも把握しながら集団の秩序を壊さずに動かなければならない。本稿では,動物の形づくりの基盤となる細胞集団運動がどのようにして制御されているのか,“協調”をキーワードとしてモデル動物を用いた研究とこれまでの知見を紹介する。
パターン形成から3D形態形成の理解へ
著者: 近藤滋
ページ範囲:P.300 - P.304
これまでの発生学で扱ってきた“パターン形成”は,ほとんどの場合,二次元の固定した場における空間パターンの形成である。しかし,実際の発生現象,特に後期発生の時期には,場そのものの大きな変形が伴うのが通常であり,その場合,今までとは異なる研究手法が必要になる
Ⅱ.技術による推進
光を用いた空間トランスクリプトーム計測
著者: 木村龍一 , 沖真弥
ページ範囲:P.305 - P.310
多細胞生物の細胞間相互作用やその機能を明らかにするためには,遺伝子発現を空間的に理解する必要がある。Photo-isolation chemistry(PIC)は筆者らが独自に開発している空間トランスクリプトーム計測技術であり,狙った領域に光を照射することで組織をバラバラにすることなくトランスクリプトーム情報を取得することができる1)。原理的には回折限界の解像度を有するため,胚や脳といった大きな組織だけでなく,細胞内小器官といった微細な空間のトランスクリプトームを計測することも可能である。本稿では,PICの原理について実際の解析例と共に紹介する。なお,本稿の内容の一部は実験医学2021年9月号に掲載の内容を要約しており,より詳細を理解したい読者はそちらも併せて参照されたい。
組織変形動態の定量と器官発生—心臓初期発生過程を例に
著者: 森下喜弘
ページ範囲:P.311 - P.316
動物の体を構成する各器官は,多くの細胞から成る1つの集合体として,しばしば非常に複雑な構造を持ち,固有の機能を発揮する。発生中の胚で各器官の正常な形がどのようにつくられるのかを理解することは,理学的な興味のみならず,先天性疾患や奇形の発生機序を知るための基礎情報として重要である。また,その知見は,機能的な器官形態のデザインや制御技術の開発へも展開可能であることから,生物学の長い歴史のなかでも重要な課題の一つとして多くの研究が行われてきた。過去数十年にわたる分子生物学の進展は,形態形成に関する主要遺伝子群の同定に成功し,細胞の分化や増殖を制御するための分子機構が明らかになってきた。
他方で,こうした分子的知見と実際に形態がつくられる物理過程の理解との間には大きなギャップが存在する。物理システムとして形態形成過程を理解するためには,器官固有の形態が,どのような組織変形や細胞集団運動により実現されているのか,またそれらが力学状態とどのような関係性にあるのかを明らかにする必要がある。近年の共焦点・2光子顕微鏡を含む計測技術は,小さく薄い組織であれば1細胞分解能で高速に計測可能とし,個々の細胞動態と組織形態変化の間の関係性を定量可能とした1-3)。更には細胞の応力・物性情報と統合し,形態形成過程を再現する数理モデルも提案されるようになった4)。しかし,高分解能での計測が難しい胚の深部で発生する立体的な器官に関しては,その組織・細胞動態について多くが未解明のままである。本稿では,脊椎動物の心臓初期発生を例に,限られた細胞軌道情報から統計的処理による組織変形写像の再構成,組織変形パターンと細胞プロセスとの定量的な関係性,動態解析結果から想定されるモデル提案までの一連の流れを紹介する5)。
三次元組織モデルの実現に向けた柔軟な培養基材の開発
著者: 大山智子 , 大山廣太郎 , 三好洋美 , 田口光正
ページ範囲:P.317 - P.321
生体内から取り出した細胞を人工的に生育させる細胞培養は,生命現象の解明のみならず,診断,創薬,治療などを広く下支えする基盤技術である。しかし近年,生体内環境とはかけ離れた硬く平坦なディッシュ上では細胞が本来の機能を喪失することが明らかになり,データの信頼性に影響を与える大きな問題として認識され始めた1-3)。この問題を解決しようと様々な試みが進められているなかで2),筆者らは生体内における細胞の周囲環境,すなわち細胞外マトリックス(extracellular matrix;ECM)の主要特性を模倣した培養基材を,量子ビーム誘起反応を活用した独自の材料加工技術によって開発している。量子ビームとは,電子線,ガンマ線,X線,イオンビームなど,高度に制御した電離放射線の総称である。画像診断やがん治療,医療器具・実験器具の滅菌処理やタンパク質の構造解析にも用いられており,生命科学・医学分野においても馴染み深いツールであろう。量子ビームには,励起・イオン化によってラジカルを生成し,分子を分解したり,共有結合でつないだりする(架橋)作用がある。これらの誘起反応を活用する筆者らの加工技術の特徴は,加熱や薬品処理を要する従来技術と異なり,生体適合性や生理活性を損なうことなく生体材料の化学的特性や機械的特性を制御できることにある。
本稿では,特にECMの柔軟性に着目して開発した培養基材によって,硬いディッシュ上ではみることができない細胞の三次元的な形づくりを誘導した2つの研究例を紹介する。
数理モデルを駆使した神経発生研究
著者: 佐藤純
ページ範囲:P.322 - P.326
脳の形成過程においては多種多様な神経細胞が正確に産生され,形態や機能が異なる神経細胞が集積して精密な神経回路を構築する。このような複雑な過程を数理モデルに置き換えることは困難であるが,着目する細胞,遺伝子を絞り込むことにより,現実的な数理モデル研究が可能となる。モデル動物であるショウジョウバエの脳は10万個もの神経細胞から成るが,哺乳類と比べればその数は限られている。進化的に保存された遺伝子セットを持ちつつも,遺伝子の重複が少ないため,限られた種類の細胞・遺伝子に着目したシンプルな数理モデルを構築することが可能となるうえ,非常に強力なハエの遺伝学的手法を用いることで,シミュレーションから得られた予測を効率よく実験的に検証することができる。筆者が取り組んできた,数理モデルを駆使した神経発生研究の一連の研究成果について紹介したい。
Ⅲ.再構成系による理解
アクチン細胞骨格構造と機能の再構成
著者: 宮﨑牧人
ページ範囲:P.327 - P.332
アクチン細胞骨格は,主にアクチン線維とミオシン分子モーターで構成される動的高次構造体であり,真核細胞に普遍的に存在する。特に動物細胞では細胞の形を決める重要な因子であり,アクチン細胞骨格の力発生が駆動する細胞の形態変化は,運動や分裂,核配置の制御,更には上皮組織の変形など,多種多様な,そして生命に本質的な機能を生み出す。その生物学的および医学的重要性ゆえ,アクチン細胞骨格に関する研究は半世紀以上にわたり,生命科学研究の中核を担うテーマであり続けている。
細胞間相互作用の再構成による多細胞構造の形成
著者: 戸田聡
ページ範囲:P.333 - P.336
動物の発生過程では,細胞は相互作用しながら自発的に様々な組織構造を形づくる。しかし,そのしくみはゲノム情報が解読された現代でも未解明な点が多く,同時に,望みの構造を持った多細胞組織を自在に作製するには至っていない。本稿では,細胞が組織構造を形成する過程を培養皿上で再現することにより,組織形成のしくみの理解や新たな組織構築技術の開発を目指す取り組みについて紹介する。
呼吸器の複雑性の理解と再構成—器官形成とオルガノイド
著者: 森本充
ページ範囲:P.337 - P.342
呼吸器は気管から肺胞まで階層的な構造を持ち,枝分かれをつくることで胸腔の限られた空間を効率的に利用して肺胞の表面積を最大化し,高効率にガス交換するための機能を獲得している。呼吸器の三次元構造は複雑で理解することも難解だが,驚くことに,その構造の広い領域が異なる個体間で保存されている。すなわち,呼吸器の組織構造は遺伝情報のなかにプログラムされている。本稿では,まず気管/気管支上皮,肺胞上皮,気管間充織の発生を解読することで呼吸器の形態形成プログラムを理解し,次に多能性幹細胞からの分化誘導による呼吸器オルガノイド創出への挑戦によって導かれる再構成論的理解の最新の知見を紹介する。
脳オルガノイドを用いたヒト脳の発生・疾患の理解
著者: 玉田篤史 , 木村俊哉 , 次山ルシラ絵美子 , 六車恵子
ページ範囲:P.343 - P.347
ES細胞やiPS細胞などの多能性幹細胞から脳組織を創出する脳オルガノイド作製技術が急速に進展している。脳オルガノイドは,特にヒトにおいて,生体脳組織の代替標本としての活用が期待されている。本稿では,脳オルガノイド技術の最新状況を概観すると共に,これを活用したヒト脳研究の現状と将来の方向性について議論する。
Ⅳ.多様な生物種に学ぶ
うじ虫の皮が体を形づくるしくみ
著者: 田尻怜子
ページ範囲:P.348 - P.352
生物の形がどうやってつくられるのかという問いに対して,従来の発生学では“体=細胞の集まり”という前提のもと,発生過程における細胞の振る舞い(細胞の変形,細胞分裂,細胞移動など)により組織がめまぐるしく変形していって最終形ができるしくみが示されてきた。しかし,生物の体の材料は細胞だけではない。ヒトの骸骨やセミの抜け殻には生きた細胞が存在しないにもかかわらず,われわれはそれぞれの生物の形をそこに見いだす。ということは,これらの生物の形を直接的に規定するのは細胞ではなく,骨や殻なのである。脊椎動物の骨も,昆虫の殻(クチクラ)も,いずれも細胞外に形成される基質である。こういった細胞外基質は生物の形づくりにどのように寄与するのだろうか? 本稿では,昆虫の形態形成に対するクチクラの寄与について,モデル生物であるショウジョウバエを用いた研究を紹介する。
ホヤ胚の神経管閉鎖ジッパリングにおける力学機構
著者: 橋本秀彦
ページ範囲:P.353 - P.358
ホヤは脊索動物のなかで最も脊椎動物に近い海産無脊椎動物である。他の脊椎動物に比べ,ホヤ胚は組織や器官構築プロセスにおいて細胞数が非常に少ない。そのため,個々の細胞がいつ,どこで物理的な力を生成し,それらの力がどのように周辺細胞と統合され細胞集団レベルで形がつくられるかを解明することができる。このような力学的な細胞間相互作用は,多細胞の形づくりにおける自己組織化メカニズムの基盤であることから1),ホヤは自己組織化メカニズムを解明するうえで優れたモデル生物であると筆者は考えている。本稿では,多細胞の形づくりにおける自己組織化メカニズムの解明を目指し,これまで筆者が行ってきたホヤの神経管閉鎖ジッパリングをつかさどる細胞集団運動の力学機構について紹介する2)。
体節空間パターンを生み出すしくみの多様性
著者: 秋山-小田康子
ページ範囲:P.359 - P.363
体節は節足動物の体の基本となる繰り返し構造である。体節の形成に先立って,胚を構成する細胞はそれぞれの位置に応じた遺伝子を発現し,全体として見事な繰り返しの縞パターンをつくり上げる。このようなパターンは節足動物に共通してみられるが,形成のしくみは多様である。特に筆者らが研究対象としているオオヒメグモではヘッジホッグシグナルが重要な働きをしており,既知のしくみとはかなり異なる。本稿では,節足動物の縞パターン形成について紹介し,その多様化について議論したい。
昆虫の翅模様の進化発生生物学
著者: 古関将斗 , 越川滋行
ページ範囲:P.364 - P.367
昆虫の翅(はね)には多様な模様がみられる。これらの模様は,進化発生生物学(エボデボ)の分野では形態進化の発生的・遺伝的基盤を模索するための優れたモデルである。近年,成虫の着色予定領域を決定する“模様形成遺伝子”が蛹期に発現することが明らかになってきた。また,模様形成遺伝子の発現制御についての知見も得られてきており,模様進化の遺伝的基盤への理解が深まりつつある。
本稿では,模様形成遺伝子について具体的な説明を加えた後で,3種類の昆虫(ショウジョウバエ,テントウムシ,ドクチョウ)についての研究事例を大まかに述べる。
連載講座 ヒトを知るモデル動物としてのゼブラフィッシュ-6
ゼブラフィッシュを用いた小脳の発生と機能解析 フリーアクセス
著者: 日比正彦 , 清水貴史
ページ範囲:P.368 - P.373
これまで,ゼブラフィッシュを用いた神経科学の研究は,中枢神経後方の脊髄や脳幹部,前方の終脳・間脳・中脳に焦点を当てたものが多かった。これは,構造と機能が単純で,脊椎動物間で構造の類似性の高い脊髄や脳幹部と,より高度な情報処理のしくみを知るため終脳・間脳・中脳を研究するという側面があった。ヒトで最大のニューロン数を持ち(脳全体の70%以上),複雑な機能を有する小脳に関しては,この十数年で研究が進んできた。本稿では,ゼブラフィッシュを用いた解析から得られた小脳の発生と機能に関する知見を概説する。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.285 - P.285
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.374 - P.375
あとがき フリーアクセス
著者: 松田道行
ページ範囲:P.376 - P.376
生き物に興味をもつ子どもたちの一番の関心は,様々な生物の多様な形や色彩でしょう。それは大人も同じで,生命の形態形成の仕組みは多くの研究者の興味をひきつけてやみません。遺伝学的アプローチは古くから行われてきましたが,本特集にもありますように,進化生物学的アプローチや数理生物学との親和性も高く,融合研究の魅力を感じさせる分野でもあります。また,近年ではメカノバイオロジーの観点からの研究も盛んです。このメカノバイオロジー研究のメッカの一つがシンガポール国立大学のメカノバイオロジー研究所です。編集の労をおとりいただいた平島博士が2022年6月からここで研究室を立ち上げています。ますますのご発展を期待しております。諸般の国内事情から,老若を問わず優秀な研究者の国外流出は今後も続くでしょう。しかし,近年の日本人のノーベル賞は,第二次世界大戦敗北後に海外に打って出て,そのまま海外で,あるいは国内に帰ってきてから世界と戦って勝ち抜いてきた先達が獲られたものです。いずれまたその波が来ることを期待したいと思います。最後になりましたが,ご多忙中のところをご寄稿いただいた諸先生方にお礼申し上げます。
基本情報
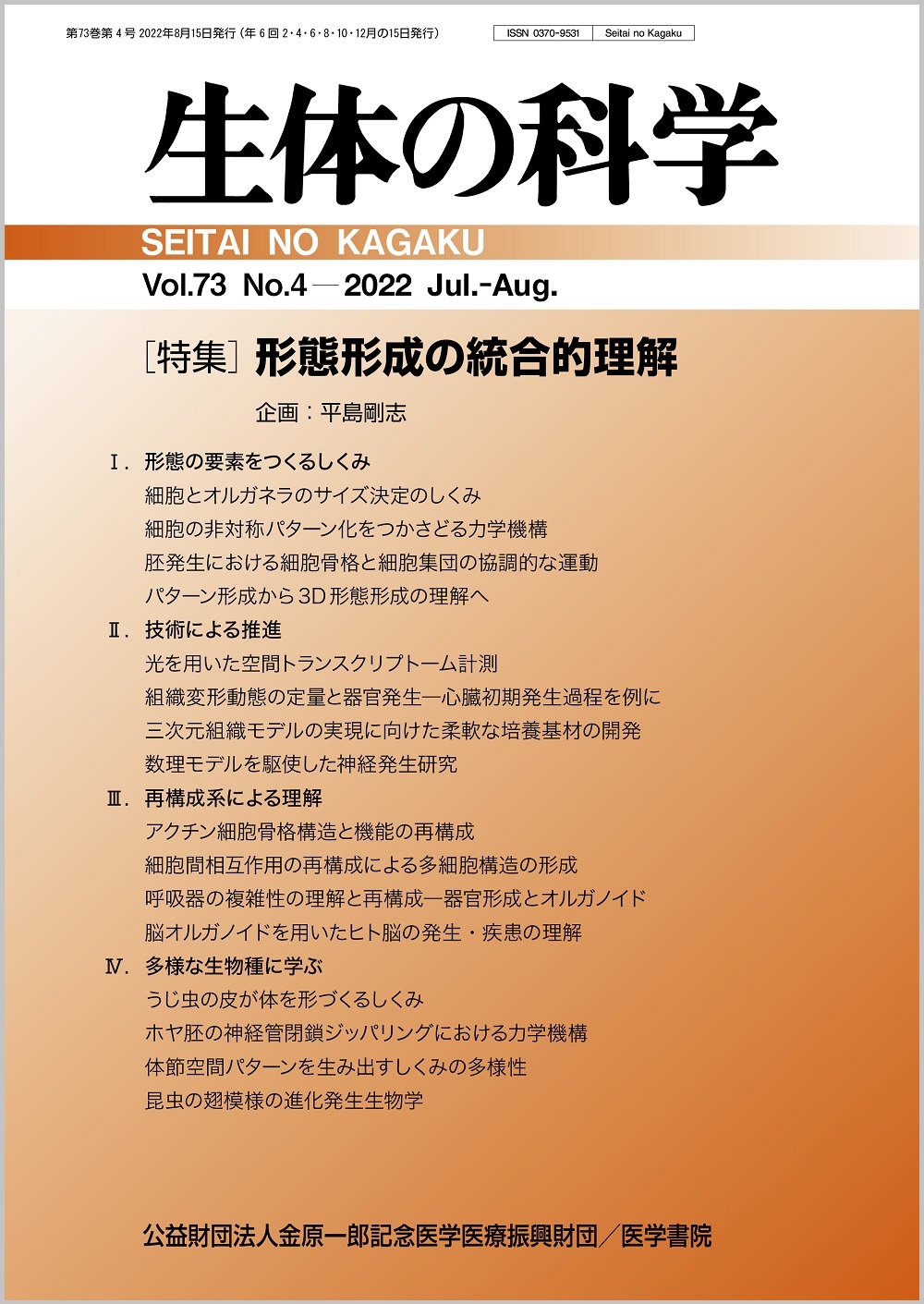
バックナンバー
75巻6号(2024年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅤ:脂肪
75巻5号(2024年10月発行)
増大特集 学術研究支援の最先端
75巻4号(2024年8月発行)
特集 シングルセルオミクス
75巻3号(2024年6月発行)
特集 高速分子動画:動的構造からタンパク質分子制御へ
75巻2号(2024年4月発行)
特集 生命現象を駆動する生体内金属動態の理解と展開
75巻1号(2024年2月発行)
特集 脳と個性
74巻6号(2023年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅣ:骨・軟骨
74巻5号(2023年10月発行)
増大特集 代謝
74巻4号(2023年8月発行)
特集 がん遺伝子の発見は現代医療を進歩させたか
74巻3号(2023年6月発行)
特集 クロマチンによる転写制御機構の最前線
74巻2号(2023年4月発行)
特集 未病の科学
74巻1号(2023年2月発行)
特集 シナプス
73巻6号(2022年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅢ:血管とリンパ管
73巻5号(2022年10月発行)
増大特集 革新脳と関連プロジェクトから見えてきた新しい脳科学
73巻4号(2022年8月発行)
特集 形態形成の統合的理解
73巻3号(2022年6月発行)
特集 リソソーム研究の新展開
73巻2号(2022年4月発行)
特集 DNA修復による生体恒常性の維持
73巻1号(2022年2月発行)
特集 意識
72巻6号(2021年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅡ:骨格筋—今後の研究の発展に向けて
72巻5号(2021年10月発行)
増大特集 脳とからだ
72巻4号(2021年8月発行)
特集 グローバル時代の新興再興感染症への科学的アプローチ
72巻3号(2021年6月発行)
特集 生物物理学の進歩—生命現象の定量的理解へ向けて
72巻2号(2021年4月発行)
特集 組織幹細胞の共通性と特殊性
72巻1号(2021年2月発行)
特集 小脳研究の未来
71巻6号(2020年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅠ:最新の皮膚科学
71巻5号(2020年10月発行)
増大特集 難病研究の進歩
71巻4号(2020年8月発行)
特集 細胞機能の構造生物学
71巻3号(2020年6月発行)
特集 スポーツ科学—2020オリンピック・パラリンピックによせて
71巻2号(2020年4月発行)
特集 ビッグデータ時代のゲノム医学
71巻1号(2020年2月発行)
特集 睡眠の制御と機能
70巻6号(2019年12月発行)
特集 科学と芸術の接点
70巻5号(2019年10月発行)
増大特集 現代医学・生物学の先駆者たち
70巻4号(2019年8月発行)
特集 メカノバイオロジー
70巻3号(2019年6月発行)
特集 免疫チェックポイント分子による生体機能制御
70巻2号(2019年4月発行)
特集 免疫系を介したシステム連関:恒常性の維持と破綻
70巻1号(2019年2月発行)
特集 脳神経回路のダイナミクスから探る脳の発達・疾患・老化
69巻6号(2018年12月発行)
特集 細胞高次機能をつかさどるオルガネラコミュニケーション
69巻5号(2018年10月発行)
増大特集 タンパク質・核酸の分子修飾
69巻4号(2018年8月発行)
特集 いかに創薬を進めるか
69巻3号(2018年6月発行)
特集 生体膜のバイオロジー
69巻2号(2018年4月発行)
特集 宇宙の極限環境から生命体の可塑性をさぐる
69巻1号(2018年2月発行)
特集 社会性と脳
68巻6号(2017年12月発行)
特集 心臓の発生・再生・創生
68巻5号(2017年10月発行)
増大特集 細胞多様性解明に資する光技術─見て,動かす
68巻4号(2017年8月発行)
特集 血管制御系と疾患
68巻3号(2017年6月発行)
特集 核内イベントの時空間制御
68巻2号(2017年4月発行)
特集 細菌叢解析の光と影
68巻1号(2017年2月発行)
特集 大脳皮質—成り立ちから機能へ
67巻6号(2016年12月発行)
特集 時間生物学の新展開
67巻5号(2016年10月発行)
増大特集 病態バイオマーカーの“いま”
67巻4号(2016年8月発行)
特集 認知症・神経変性疾患の克服への挑戦
67巻3号(2016年6月発行)
特集 脂質ワールド
67巻2号(2016年4月発行)
特集 細胞の社会学─細胞間で繰り広げられる協調と競争
67巻1号(2016年2月発行)
特集 記憶ふたたび
66巻6号(2015年12月発行)
特集 グリア研究の最先端
66巻5号(2015年10月発行)
増大特集 細胞シグナル操作法
66巻4号(2015年8月発行)
特集 新興・再興感染症と感染症対策
66巻3号(2015年6月発行)
特集 進化と発生からみた生命科学
66巻2号(2015年4月発行)
特集 使える最新ケミカルバイオロジー
66巻1号(2015年2月発行)
特集 脳と心の謎はどこまで解けたか
65巻6号(2014年12月発行)
特集 エピジェネティクスの今
65巻5号(2014年10月発行)
増大特集 生命動態システム科学
65巻4号(2014年8月発行)
特集 古典的代謝経路の新しい側面
65巻3号(2014年6月発行)
特集 器官の発生と再生の基礎
65巻2号(2014年4月発行)
特集 細胞の少数性と多様性に挑む―シングルセルアナリシス
65巻1号(2014年2月発行)
特集 精神疾患の病理機構
64巻6号(2013年12月発行)
特集 顕微鏡で物を見ることの新しい動き
64巻5号(2013年10月発行)
増大特集 細胞表面受容体
64巻4号(2013年8月発行)
特集 予測と意思決定の神経科学
64巻3号(2013年6月発行)
特集 細胞接着の制御
64巻2号(2013年4月発行)
特集 特殊な幹細胞としての骨格筋サテライト細胞
64巻1号(2013年2月発行)
特集 神経回路の計測と操作
63巻6号(2012年12月発行)
特集 リンパ管
63巻5号(2012年10月発行)
特集 細胞の分子構造と機能―核以外の細胞小器官
63巻4号(2012年8月発行)
特集 質感脳情報学への展望
63巻3号(2012年6月発行)
特集 細胞極性の制御
63巻2号(2012年4月発行)
特集 RNA干渉の実現化に向けて
63巻1号(2012年2月発行)
特集 小脳研究の課題(2)
62巻6号(2011年12月発行)
特集 コピー数変異
62巻5号(2011年10月発行)
特集 細胞核―構造と機能
62巻4号(2011年8月発行)
特集 小脳研究の課題
62巻3号(2011年6月発行)
特集 インフラマソーム
62巻2号(2011年4月発行)
特集 筋ジストロフィーの分子病態から治療へ
62巻1号(2011年2月発行)
特集 摂食制御の分子過程
61巻6号(2010年12月発行)
特集 細胞死か腫瘍化かの選択
61巻5号(2010年10月発行)
特集 シナプスをめぐるシグナリング
61巻4号(2010年8月発行)
特集 miRNA研究の最近の進歩
61巻3号(2010年6月発行)
特集 SNARE複合体-膜融合の機構
61巻2号(2010年4月発行)
特集 糖鎖のかかわる病気:発症機構,診断,治療に向けて
61巻1号(2010年2月発行)
特集 脳科学のモデル実験動物
60巻6号(2009年12月発行)
特集 ユビキチン化による生体機能の調節
60巻5号(2009年10月発行)
特集 伝達物質と受容体
60巻4号(2009年8月発行)
特集 睡眠と脳回路の可塑性
60巻3号(2009年6月発行)
特集 脳と糖脂質
60巻2号(2009年4月発行)
特集 感染症の現代的課題
60巻1号(2009年2月発行)
特集 遺伝子-脳回路-行動
59巻6号(2008年12月発行)
特集 mTORをめぐるシグナルタンパク
59巻5号(2008年10月発行)
特集 現代医学・生物学の仮説・学説2008
59巻4号(2008年8月発行)
特集 免疫学の最近の動向
59巻3号(2008年6月発行)
特集 アディポゲネシス
59巻2号(2008年4月発行)
特集 細胞外基質-研究の新たな展開
59巻1号(2008年2月発行)
特集 コンピュータと脳
58巻6号(2007年12月発行)
特集 グリケーション(糖化)
58巻5号(2007年10月発行)
特集 タンパク質間相互作用
58巻4号(2007年8月発行)
特集 嗅覚受容の分子メカニズム
58巻3号(2007年6月発行)
特集 骨の形成と破壊
58巻2号(2007年4月発行)
特集 シナプス後部構造の形成・機構と制御
58巻1号(2007年2月発行)
特集 意識―脳科学からのアプローチ
57巻6号(2006年12月発行)
特集 血管壁
57巻5号(2006年10月発行)
特集 生物進化の分子マップ
57巻4号(2006年8月発行)
特集 脳科学が求める先端技術
57巻3号(2006年6月発行)
特集 ミエリン化の機構とその異常
57巻2号(2006年4月発行)
特集 膜リサイクリング
57巻1号(2006年2月発行)
特集 こころと脳:とらえがたいものを科学する
56巻6号(2005年12月発行)
特集 構造生物学の現在と今後の展開
56巻5号(2005年10月発行)
特集 タンパク・遺伝子からみた分子病―新しく解明されたメカニズム
56巻4号(2005年8月発行)
特集 脳の遺伝子―どこでどのように働いているのか
56巻3号(2005年6月発行)
特集 Naチャネル
56巻2号(2005年4月発行)
特集 味覚のメカニズムに迫る
56巻1号(2005年2月発行)
特集 情動―喜びと恐れの脳の仕組み
55巻6号(2004年12月発行)
特集 脳の深部を探る
55巻5号(2004年10月発行)
特集 生命科学のNew Key Word
55巻4号(2004年8月発行)
特集 心筋研究の最前線
55巻3号(2004年6月発行)
特集 分子進化学の現在
55巻2号(2004年4月発行)
特集 アダプタータンパク
55巻1号(2004年2月発行)
特集 ニューロンと脳
54巻6号(2003年12月発行)
特集 オートファジー
54巻5号(2003年10月発行)
特集 創薬ゲノミクス・創薬プロテオミクス・創薬インフォマティクス
54巻4号(2003年8月発行)
特集 ラフトと細胞機能
54巻3号(2003年6月発行)
特集 クロマチン
54巻2号(2003年4月発行)
特集 樹状突起
54巻1号(2003年2月発行)
53巻6号(2002年12月発行)
特集 ゲノム全解読とポストゲノムの問題点
53巻5号(2002年10月発行)
特集 加齢の克服―21世紀の課題
53巻4号(2002年8月発行)
特集 一価イオンチャネル
53巻3号(2002年6月発行)
特集 細胞質分裂
53巻2号(2002年4月発行)
特集 RNA
53巻1号(2002年2月発行)
連続座談会 脳とこころ―21世紀の課題
52巻6号(2001年12月発行)
特集 血液脳関門研究の最近の進歩
52巻5号(2001年10月発行)
特集 モチーフ・ドメインリスト
52巻4号(2001年8月発行)
特集 骨格筋研究の新展開
52巻3号(2001年6月発行)
特集 脳の発達に関与する分子機構
52巻2号(2001年4月発行)
特集 情報伝達物質としてのATP
52巻1号(2001年2月発行)
連続座談会 脳を育む
51巻6号(2000年12月発行)
特集 機械的刺激受容の分子機構と細胞応答
51巻5号(2000年10月発行)
特集 ノックアウトマウスリスト
51巻4号(2000年8月発行)
特集 臓器(組織)とアポトーシス
51巻3号(2000年6月発行)
特集 自然免疫における異物認識と排除の分子機構
51巻2号(2000年4月発行)
特集 細胞極性の形成機序
51巻1号(2000年2月発行)
特集 脳を守る21世紀生命科学の展望
50巻6号(1999年12月発行)
特集 細胞内輸送
50巻5号(1999年10月発行)
特集 病気の分子細胞生物学
50巻4号(1999年8月発行)
特集 トランスポーターの構造と機能協関
50巻3号(1999年6月発行)
特集 時間生物学の新たな展開
50巻2号(1999年4月発行)
特集 リソソーム:最近の研究
50巻1号(1999年2月発行)
連続座談会 脳を守る
49巻6号(1998年12月発行)
特集 発生・分化とホメオボックス遺伝子
49巻5号(1998年10月発行)
特集 神経系に作用する薬物マニュアル1998
49巻4号(1998年8月発行)
特集 プロテインキナーゼCの多様な機能
49巻3号(1998年6月発行)
特集 幹細胞研究の新展開
49巻2号(1998年4月発行)
特集 血管―新しい観点から
49巻1号(1998年2月発行)
特集 言語の脳科学
48巻6号(1997年12月発行)
特集 軸索誘導
48巻5号(1997年10月発行)
特集 受容体1997
48巻4号(1997年8月発行)
特集 マトリックス生物学の最前線
48巻3号(1997年6月発行)
特集 開口分泌のメカニズムにおける新しい展開
48巻2号(1997年4月発行)
特集 最近のMAPキナーゼ系
48巻1号(1997年2月発行)
特集 21世紀の脳科学
47巻6号(1996年12月発行)
特集 老化
47巻5号(1996年10月発行)
特集 器官―その新しい視点
47巻4号(1996年8月発行)
特集 エンドサイトーシス
47巻3号(1996年6月発行)
特集 細胞分化
47巻2号(1996年4月発行)
特集 カルシウム動態と細胞機能
47巻1号(1996年2月発行)
特集 神経科学の最前線
46巻6号(1995年12月発行)
特集 病態を変えたよく効く医薬
46巻5号(1995年10月発行)
特集 遺伝子・タンパク質のファミリー・スーパーファミリー
46巻4号(1995年8月発行)
特集 ストレス蛋白質
46巻3号(1995年6月発行)
特集 ライソゾーム
46巻2号(1995年4月発行)
特集 プロテインホスファターゼ―最近の進歩
46巻1号(1995年2月発行)
特集 神経科学の謎
45巻6号(1994年12月発行)
特集 ミトコンドリア
45巻5号(1994年10月発行)
特集 動物の行動機能テスト―個体レベルと分子レベルを結ぶ
45巻4号(1994年8月発行)
特集 造血の機構
45巻3号(1994年6月発行)
特集 染色体
45巻2号(1994年4月発行)
特集 脳と分子生物学
45巻1号(1994年2月発行)
特集 グルコーストランスポーター
44巻6号(1993年12月発行)
特集 滑面小胞体をめぐる諸問題
44巻5号(1993年10月発行)
特集 現代医学・生物学の仮説・学説
44巻4号(1993年8月発行)
特集 細胞接着
44巻3号(1993年6月発行)
特集 カルシウムイオンを介した調節機構の新しい問題点
44巻2号(1993年4月発行)
特集 蛋白質の細胞内転送とその異常
44巻1号(1993年2月発行)
座談会 脳と遺伝子
43巻6号(1992年12月発行)
特集 成長因子受容体/最近の進歩
43巻5号(1992年10月発行)
特集 〈研究室で役に立つ細胞株〉
43巻4号(1992年8月発行)
特集 細胞機能とリン酸化
43巻3号(1992年6月発行)
特集 血管新生
43巻2号(1992年4月発行)
特集 大脳皮質発達の化学的側面
43巻1号(1992年2月発行)
特集 意識と脳
42巻6号(1991年12月発行)
特集 細胞活動の日周リズム
42巻5号(1991年10月発行)
特集 神経系に作用する薬物マニュアル
42巻4号(1991年8月発行)
特集 開口分泌の細胞内過程
42巻3号(1991年6月発行)
特集 ペルオキシソーム/最近の進歩
42巻2号(1991年4月発行)
特集 脳の移植と再生
42巻1号(1991年2月発行)
特集 脳と免疫
41巻6号(1990年12月発行)
特集 注目の実験モデル動物
41巻5号(1990年10月発行)
特集 LTPとLTD:その分子機構
41巻4号(1990年8月発行)
特集 New proteins
41巻3号(1990年6月発行)
特集 シナプスの形成と動態
41巻2号(1990年4月発行)
特集 細胞接着
41巻1号(1990年2月発行)
特集 発がんのメカニズム/最近の知見
40巻6号(1989年12月発行)
特集 ギャップ結合
40巻5号(1989年10月発行)
特集 核内蛋白質
40巻4号(1989年8月発行)
特集 研究室で役に立つ新しい試薬
40巻3号(1989年6月発行)
特集 細胞骨格異常
40巻2号(1989年4月発行)
特集 大脳/神経科学からのアプローチ
40巻1号(1989年2月発行)
特集 分子進化
39巻6号(1988年12月発行)
特集 細胞内における蛋白質局在化機構
39巻5号(1988年10月発行)
特集 細胞測定法マニュアル
39巻4号(1988年8月発行)
特集 細胞外マトリックス
39巻3号(1988年6月発行)
特集 肺の微細構造と機能
39巻2号(1988年4月発行)
特集 生体運動の分子機構/研究の発展
39巻1号(1988年2月発行)
特集 遺伝子疾患解析の発展
38巻6号(1987年12月発行)
-チャンネルの最近の動向
38巻5号(1987年10月発行)
特集 細胞生物学における免疫実験マニュアル
38巻4号(1987年8月発行)
特集 視覚初期過程の分子機構
38巻3号(1987年6月発行)
特集 人間の脳
38巻2号(1987年4月発行)
特集 体液カルシウムのホメオスタシス
38巻1号(1987年2月発行)
特集 医学におけるブレイクスルー/基礎研究からの挑戦
37巻6号(1986年12月発行)
特集 神経活性物質受容体と情報伝達
37巻5号(1986年10月発行)
特集 中間径フィラメント
37巻4号(1986年8月発行)
特集 細胞生物学実験マニュアル
37巻3号(1986年6月発行)
特集 脳の化学的トポグラフィー
37巻2号(1986年4月発行)
特集 血小板凝集
37巻1号(1986年2月発行)
特集 脳のモデル
36巻6号(1985年12月発行)
特集 脂肪組織
36巻5号(1985年10月発行)
特集 細胞分裂をめぐって
36巻4号(1985年8月発行)
特集 神経科学実験マニュアル
36巻3号(1985年6月発行)
特集 血管内皮細胞と微小循環
36巻2号(1985年4月発行)
特集 肝細胞と胆汁酸分泌
36巻1号(1985年2月発行)
特集 Transmembrane Control
35巻6号(1984年12月発行)
特集 細胞毒マニュアル—実験に用いられる細胞毒の知識
35巻5号(1984年10月発行)
特集 中枢神経系の再構築
35巻4号(1984年8月発行)
特集 ゲノムの構造
35巻3号(1984年6月発行)
特集 神経科学の仮説
35巻2号(1984年4月発行)
特集 哺乳類の初期発生
35巻1号(1984年2月発行)
特集 細胞生物学の現状と展望
34巻6号(1983年12月発行)
特集 蛋白質の代謝回転
34巻5号(1983年10月発行)
特集 受容・応答の膜分子論
34巻4号(1983年8月発行)
特集 コンピュータによる生物現象の再構成
34巻3号(1983年6月発行)
特集 細胞の極性
34巻2号(1983年4月発行)
特集 モノアミン系
34巻1号(1983年2月発行)
特集 腸管の吸収機構
33巻6号(1982年12月発行)
特集 低栄養と生体機能
33巻5号(1982年10月発行)
特集 成長因子
33巻4号(1982年8月発行)
特集 リン酸化
33巻3号(1982年6月発行)
特集 神経発生の基礎
33巻2号(1982年4月発行)
特集 細胞の寿命と老化
33巻1号(1982年2月発行)
特集 細胞核
32巻6号(1981年12月発行)
特集 筋小胞体研究の進歩
32巻5号(1981年10月発行)
特集 ペプチド作働性シナプス
32巻4号(1981年8月発行)
特集 膜の転送
32巻3号(1981年6月発行)
特集 リポプロテイン
32巻2号(1981年4月発行)
特集 チャネルの概念と実体
32巻1号(1981年2月発行)
特集 細胞骨格
31巻6号(1980年12月発行)
特集 大脳の機能局在
31巻5号(1980年10月発行)
特集 カルシウムイオン受容タンパク
31巻4号(1980年8月発行)
特集 化学浸透共役仮説
31巻3号(1980年6月発行)
特集 赤血球膜の分子構築
31巻2号(1980年4月発行)
特集 免疫系の情報識別
31巻1号(1980年2月発行)
特集 ゴルジ装置
30巻6号(1979年12月発行)
特集 細胞間コミニケーション
30巻5号(1979年10月発行)
特集 In vitro運動系
30巻4号(1979年8月発行)
輸送系の調節
30巻3号(1979年6月発行)
特集 網膜の構造と機能
30巻2号(1979年4月発行)
特集 神経伝達物質の同定
30巻1号(1979年2月発行)
特集 生物物理学の進歩—第6回国際生物物理学会議より
29巻6号(1978年12月発行)
特集 最近の神経科学から
29巻5号(1978年10月発行)
特集 下垂体:前葉
29巻4号(1978年8月発行)
特集 中枢のペプチド
29巻3号(1978年6月発行)
特集 心臓のリズム発生
29巻2号(1978年4月発行)
特集 腎機能
29巻1号(1978年2月発行)
特集 膜脂質の再検討
28巻6号(1977年12月発行)
特集 青斑核
28巻5号(1977年10月発行)
特集 小胞体
28巻4号(1977年8月発行)
特集 微小管の構造と機能
28巻3号(1977年6月発行)
特集 神経回路網と脳機能
28巻2号(1977年4月発行)
特集 生体の修復
28巻1号(1977年2月発行)
特集 生体の科学の現状と動向
27巻6号(1976年12月発行)
特集 松果体
27巻5号(1976年10月発行)
特集 遺伝マウス・ラット
27巻4号(1976年8月発行)
特集 形質発現における制御
27巻3号(1976年6月発行)
特集 生体と化学的環境
27巻2号(1976年4月発行)
特集 分泌腺
27巻1号(1976年2月発行)
特集 光受容
26巻6号(1975年12月発行)
特集 自律神経と平滑筋の再検討
26巻5号(1975年10月発行)
特集 脳のプログラミング
26巻4号(1975年8月発行)
特集 受精機構をめぐつて
26巻3号(1975年6月発行)
特集 細胞表面と免疫
26巻2号(1975年4月発行)
特集 感覚有毛細胞
26巻1号(1975年2月発行)
特集 体内のセンサー
25巻5号(1974年12月発行)
特集 生体膜—その基本的課題
25巻4号(1974年8月発行)
特集 伝達物質と受容物質
25巻3号(1974年6月発行)
特集 脳の高次機能へのアプローチ
25巻2号(1974年4月発行)
特集 筋細胞の分化
25巻1号(1974年2月発行)
特集 生体の科学 展望と夢
24巻6号(1973年12月発行)
24巻5号(1973年10月発行)
24巻4号(1973年8月発行)
24巻3号(1973年6月発行)
24巻2号(1973年4月発行)
24巻1号(1973年2月発行)
23巻6号(1972年12月発行)
23巻5号(1972年10月発行)
23巻4号(1972年8月発行)
23巻3号(1972年6月発行)
23巻2号(1972年4月発行)
23巻1号(1972年2月発行)
22巻6号(1971年12月発行)
22巻5号(1971年10月発行)
22巻4号(1971年8月発行)
22巻3号(1971年6月発行)
22巻2号(1971年4月発行)
22巻1号(1971年2月発行)
21巻7号(1970年12月発行)
21巻6号(1970年10月発行)
21巻4号(1970年8月発行)
特集 代謝と機能
21巻5号(1970年8月発行)
21巻3号(1970年6月発行)
21巻2号(1970年4月発行)
21巻1号(1970年2月発行)
20巻6号(1969年12月発行)
20巻5号(1969年10月発行)
20巻4号(1969年8月発行)
20巻3号(1969年6月発行)
20巻2号(1969年4月発行)
20巻1号(1969年2月発行)
19巻6号(1968年12月発行)
19巻5号(1968年10月発行)
19巻4号(1968年8月発行)
19巻3号(1968年6月発行)
19巻2号(1968年4月発行)
19巻1号(1968年2月発行)
18巻6号(1967年12月発行)
18巻5号(1967年10月発行)
18巻4号(1967年8月発行)
18巻3号(1967年6月発行)
18巻2号(1967年4月発行)
18巻1号(1967年2月発行)
17巻6号(1966年12月発行)
17巻5号(1966年10月発行)
17巻4号(1966年8月発行)
17巻3号(1966年6月発行)
17巻2号(1966年4月発行)
17巻1号(1966年2月発行)
16巻6号(1965年12月発行)
16巻5号(1965年10月発行)
16巻4号(1965年8月発行)
16巻3号(1965年6月発行)
16巻2号(1965年4月発行)
16巻1号(1965年2月発行)
15巻6号(1964年12月発行)
特集 生体膜その3
15巻5号(1964年10月発行)
特集 生体膜その2
15巻4号(1964年8月発行)
特集 生体膜その1
15巻3号(1964年6月発行)
特集 第13回日本生理科学連合シンポジウム
15巻2号(1964年4月発行)
15巻1号(1964年2月発行)
14巻6号(1963年12月発行)
特集 興奮收縮伝関
14巻5号(1963年10月発行)
14巻4号(1963年8月発行)
14巻3号(1963年6月発行)
14巻1号(1963年2月発行)
特集 第9回中枢神経系の生理学シンポジウム
14巻2号(1963年2月発行)
13巻6号(1962年12月発行)
13巻5号(1962年10月発行)
特集 生物々理—生理学生物々理若手グループ第1回ミーティングから
13巻4号(1962年8月発行)
13巻3号(1962年6月発行)
13巻2号(1962年4月発行)
Symposium on Permeability of Biological Membranes
13巻1号(1962年2月発行)
12巻6号(1961年12月発行)
12巻5号(1961年10月発行)
12巻4号(1961年8月発行)
12巻3号(1961年6月発行)
12巻2号(1961年4月発行)
12巻1号(1961年2月発行)
11巻6号(1960年12月発行)
Symposium On Active Transport
11巻5号(1960年10月発行)
11巻4号(1960年8月発行)
11巻3号(1960年6月発行)
11巻2号(1960年4月発行)
11巻1号(1960年2月発行)
10巻6号(1959年12月発行)
10巻5号(1959年10月発行)
10巻4号(1959年8月発行)
10巻3号(1959年6月発行)
10巻2号(1959年4月発行)
10巻1号(1959年2月発行)
8巻6号(1957年12月発行)
8巻5号(1957年10月発行)
特集 酵素と生物
8巻4号(1957年8月発行)
8巻3号(1957年6月発行)
8巻2号(1957年4月発行)
8巻1号(1957年2月発行)
