がん遺伝子発見のノーベル生理学・医学賞は1989年だが,関連する動物の発がんウイルスの遺伝子研究は1960年代後半からである。当時東京大学医科学研究所の豊島久真男先生の「化学と生物」における1983年の総説には,“発癌機構の一元的理解も真近かか”と記されている。私自身の1987年初めての日本がん学会ポスター発表会場で平井久丸先生と2人で立っていたら,豊島先生がいらして,じっくりポスターをご覧になり,Ephのエクソン境界に関するアドバイスをいただいたことがあった。オンコジーン・がん遺伝子というと最近ではやや陳腐に聞こえるため本特集のテーマはあえて疑問形にした。私自身の答えは,「進歩を持続的なものとし,また障壁を明確化した」である。
ハリケーンのように絶大な力で発展し,1970年ごろから始まった血管新生,最近では炎症なども巻き込みマージしてきた。第一に診断,第二に治療,は医療の基本である。がんの遺伝子診断が保険収載され,ガイドライン策定で学会を,またがんゲノム医療拠点病院の設置などで行政をも動かしている。この第二の視点では,BCR-ABL標的薬の成功が分子標的薬という言葉さえつくり出したと言っても過言ではないが,すべての薬は標的となる分子が,また薬剤耐性が,最初から存在するのは歴史的事実である。重要な分子標的が決定していても開発が困難で科学の進歩に依存しなければならないものもあるが,薬ができたからといって優れているとは限らない。薬は分子ではなく病気を標的にしなければ優れた創薬とは言えないからである。第三は,実験技術の進歩を誘導し分子生物学へ貢献した。シグナル伝達,その代謝との連関,エピジェネティックス,遺伝子組換えによるモデル動物の開発,創薬を目指した結晶構造解析,などである。そのなかで,がん遺伝子の機能が多様であるために,神経,免疫,発生などがん生物と一見異なる分野への進展や貢献を見せてきただけでなく,がん抑制遺伝子,悪循環,ダブルフィードバック,逆説的作用,補完,分解・消失など細胞内分子論におけるロジックの発見を誘導した。第四は,凄まじい発展がゆえに,がん生物学における障壁も明らかになってしまった。がん転移などである。Signatureがいまだに存在せず,生体の全身における炎症を基盤としている。
雑誌目次
生体の科学74巻4号
2023年08月発行
雑誌目次
特集 がん遺伝子の発見は現代医療を進歩させたか
特集「がん遺伝子の発見は現代医療を進歩させたか」によせて フリーアクセス
著者: 丸義朗
ページ範囲:P.288 - P.288
Ⅰ.がん遺伝子研究の新しい展開
著者: 田中伯享 , 坂本毅治
ページ範囲:P.289 - P.294
主に3種類のアイソフォーム(KRAS,NRAS,HRAS)で構成されるRASのうち,
著者: 衣斐寛倫
ページ範囲:P.295 - P.299
RAFタンパク質は,RASと並びMAPKシグナルの主要構成分子である。
著者: 近藤彩奈 , 藤原智洋
ページ範囲:P.300 - P.305
肺がんの新規ドライバー遺伝子“
著者: 泉大樹 , 松本慎吾 , 葉清隆 , 小林進 , 後藤功一
ページ範囲:P.306 - P.311
非小細胞肺がんでは,様々なドライバー遺伝子を標的とした分子標的治療(個別化医療)が確立してきている。今回,筆者らは肺がん遺伝子スクリーニング基盤(LC-SCRUM-Asia)を通じて,新規ドライバー遺伝子である
がん遺伝子
著者: 後藤典子
ページ範囲:P.312 - P.315
がん遺伝子
がん悪性形質をつかさどるMYCの新機能と制御
著者: 杉原英志 , 佐谷秀行
ページ範囲:P.316 - P.321
MYCは転写因子として標的分子の発現制御により,細胞増殖や不死化,血管新生や代謝のリプログラミングといったがん悪性形質を促進する強力なドライバー遺伝子である。近年,MYCはスーパーエンハンサーによって過剰発現することやがん免疫の抑制およびスプライシング異常の誘導,多量体形成による複製フォークの防御など,新たな重要な機能が報告された。しかし,長年の研究にもかかわらずいまだMYCを標的とした医療は実現していない。本稿では,MYCの基本的な機能と最新の重要トピックを概説し,MYC標的治療の開発状況について紹介する。
著者: 塚原富士子
ページ範囲:P.322 - P.326
慢性骨髄性白血病(CML)の原因分子であるBCR-ABLチロシンキナーゼは,9番染色体と22番染色体の相互転座により形成された
著者: 家口勝昭
ページ範囲:P.327 - P.331
上皮増殖因子受容体をはじめとする受容体型チロシンキナーゼは,様々ながんにおいて発現の亢進や活性化変異などが明らかになり,がんの治療標的としてこれまで多くの分子標的薬が開発されてきた。一方,Eph受容体チロシンキナーゼは多くのがんで発現の亢進が認められ,がんの発生,進展,転移に関与していることが示唆されているが,臨床応用されているEph受容体を標的とした分子標的薬は存在しない。本稿では
阻害薬による標的キナーゼの構造的活性化とがん増殖シグナルの誘発
著者: 渡邊直樹
ページ範囲:P.332 - P.335
がん関連キナーゼを阻害する低分子化合物が数多く導入されている。筆者らは,ライブセルイメージングを用い,キナーゼ阻害薬がc-Srcの自己抑制構造を崩し活性型に変化させることを発見した。
著者: 西田俊朗
ページ範囲:P.336 - P.339
消化管間質腫瘍(gastrointestinal stromal tumor;GIST)は,消化管壁内に発生するKITやDOG-1タンパク質を発現する紡錘型,あるいは類上皮型の腫瘍細胞から成る間葉系腫瘍である。臨床的に悪性の経過をたどるものは肉腫で,臨床的GISTの発症頻度は,人口10万人当たり1.0人/年程度である。食道から肛門までのすべての消化管の主に筋層(まれに粘膜下層)に発生し,胃が60-70%と最も多く,次に小腸(20-30%),大腸(主に直腸:5%),食道(5%以下),その他消化管外(5%以下)である1,2)。発症年齢の中央値は60歳代であるが,小児期にもまれに発症する。成人GISTの多くは
CrkとCasにより媒介される腫瘍悪性化シグナル
著者: 堺隆一
ページ範囲:P.340 - P.344
がん遺伝子産物v-Crkは,酵素活性を持たないアダプタータンパク質でありながら細胞内タンパク質のチロシンリン酸化を誘導し,その独特ながん化の誘導機構に興味が持たれてきた。一方,p130Cas(以降Casと呼ぶ)はSrcファミリーキナーゼ(SFK)の主要な基質として,がんの悪性化のカギを握る分子と考えられてきた。本稿では,がんにおけるCrkやCasなどの役割について,両者の媒介するシグナルを中心にまとめたい。
Ⅱ.遺伝子技術
融合遺伝子と移植モデル
著者: 中村卓郎
ページ範囲:P.345 - P.348
ヒトのがんで同定された異常ながん遺伝子が,果たして生体内で同様のがんを誘導することが可能なのか。この疑問に答えるには動物モデルによる再現が近道である。早くから開発されたモデルとして,がん遺伝子を目標の細胞種で発現させるトランスジェニックマウスが現在も広く使われている。その後ノックアウト・ノックインマウスの開発により,変異がん遺伝子の発現を時空間的に制御することも可能となり,広く利用されるに至っている。このような胚細胞レベルで遺伝子を導入する遺伝子組換え生物としてのモデルとは別に,体細胞変異体であるがん細胞や遺伝子導入細胞を移植するモデルも古くから利用されている。
本特集が扱うがん遺伝子,特に融合遺伝子の性質を理解するために大きく貢献してきた
Ⅲ.先駆者による温故知新
著者: 服部成介
ページ範囲:P.349 - P.352
著者: 伊庭英夫
ページ範囲:P.353 - P.358
40年近く前に身を置いたOncogene Researchの分野で経験した異様とも言うべき熱気と興奮を筆者は今でも忘れることができない。この分野に入ってから,次から次へと浮かんでくる疑問と,限られた研究費のなかでこのうちどの疑問をどのように追求すべきかに悩みながら,現在まであっという間に至ってしまった気がする。本稿では,筆者のかなり限られた経験をnarrativeに振り返りながらOncogene Researchの大きな潮流の一端をお伝えしたい。若い方々の今後の研究の進め方の参考に少しでもなれば幸いである。
著者: 徳永文稔
ページ範囲:P.359 - P.364
1970年代,カリフォルニア工科大学のRenato Dulbeccoらによるレトロウイルスの研究,特にRous肉腫ウイルス(Rous sarcoma virus;RSV)の研究復興を機に腫瘍ウイルスが誘起する発がん研究が注目を浴びた。今日,各種接着細胞の培地として汎用されるDMEM(ダルベッコ変法イーグル培地)は,もともとDulbeccoらがポリオーマウイルス発がん研究用に,イーグル最小必須培地からアミノ酸とビタミン量を強化したものである。1975年,Dulbeccoとその学生であったHoward Martin Temin,同じくDulbeccoの指導を受けたDavid Baltimoreが,レトロウイルス増殖に必須な逆転写酵素(RNA依存性DNAポリメラーゼ)の発見によりノーベル生理学・医学賞を受賞した。その後もレトロウイルスが包含するがん遺伝子と宿主細胞に存在するがん原遺伝子の正常機能と異常に関する研究は,がんのみならず細胞生物学研究に莫大な貢献をした。
本稿では,TeminやBaltimoreが大いに関係する細網内皮症ウイルス(reticuloendotheliosis virus;REV)がコードするがん遺伝子の
VEGF受容体ファミリーの血管・リンパ管新生と疾患への関与
著者: 澁谷正史
ページ範囲:P.365 - P.369
約30年前,血管・リンパ管の新生を制御するシグナル系は,ほとんど明らかではなかった。しかし,1990年代にそれらを制御する基本的な系“VEGF-VEGFRファミリー”が見いだされ,現在では血管系のみならず多くの疾患との関係が明らかになっている。本稿では,これらを報告したい1,2)。
解説
—第1回生体の科学賞 受賞記念論文—充填知覚の神経機構の理解の現状 フリーアクセス
著者: 小松英彦 , 齊藤治美
ページ範囲:P.370 - P.375
視覚における充填知覚とは,視野の中のある領域に,その部分には物理的には存在しない色や明るさや模様が知覚される現象のことを指す。物理的な刺激と知覚が対応しないために一種の錯視と言えるが,実は視知覚にとって非常に重要な機能である。このことを示す古典的な例に静止網膜像の実験がある。この実験では,内側が緑色で外側が赤色の同心円の図形を見ているときに,赤色と緑色の境界が網膜上で静止するようにしてやると,しばらくすると周囲の赤色が内部もうずめて一様な赤い円盤が知覚された。この現象は,正常な視野で面が見えるときにも,面の境界部分の情報が面の内部に充填する過程が重要であることを示している。視覚野で輪郭が検出され,その情報が統合されて複雑な図形の認識が行われる処理と並行して,輪郭部分で検出された明るさや色の情報を用いて図形内部の面が形成されるのである。
充填知覚は,正常に物体を見るときに働いている基本的な視覚系のしくみが生み出す知覚現象と考えられる。前述した静止網膜像の知覚を体験するためには特殊な装置が必要だが,充填知覚は様々な事態で簡単に観察することができる。図1に幾つかの例を示した。充填知覚は視覚系の重要な機能であるにもかかわらず,その処理の実態については不明な部分が多い。本稿では,筆者らの最近の研究とそれに基づく仮説も含めて,充填知覚に関する理解の現状について述べたいと思う。
多指症を防ぐモルフォゲン濃度勾配の新しい形成機構 フリーアクセス
著者: 田中庸介
ページ範囲:P.376 - P.381
いかにして体の座標軸が定まるかは,発生生物学の永年の課題の一つであった。物質レベルは,座標軸を表象して組織のふるまいを誘導する“モルフォゲン”の濃度勾配が安定的に形成されるのはなぜか,という問いに置き換えられる。モルフォゲンを特異的に産生する細胞群を“オーガナイザー”と呼ぶ。ところが,タンパク質レベルにおいて,オーガナイザーから産生されるモルフォゲンのふるまいは初期胚ではほとんど可視化できておらず,オーガナイザー領域におけるモルフォゲン遺伝子発現と,その下流の遺伝子発現の様子から間接的に推測するほかはなかった。今回,Shhタンパク質の濃度勾配をノックアウトマウスで可視化すると共に,その形成機構を細胞生物学的に解析することにより,新しい2層性の勾配形成システムの仮説を立てることができた。
ソニック・ヘッジホッグ(Shh)は最も著名なモルフォゲンの一つである。神経管では,腹側の脊索ならびに神経管の底板から産生され,背側に向けて濃度勾配を形成する。実際,Shhシグナルが減弱する変異マウスでは神経管が背側化する1)。異なったShh濃度の培地で培養した神経前駆細胞は,それぞれの濃度に従い,異なった背腹軸分化マーカーを発現する2)。すなわち,組織はShh濃度の減衰の様子から自らの座標を知り,発生運命を決定すると考えられる。体肢芽においては,その後部にShhのmRNAを特異的に発現するオーガナイザー領域があり,極性化活性域(ZPA)と呼ばれている(図1)。体肢芽の前部に異所的にShhを発現させたり,上流の遺伝子変異によってそれを異所的に発現したりすると,手指の発生に擾乱が生じる3,4)。Shhシグナリングの下流因子であるPtch1やGli1は体肢芽の後部に強く発現し,その抑制因子のGli3はこれと拮抗する勾配を示す。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.287 - P.287
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.382 - P.383
あとがき フリーアクセス
著者: 栗原裕基
ページ範囲:P.384 - P.384
筆者が大学を卒業した約40年前は,遺伝子工学技術の確立と急速な進歩により新しい遺伝子が次々と発見された,まさに分子生物学の興隆期でした。この新しい生物学の潮流の中でその先導的役割を果たしていたのが,本特集企画のテーマである「オンコジーン研究」で,「オンコジーン」という言葉自体にさえ,若い研究者の卵を惹き付ける何か魔力のようなものを感じさせられたものでした。今回ゲストエディターをお願いした丸義朗先生は,そのような時代にまさに同世代若手の旗手としてこの分野に飛び込み,東京大学第三内科で故平井久丸先生とともに新しいオンコジーン
本特集号ではさらに,「充填知覚」という視覚系の重要な機能に関する研究で第1回生体の科学賞を受賞された小松英彦先生,発生生物学の重要課題であるモルフォゲン濃度勾配の形成機構を解明された田中庸介先生に,それぞれ解説記事を寄稿していただきました。それぞれに分野は異なりますが,生命現象の重要な機構に焦点を当てた大変興味深い内容です。ご執筆いただいたすべての先生方に,心より感謝申し上げます。(栗原裕基)
基本情報
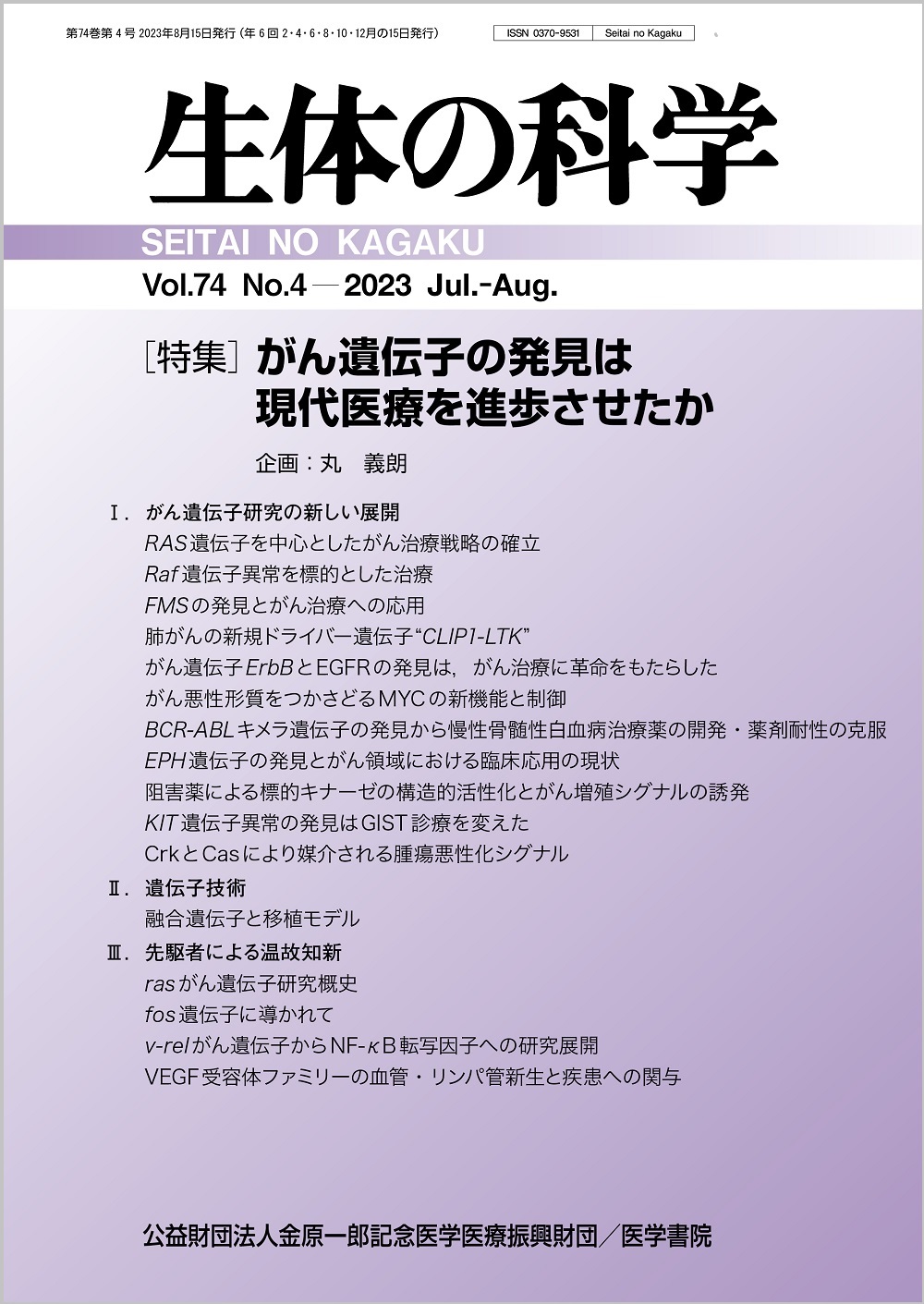
バックナンバー
75巻6号(2024年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅤ:脂肪
75巻5号(2024年10月発行)
増大特集 学術研究支援の最先端
75巻4号(2024年8月発行)
特集 シングルセルオミクス
75巻3号(2024年6月発行)
特集 高速分子動画:動的構造からタンパク質分子制御へ
75巻2号(2024年4月発行)
特集 生命現象を駆動する生体内金属動態の理解と展開
75巻1号(2024年2月発行)
特集 脳と個性
74巻6号(2023年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅣ:骨・軟骨
74巻5号(2023年10月発行)
増大特集 代謝
74巻4号(2023年8月発行)
特集 がん遺伝子の発見は現代医療を進歩させたか
74巻3号(2023年6月発行)
特集 クロマチンによる転写制御機構の最前線
74巻2号(2023年4月発行)
特集 未病の科学
74巻1号(2023年2月発行)
特集 シナプス
73巻6号(2022年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅢ:血管とリンパ管
73巻5号(2022年10月発行)
増大特集 革新脳と関連プロジェクトから見えてきた新しい脳科学
73巻4号(2022年8月発行)
特集 形態形成の統合的理解
73巻3号(2022年6月発行)
特集 リソソーム研究の新展開
73巻2号(2022年4月発行)
特集 DNA修復による生体恒常性の維持
73巻1号(2022年2月発行)
特集 意識
72巻6号(2021年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅡ:骨格筋—今後の研究の発展に向けて
72巻5号(2021年10月発行)
増大特集 脳とからだ
72巻4号(2021年8月発行)
特集 グローバル時代の新興再興感染症への科学的アプローチ
72巻3号(2021年6月発行)
特集 生物物理学の進歩—生命現象の定量的理解へ向けて
72巻2号(2021年4月発行)
特集 組織幹細胞の共通性と特殊性
72巻1号(2021年2月発行)
特集 小脳研究の未来
71巻6号(2020年12月発行)
特集 新組織学シリーズⅠ:最新の皮膚科学
71巻5号(2020年10月発行)
増大特集 難病研究の進歩
71巻4号(2020年8月発行)
特集 細胞機能の構造生物学
71巻3号(2020年6月発行)
特集 スポーツ科学—2020オリンピック・パラリンピックによせて
71巻2号(2020年4月発行)
特集 ビッグデータ時代のゲノム医学
71巻1号(2020年2月発行)
特集 睡眠の制御と機能
70巻6号(2019年12月発行)
特集 科学と芸術の接点
70巻5号(2019年10月発行)
増大特集 現代医学・生物学の先駆者たち
70巻4号(2019年8月発行)
特集 メカノバイオロジー
70巻3号(2019年6月発行)
特集 免疫チェックポイント分子による生体機能制御
70巻2号(2019年4月発行)
特集 免疫系を介したシステム連関:恒常性の維持と破綻
70巻1号(2019年2月発行)
特集 脳神経回路のダイナミクスから探る脳の発達・疾患・老化
69巻6号(2018年12月発行)
特集 細胞高次機能をつかさどるオルガネラコミュニケーション
69巻5号(2018年10月発行)
増大特集 タンパク質・核酸の分子修飾
69巻4号(2018年8月発行)
特集 いかに創薬を進めるか
69巻3号(2018年6月発行)
特集 生体膜のバイオロジー
69巻2号(2018年4月発行)
特集 宇宙の極限環境から生命体の可塑性をさぐる
69巻1号(2018年2月発行)
特集 社会性と脳
68巻6号(2017年12月発行)
特集 心臓の発生・再生・創生
68巻5号(2017年10月発行)
増大特集 細胞多様性解明に資する光技術─見て,動かす
68巻4号(2017年8月発行)
特集 血管制御系と疾患
68巻3号(2017年6月発行)
特集 核内イベントの時空間制御
68巻2号(2017年4月発行)
特集 細菌叢解析の光と影
68巻1号(2017年2月発行)
特集 大脳皮質—成り立ちから機能へ
67巻6号(2016年12月発行)
特集 時間生物学の新展開
67巻5号(2016年10月発行)
増大特集 病態バイオマーカーの“いま”
67巻4号(2016年8月発行)
特集 認知症・神経変性疾患の克服への挑戦
67巻3号(2016年6月発行)
特集 脂質ワールド
67巻2号(2016年4月発行)
特集 細胞の社会学─細胞間で繰り広げられる協調と競争
67巻1号(2016年2月発行)
特集 記憶ふたたび
66巻6号(2015年12月発行)
特集 グリア研究の最先端
66巻5号(2015年10月発行)
増大特集 細胞シグナル操作法
66巻4号(2015年8月発行)
特集 新興・再興感染症と感染症対策
66巻3号(2015年6月発行)
特集 進化と発生からみた生命科学
66巻2号(2015年4月発行)
特集 使える最新ケミカルバイオロジー
66巻1号(2015年2月発行)
特集 脳と心の謎はどこまで解けたか
65巻6号(2014年12月発行)
特集 エピジェネティクスの今
65巻5号(2014年10月発行)
増大特集 生命動態システム科学
65巻4号(2014年8月発行)
特集 古典的代謝経路の新しい側面
65巻3号(2014年6月発行)
特集 器官の発生と再生の基礎
65巻2号(2014年4月発行)
特集 細胞の少数性と多様性に挑む―シングルセルアナリシス
65巻1号(2014年2月発行)
特集 精神疾患の病理機構
64巻6号(2013年12月発行)
特集 顕微鏡で物を見ることの新しい動き
64巻5号(2013年10月発行)
増大特集 細胞表面受容体
64巻4号(2013年8月発行)
特集 予測と意思決定の神経科学
64巻3号(2013年6月発行)
特集 細胞接着の制御
64巻2号(2013年4月発行)
特集 特殊な幹細胞としての骨格筋サテライト細胞
64巻1号(2013年2月発行)
特集 神経回路の計測と操作
63巻6号(2012年12月発行)
特集 リンパ管
63巻5号(2012年10月発行)
特集 細胞の分子構造と機能―核以外の細胞小器官
63巻4号(2012年8月発行)
特集 質感脳情報学への展望
63巻3号(2012年6月発行)
特集 細胞極性の制御
63巻2号(2012年4月発行)
特集 RNA干渉の実現化に向けて
63巻1号(2012年2月発行)
特集 小脳研究の課題(2)
62巻6号(2011年12月発行)
特集 コピー数変異
62巻5号(2011年10月発行)
特集 細胞核―構造と機能
62巻4号(2011年8月発行)
特集 小脳研究の課題
62巻3号(2011年6月発行)
特集 インフラマソーム
62巻2号(2011年4月発行)
特集 筋ジストロフィーの分子病態から治療へ
62巻1号(2011年2月発行)
特集 摂食制御の分子過程
61巻6号(2010年12月発行)
特集 細胞死か腫瘍化かの選択
61巻5号(2010年10月発行)
特集 シナプスをめぐるシグナリング
61巻4号(2010年8月発行)
特集 miRNA研究の最近の進歩
61巻3号(2010年6月発行)
特集 SNARE複合体-膜融合の機構
61巻2号(2010年4月発行)
特集 糖鎖のかかわる病気:発症機構,診断,治療に向けて
61巻1号(2010年2月発行)
特集 脳科学のモデル実験動物
60巻6号(2009年12月発行)
特集 ユビキチン化による生体機能の調節
60巻5号(2009年10月発行)
特集 伝達物質と受容体
60巻4号(2009年8月発行)
特集 睡眠と脳回路の可塑性
60巻3号(2009年6月発行)
特集 脳と糖脂質
60巻2号(2009年4月発行)
特集 感染症の現代的課題
60巻1号(2009年2月発行)
特集 遺伝子-脳回路-行動
59巻6号(2008年12月発行)
特集 mTORをめぐるシグナルタンパク
59巻5号(2008年10月発行)
特集 現代医学・生物学の仮説・学説2008
59巻4号(2008年8月発行)
特集 免疫学の最近の動向
59巻3号(2008年6月発行)
特集 アディポゲネシス
59巻2号(2008年4月発行)
特集 細胞外基質-研究の新たな展開
59巻1号(2008年2月発行)
特集 コンピュータと脳
58巻6号(2007年12月発行)
特集 グリケーション(糖化)
58巻5号(2007年10月発行)
特集 タンパク質間相互作用
58巻4号(2007年8月発行)
特集 嗅覚受容の分子メカニズム
58巻3号(2007年6月発行)
特集 骨の形成と破壊
58巻2号(2007年4月発行)
特集 シナプス後部構造の形成・機構と制御
58巻1号(2007年2月発行)
特集 意識―脳科学からのアプローチ
57巻6号(2006年12月発行)
特集 血管壁
57巻5号(2006年10月発行)
特集 生物進化の分子マップ
57巻4号(2006年8月発行)
特集 脳科学が求める先端技術
57巻3号(2006年6月発行)
特集 ミエリン化の機構とその異常
57巻2号(2006年4月発行)
特集 膜リサイクリング
57巻1号(2006年2月発行)
特集 こころと脳:とらえがたいものを科学する
56巻6号(2005年12月発行)
特集 構造生物学の現在と今後の展開
56巻5号(2005年10月発行)
特集 タンパク・遺伝子からみた分子病―新しく解明されたメカニズム
56巻4号(2005年8月発行)
特集 脳の遺伝子―どこでどのように働いているのか
56巻3号(2005年6月発行)
特集 Naチャネル
56巻2号(2005年4月発行)
特集 味覚のメカニズムに迫る
56巻1号(2005年2月発行)
特集 情動―喜びと恐れの脳の仕組み
55巻6号(2004年12月発行)
特集 脳の深部を探る
55巻5号(2004年10月発行)
特集 生命科学のNew Key Word
55巻4号(2004年8月発行)
特集 心筋研究の最前線
55巻3号(2004年6月発行)
特集 分子進化学の現在
55巻2号(2004年4月発行)
特集 アダプタータンパク
55巻1号(2004年2月発行)
特集 ニューロンと脳
54巻6号(2003年12月発行)
特集 オートファジー
54巻5号(2003年10月発行)
特集 創薬ゲノミクス・創薬プロテオミクス・創薬インフォマティクス
54巻4号(2003年8月発行)
特集 ラフトと細胞機能
54巻3号(2003年6月発行)
特集 クロマチン
54巻2号(2003年4月発行)
特集 樹状突起
54巻1号(2003年2月発行)
53巻6号(2002年12月発行)
特集 ゲノム全解読とポストゲノムの問題点
53巻5号(2002年10月発行)
特集 加齢の克服―21世紀の課題
53巻4号(2002年8月発行)
特集 一価イオンチャネル
53巻3号(2002年6月発行)
特集 細胞質分裂
53巻2号(2002年4月発行)
特集 RNA
53巻1号(2002年2月発行)
連続座談会 脳とこころ―21世紀の課題
52巻6号(2001年12月発行)
特集 血液脳関門研究の最近の進歩
52巻5号(2001年10月発行)
特集 モチーフ・ドメインリスト
52巻4号(2001年8月発行)
特集 骨格筋研究の新展開
52巻3号(2001年6月発行)
特集 脳の発達に関与する分子機構
52巻2号(2001年4月発行)
特集 情報伝達物質としてのATP
52巻1号(2001年2月発行)
連続座談会 脳を育む
51巻6号(2000年12月発行)
特集 機械的刺激受容の分子機構と細胞応答
51巻5号(2000年10月発行)
特集 ノックアウトマウスリスト
51巻4号(2000年8月発行)
特集 臓器(組織)とアポトーシス
51巻3号(2000年6月発行)
特集 自然免疫における異物認識と排除の分子機構
51巻2号(2000年4月発行)
特集 細胞極性の形成機序
51巻1号(2000年2月発行)
特集 脳を守る21世紀生命科学の展望
50巻6号(1999年12月発行)
特集 細胞内輸送
50巻5号(1999年10月発行)
特集 病気の分子細胞生物学
50巻4号(1999年8月発行)
特集 トランスポーターの構造と機能協関
50巻3号(1999年6月発行)
特集 時間生物学の新たな展開
50巻2号(1999年4月発行)
特集 リソソーム:最近の研究
50巻1号(1999年2月発行)
連続座談会 脳を守る
49巻6号(1998年12月発行)
特集 発生・分化とホメオボックス遺伝子
49巻5号(1998年10月発行)
特集 神経系に作用する薬物マニュアル1998
49巻4号(1998年8月発行)
特集 プロテインキナーゼCの多様な機能
49巻3号(1998年6月発行)
特集 幹細胞研究の新展開
49巻2号(1998年4月発行)
特集 血管―新しい観点から
49巻1号(1998年2月発行)
特集 言語の脳科学
48巻6号(1997年12月発行)
特集 軸索誘導
48巻5号(1997年10月発行)
特集 受容体1997
48巻4号(1997年8月発行)
特集 マトリックス生物学の最前線
48巻3号(1997年6月発行)
特集 開口分泌のメカニズムにおける新しい展開
48巻2号(1997年4月発行)
特集 最近のMAPキナーゼ系
48巻1号(1997年2月発行)
特集 21世紀の脳科学
47巻6号(1996年12月発行)
特集 老化
47巻5号(1996年10月発行)
特集 器官―その新しい視点
47巻4号(1996年8月発行)
特集 エンドサイトーシス
47巻3号(1996年6月発行)
特集 細胞分化
47巻2号(1996年4月発行)
特集 カルシウム動態と細胞機能
47巻1号(1996年2月発行)
特集 神経科学の最前線
46巻6号(1995年12月発行)
特集 病態を変えたよく効く医薬
46巻5号(1995年10月発行)
特集 遺伝子・タンパク質のファミリー・スーパーファミリー
46巻4号(1995年8月発行)
特集 ストレス蛋白質
46巻3号(1995年6月発行)
特集 ライソゾーム
46巻2号(1995年4月発行)
特集 プロテインホスファターゼ―最近の進歩
46巻1号(1995年2月発行)
特集 神経科学の謎
45巻6号(1994年12月発行)
特集 ミトコンドリア
45巻5号(1994年10月発行)
特集 動物の行動機能テスト―個体レベルと分子レベルを結ぶ
45巻4号(1994年8月発行)
特集 造血の機構
45巻3号(1994年6月発行)
特集 染色体
45巻2号(1994年4月発行)
特集 脳と分子生物学
45巻1号(1994年2月発行)
特集 グルコーストランスポーター
44巻6号(1993年12月発行)
特集 滑面小胞体をめぐる諸問題
44巻5号(1993年10月発行)
特集 現代医学・生物学の仮説・学説
44巻4号(1993年8月発行)
特集 細胞接着
44巻3号(1993年6月発行)
特集 カルシウムイオンを介した調節機構の新しい問題点
44巻2号(1993年4月発行)
特集 蛋白質の細胞内転送とその異常
44巻1号(1993年2月発行)
座談会 脳と遺伝子
43巻6号(1992年12月発行)
特集 成長因子受容体/最近の進歩
43巻5号(1992年10月発行)
特集 〈研究室で役に立つ細胞株〉
43巻4号(1992年8月発行)
特集 細胞機能とリン酸化
43巻3号(1992年6月発行)
特集 血管新生
43巻2号(1992年4月発行)
特集 大脳皮質発達の化学的側面
43巻1号(1992年2月発行)
特集 意識と脳
42巻6号(1991年12月発行)
特集 細胞活動の日周リズム
42巻5号(1991年10月発行)
特集 神経系に作用する薬物マニュアル
42巻4号(1991年8月発行)
特集 開口分泌の細胞内過程
42巻3号(1991年6月発行)
特集 ペルオキシソーム/最近の進歩
42巻2号(1991年4月発行)
特集 脳の移植と再生
42巻1号(1991年2月発行)
特集 脳と免疫
41巻6号(1990年12月発行)
特集 注目の実験モデル動物
41巻5号(1990年10月発行)
特集 LTPとLTD:その分子機構
41巻4号(1990年8月発行)
特集 New proteins
41巻3号(1990年6月発行)
特集 シナプスの形成と動態
41巻2号(1990年4月発行)
特集 細胞接着
41巻1号(1990年2月発行)
特集 発がんのメカニズム/最近の知見
40巻6号(1989年12月発行)
特集 ギャップ結合
40巻5号(1989年10月発行)
特集 核内蛋白質
40巻4号(1989年8月発行)
特集 研究室で役に立つ新しい試薬
40巻3号(1989年6月発行)
特集 細胞骨格異常
40巻2号(1989年4月発行)
特集 大脳/神経科学からのアプローチ
40巻1号(1989年2月発行)
特集 分子進化
39巻6号(1988年12月発行)
特集 細胞内における蛋白質局在化機構
39巻5号(1988年10月発行)
特集 細胞測定法マニュアル
39巻4号(1988年8月発行)
特集 細胞外マトリックス
39巻3号(1988年6月発行)
特集 肺の微細構造と機能
39巻2号(1988年4月発行)
特集 生体運動の分子機構/研究の発展
39巻1号(1988年2月発行)
特集 遺伝子疾患解析の発展
38巻6号(1987年12月発行)
-チャンネルの最近の動向
38巻5号(1987年10月発行)
特集 細胞生物学における免疫実験マニュアル
38巻4号(1987年8月発行)
特集 視覚初期過程の分子機構
38巻3号(1987年6月発行)
特集 人間の脳
38巻2号(1987年4月発行)
特集 体液カルシウムのホメオスタシス
38巻1号(1987年2月発行)
特集 医学におけるブレイクスルー/基礎研究からの挑戦
37巻6号(1986年12月発行)
特集 神経活性物質受容体と情報伝達
37巻5号(1986年10月発行)
特集 中間径フィラメント
37巻4号(1986年8月発行)
特集 細胞生物学実験マニュアル
37巻3号(1986年6月発行)
特集 脳の化学的トポグラフィー
37巻2号(1986年4月発行)
特集 血小板凝集
37巻1号(1986年2月発行)
特集 脳のモデル
36巻6号(1985年12月発行)
特集 脂肪組織
36巻5号(1985年10月発行)
特集 細胞分裂をめぐって
36巻4号(1985年8月発行)
特集 神経科学実験マニュアル
36巻3号(1985年6月発行)
特集 血管内皮細胞と微小循環
36巻2号(1985年4月発行)
特集 肝細胞と胆汁酸分泌
36巻1号(1985年2月発行)
特集 Transmembrane Control
35巻6号(1984年12月発行)
特集 細胞毒マニュアル—実験に用いられる細胞毒の知識
35巻5号(1984年10月発行)
特集 中枢神経系の再構築
35巻4号(1984年8月発行)
特集 ゲノムの構造
35巻3号(1984年6月発行)
特集 神経科学の仮説
35巻2号(1984年4月発行)
特集 哺乳類の初期発生
35巻1号(1984年2月発行)
特集 細胞生物学の現状と展望
34巻6号(1983年12月発行)
特集 蛋白質の代謝回転
34巻5号(1983年10月発行)
特集 受容・応答の膜分子論
34巻4号(1983年8月発行)
特集 コンピュータによる生物現象の再構成
34巻3号(1983年6月発行)
特集 細胞の極性
34巻2号(1983年4月発行)
特集 モノアミン系
34巻1号(1983年2月発行)
特集 腸管の吸収機構
33巻6号(1982年12月発行)
特集 低栄養と生体機能
33巻5号(1982年10月発行)
特集 成長因子
33巻4号(1982年8月発行)
特集 リン酸化
33巻3号(1982年6月発行)
特集 神経発生の基礎
33巻2号(1982年4月発行)
特集 細胞の寿命と老化
33巻1号(1982年2月発行)
特集 細胞核
32巻6号(1981年12月発行)
特集 筋小胞体研究の進歩
32巻5号(1981年10月発行)
特集 ペプチド作働性シナプス
32巻4号(1981年8月発行)
特集 膜の転送
32巻3号(1981年6月発行)
特集 リポプロテイン
32巻2号(1981年4月発行)
特集 チャネルの概念と実体
32巻1号(1981年2月発行)
特集 細胞骨格
31巻6号(1980年12月発行)
特集 大脳の機能局在
31巻5号(1980年10月発行)
特集 カルシウムイオン受容タンパク
31巻4号(1980年8月発行)
特集 化学浸透共役仮説
31巻3号(1980年6月発行)
特集 赤血球膜の分子構築
31巻2号(1980年4月発行)
特集 免疫系の情報識別
31巻1号(1980年2月発行)
特集 ゴルジ装置
30巻6号(1979年12月発行)
特集 細胞間コミニケーション
30巻5号(1979年10月発行)
特集 In vitro運動系
30巻4号(1979年8月発行)
輸送系の調節
30巻3号(1979年6月発行)
特集 網膜の構造と機能
30巻2号(1979年4月発行)
特集 神経伝達物質の同定
30巻1号(1979年2月発行)
特集 生物物理学の進歩—第6回国際生物物理学会議より
29巻6号(1978年12月発行)
特集 最近の神経科学から
29巻5号(1978年10月発行)
特集 下垂体:前葉
29巻4号(1978年8月発行)
特集 中枢のペプチド
29巻3号(1978年6月発行)
特集 心臓のリズム発生
29巻2号(1978年4月発行)
特集 腎機能
29巻1号(1978年2月発行)
特集 膜脂質の再検討
28巻6号(1977年12月発行)
特集 青斑核
28巻5号(1977年10月発行)
特集 小胞体
28巻4号(1977年8月発行)
特集 微小管の構造と機能
28巻3号(1977年6月発行)
特集 神経回路網と脳機能
28巻2号(1977年4月発行)
特集 生体の修復
28巻1号(1977年2月発行)
特集 生体の科学の現状と動向
27巻6号(1976年12月発行)
特集 松果体
27巻5号(1976年10月発行)
特集 遺伝マウス・ラット
27巻4号(1976年8月発行)
特集 形質発現における制御
27巻3号(1976年6月発行)
特集 生体と化学的環境
27巻2号(1976年4月発行)
特集 分泌腺
27巻1号(1976年2月発行)
特集 光受容
26巻6号(1975年12月発行)
特集 自律神経と平滑筋の再検討
26巻5号(1975年10月発行)
特集 脳のプログラミング
26巻4号(1975年8月発行)
特集 受精機構をめぐつて
26巻3号(1975年6月発行)
特集 細胞表面と免疫
26巻2号(1975年4月発行)
特集 感覚有毛細胞
26巻1号(1975年2月発行)
特集 体内のセンサー
25巻5号(1974年12月発行)
特集 生体膜—その基本的課題
25巻4号(1974年8月発行)
特集 伝達物質と受容物質
25巻3号(1974年6月発行)
特集 脳の高次機能へのアプローチ
25巻2号(1974年4月発行)
特集 筋細胞の分化
25巻1号(1974年2月発行)
特集 生体の科学 展望と夢
24巻6号(1973年12月発行)
24巻5号(1973年10月発行)
24巻4号(1973年8月発行)
24巻3号(1973年6月発行)
24巻2号(1973年4月発行)
24巻1号(1973年2月発行)
23巻6号(1972年12月発行)
23巻5号(1972年10月発行)
23巻4号(1972年8月発行)
23巻3号(1972年6月発行)
23巻2号(1972年4月発行)
23巻1号(1972年2月発行)
22巻6号(1971年12月発行)
22巻5号(1971年10月発行)
22巻4号(1971年8月発行)
22巻3号(1971年6月発行)
22巻2号(1971年4月発行)
22巻1号(1971年2月発行)
21巻7号(1970年12月発行)
21巻6号(1970年10月発行)
21巻4号(1970年8月発行)
特集 代謝と機能
21巻5号(1970年8月発行)
21巻3号(1970年6月発行)
21巻2号(1970年4月発行)
21巻1号(1970年2月発行)
20巻6号(1969年12月発行)
20巻5号(1969年10月発行)
20巻4号(1969年8月発行)
20巻3号(1969年6月発行)
20巻2号(1969年4月発行)
20巻1号(1969年2月発行)
19巻6号(1968年12月発行)
19巻5号(1968年10月発行)
19巻4号(1968年8月発行)
19巻3号(1968年6月発行)
19巻2号(1968年4月発行)
19巻1号(1968年2月発行)
18巻6号(1967年12月発行)
18巻5号(1967年10月発行)
18巻4号(1967年8月発行)
18巻3号(1967年6月発行)
18巻2号(1967年4月発行)
18巻1号(1967年2月発行)
17巻6号(1966年12月発行)
17巻5号(1966年10月発行)
17巻4号(1966年8月発行)
17巻3号(1966年6月発行)
17巻2号(1966年4月発行)
17巻1号(1966年2月発行)
16巻6号(1965年12月発行)
16巻5号(1965年10月発行)
16巻4号(1965年8月発行)
16巻3号(1965年6月発行)
16巻2号(1965年4月発行)
16巻1号(1965年2月発行)
15巻6号(1964年12月発行)
特集 生体膜その3
15巻5号(1964年10月発行)
特集 生体膜その2
15巻4号(1964年8月発行)
特集 生体膜その1
15巻3号(1964年6月発行)
特集 第13回日本生理科学連合シンポジウム
15巻2号(1964年4月発行)
15巻1号(1964年2月発行)
14巻6号(1963年12月発行)
特集 興奮收縮伝関
14巻5号(1963年10月発行)
14巻4号(1963年8月発行)
14巻3号(1963年6月発行)
14巻1号(1963年2月発行)
特集 第9回中枢神経系の生理学シンポジウム
14巻2号(1963年2月発行)
13巻6号(1962年12月発行)
13巻5号(1962年10月発行)
特集 生物々理—生理学生物々理若手グループ第1回ミーティングから
13巻4号(1962年8月発行)
13巻3号(1962年6月発行)
13巻2号(1962年4月発行)
Symposium on Permeability of Biological Membranes
13巻1号(1962年2月発行)
12巻6号(1961年12月発行)
12巻5号(1961年10月発行)
12巻4号(1961年8月発行)
12巻3号(1961年6月発行)
12巻2号(1961年4月発行)
12巻1号(1961年2月発行)
11巻6号(1960年12月発行)
Symposium On Active Transport
11巻5号(1960年10月発行)
11巻4号(1960年8月発行)
11巻3号(1960年6月発行)
11巻2号(1960年4月発行)
11巻1号(1960年2月発行)
10巻6号(1959年12月発行)
10巻5号(1959年10月発行)
10巻4号(1959年8月発行)
10巻3号(1959年6月発行)
10巻2号(1959年4月発行)
10巻1号(1959年2月発行)
8巻6号(1957年12月発行)
8巻5号(1957年10月発行)
特集 酵素と生物
8巻4号(1957年8月発行)
8巻3号(1957年6月発行)
8巻2号(1957年4月発行)
8巻1号(1957年2月発行)
