故堅田五郞博士の書かれた「日本に於ける精神病学の日乗」のなかから,明治,大正から昭和4年に亘る間の精神病院の災禍だけをひろつて見ても,精神病院の少かつたその当時でも14件も数えられ,大体5年毎に病院が火災に見舞われていたことになるが,近年精神病院の増加と共にその火災の率が殖えたことは寒心に堪えないのである。樫田博士の調査の内で最も悲惨なのは,明治35年4月の京都船岡情神病院の火災で,60名の収容患者の内17名の焼死者を出したことは,今日までの犠牲者の率から見れば最高とも云えるのである。失火の原因の内で患者の放火によるものが2件ある。中でも大正10年1月函館区立精神病院で2日前に入院した患者が,隠し持つたマツチで放火して逃走を企てたが,その患者を阻止しようとした看護人の小指を噛み切つて逃走した珍らしい事件もある。その後昭和5年以降は確実な調査資料が得られないが,私の記憶だけでも相当数に昇つている。そのうち焼死者を出したものもかなりの件数である。
かように精神病院の火災は危険が伴うことが多いので,ややもすると人命の犠牲者を出すことになるが,かかる惨事は絶対にあつてはならぬのである。
雑誌目次
病院13巻5号
1955年11月発行
雑誌目次
--------------------
精神病院の非常事態に備えて
著者: 関根眞一
ページ範囲:P.2 - P.5
Closed Systemと医師の勤務体制(2)—病院人事管理のうち
著者: 石原信吾
ページ範囲:P.7 - P.13
テイラー(Taylor)を先達とする所謂科学的管理法が「正当なる作業量に対する正当なる賃金」(fair day's pay for fair day's task)の決定ということから出発したことは周知の通りである。賃金乃至俸給が,提供された労働力に対する反対給付である以上,この兩者の正当な等価関係を樹立することは,経営の合理化という点で第一の先決問題であることは言うまでもい。テイラーはその為に先ずtaskの標準化を科学的に検討することから始めたのである。
所で,病院に於ては,特に勤務医師の勤務に関して,このtaskの標準化及びtaskとpayとの正当なる等価的結び付きは完全に実現しているであろうか。医師に言わせれば,自分達は働きの割合に俸給が少いと主張するであろうし,病院側に言わせれば,医師は出来るだけ仕事を少くすることばかり考えていると主張するかも知れない。其処から窺われることは,現在わが国の病院では,医師のtaskとpayとは必ずしも等式関係にはなつていないということである。仕事は仕事俸給は俸給ということであれば,働かせる側では出来るだけ多くの働きを望むし,働く側では出来るだけ仕事の少いことを願うのは,当然であろう。とすれば,其処では医師の働きを刺戟するものは,少くとも俸給ではない。では何が刺戟となるか。場合によりそれは「医は仁術」という仕事に対する使命観だと言われる。
病院管理のやり方の一指針(2)
著者: 厚生省国立病院課
ページ範囲:P.15 - P.23
会護及び委員会
院長は本省の方針に従い,その範囲内で管理の全責任を負つてゆくのであるが,その際,院長個人の意見のみで運営してゆくと時により独裁,独善になり易く,又職員の創意工夫を阻み,職員の積極的な協力を得られないこととなるから,病院においては,会議及び委員会をおき,運営の適正化,明朗化をはかることが必要である。
以下,会議及び委員会(以下会議という)についての若干の心得と注意とを記述し,会議を有効に実施するうえの参考に供したい。
病院の病歴室
著者: 田口和枝
ページ範囲:P.25 - P.34
病院の一つの大きな任務として,そこで取り扱つた患者の明確な病症記録の作製や保管が重要である事は申す迄もありませんが,近年,我が国の病院でもこの方面の関心がたかまりつつあるのは喜ばしい現象だと思います。東一病院では,病歴が正確且つ完全に書かれる様に,よりたやすく,便利に利用出来る様に,という目的を持つて,昭和27年7月から,図書室の一部に病歴室を設け,病歴係を置いて,入院患者の病歴(病症記録)の保管整備を始めた事は,既に御存知の方も多いと思います。
近頃「私の所でも始めたいから」という見学の方も大分来られますので,ここに,私どもの現状及び体験を述べ,御参考に供したいと思います。私どもとしましても,これが完全なものであるとはもとより考えておりませんが,国立病院として,未だこうした仕事の分野が正式に認められてないために,定員や予算の裏附けが得られないという恵まれない条件の下に於ける,一つの試みとして御覧願いたいと思います。
病院外来部組織とサービスの改善(2)
著者: 金子敏輔
ページ範囲:P.36 - P.42
患者受付と診療分類
外来に於てはじめ患者の受付けRegistrationをまず行い,いろいろ必要事項をきいて診療券を発行するが,それからさき患者を外来診療部にどう分類して届けるかは外来のあり方の大きな問題である。いまこの患者が診療部各科に廻る過程を分けると,
1.患者自ら診療科名を決め,その科に廻る場合
2.自ら診療科名を選ぶほか,特に担当医師を指名する場合3.受付事務員に相談するか,事務員が診療科を指定して廻す場合4.外来勤務看護婦または婦長等に相談して指定專門科に案内される場合5.受付事務室接近の受入室Admitting officeに於てOPD担当医,即ちAdmitting physicianが予選診察Preliminary examinationをしてそれによつて予備分類medical classificationをして適切なる診療科に廻す方法
以上は新,旧患,救急患等によつてそれぞれ取扱いが違うが,もし分類が不明であれば一応ある科に廻して診断を確定してから診療科を決めることもあろう。この場合条件つきで受入担当医予備検査の際メモを附記することになろう。しかしアメリカの如く,こんな場合の綜合診断部があれば理想である。すなわちmedical diagnostic de-partmentである。この場合内科に附属させる行き方と分離して行う場合が考えられる。
女流建築家のみた欧洲の病院
著者: 船越輝子
ページ範囲:P.43 - P.45
今年の3月,若い建築家の団体,建築研究団体連絡会から派遣されてベルリンで開催された国際建築資材木材労働者会議に出席,その後ルーマニヤ,ソ聯,中国を経由して5月29日に帰国いたしました。
各国一個所宛位の割合で病院を見学して参りましたが,これを読んで下さるかも知れないお医者様や病院経営者の方から見ると,まるで大事な所は見落して来ている見聞記で,さぞ焦つたい思いをなさる事で御座いましよう。そうかと云つて建築的な方面から見てピタリツと焦点が合つているかと云えばそうでもないので,どうも困つた代物で御座います。
診察室の壁畫
著者: 関川弘道
ページ範囲:P.47 - P.53
国立嬉野病院の壁画
国立嬉野病院(佐賀県藤津郡嬉野町)に於ける壁画は,小生各病院を廻つた中で最も感激したものである。この壁画は昭和26年に現在長崎大学の小兒科の助教授里見正義氏の作品である(当時国立嬉野病院小兒科医長)。この壁画の製作は夏実施せられ,当時当病院庶務課長中島盛一氏(現在国立別府病院庶務課長)の決裁により施行せられたものである。
中島氏の話によると当時院長であつた古屋野博士(現長崎大学学長)が欧州からの帰路露国の旅館に於て壁画のある部屋に泊り,旅愁を慰めてくれた壁画が忘れ得ず,患者の心理療法の一助になる事を思い立ち里見氏と相談しこれが施行に当つたものという。
病院史概説(19)
著者: 岩佐潔
ページ範囲:P.55 - P.61
XX.20世紀のアメリカ病院
1)病院統計とリストの歴史
19世紀の後半に到り病院の性格は一変した。それは既に述べた様に近代医学の確立,諸技術の進歩,社会構造の変革等色々な要素に原因されていた。かくして今日我々が近代病院として認識する様な,内容について言えば科学的であり経営面より見れば合理的である病院が外面的には堂々たる高層建築として出現して来たのが20世紀の病院である。しかも,この様な高度の大規模病院が雨後の茸の様に続々として建造されているという点に今世紀の特長がある。これまで我々が各世紀の大病院として,特にその名を列挙して来た病院よりも遙に大きく遙に優れている病院を今や各地に無数に持つている。従つて我々は個々の病院について多くを語ることは出来ない。寧ろ統計的に病院増加の推移を観察する方が適切であろう。アメリカにおける病院リストの最初のものは教育庁の役人M. Tonerが編纂して1873年にアメリカ医師会から発表されたものである。
これによると1872年現在収容施設を有する病院は178でその年間入院患者総数は146,472人となつている。地区別病院数は第1表の如くで又設立年次別に見れば第2表の如く加速度的にその増加率が上昇している。経営主体による分類は第3表の様になされているがこれ等径営主体の内容については説明がない。
Doctors' Taperecord
ページ範囲:P.63 - P.64
見知らぬ人でなく
表題の映画の試写をみた。これはDr. MortonThompsonのベストセラー小説"Not as a stranger"の映画化であつて,このアメリカ映画が我が国の一般大衆にどの程度アツピールするか分らないが,医療関係者にとつては多くの興味ある話題を提供してくれる内容をもつている。2時間半に垂んとする長時間を殆んど飽かせないのは,アメリカ映画のテンポの早さだけではなさそうだ。勿論フイクシヨンであるからには或程度の誇張といつたものは免れないが,アメリカの医学生や医師の生態をかなりよく描写している。ここに描かれた医学生生活は我が国の実態からみると多分に現実ばなれした感じがなくはないが,これはむしろかなり正直な描写といつてよいであろう。教授が学生に呼びかける「ジエントルマン!」ということばが示している様に,アメリカでは医学課程はポストグラジユエイトであるから,医学生は既に一人前の紳士,即ち社会人として取扱われ,その様な生活態度が許されてもいる。医学生と看護婦との関係もそうした現実の上に理解さるべきであろう。この映画は究極に於て,医学のヒユーマニズムの昂揚を謳つているのであるが,一方今日のアメリカ医学のあり方,医師のあり方に対する痛烈な諷刺も含んでいる。
基本情報
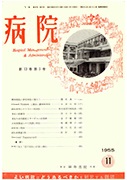
バックナンバー
83巻12号(2024年12月発行)
特集 検証 2024年度診療報酬改定—病院の機能分化と連携の行方
83巻11号(2024年11月発行)
特集 病院の価値を創る組織マネジメント
83巻10号(2024年10月発行)
特集 遠隔支援の新時代—未来のビジョンとその実現に向けて
83巻9号(2024年9月発行)
特集 持続可能な病院運営のためのコスト管理
83巻8号(2024年8月発行)
特集 潜在医療資格者をいかに活用するか
83巻7号(2024年7月発行)
特集 病院経営を科学する
83巻6号(2024年6月発行)
特集 人を重視した病院組織マネジメント
83巻5号(2024年5月発行)
特集 働き方改革を乗り越える組織変革と人材育成—エイジダイバーシティの価値を引き出す
83巻4号(2024年4月発行)
特集 地域医療連携推進法人の成功事例
83巻3号(2024年3月発行)
特集 病床稼働率アップ!—PFM導入がもたらす絶大な効果
83巻2号(2024年2月発行)
特集 在宅医療を巡る病院の経営戦略
83巻1号(2024年1月発行)
特集 超高齢者激増時代の病院経営戦略
82巻12号(2023年12月発行)
特集 人を活かす病院経営—地域で病院の存在意義を発揮するために
82巻11号(2023年11月発行)
特集 医療法人の徹底活用
82巻10号(2023年10月発行)
特集 —地域ニーズに合致した—病院機能の変革
82巻9号(2023年9月発行)
特集 —ある日突然,電カルが止まった—どうする,病院のサイバーセキュリティ
82巻8号(2023年8月発行)
特集 病院経営から考える医薬分業
82巻7号(2023年7月発行)
特集 病院リハビリテーションの進化
82巻6号(2023年6月発行)
特集 急増する高齢者救急—医療提供体制の見直しと自院の役割
82巻5号(2023年5月発行)
特集 生き残りをかけた病院の事業連携・統合—多様化する手法
82巻4号(2023年4月発行)
特集 DXでタスク・シフトせよ—働き方改革の打開策
82巻3号(2023年3月発行)
特集 これからの重症度,医療・看護必要度
82巻2号(2023年2月発行)
特集 コロナパンデミック後の病院スタッフのメンタルヘルスケア
82巻1号(2023年1月発行)
特集 社会保障制度の未来から読む病院経営
81巻12号(2022年12月発行)
特集 検証 2022年度診療報酬改定
81巻11号(2022年11月発行)
特集 戦略的病院広報—病院の魅力を高めリスクを減らす
81巻10号(2022年10月発行)
特集 心理的安全性がつくる新しい病院組織—イノベーションとリスクマネジメントの両輪を回す
81巻9号(2022年9月発行)
特集 想定外を想定せよ—病院BCPのバージョンアップ
81巻8号(2022年8月発行)
特集 病院給食の新しいカタチ
81巻7号(2022年7月発行)
特集 選定療養・評価療養制度のこれから
81巻6号(2022年6月発行)
特集 どうなる,どうする病院の外来
81巻5号(2022年5月発行)
特集 病院人事マネジメントの具体策
81巻4号(2022年4月発行)
特集 ポストコロナを見据えた公立・公的病院と民間病院の役割分担
81巻3号(2022年3月発行)
特集 これからの地域共生社会と病院経営の未来
81巻2号(2022年2月発行)
特集 すぐそこまで来た,医師の働き方改革—課題と実現可能性
81巻1号(2022年1月発行)
特集 COVID-19パンデミックから地域医療構想を再考する
80巻12号(2021年12月発行)
特集 ワクワクする病院組織づくりは可能か—人間重視の病院組織マネジメント
80巻11号(2021年11月発行)
特集 病院とお金の深い関係
80巻10号(2021年10月発行)
特集 新・ケアミックスが病院を変える—超高齢社会の患者ニーズの複合化への対応
80巻9号(2021年9月発行)
特集 次世代の病院経営者をどう育てるか
80巻8号(2021年8月発行)
特集 データヘルスで変わる病院
80巻7号(2021年7月発行)
特集 地域包括ケア時代における病院の在宅への関わり方
80巻6号(2021年6月発行)
特集 超高齢時代のリハビリテーション評価
80巻5号(2021年5月発行)
特集 働き方改革のための生産性向上
80巻4号(2021年4月発行)
特集 医薬品・医療材料をどうコントロールするか
80巻3号(2021年3月発行)
特集 Withコロナ時代の病院経営
80巻2号(2021年2月発行)
特集 大学病院は地域病院を支えられるか
80巻1号(2021年1月発行)
特集 地域医療構想を踏まえた病院機能の選択
79巻12号(2020年12月発行)
特集 2020年診療報酬改定から読む病院経営
79巻11号(2020年11月発行)
特集 医療経済からみた病院経営
79巻10号(2020年10月発行)
特集 重症度,医療・看護必要度 見直しの方向性
79巻9号(2020年9月発行)
特集 選択と集中で生き残る病院
79巻8号(2020年8月発行)
特集 病院総合医を活かす
79巻7号(2020年7月発行)
特集 病院再生はドラマだ!
79巻6号(2020年6月発行)
特集 できる事務長の育て方
79巻5号(2020年5月発行)
特集 地域包括ケアで輝く病院
79巻4号(2020年4月発行)
特集 グループ化する病院
79巻3号(2020年3月発行)
特集 病院建築の潮流
79巻2号(2020年2月発行)
特集 病院の殻を破れるか—中小病院の柔軟性を生かす経営改革
79巻1号(2020年1月発行)
特集 地域医療構想で変わるこれからの病院
78巻12号(2019年12月発行)
特集 本格化する病院のアウトカム評価
78巻11号(2019年11月発行)
特集 病院と患者の関係—informed consentを越えて
78巻10号(2019年10月発行)
特集 病院の生産性を向上させる人材育成戦略
78巻9号(2019年9月発行)
特集 ガバナンス改革で変わる病院
78巻8号(2019年8月発行)
特集 ICTが変える病院医療
78巻7号(2019年7月発行)
特集 多国籍社会に直面する病院
78巻6号(2019年6月発行)
特集 地域の健康を支える病院
78巻5号(2019年5月発行)
特集 地域の医療を残すために—病院の統合・再編
78巻4号(2019年4月発行)
特集 どうする,病院食
78巻3号(2019年3月発行)
特集 情報爆発へ病院はいかに対応するか
78巻2号(2019年2月発行)
特集 病院医療に専門医制度は貢献するか
78巻1号(2019年1月発行)
特集 平成の病院医療から次の時代へ
77巻12号(2018年12月発行)
特集 検証 平成30年度診療報酬・介護報酬同時改定
77巻11号(2018年11月発行)
特集 働き方改革の行方
77巻10号(2018年10月発行)
特集 病院マネジメント職に求められるもの
77巻9号(2018年9月発行)
特集 キャリアとして選ばれる地域病院
77巻8号(2018年8月発行)
特集 ダイバーシティ・マネジメント—多様性に対応する
77巻7号(2018年7月発行)
特集 これからの地域医療連携の形—地域医療連携推進法人とアライアンス
77巻6号(2018年6月発行)
特集 機能転換が拓く病院の未来
77巻5号(2018年5月発行)
特集 看護職のタスクシフト・タスクシェア
77巻4号(2018年4月発行)
特集 病院が直面する「すでに起こった未来」
77巻3号(2018年3月発行)
特集 地域とともに進化する中小病院
77巻2号(2018年2月発行)
特集 ステークホルダーマネジメントとしての病院広報
77巻1号(2018年1月発行)
特集 病院は2035年の夢を見るか
76巻12号(2017年12月発行)
特集 上手に補助金を活用する
76巻11号(2017年11月発行)
特集 病院の生産性とは何か
76巻10号(2017年10月発行)
特集 医師の働き方改革
76巻9号(2017年9月発行)
特集 「生きる」をデザインする病院—医療の再構築に挑戦する
76巻8号(2017年8月発行)
特集 終末期と向き合う病院
76巻7号(2017年7月発行)
特集 第7次医療計画─これまでと何が違うのか,病院への影響は?
76巻6号(2017年6月発行)
特集 備えよ常に! 病院のBCPを整備せよ
76巻5号(2017年5月発行)
特集 地域を支える病院看護師の育成
76巻4号(2017年4月発行)
特集 生き残る病院の事務職
76巻3号(2017年3月発行)
特集 2035年に生き残る病院組織論
76巻2号(2017年2月発行)
特集 DPCの新展開
76巻1号(2017年1月発行)
特集 新時代に備える病院のあり方
75巻12号(2016年12月発行)
特集 検証 平成28年度診療報酬改定
75巻11号(2016年11月発行)
特集 期待される地域包括ケア病棟・療養病床
75巻10号(2016年10月発行)
特集 地域医療構想時代の救急医療
75巻9号(2016年9月発行)
特集 病院は認知症とどう向き合うべきか
75巻8号(2016年8月発行)
特集 新専門医制度─どうなる,病院?
75巻7号(2016年7月発行)
特集 地域づくりの核としての病院
75巻6号(2016年6月発行)
特集 IPWの時代─チーム医療のための多職種間教育
75巻5号(2016年5月発行)
特集 ポジティブ・マネジメント いきいき働く職場づくり
75巻4号(2016年4月発行)
特集 医療介護連携─地域包括ケアシステムを構築するために
75巻3号(2016年3月発行)
特集 国民健康保険制度の組織改革が病院に何をもたらすか
75巻2号(2016年2月発行)
特集 進化するDPC
75巻1号(2016年1月発行)
特集 データマネジメントで変わる病院
74巻12号(2015年12月発行)
特集 ロジスティクスが病院を変える
74巻11号(2015年11月発行)
特集 医療の質指標 新時代の幕開け
74巻10号(2015年10月発行)
特集 病院の外来戦略
74巻9号(2015年9月発行)
特集 自治体病院改革は成功するのか
74巻8号(2015年8月発行)
特集 地域医療構想策定ガイドラインをどう読み解くか
74巻7号(2015年7月発行)
特集 地域創生に病院は貢献するか
74巻6号(2015年6月発行)
特集 経済学からみたこれからの医療
74巻5号(2015年5月発行)
特集 地域包括ケアの中核としての病院看護部門
74巻4号(2015年4月発行)
特集 在宅医療を支える病院
74巻3号(2015年3月発行)
特集 地域医療構想─来たるべき大変革の特効薬たりえるか
74巻2号(2015年2月発行)
特集 真のチーム医療とは
74巻1号(2015年1月発行)
特集 地域包括ケア病棟は医療を変えるか
73巻12号(2014年12月発行)
特集 検証 平成26年度診療報酬改定
73巻11号(2014年11月発行)
特集 これからの医療安全を考える
73巻10号(2014年10月発行)
特集 チーム医療における病院薬剤師の役割
73巻9号(2014年9月発行)
特集 里山資本主義と地域医療
73巻8号(2014年8月発行)
特集 多様化する病院経営
73巻7号(2014年7月発行)
特集 先端医療と病院
73巻6号(2014年6月発行)
特集 ITの活用とこれからの医療
73巻5号(2014年5月発行)
特集 病院食再考
73巻4号(2014年4月発行)
特集 求められる看護補助者の役割
73巻3号(2014年3月発行)
特集 事務職員の人材開発・キャリアパス
73巻2号(2014年2月発行)
特集 2025年に求められる病院経営のプロ
73巻1号(2014年1月発行)
特集 人口高齢化と病院医療
72巻12号(2013年12月発行)
特集 新たな専門医制度と病院
72巻11号(2013年11月発行)
特集 診療支援業務の新潮流
72巻10号(2013年10月発行)
特集 地域包括ケアと病院
72巻9号(2013年9月発行)
特集 医療計画はこう変わる
72巻8号(2013年8月発行)
特集 なぜ今,医療基本法なのか
72巻7号(2013年7月発行)
特集 病院の経営統合
72巻6号(2013年6月発行)
特集 女性医師のキャリアデザインと病院
72巻5号(2013年5月発行)
特集 これからの看護教育と病院
72巻4号(2013年4月発行)
特集 リビングウィルを考える
72巻3号(2013年3月発行)
特集 中小病院は生き残れるか
72巻2号(2013年2月発行)
特集 医療の公益性とは─医療法人制度改革の現状
72巻1号(2013年1月発行)
特集 病院の評価─課題とこれから
71巻12号(2012年12月発行)
特集 病院のBCP
71巻11号(2012年11月発行)
特集 検証“同時改定”診療・介護報酬
71巻10号(2012年10月発行)
特集 病院における歯科
71巻9号(2012年9月発行)
特集 高齢先進国のビジョン
71巻8号(2012年8月発行)
特集 病院と学生教育―地域で育てる医療人
71巻7号(2012年7月発行)
特集 病院のセキュリティ
71巻6号(2012年6月発行)
特集 変化の時代に事務長に求められるもの
71巻5号(2012年5月発行)
特集 看護職の賃金・給与体系はどうあるべきか
71巻4号(2012年4月発行)
特集 患者の医療情報探索
71巻3号(2012年3月発行)
特集 在宅療養と病院
71巻2号(2012年2月発行)
特集 病院の医師確保戦略
71巻1号(2012年1月発行)
特集 病院と日本復興
70巻12号(2011年12月発行)
特集 何を目指すチーム医療
70巻11号(2011年11月発行)
特集 医療計画と二次医療圏の今後
70巻10号(2011年10月発行)
特集 終末期における延命医療のあり方
70巻9号(2011年9月発行)
特集 地域医療を支える住民の活動
70巻8号(2011年8月発行)
特集 人口減少の衝撃 社会・病院はどう備えるか
70巻7号(2011年7月発行)
特集 地域医療再生計画を検証する
70巻6号(2011年6月発行)
特集 医療と介護はどう変わるか 平成24年診療報酬・介護報酬同時改定
70巻5号(2011年5月発行)
特集 病院は経済成長に寄与するか
70巻4号(2011年4月発行)
特集 採用看護師の教育・研修
70巻3号(2011年3月発行)
特集 自治体病院の存在意義
70巻2号(2011年2月発行)
特集 どう発展させる 病院総合医
70巻1号(2011年1月発行)
特集 病気と社会を考える
69巻12号(2010年12月発行)
特集 検証 平成22年度診療報酬改定
69巻11号(2010年11月発行)
特集 拡大するリハビリテーション医療
69巻10号(2010年10月発行)
特集 病院を取り巻く法環境
69巻9号(2010年9月発行)
特集 本格到来するDPC時代
69巻8号(2010年8月発行)
特集 病院のサステナビリティ―事業継承を考える
69巻7号(2010年7月発行)
特集 死生観が問われる時代の医療
69巻6号(2010年6月発行)
特集 災害と病院
69巻5号(2010年5月発行)
特集 長期療養ケアにおける看護の役割
69巻4号(2010年4月発行)
特集 医療の拡大がもたらす社会の厚生―医療費亡国論再考
69巻3号(2010年3月発行)
特集 医療におけるソーシャル・ビジネスの展開
69巻2号(2010年2月発行)
特集 病院管理会計とBSCの効用
69巻1号(2010年1月発行)
特集 拡大する医療・介護需要
68巻12号(2009年12月発行)
特集 今後の医師養成と病院
68巻11号(2009年11月発行)
特集 補完代替医療のこれから
68巻10号(2009年10月発行)
特集 医療費の配分を問う
68巻9号(2009年9月発行)
特集 外科医を支援する
68巻8号(2009年8月発行)
特集 医療・介護ニューディール
68巻7号(2009年7月発行)
特集 社会保障改革と病院の将来
68巻6号(2009年6月発行)
特集 医療IT化の行方
68巻5号(2009年5月発行)
特集 産業は病院市場をどう見るか
68巻4号(2009年4月発行)
特集 現場に役立つ看護師をいかに確保するか
68巻3号(2009年3月発行)
特集 NPMで公立病院は再生するか
68巻2号(2009年2月発行)
特集 医療統計の再構築に向けて
68巻1号(2009年1月発行)
特集 60周年記念号
67巻12号(2008年12月発行)
特集 検証 平成20年度診療報酬改定
67巻11号(2008年11月発行)
特集 「環境の時代」と病院
67巻10号(2008年10月発行)
特集 病院と家庭医療
67巻9号(2008年9月発行)
特集 新たな医療計画の展開
67巻8号(2008年8月発行)
特集 人口減少時代の病院
67巻7号(2008年7月発行)
特集 どうなる 特定健診・特定保健指導
67巻6号(2008年6月発行)
特集 人材不足をどう打開するか
67巻5号(2008年5月発行)
特集 変容する患者像―求められるヘルスリテラシー
67巻4号(2008年4月発行)
特集 看護師の役割を今問い直す
67巻3号(2008年3月発行)
特集 事務職員の採用とキャリア形成
67巻2号(2008年2月発行)
特集 医療に求められるイノベーション
67巻1号(2008年1月発行)
特集 個人の力と医療・社会
66巻12号(2007年12月発行)
特集 病院におけるIT化の新局面
66巻11号(2007年11月発行)
特集 躍進するアジアと病院戦略
66巻10号(2007年10月発行)
特集 病院空間とまちづくり
66巻9号(2007年9月発行)
特集 価格とコストの地域格差
66巻8号(2007年8月発行)
特集 技術革新と競争激化―特定保険医療材料の今後
66巻7号(2007年7月発行)
特集 患者負担のあり方を考える―フリーアクセスから選択責任へ
66巻6号(2007年6月発行)
特集 どう対応する 医事紛争時代
66巻5号(2007年5月発行)
特集 医療連携における看護師の役割
66巻4号(2007年4月発行)
特集 変革に立ち向かう病院―病床削減と人材難に対処する
66巻3号(2007年3月発行)
特集 地域の活性化に病院は貢献するか
66巻2号(2007年2月発行)
特集 介護保険施設と医療のあり方
66巻1号(2007年1月発行)
特集 いい病院をつくりましょう
65巻12号(2006年12月発行)
特集 検証 平成18年診療報酬改定
65巻11号(2006年11月発行)
特集 社会保障・税制改革と医療
65巻10号(2006年10月発行)
特集 在宅医療を支える地域連携システムとは
65巻9号(2006年9月発行)
特集 病院の人材確保―景気・社会構造の変化を踏まえて
65巻8号(2006年8月発行)
特集 医療と経済格差
65巻7号(2006年7月発行)
特集 医療のパフォーマンス評価
65巻6号(2006年6月発行)
特集 持つ病院,持たざる病院―法人制度から資金調達まで
65巻5号(2006年5月発行)
特集 外来機能はどうあるべきか
65巻4号(2006年4月発行)
特集 看護人員の適正化に向けて
65巻3号(2006年3月発行)
特集 新しい臨床教育手法―シミュレータの活用
65巻2号(2006年2月発行)
特集 超高齢社会の終末期ケア
65巻1号(2006年1月発行)
特集 地域医療の新たな展開と病院
64巻12号(2005年12月発行)
特集 医療政策の決定プロセス
64巻11号(2005年11月発行)
特集 病院にとって「患者の視点」とは
64巻10号(2005年10月発行)
特集 勤務医と労働基準法―医療の現実と法
64巻9号(2005年9月発行)
特集 地方分権と医療
64巻8号(2005年8月発行)
特集 病院経営のプロをどう養成するか
64巻7号(2005年7月発行)
特集 スピリチュアリティと病院
64巻6号(2005年6月発行)
特集 社会的責任(CSR)が問われる病院
64巻5号(2005年5月発行)
特集 経営陣の一翼としての看護部長
64巻4号(2005年4月発行)
特集 個人情報保護法と病院
64巻3号(2005年3月発行)
特集 今後の病院の財政基盤を問う
64巻2号(2005年2月発行)
特集 病院の質評価の選択肢は広がるか
64巻1号(2005年1月発行)
特集 医療の本質を捉える
63巻12号(2004年12月発行)
特集 派遣は人材確保に役立つか
63巻11号(2004年11月発行)
特集 パブリック・リレーションズ―地域の人の期待
63巻10号(2004年10月発行)
特集 検証 平成16年度診療報酬改定
63巻9号(2004年9月発行)
特集 動き始めた新医師臨床研修制度
63巻8号(2004年8月発行)
特集 急性期入院はDPC適用になるのか
63巻7号(2004年7月発行)
特集 病院のセーフティ・マネジメント最前線
63巻6号(2004年6月発行)
特集 急変する医薬品政策―病院としての対応
63巻5号(2004年5月発行)
特集 相補・代替医療へのニーズにどう対応するか
63巻4号(2004年4月発行)
特集 看護の臨床研修と病院
63巻3号(2004年3月発行)
特集 医療におけるナレッジ・マネジメント
63巻2号(2004年2月発行)
特集 公私の役割分担とイコール・フッティング
63巻1号(2004年1月発行)
特集 国民は医療をどう見ているか
62巻12号(2003年12月発行)
特集 亜急性医療は存在し得るか
62巻11号(2003年11月発行)
特集 どう生かす診療情報
62巻10号(2003年10月発行)
特集 変貌するか医療法人
62巻9号(2003年9月発行)
特集 変革を迫られる大学病院
62巻8号(2003年8月発行)
特集 病院のコスト管理
62巻7号(2003年7月発行)
特集 特定療養費制度の拡大と病院の対応
62巻6号(2003年6月発行)
特集 病院管理からみた患者安全
62巻5号(2003年5月発行)
特集 看護師のキャリアアップ
62巻4号(2003年4月発行)
特集 病院のカウンセリング機能
62巻3号(2003年3月発行)
特集 自立できるか自治体立病院
62巻2号(2003年2月発行)
特集 デフレ下における病院
62巻1号(2003年1月発行)
特集 医療政策の新しい潮流
61巻12号(2002年12月発行)
特集 改革期における事務長像
61巻11号(2002年11月発行)
特集 院内機能の分散化の動き
61巻10号(2002年10月発行)
特集 徹底検証 診療報酬改定2002
61巻9号(2002年9月発行)
特集 女性医師と病院
61巻8号(2002年8月発行)
特集 年功給は崩せるか
61巻7号(2002年7月発行)
特集 療養病床の行方
61巻6号(2002年6月発行)
特集 医師臨床研修必修化は病院に何をもたらすか
61巻5号(2002年5月発行)
特集 病院の外来—増やすか減らすか
61巻4号(2002年4月発行)
特集 学卒看護師の課題
61巻3号(2002年3月発行)
特集 緩和ケアの検証と今後の課題
61巻2号(2002年2月発行)
特集 病院の増改築
61巻1号(2002年1月発行)
特集 医療の規制改革と病院
60巻12号(2001年12月発行)
特集 ゲノム時代と病院
60巻11号(2001年11月発行)
特集 社会保障改革と病院
60巻10号(2001年10月発行)
特集 医療連携と病院
60巻9号(2001年9月発行)
特集 検証・変革期の病院経営
60巻8号(2001年8月発行)
特集 人材開発と管理職研修
60巻7号(2001年7月発行)
特集 病院の医療情報発信
60巻6号(2001年6月発行)
特集 施設機能分化の新たな展開
60巻5号(2001年5月発行)
特集 病院サービスの新しいメニュー
60巻4号(2001年4月発行)
特集 病院の求める看護職像
60巻3号(2001年3月発行)
特集 病院と資金調達
60巻2号(2001年2月発行)
特集 改めて病院の安全管理を問う
60巻1号(2001年1月発行)
特集 IT革命と病院
59巻12号(2000年12月発行)
特集 病院医療—21世紀への遺産
59巻11号(2000年11月発行)
特集 医療専門職の需要と供給
59巻10号(2000年10月発行)
特集 改革期の療養型病床群
59巻9号(2000年9月発行)
特集 検証 平成12年診療報酬改定
59巻8号(2000年8月発行)
特集 病院経営戦略と企画部門の役割
59巻7号(2000年7月発行)
特集 消費者(患者)の声/ニーズの吸収
59巻6号(2000年6月発行)
特集 病院としての地球環境問題への取り組み
59巻5号(2000年5月発行)
特集 中小病院—次世紀への挑戦
59巻4号(2000年4月発行)
特集 介護保険と看護
59巻3号(2000年3月発行)
特集 減価償却と耐用年数
59巻2号(2000年2月発行)
特集 病院の危機管理
59巻1号(2000年1月発行)
特集 病院・医療・社会—21世紀を展望する
58巻12号(1999年12月発行)
特集 医師養成と大学病院像
58巻11号(1999年11月発行)
特集 病院における賃金と年金
58巻10号(1999年10月発行)
特集 診療情報管理—開示に値する診療記録
58巻9号(1999年9月発行)
特集 改めて癒しの環境を問う
58巻8号(1999年8月発行)
特集 病院におけるマーケティング戦略
58巻7号(1999年7月発行)
特集 医療計画の新しい方向と病院
58巻6号(1999年6月発行)
特集 病院として介護保険にいかに対処すべきか
58巻5号(1999年5月発行)
特集 岐路に立つ中小病院
58巻4号(1999年4月発行)
特集 看護新時代
58巻3号(1999年3月発行)
特集 病院組織と意思決定—コーポレイトガバナンスとは何か
58巻2号(1999年2月発行)
特集 在院日数と病院経営
58巻1号(1999年1月発行)
特集 医療保障のグランドデザイン
57巻12号(1998年12月発行)
特集 退院後ケア
57巻11号(1998年11月発行)
特集 医療ビッグバンと公私の役割を考える
57巻10号(1998年10月発行)
特集 地域医療支援病院はどうなる
57巻9号(1998年9月発行)
特集 薬価基準制度の行方
57巻8号(1998年8月発行)
特集 入院診療計画
57巻7号(1998年7月発行)
特集 急性期包括払い方式の可能性
57巻6号(1998年6月発行)
特集 医療の標準化を考える
57巻5号(1998年5月発行)
特集 医療法人の今後
57巻4号(1998年4月発行)
特集 看護の質の評価
57巻3号(1998年3月発行)
特集 介護保険と長期ケア施設
57巻2号(1998年2月発行)
特集 医療界の世代交代
57巻1号(1998年1月発行)
特集 新時代の病院組織
56巻12号(1997年12月発行)
特集 問われる事務(部・局)長の経営能力
56巻11号(1997年11月発行)
特集 病院における情報開示
56巻10号(1997年10月発行)
特集 病院が医師を選ぶとき
56巻9号(1997年9月発行)
特集 ケアマネジメントと病院
56巻8号(1997年8月発行)
特集 病院経営における多角化戦略
56巻7号(1997年7月発行)
特集 医療保険改革と病院
56巻6号(1997年6月発行)
特集 医療関連ビジネスの展開
56巻5号(1997年5月発行)
特集 病院機能評価の動向と将来
56巻4号(1997年4月発行)
特集 ナーシング・マネジメント
56巻3号(1997年3月発行)
特集 病院におけるマルチメディア
56巻2号(1997年2月発行)
特集 病院職員の高齢化対策
56巻1号(1997年1月発行)
特集 第3次医療法改正と病院
55巻12号(1996年12月発行)
特集 「薬害問題」から学ぶこと
55巻11号(1996年11月発行)
特集 補助金と病院経営
55巻10号(1996年10月発行)
特集 介護保険制度をめぐって
55巻9号(1996年9月発行)
特集 診療報酬改定・96年4月を検証する
55巻8号(1996年8月発行)
特集 待ち時間解消はどこまでできるか
55巻7号(1996年7月発行)
特集 医療機能評価で病院はどうなる
55巻6号(1996年6月発行)
特集 病院のネットワーク化を追う
55巻5号(1996年5月発行)
特集 病院管理者としての女性
55巻4号(1996年4月発行)
特集 二交替制看護を追う
55巻3号(1996年3月発行)
特集 病院経営と医薬分業をめぐって
55巻2号(1996年2月発行)
特集 大学病院と関連病院との関係を問う
55巻1号(1996年1月発行)
特集 病院経営の改善
54巻12号(1995年12月発行)
特集 問われる病院と地域の保健活動
54巻11号(1995年11月発行)
特集 医療法人制度をめぐる諸問題
54巻10号(1995年10月発行)
特集 新しい入院療養環境
54巻9号(1995年9月発行)
特集 大災害に対するリスクマネジメント
54巻8号(1995年8月発行)
特集 病院職員の教育と研修
54巻7号(1995年7月発行)
特集 病院の食事は今…
54巻6号(1995年6月発行)
特集 病院が倒産するとき
54巻5号(1995年5月発行)
特集 特定療養費制度の功罪
54巻4号(1995年4月発行)
特集 新看護体系で病院はどうなるか
54巻3号(1995年3月発行)
特集 薬価と病院経営
54巻2号(1995年2月発行)
特集 ボランティアと病院—開かれた病院づくり
54巻1号(1995年1月発行)
特集 「21世紀福祉ビジョン」と病院
53巻12号(1994年12月発行)
特集 「病院死」を考える
53巻11号(1994年11月発行)
特集 中小病院はこれでいいのか
53巻10号(1994年10月発行)
特集 インフォームド・コンセント—語る時代から行う時代へ
53巻9号(1994年9月発行)
特集 効果的な会議
53巻8号(1994年8月発行)
特集 多様化時代の病院人事
53巻7号(1994年7月発行)
特集 病院とPR
53巻6号(1994年6月発行)
特集 院内感染対策は万全か
53巻5号(1994年5月発行)
特集 キャピタル・コストの確保をめぐって
53巻4号(1994年4月発行)
特集 揺れる基準看護
53巻3号(1994年3月発行)
特集 勤務医と病院経営
53巻2号(1994年2月発行)
特集 病院栄養業務の質の向上を目指して
53巻1号(1994年1月発行)
特集 新時代の病院像
52巻12号(1993年12月発行)
特集 第3次医療法改正はどうなるか
52巻11号(1993年11月発行)
特集 病院の長期療養サービス
52巻10号(1993年10月発行)
特集 診療記録と情報管理
52巻9号(1993年9月発行)
特集 病院の医療費体系をどうする
52巻8号(1993年8月発行)
特集 いま病院トップに求められる能力とは
52巻7号(1993年7月発行)
特集 病院のダウンサイジング
52巻6号(1993年6月発行)
特集 看護の質に何を期待するか
52巻5号(1993年5月発行)
特集 社会からみた医療の質の評価
52巻4号(1993年4月発行)
特集 外来のあり方を問う—大病院志向の流れは変えられるか
52巻3号(1993年3月発行)
特集 どうする中小病院
52巻2号(1993年2月発行)
特集 週休2日制実行のためのポイント
52巻1号(1993年1月発行)
特集 地域づくりのために病院に何ができるか
51巻12号(1992年12月発行)
特集 第2次医療法改正のインパクト
51巻11号(1992年11月発行)
特集 民間病院の承継はどうなる
51巻10号(1992年10月発行)
特集 在宅ケア新時代
51巻9号(1992年9月発行)
特集 ストックからフローへ—総合的物品管理システムをめざして
51巻8号(1992年8月発行)
特集 新診療報酬と今後の対応
51巻7号(1992年7月発行)
特集 公立病院はこれでいいのか
51巻6号(1992年6月発行)
特集 保健・医療・福祉複合体
51巻5号(1992年5月発行)
特集 こんな勤務医はいらない
51巻4号(1992年4月発行)
特集 看護業務のスリム化
51巻3号(1992年3月発行)
特集 病院クリーン作戦
51巻2号(1992年2月発行)
特集 病院と医療関連サービス
51巻1号(1992年1月発行)
特集 高齢社会と子どもの医療
50巻13号(1991年12月発行)
特集 病院経営の実態に迫る
50巻12号(1991年11月発行)
増刊号 日本の病院建築
50巻11号(1991年11月発行)
特集 病院のチェーン化・ネットワーク化
50巻10号(1991年10月発行)
特集 病院にとってのゴールドプラン
50巻9号(1991年9月発行)
特集 病院が好きになる
50巻8号(1991年8月発行)
特集 病院のヒューマン・リソースは万全か—病院職員の採用と募集
50巻7号(1991年7月発行)
特集 新しい長期療養サービス
50巻6号(1991年6月発行)
特集 病院医療の質の改善
50巻5号(1991年5月発行)
特集 看護と介護—共存の道
50巻4号(1991年4月発行)
特集 中小病院の明日を拓く
50巻3号(1991年3月発行)
特集 病院の国際化
50巻2号(1991年2月発行)
特集 変革する病院経営とトップマネジメント
50巻1号(1991年1月発行)
特集 病院のパラダイムシフト
49巻13号(1990年12月発行)
特集 今,医療計画は—見直しをどうする
49巻12号(1990年11月発行)
増刊号 医療機器・設備機器ガイド1991
49巻11号(1990年11月発行)
特集 医薬分業と病院
49巻10号(1990年10月発行)
特集 完全週休2日制をめざして
49巻9号(1990年9月発行)
特集 「高機能病院」の目指す道
49巻8号(1990年8月発行)
特集 救急医療体制の問題点と将来像
49巻7号(1990年7月発行)
特集 在院日数の短縮と退院計画
49巻6号(1990年6月発行)
特集 診療報酬請求もれゼロ作戦
49巻5号(1990年5月発行)
特集 増大する看護ニーズの分析と対応
49巻4号(1990年4月発行)
特集 在宅ケアと病院
49巻3号(1990年3月発行)
特集 グルメ時代の病院の食事
49巻2号(1990年2月発行)
特集 中小病院サバイバル
49巻1号(1990年1月発行)
特集 明るい病院づくり—快適サービスの神髄を求めて
48巻13号(1989年12月発行)
特集 病院財務管理のあり方
48巻12号(1989年11月発行)
特集 "淘汰"の時代を勝ち抜く民間病院
48巻11号(1989年10月発行)
特集 病院と医師の教育研修
48巻10号(1989年9月発行)
特集 地域づくりと病院
48巻9号(1989年8月発行)
特集 病院機能と臨床検査部門の見直し
48巻8号(1989年7月発行)
48巻7号(1989年7月発行)
特集 病院の福利厚生
48巻6号(1989年6月発行)
特集 今日的物品管理をめぐって
48巻5号(1989年5月発行)
特集 看護マネージメントの新しい波
48巻4号(1989年4月発行)
特集 施設老人ケア
48巻3号(1989年3月発行)
特集 効果的な職員教育を進めるために
48巻2号(1989年2月発行)
特集 病院と医師—組織のはざまのなかで
48巻1号(1989年1月発行)
特集 新春対談
47巻12号(1988年12月発行)
特集 わが病院のめざすもの—新・改築時の理念と実際
47巻11号(1988年11月発行)
特集 感染対策から見た医療廃棄物の諸問題
47巻10号(1988年10月発行)
特集 「老人保健施設」試行実績をこう見る
47巻9号(1988年9月発行)
特集 日本型DRGはあり得るか
47巻8号(1988年8月発行)
特集 医療におけるテクノロジー・アセスメント
47巻7号(1988年7月発行)
特集 インフォームド・コンセント
47巻6号(1988年6月発行)
特集 「病院機能評価」—現場からの検討
47巻5号(1988年5月発行)
特集 ナースに選ばれる病院
47巻4号(1988年4月発行)
特集 地域医療計画と病院
47巻3号(1988年3月発行)
特集 病院事務長の人材養成
47巻2号(1988年2月発行)
特集 週休2日制への対応を探る病院
47巻1号(1988年1月発行)
特集 病院のリフォーム
46巻12号(1987年12月発行)
特集 民間病院のこれから
46巻11号(1987年11月発行)
特集 病院と税金
46巻10号(1987年10月発行)
特集 ニードの多様化と効率的薬剤部門
46巻9号(1987年9月発行)
特集 「医師生涯教育」の場としての病院
46巻8号(1987年8月発行)
特集 AIDS不安—病院側の対応を考える
46巻7号(1987年7月発行)
特集 医療の新メニュー
46巻6号(1987年6月発行)
特集 「病院機能評価」と病院の対応
46巻5号(1987年5月発行)
特集 病院機能を高める看護の専門性
46巻4号(1987年4月発行)
特集 病院オープン化に期待する
46巻3号(1987年3月発行)
特集 ホスピタル・アイデンティティ
46巻2号(1987年2月発行)
特集 病院におけるボランティア・ワーク
46巻1号(1987年1月発行)
特集 病院ルネッサンス
45巻12号(1986年12月発行)
特集 医療における民間活力の導入
45巻11号(1986年11月発行)
特集 病院外来の新しい展開
45巻10号(1986年10月発行)
特集 医療費改定効果の実態
45巻9号(1986年9月発行)
特集 情報化社会における病院—情報システムのあり方
45巻8号(1986年8月発行)
特集 拡大する病院健康管理部門
45巻7号(1986年7月発行)
特集 勤務医の未来
45巻6号(1986年6月発行)
特集 今こそ病歴室整備へ向けて
45巻5号(1986年5月発行)
特集 看護のトップマネージメント
45巻4号(1986年4月発行)
特集 高額医療機器の経済効果
45巻3号(1986年3月発行)
特集 患者に選ばれる病院
45巻2号(1986年2月発行)
特集 取引き先と上手に付き合う
45巻1号(1986年1月発行)
特集 医療政策の変化と病院経営—'80年代前半の5年と今後の5年
44巻12号(1985年12月発行)
特集 病院中間管理職の諸問題
44巻11号(1985年11月発行)
特集 保険審査の問題点と対策
44巻10号(1985年10月発行)
特集 "一般病院"での卒後臨床研修を考える
44巻9号(1985年9月発行)
特集 病院の24時間体制
44巻8号(1985年8月発行)
特集 病院の経営危機に学ぶ
44巻7号(1985年7月発行)
特集 委託外注のチェックポイント
44巻6号(1985年6月発行)
特集 病院で死を迎える
44巻5号(1985年5月発行)
特集 再び問う—医師と看護婦の連携
44巻4号(1985年4月発行)
特集 中間施設とこれからの病院
44巻3号(1985年3月発行)
特集 効率化のための診療プログラムの総合管理
44巻2号(1985年2月発行)
特集 「患者の権利」と病院の対応
44巻1号(1985年1月発行)
特集 国民医療費の再検討
43巻12号(1984年12月発行)
43巻11号(1984年11月発行)
特集 医師急増時代と病院
43巻10号(1984年10月発行)
特集 医療ソーシャルワーカーの現在
43巻9号(1984年9月発行)
特集 心温まる病院づくり
43巻8号(1984年8月発行)
特集 老人病院の実情と課題
43巻7号(1984年7月発行)
特集 病院と「くすり」
43巻6号(1984年6月発行)
特集 病院のソフト化
43巻5号(1984年5月発行)
特集 看護度と必要要員
43巻4号(1984年4月発行)
特集 労使関係—今後の展開
43巻3号(1984年3月発行)
特集 医療費抑制下における給与費対策
43巻2号(1984年2月発行)
特集 病院トップマネージメントを考える
43巻1号(1984年1月発行)
特集 「医療法改正」の焦点
42巻12号(1983年12月発行)
特集 第一線医療と医師の研修
42巻11号(1983年11月発行)
特集 病院における減量経営の意味と対策
42巻10号(1983年10月発行)
42巻9号(1983年9月発行)
特集 主治医に協力する医師たち—麻酔・放射線・病理等の問題点
42巻8号(1983年8月発行)
42巻7号(1983年7月発行)
特集 老人保健法と病院医療の展開
42巻6号(1983年6月発行)
42巻5号(1983年5月発行)
特集 看護夜勤体制の変革
42巻4号(1983年4月発行)
42巻3号(1983年3月発行)
特集 6時夕食はなぜできないのか
42巻2号(1983年2月発行)
42巻1号(1983年1月発行)
特集 医療施設間の連携
41巻12号(1982年12月発行)
41巻11号(1982年11月発行)
特集 病院の「若返り」策—特に医師をめぐって
41巻10号(1982年10月発行)
41巻9号(1982年9月発行)
特集 病院過飽和時代への対応
41巻8号(1982年8月発行)
41巻7号(1982年7月発行)
特集 医療の変革に対応する医療関係事務
41巻6号(1982年6月発行)
41巻5号(1982年5月発行)
特集 看護管理者教育の現状と課題
41巻4号(1982年4月発行)
41巻3号(1982年3月発行)
特集 医療評価の導入
41巻2号(1982年2月発行)
41巻1号(1982年1月発行)
特集 新医療費と医療の流れ
40巻12号(1981年12月発行)
40巻11号(1981年11月発行)
特集 病院経営悪化の打開策
40巻10号(1981年10月発行)
40巻9号(1981年9月発行)
特集 パラメディカル部門の拡大
40巻8号(1981年8月発行)
40巻7号(1981年7月発行)
特集 設備投資と技術革新
40巻6号(1981年6月発行)
40巻5号(1981年5月発行)
特集 拡大する看護を探る
40巻4号(1981年4月発行)
40巻3号(1981年3月発行)
特集 医師の「外勤」問題
40巻2号(1981年2月発行)
特集 病院増改築の実例
40巻1号(1981年1月発行)
特集 「人間性回復」への動き
39巻12号(1980年12月発行)
小特集 「地域医療」の実践
39巻11号(1980年11月発行)
特集 飛躍への条件
39巻10号(1980年10月発行)
特集 救急医療その院内体制・2
39巻9号(1980年9月発行)
特集 救急医療その院内体制・1
39巻8号(1980年8月発行)
小特集 病院管理専門家の養成
39巻7号(1980年7月発行)
特集 省エネルギー時代の病院
39巻6号(1980年6月発行)
小特集 診療報酬請求審査を点検する
39巻5号(1980年5月発行)
特集 ニッパチ,その後
39巻4号(1980年4月発行)
39巻3号(1980年3月発行)
特集 診療録の保存と利用
39巻2号(1980年2月発行)
39巻1号(1980年1月発行)
特集 80年代の病院医療の課題
38巻12号(1979年12月発行)
特集 病院図書室
38巻11号(1979年11月発行)
特集 医療費の限界と病院経営
38巻10号(1979年10月発行)
特集 チェーンホスピタルとは
38巻9号(1979年9月発行)
特集 幹部間リレーションズ
38巻8号(1979年8月発行)
特集 病院給食の新しい動向
38巻7号(1979年7月発行)
特集 医療機器管理の焦点
38巻6号(1979年6月発行)
38巻5号(1979年5月発行)
特集 看護部長の課題
38巻4号(1979年4月発行)
特集 大地震と病院―宮城県沖地震を中心に
38巻3号(1979年3月発行)
特集 病院検査部門の動向と問題点
38巻2号(1979年2月発行)
特集 病院運営の経験と分析
38巻1号(1979年1月発行)
特集 変化を迫られる病院
37巻12号(1978年12月発行)
特集 患者用病院図書室
37巻11号(1978年11月発行)
特集 医療チームとしての栄養部門
37巻10号(1978年10月発行)
特集 医療施設間連携の芽生え
37巻9号(1978年9月発行)
特集 変貌する病院事務
37巻8号(1978年8月発行)
特集 末期患者の医療を考える
37巻7号(1978年7月発行)
特集 病院組織と看護の専門化
37巻6号(1978年6月発行)
特集 医療費改定の分析と批判
37巻5号(1978年5月発行)
特集 病院の汚染防止
37巻4号(1978年4月発行)
特集 薬剤事故
37巻3号(1978年3月発行)
特集 病院と付添問題
37巻2号(1978年2月発行)
特集 老人医療の課題—退院後のケア
37巻1号(1978年1月発行)
特集 病院と経営主体
36巻12号(1977年12月発行)
36巻11号(1977年11月発行)
特集 ICUの現状と展望
36巻10号(1977年10月発行)
36巻9号(1977年9月発行)
特集 世界の病院医療の動向
36巻8号(1977年8月発行)
36巻7号(1977年7月発行)
特集 各部門の能率の図り方
36巻6号(1977年6月発行)
36巻5号(1977年5月発行)
特集 管理者としての婦長
36巻4号(1977年4月発行)
36巻3号(1977年3月発行)
特集 勤務医
36巻2号(1977年2月発行)
36巻1号(1977年1月発行)
特集 医療法と病院
35巻12号(1976年12月発行)
特集 「社会の声」を聞く
35巻11号(1976年11月発行)
35巻10号(1976年10月発行)
特集 事務の精度管理
35巻9号(1976年9月発行)
35巻8号(1976年8月発行)
特集 病院と輸血管理
35巻7号(1976年7月発行)
特集 格差の広がる病院経営
35巻6号(1976年6月発行)
特集 病院と看護学校
35巻5号(1976年5月発行)
35巻4号(1976年4月発行)
35巻3号(1976年3月発行)
特集 過疎地域の医療
35巻2号(1976年2月発行)
35巻1号(1976年1月発行)
特集 大学病院の革新
34巻12号(1975年12月発行)
特集 経営能率からみた病院
34巻11号(1975年11月発行)
特集 病院と光熱水
34巻10号(1975年10月発行)
特集 病院と麻酔科
34巻9号(1975年9月発行)
特集 病院と研修
34巻8号(1975年8月発行)
特集 医療事故と病院
34巻7号(1975年7月発行)
特集 病院間の協同
34巻6号(1975年6月発行)
特集 ME機器の管理
34巻5号(1975年5月発行)
特集 新生児医療の展開
34巻4号(1975年4月発行)
特集 看護婦<不信>
34巻3号(1975年3月発行)
特集 救急医療
34巻2号(1975年2月発行)
特集 病棟閉鎖と入院制限
34巻1号(1975年1月発行)
特集 医療費の配分
33巻12号(1974年12月発行)
特集 院内感染管理の新しい課題
33巻11号(1974年11月発行)
特集 保険経済と病院の赤字
33巻10号(1974年10月発行)
特集 コンピュータ・システムのメリット・デメリット
33巻9号(1974年9月発行)
特集 近代化する病院組織と医師
33巻8号(1974年8月発行)
特集 病院のムダ
33巻7号(1974年7月発行)
特集 放射線部門の問題をさぐる
33巻6号(1974年6月発行)
特集 財務計画
33巻5号(1974年5月発行)
特集 看護婦三交替制の反省
33巻4号(1974年4月発行)
特集 病院新人教育
33巻3号(1974年3月発行)
特集 私立病院のゆくえ
33巻2号(1974年2月発行)
特集 事例からみた労働問題
33巻1号(1974年1月発行)
特集 医療計画
32巻13号(1973年12月発行)
第23回日本病院学会演題選
32巻12号(1973年12月発行)
特集 老人医療費無料化の影響
32巻11号(1973年11月発行)
特集 効果的な案内とは
32巻10号(1973年10月発行)
特集 火災対策
32巻9号(1973年9月発行)
特集 病院と保育所
32巻8号(1973年8月発行)
特集 週休2日制
32巻7号(1973年7月発行)
特集 待たせない病院
32巻6号(1973年6月発行)
特集 設備保全
32巻5号(1973年5月発行)
特集 看護に提言する
32巻4号(1973年4月発行)
特集 病院の特殊性と労基法
32巻3号(1973年3月発行)
特集 人工透析
32巻2号(1973年2月発行)
特集 人を募集する
32巻1号(1973年1月発行)
特集 ホスピタル・インダストリー
31巻13号(1972年12月発行)
特集 豊かさの中に取り残された病院
31巻12号(1972年11月発行)
特集 病院給食の変貌
31巻11号(1972年10月発行)
特集 夜間診療体制
31巻10号(1972年9月発行)
31巻9号(1972年9月発行)
特集 院内会議
31巻8号(1972年8月発行)
特集 生まれかわる病院組織
31巻7号(1972年7月発行)
特集 患者を護る
31巻6号(1972年6月発行)
特集 病院のゴミ戦争
31巻5号(1972年5月発行)
特集 看護の独立を考える
31巻4号(1972年4月発行)
特集 老人医療と病院
31巻3号(1972年3月発行)
特集 高度医療設備の経済計算
31巻2号(1972年2月発行)
特集 職員の食事
31巻1号(1972年1月発行)
特集 新しい病院への芽ばえ
30巻13号(1971年12月発行)
特集 病院外来を点検する
30巻12号(1971年11月発行)
特集 快適な病室の条件
30巻11号(1971年10月発行)
特集 人の使い方の再点検
30巻10号(1971年9月発行)
30巻9号(1971年9月発行)
特集 薬剤師のあり方を点検する
30巻8号(1971年8月発行)
特集 病院内の防犯
30巻7号(1971年7月発行)
特集 勤務時間を点検する
30巻6号(1971年6月発行)
特集 ボランティア活動
30巻5号(1971年5月発行)
特集 臨床検査を点検する
30巻4号(1971年4月発行)
特集 職場リーダー
30巻3号(1971年3月発行)
特集 不採算医療を点検する
30巻2号(1971年2月発行)
特集 病院のインテリアデザイン
30巻1号(1971年1月発行)
特集 基準看護を点検する
29巻13号(1970年12月発行)
特集 病院に残る古きもの
29巻12号(1970年11月発行)
特集 企業会計の反省
29巻11号(1970年10月発行)
特集 温食給食
29巻10号(1970年9月発行)
29巻9号(1970年9月発行)
特集 これからの病歴管理
29巻8号(1970年8月発行)
特集 ニッパチ問題
29巻7号(1970年7月発行)
特集 一般病院におけるリハビリテーション部門
29巻6号(1970年6月発行)
特集2 鼠害・虫害対策
29巻5号(1970年5月発行)
特集 病院とコンピュータ
29巻4号(1970年4月発行)
特集 入院料と差額徴収
29巻3号(1970年3月発行)
特集 総合診療
29巻2号(1970年2月発行)
特集 病院のMSWをより発展させるには
29巻1号(1970年1月発行)
特集 変化の時代の病院
28巻13号(1969年12月発行)
特集 院長
28巻12号(1969年11月発行)
特集 事務の分掌
28巻11号(1969年10月発行)
特集 輸血の管理
28巻10号(1969年9月発行)
特集 第19回日本病院学会臨時増刊号
28巻9号(1969年9月発行)
特集 医療紛争の予防
28巻8号(1969年8月発行)
特集 病院経営と薬剤
28巻7号(1969年7月発行)
特集 うるおいのある病院
28巻6号(1969年6月発行)
特集号 本誌発刊20周年記念
28巻5号(1969年5月発行)
特集 小児の給食
28巻4号(1969年4月発行)
特集 看護要員の適正配置
28巻3号(1969年3月発行)
特集 病院と労使関係
28巻2号(1969年2月発行)
特集 病院と図書館
28巻1号(1969年1月発行)
特集 日本の病院
27巻13号(1968年12月発行)
特集 手術室における看護
27巻12号(1968年11月発行)
特集 物の搬送
27巻10号(1968年10月発行)
27巻11号(1968年10月発行)
特集 病院医事業務のすすめ方
27巻9号(1968年9月発行)
特集 病院職員の需給関係
27巻8号(1968年8月発行)
特集 病院建築の新しいデザイン
27巻7号(1968年7月発行)
特集 使い捨て物品
27巻6号(1968年6月発行)
特集 病院と医師の修練
27巻5号(1968年5月発行)
特集 病院の窓口
27巻4号(1968年4月発行)
特集 中央検査部
27巻3号(1968年3月発行)
特集 新生児室の管理
27巻2号(1968年2月発行)
特集 病院給食管理
27巻1号(1968年1月発行)
特集 世界の病院
26巻13号(1967年12月発行)
特集 総婦長
26巻12号(1967年11月発行)
特集 病院と事故
26巻11号(1967年10月発行)
26巻10号(1967年10月発行)
特集 看護婦と与薬
26巻9号(1967年9月発行)
特集 病院経済の現状
26巻8号(1967年8月発行)
特集 病院の廃棄物
26巻7号(1967年7月発行)
特集 夜間の医師の当直
26巻6号(1967年6月発行)
特集 病院の倫理
26巻5号(1967年5月発行)
特集 病院職員とレクリエーション
26巻4号(1967年4月発行)
特集 病院フードサービスの施設と設備
26巻3号(1967年3月発行)
特集 保全管理
26巻2号(1967年2月発行)
特集 放射線部のあり方と問題
26巻1号(1967年1月発行)
特集 東南アジア諸国の医療事情
25巻13号(1966年12月発行)
特集 処方と調剤
25巻12号(1966年11月発行)
特集 夜間の看護
25巻10号(1966年10月発行)
25巻11号(1966年10月発行)
特集 物品補給と倉庫管理
25巻9号(1966年9月発行)
特集 大学と病院
25巻8号(1966年8月発行)
特集 病院外来のあり方
25巻7号(1966年7月発行)
特集 病院職員の募集と採用
25巻6号(1966年6月発行)
特集 病院職員の服装
25巻5号(1966年5月発行)
特集 採算管理
25巻4号(1966年4月発行)
特集 病棟の看護設備
25巻3号(1966年3月発行)
特集 結核医療と病院
25巻2号(1966年2月発行)
特集 事務長
25巻1号(1966年1月発行)
特集 病院と医療制度
24巻13号(1965年12月発行)
特集 病院の増改築に関する諸問題
24巻12号(1965年11月発行)
特集 外来看護
24巻11号(1965年10月発行)
24巻10号(1965年10月発行)
特集 病院医師の組織
24巻9号(1965年9月発行)
特集 病院業務の委託・外注
24巻8号(1965年8月発行)
特集 総合病院における精神医療
24巻7号(1965年7月発行)
特集 リネン・サプライの合理化
24巻6号(1965年6月発行)
特集 食事運搬
24巻5号(1965年5月発行)
特集 病院におけるリハビリテーション
24巻4号(1965年4月発行)
特集 PPC計画
24巻3号(1965年3月発行)
特集 購買管理
24巻2号(1965年2月発行)
特集 病歴の中央化
24巻1号(1965年1月発行)
新春特集号 パネルディスカッション
23巻12号(1964年12月発行)
特集 人件費対策
23巻11号(1964年11月発行)
特集 安全対策
23巻10号(1964年10月発行)
特集 第14回日本病院学会
23巻9号(1964年9月発行)
特集 看護婦不足の現状と対策
23巻8号(1964年8月発行)
特集 病院の薬局
23巻7号(1964年7月発行)
特集 空気調和
23巻6号(1964年6月発行)
特集 本誌発刊15周年記念
23巻5号(1964年5月発行)
特集 病院のPR
23巻4号(1964年4月発行)
特集 医療社会事業
23巻3号(1964年3月発行)
特集 患者への心づかい—T.L.C.
23巻2号(1964年2月発行)
特集 第13回日本病院学会
23巻1号(1964年1月発行)
22巻12号(1963年12月発行)
22巻11号(1963年11月発行)
特集 看護
22巻10号(1963年10月発行)
特集 病院の機械化
22巻9号(1963年9月発行)
22巻8号(1963年8月発行)
特集 病院経営の危機
22巻7号(1963年7月発行)
22巻6号(1963年6月発行)
特集 中央検査室
22巻5号(1963年5月発行)
特集 放射線部の管理
22巻4号(1963年4月発行)
特集 職員訓練
22巻3号(1963年3月発行)
22巻2号(1963年2月発行)
特集 診療管理
22巻1号(1963年1月発行)
21巻12号(1962年12月発行)
21巻11号(1962年11月発行)
21巻10号(1962年10月発行)
特集 第12回日本病院学会
21巻9号(1962年9月発行)
特集 病院給食管理の諸問題
21巻8号(1962年8月発行)
特集 人間関係
21巻7号(1962年7月発行)
特集 看護
21巻6号(1962年6月発行)
21巻5号(1962年5月発行)
特集 小児病棟の管理
21巻4号(1962年4月発行)
特集 病歴管理
21巻3号(1962年3月発行)
21巻2号(1962年2月発行)
21巻1号(1962年1月発行)
20巻12号(1961年12月発行)
20巻11号(1961年11月発行)
20巻10号(1961年10月発行)
20巻9号(1961年9月発行)
20巻8号(1961年8月発行)
特集 第11回日本病院学会総会
20巻7号(1961年7月発行)
特集 病院労務管理
20巻6号(1961年6月発行)
20巻5号(1961年5月発行)
20巻4号(1961年4月発行)
特集 病院給食
20巻3号(1961年3月発行)
20巻2号(1961年2月発行)
20巻1号(1961年1月発行)
19巻12号(1960年12月発行)
19巻11号(1960年11月発行)
19巻10号(1960年10月発行)
19巻9号(1960年9月発行)
特集 第10回日本病院学会シンポジウム
19巻8号(1960年8月発行)
特集 第10回日本病院学会
19巻7号(1960年7月発行)
19巻6号(1960年6月発行)
19巻5号(1960年5月発行)
特集 看護
19巻4号(1960年4月発行)
特集 大学病院
19巻3号(1960年3月発行)
特集 病院と緑化
19巻2号(1960年2月発行)
19巻1号(1960年1月発行)
18巻13号(1959年12月発行)
特集 病院建築
18巻12号(1959年11月発行)
特集 医事業務
18巻11号(1959年10月発行)
特集 診療管理
18巻10号(1959年9月発行)
特集 第9回日本病院学会総会
18巻8号(1959年8月発行)
18巻9号(1959年8月発行)
18巻7号(1959年7月発行)
18巻6号(1959年6月発行)
18巻5号(1959年5月発行)
18巻4号(1959年4月発行)
特集 農村病院
18巻3号(1959年3月発行)
特集 税と病院
18巻2号(1959年2月発行)
18巻1号(1959年1月発行)
17巻13号(1958年12月発行)
17巻12号(1958年11月発行)
17巻11号(1958年10月発行)
17巻10号(1958年9月発行)
17巻9号(1958年8月発行)
17巻8号(1958年7月発行)
特集 看護
17巻7号(1958年6月発行)
17巻6号(1958年5月発行)
17巻5号(1958年4月発行)
特集 病院事務の合理化
17巻4号(1958年4月発行)
17巻3号(1958年3月発行)
17巻2号(1958年2月発行)
17巻1号(1958年1月発行)
16巻12号(1957年12月発行)
16巻11号(1957年11月発行)
16巻10号(1957年10月発行)
16巻9号(1957年9月発行)
16巻8号(1957年8月発行)
16巻7号(1957年7月発行)
16巻6号(1957年6月発行)
16巻5号(1957年5月発行)
16巻4号(1957年4月発行)
16巻3号(1957年3月発行)
16巻2号(1957年2月発行)
16巻1号(1957年1月発行)
15巻6号(1956年12月発行)
15巻5号(1956年11月発行)
15巻4号(1956年10月発行)
15巻3号(1956年9月発行)
15巻2号(1956年8月発行)
15巻1号(1956年7月発行)
14巻6号(1956年6月発行)
14巻5号(1956年5月発行)
14巻4号(1956年4月発行)
14巻3号(1956年3月発行)
14巻2号(1956年2月発行)
14巻1号(1956年1月発行)
特集 Dr. MacEachern
13巻6号(1955年12月発行)
13巻5号(1955年11月発行)
13巻4号(1955年10月発行)
13巻3号(1955年9月発行)
13巻2号(1955年8月発行)
特集 第5回日本病院学会
13巻1号(1955年7月発行)
12巻6号(1955年6月発行)
12巻5号(1955年5月発行)
12巻4号(1955年4月発行)
12巻3号(1955年3月発行)
12巻2号(1955年2月発行)
12巻1号(1955年1月発行)
11巻6号(1954年12月発行)
11巻5号(1954年11月発行)
11巻4号(1954年10月発行)
11巻3号(1954年9月発行)
11巻2号(1954年8月発行)
特集 第四回日本病院学会
11巻1号(1954年7月発行)
10巻6号(1954年6月発行)
10巻5号(1954年5月発行)
10巻4号(1954年4月発行)
10巻3号(1954年3月発行)
10巻2号(1954年2月発行)
10巻1号(1954年1月発行)
