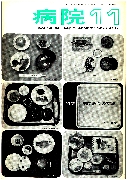文献詳細
特集 病院給食の変貌
文献概要
●はじめに
わが国における病院給食が行政的に取り上げられるようになったのは,昭和23年‘大都市における入院患者に対する食糧の増配に関する特別措置要領’にはじまり,翌24年には一般入院患者の食糧を増配し,常食および結核患者の食事に対する栄養基準が指示され,昭和29年から社会保険の病院が完全給食を実施,昭和36年6月には現在用いられている基準,すなわち‘患者食の栄養量および食事は,患者の病状に応じた適切なものとする.ただし,成人の一般食にあっては,1人1日について熱量2000Cal以上,蛋白質80g以上,脂肪20g以上とする’などを含めた,医療機関に対する基準給食承認基準指示が出されている.しかし,この基準ができてから約15年間になろうとしているが,この間,日本人の栄養所要量については,昭和34年と44年に改訂されているのに,基準給食についてはまだその改訂がなされないまま現在に至っている.この間,病院の食事は残飯が多く,おいしくないということから,その原因について,いろいろな角度から検討が行なわれてきている.そこで本稿では,昭和33年に指示された栄養基準の背景,および現状,そして今後のあり方について,食糧構成を入れて考えてみたい.
わが国における病院給食が行政的に取り上げられるようになったのは,昭和23年‘大都市における入院患者に対する食糧の増配に関する特別措置要領’にはじまり,翌24年には一般入院患者の食糧を増配し,常食および結核患者の食事に対する栄養基準が指示され,昭和29年から社会保険の病院が完全給食を実施,昭和36年6月には現在用いられている基準,すなわち‘患者食の栄養量および食事は,患者の病状に応じた適切なものとする.ただし,成人の一般食にあっては,1人1日について熱量2000Cal以上,蛋白質80g以上,脂肪20g以上とする’などを含めた,医療機関に対する基準給食承認基準指示が出されている.しかし,この基準ができてから約15年間になろうとしているが,この間,日本人の栄養所要量については,昭和34年と44年に改訂されているのに,基準給食についてはまだその改訂がなされないまま現在に至っている.この間,病院の食事は残飯が多く,おいしくないということから,その原因について,いろいろな角度から検討が行なわれてきている.そこで本稿では,昭和33年に指示された栄養基準の背景,および現状,そして今後のあり方について,食糧構成を入れて考えてみたい.
掲載誌情報