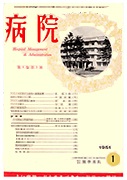文献詳細
--------------------
文献概要
前號に述べたように,東京大學の病院は英人によつて指導されたが,明治4年に獨逸の兩軍醫が着任して以來獨逸學風となつた。その外,明治初年には,各地に醫學校を附屬した病院が設立され頓に洋風の病院が盛にとり入れられるようになつた。これを學校毎に概略諸國の系統を比較すると次の如くである。
明治2年(1869年)大阪上本町大福寺に大阪假病院が設立され,人民の救療及び醫師の傳習を行わしめられた。院長は緒方惟準。蘭系(後の大阪大學)。同年,越前福井藩立病院兼醫學研究機關養病所設立。蘭系。明治3年,岡山藩,門田村操山の麓に大病院及び醫學館を興す。蘭系(後の岡山醫大)。同年,新潟において地元有志協力の下に共立病院を興し,次で第一區協定病院と稱し醫學生を養成。(後の新潟大)。佛系。同年,熊本藩病院を創設翌年醫學所を興す。(後の熊本醫大)。蘭系。明治5年,京都粟田口青蓮院内に京都府療病院を開く,また管内より醫學生を募集す。(後の京都府立醫大)。獨逸系。この療疾院は病院の標旗として赤十字旗を樹てた。これはわが國における赤十字旗使用の嚆矢で,スイスで赤十字社結成後10年目のことである。函館病院(文久元年1861創立)これは緒方洪庵の弟子の高松凌雲が明治元年の戰役で院長となり創傷にわが國で初めて石炭酸水を使用して有名であるが,この病院は明治5年米國醫師が赴任している。米系。
明治2年(1869年)大阪上本町大福寺に大阪假病院が設立され,人民の救療及び醫師の傳習を行わしめられた。院長は緒方惟準。蘭系(後の大阪大學)。同年,越前福井藩立病院兼醫學研究機關養病所設立。蘭系。明治3年,岡山藩,門田村操山の麓に大病院及び醫學館を興す。蘭系(後の岡山醫大)。同年,新潟において地元有志協力の下に共立病院を興し,次で第一區協定病院と稱し醫學生を養成。(後の新潟大)。佛系。同年,熊本藩病院を創設翌年醫學所を興す。(後の熊本醫大)。蘭系。明治5年,京都粟田口青蓮院内に京都府療病院を開く,また管内より醫學生を募集す。(後の京都府立醫大)。獨逸系。この療疾院は病院の標旗として赤十字旗を樹てた。これはわが國における赤十字旗使用の嚆矢で,スイスで赤十字社結成後10年目のことである。函館病院(文久元年1861創立)これは緒方洪庵の弟子の高松凌雲が明治元年の戰役で院長となり創傷にわが國で初めて石炭酸水を使用して有名であるが,この病院は明治5年米國醫師が赴任している。米系。
掲載誌情報