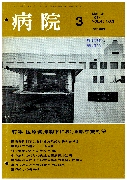文献詳細
病院職員の基礎知識 診療科の知識
文献概要
臨床検査とその歴史
生体中で生命現象が営まれているということは,生体を構成しているいろいろな成分が,物理的,化学的に極めて微妙に働き,一定のバランスを保って成り立っているということである.バランスがなんらかの原因によって徐々に,あるいは突然に崩れ始め精神的,肉体的に正常な状態でないことを感ずるようになる.これを病むという.病む原因となっているいろいろな成分のバランスがどのように崩れているかを知るために行うのが臨床検査である.
臨床検査の歴史は古く,ヒポクラテスが行った尿の観察が始まりとされており,ティオフィロス・プロトスパタリオスが体系化し,近世に至るまで医師が光を通して色や沈殿物の具合を調べて診断していた.我が国でも江戸時代に尿検査は行われていたが,体系化した臨床検査が行われるようになったのは明治時代になってからである.尿検査や細菌検査,梅毒反応,寄生虫検査などが診断の裏付けとして患者の主治医によって行われていた.第2次大戦後に導入されたアメリカ医学は,臨床検査の成績を一つの資料として診断することから検査する範囲も必然的に広くなり検査技術も,複雑になった.こうなると医師が診療の片手間に行うということができなくなり,臨床検査の中央化が進み旧陸,海軍病院や医科系大学の研究室などにいた技術者が専門に行うようになった.
生体中で生命現象が営まれているということは,生体を構成しているいろいろな成分が,物理的,化学的に極めて微妙に働き,一定のバランスを保って成り立っているということである.バランスがなんらかの原因によって徐々に,あるいは突然に崩れ始め精神的,肉体的に正常な状態でないことを感ずるようになる.これを病むという.病む原因となっているいろいろな成分のバランスがどのように崩れているかを知るために行うのが臨床検査である.
臨床検査の歴史は古く,ヒポクラテスが行った尿の観察が始まりとされており,ティオフィロス・プロトスパタリオスが体系化し,近世に至るまで医師が光を通して色や沈殿物の具合を調べて診断していた.我が国でも江戸時代に尿検査は行われていたが,体系化した臨床検査が行われるようになったのは明治時代になってからである.尿検査や細菌検査,梅毒反応,寄生虫検査などが診断の裏付けとして患者の主治医によって行われていた.第2次大戦後に導入されたアメリカ医学は,臨床検査の成績を一つの資料として診断することから検査する範囲も必然的に広くなり検査技術も,複雑になった.こうなると医師が診療の片手間に行うということができなくなり,臨床検査の中央化が進み旧陸,海軍病院や医科系大学の研究室などにいた技術者が専門に行うようになった.
掲載誌情報