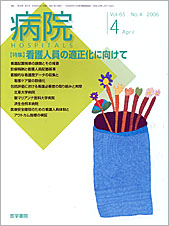1) 医療・福祉に対しては専門の公的金融として独立行政法人福祉医療機構が設置されているからでしょう.
2) 平成 15 年 10 月 1 日現在で,100 床あたりの従事者数は一般病院 108.9 人,精神病院 59.2 人となっています(出所:財団法人厚生統計協会『国民衛生の動向』2005 年第 52 巻第 9 号,p.191,表 31)
3) 出所:財団法人厚生統計協会『国民衛生の動向』2005 年第 52 巻第 9 号,p.187,表 26
4) 平成 15 年 10 月 1 日現在の病院数 9,122 には事業主が民間銀行の融資対象外である独立行政法人国立病院機構や公的病院,社会保険関係立病院なども含まれていますが,本稿ではそれらも含め,日本の全病院数をもとに話をすすめます.なお,医療法人の病院数は 5,588,個人立病院は 838 です.
5) 中小企業庁 web サイト:http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq01.html(2005.12.17 現在)
6) 信用保証協会は各都道府県に 1 つずつありますが,例外として神奈川は神奈川県と横浜市と川崎市の 3 つに,愛知は愛知県と名古屋市,岐阜は岐阜県と岐阜市,大阪は大阪府中小企業金融保証協会と大阪市に保証協会が分かれています.
7) 信用保証協会法(昭和 28 年 8 月 10 日 法律第 196 号).関係法律として中小企業信用保険法(昭和 25 年 12 月 14 日 法律第 264 号)があります.
8) 本稿では銀行と表記しますが,信用金庫,信用組合からの借入も信用保証協会の保証の対象です.
9) 国は従来,中小企業を経済的・社会的弱者と認識していましたが,平成 11 年の中小企業基本法改正以降は,中小企業を"我が国経済の活力の源泉"と位置づけています.
10) 信用保証協会が行った代位返済の元本金額の 70~80 %は,中小企業金融公庫から信用保証協会へ再保険の保険金として支払われます.その後,信用保証協会の回収努力にも関わらず回収できなかった場合,中小企業金融公庫の保険がカバーしない部分(20~30 %)は地方自治体が信用保証協会に補助金として交付します.
11) 銀行には保証約定違反や事務手続き上のオペレーションリスクは別途存在します.なお国債保有には金利上昇に伴う債券価格低下のリスクはあります.
12) 病院や企業の自己資本比率は [自己資本÷総資産] で計算されますが,銀行には BIS(国際決済銀行)規制の定義で算出する自己資本比率が適用されます.ここでは総資産は保有する資産の単純合計ではなく,資産にはリスクウェイトが掛けられて,加重平均で計算されます.リスクウェイトは自国国債や政府宛融資,現金は 0 %,他国向け債権,一般企業,病院への債権は格付段階によって区分されます.信用保証協会保証付融資は自国政府宛融資と同様にリスクウェイト 0 %として計算されています.リスクウェイト 0 %とは一般貸倒引当金は不要とされ,銀行経営にとってとても有利です.なお,BIS 規制は 2006 年末に新 BIS 規制に変更され,リスクの評価精緻化がなされる予定となっています.
13) 注 3)と同じく,病院数には信用保証協会の対象外である公的病院なども含めて話をしています.
14) 銀行経由ではなく,信用保証協会に直接申し込む方法もあります(信用保証協会によっては直接受付をしない所もあります).また自治体の利子補給制度等の制度融資を利用する場合などでは,自治体が受付窓口になる場合もあります.各地区の信用保証協会の連絡先は社団法人全国信用保証協会連合会のホームページ (http:// www.zenshinhoren.or.jp/) でご確認ください.
15) 申込様式をホームページからダウンロードできる信用保証協会もあります.
16) 中小企業が銀行借入する場合,信用保証協会の保証付融資は借入コストが低いですが,来月号で説明する国民生活金融公庫を利用すれば,もっと低利での資金調達が可能です.
17) 公認会計士,税理士,社会保険労務士,行政書士,コンサルタントなどは別です.いわゆる融資斡旋との名目での口利き料を要求する金融斡旋屋を指しています.