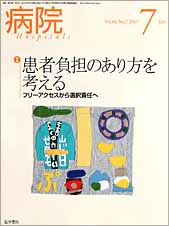文献詳細
文献概要
特集 患者負担のあり方を考える―フリーアクセスから選択責任へ
新規の診療行為の保険収載手続き―どこまで公的医療保険で面倒みるべきか?
著者: 川渕孝一1
所属機関: 1東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野
ページ範囲:P.549 - P.553
文献購入ページに移動1961年に施行された国民皆保険制度は国民すべからく平等に医療が受けられることを目的にするものである.より具体的には,医療保険料の見返りに業務外の疾病および傷害について,保険者が被保険者に現金ではなく医療サービスを給付するもの.給付の内容は,①診察,②薬剤または治療材料,③処置,手術その他の治療,④居宅における療養上の管理および治療に伴う世話その他の看護,⑤病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護(健康保険法第43条,国民健康保険法36条)などである.したがって被保険者は医療機関にかかった時には,一部負担金のみ支払えばよい.
このように,現物給付をベースとしたわが国の公的医療保険制度だが,未曾有の少子・高齢化と医療の技術進歩によってその持続可能性が危惧されている.実際,医療費の高騰に悩むドイツは2006年から選択制ではあるが,医療費の療養費払いを認めている.早晩,わが国でも介護保険と同様,医療保険も現金給付にしてはどうかという意見が浮上するかもしれない.しかし,その前に議論すべきは,現物給付制度下でどこまで公的保険でカバーし,どこまでを“自助努力”に委ねるかである.
事実,財政制度審議会が2006年6月に発表した「歳出歳入一体化に向けた基本的考え方」によれば,医療費抑制策として,①70歳以上の高齢者の自己負担率は他の世代の負担率と統一する,②食費・居住費は一般病床に入院するものも自己負担を原則とする,③後発品が存在する先発品の薬価は,後発品との差額を自己負担とする仕組みを導入する,④市販類似薬(非処方せん薬)は公的給付の対象外とする,⑤一定金額までの保険免責制を導入する,⑥高額療養費の自己負担限度額を見直す―などが並んでいる.
本稿では,新規の診療行為が保険収載される手続きがどのようになっているかについて言及した後,一定の事例を引き合いに出しながら保険未収載の現状と課題について述べる.
参考文献
掲載誌情報