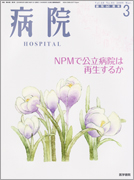文献詳細
特集 NPMで公立病院は再生するか
文献概要
■病院PFI事業への期待
1999年にPFI(Private Finance Initiative)が成立して以来,既に,300件を超える事業が実施段階に入っている.件数で見ると,学校や給食センター等が多くなっており,必ずしも公立病院が突出している訳ではないが,この間公立病院のPFI事業への関心は高かった.公立病院のPFI事業は規模の面でも付加価値の面でも他の分野の事業を圧倒する内容を有しているからだ.PFI事業の契約額の平均的な規模は100億円程度であるが,公立病院のPFI事業では2,000億円を超えるケースもある.病院施設の建設費が数百億円に届かないのが一般的であるにもかかわらず,契約額がこれほど巨額になるのは,公立病院のPFI事業が極めて広範な事業範囲を有しているからである.病院施設の設計,建設,維持管理といった一般的なPFI事業の業務に加えて,医療機器の整備・維持管理,医療関連サービスの提供,医療事務,調達,エネルギー供給,情報システムの提供,等が含まれている.公共団体が所有する施設としては最大級の病院施設に加え,その何倍ものサービス業務を含んでいるのが公立病院のPFI事業なのである.
こうした事業を運営するためには,広範な業務に対応するための技術やノウハウを有する複数の企業をとりまとめ,これらが連携してサービスを提供できるようにマネジメントする能力が求められる.上述した施設の建設,維持管理以外の契約額は広範な業務のマネジメントへの期待と対価と解釈することができる.その付加価値の高さはPFIの本家イギリスの病院PFI事業をも凌駕している.「箱モノ」と揶揄され施設の建設・維持管理以外の付加価値が低い,あるいは10億,20億円程度の投資規模のPFI事業が多い日本市場で,民間企業が公立病院のPFI事業に関心を持ったのは当然と言える.
1999年にPFI(Private Finance Initiative)が成立して以来,既に,300件を超える事業が実施段階に入っている.件数で見ると,学校や給食センター等が多くなっており,必ずしも公立病院が突出している訳ではないが,この間公立病院のPFI事業への関心は高かった.公立病院のPFI事業は規模の面でも付加価値の面でも他の分野の事業を圧倒する内容を有しているからだ.PFI事業の契約額の平均的な規模は100億円程度であるが,公立病院のPFI事業では2,000億円を超えるケースもある.病院施設の建設費が数百億円に届かないのが一般的であるにもかかわらず,契約額がこれほど巨額になるのは,公立病院のPFI事業が極めて広範な事業範囲を有しているからである.病院施設の設計,建設,維持管理といった一般的なPFI事業の業務に加えて,医療機器の整備・維持管理,医療関連サービスの提供,医療事務,調達,エネルギー供給,情報システムの提供,等が含まれている.公共団体が所有する施設としては最大級の病院施設に加え,その何倍ものサービス業務を含んでいるのが公立病院のPFI事業なのである.
こうした事業を運営するためには,広範な業務に対応するための技術やノウハウを有する複数の企業をとりまとめ,これらが連携してサービスを提供できるようにマネジメントする能力が求められる.上述した施設の建設,維持管理以外の契約額は広範な業務のマネジメントへの期待と対価と解釈することができる.その付加価値の高さはPFIの本家イギリスの病院PFI事業をも凌駕している.「箱モノ」と揶揄され施設の建設・維持管理以外の付加価値が低い,あるいは10億,20億円程度の投資規模のPFI事業が多い日本市場で,民間企業が公立病院のPFI事業に関心を持ったのは当然と言える.
掲載誌情報