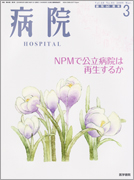文献詳細
連載 続クロストーク医療裁判・14
チーム医療における医師の刑事責任―最高裁平成17年11月15日決定の事例から
著者: 小津亮太1 奥津康祐2 花澤豊行3 岡本美孝3
所属機関: 1札幌地方・家庭裁判所室蘭支部 2東京大学大学院医学研究科法医学教室博士課程 3千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学
ページ範囲:P.241 - P.247
文献概要
第14回は刑事事件の判例を取り上げる.大学附属病院の耳鼻咽喉科で,指導医-主治医-研修医から成るチーム内で治療方針を立案し医局会議にかけ,科長が最終的に治療方針を決定する体制であった.主治医が抗がん剤の投与計画の立案を誤り,週1回投与すべき抗がん剤を連日投与するとともに,その副作用に適切に対応することなく患者を死亡させた事案である.科長は,主治医から治療方法の報告を受け了承していたが,具体的な薬剤の投与計画内容までは検討していなかった.主治医の過失自体は争いようがない事案であるが,チーム医療の責任者がどのような義務を負い,刑事責任を問われるのかという点が議論となった.
参考文献
掲載誌情報