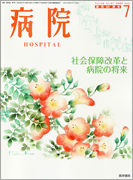文献詳細
文献概要
特集 社会保障改革と病院の将来
社会保障と税の一体改革に向けて
著者: 森信茂樹1
所属機関: 1中央大学 法科大学院
ページ範囲:P.560 - P.564
文献購入ページに移動私自身が,税と社会保障を一体的に考えることの必要性を強く認識したのは,小泉改革における「歳入・歳出一体改革」(2006年7月閣議決定)の議論であった.周知のようにこの閣議決定の内容は,「2011年度に国・地方の基礎的財政収支を黒字化するために必要となる対応額(歳出削減または歳入増が必要な額)は,16.5兆円程度で,そのうち11.4兆円から14.3兆円を歳出削減によって対応する」こととなっている.対応額(不足額)について,基本的に歳出削減でまかなうという考え方は納得できるものであるが,そこに至る議論で「歳出削減は善で,増税は悪」と単純に色分けし,対応額の7~9割を歳出削減で確保するとした思考方法は問題がある.
例えば次のようなことである.歳出削減を実行していく過程で,医療費の国庫負担の削減を図ればそれは,患者の個人負担を増加させることになる.年金の国庫負担を抑えようと思えば,基礎年金支給開始年齢(現行65歳)を引き上げざるをえないということになる.国の介護費用を削減しようとすれば,介護保険料の引き上げか,現在40歳以上となっている負担開始年齢の引き下げを行うことにつながる.現に医療費の自己負担割合は引き上げられ,生活保護の老齢加算や母子加算は削減され,2008年4月から75歳以上の老人医療保険制度も始まっている.
掲載誌情報