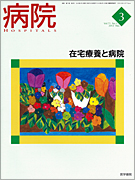文献詳細
特集 在宅療養と病院
文献概要
よく知られているように,わが国の人口構造は急速に変化している.人口数の減少とともに人口構成は一層高齢化し,国立社会保障・人口問題研究所の推計(2006年)によると,65歳以上人口は2025年に3635万人(30.5%),2055年には3646万人(40.5%)に達する1).この変化は特に都市部で著しく,2025年の65歳以上人口の増加数上位は,東京都110万人,神奈川県94万人,埼玉県85万人,大阪府75万人,千葉県72万人,愛知県67万人と推定されている2).これに伴い死亡数も増加し,2040年前後には日本全国で年間166万人とピークに達する見込みである(2010年概数119万人.出生数,死亡数が中位の変化を示したと仮定).さらに,高齢者単身世帯の増加も著しい.
このような状況の変化は,地域における医療の機能や役割分担を促す大きな要因となっている.国民側の在宅医療へのニーズも高く,厚生労働省が行った「終末期医療に関する調査」(2008年)では,終末期の療養場所として約63%が自宅(「必要になれば医療機関に入院する」を含む)を挙げている3).また,55歳以上を対象とした内閣府の「高齢者の健康に関する意識調査」(2007年度)でも,「日常生活を送る上で,介護が必要になった場合,どこで介護を受けたいか」と尋ねたところ,自宅が約42%と最も高かった4).こうしたことを背景に,在宅療養の充実がクローズアップされている.厚生労働省によると,在宅医療を必要とする人は2025年には29万人と,現在より約12万人増える見込みという.しかし一方で,最期まで自宅で療養できるのは難しいと考える割合は66%と高く(終末期医療に関する調査),人口動態調査による在宅死亡率(2010年)も,自宅12.6%,老人ホーム(介護老人保健施設を除く)3.5%に留まっていることから(図1)5),在宅医療の充実には様々な角度からの課題解決が必要である.
本稿では,筆者らが実施した平成22年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業「在宅療養支援の実態把握と機能分化に関する研究」6)の結果を中心に,主に医療提供側から在宅療養の現状を評価し,今後の方向性について考えていきたい.
このような状況の変化は,地域における医療の機能や役割分担を促す大きな要因となっている.国民側の在宅医療へのニーズも高く,厚生労働省が行った「終末期医療に関する調査」(2008年)では,終末期の療養場所として約63%が自宅(「必要になれば医療機関に入院する」を含む)を挙げている3).また,55歳以上を対象とした内閣府の「高齢者の健康に関する意識調査」(2007年度)でも,「日常生活を送る上で,介護が必要になった場合,どこで介護を受けたいか」と尋ねたところ,自宅が約42%と最も高かった4).こうしたことを背景に,在宅療養の充実がクローズアップされている.厚生労働省によると,在宅医療を必要とする人は2025年には29万人と,現在より約12万人増える見込みという.しかし一方で,最期まで自宅で療養できるのは難しいと考える割合は66%と高く(終末期医療に関する調査),人口動態調査による在宅死亡率(2010年)も,自宅12.6%,老人ホーム(介護老人保健施設を除く)3.5%に留まっていることから(図1)5),在宅医療の充実には様々な角度からの課題解決が必要である.
本稿では,筆者らが実施した平成22年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業「在宅療養支援の実態把握と機能分化に関する研究」6)の結果を中心に,主に医療提供側から在宅療養の現状を評価し,今後の方向性について考えていきたい.
参考文献
1)国立社会保障・人口問題研究所:日本の将来推計人口(平成18年12月推計),2006 http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/suikei07/index.asp
2)国立社会保障・人口問題研究所:日本の都道府県別将来推計人口(平成19年5月推計)について,2007 http://www.ipss.go.jp/pp-fuken/j/fuken2007/t-page.asp
3)厚生労働省:終末期医療に関する調査,2008
4)内閣府:高齢者の健康に関する意識調査,2008 http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h19/kenko/zentai/index.html
5)厚生労働省:平成22年(2010)人口動態調査,2011 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei10/index.html
6)武林亨(研究代表者):平成22年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業「在宅療養支援の実態把握と機能分化に関する研究」,2011 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jlr7-att/2r9852000001jlvs.pdf
7)厚生労働省:国民衛生の動向 2011/2012年版,厚生衛生統計協会,2011
8)WHO:Global Burden of Disease: Death and DALY estimates for 2004 by cause for WHO Member States http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_contry/en/index.html
9)Lynn J : Perspectives on care at the close of life. Serving patients who may die soon and their families : the role of hospice and other services. JAMA 285(7) : 925-932, 2001
10)厚生労働省:平成20年(2008)医療施設静態調査,2009 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/08/index.html
掲載誌情報