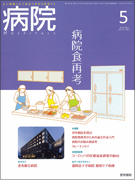文献詳細
文献概要
特集 病院食再考
病院食を再考する―病院食の現状とこれから
著者: 中村丁次1
所属機関: 1神奈川県立保健福祉大学
ページ範囲:P.346 - P.349
文献購入ページに移動人類は,古くから日常の食事や食品が病気の発症や治療に関与する事を経験的に知っていた.古今東西を問わず,日常の生活習慣や医療の中で,食事と健康や病気との関係は多く議論され,伝統的な医療や風習として残っている.しかし,現在,世界中で実施されている病院食は,18世紀後半,ヨ-ロッパで誕生した栄養学を基盤にした食事法である.その理由は,食事と病気との関係が数多く議論される中で,栄養学のみが生命科学の一部として,科学的に論理を積み重ねることができ,医療の近代化の中に組み込むことができたからだと思う.
わが国で栄養学が紹介されたのは,明治維新の際に行われたドイツ医学の導入からである.1877(明治10)年,外国人科学者として政府から招聘された医師フォイト(Foit)は,「食事と言うのは好みに従って食べるのは悪く,含有される成分によって食べること」と,栄養学の考え方と食事療法の概念を解説している.しかし,病院食が,治療の一環として位置づけられ,制度的に整理されてくるのは戦後のGHQの指導による.1947(昭和22)年,GHQは当時の病院を調査し,病院の改善の必要性を政府に指摘した.そのことを踏まえ,1948(昭和23)年に医療法が制定され,その中で病院食と病院栄養士が法的に位置づけられたのである.1950(昭和25)年には,入院患者が補食をしないで,病院の食事だけで適正な栄養量が確保できることを趣旨とした「完全給食制度」が策定され,1日に2,400kcalの食事が提供されるようになった.当時,多くの国民が食料不足のために低栄養状態に悩まされる中で,病弱者への食料は優先的に確保し,患者の栄養状態を良くしようと考えた栄養関係者の努力があったからである.
参考文献
掲載誌情報