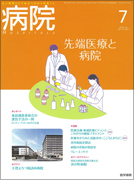83巻12号(2024年12月発行)
特集 検証 2024年度診療報酬改定—病院の機能分化と連携の行方
83巻11号(2024年11月発行)
特集 病院の価値を創る組織マネジメント
83巻10号(2024年10月発行)
特集 遠隔支援の新時代—未来のビジョンとその実現に向けて
83巻9号(2024年9月発行)
特集 持続可能な病院運営のためのコスト管理
83巻8号(2024年8月発行)
特集 潜在医療資格者をいかに活用するか
83巻7号(2024年7月発行)
特集 病院経営を科学する
83巻6号(2024年6月発行)
特集 人を重視した病院組織マネジメント
83巻5号(2024年5月発行)
特集 働き方改革を乗り越える組織変革と人材育成—エイジダイバーシティの価値を引き出す
83巻4号(2024年4月発行)
特集 地域医療連携推進法人の成功事例
83巻3号(2024年3月発行)
特集 病床稼働率アップ!—PFM導入がもたらす絶大な効果
83巻2号(2024年2月発行)
特集 在宅医療を巡る病院の経営戦略
83巻1号(2024年1月発行)
特集 超高齢者激増時代の病院経営戦略