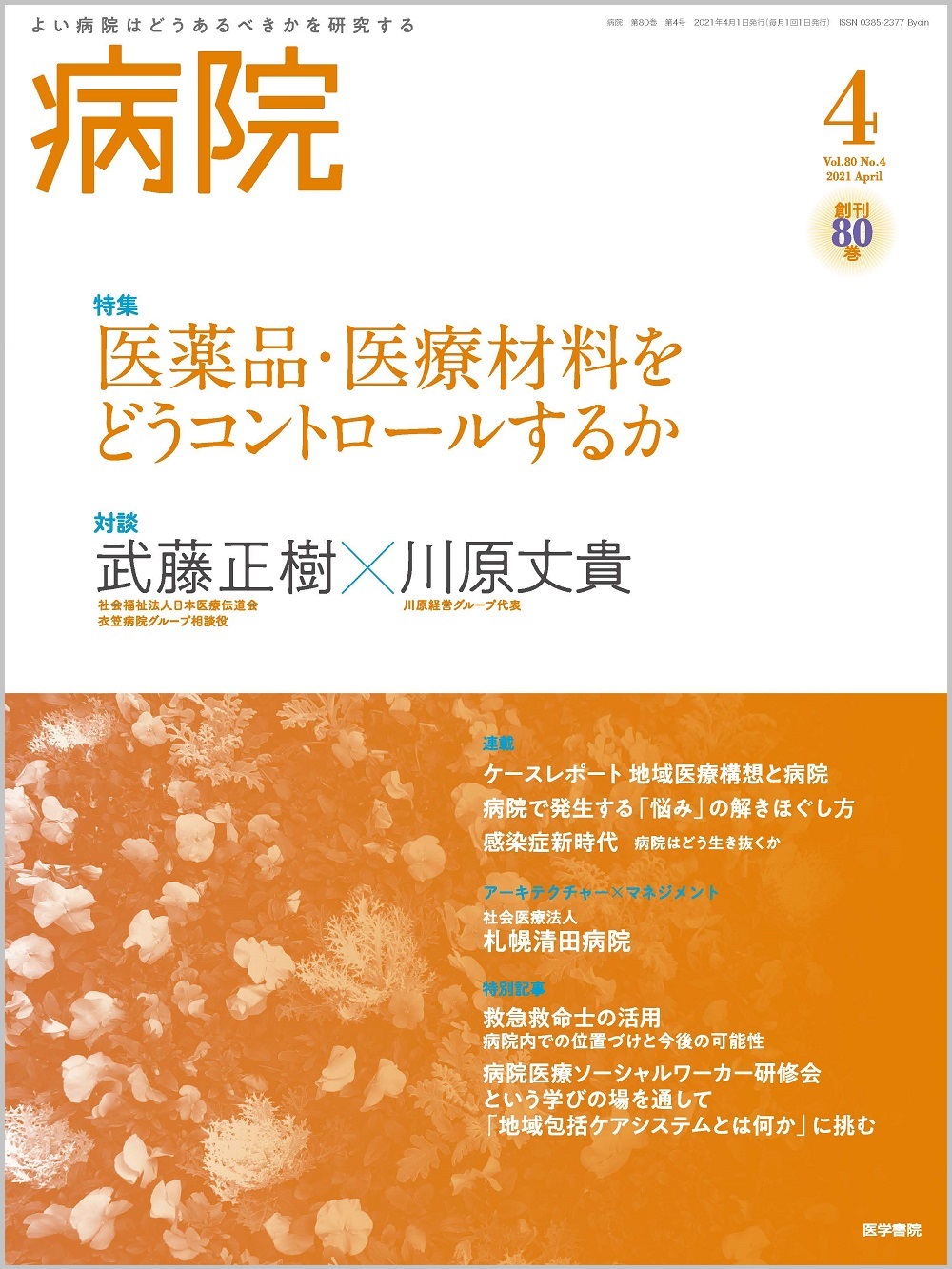文献詳細
特集 医薬品・医療材料をどうコントロールするか
医薬品・医療材料の現況
医薬品の費用対効果と価値をめぐる議論とは—高額薬剤とオカネ/いのち
著者: 五十嵐中1
所属機関: 1横浜市立大学医学群健康社会医学ユニット
ページ範囲:P.296 - P.299
文献概要
半世紀以上の長きにわたって日本では,「国民皆保険制度」という言葉が「全ての国民が公的医療制度に加入できる(実質的には,加入する義務がある)」状態という本来の定義を超えて,「その公的医療制度でほぼ全ての医薬品が賄われる」状態として理解されてきた.
本来のUniversal Health Coverage(UHC)は,世界的には「全ての人が必要な保健サービスを金銭的な困難なく享受できること」と定義される.UHCの達成度合いは3つの軸,すなわち「保健システムがカバーする人口」「保健システムがカバーするサービス」「患者の自己負担金額」で評価され,必然に「より多くの人に,より多くの保健サービスが,より低廉な自己負担で提供されている」ほど,理想的な状態とされる.それゆえ,「全ての医薬品をカバーすること」は決して必須条件ではなく,いわゆる「皆保険」を導入している国であっても,承認されている医薬品を一律に公的医療制度でカバーするのはむしろ例外的である.
承認されている医薬品のうち,「全部」ではなく「一部」をカバーする,もしくは自己負担割合・給付価格などに傾斜をつけるとなれば,何らかの基準を用いてカバーの可否や,自己負担割合・給付価格を決める必要が出てくる.だからこそ諸外国で,この基準の一部として効率性や費用対効果のデータを用いる動きが進んでいる.
全ての薬がカバーされる状況に半世紀以上「慣れ親しんできた」日本にとって,何らかの形で給付にメリハリをつけること,さらには,公的医療制度での給付の可否や,給付価格の調整に「効率性」の軸を加えることは,「医療にオカネの話を持ち込むべきでない」「海外と違って費用対効果の考え方はなじまない」のような,ある意味情動的な意見の下に阻まれることが多かった.
議論の風潮を変えたのは,2015年以降の高額薬剤の上市である(表1).第1波のオプジーボ®(免疫チェックポイント阻害薬)やソバルディ®・ハーボニー®(C型肝炎治療薬)は,高額な薬剤を多くの人が使うことによる財政影響の大きさが問題視された.財政影響が大きくなれば,保険システムの持続性が脅かされるというのは,ある意味妥当な意見である.もっともこの段階では,希少疾病など財政影響の小さな医薬品であれば,オカネの議論は不要との考え方もまた成り立っていた.
第2波のキムリア®(2019年),第3波のゾルゲンスマ®(2020年)は,いずれも希少疾病の治療薬で,財政影響は数十億円と小さい.しかし,単価が前者は3300万円・後者は1億6700万円と超高額になり,世間やメディアの耳目を集めるには十分だった.実際業界紙のみならず多くの主要メディアが,単価を見出しに据えて報じた.財政影響の大小にかかわらず,超希少疾病の薬でも,単価が高ければ「値段に見合った価値なのか?」という説明責任として,オカネの話を求められる時代になった.あわせて,第1波では半ばタブー視されてきた給付の可否まで踏み込んだ議論も,表立ってなされるようになった.
現段階では未承認であるが,米国食品医薬品局(FDA)で評価が進む認知症の抗体薬アデュカヌマブが承認・上市されれば,第1波と同様の財政影響の議論が出てくるのは必至である.誰に投与するのが最適なのかを議論する際に,オカネの要素は当然課題となろう.
掲載誌情報