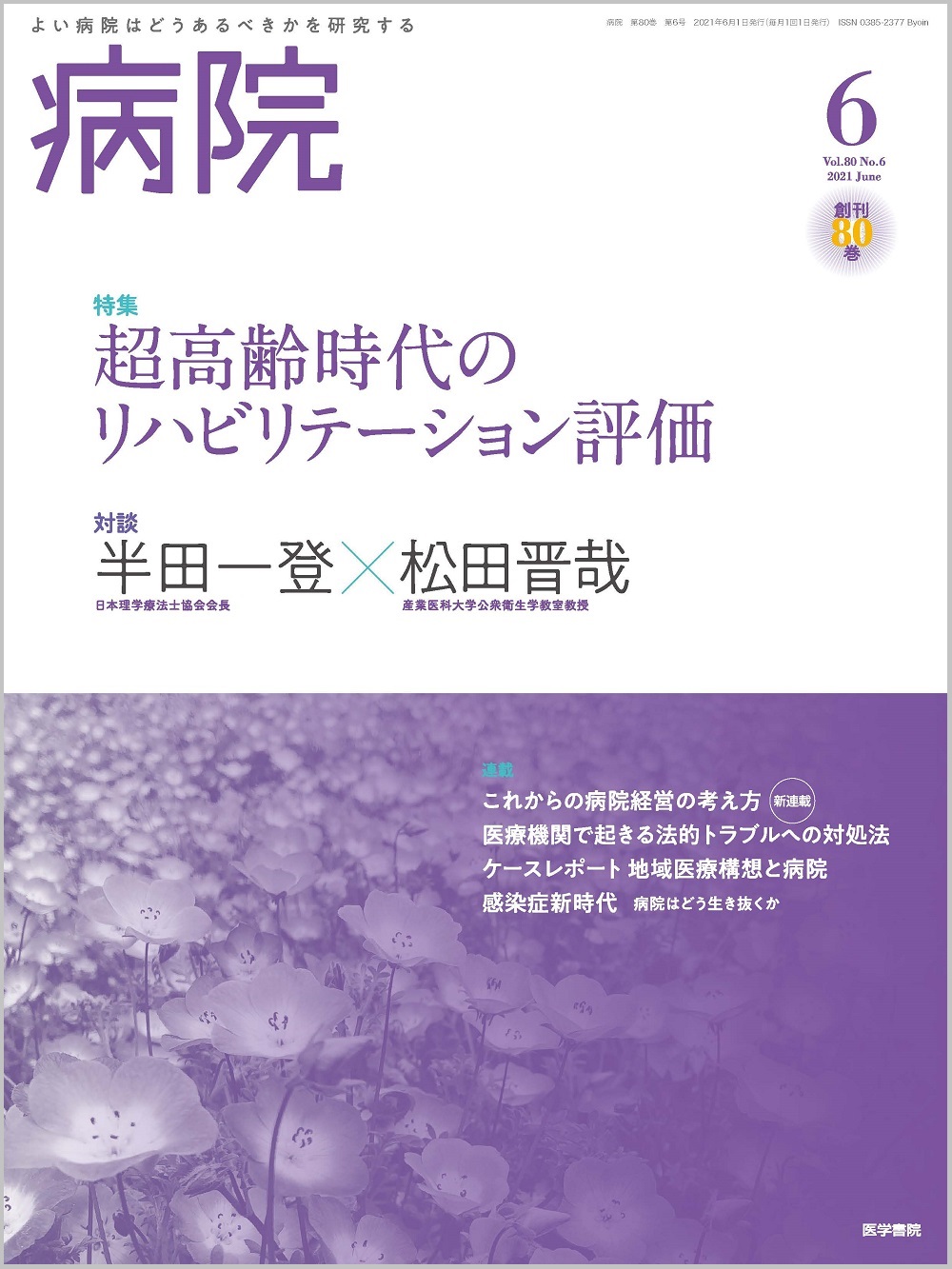文献詳細
特集 超高齢時代のリハビリテーション評価
総論 リハビリテーションの評価
文献概要
■はじめに
超高齢社会においては,急性期・回復期・慢性期に関係なく,リハビリテーションを必要とする患者が増加する.また,リハビリテーションについては漫然とそれを行うのではなく,効果のある介入を促進する目的で質の評価を行うことも求められる.こうした問題意識から,これまでの診療報酬改定ではリハビリテーションの実施に関する評価項目が増やされてきた.効果のあるリハビリテーションを評価するという視点から,例えば回復期リハビリテーション病棟においては機能改善というアウトカムと診療報酬の紐づけが行われてきた.しかしながら,この評価が導入された2016年から入棟時のFIM得点が低下し,FIM利得が大幅に増加するという事象が生じており,いわゆるクリームスキミングが行われた可能性が指摘された.これを受けて2020年度診療報酬改定ではFIM利得による評価が厳しくなった.
また,疾患別リハビリテーション対象患者については,一定の要件を満たす患者以外は,その継続ができなくなっている.具体的には要介護被保険者などの外来維持期リハビリテーションが2019年3月末で廃止された.これについて,要介護高齢者やその診療に当たってきた医師らから,対象者の生活機能が低下するのではないかという危惧が出されている.この背景には,厳しい社会保障財政の中,リハビリテーションにsupply side induced demand(供給側によって作り出される需要)があり,それが出来高払い制度の下では過剰なサービス提供につながっているのではないかという支払い側の批判がある.加えて,リハビリテーションが医療保険と介護保険とにまたがることから,維持期リハビリテーションについては,高齢者の自立支援を目的とした介護保険で手当てすることが自然であるという意見もある.
しかしながら,利用者である患者の側から考えると,リハビリテーションの連続性が必ずしも保障されていない現状には不満や疑問が残る.社会保障財政の状況が厳しい以上,制度を維持するためには,将来的に今以上の保険料あるいは税金を投入することが不可避となる.その際,国民が納得して負担を引き受けるためには,サービスの内容が質も含めて評価されることを前提に可視化されていることが必要となる.こうした可視化を進めるためには,リハビリテーション医療の情報化がカギとなる.
本稿では,上記の問題意識に基づいてリハビリテーション医療の評価の現状と今後の方向性について私見を述べたい.
超高齢社会においては,急性期・回復期・慢性期に関係なく,リハビリテーションを必要とする患者が増加する.また,リハビリテーションについては漫然とそれを行うのではなく,効果のある介入を促進する目的で質の評価を行うことも求められる.こうした問題意識から,これまでの診療報酬改定ではリハビリテーションの実施に関する評価項目が増やされてきた.効果のあるリハビリテーションを評価するという視点から,例えば回復期リハビリテーション病棟においては機能改善というアウトカムと診療報酬の紐づけが行われてきた.しかしながら,この評価が導入された2016年から入棟時のFIM得点が低下し,FIM利得が大幅に増加するという事象が生じており,いわゆるクリームスキミングが行われた可能性が指摘された.これを受けて2020年度診療報酬改定ではFIM利得による評価が厳しくなった.
また,疾患別リハビリテーション対象患者については,一定の要件を満たす患者以外は,その継続ができなくなっている.具体的には要介護被保険者などの外来維持期リハビリテーションが2019年3月末で廃止された.これについて,要介護高齢者やその診療に当たってきた医師らから,対象者の生活機能が低下するのではないかという危惧が出されている.この背景には,厳しい社会保障財政の中,リハビリテーションにsupply side induced demand(供給側によって作り出される需要)があり,それが出来高払い制度の下では過剰なサービス提供につながっているのではないかという支払い側の批判がある.加えて,リハビリテーションが医療保険と介護保険とにまたがることから,維持期リハビリテーションについては,高齢者の自立支援を目的とした介護保険で手当てすることが自然であるという意見もある.
しかしながら,利用者である患者の側から考えると,リハビリテーションの連続性が必ずしも保障されていない現状には不満や疑問が残る.社会保障財政の状況が厳しい以上,制度を維持するためには,将来的に今以上の保険料あるいは税金を投入することが不可避となる.その際,国民が納得して負担を引き受けるためには,サービスの内容が質も含めて評価されることを前提に可視化されていることが必要となる.こうした可視化を進めるためには,リハビリテーション医療の情報化がカギとなる.
本稿では,上記の問題意識に基づいてリハビリテーション医療の評価の現状と今後の方向性について私見を述べたい.
参考文献
1)厚生労働科学研究費補助金・長寿科学政策研究事業「在宅・介護施設等における慢性期の医療ニーズの評価指標等を作成するための研究 (H30-長寿-一般-003)(研究代表者:松田晋哉)」平成30年-令和2年度 総合研究報告書,令和3(2021)年3月
2)厚生労働科学研究・政策科学総合研究事業・政策科学推進研究事業「急性期の入院患者に対する医療・看護の必要性と職員配置等の指標の導入に向けた研究(20AA2002)(研究代表者:松田晋哉)」令和2年度 総括研究報告書,令和3(2021)年3月
3)厚生労働省:病床機能報告年度別病床機能報告公表データ,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html
4)産業医科大学:令和2年度老人保健事業推進費等補助金・老人保健健康増進等事業「介護サービス内容の標準コードの開発」報告書,令和3(2021)年3月
5)松田晋哉:地域医療構想のデータをどう活用するか,医学書院,2020
6)松田晋哉:医療のなにが問題なのか—超高齢社会日本の医療モデル,勁草書房,2013
掲載誌情報