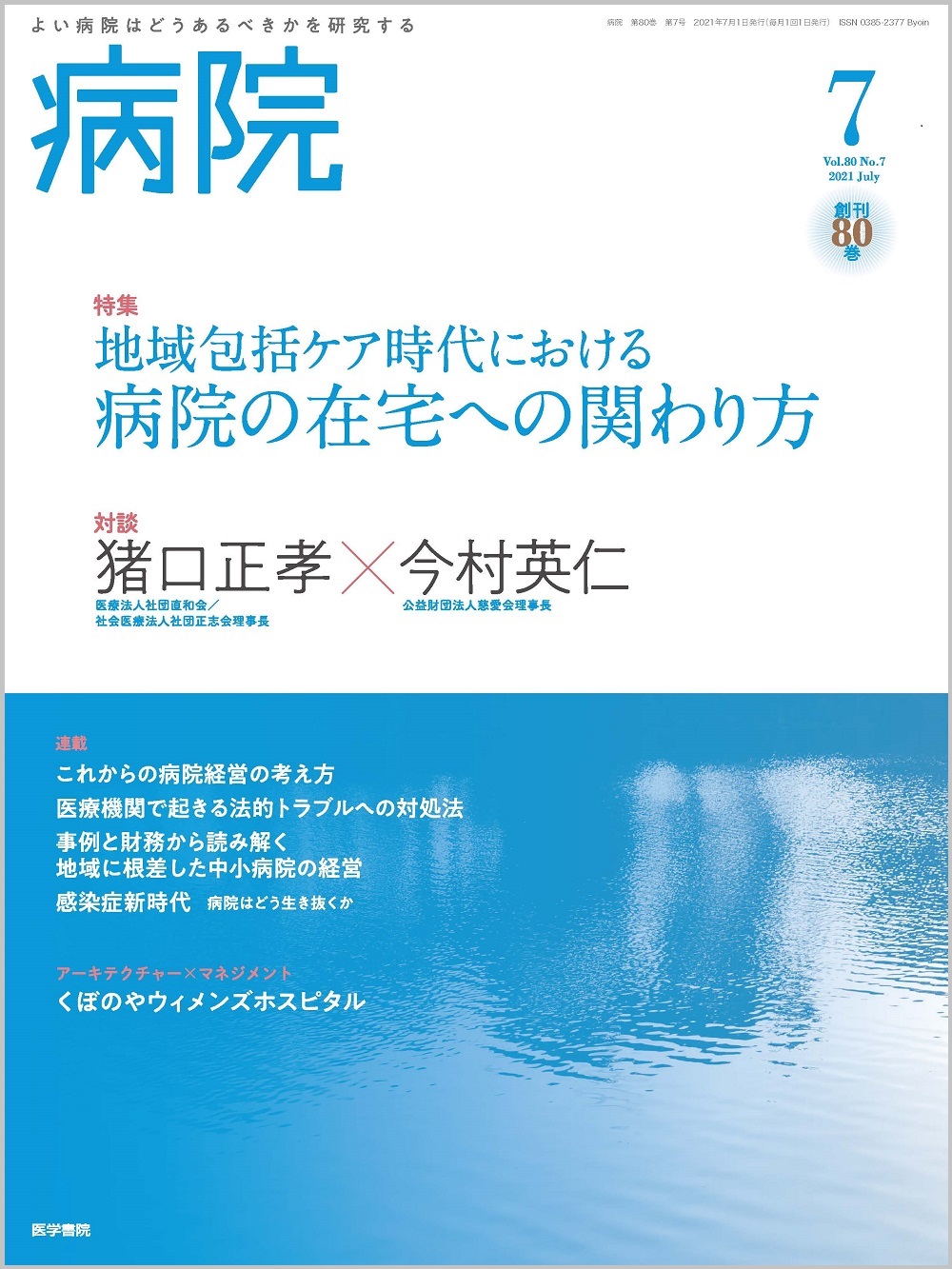文献詳細
特集 地域包括ケア時代における病院の在宅への関わり方
総論
文献概要
■はじめに
各種世論調査の結果では,多くの国民が人生の最終段階をできれば住み慣れた家で過ごしたいと考えている.しかし,「家族に面倒をかけたくない」「症状急変時の不安」などの理由により,病院や施設への入院,入所を選択する者が多いのが現実である.このような状況を踏まえて,国は在宅医療の推進を目指して種々の施策を行っている.地域医療構想の議論においても,現在療養病床で入院治療を受けている高齢患者のうち医療区分Ⅰの者の70%を在宅で診ることが予定されている.しかしながら,これらの患者は複数の慢性疾患を持っているのが一般的であり,例えば,福岡県医師会調査によれば,医療区分Ⅰの入院患者のうち63%は「家族の受け入れがあれば退院可能」と病院側は判断している1)が,核家族化が進んだ高齢世帯では必ずしも容易ではないだろう.
筆者はかつて全国の済生会組織を対象に,医療ニーズの高い高齢者の在宅事例のケースを収集し,在宅療養が継続できる条件を調査したことがある2).その結果,「かかりつけ医がいること」「もしもの時の後方病院があること」そして「その調整を24時間対応で可能な訪問看護があること」の3つが重要な要因であることを示した.このような安心感がなければ在宅ケアは継続しないし,また柔軟に在宅と入院・入所を利用できるネットワークと,それを支える情報基盤が必要であると筆者は考えている.
猪飼はその著書3)で「治療医学の場としての『病院の世紀』の終焉」について論考している.そこでは病院が単に治療だけではなく,患者のQOLに配慮した視点を持たざるを得なくなり,(地域)包括ケアの枠組みの中で再構築されていく必要性を,歴史的必然として説明している.地域包括ケアの中心は患者である.Patient centered medicineが志向されているのである.その中心として想定されているのは在宅ケアである.しかし,複数の慢性疾患を持ち,介護ニーズも高い高齢患者を,どのように在宅でケアしていくかについては,データに基づいた客観的な議論が不可欠である.
そこで,本稿では西日本のある自治体の医療および介護レセプトを用いて,訪問診療の現状について,利用している医療介護サービスおよび主たる傷病の経時的変化に着目して検討した結果などを基に,病院による在宅支援の在り方について論考する.
各種世論調査の結果では,多くの国民が人生の最終段階をできれば住み慣れた家で過ごしたいと考えている.しかし,「家族に面倒をかけたくない」「症状急変時の不安」などの理由により,病院や施設への入院,入所を選択する者が多いのが現実である.このような状況を踏まえて,国は在宅医療の推進を目指して種々の施策を行っている.地域医療構想の議論においても,現在療養病床で入院治療を受けている高齢患者のうち医療区分Ⅰの者の70%を在宅で診ることが予定されている.しかしながら,これらの患者は複数の慢性疾患を持っているのが一般的であり,例えば,福岡県医師会調査によれば,医療区分Ⅰの入院患者のうち63%は「家族の受け入れがあれば退院可能」と病院側は判断している1)が,核家族化が進んだ高齢世帯では必ずしも容易ではないだろう.
筆者はかつて全国の済生会組織を対象に,医療ニーズの高い高齢者の在宅事例のケースを収集し,在宅療養が継続できる条件を調査したことがある2).その結果,「かかりつけ医がいること」「もしもの時の後方病院があること」そして「その調整を24時間対応で可能な訪問看護があること」の3つが重要な要因であることを示した.このような安心感がなければ在宅ケアは継続しないし,また柔軟に在宅と入院・入所を利用できるネットワークと,それを支える情報基盤が必要であると筆者は考えている.
猪飼はその著書3)で「治療医学の場としての『病院の世紀』の終焉」について論考している.そこでは病院が単に治療だけではなく,患者のQOLに配慮した視点を持たざるを得なくなり,(地域)包括ケアの枠組みの中で再構築されていく必要性を,歴史的必然として説明している.地域包括ケアの中心は患者である.Patient centered medicineが志向されているのである.その中心として想定されているのは在宅ケアである.しかし,複数の慢性疾患を持ち,介護ニーズも高い高齢患者を,どのように在宅でケアしていくかについては,データに基づいた客観的な議論が不可欠である.
そこで,本稿では西日本のある自治体の医療および介護レセプトを用いて,訪問診療の現状について,利用している医療介護サービスおよび主たる傷病の経時的変化に着目して検討した結果などを基に,病院による在宅支援の在り方について論考する.
参考文献
1)福岡県医師会:療養病床及び地域包括ケア病床に関する調査報告書.平成28年3月
2)社会福祉法人恩賜財団済生会:ハイリスク在宅高齢者に対するケアマネジメント手法の開発に関する調査研究報告書.2001
3)猪飼周平:病院の世紀の理論.有斐閣,2010
4)厚生労働省:介護保険事業状況報告 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/84-1.html
5)松田晋哉:社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院—施設品質から地域品質へ 変化の先頭に立つ経営.病院75:536-543,2016
6)松田晋哉:台北市における病院を中心とした保健医療介護ネットワークによる地域包括ケアの推進.病院77:648-652,2018
7)「医療IT」かけ声倒れ—診療データ共有,登録1%どまり.日本経済新聞電子版,2019年3月14日 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42441870U9A310C1SHA000/
8)松田晋哉:医療法人社団豊生会 東苗穂病院—高齢化が進む都市部での地域包括ケアシステムの構築:病院を中核とした日本型Medical neighborhoodの実践.病院79:458-464,2020
掲載誌情報