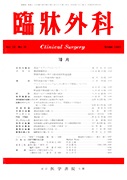文献詳細
グラフ グラフ解説
閉塞性黄疸に対する経皮経肝胆道造影—ことに不成功例の検討
著者: 堀内弘1 遠藤巌1 米山桂八1 植草実1 磯利次2 宮崎道夫2 杜子威2
所属機関: 1慶応義塾大学医学部外科学教室 2大田原赤十字病院外科
ページ範囲:P.1409 - P.1419
文献概要
経皮的に直接胆道に造影剤を注人して胆管を造影しようとする試みは,経口的あるいは経静脈的に造影剤を投与して肝から排泄される造影剤によつて肝外胆管の影像を求めようとする方法よりも以前に始まつている.Burkhardt&Müller (1920)1)が初めて経皮的胆嚢造影を行なつて以来,Huard&Do-Xan-Hop (1937)2)は経皮経肝的胆道造影を,Lee (1942)3),Royer&Solari (1947)4)らは腹腔鏡下に胆嚢を穿刺して造影を行なつている.しかし優れた経口,経静脈造影剤の出現とともに,危険と技術的困難を伴う経皮的胆道造影法は一般に広く利用されなくなつた.とはいえ経口,経静脈法によつては,ことに黄疸指数30以上,血清ビリルビン値3mg/dl以上では造影不能で,診断的根拠がえられない場合も少なくない.したがつて肝外胆管の閉塞に由来する黄疽例ではこれらの方法は全く応用価値がない.経皮経肝胆道造影法はCarter&Saypol (1952)5),Nurich (1953)6)らによつて再評価されて以来,南米において普及し,ついで英米においてとりあげられて多くの報告が診断的価値の高いことをのべている7)−19,22.33).わが国においてもことに閉塞性黄疸の診断に,ひいては治療方針の判定に極めて有用な造影法として広く受け人れられてきている20)21).
掲載誌情報