症例
患者:57歳,男性
主訴:自覚症状はない.
雑誌目次
臨床外科56巻11号
2001年10月発行
雑誌目次
特集 画像で決める癌手術の切除範囲—典型症例総覧
Ⅰ.食道癌
頸部食道癌に対する喉頭温存と喉頭・気管合併食道切除術
著者: 塩崎均 , 矢野雅彦 , 田村茂行 , 安田卓司 , 藤原義之
ページ範囲:P.13 - P.18
はじめに
従来,頸部食道癌に対する標準手術として咽頭喉頭食道摘出(咽喉食摘)手術が行われてきた1).しかしながら,術後に発声機能の喪失という大きなQOLの障害を余儀なくされる.喉頭を合併切除するための根拠は気管への腫瘍の浸潤と腫瘍の口側断端距離の安全性の確保,誤嚥の防止の3点がその主なものである.近年,喉頭摘出後の発声機能の再建手術が報告されているが,その効果ならびに持続性については問題点も多い.筆者らは化学放射線療法の効果を利用し,根治性を落とさず発声機能を温存する術式を試みている.本稿では,頸部食道癌における喉頭温存と喉頭・気管合併食道切除術の適応について画像を中心に述べる.
胸部食道癌に対する内視鏡補助下手術
著者: 細川正夫 , 久須美貴哉 , 草野真暢 , 田邉康 , 安部達也
ページ範囲:P.19 - P.25
内視鏡補助下食道癌手術
各施設で内容が異なり,内視鏡を用いて胸部操作のみ行うものから,胸部,腹部操作まで行うものものまである1).胸部操作もポート挿入のみで行うものから小開胸を加えるものまで種々である.今回,内視鏡補助下手術を筆者らが行っているポート挿人2〜3か所,側胸部に7cmの小切開を加えて行う術式とした.すなわち,胸部食道癌に対する胸部操作は内視鏡を補助的に使用して胸部食道摘出およびリンパ節郭清を行い,再建は従来と同じく開腹による術式とした.
食道癌に対する右開胸食道切除+3領域リンパ節郭清術
著者: 梶山美明 , 鶴丸昌彦 , 服部公昭 , 富田夏実 , 鳴海賢二 , 岩沼佳見
ページ範囲:P.26 - P.30
はじめに
画像診断の結果によって癌の手術術式を選択する場合,細心の注意を払っておかなければならないことはその画像診断の精度,信頼性(施行・判定する医師の能力も含めて)である.画像診断を手術術式の選択,変更の根拠にする場合には,常に「画像診断の不正確性」を完全には排除できないことを忘れてはならない.
現実の食道癌の臨床で術前検査として重要な画像診断は「癌の深達度診断」と「転移リンパ節診断」である.この2つの画像診断の結果によって胸部食道癌の標準手術である「右開胸食道切除+3領域リンパ節郭清手術」を行うのか,郭清範囲を縮小したり,内視鏡的粘膜切除などの「縮小治療」を行うのか,あるいはdown-stagingを企図して「術前治療」として化学療法や化学放射線療法を行うかが決定される.
食道癌に対する右開胸食道切除+2領域リンパ節郭清術
著者: 西巻正 , 神田達夫 , 中川悟 , 小杉伸一 , 田邊匡 , 小向慎太郎 , 本間英之 , 清水孝王 , 内藤哲也 , 石川卓 , 畠山勝義
ページ範囲:P.31 - P.35
切除範囲の決定と術式の選択
食道癌症例に対していかなる切除・郭清術式を選択するかは患者の全身状態と術前画像診断による腫瘍進展状況の総合評価で決定する.患者の重要臓器機能や栄養状態に問題がなく,また遠隔臓器転移も認めない場合,根治術式の選択に直接関係する腫瘍進展程度のパラメーターは,①原発巣の壁深達度,②リンパ節転移の有無,総数,および解剖学的存在部位,そして,③壁内転移(図1)の有無などである.その理由はこれらの因子が腫瘍のresectability(①)と切除後予後(②,③)に密接に関係するからである1,2).通常,これらの診断には食道造影検査,内視鏡検査,超音波内視鏡検査(EUS),頸部および腹部超音波検査,そして胸部(頸部下部および上腹部を含む)CTが用いられる.
教室では胸部下部食道癌(Lt)の根治に頸胸腹部3領域リンパ節郭清は意義が少ないとの検討結果1)に基づいて,1994年以降Lt原発食道癌に対する根治術式として3領域リンパ節郭清は施行していない.根治が期待される(すなわち,リンパ節転移総数が4個以内で,壁内転移と頸部リンパ節転移が認められない1,2))Lt原発浸潤癌に対しては右開胸食道切除+縦隔・腹部2領域リンパ節郭清,もしくは中・下縦隔リンパ節郭清を伴う非開胸食道切除術(根治的非開胸食道切除術)を根治術式として施行している3).
気管浸潤胸部食道癌に対する気管合併切除術
著者: 松原敏樹 , 黒田純子 , 渡久地政尚 , 川端一嘉 , 陳勁松 , 馬場哲 , 山田恵子 , 清水わか子
ページ範囲:P.36 - P.42
症例
患者:50歳代,女性
主訴:嚥下痛,嗄声
進行食道癌に対するネオアジュバント療法と食道切除術
著者: 井手博子 , 太田正穂
ページ範囲:P.43 - P.49
はじめに
進行食道癌では広範なリンパ節転移を伴う病変や隣接臓器に浸潤するT4癌が少なからず経験される.しかもこれらに対する治療は外科的切除のみで十分な予後を期待することは困難である,今日ではneoadjuvant therapyとして手術療法前に化学療法,放射線療法,化学放射線療法を併用した集学的治療が多くの施設で積極的に行われており,奏効例では根治切除が困難な高度進行食道癌が切除可能となり,長期生存する症例も経験するようになった.
本稿では,neoadjuvant therapyが奏効し,根治切除が可能となり,長期生存が得られた自験例を供覧し,neoadjuvant therapyの適応,現状について概説する.
Ⅱ.胃癌
早期胃癌に対する内視鏡的粘膜切除術
著者: 谷雅夫 , 竹下公矢
ページ範囲:P.52 - P.57
はじめに
現在の早期胃癌に対する内視鏡的粘膜切除術(EMR)の適応はリンパ節転移のないm癌であり,組織型がpap,tub1で,大きさが2cm以内の隆起型病変または1cm以内で潰瘍性病変のない陥凹型病変とする施設が多い1).
最近では手技の改良によってその適応は拡大される傾向にあり,施設(術者の考えや技量)によって必ずしも統一されているとは言いがたいが,やみくもなEMRは避けるべきであり,まずは術前に病変を正確に診断してから切除に臨むべきと考える.
早期胃癌に対する腹腔鏡補助下幽門側胃切除術
著者: 白石憲男 , 安田一弘 , 猪股雅史 , 安達洋祐 , 北野正剛
ページ範囲:P.58 - P.60
はじめに
早期胃癌に対する腹腔鏡補助下幽門側胃切除術(LADG)は,内視鏡的粘膜切除(EMR)や腹腔鏡下胃局所切除術のようなリンパ節郭清を伴わない治療法と従来からの2群リンパ節郭清を伴う開腹下幽門側胃切除術の間に位置する術式として1991年に開発された1).1990年代の後半にはその有用性が認められるようになり,多くの施設で施行されている2).本稿では実際の症例を呈示しつつ,LADGの適応と切除範囲の決定について述べたい.
センチネルリンパ節生検を伴う腹腔鏡下胃局所切除術
著者: 北川雄光 , 久保田哲朗 , 大谷吉秀 , 古川俊治 , 吉田昌 , 藤井博史 , 久保敦司 , 向井萬起男 , 北島政樹
ページ範囲:P.61 - P.64
本術式の適応とその位置づけ
1990年以降,腹腔鏡下手術の登場で消化器癌の治療体系も少なからず変化を見せている.早期胃癌外科治療体系についてもいくつかのオプションが生まれてきている.腹腔鏡下手術が臨床応用される以前は,内視鏡的粘膜切除術(endoscopicmucosal resection:EMR)の適応からはずれる胃粘膜癌は開腹手術の適応となっていた.広範囲胃粘膜癌に対するEMRはおのずと分割切除となり,切除断端癌遺残の判定やリンパ節転移の危険を予測するうえで重要な深達度診断を正確に行うことが困難となるからである.教室では粘膜癌の確実な一括全層切除を目的として,1992年から病変吊り上げ法による腹腔鏡下胃局所切除術(lesionlifting,大上法)1)を開発し,施行してきた.教室における粘膜癌リンパ節転移状況の詳細な検討から適応基準を設定してきた.また,教室では大上法による腹腔鏡下局所切除が困難な部位の病変については,大橋らが開発した腹腔鏡下胃内手術を施行してきた.一方,近年の技術革新によりEMRにおいて一括切除可能な範囲も拡大する傾向にあり,腹腔鏡下低侵襲手術とEMRの適応が次第にオーバーラップすることが指摘されてきた.この両者の適応はリンパ節転移陰性例に限定するという点では基本的に共通である.
IELMを用いた早期胃癌の神経温存縮小手術
著者: 木南伸一 , 三輪晃一 , 萱原正都
ページ範囲:P.65 - P.72
はじめに
これまで深達度Mで2〜5%,SMで15〜25%の頻度にリンパ節転移が認められることから,早期胃癌の標準治療はD2胃切除とされてきた1).D2では胃への主要脈管の多くが郭清操作に伴って切断されるので,胃切除範囲は幽門側胃切除・噴門側胃切除・胃全摘となり,3分の2以上の胃が切除されるのが通常である.かかる切除では術後に胃切除後症候群で総称される術後障害が生じ,郭清に伴う自律神経損傷が生じる.一方,早期胃癌の大部分は転移を認めず,転移陰性症例にはD2の手術侵襲と術後障害はデメリットとなる.
筆者らは1991年D2の根治性を維持し,自律神経機能を保持する迷走神経温存リンパ節郭清術(vagus-saving D2:以下,VS-D2)を開発した2).この術式の考案には早期胃癌のリンパ節転移を術中に診断することが困難であった背景があった.この術式は胃切除後患者の胆石発生,下痢,体重低下,膵臓内分泌不全3)などの障害をよく防止し,神経温存に意義のあることが実証された4).
進行胃癌に対する幽門保存胃切除術
著者: 野村幸世 , 清水伸幸 , 山口浩和 , 比企直樹 , 下山省二 , 真船健一 , 上西紀夫
ページ範囲:P.73 - P.76
はじめに
幽門保存胃切除術は1960年代にMakiらにより胃潰瘍に対する治療法として開発された術式である1).これには迷走神経を保存するか否かについては記載がないが,幽門機能が温存されるため,術後の十二指腸液の胃内逆流が予防でき,残胃炎が少なく,また,ダンピング症候群が少ないことが報告されている2〜4).1990年代になり,わが国においてM領域の早期癌に対して幽門保存胃切除術が行われるようになった5).迷走神経を温存することにより,よりよい術後の胃機能が報告されており,また,リンパ節郭清に関してもさまざまな工夫によりほぼ完全なD2郭清が行われるようになってきた6).
当科では,1993年から幽門輪から4.5cm以上離れた癌で,口側残胃が術前の胃の1/5以上残存可能な早期癌に対し幽門保存胃切除術を行ってきた.郭清度はM癌に対してはD1郭清を,SM癌に対してはD2郭清を行っている.当科における術式では迷走神経は肝枝は温存するが,幽門枝はNo.5リンパ節郭清のために右胃動脈は根部にて処理しており,あえて温存はしていない.No.6リンパ節は幽門下動脈を温存する形で郭清している.1993年から1999年に48例の幽門保存胃切除術を施行したが,全例無再発生存中である.
進行胃癌に対する(標準的)胃全摘術
著者: 片井均
ページ範囲:P.77 - P.81
はじめに
進行胃癌に対する標準的胃全摘術をここでは開胸を伴わない胃全摘(D2),膵温存手術とした1).脾門,脾動脈幹周囲リンパ節の完全郭清を目的とした膵脾合併切除の治療効果は確立していない.
進行胃癌に対するNo.16リンパ節郭清術
著者: 梨本篤 , 藪崎裕 , 田中乙雄
ページ範囲:P.82 - P.86
はじめに
胃幽門狭窄を呈し,腹部大動脈周囲(No.16)リンパ節転移を認めた高度進行胃癌症例を経験したので,術前診断とその治療戦略について検討した.No.16リンパ節は左腎静脈の下縁でa,bに分類されている(図1).さらにNo.16aを腹腔動脈根部の高さでa1とa2に分け,No.16bを下腸間膜動脈根部の高さでb1とb2に分けている.また,周在性により7領域に分類されている.なお,化学療法の効果および胃癌に関する記載は「胃癌取扱い規約(第13版)1)」に準じた.
進行胃癌に対する隣接臓器合併切除術
著者: 稲田高男 , 太田茂安 , 清水芳政 , 角辻格 , 尾形佳郎
ページ範囲:P.87 - P.91
はじめに
進行胃癌症例において,合併切除される隣接臓器としては横行結腸,膵,脾,横隔膜などが上げられる.隣接臓器の合併切除はリンパ節郭清の徹底のために膵や脾の合併切除が行われる場合と腫瘍の直接浸潤のために切除を行う場合がある.筆者らの施設における1986年から2000年末までの胃癌切除例1,489例中,隣接臓器への直接浸潤陽性(SI)と診断された症例は123例(8.3%)であり,直接浸潤臓器は延べで見ると,図1に示したように膵臓54例(38.9%)と横行結腸間膜42例(30.2%),横行結腸11例(7.9%)であり,この3臓器で大部分を占めている(図1).この3臓器に限定して癌占居部位と浸潤臓器の関係を見てみると,横行結腸および結腸間膜浸潤は中部あるいは下部病変がほとんどであり,また膵浸潤は膵浸潤の部位との関係もあるが,上部あるいは下部胃癌で浸潤が多いことがうかがわれる(表).したがって,術前検査において他臓器浸潤が診断されない症例においても,進行胃癌においては占居部位によって浸潤臓器の推定を行っておく必要がある.また合併切除の適応としては基本的に合併切除によって根治性が確保される症例である.
ここに呈示する症例は術前診断において膵への直接浸潤陽性と診断され,膵および一部の横隔膜を合併切除した進行胃癌症例である.
残胃進行癌に対する拡大残胃切除術
著者: 荒井邦佳 , 岩崎善毅 , 高橋俊雄
ページ範囲:P.93 - P.96
はじめに
残胃癌の手術は数ある胃癌手術の中で最も難しい手術である.術者になるためには胃癌手術の経験が豊富であることはもちろんであるが,肝,膵,結腸の合併切除,あるいはアプローチ法などにおいて様々な応用手技が要求される.
Ⅲ.十二指腸乳頭部癌・小腸悪性腫瘍
十二指腸乳頭部癌に対する内視鏡的乳頭切除術
著者: 伊藤彰浩 , 後藤秀実 , 廣岡芳樹 , 橋本千樹 , 丹羽克司 , 石川英樹 , 岡田直人 , 早川哲夫
ページ範囲:P.98 - P.103
はじめに
十二指腸乳頭部腫瘍に対する内視鏡的乳頭切除術は未だ広く普及した治療法ではない.初期には手術困難な進行癌症例に対する姑息的治療1)として報告され,近年では腺腫例2,3)に対する治療として散見されるようになったが,腺腫例に対してですら未だ外科的切除が第一選択されることが多いようである.消化管における粘膜切除術(EMR)と同等の評価を受けない理由は技術面と診断面に問題があると考えられる.すなわち,胆膵管の開口部であるという解剖学的特徴による安全性の確立の不十分性,そして,従来の診断学では早期癌の診断や腫瘍の胆膵管内進展の詳細な診断が困難であるため,その適応決定が不十分であることが主たる原因であろう.乳頭部領域においては管腔内超音波検査法(intraductal ultrasono-graphy:IDUS)により診断能が向上し,早期癌の診断も得られるようになった4,5),筆者らは内視鏡的切除の適応を腺腫および早期癌とし,十分なインフォームドコンセントのもと施行している.以下に,内視鏡的乳頭切除例を供覧する.
十二指腸乳頭部癌に対する膵頭十二指腸切除術
著者: 上野富雄 , 岡正朗
ページ範囲:P.104 - P.108
はじめに
十二指腸乳頭部癌と術前に確診しえた症例は,現在では“幽門輪温存膵頭十二指腸切除術”が標準術式としてほとんどの施設で適応とされている.乳頭部癌に対して胃切除を伴う従来の膵頭十二指腸切除術(以下,Whipple手術)が施行されるような症例は,同時性重複胃癌の患者を除くと,癌の局所進展やリンパ節転移のために十二指腸球部が温存できずに胃の合併切除をせざるをえなくなった場合や,乳頭部癌が強く疑われるものの,なおかつ膵頭部膵管癌との鑑別が困難な場合などであろう.
十二指腸乳頭部癌に対する幽門温存膵頭十二指腸切除術
著者: 土屋誉 , 松本岳 , 生澤史江 , 赤石敏 , 本多博 , 内藤剛 , 山本久仁治 , 小久保弘晶 , 白石振一郎 , 杉山慎一郎 , 伊藤啓 , 藤田直孝 , 小針雅男
ページ範囲:P.109 - P.113
はじめに
幽門温存膵頭十二指腸切除(pylorus preservingpancreaticoduodenectomy:PpPD)は1978年Traversoらによって報告され1),現在では術後早期の胃排出の遅延などの問題があるものの長期的にみれば食事摂取量も通常のPDに比べて多いため,多くの施設で膵頭部領域癌に対する縮小手術の1つとして行われている術式である.
本稿では術前,内視鏡にて予後良好な非潰瘍形成型に分類され,超音波内視鏡(EUS),管腔内超音波検査(IDUS)により膵,十二指腸浸潤がないT1の乳頭部癌と診断され,PpPDを行った症例を供覧する.
小腸悪性腫瘍に対する回盲部切除,小腸区域切除術
著者: 橋口陽二郎 , 望月英隆
ページ範囲:P.115 - P.120
はじめに
小腸悪性腫瘍は比較的稀であり,全消化管悪性腫瘍の0.3〜4.9%を占めるとされている1,2).本邦では悪性リンパ腫,癌,平滑筋肉腫,カルチノイドの順に頻度が高く,比較的男性に多い.部位的に診断が困難なため偶然発見されるか,症状が出現するような進行した病態で発見されることが多い.本稿では小腸腫瘍の中で最も頻度が高く,典型的と思われる回腸末端部付近に発生した悪性リンパ腫について,典型例と周辺臓器合併切除を伴う高度進行症例を呈示する.また,特殊例として消化管出血にて緊急手術を施行された小腸平滑筋肉腫の1例を示す.
Ⅳ.結腸癌
早期結腸癌に対する内視鏡的粘膜切除術
著者: 横山正 , 伊藤治 , 菊池学 , 横山功 , 横山泰久 , 渡辺聡明 , 名川弘一
ページ範囲:P.122 - P.126
はじめに
癌の治療体系において個々の症例の進展度に応じた治療が求められる一方,経済的観点や患者さんの負担の軽減から必要十分な手術前検査を選択することが重要となってきた.
早期結腸癌の内視鏡的切除の適応決定のための面像検査法として注腸X線,通常内視鏡,色素内視鏡,拡大内視鏡,超音波内視鏡,場合によってはCT,MRIまでも挙げられる.しかし,一般臨床においては通常および色素内視鏡下での適応決定がほとんどであり,本稿でも内視鏡所見を中心に記述する.
結腸癌に対する腹腔鏡下切除術
著者: 長谷川博俊 , 渡邊昌彦 , 北島政樹
ページ範囲:P.127 - P.130
はじめに
日本大腸肛門病学会外科系評議員に行った大腸癌に対する腹腔鏡下切除術の適応に関するアンケート調査によると1),現時点では早期癌に対しては標準術式として認知されており,さらに5年以内にMP'癌まで適応となるであろうとしている.SS'・SE'に対する腹腔鏡下手術は早期癌,MP癌で技術的に習熟してから施行すべきで,長期予後が出るまでは慎重に経過観察を行う必要がある.
結腸癌に対する腹腔鏡下切除術の切除範囲は基本的には開腹術と同じである,筆者らはリンパ節郭清範囲を早期癌ではD1+α,MP'癌ではD2,SS'・SE'癌ではD3としている.しかし,小切開創から病変部腸管を露出し,緊張なく切除・吻合を行うためには,剥離・授動は開腹術に比べて広めに行う必要がある.早期癌では直腸やS状結腸下部の腫瘍を除いて血管処理は腹腔内で行わず,体外で血管処理と腸管切除を行い,機能的端々吻合(functional end to end anastomois:FETE)を行っている.実際の症例を供覧する.術中体位の取り方や,手術手技の詳細については他誌を参照されたい2,3).
皮切部位を考慮した吊り上げ式ハンドアシスト腹腔鏡下腸切除術—HALS
著者: 亀山雅男 , 藤戸努 , 村田幸平 , 横山茂和 , 山田晃正 , 宮代勲 , 土岐祐一郎 , 大東弘明 , 平塚正弘 , 佐々木洋 , 石川治 , 今岡真義
ページ範囲:P.131 - P.134
はじめに
最近,早期癌に対する腹腔鏡補助下腸切除が盛んに行われるようになってきた.ところが,D3郭清を伴う進行癌の場合,かなりトレーニングを積まないと安全にできないという問題点もある.さらに,長時間気腹されることによる心肺機能への影響やport site recurrenceが懸念される.したがって,大血管周囲まで手術侵襲が及ぶ進行癌に対しては,大半の施設において未だに切開創を長くした標準的な開腹手術を行っているのが現状である.
このような背景から,筆者らは進行した大腸癌に対してもリンパ節郭清を安全かつ迅速に行えるように,左手を挿入できる最小限の切開創と腹腔鏡との併用による吊り上げ式のHALSを開発した(図1).結腸癌に対する手術は基本的に栄養血管の根部結紮と腸管の授動の2つに分かれる.そこで本術式では栄養血管の根部郭清をmini-laparo-tomyで行い,腸管の授動を腹腔鏡補助下で行うように考案した.Surgical trunkあるいは下腸間膜動脈といった中枢側のD3郭清を,正中創の直視下に行うことができれば安心できるし,何か起こってもすぐ対応できるというメリットがある.さらに,切開創が正中にあることは疼痛の緩和というメリットもあわせて持っている.
右側結腸癌に対する結腸右半切除術
著者: 亀岡信悟 , 小川真平
ページ範囲:P.135 - P.139
はじめに
右側結腸癌の術式および切除範囲は占居部位,組織型,壁深達度,リンパ節転移程度および,肝転移,腹膜播種性転移の有無などの腫瘍の臨床病理学的因子に加え,患者の背景因子(年齢,合併症の有無など)によって決定される.これらの術前評価は注腸,下部消化管内視鏡,超音波およびCTなどの画像診断から総合的に行われ,それらの診断法に熟知することが重要である.各施設によって術式選択の基準は様々であるが,筆者らは原則として結腸右半切除術の適応を表のようにしており,特に,ヘリカルCTによる壁深達度やリンパ節転移程度の診断を重視して術式を決定をしている.本稿ではこれらを中心に,結腸右半切除術を行った症例を呈示し,診断および切除範囲決定のポイントについて解説する.
左側結腸癌に対する左半結腸切除術
著者: 三木誓雄 , 小林美奈子 , 楠正人
ページ範囲:P.140 - P.143
はじめに
左側進行結腸癌に対する左半結腸切除は横行結腸の左半分,下行結腸,S状結腸を切除し,横行結腸と直腸を吻合するものである.この術式では腫瘍占拠部位が脾轡曲部,S-D junctionのどちらに近接しているか,あるいはリンパ節転移があるかないかなどにより腸管切除範囲,リンパ節郭清の程度は適宜縮小される.すなわち他の部位の結腸手術に比べ術前の画像診断,術中の正確な病期の評価で血管処理の部位や切除範囲など,手術操作が細かく変更される可能性があると言える.本稿では,術前・術中の画像診断を駆使した下行結腸癌に対するhand-assisted腹腔鏡補助下左半結腸切除術を,実際の症例を基に紹介する.
S状結腸癌に対するS状結腸切除術
著者: 加藤健志 , 吉川宣輝 , 木村豊
ページ範囲:P.144 - P.148
はじめに
癌治療の3大原則は安全性,根治性,機能性であるが,特に大腸癌の場合,患者個々の背景(グレード)に合わせた治療方法を選択する必要がある1).そのための第1歩として的確な術前診断と術前評価を行うことが重要である。本稿では,S状結腸癌に対するS状結腸切除術の治療方法の選択と,術前検査のポイントについて,典型症例を画像供覧し,考察を加える.
進行結腸癌に対する隣接臓器合併切除術
著者: 柳秀憲 , 山村武平 , 野田雅史 , 池内浩基 , 吉川麗月
ページ範囲:P.149 - P.152
はじめに
進行結腸癌の予後決定因子は遠隔転移と腹膜播種が主なものであり,他臓器浸潤結腸癌では併発する同時性遠隔転移が予後決定因子となることが多く,隣接他臓器浸潤単独で予後決定因子となることは比較的稀である.
また,結腸癌原発巣の局在部位により,浸潤しうる隣接臓器が異なるために当然治療方針も異なる.このため,本稿では同時性遠隔転移を認めない症例について,結腸癌局在部位別に術前画像診断,ストラテジーを概説する.
完全閉塞を伴う結腸癌に対する一期的手術
著者: 河村裕 , 小西文雄
ページ範囲:P.153 - P.158
症例
症例は54歳,男性.開腹手術歴なし.3日前から出現した腹部膨満,排便・排ガスの停止および嘔吐のため受診した.身体所見上著明な腹部膨満を認めた.腹部に圧痛はなく,腫瘤を触知しなかった.直腸指診でも腫瘤は触知しなかった.
腸閉塞が疑われ,直ちに腹部単純X線写真を撮影した.臥位の写真では多数の高度に拡張した小腸ループが認められ,立位の写真ではこれら小腸ループが鏡面像を形成していた(図1,2).大腸ガスは目立たず,左側結腸内に便が認められた.以上から,遠位小腸ないし大腸の閉塞と診断した.腹部所見からは絞扼はないと考えられた.原因診断とともに絶食・補液および減圧が必要であり,入院加療とした.
結腸癌穿孔例の緊急手術と人工肛門造設術
著者: 丸田守人 , 前田耕太郎 , 内海俊明 , 滝沢健次郎 , 佐藤美信 , 升森宏次 , 青山浩幸 , 千田憲一 , 勝野秀稔
ページ範囲:P.159 - P.163
はじめに
消化管穿孔と診断されると穿孔性腹膜炎を治療することが第一の目的となる.腹膜炎に対しては可及的汚染の除去,腹腔内洗浄,良好なドレナージを行い,原因となっている穿孔部位に対しては術前の患者の状態を考慮して,穿孔部を単に閉鎖するか,穿孔部を腹腔外に留置するか,原因となっている穿孔部位を切除して断端を両側あるいは口側のみ消化管瘻とするか,切除して断端を吻合するか,切除して吻合し,さらに口側に一時的人工肛門造設するかなどさまざまな術式がとれる,最も大切なことは緊急手術であるから,患者を救命することであって,穿孔部位をどうするかはあくまで二の次である。消化管穿孔の中で,結腸癌による穿孔はその頻度は必ずしも高くない.穿孔の頻度は医療施設の置かれている状況により結腸癌全体の1.1%から7.8%とさまざまであり1,2),はっきりした統計が出ていない.同様に緊急手術の術式として何が一番良いかを決めることも難しい.
Ⅴ.直腸癌・肛門管癌
早期直腸癌に対する内視鏡的粘膜切除術,経肛門的局所切除術
著者: 荒木靖三 , 白水和雄
ページ範囲:P.166 - P.168
はじめに
早期直腸癌に対する治療は局所切除とリンパ節郭清を伴う直腸切除が行われる.sm直腸癌のリンパ節転移の頻度は10%あまりで1,2),リンパ節転移の危険因子は「大腸癌取扱い規約」3)では,①明らかな脈管内浸潤陽性,②低分化あるいは未分化癌,③粘膜下浸潤が深い浸潤のうち1項目以上を有するものとしている.しかしながら,実際にはこれらのうち癌の分化度と壁深達度以外は術前診断困難な因子であり,低分化あるいは未分化癌以外の癌でmassiveな粘膜下浸潤のない早期癌症例が局所切除の適応と考えられる.したがって,局所切除術後に原発巣から十分な病理学的診断を行える診断と治療を兼ねた切除方法が要求される.また,腫瘍の局在部位や大きさによって治療方法は選択される.
本稿では早期直腸癌に対する内視鏡的粘膜切除術(EMR)4,5),経肛門的腫瘍切除術6),TEM7〜9)の適応と方法について解説する.
直腸癌に対する自律神経温存手術
著者: 山口高史 , 森谷宜皓 , 赤須孝之 , 藤田伸
ページ範囲:P.169 - P.175
はじめに
今日,癌の外科手術において根治性はもちろんのこと機能温存の要求が高くなってきた.直腸癌術式に関しては自律神経温存術が括約筋温存術とともにきわめて重要な位置を占めるようになった.かつての拡大郭清1)は高度局所進展癌に対してのみ採用され,進行直腸癌に対しても郭清を伴う自律神経温存術が標準術式となり,適応を誤らなければ根治性に問題はない2).しかし神経温存術式の分類と適応に関する意見の統一は未だなく,施設間でかなりの相違がある.ここでは筆者らの分類を紹介し,実際の症例を呈示してそれぞれの術式の適応を考察する.
直腸癌に対する低位前方切除術
著者: 森田隆幸 , 村田暁彦 , 小山基 , 丸山将輝 , 木村典央 , 佐々木睦男
ページ範囲:P.177 - P.182
はじめに
直腸癌手術の標準術式として低位前方切除術が普及してきている.本術式を行う場合,個々の症例ごとに組織型,壁深達度,リンパ節転移の有無などを検討しながら手術計画を立てなければならない.肛門括約筋温存手術か,直腸切断術か,その適応選択に迷う下部直腸癌については他誌に譲り,本稿では最も普遍的に低位前方切除術が適応されるRa直腸癌の症例を中心に,これらの問題を含め概説したい.
直腸癌に対する超低位前方切除術—結腸嚢肛門吻合術
著者: 須田武保 , 畠山勝義 , 加納恒久 , 谷達夫 , 飯合恒夫 , 岡本春彦
ページ範囲:P.183 - P.186
はじめに
直腸癌の術後QOLを高めるために,歯状線に近い下部直腸癌に対して超低位前方切除術が選択され,その再建には結腸嚢肛門吻合が行われている.ここでは本術式が行われた典型例を供覧するとともに,その適応について述べる.
直腸癌,肛門癌に対する腹会陰式直腸切断術
著者: 林哲二 , 榎本雅之 , 杉原健一
ページ範囲:P.187 - P.189
はじめに
筆者らの腹会陰式直腸切断術(Miles手術)の適応は肛門挙筋,外括約筋に対し2cmのsurgicalmarginが確保できない症例,すなわち肛門縁から腫瘍下縁までの距離が4cm以下のMP以深症例である.ただし,膀胱または前立腺に浸潤を認めれば骨盤内臓全摘術の適応になる場合がある.肛門管あるいは肛門に浸潤している腫瘍は直腸切断術の適応ではあるが,例外として扁平上皮癌では化学放射線治療が第一選択となる.
進行直腸癌に対する骨盤内臓器全摘術
著者: 池秀之 , 大木繁男 , 藤井正一 , 山口茂樹 , 岩田誠一郎 , 今田敏夫 , 嶋田紘
ページ範囲:P.190 - P.194
症例
患者:69歳,男性
主訴:血便
Ⅵ.肝癌
肝細胞癌に対する系統的区域・亜区域切除術
著者: 菅原寧彦 , 今村宏 , 伊地知正賢 , 國土典宏 , 幕内雅敏
ページ範囲:P.196 - P.202
はじめに
肝細胞癌では高頻度に腫瘍が門脈内に浸潤し,経門脈性に肝内転移巣を形成する.事実,腫瘍の門脈浸潤や肝内転移巣の有無は,これまでの報告に一貫して共通した予後不良因子として挙げられている.理論的にはこれらの因子による再発を防ぐためには,腫瘍に向かう門脈によって灌流される領域を系統的に切除するという解剖学的切除が必要となる.一方で肝細胞癌のほとんどの症例が背景に慢性肝炎や肝硬変を有しているために,肝予備能の面からはむやみな広範囲切除は適応できない場合が多い.こうした事がらを背景に,限られた肝機能条件内での解剖学的切除によって潜在的微小病巣を含めた腫瘍の切除を目的として考案されたのが,系統的亜区域切除術である1).肝細胞癌における系統的亜区域切除術を含む適応術式の選択は,肝機能条件と腫瘤条件とのバランスによる.
肝機能条件からみた許容切除量については,筆者らは図12)に示したフローチャートに従って決定しており,過去8年間の500例以上の肝細胞癌肝切除症例で術死を経験していない.系統的亜区域切除術はほぼ全肝の6分の1切除に相当し,腫瘍条件として,その進展範囲が切除する亜区域以内に限局していることが前提となり,通常は主腫瘍径が5cm程度までの肝癌に適応となる.また肝予備能からは区域切除以上が可能であるような症例でも,腫瘍の大きさや位置からは亜区域切除で十分と考えられるものに対しては亜区域切除が適応となる.
肝細胞癌に対する肝左葉切除術
著者: 矢永勝彦 , 兼松隆之
ページ範囲:P.203 - P.207
はじめに
肝左葉はCantlie線の左側で,外側区域(S2,S3)と内側区域(S4)から構成され,肝全体の約35%を占める.栄養血管は門脈左枝と左・中肝動脈であり,肝動脈奇形は左胃動脈由来の左肝動脈が約17%の頻度でみられるが,門脈左枝の奇形はまれである.灌流静脈は左肝静脈と中肝静脈の左側である.胆管系はb2,b3,b4がいろいろな形で合流して左肝管となり,これが右肝管と合流するが,ときに後区域肝管が左肝管に合流することがある.本稿では肝細胞癌に対する肝左葉切除術の適応につき,症例を提示しながら述べる.
肝細胞癌に対する左3区域切除術
著者: 宮川眞一 , 川崎誠治
ページ範囲:P.208 - P.210
はじめに
肝腫瘍に対する切除術式は3つの因子,すなわちその術式により肉眼的治癒切除が期待できること,残存予定の肝容積により生体に必要な肝臓の代謝,解毒機能が維持できること,残存予定肝における流入血管,流出血管,胆道系が温存可能かどうかにより決定される.
本稿では,肝細胞癌に対する左3区域切除術の術式の選択と切除範囲の決定について実際の症例を呈示しながら述べる.
グリソン鞘前,後枝に隣接した肝癌に対する門脈枝塞栓術を併用した肝右葉切除術
著者: 寺本研一 , 川村徹 , 中村典明 , 岡本浩之 , 神代祐至 , 真田貴弘 , 有井滋樹
ページ範囲:P.211 - P.214
はじめに
症例は慢性肝炎を併存する肝細胞癌患者である,腫瘍の位置が肝門部に近いので系統的切除施行のためには広範囲な肝切除を余儀なくされる.この症例に対して術後肝不全を避けるため,担癌領域を萎縮させ残存肝を肥大させる門脈枝塞栓術を先行したのち,肝右葉切除を施行した.画像を中心に本症例の肝切除の考え方を呈示する.
肝細胞癌に対する右3区域切除術
著者: 大坪毅人 , 高崎健 , 吉利賢治
ページ範囲:P.215 - P.219
はじめに
「原発性肝癌取扱い規約」(第4版)では,肝は5つの区域(外側区域,内側区域,前区域,後区域,尾状葉)に分類され,右3区域切除は後区域,前区域,内側区域を切除する術式で,Hr3(P,A,M)と記載される1).ここで注意すべき点は同じHr3であっても右3区域切除と左3区域切除では切除量が異なることである.
高崎2)のグリソン鞘の分岐に従った区域分けでは,尾状領域を除く肝は右区域,中区域,左区域の3本の区域枝(グリソン鞘2次分枝)それぞれの分布する区域に分けられる.右3区域切除では右区域枝および中区域枝と左区域枝のうち内側に分岐する何本かの3次分枝を切断する切除で,正常肝では肝の約75%前後の切除である(図1).左3区域切除では左区域枝と中区域枝を切断する切除で,正常肝では肝の約60%前後の切除となる3,4).
肝細胞癌に対する腹腔鏡補助下肝部分切除術
著者: 山中若樹 , 安井智明 , 北山佳弘 , 光信正夫 , 林勝彦 , 芝卓弥
ページ範囲:P.220 - P.223
はじめに
近年における消化器外科診療のブレイクスルーは低侵襲的治療,患者のQOL重視に向けた鏡視下手術の導入であろう.胆嚢摘出術に始まり,消化器領域では胃・大腸癌の早期病変,食道癌の胸部食道遊離操作,肝癌治療にまで適用されるに及んでいる.
筆者らも1992年初頭に胆嚢摘出術を開始して以来,胆嚢包ドーム切除術1),原発性2)あるいは転移性肝癌3)に対するマイクロ波凝固壊死療法(MCT),また肝切除術4,5)にも適用を拡大してきた.経験を重ねると悪性疾患に対する鏡視下手術の適応は厳格にすべきものであって,時代の趨勢に流されてむやみやたらに適用を拡大すべきものではないことがわかってきたが,この手技を身に付けておくと患者のQOL上大きな利益が得られることも事実である.1992年の報告に始まった鏡視下肝切除6)もそのひとつである.切除範囲の決定につながる画像診断の読み方が特集の目的であるが,鏡視下切除の対象は表在する小結節型腫瘍に限定されているので,本稿では鏡視下(補助下)肝切除術の適応と手技を中心に述べる.
下大静脈浸潤を伴う肝癌に対する肝切除術
著者: 神山俊哉 , 松下通明 , 伊藤東一 , 倉内宣明 , 嶋村剛 , 古川博之 , 藤堂省
ページ範囲:P.224 - P.228
はじめに
下大静脈内腫瘍栓,あるいは下大静脈浸潤を伴う肝細胞癌は切除適応が限られていたが,今日では血管外科の応用,肝移植に用いられる手術テクニックの導入によってその適応も広がりつつある.
Ⅶ.胆管癌・胆嚢癌
肝門部胆管癌に対する肝門部切除術
著者: 安藤秀明 , 伊勢憲人 , 安井應紀 , 柴田聡 , 佐藤勤 , 小山研二
ページ範囲:P.230 - P.234
はじめに
肝門部胆管癌はその解剖学的特性から根治切除率が少なく治療に難渋する場合が多い.近年,肝切除を併用した拡大切除により切除率は向上してきている.癌治療の基本として,根治切除なくして治癒はありえないが,肝門部胆管癌では根治切除を目指した場合は手術侵襲が過大となり予後不良になる場合もある.高度進行胆管癌では,根治切除のため肝移植を行った報告もあるが,その予後は不良であった.したがって,肝門部胆管癌では,ただ癌の根治切除を目指した拡大手術を行うのではなくその進行度に応じた適切な手術を行うことが必要である1).
当科では,肝門部胆管癌の基本術式として肝門部切除を行い,一側胆管切離縁にのみ癌遺残のある場合に肝切除を付加するという治療方針にしている.胆管癌進展は最終的に術中迅速診断で決定している.本稿では術前画像診断所見と手術所見での癌進展の実際を提示し,肝門部胆管癌の治療方針の考え方を示す.
肝門部胆管癌に対する尾状葉切除術
著者: 野口孝 , 山際健太郎 , 川原田嘉文
ページ範囲:P.235 - P.241
はじめに
近年,肝門部胆管近傍の詳細な解剖学的研究1,2)と各種画像診断の進歩により3),術前に肝門部胆管癌の尾状葉浸潤が診断可能となり,本疾患の根治手術において尾状葉合併切除はすでに標準術式として定着してきた.したがって肝門部胆管癌の手術の際には進展度診断のみならず手術操作の立場からも,肝のplate systemと尾状葉の解剖を十分に理解してwork upすることがkey pointである.肝門部胆管癌尾状葉浸潤の代表的な症例を画像所見と病理所見を用いて呈示する.
肝門部胆管癌に対する肝右3区域切除術
著者: 上坂克彦 , 神谷順一 , 梛野正人 , 新井利幸 , 湯浅典博 , 小田高司 , 二村雄次
ページ範囲:P.242 - P.245
はじめに
尾状葉切除を伴う肝右3区域切除術は,肝門部胆管癌のなかでは最も大量の肝を切除する術式の1つである.本術式は肝切離面が小さいものの,本術式を要する症例はかなり広範囲に進展した癌であることが多く,大量肝切除であるがゆえに術後肝不全を惹起する危険性も高いといった特徴を有している.以下,本稿では肝右3区域切除術を必要とする画像の特徴について解説する.
胆管癌に対する門脈合併切除術
著者: 近藤哲 , 加藤紘之 , 平野聡 , 安保義恭 , 田中栄一 , 奥芝俊一 , 川端真
ページ範囲:P.246 - P.250
はじめに
胆管癌で門脈合併切除が必要になる場合は,ほとんどが肝門部胆管癌である,肝門部の胆管は門脈に隣接しており,癌浸潤が胆管の線維筋層を越えると容易に門脈壁に浸潤する.根治切除例の20〜30%に門脈合併切除が施行されている1).
本稿では,広範囲に進展した進行肝門部胆管癌に対して術前に右3区域の門脈枝塞栓術2)を施行後,肝右3区域・尾状葉切除,胆管切除,門脈合併切除を施行し右外腸骨静脈グラフト間置により門脈再建を行った症例を呈示する.
胆嚢癌に対する肝床切除術
著者: 白石祐之 , 野村寛徳 , 伊佐勉 , 砂川亨 , 武藤良弘
ページ範囲:P.251 - P.254
はじめに
進行胆嚢癌に対する切除術式のうち,漿膜下浸潤(ss)胆嚢癌に対しては,胆嚢壁から2〜3cmの肝実質を切除する肝床切除術+3群リンパ節郭清を標準術式とする報告が多い1〜3).また,SSでも肝十二指腸間膜浸潤・肝門側進展が疑われる症例や,漿膜側浸潤の明らかな症例(se),肝実質浸潤がある症例(hinf 1b以上)に対しては,肝外胆管切除や膵頭十二指腸切除の付加,系統的肝切除術式(S4a+S5切除,肝右葉切除)などを選択する必要もでてくる.したがって進行胆嚢癌に対する術式決定には,深達度ss・hinf 1a(固有筋層を越えるが肝実質には達しない)までの症例とse・hinf 1b以上の症例を鑑別することが望ましい.これらの点をふまえ,本稿では漿膜側壁深達度および肝浸潤の術前診断に関して画像所見を供覧する.
胆嚢癌に対する胆嚢・S4a5肝区域切除術
著者: 田代征記 , 三宅秀則 , 安藤勤
ページ範囲:P.255 - P.259
はじめに
胆嚢癌に対する胆嚢・S4a5肝区域切除における正確な肝切除範囲をいかに決定して,切除しているかを中心に述べてみたい.
Ⅷ.膵癌
膵頭部癌に対する膵頭十二指腸切除術
著者: 山内淳一郎 , 渋谷和彦 , 江川新一 , 元井冬彦 , 砂村眞琴 , 武田和憲 , 松野正紀
ページ範囲:P.262 - P.266
膵頭十二指腸切除術における術前画像診断の意義
膵癌に対する外科的治療において,長期生存を得るための必要条件は治癒切除を行うことである.したがって,術前の画像診断では治癒切除の可能性を正確に判断することが肝要となる.とくに膵頭部癌では神経叢を含めた膵後方への浸潤,門脈,上腸間膜動脈,総肝動脈などの主要動脈への浸潤が治癒切除の可否を規定する.さらに膵癌全国登録調査結果から判断すると,「膵癌取扱い規約」による肉眼的Stage分類の後方被膜浸潤(RP),前方被膜浸潤(S),リンパ節転移(N)において,RP0,RP1,S0,S1,そしてN0,N1は外科切除術により予後の改善が期待できる1).効果が期待できない症例に対する不必要な拡大手術を回避し,合理的な手術術式を選択するためにも各種画像による術前進展度診断は重要である.
膵頭部癌に対する全胃温存膵頭十二指腸切除術
著者: 天野穂高 , 高田忠敬
ページ範囲:P.267 - P.271
はじめに
全胃幽門輪温存膵頭十二指腸切除術1,2)(PPPD:pylorus preserving pancreatoduodenecto-my)の導入当初は良性疾患を対象に施行されていたが,次第に十二指腸乳頭部癌や胆管癌などの悪性腫瘍にも応用されるようになってきた.また膵頭部癌にも適応しうる術式であることが明らかとなり3),1999年度症例の膵癌全国登録調査報告では,PDの213例に対し,PPPDは158例に施行されている.PPPDでは胃が温存されていることにより,十分な食事摂取が可能であり,術後のQOL改善に有利である.以下にその適応および要点を,症例を呈示しながら述べた.
膵癌に対する膵体尾部切除術
著者: 江上寛 , 廣田昌彦 , 小川道雄
ページ範囲:P.272 - P.276
はじめに
膵体尾部癌はその解剖学的位置関係から臨床症状の発現が遅く,多くは無症状で経過する.このため発見される膵体尾部癌は進行したものが多く,切除不能となる症例が多い.
膵体尾部切除術は膵体尾部に限局した膵癌に対して行われる.膵体尾部に存在する癌であっても,その広がりによっては膵全摘術や血管合併切除を伴う拡大切除の適応となる.膵体尾部切除術の術式選択に際しては,術前画像診断により病巣の広がりを正確に把握し,その根治性を評価したうえで適応を決定する必要がある.
膵体部癌に対する拡大膵切除術と術中照射
著者: 平岡武久 , 金光敬一郎 , 辻龍也 , 高森哲史
ページ範囲:P.283 - P.288
はじめに
膵癌は頭部癌と膵体尾部癌として取り扱われ,膵体尾部癌に対しては,癌が体部または尾部に比較的限局していても一括して論じられてきた.その理由は膵体尾部切除として対処され,また「膵癌取扱い規約」でも一緒に論じられてきたことによると思われる.しかし,最近の画像診断の進歩により膵の体部または尾部に限局した癌を診断できるようになり,これらそれぞれの進展様式に応じた切除が合理的である.今後は,体部または尾部に限局した癌は,それぞれの膵切除範囲と郭清範囲を別個に論じていく必要がある.その点に鑑み,膵体部癌の手術について言及する.
Ⅸ.甲状腺・副甲状腺癌
甲状腺癌に対する甲状腺亜全摘術+頸部リンパ節郭清術
著者: 池田佳史 , 高見博 , 佐々木裕三 , 高山純一 , 栗原英子 , 菅重尚 , 新見正則 , 小平進
ページ範囲:P.290 - P.293
はじめに
甲状腺癌は,組織学的に濾胞上皮より発生する分化癌である乳頭癌,濾胞癌と未分化癌および傍濾胞細胞より発生する髄様癌に大別される。髄様癌は基本的には甲状腺全摘が適応であり,未分化癌は手術の対象になる症例はごくわずかである.そのため甲状腺切除,リンパ節郭清術が奏効するのは乳頭癌,濾胞癌などの分化癌である.
甲状腺乳頭癌は甲状腺癌の約80%を占める.10年生存率は90%以上でありきわめて予後のよい癌であるが,その治療については,甲状腺全摘術とそれに引き続く放射線ヨード(131I)治療および生涯にわたるTSH抑制療法を全症例に対して推奨する欧米式の考え1)と,症例によっては甲状腺の切除範囲を縮小して,追加治療も行わないでよいとする日本で発展した考え方がある.
甲状腺癌に対する甲状腺全摘術+両側頸部リンパ節郭清術
著者: 吉田明
ページ範囲:P.294 - P.299
はじめに
甲状腺癌は濾胞細胞由来である分化癌(乳頭癌,濾胞癌)ときわめて悪性度の高い未分化癌,傍濾胞細胞由来の髄様癌に分類される.頻度的には乳頭癌が圧倒的に多く全体の85%以上を占める.
甲状腺癌は細胞診などの検査により術前に組織型が判明していることが多く,それぞれの生物学的な特性を考慮して術式が選択される.甲状腺全摘術+両側頸部リンパ節郭清術は,癌の根治を目的として分化癌,髄様癌に行われるが,実際には進行した乳頭癌が対象となることが多い.また遺伝性の髄様癌は多中心性に発症し,しばしばリンパ節転移を伴うことからこの術式が標準的なものとなっている.未分化癌は,有効な治療がないのが現状であり,手術は一時的な局所コントロールとして意味を持つにすぎない.一方,発育が緩慢な分化癌の場合,たとえ遠隔転移が存在していても,局所のコントロールという意味や131I治療を目的として本術式が行われることもある.
甲状腺癌気管浸潤に対する気管合併甲状腺切除術
著者: 今井常夫 , 菊森豊根 , 舟橋啓臣 , 中尾昭公
ページ範囲:P.300 - P.304
はじめに
甲状腺癌気管浸潤例において気管合併甲状腺切除術の適応となるものは分化癌,なかでも乳頭癌が大部分を占める.甲状腺未分化癌はしばしば気管浸潤を伴うが,進行が速いため未分化癌と診断がつけば気管合併切除術の適応とはならない1).一方,甲状腺乳頭癌は進行が緩徐であるので遠隔転移があっても気道狭窄,気管内出血のコントロールのために気管合併切除術の適応となる場合がある.症例ごとに年齢や全身状態を考慮して甲状腺癌の進行速度を踏まえて,広がり診断を適切に行い,手術適応,切除範囲を決定する2).
副甲状腺癌に対する拡大根治手術
著者: 竹内義明 , 井口利仁 , 柳英清 , 野島洋樹 , 蓮岡英明
ページ範囲:P.305 - P.307
はじめに
副甲状腺癌の発生頻度は低くまれなものである1).
高頻度に局所再発を引き起こす2)ことから初回手術の術式により予後が大きく左右されるため,切除範囲の決定が重要である.
甲状腺癌に対する内視鏡補助下甲状腺切除+リンパ節郭清術
著者: 原尚人
ページ範囲:P.308 - P.312
症例
患者:25歳,女性
現病歴:1年前より頸部腫瘤を自覚し,他院の超音波検査で甲状腺腫瘍を指摘され,精査目的で来院された.来院時,甲状腺左葉に2cm径の気管に固定された硬い腫瘤を触知した.頸部リンパ節は触知せず.
Ⅹ.肺癌
早期肺癌に対する拡大区域切除術
著者: 坪田紀明
ページ範囲:P.314 - P.318
はじめに
小型肺癌になぜ葉切除とリンパ節郭清を行ってきたか? 言うまでもなく小型腫瘤のなかに早期でない癌がまぎれているからである1,2).摘出の時点で早期癌の保証があれば「margin確保による部分切除」も可能となるが,そのような保証,絶対の情報など有りえないので不測の状況に備えて葉切除とリンパ節郭清を行うことになる.しかしこの方針は小型肺癌に結果的に無駄に終わるリンパ節郭清と肺の過剰切除をもたらした.
肺癌に対する気管支形成術を伴う肺葉切除術
著者: 大野陽子 , 輿石義彦 , 呉屋朝幸
ページ範囲:P.319 - P.323
はじめに
気管支形成術は良性疾患や肺機能温存を目的としてPrince-Thomas1)によってはじめて報告された.その後,気管支鏡の普及や周術期の管理の向上により,現在では根治性と機能温存を両立させる標準術式として確立されつつある.今回は実際に症例を示しつつ気管支形成術の適応と手技について述べる.
進行肺癌における隣接臓器合併切除術
著者: 門田康正
ページ範囲:P.324 - P.328
はじめに
進行肺癌手術における合併切除臓器としては縦隔内大血管(腕頭静脈,上大静脈,大動脈),脊椎,心房,肋骨,横隔膜,パンコースト腫瘍における鎖上部組織などがあるが,その手術適応については種々の議論がある1〜5).T3症例,大血管切除例の予後は比較的よいが,脊椎浸潤例の予後は不良である.
腫瘍のこれらの臓器への直接浸潤による場合には手術適応になるが,遠隔転移またはリンパ節転移巣からの浸潤例では手術適応になりにくい.手術目的は①癌の根治,②対症療法,③将来起こる可能性の高い合併症の予防,などである.
肺癌に対する拡大リンパ節郭清術
著者: 菊池功次 , 中山光男 , 山畑健 , 細村幹夫 , 坂口大介 , 宮下起幸 , 保坂靖子
ページ範囲:P.329 - P.332
はじめに
原発性肺癌におけるリンパ節郭清は「肺癌取扱い規約」の手術記載で一定範囲の縦隔郭清が治癒切除の条件のひとつとされ,異なる施設であってもかなり統一された郭清が行われている.
本稿では原発性肺癌においてCTスキャンなどの画像所見から,通常のリンパ節郭清だけでなく拡大してリンパ節郭清を行った症例についてCTスキャンの所見を提示しながら報告する.
原発性肺癌に対する胸腔鏡下手術
著者: 加賀基知三 , 井上宏司
ページ範囲:P.333 - P.337
はじめに
現状において原発性肺癌に対する標準術式は,肺門・縦隔リンパ節郭清を含む肺葉切除である.近年,胸腔鏡下手術video assisted thoracoscopicsurgery(VATS)が行われ,より低侵襲な手術が求められるようになった.一方,手術侵襲を減じるには縮小手術もひとつの策である.縮小手術は切除範囲を縮小しつつも根治性を求める積極的縮小手術1)と,高齢や低肺機能のために手術の安全性を優先した消極的縮小手術がある.また,CT装置の普及により早い(小さい)時期の肺癌が発見される機会が急増した.腫瘍径が小さくなればなるほど術前の確定診断が困難となり,診断を目的とした胸腔鏡下生検の意義は大きい。今回は,診断のために胸腔鏡下肺部分切除が有用であった小型肺癌症例を呈示する.
ⅩⅠ.乳癌
乳癌に対する胸筋温存乳房切除術
著者: 日馬幹弘 , 中山俊 , 河本敦夫
ページ範囲:P.340 - P.347
はじめに
当科における胸筋温存乳房切除の適応は以下のごとくである1).
1)局所進行乳癌症例:胸筋浸潤部が限局する 症例には胸筋部分切除を併用する.
乳癌に対する乳房扇状部分切除術
著者: 石田孝宣 , 大貫幸二 , 森谷卓也 , 石橋忠司 , 大内憲明
ページ範囲:P.348 - P.354
はじめに
乳房温存療法は日本でも乳癌の治療法の1つとして広く定着してきており,治療成績と同時に適応や術式,温存乳房内再発などの諸問題が各施設で次第に明らかとなってきた.当科においても乳房温存療法を開始してから10年が経過した.当初より解剖学的な乳管腺葉系を基盤とする切除が必要との考えからquadrantectomyを基本としているが,術前のマンモグラフィ,超音波に加えて最近では3—DMRIや3—DCTといった画像診断を用いてオーダーメードの切除範囲決定を目指している.
本稿では,術前に乳管内進展が疑われた乳房温存症例を画像を中心に供覧し,当科における乳房温存療法の実際を示す.
乳癌に対する乳房円状部分切除術
著者: 池田正 , 神野浩光 , 正村滋 , 松井哲 , 田島厳吾 , 北條隆 , 戸倉英之 , 三井洋子 , 麻賀創太 , 武藤剛 , 藤原潔 , 平松秀子 , 北島政樹
ページ範囲:P.355 - P.358
はじめに
乳癌に対する手術術式に関しては,諸外国の乳房温存術式と乳房切除術式とを比較したprospec-tive randomized trialの成績からは,いずれの術式を選択しても遠隔再発率あるいは生存率には統計的有意差のないことが確認されている1).しかし,局所再発率は術式あるいは術後照射の有無により大きく左右され,quadrantectomy followed byradiotherapyの4%2)から,lumpectomy withoutradiotherapyの39%1)に至るまで種々の報告がある.局所再発の高危険因子は,術後照射をしないことと,切除断端における癌細胞の存在である3,4).切除断端陽性の高危険因子は術式により異なり,切除範囲が狭いほど種々の要因が関係してくる5).切除断端陽性の原因は大部分が乳管内進展によるものである6).Hollandら7)によると,径2cmの乳癌でも10cm以上乳管内進展している症例がみられ,腫瘤縁から3cm離して切除しても約50%の症例では癌の遺残が乳管内にみられるという.したがって,術前にいかに乳管内進展を正確に読めるかが切除範囲を決定する重要な鍵となる.切除範囲を決めた後は,いかに正確に計画した部分を切除するかが重要となる.本稿では実際の手順に従って乳癌に対する円状乳房部分切除術の方法を記述する.
乳癌に対する胸筋合併乳房切除術
著者: 黒井克昌 , 戸井雅和 , 冨永健
ページ範囲:P.359 - P.363
はじめに
胸筋合併乳房切除術は乳房,大胸筋,小胸筋,リンパ節を一塊として切除する術式で,半世紀以上の間,乳癌に対する標準術式であったが,最近,その施行頻度は著しく減少している1).その理由として,術後に前胸部の変形が目立つこと,術後の上肢の浮腫,運動障害など,機能上,美容上の犠牲が大きいなどの問題があること,さらに症例を選べば胸筋温存乳房切除術,乳房温存術でも同等の根治性が得られることが明らかになったことが挙げられる.しかし,癌病巣が胸筋へ浸潤している症例においては本術式が適応となる.
また,広範な所属リンパ節転移(腋窩リンパ節,胸筋間リンパ節,鎖骨下リンパ節)のある症例も適応となるが,胸筋間溝の開大,小胸筋合併切除(Patey手術),あるいは牽引鉤による大胸筋挙上により,胸筋合併乳房切除術と同等のリンパ節郭清が可能な術式が多く考案され2),リンパ節転移が原因で適応となる症例は少なくなっている.
乳癌に対する一期的乳房再建術
著者: 西村正樹 , 山崎明久 , 谷野隆三郎
ページ範囲:P.365 - P.368
はじめに
今や日本においても,乳癌により乳房切除が行われたあと,一期的乳房再建術が多くの施設で行われるようになった.1980年代はじめには,広背筋筋皮弁と人工乳房(シリコン・インプラント)を用いた乳房再建術が主流であったが,80年代後半よりHartrampfら1)によって発表された異物を使用しないで腹部の自己組織のみで再建する横軸型腹直筋筋皮弁(TRAM flap)が多く用いられるようになった.TRAM flapを一度身体から切り離しマイクロサージェリーを使って胸部や腋窩の血管と吻合する方法と,筋肉からの血行を温存し胸部に移動する筋皮弁法があるが,通常は上腹壁動静脈を栄養血管とする有茎の腹直筋筋皮弁による乳房再建が多く行われている.
人工乳房は,現在生理食塩水入りのものや,シリコンジェル入りのものなどが欧米で販売されているが,日本の厚生労働省での認可を得ておらず,あくまでも医師の個人輸入という形でしか入手できない.また健康保険を使って手術を行い,同時に再建のため人工乳房を使った場合は,その材料費を患者個人に請求すると混合診療となりこれもまだ許されてない.しかし腹直筋筋皮弁を用いた再建術は健康保険で行っても差し支えない(KO16:動脈(皮)弁術,筋(皮)弁術19,900点).
乳癌に対するセンチネルリンパ節生検
著者: 沢井清司 , 中嶋啓雄 , 水田成彦 , 阪口晃一 , 鉢嶺泰司
ページ範囲:P.369 - P.373
はじめに
乳癌に対する根治術において腋窩リンパ節郭清は必須の手技として広く行われてきたが,腋窩郭清を行うと術後のセローマ,上肢リンパ浮腫などの合併症が発生し,術後のQOLを低くすることがある.センチネルリンパ節生検は,リンパ節転移のない症例を正確に判別し,無駄な腋窩郭清を省略できる手技であり,急速に普及しつつある1).本稿では,術前診断DCIS(非浸潤性乳管癌)に対して,センチネルリンパ節生検によりリンパ節郭清を省略した症例を提示する.
内視鏡併用乳腺部分切除術
著者: 玉木康博 , 三好康雄 , 野口眞三郎
ページ範囲:P.374 - P.376
はじめに
乳癌に対する根治手術は,乳房温存手術からセンチネルリンパ節生検導入へと近年ますます縮小傾向にある.乳癌手術を考える場合,根治性とともに美容的な問題,すなわち整容的QOLに配慮した手術を症例ごとに考慮する必要がある.内視鏡を応用した乳癌手術は,この意味で現在もっとも美容的に優れた手術法の一つであると思われる1〜3).しかし内視鏡手術はあくまで手術手段であり,個々の患者さんにおける切除範囲を含めた術式の適応は通常の乳房温存手術とほとんど変わるところはない。本稿では,筆者らの施設での症例を提示し,術前に必要な画像診断について解説する.
基本情報
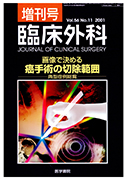
バックナンバー
79巻13号(2024年12月発行)
特集 JSES技術認定取得をめざせ2025
79巻12号(2024年11月発行)
特集 Acute Care Surgery入門
79巻11号(2024年10月発行)
増刊号 2024年最新版 外科局所解剖全図—ランドマークの出し方と損傷回避法
79巻10号(2024年10月発行)
特集 手術支援機器 百花繚乱!—ロボットとデバイスホールダー
79巻9号(2024年9月発行)
特集 徹底解説 大腸癌治療ガイドライン2024
79巻8号(2024年8月発行)
特集 合併症を起こさない食道癌手術!—ハイボリュームセンターの技を学ぼう
79巻7号(2024年7月発行)
特集 外科医が知っておくべき 肝胆膵腫瘍に対する薬物療法
79巻6号(2024年6月発行)
特集 結腸左半切除を極める
79巻5号(2024年5月発行)
特集 進化する外科教育と手術トレーニング
79巻4号(2024年4月発行)
特集 エキスパートに聞く!膵頭十二指腸切除のすべて
79巻3号(2024年3月発行)
特集 外科医必携 患者さんとのトラブルを防ぐためのハンドブック
79巻2号(2024年2月発行)
特集 ゲノム医学を外科診療に活かす!
79巻1号(2024年1月発行)
特集 若手外科医のライフハック—仕事・日常・将来を豊かにする,先輩たちの仕事術
78巻13号(2023年12月発行)
特集 ハイボリュームセンターのオペ記事《消化管癌編》
78巻12号(2023年11月発行)
特集 胃癌に対するconversion surgery—Stage Ⅳでも治したい!
78巻11号(2023年10月発行)
増刊号 —消化器・一般外科—研修医・専攻医サバイバルブック—術者として経験すべき手技のすべて
78巻10号(2023年10月発行)
特集 肝胆膵外科 高度技能専門医をめざせ!
78巻9号(2023年9月発行)
特集 見てわかる! 下部消化管手術における最適な剝離層
78巻8号(2023年8月発行)
特集 ロボット手術新時代!—極めよう食道癌・胃癌・大腸癌手術
78巻7号(2023年7月発行)
特集 術後急変!—予知・早期発見のベストプラクティス
78巻6号(2023年6月発行)
特集 消化管手術での“困難例”対処法—こんなとき,どうする?
78巻5号(2023年5月発行)
特集 術後QOLを重視した胃癌手術と再建法
78巻4号(2023年4月発行)
総特集 腹壁ヘルニア修復術の新潮流—瘢痕ヘルニア・臍ヘルニア・白線ヘルニア
78巻3号(2023年3月発行)
特集 進化する肝臓外科—高難度腹腔鏡下手術からロボット支援下手術の導入まで
78巻2号(2023年2月発行)
特集 最新医療機器・材料を使いこなす
78巻1号(2023年1月発行)
特集 外科医が知っておくべき! 免疫チェックポイント阻害薬
77巻13号(2022年12月発行)
特集 新・外科感染症診療ハンドブック
77巻12号(2022年11月発行)
特集 外科医必携 緊急対応が必要な大腸疾患
77巻11号(2022年10月発行)
増刊号 術前画像の読み解きガイド—的確な術式選択と解剖把握のために
77巻10号(2022年10月発行)
特集 外科医が担う緩和治療
77巻9号(2022年9月発行)
特集 導入! ロボット支援下ヘルニア修復術
77巻8号(2022年8月発行)
特集 よくわかる肛門疾患—診断から手術まで
77巻7号(2022年7月発行)
特集 徹底解説! 食道胃接合部癌《最新版》
77巻6号(2022年6月発行)
特集 ラパ胆を極める!
77巻5号(2022年5月発行)
特集 直腸癌局所再発に挑む—最新の治療戦略と手術手技
77巻4号(2022年4月発行)
特集 そろそろ真剣に考えよう 胃癌に対するロボット支援手術
77巻3号(2022年3月発行)
特集 肝胆膵術後合併症—どう防ぐ? どう対処する?
77巻2号(2022年2月発行)
特集 ガイドラインには書いていない 大腸癌外科治療のCQ—妥当な治療と適応を見直そう
77巻1号(2022年1月発行)
特集 外科医が知っておくべき—《最新版》栄養療法
76巻13号(2021年12月発行)
特集 Conversion surgeryアップデート
76巻12号(2021年11月発行)
特集 ストーマ・ハンドブック—外科医に必要な知識と手術手技のすべて
76巻11号(2021年10月発行)
増刊号 Stepごとに要点解説 標準術式アトラス最新版—特別付録Web動画
76巻10号(2021年10月発行)
特集 スコピストを極める
76巻9号(2021年9月発行)
特集 血管外科的手技を要する肝胆膵・移植手術
76巻8号(2021年8月発行)
特集 横行結腸癌の腹腔鏡下D3郭清手術—私のやり方,私の工夫
76巻7号(2021年7月発行)
特集 若手外科医のための食道手術ハンドブック—良性から悪性まで
76巻6号(2021年6月発行)
特集 神経・神経叢を極める—さらに精緻な消化器外科手術を求めて
76巻5号(2021年5月発行)
特集 側方リンパ節郭清のすべて—開腹からロボット手術まで
76巻4号(2021年4月発行)
特集 肥満外科A to Z
76巻3号(2021年3月発行)
特集 ロボット膵切除の導入ガイド—先行施設にノウハウを学ぶ
76巻2号(2021年2月発行)
特集 外科医のための—悪性腫瘍補助療法のすべて
76巻1号(2021年1月発行)
特集 徹底解説 術後後遺症をいかに防ぐか—コツとポイント
75巻13号(2020年12月発行)
特集 膵頭十二指腸切除の完全ガイド—定型術式から困難症例への対処法まで
75巻12号(2020年11月発行)
特集 消化器外科手術 助手の極意—開腹からロボット手術まで
75巻11号(2020年10月発行)
増刊号 早わかり縫合・吻合のすべて
75巻10号(2020年10月発行)
特集 ガイドラインには書いていない—胃癌治療のCQ
75巻9号(2020年9月発行)
特集 変貌する肝移植—適応拡大・ドナー選択・治療戦略の最先端を知る
75巻8号(2020年8月発行)
特集 遺伝性腫瘍とゲノム医療を学ぶ
75巻7号(2020年7月発行)
特集 若手外科医必携!—緊急手術の適応と術式
75巻6号(2020年6月発行)
特集 膵癌診療ガイドライン改訂を外科医はこう読み解く—ディベート&ディスカッション
75巻5号(2020年5月発行)
特集 taTMEのすべて
75巻4号(2020年4月発行)
特集 実践! 手術が上達するトレーニング法—Off the Job Trainingの最新動向
75巻3号(2020年3月発行)
特集 一般・消化器外科医のための できる! 漢方
75巻2号(2020年2月発行)
特集 「縫合不全!!」を防ぐ
75巻1号(2020年1月発行)
特集 “超”高難度手術! 他臓器合併切除術を極める
74巻13号(2019年12月発行)
特集 見せます! できる外科医のオペ記事—肝胆膵高度技能医は手術をこう描く
74巻12号(2019年11月発行)
特集 特殊な鼠径部ヘルニアに対する治療戦略
74巻11号(2019年10月発行)
増刊号 すぐに使える周術期管理マニュアル
74巻10号(2019年10月発行)
特集 腹腔鏡下胃手術のすべて
74巻9号(2019年9月発行)
特集 膵・消化管神経内分泌腫瘍—診断・治療の基本と最新動向
74巻8号(2019年8月発行)
特集 これだけは押さえたい!—大腸癌取扱い規約・治療ガイドライン—改訂のポイント
74巻7号(2019年7月発行)
特集 徹底解説! 噴門側胃切除術
74巻6号(2019年6月発行)
特集 肛門を極める
74巻5号(2019年5月発行)
特集 JSES技術認定取得をめざせ!
74巻4号(2019年4月発行)
特集 こんなときどうする!?—消化器外科の術中トラブル対処法
74巻3号(2019年3月発行)
特集 これからはじめるロボット手術
74巻2号(2019年2月発行)
特集 急性胆囊炎診療をマスターしよう
74巻1号(2019年1月発行)
特集 当直医必携!「右下腹部痛」を極める
73巻13号(2018年12月発行)
特集 ここがポイント!—サルコペニアの病態と対処法
73巻12号(2018年11月発行)
特集 炎症性腸疾患アップデート—いま外科医に求められる知識と技術
73巻11号(2018年10月発行)
増刊号 あたらしい外科局所解剖全図—ランドマークとその出し方
73巻10号(2018年10月発行)
特集 胃癌治療ガイドライン最新版を読み解く—改定のポイントとその背景
73巻9号(2018年9月発行)
特集 癌手術エキスパートになるための道
73巻8号(2018年8月発行)
特集 徹底解説! 膵尾側切除を極める
73巻7号(2018年7月発行)
特集 最新版 “腸閉塞”を極める!
73巻6号(2018年6月発行)
特集 こうやって教える・学ぶ 高難度消化器外科手術—新エキスパートへの登竜門
73巻5号(2018年5月発行)
特集 縦隔を覗き,さらにくり抜く—これからの食道・胃外科手術
73巻4号(2018年4月発行)
特集 機能温存と機能再建をめざした消化器外科手術—術後QOL向上のために
73巻3号(2018年3月発行)
特集 徹底解説!—膵頭十二指腸切除の手術手技
73巻2号(2018年2月発行)
特集 外科医が知っておくべき—最新Endoscopic Intervention
73巻1号(2018年1月発行)
特集 閉塞性大腸癌—ベストプラクティスを探す
72巻13号(2017年12月発行)
特集 最新の胆道癌診療トピックス—新たな治療戦略の可能性を探る
72巻12号(2017年11月発行)
特集 徹底解説!ここが変わった膵癌診療—新規約・ガイドラインに基づいて
72巻11号(2017年10月発行)
増刊号 手術ステップごとに理解する—標準術式アトラス
72巻10号(2017年10月発行)
特集 Conversion Surgery—進行消化器がんのトータル治療戦略
72巻9号(2017年9月発行)
特集 知っておきたい 乳がん診療のエッセンス
72巻8号(2017年8月発行)
特集 がん治療医のための漢方ハンドブック
72巻7号(2017年7月発行)
特集 イラストでわかる!—消化器手術における最適な剝離層
72巻6号(2017年6月発行)
特集 術後重大合併症—これだけは知っておきたい緊急処置法
72巻5号(2017年5月発行)
特集 百花繚乱! エネルギーデバイスを使いこなす
72巻4号(2017年4月発行)
特集 消化管吻合アラカルト—あなたの選択は?
72巻3号(2017年3月発行)
特集 目で見る腹腔鏡下肝切除—エキスパートに学ぶ!
72巻2号(2017年2月発行)
特集 ビッグデータにもとづいた—術前リスクの評価と対処法
72巻1号(2017年1月発行)
特集 最新の内視鏡外科手術の適応と注意点
71巻13号(2016年12月発行)
特集 名手からの提言—手術を極めるために
71巻12号(2016年11月発行)
特集 転移性肝腫瘍のいま—なぜ・どこが原発臓器ごとに違うのか
71巻11号(2016年10月発行)
増刊号 消化器・一般外科医のための—救急・集中治療のすべて
71巻10号(2016年10月発行)
特集 エキスパートが教える 鼠径部ヘルニアのすべて
71巻9号(2016年9月発行)
特集 食道癌手術のコツと要点
71巻8号(2016年8月発行)
特集 外科医が攻める高度進行大腸癌
71巻7号(2016年7月発行)
特集 胆管系合併症のすべて—その予防とリカバリー
71巻6号(2016年6月発行)
特集 必携 腹腔鏡下胃癌手術の完全マスター—ビギナーからエキスパートまで
71巻5号(2016年5月発行)
特集 外科臨床研究のノウハウと重要研究の総まとめ
71巻4号(2016年4月発行)
特集 大腸癌肝転移—最新の治療ストラテジー
71巻3号(2016年3月発行)
特集 術後障害のリアル—外来フォローの実力が臓器損失を補う
71巻2号(2016年2月発行)
特集 イラストでみる大腸癌腹腔鏡手術のポイント
71巻1号(2016年1月発行)
特集 十二指腸乳頭部病変に対する新たな治療戦略—新規約・新ガイドラインに基づいて
70巻13号(2015年12月発行)
特集 外科医に求められる積極的緩和医療—延命と症状緩和の狭間で
70巻12号(2015年11月発行)
特集 同時性・異時性の重複がんを見落とさない—がん診療における他臓器への目配り
70巻11号(2015年10月発行)
増刊号 消化器・一般外科手術のPearls&Tips—ワンランク上の手術を達成する技と知恵
70巻10号(2015年10月発行)
特集 エキスパートの消化管吻合を学ぶ
70巻9号(2015年9月発行)
特集 再発に挑む!—外科治療の役割
70巻8号(2015年8月発行)
特集 大腸癌腹腔鏡手術の新展開—Reduced port surgeryからロボット手術まで
70巻7号(2015年7月発行)
特集 Neoadjuvant therapyの最新の動向—がんの治療戦略はどのように変わっていくのか
70巻6号(2015年6月発行)
特集 胃切除後再建術式の工夫とその評価
70巻5号(2015年5月発行)
特集 外科医が知っておくべき がん薬物療法の副作用とその対策
70巻4号(2015年4月発行)
特集 膵・消化管神経内分泌腫瘍(GEP-NET)のアップデート
70巻3号(2015年3月発行)
特集 生検材料を手術に活かす
70巻2号(2015年2月発行)
特集 肛門良性疾患を極める—目で見る 多彩な病態へのアプローチ法
70巻1号(2015年1月発行)
特集 胆道癌外科切除—再発防止のストラテジー
69巻13号(2014年12月発行)
特集 早期胃癌の外科治療を極める—「EMR 適応外」への安全で有益な縮小手術を求めて
69巻12号(2014年11月発行)
特集 外科切除適応の境界領域—Borderline resectable cancerへの対応
69巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ERAS時代の周術期管理マニュアル
69巻10号(2014年10月発行)
特集 直腸癌局所再発に対する治療戦略―新たな展開
69巻9号(2014年9月発行)
特集 外科医が知っておくべき小腸疾患
69巻8号(2014年8月発行)
特集 肝胆膵癌の血管浸潤をどう治療するか
69巻7号(2014年7月発行)
特集 術後合併症への対処法 Surgical vs Non-Surgical―いつどのように判断するか?
69巻6号(2014年6月発行)
特集 癌の補助療法アップデート
69巻5号(2014年5月発行)
特集 消化器外科での救急医療―救急外来から手術室そして病棟まで
69巻4号(2014年4月発行)
特集 サルベージとコンバージョン―集学的治療で外科手術に求められるもの
69巻3号(2014年3月発行)
特集 究極の肛門温存術式ISR―長期成績からわかる有用性と問題点
69巻2号(2014年2月発行)
特集 ディベート★消化器・一般外科手術―選ぶのはどっちだ!
69巻1号(2014年1月発行)
特集 見直される膵癌診療の新展開
68巻13号(2013年12月発行)
特集 切徐可能なStage Ⅳ胃癌に対する外科治療
68巻12号(2013年11月発行)
特集 漢方を上手に使う―エビデンスに基づいた外科診療
68巻11号(2013年10月発行)
特集 術前画像診断のポイントと術中解剖認識
68巻10号(2013年10月発行)
特集 次代の外科専門医をめざしたトレーニングシステム
68巻9号(2013年9月発行)
特集 大腸癌腹膜播種を極める―最近の進歩と今後の展望
68巻8号(2013年8月発行)
特集 外科医のための癌免疫療法―基礎と臨床
68巻7号(2013年7月発行)
特集 NOTSS―外科医に問われる手技以外のスキル
68巻6号(2013年6月発行)
特集 胃癌腹膜転移治療の最前線
68巻5号(2013年5月発行)
特集 一般外科医が知っておくべき小児患者への対応
68巻4号(2013年4月発行)
特集 「食道胃接合部癌」に迫る!
68巻3号(2013年3月発行)
特集 CRT時代の直腸癌手術―最善の戦略は何か
68巻2号(2013年2月発行)
特集 術後の血管系合併症―その診断と対策
68巻1号(2013年1月発行)
特集 進歩する消化器外科手術―術式の温故知新
67巻13号(2012年12月発行)
特集 本当は怖い 臓器解剖変異―外科医が必ず知っておくべき知識
67巻12号(2012年11月発行)
特集 食道癌・胃癌切除後の再建法を見直す―達人の選択
67巻11号(2012年10月発行)
特集 外科医のための癌診療データ
67巻10号(2012年10月発行)
特集 炎症性腸疾患のすべて―新しい治療戦略
67巻9号(2012年9月発行)
特集 高齢者外科手術における周術期管理
67巻8号(2012年8月発行)
特集 知っておきたい放射線・粒子線治療
67巻7号(2012年7月発行)
特集 分子標的薬の有害事象とその対策
67巻6号(2012年6月発行)
特集 よくわかるNCD
67巻5号(2012年5月発行)
特集 次代のMinimally Invasive Surgery!
67巻4号(2012年4月発行)
特集 内視鏡外科手術の腕をみがく―技術認定医をめざして
67巻3号(2012年3月発行)
特集 消化器外科のドレーン管理を再考する
67巻2号(2012年2月発行)
特集 肝胆膵外科手術における術中トラブル―その予防と対処のポイント
67巻1号(2012年1月発行)
特集 「切除困難例」への化学療法後の手術―根治切除はどこまで可能か
66巻13号(2011年12月発行)
特集 外科医のための消化器内視鏡Up-to-Date
66巻12号(2011年11月発行)
特集 目で見てわかる肛門疾患治療
66巻11号(2011年10月発行)
特集 外科医のための最新癌薬物療法
66巻10号(2011年10月発行)
特集 進歩する癌転移診断―外科臨床はどう変わるのか
66巻9号(2011年9月発行)
特集 下大静脈にかかわる病態を見直す
66巻8号(2011年8月発行)
特集 画像診断の進歩をいかに手術に役立てるか
66巻7号(2011年7月発行)
特集 術前薬物療法は乳癌手術を縮小させるか
66巻6号(2011年6月発行)
特集 栄養療法―最新の知見と新たな展開
66巻5号(2011年5月発行)
特集 いま必要な外科治療に関する臨床試験の最新知識
66巻4号(2011年4月発行)
特集 悪性腫瘍の術中病理診断を効果的に活用する―どこを検索すべきか,どう対応すべきか
66巻3号(2011年3月発行)
特集 知っておくべき 外科手術の神経系合併症 その診断と対策
66巻2号(2011年2月発行)
特集 T4の癌―臓器別特性と治療戦略
66巻1号(2011年1月発行)
特集 医療経済からみた大腸癌化学療法
65巻13号(2010年12月発行)
特集 「出血量ゼロ」をめざした消化管癌の内視鏡下手術
65巻12号(2010年11月発行)
特集 新しいエネルギーデバイスの構造と使い方のコツ
65巻11号(2010年10月発行)
特集 外科医のための大腸癌の診断と治療
65巻10号(2010年10月発行)
特集 乳糜胸水・腹水を考える―その原因と対策
65巻9号(2010年9月発行)
特集 [臓器別]消化器癌終末期の特徴とターミナルケア
65巻8号(2010年8月発行)
特集 ESD時代の外科治療
65巻7号(2010年7月発行)
特集 腹壁瘢痕ヘルニア治療up date
65巻6号(2010年6月発行)
特集 癌外科治療の日本と海外との相違点
65巻5号(2010年5月発行)
特集 消化器外科手術における新しい潮流
65巻4号(2010年4月発行)
特集 消化器癌neoadjuvant chemotherapyの新展開
65巻3号(2010年3月発行)
特集 エキスパートが伝える 消化器癌手術の流れと手術助手の心得
65巻2号(2010年2月発行)
特集 外科医に必要なPET検査の知識―その有用性と問題点
65巻1号(2010年1月発行)
特集 がん診療ガイドライン―臨床現場における有効活用法
64巻13号(2009年12月発行)
特集 内視鏡下手術―もう一歩のステップアップのために
64巻12号(2009年11月発行)
特集 転移性腫瘍に対する治療戦略
64巻11号(2009年10月発行)
特集 できる!縫合・吻合
64巻10号(2009年10月発行)
特集 消化器外科における経腸栄養の意義と役割
64巻9号(2009年9月発行)
特集 外科医に求められるチーム医療Practice
64巻8号(2009年8月発行)
特集 胆囊癌根治手術をめぐる諸問題
64巻7号(2009年7月発行)
特集 肝胆膵癌に対する補助療法―治療成績の向上を目指して
64巻6号(2009年6月発行)
特集 消化器癌外科治療のrandomized controlled trial
64巻5号(2009年5月発行)
特集 炎症性腸疾患外科治療のcontroversy
64巻4号(2009年4月発行)
特集 脾臓をめぐる最近のトピックス
64巻3号(2009年3月発行)
特集 直腸癌治療―最近の進歩と動向
64巻2号(2009年2月発行)
特集 最近のGIST診療―診療ガイドラインの理解と実践
64巻1号(2009年1月発行)
特集 外科診療上知っておきたい新たな予後予測因子・スコア
63巻13号(2008年12月発行)
特集 外科におけるadjuvant/neoadjuvant chemotherapy update
63巻12号(2008年11月発行)
特集 十二指腸病変に対する外科的アプローチ
63巻11号(2008年10月発行)
特集 肛門疾患診療のすべて
63巻10号(2008年10月発行)
特集 鼠径ヘルニアの治療NOW―乳幼児から成人まで
63巻9号(2008年9月発行)
特集 がんの切除範囲を考える―診断法とその妥当性
63巻8号(2008年8月発行)
特集 St. Gallen 2007に基づいた乳癌テーラーメイド補助療法
63巻7号(2008年7月発行)
特集 実践に必要な術後創の管理
63巻6号(2008年6月発行)
特集 肝・胆・膵領域における腹腔鏡下手術の最前線
63巻5号(2008年5月発行)
特集 胆道癌外科診療を支えるエキスパートテクニック
63巻4号(2008年4月発行)
特集 消化器外科と漢方
63巻3号(2008年3月発行)
特集 術前・術中のリンパ節転移診断の方法とその有用性
63巻2号(2008年2月発行)
特集 安全な消化管器械吻合をめざして
63巻1号(2008年1月発行)
特集 機能温存手術のメリット・デメリット
62巻13号(2007年12月発行)
特集 膵臓外科の新たな展開
62巻12号(2007年11月発行)
特集 Up-to-Date外科医のための創傷治癒
62巻11号(2007年10月発行)
特集 癌診療に役立つ最新データ2007-2008
62巻10号(2007年10月発行)
特集 肛門疾患診断・治療のコツと実際
62巻9号(2007年9月発行)
特集 多発肝転移をめぐって
62巻8号(2007年8月発行)
特集 Surgical Site Infection(SSI)対策
62巻7号(2007年7月発行)
特集 乳癌の治療戦略―エビデンスとガイドラインの使い方
62巻6号(2007年6月発行)
特集 肝胆膵術後合併症―その予防のために
62巻5号(2007年5月発行)
特集 外来がん化学療法と外科
62巻4号(2007年4月発行)
特集 癌診療ガイドラインの功罪
62巻3号(2007年3月発行)
特集 術後呼吸器合併症―予防と対策の最新知識
62巻2号(2007年2月発行)
特集 外科領域におけるインフォームド・コンセントと医療安全対策
62巻1号(2007年1月発行)
特集 良性腸疾患における腹腔鏡下手術の適応と限界
61巻13号(2006年12月発行)
特集 消化器外科術後合併症の治療戦略―私たちはこのように治療している
61巻12号(2006年11月発行)
特集 生活習慣病および代謝性疾患と外科
61巻11号(2006年10月発行)
特集 イラストレイテッド外科標準術式
61巻10号(2006年10月発行)
特集 今どうしてNSTなのか?
61巻9号(2006年9月発行)
特集 消化器外科医に必要な低侵襲治療の知識
61巻8号(2006年8月発行)
特集 急性腹症における低侵襲な治療法選択
61巻7号(2006年7月発行)
特集 消化器外科における非観血的ドレナージ
61巻6号(2006年6月発行)
特集 癌の播種性病変の病態と診断・治療
61巻5号(2006年5月発行)
特集 手術のための臨床局所解剖
61巻4号(2006年4月発行)
特集 最新の手術器械―使いこなすコツを学ぶ
61巻3号(2006年3月発行)
特集 乳腺疾患を取り巻くガイドラインと最新の知見―最適な診療を目指して
61巻2号(2006年2月発行)
特集 外科医に求められる緩和医療の知識
61巻1号(2006年1月発行)
特集 GIST―診断と治療の最前線
60巻13号(2005年12月発行)
特集 消化管機能温存を考えた外科手術最前線
60巻12号(2005年11月発行)
特集 生体肝移植―最新の話題
60巻11号(2005年10月発行)
特集 癌治療のプロトコール2005-2006
60巻10号(2005年10月発行)
特集 自動吻合器・縫合器による消化管再建の標準手技と応用
60巻9号(2005年9月発行)
特集 癌告知とインフォームド・コンセント
60巻8号(2005年8月発行)
特集 肝切除のコツを知る―出血を少なくするために
60巻7号(2005年7月発行)
特集 炎症性腸疾患―治療における最近の進歩
60巻6号(2005年6月発行)
特集 化学放射線療法―現状とイメージングによる効果判定
60巻5号(2005年5月発行)
特集 外科栄養療法の新たな潮流
60巻4号(2005年4月発行)
特集 Surgical Site Infection(SSI)の現状と対策
60巻3号(2005年3月発行)
特集 急性肺塞栓症の最新診療
60巻2号(2005年2月発行)
特集 再発食道癌を考える
60巻1号(2005年1月発行)
特集 手術のグッドタイミング
59巻13号(2004年12月発行)
特集 直腸癌に対する手術のコツ
59巻12号(2004年11月発行)
特集 術中の出血コントロールと止血のノウハウ
59巻11号(2004年10月発行)
特集 小外科・外来処置マニュアル
59巻10号(2004年10月発行)
特集 周術期の輸液と感染対策
59巻9号(2004年9月発行)
特集 乳癌初回の診療:ガイドラインと主治医の裁量
59巻8号(2004年8月発行)
特集 肛門疾患診断・治療の実際
59巻7号(2004年7月発行)
特集 研修医のための外科基本手技とそのコツ
59巻6号(2004年6月発行)
特集 内視鏡外科手術を安全に行うために
59巻5号(2004年5月発行)
特集 Sentinel node navigation surgery―新たなる展開
59巻4号(2004年4月発行)
特集 甲状腺癌治療の最適化を目指して
59巻3号(2004年3月発行)
特集 肝細胞癌治療の最前線
59巻2号(2004年2月発行)
特集 GIST(gastrointestinal stromal tumor)診療の最前線
59巻1号(2004年1月発行)
特集 癌en bloc切除とnon-touch isolation techniqueの考え方と実践
58巻13号(2003年12月発行)
特集 内視鏡下手術で発展した手技・器具の外科手術への応用
58巻12号(2003年11月発行)
特集 浸潤性膵管癌の診療をどうするか
58巻11号(2003年10月発行)
特集 クリニカルパスによる外科医療の進歩
58巻10号(2003年10月発行)
特集 神経温存胃切除術
58巻9号(2003年9月発行)
特集 癌と紛らわしい各領域の諸病変
58巻8号(2003年8月発行)
特集 癌化学療法レジメンの選択とその根拠:消化器癌
58巻7号(2003年7月発行)
特集 癌化学療法レジメンの選択とその根拠:乳癌・肺癌・甲状腺癌
58巻6号(2003年6月発行)
特集 癌肝転移の治療戦略
58巻5号(2003年5月発行)
特集 栄養療法とformula
58巻4号(2003年4月発行)
特集 腹腔鏡下大腸切除術のコツ
58巻3号(2003年3月発行)
特集 Q&A器械吻合・縫合のコツ
58巻2号(2003年2月発行)
特集 胆囊癌NOW
58巻1号(2003年1月発行)
特集 外科における重症感染症とその対策
57巻13号(2002年12月発行)
特集 胃癌治療ガイドラインの検証
57巻12号(2002年11月発行)
特集 肛門疾患手術のup to date
57巻11号(2002年10月発行)
特集 癌診療に役立つ最新データ
57巻10号(2002年10月発行)
特集 内視鏡下手術の現状と問題点
57巻9号(2002年9月発行)
特集 パソコン活用術とその周辺
57巻8号(2002年8月発行)
特集 ヘルニア—最新の治療
57巻7号(2002年7月発行)
特集 外科診療とステロイド療法
57巻6号(2002年6月発行)
特集 エビデンスから見直す癌術後患者のフォローアップ
57巻5号(2002年5月発行)
特集 肝切除術のコツ
57巻4号(2002年4月発行)
特集 消化器外科における機能検査
57巻3号(2002年3月発行)
特集 乳癌:初回治療の標準化
57巻2号(2002年2月発行)
特集 食道癌治療におけるcontroversy
57巻1号(2002年1月発行)
特集 最先端の外科医療
56巻13号(2001年12月発行)
特集 IVRの現状と問題点
56巻12号(2001年11月発行)
特集 新しい医療材料と器具
56巻11号(2001年10月発行)
特集 画像で決める癌手術の切除範囲—典型症例総覧
56巻10号(2001年10月発行)
特集 甲状腺外科—最新の臨床
56巻9号(2001年9月発行)
特集 外科と消毒と感染予防
56巻8号(2001年8月発行)
特集 閉塞性黄疸の診療手順
56巻7号(2001年7月発行)
特集 肝良性疾患—鑑別診断と治療法選択のupdate
56巻6号(2001年6月発行)
特集 大腸癌の術後再発をめぐって
56巻5号(2001年5月発行)
特集 家族性腫瘍—診断と治療の現況
56巻4号(2001年4月発行)
特集 外科におけるクリニカルパスの展開
56巻3号(2001年3月発行)
特集 総胆管結石治療の最前線—手技と周辺機器の進歩
56巻2号(2001年2月発行)
特集 重症急性膵炎の診療Now
56巻1号(2001年1月発行)
特集 21世紀の外科—Tissue Engineering
55巻13号(2000年12月発行)
特集 超音波ガイド下の穿刺手技
55巻12号(2000年11月発行)
特集 胃癌術後のフォローアップ:再発と二次癌対策
55巻11号(2000年10月発行)
特集 癌治療のプロトコール—当施設はこうしている
55巻10号(2000年10月発行)
特集 ベッドサイド基本手技とコツ
55巻9号(2000年9月発行)
特集 外科医に求められる緩和医療プラクティス
55巻8号(2000年8月発行)
特集 肛門疾患診療の実際とコツ
55巻7号(2000年7月発行)
特集 抗菌薬ベストチョイス—その理論と実際
55巻6号(2000年6月発行)
特集 胃全摘後の消化管再建—術式のベストチョイス
55巻5号(2000年5月発行)
特集 輸液:その組成・アクセス・管理
55巻4号(2000年4月発行)
特集 各種ステント治療のノウハウ
55巻3号(2000年3月発行)
特集 Sentinel Node Navigation Surgery
55巻2号(2000年2月発行)
特集 イレウス診療のupdate
55巻1号(2000年1月発行)
特集 肝臓移植を理解する
54巻13号(1999年12月発行)
特集 大腸の非腫瘍性疾患—外科医のための診療指針
54巻12号(1999年11月発行)
特集 胃・十二指腸の非腫瘍性疾患—外科医のための診療指針
54巻11号(1999年10月発行)
特集 薬物療法マニュアル
54巻10号(1999年10月発行)
特集 消化管EMRの現状と問題点
54巻9号(1999年9月発行)
特集 在宅栄養療法の標準管理
54巻8号(1999年8月発行)
特集 3D画像診断の肝胆膵手術への応用
54巻7号(1999年7月発行)
特集 膵臓外科に対するチャレンジ:切離・吻合の工夫
54巻6号(1999年6月発行)
特集 直腸癌の治療—機能温存手術のプログレス
54巻5号(1999年5月発行)
特集 切除標本取扱いガイドライン—癌取扱い規約に基づいた正しい取扱い法と肉眼所見の記載法
54巻4号(1999年4月発行)
特集 Surgical deviceの有効,安全な使い方
54巻3号(1999年3月発行)
特集 器械吻合・縫合におけるコツとピットフォール
54巻2号(1999年2月発行)
特集 癌転移治療のノウハウ
54巻1号(1999年1月発行)
特集 乳癌の手術:最適化への論点
53巻13号(1998年12月発行)
特集 外科・形成外科の連携と展望
53巻12号(1998年11月発行)
特集 肝癌治療のupdate
53巻11号(1998年10月発行)
特集 縫合・吻合法のバイブル
53巻10号(1998年10月発行)
特集 胃癌術後補助化学療法をめぐって
53巻9号(1998年9月発行)
特集 急性腹膜炎—病態と治療の最前線
53巻8号(1998年8月発行)
特集 肛門疾患診断・治療のノウハウ
53巻7号(1998年7月発行)
特集 分子生物学的診断は病理診断に迫れるか
53巻6号(1998年6月発行)
特集 ここまできたDay Surgery
53巻5号(1998年5月発行)
特集 病態別補充・補正のFormula
53巻4号(1998年4月発行)
特集 早期直腸癌診療のストラテジー
53巻3号(1998年3月発行)
特集 自己血輸血の現状と将来展望
53巻2号(1998年2月発行)
特集 食道・胃静脈瘤攻略法
53巻1号(1998年1月発行)
特集 胆道ドレナージを考える
52巻13号(1997年12月発行)
特集 血管系病変と腹部消化器外科
52巻12号(1997年11月発行)
特集 消化器外科領域におけるメタリックステント
52巻11号(1997年10月発行)
特集 外来診療・小外科マニュアル
52巻10号(1997年10月発行)
特集 食道癌診療のトピックス
52巻9号(1997年9月発行)
特集 甲状腺と上皮小体の外科—最近の進歩
52巻8号(1997年8月発行)
特集 Q&A 自動吻合器・縫合器の安全,有効な使い方
52巻7号(1997年7月発行)
特集 経腸栄養法—最新の動向
52巻6号(1997年6月発行)
特集 輸血後GVHDをめぐる諸問題
52巻5号(1997年5月発行)
特集 サイトカインからみた周術期管理
52巻4号(1997年4月発行)
特集 膵瘻の予防・治療のノウハウ
52巻3号(1997年3月発行)
特集 ドレッシング—創傷管理の新たな展開
52巻2号(1997年2月発行)
特集 消化器の“前癌病変”と“ハイリスク病変”
52巻1号(1997年1月発行)
特集 転移性肺癌診療の最新ストラテジー
51巻13号(1996年12月発行)
特集 大災害に対する外科医の備え
51巻12号(1996年11月発行)
特集 外科医のためのペインクリニック
51巻11号(1996年10月発行)
特集 術前ワークアップマニュアル—入院から手術当日までの患者管理
51巻10号(1996年10月発行)
特集 胃癌治療のup-to-date—機能温存手術と縮小手術
51巻9号(1996年9月発行)
特集 急性腹症—画像診断から初期治療まで
51巻8号(1996年8月発行)
特集 直腸癌に対する肛門機能温存手術の実際
51巻7号(1996年7月発行)
特集 図解 成人鼠径ヘルニア手術
51巻6号(1996年6月発行)
特集 外科医に必要な整形外科の知識
51巻5号(1996年5月発行)
特集 肛門疾患診療のポイント—エキスパート17人のノウハウ
51巻4号(1996年4月発行)
特集 術後感染症—予防と治療の実際
51巻3号(1996年3月発行)
特集 肝炎・肝硬変患者の消化器外科手術
51巻2号(1996年2月発行)
特集 甲状腺外科の新しい展開
51巻1号(1996年1月発行)
特集 乳房温存療法の適応と実際
50巻13号(1995年12月発行)
特集 外科医のための緩和ケア
50巻12号(1995年11月発行)
特集 消化器癌手術における皮膚切開と術野展開の工夫
50巻11号(1995年10月発行)
特集 術後1週間の患者管理
50巻10号(1995年10月発行)
特集 多臓器不全—患者管理の実際
50巻9号(1995年9月発行)
特集 出血させない消化器癌手術
50巻8号(1995年8月発行)
特集 高齢者の外科—キュアとケア
50巻7号(1995年7月発行)
特集 再発消化管癌を治療する
50巻6号(1995年6月発行)
特集 外科臨床医のための基本手技
50巻5号(1995年5月発行)
特集 画像診断が変わる? MRIの新しい展開
50巻4号(1995年4月発行)
特集 新しい膵手術のテクニック
50巻3号(1995年3月発行)
特集 Q & A 人工呼吸管理とベンチレータ
50巻2号(1995年2月発行)
特集 消化器癌画像診断のノウ・ハウ
50巻1号(1995年1月発行)
特集 早期胃癌の内視鏡的根治切除
49巻13号(1994年12月発行)
特集 外科手術と輸血—最近の動向
49巻12号(1994年11月発行)
特集 ストーマの造設と管理—患者のQOLの視点から
49巻11号(1994年10月発行)
特集 施設別/新・悪性腫瘍治療のプロトコール
49巻10号(1994年10月発行)
特集 自動吻合器・縫合器を使いこなす
49巻9号(1994年9月発行)
特集 癌の外科治療とインフォームド・コンセント(IC)
49巻8号(1994年8月発行)
特集 消化器外科におけるInterventional Radiology(IVR)
49巻7号(1994年7月発行)
特集 腹腔鏡下の腹部救急疾患診療
49巻6号(1994年6月発行)
特集 静脈系疾患診療の新しい展開
49巻5号(1994年5月発行)
特集 術中肝エコーのABC
49巻4号(1994年4月発行)
特集 内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)
49巻3号(1994年3月発行)
特集 肝癌治療の最新ストラテジー
49巻2号(1994年2月発行)
特集 上部消化管の術後運動機能評価と病態
49巻1号(1994年1月発行)
特集 乳癌診療—今日の話題
48巻13号(1993年12月発行)
特集 スキルス胃癌の診断と治療
48巻12号(1993年11月発行)
特集 骨盤内悪性腫瘍の機能温存手術
48巻11号(1993年10月発行)
特集 Dos & Don'ts外来の小外科
48巻10号(1993年10月発行)
特集 今日の肺癌診療
48巻9号(1993年9月発行)
特集 食道癌治療への集学的アプローチ
48巻8号(1993年8月発行)
特集 疼痛をどうコントロールするか
48巻7号(1993年7月発行)
特集 Up-to-date総胆管結石症治療
48巻6号(1993年6月発行)
特集 MRSA感染症対策の実際
48巻5号(1993年5月発行)
特集 施設別・消化器癌術後栄養管理の実際
48巻4号(1993年4月発行)
特集 治療的ドレナージ
48巻3号(1993年3月発行)
特集 局所麻酔を行う外科医へ
48巻2号(1993年2月発行)
特集 消化管の機能温存手術
48巻1号(1993年1月発行)
特集 消化器癌切除材料取扱いマニュアル
47巻13号(1992年12月発行)
特集 今日の甲状腺癌診療
47巻12号(1992年11月発行)
特集 悪性腫瘍治療の現況—他科では今
47巻11号(1992年10月発行)
特集 外科患者・薬物療法マニュアル
47巻10号(1992年10月発行)
特集 形成外科から学び取る
47巻9号(1992年9月発行)
特集 大腸癌治療のフロンティア
47巻8号(1992年8月発行)
特集 膵癌への挑戦
47巻7号(1992年7月発行)
特集 肛門疾患診療の実際—私の方法と根拠
47巻6号(1992年6月発行)
特集 いまイレウスを診療する
47巻5号(1992年5月発行)
特集 腫瘍マーカーの理論と実際
47巻4号(1992年4月発行)
特集 静脈・経腸栄養のトピックス
47巻3号(1992年3月発行)
特集 再手術の適応と術式
47巻2号(1992年2月発行)
特集 下肢循環障害の治療—適応と限界
47巻1号(1992年1月発行)
特集 外科における超音波検査—新しい展開
46巻13号(1991年12月発行)
特集 院内感染—現状と対策
46巻12号(1991年11月発行)
特集 若年者癌診療の実際
46巻11号(1991年10月発行)
特集 術前・術後管理 '91
46巻10号(1991年10月発行)
特集 胆石症の非手術的治療—現況と問題点
46巻9号(1991年9月発行)
特集 胃癌の治療update
46巻8号(1991年8月発行)
特集 内視鏡下外科手術
46巻7号(1991年7月発行)
特集 熱傷治療のトピックス
46巻6号(1991年6月発行)
特集 食道静脈瘤治療の焦点
46巻5号(1991年5月発行)
特集 術前一般検査—異常値の読みと対策
46巻4号(1991年4月発行)
特集 癌のPalliative Therapy
46巻3号(1991年3月発行)
特集 乳房温存療法の実践
46巻2号(1991年2月発行)
特集 急性腹症の近辺—他科からのアドバイス
46巻1号(1991年1月発行)
特集 Day Surgeryはどこまで可能か
45巻13号(1990年12月発行)
特集 進行癌の画像診断—治癒切除の判定をどうするか
45巻12号(1990年11月発行)
特集 癌手術の補助療法—現状と展望
45巻11号(1990年10月発行)
特集 保存的治療の適応と限界—外科から,内科から
45巻10号(1990年10月発行)
特集 胸水・腹水への対処
45巻9号(1990年9月発行)
特集 消化管吻合法—私の方法とコツ
45巻8号(1990年8月発行)
特集 臓器全摘術の適応と問題点
45巻7号(1990年7月発行)
特集 外科医のための整形外科
45巻6号(1990年6月発行)
特集 転移性肝癌の治療
45巻5号(1990年5月発行)
特集 腹部血管病変の診療
45巻4号(1990年4月発行)
特集 今日のストーマ
45巻3号(1990年3月発行)
特集 新しい手術材料—特徴と使い方
45巻2号(1990年2月発行)
特集 Endoscopic Surgery—適応と手技
45巻1号(1990年1月発行)
特集 肺癌の診断と治療 '90
44巻13号(1989年12月発行)
特集 小児外科
44巻12号(1989年11月発行)
特集 胆嚢癌の外科
44巻11号(1989年10月発行)
特集 肛門疾患治療の現況
44巻10号(1989年9月発行)
特集 鼎談
44巻9号(1989年9月発行)
特集 がん放射線療法の現況と進歩
44巻8号(1989年8月発行)
特集 臓器生検の適応と手技
44巻7号(1989年7月発行)
特集 食道癌の手術
44巻6号(1989年6月発行)
特集 胃癌治療の最近の話題
44巻5号(1989年5月発行)
特集 外科臨床における病態別栄養
44巻4号(1989年4月発行)
特集 消化器良性疾患の手術適応—最近の考え方
44巻3号(1989年3月発行)
特集 肝門部胆管癌の治療
44巻2号(1989年2月発行)
特集 80歳以上高齢者の手術
44巻1号(1989年1月発行)
特集 膵臓の外科—up to date
43巻13号(1988年12月発行)
特集 直腸癌の手術
43巻12号(1988年11月発行)
特集 Drug Delivery Systemを利用した癌治療
43巻11号(1988年10月発行)
特集 外科医のためのMRIの臨床
43巻10号(1988年9月発行)
特集 高位胃潰瘍治療の問題点—外科から,内科から
43巻9号(1988年8月発行)
特集 消化器癌の相対非治癒切除
43巻8号(1988年7月発行)
特集 多発外傷—初療60分
43巻7号(1988年6月発行)
特集 鼠径ヘルニアの診療
43巻6号(1988年5月発行)
特集 —そこが知りたい—消化器外科手術のテクニックとコツ96
43巻5号(1988年5月発行)
特集 急性腹症のX線像・エコー像
43巻4号(1988年4月発行)
特集 外科診療における酸塩基平衡の異常
43巻3号(1988年3月発行)
特集 手術と輸血—最近のトピックス
43巻2号(1988年2月発行)
特集 集中治療を要する術後合併症
43巻1号(1988年1月発行)
特集 臓器移植のup to date '88
42巻13号(1987年12月発行)
特集 外科的感染症と抗生物質の選択
42巻12号(1987年11月発行)
特集 胆石症—最近の話題
42巻11号(1987年10月発行)
特集 Interventional Radiologyの現況
42巻10号(1987年9月発行)
特集 癌術後follow upと再発時の対策
42巻9号(1987年8月発行)
特集 乳癌診療のUp-to-date
42巻8号(1987年7月発行)
特集 いわゆる消化器早期癌の術後再発—その実態と対策
42巻7号(1987年6月発行)
特集 外科医の触診
42巻6号(1987年5月発行)
特集 [施設別]悪性腫瘍治療方針のプロトコール
42巻5号(1987年5月発行)
特集 外科医のための超音波応用診断手技
42巻4号(1987年4月発行)
特集 頸部腫瘤の臨床
42巻3号(1987年3月発行)
特集 消化管のEmergency—穿孔・破裂
42巻2号(1987年2月発行)
特集 外科医が使える形成外科手技
42巻1号(1987年1月発行)
特集 今日の肺癌治療 '87
41巻13号(1986年12月発行)
特集 ストーマをめぐる最近の話題
41巻12号(1986年11月発行)
特集 MOF患者のArtificial Support
41巻11号(1986年10月発行)
特集 胃癌手術の限界と合理化
41巻10号(1986年9月発行)
特集 食道静脈瘤硬化療法—その適応と手技上のポイント
41巻9号(1986年8月発行)
特集 悪性腫瘍を疑うX線像
41巻8号(1986年7月発行)
特集 重症患者の輸液・栄養
41巻7号(1986年6月発行)
特集 肛門部疾患診療のテクニック
41巻6号(1986年6月発行)
特集 外科患者・薬物療法マニュアル
41巻5号(1986年5月発行)
特集 甲状腺癌の診断と治療
41巻4号(1986年4月発行)
特集 食道癌手術手技上のポイント
41巻3号(1986年3月発行)
特集 糖尿病合併患者の手術と管理
41巻2号(1986年2月発行)
特集 Borrmann 4型胃癌—私の治療
41巻1号(1986年1月発行)
特集 胆嚢隆起性病変をどうするか
40巻13号(1985年12月発行)
特集 肝内胆石に対する胆道ドレナージ手術
40巻12号(1985年11月発行)
特集 肝硬変合併患者の手術と管理
40巻11号(1985年10月発行)
特集 消化器外科医のための血管外科手技
40巻10号(1985年9月発行)
特集 症例による急性腹症の画像診断
40巻9号(1985年8月発行)
特集 Iatrogenic Abdominal Trauma—その予防と対策
40巻8号(1985年7月発行)
特集 噴門部癌の手術術式—適応と根拠
40巻6号(1985年6月発行)
特集 がん・画像診断の死角
40巻7号(1985年6月発行)
特集 鼎談・高齢者の消化管手術—手術適応のボーダーライン
40巻5号(1985年5月発行)
特集 膵頭十二指腸切除後の再建法のポイント
40巻4号(1985年4月発行)
特集 急性虫垂炎の臨床
40巻3号(1985年3月発行)
特集 癌のSurgical Emergencies
40巻2号(1985年2月発行)
特集 腹膜炎治療のノウ・ハウ
40巻1号(1985年1月発行)
特集 最近の経腸栄養法と外科
39巻12号(1984年12月発行)
特集 大腸切除と機能温存
39巻11号(1984年11月発行)
特集 胃癌—最近の話題
39巻10号(1984年10月発行)
特集 胆管癌の外科
39巻9号(1984年9月発行)
特集 どこまで活用できるか新しい手術器械
39巻8号(1984年8月発行)
特集 外傷の総合画像診断と初療
39巻7号(1984年7月発行)
特集 肝臓癌のTAE療法
39巻6号(1984年6月発行)
特集 〔Q & A〕術中トラブル対処法—私はこうしている
39巻5号(1984年5月発行)
特集 外科におけるクリティカル・ケア
39巻4号(1984年4月発行)
特集 臓器移植の最前線
39巻3号(1984年3月発行)
特集 外科感染症と免疫
39巻2号(1984年2月発行)
特集 がんの集学的治療をどうするか
39巻1号(1984年1月発行)
特集 今日の肺癌
38巻12号(1983年12月発行)
特集 プラスマフェレーシス
38巻11号(1983年11月発行)
特集 胃・十二指腸潰瘍
38巻10号(1983年10月発行)
特集 下部消化管出血
38巻9号(1983年9月発行)
特集 肝硬変と手術
38巻8号(1983年8月発行)
特集 臓器全摘後の病態と管理
38巻7号(1983年7月発行)
特集 鼠径・大腿ヘルニアの話題
38巻6号(1983年6月発行)
特集 吻合法—目でみるポイントとコツ
38巻5号(1983年5月発行)
特集 緊急減黄術—テクニックとそのコツ
38巻4号(1983年4月発行)
特集 癌手術と再建
38巻3号(1983年3月発行)
特集 腹部外傷の超音波診断
38巻2号(1983年2月発行)
特集 脾摘をめぐる話題
38巻1号(1983年1月発行)
特集 よくみる肛門部疾患診療のポイント
37巻12号(1982年12月発行)
特集 膵・胆管合流異常の外科
37巻11号(1982年11月発行)
特集 末梢血管障害の非侵襲的検査法
37巻10号(1982年10月発行)
特集 新しい抗生物質と外科
37巻9号(1982年9月発行)
特集 Controversy;皮切と到達経路
37巻8号(1982年8月発行)
特集 今日の人工肛門
37巻7号(1982年7月発行)
特集 胆石症をめぐる最近の話題
37巻6号(1982年6月発行)
特集 乳癌の縮小根治手術
37巻5号(1982年5月発行)
特集 外科外来マニュアル
37巻4号(1982年4月発行)
特集 レーザーと外科
37巻3号(1982年3月発行)
特集 人工呼吸管理のPit fall
37巻2号(1982年2月発行)
特集 食道静脈瘤手術
37巻1号(1982年1月発行)
特集 術中エコー
36巻12号(1981年12月発行)
特集 インスリン併用の高カロリー栄養法
36巻11号(1981年11月発行)
特集 迷切後の諸問題
36巻10号(1981年10月発行)
特集 膵炎診療のControversy
36巻9号(1981年9月発行)
特集 上部胆管癌の外科
36巻8号(1981年8月発行)
特集 手指の外傷—初期診療の実際
36巻7号(1981年7月発行)
特集 上部消化管出血—保存的止血法のトピックス
36巻6号(1981年6月発行)
特集 外傷の画像診断
36巻5号(1981年5月発行)
特集 Multiple Organ Failure
36巻4号(1981年4月発行)
特集 術後1週間の患者管理
36巻3号(1981年3月発行)
特集 晩期癌患者のcare
36巻2号(1981年2月発行)
特集 胃癌のAdjuvant Chemotherapy
36巻1号(1981年1月発行)
特集 RI診断の進歩
35巻12号(1980年12月発行)
特集 癌と栄養
35巻11号(1980年11月発行)
特集 私の縫合材料と縫合法
35巻10号(1980年10月発行)
特集 胆道ドレナージに伴うトラブル
35巻9号(1980年9月発行)
特集 消化管手術と器械吻合
35巻8号(1980年8月発行)
特集 閉塞性黄疸—最近の診断法の進歩
35巻7号(1980年7月発行)
特集 大腸癌根治手術の再検討—ポリペクトミーから拡大郭清まで
35巻6号(1980年6月発行)
特集 最近の呼吸管理法をめぐるQ&A
35巻5号(1980年5月発行)
特集 癌のリンパ節郭清をどうするか
35巻4号(1980年4月発行)
特集 膵癌と膵頭十二指腸切除術
35巻3号(1980年3月発行)
特集 血管カテーテルの治療への応用
35巻2号(1980年2月発行)
特集 外科医のための麻酔
35巻1号(1980年1月発行)
特集 遺残胆石
34巻12号(1979年12月発行)
特集 噴門部癌の特性と外科治療
34巻11号(1979年11月発行)
特集 熱傷治療のトピックス
34巻10号(1979年10月発行)
特集 急性胆嚢炎の治療
34巻9号(1979年9月発行)
特集 手術と抗生物質
34巻8号(1979年8月発行)
特集 術中・術後の出血
34巻7号(1979年7月発行)
特集 Crohn病とその辺縁疾患
34巻6号(1979年6月発行)
特集 これだけは知っておきたい手術の適応とタイミング—注意したい疾患45
34巻5号(1979年5月発行)
特集 外科と血管造影—〈読影のポイント,鑑別のコツ〉
34巻4号(1979年4月発行)
特集 Elemental Diet
34巻3号(1979年3月発行)
特集 成分輸血
34巻2号(1979年2月発行)
特集 外科とエコー
34巻1号(1979年1月発行)
特集 ショックをめぐる新しい話題
33巻12号(1978年12月発行)
特集 非定形的乳切の術式と適応
33巻11号(1978年11月発行)
特集 検査と合併症—おこさないためには、おこしてしまったら
33巻10号(1978年10月発行)
特集 今日の癌免疫療法
33巻9号(1978年9月発行)
特集 食道癌手術の近況
33巻8号(1978年8月発行)
特集 老年者の手術—併存疾患の診かた・とらえ方
33巻7号(1978年7月発行)
特集 臓器大量切除と栄養
33巻6号(1978年6月発行)
特集 T-tubeと胆道鏡
33巻5号(1978年5月発行)
特集 乳幼児急性腹症—診断のポイントとfirst aid
33巻4号(1978年4月発行)
特集 術後呼吸障害とその管理
33巻3号(1978年3月発行)
特集 CTスキャン
33巻2号(1978年2月発行)
特集 消化性潰瘍と迷切術
33巻1号(1978年1月発行)
特集 最近の手術材料と器具
32巻12号(1977年12月発行)
特集 目でみる話題の消化器手術
32巻11号(1977年11月発行)
特集 Biopsyの再検討
32巻10号(1977年10月発行)
特集 肺癌—新しい診療のポイント
32巻9号(1977年9月発行)
特集 逆流性食道炎
32巻8号(1977年8月発行)
特集 上部消化管大量出血
32巻7号(1977年7月発行)
特集 甲状腺機能亢進症—外科医の役割
32巻6号(1977年6月発行)
特集 今日の胆道造影
32巻5号(1977年5月発行)
特集 非癌性乳腺疾患の外科
32巻4号(1977年4月発行)
特集 ヘルニア再検討
32巻3号(1977年3月発行)
特集 外科と薬剤
32巻2号(1977年2月発行)
特集 腹部手術後の輸液—私はこうしている
32巻1号(1977年1月発行)
特集 人工肛門のAfter Care
31巻12号(1976年12月発行)
特集 胆道手術後の困難症
31巻11号(1976年11月発行)
特集 術後の急性機能不全
31巻10号(1976年10月発行)
特集 肝切除の術式
31巻9号(1976年9月発行)
特集 進行胃癌の化学療法
31巻8号(1976年8月発行)
特集 特殊な消化性潰瘍
31巻7号(1976年7月発行)
特集 重度外傷
31巻6号(1976年6月発行)
特集 早期大腸癌の外科
31巻5号(1976年5月発行)
特集 大量輸血
31巻4号(1976年4月発行)
特集 手術とHyperalimentation
31巻3号(1976年3月発行)
特集 急性腹症のX線像
31巻2号(1976年2月発行)
特集 手術と肝障害
31巻1号(1976年1月発行)
特集 遠隔成績よりみた早期胃癌
30巻12号(1975年12月発行)
特集 脳卒中の外科
30巻11号(1975年11月発行)
特集 癌免疫と外科治療
30巻10号(1975年10月発行)
特集 凍結外科—Cryosurgery
30巻9号(1975年9月発行)
特集 縫合法—反省と再検討
30巻8号(1975年8月発行)
特集 消化管の創傷治癒
30巻7号(1975年7月発行)
特集 手術と副損傷
30巻6号(1975年6月発行)
特集 乳癌—最近の趨勢
30巻5号(1975年5月発行)
特集 胃切除後にくるもの—その対策と治療
30巻4号(1975年4月発行)
特集 腹部外科のPhysical Signs
30巻3号(1975年3月発行)
特集 閉塞性黄疸
30巻2号(1975年2月発行)
特集 ショック治療の新しい考え方
30巻1号(1975年1月発行)
特集 手の外科
29巻12号(1974年12月発行)
特集 一般外科医のための小児外科
29巻11号(1974年11月発行)
特集 外科と血栓
29巻9号(1974年10月発行)
29巻8号(1974年8月発行)
特集 外傷救急診療におけるDo's & Don'ts
29巻7号(1974年7月発行)
特集 痔核と痔瘻の外科
29巻6号(1974年6月発行)
特集 胸部食道癌の外科
29巻5号(1974年5月発行)
特集 老人外科—老年者胆道系疾患の外科
29巻4号(1974年4月発行)
特集 腹部緊急疾患におけるDo's & Don'ts
29巻3号(1974年3月発行)
特集 胃全剔
29巻2号(1974年2月発行)
特集 消化管手術と内視鏡
29巻1号(1974年1月発行)
特集 外科とME—その現況と将来
28巻12号(1973年12月発行)
特集 外科と栄養—高カロリー輸液の問題点
28巻11号(1973年11月発行)
特集 膵炎の外科
28巻10号(1973年10月発行)
特集 外科医のための臨床検査
28巻9号(1973年9月発行)
28巻8号(1973年8月発行)
特集 急性腹膜炎
28巻7号(1973年7月発行)
特集 再発癌—follow-upとその治療
28巻6号(1973年6月発行)
特集 麻酔—外科医のために
28巻5号(1973年5月発行)
特集 外科と感染—その基本的対策とPitfall
28巻4号(1973年4月発行)
特集 術後ドレナージの実際
28巻3号(1973年3月発行)
特集 肝癌の外科
28巻2号(1973年2月発行)
特集 今日の救急
28巻1号(1973年1月発行)
特集 外科と大腸—癌とポリープを中心に
27巻12号(1972年12月発行)
特集 外科と大腸—炎症性疾患を中心に
27巻11号(1972年11月発行)
特集 末梢血管の外科
27巻10号(1972年10月発行)
特集 頸部血管障害
27巻9号(1972年9月発行)
特集 出血治療のPitfall
27巻8号(1972年8月発行)
特集 胆道外科のPitfall
27巻7号(1972年7月発行)
特集 皮膚切開法と到達法・Ⅱ
27巻6号(1972年6月発行)
特集 皮膚切開法と到達法・Ⅰ
27巻5号(1972年5月発行)
特集 日常外科の総点検・Ⅱ
27巻4号(1972年4月発行)
特集 日常外科の総点検・Ⅰ
27巻3号(1972年3月発行)
特集 黄疸の外科
27巻2号(1972年2月発行)
特集 瘻—その問題点
27巻1号(1972年1月発行)
特集 早期癌の外科治療
26巻12号(1971年12月発行)
特集 胃癌根治手術の問題点
26巻11号(1971年11月発行)
特集 小児外科の焦点
26巻10号(1971年10月発行)
26巻9号(1971年9月発行)
特集 上腹部痛—誤りやすい疾患の診療
26巻8号(1971年8月発行)
特集 今日の外傷—外傷患者の初診と初療
26巻7号(1971年7月発行)
26巻6号(1971年6月発行)
特集 手術とその根拠・Ⅱ
26巻5号(1971年5月発行)
特集 手術とその根拠・Ⅰ
26巻4号(1971年4月発行)
特集 外科とくすり—副作用と適正な使用法
26巻3号(1971年3月発行)
特集 緊急手術後の合併症・Ⅱ
26巻2号(1971年2月発行)
特集 緊急手術後の合併症・Ⅰ
26巻1号(1971年1月発行)
特集 これからの外科
25巻12号(1970年12月発行)
特集 Silent Disease
25巻11号(1970年11月発行)
特集 輸液の臨床
25巻10号(1970年10月発行)
特集 熱傷の早期治療
25巻9号(1970年9月発行)
特集 術後早期の再手術
25巻8号(1970年8月発行)
特集 縫合糸の問題点
25巻7号(1970年7月発行)
特集 腫瘍の病理と臨床
25巻6号(1970年6月発行)
特集 縫合不全
25巻5号(1970年5月発行)
特集 外科領域における感染症
25巻4号(1970年4月発行)
特集 心臓と血管の外科
25巻3号(1970年3月発行)
特集 手術と出血対策Ⅱ
25巻2号(1970年2月発行)
特集 手術と出血対策Ⅰ
25巻1号(1970年1月発行)
特集 特殊な輸血とその現況
24巻12号(1969年12月発行)
特集 全身状態とSurgical Risk
24巻11号(1969年11月発行)
特集 腸瘻の問題点
24巻10号(1969年10月発行)
特集 緊急手術の手技・Ⅱ
24巻9号(1969年9月発行)
特集 緊急手術の手技・Ⅰ
24巻8号(1969年8月発行)
特集 良性腫瘍
24巻7号(1969年7月発行)
24巻6号(1969年6月発行)
24巻5号(1969年5月発行)
特集 臨床麻酔の問題点
24巻4号(1969年4月発行)
特集 緊急手術適応のきめ手
24巻3号(1969年3月発行)
特集 消化器疾患の新しい診断法
24巻2号(1969年2月発行)
特集 乳腺疾患—その診療の進歩
24巻1号(1969年1月発行)
特集 人工臓器への歩み
23巻13号(1968年12月発行)
特集 癌外科の進歩—現状と将来
23巻12号(1968年11月発行)
特集 顔面損傷のファースト・エイド
23巻11号(1968年10月発行)
特集 Encephalopathyの臨床
23巻10号(1968年9月発行)
特集 肛門外科
23巻9号(1968年8月発行)
特集 脈管造影
23巻8号(1968年7月発行)
特集 膵・胆・肝の外科
23巻7号(1968年6月発行)
特集 手と足の外傷
23巻6号(1968年6月発行)
特集 木本誠二教授退官記念特集
23巻5号(1968年5月発行)
特集 臓器移植の可能性
23巻4号(1968年4月発行)
特集 最良の手術時点
23巻3号(1968年3月発行)
特集 術後困難症の処置
23巻2号(1968年2月発行)
特集 出血の問題点
23巻1号(1968年1月発行)
特集 初療の要点
22巻12号(1967年12月発行)
特集 鞭打ち損傷の問題点
22巻11号(1967年11月発行)
特集 肝腫瘍外科の課題
22巻10号(1967年10月発行)
特集 イレウスの治療—その困難な問題点
22巻9号(1967年9月発行)
特集 甲状腺疾患の問題点
22巻8号(1967年8月発行)
特集 胃・十二指腸潰瘍の手術
22巻7号(1967年7月発行)
特集 救急患者の取扱い方
22巻6号(1967年6月発行)
特集 血管の外科
22巻5号(1967年5月発行)
特集 胆石症手術の問題点
22巻4号(1967年4月発行)
特集 進行性消化器癌の外科
22巻3号(1967年3月発行)
特集 頭部外傷処置の実際
22巻2号(1967年2月発行)
特集 臨床検査後の偶発症
22巻1号(1967年1月発行)
特集 鼠径・陰嚢ヘルニアの問題点
21巻12号(1966年12月発行)
特集 虫垂炎—その困難な問題点
21巻11号(1966年11月発行)
特集 小児疾患の早期診断と手術適応
21巻10号(1966年10月発行)
21巻9号(1966年9月発行)
21巻8号(1966年8月発行)
特集 腫瘍の外科
21巻7号(1966年7月発行)
21巻6号(1966年6月発行)
21巻5号(1966年5月発行)
特集 癌患者の栄養問題
21巻4号(1966年4月発行)
特集 胃手術後の困難症
21巻3号(1966年3月発行)
21巻2号(1966年2月発行)
特集 癌の補助療法・2
21巻1号(1966年1月発行)
特集 癌の補助療法・1
20巻12号(1965年12月発行)
20巻11号(1965年11月発行)
特集 熱傷の治療
20巻10号(1965年10月発行)
20巻9号(1965年9月発行)
特集 腹部外科の臨床
20巻8号(1965年8月発行)
特集 癌手術例の検討
20巻7号(1965年7月発行)
特集 術後感染症
20巻6号(1965年6月発行)
特集 腹部疾患縫合不全
20巻5号(1965年5月発行)
特集 胸部疾患縫合不全
20巻4号(1965年4月発行)
20巻3号(1965年3月発行)
20巻2号(1965年2月発行)
特集 外科と内分泌・2
20巻1号(1965年1月発行)
特集 外科と内分泌・1
19巻12号(1964年12月発行)
特集 外科と保険診療
19巻11号(1964年11月発行)
19巻10号(1964年10月発行)
19巻9号(1964年9月発行)
特集 脳・頸部・胸部の症例
19巻8号(1964年8月発行)
特集 小児外科
19巻7号(1964年7月発行)
19巻6号(1964年6月発行)
特集 外傷の救急処置
19巻5号(1964年5月発行)
特集 癌の治療成績の向上
19巻4号(1964年4月発行)
19巻3号(1964年3月発行)
19巻2号(1964年2月発行)
19巻1号(1964年1月発行)
18巻12号(1963年12月発行)
18巻11号(1963年11月発行)
18巻10号(1963年10月発行)
特集 整形外科症例集
18巻9号(1963年9月発行)
18巻8号(1963年8月発行)
18巻7号(1963年7月発行)
18巻6号(1963年6月発行)
18巻5号(1963年5月発行)
18巻4号(1963年4月発行)
18巻3号(1963年3月発行)
18巻2号(1963年2月発行)
18巻1号(1963年1月発行)
17巻12号(1962年12月発行)
17巻11号(1962年11月発行)
17巻10号(1962年10月発行)
特集 麻酔
17巻9号(1962年9月発行)
17巻8号(1962年8月発行)
特集 手こずつた症例―私の経験した診断治療上の困難症(Ⅱ)
17巻7号(1962年7月発行)
17巻6号(1962年6月発行)
特集 手こずつた症例―私の経験した診断治療上の困難症(Ⅰ)
17巻5号(1962年5月発行)
17巻4号(1962年4月発行)
17巻3号(1962年3月発行)
17巻2号(1962年2月発行)
17巻1号(1962年1月発行)
16巻12号(1961年12月発行)
16巻11号(1961年11月発行)
16巻10号(1961年10月発行)
16巻9号(1961年9月発行)
16巻8号(1961年8月発行)
16巻7号(1961年7月発行)
16巻6号(1961年6月発行)
16巻5号(1961年5月発行)
16巻4号(1961年4月発行)
16巻3号(1961年3月発行)
16巻2号(1961年2月発行)
16巻1号(1961年1月発行)
15巻12号(1960年12月発行)
15巻11号(1960年11月発行)
15巻10号(1960年10月発行)
15巻9号(1960年9月発行)
15巻8号(1960年8月発行)
15巻7号(1960年7月発行)
15巻6号(1960年6月発行)
15巻5号(1960年5月発行)
15巻4号(1960年4月発行)
15巻3号(1960年3月発行)
15巻2号(1960年2月発行)
15巻1号(1960年1月発行)
14巻12号(1959年12月発行)
14巻11号(1959年11月発行)
14巻10号(1959年10月発行)
14巻9号(1959年9月発行)
14巻8号(1959年8月発行)
14巻7号(1959年7月発行)
14巻6号(1959年6月発行)
14巻5号(1959年5月発行)
14巻4号(1959年4月発行)
14巻3号(1959年3月発行)
特集 腹部外科
14巻2号(1959年2月発行)
14巻1号(1959年1月発行)
13巻12号(1958年12月発行)
13巻11号(1958年11月発行)
13巻10号(1958年10月発行)
13巻9号(1958年9月発行)
13巻8号(1958年8月発行)
13巻7号(1958年7月発行)
特集 外科的・内科的療法の限界・2
13巻6号(1958年6月発行)
13巻5号(1958年5月発行)
特集 外科的・内科的療法の限界
13巻4号(1958年4月発行)
13巻3号(1958年3月発行)
13巻2号(1958年2月発行)
特集 腫瘍
13巻1号(1958年1月発行)
12巻12号(1957年12月発行)
12巻11号(1957年11月発行)
特集 乳腺腫瘍
12巻10号(1957年10月発行)
12巻9号(1957年9月発行)
12巻8号(1957年8月発行)
12巻7号(1957年7月発行)
12巻6号(1957年6月発行)
12巻5号(1957年5月発行)
12巻4号(1957年4月発行)
特集 腫瘍
12巻3号(1957年3月発行)
12巻2号(1957年2月発行)
12巻1号(1957年1月発行)
11巻13号(1956年12月発行)
特集 吐血と下血
11巻12号(1956年12月発行)
11巻11号(1956年11月発行)
11巻10号(1956年10月発行)
11巻9号(1956年9月発行)
11巻8号(1956年8月発行)
11巻7号(1956年7月発行)
11巻6号(1956年6月発行)
11巻5号(1956年5月発行)
11巻4号(1956年4月発行)
11巻3号(1956年3月発行)
11巻2号(1956年2月発行)
11巻1号(1956年1月発行)
10巻13号(1955年12月発行)
10巻11号(1955年11月発行)
特集 偶發症との救急處置
10巻12号(1955年11月発行)
10巻10号(1955年10月発行)
10巻9号(1955年9月発行)
10巻8号(1955年8月発行)
10巻7号(1955年7月発行)
10巻6号(1955年6月発行)
10巻5号(1955年5月発行)
10巻4号(1955年4月発行)
10巻3号(1955年3月発行)
10巻2号(1955年2月発行)
10巻1号(1955年1月発行)
9巻12号(1954年12月発行)
9巻11号(1954年11月発行)
特集 整形外科特集号
9巻10号(1954年10月発行)
9巻9号(1954年9月発行)
特集 慢性胃炎と胃潰瘍
9巻8号(1954年8月発行)
9巻7号(1954年7月発行)
9巻6号(1954年6月発行)
9巻5号(1954年5月発行)
9巻4号(1954年4月発行)
9巻3号(1954年3月発行)
9巻2号(1954年2月発行)
9巻1号(1954年1月発行)
8巻13号(1953年12月発行)
特集 頸部外科臨床の進歩
8巻12号(1953年12月発行)
8巻11号(1953年11月発行)
8巻10号(1953年10月発行)
8巻9号(1953年9月発行)
特集 最新の麻醉
8巻8号(1953年8月発行)
特集 輸血・輸液の諸問題
8巻7号(1953年7月発行)
8巻6号(1953年6月発行)
8巻5号(1953年5月発行)
8巻4号(1953年4月発行)
8巻3号(1953年3月発行)
8巻2号(1953年2月発行)
8巻1号(1953年1月発行)
7巻13号(1952年12月発行)
7巻12号(1952年11月発行)
7巻11号(1952年11月発行)
特集 上腹部外科臨床の進歩
7巻10号(1952年10月発行)
7巻9号(1952年9月発行)
7巻8号(1952年8月発行)
7巻7号(1952年7月発行)
7巻6号(1952年6月発行)
7巻5号(1952年5月発行)
7巻4号(1952年4月発行)
7巻3号(1952年3月発行)
7巻2号(1952年2月発行)
7巻1号(1952年1月発行)
6巻12号(1951年12月発行)
6巻11号(1951年11月発行)
6巻10号(1951年10月発行)
6巻9号(1951年9月発行)
6巻8号(1951年8月発行)
6巻7号(1951年7月発行)
6巻6号(1951年6月発行)
6巻5号(1951年5月発行)
6巻4号(1951年4月発行)
6巻3号(1951年3月発行)
6巻2号(1951年2月発行)
6巻1号(1951年1月発行)
5巻12号(1950年12月発行)
5巻11号(1950年11月発行)
5巻10号(1950年10月発行)
5巻9号(1950年9月発行)
特集 蛋白・3
5巻8号(1950年8月発行)
特集 蛋白・2
5巻7号(1950年7月発行)
特集 蛋白問題・1
5巻6号(1950年6月発行)
5巻5号(1950年5月発行)
特集 Cancer・2
5巻4号(1950年4月発行)
特集 Cancer・1
5巻3号(1950年3月発行)
5巻2号(1950年2月発行)
5巻1号(1950年1月発行)
4巻12号(1949年12月発行)
4巻11号(1949年11月発行)
4巻10号(1949年10月発行)
4巻9号(1949年9月発行)
4巻8号(1949年8月発行)
4巻7号(1949年7月発行)
4巻6号(1949年6月発行)
4巻5号(1949年5月発行)
4巻4号(1949年4月発行)
4巻3号(1949年3月発行)
4巻2号(1949年2月発行)
4巻1号(1949年1月発行)
