周術期管理は外科医にとって必須の仕事ですが,医療が多様化した現在においては必要とされる知識は広範に及びます.また,周術期管理の進歩の中で,非常に専門的な技術や知識を必要とする特殊な治療法も行われるようになっています.5年前に本書が取り上げたenhanced recovery after surgery(ERAS)の概念は広く普及し,日常診療に取り入れられています.
「周術期管理マニュアル」としては5年ぶりの刊行となる本増刊号では,この5年間の周術期管理の進歩を網羅的にupdateするばかりでなく,“すぐに使える”ことを念頭に,術式ごとの周術期管理のめやすを視覚的なチャートにまとめて提示するとともに,薬物療法についてはできるだけ具体的な処方を記載するようにしました.また,特に重要な合併症,専門性の高い治療法に焦点を当て,臨床医にとって活用しやすく,かつインパクトの高い周術期管理マニュアルをめざしました.
雑誌目次
臨床外科74巻11号
2019年10月発行
雑誌目次
増刊号 すぐに使える周術期管理マニュアル
序 フリーアクセス
著者: 橋口陽二郎
ページ範囲:P.1 - P.1
Ⅰ章 周術期管理・総論
ERASの現状
著者: 福島亮治
ページ範囲:P.8 - P.10
ERASは,enhanced recovery after surgeryの頭文字をとった周術期管理プログラムであり,欧州で商標登録されている.わが国では“術後回復力強化プログラム”などと翻訳されることが多い.一言でいえば“早く合併症を起こすことなく回復し,早く退院できるようなプログラム”である.その目的を達成するためにevidence basedの,さまざまな周術期管理法(elements)を集学的に実行する.“fast-track surgery”,“enforced multimodal rehabilitation program”,“accelerated rehabilitation care”などとも呼ばれ,世界的にその普及がすすんできた.わが国でも日本外科代謝栄養学会がESSENSE(ESsential Strategy for Early Normalization after Surgery with patient's Excellent satisfaction)プロジェクトを立ち上げている1).
本稿では,ERASのこれまでの歩みと現状について概説する.
術前術後栄養管理
著者: 牛久秀樹 , 比企直樹 , 細田桂 , 新原正大 , 櫻谷美貴子 , 鷲尾真理愛 , 原田宏輝 , 山下継史
ページ範囲:P.11 - P.14
術前栄養管理
●術前栄養管理の必要性
栄養不良患者は創傷治癒の遅延や術後の感染性合併症の発生率が高く,術後死亡率の増大,入院期間の延長,医療費の増大に繋がる1〜3).積極的な栄養管理を行うことにより改善が期待できるという報告もある4,5).
高度栄養不良患者には,手術を遅らせても10〜14日間の術前栄養管理を行うことが推奨されている6).
輸液管理
著者: 鍋谷圭宏 , 坂本昭雄
ページ範囲:P.15 - P.18
周術期輸液管理の意義
近年,消化器外科を含むさまざまな外科手術において,Enhanced Recovery after Surgery(ERAS®)やわが国の“ESsential Strategy for Early Normalization after Surgery with patient's Excellent satisfaction(ESSENSE)”など術後回復促進プログラムが導入されている1〜3).周術期には腸を使う栄養管理がまず選択され,術前後の絶飲食期間が短くなった.それに伴い,輸液を要する期間も短くなったが,より一層適時適切な管理が求められるようになった.
周術期の輸液管理の目的は,①水分・電解質補給と②栄養(エネルギー)投与であるが,消化器外科患者以外は積極的に②を目指す必要性は低いと思われる.そこで本稿では,栄養管理としての輸液を要する消化器外科周術期を念頭におき,最近の知見を踏まえた輸液管理の適応・意義やその実際など(表1)を概説する.
輸血療法
著者: 河野武弘
ページ範囲:P.19 - P.23
周術期における輸血療法の概要
輸血療法は,量的に減少,または機能的に低下した血液成分を補充することによって臨床症状の改善を図る補充療法であり,他家血輸血においては成分輸血を原則とする.輸血用血液製剤は,日本赤十字社によって,献血者から提供された血液から製造される.その過程には,国が定めた採血基準と受血者の安全確保のための基準を満たした献血受付,病原体検査等の安全性確認,副作用予防のための白血球除去や,放射線照射等を含み,製造された輸血用血液製剤は,最適な条件で保管され,医療機関からの発注に基づいて地域の血液センターより供給される.
輸血療法には,安全で適正な実施が求められている.法的には,「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(血液法)」は,血液製剤の適正な使用と安全性に関する情報の収集及び提供に努めることを医療関係者の責務と定めている.また,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法,旧薬事法)」は,輸血用血液製剤を「特定生物由来製品」と定義し,その使用の際に,表示事項の把握,患者(またはその家族)に製品のリスクとベネフィットについての説明,記録の作成及び保管(20年間),副作用等の報告を義務付けている.
疼痛管理
著者: 柿沼玲史
ページ範囲:P.24 - P.29
周術期の痛みと鎮痛の意義
消化器外科領域では,術式の低侵襲化とともに術後回復能力強化プログラム(enhanced recovery after surgery:ERAS®)が確立されつつある1).術後の離床促進と消化管機能障害の回避がポイントであり,鎮痛の質が大きく関与する.本稿ではERASの観点を踏まえた周術期の疼痛管理について述べる.
周術期感染対策
著者: 宮崎安弘 , 黒川幸典 , 高橋剛 , 牧野知紀 , 田中晃司 , 山﨑誠 , 土岐祐一郎
ページ範囲:P.30 - P.34
周術期感染症の合併は患者の苦痛・QOLの低下につながるだけではなく,入院期間の延長・再入院率の増加,ひいてはそれに伴う医療費の増大,加えて抗菌薬使用量の増加,死亡率の増加など多くの不利益につながることから,感染対策は周術期管理の中でも最も重要なものの1つである.
術後に起きる感染症は,手術操作を直接加えた部位に起こる手術部位感染(surgical site infections:SSI)と呼吸器感染・尿路感染・血流感染などの遠隔部位感染(remote infections)とに分けられる1).食道癌術後呼吸器感染や中心静脈栄養管理中の血流感染などが遠隔部位感染に該当するが,これらは他稿あるいは他誌を参照されたい.
周術期静脈血栓症対策
著者: 瀧井康公 , 丸山聡 , 野上仁
ページ範囲:P.35 - P.38
脈血栓症とは
肺血栓塞栓症(pulmonary thromboembolism:PTE)は発症する頻度は少ないが,周術期に一旦起きると致死率の高い疾患として,一般・消化器外科医が頭に入れておくべき病態である.その原因と考えられている深部静脈血栓症(deep vein thrombosis:DVT)とともに,静脈血栓塞栓症(venous thromboembolism:VTE)と総称されている.症状の有無により,症候性VTEと無症候性VTEとも分類される.
術前リスクスコア
著者: 端山軍 , 松田圭二 , 大野航平 , 岡田有加 , 八木貴博 , 福島慶久 , 島田竜 , 小澤毅士 , 土屋剛史 , 野澤慶次郎 , 橋口陽二郎
ページ範囲:P.39 - P.41
さまざまなリスクスコア
術前に患者の全身状態を把握し手術に対するリスクを評価することは術後合併症を減少させるうえで非常に重要である.
患者の術前状態や手術の侵襲をスコアし術前のリスクを客観的に評価する方法として,1963年に米国から発表されたASA(American Society of Anesthesiologists physiological status classification)-PS(physical status)1):米国麻酔学会術前状態分類や,1991年に英国で発表されたPOSSUM(Physiological and Operative Severity Score for the enumeration of mortality and morbidity)2),1997年に米国で発表されたVAスコア,1999年に発表されたE-PASS(Estimation of Ability and Surgical Stress)3),2004年にイタリアで発表されたDonati Model4),などが考案され用いられている.
Ⅱ章 併存症をもつ患者の評価とその術前・術後管理 心疾患
心疾患・心不全
著者: 尾澤直美 , 下川智樹
ページ範囲:P.47 - P.49
術前評価
周術期の心合併症予測は,「非心臓手術内容に基づく評価」と「心疾患に基づく評価」とで行い,必要に応じて以下の検査を行う(図1).
高血圧
著者: 近田正英
ページ範囲:P.50 - P.51
術前評価
●高血圧は,本邦を含めた世界のガイドラインで,収縮期血圧140 mmHg以上,拡張期血圧90 mmHg以上と定義されている.至適血圧といわれる収縮期血圧120 mmHg未満,拡張期血圧80 mmHg未満を超えて血圧が上昇するほど心筋梗塞,脳卒中,慢性腎臓病などの罹患リスクと死亡リスクが高くなる.
●高血圧を呈する患者では,まず一般的な検査として,血液生化学検査で糖尿病,高脂血症,高尿酸血症,腎機能障害を精査する.次に,胸部X線写真,心電図で大動脈疾患,心筋梗塞,不整脈の有無を検索する.
呼吸器疾患
慢性閉塞性肺疾患
著者: 松谷哲行
ページ範囲:P.53 - P.55
術前評価
●慢性閉塞性肺疾患(COPD)は,「タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することなどにより生じる肺疾患であり,呼吸機能検査で気流閉塞を示す.気流閉塞は末梢気道病変と気腫性病変が様々な割合で複合的に関与し起こる.臨床的には,徐々に進行する労作時の呼吸困難や慢性の咳・痰を示すが,これらの症状に乏しいこともある」と,日本呼吸器学会で定義されている1).
●気管支拡張薬吸入後の呼吸機能検査(スパイロメトリー)で一秒率(FEV1.0/FVC)が70%未満であることでCOPDの診断となり,%FEV1.0の値で病期分類される(表1)1).
気管支喘息
著者: 松谷哲行
ページ範囲:P.56 - P.58
術前評価
●気管支喘息は,「気道の慢性炎症を本態とし,変動性を持った気道狭窄(喘鳴,呼吸困難)や咳などの臨床症状で特徴付けられた疾患」と日本アレルギー学会で定義されている1).
●病態の特徴は,「好酸球性気道炎症」「気道過敏性亢進」「可逆性気道狭窄」の3つである.
肝疾患
腎疾患
腎不全
著者: 金子智之 , 西松寛明 , 中川徹
ページ範囲:P.62 - P.64
術前評価
●腎機能評価と腎不全の定義
●慢性腎臓病(CKD)は,腎障害や腎機能の低下が持続する疾患である.CKDは,①GFR<60 mL/分/1.73 m2もしくは,②尿異常,画像診断,血液,病理で腎障害の存在が明らかな場合〔特に0.15 g/gCr以上のタンパク尿(30 mg/gCr以上のアルブミン尿)の存在が重要〕,のいずれかが3か月以上持続する状態と定義されている1).
透析患者
著者: 松本明彦 , 久米春喜 , 中川徹
ページ範囲:P.65 - P.67
術前評価
●抗凝固薬・抗血小板薬:服薬の有無を十分に問診する.術前の休薬期間や,代替薬への変更の可否を確認する1).
●心機能:心電図,心エコーで虚血性心疾患や弁膜症をスクリーニングし,所見に応じて循環器内科へコンサルトし,負荷心電図や冠動脈造影検査(CAG)での精査を行う1,2).
内分泌・代謝疾患
糖尿病
著者: 江戸直樹
ページ範囲:P.68 - P.69
術前評価
●糖尿病の病型や経過,合併症の有無についての問診を行う.
●1型糖尿病か2型糖尿病か? 糖尿病治療歴は? かかりつけ医から合併症についてどのような説明を受けているか.「糖尿病でかかりつけの診療を受けている」という単なる事実の確認だけで終わらず,必要に応じてかかりつけ医へ問い合わせを行う.
ステロイド投与例
著者: 篠崎大
ページ範囲:P.73 - P.74
ステロイドカバー
●副腎皮質ホルモンには,鉱質コルチコイド(アルドステロンなど),糖質コルチコイド(コルチゾールなど),性ホルモン(アンドロゲン,エストロゲンなど)がある.
●視床下部から副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)が分泌されると,下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌が促進される.ACTHは副腎皮質を刺激し,コルチゾールの分泌を促進する(視床下部・下垂体・副腎皮質系).コルチゾールは視床下部と脳下垂体前葉を抑制する(ネガティブフィードバック).
その他
脳梗塞
著者: 大井川秀聡
ページ範囲:P.75 - P.77
術前評価
●脳梗塞の既往のある患者は再発率も高く,周術期には脳梗塞の再発予防を考慮した全身管理が必要である.
●脳梗塞の再発は,発症後1週間以内が最も高率に認められるが,数か月間は依然として再発の危険性が高い状況にあると考えられる.再発率が低下するのは2〜3年後からとの報告もあり,少なくとも脳梗塞発症後1年未満の患者では手術時期を十分に検討する必要がある.
精神疾患
著者: 徳倉達也
ページ範囲:P.78 - P.80
術前評価
●精神疾患の診断は,アメリカ精神医学会が作成した精神医学的診断基準「Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed(DSM-5)」に基づいていることが多い.
●双極性障害は,双極性感情障害,躁うつ病とも呼称される.自閉スペクトラム症は,(厳密には議論があるが)広汎性発達障害,アスペルガー症候群などの概念も含む.
妊娠中
著者: 杉原武 , 木戸浩一郎 , 綾部琢哉
ページ範囲:P.81 - P.83
術前評価
●女性における妊娠は,ヒトが種として生命を紡いでいくために必要不可欠な状態であり,女性の体内に別の生命が存在する特殊な状況である.母体には解剖学的,生理的変化が起こっており,このことを十分に理解して周術期管理を行う必要がある.
●妊娠中の非産科手術の頻度は0.75%と報告1)されている.妊娠中に手術が必要となる状況は限られており,母体だけでなく胎児への影響も考えれば回避できるに越したことはない.そのなかで外科的な介入が必要な状況は,急性疾患あるいは悪性腫瘍に罹患した場合などが考えられる.急性疾患であればすべての時期にわたって緊急手術が必要となるが,悪性腫瘍であればその疾患における予後と在胎週数などを総合して個別に判断する必要がある.
高齢者
著者: 須田健 , 瀬下明良 , 土田明彦
ページ範囲:P.84 - P.85
術前評価
●高齢者の臨床的特徴として,①多くの臓器・組織に疾患を有している,②症状・経過が非定型的である,③薬物による副作用が出やすい,④うつ状態が症状を修飾する,⑤廃用性変化がみられる,⑥個人差が大きい,が挙げられる1).
●特に75歳以上の80.2%は2疾患以上,65%は3疾患以上の慢性疾患を併存している2).種々の生活機能障害を有するため,多角包括的に評価をする.
抗凝固薬・抗血小板薬使用時
著者: 新本春夫
ページ範囲:P.86 - P.89
術前評価
●抗凝固薬や抗血小板薬を内服している場合には,脳および心血管系の疾患に関する既往歴,治療歴を患者本人だけでなく家族からも入念に聴取することが肝要である.
●当該薬物を処方した医師に原疾患と現在の病状,薬剤の一時中止の可否,周術期の注意点や中止した場合の術後再開時期などを問い合わせる.
血液凝固異常(先天性)
著者: 川杉和夫
ページ範囲:P.90 - P.92
血液凝固異常のおもな疾患
先天性の血液凝固異常(血栓性素因)とは,生理的な凝固制御因子であるアンチトロンビン(antithrombin:AT),プロテインC(protein C:PC),プロテインS(protein S:PS)の遺伝子に異常が生じ,凝固を抑制するこれらの因子活性が低下して,血栓症を発症しやすい状態にあることを意味する.さらに,先天性血栓性素因の原因には,上記のほかにヘパリンコファクターⅡ欠乏症,プラスミノゲン異常症などの疾患も存在する.しかし,それら疾患は頻度的に非常に稀であり,また,病態として必ずしも確立されていない疾患も含まれており,先天性血栓性素因といえば,AT欠乏症,PC欠乏症,PS欠乏症を指すのが一般的である.
一方欧米では,凝固第Ⅴ因子ライデン変異1)(Factor Ⅴ Leiden;第Ⅴ因子506のArgがGlnに置換)が主要な先天性血栓性素因であり,白人の血栓症患者の10〜20%にも及んでいる.しかし,いまだに日本人においてはFactor Ⅴ Leidenが検出されておらず,本邦の患者に限れば,この疾患を現時点では考慮しなくてよい.
Ⅲ章 術式別の術前・術中・術後管理 食道
開胸食道切除術
著者: 加藤寛章 , 白石治 , 岩間密 , 安田篤 , 新海政幸 , 木村豊 , 安田卓司
ページ範囲:P.94 - P.97
術前管理
●術前検査
食道癌に対する食道切除術は,頸部,胸部,腹部と3領域にまたがる非常に高侵襲な手術であり,合併症が重篤化すると致死的になりうるリスクもあるため,術前には,全身状態・耐術能の評価に加え,術後肺炎を中心とした合併症のリスク評価と予防対策を行う.
一般的な術前検査(血液検査,尿検査,フローボリュームによる肺機能検査,心電図)に加え,高齢者や嚥下機能低下が疑われる場合は,嚥下造影検査(videofluoroscopic examination of swallowing:VF),嚥下内視鏡検査(videoendoscopic examination of swallowing:VE)による嚥下機能評価を行っている.当科の標準再建術式は胃管胸骨後挙上頸部吻合であるが,呼吸機能が低い場合や誤嚥リスクが高い場合は,癌の状態などと合わせて判断して,二期分割手術や,嚥下機能を温存するために高位胸腔内吻合などの術式を選択することになる.
胸腔鏡下食道切除術
著者: 菊池寛利 , 平松良浩 , 川田三四郎 , 神谷欣志 , 竹内裕也
ページ範囲:P.99 - P.102
術前管理
●外来初診時
採血,尿検査,胸腹部X線,心電図,呼吸機能検査などを行い,併存疾患の有無や呼吸機能などを評価する.可能であれば初診当日より周術期チームによる介入を開始する.食道癌の治療日記(当院作成)を渡し,手術に向けての治療計画の共有や患者の治療意識向上を図る(資料1).
喫煙中の場合には禁煙を徹底し,必要に応じて禁煙外来の受診を勧める.呼吸機能検査の結果にかかわらず,スーフル(ポーラファルマ)およびコーチ2(スミスメディカル)を購入していただき,使用法について動画を用いて説明し,呼吸機能訓練を開始する(図1).
縦隔鏡下食道切除術
著者: 小西博貴 , 藤原斉 , 塩崎敦 , 大辻英吾
ページ範囲:P.103 - P.105
術前管理
●術前評価:初診〜入院前
外来初診時には,採血・尿検査,心電図,呼吸機能検査などの術前一般検査を施行し,耐術能の評価を行う.未施行の画像検査があれば依頼する.
耳鼻科診察を依頼し,頭頸部領域の重複癌の有無や声帯運動の評価を行う.また,併存疾患・既往症に応じて,循環器内科や糖尿病内科などへの診察を依頼するとともに,術前に中止や変更の必要がある薬剤(抗凝固薬,内服血糖降下薬など)を確認する.
化学放射線療法後のsalvage手術
著者: 金森淳 , 小熊潤也 , 大幸宏幸
ページ範囲:P.106 - P.108
術前管理
食道癌の根治的化学放射線療法(dCRT)後の遺残・再発に対するsalvage手術は,日常診療の一つとなりつつある1).しかし,肺合併症などの術後合併症の発生頻度および在院死亡率は依然として高く,慎重な術前評価と周術期管理が求められる.近年,食道外科医だけでなく,看護師・薬剤師・歯科医師・理学療法士など多職種の周術期チームによる包括的な術前管理を行う施設が多くなってきている.通常の術前治療後の予定された食道切除と比較すると,salvage手術の場合,手術決定から手術日まで短期間であることが多く,患者や家族の治療意欲・理解に応じた,より綿密な介入が求められる.また,心肺への50 Gy以上の放射線照射により,心囊水や胸水の貯留を認める場合があり,術前に適宜ドレナージしておくことが重要である.
食道アカラシア
著者: 竹村雅至 , 瀧井麻美子 , 大嶋勉 , 田中芳憲 , 藤尾長久
ページ範囲:P.109 - P.111
食道アカラシアに対する治療は,内服治療・内視鏡的バルーン拡張術・開腹または腹腔鏡下筋層切開術・経口内視鏡的筋層切開術(Per oral endoscopic myotomy:POEM)があるが,最近ではPOEMが治療の主流になってきており,外科的治療を適応する症例は減少してきている1,2).しかし,外科的な筋層切開術が行われなくなったわけでは決してない.さらに,最近の外科的治療は腹腔鏡下に行われることが多く,開腹既往のある症例を除き開腹で行われることは非常に稀である.
どの症例に外科的治療を適応するかに関しての厳密な基準はないが,外科的な治療を適応する際には,①保存的治療が無効,②全身麻酔が可能な状態,③重篤な他臓器合併症がない,④アカラシアによる症状がある,などであるが,一方で外科的治療による様々な合併症の発症や,手術の結果によっては症状の改善に乏しい可能性や,術後に逆流性食道炎を生じることもあり,術前に十分説明をしたうえで適応するのは当然である.
食道裂孔ヘルニア(GERDを含む)
著者: 秋元俊亮 , 矢野文章 , 三森教雄
ページ範囲:P.112 - P.114
食道裂孔ヘルニア(胃食道逆流症:GERDを含む)は,上部消化管内視鏡検査数の増加や高齢化などによって,軽症例を含めると比較的頻繁に診断されるようになった.また,内視鏡外科手術に関するアンケート調査によると,胃食道逆流症手術は本邦で2010年に167件,2015年に286件,2017年に358件と年々増加している1).
教室では,食道裂孔ヘルニアに対して腹腔鏡アプローチにて胃の腹腔内への還納,裂孔縫縮,逆流防止処置としてToupet噴門形成術を基本術式としている.噴門形成術にはNissen法もあるが,術後つかえ感の発現率がToupet法より有意に高いと報告されている2).①3 cm以上の滑脱型ヘルニア,傍食道型もしくは混合型ヘルニア,②75歳以上,③BMI 28 kg/m2以上の症例に対してメッシュ補強を追加している.さらに,混合型もしくは傍食道型ヘルニア症例には胃壁と腹壁の固定を3〜4針行っている.
胃
胃切除術・胃全摘術
著者: 佐藤敏 , 田中千恵 , 小寺泰弘
ページ範囲:P.115 - P.118
術前管理
●全身管理
入院前に外来で一般的な全身麻酔の術前検査として,胸部単純X線写真,心電図,呼吸機能検査,血算・生化学検査,凝固能検査,感染症検査を行う.また,喫煙者に対しては必ず禁煙指導を行わなければならない.術前検査で異常を認めた場合には,該当する診療科に耐術能の評価などを依頼する.同時に,特別な周術期管理が必要な併存疾患を有する場合,適切に評価および術前治療を行う.例えば,心疾患が併存する場合や脳梗塞後の場合には,当該診療科による詳細な評価や抗凝固薬(抗血栓薬)を中止した場合のヘパリン化の必要性を確認し,肺疾患を有する場合には呼吸のリハビリ,糖尿病を有する場合には適切な血糖コントロールをする.また,入院時には当該診療科との連携の確認をしておく.
また,術前にDダイマーを測定することが望ましいと考える.当院では2.5 μg/mL以上の場合には下肢血管エコー検査を行い,深部静脈血栓の有無を検索する.血栓が確認された場合には,血管外科に依頼し,周術期に抗血栓薬の投与や下大静脈(IVC)フィルターを挿入する必要性があるかどうかを確認する.
小腸・大腸
虫垂切除術
著者: 河合賢二
ページ範囲:P.119 - P.121
虫垂切除術の対象となる疾患は急性虫垂炎・慢性虫垂炎・虫垂腫瘍などである.慢性虫垂炎・虫垂腫瘍などに対する手術は待機的手術となる一方で,急性疾患である急性虫垂炎に対しては緊急手術を行うことが多い.近年では,急性虫垂炎に対する待機的虫垂切除術(interval appendectomy)の概念が普及しつつある.interval appendectomyは,手術難度の高い急性期に手術を行わずに,炎症の沈静化を待つことで回盲部切除などの拡大手術を回避することを目標とした治療戦略である.しかしながら,今日でも急性虫垂炎に対して緊急手術を行う機会は依然として多い.本稿では,最も頻度の多い急性虫垂炎に対する緊急での虫垂切除術の管理について概説する.
結腸切除術
著者: 岡澤裕 , 盧尚志 , 髙橋里奈 , 水越幸輔 , 嵩原一裕 , 神山博彦 , 小島豊 , 坂本一博
ページ範囲:P.123 - P.126
術前管理
結腸切除の対象となる疾患には良性から悪性まで様々な疾患がある.術式は各疾患の発生部位によって決定される(表1).しかし,疾患や術式にかかわらず,術前の評価項目はほぼ同様である.当科で術前に行っている検査を示す(表2).
直腸前方切除術
著者: 茂原富美 , 青柳康子 , 山本雄大 , 高岡亜弓 , 松宮由利子 , 馬場裕信 , 菊池章史 , 山内慎一 , 松山貴俊 , 絹笠祐介
ページ範囲:P.127 - P.130
術前評価・管理
当院では直腸前方切除の多くをロボット支援下手術で施行しているが,ロボット手術特有のものはなく,腹腔鏡手術でも同様の管理を行っている.
腹会陰式直腸切断術(側方郭清を伴う)
著者: 渡部顕 , 大田貢由
ページ範囲:P.131 - P.133
術前管理
●術前検査
直腸癌の病期診断に必要な検査に加えて,併存疾患の評価や全身麻酔に必要な検査を行う.高齢者では心疾患や脳血管性疾患に関連して抗凝固薬を内服している症例が多いので,問診で明らかにしておく.抗凝固薬の内服が明らかになった場合には,周術期における抗凝固薬の中断,変更について各疾患の担当医と協議したうえで方針を決定している.
直腸切断術では縫合不全のリスクはないものの,骨盤死腔炎が特徴的な術後合併症の一つで,危険因子として糖尿病や年齢,術前化学放射線療法が報告されている1).介入可能な糖尿病については術前に専門科と相談し,良好なコントロールを行うことが必須である.
骨盤内臓全摘術
著者: 池秀之 , 上向伸幸 , 谷口浩一
ページ範囲:P.134 - P.137
骨盤内臓全摘術は原発性直腸癌または直腸癌局所再発が膀胱,前立腺に浸潤する場合に行われることが多い1,2).濱野による骨盤内臓全摘術1,084例のアンケート集計では原発例が73%,再発例が24%,不明が3%であった3).骨盤内臓全摘術には直腸,膀胱,生殖器を一塊として切除するtotal pelvic exenteration(TPE)と女性における直腸,子宮,腟,卵巣を合併切除する後方骨盤内臓全摘術(posterior pelvic exenteration)および直腸を残して膀胱と女性生殖器を切除する前方骨盤内臓全摘術(anterior pelvic exenteration)があるが,一般的には尿路系の合併切除を伴うTPEを指す.近年は腹腔鏡手術の進歩により,腹腔鏡下骨盤内臓全摘術4,5),ロボット支援骨盤内臓全摘6)も試みられている.
膀胱,前立腺への浸潤の診断は,直腸指診で腫瘍の可動性が不良な場合に浸潤を疑う.画像診断ではCT, MRIを行うことにより診断する7).また,膀胱鏡を行い,膀胱内への浸潤の部位,範囲を診断する.女性においては婦人科併診を行い腟からの超音波検査も有用である.膀胱三角部への浸潤,前立腺深部への浸潤,尿道への浸潤がある場合には骨盤内臓全摘術の適応となる.MRIによる側方リンパ節転移診断も重要である.
大腸全摘術(潰瘍性大腸炎に対する)
著者: 板橋道朗 , 中尾紗由美 , 谷公孝 , 中川亮輔 , 腰野蔵人 , 番場嘉子 , 小川真平 , 山本雅一
ページ範囲:P.138 - P.141
術前管理
●入院
当科では,原則手術2日前に入院としている.そのため,術前評価と管理は入院前から開始されており,基本的な全身麻酔に必要な検査を施行した後に,麻酔科外来を受診したのち入院となる.
小腸大量切除術(SMA閉塞症を中心に)
著者: 天野邦彦 , 山本瑛介 , 石田秀行
ページ範囲:P.142 - P.146
小腸大量切除が必要となりうる疾患としては,上腸間膜動脈閉塞症(superior mesenteric artery occulusion:SMAO)や非閉塞性腸間膜虚血(non-occlusive mesenteric ischemia:NOMI),絞扼性イレウスに伴う腸管壊死が緊急性の高い疾患として挙げられる.また,広範な癒着性イレウスや巨大な腹腔内腫瘍性病変の切除時,炎症性腸疾患(特にクローン病により小腸切除を繰り返す場合など),腹部外傷の場合などでも結果として小腸大量切除が必要となる可能性がある.
今回,小腸大量切除となる疾患の中では最も日常診療で遭遇することが多いと思われるSMAOを中心に術前・術中・術後管理について述べる.
肛門疾患手術
著者: 赤瀬崇嘉 , 栗原浩幸 , 高林一浩 , 赤羽根拓弥 , 中村圭介 , 金井忠男
ページ範囲:P.151 - P.154
術前管理:入院前編
肛門疾患に対する治療は,疾患と患者の全身状態を考慮して選択される.一般的な肛門疾患(痔核,裂肛,痔瘻,直腸脱など)の手術は通常,低位腰椎麻酔や仙骨硬膜外麻酔の下で行われるが,患者のリスクが高い場合や病変が軽度のものであれば局所麻酔のもとで行うこともある.治療する疾患の病態を評価することと,患者の全身状態の評価を行うことが必要である.肛門疾患手術は緊急度が高くないため,全身評価を行った後に手術を行う.
肝
通常肝切除
著者: 佐野圭二
ページ範囲:P.155 - P.157
術前管理
周術期管理において,肝切除がほかの手術と大きく異なるポイントは,致命的合併症である肝不全のリスクをいかに回避するか,という点である.肝切除の主な適応疾患のうち,肝細胞癌は背景肝がウイルス性肝障害やアルコール性肝障害など障害肝であることが多く,また転移性肝腫瘍においても術前化学療法による薬剤性肝障害の合併や多発症例に対する広範囲肝切除などにより,肝切除術後肝不全は約2%でみられている1).よって,術前から術後肝不全を回避するための管理を十分に行う必要がある.
大量肝切除・二期的肝切除
著者: 小暮正晴 , 松木亮太 , 中里徹矢 , 鈴木裕 , 森俊幸 , 阪本良弘
ページ範囲:P.158 - P.162
術前評価
●適応
2区域以上の大量肝切除は,大きな肝腫瘍や肝中央部に位置し主要脈管に浸潤・固着する腫瘍,門脈一次分枝に腫瘍栓を伴う肝腫瘍,多発の転移性肝癌,肝門部領域胆管癌,肝門部へ浸潤した胆囊癌や肝内胆管癌などに適応となる.大腸癌の両葉多発転移に対しては,肝実質をできる限り残すparenchymal-sparing hepatectomyがoncologicalには有利であるが1),場合により2区域以上の肝切除が必要となることがある.
このように2区域以上の肝切除を一期的に行うと肝切除量が過大となり,術後の肝不全が懸念される場合には,一般に門脈塞栓術を術前に施行し,2週間以上の待機期間を経て,切除予定肝の縮小と温存予定肝の再生肥大の後に根治的肝切除を行う.右肝切除を伴う肝門部領域胆管癌の切除では,全肝比率で40%以上の予定残肝(future liver remnant:FLR)容量を確保するために,原則として門脈右枝の門脈塞栓術(portal vein embolization:PVE)を施行する2).あるいは,両葉多発肝転移症例でPVE後に一期的に左肝の腫瘍の切除と右肝切除を併施することも可能である.
化学療法後の肝切除
著者: 増田晃一 , 有田淳一 , 長谷川潔
ページ範囲:P.163 - P.166
化学療法後の肝臓に対する肝切除は,多くは結腸・直腸癌を原発とする転移性肝癌に対する肝切除である.したがって,以下は,主に結腸・直腸癌の肝転移に対する術前化学療法(neoadjuvant chemotherapy)後あるいは,切除不能症例に対して化学療法が奏効した後にconversion surgeryとして行う肝切除についての周術期管理として記載するが,他癌腫においても応用が可能である.
周術期管理については,基本的には化学療法非実施例と変わらないが,化学療法による肝障害と術後合併症率の上昇を考慮した,より慎重な管理が必要となる.
肝腫瘍に対するablation
著者: 髙浦健太 , 黒崎雅之
ページ範囲:P.168 - P.170
肝腫瘍,特に肝細胞癌に対する局所療法として,2004年に経皮的ラジオ波焼灼療法(radiofrequency ablation:RFA)が保険適用となって以降は,局所の根治性や生命予後から,ガイドライン上もRFAが標準治療の一つとされている1,2,3).
穿刺方法については,エコーガイド下や腹腔鏡下に穿刺針を直接穿刺する方法や,当院のように,ガイドニードルおよび内外筒針を用いた2ステップ穿刺も方法の一つである(図1).
胆
胆囊摘出術
著者: 中島康介 , 尾崎貴洋 , 田中寛人 , 大友直樹 , 水口法生 , 岡本知美 , 三島江平 , 五十嵐一晴 , 本多正幸 , 豊田真之 , 若林剛
ページ範囲:P.171 - P.174
術前管理
●手術危険因子
Tokyo Guidelines 2018(以下TG18)では,重症度別に患者の手術危険因子が提示された1).手術の危険因子には,Grade Ⅰ(軽症),Grade Ⅱ(中等症)では年齢調整を含めたチャールソン併存疾患指数(age-adjusted Charlson cormobidity index:CCI)2,3),ならびに,米国麻酔科学会による術前状態分類(ASA-PS)4)を用い,Grade Ⅲ(重症)ではCCI,ASA-PSに加え,臓器障害の種類(治療反応性臓器障害または致死性臓器障害)を用い,評価した.さらにGrade Ⅱ,Ⅲの手術難度が高いと思われる患者に対する腹腔鏡下胆囊摘出術(Lap-C)は,急性胆囊炎手術に熟練した内視鏡外科医のもとで行い,Grade Ⅲ症例は集中治療を含めた全身管理の可能な施設において診療を行うことを原則とした.
表1はASA-PS分類で,アメリカ麻酔学会が提供する外科手術患者の術前状態把握のため作成された指標を改変して示した4).手術危険因子は「年齢調整を含めたチャールソン併存疾患指数」(表2)に示した2,3).国際疾病分類コードに基づいた患者の併存疾患を分類する指数で,点数が高いほど死亡率が高くなる.
胆囊癌に対する拡大胆摘術
著者: 三浦宏平 , 坂田純 , 廣瀬雄己 , 堅田朋大 , 滝沢一泰 , 小林隆 , 若井俊文
ページ範囲:P.175 - P.178
術前管理
●手術適応
胆囊癌の根治切除を実施する際には,癌遺残のない手術(R0手術)を達成することが重要である1,2).当科における胆囊癌に対する拡大胆摘術は,担癌胆囊,胆囊床側肝臓,肝外胆管,領域リンパ節(肝十二指腸間膜内リンパ節+No. 13aリンパ節+No. 8apリンパ節)をen blocに摘出する,いわゆるGlenn手術変法を基本としている3,4).
拡大胆摘術の適応は,原則,①局所進展度が漿膜下層あるいは胆囊床部筋層周囲の結合組織に留まるT2胆囊癌,②肝内進展が比較的軽度なT3胆囊癌(肝以外の臓器への進展が存在しないか,存在しても軽度なもの)としている.これ以上の局所進展を呈する場合は,拡大胆摘術でR0手術を達成することは困難なことが多く,拡大手術(拡大肝右葉切除術や膵頭十二指腸切除術)の付加を考慮する3).
肝門部胆管癌手術
著者: 東尚伸 , 阿部雄太 , 堀周太郎 , 大島剛 , 八木洋 , 北郷実 , 篠田昌宏 , 北川雄光
ページ範囲:P.179 - P.182
術前管理
肝門部領域胆管癌は,根治性と安全性を両立させつつ手術適応を失わないためにも,適切な術前管理は極めて重要である.以下に,当科における術前検査項目の内容を記す.
膵
膵頭十二指腸切除術
著者: 山本智久 , 里井壯平 , 山木壮 , 廣岡智 , 松井陽一 , 関本貢嗣
ページ範囲:P.183 - P.187
術前管理
●栄養
術前の低アルブミン血症は手術部位感染(SSI),肺炎,敗血症などの術後合併症リスクであり1),術前の栄養状態改善が合併症低減のためには重要な介入因子であると考えられる.
そのため,低アルブミン血症を認める場合は,術前から消化酵素剤および成分栄養剤などの投与により,栄養改善を図るべきである.
膵体尾部切除術
著者: 川井学 , 山上裕機
ページ範囲:P.188 - P.192
2012年,欧州静脈経腸栄養学会から膵切除に対する術後回復能力を強化するために術後回復能力強化プログラムenhanced recovery after surgery(ERAS)が提唱され1),周術期管理は大きく変化した(表1).本稿では,膵体尾部切除における現在の術前・術中・術後管理につき述べる.
膵全摘術
著者: 亀井敬子 , 松本逸平 , 竹山宜典
ページ範囲:P.193 - P.196
膵全摘術は,膵内外分泌機能の完全脱落をきたすため,栄養管理や血糖コントロールに難渋し,QOLを著しく損なう術式であるとされてきた.しかし近年,外科手術手技の向上と,高力価膵消化酵素剤の開発や強化インスリン療法の導入などにより,一定のQOL保持が可能となり,その適応症例は増加している.さらに膵切除後の残膵再発などによる残膵全摘術も増加している.
その施行に際しては,術前に十分なインフォームド・コンセントを行い,術後の病態を患者本人に十分に理解してもらうことが重要である.また,治療早期から,外科医と糖尿病内科医が密接に連携するとともに,患者への教育,栄養士や患者家族の適切なサポートなども極めて重要である.膵全摘術後はインスリン自己注射が必須であるため,自己注射が行えない者,理解できない者,独居の患者などには,膵全摘術の適応を慎重に判断する必要がある.また,膵癌における膵全摘術はいまだ予後不良であるとの報告も多いため,術前療法などの集学的治療も考慮し,安易に膵全摘術を選択すべきではない.本稿では,膵全摘術後の栄養代謝管理の要点を中心に述べる.
その他
乳房切除術
著者: 萬谷京子 , 大木慶子 , 逢坂佳宗
ページ範囲:P.197 - P.201
乳房切除術の周術期管理は,各施設で工夫が重ねられていることと拝察する.本稿では,当施設で行っている現在の方法・工夫について述べる.
本術式に特徴的な合併症は,術中体位による頸部・肩関節部・上肢などの筋肉痛・神経障害,消毒液塗布やテープ貼付による接触性皮膚炎・水疱,出血,血清腫,皮弁の血流障害,縫合不全,感染,創痛,皮弁作製領域の知覚異常,ドレーンが皮下の組織に接触することに伴う出血や痛みなどである.これらのうち,完全な予防が困難で,全身状態に影響を与える可能性があり,速やかな対処が必要になる合併症は,出血である.
脾臓摘出術
著者: 三澤健之
ページ範囲:P.202 - P.205
術前管理
脾臓摘出術の適応は,特発性血小板減少性紫斑病(ITP)や遺伝性球状赤血球症(HS)に代表される血液疾患,門脈圧亢進症に伴う脾機能亢進症,および脾腫瘍,脾動脈瘤など様々であり,それぞれの基礎疾患に即した術前管理が基本となることはいうまでもない.
鼠径部ヘルニア(成人)
著者: 稲葉毅 , 宮崎恭介 , 武藤泰彦
ページ範囲:P.206 - P.209
〔注意〕本特集で取り上げられている他の術式と比較し,鼠径部ヘルニア手術では大きく異なる点が2点ある.第1は,術式と麻酔法のバリエーションが多く,それも多くの場合は患者の病態によってではなく,施設の方針によって決められていること.第2は,第1の点とも大きく関連しているが,日帰り手術(短期滞在型手術)の普及が推進されていることである.当然ながら,周術期管理の方法も,該当施設がその2点をどう扱っているかによって大きな差異があることをお断りしておく.
鼠経ヘルニア(小児)
著者: 細田利史
ページ範囲:P.210 - P.213
術前管理
●手術のタイミング
嵌頓を起こす危険性があるため,基本的には診断した時点で可及的速やかに手術を予定する必要がある.ただし,生後6か月までは腹膜鞘状突起が自然閉鎖し腸管の脱出が消失することがあるので,生後6か月以降に手術を施行している.しかし,腸管脱出を頻回に繰り返す症例や卵巣卵管が滑脱している症例は,血流障害を生じる可能性があるので,6か月以内であっても早期に手術を施行している.
新生児時期でも手術を施行している施設も多数あり,意見の分かれるところではあるので,今後のさらなる検討が必要と思われる.
Ⅳ章 術後合併症とその管理 A 重点術後合併症の管理ポイント
術後合併症診断のアルゴリズム
著者: 小澤毅士 , 大野航平 , 岡田有加 , 八木貴博 , 福島慶久 , 島田竜 , 端山軍 , 土屋剛史 , 野澤慶次郎 , 松田圭二 , 橋口陽二郎
ページ範囲:P.216 - P.219
術後合併症の診断
Clavien-Dindo分類で知られるPierre-Alain Clavienによると,術後合併症の定義は「Any deviation from the ideal postoperative course」であり,狭義には手術の直接的侵襲の結果生じた合併症だが,広義には手術,麻酔という侵襲により顕在化してくる全身合併症や,薬剤性障害など,“すべての理想的な術後経過からの逸脱”を含む1).このように定義する理由として,手術による“直接的”な結果がどこまで直接的かということは客観性に欠け,それぞれの外科医で判断が異なるため,すべての合併症を術後合併症に含まないと過少報告につながるため,とDaniel Dindoは報告している.実際,明らかに直接的な合併症,例えば縫合不全ですらその定義・診断が各外科医において一致しないという報告も認めるように,術後合併症診断にはどうしても術者は“こんなことは起こりえない”といった過少評価をしがちで,時に適切な判断ができないことがあることを常に肝に銘じる必要がある2).
ここでは紙面の関係上,狭義の術後合併症診断に限ってその診断のアルゴリズムを示す.術後合併症診断は大きく,単純に診断を付けることと,その重症度を診断することに分けられる.前者の診断に関して重要なことは,まず起こりうる合併症の頻度,起こりやすい時期について熟知するとともに,どのような症状・検査所見が出うるのかをしっかりと把握しておくことである.さらには,患者の術前リスクを十分に評価し,認識しておく必要があることはいうまでもない.
縫合不全(食道癌)
著者: 八木浩一 , 瀬戸泰之
ページ範囲:P.220 - P.224
症状(発症時期・発見の契機)
通常,術後1週間以内に発症する.頸部吻合の場合,頸部の発赤,ドレーンから唾液混じりの排液があり,胸腔内吻合の場合,胸腔ドレーンからの唾液,胃液,胆汁混じりの排液を認める.炎症反応高値,発熱,頻脈,呼吸数増加となることが多い.特に胸腔内吻合では,急速にバイタルサインが悪化し,縫合不全の確定診断の前に気管内挿管,人工呼吸器管理,集中治療管理が必要となることもある.明らかな臨床症状がなくとも炎症反応高値や発熱を認め,その熱源検索のCT検査が発見の契機となることがある.遅発性縫合不全の報告もある.
縫合不全(直腸癌低位前方切除術)
著者: 神藤英二 , 永田健 , 梶原由規 , 岡本耕一 , 上野秀樹
ページ範囲:P.225 - P.229
症状
低位前方切除術における吻合部の縫合不全は重大な合併症の1つであり,時に重篤化し緊急の対応を迫られる.縫合不全とは,再建腸管同士の壁連続性の破綻によって,腸管内腔が腸管外へ異常に交通した状況と定義される.吻合機器や手技に起因する場合は比較的早期の発症となる.水様性下痢などの物理的刺激が原因となることも多く,発症は排便のタイミングと一致する.血流不全や創傷治癒過程の問題で発症する場合には,術後1週間程度を経て発症することもある.一方,3週以降に発症する遅発性縫合不全は稀であり,その頻度を1.3%と報告する検討もある1).
縫合不全の初期症状としては,発熱と腹痛が最も一般的である.ドレーンから排出される汚染された腹水,ガス,便,膿を契機に診断されることが多い.周囲臓器との間に瘻孔を形成することもあることから,創部や腟についても排出内容に注意する.肛門からの排膿も縫合不全を疑う所見である.
術後イレウスと小腸閉塞
著者: 藤井正一 , 出口貴司 , 有村隆明 , 金澤真作 , 堤謙二 , 内山周也
ページ範囲:P.230 - P.234
腸閉塞は腹部手術後の重要な合併症で,定義は「何らかの原因で腸管内容の肛門側への輸送が障害された病態」とされる1).成因により機能的と機械的に大別され対処法も自ずと異なってくる.しかし,本邦の臨床現場では機能的腸閉塞も機械的腸閉塞も「イレウス」でひとくくりにされ,明確に区別されてないことが多い.欧米では機能的腸閉塞はileusであり,機械的腸閉塞はbowel obstructionとして区別される.本稿の表題は「術後イレウスと小腸閉塞」としたが,ここでは術後イレウスとは機能的腸閉塞,小腸閉塞は機械的腸閉塞と区別して論ずる.
膵瘻
著者: 松本奏吉 , 仲田興平 , 渡邉雄介 , 森泰寿 , 池永直樹 , 宮坂義浩 , 大塚隆生 , 中村雅史
ページ範囲:P.235 - P.238
術後膵瘻(postoperative pancreatic fistula;POPF)は膵頭十二指腸切除術(PD)および膵体尾部切除術(DP)をはじめとした膵切除術における最も重大な合併症の1つで,ハイボリュームセンターにおいても3〜45%に生じるとされており,その確実な予防法は未だ確立されていない1).本項では,最新の知見を混じえ,POPFへの対応について概説する.
胆汁漏
著者: 津川大介 , 福本巧
ページ範囲:P.239 - P.243
症状(発症時期・発見の契機)
発症時期は術直後から術後早期が多く,術中に留置したドレーン排液より診断される.2011年International Study Group of Liver Surgery(ISGLS)により,術後3日目以降のドレーン排液中のビリルビン値が血清ビリルビン値の3倍以上の場合,または胆汁貯留に対するドレナージ処置や胆汁性腹膜炎に対して手術が必要な場合を胆汁漏と定義している1).術中にドレーンを留置しない場合,もしくはドレナージが不良の場合は,感染徴候が出現してから診断されることがある.また無症状に経過してCTを撮影して初めて診断される症例も存在する.稀に術後2週間以上経過してから遅発性に胆汁漏が発生する症例も存在するがその成因は不明なことが多い.術中のエネルギーデバイスによる胆管の熱損傷や胆管吻合部の血流障害などがその原因として推測されている.
胆汁漏の発生頻度は,National Clinical Database(NCD)Feedbackによると7.66%(2013〜2017肝切除術後・全国集計)とされており,肝胆膵外科領域では決して稀な合併症ではなく,常にその可能性を念頭に置き術中操作,術後管理を行う必要がある.胆汁漏の発生頻度を低下させるためには,胆汁漏を起こさない確実な手術手技が重要であることはいうまでもないが,それ以外にも術中胆汁リークテスト〔色素法・インドシアニングリーン(ICG)法〕,術中胆管造影,肝離断面へのフィブリン糊の散布などさまざまな工夫がなされている.しかし,いずれの対策でも胆汁漏を完全に防ぐことは困難で,胆汁漏は肝内胆管から乳頭部まで胆道のいずれの部位からも起こり得る.肝切除では肝切離面の胆管から,膵頭十二指腸切除や肝移植などの胆道再建を伴う手術では胆管・空腸吻合や胆管・胆管吻合部から,胆囊摘出術,総胆管截石術では胆管,胆囊管閉鎖部や胆管損傷部から胆汁が漏出する.乳頭部近傍の十二指腸損傷でも胆汁様の腸液の漏出が起こり,時にその鑑別が困難となる.
肝不全
著者: 石井隆道 , 海道利実 , 上本伸二
ページ範囲:P.244 - P.247
症状
本項ではおもに肝臓手術後の肝不全について述べる.非肝臓手術後の肝不全も基本的に治療・対処法は同じである.
2011年にInternational Study Group of Liver Surgery(ISGLS)によって術後肝不全は「肝臓の合成機能,排泄機能および解毒機能が障害される状態であり,術後5日目以降でプロトロンビン時間が延長し,かつそれに随伴する高ビリルビン血症によって特徴付けられる」と定義された1).これは通常術後5日目以内には肝機能の回復が見られるという報告を元に定められており,広く使用されるようになってきている.一方,臨床経過からは慢性的に進行する肝不全も見られる.緩徐に凝固障害や高ビリルビン血症が進行してくるが,元の慢性肝障害に過大手術侵襲が加わり慢性肝不全として顕在化してくるものである.
術後胆道狭窄
著者: 賀川真吾 , 高屋敷吏 , 大塚将之
ページ範囲:P.248 - P.250
症状(発症時期・発見の契機)
術後胆道狭窄の原因としては,悪性疾患の術後再発病変による胆道狭窄も多く経験されるが,今回は術後合併症の観点から良性胆道狭窄につき概説する.
胆道狭窄の原因としては,腹腔鏡下胆囊摘出時の胆管損傷後,肝外胆管切除・胆管空腸吻合や胆管胆管吻合術後の吻合部狭窄などが挙げられる.診断契機としては,「繰り返す胆管炎」が最も多く,「黄疸」や「肝胆道系酵素上昇」により,各種画像検査が行われている.
肺塞栓
著者: 國崎主税 , 宮本洋 , 佐藤圭 , 田中優作 , 土屋伸広 , 佐藤渉 , 小坂隆司 , 秋山浩利 , 遠藤格
ページ範囲:P.251 - P.254
症状
術後肺塞栓は,術後初めて起床し歩行する際に起こることが多いとされているが,術後数日,退院後に起こることもあり,症状の変化に留意しなければならない.最多の症状は突然の息苦しさである.動脈血中の酸素濃度は低くなるので,安静時でも頻脈,頻呼吸となることもある.次に胸痛が多い.典型症状は吸気時の鋭い痛みで,胸膜炎の際の疼痛と似ている.吸気時には肺動脈内の圧が上昇し,血圧が下がるので冠動脈血流が少なくなり胸痛の原因となる.また,漠然とした前胸部痛や,胸部圧迫感・不快感といった胸部痛もある.ほかの症状として失神,ショック,心肺停止が起こりえる.原因は心拍出量減少による血圧低下,神経反射の影響があるためと考えられている.病状がきわめて重い場合は,突然死することもある.一般に肺塞栓症は深部静脈血栓症から進展ことがほとんどであるので,片側下肢の腫脹,痛み,皮膚の色の変化が伴う上記症状は,強く肺塞栓症を疑う必要がある.
偽膜性腸炎
著者: 松田圭二 , 大野航平 , 岡田有加 , 八木貴博 , 塚本充雄 , 福島慶久 , 堀内敦 , 山田英樹 , 小澤毅士 , 島田竜 , 端山軍 , 土屋剛史 , 野澤慶次郎 , 青柳仁 , 磯野朱里 , 阿部浩一郎 , 小田島慎也 , 山本貴嗣 , 橋口陽二郎
ページ範囲:P.256 - P.258
症状
抗菌薬による腸炎は偽膜性腸炎と抗菌薬起因性急性出血性大腸炎に大別される.当初,偽膜性腸炎の原因医薬品としてリンコマイシンやクリンダマイシンが注目されたが,現在ではほとんどすべての抗菌薬が原因医薬品となりうると考えられている.偽膜性腸炎は
DIC
著者: 高島順平 , 小林宏寿 , 服部豊 , 藤嶋誠一郎 , 兼松恭平 , 藤本大祐 , 内藤善久 , 谷口桂三 , 松谷哲行
ページ範囲:P.259 - P.262
播種性血管内凝固症候群(disseminated intravascular coagulation:DIC)は,さまざまな基礎疾患の存在下において全身性持続性に過剰な凝固反応の亢進や血管内皮細胞障害をきたす.その結果,主として微小血管内に血栓が形成され,微小循環障害に伴う全身の臓器障害と消費性凝固障害に伴う出血傾向を引き起こす病態である1).
DICの原因病態は多岐にわたる.高齢化の影響もあり,臨床の場で実際に救急患者や術後患者のDICに遭遇する場面は少なくない.その中でもよく遭遇する病態として敗血症が挙げられる.敗血症診療ガイドライン2)では,敗血症によりDICが惹起されると,凝固障害から多臓器障害へと至り,高い死亡率へとつながるとされており,DICは極めて重大な病態である.
B 系統別術後合併症の管理ポイント 消化器系
乳び胸・乳び腹水
著者: 藤原直人 , 佐藤弘 , 宮脇豊 , 岡本光順 , 桜本信一 , 山口茂樹 , 小山勇
ページ範囲:P.263 - P.265
乳び胸
症状
●食道癌に対する食道切除術後に,胸腔ドレーンから大量の漿液性排液を認めた場合には乳び胸を疑う必要がある.胸腔内における胸管(図1)またはその主要分枝の損傷により,術後リンパ液が大量に胸腔内へ漏出する病態である.
●リンパ管内の流量は,経管栄養や食事の開始(特に脂肪成分の腸管からの吸収)によって増加するため,これらを契機に排液量が増加した場合は術後乳び胸の可能性が高い.
循環器系
不整脈
著者: 合屋雅彦
ページ範囲:P.269 - P.271
心臓手術を含む胸部手術の合併症として心房細動の頻度が高い.冠動脈バイパス術後には15〜40%に発症するとされている.また,稀ではあるが心手術後に心室細動が頻回に発症する症例が報告されている.本稿では術後の心房細動,心室細動に関し述べる.
心不全
著者: 藤原立樹
ページ範囲:P.272 - P.275
症状
●心不全とは,心臓に器質的あるいは機能的異常が生じてポンプ機能が破綻し,心室拡張末期圧の上昇や主要臓器への灌流不全をきたし,それに基づく症状や徴候が出現または悪化する病態である.
●心不全では左室拡張末期圧や左房圧の上昇に伴う肺静脈のうっ血による左心不全症状と,右房圧の上昇に伴う体静脈のうっ血による右心不全症状,それに心拍出量減少に伴う症状が認められる.
呼吸器系
無気肺
著者: 堺崇 , 坂尾幸則
ページ範囲:P.276 - P.277
症状
●肺胞虚脱が起こり,肺の含気が減少した状態.
●無気肺は肺動脈からの血流が十分酸素化されずに肺静脈に流入するため動脈血酸素飽和度が低下する.呼吸困難をきたし,聴診では肺胞呼吸音減弱および打診時の濁音を認める.頻脈,胸痛,発熱をきたす症例もある.多くは喀痰による気管支閉塞(閉塞性無気肺)によるものが多く,胸水の圧排・急性肺障害(非閉塞性無気肺)も原因となることがある1).
気胸
著者: 唐崎隆弘 , 中島淳
ページ範囲:P.278 - P.279
症状
●胸腔内に空気の貯留する状態が気胸であり,自然気胸(原発性または続発性),外傷性,医原性(中心静脈カテーテル挿入操作や陽圧換気に起因するもの)に分類される.
●症状は,肺の虚脱程度やもともとの呼吸機能によって大きく変化する.典型的には胸痛,咳などの胸膜刺激症状や,酸素化の低下,呼吸困難を呈する.無症候ながら胸部画像検査で偶然発見されることもある.
呼吸不全
著者: 福田俊
ページ範囲:P.280 - P.282
症状
●呼吸不全は,なんらかの原因で動脈血酸素分圧が60 Torr以下となったものと定義され,急性呼吸不全,慢性呼吸不全,慢性呼吸不全の急性増悪に大別される.また,動脈血二酸化炭素分圧の上昇を認めないⅠ型と,10 Torr以上の上昇を認めるⅡ型に分類される1).
●急性呼吸不全の症状は低酸素血症の程度により以下のような症状がみられる.
精神・神経系
術後せん妄
著者: 徳倉達也
ページ範囲:P.283 - P.285
症状
●せん妄は,急性もしくは亜急性の意識障害であり,注意・認知機能が障害される.
●入院患者にしばしば生じ,手術後に生じるせん妄である術後せん妄の発症率は15〜50%程度とされ,入院長期化,死亡率増加,認知機能低下などの転帰につながる.
不眠症
著者: 徳倉達也
ページ範囲:P.286 - P.288
症状
●不眠の症状は,入眠困難(寝つきが悪い),中途覚醒(途中で目が覚める),早朝覚醒(朝早く目が覚める),熟眠困難(ぐっすり眠れない)に主に分類される.
●不眠を有する患者は多いが,特に周術期には,入院・手術による環境変化,手術侵襲に伴う疼痛,不快な症状,安静臥床,不安などを誘因として不眠が頻発する.
術後反回神経麻痺
著者: 小柳和夫 , 小澤壯治 , 數野暁人 , 山本美穂 , 二宮大和 , 谷田部健太郎 , 樋口格
ページ範囲:P.289 - P.291
症状
要点:片側麻痺と両側麻痺では初期症状は異なり,両側麻痺の場合には緊急の再挿管が必要になることがある.
●一般消化器外科領域では,食道癌や甲状腺の術後合併症としての頻度が高い.
嚥下困難
著者: 山田和彦 , 野原京子 , 榎本直記 , 月永暁裕 , 藤谷順子 , 國土典宏
ページ範囲:P.292 - P.294
症状
●嚥下困難による栄養障害は,食道癌のような頸部を操作する手術や脳血管障害だけではなく,さまざまな要因により出現しうる.後期高齢者,脳梗塞の既往,フレイルサイクルの存在や低栄養状態は術後に嚥下障害を起こすハイリスク症例であり,二次性サルコペニア自体が嚥下の機能を低下させる1).
●色々なタイプの誤嚥がある
内分泌・代謝系
術後耐糖能異常
著者: 竹内彬 , 山田哲也
ページ範囲:P.295 - P.297
症状
●術前より糖尿病を有する患者はもちろんのこと,そうでない場合であっても術後は手術侵襲やストレス,炎症,輸液や経管栄養などの影響を受けて耐糖能が悪化する.
●高血糖そのものの自覚症状としては口渇,多飲,多尿などがあるが,術後の患者は自覚症状を十分に認識できないことも多く注意を要する.
腎・尿路系
急性腎障害
著者: 高橋直宏 , 蘇原映誠
ページ範囲:P.298 - P.299
症状
●腎疾患の既往がない場合,術後急性腎障害の頻度は心臓手術で約20%,非心臓手術では約10%(大腸手術)〜約30%(肝移植術)と手術内容によって大きく異なる.いずれにせよ急性腎障害が術後合併症のなかでも高頻度なものであることは間違いない.
●急性腎障害は,術後検査での血清尿素窒素値・クレアチニン値の上昇または乏尿・無尿によって認識されることが多い.血液検査では高カリウム血症を呈することもある.また,術後炎症および心不全の併存により,高度の浮腫をきたすこともある.
排尿障害
著者: 野間康央 , 堀江重郎
ページ範囲:P.300 - P.301
症状
●排尿障害の病態は,排出障害と蓄尿障害に区分される.
●排出障害の症状は,尿閉,尿線の細化,残尿感,腹圧排尿などがある.
尿路感染
著者: 小杉千弘 , 幸田圭史 , 清水宏明 , 山崎将人 , 首藤潔彦 , 成島一夫 , 野島広之 , 細川勇 , 村上崇 , 高橋理彦 , 宮澤幸正
ページ範囲:P.302 - P.303
外科手術後の大部分は尿路系手術操作を伴わないにもかかわらず,術後合併症として尿路感染症は数%程度で発生するとされる1〜3).本稿では術後尿路感染症について述べる
感染系
創感染
著者: 針原康
ページ範囲:P.304 - P.305
症状
●創感染の原因は,主として,術中の創部の細菌汚染である.
●創感染の発症を防ぐには,術中の細菌汚染を防ぐこと,閉創時に創洗浄を行い汚染細菌数を減少させること,適切な予防抗菌薬の投与により,生体防御能を高めることなど,術中から術後早期の対策が重要である.
腹腔内膿瘍
著者: 土屋剛史 , 大野航平 , 岡田有加 , 八木貴博 , 福島慶久 , 島田竜 , 小澤毅士 , 端山軍 , 野澤慶次郎 , 松田圭二 , 橋口陽二郎
ページ範囲:P.306 - P.307
腹腔内膿瘍は,その成因から,消化管穿孔や虫垂炎など腹膜炎の緊急手術に続発するもの(続発性)と,待機手術の術後に起きるもの(術後性),特に縫合不全などに起因するものに,大きく分けることができる.
膿瘍が形成される部位は,主に原因となる臓器の隣接部である.それ以外では,腹腔内の低い位置に貯留する.すなわち,左右の横隔膜下や傍結腸溝,Morrison窩,Douglas窩に膿瘍形成が起こりやすい.稀に,腸間膜の間に形成されることもある.つまり,手術の際にドレーンを留置する部位と概ね一致するため,膿瘍形成の予防には,適切な部位に,跳ねないドレーンを留置することが非常に重要である.
壊死性筋膜炎
著者: 岡本耕一 , 神藤英二 , 梶原由規 , 上野秀樹
ページ範囲:P.308 - P.309
症状
●壊死性筋膜炎は浅筋膜とその周囲組織の広範な壊死を特徴とする感染症である.
●四肢,陰部,腹部に好発し,境界不明瞭な限局性の浮腫,発赤,疼痛および圧痛が初期症状である.そのため,初診時には蜂窩織炎や膿瘍などと診断されることが多い.
サイトメガロウイルス感染症
著者: 日吉雅也 , 石原聡一郎
ページ範囲:P.310 - P.312
症状
●サイトメガロウイルス(CMV)はヘルペスウイルスの一種で,通常,幼少時に感染し,ほとんどが不顕性感染のまま,生涯その宿主に潜伏感染する.特に免疫が弱っている状態で感染すると肺炎,網膜炎,胃腸炎,脳炎などが引き起こされる.
●エイズ患者,移植患者,ステロイド使用,抗癌薬治療患者がCMV感染症のハイリスクとされるが,免疫抑制薬治療,膠原病,糖尿病,腎不全,敗血症,外傷などの疾患を有する患者にも起こることがある1).
各種耐性菌による感染症
著者: 松永直久
ページ範囲:P.314 - P.319
耐性菌感染症治療,その前に
●耐性菌感染症治療に限らず,抗菌薬を投与する際には「どこに」「何が」炎症を起こしているかを意識する.そのために関連する症状・徴候・血液や画像検査で感染部位(「どこに」)を評価し,グラム染色検査や培養検査で原因微生物(「何が」)を評価する.
●熱源精査のルーチンとしては,血液培養に加えて,尿定性・沈渣と尿グラム染色・培養検査を行う(尿路感染症では発熱しか症状が出ないことも多い).胸部X線検査も検討する.
敗血症性ショック
著者: 髙橋一哉 , 深柄和彦
ページ範囲:P.320 - P.321
症状
●敗血症性ショックの管理に関する国際ガイドラインであるSurviving Sepsis Campaign Guidelines 20161)では,敗血症性ショックは「敗血症の一型であり,循環および細胞・代謝機能不全を伴い,高い死亡率と関連している状態」と定義されている.「低血圧であるか」「臓器不全や組織低灌流による症状があるか」「感染症か否か」を早期に認識し,迅速に対応することが重要である.
血液凝固系
HIT
著者: 岡本好司
ページ範囲:P.322 - P.323
ヘパリンは,臨床現場で最も汎用されている注射用抗凝固薬である.ヘパリン使用中に動静脈血栓症や血小板減少症を副作用として呈することがある.これがヘパリン起因性血小板減少症(heparin-induced thrombocytopenia:HIT)である.
門脈血栓症
著者: 長尾吉泰 , 原田昇 , 吉屋匠平 , 武石一樹 , 戸島剛男 , 伊藤心二 , 池上徹 , 吉住朋晴 , 森正樹
ページ範囲:P.324 - P.328
周術期における門脈血栓症は,腸管うっ血・難治性腹水・肝機能障害などの原因となり,周術期管理において不利益となる.急速に門脈血流が障害されると,肝不全・播種性血管内凝固症候群といった重篤な病態に陥ってしまうため,早期発見・早期治療が不可欠である.また慢性期に移行し,血栓が器質化すると,門脈圧亢進症を発症し,食道および胃静脈瘤を発生させ,静脈瘤出血を引き起こす.
診断は非侵襲的で感度も高い超音波検査を中心に,採血およびCT/MRIも併用して総合的に行う.治療としては,抗凝固療法が中心となるが,時には血管内治療や外科的治療も選択肢となる.依然確立された治療方針はないが,本稿ではこれまでの報告に基づき,門脈血栓症について概説したい.
後天性血友病
著者: 熊本宜文 , 松山隆生 , 三宅健太郎 , 本間祐樹 , 澤田雄 , 藪下泰宏 , 武田和永 , 遠藤格
ページ範囲:P.329 - P.330
後天性血友病A診療ガイドラインでは,本症の診断ならびに治療は本疾患に精通している医師の指導の下で行われることが望ましいとされている1).
Ⅴ章 特殊な治療手技
CTガイド下ドレナージ
著者: 佐藤洋造 , 稲葉吉隆 , 清水泰博
ページ範囲:P.332 - P.335
適応
各種外科手術後の膿瘍形成に対して,画像ガイド下にドレナージを施行することがあり,画像モダリティとしてはUSまたはCTが用いられることで多い.USガイド下のメリットとしては,穿刺時にリアルタイムで観察が可能である,脈管構造をカラードップラーも併用すれば詳細に評価可能である,被曝がないといったことが挙げられるが,一方深部の病変や穿刺経路に空気が介在すると描出困難なことがある,というデメリットがある.CTガイド下のメリットとしては,解剖学的位置が把握しやすい,深部の病変でも問題なく同定できる,ドレナージカテーテル挿入後の合併症の有無の確認が容易,といったことがある1,2).適応も広く非常に有用な手技であるが,基本的に単純CT下で行うため,肝臓内の脈管は描出不良であり,骨盤内の脈管なども他臓器と接していると詳細な評価は困難であり,膿瘍形成発見の契機となった造影CTも参照して穿刺経路を計画する必要がある1).
経皮的止血—術後のさまざまな出血に対する止血術
著者: 山本真由
ページ範囲:P.336 - P.339
術後性出血には動脈性が最も重篤なものであるが,静脈性,リンパ性の出血も時に重篤になる.本稿では,さまざまな出血に対する塞栓術について適応を中心に紹介する.手技内容の詳細については,専門書を参考にしていただきたい.
ECMO
著者: 安部隆三
ページ範囲:P.340 - P.343
ECMOに関する基本事項
ECMO(extracorporeal membrane oxygenation:体外式膜型人工肺)は,重症心不全,重症呼吸不全患者に対して使用される人工心肺を用いた生命維持法であり,近年その施行症例数が増加している1).ECLS(extracorporeal life support:体外式生命補助)と呼ばれることもあり,また,経皮的に導入した場合にはPCPS(percutaneous cardiopulmonary support:経皮的心肺補助)とも呼ばれる.
ECMOの基本構造は,ポンプ,膜型人工肺,脱血および送血カニュレと,それらを接続する回路からなる.ポンプは通常,遠心ポンプが用いられる.血管内に留置した脱血カニュレから遠心ポンプで血液を体外に引き出し,人工肺にて酸素化,二酸化炭素排出を行ったうえで,送血カニュレ経由で体内に送り込む仕組みである.
血液浄化療法・PMX-DHP
著者: 小野聡 , 青笹季文 , 蒲池良平 , 岡崎幸生
ページ範囲:P.344 - P.348
血液浄化療法とは
血液浄化療法は血液中に存在する病因物質を体外循環を通して除去,場合によっては不足しているものを補う治療法で,血液透析(hemodialysis:HD),血液濾過(hemofiltration:HF),血液濾過透析(hemodiafiltration:HDF),血漿交換(plasma exchange),血液吸着(hemoadsorption),血漿吸着(plasma adsorption),血球吸着(cytapheresis)などがあり,最も広く行われている血液浄化療法は,慢性腎不全患者に対して行う血液透析である.
本稿では外科周術期および集中治療領域で施行されることの多い持続的血液濾過透析(continuous hemodiafiltration:CHDF)と2014年から保険適用となったセプザイリス®によるサイトカイン吸着除去,そしてエンドトキシン吸着療法(polymyxin B-direct hemoperfusion:PMX-DHP)について述べる.
ステロイド療法—周術期の合併症に対する適応と方法
著者: 今泉均
ページ範囲:P.350 - P.354
ステロイドは強力な抗炎症作用と免疫抑制作用をもち,炎症性疾患や悪性腫瘍,臓器移植の治療薬として広く臨床応用されている薬剤である.本稿では,ステロイド製剤の分類と効果,特徴について整理後に,周術期の合併症に対するステロイド療法の使い方について概説する.
Interventional endoscopy
著者: 冨嶋享 , 藤澤聡郎 , 伊佐山浩通
ページ範囲:P.356 - P.359
Interventional EUSとは
超音波内視鏡(EUS)は消化管を介して胆道・膵臓を詳細に観察することができるmodalityである.その感度は高く,CT・MRIで見つからない微小病変の検出も可能であり,胆膵系疾患の早期発見そして予後を改善するために必要不可欠な手技であると考えられる.Interventional EUSはここでは治療的穿刺を指し,デバイスの進化とともにEUS関連手技は進歩してきている.その進歩はEUS下針生検のみにとどまらず,EUSにて描出できるすべてのtargetに対して薬剤やマーカーの注入,そしてドレナージチューブやステントの挿入など先進的な治療も可能になってきている.2012年に超音波内視鏡下瘻孔形成術(腹腔内膿瘍に関するもの)として保険収載され,超音波内視鏡下に膵仮性囊胞・膵膿瘍・閉塞性黄疸・骨盤内膿瘍に対して瘻孔形成術が算定可能である.
具体的に閉塞性黄疸に対する瘻孔形成術としては,(1)超音波内視鏡下胆管ドレナージ(EUS-guided biliary drainage;EUS-BD)がある.EUS-BDはそのドレナージ経路により①EUSガイド下胆管十二指腸吻合術(EUS-guided choledochoduodenostomy;EUS-CDS),②EUSガイド下胆管胃吻合術(EUS-guided hepaticogastrostomy;EUS-HGS),③EUSガイド下胆管空腸吻合術(EUS-guided hepaticojejunostomy;EUS-HJS)に分けられ,また瘻孔を形成しない方法として④EUS-antegrade stenting(EUS-AGS)や⑤EUS-rendezvous assisted ERCP(EUS-RV)があり,計5つに分けられる.
ひとやすみ・182
マインドコントロールで前向きに
著者: 中川国利
ページ範囲:P.72 - P.72
医師の自死率は他職種より高いとされ,原因として長時間労働,さらにはストレスの多い職場環境が指摘されている.とくに外科医の職場環境は過酷であり,自ら選んだ外科医を続けるためには個人的にも対応策が求められる.
長時間労働は最近の働き方改革でも大きな課題となっており,時間外勤務の短縮や有給休暇の取得が推進されつつある.しかしながら医師だけが例外とされ,今後も医師の過労死や過労自死が危惧される.なお私の大学同級生では87名中5名が既に死亡しているが,内3名が実に自死である.今更ながら医師が過酷な職場環境に置かれていることを認識した次第である.
昨日の患者
失われた父親の権威
著者: 中川国利
ページ範囲:P.247 - P.247
社会からは有能な医師として評価されているベテラン外科医でも,日常生活を共にしている家族からの信頼を保ち続けることは至難の技である.診断が特に困難な急性疾患の初期段階で息子の病気を誤診し,家族からの信頼を失った先輩外科医S先生を紹介する.
30年ほど前にもなるが,一緒に勤めていたS先生の奥さんが小学生の息子を連れて私の外来を受診した.息子は2日前から心窩部痛そして右下腹部痛が生じ,38℃台の発熱を訴えていた.そこでベッドに横たえ,右下腹部を触れた.すると著明な筋性防御を伴う圧痛を認め,典型的な急性虫垂炎の症状を呈していたため,急性虫垂炎と診断した.また血液検査では白血球数やCRPの著明な増加を,腹部超音波検査でも虫垂壁肥厚や膿瘍を認め,明白な虫垂炎所見であった.そこで父親であるS先生に報告した.するとS先生も急性虫垂炎と診断し,自らが主治医として息子の虫垂切除術を施行した.虫垂は穿孔し,周囲に膿瘍を形成していたが,手術は順調に終了した.
1200字通信・136
寿命あれこれ
著者: 板野聡
ページ範囲:P.313 - P.313
各国の衛生事情や医療水準のバロメーターの1つに平均寿命があります.そして,最近の高齢化にともない,ただ単に生存していたということではなく,「正常な生活を営むことができている」という意味で「健康寿命」という言葉が使われ始めています.
日本人の平均寿命は,2010年の時点で男性が79.55歳,女性が86.30歳で,世界でもトップクラスの長寿国と言われています.一方で,健康寿命は,男性で70.42歳,女性が73.62歳となっており,平均寿命との差(男性で約9年,女性で約12年)が,医療や要介護などの支援が必要な期間とされています.したがって,この差が大きくなるほど社会保障費が大きくなるため,現在盛んに健康寿命を延ばし,その差を小さくすることが勧められています.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.2 - P.5
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.355 - P.355
奥付 フリーアクセス
ページ範囲:P.360 - P.360
基本情報
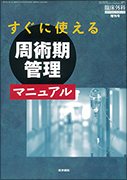
バックナンバー
79巻13号(2024年12月発行)
特集 JSES技術認定取得をめざせ2025
79巻12号(2024年11月発行)
特集 Acute Care Surgery入門
79巻11号(2024年10月発行)
増刊号 2024年最新版 外科局所解剖全図—ランドマークの出し方と損傷回避法
79巻10号(2024年10月発行)
特集 手術支援機器 百花繚乱!—ロボットとデバイスホールダー
79巻9号(2024年9月発行)
特集 徹底解説 大腸癌治療ガイドライン2024
79巻8号(2024年8月発行)
特集 合併症を起こさない食道癌手術!—ハイボリュームセンターの技を学ぼう
79巻7号(2024年7月発行)
特集 外科医が知っておくべき 肝胆膵腫瘍に対する薬物療法
79巻6号(2024年6月発行)
特集 結腸左半切除を極める
79巻5号(2024年5月発行)
特集 進化する外科教育と手術トレーニング
79巻4号(2024年4月発行)
特集 エキスパートに聞く!膵頭十二指腸切除のすべて
79巻3号(2024年3月発行)
特集 外科医必携 患者さんとのトラブルを防ぐためのハンドブック
79巻2号(2024年2月発行)
特集 ゲノム医学を外科診療に活かす!
79巻1号(2024年1月発行)
特集 若手外科医のライフハック—仕事・日常・将来を豊かにする,先輩たちの仕事術
78巻13号(2023年12月発行)
特集 ハイボリュームセンターのオペ記事《消化管癌編》
78巻12号(2023年11月発行)
特集 胃癌に対するconversion surgery—Stage Ⅳでも治したい!
78巻11号(2023年10月発行)
増刊号 —消化器・一般外科—研修医・専攻医サバイバルブック—術者として経験すべき手技のすべて
78巻10号(2023年10月発行)
特集 肝胆膵外科 高度技能専門医をめざせ!
78巻9号(2023年9月発行)
特集 見てわかる! 下部消化管手術における最適な剝離層
78巻8号(2023年8月発行)
特集 ロボット手術新時代!—極めよう食道癌・胃癌・大腸癌手術
78巻7号(2023年7月発行)
特集 術後急変!—予知・早期発見のベストプラクティス
78巻6号(2023年6月発行)
特集 消化管手術での“困難例”対処法—こんなとき,どうする?
78巻5号(2023年5月発行)
特集 術後QOLを重視した胃癌手術と再建法
78巻4号(2023年4月発行)
総特集 腹壁ヘルニア修復術の新潮流—瘢痕ヘルニア・臍ヘルニア・白線ヘルニア
78巻3号(2023年3月発行)
特集 進化する肝臓外科—高難度腹腔鏡下手術からロボット支援下手術の導入まで
78巻2号(2023年2月発行)
特集 最新医療機器・材料を使いこなす
78巻1号(2023年1月発行)
特集 外科医が知っておくべき! 免疫チェックポイント阻害薬
77巻13号(2022年12月発行)
特集 新・外科感染症診療ハンドブック
77巻12号(2022年11月発行)
特集 外科医必携 緊急対応が必要な大腸疾患
77巻11号(2022年10月発行)
増刊号 術前画像の読み解きガイド—的確な術式選択と解剖把握のために
77巻10号(2022年10月発行)
特集 外科医が担う緩和治療
77巻9号(2022年9月発行)
特集 導入! ロボット支援下ヘルニア修復術
77巻8号(2022年8月発行)
特集 よくわかる肛門疾患—診断から手術まで
77巻7号(2022年7月発行)
特集 徹底解説! 食道胃接合部癌《最新版》
77巻6号(2022年6月発行)
特集 ラパ胆を極める!
77巻5号(2022年5月発行)
特集 直腸癌局所再発に挑む—最新の治療戦略と手術手技
77巻4号(2022年4月発行)
特集 そろそろ真剣に考えよう 胃癌に対するロボット支援手術
77巻3号(2022年3月発行)
特集 肝胆膵術後合併症—どう防ぐ? どう対処する?
77巻2号(2022年2月発行)
特集 ガイドラインには書いていない 大腸癌外科治療のCQ—妥当な治療と適応を見直そう
77巻1号(2022年1月発行)
特集 外科医が知っておくべき—《最新版》栄養療法
76巻13号(2021年12月発行)
特集 Conversion surgeryアップデート
76巻12号(2021年11月発行)
特集 ストーマ・ハンドブック—外科医に必要な知識と手術手技のすべて
76巻11号(2021年10月発行)
増刊号 Stepごとに要点解説 標準術式アトラス最新版—特別付録Web動画
76巻10号(2021年10月発行)
特集 スコピストを極める
76巻9号(2021年9月発行)
特集 血管外科的手技を要する肝胆膵・移植手術
76巻8号(2021年8月発行)
特集 横行結腸癌の腹腔鏡下D3郭清手術—私のやり方,私の工夫
76巻7号(2021年7月発行)
特集 若手外科医のための食道手術ハンドブック—良性から悪性まで
76巻6号(2021年6月発行)
特集 神経・神経叢を極める—さらに精緻な消化器外科手術を求めて
76巻5号(2021年5月発行)
特集 側方リンパ節郭清のすべて—開腹からロボット手術まで
76巻4号(2021年4月発行)
特集 肥満外科A to Z
76巻3号(2021年3月発行)
特集 ロボット膵切除の導入ガイド—先行施設にノウハウを学ぶ
76巻2号(2021年2月発行)
特集 外科医のための—悪性腫瘍補助療法のすべて
76巻1号(2021年1月発行)
特集 徹底解説 術後後遺症をいかに防ぐか—コツとポイント
75巻13号(2020年12月発行)
特集 膵頭十二指腸切除の完全ガイド—定型術式から困難症例への対処法まで
75巻12号(2020年11月発行)
特集 消化器外科手術 助手の極意—開腹からロボット手術まで
75巻11号(2020年10月発行)
増刊号 早わかり縫合・吻合のすべて
75巻10号(2020年10月発行)
特集 ガイドラインには書いていない—胃癌治療のCQ
75巻9号(2020年9月発行)
特集 変貌する肝移植—適応拡大・ドナー選択・治療戦略の最先端を知る
75巻8号(2020年8月発行)
特集 遺伝性腫瘍とゲノム医療を学ぶ
75巻7号(2020年7月発行)
特集 若手外科医必携!—緊急手術の適応と術式
75巻6号(2020年6月発行)
特集 膵癌診療ガイドライン改訂を外科医はこう読み解く—ディベート&ディスカッション
75巻5号(2020年5月発行)
特集 taTMEのすべて
75巻4号(2020年4月発行)
特集 実践! 手術が上達するトレーニング法—Off the Job Trainingの最新動向
75巻3号(2020年3月発行)
特集 一般・消化器外科医のための できる! 漢方
75巻2号(2020年2月発行)
特集 「縫合不全!!」を防ぐ
75巻1号(2020年1月発行)
特集 “超”高難度手術! 他臓器合併切除術を極める
74巻13号(2019年12月発行)
特集 見せます! できる外科医のオペ記事—肝胆膵高度技能医は手術をこう描く
74巻12号(2019年11月発行)
特集 特殊な鼠径部ヘルニアに対する治療戦略
74巻11号(2019年10月発行)
増刊号 すぐに使える周術期管理マニュアル
74巻10号(2019年10月発行)
特集 腹腔鏡下胃手術のすべて
74巻9号(2019年9月発行)
特集 膵・消化管神経内分泌腫瘍—診断・治療の基本と最新動向
74巻8号(2019年8月発行)
特集 これだけは押さえたい!—大腸癌取扱い規約・治療ガイドライン—改訂のポイント
74巻7号(2019年7月発行)
特集 徹底解説! 噴門側胃切除術
74巻6号(2019年6月発行)
特集 肛門を極める
74巻5号(2019年5月発行)
特集 JSES技術認定取得をめざせ!
74巻4号(2019年4月発行)
特集 こんなときどうする!?—消化器外科の術中トラブル対処法
74巻3号(2019年3月発行)
特集 これからはじめるロボット手術
74巻2号(2019年2月発行)
特集 急性胆囊炎診療をマスターしよう
74巻1号(2019年1月発行)
特集 当直医必携!「右下腹部痛」を極める
73巻13号(2018年12月発行)
特集 ここがポイント!—サルコペニアの病態と対処法
73巻12号(2018年11月発行)
特集 炎症性腸疾患アップデート—いま外科医に求められる知識と技術
73巻11号(2018年10月発行)
増刊号 あたらしい外科局所解剖全図—ランドマークとその出し方
73巻10号(2018年10月発行)
特集 胃癌治療ガイドライン最新版を読み解く—改定のポイントとその背景
73巻9号(2018年9月発行)
特集 癌手術エキスパートになるための道
73巻8号(2018年8月発行)
特集 徹底解説! 膵尾側切除を極める
73巻7号(2018年7月発行)
特集 最新版 “腸閉塞”を極める!
73巻6号(2018年6月発行)
特集 こうやって教える・学ぶ 高難度消化器外科手術—新エキスパートへの登竜門
73巻5号(2018年5月発行)
特集 縦隔を覗き,さらにくり抜く—これからの食道・胃外科手術
73巻4号(2018年4月発行)
特集 機能温存と機能再建をめざした消化器外科手術—術後QOL向上のために
73巻3号(2018年3月発行)
特集 徹底解説!—膵頭十二指腸切除の手術手技
73巻2号(2018年2月発行)
特集 外科医が知っておくべき—最新Endoscopic Intervention
73巻1号(2018年1月発行)
特集 閉塞性大腸癌—ベストプラクティスを探す
72巻13号(2017年12月発行)
特集 最新の胆道癌診療トピックス—新たな治療戦略の可能性を探る
72巻12号(2017年11月発行)
特集 徹底解説!ここが変わった膵癌診療—新規約・ガイドラインに基づいて
72巻11号(2017年10月発行)
増刊号 手術ステップごとに理解する—標準術式アトラス
72巻10号(2017年10月発行)
特集 Conversion Surgery—進行消化器がんのトータル治療戦略
72巻9号(2017年9月発行)
特集 知っておきたい 乳がん診療のエッセンス
72巻8号(2017年8月発行)
特集 がん治療医のための漢方ハンドブック
72巻7号(2017年7月発行)
特集 イラストでわかる!—消化器手術における最適な剝離層
72巻6号(2017年6月発行)
特集 術後重大合併症—これだけは知っておきたい緊急処置法
72巻5号(2017年5月発行)
特集 百花繚乱! エネルギーデバイスを使いこなす
72巻4号(2017年4月発行)
特集 消化管吻合アラカルト—あなたの選択は?
72巻3号(2017年3月発行)
特集 目で見る腹腔鏡下肝切除—エキスパートに学ぶ!
72巻2号(2017年2月発行)
特集 ビッグデータにもとづいた—術前リスクの評価と対処法
72巻1号(2017年1月発行)
特集 最新の内視鏡外科手術の適応と注意点
71巻13号(2016年12月発行)
特集 名手からの提言—手術を極めるために
71巻12号(2016年11月発行)
特集 転移性肝腫瘍のいま—なぜ・どこが原発臓器ごとに違うのか
71巻11号(2016年10月発行)
増刊号 消化器・一般外科医のための—救急・集中治療のすべて
71巻10号(2016年10月発行)
特集 エキスパートが教える 鼠径部ヘルニアのすべて
71巻9号(2016年9月発行)
特集 食道癌手術のコツと要点
71巻8号(2016年8月発行)
特集 外科医が攻める高度進行大腸癌
71巻7号(2016年7月発行)
特集 胆管系合併症のすべて—その予防とリカバリー
71巻6号(2016年6月発行)
特集 必携 腹腔鏡下胃癌手術の完全マスター—ビギナーからエキスパートまで
71巻5号(2016年5月発行)
特集 外科臨床研究のノウハウと重要研究の総まとめ
71巻4号(2016年4月発行)
特集 大腸癌肝転移—最新の治療ストラテジー
71巻3号(2016年3月発行)
特集 術後障害のリアル—外来フォローの実力が臓器損失を補う
71巻2号(2016年2月発行)
特集 イラストでみる大腸癌腹腔鏡手術のポイント
71巻1号(2016年1月発行)
特集 十二指腸乳頭部病変に対する新たな治療戦略—新規約・新ガイドラインに基づいて
70巻13号(2015年12月発行)
特集 外科医に求められる積極的緩和医療—延命と症状緩和の狭間で
70巻12号(2015年11月発行)
特集 同時性・異時性の重複がんを見落とさない—がん診療における他臓器への目配り
70巻11号(2015年10月発行)
増刊号 消化器・一般外科手術のPearls&Tips—ワンランク上の手術を達成する技と知恵
70巻10号(2015年10月発行)
特集 エキスパートの消化管吻合を学ぶ
70巻9号(2015年9月発行)
特集 再発に挑む!—外科治療の役割
70巻8号(2015年8月発行)
特集 大腸癌腹腔鏡手術の新展開—Reduced port surgeryからロボット手術まで
70巻7号(2015年7月発行)
特集 Neoadjuvant therapyの最新の動向—がんの治療戦略はどのように変わっていくのか
70巻6号(2015年6月発行)
特集 胃切除後再建術式の工夫とその評価
70巻5号(2015年5月発行)
特集 外科医が知っておくべき がん薬物療法の副作用とその対策
70巻4号(2015年4月発行)
特集 膵・消化管神経内分泌腫瘍(GEP-NET)のアップデート
70巻3号(2015年3月発行)
特集 生検材料を手術に活かす
70巻2号(2015年2月発行)
特集 肛門良性疾患を極める—目で見る 多彩な病態へのアプローチ法
70巻1号(2015年1月発行)
特集 胆道癌外科切除—再発防止のストラテジー
69巻13号(2014年12月発行)
特集 早期胃癌の外科治療を極める—「EMR 適応外」への安全で有益な縮小手術を求めて
69巻12号(2014年11月発行)
特集 外科切除適応の境界領域—Borderline resectable cancerへの対応
69巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ERAS時代の周術期管理マニュアル
69巻10号(2014年10月発行)
特集 直腸癌局所再発に対する治療戦略―新たな展開
69巻9号(2014年9月発行)
特集 外科医が知っておくべき小腸疾患
69巻8号(2014年8月発行)
特集 肝胆膵癌の血管浸潤をどう治療するか
69巻7号(2014年7月発行)
特集 術後合併症への対処法 Surgical vs Non-Surgical―いつどのように判断するか?
69巻6号(2014年6月発行)
特集 癌の補助療法アップデート
69巻5号(2014年5月発行)
特集 消化器外科での救急医療―救急外来から手術室そして病棟まで
69巻4号(2014年4月発行)
特集 サルベージとコンバージョン―集学的治療で外科手術に求められるもの
69巻3号(2014年3月発行)
特集 究極の肛門温存術式ISR―長期成績からわかる有用性と問題点
69巻2号(2014年2月発行)
特集 ディベート★消化器・一般外科手術―選ぶのはどっちだ!
69巻1号(2014年1月発行)
特集 見直される膵癌診療の新展開
68巻13号(2013年12月発行)
特集 切徐可能なStage Ⅳ胃癌に対する外科治療
68巻12号(2013年11月発行)
特集 漢方を上手に使う―エビデンスに基づいた外科診療
68巻11号(2013年10月発行)
特集 術前画像診断のポイントと術中解剖認識
68巻10号(2013年10月発行)
特集 次代の外科専門医をめざしたトレーニングシステム
68巻9号(2013年9月発行)
特集 大腸癌腹膜播種を極める―最近の進歩と今後の展望
68巻8号(2013年8月発行)
特集 外科医のための癌免疫療法―基礎と臨床
68巻7号(2013年7月発行)
特集 NOTSS―外科医に問われる手技以外のスキル
68巻6号(2013年6月発行)
特集 胃癌腹膜転移治療の最前線
68巻5号(2013年5月発行)
特集 一般外科医が知っておくべき小児患者への対応
68巻4号(2013年4月発行)
特集 「食道胃接合部癌」に迫る!
68巻3号(2013年3月発行)
特集 CRT時代の直腸癌手術―最善の戦略は何か
68巻2号(2013年2月発行)
特集 術後の血管系合併症―その診断と対策
68巻1号(2013年1月発行)
特集 進歩する消化器外科手術―術式の温故知新
67巻13号(2012年12月発行)
特集 本当は怖い 臓器解剖変異―外科医が必ず知っておくべき知識
67巻12号(2012年11月発行)
特集 食道癌・胃癌切除後の再建法を見直す―達人の選択
67巻11号(2012年10月発行)
特集 外科医のための癌診療データ
67巻10号(2012年10月発行)
特集 炎症性腸疾患のすべて―新しい治療戦略
67巻9号(2012年9月発行)
特集 高齢者外科手術における周術期管理
67巻8号(2012年8月発行)
特集 知っておきたい放射線・粒子線治療
67巻7号(2012年7月発行)
特集 分子標的薬の有害事象とその対策
67巻6号(2012年6月発行)
特集 よくわかるNCD
67巻5号(2012年5月発行)
特集 次代のMinimally Invasive Surgery!
67巻4号(2012年4月発行)
特集 内視鏡外科手術の腕をみがく―技術認定医をめざして
67巻3号(2012年3月発行)
特集 消化器外科のドレーン管理を再考する
67巻2号(2012年2月発行)
特集 肝胆膵外科手術における術中トラブル―その予防と対処のポイント
67巻1号(2012年1月発行)
特集 「切除困難例」への化学療法後の手術―根治切除はどこまで可能か
66巻13号(2011年12月発行)
特集 外科医のための消化器内視鏡Up-to-Date
66巻12号(2011年11月発行)
特集 目で見てわかる肛門疾患治療
66巻11号(2011年10月発行)
特集 外科医のための最新癌薬物療法
66巻10号(2011年10月発行)
特集 進歩する癌転移診断―外科臨床はどう変わるのか
66巻9号(2011年9月発行)
特集 下大静脈にかかわる病態を見直す
66巻8号(2011年8月発行)
特集 画像診断の進歩をいかに手術に役立てるか
66巻7号(2011年7月発行)
特集 術前薬物療法は乳癌手術を縮小させるか
66巻6号(2011年6月発行)
特集 栄養療法―最新の知見と新たな展開
66巻5号(2011年5月発行)
特集 いま必要な外科治療に関する臨床試験の最新知識
66巻4号(2011年4月発行)
特集 悪性腫瘍の術中病理診断を効果的に活用する―どこを検索すべきか,どう対応すべきか
66巻3号(2011年3月発行)
特集 知っておくべき 外科手術の神経系合併症 その診断と対策
66巻2号(2011年2月発行)
特集 T4の癌―臓器別特性と治療戦略
66巻1号(2011年1月発行)
特集 医療経済からみた大腸癌化学療法
65巻13号(2010年12月発行)
特集 「出血量ゼロ」をめざした消化管癌の内視鏡下手術
65巻12号(2010年11月発行)
特集 新しいエネルギーデバイスの構造と使い方のコツ
65巻11号(2010年10月発行)
特集 外科医のための大腸癌の診断と治療
65巻10号(2010年10月発行)
特集 乳糜胸水・腹水を考える―その原因と対策
65巻9号(2010年9月発行)
特集 [臓器別]消化器癌終末期の特徴とターミナルケア
65巻8号(2010年8月発行)
特集 ESD時代の外科治療
65巻7号(2010年7月発行)
特集 腹壁瘢痕ヘルニア治療up date
65巻6号(2010年6月発行)
特集 癌外科治療の日本と海外との相違点
65巻5号(2010年5月発行)
特集 消化器外科手術における新しい潮流
65巻4号(2010年4月発行)
特集 消化器癌neoadjuvant chemotherapyの新展開
65巻3号(2010年3月発行)
特集 エキスパートが伝える 消化器癌手術の流れと手術助手の心得
65巻2号(2010年2月発行)
特集 外科医に必要なPET検査の知識―その有用性と問題点
65巻1号(2010年1月発行)
特集 がん診療ガイドライン―臨床現場における有効活用法
64巻13号(2009年12月発行)
特集 内視鏡下手術―もう一歩のステップアップのために
64巻12号(2009年11月発行)
特集 転移性腫瘍に対する治療戦略
64巻11号(2009年10月発行)
特集 できる!縫合・吻合
64巻10号(2009年10月発行)
特集 消化器外科における経腸栄養の意義と役割
64巻9号(2009年9月発行)
特集 外科医に求められるチーム医療Practice
64巻8号(2009年8月発行)
特集 胆囊癌根治手術をめぐる諸問題
64巻7号(2009年7月発行)
特集 肝胆膵癌に対する補助療法―治療成績の向上を目指して
64巻6号(2009年6月発行)
特集 消化器癌外科治療のrandomized controlled trial
64巻5号(2009年5月発行)
特集 炎症性腸疾患外科治療のcontroversy
64巻4号(2009年4月発行)
特集 脾臓をめぐる最近のトピックス
64巻3号(2009年3月発行)
特集 直腸癌治療―最近の進歩と動向
64巻2号(2009年2月発行)
特集 最近のGIST診療―診療ガイドラインの理解と実践
64巻1号(2009年1月発行)
特集 外科診療上知っておきたい新たな予後予測因子・スコア
63巻13号(2008年12月発行)
特集 外科におけるadjuvant/neoadjuvant chemotherapy update
63巻12号(2008年11月発行)
特集 十二指腸病変に対する外科的アプローチ
63巻11号(2008年10月発行)
特集 肛門疾患診療のすべて
63巻10号(2008年10月発行)
特集 鼠径ヘルニアの治療NOW―乳幼児から成人まで
63巻9号(2008年9月発行)
特集 がんの切除範囲を考える―診断法とその妥当性
63巻8号(2008年8月発行)
特集 St. Gallen 2007に基づいた乳癌テーラーメイド補助療法
63巻7号(2008年7月発行)
特集 実践に必要な術後創の管理
63巻6号(2008年6月発行)
特集 肝・胆・膵領域における腹腔鏡下手術の最前線
63巻5号(2008年5月発行)
特集 胆道癌外科診療を支えるエキスパートテクニック
63巻4号(2008年4月発行)
特集 消化器外科と漢方
63巻3号(2008年3月発行)
特集 術前・術中のリンパ節転移診断の方法とその有用性
63巻2号(2008年2月発行)
特集 安全な消化管器械吻合をめざして
63巻1号(2008年1月発行)
特集 機能温存手術のメリット・デメリット
62巻13号(2007年12月発行)
特集 膵臓外科の新たな展開
62巻12号(2007年11月発行)
特集 Up-to-Date外科医のための創傷治癒
62巻11号(2007年10月発行)
特集 癌診療に役立つ最新データ2007-2008
62巻10号(2007年10月発行)
特集 肛門疾患診断・治療のコツと実際
62巻9号(2007年9月発行)
特集 多発肝転移をめぐって
62巻8号(2007年8月発行)
特集 Surgical Site Infection(SSI)対策
62巻7号(2007年7月発行)
特集 乳癌の治療戦略―エビデンスとガイドラインの使い方
62巻6号(2007年6月発行)
特集 肝胆膵術後合併症―その予防のために
62巻5号(2007年5月発行)
特集 外来がん化学療法と外科
62巻4号(2007年4月発行)
特集 癌診療ガイドラインの功罪
62巻3号(2007年3月発行)
特集 術後呼吸器合併症―予防と対策の最新知識
62巻2号(2007年2月発行)
特集 外科領域におけるインフォームド・コンセントと医療安全対策
62巻1号(2007年1月発行)
特集 良性腸疾患における腹腔鏡下手術の適応と限界
61巻13号(2006年12月発行)
特集 消化器外科術後合併症の治療戦略―私たちはこのように治療している
61巻12号(2006年11月発行)
特集 生活習慣病および代謝性疾患と外科
61巻11号(2006年10月発行)
特集 イラストレイテッド外科標準術式
61巻10号(2006年10月発行)
特集 今どうしてNSTなのか?
61巻9号(2006年9月発行)
特集 消化器外科医に必要な低侵襲治療の知識
61巻8号(2006年8月発行)
特集 急性腹症における低侵襲な治療法選択
61巻7号(2006年7月発行)
特集 消化器外科における非観血的ドレナージ
61巻6号(2006年6月発行)
特集 癌の播種性病変の病態と診断・治療
61巻5号(2006年5月発行)
特集 手術のための臨床局所解剖
61巻4号(2006年4月発行)
特集 最新の手術器械―使いこなすコツを学ぶ
61巻3号(2006年3月発行)
特集 乳腺疾患を取り巻くガイドラインと最新の知見―最適な診療を目指して
61巻2号(2006年2月発行)
特集 外科医に求められる緩和医療の知識
61巻1号(2006年1月発行)
特集 GIST―診断と治療の最前線
60巻13号(2005年12月発行)
特集 消化管機能温存を考えた外科手術最前線
60巻12号(2005年11月発行)
特集 生体肝移植―最新の話題
60巻11号(2005年10月発行)
特集 癌治療のプロトコール2005-2006
60巻10号(2005年10月発行)
特集 自動吻合器・縫合器による消化管再建の標準手技と応用
60巻9号(2005年9月発行)
特集 癌告知とインフォームド・コンセント
60巻8号(2005年8月発行)
特集 肝切除のコツを知る―出血を少なくするために
60巻7号(2005年7月発行)
特集 炎症性腸疾患―治療における最近の進歩
60巻6号(2005年6月発行)
特集 化学放射線療法―現状とイメージングによる効果判定
60巻5号(2005年5月発行)
特集 外科栄養療法の新たな潮流
60巻4号(2005年4月発行)
特集 Surgical Site Infection(SSI)の現状と対策
60巻3号(2005年3月発行)
特集 急性肺塞栓症の最新診療
60巻2号(2005年2月発行)
特集 再発食道癌を考える
60巻1号(2005年1月発行)
特集 手術のグッドタイミング
59巻13号(2004年12月発行)
特集 直腸癌に対する手術のコツ
59巻12号(2004年11月発行)
特集 術中の出血コントロールと止血のノウハウ
59巻11号(2004年10月発行)
特集 小外科・外来処置マニュアル
59巻10号(2004年10月発行)
特集 周術期の輸液と感染対策
59巻9号(2004年9月発行)
特集 乳癌初回の診療:ガイドラインと主治医の裁量
59巻8号(2004年8月発行)
特集 肛門疾患診断・治療の実際
59巻7号(2004年7月発行)
特集 研修医のための外科基本手技とそのコツ
59巻6号(2004年6月発行)
特集 内視鏡外科手術を安全に行うために
59巻5号(2004年5月発行)
特集 Sentinel node navigation surgery―新たなる展開
59巻4号(2004年4月発行)
特集 甲状腺癌治療の最適化を目指して
59巻3号(2004年3月発行)
特集 肝細胞癌治療の最前線
59巻2号(2004年2月発行)
特集 GIST(gastrointestinal stromal tumor)診療の最前線
59巻1号(2004年1月発行)
特集 癌en bloc切除とnon-touch isolation techniqueの考え方と実践
58巻13号(2003年12月発行)
特集 内視鏡下手術で発展した手技・器具の外科手術への応用
58巻12号(2003年11月発行)
特集 浸潤性膵管癌の診療をどうするか
58巻11号(2003年10月発行)
特集 クリニカルパスによる外科医療の進歩
58巻10号(2003年10月発行)
特集 神経温存胃切除術
58巻9号(2003年9月発行)
特集 癌と紛らわしい各領域の諸病変
58巻8号(2003年8月発行)
特集 癌化学療法レジメンの選択とその根拠:消化器癌
58巻7号(2003年7月発行)
特集 癌化学療法レジメンの選択とその根拠:乳癌・肺癌・甲状腺癌
58巻6号(2003年6月発行)
特集 癌肝転移の治療戦略
58巻5号(2003年5月発行)
特集 栄養療法とformula
58巻4号(2003年4月発行)
特集 腹腔鏡下大腸切除術のコツ
58巻3号(2003年3月発行)
特集 Q&A器械吻合・縫合のコツ
58巻2号(2003年2月発行)
特集 胆囊癌NOW
58巻1号(2003年1月発行)
特集 外科における重症感染症とその対策
57巻13号(2002年12月発行)
特集 胃癌治療ガイドラインの検証
57巻12号(2002年11月発行)
特集 肛門疾患手術のup to date
57巻11号(2002年10月発行)
特集 癌診療に役立つ最新データ
57巻10号(2002年10月発行)
特集 内視鏡下手術の現状と問題点
57巻9号(2002年9月発行)
特集 パソコン活用術とその周辺
57巻8号(2002年8月発行)
特集 ヘルニア—最新の治療
57巻7号(2002年7月発行)
特集 外科診療とステロイド療法
57巻6号(2002年6月発行)
特集 エビデンスから見直す癌術後患者のフォローアップ
57巻5号(2002年5月発行)
特集 肝切除術のコツ
57巻4号(2002年4月発行)
特集 消化器外科における機能検査
57巻3号(2002年3月発行)
特集 乳癌:初回治療の標準化
57巻2号(2002年2月発行)
特集 食道癌治療におけるcontroversy
57巻1号(2002年1月発行)
特集 最先端の外科医療
56巻13号(2001年12月発行)
特集 IVRの現状と問題点
56巻12号(2001年11月発行)
特集 新しい医療材料と器具
56巻11号(2001年10月発行)
特集 画像で決める癌手術の切除範囲—典型症例総覧
56巻10号(2001年10月発行)
特集 甲状腺外科—最新の臨床
56巻9号(2001年9月発行)
特集 外科と消毒と感染予防
56巻8号(2001年8月発行)
特集 閉塞性黄疸の診療手順
56巻7号(2001年7月発行)
特集 肝良性疾患—鑑別診断と治療法選択のupdate
56巻6号(2001年6月発行)
特集 大腸癌の術後再発をめぐって
56巻5号(2001年5月発行)
特集 家族性腫瘍—診断と治療の現況
56巻4号(2001年4月発行)
特集 外科におけるクリニカルパスの展開
56巻3号(2001年3月発行)
特集 総胆管結石治療の最前線—手技と周辺機器の進歩
56巻2号(2001年2月発行)
特集 重症急性膵炎の診療Now
56巻1号(2001年1月発行)
特集 21世紀の外科—Tissue Engineering
55巻13号(2000年12月発行)
特集 超音波ガイド下の穿刺手技
55巻12号(2000年11月発行)
特集 胃癌術後のフォローアップ:再発と二次癌対策
55巻11号(2000年10月発行)
特集 癌治療のプロトコール—当施設はこうしている
55巻10号(2000年10月発行)
特集 ベッドサイド基本手技とコツ
55巻9号(2000年9月発行)
特集 外科医に求められる緩和医療プラクティス
55巻8号(2000年8月発行)
特集 肛門疾患診療の実際とコツ
55巻7号(2000年7月発行)
特集 抗菌薬ベストチョイス—その理論と実際
55巻6号(2000年6月発行)
特集 胃全摘後の消化管再建—術式のベストチョイス
55巻5号(2000年5月発行)
特集 輸液:その組成・アクセス・管理
55巻4号(2000年4月発行)
特集 各種ステント治療のノウハウ
55巻3号(2000年3月発行)
特集 Sentinel Node Navigation Surgery
55巻2号(2000年2月発行)
特集 イレウス診療のupdate
55巻1号(2000年1月発行)
特集 肝臓移植を理解する
54巻13号(1999年12月発行)
特集 大腸の非腫瘍性疾患—外科医のための診療指針
54巻12号(1999年11月発行)
特集 胃・十二指腸の非腫瘍性疾患—外科医のための診療指針
54巻11号(1999年10月発行)
特集 薬物療法マニュアル
54巻10号(1999年10月発行)
特集 消化管EMRの現状と問題点
54巻9号(1999年9月発行)
特集 在宅栄養療法の標準管理
54巻8号(1999年8月発行)
特集 3D画像診断の肝胆膵手術への応用
54巻7号(1999年7月発行)
特集 膵臓外科に対するチャレンジ:切離・吻合の工夫
54巻6号(1999年6月発行)
特集 直腸癌の治療—機能温存手術のプログレス
54巻5号(1999年5月発行)
特集 切除標本取扱いガイドライン—癌取扱い規約に基づいた正しい取扱い法と肉眼所見の記載法
54巻4号(1999年4月発行)
特集 Surgical deviceの有効,安全な使い方
54巻3号(1999年3月発行)
特集 器械吻合・縫合におけるコツとピットフォール
54巻2号(1999年2月発行)
特集 癌転移治療のノウハウ
54巻1号(1999年1月発行)
特集 乳癌の手術:最適化への論点
53巻13号(1998年12月発行)
特集 外科・形成外科の連携と展望
53巻12号(1998年11月発行)
特集 肝癌治療のupdate
53巻11号(1998年10月発行)
特集 縫合・吻合法のバイブル
53巻10号(1998年10月発行)
特集 胃癌術後補助化学療法をめぐって
53巻9号(1998年9月発行)
特集 急性腹膜炎—病態と治療の最前線
53巻8号(1998年8月発行)
特集 肛門疾患診断・治療のノウハウ
53巻7号(1998年7月発行)
特集 分子生物学的診断は病理診断に迫れるか
53巻6号(1998年6月発行)
特集 ここまできたDay Surgery
53巻5号(1998年5月発行)
特集 病態別補充・補正のFormula
53巻4号(1998年4月発行)
特集 早期直腸癌診療のストラテジー
53巻3号(1998年3月発行)
特集 自己血輸血の現状と将来展望
53巻2号(1998年2月発行)
特集 食道・胃静脈瘤攻略法
53巻1号(1998年1月発行)
特集 胆道ドレナージを考える
52巻13号(1997年12月発行)
特集 血管系病変と腹部消化器外科
52巻12号(1997年11月発行)
特集 消化器外科領域におけるメタリックステント
52巻11号(1997年10月発行)
特集 外来診療・小外科マニュアル
52巻10号(1997年10月発行)
特集 食道癌診療のトピックス
52巻9号(1997年9月発行)
特集 甲状腺と上皮小体の外科—最近の進歩
52巻8号(1997年8月発行)
特集 Q&A 自動吻合器・縫合器の安全,有効な使い方
52巻7号(1997年7月発行)
特集 経腸栄養法—最新の動向
52巻6号(1997年6月発行)
特集 輸血後GVHDをめぐる諸問題
52巻5号(1997年5月発行)
特集 サイトカインからみた周術期管理
52巻4号(1997年4月発行)
特集 膵瘻の予防・治療のノウハウ
52巻3号(1997年3月発行)
特集 ドレッシング—創傷管理の新たな展開
52巻2号(1997年2月発行)
特集 消化器の“前癌病変”と“ハイリスク病変”
52巻1号(1997年1月発行)
特集 転移性肺癌診療の最新ストラテジー
51巻13号(1996年12月発行)
特集 大災害に対する外科医の備え
51巻12号(1996年11月発行)
特集 外科医のためのペインクリニック
51巻11号(1996年10月発行)
特集 術前ワークアップマニュアル—入院から手術当日までの患者管理
51巻10号(1996年10月発行)
特集 胃癌治療のup-to-date—機能温存手術と縮小手術
51巻9号(1996年9月発行)
特集 急性腹症—画像診断から初期治療まで
51巻8号(1996年8月発行)
特集 直腸癌に対する肛門機能温存手術の実際
51巻7号(1996年7月発行)
特集 図解 成人鼠径ヘルニア手術
51巻6号(1996年6月発行)
特集 外科医に必要な整形外科の知識
51巻5号(1996年5月発行)
特集 肛門疾患診療のポイント—エキスパート17人のノウハウ
51巻4号(1996年4月発行)
特集 術後感染症—予防と治療の実際
51巻3号(1996年3月発行)
特集 肝炎・肝硬変患者の消化器外科手術
51巻2号(1996年2月発行)
特集 甲状腺外科の新しい展開
51巻1号(1996年1月発行)
特集 乳房温存療法の適応と実際
50巻13号(1995年12月発行)
特集 外科医のための緩和ケア
50巻12号(1995年11月発行)
特集 消化器癌手術における皮膚切開と術野展開の工夫
50巻11号(1995年10月発行)
特集 術後1週間の患者管理
50巻10号(1995年10月発行)
特集 多臓器不全—患者管理の実際
50巻9号(1995年9月発行)
特集 出血させない消化器癌手術
50巻8号(1995年8月発行)
特集 高齢者の外科—キュアとケア
50巻7号(1995年7月発行)
特集 再発消化管癌を治療する
50巻6号(1995年6月発行)
特集 外科臨床医のための基本手技
50巻5号(1995年5月発行)
特集 画像診断が変わる? MRIの新しい展開
50巻4号(1995年4月発行)
特集 新しい膵手術のテクニック
50巻3号(1995年3月発行)
特集 Q & A 人工呼吸管理とベンチレータ
50巻2号(1995年2月発行)
特集 消化器癌画像診断のノウ・ハウ
50巻1号(1995年1月発行)
特集 早期胃癌の内視鏡的根治切除
49巻13号(1994年12月発行)
特集 外科手術と輸血—最近の動向
49巻12号(1994年11月発行)
特集 ストーマの造設と管理—患者のQOLの視点から
49巻11号(1994年10月発行)
特集 施設別/新・悪性腫瘍治療のプロトコール
49巻10号(1994年10月発行)
特集 自動吻合器・縫合器を使いこなす
49巻9号(1994年9月発行)
特集 癌の外科治療とインフォームド・コンセント(IC)
49巻8号(1994年8月発行)
特集 消化器外科におけるInterventional Radiology(IVR)
49巻7号(1994年7月発行)
特集 腹腔鏡下の腹部救急疾患診療
49巻6号(1994年6月発行)
特集 静脈系疾患診療の新しい展開
49巻5号(1994年5月発行)
特集 術中肝エコーのABC
49巻4号(1994年4月発行)
特集 内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)
49巻3号(1994年3月発行)
特集 肝癌治療の最新ストラテジー
49巻2号(1994年2月発行)
特集 上部消化管の術後運動機能評価と病態
49巻1号(1994年1月発行)
特集 乳癌診療—今日の話題
48巻13号(1993年12月発行)
特集 スキルス胃癌の診断と治療
48巻12号(1993年11月発行)
特集 骨盤内悪性腫瘍の機能温存手術
48巻11号(1993年10月発行)
特集 Dos & Don'ts外来の小外科
48巻10号(1993年10月発行)
特集 今日の肺癌診療
48巻9号(1993年9月発行)
特集 食道癌治療への集学的アプローチ
48巻8号(1993年8月発行)
特集 疼痛をどうコントロールするか
48巻7号(1993年7月発行)
特集 Up-to-date総胆管結石症治療
48巻6号(1993年6月発行)
特集 MRSA感染症対策の実際
48巻5号(1993年5月発行)
特集 施設別・消化器癌術後栄養管理の実際
48巻4号(1993年4月発行)
特集 治療的ドレナージ
48巻3号(1993年3月発行)
特集 局所麻酔を行う外科医へ
48巻2号(1993年2月発行)
特集 消化管の機能温存手術
48巻1号(1993年1月発行)
特集 消化器癌切除材料取扱いマニュアル
47巻13号(1992年12月発行)
特集 今日の甲状腺癌診療
47巻12号(1992年11月発行)
特集 悪性腫瘍治療の現況—他科では今
47巻11号(1992年10月発行)
特集 外科患者・薬物療法マニュアル
47巻10号(1992年10月発行)
特集 形成外科から学び取る
47巻9号(1992年9月発行)
特集 大腸癌治療のフロンティア
47巻8号(1992年8月発行)
特集 膵癌への挑戦
47巻7号(1992年7月発行)
特集 肛門疾患診療の実際—私の方法と根拠
47巻6号(1992年6月発行)
特集 いまイレウスを診療する
47巻5号(1992年5月発行)
特集 腫瘍マーカーの理論と実際
47巻4号(1992年4月発行)
特集 静脈・経腸栄養のトピックス
47巻3号(1992年3月発行)
特集 再手術の適応と術式
47巻2号(1992年2月発行)
特集 下肢循環障害の治療—適応と限界
47巻1号(1992年1月発行)
特集 外科における超音波検査—新しい展開
46巻13号(1991年12月発行)
特集 院内感染—現状と対策
46巻12号(1991年11月発行)
特集 若年者癌診療の実際
46巻11号(1991年10月発行)
特集 術前・術後管理 '91
46巻10号(1991年10月発行)
特集 胆石症の非手術的治療—現況と問題点
46巻9号(1991年9月発行)
特集 胃癌の治療update
46巻8号(1991年8月発行)
特集 内視鏡下外科手術
46巻7号(1991年7月発行)
特集 熱傷治療のトピックス
46巻6号(1991年6月発行)
特集 食道静脈瘤治療の焦点
46巻5号(1991年5月発行)
特集 術前一般検査—異常値の読みと対策
46巻4号(1991年4月発行)
特集 癌のPalliative Therapy
46巻3号(1991年3月発行)
特集 乳房温存療法の実践
46巻2号(1991年2月発行)
特集 急性腹症の近辺—他科からのアドバイス
46巻1号(1991年1月発行)
特集 Day Surgeryはどこまで可能か
45巻13号(1990年12月発行)
特集 進行癌の画像診断—治癒切除の判定をどうするか
45巻12号(1990年11月発行)
特集 癌手術の補助療法—現状と展望
45巻11号(1990年10月発行)
特集 保存的治療の適応と限界—外科から,内科から
45巻10号(1990年10月発行)
特集 胸水・腹水への対処
45巻9号(1990年9月発行)
特集 消化管吻合法—私の方法とコツ
45巻8号(1990年8月発行)
特集 臓器全摘術の適応と問題点
45巻7号(1990年7月発行)
特集 外科医のための整形外科
45巻6号(1990年6月発行)
特集 転移性肝癌の治療
45巻5号(1990年5月発行)
特集 腹部血管病変の診療
45巻4号(1990年4月発行)
特集 今日のストーマ
45巻3号(1990年3月発行)
特集 新しい手術材料—特徴と使い方
45巻2号(1990年2月発行)
特集 Endoscopic Surgery—適応と手技
45巻1号(1990年1月発行)
特集 肺癌の診断と治療 '90
44巻13号(1989年12月発行)
特集 小児外科
44巻12号(1989年11月発行)
特集 胆嚢癌の外科
44巻11号(1989年10月発行)
特集 肛門疾患治療の現況
44巻10号(1989年9月発行)
特集 鼎談
44巻9号(1989年9月発行)
特集 がん放射線療法の現況と進歩
44巻8号(1989年8月発行)
特集 臓器生検の適応と手技
44巻7号(1989年7月発行)
特集 食道癌の手術
44巻6号(1989年6月発行)
特集 胃癌治療の最近の話題
44巻5号(1989年5月発行)
特集 外科臨床における病態別栄養
44巻4号(1989年4月発行)
特集 消化器良性疾患の手術適応—最近の考え方
44巻3号(1989年3月発行)
特集 肝門部胆管癌の治療
44巻2号(1989年2月発行)
特集 80歳以上高齢者の手術
44巻1号(1989年1月発行)
特集 膵臓の外科—up to date
43巻13号(1988年12月発行)
特集 直腸癌の手術
43巻12号(1988年11月発行)
特集 Drug Delivery Systemを利用した癌治療
43巻11号(1988年10月発行)
特集 外科医のためのMRIの臨床
43巻10号(1988年9月発行)
特集 高位胃潰瘍治療の問題点—外科から,内科から
43巻9号(1988年8月発行)
特集 消化器癌の相対非治癒切除
43巻8号(1988年7月発行)
特集 多発外傷—初療60分
43巻7号(1988年6月発行)
特集 鼠径ヘルニアの診療
43巻6号(1988年5月発行)
特集 —そこが知りたい—消化器外科手術のテクニックとコツ96
43巻5号(1988年5月発行)
特集 急性腹症のX線像・エコー像
43巻4号(1988年4月発行)
特集 外科診療における酸塩基平衡の異常
43巻3号(1988年3月発行)
特集 手術と輸血—最近のトピックス
43巻2号(1988年2月発行)
特集 集中治療を要する術後合併症
43巻1号(1988年1月発行)
特集 臓器移植のup to date '88
42巻13号(1987年12月発行)
特集 外科的感染症と抗生物質の選択
42巻12号(1987年11月発行)
特集 胆石症—最近の話題
42巻11号(1987年10月発行)
特集 Interventional Radiologyの現況
42巻10号(1987年9月発行)
特集 癌術後follow upと再発時の対策
42巻9号(1987年8月発行)
特集 乳癌診療のUp-to-date
42巻8号(1987年7月発行)
特集 いわゆる消化器早期癌の術後再発—その実態と対策
42巻7号(1987年6月発行)
特集 外科医の触診
42巻6号(1987年5月発行)
特集 [施設別]悪性腫瘍治療方針のプロトコール
42巻5号(1987年5月発行)
特集 外科医のための超音波応用診断手技
42巻4号(1987年4月発行)
特集 頸部腫瘤の臨床
42巻3号(1987年3月発行)
特集 消化管のEmergency—穿孔・破裂
42巻2号(1987年2月発行)
特集 外科医が使える形成外科手技
42巻1号(1987年1月発行)
特集 今日の肺癌治療 '87
41巻13号(1986年12月発行)
特集 ストーマをめぐる最近の話題
41巻12号(1986年11月発行)
特集 MOF患者のArtificial Support
41巻11号(1986年10月発行)
特集 胃癌手術の限界と合理化
41巻10号(1986年9月発行)
特集 食道静脈瘤硬化療法—その適応と手技上のポイント
41巻9号(1986年8月発行)
特集 悪性腫瘍を疑うX線像
41巻8号(1986年7月発行)
特集 重症患者の輸液・栄養
41巻7号(1986年6月発行)
特集 肛門部疾患診療のテクニック
41巻6号(1986年6月発行)
特集 外科患者・薬物療法マニュアル
41巻5号(1986年5月発行)
特集 甲状腺癌の診断と治療
41巻4号(1986年4月発行)
特集 食道癌手術手技上のポイント
41巻3号(1986年3月発行)
特集 糖尿病合併患者の手術と管理
41巻2号(1986年2月発行)
特集 Borrmann 4型胃癌—私の治療
41巻1号(1986年1月発行)
特集 胆嚢隆起性病変をどうするか
40巻13号(1985年12月発行)
特集 肝内胆石に対する胆道ドレナージ手術
40巻12号(1985年11月発行)
特集 肝硬変合併患者の手術と管理
40巻11号(1985年10月発行)
特集 消化器外科医のための血管外科手技
40巻10号(1985年9月発行)
特集 症例による急性腹症の画像診断
40巻9号(1985年8月発行)
特集 Iatrogenic Abdominal Trauma—その予防と対策
40巻8号(1985年7月発行)
特集 噴門部癌の手術術式—適応と根拠
40巻6号(1985年6月発行)
特集 がん・画像診断の死角
40巻7号(1985年6月発行)
特集 鼎談・高齢者の消化管手術—手術適応のボーダーライン
40巻5号(1985年5月発行)
特集 膵頭十二指腸切除後の再建法のポイント
40巻4号(1985年4月発行)
特集 急性虫垂炎の臨床
40巻3号(1985年3月発行)
特集 癌のSurgical Emergencies
40巻2号(1985年2月発行)
特集 腹膜炎治療のノウ・ハウ
40巻1号(1985年1月発行)
特集 最近の経腸栄養法と外科
39巻12号(1984年12月発行)
特集 大腸切除と機能温存
39巻11号(1984年11月発行)
特集 胃癌—最近の話題
39巻10号(1984年10月発行)
特集 胆管癌の外科
39巻9号(1984年9月発行)
特集 どこまで活用できるか新しい手術器械
39巻8号(1984年8月発行)
特集 外傷の総合画像診断と初療
39巻7号(1984年7月発行)
特集 肝臓癌のTAE療法
39巻6号(1984年6月発行)
特集 〔Q & A〕術中トラブル対処法—私はこうしている
39巻5号(1984年5月発行)
特集 外科におけるクリティカル・ケア
39巻4号(1984年4月発行)
特集 臓器移植の最前線
39巻3号(1984年3月発行)
特集 外科感染症と免疫
39巻2号(1984年2月発行)
特集 がんの集学的治療をどうするか
39巻1号(1984年1月発行)
特集 今日の肺癌
38巻12号(1983年12月発行)
特集 プラスマフェレーシス
38巻11号(1983年11月発行)
特集 胃・十二指腸潰瘍
38巻10号(1983年10月発行)
特集 下部消化管出血
38巻9号(1983年9月発行)
特集 肝硬変と手術
38巻8号(1983年8月発行)
特集 臓器全摘後の病態と管理
38巻7号(1983年7月発行)
特集 鼠径・大腿ヘルニアの話題
38巻6号(1983年6月発行)
特集 吻合法—目でみるポイントとコツ
38巻5号(1983年5月発行)
特集 緊急減黄術—テクニックとそのコツ
38巻4号(1983年4月発行)
特集 癌手術と再建
38巻3号(1983年3月発行)
特集 腹部外傷の超音波診断
38巻2号(1983年2月発行)
特集 脾摘をめぐる話題
38巻1号(1983年1月発行)
特集 よくみる肛門部疾患診療のポイント
37巻12号(1982年12月発行)
特集 膵・胆管合流異常の外科
37巻11号(1982年11月発行)
特集 末梢血管障害の非侵襲的検査法
37巻10号(1982年10月発行)
特集 新しい抗生物質と外科
37巻9号(1982年9月発行)
特集 Controversy;皮切と到達経路
37巻8号(1982年8月発行)
特集 今日の人工肛門
37巻7号(1982年7月発行)
特集 胆石症をめぐる最近の話題
37巻6号(1982年6月発行)
特集 乳癌の縮小根治手術
37巻5号(1982年5月発行)
特集 外科外来マニュアル
37巻4号(1982年4月発行)
特集 レーザーと外科
37巻3号(1982年3月発行)
特集 人工呼吸管理のPit fall
37巻2号(1982年2月発行)
特集 食道静脈瘤手術
37巻1号(1982年1月発行)
特集 術中エコー
36巻12号(1981年12月発行)
特集 インスリン併用の高カロリー栄養法
36巻11号(1981年11月発行)
特集 迷切後の諸問題
36巻10号(1981年10月発行)
特集 膵炎診療のControversy
36巻9号(1981年9月発行)
特集 上部胆管癌の外科
36巻8号(1981年8月発行)
特集 手指の外傷—初期診療の実際
36巻7号(1981年7月発行)
特集 上部消化管出血—保存的止血法のトピックス
36巻6号(1981年6月発行)
特集 外傷の画像診断
36巻5号(1981年5月発行)
特集 Multiple Organ Failure
36巻4号(1981年4月発行)
特集 術後1週間の患者管理
36巻3号(1981年3月発行)
特集 晩期癌患者のcare
36巻2号(1981年2月発行)
特集 胃癌のAdjuvant Chemotherapy
36巻1号(1981年1月発行)
特集 RI診断の進歩
35巻12号(1980年12月発行)
特集 癌と栄養
35巻11号(1980年11月発行)
特集 私の縫合材料と縫合法
35巻10号(1980年10月発行)
特集 胆道ドレナージに伴うトラブル
35巻9号(1980年9月発行)
特集 消化管手術と器械吻合
35巻8号(1980年8月発行)
特集 閉塞性黄疸—最近の診断法の進歩
35巻7号(1980年7月発行)
特集 大腸癌根治手術の再検討—ポリペクトミーから拡大郭清まで
35巻6号(1980年6月発行)
特集 最近の呼吸管理法をめぐるQ&A
35巻5号(1980年5月発行)
特集 癌のリンパ節郭清をどうするか
35巻4号(1980年4月発行)
特集 膵癌と膵頭十二指腸切除術
35巻3号(1980年3月発行)
特集 血管カテーテルの治療への応用
35巻2号(1980年2月発行)
特集 外科医のための麻酔
35巻1号(1980年1月発行)
特集 遺残胆石
34巻12号(1979年12月発行)
特集 噴門部癌の特性と外科治療
34巻11号(1979年11月発行)
特集 熱傷治療のトピックス
34巻10号(1979年10月発行)
特集 急性胆嚢炎の治療
34巻9号(1979年9月発行)
特集 手術と抗生物質
34巻8号(1979年8月発行)
特集 術中・術後の出血
34巻7号(1979年7月発行)
特集 Crohn病とその辺縁疾患
34巻6号(1979年6月発行)
特集 これだけは知っておきたい手術の適応とタイミング—注意したい疾患45
34巻5号(1979年5月発行)
特集 外科と血管造影—〈読影のポイント,鑑別のコツ〉
34巻4号(1979年4月発行)
特集 Elemental Diet
34巻3号(1979年3月発行)
特集 成分輸血
34巻2号(1979年2月発行)
特集 外科とエコー
34巻1号(1979年1月発行)
特集 ショックをめぐる新しい話題
33巻12号(1978年12月発行)
特集 非定形的乳切の術式と適応
33巻11号(1978年11月発行)
特集 検査と合併症—おこさないためには、おこしてしまったら
33巻10号(1978年10月発行)
特集 今日の癌免疫療法
33巻9号(1978年9月発行)
特集 食道癌手術の近況
33巻8号(1978年8月発行)
特集 老年者の手術—併存疾患の診かた・とらえ方
33巻7号(1978年7月発行)
特集 臓器大量切除と栄養
33巻6号(1978年6月発行)
特集 T-tubeと胆道鏡
33巻5号(1978年5月発行)
特集 乳幼児急性腹症—診断のポイントとfirst aid
33巻4号(1978年4月発行)
特集 術後呼吸障害とその管理
33巻3号(1978年3月発行)
特集 CTスキャン
33巻2号(1978年2月発行)
特集 消化性潰瘍と迷切術
33巻1号(1978年1月発行)
特集 最近の手術材料と器具
32巻12号(1977年12月発行)
特集 目でみる話題の消化器手術
32巻11号(1977年11月発行)
特集 Biopsyの再検討
32巻10号(1977年10月発行)
特集 肺癌—新しい診療のポイント
32巻9号(1977年9月発行)
特集 逆流性食道炎
32巻8号(1977年8月発行)
特集 上部消化管大量出血
32巻7号(1977年7月発行)
特集 甲状腺機能亢進症—外科医の役割
32巻6号(1977年6月発行)
特集 今日の胆道造影
32巻5号(1977年5月発行)
特集 非癌性乳腺疾患の外科
32巻4号(1977年4月発行)
特集 ヘルニア再検討
32巻3号(1977年3月発行)
特集 外科と薬剤
32巻2号(1977年2月発行)
特集 腹部手術後の輸液—私はこうしている
32巻1号(1977年1月発行)
特集 人工肛門のAfter Care
31巻12号(1976年12月発行)
特集 胆道手術後の困難症
31巻11号(1976年11月発行)
特集 術後の急性機能不全
31巻10号(1976年10月発行)
特集 肝切除の術式
31巻9号(1976年9月発行)
特集 進行胃癌の化学療法
31巻8号(1976年8月発行)
特集 特殊な消化性潰瘍
31巻7号(1976年7月発行)
特集 重度外傷
31巻6号(1976年6月発行)
特集 早期大腸癌の外科
31巻5号(1976年5月発行)
特集 大量輸血
31巻4号(1976年4月発行)
特集 手術とHyperalimentation
31巻3号(1976年3月発行)
特集 急性腹症のX線像
31巻2号(1976年2月発行)
特集 手術と肝障害
31巻1号(1976年1月発行)
特集 遠隔成績よりみた早期胃癌
30巻12号(1975年12月発行)
特集 脳卒中の外科
30巻11号(1975年11月発行)
特集 癌免疫と外科治療
30巻10号(1975年10月発行)
特集 凍結外科—Cryosurgery
30巻9号(1975年9月発行)
特集 縫合法—反省と再検討
30巻8号(1975年8月発行)
特集 消化管の創傷治癒
30巻7号(1975年7月発行)
特集 手術と副損傷
30巻6号(1975年6月発行)
特集 乳癌—最近の趨勢
30巻5号(1975年5月発行)
特集 胃切除後にくるもの—その対策と治療
30巻4号(1975年4月発行)
特集 腹部外科のPhysical Signs
30巻3号(1975年3月発行)
特集 閉塞性黄疸
30巻2号(1975年2月発行)
特集 ショック治療の新しい考え方
30巻1号(1975年1月発行)
特集 手の外科
29巻12号(1974年12月発行)
特集 一般外科医のための小児外科
29巻11号(1974年11月発行)
特集 外科と血栓
29巻9号(1974年10月発行)
29巻8号(1974年8月発行)
特集 外傷救急診療におけるDo's & Don'ts
29巻7号(1974年7月発行)
特集 痔核と痔瘻の外科
29巻6号(1974年6月発行)
特集 胸部食道癌の外科
29巻5号(1974年5月発行)
特集 老人外科—老年者胆道系疾患の外科
29巻4号(1974年4月発行)
特集 腹部緊急疾患におけるDo's & Don'ts
29巻3号(1974年3月発行)
特集 胃全剔
29巻2号(1974年2月発行)
特集 消化管手術と内視鏡
29巻1号(1974年1月発行)
特集 外科とME—その現況と将来
28巻12号(1973年12月発行)
特集 外科と栄養—高カロリー輸液の問題点
28巻11号(1973年11月発行)
特集 膵炎の外科
28巻10号(1973年10月発行)
特集 外科医のための臨床検査
28巻9号(1973年9月発行)
28巻8号(1973年8月発行)
特集 急性腹膜炎
28巻7号(1973年7月発行)
特集 再発癌—follow-upとその治療
28巻6号(1973年6月発行)
特集 麻酔—外科医のために
28巻5号(1973年5月発行)
特集 外科と感染—その基本的対策とPitfall
28巻4号(1973年4月発行)
特集 術後ドレナージの実際
28巻3号(1973年3月発行)
特集 肝癌の外科
28巻2号(1973年2月発行)
特集 今日の救急
28巻1号(1973年1月発行)
特集 外科と大腸—癌とポリープを中心に
27巻12号(1972年12月発行)
特集 外科と大腸—炎症性疾患を中心に
27巻11号(1972年11月発行)
特集 末梢血管の外科
27巻10号(1972年10月発行)
特集 頸部血管障害
27巻9号(1972年9月発行)
特集 出血治療のPitfall
27巻8号(1972年8月発行)
特集 胆道外科のPitfall
27巻7号(1972年7月発行)
特集 皮膚切開法と到達法・Ⅱ
27巻6号(1972年6月発行)
特集 皮膚切開法と到達法・Ⅰ
27巻5号(1972年5月発行)
特集 日常外科の総点検・Ⅱ
27巻4号(1972年4月発行)
特集 日常外科の総点検・Ⅰ
27巻3号(1972年3月発行)
特集 黄疸の外科
27巻2号(1972年2月発行)
特集 瘻—その問題点
27巻1号(1972年1月発行)
特集 早期癌の外科治療
26巻12号(1971年12月発行)
特集 胃癌根治手術の問題点
26巻11号(1971年11月発行)
特集 小児外科の焦点
26巻10号(1971年10月発行)
26巻9号(1971年9月発行)
特集 上腹部痛—誤りやすい疾患の診療
26巻8号(1971年8月発行)
特集 今日の外傷—外傷患者の初診と初療
26巻7号(1971年7月発行)
26巻6号(1971年6月発行)
特集 手術とその根拠・Ⅱ
26巻5号(1971年5月発行)
特集 手術とその根拠・Ⅰ
26巻4号(1971年4月発行)
特集 外科とくすり—副作用と適正な使用法
26巻3号(1971年3月発行)
特集 緊急手術後の合併症・Ⅱ
26巻2号(1971年2月発行)
特集 緊急手術後の合併症・Ⅰ
26巻1号(1971年1月発行)
特集 これからの外科
25巻12号(1970年12月発行)
特集 Silent Disease
25巻11号(1970年11月発行)
特集 輸液の臨床
25巻10号(1970年10月発行)
特集 熱傷の早期治療
25巻9号(1970年9月発行)
特集 術後早期の再手術
25巻8号(1970年8月発行)
特集 縫合糸の問題点
25巻7号(1970年7月発行)
特集 腫瘍の病理と臨床
25巻6号(1970年6月発行)
特集 縫合不全
25巻5号(1970年5月発行)
特集 外科領域における感染症
25巻4号(1970年4月発行)
特集 心臓と血管の外科
25巻3号(1970年3月発行)
特集 手術と出血対策Ⅱ
25巻2号(1970年2月発行)
特集 手術と出血対策Ⅰ
25巻1号(1970年1月発行)
特集 特殊な輸血とその現況
24巻12号(1969年12月発行)
特集 全身状態とSurgical Risk
24巻11号(1969年11月発行)
特集 腸瘻の問題点
24巻10号(1969年10月発行)
特集 緊急手術の手技・Ⅱ
24巻9号(1969年9月発行)
特集 緊急手術の手技・Ⅰ
24巻8号(1969年8月発行)
特集 良性腫瘍
24巻7号(1969年7月発行)
24巻6号(1969年6月発行)
24巻5号(1969年5月発行)
特集 臨床麻酔の問題点
24巻4号(1969年4月発行)
特集 緊急手術適応のきめ手
24巻3号(1969年3月発行)
特集 消化器疾患の新しい診断法
24巻2号(1969年2月発行)
特集 乳腺疾患—その診療の進歩
24巻1号(1969年1月発行)
特集 人工臓器への歩み
23巻13号(1968年12月発行)
特集 癌外科の進歩—現状と将来
23巻12号(1968年11月発行)
特集 顔面損傷のファースト・エイド
23巻11号(1968年10月発行)
特集 Encephalopathyの臨床
23巻10号(1968年9月発行)
特集 肛門外科
23巻9号(1968年8月発行)
特集 脈管造影
23巻8号(1968年7月発行)
特集 膵・胆・肝の外科
23巻7号(1968年6月発行)
特集 手と足の外傷
23巻6号(1968年6月発行)
特集 木本誠二教授退官記念特集
23巻5号(1968年5月発行)
特集 臓器移植の可能性
23巻4号(1968年4月発行)
特集 最良の手術時点
23巻3号(1968年3月発行)
特集 術後困難症の処置
23巻2号(1968年2月発行)
特集 出血の問題点
23巻1号(1968年1月発行)
特集 初療の要点
22巻12号(1967年12月発行)
特集 鞭打ち損傷の問題点
22巻11号(1967年11月発行)
特集 肝腫瘍外科の課題
22巻10号(1967年10月発行)
特集 イレウスの治療—その困難な問題点
22巻9号(1967年9月発行)
特集 甲状腺疾患の問題点
22巻8号(1967年8月発行)
特集 胃・十二指腸潰瘍の手術
22巻7号(1967年7月発行)
特集 救急患者の取扱い方
22巻6号(1967年6月発行)
特集 血管の外科
22巻5号(1967年5月発行)
特集 胆石症手術の問題点
22巻4号(1967年4月発行)
特集 進行性消化器癌の外科
22巻3号(1967年3月発行)
特集 頭部外傷処置の実際
22巻2号(1967年2月発行)
特集 臨床検査後の偶発症
22巻1号(1967年1月発行)
特集 鼠径・陰嚢ヘルニアの問題点
21巻12号(1966年12月発行)
特集 虫垂炎—その困難な問題点
21巻11号(1966年11月発行)
特集 小児疾患の早期診断と手術適応
21巻10号(1966年10月発行)
21巻9号(1966年9月発行)
21巻8号(1966年8月発行)
特集 腫瘍の外科
21巻7号(1966年7月発行)
21巻6号(1966年6月発行)
21巻5号(1966年5月発行)
特集 癌患者の栄養問題
21巻4号(1966年4月発行)
特集 胃手術後の困難症
21巻3号(1966年3月発行)
21巻2号(1966年2月発行)
特集 癌の補助療法・2
21巻1号(1966年1月発行)
特集 癌の補助療法・1
20巻12号(1965年12月発行)
20巻11号(1965年11月発行)
特集 熱傷の治療
20巻10号(1965年10月発行)
20巻9号(1965年9月発行)
特集 腹部外科の臨床
20巻8号(1965年8月発行)
特集 癌手術例の検討
20巻7号(1965年7月発行)
特集 術後感染症
20巻6号(1965年6月発行)
特集 腹部疾患縫合不全
20巻5号(1965年5月発行)
特集 胸部疾患縫合不全
20巻4号(1965年4月発行)
20巻3号(1965年3月発行)
20巻2号(1965年2月発行)
特集 外科と内分泌・2
20巻1号(1965年1月発行)
特集 外科と内分泌・1
19巻12号(1964年12月発行)
特集 外科と保険診療
19巻11号(1964年11月発行)
19巻10号(1964年10月発行)
19巻9号(1964年9月発行)
特集 脳・頸部・胸部の症例
19巻8号(1964年8月発行)
特集 小児外科
19巻7号(1964年7月発行)
19巻6号(1964年6月発行)
特集 外傷の救急処置
19巻5号(1964年5月発行)
特集 癌の治療成績の向上
19巻4号(1964年4月発行)
19巻3号(1964年3月発行)
19巻2号(1964年2月発行)
19巻1号(1964年1月発行)
18巻12号(1963年12月発行)
18巻11号(1963年11月発行)
18巻10号(1963年10月発行)
特集 整形外科症例集
18巻9号(1963年9月発行)
18巻8号(1963年8月発行)
18巻7号(1963年7月発行)
18巻6号(1963年6月発行)
18巻5号(1963年5月発行)
18巻4号(1963年4月発行)
18巻3号(1963年3月発行)
18巻2号(1963年2月発行)
18巻1号(1963年1月発行)
17巻12号(1962年12月発行)
17巻11号(1962年11月発行)
17巻10号(1962年10月発行)
特集 麻酔
17巻9号(1962年9月発行)
17巻8号(1962年8月発行)
特集 手こずつた症例―私の経験した診断治療上の困難症(Ⅱ)
17巻7号(1962年7月発行)
17巻6号(1962年6月発行)
特集 手こずつた症例―私の経験した診断治療上の困難症(Ⅰ)
17巻5号(1962年5月発行)
17巻4号(1962年4月発行)
17巻3号(1962年3月発行)
17巻2号(1962年2月発行)
17巻1号(1962年1月発行)
16巻12号(1961年12月発行)
16巻11号(1961年11月発行)
16巻10号(1961年10月発行)
16巻9号(1961年9月発行)
16巻8号(1961年8月発行)
16巻7号(1961年7月発行)
16巻6号(1961年6月発行)
16巻5号(1961年5月発行)
16巻4号(1961年4月発行)
16巻3号(1961年3月発行)
16巻2号(1961年2月発行)
16巻1号(1961年1月発行)
15巻12号(1960年12月発行)
15巻11号(1960年11月発行)
15巻10号(1960年10月発行)
15巻9号(1960年9月発行)
15巻8号(1960年8月発行)
15巻7号(1960年7月発行)
15巻6号(1960年6月発行)
15巻5号(1960年5月発行)
15巻4号(1960年4月発行)
15巻3号(1960年3月発行)
15巻2号(1960年2月発行)
15巻1号(1960年1月発行)
14巻12号(1959年12月発行)
14巻11号(1959年11月発行)
14巻10号(1959年10月発行)
14巻9号(1959年9月発行)
14巻8号(1959年8月発行)
14巻7号(1959年7月発行)
14巻6号(1959年6月発行)
14巻5号(1959年5月発行)
14巻4号(1959年4月発行)
14巻3号(1959年3月発行)
特集 腹部外科
14巻2号(1959年2月発行)
14巻1号(1959年1月発行)
13巻12号(1958年12月発行)
13巻11号(1958年11月発行)
13巻10号(1958年10月発行)
13巻9号(1958年9月発行)
13巻8号(1958年8月発行)
13巻7号(1958年7月発行)
特集 外科的・内科的療法の限界・2
13巻6号(1958年6月発行)
13巻5号(1958年5月発行)
特集 外科的・内科的療法の限界
13巻4号(1958年4月発行)
13巻3号(1958年3月発行)
13巻2号(1958年2月発行)
特集 腫瘍
13巻1号(1958年1月発行)
12巻12号(1957年12月発行)
12巻11号(1957年11月発行)
特集 乳腺腫瘍
12巻10号(1957年10月発行)
12巻9号(1957年9月発行)
12巻8号(1957年8月発行)
12巻7号(1957年7月発行)
12巻6号(1957年6月発行)
12巻5号(1957年5月発行)
12巻4号(1957年4月発行)
特集 腫瘍
12巻3号(1957年3月発行)
12巻2号(1957年2月発行)
12巻1号(1957年1月発行)
11巻13号(1956年12月発行)
特集 吐血と下血
11巻12号(1956年12月発行)
11巻11号(1956年11月発行)
11巻10号(1956年10月発行)
11巻9号(1956年9月発行)
11巻8号(1956年8月発行)
11巻7号(1956年7月発行)
11巻6号(1956年6月発行)
11巻5号(1956年5月発行)
11巻4号(1956年4月発行)
11巻3号(1956年3月発行)
11巻2号(1956年2月発行)
11巻1号(1956年1月発行)
10巻13号(1955年12月発行)
10巻11号(1955年11月発行)
特集 偶發症との救急處置
10巻12号(1955年11月発行)
10巻10号(1955年10月発行)
10巻9号(1955年9月発行)
10巻8号(1955年8月発行)
10巻7号(1955年7月発行)
10巻6号(1955年6月発行)
10巻5号(1955年5月発行)
10巻4号(1955年4月発行)
10巻3号(1955年3月発行)
10巻2号(1955年2月発行)
10巻1号(1955年1月発行)
9巻12号(1954年12月発行)
9巻11号(1954年11月発行)
特集 整形外科特集号
9巻10号(1954年10月発行)
9巻9号(1954年9月発行)
特集 慢性胃炎と胃潰瘍
9巻8号(1954年8月発行)
9巻7号(1954年7月発行)
9巻6号(1954年6月発行)
9巻5号(1954年5月発行)
9巻4号(1954年4月発行)
9巻3号(1954年3月発行)
9巻2号(1954年2月発行)
9巻1号(1954年1月発行)
8巻13号(1953年12月発行)
特集 頸部外科臨床の進歩
8巻12号(1953年12月発行)
8巻11号(1953年11月発行)
8巻10号(1953年10月発行)
8巻9号(1953年9月発行)
特集 最新の麻醉
8巻8号(1953年8月発行)
特集 輸血・輸液の諸問題
8巻7号(1953年7月発行)
8巻6号(1953年6月発行)
8巻5号(1953年5月発行)
8巻4号(1953年4月発行)
8巻3号(1953年3月発行)
8巻2号(1953年2月発行)
8巻1号(1953年1月発行)
7巻13号(1952年12月発行)
7巻12号(1952年11月発行)
7巻11号(1952年11月発行)
特集 上腹部外科臨床の進歩
7巻10号(1952年10月発行)
7巻9号(1952年9月発行)
7巻8号(1952年8月発行)
7巻7号(1952年7月発行)
7巻6号(1952年6月発行)
7巻5号(1952年5月発行)
7巻4号(1952年4月発行)
7巻3号(1952年3月発行)
7巻2号(1952年2月発行)
7巻1号(1952年1月発行)
6巻12号(1951年12月発行)
6巻11号(1951年11月発行)
6巻10号(1951年10月発行)
6巻9号(1951年9月発行)
6巻8号(1951年8月発行)
6巻7号(1951年7月発行)
6巻6号(1951年6月発行)
6巻5号(1951年5月発行)
6巻4号(1951年4月発行)
6巻3号(1951年3月発行)
6巻2号(1951年2月発行)
6巻1号(1951年1月発行)
5巻12号(1950年12月発行)
5巻11号(1950年11月発行)
5巻10号(1950年10月発行)
5巻9号(1950年9月発行)
特集 蛋白・3
5巻8号(1950年8月発行)
特集 蛋白・2
5巻7号(1950年7月発行)
特集 蛋白問題・1
5巻6号(1950年6月発行)
5巻5号(1950年5月発行)
特集 Cancer・2
5巻4号(1950年4月発行)
特集 Cancer・1
5巻3号(1950年3月発行)
5巻2号(1950年2月発行)
5巻1号(1950年1月発行)
4巻12号(1949年12月発行)
4巻11号(1949年11月発行)
4巻10号(1949年10月発行)
4巻9号(1949年9月発行)
4巻8号(1949年8月発行)
4巻7号(1949年7月発行)
4巻6号(1949年6月発行)
4巻5号(1949年5月発行)
4巻4号(1949年4月発行)
4巻3号(1949年3月発行)
4巻2号(1949年2月発行)
4巻1号(1949年1月発行)
