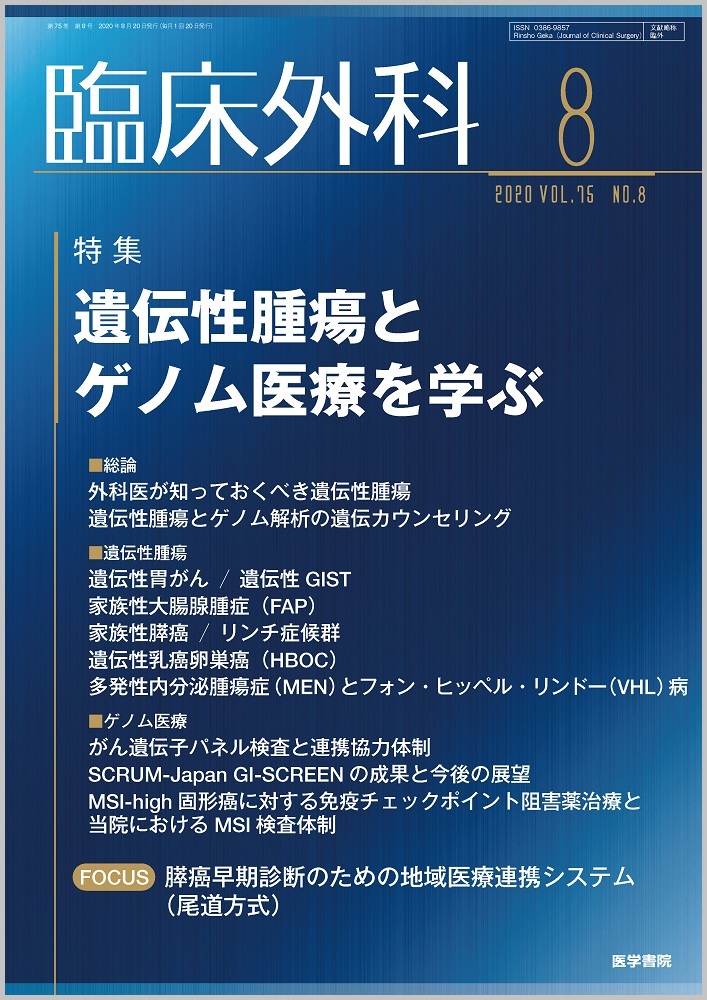文献詳細
FOCUS
文献概要
尾道方式とは
膵癌は現在でも予後不良の疾患であり,5年生存率は男性で7.9%,女性で7.5%と報告されている1).その改善には早期診断が必須であるが,近年,病診連携を生かした膵癌早期診断プロジェクトが各地で展開され,その結果,外科的切除率の改善,早期診断例の増加,5年生存率の改善など一定の成果が報告されている2).
当院が所属する広島県尾道市医師会では,2007年から“膵癌早期診断プロジェクト(尾道方式)”が展開されている.従来から尾道市医師会では,かかりつけ医を中心に病院医師,看護師,薬剤師など各種医療スタッフが多職種で連携し,入院患者が在宅療養へ移行するシステムが稼動しており,情報交換が緊密で病診連携が良好であった3).一方,2006年に日本膵臓学会から発刊された膵癌診療ガイドラインに,危険因子が初めて記載された4)ことが契機となり,医師会での討論を経て,2007年から尾道方式が開始された3).なお,危険因子はガイドラインの改訂とともに項目がアップデートされており(表1)5),2019年版の内容が共有されている.
膵癌は現在でも予後不良の疾患であり,5年生存率は男性で7.9%,女性で7.5%と報告されている1).その改善には早期診断が必須であるが,近年,病診連携を生かした膵癌早期診断プロジェクトが各地で展開され,その結果,外科的切除率の改善,早期診断例の増加,5年生存率の改善など一定の成果が報告されている2).
当院が所属する広島県尾道市医師会では,2007年から“膵癌早期診断プロジェクト(尾道方式)”が展開されている.従来から尾道市医師会では,かかりつけ医を中心に病院医師,看護師,薬剤師など各種医療スタッフが多職種で連携し,入院患者が在宅療養へ移行するシステムが稼動しており,情報交換が緊密で病診連携が良好であった3).一方,2006年に日本膵臓学会から発刊された膵癌診療ガイドラインに,危険因子が初めて記載された4)ことが契機となり,医師会での討論を経て,2007年から尾道方式が開始された3).なお,危険因子はガイドラインの改訂とともに項目がアップデートされており(表1)5),2019年版の内容が共有されている.
参考文献
1)国立がん研究センターがん対策情報センター:がん登録・統計〔https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html〕
2)花田敬士,清水晃典,南 智之:膵癌早期発見への取り組み—地域医療連携システムの構築.日消誌115:327-333,2018
3)花田敬士,宮野良隆:病診連携を基軸とした膵癌早期診断.日本医事新報4832:41-46,2016
4)日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン作成小委員会(編):科学的根拠に基づく膵癌診療ガイドライン2006年版.金原出版,2006
5)日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン改訂委員会(編):膵癌診療ガイドライン2019年版.金原出版,2019
6)Iiboshi T, Hanada K, Fukuda T, et al:Value of cytodiagnosis using endoscopic nasopancreatic drainage for early diagnosis of pancreatic cancer. Pancreas 41:523-529, 2012
7)花田敬士,栗原啓介,清水晃典,他:膵癌早期診断における地域医療型システム構築の課題と役割:地方型.胆と膵41:375-379,2020
8)花田敬士,南 智之,岡崎彰仁,他:膵癌早期診断プロジェクト.胆と膵37:1181-1186,2016
掲載誌情報