消化器・一般外科領域での日本内視鏡外科学会技術認定取得は,若い外科医の目標,それに伴う技術向上の原動力として,いまだに重要な位置づけとなっている.一方で,その合格率は決して高くなく,狭き門であることは否めない.さらに2024年度より消化管領域ではロボット支援手術も加わった.本特集では,それぞれの領域のエキスパートに,これから技術認定取得をめざす若手医師に向け,各術式で減点になりやすいポイントを中心に,技術認定取得のコツについて解説していただいた.
雑誌目次
臨床外科79巻13号
2024年12月発行
雑誌目次
特集 JSES技術認定取得をめざせ2025
総論
JSES技術認定制度の概要—共通基準改訂とロボット支援手術の技術認定審査を中心に
著者: 黒柳洋弥
ページ範囲:P.1326 - P.1329
技術認定試験を受けるにあたってのアドバイス
◆誰でもできる簡単なステップを丁寧に確実に遂行していけば合格できる.
◆癌手術が対象術式の場合,病変にできるだけ触らない,適切なリンパ節郭清・切除範囲とするなど,癌手術の原則が重要である.
食道
胸腔鏡下食道切除術
著者: 川久保博文
ページ範囲:P.1330 - P.1334
技術認定試験を受けるにあたってのアドバイス
◆応募の手引きは熟読し,これに沿って審査ビデオを作成し,提出する.手引きに沿わないビデオはどんなに素晴らしい手技であっても,合格にはならない.
◆縦隔内の解剖を熟知し,適切な剝離層で,無駄な操作をせずに丁寧に手術し,切除すべき組織を切除すればよい.普段の手術からそれを心掛けていれば合格できる.
◆手術の主体性は重要である.助手やスコピストに指示して,連携し,良好な術野展開と適切なカウンタートラクションをかけてもらうことが必要である.
ロボット支援食道切除術
著者: 西田泰治 , 真鍋達也 , 能城浩和
ページ範囲:P.1336 - P.1343
技術認定試験を受けるにあたってのアドバイス
◆術野はロボットアームもしくは助手を使って明瞭に展開され,正しい解剖認識の下で操作をすること.
◆手術操作は触覚の欠如などロボットの特性を理解し,安全が担保された基本手技に基づき行うこと.
◆ビデオの選択は,多少の出血や解剖誤認があっても的確に修正できており,上記が確実に伝わるものを選ぶこと.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年12月末まで)。
胃
腹腔鏡下幽門側胃切除術
著者: 坂東悦郎 , 松本陽介 , 高橋恭太 , 服部卓 , 井上誠司 , 阿部恭 , 小関佑介 , 古川健一朗 , 藤谷啓一 , 谷澤豊
ページ範囲:P.1345 - P.1351
技術認定を受けるにあたってのアドバイス
◆名人芸を要求されている認定試験ではありません.学会が推奨している安全な手技を行うことに徹してください.
◆ただ手術を行うのではなく,準備とその後のチームとしてのレビューが重要です.そのために最新の情報を得ていく必要があります.
◆No. 6は結腸授動(いわゆるtake down),膵上縁郭清は固有肝動脈同定(に伴う右胃動脈の同定)が最重要で,これらが正確に施行できればそのあとは自動的に操作が進行します.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年12月末まで)。
ロボット支援幽門側胃切除術
著者: 佐川弘之 , 辻恵理 , 藤田康平 , 齋藤正樹 , 原田真之資 , 伊藤直 , 早川俊輔 , 小川了 , 三井章 , 瀧口修司
ページ範囲:P.1352 - P.1359
技術認定試験を受けるにあたってのアドバイス
◆ロボット手術の「特性」を理解したうえで根治性かつ安全性のある円滑な手術を.
◆どう観て,どう判断し,どう助手に指示を出し,自らの手技につなげているかが重要.
◆技術認定取得は,外科医として成長するうえでの一つのステップであり,日常的に良い手技,手術をめざして精進を.
大腸
腹腔鏡下S状結腸切除術
著者: 向井俊貴 , 秋吉高志
ページ範囲:P.1360 - P.1366
技術認定試験を受けるにあたってのアドバイス
◆技術認定審査では腹腔鏡手技の習熟だけではなく,癌の手術として適切かが問われる.
◆手術ビデオを見れば(解説がなくても)何をしようとしているのかがわかる手術を心掛ける.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年12月末まで)。
ロボット支援S状結腸切除術
著者: 吉松軍平 , 塩川桂一 , 竹下一生 , 下河邉久陽 , 佐原くるみ , 棟近太郎 , 長野秀紀 , 松本芳子 , 長谷川傑
ページ範囲:P.1368 - P.1378
技術認定試験を受けるにあたってのアドバイス
◆多関節機能を利用したL字展開をマスターし,展開の定型化を行おう.
◆4番アームによる展開の適正化と,カメラ位置の適正化を細かく行おう.
◆ロボット鉗子どうし,ロボット鉗子と助手の鉗子の干渉には注意!
胆道
腹腔鏡下胆囊摘出術
著者: 梅澤昭子 , 春田英律
ページ範囲:P.1379 - P.1384
技術認定試験を受けるにあたってのアドバイス
◆高度なテクニックの披露ではなく,基本(審査項目)をしっかりと押さえているビデオが望ましい.
◆ランドマークの確認,Critical View of Safetyの確認,など臓器別評価項目に挙げられている点は確実に記録する.
◆胆囊摘出術の手技は剝離操作が主体だが,全体を通じて術野展開と層の見極めに留意して丁寧に行う.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年12月末まで)。
ヘルニア
腹腔鏡下鼠経ヘルニア修復術:TAPP法
著者: 植野望
ページ範囲:P.1386 - P.1394
技術認定試験を受けるにあたってのアドバイス
◆採点基準を入念にチェックし理解したうえで準備することが重要である.
◆スコピスト以外の助手がいない手術であるため,よりいっそう両側鉗子の協調運動の向上を心掛けるべきである.
◆複数症例の提出に備え,日常の手術において常に審査を意識し均質な操作に努めるべきである.
肝臓
腹腔鏡下肝切除術
著者: 伴大輔 , 浅野大輔 , 石川喜也 , 渡辺秀一 , 上田浩樹 , 赤星径一 , 小野宏晃
ページ範囲:P.1395 - P.1398
技術認定試験を受けるにあたってのアドバイス
◆認定試験に通過するための安易な症例を選ばない.
◆脈管を露出確認して裏をとり,確実に処理をする.
◆ドライな視野で手術を行う.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年12月末まで)。
膵臓
腹腔鏡下尾側膵切除術
著者: 阿部俊也 , 仲田興平 , 渡邉雄介 , 井手野昇 , 池永直樹 , 中村雅史
ページ範囲:P.1399 - P.1404
技術認定医試験を受けるにあたってのアドバイス
◆術者の主体性や助手との連携を向上し,手術をより安全かつ円滑に進めることが大切だが,そのためにはチーム内で手術を定型化することが重要である.
◆膵周囲の脈管の解剖には様々な破格がみられるため,術前のMDCTで各症例の解剖を正確に把握しておくことが重要である.
◆術野を広く展開し,組織には愛護的かつ適切な緊張をかけ,常にドライな術野を保ちながら安全に手術を進めることが重要である.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年12月末まで)。
ロボット支援膵体尾部切除術
著者: 蔵原弘 , 伊地知徹也 , 新地洋之 , 大塚隆生
ページ範囲:P.1405 - P.1411
技術認定医試験を受けるにあたってのアドバイス
◆術野展開,剝離・切離操作は術者主導で行い,助手まかせにしない.
◆助手による吸引をこまめに行い,ドライな術野で繊細な操作を心掛ける.
◆ロボットの得意な血管剝離操作などの手技を十分に利用する.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年12月末まで)。
腹壁ヘルニア修復術道場・6
腹壁瘢痕ヘルニア手術①正中腹壁瘢痕ヘルニア—(ⅱ)4〜10 cm(eTEPを中心に)
著者: 今村清隆
ページ範囲:P.1412 - P.1417
はじめに
Enhanced view totally extraperitoneal(eTEP)は技術的な難度が高く,一定の学習曲線を要することで知られ,手術時間も長くなりがちである.しかし,多様なヘルニアに対応できること,感染率が低いこと,大きなメッシュを留置可能なこと,術後疼痛が少ないこと,薄いメッシュが使用できること,コンポジットメッシュやタッカーが必要ないため低コストであること,そして次の腹部手術時にもintraperitoneal onlay mesh(IPOM)ほどメッシュが妨げになりにくいことなど,数多くの利点がある.2023年に報告された欧州ヘルニア学会による正中腹壁瘢痕ヘルニアガイドラインでも,筋層下修復術が強く推奨されている1).これらを考慮したうえで,当科ではeTEPを腹壁瘢痕ヘルニア治療の主軸としている.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年12月末まで)。
病院めぐり
名古屋セントラル病院外科
著者: 大島健司
ページ範囲:P.1418 - P.1418
当院は,1919年に日本国有鉄道名古屋鉄道治療所として開設されたのが始まりで,1989年にJR東海総合病院と名称変更し,2006年7月には,多様化する医療ニーズや医療技術の向上を受けて,現在地に新築・移転し「名古屋セントラル病院」と改称しました.JR名古屋駅から徒歩でおよそ10分の好立地にあり,東海大地震にも耐えうる免震構造を有する198床全室個室の病院です.規模としてはさほど大きくありませんが,小児科,精神科,産科を除くほとんどすべての診療科がそろっており,二次救急病院として地域の救急患者を積極的に受け入れています.
医療機器としては,脳神経外科手術システム(ブレインスイート),高精度放射線治療装置(Versa HD),PET/CT,3テスラMRI,320列マルチスライスCT,自動ブレストボリュームスキャナー(ABVS)など多くの先進医療機器を備えており,2022年3月からは手術用支援ロボット「hinotori」による手術も開始しました.人間ドックにもこれらの先進医療機器を活用して充実したメニューやオプションをそろえ,予防医学にも積極的に取り組んでいます.
FOCUS
海外における手術技術評価の歴史から学ぶ—技術評価の現在と今後の課題
著者: 井垣尊弘
ページ範囲:P.1419 - P.1426
はじめに
1900年代に腹腔鏡下胆囊摘出術が施行されて以来,内視鏡外科手術は100年以上の歴史があり,その過程に手術手技評価の歴史がある.技術評価そのものは手の動きや鉗子の操作性をセンサーなどで数値化し手先の巧緻性を評価するところから始まったが,手術が進歩し手術技術を広い視点から評価するようになったことで,さらなる発展を遂げていった.
日本では1990年代に腹腔鏡手術が導入された.当初は内視鏡外科手術手技に関連した医療事故が多発し,マスメディアに大々的に取り上げられたため,内視鏡外科手術の発展に歯止めがかかるような動きもあった.そこで「安全な手術の普及と指導医の育成」が急務となり,一定レベル以上の技術や指導性を有する医師の認定制度が必要であるとの認識から,日本内視鏡外科学会(JSES)が2004年に内視鏡外科技術認定制度を発足させた.それは現在に至るまで内視鏡外科手術の安全な普及に多大なる貢献をしており,時代の変化に合わせて今もなお改定され続け,若手外科医の大きな目標となっている.本稿では世界の手術技術評価の歴史を紐解き,そのあり方を模索しながら,技術評価における課題について触れていきたい.
臨床報告
口側結腸へ壁内転移をきたした横行結腸癌の1例
著者: 髙取寛之 , 塗木健介 , 野元三治
ページ範囲:P.1427 - P.1432
要旨
直腸癌壁内転移の報告は散見されるが,結腸癌の壁内転移は稀である.術前検査では壁内転移の存在に気付いておらず,摘出標本の肉眼所見および病理学的診断で結腸癌壁内転移の存在が判明した.症例は66歳,男性.腹痛と吐き気を主訴に近医を受診し,腹部非造影CTで左側横行結腸の壁肥厚を指摘されたため,精査依頼で当院へ紹介となった.下部内視鏡検査で横行結腸癌の診断に至り,腹腔鏡補助下結腸部分切除術を施行した.摘出した結腸で正常粘膜の介在する2か所の腫瘍を認めた.病理診断で肛門側腫瘍が原発巣で口側腫瘍は壁内転移巣と診断した.
書評
—松尾貴公(著)—レジデントのためのビジネススキル・マナー—医師として成功の一歩を踏み出す仕事術55 フリーアクセス
著者: 野木真将
ページ範囲:P.1335 - P.1335
本書は,医療の現場で働く医師が公私にわたって日常的に直面するさまざまな状況において必要なビジネススキルやマナーを詳しく解説しています.以下に,本書を読んで特に印象に残ったポイントを紹介します.
まず,敬語の使い方は医療現場で非常に重要ですが,本書の「上下逆転敬語」(p. 30)の章は特に参考になりました.日常の業務で間違いやすいポイントを具体的に解説しており,私自身も気を付けなければと感じました.また,医療従事者としての院内での行動は常に見られているという点も印象的でした.これは,私が勤務するハワイの病院でもよく「on-stage, off-stage」として注意喚起されるポイントです.患者や同僚に対する態度はプロフェッショナリズムを保つために重要であると再認識しました.
—下妻晃二郎(監修) 能登真一(編)—臨床・研究で活用できる! QOL評価マニュアル フリーアクセス
著者: 齋藤信也
ページ範囲:P.1411 - P.1411
医療関係者でQOLという言葉を知らない人は皆無ではないかと思う.私は外科医であるが,外科ではこれまで根治性を重視し,QOLを軽視しがちであった歴史がある.そこに乳房温存や,機能温存手術が導入される中で,それがもたらすQOLの改善を測ってみたいという素朴な気持ちが生じてくる.ところがいざQOLの測定となると,使用可能な日本語版尺度がなかったり,あったとしても,不自然な日本語で,それをわかりやすく変更しようとすると「そんなことをしてはいけない!」と言われたり,さらには「勝手に使うと著作権者から訴えられるよ」などと脅かされると,少し気がなえてくる.加えて,信頼性とか妥当性とか,測定特性とか計量心理学の用語が頻出すると「うーん」となってしまいがちである.
そこに現れた待望の一冊が本書『臨床・研究で活用できる! QOL評価マニュアル』である.編者の能登真一先生は,理論と実践の両面にわたり,斯界をけん引してきたリーダーでもあるが,同書を「臨床・研究で『活用』できる『マニュアル』」と明確に性格付けている.背景となる理論は過不足なくコンパクトにまとめられている上に,「尺度別」に具体的な記載がなされている点がユニークである.「マニュアル」としてその尺度の特徴・開発経緯・日本語版の開発・版権の使用に当たっての注意点・質問票そのもの・スコアの算出方法と解釈・測定特性・エビデンスが,一覧できる利便性の大きさは類書にはないものである.しかもわが国でその尺度を開発(翻訳)した当事者がその項目を執筆しているということで,版権のことも具体的でわかりやすく記載されている.これ一冊あれば,QOL測定のハードルはとても低くなる.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1322 - P.1323
原稿募集 「臨床外科」交見室 フリーアクセス
ページ範囲:P.1366 - P.1366
原稿募集 私の工夫—手術・処置・手順 フリーアクセス
ページ範囲:P.1404 - P.1404
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1436 - P.1436
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1437 - P.1437
あとがき フリーアクセス
著者: 絹笠祐介
ページ範囲:P.1438 - P.1438
JSES技術認定を取得した際の思い出は,今振り返ると非常に感慨深いものがあります.私自身,初回の試験では不合格という結果に終わりました.その時の気持ちは,残念さよりもむしろ審査に対する不満が大きかったことを覚えています.試験の結果・コメントに納得がいかず,「本当にこれが公正な評価なのか?」と疑問を抱いたのです.おそらく,同じように感じた方も多いのではないでしょうか.
しかし,その後の経験を通じて,あの時の自分の技術レベルがどの程度であったかを冷静に理解することができました.ビデオ審査という形式で公正な試験を行うことは難しいかもしれませんが,技術が優れている人は間違いなく合格するという事実もまた,否定できません.試験に対する不満を口にすることは簡単ですが,それは結局,自分の技術がその程度であったことを示しているに過ぎないのです.
「臨床外科」第79巻 総目次 フリーアクセス
ページ範囲:P. - P.
基本情報
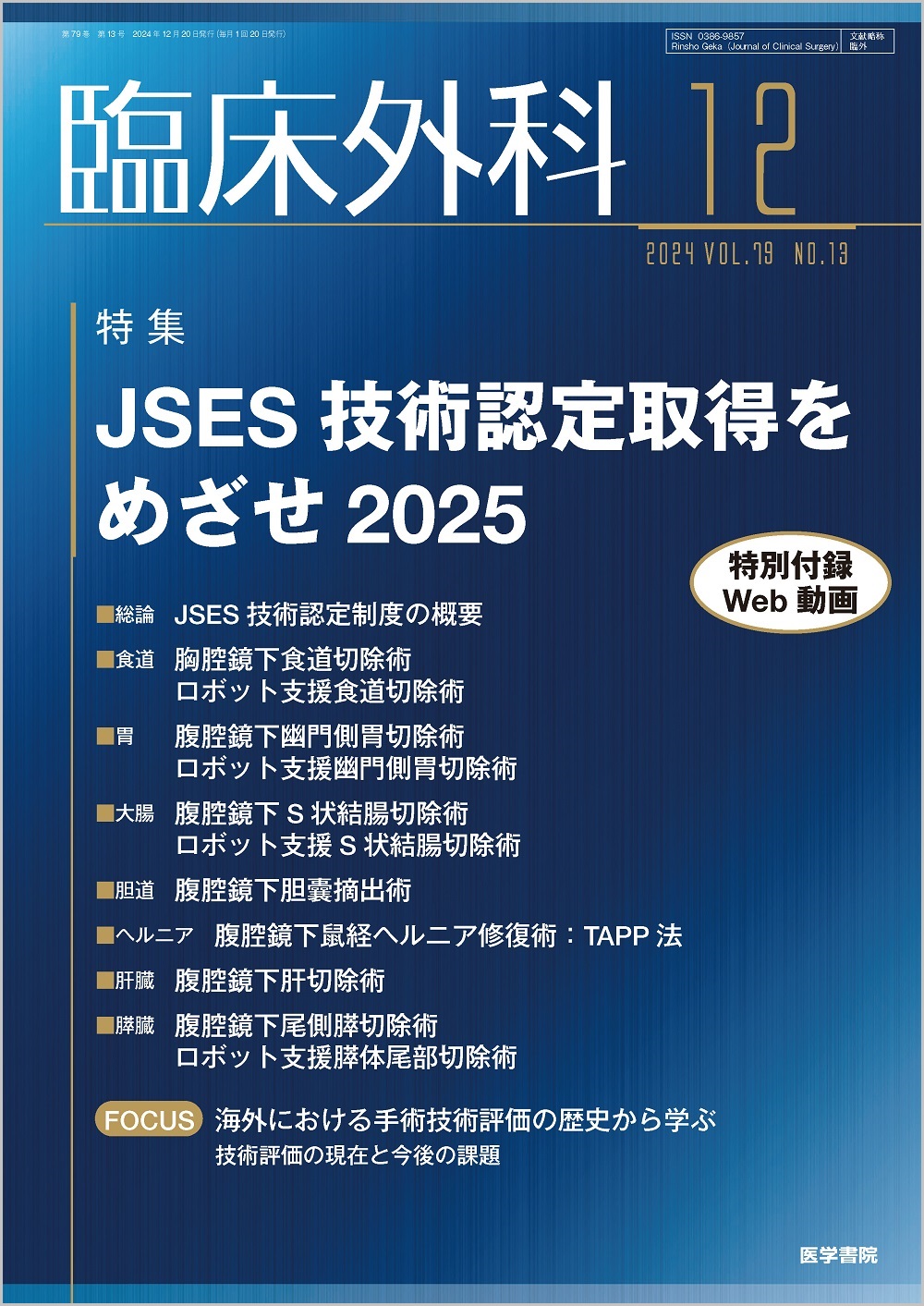
バックナンバー
79巻13号(2024年12月発行)
特集 JSES技術認定取得をめざせ2025
79巻12号(2024年11月発行)
特集 Acute Care Surgery入門
79巻11号(2024年10月発行)
増刊号 2024年最新版 外科局所解剖全図—ランドマークの出し方と損傷回避法
79巻10号(2024年10月発行)
特集 手術支援機器 百花繚乱!—ロボットとデバイスホールダー
79巻9号(2024年9月発行)
特集 徹底解説 大腸癌治療ガイドライン2024
79巻8号(2024年8月発行)
特集 合併症を起こさない食道癌手術!—ハイボリュームセンターの技を学ぼう
79巻7号(2024年7月発行)
特集 外科医が知っておくべき 肝胆膵腫瘍に対する薬物療法
79巻6号(2024年6月発行)
特集 結腸左半切除を極める
79巻5号(2024年5月発行)
特集 進化する外科教育と手術トレーニング
79巻4号(2024年4月発行)
特集 エキスパートに聞く!膵頭十二指腸切除のすべて
79巻3号(2024年3月発行)
特集 外科医必携 患者さんとのトラブルを防ぐためのハンドブック
79巻2号(2024年2月発行)
特集 ゲノム医学を外科診療に活かす!
79巻1号(2024年1月発行)
特集 若手外科医のライフハック—仕事・日常・将来を豊かにする,先輩たちの仕事術
78巻13号(2023年12月発行)
特集 ハイボリュームセンターのオペ記事《消化管癌編》
78巻12号(2023年11月発行)
特集 胃癌に対するconversion surgery—Stage Ⅳでも治したい!
78巻11号(2023年10月発行)
増刊号 —消化器・一般外科—研修医・専攻医サバイバルブック—術者として経験すべき手技のすべて
78巻10号(2023年10月発行)
特集 肝胆膵外科 高度技能専門医をめざせ!
78巻9号(2023年9月発行)
特集 見てわかる! 下部消化管手術における最適な剝離層
78巻8号(2023年8月発行)
特集 ロボット手術新時代!—極めよう食道癌・胃癌・大腸癌手術
78巻7号(2023年7月発行)
特集 術後急変!—予知・早期発見のベストプラクティス
78巻6号(2023年6月発行)
特集 消化管手術での“困難例”対処法—こんなとき,どうする?
78巻5号(2023年5月発行)
特集 術後QOLを重視した胃癌手術と再建法
78巻4号(2023年4月発行)
総特集 腹壁ヘルニア修復術の新潮流—瘢痕ヘルニア・臍ヘルニア・白線ヘルニア
78巻3号(2023年3月発行)
特集 進化する肝臓外科—高難度腹腔鏡下手術からロボット支援下手術の導入まで
78巻2号(2023年2月発行)
特集 最新医療機器・材料を使いこなす
78巻1号(2023年1月発行)
特集 外科医が知っておくべき! 免疫チェックポイント阻害薬
77巻13号(2022年12月発行)
特集 新・外科感染症診療ハンドブック
77巻12号(2022年11月発行)
特集 外科医必携 緊急対応が必要な大腸疾患
77巻11号(2022年10月発行)
増刊号 術前画像の読み解きガイド—的確な術式選択と解剖把握のために
77巻10号(2022年10月発行)
特集 外科医が担う緩和治療
77巻9号(2022年9月発行)
特集 導入! ロボット支援下ヘルニア修復術
77巻8号(2022年8月発行)
特集 よくわかる肛門疾患—診断から手術まで
77巻7号(2022年7月発行)
特集 徹底解説! 食道胃接合部癌《最新版》
77巻6号(2022年6月発行)
特集 ラパ胆を極める!
77巻5号(2022年5月発行)
特集 直腸癌局所再発に挑む—最新の治療戦略と手術手技
77巻4号(2022年4月発行)
特集 そろそろ真剣に考えよう 胃癌に対するロボット支援手術
77巻3号(2022年3月発行)
特集 肝胆膵術後合併症—どう防ぐ? どう対処する?
77巻2号(2022年2月発行)
特集 ガイドラインには書いていない 大腸癌外科治療のCQ—妥当な治療と適応を見直そう
77巻1号(2022年1月発行)
特集 外科医が知っておくべき—《最新版》栄養療法
76巻13号(2021年12月発行)
特集 Conversion surgeryアップデート
76巻12号(2021年11月発行)
特集 ストーマ・ハンドブック—外科医に必要な知識と手術手技のすべて
76巻11号(2021年10月発行)
増刊号 Stepごとに要点解説 標準術式アトラス最新版—特別付録Web動画
76巻10号(2021年10月発行)
特集 スコピストを極める
76巻9号(2021年9月発行)
特集 血管外科的手技を要する肝胆膵・移植手術
76巻8号(2021年8月発行)
特集 横行結腸癌の腹腔鏡下D3郭清手術—私のやり方,私の工夫
76巻7号(2021年7月発行)
特集 若手外科医のための食道手術ハンドブック—良性から悪性まで
76巻6号(2021年6月発行)
特集 神経・神経叢を極める—さらに精緻な消化器外科手術を求めて
76巻5号(2021年5月発行)
特集 側方リンパ節郭清のすべて—開腹からロボット手術まで
76巻4号(2021年4月発行)
特集 肥満外科A to Z
76巻3号(2021年3月発行)
特集 ロボット膵切除の導入ガイド—先行施設にノウハウを学ぶ
76巻2号(2021年2月発行)
特集 外科医のための—悪性腫瘍補助療法のすべて
76巻1号(2021年1月発行)
特集 徹底解説 術後後遺症をいかに防ぐか—コツとポイント
75巻13号(2020年12月発行)
特集 膵頭十二指腸切除の完全ガイド—定型術式から困難症例への対処法まで
75巻12号(2020年11月発行)
特集 消化器外科手術 助手の極意—開腹からロボット手術まで
75巻11号(2020年10月発行)
増刊号 早わかり縫合・吻合のすべて
75巻10号(2020年10月発行)
特集 ガイドラインには書いていない—胃癌治療のCQ
75巻9号(2020年9月発行)
特集 変貌する肝移植—適応拡大・ドナー選択・治療戦略の最先端を知る
75巻8号(2020年8月発行)
特集 遺伝性腫瘍とゲノム医療を学ぶ
75巻7号(2020年7月発行)
特集 若手外科医必携!—緊急手術の適応と術式
75巻6号(2020年6月発行)
特集 膵癌診療ガイドライン改訂を外科医はこう読み解く—ディベート&ディスカッション
75巻5号(2020年5月発行)
特集 taTMEのすべて
75巻4号(2020年4月発行)
特集 実践! 手術が上達するトレーニング法—Off the Job Trainingの最新動向
75巻3号(2020年3月発行)
特集 一般・消化器外科医のための できる! 漢方
75巻2号(2020年2月発行)
特集 「縫合不全!!」を防ぐ
75巻1号(2020年1月発行)
特集 “超”高難度手術! 他臓器合併切除術を極める
74巻13号(2019年12月発行)
特集 見せます! できる外科医のオペ記事—肝胆膵高度技能医は手術をこう描く
74巻12号(2019年11月発行)
特集 特殊な鼠径部ヘルニアに対する治療戦略
74巻11号(2019年10月発行)
増刊号 すぐに使える周術期管理マニュアル
74巻10号(2019年10月発行)
特集 腹腔鏡下胃手術のすべて
74巻9号(2019年9月発行)
特集 膵・消化管神経内分泌腫瘍—診断・治療の基本と最新動向
74巻8号(2019年8月発行)
特集 これだけは押さえたい!—大腸癌取扱い規約・治療ガイドライン—改訂のポイント
74巻7号(2019年7月発行)
特集 徹底解説! 噴門側胃切除術
74巻6号(2019年6月発行)
特集 肛門を極める
74巻5号(2019年5月発行)
特集 JSES技術認定取得をめざせ!
74巻4号(2019年4月発行)
特集 こんなときどうする!?—消化器外科の術中トラブル対処法
74巻3号(2019年3月発行)
特集 これからはじめるロボット手術
74巻2号(2019年2月発行)
特集 急性胆囊炎診療をマスターしよう
74巻1号(2019年1月発行)
特集 当直医必携!「右下腹部痛」を極める
73巻13号(2018年12月発行)
特集 ここがポイント!—サルコペニアの病態と対処法
73巻12号(2018年11月発行)
特集 炎症性腸疾患アップデート—いま外科医に求められる知識と技術
73巻11号(2018年10月発行)
増刊号 あたらしい外科局所解剖全図—ランドマークとその出し方
73巻10号(2018年10月発行)
特集 胃癌治療ガイドライン最新版を読み解く—改定のポイントとその背景
73巻9号(2018年9月発行)
特集 癌手術エキスパートになるための道
73巻8号(2018年8月発行)
特集 徹底解説! 膵尾側切除を極める
73巻7号(2018年7月発行)
特集 最新版 “腸閉塞”を極める!
73巻6号(2018年6月発行)
特集 こうやって教える・学ぶ 高難度消化器外科手術—新エキスパートへの登竜門
73巻5号(2018年5月発行)
特集 縦隔を覗き,さらにくり抜く—これからの食道・胃外科手術
73巻4号(2018年4月発行)
特集 機能温存と機能再建をめざした消化器外科手術—術後QOL向上のために
73巻3号(2018年3月発行)
特集 徹底解説!—膵頭十二指腸切除の手術手技
73巻2号(2018年2月発行)
特集 外科医が知っておくべき—最新Endoscopic Intervention
73巻1号(2018年1月発行)
特集 閉塞性大腸癌—ベストプラクティスを探す
72巻13号(2017年12月発行)
特集 最新の胆道癌診療トピックス—新たな治療戦略の可能性を探る
72巻12号(2017年11月発行)
特集 徹底解説!ここが変わった膵癌診療—新規約・ガイドラインに基づいて
72巻11号(2017年10月発行)
増刊号 手術ステップごとに理解する—標準術式アトラス
72巻10号(2017年10月発行)
特集 Conversion Surgery—進行消化器がんのトータル治療戦略
72巻9号(2017年9月発行)
特集 知っておきたい 乳がん診療のエッセンス
72巻8号(2017年8月発行)
特集 がん治療医のための漢方ハンドブック
72巻7号(2017年7月発行)
特集 イラストでわかる!—消化器手術における最適な剝離層
72巻6号(2017年6月発行)
特集 術後重大合併症—これだけは知っておきたい緊急処置法
72巻5号(2017年5月発行)
特集 百花繚乱! エネルギーデバイスを使いこなす
72巻4号(2017年4月発行)
特集 消化管吻合アラカルト—あなたの選択は?
72巻3号(2017年3月発行)
特集 目で見る腹腔鏡下肝切除—エキスパートに学ぶ!
72巻2号(2017年2月発行)
特集 ビッグデータにもとづいた—術前リスクの評価と対処法
72巻1号(2017年1月発行)
特集 最新の内視鏡外科手術の適応と注意点
71巻13号(2016年12月発行)
特集 名手からの提言—手術を極めるために
71巻12号(2016年11月発行)
特集 転移性肝腫瘍のいま—なぜ・どこが原発臓器ごとに違うのか
71巻11号(2016年10月発行)
増刊号 消化器・一般外科医のための—救急・集中治療のすべて
71巻10号(2016年10月発行)
特集 エキスパートが教える 鼠径部ヘルニアのすべて
71巻9号(2016年9月発行)
特集 食道癌手術のコツと要点
71巻8号(2016年8月発行)
特集 外科医が攻める高度進行大腸癌
71巻7号(2016年7月発行)
特集 胆管系合併症のすべて—その予防とリカバリー
71巻6号(2016年6月発行)
特集 必携 腹腔鏡下胃癌手術の完全マスター—ビギナーからエキスパートまで
71巻5号(2016年5月発行)
特集 外科臨床研究のノウハウと重要研究の総まとめ
71巻4号(2016年4月発行)
特集 大腸癌肝転移—最新の治療ストラテジー
71巻3号(2016年3月発行)
特集 術後障害のリアル—外来フォローの実力が臓器損失を補う
71巻2号(2016年2月発行)
特集 イラストでみる大腸癌腹腔鏡手術のポイント
71巻1号(2016年1月発行)
特集 十二指腸乳頭部病変に対する新たな治療戦略—新規約・新ガイドラインに基づいて
70巻13号(2015年12月発行)
特集 外科医に求められる積極的緩和医療—延命と症状緩和の狭間で
70巻12号(2015年11月発行)
特集 同時性・異時性の重複がんを見落とさない—がん診療における他臓器への目配り
70巻11号(2015年10月発行)
増刊号 消化器・一般外科手術のPearls&Tips—ワンランク上の手術を達成する技と知恵
70巻10号(2015年10月発行)
特集 エキスパートの消化管吻合を学ぶ
70巻9号(2015年9月発行)
特集 再発に挑む!—外科治療の役割
70巻8号(2015年8月発行)
特集 大腸癌腹腔鏡手術の新展開—Reduced port surgeryからロボット手術まで
70巻7号(2015年7月発行)
特集 Neoadjuvant therapyの最新の動向—がんの治療戦略はどのように変わっていくのか
70巻6号(2015年6月発行)
特集 胃切除後再建術式の工夫とその評価
70巻5号(2015年5月発行)
特集 外科医が知っておくべき がん薬物療法の副作用とその対策
70巻4号(2015年4月発行)
特集 膵・消化管神経内分泌腫瘍(GEP-NET)のアップデート
70巻3号(2015年3月発行)
特集 生検材料を手術に活かす
70巻2号(2015年2月発行)
特集 肛門良性疾患を極める—目で見る 多彩な病態へのアプローチ法
70巻1号(2015年1月発行)
特集 胆道癌外科切除—再発防止のストラテジー
69巻13号(2014年12月発行)
特集 早期胃癌の外科治療を極める—「EMR 適応外」への安全で有益な縮小手術を求めて
69巻12号(2014年11月発行)
特集 外科切除適応の境界領域—Borderline resectable cancerへの対応
69巻11号(2014年10月発行)
増刊号 ERAS時代の周術期管理マニュアル
69巻10号(2014年10月発行)
特集 直腸癌局所再発に対する治療戦略―新たな展開
69巻9号(2014年9月発行)
特集 外科医が知っておくべき小腸疾患
69巻8号(2014年8月発行)
特集 肝胆膵癌の血管浸潤をどう治療するか
69巻7号(2014年7月発行)
特集 術後合併症への対処法 Surgical vs Non-Surgical―いつどのように判断するか?
69巻6号(2014年6月発行)
特集 癌の補助療法アップデート
69巻5号(2014年5月発行)
特集 消化器外科での救急医療―救急外来から手術室そして病棟まで
69巻4号(2014年4月発行)
特集 サルベージとコンバージョン―集学的治療で外科手術に求められるもの
69巻3号(2014年3月発行)
特集 究極の肛門温存術式ISR―長期成績からわかる有用性と問題点
69巻2号(2014年2月発行)
特集 ディベート★消化器・一般外科手術―選ぶのはどっちだ!
69巻1号(2014年1月発行)
特集 見直される膵癌診療の新展開
68巻13号(2013年12月発行)
特集 切徐可能なStage Ⅳ胃癌に対する外科治療
68巻12号(2013年11月発行)
特集 漢方を上手に使う―エビデンスに基づいた外科診療
68巻11号(2013年10月発行)
特集 術前画像診断のポイントと術中解剖認識
68巻10号(2013年10月発行)
特集 次代の外科専門医をめざしたトレーニングシステム
68巻9号(2013年9月発行)
特集 大腸癌腹膜播種を極める―最近の進歩と今後の展望
68巻8号(2013年8月発行)
特集 外科医のための癌免疫療法―基礎と臨床
68巻7号(2013年7月発行)
特集 NOTSS―外科医に問われる手技以外のスキル
68巻6号(2013年6月発行)
特集 胃癌腹膜転移治療の最前線
68巻5号(2013年5月発行)
特集 一般外科医が知っておくべき小児患者への対応
68巻4号(2013年4月発行)
特集 「食道胃接合部癌」に迫る!
68巻3号(2013年3月発行)
特集 CRT時代の直腸癌手術―最善の戦略は何か
68巻2号(2013年2月発行)
特集 術後の血管系合併症―その診断と対策
68巻1号(2013年1月発行)
特集 進歩する消化器外科手術―術式の温故知新
67巻13号(2012年12月発行)
特集 本当は怖い 臓器解剖変異―外科医が必ず知っておくべき知識
67巻12号(2012年11月発行)
特集 食道癌・胃癌切除後の再建法を見直す―達人の選択
67巻11号(2012年10月発行)
特集 外科医のための癌診療データ
67巻10号(2012年10月発行)
特集 炎症性腸疾患のすべて―新しい治療戦略
67巻9号(2012年9月発行)
特集 高齢者外科手術における周術期管理
67巻8号(2012年8月発行)
特集 知っておきたい放射線・粒子線治療
67巻7号(2012年7月発行)
特集 分子標的薬の有害事象とその対策
67巻6号(2012年6月発行)
特集 よくわかるNCD
67巻5号(2012年5月発行)
特集 次代のMinimally Invasive Surgery!
67巻4号(2012年4月発行)
特集 内視鏡外科手術の腕をみがく―技術認定医をめざして
67巻3号(2012年3月発行)
特集 消化器外科のドレーン管理を再考する
67巻2号(2012年2月発行)
特集 肝胆膵外科手術における術中トラブル―その予防と対処のポイント
67巻1号(2012年1月発行)
特集 「切除困難例」への化学療法後の手術―根治切除はどこまで可能か
66巻13号(2011年12月発行)
特集 外科医のための消化器内視鏡Up-to-Date
66巻12号(2011年11月発行)
特集 目で見てわかる肛門疾患治療
66巻11号(2011年10月発行)
特集 外科医のための最新癌薬物療法
66巻10号(2011年10月発行)
特集 進歩する癌転移診断―外科臨床はどう変わるのか
66巻9号(2011年9月発行)
特集 下大静脈にかかわる病態を見直す
66巻8号(2011年8月発行)
特集 画像診断の進歩をいかに手術に役立てるか
66巻7号(2011年7月発行)
特集 術前薬物療法は乳癌手術を縮小させるか
66巻6号(2011年6月発行)
特集 栄養療法―最新の知見と新たな展開
66巻5号(2011年5月発行)
特集 いま必要な外科治療に関する臨床試験の最新知識
66巻4号(2011年4月発行)
特集 悪性腫瘍の術中病理診断を効果的に活用する―どこを検索すべきか,どう対応すべきか
66巻3号(2011年3月発行)
特集 知っておくべき 外科手術の神経系合併症 その診断と対策
66巻2号(2011年2月発行)
特集 T4の癌―臓器別特性と治療戦略
66巻1号(2011年1月発行)
特集 医療経済からみた大腸癌化学療法
65巻13号(2010年12月発行)
特集 「出血量ゼロ」をめざした消化管癌の内視鏡下手術
65巻12号(2010年11月発行)
特集 新しいエネルギーデバイスの構造と使い方のコツ
65巻11号(2010年10月発行)
特集 外科医のための大腸癌の診断と治療
65巻10号(2010年10月発行)
特集 乳糜胸水・腹水を考える―その原因と対策
65巻9号(2010年9月発行)
特集 [臓器別]消化器癌終末期の特徴とターミナルケア
65巻8号(2010年8月発行)
特集 ESD時代の外科治療
65巻7号(2010年7月発行)
特集 腹壁瘢痕ヘルニア治療up date
65巻6号(2010年6月発行)
特集 癌外科治療の日本と海外との相違点
65巻5号(2010年5月発行)
特集 消化器外科手術における新しい潮流
65巻4号(2010年4月発行)
特集 消化器癌neoadjuvant chemotherapyの新展開
65巻3号(2010年3月発行)
特集 エキスパートが伝える 消化器癌手術の流れと手術助手の心得
65巻2号(2010年2月発行)
特集 外科医に必要なPET検査の知識―その有用性と問題点
65巻1号(2010年1月発行)
特集 がん診療ガイドライン―臨床現場における有効活用法
64巻13号(2009年12月発行)
特集 内視鏡下手術―もう一歩のステップアップのために
64巻12号(2009年11月発行)
特集 転移性腫瘍に対する治療戦略
64巻11号(2009年10月発行)
特集 できる!縫合・吻合
64巻10号(2009年10月発行)
特集 消化器外科における経腸栄養の意義と役割
64巻9号(2009年9月発行)
特集 外科医に求められるチーム医療Practice
64巻8号(2009年8月発行)
特集 胆囊癌根治手術をめぐる諸問題
64巻7号(2009年7月発行)
特集 肝胆膵癌に対する補助療法―治療成績の向上を目指して
64巻6号(2009年6月発行)
特集 消化器癌外科治療のrandomized controlled trial
64巻5号(2009年5月発行)
特集 炎症性腸疾患外科治療のcontroversy
64巻4号(2009年4月発行)
特集 脾臓をめぐる最近のトピックス
64巻3号(2009年3月発行)
特集 直腸癌治療―最近の進歩と動向
64巻2号(2009年2月発行)
特集 最近のGIST診療―診療ガイドラインの理解と実践
64巻1号(2009年1月発行)
特集 外科診療上知っておきたい新たな予後予測因子・スコア
63巻13号(2008年12月発行)
特集 外科におけるadjuvant/neoadjuvant chemotherapy update
63巻12号(2008年11月発行)
特集 十二指腸病変に対する外科的アプローチ
63巻11号(2008年10月発行)
特集 肛門疾患診療のすべて
63巻10号(2008年10月発行)
特集 鼠径ヘルニアの治療NOW―乳幼児から成人まで
63巻9号(2008年9月発行)
特集 がんの切除範囲を考える―診断法とその妥当性
63巻8号(2008年8月発行)
特集 St. Gallen 2007に基づいた乳癌テーラーメイド補助療法
63巻7号(2008年7月発行)
特集 実践に必要な術後創の管理
63巻6号(2008年6月発行)
特集 肝・胆・膵領域における腹腔鏡下手術の最前線
63巻5号(2008年5月発行)
特集 胆道癌外科診療を支えるエキスパートテクニック
63巻4号(2008年4月発行)
特集 消化器外科と漢方
63巻3号(2008年3月発行)
特集 術前・術中のリンパ節転移診断の方法とその有用性
63巻2号(2008年2月発行)
特集 安全な消化管器械吻合をめざして
63巻1号(2008年1月発行)
特集 機能温存手術のメリット・デメリット
62巻13号(2007年12月発行)
特集 膵臓外科の新たな展開
62巻12号(2007年11月発行)
特集 Up-to-Date外科医のための創傷治癒
62巻11号(2007年10月発行)
特集 癌診療に役立つ最新データ2007-2008
62巻10号(2007年10月発行)
特集 肛門疾患診断・治療のコツと実際
62巻9号(2007年9月発行)
特集 多発肝転移をめぐって
62巻8号(2007年8月発行)
特集 Surgical Site Infection(SSI)対策
62巻7号(2007年7月発行)
特集 乳癌の治療戦略―エビデンスとガイドラインの使い方
62巻6号(2007年6月発行)
特集 肝胆膵術後合併症―その予防のために
62巻5号(2007年5月発行)
特集 外来がん化学療法と外科
62巻4号(2007年4月発行)
特集 癌診療ガイドラインの功罪
62巻3号(2007年3月発行)
特集 術後呼吸器合併症―予防と対策の最新知識
62巻2号(2007年2月発行)
特集 外科領域におけるインフォームド・コンセントと医療安全対策
62巻1号(2007年1月発行)
特集 良性腸疾患における腹腔鏡下手術の適応と限界
61巻13号(2006年12月発行)
特集 消化器外科術後合併症の治療戦略―私たちはこのように治療している
61巻12号(2006年11月発行)
特集 生活習慣病および代謝性疾患と外科
61巻11号(2006年10月発行)
特集 イラストレイテッド外科標準術式
61巻10号(2006年10月発行)
特集 今どうしてNSTなのか?
61巻9号(2006年9月発行)
特集 消化器外科医に必要な低侵襲治療の知識
61巻8号(2006年8月発行)
特集 急性腹症における低侵襲な治療法選択
61巻7号(2006年7月発行)
特集 消化器外科における非観血的ドレナージ
61巻6号(2006年6月発行)
特集 癌の播種性病変の病態と診断・治療
61巻5号(2006年5月発行)
特集 手術のための臨床局所解剖
61巻4号(2006年4月発行)
特集 最新の手術器械―使いこなすコツを学ぶ
61巻3号(2006年3月発行)
特集 乳腺疾患を取り巻くガイドラインと最新の知見―最適な診療を目指して
61巻2号(2006年2月発行)
特集 外科医に求められる緩和医療の知識
61巻1号(2006年1月発行)
特集 GIST―診断と治療の最前線
60巻13号(2005年12月発行)
特集 消化管機能温存を考えた外科手術最前線
60巻12号(2005年11月発行)
特集 生体肝移植―最新の話題
60巻11号(2005年10月発行)
特集 癌治療のプロトコール2005-2006
60巻10号(2005年10月発行)
特集 自動吻合器・縫合器による消化管再建の標準手技と応用
60巻9号(2005年9月発行)
特集 癌告知とインフォームド・コンセント
60巻8号(2005年8月発行)
特集 肝切除のコツを知る―出血を少なくするために
60巻7号(2005年7月発行)
特集 炎症性腸疾患―治療における最近の進歩
60巻6号(2005年6月発行)
特集 化学放射線療法―現状とイメージングによる効果判定
60巻5号(2005年5月発行)
特集 外科栄養療法の新たな潮流
60巻4号(2005年4月発行)
特集 Surgical Site Infection(SSI)の現状と対策
60巻3号(2005年3月発行)
特集 急性肺塞栓症の最新診療
60巻2号(2005年2月発行)
特集 再発食道癌を考える
60巻1号(2005年1月発行)
特集 手術のグッドタイミング
59巻13号(2004年12月発行)
特集 直腸癌に対する手術のコツ
59巻12号(2004年11月発行)
特集 術中の出血コントロールと止血のノウハウ
59巻11号(2004年10月発行)
特集 小外科・外来処置マニュアル
59巻10号(2004年10月発行)
特集 周術期の輸液と感染対策
59巻9号(2004年9月発行)
特集 乳癌初回の診療:ガイドラインと主治医の裁量
59巻8号(2004年8月発行)
特集 肛門疾患診断・治療の実際
59巻7号(2004年7月発行)
特集 研修医のための外科基本手技とそのコツ
59巻6号(2004年6月発行)
特集 内視鏡外科手術を安全に行うために
59巻5号(2004年5月発行)
特集 Sentinel node navigation surgery―新たなる展開
59巻4号(2004年4月発行)
特集 甲状腺癌治療の最適化を目指して
59巻3号(2004年3月発行)
特集 肝細胞癌治療の最前線
59巻2号(2004年2月発行)
特集 GIST(gastrointestinal stromal tumor)診療の最前線
59巻1号(2004年1月発行)
特集 癌en bloc切除とnon-touch isolation techniqueの考え方と実践
58巻13号(2003年12月発行)
特集 内視鏡下手術で発展した手技・器具の外科手術への応用
58巻12号(2003年11月発行)
特集 浸潤性膵管癌の診療をどうするか
58巻11号(2003年10月発行)
特集 クリニカルパスによる外科医療の進歩
58巻10号(2003年10月発行)
特集 神経温存胃切除術
58巻9号(2003年9月発行)
特集 癌と紛らわしい各領域の諸病変
58巻8号(2003年8月発行)
特集 癌化学療法レジメンの選択とその根拠:消化器癌
58巻7号(2003年7月発行)
特集 癌化学療法レジメンの選択とその根拠:乳癌・肺癌・甲状腺癌
58巻6号(2003年6月発行)
特集 癌肝転移の治療戦略
58巻5号(2003年5月発行)
特集 栄養療法とformula
58巻4号(2003年4月発行)
特集 腹腔鏡下大腸切除術のコツ
58巻3号(2003年3月発行)
特集 Q&A器械吻合・縫合のコツ
58巻2号(2003年2月発行)
特集 胆囊癌NOW
58巻1号(2003年1月発行)
特集 外科における重症感染症とその対策
57巻13号(2002年12月発行)
特集 胃癌治療ガイドラインの検証
57巻12号(2002年11月発行)
特集 肛門疾患手術のup to date
57巻11号(2002年10月発行)
特集 癌診療に役立つ最新データ
57巻10号(2002年10月発行)
特集 内視鏡下手術の現状と問題点
57巻9号(2002年9月発行)
特集 パソコン活用術とその周辺
57巻8号(2002年8月発行)
特集 ヘルニア—最新の治療
57巻7号(2002年7月発行)
特集 外科診療とステロイド療法
57巻6号(2002年6月発行)
特集 エビデンスから見直す癌術後患者のフォローアップ
57巻5号(2002年5月発行)
特集 肝切除術のコツ
57巻4号(2002年4月発行)
特集 消化器外科における機能検査
57巻3号(2002年3月発行)
特集 乳癌:初回治療の標準化
57巻2号(2002年2月発行)
特集 食道癌治療におけるcontroversy
57巻1号(2002年1月発行)
特集 最先端の外科医療
56巻13号(2001年12月発行)
特集 IVRの現状と問題点
56巻12号(2001年11月発行)
特集 新しい医療材料と器具
56巻11号(2001年10月発行)
特集 画像で決める癌手術の切除範囲—典型症例総覧
56巻10号(2001年10月発行)
特集 甲状腺外科—最新の臨床
56巻9号(2001年9月発行)
特集 外科と消毒と感染予防
56巻8号(2001年8月発行)
特集 閉塞性黄疸の診療手順
56巻7号(2001年7月発行)
特集 肝良性疾患—鑑別診断と治療法選択のupdate
56巻6号(2001年6月発行)
特集 大腸癌の術後再発をめぐって
56巻5号(2001年5月発行)
特集 家族性腫瘍—診断と治療の現況
56巻4号(2001年4月発行)
特集 外科におけるクリニカルパスの展開
56巻3号(2001年3月発行)
特集 総胆管結石治療の最前線—手技と周辺機器の進歩
56巻2号(2001年2月発行)
特集 重症急性膵炎の診療Now
56巻1号(2001年1月発行)
特集 21世紀の外科—Tissue Engineering
55巻13号(2000年12月発行)
特集 超音波ガイド下の穿刺手技
55巻12号(2000年11月発行)
特集 胃癌術後のフォローアップ:再発と二次癌対策
55巻11号(2000年10月発行)
特集 癌治療のプロトコール—当施設はこうしている
55巻10号(2000年10月発行)
特集 ベッドサイド基本手技とコツ
55巻9号(2000年9月発行)
特集 外科医に求められる緩和医療プラクティス
55巻8号(2000年8月発行)
特集 肛門疾患診療の実際とコツ
55巻7号(2000年7月発行)
特集 抗菌薬ベストチョイス—その理論と実際
55巻6号(2000年6月発行)
特集 胃全摘後の消化管再建—術式のベストチョイス
55巻5号(2000年5月発行)
特集 輸液:その組成・アクセス・管理
55巻4号(2000年4月発行)
特集 各種ステント治療のノウハウ
55巻3号(2000年3月発行)
特集 Sentinel Node Navigation Surgery
55巻2号(2000年2月発行)
特集 イレウス診療のupdate
55巻1号(2000年1月発行)
特集 肝臓移植を理解する
54巻13号(1999年12月発行)
特集 大腸の非腫瘍性疾患—外科医のための診療指針
54巻12号(1999年11月発行)
特集 胃・十二指腸の非腫瘍性疾患—外科医のための診療指針
54巻11号(1999年10月発行)
特集 薬物療法マニュアル
54巻10号(1999年10月発行)
特集 消化管EMRの現状と問題点
54巻9号(1999年9月発行)
特集 在宅栄養療法の標準管理
54巻8号(1999年8月発行)
特集 3D画像診断の肝胆膵手術への応用
54巻7号(1999年7月発行)
特集 膵臓外科に対するチャレンジ:切離・吻合の工夫
54巻6号(1999年6月発行)
特集 直腸癌の治療—機能温存手術のプログレス
54巻5号(1999年5月発行)
特集 切除標本取扱いガイドライン—癌取扱い規約に基づいた正しい取扱い法と肉眼所見の記載法
54巻4号(1999年4月発行)
特集 Surgical deviceの有効,安全な使い方
54巻3号(1999年3月発行)
特集 器械吻合・縫合におけるコツとピットフォール
54巻2号(1999年2月発行)
特集 癌転移治療のノウハウ
54巻1号(1999年1月発行)
特集 乳癌の手術:最適化への論点
53巻13号(1998年12月発行)
特集 外科・形成外科の連携と展望
53巻12号(1998年11月発行)
特集 肝癌治療のupdate
53巻11号(1998年10月発行)
特集 縫合・吻合法のバイブル
53巻10号(1998年10月発行)
特集 胃癌術後補助化学療法をめぐって
53巻9号(1998年9月発行)
特集 急性腹膜炎—病態と治療の最前線
53巻8号(1998年8月発行)
特集 肛門疾患診断・治療のノウハウ
53巻7号(1998年7月発行)
特集 分子生物学的診断は病理診断に迫れるか
53巻6号(1998年6月発行)
特集 ここまできたDay Surgery
53巻5号(1998年5月発行)
特集 病態別補充・補正のFormula
53巻4号(1998年4月発行)
特集 早期直腸癌診療のストラテジー
53巻3号(1998年3月発行)
特集 自己血輸血の現状と将来展望
53巻2号(1998年2月発行)
特集 食道・胃静脈瘤攻略法
53巻1号(1998年1月発行)
特集 胆道ドレナージを考える
52巻13号(1997年12月発行)
特集 血管系病変と腹部消化器外科
52巻12号(1997年11月発行)
特集 消化器外科領域におけるメタリックステント
52巻11号(1997年10月発行)
特集 外来診療・小外科マニュアル
52巻10号(1997年10月発行)
特集 食道癌診療のトピックス
52巻9号(1997年9月発行)
特集 甲状腺と上皮小体の外科—最近の進歩
52巻8号(1997年8月発行)
特集 Q&A 自動吻合器・縫合器の安全,有効な使い方
52巻7号(1997年7月発行)
特集 経腸栄養法—最新の動向
52巻6号(1997年6月発行)
特集 輸血後GVHDをめぐる諸問題
52巻5号(1997年5月発行)
特集 サイトカインからみた周術期管理
52巻4号(1997年4月発行)
特集 膵瘻の予防・治療のノウハウ
52巻3号(1997年3月発行)
特集 ドレッシング—創傷管理の新たな展開
52巻2号(1997年2月発行)
特集 消化器の“前癌病変”と“ハイリスク病変”
52巻1号(1997年1月発行)
特集 転移性肺癌診療の最新ストラテジー
51巻13号(1996年12月発行)
特集 大災害に対する外科医の備え
51巻12号(1996年11月発行)
特集 外科医のためのペインクリニック
51巻11号(1996年10月発行)
特集 術前ワークアップマニュアル—入院から手術当日までの患者管理
51巻10号(1996年10月発行)
特集 胃癌治療のup-to-date—機能温存手術と縮小手術
51巻9号(1996年9月発行)
特集 急性腹症—画像診断から初期治療まで
51巻8号(1996年8月発行)
特集 直腸癌に対する肛門機能温存手術の実際
51巻7号(1996年7月発行)
特集 図解 成人鼠径ヘルニア手術
51巻6号(1996年6月発行)
特集 外科医に必要な整形外科の知識
51巻5号(1996年5月発行)
特集 肛門疾患診療のポイント—エキスパート17人のノウハウ
51巻4号(1996年4月発行)
特集 術後感染症—予防と治療の実際
51巻3号(1996年3月発行)
特集 肝炎・肝硬変患者の消化器外科手術
51巻2号(1996年2月発行)
特集 甲状腺外科の新しい展開
51巻1号(1996年1月発行)
特集 乳房温存療法の適応と実際
50巻13号(1995年12月発行)
特集 外科医のための緩和ケア
50巻12号(1995年11月発行)
特集 消化器癌手術における皮膚切開と術野展開の工夫
50巻11号(1995年10月発行)
特集 術後1週間の患者管理
50巻10号(1995年10月発行)
特集 多臓器不全—患者管理の実際
50巻9号(1995年9月発行)
特集 出血させない消化器癌手術
50巻8号(1995年8月発行)
特集 高齢者の外科—キュアとケア
50巻7号(1995年7月発行)
特集 再発消化管癌を治療する
50巻6号(1995年6月発行)
特集 外科臨床医のための基本手技
50巻5号(1995年5月発行)
特集 画像診断が変わる? MRIの新しい展開
50巻4号(1995年4月発行)
特集 新しい膵手術のテクニック
50巻3号(1995年3月発行)
特集 Q & A 人工呼吸管理とベンチレータ
50巻2号(1995年2月発行)
特集 消化器癌画像診断のノウ・ハウ
50巻1号(1995年1月発行)
特集 早期胃癌の内視鏡的根治切除
49巻13号(1994年12月発行)
特集 外科手術と輸血—最近の動向
49巻12号(1994年11月発行)
特集 ストーマの造設と管理—患者のQOLの視点から
49巻11号(1994年10月発行)
特集 施設別/新・悪性腫瘍治療のプロトコール
49巻10号(1994年10月発行)
特集 自動吻合器・縫合器を使いこなす
49巻9号(1994年9月発行)
特集 癌の外科治療とインフォームド・コンセント(IC)
49巻8号(1994年8月発行)
特集 消化器外科におけるInterventional Radiology(IVR)
49巻7号(1994年7月発行)
特集 腹腔鏡下の腹部救急疾患診療
49巻6号(1994年6月発行)
特集 静脈系疾患診療の新しい展開
49巻5号(1994年5月発行)
特集 術中肝エコーのABC
49巻4号(1994年4月発行)
特集 内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)
49巻3号(1994年3月発行)
特集 肝癌治療の最新ストラテジー
49巻2号(1994年2月発行)
特集 上部消化管の術後運動機能評価と病態
49巻1号(1994年1月発行)
特集 乳癌診療—今日の話題
48巻13号(1993年12月発行)
特集 スキルス胃癌の診断と治療
48巻12号(1993年11月発行)
特集 骨盤内悪性腫瘍の機能温存手術
48巻11号(1993年10月発行)
特集 Dos & Don'ts外来の小外科
48巻10号(1993年10月発行)
特集 今日の肺癌診療
48巻9号(1993年9月発行)
特集 食道癌治療への集学的アプローチ
48巻8号(1993年8月発行)
特集 疼痛をどうコントロールするか
48巻7号(1993年7月発行)
特集 Up-to-date総胆管結石症治療
48巻6号(1993年6月発行)
特集 MRSA感染症対策の実際
48巻5号(1993年5月発行)
特集 施設別・消化器癌術後栄養管理の実際
48巻4号(1993年4月発行)
特集 治療的ドレナージ
48巻3号(1993年3月発行)
特集 局所麻酔を行う外科医へ
48巻2号(1993年2月発行)
特集 消化管の機能温存手術
48巻1号(1993年1月発行)
特集 消化器癌切除材料取扱いマニュアル
47巻13号(1992年12月発行)
特集 今日の甲状腺癌診療
47巻12号(1992年11月発行)
特集 悪性腫瘍治療の現況—他科では今
47巻11号(1992年10月発行)
特集 外科患者・薬物療法マニュアル
47巻10号(1992年10月発行)
特集 形成外科から学び取る
47巻9号(1992年9月発行)
特集 大腸癌治療のフロンティア
47巻8号(1992年8月発行)
特集 膵癌への挑戦
47巻7号(1992年7月発行)
特集 肛門疾患診療の実際—私の方法と根拠
47巻6号(1992年6月発行)
特集 いまイレウスを診療する
47巻5号(1992年5月発行)
特集 腫瘍マーカーの理論と実際
47巻4号(1992年4月発行)
特集 静脈・経腸栄養のトピックス
47巻3号(1992年3月発行)
特集 再手術の適応と術式
47巻2号(1992年2月発行)
特集 下肢循環障害の治療—適応と限界
47巻1号(1992年1月発行)
特集 外科における超音波検査—新しい展開
46巻13号(1991年12月発行)
特集 院内感染—現状と対策
46巻12号(1991年11月発行)
特集 若年者癌診療の実際
46巻11号(1991年10月発行)
特集 術前・術後管理 '91
46巻10号(1991年10月発行)
特集 胆石症の非手術的治療—現況と問題点
46巻9号(1991年9月発行)
特集 胃癌の治療update
46巻8号(1991年8月発行)
特集 内視鏡下外科手術
46巻7号(1991年7月発行)
特集 熱傷治療のトピックス
46巻6号(1991年6月発行)
特集 食道静脈瘤治療の焦点
46巻5号(1991年5月発行)
特集 術前一般検査—異常値の読みと対策
46巻4号(1991年4月発行)
特集 癌のPalliative Therapy
46巻3号(1991年3月発行)
特集 乳房温存療法の実践
46巻2号(1991年2月発行)
特集 急性腹症の近辺—他科からのアドバイス
46巻1号(1991年1月発行)
特集 Day Surgeryはどこまで可能か
45巻13号(1990年12月発行)
特集 進行癌の画像診断—治癒切除の判定をどうするか
45巻12号(1990年11月発行)
特集 癌手術の補助療法—現状と展望
45巻11号(1990年10月発行)
特集 保存的治療の適応と限界—外科から,内科から
45巻10号(1990年10月発行)
特集 胸水・腹水への対処
45巻9号(1990年9月発行)
特集 消化管吻合法—私の方法とコツ
45巻8号(1990年8月発行)
特集 臓器全摘術の適応と問題点
45巻7号(1990年7月発行)
特集 外科医のための整形外科
45巻6号(1990年6月発行)
特集 転移性肝癌の治療
45巻5号(1990年5月発行)
特集 腹部血管病変の診療
45巻4号(1990年4月発行)
特集 今日のストーマ
45巻3号(1990年3月発行)
特集 新しい手術材料—特徴と使い方
45巻2号(1990年2月発行)
特集 Endoscopic Surgery—適応と手技
45巻1号(1990年1月発行)
特集 肺癌の診断と治療 '90
44巻13号(1989年12月発行)
特集 小児外科
44巻12号(1989年11月発行)
特集 胆嚢癌の外科
44巻11号(1989年10月発行)
特集 肛門疾患治療の現況
44巻10号(1989年9月発行)
特集 鼎談
44巻9号(1989年9月発行)
特集 がん放射線療法の現況と進歩
44巻8号(1989年8月発行)
特集 臓器生検の適応と手技
44巻7号(1989年7月発行)
特集 食道癌の手術
44巻6号(1989年6月発行)
特集 胃癌治療の最近の話題
44巻5号(1989年5月発行)
特集 外科臨床における病態別栄養
44巻4号(1989年4月発行)
特集 消化器良性疾患の手術適応—最近の考え方
44巻3号(1989年3月発行)
特集 肝門部胆管癌の治療
44巻2号(1989年2月発行)
特集 80歳以上高齢者の手術
44巻1号(1989年1月発行)
特集 膵臓の外科—up to date
43巻13号(1988年12月発行)
特集 直腸癌の手術
43巻12号(1988年11月発行)
特集 Drug Delivery Systemを利用した癌治療
43巻11号(1988年10月発行)
特集 外科医のためのMRIの臨床
43巻10号(1988年9月発行)
特集 高位胃潰瘍治療の問題点—外科から,内科から
43巻9号(1988年8月発行)
特集 消化器癌の相対非治癒切除
43巻8号(1988年7月発行)
特集 多発外傷—初療60分
43巻7号(1988年6月発行)
特集 鼠径ヘルニアの診療
43巻6号(1988年5月発行)
特集 —そこが知りたい—消化器外科手術のテクニックとコツ96
43巻5号(1988年5月発行)
特集 急性腹症のX線像・エコー像
43巻4号(1988年4月発行)
特集 外科診療における酸塩基平衡の異常
43巻3号(1988年3月発行)
特集 手術と輸血—最近のトピックス
43巻2号(1988年2月発行)
特集 集中治療を要する術後合併症
43巻1号(1988年1月発行)
特集 臓器移植のup to date '88
42巻13号(1987年12月発行)
特集 外科的感染症と抗生物質の選択
42巻12号(1987年11月発行)
特集 胆石症—最近の話題
42巻11号(1987年10月発行)
特集 Interventional Radiologyの現況
42巻10号(1987年9月発行)
特集 癌術後follow upと再発時の対策
42巻9号(1987年8月発行)
特集 乳癌診療のUp-to-date
42巻8号(1987年7月発行)
特集 いわゆる消化器早期癌の術後再発—その実態と対策
42巻7号(1987年6月発行)
特集 外科医の触診
42巻6号(1987年5月発行)
特集 [施設別]悪性腫瘍治療方針のプロトコール
42巻5号(1987年5月発行)
特集 外科医のための超音波応用診断手技
42巻4号(1987年4月発行)
特集 頸部腫瘤の臨床
42巻3号(1987年3月発行)
特集 消化管のEmergency—穿孔・破裂
42巻2号(1987年2月発行)
特集 外科医が使える形成外科手技
42巻1号(1987年1月発行)
特集 今日の肺癌治療 '87
41巻13号(1986年12月発行)
特集 ストーマをめぐる最近の話題
41巻12号(1986年11月発行)
特集 MOF患者のArtificial Support
41巻11号(1986年10月発行)
特集 胃癌手術の限界と合理化
41巻10号(1986年9月発行)
特集 食道静脈瘤硬化療法—その適応と手技上のポイント
41巻9号(1986年8月発行)
特集 悪性腫瘍を疑うX線像
41巻8号(1986年7月発行)
特集 重症患者の輸液・栄養
41巻7号(1986年6月発行)
特集 肛門部疾患診療のテクニック
41巻6号(1986年6月発行)
特集 外科患者・薬物療法マニュアル
41巻5号(1986年5月発行)
特集 甲状腺癌の診断と治療
41巻4号(1986年4月発行)
特集 食道癌手術手技上のポイント
41巻3号(1986年3月発行)
特集 糖尿病合併患者の手術と管理
41巻2号(1986年2月発行)
特集 Borrmann 4型胃癌—私の治療
41巻1号(1986年1月発行)
特集 胆嚢隆起性病変をどうするか
40巻13号(1985年12月発行)
特集 肝内胆石に対する胆道ドレナージ手術
40巻12号(1985年11月発行)
特集 肝硬変合併患者の手術と管理
40巻11号(1985年10月発行)
特集 消化器外科医のための血管外科手技
40巻10号(1985年9月発行)
特集 症例による急性腹症の画像診断
40巻9号(1985年8月発行)
特集 Iatrogenic Abdominal Trauma—その予防と対策
40巻8号(1985年7月発行)
特集 噴門部癌の手術術式—適応と根拠
40巻6号(1985年6月発行)
特集 がん・画像診断の死角
40巻7号(1985年6月発行)
特集 鼎談・高齢者の消化管手術—手術適応のボーダーライン
40巻5号(1985年5月発行)
特集 膵頭十二指腸切除後の再建法のポイント
40巻4号(1985年4月発行)
特集 急性虫垂炎の臨床
40巻3号(1985年3月発行)
特集 癌のSurgical Emergencies
40巻2号(1985年2月発行)
特集 腹膜炎治療のノウ・ハウ
40巻1号(1985年1月発行)
特集 最近の経腸栄養法と外科
39巻12号(1984年12月発行)
特集 大腸切除と機能温存
39巻11号(1984年11月発行)
特集 胃癌—最近の話題
39巻10号(1984年10月発行)
特集 胆管癌の外科
39巻9号(1984年9月発行)
特集 どこまで活用できるか新しい手術器械
39巻8号(1984年8月発行)
特集 外傷の総合画像診断と初療
39巻7号(1984年7月発行)
特集 肝臓癌のTAE療法
39巻6号(1984年6月発行)
特集 〔Q & A〕術中トラブル対処法—私はこうしている
39巻5号(1984年5月発行)
特集 外科におけるクリティカル・ケア
39巻4号(1984年4月発行)
特集 臓器移植の最前線
39巻3号(1984年3月発行)
特集 外科感染症と免疫
39巻2号(1984年2月発行)
特集 がんの集学的治療をどうするか
39巻1号(1984年1月発行)
特集 今日の肺癌
38巻12号(1983年12月発行)
特集 プラスマフェレーシス
38巻11号(1983年11月発行)
特集 胃・十二指腸潰瘍
38巻10号(1983年10月発行)
特集 下部消化管出血
38巻9号(1983年9月発行)
特集 肝硬変と手術
38巻8号(1983年8月発行)
特集 臓器全摘後の病態と管理
38巻7号(1983年7月発行)
特集 鼠径・大腿ヘルニアの話題
38巻6号(1983年6月発行)
特集 吻合法—目でみるポイントとコツ
38巻5号(1983年5月発行)
特集 緊急減黄術—テクニックとそのコツ
38巻4号(1983年4月発行)
特集 癌手術と再建
38巻3号(1983年3月発行)
特集 腹部外傷の超音波診断
38巻2号(1983年2月発行)
特集 脾摘をめぐる話題
38巻1号(1983年1月発行)
特集 よくみる肛門部疾患診療のポイント
37巻12号(1982年12月発行)
特集 膵・胆管合流異常の外科
37巻11号(1982年11月発行)
特集 末梢血管障害の非侵襲的検査法
37巻10号(1982年10月発行)
特集 新しい抗生物質と外科
37巻9号(1982年9月発行)
特集 Controversy;皮切と到達経路
37巻8号(1982年8月発行)
特集 今日の人工肛門
37巻7号(1982年7月発行)
特集 胆石症をめぐる最近の話題
37巻6号(1982年6月発行)
特集 乳癌の縮小根治手術
37巻5号(1982年5月発行)
特集 外科外来マニュアル
37巻4号(1982年4月発行)
特集 レーザーと外科
37巻3号(1982年3月発行)
特集 人工呼吸管理のPit fall
37巻2号(1982年2月発行)
特集 食道静脈瘤手術
37巻1号(1982年1月発行)
特集 術中エコー
36巻12号(1981年12月発行)
特集 インスリン併用の高カロリー栄養法
36巻11号(1981年11月発行)
特集 迷切後の諸問題
36巻10号(1981年10月発行)
特集 膵炎診療のControversy
36巻9号(1981年9月発行)
特集 上部胆管癌の外科
36巻8号(1981年8月発行)
特集 手指の外傷—初期診療の実際
36巻7号(1981年7月発行)
特集 上部消化管出血—保存的止血法のトピックス
36巻6号(1981年6月発行)
特集 外傷の画像診断
36巻5号(1981年5月発行)
特集 Multiple Organ Failure
36巻4号(1981年4月発行)
特集 術後1週間の患者管理
36巻3号(1981年3月発行)
特集 晩期癌患者のcare
36巻2号(1981年2月発行)
特集 胃癌のAdjuvant Chemotherapy
36巻1号(1981年1月発行)
特集 RI診断の進歩
35巻12号(1980年12月発行)
特集 癌と栄養
35巻11号(1980年11月発行)
特集 私の縫合材料と縫合法
35巻10号(1980年10月発行)
特集 胆道ドレナージに伴うトラブル
35巻9号(1980年9月発行)
特集 消化管手術と器械吻合
35巻8号(1980年8月発行)
特集 閉塞性黄疸—最近の診断法の進歩
35巻7号(1980年7月発行)
特集 大腸癌根治手術の再検討—ポリペクトミーから拡大郭清まで
35巻6号(1980年6月発行)
特集 最近の呼吸管理法をめぐるQ&A
35巻5号(1980年5月発行)
特集 癌のリンパ節郭清をどうするか
35巻4号(1980年4月発行)
特集 膵癌と膵頭十二指腸切除術
35巻3号(1980年3月発行)
特集 血管カテーテルの治療への応用
35巻2号(1980年2月発行)
特集 外科医のための麻酔
35巻1号(1980年1月発行)
特集 遺残胆石
34巻12号(1979年12月発行)
特集 噴門部癌の特性と外科治療
34巻11号(1979年11月発行)
特集 熱傷治療のトピックス
34巻10号(1979年10月発行)
特集 急性胆嚢炎の治療
34巻9号(1979年9月発行)
特集 手術と抗生物質
34巻8号(1979年8月発行)
特集 術中・術後の出血
34巻7号(1979年7月発行)
特集 Crohn病とその辺縁疾患
34巻6号(1979年6月発行)
特集 これだけは知っておきたい手術の適応とタイミング—注意したい疾患45
34巻5号(1979年5月発行)
特集 外科と血管造影—〈読影のポイント,鑑別のコツ〉
34巻4号(1979年4月発行)
特集 Elemental Diet
34巻3号(1979年3月発行)
特集 成分輸血
34巻2号(1979年2月発行)
特集 外科とエコー
34巻1号(1979年1月発行)
特集 ショックをめぐる新しい話題
33巻12号(1978年12月発行)
特集 非定形的乳切の術式と適応
33巻11号(1978年11月発行)
特集 検査と合併症—おこさないためには、おこしてしまったら
33巻10号(1978年10月発行)
特集 今日の癌免疫療法
33巻9号(1978年9月発行)
特集 食道癌手術の近況
33巻8号(1978年8月発行)
特集 老年者の手術—併存疾患の診かた・とらえ方
33巻7号(1978年7月発行)
特集 臓器大量切除と栄養
33巻6号(1978年6月発行)
特集 T-tubeと胆道鏡
33巻5号(1978年5月発行)
特集 乳幼児急性腹症—診断のポイントとfirst aid
33巻4号(1978年4月発行)
特集 術後呼吸障害とその管理
33巻3号(1978年3月発行)
特集 CTスキャン
33巻2号(1978年2月発行)
特集 消化性潰瘍と迷切術
33巻1号(1978年1月発行)
特集 最近の手術材料と器具
32巻12号(1977年12月発行)
特集 目でみる話題の消化器手術
32巻11号(1977年11月発行)
特集 Biopsyの再検討
32巻10号(1977年10月発行)
特集 肺癌—新しい診療のポイント
32巻9号(1977年9月発行)
特集 逆流性食道炎
32巻8号(1977年8月発行)
特集 上部消化管大量出血
32巻7号(1977年7月発行)
特集 甲状腺機能亢進症—外科医の役割
32巻6号(1977年6月発行)
特集 今日の胆道造影
32巻5号(1977年5月発行)
特集 非癌性乳腺疾患の外科
32巻4号(1977年4月発行)
特集 ヘルニア再検討
32巻3号(1977年3月発行)
特集 外科と薬剤
32巻2号(1977年2月発行)
特集 腹部手術後の輸液—私はこうしている
32巻1号(1977年1月発行)
特集 人工肛門のAfter Care
31巻12号(1976年12月発行)
特集 胆道手術後の困難症
31巻11号(1976年11月発行)
特集 術後の急性機能不全
31巻10号(1976年10月発行)
特集 肝切除の術式
31巻9号(1976年9月発行)
特集 進行胃癌の化学療法
31巻8号(1976年8月発行)
特集 特殊な消化性潰瘍
31巻7号(1976年7月発行)
特集 重度外傷
31巻6号(1976年6月発行)
特集 早期大腸癌の外科
31巻5号(1976年5月発行)
特集 大量輸血
31巻4号(1976年4月発行)
特集 手術とHyperalimentation
31巻3号(1976年3月発行)
特集 急性腹症のX線像
31巻2号(1976年2月発行)
特集 手術と肝障害
31巻1号(1976年1月発行)
特集 遠隔成績よりみた早期胃癌
30巻12号(1975年12月発行)
特集 脳卒中の外科
30巻11号(1975年11月発行)
特集 癌免疫と外科治療
30巻10号(1975年10月発行)
特集 凍結外科—Cryosurgery
30巻9号(1975年9月発行)
特集 縫合法—反省と再検討
30巻8号(1975年8月発行)
特集 消化管の創傷治癒
30巻7号(1975年7月発行)
特集 手術と副損傷
30巻6号(1975年6月発行)
特集 乳癌—最近の趨勢
30巻5号(1975年5月発行)
特集 胃切除後にくるもの—その対策と治療
30巻4号(1975年4月発行)
特集 腹部外科のPhysical Signs
30巻3号(1975年3月発行)
特集 閉塞性黄疸
30巻2号(1975年2月発行)
特集 ショック治療の新しい考え方
30巻1号(1975年1月発行)
特集 手の外科
29巻12号(1974年12月発行)
特集 一般外科医のための小児外科
29巻11号(1974年11月発行)
特集 外科と血栓
29巻9号(1974年10月発行)
29巻8号(1974年8月発行)
特集 外傷救急診療におけるDo's & Don'ts
29巻7号(1974年7月発行)
特集 痔核と痔瘻の外科
29巻6号(1974年6月発行)
特集 胸部食道癌の外科
29巻5号(1974年5月発行)
特集 老人外科—老年者胆道系疾患の外科
29巻4号(1974年4月発行)
特集 腹部緊急疾患におけるDo's & Don'ts
29巻3号(1974年3月発行)
特集 胃全剔
29巻2号(1974年2月発行)
特集 消化管手術と内視鏡
29巻1号(1974年1月発行)
特集 外科とME—その現況と将来
28巻12号(1973年12月発行)
特集 外科と栄養—高カロリー輸液の問題点
28巻11号(1973年11月発行)
特集 膵炎の外科
28巻10号(1973年10月発行)
特集 外科医のための臨床検査
28巻9号(1973年9月発行)
28巻8号(1973年8月発行)
特集 急性腹膜炎
28巻7号(1973年7月発行)
特集 再発癌—follow-upとその治療
28巻6号(1973年6月発行)
特集 麻酔—外科医のために
28巻5号(1973年5月発行)
特集 外科と感染—その基本的対策とPitfall
28巻4号(1973年4月発行)
特集 術後ドレナージの実際
28巻3号(1973年3月発行)
特集 肝癌の外科
28巻2号(1973年2月発行)
特集 今日の救急
28巻1号(1973年1月発行)
特集 外科と大腸—癌とポリープを中心に
27巻12号(1972年12月発行)
特集 外科と大腸—炎症性疾患を中心に
27巻11号(1972年11月発行)
特集 末梢血管の外科
27巻10号(1972年10月発行)
特集 頸部血管障害
27巻9号(1972年9月発行)
特集 出血治療のPitfall
27巻8号(1972年8月発行)
特集 胆道外科のPitfall
27巻7号(1972年7月発行)
特集 皮膚切開法と到達法・Ⅱ
27巻6号(1972年6月発行)
特集 皮膚切開法と到達法・Ⅰ
27巻5号(1972年5月発行)
特集 日常外科の総点検・Ⅱ
27巻4号(1972年4月発行)
特集 日常外科の総点検・Ⅰ
27巻3号(1972年3月発行)
特集 黄疸の外科
27巻2号(1972年2月発行)
特集 瘻—その問題点
27巻1号(1972年1月発行)
特集 早期癌の外科治療
26巻12号(1971年12月発行)
特集 胃癌根治手術の問題点
26巻11号(1971年11月発行)
特集 小児外科の焦点
26巻10号(1971年10月発行)
26巻9号(1971年9月発行)
特集 上腹部痛—誤りやすい疾患の診療
26巻8号(1971年8月発行)
特集 今日の外傷—外傷患者の初診と初療
26巻7号(1971年7月発行)
26巻6号(1971年6月発行)
特集 手術とその根拠・Ⅱ
26巻5号(1971年5月発行)
特集 手術とその根拠・Ⅰ
26巻4号(1971年4月発行)
特集 外科とくすり—副作用と適正な使用法
26巻3号(1971年3月発行)
特集 緊急手術後の合併症・Ⅱ
26巻2号(1971年2月発行)
特集 緊急手術後の合併症・Ⅰ
26巻1号(1971年1月発行)
特集 これからの外科
25巻12号(1970年12月発行)
特集 Silent Disease
25巻11号(1970年11月発行)
特集 輸液の臨床
25巻10号(1970年10月発行)
特集 熱傷の早期治療
25巻9号(1970年9月発行)
特集 術後早期の再手術
25巻8号(1970年8月発行)
特集 縫合糸の問題点
25巻7号(1970年7月発行)
特集 腫瘍の病理と臨床
25巻6号(1970年6月発行)
特集 縫合不全
25巻5号(1970年5月発行)
特集 外科領域における感染症
25巻4号(1970年4月発行)
特集 心臓と血管の外科
25巻3号(1970年3月発行)
特集 手術と出血対策Ⅱ
25巻2号(1970年2月発行)
特集 手術と出血対策Ⅰ
25巻1号(1970年1月発行)
特集 特殊な輸血とその現況
24巻12号(1969年12月発行)
特集 全身状態とSurgical Risk
24巻11号(1969年11月発行)
特集 腸瘻の問題点
24巻10号(1969年10月発行)
特集 緊急手術の手技・Ⅱ
24巻9号(1969年9月発行)
特集 緊急手術の手技・Ⅰ
24巻8号(1969年8月発行)
特集 良性腫瘍
24巻7号(1969年7月発行)
24巻6号(1969年6月発行)
24巻5号(1969年5月発行)
特集 臨床麻酔の問題点
24巻4号(1969年4月発行)
特集 緊急手術適応のきめ手
24巻3号(1969年3月発行)
特集 消化器疾患の新しい診断法
24巻2号(1969年2月発行)
特集 乳腺疾患—その診療の進歩
24巻1号(1969年1月発行)
特集 人工臓器への歩み
23巻13号(1968年12月発行)
特集 癌外科の進歩—現状と将来
23巻12号(1968年11月発行)
特集 顔面損傷のファースト・エイド
23巻11号(1968年10月発行)
特集 Encephalopathyの臨床
23巻10号(1968年9月発行)
特集 肛門外科
23巻9号(1968年8月発行)
特集 脈管造影
23巻8号(1968年7月発行)
特集 膵・胆・肝の外科
23巻7号(1968年6月発行)
特集 手と足の外傷
23巻6号(1968年6月発行)
特集 木本誠二教授退官記念特集
23巻5号(1968年5月発行)
特集 臓器移植の可能性
23巻4号(1968年4月発行)
特集 最良の手術時点
23巻3号(1968年3月発行)
特集 術後困難症の処置
23巻2号(1968年2月発行)
特集 出血の問題点
23巻1号(1968年1月発行)
特集 初療の要点
22巻12号(1967年12月発行)
特集 鞭打ち損傷の問題点
22巻11号(1967年11月発行)
特集 肝腫瘍外科の課題
22巻10号(1967年10月発行)
特集 イレウスの治療—その困難な問題点
22巻9号(1967年9月発行)
特集 甲状腺疾患の問題点
22巻8号(1967年8月発行)
特集 胃・十二指腸潰瘍の手術
22巻7号(1967年7月発行)
特集 救急患者の取扱い方
22巻6号(1967年6月発行)
特集 血管の外科
22巻5号(1967年5月発行)
特集 胆石症手術の問題点
22巻4号(1967年4月発行)
特集 進行性消化器癌の外科
22巻3号(1967年3月発行)
特集 頭部外傷処置の実際
22巻2号(1967年2月発行)
特集 臨床検査後の偶発症
22巻1号(1967年1月発行)
特集 鼠径・陰嚢ヘルニアの問題点
21巻12号(1966年12月発行)
特集 虫垂炎—その困難な問題点
21巻11号(1966年11月発行)
特集 小児疾患の早期診断と手術適応
21巻10号(1966年10月発行)
21巻9号(1966年9月発行)
21巻8号(1966年8月発行)
特集 腫瘍の外科
21巻7号(1966年7月発行)
21巻6号(1966年6月発行)
21巻5号(1966年5月発行)
特集 癌患者の栄養問題
21巻4号(1966年4月発行)
特集 胃手術後の困難症
21巻3号(1966年3月発行)
21巻2号(1966年2月発行)
特集 癌の補助療法・2
21巻1号(1966年1月発行)
特集 癌の補助療法・1
20巻12号(1965年12月発行)
20巻11号(1965年11月発行)
特集 熱傷の治療
20巻10号(1965年10月発行)
20巻9号(1965年9月発行)
特集 腹部外科の臨床
20巻8号(1965年8月発行)
特集 癌手術例の検討
20巻7号(1965年7月発行)
特集 術後感染症
20巻6号(1965年6月発行)
特集 腹部疾患縫合不全
20巻5号(1965年5月発行)
特集 胸部疾患縫合不全
20巻4号(1965年4月発行)
20巻3号(1965年3月発行)
20巻2号(1965年2月発行)
特集 外科と内分泌・2
20巻1号(1965年1月発行)
特集 外科と内分泌・1
19巻12号(1964年12月発行)
特集 外科と保険診療
19巻11号(1964年11月発行)
19巻10号(1964年10月発行)
19巻9号(1964年9月発行)
特集 脳・頸部・胸部の症例
19巻8号(1964年8月発行)
特集 小児外科
19巻7号(1964年7月発行)
19巻6号(1964年6月発行)
特集 外傷の救急処置
19巻5号(1964年5月発行)
特集 癌の治療成績の向上
19巻4号(1964年4月発行)
19巻3号(1964年3月発行)
19巻2号(1964年2月発行)
19巻1号(1964年1月発行)
18巻12号(1963年12月発行)
18巻11号(1963年11月発行)
18巻10号(1963年10月発行)
特集 整形外科症例集
18巻9号(1963年9月発行)
18巻8号(1963年8月発行)
18巻7号(1963年7月発行)
18巻6号(1963年6月発行)
18巻5号(1963年5月発行)
18巻4号(1963年4月発行)
18巻3号(1963年3月発行)
18巻2号(1963年2月発行)
18巻1号(1963年1月発行)
17巻12号(1962年12月発行)
17巻11号(1962年11月発行)
17巻10号(1962年10月発行)
特集 麻酔
17巻9号(1962年9月発行)
17巻8号(1962年8月発行)
特集 手こずつた症例―私の経験した診断治療上の困難症(Ⅱ)
17巻7号(1962年7月発行)
17巻6号(1962年6月発行)
特集 手こずつた症例―私の経験した診断治療上の困難症(Ⅰ)
17巻5号(1962年5月発行)
17巻4号(1962年4月発行)
17巻3号(1962年3月発行)
17巻2号(1962年2月発行)
17巻1号(1962年1月発行)
16巻12号(1961年12月発行)
16巻11号(1961年11月発行)
16巻10号(1961年10月発行)
16巻9号(1961年9月発行)
16巻8号(1961年8月発行)
16巻7号(1961年7月発行)
16巻6号(1961年6月発行)
16巻5号(1961年5月発行)
16巻4号(1961年4月発行)
16巻3号(1961年3月発行)
16巻2号(1961年2月発行)
16巻1号(1961年1月発行)
15巻12号(1960年12月発行)
15巻11号(1960年11月発行)
15巻10号(1960年10月発行)
15巻9号(1960年9月発行)
15巻8号(1960年8月発行)
15巻7号(1960年7月発行)
15巻6号(1960年6月発行)
15巻5号(1960年5月発行)
15巻4号(1960年4月発行)
15巻3号(1960年3月発行)
15巻2号(1960年2月発行)
15巻1号(1960年1月発行)
14巻12号(1959年12月発行)
14巻11号(1959年11月発行)
14巻10号(1959年10月発行)
14巻9号(1959年9月発行)
14巻8号(1959年8月発行)
14巻7号(1959年7月発行)
14巻6号(1959年6月発行)
14巻5号(1959年5月発行)
14巻4号(1959年4月発行)
14巻3号(1959年3月発行)
特集 腹部外科
14巻2号(1959年2月発行)
14巻1号(1959年1月発行)
13巻12号(1958年12月発行)
13巻11号(1958年11月発行)
13巻10号(1958年10月発行)
13巻9号(1958年9月発行)
13巻8号(1958年8月発行)
13巻7号(1958年7月発行)
特集 外科的・内科的療法の限界・2
13巻6号(1958年6月発行)
13巻5号(1958年5月発行)
特集 外科的・内科的療法の限界
13巻4号(1958年4月発行)
13巻3号(1958年3月発行)
13巻2号(1958年2月発行)
特集 腫瘍
13巻1号(1958年1月発行)
12巻12号(1957年12月発行)
12巻11号(1957年11月発行)
特集 乳腺腫瘍
12巻10号(1957年10月発行)
12巻9号(1957年9月発行)
12巻8号(1957年8月発行)
12巻7号(1957年7月発行)
12巻6号(1957年6月発行)
12巻5号(1957年5月発行)
12巻4号(1957年4月発行)
特集 腫瘍
12巻3号(1957年3月発行)
12巻2号(1957年2月発行)
12巻1号(1957年1月発行)
11巻13号(1956年12月発行)
特集 吐血と下血
11巻12号(1956年12月発行)
11巻11号(1956年11月発行)
11巻10号(1956年10月発行)
11巻9号(1956年9月発行)
11巻8号(1956年8月発行)
11巻7号(1956年7月発行)
11巻6号(1956年6月発行)
11巻5号(1956年5月発行)
11巻4号(1956年4月発行)
11巻3号(1956年3月発行)
11巻2号(1956年2月発行)
11巻1号(1956年1月発行)
10巻13号(1955年12月発行)
10巻11号(1955年11月発行)
特集 偶發症との救急處置
10巻12号(1955年11月発行)
10巻10号(1955年10月発行)
10巻9号(1955年9月発行)
10巻8号(1955年8月発行)
10巻7号(1955年7月発行)
10巻6号(1955年6月発行)
10巻5号(1955年5月発行)
10巻4号(1955年4月発行)
10巻3号(1955年3月発行)
10巻2号(1955年2月発行)
10巻1号(1955年1月発行)
9巻12号(1954年12月発行)
9巻11号(1954年11月発行)
特集 整形外科特集号
9巻10号(1954年10月発行)
9巻9号(1954年9月発行)
特集 慢性胃炎と胃潰瘍
9巻8号(1954年8月発行)
9巻7号(1954年7月発行)
9巻6号(1954年6月発行)
9巻5号(1954年5月発行)
9巻4号(1954年4月発行)
9巻3号(1954年3月発行)
9巻2号(1954年2月発行)
9巻1号(1954年1月発行)
8巻13号(1953年12月発行)
特集 頸部外科臨床の進歩
8巻12号(1953年12月発行)
8巻11号(1953年11月発行)
8巻10号(1953年10月発行)
8巻9号(1953年9月発行)
特集 最新の麻醉
8巻8号(1953年8月発行)
特集 輸血・輸液の諸問題
8巻7号(1953年7月発行)
8巻6号(1953年6月発行)
8巻5号(1953年5月発行)
8巻4号(1953年4月発行)
8巻3号(1953年3月発行)
8巻2号(1953年2月発行)
8巻1号(1953年1月発行)
7巻13号(1952年12月発行)
7巻12号(1952年11月発行)
7巻11号(1952年11月発行)
特集 上腹部外科臨床の進歩
7巻10号(1952年10月発行)
7巻9号(1952年9月発行)
7巻8号(1952年8月発行)
7巻7号(1952年7月発行)
7巻6号(1952年6月発行)
7巻5号(1952年5月発行)
7巻4号(1952年4月発行)
7巻3号(1952年3月発行)
7巻2号(1952年2月発行)
7巻1号(1952年1月発行)
6巻12号(1951年12月発行)
6巻11号(1951年11月発行)
6巻10号(1951年10月発行)
6巻9号(1951年9月発行)
6巻8号(1951年8月発行)
6巻7号(1951年7月発行)
6巻6号(1951年6月発行)
6巻5号(1951年5月発行)
6巻4号(1951年4月発行)
6巻3号(1951年3月発行)
6巻2号(1951年2月発行)
6巻1号(1951年1月発行)
5巻12号(1950年12月発行)
5巻11号(1950年11月発行)
5巻10号(1950年10月発行)
5巻9号(1950年9月発行)
特集 蛋白・3
5巻8号(1950年8月発行)
特集 蛋白・2
5巻7号(1950年7月発行)
特集 蛋白問題・1
5巻6号(1950年6月発行)
5巻5号(1950年5月発行)
特集 Cancer・2
5巻4号(1950年4月発行)
特集 Cancer・1
5巻3号(1950年3月発行)
5巻2号(1950年2月発行)
5巻1号(1950年1月発行)
4巻12号(1949年12月発行)
4巻11号(1949年11月発行)
4巻10号(1949年10月発行)
4巻9号(1949年9月発行)
4巻8号(1949年8月発行)
4巻7号(1949年7月発行)
4巻6号(1949年6月発行)
4巻5号(1949年5月発行)
4巻4号(1949年4月発行)
4巻3号(1949年3月発行)
4巻2号(1949年2月発行)
4巻1号(1949年1月発行)
