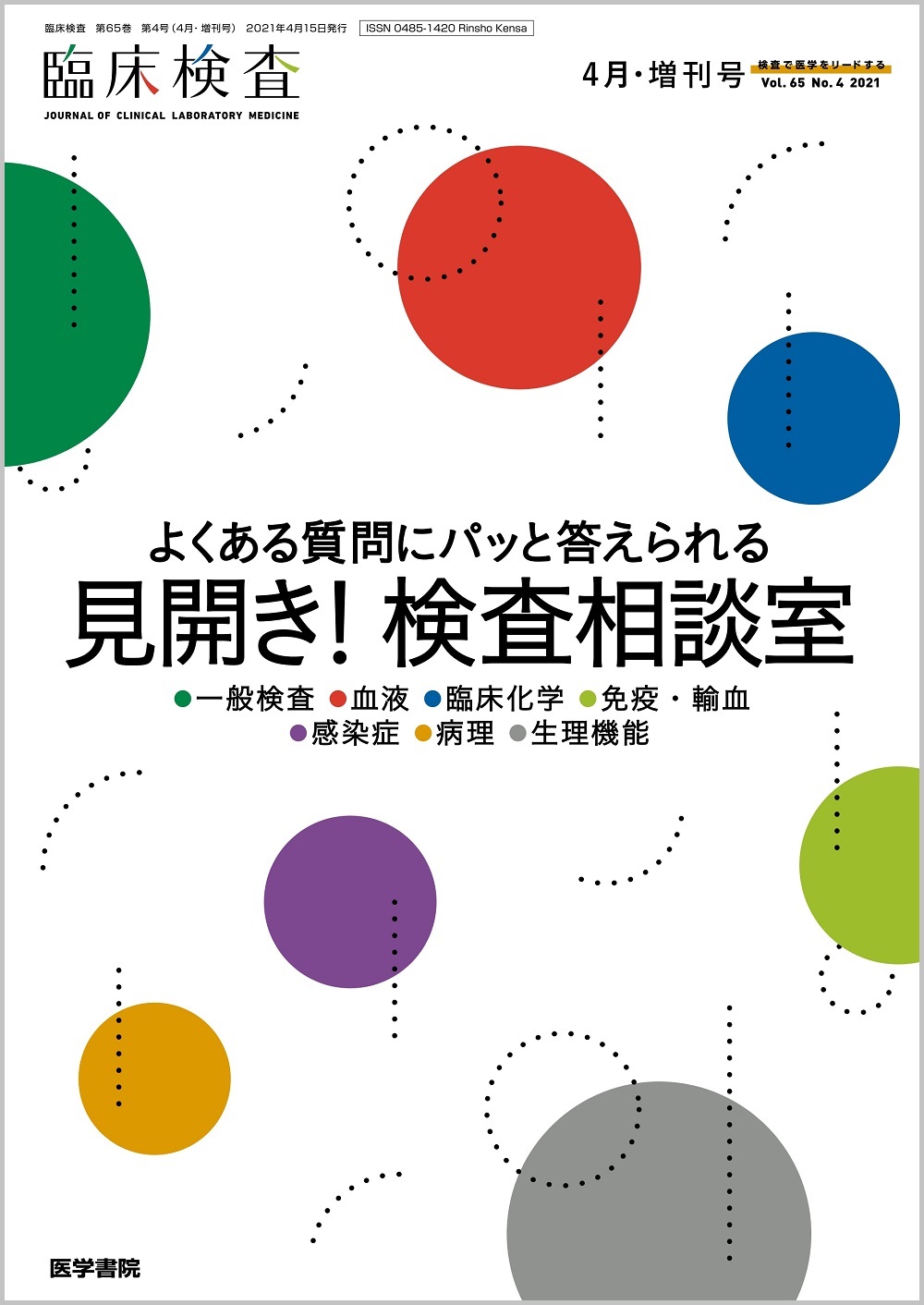文献詳細
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
感染症
SARS-CoV-2のPCR検査の感度はどの程度ありますか?
著者: 山元佳1
所属機関: 1国立国際医療研究センター 国際感染症センター
ページ範囲:P.432 - P.433
文献概要
検出感度(検出限界)の意としては各SARS-CoV-2 RT-qPCR(以下,SARS-CoV-2 PCR)キット間の差は明らかではないが,LAMPなどの核酸検出検査や抗原検査と比べてPCRはより少ない核酸量を検出可能である.検査感度は“真の陽性”と判断された症例を“真の陽性,偽の陰性”で除したものである.ただし,COVID-19の真の陽性を規定する検査は,ほかならぬPCR検査をはじめとした核酸検出検査である.流行の当初,感度70%はSARS-CoV-2 PCR検査を反復して陽性であったものを診断のゴールドスタンダードとして,初回PCR検査の診断についての感度を算出したものであった.開発の黎明期であった点や検体が咽頭拭い液であったという問題もあり,その後のメタ解析で感度は90%前後と報告されている1).
それでも十分な感度ではないと考えて,PCR反復を行う医療機関は多かったが,その意義は乏しい.非常に疑わしい肺炎像を有し,臨床上低酸素などの問題を伴っている場合や濃厚な接触歴があるうえで発熱などの鑑別を行う場合には一定の診断的な意義は存在するが,それ以外の場面ではほぼ意義がない.本感染症の診断意義の1つに感染拡大防止があるが,感染拡大をきたす可能性のある病早期(発症前から発症7〜10日以内)2)においてPCRが偽陰性となる症例は非常に少ない可能性が高いことがウイルス検出の推移から推測できる3).
参考文献
掲載誌情報