コロナ禍が長引くうちに再発見や再認識したことの1つに,強迫はやはり一筋縄ではいかないということがある。診断は一律ではないものの,子ども時代に始まる強迫に悩む人たちの診療を担当していると,コロナ禍で不安が高まって強迫的になった人にも出会う。その中には,自分の排泄物や身体の一部に触れることを極度に嫌うと同時に,ドアノブをはじめとする周囲のものを平気で触っている思春期の男児が何人かいて,汚染に関する強迫という形をとっていても必ずしも均質ではないと感じられる。それどころか,強迫を軽減するために通院してきている一方で,手洗いや消毒が推奨される状況になり,以前から行ってきた汚染を避ける行動がようやく認められるようになったと自ら満足げに話す人が何人もいて,強迫の位置付けを考えさせられることがある。
DSM-5では,強迫で特徴付けられる一群の疾患が不安症群とは別に,強迫症(obsessive-compulsive disorder:OCD)および関連症群とまとめられた。DSM-5を作成する過程では,自閉スペクトラム症をはじめとする神経発達症,衝動制御障害や嗜癖性障害までを視野に入れて強迫スペクトラム障害が提案されていたが,最終的にはOCDを軸にかなり絞り込まれたものである。とはいえ,DSM-5のOCDでは自我違和性や不合理性の認識が必ずしも必要ではなくなっており,かつての強迫神経症より広い範囲を取り込んでいる。
雑誌目次
精神医学63巻6号
2021年06月発行
雑誌目次
特集 強迫についてあらためて考える
特集にあたって フリーアクセス
著者: 金生由紀子
ページ範囲:P.889 - P.889
神経発達症における強迫
著者: 岡田俊
ページ範囲:P.891 - P.896
抄録 強迫症状は,複数のディメンジョンに分かれ,多様性を有することが知られているだけではなく,不安から衝動性に至るスペクトラムを形成し,強迫に関連する障害群の中には,自閉スペクトラム症やトゥレット症も位置付けられる。自閉スペクトラム症においては,衝動性の強い強迫性や常同性がみられるが,不安の存在は強迫症状を増悪させる。トゥレット症における強迫は,just rightと表現される衝動性の色彩の強い強迫性が特徴的であるが,思春期に不安症を伴う例も少なくない。神経発達症の強迫の多くは,ドパミン系の病理を反映するが,不安も関与するなど,その病理は多層的である。神経発達症における強迫の理解は,まだ十分とはいえず,神経発達症の病態と強迫症状の詳細との関連を仔細に検討することで,その解明が期待される。
不安の病気としての強迫症—強迫神経症から強迫スペクトラムに至る過程を含めて
著者: 松永寿人 , 向井馨一郎 , 山西恭輔
ページ範囲:P.897 - P.904
抄録 強迫症(OCD)は,それが独立した疾患とされて以降,DSM-Ⅲに至るまで,Freudが確立した神経症概念に則った“強迫神経症”として不安や葛藤などの心理的機制が重視されてきた。1980年のDSM-Ⅲ改訂では,OCDへと変遷し,病的不安を中核病理として共有する不安障害の一型となされた。このように長きにわたり,OCDは“不安の病気”とみなされ分類されてきたが,2013年に改訂されたDSM-5では,OCDは不安症群から分離され,「とらわれ」や「繰り返し行為」を共有する強迫症および関連症群という新たなカテゴリーの中核に位置付けられた。
このような約一世紀間のOCDの診断的位置付けを巡るパラダイムシフトは,各時代における発症機序や精神病理,神経生物学的病態理解の時間的変遷を反映するとともに,OCDの拡がり,そして多様性を示唆するものと考えた。
摂食障害における強迫
著者: 濱谷沙世 , 松本一記
ページ範囲:P.905 - P.912
抄録 摂食障害の臨床においては,患者の強迫的な振る舞いがしばしば観察される。これまでに行われてきた研究により,摂食障害の強迫を説明し得る興味深い知見が数多く発見されており,摂食障害と強迫症の関係については,古くから関心深い議論が繰り広げられてきた。強迫的な行為には,認知柔軟性と中枢性統合の障害に起因する可能性があり,この認知機能障害は摂食障害と強迫症のいずれの疾患においても認められる。治療については,強迫症に対しても有効性が確立されている認知行動療法は神経性過食症と過食性障害にはきわめて高い治療成績を誇るが,神経性やせ症に関しては効果が限られている。本稿では,最新の知見に触れつつ,両疾患の共通点と相違点について,診断学,神経心理学,そして治療の側面から包括的に考察したい。
統合失調症と強迫との関連—その歴史と論点の整理
著者: 広沢正孝
ページ範囲:P.913 - P.922
抄録 統合失調症患者において強迫症状がみられることは少なくない。そのためか,100年以上にわたる精神医学の歴史の中で,統合失調症と強迫をめぐる議論が展開されてきた。しかし近代自己の確立とその維持に重点を置いた19〜20世紀の精神医学と生物学的エビデンスに重点を置いた現代のそれとにおいては,強迫概念自体が変化してきている。統合失調症と強迫の関係も,そのような時代の流れを前提として議論する必要があろう。DSM-5においては,強迫症の診断に病識が問われなくなった。このことが統合失調症と強迫症の関連,統合失調症における強迫の持つ意味の解釈にいかなる影響を与え得るか,本論では縦断的な視点で再考した。その結果,特に統合失調症における強迫の持つ意味に関しては,元より強迫症状の中でも「くりかえし」,「とらわれ」といった現象を対象とした議論にほぼ限られており,そこで得られた知見はDSM-5の時代においても有用であると思われた。
強迫症の薬物療法
著者: 住谷さつき
ページ範囲:P.923 - P.931
抄録 強迫症(obsessive-compulsive disorder:OCD)の薬物治療の基本は選択的セロトニン再取り込み阻害薬(selective serotonin reuptake inhibitor:SSRI)を十分量,十分期間使用することであるが,SSRIで治療可能な症例は40〜60%とされている。はじめに使用したSSRIに効果が認められなかったり副作用で服用が難しかったりするときは他のSSRIに変更するか,非定型抗精神病薬の付加による増強療法を行うのが一般的である。抗精神病薬の付加に反応があるのは45〜70%とされているが,仮に半分の患者にSSRIが効果を示し残りの半分の半分が抗精神病薬の付加に反応しても,4分の1の患者は薬物治療抵抗性ということになる。近年,薬物治療抵抗性の患者に対しては別の機序の薬物による増強療法の効果も検証されており,特にグルタミン酸系の薬物に注目が集まっている。
強迫症の認知行動療法
著者: 中嶋愛一郎 , 蟹江絢子
ページ範囲:P.933 - P.942
抄録 英国のNICEガイドラインをはじめとして,強迫症のさまざまな治療ガイドラインでは,薬物療法以外にエビデンスの高い治療として認知行動療法が勧められている。強迫症の認知行動療法として最も有効性が示されている方法は曝露反応妨害法(exposure and response prevention:ERP)である。ERPは,強迫観念が生じる引き金への曝露をした上で(exposure),強迫行為や回避行動を抑制し(response prevention),強迫観念から生じる不快な感情への耐性をつけていく方法である。標準的なERPは馴化モデルを理論的背景とした方法だが,近年,制止学習理論を用いた方法がERPに応用されている。また,困難例やERPの実施に抵抗がある患者には,認知療法を組み合わせることもある。本稿では,ERPの理論的な背景とその実施方法,制止学習理論に基づいたERPと認知療法,新型コロナウイルス感染症のパンデミックが認知行動療法の実施に与える影響について概説する。
強迫症に対する森田療法
著者: 舘野歩
ページ範囲:P.943 - P.951
抄録 強迫症に対する森田療法の治療方針を整理した。身体へとらわれている群で不安軽減を目的としているタイプの強迫症は外来森田療法を主としSSRIはあくまで補助的に使用する。また衝動行為を伴う強迫症に対しては衝動行為に対する具体的な対処と強迫症状を自我違和化するアプローチを行う。常同行為に近い強迫症に対しては早期からSSRIだけでなく抗精神病薬を使用し,薬物療法を主軸として補助的に森田療法的なアプローチを行う。
従来森田療法は身体へとらわれている群で不安軽減を目的としているタイプの強迫症に対して行われた一方,それ以外のタイプは森田療法の適応外として扱われてきたきらいがある。今回筆者が提唱したように目の前の強迫症のタイプに応じて森田療法のエッセンスを柔軟に使う姿勢が大切である。
強迫症へのニューロモデュレーション—DBS,rTMS,ECT
著者: 渡辺杏里 , 中前貴
ページ範囲:P.953 - P.959
抄録 強迫症(OCD)は,ガイドラインでは曝露反応妨害法などの認知行動療法,選択的セロトニン取り込み阻害薬や第二世代抗精神病薬などによる薬物療法が推奨されている。しかし,これらの治療を十分に行っても治療反応に乏しい治療抵抗性OCDの場合,ニューロモデュレーションも治療選択肢となる。OCDに対する有効性が報告されているニューロモデュレーションには,脳深部刺激療法(DBS),反復経頭蓋磁気刺激療法(rTMS),電気けいれん療法(ECT)などがある。これらは,それぞれ立ち位置が異なっている。本稿ではこの違いも踏まえながら,OCDへのニューロモデュレーションに関する知見と課題について論じる。
強迫症のニューロイメージング
著者: 酒井雄希
ページ範囲:P.961 - P.967
抄録 強迫症は強迫症および関連症群の一つであるが,その生物学的背景に関するエビデンスは,他の強迫で特徴付けられる疾患と比較して最もよく蓄積されている。強迫症は,繰り返される不安と,それを軽減するための繰り返し行動で特徴付けられる精神神経疾患である。生涯有病率約2%とよくみられる疾患で,人生の比較的早期に発症することが多いこともあり,生活に多大な影響を与える。前頭葉-線条体回路の変化がその病態の中心と考えられており,ニューロイメージング研究でも前頭葉-線条体回路における変化が報告されてきた。しかし近年,特に安静状態の機能的MRIを用いたネットワークレベルでの研究が盛んに行われるようになり,当初仮説立てられていたより広範囲の脳ネットワーク変化が報告されるようになってきている。本稿では強迫症のニューロイメージングの中でも,特に安静状態機能的MRIを用いて脳ネットワークを評価した研究に関して概説する。
強迫とこころの発達
著者: 金生由紀子
ページ範囲:P.969 - P.975
抄録 強迫とこころの発達について,一般の子ども・若者における知見を中心に先行研究を検討した。反復的,儀式的行動は,強迫様行動とも言うことができ,2〜4歳の一般の幼児の大多数に認められ,その時期における定型発達の一部と思われる。5〜6歳になると実行機能の発達が進み,自己制御が高まるとともに不安が軽減されて強迫様行動が減少すると思われる。一方,強迫症状は,一般の子ども・若者で,10歳からいったん減少した後に20歳に近づくと増加に転じる可能性が高く,強迫症(OCD)の発症年齢が10歳前後と20歳前後という2つのピークを有することに対応すると思われる。強迫性と神経ネットワーク結合との関連が示唆されており,発達の経過中で相互に影響する可能性があるが,さらなる検討を要すると思われる。強迫様行動と強迫症状の関連が示されているが,それについても検討を進めることが望まれる。
研究と報告
医療観察法における鑑定入院の質の評価—鑑定入院アウトカム指標の確立を目指して
著者: 椎名明大 , 佐藤愛子 , 新津富央 , 五十嵐禎人 , 伊豫雅臣
ページ範囲:P.977 - P.993
抄録 医療観察法の鑑定入院制度については,鑑定入院の目標設定が曖昧でアウトカムを事後的に評価する仕組みがない,という問題が指摘されていた。我々は先行研究において,鑑定入院のアウトカムを評価するための指標として139項目を抽出した。本研究ではこれらの項目を試用し,鑑定入院対象者およびその関係者から意見を聴取することを通じて,鑑定入院アウトカム指標の確立を試みた。計20例の対象者にかかわる延べ160人から回答を得た。対象者本人の納得や多職種チームの協働などに関する34項目が,可用性が高く,かつ現時点での達成率が十分でないことが示された。これらの項目が,鑑定入院のアウトカム評価のため有用である可能性が示唆された。
短報
治療経過中に双極性障害の合併が明らかになり少量の炭酸リチウムが転換症状に奏功した青年男性症例
著者: 沖田恭治 , 佐竹直子 , 野田隆政
ページ範囲:P.995 - P.999
抄録 Lithium carbonateが転換症状に効果を示した,19歳の転換性障害と双極性障害を併発した症例を報告する。児童期から繰り返し転換症状を認めていたが,高校3年の受験期より利き手である右上肢の運動麻痺が持続するようになった。器質的な精査をされたが異常は認めず,当院を受診した。経過中に抑うつ気分が顕在化し,escitaropramを投与したところ,一過性の躁的なエピソードを認めた。その後,高揚気分が出現した際にlithium carbonateを開始したところ,運動麻痺症状も速やかに改善した。転換性障害患者の約3割が双極性障害を合併しているという報告もあり,今後気分変動との関連にも注目した調査や研究の必要性を示唆する症例と考えられる。
紹介
包括システムからR-PASへ—ロールシャッハ・テストの新体系の普及に向けて
著者: 井上直美 , 水野雅文
ページ範囲:P.1001 - P.1012
はじめに
ロールシャッハ・テストは,スイスの精神科医であったHermann Rorschachが1921年にモノグラフ『精神診断学』(“Psychodiagnostik”)1)の刊行とともに発表した10枚の図版刺激から成る心理検査であり,精神科臨床において広く用いられてきた。誕生から100年経った今でも,図版は当時と同じものが使用され続けているが,テストの実施解釈法(“システム”と呼ばれる)に関しては多くの流派が生まれてきた。1974年に5つの体系を統合し,2003年まで改訂が続けられた包括システム(Comprehensive System:CS)2,3)は,異なる実施法の結果を比較可能にした初の統一化されたシステムであり,国際的にも最も使用頻度の高い実施解釈法であった4)。
しかしながら,CSには多くの不備があったため,2011年に米国の研究者Meyerらにより大幅な改良を加えられて作成されたのがRorschach Performance Assessment System(R-PAS)5)である。R-PASは,その後米国以外の国々にも広がり,いまや臨床や研究において用いられるシステムとしてはCSをしのいで主流になりつつある。
本論では,日本ではまだよく知られていない最新のロールシャッハ・システムであるR-PASについて具体的な検査結果の例を示して概説し,特に精神科臨床においてCSの代わりにR-PASを用いることの利点,および導入にあたっての課題を述べる。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P. - P.
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1014 - P.1014
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1015 - P.1015
読者アンケート
ページ範囲:P.1016 - P.1016
奥付 フリーアクセス
ページ範囲:P.1020 - P.1020
基本情報
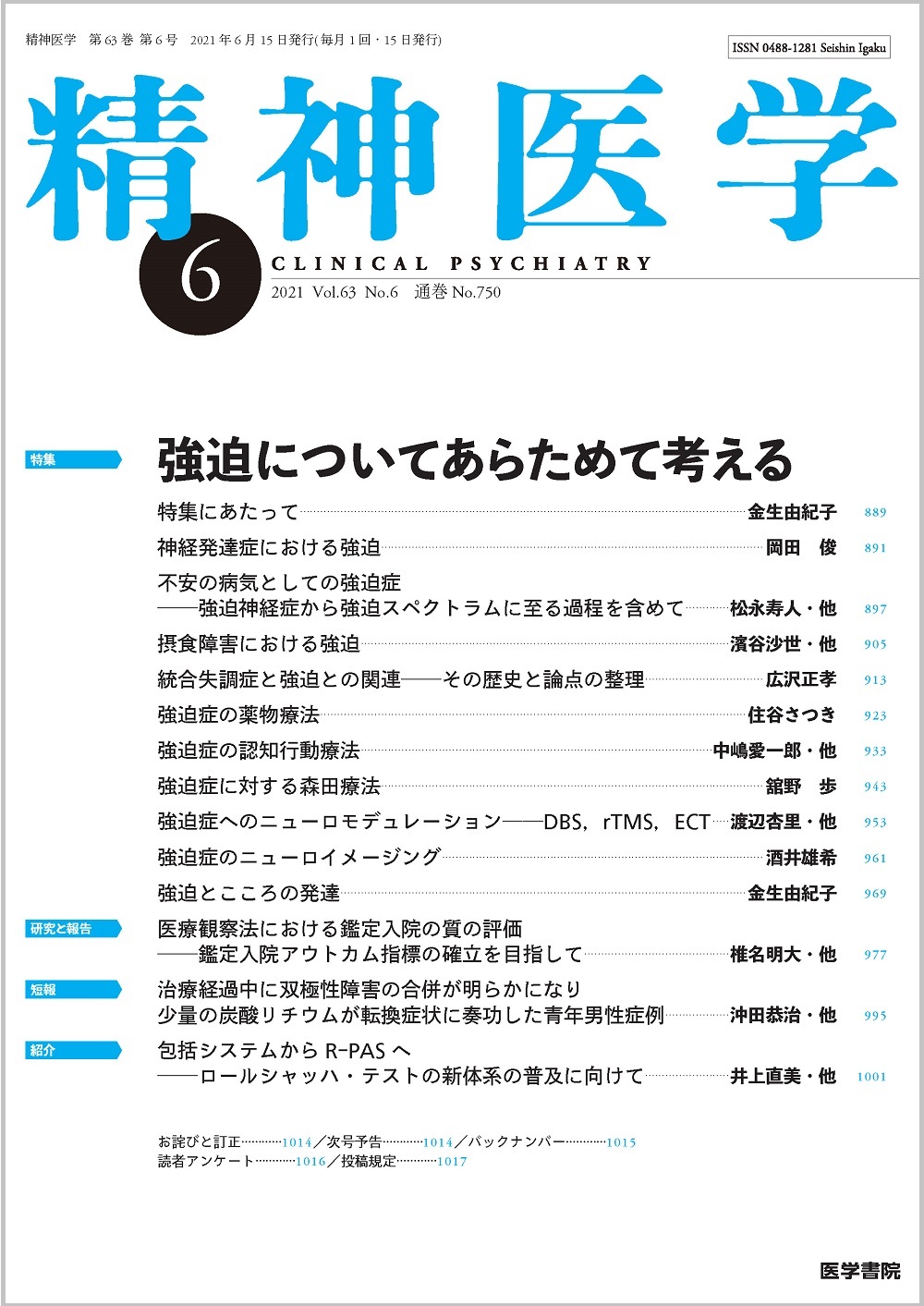
バックナンバー
66巻12号(2024年12月発行)
特集 「治療を終える」に向き合う
66巻11号(2024年11月発行)
特集 「難治例」の臨床—治療に難渋する時の診断,治療,そして予防
66巻10号(2024年10月発行)
特集 不登校の理解と支援
66巻9号(2024年9月発行)
特集 —身体疾患の患者・家族のこころを支える—コンサルテーション・リエゾン精神医学
66巻8号(2024年8月発行)
特集 現代における解離—診断概念の変遷を踏まえ臨床的な理解を深める
66巻7号(2024年7月発行)
特集 アディクション—コロナ禍で変わったこと,変わらないこと
66巻6号(2024年6月発行)
特集 精神疾患の気づきと病識
66巻5号(2024年5月発行)
増大号特集 精神科診療における臨床評価尺度・検査を極める—エキスパートによる実践的活用法
66巻4号(2024年4月発行)
特集 精神疾患・精神症状にはどこまで脳器質的背景があるのか—現代の視点から見直す
66巻3号(2024年3月発行)
特集 精神疾患への栄養学的アプローチ
66巻2号(2024年2月発行)
特集 うつ病のバイオマーカー開発の試み
66巻1号(2024年1月発行)
特集 性差と精神医学—なぜ頻度や重症度に差があるのか
65巻12号(2023年12月発行)
特集 精神科領域の専門資格—どうやって取得し,どのように臨床へ活かすか
65巻11号(2023年11月発行)
特集 精神疾患回復の時間経過を見通す
65巻10号(2023年10月発行)
特集 DSM-5からDSM-5-TRへ—何が変わったのか
65巻9号(2023年9月発行)
特集 拡がり続ける摂食障害(摂食症)—一般化とともに拡散・難治化する精神病理にどう対処するか
65巻8号(2023年8月発行)
特集 複雑性PTSDの臨床
65巻7号(2023年7月発行)
特集 子どものうつ病に気づく
65巻6号(2023年6月発行)
特集 精神科医療の必須検査—精神科医が知っておきたい臨床検査の最前線
65巻5号(2023年5月発行)
増大号特集 いま,知っておきたい発達障害 Q&A 98
65巻4号(2023年4月発行)
特集 わが国の若手による統合失調症研究最前線
65巻3号(2023年3月発行)
特集 災害精神医学—自然災害,人為災害,感染症パンデミックとこころのケア
65巻2号(2023年2月発行)
特集 精神医療・精神医学の組織文化のパラダイムシフト
65巻1号(2023年1月発行)
特集 精神医学における臨床研究のすゝめ—わが国で行われたさまざまな精神医学臨床研究を参考にして
64巻12号(2022年12月発行)
特集 死別にまつわる心理的苦痛—背景理論からケアおよびマネジメントまで
64巻11号(2022年11月発行)
特集 ひきこもりの理解と支援
64巻10号(2022年10月発行)
特集 精神・神経疾患に併存する過眠の背景病態と治療マネジメント
64巻9号(2022年9月発行)
特集 学校で精神疾患を「自分のこと」として教育する
64巻8号(2022年8月発行)
特集 ジェンダーをめぐる諸課題を理解する
64巻7号(2022年7月発行)
特集 Withコロナ時代の精神医学教育の進歩—卒前教育から生涯教育まで
64巻6号(2022年6月発行)
特集 認知症診療の新潮流—近未来の認知症診療に向けて
64巻5号(2022年5月発行)
増大号特集 精神科診療のピットフォール
64巻4号(2022年4月発行)
特集 家族支援を考える
64巻3号(2022年3月発行)
特集 精神神経疾患の治療とQOL
64巻2号(2022年2月発行)
特集 精神科におけるオンライン診療
64巻1号(2022年1月発行)
特集 超高齢期の精神疾患
63巻12号(2021年12月発行)
特集 うつ病のニューロモデュレーション治療の新展開
63巻11号(2021年11月発行)
特集 「実感と納得」に向けた病気と治療の伝え方
63巻10号(2021年10月発行)
特集 統合失調症の心理社会的治療—どのように使い分け,効果を最大化するか
63巻9号(2021年9月発行)
特集 産業精神保健の現状と課題
63巻8号(2021年8月発行)
特集 認知症診療における精神科医の役割を再考する
63巻7号(2021年7月発行)
特集 自殺の現状と予防対策—COVID-19の影響も含めて
63巻6号(2021年6月発行)
特集 強迫についてあらためて考える
63巻5号(2021年5月発行)
増大号特集 精神科クリニカル・パール—先達に学ぶ
63巻4号(2021年4月発行)
特集 精神医療に関する疫学のトピック—記述疫学,リスク研究からコホート研究まで
63巻3号(2021年3月発行)
特集 サイコーシスとは何か—概念,病態生理,診断・治療における意義
63巻2号(2021年2月発行)
特集 いじめと精神医学
63巻1号(2021年1月発行)
特集 新型コロナウイルス感染症ただなかの精神医療
62巻12号(2020年12月発行)
特集 身体症状症の病態と治療—器質因がはっきりしない身体症状をどう扱うか?
62巻11号(2020年11月発行)
特集 若年性認知症の疫学・臨床・社会支援
62巻10号(2020年10月発行)
特集 精神科臨床における共同意思決定(SDM)
62巻9号(2020年9月発行)
特集 周産期メンタルヘルスの今
62巻8号(2020年8月発行)
特集 精神科医療における病名告知—伝えるか,伝えるべきでないか?伝えるなら,いつ,どのように伝えるか?
62巻7号(2020年7月発行)
特集 「大人の発達障害」をめぐる最近の動向
62巻6号(2020年6月発行)
特集 精神科診断分類の背景にある考え方
62巻5号(2020年5月発行)
増大号特集 精神科診療のエビデンス—国内外の重要ガイドライン解説
62巻4号(2020年4月発行)
特集 ベンゾジアゼピン受容体作動薬の問題点と適正使用
62巻3号(2020年3月発行)
特集 精神医学・医療の未来を拓く人材育成
62巻2号(2020年2月発行)
特集 発達障害と認知症をめぐって
62巻1号(2020年1月発行)
特集 SUN☺D臨床試験のインパクト—日本初の医師主導型抗うつ薬大規模臨床試験から学ぶ
61巻12号(2019年12月発行)
特集 精神疾患における病識・疾病認識—治療における意義
61巻11号(2019年11月発行)
特集 医療現場での怒り—どのように評価しどのように対応するべきか
61巻10号(2019年10月発行)
特集 トラウマインフォームドケアと小児期逆境体験
61巻9号(2019年9月発行)
特集 高齢者の精神科救急・急性期医療
61巻8号(2019年8月発行)
特集 光と精神医学
61巻7号(2019年7月発行)
特集 今再び問う,内因性精神疾患と心因性精神疾患の概念
61巻6号(2019年6月発行)
特集 マインドフルネス療法は他の精神療法と何が違うのか?
61巻5号(2019年5月発行)
特集 精神医学における主観と主体
61巻4号(2019年4月発行)
特集 統合失調症の治療ゴールをめぐって
61巻3号(2019年3月発行)
特集 ICD-11のチェックポイント
61巻2号(2019年2月発行)
オピニオン パーソナリティ障害の現在
61巻1号(2019年1月発行)
特集 高齢者のメンタルヘルス
60巻12号(2018年12月発行)
特集 精神科臨床から何を学び,何を継承し,精神医学を改革・改良できたか(Ⅱ)
60巻11号(2018年11月発行)
特集 精神科臨床から何を学び,何を継承し,精神医学を改革・改良できたか(Ⅰ)
60巻10号(2018年10月発行)
特集 こころの発達の問題に関する“古典”をふりかえる
60巻9号(2018年9月発行)
特集 不眠症の治療と睡眠薬
60巻8号(2018年8月発行)
特集 作業療法を活用するには
60巻7号(2018年7月発行)
特集 双極Ⅱ型をめぐる諸問題
60巻6号(2018年6月発行)
特集 医療・医学の課題としての身体合併症
60巻5号(2018年5月発行)
特集 サイコオンコロジー
60巻4号(2018年4月発行)
特集 精神科診療におけるてんかん
60巻3号(2018年3月発行)
特集 せん妄をめぐる最近の動向
60巻2号(2018年2月発行)
特集 多様なアディクションとその対応
60巻1号(2018年1月発行)
特集 Research Domain Criteria(RDoC)プロジェクトの目指す新たな精神医学診断・評価システム
59巻12号(2017年12月発行)
特集 「統合失調症」再考(Ⅱ)
59巻11号(2017年11月発行)
特集 「統合失調症」再考(Ⅰ)
59巻10号(2017年10月発行)
59巻9号(2017年9月発行)
特集 精神疾患の生物学的診断指標—現状と開発研究の展望
59巻8号(2017年8月発行)
特集 国連障害者権利条約と権利ベースのアプローチ
59巻7号(2017年7月発行)
特集 MRIのT2・FLAIR画像での白質高信号の意味を読み解く
59巻6号(2017年6月発行)
特集 精神医学と睡眠学の接点
59巻5号(2017年5月発行)
特集 認知行動療法の現在とこれから—医療現場への普及と質の確保に向けて
59巻4号(2017年4月発行)
特集 改正道路交通法と医療の視点
59巻3号(2017年3月発行)
特集 ADHDをめぐる最近の動向
59巻2号(2017年2月発行)
オピニオン 精神科医にとっての薬物療法の意味
59巻1号(2017年1月発行)
特集 インターネット依存の現在
58巻12号(2016年12月発行)
58巻11号(2016年11月発行)
特集 認知症の人の認知機能障害,生活障害,行動・心理症状の構造
58巻10号(2016年10月発行)
58巻9号(2016年9月発行)
特集 精神科臨床にみる家庭・家族の現在—何が変わり何が変わらないのか?
58巻8号(2016年8月発行)
58巻7号(2016年7月発行)
特集 精神疾患の予防と早期治療アップデート
58巻6号(2016年6月発行)
58巻5号(2016年5月発行)
特集 成人の自閉スペクトラム症とライフステージの課題
58巻4号(2016年4月発行)
58巻3号(2016年3月発行)
58巻2号(2016年2月発行)
特集 妊娠・出産・育児とメンタルヘルスケア
58巻1号(2016年1月発行)
特集 社会認知研究の最近の動向
57巻12号(2015年12月発行)
57巻11号(2015年11月発行)
シンポジウム 家族と当事者からみた精神科医療・精神医学
57巻10号(2015年10月発行)
特集 精神医学と神経学の境界領域—最近のトピックスから
57巻9号(2015年9月発行)
特集 統合失調症の認知機能障害の臨床的意義
57巻8号(2015年8月発行)
オピニオン DSM-5—私はこう思う
57巻7号(2015年7月発行)
特集 自殺対策の現状
57巻6号(2015年6月発行)
57巻5号(2015年5月発行)
57巻4号(2015年4月発行)
特集 リエゾン精神医学の現状と今後の展望(Ⅱ)
57巻3号(2015年3月発行)
特集 リエゾン精神医学の現状と今後の展望(Ⅰ)
57巻2号(2015年2月発行)
57巻1号(2015年1月発行)
特集 今後の産業精神保健の課題—近年の行政施策の動向をふまえて
56巻12号(2014年12月発行)
56巻11号(2014年11月発行)
56巻10号(2014年10月発行)
特集 良質かつ適切な医療の提供—改正精神保健福祉法41条の具体化
56巻9号(2014年9月発行)
特集 うつ病の早期介入,予防(Ⅱ)
56巻8号(2014年8月発行)
特集 うつ病の早期介入,予防(Ⅰ)
56巻7号(2014年7月発行)
56巻6号(2014年6月発行)
56巻5号(2014年5月発行)
特集 大学生とメンタルヘルス―保健管理センターのチャレンジ
56巻4号(2014年4月発行)
56巻3号(2014年3月発行)
56巻2号(2014年2月発行)
56巻1号(2014年1月発行)
55巻12号(2013年12月発行)
55巻11号(2013年11月発行)
特集 アンチスティグマ活動の新しい転機Ⅱ
55巻10号(2013年10月発行)
特集 アンチスティグマ活動の新しい転機Ⅰ
55巻9号(2013年9月発行)
オピニオン 精神科医にとっての精神療法の意味
55巻8号(2013年8月発行)
特集 職場のメンタルヘルスと復職支援─その効果的な利用のために
55巻7号(2013年7月発行)
55巻6号(2013年6月発行)
55巻5号(2013年5月発行)
55巻4号(2013年4月発行)
55巻3号(2013年3月発行)
特集 SST最近の進歩と広がり
55巻2号(2013年2月発行)
55巻1号(2013年1月発行)
54巻12号(2012年12月発行)
54巻11号(2012年11月発行)
特集 アルコール・薬物関連障害
54巻10号(2012年10月発行)
特集 医療法に基づく精神疾患の地域医療計画策定
54巻9号(2012年9月発行)
54巻8号(2012年8月発行)
54巻7号(2012年7月発行)
54巻6号(2012年6月発行)
54巻5号(2012年5月発行)
54巻4号(2012年4月発行)
オピニオン マインドフルネス/アクセプタンス認知行動療法と森田療法
54巻3号(2012年3月発行)
オピニオン 認知症の終末期医療の対応:現状と課題―尊厳をどう守るか
54巻2号(2012年2月発行)
特集 障害者権利条約批准に係る国内法の整備:今後の精神科医療改革への萌芽
54巻1号(2012年1月発行)
53巻12号(2011年12月発行)
シンポジウム 精神医学研究の到達点と展望
53巻11号(2011年11月発行)
特集 震災時の避難大作戦:精神科編
53巻10号(2011年10月発行)
特集 裁判員制度と精神鑑定
53巻9号(2011年9月発行)
53巻8号(2011年8月発行)
特集 性同一性障害(GID)
53巻7号(2011年7月発行)
53巻6号(2011年6月発行)
53巻5号(2011年5月発行)
特集 成人てんかんの国際分類と医療の現状
53巻4号(2011年4月発行)
シンポジウム 気分障害の生物学的研究の最新動向─DSM,ICD改訂に向けて
53巻3号(2011年3月発行)
53巻2号(2011年2月発行)
特集 統合失調症の予後改善に向けての新たな戦略
53巻1号(2011年1月発行)
52巻12号(2010年12月発行)
52巻11号(2010年11月発行)
52巻10号(2010年10月発行)
特集 高次脳機能障害をめぐって
52巻9号(2010年9月発行)
52巻8号(2010年8月発行)
52巻7号(2010年7月発行)
52巻6号(2010年6月発行)
52巻5号(2010年5月発行)
特集 児童期における精神疾患の非定型性―成人期の精神疾患と対比して
52巻4号(2010年4月発行)
特集 内因性精神疾患の死後脳研究
52巻3号(2010年3月発行)
特集 総合病院精神科衰退の危機と総合病院精神医学会の果たすべき役割
52巻2号(2010年2月発行)
52巻1号(2010年1月発行)
51巻12号(2009年12月発行)
51巻11号(2009年11月発行)
特集 現代の自殺をめぐる話題
51巻10号(2009年10月発行)
特集 若年性認知症をめぐる諸問題
51巻9号(2009年9月発行)
51巻8号(2009年8月発行)
51巻7号(2009年7月発行)
特集 精神疾患と睡眠マネージメント―最新の知見
51巻6号(2009年6月発行)
51巻5号(2009年5月発行)
51巻4号(2009年4月発行)
シンポジウム うつ病と自殺に医師はどう対応するのか―医師臨床研修並びに生涯研修における精神科の役割
51巻3号(2009年3月発行)
特集 社会脳をめぐって
51巻2号(2009年2月発行)
シンポジウム 統合失調症の脳科学
51巻1号(2009年1月発行)
50巻12号(2008年12月発行)
特集 Assertive Community Treatment(ACT)は日本の地域精神医療の柱になれるか?
50巻11号(2008年11月発行)
50巻10号(2008年10月発行)
50巻9号(2008年9月発行)
50巻8号(2008年8月発行)
特集 成人期のアスペルガー症候群・Ⅱ
50巻7号(2008年7月発行)
特集 成人期のアスペルガー症候群・Ⅰ
50巻6号(2008年6月発行)
特集 疲労と精神障害―ストレス-疲労-精神障害について
50巻5号(2008年5月発行)
50巻4号(2008年4月発行)
50巻3号(2008年3月発行)
特集 精神疾患に対する早期介入の現状と将来
50巻2号(2008年2月発行)
50巻1号(2008年1月発行)
特集 精神医学的コミュニケーションとは何か―精神科専門医を目指す人のために
49巻12号(2007年12月発行)
49巻11号(2007年11月発行)
シンポジウム ストレスと精神生物学―新しい診断法を目指して
49巻10号(2007年10月発行)
49巻9号(2007年9月発行)
特集 「緩和ケアチーム」―精神科医に期待すること,精神科医ができること
49巻8号(2007年8月発行)
49巻7号(2007年7月発行)
特集 レビー小体型認知症をめぐって
49巻6号(2007年6月発行)
49巻5号(2007年5月発行)
特集 睡眠と精神医学:「睡眠精神医学」の推進
49巻4号(2007年4月発行)
49巻3号(2007年3月発行)
特集 統合失調症と感情障害の補助診断法の最近の進歩
49巻2号(2007年2月発行)
49巻1号(2007年1月発行)
シンポジウム 児童思春期の攻撃性・衝動性の理解と援助-ライフサイクルの視点から考える
48巻12号(2006年12月発行)
シンポジウム 気分障害治療の新たな展開
48巻11号(2006年11月発行)
48巻10号(2006年10月発行)
48巻9号(2006年9月発行)
特集 新医師臨床研修制度に基づく精神科ローテート研修の評価
48巻8号(2006年8月発行)
48巻7号(2006年7月発行)
48巻6号(2006年6月発行)
特集 オグメンテーション療法か,多剤併用療法か
48巻5号(2006年5月発行)
シンポジウム MCIとLNTDをめぐって
48巻4号(2006年4月発行)
48巻3号(2006年3月発行)
特集 災害精神医学の10年―経験から学ぶ
48巻2号(2006年2月発行)
48巻1号(2006年1月発行)
47巻12号(2005年12月発行)
シンポジウム 精神医療システムの改革:その理念とエビデンス
47巻11号(2005年11月発行)
特集 電気けいれん療法
47巻10号(2005年10月発行)
47巻9号(2005年9月発行)
47巻8号(2005年8月発行)
特集 リエゾン精神医学の現状と課題
47巻7号(2005年7月発行)
47巻6号(2005年6月発行)
47巻5号(2005年5月発行)
47巻4号(2005年4月発行)
47巻3号(2005年3月発行)
47巻2号(2005年2月発行)
特集 時代による精神疾患の病像変化
47巻1号(2005年1月発行)
46巻12号(2004年12月発行)
46巻11号(2004年11月発行)
46巻10号(2004年10月発行)
特集 精神科医療における介護保険制度
46巻9号(2004年9月発行)
46巻8号(2004年8月発行)
シンポジウム 精神障害治療の新展開
46巻7号(2004年7月発行)
46巻6号(2004年6月発行)
特集 精神科医療における危機介入
46巻5号(2004年5月発行)
46巻4号(2004年4月発行)
46巻3号(2004年3月発行)
46巻2号(2004年2月発行)
46巻1号(2004年1月発行)
特集 臨床心理技術者の国家資格化についての主張
45巻12号(2003年12月発行)
特集 統合失調症と認知機能―最近の話題
45巻11号(2003年11月発行)
特集 ICFと精神医学
45巻10号(2003年10月発行)
特集 新医師臨床研修制度における精神科研修はどうあるべきか
45巻9号(2003年9月発行)
45巻8号(2003年8月発行)
シンポジウム 痴呆症とパーキンソン病研究の新展開―原因分子の発見をてがかりとして
45巻7号(2003年7月発行)
45巻6号(2003年6月発行)
特集 統合失調症とは何か―Schizophrenia概念の変遷
45巻5号(2003年5月発行)
45巻4号(2003年4月発行)
特集 新医師臨床研修制度の課題―求められる医師像と精神科卒後教育の役割
45巻3号(2003年3月発行)
特集 ひきこもりの病理と診断・治療
45巻2号(2003年2月発行)
45巻1号(2003年1月発行)
44巻12号(2002年12月発行)
シンポジウム WHO精神保健レポートと日本の課題
44巻11号(2002年11月発行)
特集 精神疾患の脳画像解析と臨床応用の将来
44巻10号(2002年10月発行)
44巻9号(2002年9月発行)
44巻8号(2002年8月発行)
特集 精神疾患と認知機能
44巻7号(2002年7月発行)
特別企画 WPA 2002 横浜大会に期待する
44巻6号(2002年6月発行)
特集 司法精神医学の今日的課題
44巻5号(2002年5月発行)
44巻4号(2002年4月発行)
44巻3号(2002年3月発行)
特集 新しい向精神薬の薬理・治療
44巻2号(2002年2月発行)
44巻1号(2002年1月発行)
43巻12号(2001年12月発行)
43巻11号(2001年11月発行)
特集 青少年犯罪と精神医学
43巻10号(2001年10月発行)
シンポジウム 精神分裂病の心理社会的治療の進歩
43巻9号(2001年9月発行)
43巻8号(2001年8月発行)
43巻7号(2001年7月発行)
43巻6号(2001年6月発行)
特集 社会構造の変化と高齢者問題
43巻5号(2001年5月発行)
特別企画 薬物依存者に対する精神保健・精神科医療体制
43巻4号(2001年4月発行)
43巻3号(2001年3月発行)
43巻2号(2001年2月発行)
特集 今,なぜ病跡学か
43巻1号(2001年1月発行)
42巻12号(2000年12月発行)
シンポジウム ライフサイクルと睡眠障害
42巻11号(2000年11月発行)
42巻10号(2000年10月発行)
特集 職場の精神保健
42巻9号(2000年9月発行)
42巻8号(2000年8月発行)
42巻7号(2000年7月発行)
42巻6号(2000年6月発行)
42巻5号(2000年5月発行)
特集 精神疾患の発病規定因子
42巻4号(2000年4月発行)
42巻3号(2000年3月発行)
特別企画 精神医学,医療の将来
42巻2号(2000年2月発行)
シンポジウム 新しい精神医学の構築—21世紀への展望
42巻1号(2000年1月発行)
41巻12号(1999年12月発行)
特集 児童精神科医療の課題
41巻11号(1999年11月発行)
41巻10号(1999年10月発行)
41巻9号(1999年9月発行)
41巻8号(1999年8月発行)
41巻7号(1999年7月発行)
41巻6号(1999年6月発行)
特集 治療抵抗性の精神障害とその対応
41巻5号(1999年5月発行)
41巻4号(1999年4月発行)
41巻3号(1999年3月発行)
41巻2号(1999年2月発行)
41巻1号(1999年1月発行)
特集 記憶障害の臨床
40巻12号(1998年12月発行)
シンポジウム がん,臓器移植とリエゾン精神医学—チーム医療における心のケア
40巻11号(1998年11月発行)
40巻10号(1998年10月発行)
40巻9号(1998年9月発行)
40巻8号(1998年8月発行)
シンポジウム 災害のもたらすもの—阪神・淡路大震災復興期のメンタルヘルス
40巻7号(1998年7月発行)
40巻6号(1998年6月発行)
40巻5号(1998年5月発行)
特集 アジアにおける最近の精神医学事情
40巻4号(1998年4月発行)
40巻3号(1998年3月発行)
40巻2号(1998年2月発行)
特集 精神病像を伴う躁うつ病および分裂感情障害の位置づけ—生物学的マーカーと診断・治療
40巻1号(1998年1月発行)
39巻12号(1997年12月発行)
39巻11号(1997年11月発行)
特集 精神科における合理的薬物選択アルゴリズム
39巻10号(1997年10月発行)
39巻9号(1997年9月発行)
39巻8号(1997年8月発行)
シンポジウム スーパービジョンとコンサルテーション—地域精神医療の方法
39巻7号(1997年7月発行)
39巻6号(1997年6月発行)
39巻5号(1997年5月発行)
特集 学校精神保健—教育との連携の実際
39巻4号(1997年4月発行)
39巻3号(1997年3月発行)
39巻2号(1997年2月発行)
39巻1号(1997年1月発行)
38巻12号(1996年12月発行)
シンポジウム 痴呆の薬物療法の最前線—向知性薬の臨床と基礎
38巻11号(1996年11月発行)
特集 精神医学における分子生物学的研究
38巻10号(1996年10月発行)
38巻9号(1996年9月発行)
38巻8号(1996年8月発行)
38巻7号(1996年7月発行)
38巻6号(1996年6月発行)
38巻5号(1996年5月発行)
特集 精神病理学の方法論—記述か計量か
38巻4号(1996年4月発行)
38巻3号(1996年3月発行)
38巻2号(1996年2月発行)
38巻1号(1996年1月発行)
37巻12号(1995年12月発行)
37巻11号(1995年11月発行)
37巻10号(1995年10月発行)
37巻9号(1995年9月発行)
37巻8号(1995年8月発行)
特集 外来精神科医療の現状と課題
37巻7号(1995年7月発行)
特集 阪神・淡路大震災—現場からの報告
37巻6号(1995年6月発行)
37巻5号(1995年5月発行)
37巻4号(1995年4月発行)
37巻3号(1995年3月発行)
37巻2号(1995年2月発行)
37巻1号(1995年1月発行)
特集 分裂病者の社会復帰—新しい展開
36巻12号(1994年12月発行)
シンポジウム アルツハイマー型痴呆の診断をめぐって
36巻11号(1994年11月発行)
36巻10号(1994年10月発行)
36巻9号(1994年9月発行)
36巻8号(1994年8月発行)
36巻7号(1994年7月発行)
36巻6号(1994年6月発行)
特集 精神医学と生物科学のクロストーク
36巻5号(1994年5月発行)
特集 精神疾患の新しい診断分類
36巻4号(1994年4月発行)
36巻3号(1994年3月発行)
36巻2号(1994年2月発行)
36巻1号(1994年1月発行)
特集 精神科治療の奏効機序
35巻12号(1993年12月発行)
35巻11号(1993年11月発行)
35巻10号(1993年10月発行)
35巻9号(1993年9月発行)
35巻8号(1993年8月発行)
シンポジウム 精神障害者の権利と能力—精神医学的倫理のジレンマ
35巻7号(1993年7月発行)
35巻6号(1993年6月発行)
35巻5号(1993年5月発行)
35巻4号(1993年4月発行)
特集 現代日本の社会精神病理
35巻3号(1993年3月発行)
35巻2号(1993年2月発行)
特集 加齢に関する精神医学的な問題
35巻1号(1993年1月発行)
34巻12号(1992年12月発行)
特集 精神科領域におけるインフォームド・コンセント
34巻11号(1992年11月発行)
34巻10号(1992年10月発行)
34巻9号(1992年9月発行)
34巻8号(1992年8月発行)
特集 薬物依存の臨床
34巻7号(1992年7月発行)
34巻6号(1992年6月発行)
34巻5号(1992年5月発行)
34巻4号(1992年4月発行)
34巻3号(1992年3月発行)
シンポジウム 境界例の診断と治療
34巻2号(1992年2月発行)
34巻1号(1992年1月発行)
33巻12号(1991年12月発行)
特集 不安の病理
33巻11号(1991年11月発行)
33巻10号(1991年10月発行)
33巻9号(1991年9月発行)
33巻8号(1991年8月発行)
33巻7号(1991年7月発行)
33巻6号(1991年6月発行)
33巻5号(1991年5月発行)
33巻4号(1991年4月発行)
33巻3号(1991年3月発行)
33巻2号(1991年2月発行)
特集 精神科領域におけるレセプター機能の研究の進歩
33巻1号(1991年1月発行)
32巻12号(1990年12月発行)
シンポジウム 「うつ」と睡眠
32巻11号(1990年11月発行)
32巻10号(1990年10月発行)
32巻9号(1990年9月発行)
32巻8号(1990年8月発行)
特集 精神疾患の現代的病像をめぐって
32巻7号(1990年7月発行)
32巻6号(1990年6月発行)
特集 精神分裂病の生物学的研究
32巻5号(1990年5月発行)
32巻4号(1990年4月発行)
32巻3号(1990年3月発行)
特集 向精神薬の見逃されやすい副作用と対策
32巻2号(1990年2月発行)
32巻1号(1990年1月発行)
31巻12号(1989年12月発行)
31巻11号(1989年11月発行)
31巻10号(1989年10月発行)
シンポジウム 精神障害者の責任能力
31巻9号(1989年9月発行)
31巻8号(1989年8月発行)
31巻7号(1989年7月発行)
31巻6号(1989年6月発行)
特集 現代社会と家族—諸病態との関連から
31巻5号(1989年5月発行)
31巻4号(1989年4月発行)
31巻3号(1989年3月発行)
31巻2号(1989年2月発行)
31巻1号(1989年1月発行)
特集 サーカディアンリズム—基礎から臨床へ
30巻12号(1988年12月発行)
30巻11号(1988年11月発行)
シンポジウム 痴呆とパーキンソニズム
30巻10号(1988年10月発行)
30巻9号(1988年9月発行)
特集 世界の精神科医療の動向
30巻8号(1988年8月発行)
30巻7号(1988年7月発行)
30巻6号(1988年6月発行)
シンポジウム 地域ケアと精神保健
30巻5号(1988年5月発行)
30巻4号(1988年4月発行)
創刊30周年記念特集 精神医学—最近の進歩 第2部
30巻3号(1988年3月発行)
創刊30周年記念特集 精神医学—最近の進歩 第1部
30巻2号(1988年2月発行)
30巻1号(1988年1月発行)
29巻12号(1987年12月発行)
特集 躁うつ病とセロトニン
29巻11号(1987年11月発行)
29巻10号(1987年10月発行)
29巻9号(1987年9月発行)
29巻8号(1987年8月発行)
29巻7号(1987年7月発行)
29巻6号(1987年6月発行)
29巻5号(1987年5月発行)
29巻4号(1987年4月発行)
29巻3号(1987年3月発行)
29巻2号(1987年2月発行)
29巻1号(1987年1月発行)
特集 老年精神医学
28巻12号(1986年12月発行)
28巻11号(1986年11月発行)
特集 脳の働きと心―大脳の機能をめぐって
28巻10号(1986年10月発行)
28巻9号(1986年9月発行)
28巻8号(1986年8月発行)
28巻7号(1986年7月発行)
28巻6号(1986年6月発行)
28巻5号(1986年5月発行)
28巻4号(1986年4月発行)
28巻3号(1986年3月発行)
28巻2号(1986年2月発行)
特集 現代の子供—心身の発達とその病理—東京都精神医学総合研究所 第13回シンボジウムから
28巻1号(1986年1月発行)
27巻12号(1985年12月発行)
特集 摂食障害の心理と治療
27巻11号(1985年11月発行)
27巻10号(1985年10月発行)
27巻9号(1985年9月発行)
27巻8号(1985年8月発行)
27巻7号(1985年7月発行)
27巻6号(1985年6月発行)
特集 前頭葉の神経心理学
27巻5号(1985年5月発行)
特集 精神分裂病の成因と治療—東京都精神医学総合研究所 第12回シンポジウムから
27巻4号(1985年4月発行)
27巻3号(1985年3月発行)
27巻2号(1985年2月発行)
特集 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome)―その病態と臨床
27巻1号(1985年1月発行)
26巻12号(1984年12月発行)
26巻11号(1984年11月発行)
26巻10号(1984年10月発行)
26巻9号(1984年9月発行)
26巻8号(1984年8月発行)
26巻7号(1984年7月発行)
特集 側頭葉障害における言語症状
26巻6号(1984年6月発行)
26巻5号(1984年5月発行)
26巻4号(1984年4月発行)
26巻3号(1984年3月発行)
26巻2号(1984年2月発行)
特集 DSM-III—その有用性と問題点
26巻1号(1984年1月発行)
特集 精神疾患に対する神経内分泌的アプローチ
25巻12号(1983年12月発行)
特集 カルバマゼピンの向精神作用
25巻11号(1983年11月発行)
25巻10号(1983年10月発行)
特集 少年非行の心理と病理—東京都精神医学総合研究所 第11回シンポジウムから
25巻9号(1983年9月発行)
25巻8号(1983年8月発行)
特集 児童精神医学の現状と将来—都立梅ケ丘病院30周年記念シンポジウムから
25巻7号(1983年7月発行)
25巻6号(1983年6月発行)
25巻5号(1983年5月発行)
25巻4号(1983年4月発行)
特集 聴覚失認
25巻3号(1983年3月発行)
特集 精神医学における病態モデル
25巻2号(1983年2月発行)
特集 薬物と睡眠をめぐって
25巻1号(1983年1月発行)
24巻12号(1982年12月発行)
特集 アルコール依存症の精神医学—東京都精神医学総合研究所 第10回シンポジウムから
24巻11号(1982年11月発行)
24巻10号(1982年10月発行)
特集 精神科診療所をめぐる諸問題
24巻9号(1982年9月発行)
24巻8号(1982年8月発行)
24巻7号(1982年7月発行)
24巻6号(1982年6月発行)
24巻5号(1982年5月発行)
24巻4号(1982年4月発行)
特集 視覚失認
24巻3号(1982年3月発行)
24巻2号(1982年2月発行)
特集 リチウムの臨床と基礎—最近の話題
24巻1号(1982年1月発行)
23巻12号(1981年12月発行)
23巻11号(1981年11月発行)
特集 Ⅱ.アジアにおける精神衛生問題
23巻10号(1981年10月発行)
特集 失行
23巻9号(1981年9月発行)
23巻8号(1981年8月発行)
23巻7号(1981年7月発行)
特集 てんかんのメカニズムと治療—東京都精神医学総合研究所 第8回シンポジウムから
23巻6号(1981年6月発行)
23巻5号(1981年5月発行)
23巻4号(1981年4月発行)
23巻3号(1981年3月発行)
23巻2号(1981年2月発行)
23巻1号(1981年1月発行)
22巻12号(1980年12月発行)
特集 躁うつ病の生物学
22巻11号(1980年11月発行)
特集 Butyrophenone系抗精神病薬の臨床精神薬理学
22巻10号(1980年10月発行)
特集 日本精神医学と松沢病院
22巻9号(1980年9月発行)
22巻8号(1980年8月発行)
特集 思春期の精神医学的諸問題—東京都精神医学総合研究所 第7回シンポジウムから
22巻7号(1980年7月発行)
特集 Brain Function Testへのアプローチ
22巻6号(1980年6月発行)
22巻5号(1980年5月発行)
特集 睡眠研究—最近の進歩
22巻4号(1980年4月発行)
22巻3号(1980年3月発行)
22巻2号(1980年2月発行)
特集 向精神薬をめぐる最近の諸問題
22巻1号(1980年1月発行)
特集 幻覚
21巻12号(1979年12月発行)
21巻11号(1979年11月発行)
特集 精神分裂病の生物学
21巻10号(1979年10月発行)
21巻9号(1979年9月発行)
21巻8号(1979年8月発行)
特集 老人の精神障害—東京都精神医学総合研究所,第6回シンポジウムから
21巻7号(1979年7月発行)
特集 精神分裂病の遺伝因と環境因
21巻6号(1979年6月発行)
特集 創刊20周年記念 第2部
21巻5号(1979年5月発行)
特集 創刊20周年記念 第1部
21巻4号(1979年4月発行)
21巻3号(1979年3月発行)
21巻2号(1979年2月発行)
特集 妄想
21巻1号(1979年1月発行)
20巻12号(1978年12月発行)
特集 精神鑑定
20巻11号(1978年11月発行)
20巻10号(1978年10月発行)
シンポジウム 精神分裂病者の治療について—東京都精神医学総合研究所,第5回シンポジウムから
20巻9号(1978年9月発行)
20巻8号(1978年8月発行)
20巻7号(1978年7月発行)
20巻6号(1978年6月発行)
20巻5号(1978年5月発行)
20巻4号(1978年4月発行)
20巻3号(1978年3月発行)
20巻2号(1978年2月発行)
20巻1号(1978年1月発行)
19巻12号(1977年12月発行)
特集 青年期の精神病理
19巻11号(1977年11月発行)
シンポジウム こころとからだ—東京都精神医学総合研究所,第4回シンポジウムから
19巻10号(1977年10月発行)
19巻9号(1977年9月発行)
19巻8号(1977年8月発行)
特集 在宅精神医療(2)—社会復帰活動とその周辺
19巻7号(1977年7月発行)
19巻6号(1977年6月発行)
19巻5号(1977年5月発行)
19巻4号(1977年4月発行)
特集 精神分裂病の精神生理学
19巻3号(1977年3月発行)
19巻2号(1977年2月発行)
シンポジウム 生のリズムとその障害—東京都精神医学総合研究所,第3回シンポジウムから
19巻1号(1977年1月発行)
18巻12号(1976年12月発行)
特集 近代日本の宗教と精神医学
18巻11号(1976年11月発行)
18巻10号(1976年10月発行)
18巻9号(1976年9月発行)
18巻8号(1976年8月発行)
18巻7号(1976年7月発行)
18巻6号(1976年6月発行)
特集 在宅精神医療—日常生活における指導と治療
18巻5号(1976年5月発行)
シンポジウム 大都市の病理と精神障害—東京都精神医学総合研究所第2回シンポジウムから
18巻4号(1976年4月発行)
18巻3号(1976年3月発行)
18巻2号(1976年2月発行)
18巻1号(1976年1月発行)
17巻13号(1975年12月発行)
臨時増刊号特集 精神医学における日本的特性
17巻12号(1975年12月発行)
17巻11号(1975年11月発行)
17巻10号(1975年10月発行)
17巻9号(1975年9月発行)
17巻8号(1975年8月発行)
17巻7号(1975年7月発行)
17巻6号(1975年6月発行)
17巻5号(1975年5月発行)
17巻4号(1975年4月発行)
17巻3号(1975年3月発行)
17巻2号(1975年2月発行)
17巻1号(1975年1月発行)
16巻12号(1974年12月発行)
16巻11号(1974年11月発行)
シンポジウム 現代における精神医学研究の課題—東京都精神医学総合研究所開設記念シンポジウムから
16巻10号(1974年10月発行)
16巻9号(1974年9月発行)
16巻7号(1974年7月発行)
シンポジウム 向精神薬療法の現状と問題点—Dr. Frank J. Ayd, Jr. を迎えて
16巻6号(1974年6月発行)
誌上シンポジウム 日本の精神医療についての4つの意見
16巻5号(1974年5月発行)
16巻4号(1974年4月発行)
16巻3号(1974年3月発行)
16巻2号(1974年2月発行)
16巻1号(1974年1月発行)
15巻12号(1973年12月発行)
特集 精神障害と家族
15巻11号(1973年11月発行)
15巻10号(1973年10月発行)
15巻9号(1973年9月発行)
15巻8号(1973年8月発行)
15巻7号(1973年7月発行)
15巻6号(1973年6月発行)
15巻5号(1973年5月発行)
15巻4号(1973年4月発行)
特集 痴呆の臨床と鑑別
15巻3号(1973年3月発行)
15巻2号(1973年2月発行)
15巻1号(1973年1月発行)
14巻12号(1972年12月発行)
特集 精神障害者の動態
14巻11号(1972年11月発行)
14巻10号(1972年10月発行)
14巻9号(1972年9月発行)
14巻8号(1972年8月発行)
14巻7号(1972年7月発行)
14巻6号(1972年6月発行)
14巻5号(1972年5月発行)
特集 てんかん分類へのアプローチ
14巻4号(1972年4月発行)
14巻3号(1972年3月発行)
14巻2号(1972年2月発行)
特集 作業療法
14巻1号(1972年1月発行)
13巻12号(1971年12月発行)
特集 社会変動と精神医学
13巻11号(1971年11月発行)
13巻10号(1971年10月発行)
特集 内因性精神病の生物学的研究
13巻9号(1971年9月発行)
13巻8号(1971年8月発行)
13巻7号(1971年7月発行)
13巻6号(1971年6月発行)
13巻5号(1971年5月発行)
特集 向精神薬をめぐる問題点
13巻4号(1971年4月発行)
13巻3号(1971年3月発行)
13巻2号(1971年2月発行)
13巻1号(1971年1月発行)
12巻12号(1970年12月発行)
特集 社会のなかの精神科医
12巻11号(1970年11月発行)
12巻10号(1970年10月発行)
12巻9号(1970年9月発行)
12巻8号(1970年8月発行)
12巻7号(1970年7月発行)
12巻6号(1970年6月発行)
特集 境界例の病理と治療
12巻5号(1970年5月発行)
特集 対人恐怖
12巻4号(1970年4月発行)
12巻3号(1970年3月発行)
12巻2号(1970年2月発行)
特集 医療危機と精神科医—第6回日本精神病理・精神療法学会 討論集会をめぐって
12巻1号(1970年1月発行)
11巻12号(1969年12月発行)
11巻11号(1969年11月発行)
11巻10号(1969年10月発行)
11巻9号(1969年9月発行)
11巻8号(1969年8月発行)
11巻7号(1969年7月発行)
11巻6号(1969年6月発行)
11巻5号(1969年5月発行)
特集 心気症をめぐつて
11巻4号(1969年4月発行)
11巻3号(1969年3月発行)
特集 医学教育と精神療法
11巻2号(1969年2月発行)
11巻1号(1969年1月発行)
10巻12号(1968年12月発行)
10巻11号(1968年11月発行)
10巻10号(1968年10月発行)
10巻9号(1968年9月発行)
10巻8号(1968年8月発行)
10巻7号(1968年7月発行)
特集 集団精神療法(日本精神病理・精神療法学会第4回大会シンポジウム)
10巻6号(1968年6月発行)
10巻5号(1968年5月発行)
特集 うつ病—日本精神病理・精神療法学会(第4回大会シンポジウム)
10巻4号(1968年4月発行)
10巻3号(1968年3月発行)
10巻2号(1968年2月発行)
10巻1号(1968年1月発行)
9巻12号(1967年12月発行)
9巻11号(1967年11月発行)
9巻10号(1967年10月発行)
9巻9号(1967年9月発行)
9巻8号(1967年8月発行)
9巻7号(1967年7月発行)
特集 精神療法の技法と理論—とくに人間関係と治癒像をめぐって
9巻6号(1967年6月発行)
特集 心因をめぐる諸問題
9巻5号(1967年5月発行)
特集 創造と表現の病理
9巻4号(1967年4月発行)
特集 精神療法における治癒機転
9巻3号(1967年3月発行)
9巻2号(1967年2月発行)
特集 精神分裂病の診断基準—とくに“Praecoxgefühl”について
9巻1号(1967年1月発行)
特集 内因性精神病の疾病論
8巻12号(1966年12月発行)
特集 うつ病の臨床
8巻11号(1966年11月発行)
特集 宗教と精神医学
8巻10号(1966年10月発行)
特集 地域精神医学—その理論と実践
8巻9号(1966年9月発行)
8巻8号(1966年8月発行)
8巻7号(1966年7月発行)
特集 精神医療体系のなかでの精神病院の位置づけ
8巻6号(1966年6月発行)
特集 薬物と精神療法
8巻5号(1966年5月発行)
8巻4号(1966年4月発行)
特集 精神分裂病の家族研究
8巻3号(1966年3月発行)
特集 精神活動とポリグラフ
8巻2号(1966年2月発行)
8巻1号(1966年1月発行)
7巻12号(1965年12月発行)
7巻11号(1965年11月発行)
7巻10号(1965年10月発行)
7巻9号(1965年9月発行)
7巻8号(1965年8月発行)
7巻7号(1965年7月発行)
7巻6号(1965年6月発行)
特集 呉秀三先生の生誕100年を記念して
7巻5号(1965年5月発行)
7巻4号(1965年4月発行)
7巻3号(1965年3月発行)
特集 精神分裂病の“治癒”とは何か
7巻2号(1965年2月発行)
特集 精神療法の限界と危険
7巻1号(1965年1月発行)
6巻12号(1964年12月発行)
6巻11号(1964年11月発行)
特集 向精神薬・抗けいれん剤の効果判定法
6巻10号(1964年10月発行)
6巻9号(1964年9月発行)
6巻8号(1964年8月発行)
6巻7号(1964年7月発行)
6巻6号(1964年6月発行)
6巻5号(1964年5月発行)
6巻4号(1964年4月発行)
6巻3号(1964年3月発行)
6巻2号(1964年2月発行)
特集 神経症の日本的特性
6巻1号(1964年1月発行)
特集 近接領域からの発言
5巻12号(1963年12月発行)
5巻11号(1963年11月発行)
5巻10号(1963年10月発行)
5巻9号(1963年9月発行)
5巻8号(1963年8月発行)
5巻7号(1963年7月発行)
5巻6号(1963年6月発行)
5巻5号(1963年5月発行)
5巻4号(1963年4月発行)
5巻3号(1963年3月発行)
特集 てんかん
5巻2号(1963年2月発行)
特集 病識〔精神病理懇話会講演および討議〕
5巻1号(1963年1月発行)
4巻12号(1962年12月発行)
4巻11号(1962年11月発行)
特集 睡眠
4巻10号(1962年10月発行)
4巻9号(1962年9月発行)
4巻8号(1962年8月発行)
4巻7号(1962年7月発行)
4巻6号(1962年6月発行)
4巻5号(1962年5月発行)
4巻4号(1962年4月発行)
4巻3号(1962年3月発行)
4巻2号(1962年2月発行)
4巻1号(1962年1月発行)
3巻12号(1961年12月発行)
特集 非定型内因性精神病
3巻11号(1961年11月発行)
3巻10号(1961年10月発行)
3巻9号(1961年9月発行)
3巻8号(1961年8月発行)
3巻7号(1961年7月発行)
3巻6号(1961年6月発行)
3巻5号(1961年5月発行)
3巻4号(1961年4月発行)
3巻3号(1961年3月発行)
3巻2号(1961年2月発行)
3巻1号(1961年1月発行)
特集 妄想の人間学—精神病理懇話会講演ならびに討論
