現代において,うつ病はあらゆる年代における精神健康上の重大な疾病負荷であることが共通認識となりつつある。伝統的な臨床医学においては,うつ病は成人期,特に中年期以降に有病率が増加することが,共通認識とされてきた。有病率を見積もるための疫学調査や臨床研究のデータも,こうした認識を裏付ける一方で,なぜ成人期以降にうつ病が増加するのかを説明づける生物学的な証拠はきわめて乏しい。古典的な精神病理学および社会心理学的考察の多くは,一定の心理的成熟とともに,身体的老化(衰え),社会的ストレスなどの複合的要因により,うつの発症を説明している。
近年,子どものうつ症状は,成人とは異なる表現型をとるという考え方が支持されるようになった。子どもにおける心理ストレスに対する反応の未成熟性や,適応不全の表現形における成人との差異を考えると,こうした考え方には一定の説得力がある。少なくとも,子どもは成人よりもストレス脆弱性が高く,うつ病の発症やこれに伴う社会的逸脱による発達・成熟上のデメリットを考慮すると,より早期に適切な介入をすべきであるという発想は妥当であり,このために早期に診断する必要性はもっともであろう。
雑誌目次
精神医学65巻7号
2023年07月発行
雑誌目次
特集 子どものうつ病に気づく
特集にあたって フリーアクセス
著者: 稲垣貴彦 , 栗山健一
ページ範囲:P.971 - P.972
現代の日本における子どものうつ病臨床の現状
著者: 稲垣貴彦
ページ範囲:P.973 - P.979
抄録
子どものうつ病は,再発率が46.6%あるとはいえ,1年以内に66.3%が,5年以内に96.4%が寛解する,比較的予後のよい疾患である。しかし,種々の問題行動の原因になり,教育達成度の低下や,成人した後の福祉依存度や失業率の増加といった,心理社会的機能の悪化につながり,早期発見・早期治療が重要である。
子どもにおける有病率は精神障害全体で13.4%に対し,うつ病が1.3%である。しかし日本においては,メンタルヘルスの問題で受診した子どものうち,気分障害全体で男子の2%,女子の6%を占めるにすぎない。うつ病の診断に必要とされる情報量は膨大であるが,日本の臨床状況においては許容される時間が諸外国に比べて短く,うつ病の見落としが懸念される。
日本における子どもの心の臨床での現状を踏まえた上で,子どものうつ病の早期発見,つまり日々の臨床の中で子どものうつ病に適切に気づく方法について検討する必要がある。
英国における子どものうつ病臨床
著者: 森野百合子
ページ範囲:P.980 - P.986
抄録
各国の医療制度の違いや医療資源の違いは,子どものうつ病臨床を含め,すべての臨床活動のあり方に大きな影響を与える。英国の児童・思春期精神科でトレーニングを受け,その後日本で臨床を行っている筆者の経験から,日本と英国の医療制度を比較し,その違いについて述べた。その大きな違いの一つとして,英国では医療のシステムが階層化されていること,また児童・思春期精神科臨床においては精神療法的アプローチや,疾病予防が重視されていることが挙げられる。英国では子どものうつ病の治療においては,まず精神療法を行うのが一般的である。英国のNational Institute for Health and Care Excellence(NICE)による子どものうつ病アセスメントと治療についてのガイドラインと併せて,英国での子どものうつ病の臨床の実際につき報告する。
子どものうつ病の臨床におけるライフコースと発達精神病理学の視点
著者: 山下洋
ページ範囲:P.988 - P.994
抄録
抑うつ(depression)がライフコースを通じてみられる気分における1つの状態であることが共通認識となり,子どものうつについての実態把握と早期発見と予防に向けた啓発活動も広がっている。早期発達の重要性の観点から学齢前期の抑うつについて1940年代から養育的ケアの剥奪との関連が注目され,子どもにおける対象喪失と悲嘆という概念化と啓発から,小児医療における母児同室,児童福祉における脱施設化などの社会運動につながった。1980年代以降,発達精神病理学に基づくコホート研究からリプロダクティブ・イベントとしての思春期とうつ病の発症脆弱性の性差という病態モデルが示された。全世界的なCOVID-19パンデミックにおいて発達途上の子どもと家族にとっての心理社会的ストレスと抑うつの関連が社会的注目を浴びた。これを契機に生物・心理・社会的な枠組みから,この時期の発症脆弱性に対してレジリエンスに基づく統一プロトコールやアタッチメントに基づく介入が社会実装され,学校や家庭に対して提供されることが望まれる。
子どものうつ病の神経生物学
著者: 岡田俊
ページ範囲:P.996 - P.999
抄録
子どものうつ病は,その臨床経過や治療反応性から成人期と比べて非定型的であることが報告されてきた。子どものうつ病が確固とした病態たりえているかを調べる最善な方法は,神経生物学的エビデンスに基づく明確化であり,本稿では,これらのエビデンスを展望した。その結果,核磁気共鳴画像では海馬や眼窩前頭皮質の低容積が,脳波活動では左右非対称性が報告されるなど,成人期と共通する知見が認められた。しかし,単一光子放射断層撮影では,異なる所見を示す2群があると報告されるなど異質性が報告されているほか,近赤外線分光法では抑うつ症状の改善とともに酸素化ヘモグロビン濃度も上昇するなど,state markerとしての役割も認められる。子どものうつ病を神経生物学的に規定するためには,ほかの精神疾患や神経発達症特性の交絡を考慮すること,経過を踏まえたより厳密な診断を採用するなどの方法論が求められる一方,十分なサンプルサイズが求められるという課題を有することを指摘した。
臨床の場面でうつ病の子どもはどのように見えるのか
著者: 館農勝
ページ範囲:P.1000 - P.1005
抄録
子どものうつ病では,症状の見え方が大人とは異なり,行動の変化として現れることも多い。子どもでは,抑うつ気分は易怒的な気分として現れることはよく知られている。低年齢では気分を言語化することは困難で身体症状を訴えることが多い。時には,精神病様症状を伴うこともある。中途覚醒や早朝覚醒はうつ病を示唆するとの意見もある。大人ではうつ病性仮性認知症が知られているが,子どものうつ病における思考力の減退は,友だち付き合いの減少や学業成績の低下につながることもある。「消えたい」との訴えは自殺関連行動と関係しており注意が必要である。うつ症状に加え,背景要因を含めた全体像の理解と慎重なアセスメントが必要である。
子どものうつ病は周囲の大人(親や教師)にどのように見えているのか
著者: 山田敦朗
ページ範囲:P.1007 - P.1015
抄録
子どものうつ病は,親や教師にとっては,今なお認識されているとは言いがたい。本人の発達特性,学校などの社会的環境,家庭環境といった要因が背景にあり,これに発症要因が加わって発症することが多い。周囲の大人には,これらすべてが重なって不調になっている状態がおぼろげながらにしか見えていないことも多く,発症要因をはじめ目立つ要因ばかりに目が行きがちである。不登校や身体症状が前面に出ているようなケースでは,表面的な症状にとらわれ,状態のみを改善することや原因探しに終始してしまうことも少なくない。診療においては,操作的診断基準を用いてきちんと評価するとともに,背景にある要因を丁寧に検討していくことが求められる。神経発達症の併存が多いことから,神経発達症の評価も行っていくべきである。治療では,心理社会的介入を優先することが大切で,親や教師に寄り添った対応を心がける。
発達過程でのうつ病の気づき—小児科医のまなざし
著者: 阪上由子 , 澤井ちひろ
ページ範囲:P.1017 - P.1021
抄録
児童思春期のうつ病の早期発見にはリスク因子の同定,ハイリスク群の抽出が有用である。リスク因子としては周産期エピソード(早産・極低出生体重児)や家族歴(気分障害や神経発達症),養育環境・心理社会的問題(逆境的小児期体験など),慢性身体疾患や神経発達症の併存などが挙げられる。これらのリスク因子に慢性的な感情行動調整の困難さ(irritability)を伴うと,うつ病を発症するリスクがより高くなることが知られている。児童思春期のうつ病の診断には発達段階による症状の違いに留意し,本人・家族からだけでなく,第三者からの詳細な情報収集に基づき家族機能や学校生活も含めた包括的なアセスメントを行うことが重要である。神経発達症とその周辺領域を主に診療する小児科医の視点に基づき,発達段階によるうつ病の症候学的な変化と発症のリスク因子について述べる。
子どもの行動の問題からうつ病に気づく
著者: 田中恒彦
ページ範囲:P.1022 - P.1027
抄録
うつ病は子どものメンタルヘルスにおける重要な問題であり,約3%の子どもが罹患しているだけでなく,多くの人が抑うつ症状を経験している。子どもは自身の不調に気づきにくく,発達や周囲との関係性などの要因で不調を伝えることが難しいため,周囲の大人が観察を通じて問題を理解していくことになる。そこで,子どもの問題行動の特徴を理解することが正確な診断とサポートのために重要になる。本稿では,児童期と思春期・青年期のうつ病の特徴を紹介し,それらの症状によって引き起こされる行動の問題を事例を通して解説した。これまでの研究から,不登校や成績の低下,課外活動の減少,自傷行為,引きこもり,睡眠障害,インターネット・ゲーム依存,反抗挑戦的な態度などの行動問題がうつ病と関連することが明らかになっている。
神経発達症の成長の中でのうつ病の気づき
著者: 辻井農亜
ページ範囲:P.1028 - P.1032
抄録
神経発達症は発達期に発症する一群の疾患であり,個人的,社会的,学業,または職業における機能の障害を引き起こす発達の欠陥により特徴づけられる。神経発達症を持つ子どもにはうつ病が併存しやすいことが知られている。臨床においては,神経発達症をうつ病発症のリスクの1つとして捉え,神経発達症を持つ子どもの特性,家族や友人または学校といった環境などとの相互作用のバランスが破綻したときに不安や抑うつが現れ,それがうつ病に発展すると捉えると理解し対応しやすい。一人ひとりの神経発達症を持つ子どもの社会生活全体を見渡し,育み支え続けることがうつ病の気づきにつながると考えられる。
児童青年期における不安症の診断と治療
著者: 鈴木太
ページ範囲:P.1034 - P.1040
抄録
抑うつ障害と不安症は神経生物学的には異なる表現型であると見なされているが,いずれも内在化障害に分類され,互いに併存しやすく,治療反応性が類似している。抑うつ障害と不安症を併存する児童や青年は,いずれかだけを有した人と比べて,より重度で,治療に反応しにくい。臨床家は不安症の典型的な発症年齢,抑うつ障害と不安症の発達モデルを意識しながらアセスメントし,不安症をより早期に認識して,集中的な精神医学的治療を導入すべきである。Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version, DSM-5(K-SADS-PL-5)などの構造化面接は不安症を包括的にアセスメントするための助けとなる。抗うつ薬と認知行動療法は不安症治療の選択肢となる。
適応障害とうつ病性障害との鑑別
著者: 太田陽 , 藤田純一
ページ範囲:P.1041 - P.1046
抄録
適応障害に関して,かつては「ゴミ箱診断」などと揶揄され,特にうつ病性障害との鑑別については曖昧になっていた。特に,児童青年期のうつ病エピソードを過小評価する臨床医の診療姿勢や経験不足によって,うつ病性障害と診断される病状を適応障害としてしまう,あるいは正常範囲とみなしてしまうなど,誤診の危険性をはらんでいた。
ICD-11の中で,適応障害は反芻思考と過度な不安によって,ストレス因もしくはその結果について先行する不安が生じると定義されたことで,より明確になった。治療についても現状は経過観察として対応していくが,若年者の一定数に自殺リスクを伴うことがあるため,注意深くみていく必要がある。そのためにも,適応障害とうつ病性障害についてはそれぞれの診断基準に従って鑑別を行い,適切な治療を進めていく必要がある。
児童・思春期の抑うつ—躁転の危険因子と治療の戦略
著者: 庄司絵理 , 加藤忠史 , 内田舞
ページ範囲:P.1048 - P.1056
抄録
うつ病の発症率は12歳以降では成人とほぼ同様であるとされている一方,子どもには独特の社会・心理学的な問題があり,臨床像が一般精神医学には当てはまらない場合も多い。特に双極性障害の臨床像は不安定で,若年発症の大うつ病性エピソードは,実は双極性障害であったという場合も少なくない。鑑別は困難をきわめる一方,その後の治療方針にかかわるため,リスクファクターや臨床像に注意しながら,診断と治療を行っていくことが重要である。現在知られている躁転の危険因子として気分障害(うつ病性障害,双極性障害)の家族歴,情動調節障害(emotional dysregulation),行動制御障害(behavioral dysregulation),閾値以下の躁症状,幻覚や妄想などの精神病症状の併発が挙げられる。さらには将来の躁転を踏まえた治療戦略,躁転してしまった場合のアプローチについて言及した。
短報
強度行動障害のある自閉スペクトラム症男児の入院治療における保育士の役割
著者: 荒木陽子 , 川内裕子 , 坂上沙織 , 宮尾隆行 , 鳥羽麻奈美 , 花房昌美 , 岩田和彦
ページ範囲:P.1058 - P.1061
抄録
大阪精神医療センター児童病棟は,医療型障害児入所施設の機能も有しているため,児童精神科医,看護師のほかに保育士などが配置されている。今回我々は,幼少時に療育を受ける機会がないまま就学し,いじめやからかいを受け,不適応行動のため小学校や福祉現場から受け入れが難しくなった10歳自閉症男児の症例を経験した。医師や看護師が不適応行動の変容に注目する一方で,保育士は複数の職員と愛着関係を育むよう働きかけ,男児の対人相互交流能力を高めた。こうした人手がかかる治療は,公的病院でさえ医療経済的に担うのが難しくなりつつあり,診療報酬上でも,保育士の配置や個別療育に関し加算評価が望まれる。
ミニレビュー
自己教師あり深層学習を用いた精神疾患脳画像研究
著者: 山口博行 , 山下祐一
ページ範囲:P.1064 - P.1074
抄録
深層学習は,精神疾患の脳画像研究を進める上で有望な技術として期待されている。しかし,精神疾患は遺伝的・臨床的異質性が指摘されており,研究には大きな困難が伴う。本論文では,上述の問題を克服するために筆者らがこれまで報告してきた試みを紹介する。研究では,学習データ自身をラベルとする自己教師あり深層学習の手法を用いた。提案モデルは3次元脳構造MRIデータから,精神疾患の診断ラベルを用いないにもかかわらず,症状などの臨床情報との関連性を保持した特徴量を抽出可能であった。提案モデルは精神疾患のような異質性を持つ集団に対し有効と考えられ,データ駆動型の新たな診断基準の開発につながる可能性がある。
追悼
小阪憲司先生を偲んで
著者: 井関栄三
ページ範囲:P.1075 - P.1077
横浜市立大学名誉教授の小阪憲司先生が,2023年3月16日に逝去されました。小阪先生は「レビー小体型認知症」(dementia with Lewy bodies:DLB)の発見者である著名な研究者であり,日本が世界に誇る老年精神医学者であり神経病理学者です。先生は,1965年に金沢大学医学部をご卒業になり,名古屋大学医学部精神医学教室に入局されました。その後,1975年に東京都精神医学総合研究所副参事研究員となり,精神科臨床を都立松沢病院で行い,老年精神医学と神経病理学の道を深めていかれました。1977年にドイツ・マックスプランク精神医学研究所特別研究員,1985年に東京都精神医学総合研究所神経病理研究室主任となりました。この間,当時はまだ知られていなかったDLBの剖検例を初めて報告して以来,多数の剖検例の報告を行い,臨床所見とレビー小体の病変分布から,現在のDLBとパーキンソン病(Parkinson's disease:PD)を含むレビー小体病(Lewy body disease:LBD)の臨床病理学的疾患概念を確立しました。新たな疾患単位の確立には,優れた臨床家と病理学者であること,さらに緻密な観察眼と大胆な構想力が求められ,先生はまさにこれらを併せ持つ研究者でした。また,「石灰沈着を伴うびまん性神経原線維変化病」も先生が初めて報告し,命名した認知症疾患です。私も新潟大学脳研究所で神経病理学を学んでいた関係で,小阪先生のお名前は存じていましたが,直接お会いしたのは私が横浜市立大学医学部精神医学教室に在籍していたときでした。認知症の剖検例を見せていただくために東京都精神医学総合研究所神経病理研究室に伺い,先生から認知症の臨床神経病理学の面白さ,ご自分の提唱された当時の「びまん性レビー小体病」(diffuse Lewy body disease:DLBD)のお話を伺っておりました。
その後,1991年に先生は横浜市立大学医学部精神医学教室の教授となり,私は講師から助教授として12年間,ご一緒に仕事をさせていただき,親しくご指導いただきました。先生は学問に関しては厳しい方でしたが,実にフランクでなんでも相談できる方でした。老年精神医学の臨床では,横浜市立大学に認知症疾患治療研究センターを作られ,認知症専門外来を発展させ,横浜市福祉局との疫学研究なども行いました。神経病理学の研究では,毎週開かれる剖検例の病理カンファレンスには,自ら参加されてご指導いただきました。当時は,まだDLBの疾患概念は世界に共通のものとはなっておらず,レビー小体をもつ剖検例がいくつもの異なる名称で報告され,混沌とした時代でした。当然,DLBの頻度なども分かっておらず,現在,「アルツハイマー型認知症」に次ぐ第二の認知症疾患になるとは想像しておりませんでした。このため,当初は私たちも剖検例の臨床病理学的研究を引き続いて行っておりましたが,その後,1997年に,DLBおよびPDの原因蛋白がαシヌクレインであることが明らかとなり,私たちの神経病理研究はαシヌクレインを用いた免疫組織化学,免疫電子顕微鏡を用いた病態機序の解明を目指した研究に移ってまいりました。1995年,DLBの第1回国際ワークショップ(International Workshop on DLB and PDD)が開催され,DLBの概念が国際的に共通のものとなり,現在につながるDLBの臨床病理診断基準が作成されました。先生はその中心的役割を果たし,その後のワークショップでも常に新しい研究成果を発表されてこられました。
書評
—福武敏夫 著—神経症状の診かた・考えかた 第3版—General Neurologyのすすめ フリーアクセス
著者: 尾久守侑
ページ範囲:P.1063 - P.1063
本書の初版が出版されたのは2014年の5月で,病棟に出たばかりの研修医1年目だった私はこれを直ちに買って勉強をした。知らないことばかりだった。第2版が出版された2017年には精神科医2年目で,てんかんセンターに勤めていた。当然買って読んだ。知らないことばかりだった。そして第3版の出版された今年2023年はそんな私も医者10年目になった。今回は買わなかった。買う前に医学書院が本を送ってくれたからである。そして読んだ。知らないことばかりだった。
と,書くと何度も読んでいるのにその都度内容を忘れているのかと驚いてしまうが,実際全てを記憶できていない部分はまああるにせよ,そういうことを言いたいわけではない。まず第一に,内容が毎回更新されている。改訂にあたって新しい客観的知見が追記されることはしばしばあることだが,すでに熟達した臨床家である著者の臨床感覚も新鮮に更新されており驚(きょう)愕(がく)する。網羅性が増していること以上に,時を経て複数回テキストを再読し書き直したことによって,1冊を読み通したときにわれわれ読者に憑依する著者の臨床感覚に年輪のような重層性が生まれており,これは並大抵の医学書の改訂では起こり得ない現象だと思う。
—加藤 実 著—子どもの「痛み」がわかる本—はじめて学ぶ慢性痛診療 フリーアクセス
著者: 余谷暢之
ページ範囲:P.1079 - P.1079
子どもの痛みは歴史的に過小評価されてきました。その中で,多くの研究者たちが子どもの痛みについてのエビデンスを積み重ね,「子どもはむしろ痛みを感じやすい」ことが明らかになりました。その結果,諸外国では子どもへの痛みの対応が丁寧に実践されていますが,わが国においては十分に対処されているとはいえない状況があります。著者である加藤実先生は子どもの痛みに真摯に向き合い,丁寧に臨床を重ねられ,さまざまな学会でその重要性を訴えてこられました。その集大成が本書であると思います。
本書で紹介されている慢性痛は,急性痛とは異なるアプローチが必要となりますが,そもそも小児領域では急性痛,慢性痛という概念すら十分に浸透していない状況です。慢性痛は心理的苦痛や社会的影響を伴い,子どもたちの生活の質に深刻な影響を及ぼす可能性があり,生物心理社会的(biopsychosocial)アプローチが必要となります。3〜4人に1人が経験するとされ決してまれでない慢性痛は,小児プライマリケア診療においても重要な領域ですが,体系立って学ぶ機会が少なく,本書の役割は大きいといえます。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P. - P.
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1080 - P.1080
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1081 - P.1081
奥付 フリーアクセス
ページ範囲:P.1086 - P.1086
基本情報
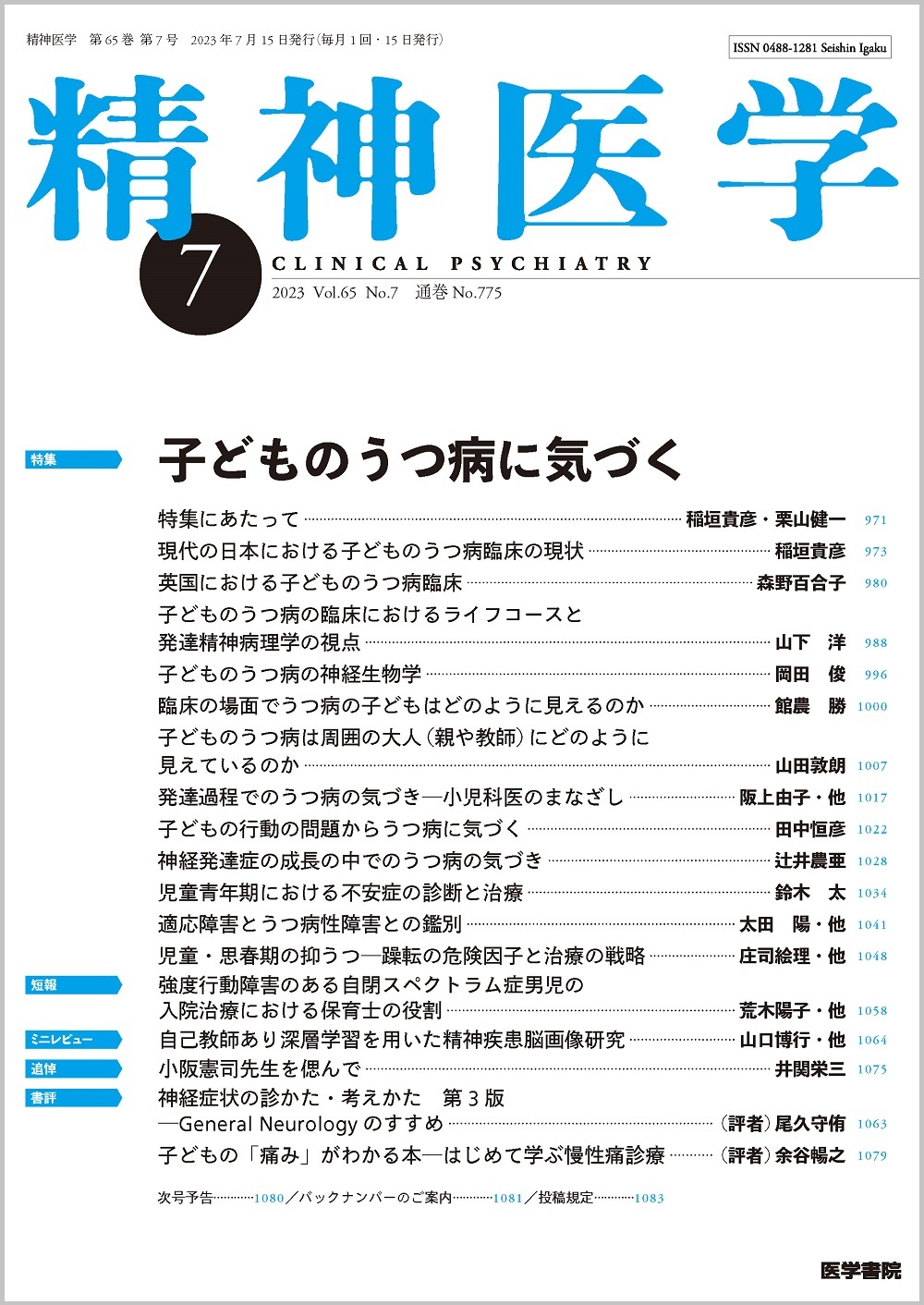
バックナンバー
66巻12号(2024年12月発行)
特集 「治療を終える」に向き合う
66巻11号(2024年11月発行)
特集 「難治例」の臨床—治療に難渋する時の診断,治療,そして予防
66巻10号(2024年10月発行)
特集 不登校の理解と支援
66巻9号(2024年9月発行)
特集 —身体疾患の患者・家族のこころを支える—コンサルテーション・リエゾン精神医学
66巻8号(2024年8月発行)
特集 現代における解離—診断概念の変遷を踏まえ臨床的な理解を深める
66巻7号(2024年7月発行)
特集 アディクション—コロナ禍で変わったこと,変わらないこと
66巻6号(2024年6月発行)
特集 精神疾患の気づきと病識
66巻5号(2024年5月発行)
増大号特集 精神科診療における臨床評価尺度・検査を極める—エキスパートによる実践的活用法
66巻4号(2024年4月発行)
特集 精神疾患・精神症状にはどこまで脳器質的背景があるのか—現代の視点から見直す
66巻3号(2024年3月発行)
特集 精神疾患への栄養学的アプローチ
66巻2号(2024年2月発行)
特集 うつ病のバイオマーカー開発の試み
66巻1号(2024年1月発行)
特集 性差と精神医学—なぜ頻度や重症度に差があるのか
65巻12号(2023年12月発行)
特集 精神科領域の専門資格—どうやって取得し,どのように臨床へ活かすか
65巻11号(2023年11月発行)
特集 精神疾患回復の時間経過を見通す
65巻10号(2023年10月発行)
特集 DSM-5からDSM-5-TRへ—何が変わったのか
65巻9号(2023年9月発行)
特集 拡がり続ける摂食障害(摂食症)—一般化とともに拡散・難治化する精神病理にどう対処するか
65巻8号(2023年8月発行)
特集 複雑性PTSDの臨床
65巻7号(2023年7月発行)
特集 子どものうつ病に気づく
65巻6号(2023年6月発行)
特集 精神科医療の必須検査—精神科医が知っておきたい臨床検査の最前線
65巻5号(2023年5月発行)
増大号特集 いま,知っておきたい発達障害 Q&A 98
65巻4号(2023年4月発行)
特集 わが国の若手による統合失調症研究最前線
65巻3号(2023年3月発行)
特集 災害精神医学—自然災害,人為災害,感染症パンデミックとこころのケア
65巻2号(2023年2月発行)
特集 精神医療・精神医学の組織文化のパラダイムシフト
65巻1号(2023年1月発行)
特集 精神医学における臨床研究のすゝめ—わが国で行われたさまざまな精神医学臨床研究を参考にして
64巻12号(2022年12月発行)
特集 死別にまつわる心理的苦痛—背景理論からケアおよびマネジメントまで
64巻11号(2022年11月発行)
特集 ひきこもりの理解と支援
64巻10号(2022年10月発行)
特集 精神・神経疾患に併存する過眠の背景病態と治療マネジメント
64巻9号(2022年9月発行)
特集 学校で精神疾患を「自分のこと」として教育する
64巻8号(2022年8月発行)
特集 ジェンダーをめぐる諸課題を理解する
64巻7号(2022年7月発行)
特集 Withコロナ時代の精神医学教育の進歩—卒前教育から生涯教育まで
64巻6号(2022年6月発行)
特集 認知症診療の新潮流—近未来の認知症診療に向けて
64巻5号(2022年5月発行)
増大号特集 精神科診療のピットフォール
64巻4号(2022年4月発行)
特集 家族支援を考える
64巻3号(2022年3月発行)
特集 精神神経疾患の治療とQOL
64巻2号(2022年2月発行)
特集 精神科におけるオンライン診療
64巻1号(2022年1月発行)
特集 超高齢期の精神疾患
63巻12号(2021年12月発行)
特集 うつ病のニューロモデュレーション治療の新展開
63巻11号(2021年11月発行)
特集 「実感と納得」に向けた病気と治療の伝え方
63巻10号(2021年10月発行)
特集 統合失調症の心理社会的治療—どのように使い分け,効果を最大化するか
63巻9号(2021年9月発行)
特集 産業精神保健の現状と課題
63巻8号(2021年8月発行)
特集 認知症診療における精神科医の役割を再考する
63巻7号(2021年7月発行)
特集 自殺の現状と予防対策—COVID-19の影響も含めて
63巻6号(2021年6月発行)
特集 強迫についてあらためて考える
63巻5号(2021年5月発行)
増大号特集 精神科クリニカル・パール—先達に学ぶ
63巻4号(2021年4月発行)
特集 精神医療に関する疫学のトピック—記述疫学,リスク研究からコホート研究まで
63巻3号(2021年3月発行)
特集 サイコーシスとは何か—概念,病態生理,診断・治療における意義
63巻2号(2021年2月発行)
特集 いじめと精神医学
63巻1号(2021年1月発行)
特集 新型コロナウイルス感染症ただなかの精神医療
62巻12号(2020年12月発行)
特集 身体症状症の病態と治療—器質因がはっきりしない身体症状をどう扱うか?
62巻11号(2020年11月発行)
特集 若年性認知症の疫学・臨床・社会支援
62巻10号(2020年10月発行)
特集 精神科臨床における共同意思決定(SDM)
62巻9号(2020年9月発行)
特集 周産期メンタルヘルスの今
62巻8号(2020年8月発行)
特集 精神科医療における病名告知—伝えるか,伝えるべきでないか?伝えるなら,いつ,どのように伝えるか?
62巻7号(2020年7月発行)
特集 「大人の発達障害」をめぐる最近の動向
62巻6号(2020年6月発行)
特集 精神科診断分類の背景にある考え方
62巻5号(2020年5月発行)
増大号特集 精神科診療のエビデンス—国内外の重要ガイドライン解説
62巻4号(2020年4月発行)
特集 ベンゾジアゼピン受容体作動薬の問題点と適正使用
62巻3号(2020年3月発行)
特集 精神医学・医療の未来を拓く人材育成
62巻2号(2020年2月発行)
特集 発達障害と認知症をめぐって
62巻1号(2020年1月発行)
特集 SUN☺D臨床試験のインパクト—日本初の医師主導型抗うつ薬大規模臨床試験から学ぶ
61巻12号(2019年12月発行)
特集 精神疾患における病識・疾病認識—治療における意義
61巻11号(2019年11月発行)
特集 医療現場での怒り—どのように評価しどのように対応するべきか
61巻10号(2019年10月発行)
特集 トラウマインフォームドケアと小児期逆境体験
61巻9号(2019年9月発行)
特集 高齢者の精神科救急・急性期医療
61巻8号(2019年8月発行)
特集 光と精神医学
61巻7号(2019年7月発行)
特集 今再び問う,内因性精神疾患と心因性精神疾患の概念
61巻6号(2019年6月発行)
特集 マインドフルネス療法は他の精神療法と何が違うのか?
61巻5号(2019年5月発行)
特集 精神医学における主観と主体
61巻4号(2019年4月発行)
特集 統合失調症の治療ゴールをめぐって
61巻3号(2019年3月発行)
特集 ICD-11のチェックポイント
61巻2号(2019年2月発行)
オピニオン パーソナリティ障害の現在
61巻1号(2019年1月発行)
特集 高齢者のメンタルヘルス
60巻12号(2018年12月発行)
特集 精神科臨床から何を学び,何を継承し,精神医学を改革・改良できたか(Ⅱ)
60巻11号(2018年11月発行)
特集 精神科臨床から何を学び,何を継承し,精神医学を改革・改良できたか(Ⅰ)
60巻10号(2018年10月発行)
特集 こころの発達の問題に関する“古典”をふりかえる
60巻9号(2018年9月発行)
特集 不眠症の治療と睡眠薬
60巻8号(2018年8月発行)
特集 作業療法を活用するには
60巻7号(2018年7月発行)
特集 双極Ⅱ型をめぐる諸問題
60巻6号(2018年6月発行)
特集 医療・医学の課題としての身体合併症
60巻5号(2018年5月発行)
特集 サイコオンコロジー
60巻4号(2018年4月発行)
特集 精神科診療におけるてんかん
60巻3号(2018年3月発行)
特集 せん妄をめぐる最近の動向
60巻2号(2018年2月発行)
特集 多様なアディクションとその対応
60巻1号(2018年1月発行)
特集 Research Domain Criteria(RDoC)プロジェクトの目指す新たな精神医学診断・評価システム
59巻12号(2017年12月発行)
特集 「統合失調症」再考(Ⅱ)
59巻11号(2017年11月発行)
特集 「統合失調症」再考(Ⅰ)
59巻10号(2017年10月発行)
59巻9号(2017年9月発行)
特集 精神疾患の生物学的診断指標—現状と開発研究の展望
59巻8号(2017年8月発行)
特集 国連障害者権利条約と権利ベースのアプローチ
59巻7号(2017年7月発行)
特集 MRIのT2・FLAIR画像での白質高信号の意味を読み解く
59巻6号(2017年6月発行)
特集 精神医学と睡眠学の接点
59巻5号(2017年5月発行)
特集 認知行動療法の現在とこれから—医療現場への普及と質の確保に向けて
59巻4号(2017年4月発行)
特集 改正道路交通法と医療の視点
59巻3号(2017年3月発行)
特集 ADHDをめぐる最近の動向
59巻2号(2017年2月発行)
オピニオン 精神科医にとっての薬物療法の意味
59巻1号(2017年1月発行)
特集 インターネット依存の現在
58巻12号(2016年12月発行)
58巻11号(2016年11月発行)
特集 認知症の人の認知機能障害,生活障害,行動・心理症状の構造
58巻10号(2016年10月発行)
58巻9号(2016年9月発行)
特集 精神科臨床にみる家庭・家族の現在—何が変わり何が変わらないのか?
58巻8号(2016年8月発行)
58巻7号(2016年7月発行)
特集 精神疾患の予防と早期治療アップデート
58巻6号(2016年6月発行)
58巻5号(2016年5月発行)
特集 成人の自閉スペクトラム症とライフステージの課題
58巻4号(2016年4月発行)
58巻3号(2016年3月発行)
58巻2号(2016年2月発行)
特集 妊娠・出産・育児とメンタルヘルスケア
58巻1号(2016年1月発行)
特集 社会認知研究の最近の動向
57巻12号(2015年12月発行)
57巻11号(2015年11月発行)
シンポジウム 家族と当事者からみた精神科医療・精神医学
57巻10号(2015年10月発行)
特集 精神医学と神経学の境界領域—最近のトピックスから
57巻9号(2015年9月発行)
特集 統合失調症の認知機能障害の臨床的意義
57巻8号(2015年8月発行)
オピニオン DSM-5—私はこう思う
57巻7号(2015年7月発行)
特集 自殺対策の現状
57巻6号(2015年6月発行)
57巻5号(2015年5月発行)
57巻4号(2015年4月発行)
特集 リエゾン精神医学の現状と今後の展望(Ⅱ)
57巻3号(2015年3月発行)
特集 リエゾン精神医学の現状と今後の展望(Ⅰ)
57巻2号(2015年2月発行)
57巻1号(2015年1月発行)
特集 今後の産業精神保健の課題—近年の行政施策の動向をふまえて
56巻12号(2014年12月発行)
56巻11号(2014年11月発行)
56巻10号(2014年10月発行)
特集 良質かつ適切な医療の提供—改正精神保健福祉法41条の具体化
56巻9号(2014年9月発行)
特集 うつ病の早期介入,予防(Ⅱ)
56巻8号(2014年8月発行)
特集 うつ病の早期介入,予防(Ⅰ)
56巻7号(2014年7月発行)
56巻6号(2014年6月発行)
56巻5号(2014年5月発行)
特集 大学生とメンタルヘルス―保健管理センターのチャレンジ
56巻4号(2014年4月発行)
56巻3号(2014年3月発行)
56巻2号(2014年2月発行)
56巻1号(2014年1月発行)
55巻12号(2013年12月発行)
55巻11号(2013年11月発行)
特集 アンチスティグマ活動の新しい転機Ⅱ
55巻10号(2013年10月発行)
特集 アンチスティグマ活動の新しい転機Ⅰ
55巻9号(2013年9月発行)
オピニオン 精神科医にとっての精神療法の意味
55巻8号(2013年8月発行)
特集 職場のメンタルヘルスと復職支援─その効果的な利用のために
55巻7号(2013年7月発行)
55巻6号(2013年6月発行)
55巻5号(2013年5月発行)
55巻4号(2013年4月発行)
55巻3号(2013年3月発行)
特集 SST最近の進歩と広がり
55巻2号(2013年2月発行)
55巻1号(2013年1月発行)
54巻12号(2012年12月発行)
54巻11号(2012年11月発行)
特集 アルコール・薬物関連障害
54巻10号(2012年10月発行)
特集 医療法に基づく精神疾患の地域医療計画策定
54巻9号(2012年9月発行)
54巻8号(2012年8月発行)
54巻7号(2012年7月発行)
54巻6号(2012年6月発行)
54巻5号(2012年5月発行)
54巻4号(2012年4月発行)
オピニオン マインドフルネス/アクセプタンス認知行動療法と森田療法
54巻3号(2012年3月発行)
オピニオン 認知症の終末期医療の対応:現状と課題―尊厳をどう守るか
54巻2号(2012年2月発行)
特集 障害者権利条約批准に係る国内法の整備:今後の精神科医療改革への萌芽
54巻1号(2012年1月発行)
53巻12号(2011年12月発行)
シンポジウム 精神医学研究の到達点と展望
53巻11号(2011年11月発行)
特集 震災時の避難大作戦:精神科編
53巻10号(2011年10月発行)
特集 裁判員制度と精神鑑定
53巻9号(2011年9月発行)
53巻8号(2011年8月発行)
特集 性同一性障害(GID)
53巻7号(2011年7月発行)
53巻6号(2011年6月発行)
53巻5号(2011年5月発行)
特集 成人てんかんの国際分類と医療の現状
53巻4号(2011年4月発行)
シンポジウム 気分障害の生物学的研究の最新動向─DSM,ICD改訂に向けて
53巻3号(2011年3月発行)
53巻2号(2011年2月発行)
特集 統合失調症の予後改善に向けての新たな戦略
53巻1号(2011年1月発行)
52巻12号(2010年12月発行)
52巻11号(2010年11月発行)
52巻10号(2010年10月発行)
特集 高次脳機能障害をめぐって
52巻9号(2010年9月発行)
52巻8号(2010年8月発行)
52巻7号(2010年7月発行)
52巻6号(2010年6月発行)
52巻5号(2010年5月発行)
特集 児童期における精神疾患の非定型性―成人期の精神疾患と対比して
52巻4号(2010年4月発行)
特集 内因性精神疾患の死後脳研究
52巻3号(2010年3月発行)
特集 総合病院精神科衰退の危機と総合病院精神医学会の果たすべき役割
52巻2号(2010年2月発行)
52巻1号(2010年1月発行)
51巻12号(2009年12月発行)
51巻11号(2009年11月発行)
特集 現代の自殺をめぐる話題
51巻10号(2009年10月発行)
特集 若年性認知症をめぐる諸問題
51巻9号(2009年9月発行)
51巻8号(2009年8月発行)
51巻7号(2009年7月発行)
特集 精神疾患と睡眠マネージメント―最新の知見
51巻6号(2009年6月発行)
51巻5号(2009年5月発行)
51巻4号(2009年4月発行)
シンポジウム うつ病と自殺に医師はどう対応するのか―医師臨床研修並びに生涯研修における精神科の役割
51巻3号(2009年3月発行)
特集 社会脳をめぐって
51巻2号(2009年2月発行)
シンポジウム 統合失調症の脳科学
51巻1号(2009年1月発行)
50巻12号(2008年12月発行)
特集 Assertive Community Treatment(ACT)は日本の地域精神医療の柱になれるか?
50巻11号(2008年11月発行)
50巻10号(2008年10月発行)
50巻9号(2008年9月発行)
50巻8号(2008年8月発行)
特集 成人期のアスペルガー症候群・Ⅱ
50巻7号(2008年7月発行)
特集 成人期のアスペルガー症候群・Ⅰ
50巻6号(2008年6月発行)
特集 疲労と精神障害―ストレス-疲労-精神障害について
50巻5号(2008年5月発行)
50巻4号(2008年4月発行)
50巻3号(2008年3月発行)
特集 精神疾患に対する早期介入の現状と将来
50巻2号(2008年2月発行)
50巻1号(2008年1月発行)
特集 精神医学的コミュニケーションとは何か―精神科専門医を目指す人のために
49巻12号(2007年12月発行)
49巻11号(2007年11月発行)
シンポジウム ストレスと精神生物学―新しい診断法を目指して
49巻10号(2007年10月発行)
49巻9号(2007年9月発行)
特集 「緩和ケアチーム」―精神科医に期待すること,精神科医ができること
49巻8号(2007年8月発行)
49巻7号(2007年7月発行)
特集 レビー小体型認知症をめぐって
49巻6号(2007年6月発行)
49巻5号(2007年5月発行)
特集 睡眠と精神医学:「睡眠精神医学」の推進
49巻4号(2007年4月発行)
49巻3号(2007年3月発行)
特集 統合失調症と感情障害の補助診断法の最近の進歩
49巻2号(2007年2月発行)
49巻1号(2007年1月発行)
シンポジウム 児童思春期の攻撃性・衝動性の理解と援助-ライフサイクルの視点から考える
48巻12号(2006年12月発行)
シンポジウム 気分障害治療の新たな展開
48巻11号(2006年11月発行)
48巻10号(2006年10月発行)
48巻9号(2006年9月発行)
特集 新医師臨床研修制度に基づく精神科ローテート研修の評価
48巻8号(2006年8月発行)
48巻7号(2006年7月発行)
48巻6号(2006年6月発行)
特集 オグメンテーション療法か,多剤併用療法か
48巻5号(2006年5月発行)
シンポジウム MCIとLNTDをめぐって
48巻4号(2006年4月発行)
48巻3号(2006年3月発行)
特集 災害精神医学の10年―経験から学ぶ
48巻2号(2006年2月発行)
48巻1号(2006年1月発行)
47巻12号(2005年12月発行)
シンポジウム 精神医療システムの改革:その理念とエビデンス
47巻11号(2005年11月発行)
特集 電気けいれん療法
47巻10号(2005年10月発行)
47巻9号(2005年9月発行)
47巻8号(2005年8月発行)
特集 リエゾン精神医学の現状と課題
47巻7号(2005年7月発行)
47巻6号(2005年6月発行)
47巻5号(2005年5月発行)
47巻4号(2005年4月発行)
47巻3号(2005年3月発行)
47巻2号(2005年2月発行)
特集 時代による精神疾患の病像変化
47巻1号(2005年1月発行)
46巻12号(2004年12月発行)
46巻11号(2004年11月発行)
46巻10号(2004年10月発行)
特集 精神科医療における介護保険制度
46巻9号(2004年9月発行)
46巻8号(2004年8月発行)
シンポジウム 精神障害治療の新展開
46巻7号(2004年7月発行)
46巻6号(2004年6月発行)
特集 精神科医療における危機介入
46巻5号(2004年5月発行)
46巻4号(2004年4月発行)
46巻3号(2004年3月発行)
46巻2号(2004年2月発行)
46巻1号(2004年1月発行)
特集 臨床心理技術者の国家資格化についての主張
45巻12号(2003年12月発行)
特集 統合失調症と認知機能―最近の話題
45巻11号(2003年11月発行)
特集 ICFと精神医学
45巻10号(2003年10月発行)
特集 新医師臨床研修制度における精神科研修はどうあるべきか
45巻9号(2003年9月発行)
45巻8号(2003年8月発行)
シンポジウム 痴呆症とパーキンソン病研究の新展開―原因分子の発見をてがかりとして
45巻7号(2003年7月発行)
45巻6号(2003年6月発行)
特集 統合失調症とは何か―Schizophrenia概念の変遷
45巻5号(2003年5月発行)
45巻4号(2003年4月発行)
特集 新医師臨床研修制度の課題―求められる医師像と精神科卒後教育の役割
45巻3号(2003年3月発行)
特集 ひきこもりの病理と診断・治療
45巻2号(2003年2月発行)
45巻1号(2003年1月発行)
44巻12号(2002年12月発行)
シンポジウム WHO精神保健レポートと日本の課題
44巻11号(2002年11月発行)
特集 精神疾患の脳画像解析と臨床応用の将来
44巻10号(2002年10月発行)
44巻9号(2002年9月発行)
44巻8号(2002年8月発行)
特集 精神疾患と認知機能
44巻7号(2002年7月発行)
特別企画 WPA 2002 横浜大会に期待する
44巻6号(2002年6月発行)
特集 司法精神医学の今日的課題
44巻5号(2002年5月発行)
44巻4号(2002年4月発行)
44巻3号(2002年3月発行)
特集 新しい向精神薬の薬理・治療
44巻2号(2002年2月発行)
44巻1号(2002年1月発行)
43巻12号(2001年12月発行)
43巻11号(2001年11月発行)
特集 青少年犯罪と精神医学
43巻10号(2001年10月発行)
シンポジウム 精神分裂病の心理社会的治療の進歩
43巻9号(2001年9月発行)
43巻8号(2001年8月発行)
43巻7号(2001年7月発行)
43巻6号(2001年6月発行)
特集 社会構造の変化と高齢者問題
43巻5号(2001年5月発行)
特別企画 薬物依存者に対する精神保健・精神科医療体制
43巻4号(2001年4月発行)
43巻3号(2001年3月発行)
43巻2号(2001年2月発行)
特集 今,なぜ病跡学か
43巻1号(2001年1月発行)
42巻12号(2000年12月発行)
シンポジウム ライフサイクルと睡眠障害
42巻11号(2000年11月発行)
42巻10号(2000年10月発行)
特集 職場の精神保健
42巻9号(2000年9月発行)
42巻8号(2000年8月発行)
42巻7号(2000年7月発行)
42巻6号(2000年6月発行)
42巻5号(2000年5月発行)
特集 精神疾患の発病規定因子
42巻4号(2000年4月発行)
42巻3号(2000年3月発行)
特別企画 精神医学,医療の将来
42巻2号(2000年2月発行)
シンポジウム 新しい精神医学の構築—21世紀への展望
42巻1号(2000年1月発行)
41巻12号(1999年12月発行)
特集 児童精神科医療の課題
41巻11号(1999年11月発行)
41巻10号(1999年10月発行)
41巻9号(1999年9月発行)
41巻8号(1999年8月発行)
41巻7号(1999年7月発行)
41巻6号(1999年6月発行)
特集 治療抵抗性の精神障害とその対応
41巻5号(1999年5月発行)
41巻4号(1999年4月発行)
41巻3号(1999年3月発行)
41巻2号(1999年2月発行)
41巻1号(1999年1月発行)
特集 記憶障害の臨床
40巻12号(1998年12月発行)
シンポジウム がん,臓器移植とリエゾン精神医学—チーム医療における心のケア
40巻11号(1998年11月発行)
40巻10号(1998年10月発行)
40巻9号(1998年9月発行)
40巻8号(1998年8月発行)
シンポジウム 災害のもたらすもの—阪神・淡路大震災復興期のメンタルヘルス
40巻7号(1998年7月発行)
40巻6号(1998年6月発行)
40巻5号(1998年5月発行)
特集 アジアにおける最近の精神医学事情
40巻4号(1998年4月発行)
40巻3号(1998年3月発行)
40巻2号(1998年2月発行)
特集 精神病像を伴う躁うつ病および分裂感情障害の位置づけ—生物学的マーカーと診断・治療
40巻1号(1998年1月発行)
39巻12号(1997年12月発行)
39巻11号(1997年11月発行)
特集 精神科における合理的薬物選択アルゴリズム
39巻10号(1997年10月発行)
39巻9号(1997年9月発行)
39巻8号(1997年8月発行)
シンポジウム スーパービジョンとコンサルテーション—地域精神医療の方法
39巻7号(1997年7月発行)
39巻6号(1997年6月発行)
39巻5号(1997年5月発行)
特集 学校精神保健—教育との連携の実際
39巻4号(1997年4月発行)
39巻3号(1997年3月発行)
39巻2号(1997年2月発行)
39巻1号(1997年1月発行)
38巻12号(1996年12月発行)
シンポジウム 痴呆の薬物療法の最前線—向知性薬の臨床と基礎
38巻11号(1996年11月発行)
特集 精神医学における分子生物学的研究
38巻10号(1996年10月発行)
38巻9号(1996年9月発行)
38巻8号(1996年8月発行)
38巻7号(1996年7月発行)
38巻6号(1996年6月発行)
38巻5号(1996年5月発行)
特集 精神病理学の方法論—記述か計量か
38巻4号(1996年4月発行)
38巻3号(1996年3月発行)
38巻2号(1996年2月発行)
38巻1号(1996年1月発行)
37巻12号(1995年12月発行)
37巻11号(1995年11月発行)
37巻10号(1995年10月発行)
37巻9号(1995年9月発行)
37巻8号(1995年8月発行)
特集 外来精神科医療の現状と課題
37巻7号(1995年7月発行)
特集 阪神・淡路大震災—現場からの報告
37巻6号(1995年6月発行)
37巻5号(1995年5月発行)
37巻4号(1995年4月発行)
37巻3号(1995年3月発行)
37巻2号(1995年2月発行)
37巻1号(1995年1月発行)
特集 分裂病者の社会復帰—新しい展開
36巻12号(1994年12月発行)
シンポジウム アルツハイマー型痴呆の診断をめぐって
36巻11号(1994年11月発行)
36巻10号(1994年10月発行)
36巻9号(1994年9月発行)
36巻8号(1994年8月発行)
36巻7号(1994年7月発行)
36巻6号(1994年6月発行)
特集 精神医学と生物科学のクロストーク
36巻5号(1994年5月発行)
特集 精神疾患の新しい診断分類
36巻4号(1994年4月発行)
36巻3号(1994年3月発行)
36巻2号(1994年2月発行)
36巻1号(1994年1月発行)
特集 精神科治療の奏効機序
35巻12号(1993年12月発行)
35巻11号(1993年11月発行)
35巻10号(1993年10月発行)
35巻9号(1993年9月発行)
35巻8号(1993年8月発行)
シンポジウム 精神障害者の権利と能力—精神医学的倫理のジレンマ
35巻7号(1993年7月発行)
35巻6号(1993年6月発行)
35巻5号(1993年5月発行)
35巻4号(1993年4月発行)
特集 現代日本の社会精神病理
35巻3号(1993年3月発行)
35巻2号(1993年2月発行)
特集 加齢に関する精神医学的な問題
35巻1号(1993年1月発行)
34巻12号(1992年12月発行)
特集 精神科領域におけるインフォームド・コンセント
34巻11号(1992年11月発行)
34巻10号(1992年10月発行)
34巻9号(1992年9月発行)
34巻8号(1992年8月発行)
特集 薬物依存の臨床
34巻7号(1992年7月発行)
34巻6号(1992年6月発行)
34巻5号(1992年5月発行)
34巻4号(1992年4月発行)
34巻3号(1992年3月発行)
シンポジウム 境界例の診断と治療
34巻2号(1992年2月発行)
34巻1号(1992年1月発行)
33巻12号(1991年12月発行)
特集 不安の病理
33巻11号(1991年11月発行)
33巻10号(1991年10月発行)
33巻9号(1991年9月発行)
33巻8号(1991年8月発行)
33巻7号(1991年7月発行)
33巻6号(1991年6月発行)
33巻5号(1991年5月発行)
33巻4号(1991年4月発行)
33巻3号(1991年3月発行)
33巻2号(1991年2月発行)
特集 精神科領域におけるレセプター機能の研究の進歩
33巻1号(1991年1月発行)
32巻12号(1990年12月発行)
シンポジウム 「うつ」と睡眠
32巻11号(1990年11月発行)
32巻10号(1990年10月発行)
32巻9号(1990年9月発行)
32巻8号(1990年8月発行)
特集 精神疾患の現代的病像をめぐって
32巻7号(1990年7月発行)
32巻6号(1990年6月発行)
特集 精神分裂病の生物学的研究
32巻5号(1990年5月発行)
32巻4号(1990年4月発行)
32巻3号(1990年3月発行)
特集 向精神薬の見逃されやすい副作用と対策
32巻2号(1990年2月発行)
32巻1号(1990年1月発行)
31巻12号(1989年12月発行)
31巻11号(1989年11月発行)
31巻10号(1989年10月発行)
シンポジウム 精神障害者の責任能力
31巻9号(1989年9月発行)
31巻8号(1989年8月発行)
31巻7号(1989年7月発行)
31巻6号(1989年6月発行)
特集 現代社会と家族—諸病態との関連から
31巻5号(1989年5月発行)
31巻4号(1989年4月発行)
31巻3号(1989年3月発行)
31巻2号(1989年2月発行)
31巻1号(1989年1月発行)
特集 サーカディアンリズム—基礎から臨床へ
30巻12号(1988年12月発行)
30巻11号(1988年11月発行)
シンポジウム 痴呆とパーキンソニズム
30巻10号(1988年10月発行)
30巻9号(1988年9月発行)
特集 世界の精神科医療の動向
30巻8号(1988年8月発行)
30巻7号(1988年7月発行)
30巻6号(1988年6月発行)
シンポジウム 地域ケアと精神保健
30巻5号(1988年5月発行)
30巻4号(1988年4月発行)
創刊30周年記念特集 精神医学—最近の進歩 第2部
30巻3号(1988年3月発行)
創刊30周年記念特集 精神医学—最近の進歩 第1部
30巻2号(1988年2月発行)
30巻1号(1988年1月発行)
29巻12号(1987年12月発行)
特集 躁うつ病とセロトニン
29巻11号(1987年11月発行)
29巻10号(1987年10月発行)
29巻9号(1987年9月発行)
29巻8号(1987年8月発行)
29巻7号(1987年7月発行)
29巻6号(1987年6月発行)
29巻5号(1987年5月発行)
29巻4号(1987年4月発行)
29巻3号(1987年3月発行)
29巻2号(1987年2月発行)
29巻1号(1987年1月発行)
特集 老年精神医学
28巻12号(1986年12月発行)
28巻11号(1986年11月発行)
特集 脳の働きと心―大脳の機能をめぐって
28巻10号(1986年10月発行)
28巻9号(1986年9月発行)
28巻8号(1986年8月発行)
28巻7号(1986年7月発行)
28巻6号(1986年6月発行)
28巻5号(1986年5月発行)
28巻4号(1986年4月発行)
28巻3号(1986年3月発行)
28巻2号(1986年2月発行)
特集 現代の子供—心身の発達とその病理—東京都精神医学総合研究所 第13回シンボジウムから
28巻1号(1986年1月発行)
27巻12号(1985年12月発行)
特集 摂食障害の心理と治療
27巻11号(1985年11月発行)
27巻10号(1985年10月発行)
27巻9号(1985年9月発行)
27巻8号(1985年8月発行)
27巻7号(1985年7月発行)
27巻6号(1985年6月発行)
特集 前頭葉の神経心理学
27巻5号(1985年5月発行)
特集 精神分裂病の成因と治療—東京都精神医学総合研究所 第12回シンポジウムから
27巻4号(1985年4月発行)
27巻3号(1985年3月発行)
27巻2号(1985年2月発行)
特集 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome)―その病態と臨床
27巻1号(1985年1月発行)
26巻12号(1984年12月発行)
26巻11号(1984年11月発行)
26巻10号(1984年10月発行)
26巻9号(1984年9月発行)
26巻8号(1984年8月発行)
26巻7号(1984年7月発行)
特集 側頭葉障害における言語症状
26巻6号(1984年6月発行)
26巻5号(1984年5月発行)
26巻4号(1984年4月発行)
26巻3号(1984年3月発行)
26巻2号(1984年2月発行)
特集 DSM-III—その有用性と問題点
26巻1号(1984年1月発行)
特集 精神疾患に対する神経内分泌的アプローチ
25巻12号(1983年12月発行)
特集 カルバマゼピンの向精神作用
25巻11号(1983年11月発行)
25巻10号(1983年10月発行)
特集 少年非行の心理と病理—東京都精神医学総合研究所 第11回シンポジウムから
25巻9号(1983年9月発行)
25巻8号(1983年8月発行)
特集 児童精神医学の現状と将来—都立梅ケ丘病院30周年記念シンポジウムから
25巻7号(1983年7月発行)
25巻6号(1983年6月発行)
25巻5号(1983年5月発行)
25巻4号(1983年4月発行)
特集 聴覚失認
25巻3号(1983年3月発行)
特集 精神医学における病態モデル
25巻2号(1983年2月発行)
特集 薬物と睡眠をめぐって
25巻1号(1983年1月発行)
24巻12号(1982年12月発行)
特集 アルコール依存症の精神医学—東京都精神医学総合研究所 第10回シンポジウムから
24巻11号(1982年11月発行)
24巻10号(1982年10月発行)
特集 精神科診療所をめぐる諸問題
24巻9号(1982年9月発行)
24巻8号(1982年8月発行)
24巻7号(1982年7月発行)
24巻6号(1982年6月発行)
24巻5号(1982年5月発行)
24巻4号(1982年4月発行)
特集 視覚失認
24巻3号(1982年3月発行)
24巻2号(1982年2月発行)
特集 リチウムの臨床と基礎—最近の話題
24巻1号(1982年1月発行)
23巻12号(1981年12月発行)
23巻11号(1981年11月発行)
特集 Ⅱ.アジアにおける精神衛生問題
23巻10号(1981年10月発行)
特集 失行
23巻9号(1981年9月発行)
23巻8号(1981年8月発行)
23巻7号(1981年7月発行)
特集 てんかんのメカニズムと治療—東京都精神医学総合研究所 第8回シンポジウムから
23巻6号(1981年6月発行)
23巻5号(1981年5月発行)
23巻4号(1981年4月発行)
23巻3号(1981年3月発行)
23巻2号(1981年2月発行)
23巻1号(1981年1月発行)
22巻12号(1980年12月発行)
特集 躁うつ病の生物学
22巻11号(1980年11月発行)
特集 Butyrophenone系抗精神病薬の臨床精神薬理学
22巻10号(1980年10月発行)
特集 日本精神医学と松沢病院
22巻9号(1980年9月発行)
22巻8号(1980年8月発行)
特集 思春期の精神医学的諸問題—東京都精神医学総合研究所 第7回シンポジウムから
22巻7号(1980年7月発行)
特集 Brain Function Testへのアプローチ
22巻6号(1980年6月発行)
22巻5号(1980年5月発行)
特集 睡眠研究—最近の進歩
22巻4号(1980年4月発行)
22巻3号(1980年3月発行)
22巻2号(1980年2月発行)
特集 向精神薬をめぐる最近の諸問題
22巻1号(1980年1月発行)
特集 幻覚
21巻12号(1979年12月発行)
21巻11号(1979年11月発行)
特集 精神分裂病の生物学
21巻10号(1979年10月発行)
21巻9号(1979年9月発行)
21巻8号(1979年8月発行)
特集 老人の精神障害—東京都精神医学総合研究所,第6回シンポジウムから
21巻7号(1979年7月発行)
特集 精神分裂病の遺伝因と環境因
21巻6号(1979年6月発行)
特集 創刊20周年記念 第2部
21巻5号(1979年5月発行)
特集 創刊20周年記念 第1部
21巻4号(1979年4月発行)
21巻3号(1979年3月発行)
21巻2号(1979年2月発行)
特集 妄想
21巻1号(1979年1月発行)
20巻12号(1978年12月発行)
特集 精神鑑定
20巻11号(1978年11月発行)
20巻10号(1978年10月発行)
シンポジウム 精神分裂病者の治療について—東京都精神医学総合研究所,第5回シンポジウムから
20巻9号(1978年9月発行)
20巻8号(1978年8月発行)
20巻7号(1978年7月発行)
20巻6号(1978年6月発行)
20巻5号(1978年5月発行)
20巻4号(1978年4月発行)
20巻3号(1978年3月発行)
20巻2号(1978年2月発行)
20巻1号(1978年1月発行)
19巻12号(1977年12月発行)
特集 青年期の精神病理
19巻11号(1977年11月発行)
シンポジウム こころとからだ—東京都精神医学総合研究所,第4回シンポジウムから
19巻10号(1977年10月発行)
19巻9号(1977年9月発行)
19巻8号(1977年8月発行)
特集 在宅精神医療(2)—社会復帰活動とその周辺
19巻7号(1977年7月発行)
19巻6号(1977年6月発行)
19巻5号(1977年5月発行)
19巻4号(1977年4月発行)
特集 精神分裂病の精神生理学
19巻3号(1977年3月発行)
19巻2号(1977年2月発行)
シンポジウム 生のリズムとその障害—東京都精神医学総合研究所,第3回シンポジウムから
19巻1号(1977年1月発行)
18巻12号(1976年12月発行)
特集 近代日本の宗教と精神医学
18巻11号(1976年11月発行)
18巻10号(1976年10月発行)
18巻9号(1976年9月発行)
18巻8号(1976年8月発行)
18巻7号(1976年7月発行)
18巻6号(1976年6月発行)
特集 在宅精神医療—日常生活における指導と治療
18巻5号(1976年5月発行)
シンポジウム 大都市の病理と精神障害—東京都精神医学総合研究所第2回シンポジウムから
18巻4号(1976年4月発行)
18巻3号(1976年3月発行)
18巻2号(1976年2月発行)
18巻1号(1976年1月発行)
17巻13号(1975年12月発行)
臨時増刊号特集 精神医学における日本的特性
17巻12号(1975年12月発行)
17巻11号(1975年11月発行)
17巻10号(1975年10月発行)
17巻9号(1975年9月発行)
17巻8号(1975年8月発行)
17巻7号(1975年7月発行)
17巻6号(1975年6月発行)
17巻5号(1975年5月発行)
17巻4号(1975年4月発行)
17巻3号(1975年3月発行)
17巻2号(1975年2月発行)
17巻1号(1975年1月発行)
16巻12号(1974年12月発行)
16巻11号(1974年11月発行)
シンポジウム 現代における精神医学研究の課題—東京都精神医学総合研究所開設記念シンポジウムから
16巻10号(1974年10月発行)
16巻9号(1974年9月発行)
16巻7号(1974年7月発行)
シンポジウム 向精神薬療法の現状と問題点—Dr. Frank J. Ayd, Jr. を迎えて
16巻6号(1974年6月発行)
誌上シンポジウム 日本の精神医療についての4つの意見
16巻5号(1974年5月発行)
16巻4号(1974年4月発行)
16巻3号(1974年3月発行)
16巻2号(1974年2月発行)
16巻1号(1974年1月発行)
15巻12号(1973年12月発行)
特集 精神障害と家族
15巻11号(1973年11月発行)
15巻10号(1973年10月発行)
15巻9号(1973年9月発行)
15巻8号(1973年8月発行)
15巻7号(1973年7月発行)
15巻6号(1973年6月発行)
15巻5号(1973年5月発行)
15巻4号(1973年4月発行)
特集 痴呆の臨床と鑑別
15巻3号(1973年3月発行)
15巻2号(1973年2月発行)
15巻1号(1973年1月発行)
14巻12号(1972年12月発行)
特集 精神障害者の動態
14巻11号(1972年11月発行)
14巻10号(1972年10月発行)
14巻9号(1972年9月発行)
14巻8号(1972年8月発行)
14巻7号(1972年7月発行)
14巻6号(1972年6月発行)
14巻5号(1972年5月発行)
特集 てんかん分類へのアプローチ
14巻4号(1972年4月発行)
14巻3号(1972年3月発行)
14巻2号(1972年2月発行)
特集 作業療法
14巻1号(1972年1月発行)
13巻12号(1971年12月発行)
特集 社会変動と精神医学
13巻11号(1971年11月発行)
13巻10号(1971年10月発行)
特集 内因性精神病の生物学的研究
13巻9号(1971年9月発行)
13巻8号(1971年8月発行)
13巻7号(1971年7月発行)
13巻6号(1971年6月発行)
13巻5号(1971年5月発行)
特集 向精神薬をめぐる問題点
13巻4号(1971年4月発行)
13巻3号(1971年3月発行)
13巻2号(1971年2月発行)
13巻1号(1971年1月発行)
12巻12号(1970年12月発行)
特集 社会のなかの精神科医
12巻11号(1970年11月発行)
12巻10号(1970年10月発行)
12巻9号(1970年9月発行)
12巻8号(1970年8月発行)
12巻7号(1970年7月発行)
12巻6号(1970年6月発行)
特集 境界例の病理と治療
12巻5号(1970年5月発行)
特集 対人恐怖
12巻4号(1970年4月発行)
12巻3号(1970年3月発行)
12巻2号(1970年2月発行)
特集 医療危機と精神科医—第6回日本精神病理・精神療法学会 討論集会をめぐって
12巻1号(1970年1月発行)
11巻12号(1969年12月発行)
11巻11号(1969年11月発行)
11巻10号(1969年10月発行)
11巻9号(1969年9月発行)
11巻8号(1969年8月発行)
11巻7号(1969年7月発行)
11巻6号(1969年6月発行)
11巻5号(1969年5月発行)
特集 心気症をめぐつて
11巻4号(1969年4月発行)
11巻3号(1969年3月発行)
特集 医学教育と精神療法
11巻2号(1969年2月発行)
11巻1号(1969年1月発行)
10巻12号(1968年12月発行)
10巻11号(1968年11月発行)
10巻10号(1968年10月発行)
10巻9号(1968年9月発行)
10巻8号(1968年8月発行)
10巻7号(1968年7月発行)
特集 集団精神療法(日本精神病理・精神療法学会第4回大会シンポジウム)
10巻6号(1968年6月発行)
10巻5号(1968年5月発行)
特集 うつ病—日本精神病理・精神療法学会(第4回大会シンポジウム)
10巻4号(1968年4月発行)
10巻3号(1968年3月発行)
10巻2号(1968年2月発行)
10巻1号(1968年1月発行)
9巻12号(1967年12月発行)
9巻11号(1967年11月発行)
9巻10号(1967年10月発行)
9巻9号(1967年9月発行)
9巻8号(1967年8月発行)
9巻7号(1967年7月発行)
特集 精神療法の技法と理論—とくに人間関係と治癒像をめぐって
9巻6号(1967年6月発行)
特集 心因をめぐる諸問題
9巻5号(1967年5月発行)
特集 創造と表現の病理
9巻4号(1967年4月発行)
特集 精神療法における治癒機転
9巻3号(1967年3月発行)
9巻2号(1967年2月発行)
特集 精神分裂病の診断基準—とくに“Praecoxgefühl”について
9巻1号(1967年1月発行)
特集 内因性精神病の疾病論
8巻12号(1966年12月発行)
特集 うつ病の臨床
8巻11号(1966年11月発行)
特集 宗教と精神医学
8巻10号(1966年10月発行)
特集 地域精神医学—その理論と実践
8巻9号(1966年9月発行)
8巻8号(1966年8月発行)
8巻7号(1966年7月発行)
特集 精神医療体系のなかでの精神病院の位置づけ
8巻6号(1966年6月発行)
特集 薬物と精神療法
8巻5号(1966年5月発行)
8巻4号(1966年4月発行)
特集 精神分裂病の家族研究
8巻3号(1966年3月発行)
特集 精神活動とポリグラフ
8巻2号(1966年2月発行)
8巻1号(1966年1月発行)
7巻12号(1965年12月発行)
7巻11号(1965年11月発行)
7巻10号(1965年10月発行)
7巻9号(1965年9月発行)
7巻8号(1965年8月発行)
7巻7号(1965年7月発行)
7巻6号(1965年6月発行)
特集 呉秀三先生の生誕100年を記念して
7巻5号(1965年5月発行)
7巻4号(1965年4月発行)
7巻3号(1965年3月発行)
特集 精神分裂病の“治癒”とは何か
7巻2号(1965年2月発行)
特集 精神療法の限界と危険
7巻1号(1965年1月発行)
6巻12号(1964年12月発行)
6巻11号(1964年11月発行)
特集 向精神薬・抗けいれん剤の効果判定法
6巻10号(1964年10月発行)
6巻9号(1964年9月発行)
6巻8号(1964年8月発行)
6巻7号(1964年7月発行)
6巻6号(1964年6月発行)
6巻5号(1964年5月発行)
6巻4号(1964年4月発行)
6巻3号(1964年3月発行)
6巻2号(1964年2月発行)
特集 神経症の日本的特性
6巻1号(1964年1月発行)
特集 近接領域からの発言
5巻12号(1963年12月発行)
5巻11号(1963年11月発行)
5巻10号(1963年10月発行)
5巻9号(1963年9月発行)
5巻8号(1963年8月発行)
5巻7号(1963年7月発行)
5巻6号(1963年6月発行)
5巻5号(1963年5月発行)
5巻4号(1963年4月発行)
5巻3号(1963年3月発行)
特集 てんかん
5巻2号(1963年2月発行)
特集 病識〔精神病理懇話会講演および討議〕
5巻1号(1963年1月発行)
4巻12号(1962年12月発行)
4巻11号(1962年11月発行)
特集 睡眠
4巻10号(1962年10月発行)
4巻9号(1962年9月発行)
4巻8号(1962年8月発行)
4巻7号(1962年7月発行)
4巻6号(1962年6月発行)
4巻5号(1962年5月発行)
4巻4号(1962年4月発行)
4巻3号(1962年3月発行)
4巻2号(1962年2月発行)
4巻1号(1962年1月発行)
3巻12号(1961年12月発行)
特集 非定型内因性精神病
3巻11号(1961年11月発行)
3巻10号(1961年10月発行)
3巻9号(1961年9月発行)
3巻8号(1961年8月発行)
3巻7号(1961年7月発行)
3巻6号(1961年6月発行)
3巻5号(1961年5月発行)
3巻4号(1961年4月発行)
3巻3号(1961年3月発行)
3巻2号(1961年2月発行)
3巻1号(1961年1月発行)
特集 妄想の人間学—精神病理懇話会講演ならびに討論
