内視鏡観察に必要な咽頭(pharynx)および喉頭(larynx)の解剖学用語について説明する.各部位の定義は「頭頸部癌取扱い規約第5版」1)に従いつつ,若干の補足を加えて記載する.
雑誌目次
胃と腸52巻5号
2017年05月発行
雑誌目次
増刊号 図説「胃と腸」所見用語集2017
解剖・組織
食道の解剖用語(anatomy of the esophagus)
著者: 新井冨生
ページ範囲:P.528 - P.530
定義
1.食道の肉眼的解剖
食道は食道入口部から食道胃接合部(esophagogastric junction ; EGJ)までを言い,頸部食道,胸部食道,腹部食道に分類される(シェーマ1).それぞれの定義は以下の通りである1).
頸部食道:食道入口部(輪状軟骨下縁)から胸骨上縁までを指す.
胃の解剖用語(anatomical terminology of stomach)
著者: 二村聡
ページ範囲:P.531 - P.534
定義
1.一般的事項
1)形状と位置と肉眼解剖学的名称
胃(stomach)は,消化管のうち,食道と十二指腸との間を成すJ字形の袋状器官である.機能的には嚥下物を一時的に貯めて,その間,塩酸やペプシンなどを含む胃液により半液状食物(び粥)とし,これを少量ずつ十二指腸に送り出している.胃は,腹腔の左上部に位置し,左上後の胃底(穹窿部)から胃体そして幽門部(前庭部)へと右下前方へ進むにつれ狭くなり,その形と拡がりは内容量,体位,胃壁の緊張などによって変化する.成人胃の解剖学名称は,解剖学者と臨床家の間で用いる術語が多少異なる.これには,本質的な見解の相違もあろうし,古くからの慣習の違いもあろう.事実,胃幽門部は,幽門洞とも前庭部とも呼称されている.なお,「胃癌取扱い規約第14版」1)では,小彎・大彎をそれぞれ三等分し,胃上部(U),胃中部(M),胃下部(L)とする三領域を提唱しているが,これらはあくまで区分であって解剖学的名称ではない.本稿では,読者の便宜をはかり,X線または内視鏡診断の際に頻用される術語を優先的に採用した(Fig. 1).前壁と後壁が小彎と大彎で連続し,内腔を囲み,噴門で食道と,幽門で十二指腸と連絡している.通常,胃の前壁の右上部は肝臓に,左上部は横隔膜に,また,後壁は膵臓に,下縁すなわち大彎は横行結腸に,胃底は脾臓に接している.
小腸の解剖用語(anatomical terminology of small intestine)
著者: 江頭由太郎
ページ範囲:P.535 - P.537
小腸の解剖1)2)
1.小腸の全体
消化管の胃幽門輪の肛門側から始まり,回盲弁(Bauhin弁)の口側に終わる部分が小腸である.その全長は,5〜7m,平均で約6mとされている.小腸は口側より十二指腸,空腸,回腸の3部位に分けられる.十二指腸と空腸の明瞭な境界は組織学的には存在しないが,解剖学的には十二指腸空腸曲(Treitz靱帯付着部)より口側を十二指腸,肛門側を空腸とされる.空腸と回腸の明瞭な境界は解剖学的にも組織学的にも存在しないが,慣習的には十二指腸を除いた小腸の口側40%を空腸,肛門側60%が回腸とされる.
大腸の解剖用語(basic anatomical term of large intestine)
著者: 味岡洋一 , 杉野英明
ページ範囲:P.538 - P.540
解剖
大腸は全長約1.5mの管腔臓器で結腸と直腸に大別され,結腸は口側から盲腸(C),上行結腸(A),横行結腸(T),下行結腸(D),S状結腸(S)の区分から成り,直腸(R)は直腸S状部(RS),上部直腸(Ra),下部直腸(Rb)に区分される(シェーマ).上行結腸と横行結腸の移行部は右結腸曲(肝彎曲),横行結腸と下行結腸の移行部は左結腸曲(脾彎曲)と呼ばれる.「大腸癌取扱い規約 第8版」は,それぞれの区分を以下のように定義している.
肛門・肛門管の解剖用語(anatomy of anus and anal canal)
著者: 藤原美奈子
ページ範囲:P.541 - P.542
定義
肛門(anus)は,消化管の終末部であり,糞便の排出口として認識されている.視診の際に確認できる外口(anal orifice)と肛門周囲の皮膚との境界,つまり外口の縁である肛門縁(anal verge)から成るものを一般的に肛門と呼ぶが,その範囲の規定はいまだ不明瞭である.肛門縁より1.5〜2.0cmほど奥に歯状線(rental line)が存在し,これが肛門と直腸の接合部,すなわち発生学的には外胚葉と内胚葉の接合部になる.歯状線は隆起を形成する肛門乳頭(anal papilla)と陥凹を形成する肛門陰窩(anal crypt)から形成される.肛門陰窩には肛門導管(anal duct)が開口しており,肛門腺(anal gland)へと続く1).
肛門管(anal canal)の定義もさまざまで,肛門縁から歯状線までが解剖学的肛門管(anatomical anal canal),肛門縁から恥骨直腸筋付着部上縁までが外科的肛門管(surgical anal canal),内肛門括約筋の上下縁で囲まれる部分を組織学的肛門管(pathological anal canal)と呼ばれている2).内肛門括約筋は,直腸固有筋層の内輪筋に連続した平滑筋であり,肛門縁上部まで伸びていることから,外科的肛門管と組織学的肛門管はほぼ近しい部分を指していると考えることもできる(シェーマ).
画像所見〔咽喉頭・食道〕
glycogenic acanthosis
著者: 丸山保彦
ページ範囲:P.543 - P.543
定義
GA(glycogenic acanthosis)は上皮層肥厚,特に細胞質内にグリコーゲン顆粒を有する有棘細胞の肥厚である.通常内視鏡観察では,数mm〜1cm程度の類円形で表面平滑な限局性白色隆起を呈し,多発して存在することが多く,高齢者男性の食道でよく観察される(Fig. 1).NBI観察では周囲より血管密度が低いことを反映して白色調を呈し,ヨード染色では濃染する(Fig. 2).GAに近接すると,その表面に程度の差はあるが白濁した微細な点状〜棘状隆起が伸び出している所見を観察できる(Fig. 3).同部はヨード染色像で点状に抜け,皮膚の脂腺開口部に類似して見える(Fig. 4).
黄色腫(xanthoma)
著者: 高木靖寛
ページ範囲:P.544 - P.544
定義
泡沫細胞,すなわち黄色腫細胞の集簇による病変である.胃ではよく認められるが内視鏡検査による食道での頻度は0.46%とまれである1).病理組織学的に黄色腫細胞は扁平上皮間結合組織乳頭部に嵌り込むように存在するため2),この所見が内視鏡像にも反映される.すなわち,典型例では多数で点状の黄白色小顆粒の集簇として観察される(Fig. 1a).拡大観察では乳頭の配列に一致して黄白色顆粒がみられ,このなかに縮れて走行する微細血管が観察され特徴的である2)(Fig. 1b).黄色腫細胞の量が多く充満した場合は顆粒結節状となることもある.
食道皮脂腺(esophageal sebaceous gland)
著者: 高木靖寛
ページ範囲:P.545 - P.545
定義
通常,異所性皮脂腺は外胚葉起源臓器の口唇,口腔,唾液腺,包皮,陰唇などにみられるが,食道は内胚葉由来であり,発生臓器としてはまれである.浜本ら1)の本邦報告例32例の集計では,男女比は26:6で男性に多く,平均年齢は56.8歳で,約70%と多くが多発例である.本庶ら2)の内視鏡検査による発見頻度は,4,581件のうち7例(0.15%)であった.内視鏡的には小黄白色結節が散在するものや,結節や小顆粒が混在して多発するものなどさまざまな分布がみられる.典型的なものは5mm以下のやや混濁した黄白色調の小扁平隆起や顆粒状を呈し,個々の形態は花弁状から偽足状を示す(Fig. 1a).表面の観察では,皮脂腺導管部分が円型の微細血管で囲まれた白色の小突起として認められる3)(Fig. 1b).
孤立性静脈拡張(solitary venous dilatation)
著者: 有吉隆佑 , 梅垣英次
ページ範囲:P.546 - P.546
定義
一般に“孤立性静脈瘤”,“孤在性静脈瘤”とも呼ばれるが,消化器内視鏡用語集では“孤立性静脈拡張(solitary venous dilatation)”と称され,“食道の上・中部に認められる孤在性の青色小隆起で,限局性に拡張した粘膜下静脈の他に食道腺の貯留囊胞などがある”とされている1).血管腫に含まれるともされるが,その厳密な区別は臨床的・病理学的に明確にされていない.成因は不明で,門脈圧亢進症に伴い下部食道に発生する静脈瘤や,上大静脈圧の上昇に起因し,主に上部食道に発生する“downhill varices”2)とは異なった疾患と考えられている.
異所性胃粘膜(ectopic gastric mucosa)
著者: 松岡晃生 , 梅垣英次
ページ範囲:P.547 - P.547
定義
異所性胃粘膜は“胃粘膜の組織学的特徴が胃の境界の外側に異所性に認められるもの”と定義され,主細胞や副細胞を持つ胃底腺粘膜から成り立つことが多く,全消化管に生じうる.
食道では円柱上皮から重層扁平上皮への置換が胎生5〜6週ころに食道中部から始まり,口側および肛門側へ進展するとされているが,その過程で円柱上皮の遺残したものが食道異所性胃粘膜と考えられている1).
食道メラノーシスと食道メラノーマ(melanosis of the esophagus, melanoma of the esophagus)
著者: 三浦昭順 , 堀口慎一郎
ページ範囲:P.548 - P.548
定義
重層扁平上皮に覆われた食道粘膜は,通常は灰白色調の光沢のある粘膜として観察される.これは,食道の基底層にメラノサイトがごく少数(2〜8%)しか存在せず,メラニン顆粒を認めないからである.基底層のメラニン顆粒が著しく増加することにより,食道粘膜が黒色調を呈するものをメラノーシスと言う(Fig. 1,2).内視鏡検査による一般人の頻度は約0.1%程度とされているが,扁平上皮癌周囲では30%程度に認められる1).
基底層のメラノサイトから発生する腫瘍が悪性黒色腫である(Fig. 3,4).食道原発悪性黒色腫の頻度は少なく,本邦の食道悪性腫瘍の0.1〜0.9%とされる.中下部食道に80%と多く,ほとんどが隆起性腫瘍を形成し,有茎性あるいは亜有茎性のポリープ状隆起が約1/3を占める.腫瘍細胞の産生するメラニン色素の量により腫瘍の色調は異なり,黒色から褐色調,灰色調などさまざまである(melanotic type)が,10%程度に無色素性の腫瘍(amelanotic type)もみられる.
ヨード不染帯(unstained area of the iodine staining)
著者: 長尾知子 , 藤原純子
ページ範囲:P.549 - P.549
定義
ヨード液を食道内腔に撒布した際に,茶褐色に染色されず黄白色を示す部分をヨード不染帯と言う.ヨード染色は食道粘膜上皮の表層,および有棘細胞層内に蓄えられているグリコーゲンとヨウ素が反応する化学反応を利用したものである.したがって,グリコーゲンを産生する正常食道上皮が薄くなれば,染色性が低下し淡染帯となり,上皮が欠損したり,消失すれば不染帯となる.ヨード不染帯を示すものには,①病的な粘膜上皮〔上皮内癌(Fig. 1,2),粘膜癌,扁平上皮内腫瘍,hyperkeratosis,parakeratosis,食道炎などの炎症性変化〕,②粘膜上皮の欠損(びらん,潰瘍,癌組織の露出部,異所性胃粘膜),③正常粘膜(萎縮)などが挙げられる.ヨード染色は,食道癌のハイリスク群におけるスクリーニングとして必須とされてきた1)が,NBIが普及し,病変の拾い上げが比較的容易になった近年では,病変の範囲診断および癌と非癌との鑑別2)において,重要な役割を果たしている.
pink color sign
著者: 松井俊大 , 千葉哲磨
ページ範囲:P.550 - P.550
定義
健常な食道粘膜にヨード染色を行うと,上皮内の有棘層に含まれるグリコーゲン顆粒とヨードが結合し,食道粘膜を茶褐色に染色する.しかし,グリコーゲンを産生する正常食道上皮が薄くなったり,消失したりすると,ヨードの染色性は低下し,不染帯となる.異型細胞が上皮の下層にとどまる場合は,上皮内にグリコーゲンがある程度保たれているため,ヨード淡染帯を示すが,上皮全層が異型細胞で置換されると,上皮内にグリコーゲンがなくなり,ヨード不染帯となる.このヨード不染帯が,数分後に本来の病変の色調であるピンク色を呈するようになる現象を,大森ら1)はPC sign(pink color sign)と命名した.PC signの原理については,いまだ不明な点も多いが,異型が高度になると上皮のバリア機構が障害され,染色後,早期にヨードが上皮内から消失し,本来の粘膜の色調であるピンク色を呈するという説2),また,PC signは病変の異型性ではなく,残存した正常上皮の厚さを反映しているのではないかとする意見もある.
顆粒細胞腫(granular cell tumor)
著者: 高木靖寛
ページ範囲:P.551 - P.551
定義
顆粒細胞腫は,Schwann細胞由来の腫瘍とされ,全身のいかなる臓器にも発生する.好発部位は皮膚や舌で,5〜9%が消化管に発生し,その多くは食道にみられる.ややくすんだ黄白色調の粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)で,大きさ10mm以下のものでは半球状,丘状の非特異的な形態であるが,10mm以上の大きさになると「臼歯状所見」と表現される特徴的な形態を示し,内視鏡像のみでも比較的診断は容易である(Fig. 1a)1).
食道粘膜剝離症(exfoliation of esophageal mucosa)
著者: 高木靖寛 , 大津健聖 , 宗祐人
ページ範囲:P.552 - P.552
定義
いわゆる食道粘膜剝離症の疾患概念における区別は明らかではないが,広義において,表層上皮が剝離する表層性食道粘膜剝離症と,粘膜下層より表層が剝離する食道粘膜剝離症に大別される.
volcano-like appearance
著者: 田中一平 , 平澤大
ページ範囲:P.553 - P.553
定義
volcano-like appearanceとは,境界明瞭で辺縁隆起がやや目立つ浅い潰瘍を呈する食道の内視鏡所見である(Fig. 1).ヘルペス食道炎に特徴的な所見で,volcano ulcersやvolcano lesionとも呼ばれている.1986年にAghaら1)によって報告され,ヘルペス食道炎患者の約75%に認められる.
大きさは数mm〜20mm程度とさまざまで,進行に伴い潰瘍は癒合し,帯状,地図状となり易出血性を示す(Fig. 2).
黒色食道(急性壊死性食道炎)〔black esophagus(acute necrotizing esophagitis)〕
著者: 上村直実
ページ範囲:P.554 - P.554
定義
急性壊死性食道炎は1990年にGoldenbergら1)が初めて内視鏡的に診断したもので,上部消化管内視鏡検査で特徴的な食道粘膜の黒色変化を呈する疾患である.2014年までの本邦における報告例は30例と極めてまれな疾患で,通常,“黒色食道”と呼称されている(Fig. 1〜5).内視鏡所見の特徴は,びまん性,全周性の黒色変化であるが,Moretoら2)による診断基準では,①急性に生ずる食道粘膜全周性の黒色変化,②病変の主座が下部食道(遠位側1/3)に認められ,胃粘膜は正常で胃粘膜との境界が明瞭,③食道粘膜を損傷する他の要因がない,という3項目を満足することが挙げられている.なお,食道粘膜が黒変する原因としては,壊死組織内の血液が凝固あるいは胃酸の曝露により黒色化するものと推測されており,病理組織学的所見では壊死物質と肉芽組織の混在が特徴である.
柵状血管(esophageal palisade vessels)
著者: 竹内学
ページ範囲:P.555 - P.555
定義
胃噴門部の粘膜下層から食道の粘膜固有層に移行し,粘膜固有層で2〜3cm縦走し,食道の粘膜下層に至る静脈の存在が1966年De Carvalho1)により報告され,食道柵状血管と命名された.内視鏡的には,下部食道に縦走する血管群として認識される.食道胃接合部(esophagogastric junction ; EGJ)は病理組織学的に食道と胃の筋層境界と定義されており,胃噴門部筋層には斜走筋が存在するが,食道には存在しない.この斜走筋の上縁が理論上EGJの境界であるが,組織切片上であってもその同定は難しい.そこで,星原ら2)は下部食道柵状血管の下端をEGJの適切な指標として提唱し,現在本邦におけるEGJの診断に用いられている.また,病理学的には柵状血管は胃上部粘膜内血管より有意に血管径が太く(約100μm以上),この血管径の違いが食道と胃の指標になりうるとされている3).
畳目模様(tatamime sign)
著者: 岩城智之
ページ範囲:P.556 - P.556
定義
畳目模様(tatamime sign)は“畳の目サイン”などとも呼ばれ,食道の内視鏡観察時にみられる輪状のひだのことを指す.あたかも畳の目のように細かな輪状ひだが横走することから,ニックネーム的に使用されている1).
brownish area,metallic silver sign
著者: 竹内学
ページ範囲:P.557 - P.557
定義
brownish areaは画像強調イメージングのひとつであるNBI観察により,咽頭・食道領域で主に腫瘍性病変にみられる境界を有する茶褐色調領域と定義される1)(Fig. 1).NBI観察は白色光観察に比べて,咽頭・食道扁平上皮癌の検出率・診断精度が有意に優れており,癌拾い上げのための重要な所見である.brownish areaは血管の増生と血管間のbackground colorationによるものとされており,炎症(Fig. 2)や上皮の菲薄化(Fig. 3),さらに毛細血管の増生などでも茶褐色調を呈することもある.
metallic silver signは,ヨード撒布後の不染帯部分がピンク色に変化するPC(pink color)signを呈する部分がNBI観察では銀色に光る所見と定義される2)(Fig. 4).通常観察によるPC signに比べてコントラストが明瞭となり視認性がよいとされる.
epidermization
著者: 剛﨑有加 , 門馬久美子 , 堀口慎一郎
ページ範囲:P.558 - P.558
定義
本来,食道上皮は非角化重層扁平上皮から成る.食道epidermization(類表皮化)は,組織学的に扁平上皮表面に厚い角化層を有するのが特徴であり,皮膚の表皮に類似していることから,このように呼ばれている.しかし,食道epidermizationに関する報告例は少なく,慢性炎症がepidermizationの形成に関与している可能性も示唆されているが,真の成因や発生頻度,自然経過などについては不明である.内視鏡的には“鱗状”あるいは“毛羽立ちを有する”白色の角化上皮が,あたかも食道粘膜に付着しているかのように観察され,ヨード染色では不染を示す1)2).境界明瞭な白色隆起を示す病変として,parakeratosis(錯角化)やhyperkeratosis(過角化)なども挙げられるが,内視鏡所見のみで鑑別することは難しく,epidermizationの診断には病理組織所見が必要である.epidermizationの組織所見(Fig.4)の特徴は,重層扁平上皮の表層に厚い角化層を有し,その直下にはケラトヒアリン顆粒を有する顆粒層を伴う点である.
上皮乳頭内血管ループ(intra-epithelial papillary capillary loop)
著者: 井上晴洋
ページ範囲:P.559 - P.559
定義
咽頭および食道の扁平上皮に存在するループ状の毛細血管である.扁平上皮では粘膜固有層が上皮内に乳頭状に突出する.その乳頭内を走るループ状の終末血管がIPCL(intra-epithelial papillary capillary loop)である1)(Fig. 1)(厳密には,上皮の境界を基底層と定義すると,IPCLは粘膜固有層の血管とも言える).IPCLは乳頭内で扁平上皮の基底層に近く存在し,上皮内癌では特徴的な変化(拡張・蛇行・口径不同・形状不均一)を来す2)(Fig. 2,シェーマ).通常光の拡大観察でも視認可能であるが,IEE(image-enhanced endoscopy)の併用拡大観察により,茶褐色のループ状血管としてよく観察される.
上皮下進展(subepithelial extension)
著者: 橋本林太朗 , 平澤大
ページ範囲:P.560 - P.560
定義
Barrett食道では,隣接する扁平上皮下に腸上皮化生(subsquamous intestinal metaplasia ; SSIM)の進展がしばしばみられる.その機序は酸などの刺激に対する治癒過程での扁平上皮再上皮化と考えられている.SSIMの内視鏡検査での診断は現時点では生検でのみ可能とされる.欧米ではSSIMはBarrett食道腺癌の発生と関連していると考えられている1).Barrett食道腺癌EMR標本の検討では98%にSSIMがみられた2).
一方,Barrett食道腺癌が扁平上皮と接している場合,正常の扁平上皮下に腺癌が進展していること(Barrett's cancer under the squamous epithelium ; BCUS)がある.このBCUS部では癌が表層に露出していないため,内視鏡検査による範囲診断が困難な場合がある3).Barrett食道腺癌を覆う扁平上皮が薄い場合は,扁平上皮下の腺癌部分が発赤調に透見されたり(Fig. 1),NBI観察で淡い茶色様変化(Fig. 2)を呈したりする場合がある.厚い扁平上皮に覆われると,それらの所見もみられなくなる.
コークスクリュー様所見(corkscrew-like appearance)
著者: 伊藤公訓
ページ範囲:P.561 - P.561
定義
食道運動機能異常症で認められる特徴的な食道内視鏡所見であり,胸部中部ないし下部食道における非蠕動性同期性収縮を反映している.
内視鏡的には,らせん状ないし多発輪状の異常収縮が観察される(Fig. 1).口側には,食物や唾液の停滞を伴っていることも多い.食道X線造影検査では,バリウムの通過障害とともに,コークスクリュー様,数珠玉状と表現される異常収縮が認められる(Fig. 2).
縦走溝(longitudinal furrow)
著者: 丸山保彦
ページ範囲:P.562 - P.562
定義
食道長軸方向に縦走する幅の狭いひび割れ状,亀裂様の溝である(Fig. 1〜3).好酸球性食道炎の約半数に出現し,最も出現頻度の高く,最も特異的な所見である1).好酸球性食道炎の診断基準(2015年)をTable 1に示す.
画像所見〔胃〕
瀑状胃,牛角胃(cascade stomach, steerhorn stomach)
著者: 外山雄三 , 長浜隆司
ページ範囲:P.563 - P.563
瀑状胃の定義
瀑状胃とは,噴門直下の高さで胃体部後壁が鋭角をなして屈曲し,胃穹窿部が主として左後方へ囊状に区切られている胃型である.立位で嚥下されたバリウムが胃穹窿部を盃状に満たした後に胃体下部にこぼれ落ちる型の変形胃の形態学的呼称とも言われている1)(Fig. 1,2).
牛角胃の定義
牛角胃とは,胃の形が牛の角のような形態を呈するものに対して用いられ,横胃とも呼ばれる(Fig. 3)3).比較的緊張度の高い胃の状態でみられ,肥満体型や筋肉質の男性に多い.
幽門狭窄(pyloric stenosis)
著者: 細川治
ページ範囲:P.564 - P.564
定義
胃上中部が胃酸,ペプシンを含む消化液を分泌して食物の消化を行うのに対して,幽門前庭部などの下部は食物を腸に排出する機能を受け持つ.幽門狭窄とは幽門前庭部から球部の一部に狭窄を来して排出障害となり,胃内に食物が停滞した状態を表す用語である.左側臥位で内視鏡を挿入すると十分な絶食の後でも胃穹窿部から胃体部大彎にかけて食物残渣が残り,胃下部に狭小化所見が認められる.非腫瘍性としては良性潰瘍が反復した場合(Fig. 1)に認められることが多かったが,Crohn病の上部消化管病変や好酸性胃腸炎あるいは胃梅毒に伴って発生した報告もある.腫瘍性病変では進行胃癌(Fig. 2)で幽門狭窄を来すことが多いが,早期胃癌が幽門輪近傍に発生した場合にも起こりうる1).壁外からの圧排や腫瘍性病変の浸潤で狭窄を来す場合も認められる.
胃小区模様(gastric area)
著者: 八木一芳
ページ範囲:P.565 - P.565
定義
胃小区模様とは,胃粘膜表面に溝によって小さく区画されている模様を指す1).胃小区の大きさは切除胃固定標本で幽門腺領域では長径3〜6mm,短径2〜3mm,胃底腺領域では径2〜3mmとされている1)2).病理組織学的には,胃小区を囲っているのは樹枝状に分岐した大型の胃小溝である3).胃小区の形態分類は井田1)の分類がある.この分類はコントラスト法によって描出される胃小区を幽門腺粘膜と胃底腺粘膜に分けて,前者をP型,後者をF型としている.萎縮性変化の進行とともに小区間溝は広く深くなり,小区の形態も不整になり,その形態がP0〜P3,F0〜F3までに分類されている1).
小彎短縮,囊状胃〔shortening of lesser curvature, Beutelmagen(wallet stomach)〕
著者: 山本栄篤 , 長浜隆司
ページ範囲:P.566 - P.566
定義
胃X線造影所見で表される病的変形の名称である.小彎短縮とは,潰瘍などが原因で胃角から幽門輪の距離が短縮する現象.囊状胃とは,大彎の伸展は保たれたまま小彎短縮が高度となり前庭部小彎が消失し,胃角そのものが幽門小彎になり胃全体が袋状を呈した状態の胃.
ニッシェ(正面,側面)(niche, Nische)
著者: 入口陽介 , 水谷勝
ページ範囲:P.567 - P.567
定義
ニッシェとは,開放性潰瘍を表現するX線造影所見である.ニッシェは,英語でniche,ドイツ語でNische,日本語では壁龕(へきがん)と訳されており,壁龕とは建物の壁に彫像や花瓶などを置くために設けられた装飾的なくぼみのことである(Fig. 1).
胃壁の一部が欠損した部分(開放性潰瘍)にバリウム造影剤が溜まって描出されるX線造影像が壁龕に似ていることから命名されており,本邦ではニッシェとして用いられている.ニッシェは,良性胃潰瘍だけでなく,潰瘍を合併する胃癌や腫瘍性病変などにもみられる1).正面ニッシェと側面ニッシェがあるが,正面ニッシェは,境界明瞭なバリウム造影剤の濃い溜まり像として正面に描出された像(Fig. 2),側面ニッシェは,胃の滑らかな辺縁から胃外側に突出した所見として側面に描出された像(Fig. 3)を言う.
胃角開大(widening of gastric angulus)
著者: 八巻悟郎 , 奥田圭二
ページ範囲:P.568 - P.568
定義
胃角が開くということは,胃角部小彎,ないし,その付近に病変があって常態のように胃角をつくれないということである.胃角部が硬くなって(Fig. 1,2),胃壁が伸縮できない状態を言う.病変としては,潰瘍でも癌でもよい1).
彎入,透亮像(indentation, translucency)
著者: 細川治 , 横山力也
ページ範囲:P.569 - P.569
彎入の定義
X線造影所見における用語である.胃を適度に伸展した状態で撮像した際に,辺縁にくびれが生じた所見を呈することを指す.生理的な場合にも認められるが,胃壁の病的な変化から出現する際の彎入は重大な所見である.
透亮像の定義
骨や肺気管支,血管のX線造影所見でも使用される用語である.胃X線検査で使用する際は,隆起性病変が正面像としてバリウムをはじいて現れている所見1)である.胃の場合には抜けている領域が空虚ではなく,粘膜像が存在する.
壁硬化像(rigidity of the wall, stiffness)
著者: 入口陽介 , 高柳聡
ページ範囲:P.570 - P.570
定義
壁硬化像とは,胃癌の粘膜下層以深への浸潤,炎症や潰瘍に伴う線維化などによって,胃壁に器質的変化が生じ弾性が失われた結果,胃壁が硬く伸展性が悪くなった状態を描出した画像所見である(Fig. 1〜4).
X線造影検査では,胃壁は,本来,緩やかで平滑な曲線として描出されるが,壁の硬化がある部分では,緩やかな曲線が失われて直線化や不規則な凹凸などの所見を認める1).壁硬化が広範囲に拡がればバランスの悪い不自然な胃形として描出される.空気量を変えて胃壁の伸展度合いを変化させて描出すると,壁硬化の範囲,深さ,程度を知ることができる.
伸展不良(poor distensibility of the wall)
著者: 入口陽介 , 冨野泰弘 , 山村彰彦
ページ範囲:P.571 - P.571
定義
伸展不良とは,X線検査の充満像ではバリウムで,二重造影像では空気またはガス(発泡剤)で,胃を膨らませて胃壁を伸展させるも,胃壁の硬化などによって伸展が悪くなった状態を表現する用語である(Fig. 1,2).胃壁の伸展が不良な場合,胃体部のひだ間の伸展不良を認めたり(Fig. 3),正常な胃と比較して胃形のバランスが悪い場合には(Fig. 4),胃壁のびまん性硬化があると判定する.その場合,癌が粘膜下層以深へ浸潤したスキルス胃癌を疑うが(Fig. 3,4),スキルス胃癌であれば,通常,原発巣となる陥凹性変化があり,生検で未分化型癌が認められる.ただし,原発巣が不明瞭で生検で癌を認めない例もあり,注意が必要である.また,広範な線維化を来すような特殊な病態や漿膜側の炎症後の癒着や他臓器癌の漿膜浸潤,感染症など,伸展不良を来す疾患は多い1).
leather bottle like appearance
著者: 宇賀治良平 , 長浜隆司
ページ範囲:P.572 - P.572
定義
スキルス胃癌が進行した状態において胃が縮小硬化し,革袋状の形態を呈することをleather bottle like appearanceという1).
巨大皺襞(giant rugae)
著者: 梅垣英次 , 佐野村誠
ページ範囲:P.573 - P.573
定義
巨大皺襞には明確な定義はないが,X線学的には二重造影にて皺襞幅が10mm以上を呈し,内視鏡的には十分な送気によって腫大・屈曲蛇行したひだが認められ,ひだ間の溝は狭くなる.また,ひだの屈曲蛇行所見が強くなると,大脳回転様の像を呈することもある.巨大皺襞は良悪性にかかわらずさまざまな疾患で認められ,粘膜あるいは粘膜下以深の病理学的変化に伴って形成されるが,①胃腺の肥大や過形成によるびまん性の肥厚(肥厚性胃炎,Ménétrier病,Cronkhite-Canada症候群),②粘膜間質の浮腫や種々の細胞浸潤による粘膜・粘膜下層の肥厚(悪性リンパ腫),③粘膜下層や筋層の線維性組織増生を伴う収縮(スキルス型胃癌),④漿膜側からの炎症波及(急性膵炎など),に分類される1).
ベルギーワッフル様外観(morphologically similar to belgian waffle)
著者: 入口陽介 , 浜田勉
ページ範囲:P.574 - P.574
定義
スキルス胃癌の線維性収縮が軽度〜中等度の場合,胃体部大彎の縦走するひだに交錯する横走する粘膜ひだを認め,ベルギーワッフル(Fig. 1)に類似していることから呼称されている1).胃底腺領域に原発巣が存在するスキルス胃癌では,原発巣以外の粘膜層には癌浸潤は認めないため粘膜層の伸展は良好であるのに対して,粘膜下層以深に浸潤している領域では,器質的変化が生じて弾性が消失し,長軸方向と短軸方向の両方向への短縮が認められ,縦走するひだに横走するひだが生じ交錯する形態を呈することがある(Fig. 2,3).
稜線状発赤(kammrötung)
著者: 山本浩隆
ページ範囲:P.575 - P.575
定義
稜線状発赤は胃体部小彎や前庭部大彎を中心に,胃長軸方向に平行に縦走する,数条の帯状発赤である(Fig. 1〜3).発赤は胃皺襞の頂上部に一致して観察される.欧文表記はドイツ語のkammrötungであり,本来は畝に沿う発赤という語意であるが,kammを“櫛”と誤訳されたことで,櫛でこすってできたような内視鏡所見も相まって本邦では櫛状発赤と広まったようである.「消化器内視鏡用語集第3版」では櫛状発赤は稜線状発赤として改められている1).1956年にHenningが表層性胃炎の1所見として報告2)しているが,病理組織学的には細胞浸潤はみられず,発赤部における表層血管のうっ血が確認される3).一般に非萎縮粘膜の過酸・正酸例にみられることから,稜線状発赤の成因としては胃の蠕動収縮時に皺襞の尾根にうっ血が生じ,そこに接する胃酸が作用しているものと考えられる.
たこいぼ状隆起(varioliform gastritis)
著者: 小林亜也子 , 中村真一
ページ範囲:P.576 - P.576
定義
中心に小陥凹がある疣状の隆起をたこいぼ状隆起と呼び,たこの吸盤に似ていることからこの名がつけられた(Fig. 1,2).たこいぼびらん,疣状胃炎,隆起型びらん(raised erosion)とほぼ同義であり,updated Sydney systemの胃炎分類にも記載されている1).
ポリープ状,棍棒状,数珠状などの形態をとり,前庭部に好発するが胃体部に認めることもある.多発することが多いが,単発のこともある.中心の陥凹は発赤調で同心円状を呈し白苔を伴うこともあるが,蚕食像などの悪性所見を認めない(Fig. 3).病理組織学的には中心のびらんとその周辺の胃固有腺の過形成である.びらんが治癒すると半球状隆起として観察される.
いくら状胃炎(congestive gastropathy)
著者: 中村真一 , 岸野真衣子
ページ範囲:P.577 - P.577
定義
McCormackら1)は門脈圧亢進症による消化管病変のなかに,食道・胃静脈瘤や急性胃炎,消化性潰瘍などと異なる,胃粘膜のうっ血により胃の粘膜固有層や粘膜下層における微小血管の拡張を来し,内視鏡的に特有な発赤所見を呈する病態を門脈圧亢進症性胃症(portal hypertensive gastropathy ; PHG)とし,PHGに伴う胃粘膜障害をcongestive gastropathyとして提唱した.PHGの内視鏡所見は胃体部を中心とした広範な発赤と浮腫,胃小区と腺窩の拡張像を認め,“いくら状胃炎”と表現される(Fig. 1).時に斑状のびまん性発赤や出血,びらんや浅い潰瘍を伴うこともある.
McCormackら1)はPHGの内視鏡所見を,①軽症:軽度の発赤,線状発赤(粘膜ひだ上のストライプ様発赤),浮腫状の発赤した粘膜が白色の網目状パターンで境界されたsnakeskin(mosaic)pattern(Fig. 2,3)と,②重症:高度の発赤斑としてcherry red spotおよび,びまん性発赤,とに分類している.豊永ら2)の臓器反射スペクトル法による重症度分類もある.
敷石状胃粘膜(cobblestone appearance)
著者: 春間賢 , 高張康介
ページ範囲:P.578 - P.578
定義
消化管粘膜が敷石状に見える所見は,Crohn病の消化管病変の特徴的な変化で,診断基準の一つになっている.縦走潰瘍に取り囲まれた浮腫を伴う非潰瘍粘膜が4〜7mmの半球状隆起の集合となり,丸い石を敷き詰めたように見える所見や,時に,炎症性ポリポーシスも敷石状粘膜に含まれる.最近,プロトンポンプ阻害薬(proton pump inhibitor ; PPI)を中心とした胃酸分泌抑制薬を長期使用する機会が増加し,これまでに経験したことのない胃粘膜変化を経験するようになった.敷石状胃粘膜もその一つで,胃体部に均一な小隆起が多発する変化で,粘膜がもこもこして見えることから,当初は,“もこもこ胃炎”と筆者らは呼んでいたが,組織学的には炎症は伴わないので,敷石状胃粘膜が形態学的にもふさわしい1)2).
敷石状胃粘膜は,正面に見える胃体下部前壁や大彎を見下ろしたとき,胃角部から反転で胃体部前壁を見上げたときによく観察できる.通常,粘膜ひだの増加を伴っており,胃体部粘膜の萎縮のない症例に多く認められるため3),多くは胃体下部小彎にも粘膜ひだが認められる.当初は,ひだの過形成変化と考えたが,よく観察すると,ひだの幅が太くなっていることは少なく,ひだの数の増加と蛇行,さらに,敷石状の変化が粘膜ひだにも認められることから,一見,Crohn病で認められる竹の節様に見えるが,節に見える部分はくぼんでおり,連なった蓮根様で,“lotus root sign”と名付けている(Fig. 1).
腸上皮化生(intestinal metaplasia)
著者: 末廣満彦 , 春間賢
ページ範囲:P.579 - P.579
定義
腸上皮化生はHelicobacter pylori(H. pylori)感染などにより胃粘膜上皮がびらんと再生を繰り返すことにより,腸管粘膜上皮の形態に変化した状態であり,胃癌発生の高危険群でもある.腸上皮化生には細胞組成から完全型と不完全型に分けられ,完全型では吸収上皮と杯細胞,Paneth細胞から成り,刷子縁様構造を伴い小腸粘膜と同じ形態と構造を持つ.不完全型はPaneth細胞を欠き,胃型と腸型の細胞が混在する胃腸混合型の腸上皮化生と考えられている.また,化生胃小区の形態より隆起型,平坦型,陥凹型に分けられる.
腸上皮化生は現感染のみではなく,H. pylori除菌後でも観察され,長期間にわたり残存する.除菌後の特徴的な所見として地図状発赤があるが,生検による組織検査では腸上皮化生の所見が得られることが多い.
びらんと潰瘍(gastric erosion, gastric ulcer)
著者: 丸山保彦
ページ範囲:P.580 - P.580
定義
村上ら1)は,組織欠損の深さをUl-I(粘膜のみ),Ul-II(粘膜下層まで),Ul-III(固有筋層まで),Ul-IV(漿膜層に達する)に分類した(シェーマ).これらの分類から,Ul-Iまでをびらんとし,Ul-II以上が潰瘍と定義される.
不整形陥凹(irregular shaped depression)
著者: 赤松泰次
ページ範囲:P.581 - P.581
定義
病変の形態が,円形(隆起性病変の場合は球状または半球状)ないし類円形の場合は整,それ以外の場合は不整と呼ばれている(シェーマ).これに対して不整形陥凹とは,病変の辺縁が内に向かって凸の形態を示す場合を指し,星芒形とも呼ばれる.不整形陥凹性病変を認めた場合,まず胃癌(Fig. 1,2)1)や悪性リンパ腫(Fig. 3,4)2)といった悪性病変の可能性を考慮しなければならないが,急性潰瘍や胃梅毒などの特殊型胃炎に伴う潰瘍も不整形を呈する場合がある.一方,消化性胃潰瘍の辺縁は通常,外に向かって凸で,円形ないし類円形の整の形態を示す.陥凹性病変を認めた場合は,まず辺縁の形状に注目して整か不整かを見極めることが,胃陥凹性病変の鑑別診断に重要である.
発赤・褪色(redness, fading)
著者: 赤松泰次
ページ範囲:P.582 - P.582
定義
背景粘膜の色調と比較して,赤みが強く見える場合を“発赤”と言い,白色調に見える場合を“褪色”と表現する.背景粘膜の色調は,Helicobacter pylori(H. pylori)の感染状態(未感染,既感染,現感染)や胃粘膜萎縮の程度によって異なるため,“発赤”や“褪色”はかなり主観的な所見である.これらの所見は腫瘍性病変と非腫瘍性病変のいずれにも認められるが,本稿では腫瘍性病変における色調について述べる.
ひだ集中(Faltenkonvergenz, convergency of folds)
著者: 入口陽介 , 細井董三
ページ範囲:P.583 - P.583
定義
ひだ集中は,潰瘍あるいは潰瘍瘢痕に向かって周囲から粘膜ひだが集中する現象を指し,1921年,Eisler-Lenkによって初めて記載された.1926年,Hauserは大きさが1cm以上で筋層深くまで達していて,粘膜筋板と固有筋層との融合を伴う潰瘍には著明なひだ集中像を認め,潰瘍が大きくて深いほどひだ集中像は著明に現れると述べている.ひだ集中は潰瘍のほか潰瘍瘢痕を伴う胃癌などの腫瘍性病変でも認められるため,鑑別診断が必要となる.本邦では,胃体部大彎を中心に既存のひだの数本が1点または2点以上の中心点に向かって走行している状態をひだ集中(Fig. 1,2),もともとひだのない領域にみられる集中像を粘膜集中像(Fig. 3,)と分けて呼ぶ場合がある.ひだ集中の成因については,粘膜筋板と潰瘍底の瘢痕収縮によると考えられており,潰瘍の新旧や治癒傾向の判定,さらに良・悪性の鑑別にも利用される1).
蚕食像,ひだの中断・先細り・肥大・融合・接合・周堤(abrupt ending, tapering of the fold, club-like thickening, fusion of folds, fusion of the converging folds with annular formation)
著者: 田中一平 , 長南明道
ページ範囲:P.584 - P.585
定義
蚕食像は陥凹型胃癌の辺縁にみられる微細な不整所見で,悪性診断の最も重要な指標のひとつである.ひだ集中の有無や深達度,組織型に関係なく認められる1).
蚕食像とは読んで字のごとく,蚕が食べた桑の葉の形態に似ていることに由来した名称である.虫食い像とも呼ばれ,海外ではmoth-eaten,encroachmentと訳されている.
インゼル,聖域(insel)
著者: 坪井瑠美子 , 長南明道
ページ範囲:P.586 - P.586
定義
インゼル(insel)はドイツ語で島という意味で,0-IIc型未分化型癌の陥凹内に島状に取り残された粘膜のことを称する(まれに分化型癌でもみられる)1).インゼルの表面に癌組織が認められる場合もあるが,実際には癌の浸潤が少ないことから,日本語では“島状粘膜残存”,“聖域”と呼ばれてきた.ただし,正常粘膜の取り残しなのか,再生粘膜なのかは文献上でも明らかでない.インゼルについて欧米の論文での記述はまれで,早期胃癌の診断学を完成させた本邦で生まれた用語である2).
隆起の立ち上がり(finding of standing up in polypoid lesions)
著者: 赤松泰次
ページ範囲:P.587 - P.587
定義
胃隆起性病変の鑑別診断(アルゴリズム)1)において,“立ち上がり”の所見は重要である.山田分類(シェーマ)2)に従うと,I型とは“隆起の起始部が滑らかで,明確な境界線を形成しないもの”,II型とは“隆起の起始部に明確な境界線を認めるが,くびれはないもの”,III型とは“隆起の起始部に明らかなくびれを認めるが,茎はないもの”,IV型とは“明らかな茎を有するもの”と定義されている1).
噴門開大(食道裂孔ヘルニアを含む)(hiatal hernia)
著者: 金坂卓 , 上堂文也
ページ範囲:P.588 - P.588
定義
食道裂孔ヘルニアは胃の一部が食道裂孔に嵌入した状態であり,横隔膜ヘルニアの中では最も頻度が高い.内視鏡検査では食道胃接合部と食道裂孔の位置のずれを同定することで診断できる.食道裂孔ヘルニアはX線造影検査における形態の違いから滑脱型,傍食道型,混合型に分類される.
噴門開大は食道裂孔の大きさを反映し,胃内で反転観察したときに食道裂孔部にみられるスコープ周囲の間隙として認識される.Hillら1)は,噴門開大の程度を内視鏡的に評価したGEFV(gastroesophageal flap valve)の分類を提唱している(Fig. 1).GEFV分類のGrade III以上ではほとんどの例で食道裂孔ヘルニアを合併しており,このGradeが高いほど逆流性食道炎を合併しやすいと考えられる.
幽門輪変形(pyloric deformity)
著者: 岸野真衣子
ページ範囲:P.589 - P.589
定義
正常な幽門は通常内視鏡観察時には開放しており,その輪郭は平滑である.しかし詳細にみると辺縁は決して正円ではなく,多くの場合小彎側が幽門輪内に突出している1)(Fig. 1).
幽門輪変形は,辺縁のひきつれや浮腫,発赤など軽度のものから,胃内容物の流出障害を来す狭窄までを指す.軽度の変形は,十二指腸潰瘍や幽門部びらんなど良性疾患によるものが多いが,伸展性の悪い変形や狭窄は,胃癌,十二指腸癌や他臓器癌の浸潤など悪性疾患によるものも多い.
腺境界(atrophic border)
著者: 吉田将雄 , 小野裕之
ページ範囲:P.590 - P.590
定義
解剖学的には固有胃腺は口側から噴門腺,胃底腺,幽門腺の領域に分類されるため,腺境界は噴門腺─胃底腺境界と胃底腺─幽門腺境界の2つが存在するが,一般に腺境界とは後者のことを指す.H. pylori感染をはじめとする慢性炎症により胃底腺の減少・消失が起こり,胃底腺粘膜が幽門腺類似の腺管へ変化し(偽幽門腺化生),境界が変動していくため萎縮境界とも呼ばれる.具体的には腺境界は前庭部から胃体部小彎側を中心に弧を描きながら口側に移動し,噴門を越えた後に,胃体部大彎側へ移動する.萎縮境界には非萎縮粘膜と萎縮粘膜が混在するため,厳密には萎縮のない胃底腺領域の肛門側限界線(F線),胃底腺が巣状に残存する中間帯,中間帯の肛門側限界線(f線)から成り,線というよりは幅をもって帯状に存在する1).
架橋ひだ(bridging fold)
著者: 阿部洋文 , 梅垣英次
ページ範囲:P.591 - P.591
定義
粘膜下層以深に病変の主座を置く隆起により周囲粘膜が引っ張り上げられて,隆起の周囲から隆起表面に向かい,橋が架かるように途絶せずなだらかに移行するひだのことをbridging fold(架橋ひだ)と定義される1).この所見を認めた場合,粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)や非上皮性腫瘍を第一に考える.ただし,癌でも粘膜表層でなく粘膜下層以深に腫瘍塊を形成した場合や,粘膜下層にリンパ組織増生(carcinoma with lymphoid stromaなど),線維化,粘液産生を伴う場合にも同様の所見を呈することがある.
delle
著者: 岸田圭弘 , 小野裕之
ページ範囲:P.592 - P.592
定義
delleとは,ドイツ語で凹窩・くぼみを意味する.内視鏡所見では0-IIc型病変や潰瘍性病変といった上皮性病変に用いられることは少なく,非腫瘍粘膜に被覆された粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)の粘膜面にできた小陥凹・小潰瘍を示す場合に用いられる(Fig. 1〜3).すなわち,間葉系腫瘍のうちGIST(gastrointestinal stromal tumor),筋原性腫瘍である平滑筋腫,神経原性腫瘍である神経鞘腫・顆粒細胞腫,脂肪腫,glomus腫瘍のほか,悪性リンパ腫,また上皮性腫瘍のなかでも基底膜由来のカルチノイドや他臓器癌の壁内転移などの病変に用いられる1).なお,異所性膵組織(迷入膵)の導管開口部にみられる陥凹については,臍窩と呼ぶ.
牛眼像(bull's eye appearance)
著者: 細川治 , 柳本邦夫
ページ範囲:P.593 - P.593
定義
bull's eye appearanceは皮膚疾患や眼疾患などのさまざまな医学領域で使用されている用語である.胃においては血行性に転移した転移性腫瘍が粘膜下層や固有筋層で成長して半球状の形態を示す場合に用いられる1).周囲より明らかに隆起した類円形の限局性病変で,中央にdelleや潰瘍形成を伴う.隆起の立ち上がりは周囲粘膜と同様の性状を呈しているが,頂部に向かって次第に変化を来す場合が認められる.一方,頂部の一段低くなった領域に達するまで変わりない粘膜に覆われることがあり,その形態は転移してきた癌腫の細胞成分や線維成分の増殖の多寡により異なる(Fig. 1〜4).最初に悪性黒色腫転移例が報告された2)が,肺癌,膵癌,結腸癌,悪性リンパ腫の胃転移例でも同様の特徴を持つことがある.乳癌の胃転移はこの形態をとらず,スキルス胃癌に類似した形状が多く報告されている.
クッションサイン(cushion sign)
著者: 細谷和也 , 小野裕之
ページ範囲:P.594 - P.594
定義
粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)は“粘膜よりも下方に存在する壁内病変により粘膜が挙上されて生じた隆起”である1).鑑別にあたり,まず通常観察で部位や腫瘍径,個数,色調,表面性状を観察する.続いて鉗子で押した際の変形・可動性により粘膜内病変の硬さを類推する.脂肪腫のような軟らかい病変であれば,鉗子で圧迫した際に,表面が下降し,圧迫を解除すると速やかに元の形態に戻る.これを“cushion sign”(Fig. 1,2)あるいは“pillow sign”という2).また,空気量や蠕動など外力による変形(squeeze sign)や,粘膜を生検鉗子で把持し,引っ張り上げた際にテントを張ったような形態(tenting sign)がみられれば,同様に軟らかな病変が予想される.
圧排像(compression)
著者: 赤松泰次
ページ範囲:P.595 - P.595
定義
圧排像とは,胃に隣接する臓器(肝臓,脾臓,膵臓,小腸,大腸,食道,リンパ節,腹膜など)によって,胃壁の一部が圧迫される所見である.原因はさまざまで,隣接する臓器の病的腫大(炎症や腫瘍など),囊胞,腸管ガスなどがある.圧排像を認める部位より,原因臓器の推定がある程度可能である.例えば,胃上部前壁の圧排は肝臓(Fig. 1)や脾臓,胃体部後壁の圧排は膵臓(Fig. 2,3)1),胃体部大彎の圧排は腸管などが多い.
Dieulafoy潰瘍(Dieulafoy's lesion)
著者: 丸山保彦
ページ範囲:P.596 - P.596
定義
1898年にフランスのDieulafoy1)が,コイン大の比較的小さく浅い潰瘍から大量の吐血を来し失血死すると報告した潰瘍である.内視鏡検査では,潰瘍が浅く小さな割にアンバランスな太い露出血管がみられることが特徴的所見である(Fig. 1).胃体上部に好発し,潰瘍周囲には浮腫性の隆起や皺襞集中は通常認められない.明確な定義がないため,angiodysplasia,angioectasiaやAVM(arteriovenous malformation)などのさまざまな疾患と混同して報告されることもあった.
胃底腺ポリポーシス(fundic gland polyposis)
著者: 春間賢 , 鎌田智有
ページ範囲:P.597 - P.597
定義
胃底腺の過形成と囊胞状拡張から成る胃底腺ポリープが,胃体部から胃穹窿部に多発するものを胃底腺ポリポーシスと呼び,個数には定義はなく,もともとは家族性大腸腺腫症に合併した胃病変として報告された1).その後,家族性大腸腺腫症に合併しない胃底腺ポリポーシスも指摘され2),胃底腺ポリープは,Helicobacter pylori(H. pylori)感染陰性の胃に発生することが多く3),H. pylori感染陰性者が増加しているため,最近では,家族性大腸腺腫症に合併しない胃底腺ポリポーシスの頻度が増えている.さらに,最近,プロトンポンプ阻害薬(proton pump inhibitor ; PPI)の長期投与で胃底腺ポリープが新たに発生し,既存のポリープが増加・増大し,胃底腺ポリポージスの形態を示すことがある4).PPIによるものは,薬剤の減量,H2受容体拮抗薬への変更,あるいは中止で改善する.
竹の節状外観(bamboo-joint like appearance)
著者: 斉藤裕輔 , 横田欽一
ページ範囲:P.598 - P.598
定義
主にCrohn病(Crohn's disease ; CD)患者の胃に認められる画像所見である.胃噴門部から胃体部小彎にかけて2〜4条の腫大した皺襞と,それらを規則正しく横切る亀裂状の陥凹が縦に配列する所見を“竹の節状外観”とした(Fig. 1,2).また,皺襞の腫大が目立たず,軽微な浅い陥凹のみの所見も認められることがあり,縦走配列陥凹(longitudinally aligned furrows)とした1)2)(Fig. 3).
耳介様周堤(リンパ腫)(auriculate ulcer mound)
著者: 中村昌太郎 , 松本主之
ページ範囲:P.599 - P.599
定義
潰瘍形成を伴う消化管腫瘍において,潰瘍辺縁に認める不整所見のない健常粘膜に覆われた幅の狭い隆起部分を耳介様周堤と呼称している.その形状が耳介の耳輪に類似していることに由来する.
一般に,耳介様周堤は分化型癌ではみられず,びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(diffuse large B-cell lymphoma ; DLBCL)などの高悪性度リンパ腫に特徴的な所見とされている(Fig. 1 1)〜3).しかし,低分化腺癌やリンパ球浸潤胃癌を含む未分化型癌でも,しばしば耳介様周堤を呈するので注意が必要である.このほか,腸管Behçet病または単純性潰瘍,サイトメガロウイルス感染性腸炎などでみられる打ち抜き様潰瘍でも,同様の周堤が観察されることがあるが,耳介様周堤の名称は,通常は腫瘍性病変に限定して使用される.
RAC(regular arrangement of collecting venules)
著者: 八木一芳
ページ範囲:P.600 - P.600
定義
Helicobacter pylori(H. pylori)未感染の正常胃では胃底腺領域に集合細静脈が規則的に配列する像が観察される.その内視鏡像をRAC(regular arrangement of collecting venules)という1)2).遠景では“規則的な無数の点”として視認され,近接では“ヒトデ状の模様が整然と配列する像”として視認される1).このRAC像が胃体部全体に観察される場合,RAC陽性としてH. pylori未感染の正常胃と判定する1)2).RAC陽性の場合は95%の正診率でH. pylori未感染の正常胃である1)2).
腺窩辺縁上皮〔marginal crypt epithelium(MCE)〕
著者: 八尾建史
ページ範囲:P.601 - P.601
定義
シェーマ1は,胃体部腺粘膜の表面から腺窩(crypt)までの比較的表層の組織断面図である.なお,腺頸部から深部の構造は光が到達しないので省略している.胃体部の腺窩は,粘膜表面に対して垂直に凹んでいるのが特徴である.組織学的には,表面の被蓋上皮(surface epithelium)も腺窩の上皮(crypt epithelium)も同じ腺窩上皮(foveolar epithelium)から成るが,NBI併用拡大内視鏡で視覚化される像は異なる.したがって,表面上皮(surface epithelium)と腺窩のへり,すなわち腺窩辺縁上皮(marginal crypt epithelium ; MCE)に区別する.一般に,NBI併用拡大内視鏡において,表面上皮は視覚化されないので,腺窩辺縁上皮が表面微細構造の指標として拡大内視鏡診断に用いられる1).
シェーマ2に腺窩辺縁上皮が視覚化される機序を示している.垂直方向に配列した腺窩辺縁上皮に短波長の狭帯域光を投射すると,後方散乱が起こり,それが垂直方向に集積し,白色半透明の帯状の腺窩辺縁上皮として視覚化される1).
white zone
著者: 八木一芳
ページ範囲:P.602 - P.602
定義
NBI拡大観察時,粘膜模様は白っぽい縁で認識される.その白っぽい縁がwhite zone1)2)である.血管を内包する粘膜模様の縁取りをするwhite zone(Fig. 1,黄矢印)や点状や円形に観察されるwhite zone(Fig. 1,白矢印)が存在する.前者は乳頭・顆粒状の粘膜模様で観察され,後者は小さな円形開口部などに観察される.
NBI拡大観察で真上から観察した場合,腺窩辺縁上皮に入るNBI光は血管に当たらず,散乱により白縁として観察される.この腺窩辺縁上皮がwhite zoneとして観察される(Fig. 2)2).しかし,斜めからNBI拡大観察した場合は窩間部から腺窩上皮に抜けるNBI光が血管に当たらず,散乱により白縁として観察される.すなわち,窩間部から腺窩上皮の部分がwhite zoneとなる(Fig. 3)2).このようにwhite zoneは基本的に上皮を表しているが,NBI光の方向によって表す上皮の解剖学的部位は異なる.
light blue crest
著者: 上堂文也
ページ範囲:P.603 - P.603
定義
胃の腸上皮化生はH. pyloriの慢性感染によって,胃粘膜が腸の形質を持つ粘膜に変化する現象で,胃癌発生のリスクと密接に関連している.NBI併用拡大観察で腸上皮化生をみると,上皮の辺縁部(表面)に青白色調の光の線を認める(Fig. 1,2).これが,LBC(light blue crest)で“上皮の表層を縁取る青白い線”と定義されている1).病理組織学的腸上皮化生の診断に有用である(感度:89%,特異度:93%).
白色不透明物質〔white opaque substance(WOS)〕
著者: 八尾建史
ページ範囲:P.604 - P.604
定義
2002年に筆者ら1)は,拡大内視鏡を胃粘膜に応用し,世界に先駆けて早期胃癌に特徴的な微小血管構築像について報告し,従来の内視鏡で診断が困難な胃病変に対する癌・非癌の鑑別診断に有用であることを報告した.一方,正常胃粘膜においては観察されないが,毛細血管レベルまでの分解能を有する拡大内視鏡を用いても,慢性胃炎粘膜における腸上皮化生・腺腫・癌の表層に白色の物質が存在し,上皮下の血管が透見できない現象を発見した.しかしながら,当時は本物質の正体が不明であったので,白色不透明物質(white opaque substance ; WOS)と命名し,早期胃癌と胃腺腫を鑑別する新しい光学的マーカーとなりうる可能性について報告した1)(Fig. 1,2).長らく,WOSの正体は不明であったが,ついにその正体は,“上皮を含む腫瘍の表層部に集積した微小な脂肪滴であること”(Fig. 3)を明らかにした2).さらに,胃のみならず大腸のあらゆる上皮性病変についてもWOSが存在することとその臨床的意義について,報告した3).
corkscrew pattern
著者: 金坂卓 , 上堂文也
ページ範囲:P.605 - P.605
定義
Nakayoshiら1)は陥凹型早期胃癌の拡大内視鏡所見に着目し,メッシュ様のネットワークを形成する微小血管を“fine network(Fig. 1)”,孤立して無秩序に走行する微小血管を“corkscrew(Fig. 2)”と定義している.前者は分化型癌の66%(72/109)および未分化型癌の4%(2/56),後者は分化型癌の4%(4/109)および未分化型癌の86%(48/56)に認められ,それぞれ分化型癌および未分化型癌と関連する所見と考えられた.Sumieら2)はこれらの所見の,分化型癌と未分化型癌の鑑別に対する診断能を後向きに評価している.早期胃癌100病変の検討で,感度,特異度,正診率はそれぞれ62%,86%,79%であった2).
WGA(white globe appearance)
著者: 土山寿志
ページ範囲:P.606 - P.606
定義
WGA(white globe appearance)とは,“NBI併用拡大内視鏡観察中に認める,上皮直下に存在する小さな(1mm以下の)白色球状外観”と定義されている.“上皮直下”とは上皮内の微小血管下に存在することを意味し,“球状”であることは中心から辺縁に向かって白さが乏しくなることから推測できる(Fig. 1)1).NBI併用拡大内視鏡の拡大倍率は問わないが,最大倍率のほうがWGAを判定しやすい.なお,頻度は不明であるが食道腺癌や大腸癌でも確認できる内視鏡所見である.
VEC pattern
著者: 金光高雄 , 八尾建史
ページ範囲:P.607 - P.607
定義
VEC(vessels within epithelial circle)pattern(円形上皮内血管パターン)とは,NBI併用拡大内視鏡観察において,正円形(circular)の腺窩辺縁上皮(marginal crypt epithelium ; MCE)で囲まれた円形の窩間部上皮下に血管が存在する所見である1)(Fig. 1,2).
NBI併用拡大内視鏡により視覚化される正円形の上皮は,組織学的に乳頭状すなわち指状の突起部を縁取る腺窩上皮に対応する(Fig. 3).また,内視鏡で捉えられた円形上皮内の血管は,組織学的に指状の突起部の上皮下の間質に増生した血管に対応する(シェーマ).
foveolar type,groove type
著者: 神崎洋光 , 上堂文也
ページ範囲:P.608 - P.608
定義
胃の拡大内視鏡観察において観察される胃粘膜構造の分類である.
foveolar type(腺窩型,Fig. 1).腺開口部が点状〜単線状の形態を表す粘膜構造を示す.胃底腺領域においてH. pylori未感染の正常粘膜,または萎縮や腸上皮化生の少ない胃底腺粘膜の模様はこのタイプである.病理組織学的に管状の腺管が“窩(あな)”状に開口する粘膜の表面構造を反映する.
A-B分類(A-B classification)
著者: 八木一芳
ページ範囲:P.609 - P.609
定義
Helicobacter pylori(H. pylori)慢性胃炎は炎症とともに粘膜萎縮を生ずる.拡大内視鏡的にその変化は胃底腺粘膜で著明である.幽門腺粘膜ではその変化は乏しい.H. pylori未感染の胃底腺粘膜の拡大内視鏡像をB-0,H. pylori未感染の幽門腺粘膜の拡大内視鏡像をA-0とし,H. pylori感染により生ずる拡大内視鏡像の変化を示したものがA-B分類である(Fig. 1)1)2).
多発性白色扁平隆起〔multiple white and flat elevated lesions(MFWL)〕
著者: 川口実
ページ範囲:P.610 - P.610
定義
“白色扁平隆起”は筆者ら1)が2007年に報告したもので,その通常内視鏡所見の特徴は,①白色,②扁平隆起,③多発性,④胃体部に認める,⑤周囲粘膜に萎縮がない,などである(Fig. 1,2).病理組織学的特徴は,①腺窩上皮の過形成,②胃底腺萎縮,③炎症細胞浸潤は軽度で,単核球主体などである(Fig. 3).
その後,春間ら2)が多数例を検討し,“多発性白色扁平隆起(春間・川口病変)”として報告している.
良性サイクル(benign cycle)
著者: 小澤俊文
ページ範囲:P.611 - P.611
定義
胃潰瘍は臨床経過により急性潰瘍と慢性潰瘍とに分類される.良性サイクルとは,後者の慢性潰瘍で観察される,治癒と再発を繰り返す病態を指す.急性潰瘍がストレスや薬剤など明らかな原因と考えられる要因を除去することで治癒に向かい,再発や難治化を来さないことと対照的である.病期的には,活動期,治癒過程期,瘢痕期に分類される1)(Table 1).Helicobacter pylori感染などの原因が除去されないと,A1→H1→S1→A2→H2→S2のように潰瘍が再発と治癒を繰り返す(Fig. 1〜6),すなわち良性サイクルが観察されることとなる2).再発性潰瘍では活動期でも皺襞集中を伴う(Fig. 4).
悪性サイクル(malignant cycle)
著者: 赤松泰次
ページ範囲:P.612 - P.612
定義
シェーマ1)に示すように,良性の消化性潰瘍は活動期(A1,A2),治癒過程期(H1,H2),瘢痕期(S1,S2)と変化し,再発すると瘢痕期から再び活動期に戻ることを“良性サイクル”と言う(崎田・三輪分類)1).また,陥凹型早期胃癌(0-IIc病変)の中に形成される潰瘍も同じような経過を示し,これを“悪性サイクル”と呼ぶ.すなわち,0-IIc病変内に潰瘍を形成すると,0-III病変(活動期に相当)または0-III+IIc病変(Fig. 1)ないし0-IIc+III病変(治癒過程期に相当)となり,潰瘍が瘢痕化すると0-IIc+Ul scar(瘢痕期に相当,Fig. 2,3)に肉眼型が変化する.さらに,潰瘍が再発すると0-III病変ないし0-III+IIc病変に戻る.しかし,胃癌と診断した時点で通常切除されるため,悪性サイクル全体を通して観察する機会は少ない.
胃粘膜萎縮の内視鏡所見(endoscopic findings of gastric atrophy)
著者: 榊信廣
ページ範囲:P.613 - P.613
定義
胃粘膜萎縮は一般的に“組織学的な胃固有腺の減少・消失”と定義される.updated Sydney system1)では,“胃粘膜萎縮は腺組織の減少と定義される.萎縮は粘膜の菲薄化を導き,強い粘膜障害を起こすすべての病的状態の基準となる”と記載されている.
日本人に一般的にみられるHelicobacter pylori(H. pylori)感染胃炎の結果として発生する萎縮性胃炎の場合は,胃底腺が萎縮・消失する変化だけでなく,腸上皮化生,そして腺窩上皮の過形成を伴い複雑な形態をとるのが一般的である.
画像所見〔十二指腸〕
しもふり潰瘍(salt and pepper ulcer)
著者: 春間賢 , 鎌田智有
ページ範囲:P.614 - P.614
定義
オリジナルは,十二指腸潰瘍症例の,不均一な発赤した十二指腸球部粘膜に観察される,小さな白苔が点々とみられる状態を意味し,集簇することが多く,所見が霜降り肉に似ていることから,大井1)によりカタカナ表記のシモフリ潰瘍と名付けられた.その後,シモフリ状態2)やシモフリ像3),しもふり潰瘍4)あるいは霜降り潰瘍と呼ばれ,表層の病変であることから,“しもふり”あるいは“霜降りびらん”とも呼ばれるようになっている(Fig. 1).
ridge
著者: 赤松泰次
ページ範囲:P.615 - P.615
定義
十二指腸潰瘍はしばしば多発傾向があるが,2つの十二指腸潰瘍(瘢痕)の間に形成される稜線状の変形をridgeと呼ぶ(Fig. 1).ridgeを形成すると十二指腸球部は偽憩室様の変形を来すことがあり,変形した部分を“タッシェ”(Fig. 2)という.ridgeは単発の十二指腸潰瘍では形成されず,2つの潰瘍の治癒過程で生じる線維化により,潰瘍がお互いに引き合うようにして形成される.
タッシェ(tasche)
著者: 入口陽介 , 山里哲郎
ページ範囲:P.616 - P.616
定義
タッシェ(tasche)は,十二指腸球部の潰瘍または潰瘍瘢痕による潰瘍側の収縮とそれによる正常部分の憩室様膨隆を示すX線造影所見で,潰瘍と幽門輪との間に認められる(Fig. 1〜3).
十二指腸潰瘍のX線診断は,Akerlund(1921年),Berg(1926年)らによってほぼ確立された.タッシェは,1918年に,Hartにより初めて記載され,Schinzによって球部変形のX線所見は大彎側に多く認められることが報告された.その後,Stein(1964年),白壁(1965年)によって十二指腸球部変形の整理がなされた.白壁1)は,変形,狭窄の程度に線状潰瘍,多発潰瘍,さらに瘢痕化潰瘍の概念を加え診断図を示した.十二指腸球部変形は,十二指腸球部の大彎・小彎側の彎入,十二指腸球部の攣縮,タッシェ形成,十二指腸球部萎縮すなわち十二指腸球部癆などがある.辺縁の所見で,陥凹を示すもの(切れ込み,彎入,陥凹,牽引)と出っぱりを示すもの(タッシェ,ニッシェ),それに幽門の変化として幽門非対称,幽門狭窄などがある2).
ノッチ(notch)
著者: 佐野村誠 , 國弘真己
ページ範囲:P.617 - P.617
定義
Crohn病に合併する上部消化管病変は,Crohn病の診断基準の副所見のひとつとして取り上げられている(Table 1).その中でも胃・十二指腸病変に特徴的な所見は,胃病変である“竹の節状外観”と十二指腸病変の“ノッチ様陥凹”である.いずれもインジゴカルミン撒布によりわずかに認識できる程度のものから,通常観察でも明らかに認識できる高度なものまでさまざまである.
十二指腸の“ノッチ様陥凹”は球部から下行部のKerckring皺襞(輪状ひだ)に数本の切れ込みを呈する所見である1).輪状ひだ上の陥凹をノッチ(Fig. 1)と呼び,縦に配列した“ノッチ様陥凹”を呈し,さらに高度になると,ひきつれ所見を伴う(Fig. 2,3).
胃上皮化生(gastric metaplasia)
著者: 金坂卓 , 上堂文也
ページ範囲:P.618 - P.618
定義
十二指腸に胃上皮化生が存在することは,1923年にNicholson1)によって初めて報告された.十二指腸粘膜に胃底腺組織と胃型被覆上皮の両者を有するものが異所性胃粘膜,これに対して胃底腺組織を伴わず胃型被覆上皮のみを有するものが胃上皮化生と定義されることが多い.
胃上皮化生は異所性胃粘膜と比較して萎縮性胃炎を合併する頻度が高く〔100%(16/16)vs. 16%(5/32)〕,Helicobacter pylori(H. pylori)陽性率も高い〔92%(12/13)vs. 9%(2/22)〕2).また,十二指腸潰瘍の生検組織の86%(38/44)に胃上皮化生が存在し,その大半にH. pyloriが存在することから,胃上皮化生へのH. pylori感染を十二指腸潰瘍の一因とする報告もある3).
異所性胃粘膜(ectopic gastric mucosa)
著者: 小林惇一
ページ範囲:P.619 - P.619
定義
広義には十二指腸に認められる異所性胃上皮全体を指すが,そのなかでも固有胃腺を伴ったものが狭義の異所性胃粘膜と呼ばれている.その成因は先天的な胃組織の迷入であるとされている.一方,固有胃腺を伴わない異所性胃上皮は胃上皮化生と呼ばれ,炎症などに伴ってみられる後天的な変化である.本項では狭義の異所性胃粘膜について述べる.
異所性胃粘膜の頻度は0.5〜2%と報告されている1)2).主として球部にみられる所見であり,典型的には,単発または多発の正色〜発赤調を呈する隆起性病変として認識される(Fig. 1,2).経時的に観察すると形態的変化は乏しいことが多い.異所性胃粘膜を母地とした発癌も報告されており,特に大きいものや形態が変化したものなどについては詳細な観察が必要である.
画像所見〔腸〕
縦走潰瘍(longitudinal ulcer)
著者: 斉藤裕輔 , 垂石正樹
ページ範囲:P.620 - P.621
定義
縦走潰瘍とは,厳密には腸管長軸方向に走行する4〜5cmを超える潰瘍と定義されるが,一般的には3cm程度の短い病変にも用いられている1).
輪状潰瘍(annular ulcer, circular ulcer)
著者: 大川清孝 , 上田渉
ページ範囲:P.622 - P.622
定義
輪状潰瘍は腸管の短軸方向に走行する潰瘍であり,幅が広くなったものを帯状潰瘍と言う.全周性でなくてもこの用語が用いられており,周在性に関する定義はない.ほぼ同様の意味で横走潰瘍という言葉が用いられることがある1).
アフタ,アフタ様潰瘍(aphtha, aphtoid ulcer)
著者: 吉岡慎一郎 , 光山慶一
ページ範囲:P.623 - P.623
定義
アフタ(aphtha)およびアフタ様潰瘍(aphthoid ulcer)については,一般的には口腔粘膜のアフタに類似した病変が消化管粘膜に認められる場合に用いられるが,明確な定義はなく異なる見解が混在している1)〜3).本稿では「日本消化器内視鏡学会用語集第3版」と「胃と腸用語事典」の両見解を踏まえ,アフタ,アフタ様潰瘍はほぼ同じ病変を指し示すものとし,単なるびらんと区別するために紅暈を伴う小さな潰瘍もしくはびらんを“アフタ様病変”と定義して解説する.
びまん性病変(diffuse lesion)
著者: 江﨑幹宏 , 松本主之
ページ範囲:P.624 - P.625
定義
“びまん性”とは“病変がはっきりと限定することができず広範囲に拡がっている状態”と定義され,“限局性”に対比する用語である.びまん性病変の所見は皺襞肥厚,皺襞消失,多発結節,顆粒状粘膜,およびこれらの組み合わせに分類される1).加えて種々の程度にびらんや潰瘍形成を伴う場合が多い.
炎症性ポリープ(inflammatory polyp)
著者: 清水誠治
ページ範囲:P.626 - P.627
定義
炎症性ポリープは炎症によって形成される粘膜の隆起であり,炎症を背景に形成されるポリープと炎症自体が構成要素であるポリープがある.
前者は狭義の炎症性ポリープである.多発すれば炎症性ポリポーシスと呼ばれるが,数についての規定はない.発生機序から,①粘膜固有層や粘膜下層の炎症によって形成される隆起,②多発潰瘍の周囲,介在粘膜が相対的に隆起(厳密には偽ポリープ),③潰瘍修復の際に炎症性肉芽が隆起,④炎症に伴う線維化により狭窄した腸管で相対的に粘膜がたるんで形成される隆起,⑤潰瘍治癒過程で過剰に再生した粘膜によって形成される紐状あるいは複雑な形状の隆起に分けられる1).炎症性ポリープ(ポリポーシス)を形成する疾患としては潰瘍性大腸炎とCrohn病が代表的であるが,大腸憩室疾患でもみられる.感染性腸炎では主に腸結核とアメーバ性大腸炎であるが,腸結核にみられる炎症性ポリープは萎縮瘢痕帯を伴い小型半球状である.
cobblestone appearance
著者: 山口智子 , 松本主之
ページ範囲:P.628 - P.628
定義
cobblestone appearanceは敷石像,敷石様外観とも呼ばれ,Crohn病(Crohn's disease ; CD)の診断基準の主要所見のひとつに挙げられている.多発潰瘍の介在粘膜に玉石状の隆起が多発した状態であり,その呼称はあたかも大小の石を敷き詰めた歩道のようにみえることに由来する(Fig. 1,2)1).cobblestone appearanceは小腸・大腸の活動期CDの特徴とされるが,密在した炎症性ポリープもcobblestone appearanceと呼ばれる.しかし,この際は縦走潰瘍を伴わない.活動期CDでは,敷石像に一致して病理学的には粘膜下層の浮腫と高度の炎症細胞浸潤がみられる.通常,深部大腸にみられることが多く,小腸では典型的なcobblestone appearanceを呈する頻度は低い.しかし,他の小腸疾患でcobblestone appearanceを伴う疾患は少ないため,CDの小腸病変の診断において特異性の高い所見とも言える.高度のcobblestone appearanceは難治化の予測因子でもあり,高度もしくは広範囲のcobblestone appearanceを認める症例では,早期の抗TNFα抗体などの治療選択が必要と考えられる.
網目像(fine network pattern)
著者: 赤坂理三郎 , 松本主之
ページ範囲:P.629 - P.629
定義
大腸の正常粘膜表面には腸管短軸方向にほぼ平行して走る無数の微細な溝があり,無名溝と呼ばれる.無名溝には時に交叉し,これによって囲まれるやや細長い“小区”があり,微細網目構造となっている.これは網目像(fine network pattern ; FNP)と呼ばれる.病変部分ではこの構造が消失し,組織学的な病変部分と一致している.
FNPは1965年にWilliams1)により“innominate grooves”として報告された.その後,1971年に狩谷,西澤ら2)は“innominate grooves”から形成される大腸粘膜の微細な模様を“網目像(FNP)”と名付けた.このFNPはX線造影像で再現可能な最小単位であり,大腸二重造影像の基本像となる(Fig. 1).
白色絨毛(white villi)
著者: 平田敬 , 蔵原晃一
ページ範囲:P.630 - P.630
定義
通常内視鏡観察時に,十二指腸あるいは小腸において,絨毛の外形に一致した白色化により粘膜面全体が均一に白色調を呈するものを白色絨毛,散在性に小さく明瞭な白点を示すものを撒布性白点(白斑)と呼称する.いずれの白色調変化も腸に吸収された食事性脂肪の転送障害あるいは遅延を反映しており,白色絨毛は吸収された脂肪の中心乳糜管への転送障害/遅延により脂肪が吸収上皮細胞内や粘膜固有層内に分布していることを,撒布性白点は中心乳糜管から中枢側への転送障害/遅延による中心乳糜管の拡張を反映しているとされる1).
白色絨毛と撒布性白点は必ずしも病的所見ではなく,健常者でも観察されることがある.食事性脂肪摂取量が多い場合や,胃運動能が低下している場合には,脂肪の吸収・転送が遅延する結果みられる.また,脂肪摂取から内視鏡検査までの時間が短い場合にも観察される.
緊満感(expanding appearance)
著者: 髙木亮 , 山野泰穂
ページ範囲:P.631 - P.631
定義
緊満感とは,主に隆起型腫瘍で用いる用語で,腫瘍が深部で膨張性発育を呈するため,腫瘍表面で風船が膨らんだような張りや光沢1)を示す所見のことである(Fig. 1〜4).癌の場合,①粘膜内または粘膜下層に浸潤した癌量が多いこと2),②SM高度浸潤を来すことによってDR(desmoplastic reaction)が生じること,③粘液癌の併存,などがこの所見の出現する原因と考えられるが,単独あるいは合併も含めてNET(neuroendocrine tumor)などの非上皮性腫瘍でも認められることがある.
non-lifting sign
著者: 永田務
ページ範囲:P.632 - P.632
定義
non-lifting signとは,Unoら1)に提唱された用語であり,腫瘍の粘膜下層(submucosa ; SM)に局所注射しても,腫瘍自体が盛り上がらず,SMに線維化を来している状態を示す.原因としては,SM以深への癌(腫瘍)の浸潤(Fig. 1,2)やUl-II以深への潰瘍合併,炎症や機械的刺激に伴う,間質反応や線維化があると考えられ,内視鏡的に判断できる所見である2).
大腸癌研究会より出されたガイドライン3)(2014年)によると,大腸癌の内視鏡治療の原則として,“癌が粘膜にとどまっている場合や,粘膜下層に浸潤していても,浸潤の程度がわずかで,転移の可能性が低いと判断される場合”とされている.
白斑(white spots)
著者: 廣田茂 , 松本主之
ページ範囲:P.633 - P.633
定義
大腸内視鏡検査の際に,病変の周囲を取り囲むように白色調の点状所見を認めることがある(Fig. 1〜3).これを白斑(white spots)と呼んでいる.進行大腸癌やSM癌の際に,病変よりわずかに距離をおいた粘膜にみられることが多い.腺腫性ポリープ(adenoma)の周囲にも認めることがある.この病変を取り囲むように存在する白斑の正体はfoamy cell(マクロファージ)である.白斑は粘膜表面にのみ存在するのではなく,病変を取り囲む城壁のように粘膜深部まで存在することもある1).
白斑(foamy cell)の意味することは,malignant potentialの高い病変に対する,進展抑制と考えられている.病変よりわずかに距離をおいて存在することから,物理的な壁として進展抑制をしているようにも見受けられるが,シグナルを出して系統的に進展抑制をしていると考えられている1).進行大腸癌に関して言えば,白斑の存在する群と存在しない群では,白斑の存在する群のほうが有意にリンパ節転移が少なかった1).腺腫性ポリープにおいては,現時点はおとなしいがmalignant potentialが高い可能性が考えられる.
陥凹局面(depressed irregular margin)
著者: 工藤進英
ページ範囲:P.634 - P.634
定義
われわれは大腸平坦・陥凹型病変における陥凹を辺縁の性状から棘状,星芒状,面状不整に分類した1).棘状不整とは,陥凹が棘状を呈し,辺縁隆部との段差が明瞭でなく,なだらかに移行する状態である(Fig. 1).一方,星芒状不整は内側に凸であり,面状不整は凸部分が認められない陥凹で,いずれも局面を有する陥凹である.この陥凹辺縁の不整は病変の性質をよく示している(Fig. 2).de novo腫瘍である陥凹型腫瘍では,局面を有する陥凹,すなわち陥凹辺縁の面状もしくは星芒状不整を呈することが一般的である(Fig. 3).一方で明瞭な局面を有さない平坦型病変(いわゆるIIa+dep)では,棘状不整を呈する.
skip lesion
著者: 朝倉謙輔 , 松本主之
ページ範囲:P.635 - P.635
定義
skip lesionとは,X線造影所見・内視鏡所見または肉眼的に消化管病変が正常粘膜像を介して離れて存在する状態の総称である(Fig. 1,2).診断基準改訂案1)にCrohn病にみられる所見として,“非連続性病変または区域性病変(skip lesion)”が明記されている.しかし,本症に特異的な所見ではない.潰瘍性大腸炎ではskip lesionの対義語である“連続性病変”が特徴とされ,skip lesionとともに両疾患を区別する重要な所見とされてきたが,必ずしも鑑別能は高くない.一方,Crohn病においてはskip lesionの介在正常粘膜においても本症の診断基準のひとつであるgranulomaが検出されることがある.
萎縮瘢痕帯(scared area with discoloration)
著者: 大川清孝 , 大庭宏子
ページ範囲:P.636 - P.636
定義
1977年に白壁ら1)の「大腸結核のX線診断」という論文により“潰瘍瘢痕を伴う萎縮帯”という用語が初めて記載された.その後一般的な使用には冗長的であったため萎縮瘢痕帯という表現が慣用的に用いられ,現在に至る2).白壁らは手術を施行し総合的に腸結核と診断した47例の肉眼所見,X線造影所見,病理組織学的所見などを検討した.その結果,腸粘膜またはリンパ節に乾酪壊死がみられ結核と確定診断できた症例と,非乾酪性肉芽腫を認めた,あるいは肉芽腫を認めなかった症例において,共通した肉眼所見として萎縮瘢痕帯を見い出した.すなわち,乾酪壊死を認めなくても,萎縮瘢痕帯を認めた場合には腸結核と診断できる可能性が高いと述べた.また,萎縮瘢痕帯を示す結核以外の疾患はほぼないことも根拠とした.萎縮瘢痕帯とは炎症性ポリープの多発,潰瘍瘢痕の多発,萎縮した粘膜などで構成される区域性領域であり,治癒傾向の著明な腸結核病変を意味する3).
偽膜(pseudomembrane)
著者: 三上栄 , 清水誠治
ページ範囲:P.637 - P.637
定義
偽膜とは白色から黄白色の扁平または半球状の丈の低い隆起であり,組織学的には壊死物質が塊状に粘膜上に堆積したものでフィブリン,粘液,好中球,および上皮残渣で構成される.
偽膜を認める腸炎を偽膜性腸炎と総称するが,臨床現場では通常Clostridium difficile感染症(Clostridium difficile infection ; CDI)のことを指す.CDIに伴う偽膜は全大腸に認めるが,その分布は左側結腸に高度で直腸にもみられる1).偽膜の周辺粘膜は正常か軽度浮腫状であり,びらんや潰瘍を伴うことはまれである(Fig. 1).進行例や重症例では,偽膜は増大し癒合傾向を示す(Fig. 2).偽膜性腸炎の病理組織像は偽膜の形成とその直下の表層粘膜の凝固壊死が特徴である.
coiled-spring appearance(sign)
著者: 蔵原晃一 , 田中貴英
ページ範囲:P.638 - P.638
定義
coiled-spring appearanceは腸重積に特徴的なX線造影像である(Fig. 1)1).腸重積の多くは腸管内の腫瘤性病変が先頭となって発症するが,重積部は3層の腸壁から成り,嵌入を受け入れる腸の部分を夾鞘部,嵌入する腸の部分を嵌入部,夾鞘部と嵌入部の間を受容部と呼称する.消化管X線造影検査において,腸重積の嵌入部と夾鞘部の間が緊密でない場合に夾鞘部と受容部の間隙に造影剤が進入し,夾鞘部のhaustraあるいはKerckring皺襞が密在して造影される.この像をcoiled-spring appearanceと呼ぶ1).また,嵌入部と夾鞘部の間が緊密で夾鞘部と受容部の間隙へ造影剤が進入しない場合,蟹爪像(concave pressure defect)と呼ばれるX線造影像を呈する1).
keyboard sign
著者: 横溝千尋
ページ範囲:P.639 - P.639
定義
腸閉塞などにより拡張した小腸内で,Kerckring皺襞がピアノの鍵盤(keyboard)状に類似した像を呈する腹部超音波所見である(Fig. 1).一般にイレウスの超音波所見は拡張した腸管と本所見のほか,血行障害を伴わない単純性イレウスでは腸内容物の浮動(to and fro movement)を,血行障害を伴う絞扼性イレウスでは腸内容物の浮動や腸蠕動の減弱を早期から認め,時間経過とともに腸管壁肥厚(静脈閉塞)や壁菲薄化(動脈閉塞),Kerckring皺襞が不明瞭化して腹水が急速に増加する(Table 1).イレウスの診断における腹部超音波検査は感度,特異度ともに腹部単純X線検査よりも優れているが1),閉塞部位や原因,絞扼の有無などの診断はCT検査に劣り2),絞扼性イレウスの超音波診断は陽性的中率73%との報告がある3).よって,現状は造影剤アレルギーなどCT検査禁忌症例,妊娠症例や救急のベッドサイドで超音波検査が重用されている.
apple-core sign
著者: 斉藤裕輔 , 杉山隆治
ページ範囲:P.640 - P.640
定義
apple-core sign(アップルコアサイン)は小腸・大腸の2型進行癌のX線的特徴とされている(Fig. 1〜3).
カラーボタン様潰瘍(collar-button ulcer)
著者: 鳥谷洋右 , 蔵原晃一
ページ範囲:P.641 - P.641
定義
カラーボタン様潰瘍は,主として重症潰瘍性大腸炎における下掘れ潰瘍のX線造影所見として用いられる.すなわち,潰瘍底部で側方に拡がった潰瘍がバリウム斑として描出された場合,その形態がカラーボタンに類似していることから名付けられた.潰瘍の深さはUl-IIにとどまるが,組織欠損が粘膜下層で水平方向に進展するため,潰瘍底部で幅の広い下掘れ状となり,そのためバリウム斑もカラーボタン状となる1).潰瘍性大腸炎では重症度の指標にとされているが2),潰瘍性大腸炎に限らず,Crohn病や腸管Behçet病(Fig. 1,2)3),腸管感染症の潰瘍でも同様の所見が認められる.
偽憩室形成(pseudodiverticular formation)
著者: 斉藤裕輔 , 富永素矢
ページ範囲:P.642 - P.642
定義
偽憩室形成は憩室様膨隆とも呼ばれ,全消化管で認められるが,特に十二指腸球部,小腸,大腸で高頻度に認められるX線造影・内視鏡所見である.
空気変形(air-induced deformation)
著者: 松下弘雄 , 山野泰穂
ページ範囲:P.643 - P.643
定義
空気変形とは空気量を増減することにより観察される内視鏡所見である.病変部と正常部の伸展性の違いにより生じる所見であり,主に表面陥凹型の病変に対して使用される用語である.
当初は「管腔内の空気を減量することで“病変の辺縁の正常粘膜,過形成性粘膜”が膨隆し相対的に陥凹部が著明になり,逆に空気を増量することで平坦化する所見を陽性とする」1)とした.しかし,実際には病変周囲のみではなく病変自体もその病変の質,腫瘍量に応じて変化するため,“病変および周囲粘膜を含めた変化”とみるのが妥当である.
スピクラフォーメーション(spicula formation)
著者: 川崎啓祐 , 松本主之
ページ範囲:P.644 - P.644
定義
spiculaとは垂直という意味であり,ある病変や構造物に対し垂直方向に伸びる棘状突起のことを指す.胸部X線検査やCT検査では肺癌を,マンモグラフィでは乳癌を疑う所見である.一方,消化管領域では注腸X線造影検査で認められる所見であり,炎症性腸疾患や感染性腸炎などでみられる1)2).すなわち,spicula formationとは注腸X線造影検査で腸管の長軸方向に対し垂直方向に伸びる棘状突起が描出されたものであり,軽微な粘膜欠損に合致する所見と考えられている(Fig. 1〜4).腸管が鉛管状になると,腸管壁が直線化しspicula formationが強調される.
腸管壁内ガス像(intramural gas appearance)
著者: 萱嶋善行 , 蔵原晃一
ページ範囲:P.645 - P.645
定義
腸管壁内ガス像は,小腸あるいは大腸の粘膜下ないし漿膜下にガスが貯留した所見を言う.多くは多発し腸管囊胞様気腫症(あるいは腸管囊腫様気腫など)と呼称される1).腸管囊胞様気腫症は特発性と続発性に分類され,続発性の多くは,各種消化管疾患,慢性呼吸器疾患,膠原病,薬剤(αグルコシダーゼ阻害薬など)などとの関係が推察されている2).本症は特徴的な含気性の多発性囊胞であることから,腹部単純X線や腹部CTでは,腸管壁に沿った大小不同,類円形のブドウ房状・蜂巣状の透亮像を呈する(Fig. 1a).X線造影検査では,腸管壁に一致した表面平滑で軟らかい多発性の粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)様の陰影欠損がみられる(Fig. 1b).内視鏡検査では,大小不同で半球状の軟らかい多発性SMT様隆起として認められる(Fig. 1c).生検を施行するとガスが排出され平坦化する.病理組織学的には気腫内腔を組織球や異物巨細胞が被覆する.漿膜下の気腫が腹腔内に破裂するとfree airとしてみられ,消化管穿孔との鑑別が必要になるが,腹膜刺激症状を伴わない.
鳥の嘴像(bird's beak sign)
著者: 進藤洋一郎 , 鶴田修
ページ範囲:P.646 - P.646
定義
S状結腸軸捻症は,S状結腸が腸間膜の長軸を中心として腸間膜根部で捻転したもので,360°以上捻転すると,S状結腸内腔は口側,肛門側共に閉塞し,馬蹄形に拡張する.結腸捻転症の中でS状結腸捻転が発生部位としては最多であり,360°の1回転がほとんどである.腹部単純X線像では,馬蹄形に拡張した腸管ガス像が特徴的であり(=coffee bean sign,Fig. 1),立位像では輸入・輸出両脚にそれぞれ鏡面像をみることもある.
注腸X線造影検査を行うと,注入したバリウムにより直腸は拡張するが,捻転を起こしている部より口側へはバリウムは進まない.内腔はこの盲端部に向かって先細り様に狭窄する.狭窄部より肛門側の直腸は拡張しており,この部が鳥の胴体のように見え,先細りの先端が嘴状に見える.そのため,狭窄部があたかも鳥の嘴のように見えることから,bird's beak sign(鳥の嘴像)と言われる(Fig. 2).
蟹爪様所見(crab's claw-like appearance)
著者: 斉藤裕輔 , 佐々木貴弘
ページ範囲:P.647 - P.647
定義
腸重積を示す注腸X線造影所見である.腸重積は腸管の一部が先進部となって腸蠕動とともに肛門側の腸管内腔に陥入し,腸管が重積状態となったもので,通過障害を来し絞扼性イレウスとなることが多い.重積の発生部位によって,①小腸─小腸型,②結腸─結腸型,③回腸─結腸型に分類されるが,頻度的には回腸─結腸型が最も多い1).
粘膜橋,粘膜紐,polypoid mucosal tag(mucosal bridge, mucosal tag)
著者: 福永秀平 , 光山慶一
ページ範囲:P.648 - P.648
定義
粘膜橋(mucosal bridge)とは消化管粘膜面の特異な形態に対する呼称であり,その病態は食道,胃,十二指腸,大腸にみることができる.大腸での報告が最も多く,形態上の特徴は消化管粘膜面から管腔方向にアーチ状に形成される橋梁構造であり,その橋桁に相当するband状の部分は浮腫状,不整形,平滑など種々の様相を呈するが,全周にわたって粘膜で覆われている.消化管内腔方向の面は本来の粘膜で,消化管壁方向の面は再生粘膜で覆われていることが多い(Fig. 1a,b)1).粘膜紐(mucosal tag)は,下掘れ潰瘍辺縁の粘膜がポリープ状に垂れ下がったものを指し,樹枝状,珊瑚状,ブドウの房状,鍾乳石状を呈するようになると粘膜橋に極めて近い状態となる(Fig. 1c)2).
内反(内翻),翻転(反転)(inversion)
著者: 小林広幸 , 渕上忠彦
ページ範囲:P.649 - P.649
定義
本邦の医学辞書には消化管に関連した内反・翻転に該当する用語の記載は乏しく,inversion(ステッドマン医学大辞典 第6版)で調べても,“内方,逆方向など既存の向きと反対の方向に向きを変えること”という漠然とした和訳のみで,国語辞典(大辞林 第3版)では“ひっくり返すこと”と記載されている.したがって,これを消化管(腸)の画像所見(疾患)に当てはめてみると(筆者の推測であるが),“その組織が本来あるべき部位から何らかの要因で腸管内に向きを変えている病態”と言えよう.これに該当する腸の疾患としては,Meckel憩室内翻,大腸憩室反転,虫垂翻転(重積)などが挙げられる.なお,これらの疾患では内反と翻転以外にも,同義語として内翻,反転という用語が少なからず用いられているが,各用語の厳密な区別はなされていない.
transverse ridging
著者: 貫陽一郎 , 江﨑幹宏
ページ範囲:P.650 - P.650
定義
“transverse ridging”は横に走るあぜ道を意味し,消化管画像所見においては腸管の長軸方向に垂直に走行するひだ所見を指す.Schwartzら1)が虚血性大腸病変でみられるX線造影所見のひとつとして報告したのが最初であり,主に注腸X線造影検査の画像所見として用いられる.
正常の大腸では十分な空気量で伸展させるとhaustra以外の皺襞は不明瞭となるため,本所見を認める場合には大腸壁の伸展不良が存在することが示唆される.成因としては腸管壁の浮腫性変化が主体と考えられているが,虚血性大腸炎の急性期にみられる拇指圧痕像とは異なり,浮腫に加えて線維化などによる区域性の伸展不良を伴うことにより,本所見が明瞭となる.
管状狭小(tubular narrowing)
著者: 永田信二 , 向井伸一
ページ範囲:P.651 - P.651
定義
国語辞典を引くと,狭小とは狭くて小さいこと,狭窄とは狭くすぼまっていること,と記載されている.腸管においては,狭小は内視鏡が挿入可能であるが,狭窄では内視鏡が通過しないことである.すなわち,管状狭小は正常の部分に比べて病変部で腸管径の減少した領域が管状に見える所見である.管状狭小,狭窄の場合,全体像の把握には注腸X線造影検査が必要になることがある1)(Fig. 1〜3).
鋸歯状(serrated)
著者: 田中義人 , 山野泰穂
ページ範囲:P.652 - P.652
定義
鋸歯状とは“のこぎりの歯”状の形態を指し,大腸において腺腔内にこのような構造を有する病変は鋸歯状病変と総称され,2010年のWHO分類ではHP(hyperplastic polyp),SSA/P(sessile serrated adenoma/polyp,Fig. 1),TSA(traditional serrated adenoma,Fig. 2)に大別されている.HPは長らく悪性化しえない非腫瘍性ポリープとして認識されていたが,近年の研究により,現在ではHPの一部はSSA/PもしくはTSAの初期病変と考えられており,さらにそれらが種々の遺伝子異常を背景として発癌するserrated pathwayが提唱された.特にSSA/PはBRAF変異,CIMP(CpG island methylator phenotype)といった遺伝子異常を高頻度に認め,孤発性MSI(microsatellite instability)陽性大腸癌の前駆病変として大変注目されている.
拇指圧痕像(thumb-printing)
著者: 蔵原晃一 , 田中貴英
ページ範囲:P.653 - P.653
定義
拇指圧痕像(thumb-printing)は,消化管X線造影検査の充盈像ないし二重造影像において,拇指で押した痕のように見える卵円形の丸みを帯びた陰影欠損を言い,辺縁に片側性ないし両側性に連なる像としてみられる.腸管の粘膜浮腫がX線造影の辺縁像に反映された所見であり,壁の伸展性は保たれているため,空気量の増減によりその像は変化しやすく,また蠕動亢進により強調される.同義語にpseudo tumors,scallopingなどがある1).
圧排像(exclusion, compression)
著者: 永田信二 , 向井伸一
ページ範囲:P.654 - P.654
定義
腸管が外部から圧迫されている状態である.原因は多岐にわたり周囲臓器,腫瘍,出血,浮腫などがある1).
収縮・攣縮(contraction, spasm)
著者: 佐野村誠 , 柿本一城
ページ範囲:P.655 - P.655
定義
収縮(contraction)とは,生理的,機能的な消化管の内径の減少であり,筋層の運動である蠕動運動や括約筋が閉じるために生じ,筋収縮と関連している.送気や圧力をかけることにより解除される1).大腸には7か所の生理的収縮を認める部位が知られている(シェーマ)2).注腸X線造影検査において,鎮痙剤を前投与した場合には,この生理的収縮はあまりみられないが,鎮痙剤を投与しない場合や,検査時間が長くなり鎮痙剤の効果が消失してしまった場合などに,しばしばみられる3).
攣縮(spasm)とは,非生理的,機能的な消化管の内腔の狭小化,急激な不随意の収縮であり,痛みと運動の歪みを伴う.攣縮状態のX線所見としては,小腸では通過時間の短縮,運動亢進所見としての粉雪像,分節像などがみられる.大腸では緊張亢進を反映するハウストラの不規則,痙攣性収縮による縦走レリーフ像,紐状陰影などがみられる1).
口腔内アフタ(oral aphtha)
著者: 大井充 , 梅垣英次
ページ範囲:P.656 - P.656
定義
アフタ(aphtha)は同類の語にアフタ様病変,アフタ性びらん,アフタ性潰瘍などがあり,今日までに報告された各文献で紅暈の有無やびらんと潰瘍の区別などの定義が少しずつ異なっており,かなりあいまいな表現である.ここでは「胃と腸用語集2012」に則り1),アフタ様病変として,紅暈を伴う小さな潰瘍もしくはびらんと定義する.“口腔内アフタ”も,口内炎や口腔内粘膜障害などとはっきり区別せず混同していることが多い.実際多くの症例で患者は“口内炎ができた”と訴える.
回盲弁開大(ileocecal valve incompetence)
著者: 三上栄 , 清水誠治
ページ範囲:P.657 - P.657
定義
“回盲弁”は回腸末端と盲腸との間に位置する弁状の構造物で,回腸末端の粘膜,粘膜下組織,および筋層が盲腸内腔へ入り込み,盲腸内で反転して上唇と下唇を形成し,結腸の内容物が回腸に逆流するのを防ぐ役割をしている1).その回盲弁が開大する代表的な疾患としては腸結核が挙げられる.腸結核は,感染の進展がリンパの流れに沿って起こり,感染に伴い粘膜表面に近いリンパ濾胞に結核結節が形成され濾胞外へと拡がる.最終的にそれが粘膜表面に露出し,潰瘍が形成される.そのため病変はリンパ装置の多い回盲部に好発する.腸結核に特徴的な画像所見としては,回腸末端から右側結腸にみられる多発性の不整形潰瘍,輪状・帯状潰瘍などの活動性病変と萎縮瘢痕帯や治癒過程の潰瘍病変との混在がみられる.それらが慢性的に繰り返され,粘膜のひきつれや変形が起こることで偽憩室を形成したり,回盲弁が開大したりすると考えられる2)(Fig. 1,2).
腸間膜付着側・付着対側(mesenteric side, antimesenteric side)
著者: 斉藤裕輔 , 稲場勇平
ページ範囲:P.658 - P.658
定義
腸間膜(mesentery)は腹部内臓を包み込む往復2葉の腹膜が合わさって生じる膜構造物を指し,狭義には空・回腸の間膜を腸間膜と呼ぶ.その根部〔腸間膜根(root of mesentery)〕は第二腰椎体の左方から右腸骨窩に約15cmの長さを持つ.腸間膜は消化管に出入りする脈管・神経の通路として重要である.
腸間膜付着側とは,空腸,回腸における小腸係蹄の内側を,付着対側とは小腸係蹄の外側を指す.内視鏡検査時に観察しやすい側がおおよそ腸間膜付着対側,斜向かいとなり見づらい部位が腸間膜付着側である.小腸疾患,特に炎症性疾患を診断する際,この腸間膜付着側・付着対側の概念は極めて重要である1).
haustraの消失(disappearance of haustra of the colon)
著者: 斉藤裕輔 , 垂石正樹
ページ範囲:P.659 - P.659
定義
haustra(結腸膨起)とは,結腸に特徴的に認められる,規則正しく配列する,結腸外側への隆起を指す.結腸には3か所の縦走筋層の発達した結腸紐を認めるため,その部位で収縮している.そのため結腸は全体として長軸方向にわずかに収縮しているが,結腸紐の間の部分では余った腸壁が手繰られて一定間隔をおいて区切るように外側に膨隆するhaustra(結腸膨起)と内腔の半月ひだが形成される.haustraは右側結腸でより目立つ1).
小黄色斑(small yellowish spot)
著者: 上野義隆 , 田中信治
ページ範囲:P.660 - P.660
定義
潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis ; UC)の活動期内視鏡所見のひとつで,粘膜上の微細な黄味を帯びた点状斑と定義されている.主に軽症のUCの活動部,UCの活動部の境界付近,活動部位の口側に正常粘膜を介して島状に認められる.1960年代直達鏡での観察が行われていた時代に,田島1)により本疾患の初期像として見い出され,報告,命名された.当時は粟粒膿腫あるいは粟粒膿瘍(miliary abscess)とも称されている.厚生労働省研究班の活動期内視鏡所見の軽度に分類される小黄色点と同義である.微小な黄白色の点が密に散在性に存在するが,背景粘膜が発赤している場合,その発見は容易である(Fig. 1〜4).UCの活動性病変の最小単位と考えられている.現在の電子スコープでは黄色ではなく白色点として観察されるが,慣習的に小黄色斑の名称が使用されている.
リンパ濾胞増殖(lymphoid follicular hyperplasia)
著者: 平野敦士 , 江﨑幹宏
ページ範囲:P.661 - P.662
定義
リンパ濾胞増殖とは,消化管の粘膜固有層または粘膜下層に多発性・びまん性に増大したリンパ濾胞を認める状態を指すが,同組織所見が推察される上皮性変化を認めない類円形小隆起の多発した画像所見に対しても用いられる.
一般には,リンパ濾胞増殖という用語は良性疾患で用いられるが,悪性リンパ腫で類似した画像所見を呈する際に便宜上用いられる場合もある.また,炎症性腸疾患でみられるアフタ様病変もリンパ濾胞増殖とほぼ同義語として取り扱われる1).直腸を中心とした遠位大腸にリンパ濾胞増殖を認める場合,炎症性腸疾患の初期病変をはじめとした疾患の鑑別が必要である.
ダンベル型(腫瘤)〔dumbbell type(tumor)〕
著者: 蔵原晃一 , 大城由美
ページ範囲:P.663 - P.663
定義
ダンベル(dumbbell)はウエイトトレーニング器具の一種である.dumbは“音が出ない”,bellは“教会の釣鐘”を意味し,中世欧州で,音が出ない状態にした教会の釣鐘をトレーニングに用いていた名残である.現在ではバーの両端に同じ大きさの重しがついた器具を指す.ダンベル型腫瘤とは,消化管の場合,管腔内と管腔外の両方向に同程度発育した腫瘤を言い1),GIST(gastrointestinal stromal tumor)の一型がそれに該当する.
GISTは,固有筋層内に存在するCajal介在細胞様の分化を呈し固有筋層に関連して発生するため,管腔内には粘膜下腫瘍(SMT)像を形成する2)(Fig. 1a)3).その発育形式から,管内型(intra-luminal),管外型(extra-luminal),壁内型(intra-mural)と混合型(管内管外型:dumbbell)の4型に分類されるが,胃では管内型が,小腸では管外型ないし混合型が多いとされる.混合型は固有筋層から粘膜下層側と漿膜下層側の双方向に同程度発育した場合を言い,ダンベル型を呈する.
憩室関連(憩室性)大腸炎(diverticular colitis)
著者: 清水誠治
ページ範囲:P.664 - P.664
定義
憩室関連(憩室性)大腸炎は憩室を伴う大腸の憩室間粘膜にみられる慢性炎症の総称として用いられる疾患名であり,通常憩室自体の炎症ではない1)2).欧米では多数の報告があり,segmental colitis,crescentic fold disease,diverticular disease-associated(chronic)colitis,diverticular colitis,SCAD(segmental colitis associated with diverticula/diverticulosis),SACD syndromeなど多彩な名称で報告されている.頻度は大腸内視鏡検査症例の1%前後,憩室症例の数%とされている1).本邦における報告例は少ないが,実際はそれほどまれな疾患ではないと考えられる.下痢,血便,腹痛などの症状を契機に診断されることが多いが,本症による症状とは限らない.欧米ではS状結腸の病変がほとんどであるが,右側結腸憩室の頻度が高い本邦では上行結腸にもみられる.
もともと,憩室に伴う炎症性変化と潰瘍性大腸炎(UC)・Crohn病(CD)の合併を区別することを目的につくられた概念である.欧米では直腸粘膜が内視鏡的にも生検組織学的にも正常であることが診断の必須条件とされている.しかし極めて多彩な病態を含むあいまいな疾患概念であり,今後疾患概念の見直しが必要と考えられる.
イクラ状粘膜(salmon roe appearance)
著者: 斎藤彰一 , 平澤俊明
ページ範囲:P.665 - P.665
定義
“イクラ状粘膜”は,クラミジア直腸炎に特徴的な内視鏡所見(Fig. 1)である1)2).クラミジア直腸炎はChlamydia trachomatis感染による性行為感染症で比較的まれな疾患とされるが,通常の日常検査で遭遇する疾患のひとつである.特徴的な内視鏡所見を把握していなければ確定診断に至らない疾患である.
感染経路として,肛門性交により直接直腸粘膜に感染する場合や,感染した腟分泌物が直腸内へ流入する経路も考えられている.
target sign
著者: 松野雄一 , 江﨑幹宏
ページ範囲:P.666 - P.666
定義
target sign(標的像)は,1977年にWeissbergら1)が初めて使用した用語で腸重積時にみられる所見である.腸重積は,連続する腸管が嵌入することで発症する.重積部の横断面は,超音波検査で高エコー層と低エコー層が複数重なった類円形の腫瘤像として描出され,あたかも標的のように見えることからtarget signと命名されている(Fig. 1).別名multiple concentric ring signとも表現される2).CT検査においても,重積部は腫瘤像の内部に脂肪組織がリング状または三日月状に存在するように見えるため,同様にtarget signという用語が使用される(Fig. 2,シェーマ).なお,腸重積以外にも転移性肝癌が辺縁に低エコーを伴った高エコー性腫瘤として描出される際にtarget signが使用されることがある.
collagenous colitis
著者: 清水誠治
ページ範囲:P.667 - P.667
定義
1976年にLindström1)が慢性下痢と腹痛を来し,注腸X線や直腸鏡では異常がなく,直腸粘膜生検で上皮基底膜直下に厚い膠原線維束がみられた女性患者をCC(collagenous colitis)として最初に報告した.最近では主に組織学的所見に基づいて診断が行われている2).CCの病理組織学的特徴は,①大腸の表層上皮直下の膠原線維束の肥厚(≧10μm),②粘膜固有層のリンパ球・形質細胞浸潤,③陰窩の正常配列であり,④表層上皮の剝離・平坦化,⑤上皮内リンパ球の増加もみられる.
病因に関して自己免疫,遺伝的素因,腸管感染,胆汁代謝異常,食物アレルギーなどさまざまな仮説があるが,本邦では薬剤に関連した症例がほとんどである2)3).発症に関与するとされている薬剤は,プロトンポンプ阻害薬(PPI),非ステロイド性消炎鎮痛薬,H2受容体拮抗薬,アカルボース,選択的セロトニン再取り込み阻害薬,チクロピジン,スタチン製剤などが代表的である.
大腸メラノーシス(melanosis coli)
著者: 野村昌史 , 大森優子
ページ範囲:P.668 - P.668
定義
粘膜固有層内に黄褐色色素顆粒(リポフスチン)を満たしたマクロファージが出現することにより,大腸粘膜が褐色から黒色調を呈した状態で,センナ,大黄,アロエなどのアントラキノン系大腸刺激性下剤を長期間内服することにより生じる.このマクロファージは時に粘膜下層にもみられることがある.
1829年,Cruveilhierが慢性の下痢を訴える患者の大腸が墨汁(チャイニーズ・インク)のようだったと記載したのがはじまりとされ,Virchowは剖検例で同様の症例を経験し,大腸メラノーシスという用語を初めて使用した1).
非特異性多発性小腸潰瘍症(chronic enteropathy associated with SLCO2A1 gene)
著者: 梅野淳嗣 , 江﨑幹宏
ページ範囲:P.669 - P.669
定義
非特異性多発性小腸潰瘍症は,病理学的に肉芽腫など特異的な炎症所見のない潰瘍が小腸に多発する疾患である1)2).女性に好発し,持続的な潜出血による慢性の貧血と低蛋白血症を来し,難治性の経過をたどる.近年,プロスタグランジン輸送体をコードするSLCO2A1遺伝子の変異に起因する常染色体劣性遺伝病であることが明らかとなり,“CEAS(chronic enteropathy associated with SLCO2A1 gene)”という呼称が新たに提唱された3).同遺伝子変異は肥厚性皮膚骨膜症の原因でもあり,本症においても消化管外徴候として,ばち指,皮膚肥厚や骨膜症などを認めることがある.副腎皮質ステロイドやチオプリン製剤などは無効であり,貧血と低栄養状態に対する鉄剤投与や栄養療法が治療の中心となる.
腸間膜静脈硬化症(mesenteric phlebosclerosis)
著者: 大津健聖 , 平井郁仁
ページ範囲:P.670 - P.670
定義
腸間膜静脈硬化症(mesenteric phlebosclerosis ; MP)は,1993年にIwashitaら1)が新しい疾患概念として提唱した.基本的な病態は,腸壁から腸間膜静脈における石灰化に伴う腸管循環不全による虚血と考えられており,右側結腸を中心に炎症反応を伴わない慢性虚血性変化とされている.近年,MPと漢方薬長期内服との関連性が報告されている.なかでも,漢方薬で頻用される生薬である山梔子は8割以上の症例で内服されており,強い関連が考えられる2).MPを疑う症例には,特に薬剤内服歴などの詳細な病歴聴取が必要である.
大腸憩室(diverticulosis of the large intestine)
著者: 三上栄 , 清水誠治
ページ範囲:P.671 - P.671
定義
“憩室”とは消化管壁の一部または全層が壁外に囊状に突出した構造のことを言う.大腸憩室は憩室壁に固有筋層を欠く仮性憩室がほとんどを占める.欧米では30〜40%,本邦では10〜20%の頻度で認める1).欧米では9割以上がS状結腸に認められ,本邦では約7割が右側結腸に認められるが,加齢とともに左側大腸に認める割合が増加する1).大腸憩室の発生原因としては内圧の亢進が考えられており,憩室が起こる部位は大腸壁でも内圧の刺激に弱い血管筋層穿通部である結腸紐の両脇が多いとされている.そのため,初期の憩室の部位に太い静脈が観察されることが多い1)(Fig. 1).
大腸憩室の画像診断は注腸X線造影検査が最も適しており,特に腸管が長軸方向に短縮した多発憩室を認める症例では内視鏡検査による憩室の観察は困難であるが,注腸X線造影検査では描出が可能である(Fig. 2).画像上は腸管から突出するようなバリウムのたまりを認め,二重造影像では円形・涙滴様陰影を呈する(Fig. 3)が,変形を伴う場合は憩室炎の既往が疑われる.
画像所見〔全消化管〕
側面変形(lateral deformity)
著者: 入口陽介 , 小田丈二
ページ範囲:P.672 - P.672
定義
X線造影検査における,辺縁像は平滑な曲線を描くが,適切な空気量で十分に伸展した状態で撮影をすると,病変部における壁の伸展性の差による二重造影側面像が現れる.これを側面変形という(Fig. 1,2).病理組織学的に,癌部の癌細胞量とそれに伴う線維化などの器質的変化が壁の伸展性と関係していると考えられている.撮影する角度を変え再現性を考慮し,最も変形が強い部分を最深部として深達度診断を行う.しかし,側面像だけでなく,正面像による形態的特徴と照合して診断を行うことで,より正確な深達度診断を得ることができる.
牛尾ら1)は,消化管癌の側面変形の型を,無変形,角状変形,弧状変形,台状変形の4つのパターンに分類し,主に大腸の深達度診断に用いた.無変形は粘膜層〜粘膜下層にわずか,角状変形は粘膜下層への中等度浸潤,弧状変形は粘膜下層に高度浸潤〜固有筋層にわずか,台状変形は固有筋層またはそれ以深に浸潤した進行癌と報告1)した(シェーマ1).
discrete ulcer
著者: 亀田昌司 , 蔵原晃一
ページ範囲:P.673 - P.673
定義
腸炎(小腸炎・大腸炎)は,その肉眼所見から,びまん性炎症を伴う腸炎とdiscrete ulcerから成る腸炎に分類される1).discrete ulcerとは,ほぼ正常にみえる粘膜(normal-appearing intestinal mucosa)に周囲を取り囲まれた開放性潰瘍を言い,潰瘍自体の形態は問われないため原因疾患ごとに類円形,縦走,輪状潰瘍などさまざまな形態を呈する.discrete ulcerから成る腸炎の場合,多発性,非連続性に分布する多発性潰瘍の介在粘膜は発赤・浮腫を欠き,血管透見像もほぼ正常に観察される.
顆粒状,結節状(granular, nodular)
著者: 佐野村誠 , 柿本一城
ページ範囲:P.674 - P.674
定義
顆粒状(granular,シェーマ1))とは,数mm以下の半球状に近い隆起(顆粒,granule)が集合して存在する状態を言う.十二指腸のAA型アミロイドーシス(Fig. 1)など顆粒が小さい場合,微細顆粒状粘膜と呼称される.
結節状(nodular,シェーマ1))とは,顆粒より大きく,種々の大きさの小隆起(結節,nodule)が広範にみられる状態を指す2).その結節の大きさにより,小結節,粗大結節などと呼称される.
地図状潰瘍(geographic ulcer)
著者: 趙栄済
ページ範囲:P.675 - P.675
定義
“地図状”という用語は,“地図”から想起される形状への類似性の点から用いられている.したがって,表記者の主観に依拠するところが大きく,“不整形”という表現と重複する場合があり,“不整形地図状”とも形容される.“地図状潰瘍”は,共通する概念としては,比較的浅く,辺縁は不整形で拡がりがあり,連続性や大きさは問わない.また,潰瘍部が周辺と明瞭な差異を呈しないことが多いため,X線造影像よりも,主として微細な観察が可能な内視鏡像で表現される.
陰影欠損(schattenminus)
著者: 八巻悟郎 , 奥田圭二
ページ範囲:P.676 - P.676
定義
陰影欠損とはバリウムまたは空気(造影剤)で満たされた胃陰影の辺縁が,何らかの原因によって部分的に欠損した場合を言う1).通常は充盈像や圧迫像に対して用いられるが,半充盈のような二重造影や粘膜像に近い圧迫像に対して用いることもある.充盈の欠損または陰影の脱落は,胃内腔に向かって発育した腫瘍自体が間接に現す鋳型像にほかならない.つまり,胃内腔に向かって突出した隆起性病変であれば,胃癌に限らず陰影欠損として現れる(シェーマ)2).
癌に潰瘍を合併している場合は,陰影欠損(Schattenminus)の中に潰瘍部と一致して突出像(Schattenplus)が現れる.このことをSchattenplus im Schattenminusと言う.
打ち抜き潰瘍(punched-out ulcer)
著者: 吉田雄一朗 , 蔵原晃一
ページ範囲:P.677 - P.677
定義
打ち抜き潰瘍(punched-out ulcer)とは,境界明瞭で断崖状に下掘れする潰瘍を指す.腸管Behçet病,単純性潰瘍あるいはサイトメガロウイルス(CMV)感染症でみられることが多い.
腸管Behçetの病変は食道から直腸まで全消化管に生じうるが,好発部位は回盲部で,円形ないし類円形の境界明瞭な下掘れ潰瘍が特徴的であり,多くは打ち抜き潰瘍を呈し,定型病変とされる1)2)(Fig. 1a).病理組織学的には非特異的炎症によるUl-IVの開放性潰瘍である3).回盲部以外の大腸(Fig. 1b)や小腸あるいは上部消化管にも同時性ないし異時性に大小の潰瘍を認め,定型病変に類似した打ち抜き潰瘍を呈することがある.単純性潰瘍もまた回盲部および小腸と大腸にBehçet病と同様の打ち抜き潰瘍を認める1)〜3).CMV感染症(CMV食道炎,CMV胃腸炎)も全消化管に大小さまざまな潰瘍性病変を形成する.潰瘍の発症機序として,血管内皮細胞にCMVが感染し,内皮細胞機能障害,血管炎,血流障害を起こすためと考えられている3).本症の潰瘍は地図状,類円形,輪状など多彩な形態を呈するが,多くは下掘れ傾向で,小腸,大腸あるいは食道や胃(Fig. 2)に打ち抜き潰瘍を認めることがある3).
病理
深掘れ潰瘍,下掘れ潰瘍〔deep(-mining)ulcer, undermining ulcer〕
著者: 藤原美奈子
ページ範囲:P.678 - P.678
定義
潰瘍とは,組織の壊死に基づく粘膜や皮膚の一定の深さに達する組織欠損を潰瘍という1).病理学的に,組織欠損の深さにより潰瘍はUl-I〜IVまで亜分類される.Ul-III〜IVの深い潰瘍で辺縁が断崖状に切れ込んだ潰瘍を病理学的に“深掘れ潰瘍”と呼び,それを表す肉眼的所見用語として“打ち抜き潰瘍”や“punched-out ulcer”などが挙げられる(Fig. 1,2).もともと“深掘れ(ふかぼれ)”とは,“激しい流れや波浪などにより堤防の表法面(おもてのりめん,川側斜面)の土が削り取られる現象”を意味する河川用語で,その形状から,断崖状に切れ込んだ深い潰瘍を指して,この名称が生まれたと推察される.
“下掘れ潰瘍”あるいは“下掘れ”という言葉は,腸管Behçet病や単純性潰瘍において使用頻度の高い言葉(おそらく病理学的用語)であり2)3),しばしば“深掘れ潰瘍”と混同されやすい.しかし両者は異なった形状の潰瘍を指す病理学用語として用いられるべきであり,“下掘れ潰瘍”という言葉は字の通り,“下にえぐれる潰瘍”のことで,粘膜下層を主体に組織欠損が側面方向に深くえぐれるように認められる潰瘍のことを指すべきである(Fig. 3).
cobblestone像と炎症性ポリポーシス(cobblestone like appearance, inflammatory polyposis)
著者: 江頭由太郎
ページ範囲:P.679 - P.679
cobblestone像の定義
cobblestone像とは,Crohn病に特徴的な画像所見・肉眼所見で,縦走潰瘍の辺縁粘膜にみられる類円形の小隆起が“敷石状に”集簇した形態像である(Fig. 1).小腸,大腸いずれにもみられる所見であるが,大腸にみられる頻度が高い.cobblestone像は,表面の色調変化が乏しく平滑で,大きさ・形が比較的均一な隆起が均等に分布するのが特徴である.その成因は網目状に縦横に形成されたびらん・潰瘍による粘膜の区画化に加え,粘膜下の炎症を原因とする粘膜下組織の進展不良による粘膜層の縦横両方向の収縮が関与していると考えられる.
炎症性ポリポーシスの定義
慢性の炎症性腸疾患を基盤として発生する炎症性ポリープは多発することが多く,個数が多い場合は炎症性ポリポーシスと呼ばれる.炎症性ポリポーシスの成因は,慢性炎症による粘膜の過剰な再生により生ずる場合と,潰瘍の取り残した島状粘膜が多発ポリープ様の形態を呈する場合がある(後者は偽ポリポーシスとして,炎症性ポリポーシスと区別する考え方もある).ポリープの肉眼像は楕円形,棍棒状,紐状など不整形で奇妙な形態のものが多く,粘膜層の活動性炎症を反映して表面色調は発赤調を呈することが多い.filiform polyposisは指状,紐状の細長いポリープが集簇性に多発する,炎症性ポリポーシスの特殊型である.filiform polyposisはCrohn病,潰瘍性大腸炎のIBD(inflammatory bowel disease)や結核性腸炎でみられ,特にCrohn病での報告が多いが,Fig. 2の症例のように憩室症にも合併しうる.
結節状,顆粒状,微細顆粒状,絨毛状,分葉状,脳回状(nodular, granular, fine granular, villous, lobular, gyrus-like)
著者: 岩渕三哉 , 須貝美佳
ページ範囲:P.680 - P.681
定義
標記の用語を肉眼所見として用いる場合には,1個または複数の隆起から成る隆起性病変の表面性状の表現に用いられることが多い.結節状,顆粒状,分葉状,脳回状は複数の隆起の融合や集簇から成る隆起性病変の表面性状に用いられ,微細顆粒状と絨毛状所見は隆起表面の微細な性状に用いられることが多い.本稿では胃と大腸の隆起性病変について記載する.
粘膜下腫瘍様隆起(submucosal tumor-like protrusion)
著者: 海崎泰治
ページ範囲:P.682 - P.682
定義
粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)は,“主病変が周囲粘膜と同様の粘膜に覆われて半球状または球状に管内に突出した病変を総称する臨床的名称”であり1),腫瘍の病理学的疾患単位ではない.本邦では,1958年に胃粘膜下腫瘍において最初にこの臨床診断名が用いられ,1960年代前半までは胃の良性非上皮性腫瘍を総括的に診断する用語として用いられていた.その後,迷入膵や胃囊胞などの上皮性の病変や,悪性リンパ腫や当時の平滑筋肉腫などの悪性例なども“粘膜下腫瘍”に含まれることが知られるところとなった.よって,腫瘍という名称を用いるが真の新生物のみではなく炎症性腫瘤や囊胞などをも含む疾患の総称ということになり,前述の所見を有する病変は正確には“粘膜下腫瘍様隆起”の名称が用いられるべきである.
異型度と分化度(atypia, differentiation)
著者: 味岡洋一 , 加藤卓
ページ範囲:P.683 - P.683
定義
異型度(atypia)とは,腫瘍の発生健常組織との形態学的乖離の程度を表す用語で,乖離の程度が高いものは高異型度,低いものは低異型度と呼ばれる.一方,分化度(differentiation)は,異型度とは逆に,健常組織との形態学的類似性を表す用語で,類似性の高いものは高分化,低いものは低分化もしくは未分化,その中間は中分化と呼ばれる.異型度,分化度共に腫瘍の細胞像(細胞異型度,細胞分化度),組織構築像(構造異型度,構造分化度)の両者に用いられる.
管状,乳頭状,絨毛状,鋸歯状(tubular, papillary, villous, serrated)
著者: 新井冨生
ページ範囲:P.684 - P.684
定義
1.管状
“管状”は筒状構造をとり,間質は筒の外側に存在する形態に用いる(Fig. 1).腫瘍細胞の極性は,管腔内に分泌面が向かう.
形質(phenotypic expression)
著者: 九嶋亮治
ページ範囲:P.685 - P.686
定義
1.消化管における組織発生論の基本と形質
消化管粘膜に発生する円柱上皮系腫瘍の“形質”発現について解説する.腫瘍は発生母地の形態・機能を模倣するため,胃粘膜に発生する腫瘍は胃固有上皮に類似し“胃型”形質を,腸粘膜に発生する腫瘍は腸の上皮に類似し“腸型”形質を発現する.しかし,発生母地となる粘膜(前癌状態・病変)の形質が,炎症や化生などで正常(固有)粘膜から変化している場合,そこに発生する腫瘍の形質は前癌状態・病変のそれに類似しうるのである.つまり,“胃の腺腫や腺癌は腸上皮化生を伴う炎症を背景に発生することが多いため,腸型形質を多く発現するが,大腸の腺腫や腺癌にはそのような背景がないため,腸型(大腸型)形質を発現することが多い”という理解が基本となる.各部位の代表的病変における形質発現について簡潔に説明するが,例外も多く,同じ腫瘍内でも多様性があり,時間経過(進展)とともに変化しうる.
増殖帯(proliferative cell zone, generative zone)
著者: 根本哲生 , 土方一範
ページ範囲:P.687 - P.687
定義
増殖帯(増殖細胞帯・細胞増殖帯)とは,ある組織内で増殖能を有する細胞が領域性をもって集合している部分を指す.細胞増殖は基本的には機能的に分化しきっていない細胞(広い意味での未分化細胞)に起こると考えられるので,増殖帯は幹細胞および未分化細胞の分布する場とも言える.特に消化管ではその領域が“帯状”に分布していること,腫瘍発生の場と考えられること,分布の変化が病態を考えるうえで重要な情報となることから,増殖帯は消化管病理においては頻用される単語である.
細胞増殖周期に入っている細胞(G1,S,G2,M期,すなわちG0期以外の細胞)はKi-67(MIB-1)抗体で免疫組織化学的に核が染色される細胞として同定することが可能であり,消化管病理においてはKi-67陽性細胞が分布する領域を増殖帯と見なしている.
浸潤,偽浸潤(invasion, pseudoinvasion)
著者: 伴慎一
ページ範囲:P.688 - P.688
定義
悪性腫瘍である大腸癌(腺癌)は,粘膜組織に発生した後,粘膜下組織に侵入・増殖し,粘膜下組織への“浸潤”と呼ばれる(Fig. 1,2).一方,良性腫瘍である大腸腺腫も,その一部が粘膜下組織に侵入した所見を呈する場合があり,腺腫の“偽浸潤”と称されている1)(Fig. 3,4).偽浸潤という用語・概念は,大腸腺癌の明らかな粘膜下組織浸潤所見とは区別すべき,腺癌でない上皮性腫瘍が示す癌浸潤様所見が存在すること,粘膜下組織への腫瘍組織の侵入像が癌であることの絶対的な診断基準とはならないことを,“偽”浸潤として強調したものと理解される.S状結腸の比較的大型の有茎性病変を呈する腺腫によく認められる所見であり,蠕動運動に伴う捻転や牽引のような物理的な傷害が病変に繰り返し加わった結果,粘膜内の腫瘍組織の粘膜下への脱出を来したものと見なされている1)2).
簇出(budding, sprouting)
著者: 海崎泰治
ページ範囲:P.689 - P.689
定義
簇出(ぞくしゅつ,そうしゅつ)は組織学的な腫瘍の浸潤様式を表現する用語のひとつで,2010年の「大腸癌治療ガイドライン」1)において“癌発育先進部間質に浸潤性に存在する単個または5個未満の構成細胞から成る癌胞巣”と定義されている(Fig. 1).現在では,大腸癌内視鏡治療後の追加手術の必要性を検討するうえでの重要な病理組織学的因子であることが示されている.
“簇出”の用語の起源は1950年代に今井2)により提唱された.癌腫の発育様式のひとつとして簇出発育型が定義され,癌胞巣先端部における蕾状芽出像または個細胞性離脱像のほか,硬性(スキルス)癌のようなびまん浸潤像までの広い所見を指し,英語表記としては“sprouting”が用いられた.その後,現在の定義とほぼ一致した所見を指す概念として,“tumor budding”が提唱され,大腸進行癌症例においてリンパ管侵襲やリンパ節転移と相関し,リンパ管侵襲よりも発見しやすい所見であることが示された.しかし,それらの研究で用いられた簇出の定義や評価方法にはあいまいな要素を含んでいたため,大腸癌研究会のプロジェクト研究3)により“簇出”の厳密な定義をしたうえで,粘膜下層浸潤癌(SM癌)におけるリンパ節転移危険因子としての臨床的意義が検討された.その結果,簇出軽度(Grade 1)群(リンパ節転移6.7%と簇出高度(Grade 2/3)群(26.9%)の比較で両者に有意な差を認め,多変量解析では簇出が独立したリンパ節転移の危険因子であることが示された.
LEL(lymphoepithelial lesion)
著者: 伴慎一
ページ範囲:P.690 - P.690
定義
LEL(lymphoepithelial lesion:リンパ上皮病変)は,MALT(mucosa-associated lymphoid tissue)リンパ腫に特徴的で,その組織学的診断に際して重要な所見として,MALTリンパ腫の概念の提唱とともに注目されるようになったものである.増殖したリンパ腫細胞が,3個以上の小集簇を呈して粘膜上皮・腺管部に浸潤し,浸潤部の腺管の変形・破壊を来している所見を言う1)〜3)(Fig. 1〜4).
collagen band
著者: 松原亜季子 , 九嶋亮治
ページ範囲:P.691 - P.691
定義
collagen bandまたはsubepithelial collagen bandとは,粘膜最表層,被蓋上皮直下に沈着した膠原線維の帯状構造物を指し,CC(collagenous colitis)およびCG(collagenous gastritis)でみられる所見である(Fig. 1).
英語文献を検索すると,subepithelial collagen bandとともにsubepithelial collagen layerという用語も散見でき,英文ではどちらを使用してもよいようである.なお,1976年にLindström1)が最初にCCの症例報告を行った際はcollagenous layerと記載されている.この表現は1990年代まではよく使われていたが,最近は少数派である.
腺管立ち枯れ像(ghost outlines of crypt)
著者: 鬼島宏
ページ範囲:P.692 - P.692
定義
腸管粘膜が陰窩(腺管)の形状をとどめながら,虚血により陰窩上皮(腺上皮)が脱落した病態である.噛み砕いた表現では,陰窩の残骸・外枠が認められるため,消失した陰窩の存在がうかがえる所見である.虚血性病変では,炎症性変化に乏しく,虚血に最も脆弱な陰窩上皮が最初に傷害されるため,陰窩上皮が萎縮(丈の低下)・消失し,その結果として陰窩(腺管)の立ち枯れ像が生じる.一方,通常の腸炎では,炎症反応により陰窩上皮・粘膜固有層の両者の組織傷害を来して,びらんや潰瘍が形成される.
虚血性腸炎の組織学的特徴は,①腺管の立ち枯れ像,②高度な杯細胞減少,③フィブリン沈着,④出血・うっ血,であり,これら4所見がそろえば,虚血性腸炎の診断根拠となりうる(Fig. 1〜3).
偽膜(pseudomembrane)
著者: 江頭由太郎
ページ範囲:P.693 - P.693
定義
偽膜とは,消化管の粘膜面に強固に付着した壊死性滲出物である.偽膜の肉眼的特徴は白色〜黄白色〜黄色で,円形〜卵円形の1〜10mm大の無茎性隆起を呈する.時に,不整形で大きな面状の病変を形成し,文字通り“膜様”の形態を呈する.偽膜の介在粘膜は浮腫がみられることが多いが,炎症性変化は乏しい.組織学的には,偽膜はフィブリン析出と好中球浸潤の目立つ壊死性滲出物である(Fig. 1).偽膜下の組織には壊死性変化を伴う粘膜が残存している場合と,びらんあるいは浅い潰瘍により粘膜が欠損している場合がある.内視鏡検査において,偽膜は水洗においても粘膜面から剝離せず,無理に機械的に剝離すると,粘膜下の組織を損傷し出血を来す.この特徴は,偽膜の主成分であるフィブリンにより偽膜が粘膜組織に強固に接着されていることによる.
肉芽,肉芽腫,膿瘍(granulation, granuloma, abscess)
著者: 八尾隆史
ページ範囲:P.694 - P.694
肉芽,肉芽腫の定義
肉芽は毛細血管に富んだ新生結合組織(幼弱な結合組織)であり(Fig. 1),肉眼的に顆粒状の盛り上がりを示すためgranulation tissueと呼ばれる.
肉芽腫という言葉は,もともとVirchow(1865年)が肉芽から成る限局性の腫瘤あるいは腫瘍という意味で用いたが,現在では炎症性のものを指している.肉芽腫には,普通の肉芽から形成されるものと,マクロファージないし類上皮細胞(腫大した組織球)の結節状増殖から成るものがある.後者は①サルコイドーシス型,②結核型,③偽結核型,④異物型の肉芽腫,⑤Aschoff結節(リウマチ熱での心臓の肉芽腫),⑥リウマトイド結節(関節リウマチで出現)に分類される.これらのうち,結核型は乾酪化,偽結核型(エルシニア腸炎など)は膿瘍化,リウマトイド結節は類線維素壊死という特徴的な中心壊死を伴う.
膿瘍の定義
膿瘍は,臓器組織の内部で起こる限局性の化膿性炎症で,炎症局所の組織が崩壊した好中球から遊離される各種の分解酵素の働きで融解し,膿が貯留した病巣である(Fig. 3).
陰窩炎,陰窩膿瘍(cryptitis, crypt abscess)
著者: 八尾隆史
ページ範囲:P.695 - P.695
定義
陰窩(crypt)とは,小腸では絨毛の奥にある管状のくぼみを意味する.大腸では絨毛がないため表面からのくぼみ全体のことを指す.
陰窩炎とは,炎症性の腸疾患の際に,好中球浸潤が陰窩上皮内に波及した状態である.
線維筋症(fibromuscular obliteration)
著者: 和田了
ページ範囲:P.696 - P.696
定義
線維筋症(fibromuscular obliteration ; FO)は,“消化管粘膜固有層の線維筋組織の増生”と定義される1).具体的には,粘膜固有層の間質に,粘膜筋板の肥厚・不規則な立ち上がりから成る平滑筋成分および線維芽細胞などの線維成分の混合した成分として光学顕微鏡的に観察される組織像(Fig. 1〜3)である.
アポトーシス(apoptosis)
著者: 菅井有
ページ範囲:P.697 - P.697
定義
アポトーシスとは,細胞における細胞死のことで,壊死と対比的に用いられる1).アポトーシスは多細胞生物にとってより好ましい状態を保持するために能動的に行われ,その機序も厳密に設計・管理されている(ウイルス感染細胞などを想定せよ)1).このような観点から,アポトーシスのことをプログラミングされた細胞死(programed cell death)とも言う.
IEL(intraepithelial lymphocytes)
著者: 二村聡 , 石橋英樹
ページ範囲:P.698 - P.698
定義
IELは,腸管をはじめ舌,子宮・腟などの粘膜構成上皮間に存在するリンパ球(の総称)と定義され,上皮内リンパ球または上皮細胞間リンパ球と邦訳される.IELのほとんど(90%以上)がCD3e陽性かつCD8陽性のTリンパ球(T細胞)である(Fig. 1).上皮のE-カドヘリンと結合するαEβ7インテグリン(CD103)を有するため上皮細胞(epithelial cell)に挟まるように存在し,これがIELと称されるゆえんである.なお,他稿で解説されるLEL(lymphoepithelial lesion)と混同せぬよう注意したい.
過誤腫(hamartoma)
著者: 岩下明德
ページ範囲:P.699 - P.700
定義
胎生期における組織の形成異常によって腫瘍様の奇形を生ずることがあるが,これは当該個体(宿主)組織と同調的平行的に発育する点が真の腫瘍(新生物)と異なる.Albrecht(1904)は,この腫瘍様組織奇形を過誤腫(hamartoma)と分離腫に分類した1).過誤腫とは,胎生期に組織成分の量的組み合わせの割合を誤ったがために生じたもの(例 ; 消化管のリンパ管腫,血管腫)(Fig. 1,2),分離腫とは同じく胎生期に組織成分の異所的分離迷入によって発生したもの(例 ; 消化管の異所膵)で,それぞれ腫瘍の外観に似て結節状を呈するが,通常自律的増殖は行わない.しかし,まれに過誤腫,分離腫が自律的発育に転じ,真の腫瘍となることがある.その場合は,それぞれ過誤芽腫(hamartoblastoma),分離芽腫(choristoblastoma)と呼ぶ.
dysplasia-associated lesion or mass(DALM)
著者: 味岡洋一 , 谷優佑
ページ範囲:P.701 - P.701
定義
欧米の病理診断分類では,UC(ulcerative colitis)に発生した粘膜内腫瘍はすべてdysplasiaと診断されるが,生検でdysplasiaと診断された病変が内視鏡的に隆起として認識可能な場合,dysplasia-associated(with a macroscopic)lesion or mass(DALM)1)と呼ばれる(Fig. 1a).
横這型胃癌,手つなぎ型腺管癌(crawling-type adenocarcinoma of the stomach)
著者: 河内洋
ページ範囲:P.702 - P.702
定義
滝澤1)は,以下の病理組織学的特徴を示す胃癌を,“横這型癌(crawling cancer)”と呼んだ.①萎縮した粘膜を背景にして,細胞増殖帯に相当する粘膜の中間層を中心に,固有層内を広く進展する傾向が顕著.②不整な形態の腺管が互いに融合しながら,粘膜固有層内を水平方向に密度の低い増殖を示す癌で,核異型は軽い.③粘膜表層の上皮は腫瘍性腺管に連続するが,異型は認められず,どこまで癌とするか判断が難しい場合が多い.④印環細胞癌の所見を合併することがある.⑤腸上皮化生腺管に類似することも多い.
加藤2)は,特徴的な分岐・融合腺管の形態に着目し,“手つなぎ型腺管癌”と表現した.いずれの術語も同一病変を意味すると理解されている.“横這型・手つなぎ型癌”のように両者が併記されることもある.
desmoplasia
著者: 菅井有
ページ範囲:P.703 - P.703
定義
癌が浸潤すると,癌細胞は自らに都合がよいように,局所の環境を変更することが知られている(癌の微小環境).この際に癌組織周囲に出現するのがdesmoplasiaで,組織学的には線維芽細胞の増生(線維化)として観察される1).
hyperkeratosis,hyperparakeratosis
著者: 根本哲生
ページ範囲:P.704 - P.704
定義
hyperkeratosis(過角化)とは,重層扁平上皮のcornified layer〔角質層(角化層)〕の厚さが本来より増している状態を指す1).角質層は扁平上皮の最表層に位置し,最も分化〔角化(keratinization)〕の進んだ細胞から成る.光学顕微鏡的には好酸性で扁平,核の消失した細胞が層状となった部分である.口腔・食道をはじめとする粘膜領域では皮膚(表皮)と異なり,生理的に角質層は存在しない.よって,消化管領域においては明らかに認識される角質層が存在することが過角化とも言える.
parakeratosisは錯角化あるいは不全角化と訳される.錯角化とは角質層の細胞内に本来みられないはずの核が存在する場合を言う1).錯角化が認識されるためには角質層の出現が前提となるので,消化管粘膜において錯角化は必然的に過角化部分における錯角化,すなわち錯過角化(hyperparakeratosis)の状態となる.
parietal cell protrusion / hyperplasia
著者: 向所賢一 , 九嶋亮治
ページ範囲:P.705 - P.705
定義
parietal cell protrusion(PCP)は,parietal cell hyperplasia,parietal cell pseudohypertrophyなどとも呼ばれ,胃食道逆流症に対してやNSAIDs投与時の消化性潰瘍予防目的で,プロトンポンプ阻害薬(PPI)の長期投与が行われた症例でよくみられる.しかし,PCPはPPI投与時のみにみられる特異的な所見ではなく,自己免疫性胃炎,胃切除後,Zollinger-Ellison症候群など高ガストリン血症を来した症例にも認められることがある1).PCPが発生する機序は,上昇した血清ガストリンに壁細胞が反応し,主細胞よりも壁細胞の背が高くなるために壁細胞が尖った帽子のようにみえることによる1).
分類
プラハ分類(Prague C & M criteria)
著者: 竹内学
ページ範囲:P.706 - P.707
定義
プラハ分類(Prague C & M criteria ; Endoscopic Grading System for Barrett's esophagus)はBarrett食道に対する内視鏡評価の標準化を目指して,2003年にInternational Working Group for the Classification of Oesophagitisにより提唱された分類である1).この内視鏡診断によるプラハ分類は,なお,英国を除く欧米ではBarrett粘膜の診断には生検による腸上皮化生の証明が必須となるため,この組織学的に証明されるBarrett食道とは区別される.プラハ分類では食道胃接合部(esophagogastric junction ; EGJ)より伸びる口側の全周性円柱上皮部分の長さをC(circumferential extent),最も口側の非全周性円柱上皮までの長さをM(maximum extent)とし,このCとMの2つの項目を用いて記載するように規定されている(シェーマ).また,この分類はinterあるいはintra-observerの一致率が高く,信憑性のある分類として推奨されている.
ロサンゼルス分類(Los Angeles classification)
著者: 久礼里江 , 中村真一
ページ範囲:P.708 - P.709
定義
「胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン」1)によると,胃食道逆流症(gastroesophageal reflux disease ; GERD)は胃食道逆流(gastroesophageal reflux ; GER)によりひき起こされる食道粘膜傷害と煩わしい症状のいずれかまたは両者をひき起こす疾患であり,食道粘膜傷害を有する“びらん性GERD”と症状のみを認める“非びらん性GERD”に分類される.
ロサンゼルス分類は,1994年のロサンゼルスで行われた世界消化器病学会で発表されたびらん性GERDの内視鏡分類である2).従来の分類は病理学的なびらん・潰瘍を定義として使用していたのに対して,ロサンゼルス分類では内視鏡的観察による粘膜傷害(mucosal break)という概念が導入された.mucosal breakとは“より正常にみえる周囲粘膜と明確に区別される白苔ないしは発赤を有する領域”とされ,その程度により重症度がGrade分類された(Table 1,Fig. 1〜10).軽症例の多い本邦ではmucosal breakを伴わないGrade 0というカテゴリーを加えた改訂ロサンゼルス分類3)もある(Grade 0とはGrade NとGrade Mを合わせたもの指す).
日本食道学会拡大内視鏡分類(magnified endoscopic classification for superficial esophageal squamous cell carcinoma─classiification of the Japan Esophageal Society)
著者: 小山恒男 , 高橋亜紀子
ページ範囲:P.710 - P.711
定義
日本食道学会は,食道扁平上皮の拡大内視鏡所見を解析し,表在型食道扁平上皮癌の鑑別診断,深達度診断へ応用することを目的として,2010年に拡大内視鏡による食道表在癌深達度診断基準検討委員会を発足させた.基盤となったのはInoue分類1),Arima分類2)であり,この2名を含む10名の委員に加え,幕内博康,吉田操の両顧問にご指導いただいて,日本食道学会分類を作成した3).
食道癌の肉眼型分類(macroscopic classification of the esophageal cancer)
著者: 門馬久美子
ページ範囲:P.712 - P.713
定義
食道癌の肉眼型分類は,「食道癌取扱い規約第11版」1)に記載された規約を用いている.規約による肉眼型を以下に示す.
食道静脈瘤の所見(L,F,C,RC,BS,MF)(endoscopic findings of esophageal varices)
著者: 小原勝敏
ページ範囲:P.714 - P.715
定義
持続的な門脈圧亢進状態に伴い,生理的に存在する門脈─大循環系交通枝は径が拡大し,門脈から大循環への血流ルートとしての役割を担うようになる.食道静脈瘤はこの門脈─大循環側副血行路の一部であり,食道の粘膜下層を中心に静脈が腫瘤状に拡張したものである.食道静脈瘤の基礎疾患は,肝硬変,特発性門脈圧亢進症,肝外門脈閉塞症,Budd-Chiari症候群などであるが,90%以上は肝硬変が占める.食道静脈瘤出血は基礎疾患ゆえに致命的となることもあり,止血できても二次性肝不全により死亡することも多い.ゆえに,食道静脈瘤所見から出血のリスクを検証し,内視鏡治療によって出血や再出血を未然に防止することが重要である.
食道アカラシアのX線分類(radiographic classification of esophageal achalasia)
著者: 高木靖寛
ページ範囲:P.716 - P.716
定義
食道アカラシアのX線所見は,食道の拡張,残渣や造影剤の食道内停滞,胃移行部の平滑な狭窄像“bird's beak”(鳥嘴状),胃泡の消失,同期性異常収縮波などで,発泡剤や鎮痙薬を投与せずに撮影される.X線造影像による分類では拡張型分類と拡張度分類がある.従来,拡張型は1)紡錘型,2)フラスコ型,3)S状型に分類されていたが,現在では1)2)をまとめて,①直線型(straight type ; St type)(Fig. 1a),②シグモイド型(sigmoid type ; Sg type)(Fig. 1b)に分けている.さらに②は食道の蛇行が強くL字型を呈するものを進行シグモイド型(advanced sigmoid type ; aSg type)と亜分類している1).
食道裂孔ヘルニア(hiatal hernia)
著者: 日向有紀子 , 中村真一
ページ範囲:P.717 - P.717
定義
胸腔と腹腔を分けている横隔膜には大動脈,大静脈,食道を通すそれぞれの裂孔がある.食道裂孔ヘルニアは横隔膜ヘルニアのひとつであり,食道裂孔を通して腹腔内の臓器が胸腔内に脱出している状態を言い,多くは胃の一部が胸腔側に脱出する.
食道裂孔ヘルニアは下記の3つの型に分類される1).
Forrest分類(Forrest's classification)
著者: 小澤俊文
ページ範囲:P.718 - P.718
定義
Forrest分類とは,1974年にJohn Forrestが発表した潰瘍の出血状態による分類である.現在ではHeldweinら1)が1989年に改変したものが広く用いられている.この分類は再出血率や死亡率,外科手術移行率など予後を予測するうえで重要かつ有用である.
シドニー分類(Sydney system)
著者: 加藤元嗣
ページ範囲:P.719 - P.719
定義
1990年にオーストラリアのシドニーで開催された世界消化器病学会において,欧米6か国の研究者が中心となり,新たな胃炎分類としてSydney system(シドニー分類)が提唱された(Fig. 1)1)〜3).その背景には,H. pylori感染が最も重要な胃炎の原因と考えられるようになり,除菌判定にも用いることができ,単純で包括的かつ理解しやすい胃炎分類を作成する目的があった.シドニー分類では組織学部門と内視鏡部門より構成されたが,組織学部門は1996年にupdated Sydney systemとして改訂がなされた4).シドニー分類では内視鏡所見,病理組織学的所見および成因を整理統合することが試みられており,分類というより記載方法という色彩が強い.それは内視鏡的に正常と診断しても,病理組織学的には40%以上に慢性胃炎の変化を認めるなど,内視鏡所見と病理組織学的所見には大きな不一致が存在しているとの原則に基づいている.
胃炎の京都分類(Kyoto classification of gastritis)
著者: 末廣満彦 , 春間賢
ページ範囲:P.720 - P.721
定義
胃炎の京都分類とは,2013年に京都で開催された第85回日本消化器内視鏡学会総会を機に,これまでの国内外の胃炎分類を考慮し,より簡便で客観性のある胃炎所見をH. pyloriの感染状態に準じて取り上げた新しい胃炎の分類である.H. pyloriの感染を未感染,現感染,既感染・除菌後の3つのフェーズに分けて胃炎の内視鏡所見を診断することを基本とした分類であり,胃炎で認められる19の内視鏡所見についてそれぞれどの状態で認められるかを示している(Table 1)1).さらに,胃癌のリスクを評価する内視鏡所見スコアと内視鏡所見の記載方法も付記されている.
胃癌の肉眼分類(macroscopic types of gastric cancer)
著者: 細川治 , 渡邊透
ページ範囲:P.722 - P.723
定義
日本胃癌学会による「胃癌取扱い規約 第14版」1)に基づいて分類される(シェーマ1).基本分類(Table 1)には0型〜5型までの6種類が存在し,0型(表在型)(Table 2)は5種類に亜分類される.従来のBorrmann分類や早期胃癌分類を改変したものである.
VS classification system
著者: 八尾建史
ページ範囲:P.724 - P.725
定義と概説
拡大内視鏡で観察される胃粘膜の解剖学的構造は,微小血管構築像〔microvascular(MV)pattern ; V〕と表面微細構造〔microsurface(MS)pattern ; S〕の2つに大きく分類される.
正常胃体部粘膜の拡大内視鏡像(Fig. 1)を参照し,胃拡大内視鏡により視覚化される微小血管構築像と表面微細構造について視覚化される解剖学的指標をTable 1に示す1)〜3).
H. pylori未感染・現感染・既感染(Kyoto classification of gastritis)
著者: 鎌田智有 , 春間賢
ページ範囲:P.726 - P.729
定義
一般的に,これまでにHelicobacter pylori(H. pylori)菌に感染していない胃粘膜をH. pylori未感染粘膜,現在H. pylori菌に感染している胃粘膜を現感染粘膜,除菌後や高度萎縮および腸上皮化生に伴うH. pylori菌の自然消退など過去の粘膜を既感染粘膜と定義される.
ABC分類(ABC classification)
著者: 井上和彦
ページ範囲:P.730 - P.730
定義
胃癌発生にH. pylori感染は必要条件と位置付けられ,それに伴う胃粘膜の炎症や萎縮が強く関与していることは明らかとなっている.簡便な血液検査である血清H. pylori抗体でH. pylori感染を,血清ペプシノゲン(PG)法で胃粘膜萎縮を判断し,その組み合わせで胃癌リスク層別化を行う方法をABC分類という1).
血清H. pylori抗体(−)PG法(−)をA群,血清H. pylori抗体(+)PG法(−)をB群,血清H. pylori抗体(+)PG法(+)をC群,血清H. pylori抗体(−)PG法(+)をD群として開始したが,D群の占める割合は非常に低く,PG法(+)を一括してC群として扱うことが多い.そして,胃癌罹患リスクに関するメタアナリシスでABCD 4群分類では有意差は示されず,ABC 3群分類で各群間の有意差を認めたと報告されている2).
Lugano国際会議分類(Lugano International Conference classification)
著者: 岩井朋洋 , 小野裕之
ページ範囲:P.731 - P.731
定義
節性・節外性を問わず悪性リンパ腫の診断の基本は組織診断と臨床病期診断であり,治療法の決定に極めて重要である.一般的に悪性リンパ腫の病期分類はAnn Arbor分類1)が用いられる.しかし,消化管原発の悪性リンパ腫では,もともと節性リンパ腫の病期分類であったAnn Arbor分類は,深達度や隣接臓器への浸潤が考慮されておらず,多くが節外性リンパ腫である消化管悪性リンパ腫には不向きであると考えられていた.
Ann Arbor分類を改訂したMusshoffらの分類2)ではStage IIを所属リンパ節にとどまるStage II1と腹腔内遠隔リンパ節に拡がるStage II2に分け,さらに改訂したLugano国際会議分類(Table 1)3)はLuganoで1993年に開催された会議で出され,隣接臓器や周辺臓器への浸潤をStage IIEと区別し,Stage IIIをなくし,横隔膜上のリンパ節浸潤をStage IVと分類している.現在では,消化管リンパ腫で広く受け入れられている病期分類である.
大腸癌の肉眼型分類(classification of gross appearance for colorectal carcinoma)
著者: 二宮悠樹 , 田中信治
ページ範囲:P.732 - P.733
定義
大腸癌の肉眼型分類は,「大腸癌取扱い規約」1)において定義されており,その基本分類はTable 1の通りである(シェーマ1,2,Fig. 1〜10).このなかで,1〜5型は胃癌の肉眼型分類2)とほぼ同じであり,1〜4型は進行癌の肉眼型を意味する(シェーマ2).
0型は早期癌の分類であるが,早期胃癌2)とは少し異なる.隆起型0-I型は,0-Ip,0-Isp,0-Isに細分類され,表面型0-II型は早期胃癌と同様に0-IIa,0-IIb,0-IIcに細分類されるが,大腸にはIII型早期癌は存在しないので省かれている(シェーマ1).複合病変では,目立つ所見から順に“+”記号でつないで記載する.また,早期大腸癌の形態を形成する要素として,腺腫成分や過形成成分を含むことも多いが,肉眼型を決定する際には組織発生や癌/非癌,腫瘍/非腫瘍の違いを考慮せずに,病変の形を全体像として捉える.なお,0型は小さい病変が多いので,肉眼型は送気により腸壁の十分伸展された内視鏡所見で判定する.凹凸の評価のためにはインジゴカルミン撒布が望ましい.パリ分類3)では0-IIa型は,病変の高さが閉じた生検鉗子の高さ(約2.5mm)を超えないものを指し,それより高い病変は0-Is型に分類されること,0-Isp型は臨床的意義がないため省かれておりType 0-Isに含まれることが「大腸癌取扱い規約」と異なる.
NSAIDs起因性腸病変の所見(NSAIDs-induced intestinal lesions)
著者: 蔵原晃一 , 松本主之
ページ範囲:P.734 - P.735
定義
非ステロイド性抗炎症薬(nonsteroidal anti-inflammatory drugs:NSAIDs)起因性腸病変は,低用量アスピリンを含むNSAIDsによって正常な小腸ないし大腸に惹起された粘膜病変と定義される.
NSAIDs起因性腸病変の肉眼像や病理組織像は非特異的な所見にとどまるため,診断には,他の薬剤性腸炎と同様に,腸病変(潰瘍,腸炎)の確認とNSAIDsの使用歴の確認に加え,生検と培養による他疾患の除外とNSAIDsの使用中止による病変の治癒軽快の確認を要する1)2)(Table 1).
pit pattern分類(pit pattern classification)
著者: 前山泰彦 , 鶴田修
ページ範囲:P.736 - P.736
定義
pitとは,粘膜表面の大きさ約50〜100μm程度の腺管開口部のことであり,その大きさ,形態や配列を観察する診断方法がpit pattern診断である.大腸病変のpit patternに関しては実体顕微鏡下での報告に始まり,その後平坦・陥凹型大腸早期癌に関しての実体顕微鏡像の検討が工藤ら1)により報告されて以来その診断学はより普及したと考えられる.pit patternは,現在は工藤・鶴田分類2)としてI〜V型に分類されている(Fig. 1).
I型,II型pitは非腫瘍性病変に相当し,III型,IV型は腺腫に,V型は癌に相当するpitと考えられている.V型はpitの配列の乱れ,大小不同,左右非対称などの不整化したVI型(irregular)と,pit自体が腫瘍細胞のために閉じたり消失したり,無構造な表面構造となったVN型(non structure)に区分している.病理組織学的にはほとんどが癌であり,特にある領域をもってVN型を呈する病変はSM癌に認められる.また,VI型に関しては,内腔狭小,辺縁不整,輪郭不明瞭,stromal areaの染色性低下,scratch signを呈するものはVI型高度不整とされ,より深達度の深い病変を示唆している.
大腸腫瘍NBI拡大所見統一分類〔JNET(the Japan NBI Expert Team)classification〕
著者: 住元旭 , 田中信治
ページ範囲:P.737 - P.738
定義
JNET(the Japan NBI Expert Team)分類とは,大腸腫瘍に対する組織・深達度などの質的診断を目的とした本邦のNBI拡大内視鏡所見統一分類であり,vessel patternとsurface patternの2つのNBI拡大観察所見を診断指標としたType 1,2A,2B,3から成るカテゴリー分類である.
大腸T1(SM)癌内視鏡治療根治基準(curative condition after endoscopic resection for T1 colorectal carcinoma)
著者: 岡志郎 , 田中信治
ページ範囲:P.739 - P.739
定義
大腸T1(SM)癌のリンパ節転移率は全体で約10%程度であるが,内視鏡的摘除標本の適切な病理組織学的評価によって転移リスクを層別化し,経過観察可能かリンパ節郭清を伴う追加手術が必要かを判断する.「大腸癌治療ガイドライン2016年度版」1)では,内視鏡的摘除をされたpT1(SM)大腸癌の追加治療の適応基準(内視鏡的摘除後追加手術考慮群)として,“切除深部断端陽性は絶対適応”としている.また,“①SM浸潤度1,000μm以上,②脈管侵襲陽性,③低分化腺癌・印環細胞癌・粘液癌,④浸潤先進部の簇出(budding)Grade 2/3の因子のうちひとつでも認めれば追加手術を考慮する”としている(Table 1)1).
小腸血管性病変の内視鏡所見分類(矢野・山本分類)〔endoscopic classification of vascular lesions of the small intestine(Yano-Yamamoto classification)〕
著者: 矢野智則
ページ範囲:P.740 - P.740
定義
小腸の血管性病変は近年の技術進歩により内視鏡診断・治療が可能になった.消化管の血管性病変は,病態が全く異なる静脈瘤や血管腫を除けば,病理組織学的に,①静脈・毛細血管の特徴を持つ病変(angioectasia),②動脈の特徴を持つ病変(Dieulafoy's lesion),③動脈と静脈の特徴を持つ病変(arteriovenous malformation),の3種類に分類される1).病態を判断して適切な治療を行うために重要な,動脈成分の有無,つまり拍動性の有無に着目して小腸血管性病変の内視鏡所見を以下の6種類に分類2)したものが,この分類である.
Vienna分類と胃と大腸のGroup分類(Vienna classification and Group classification of the stomach and colorectum)
著者: 八尾隆史
ページ範囲:P.741 - P.742
定義
1.Vienna分類
消化管上皮の生検組織診断基準が,欧米では間質浸潤を根拠として癌と判定するが,本邦では浸潤の有無にかかわらず細胞異型と構造異型により癌と判定するという違いがあった.その診断の統一のため,1998年にウィーンで開催された消化管粘膜内腫瘍診断のコンセンサスミーティングが開催され,消化管上皮性腫瘍のVienna分類が作成された(Table 1).Vienna分類では非腫瘍性(Category 1),腫瘍性(Category 3〜5),腫瘍かどうかの判定が困難(Category 2)の3群に分類することを基本として,腫瘍性のうち低異型度のものはCategory 3,高異型度のものはCategory 4,粘膜内もしくは粘膜下層以深への浸潤があるものはCategory 5に分類される.そしてさらに,Category 3には低異型度の腺腫と低異型度の非浸潤性上皮性腫瘍が含まれ,Category 4には高異型度の腺腫(4.1),非浸潤癌(4.2),浸潤性癌を疑うもの(4.3)が含まれ,Category 5には浸潤性のある癌のみが含まれる.
なお,Vienna分類は食道〜大腸まで全消化管(炎症性腸疾患の腫瘍性病変も含む)の病理診断に用いられ,さらに生検のみならず切除材料の病理診断にも用いられる.
潰瘍性大腸炎における異型上皮の厚労省分類
著者: 味岡洋一 , 渡辺佳緒里
ページ範囲:P.743 - P.743
定義
厚生省(当時)特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班(武藤班)で提唱された,潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis ; UC)に発生した異型上皮に対する日本独自の病理組織分類である1)(Table 1).内視鏡サーベイランスへの応用を主目的としたものであるが,生検診断のみならず手術材料にも応用しうる.
黒丸の分類(Kuromaru's classification)
著者: 大川清孝 , 青木哲哉
ページ範囲:P.744 - P.744
定義
黒丸は肺結核患者400例の病理解剖標本を検討し,肉眼像を用いて腸結核の活動性潰瘍を8型に分類した(シェーマ)1).原文のまま記載すると,I型は初期の病変で粟粒大ないし麻実大の結核結節である.II型は結核結節の壊死物質が粘膜を破って腸腔に排出され,小潰瘍を形成したものである(Fig. 1).III型はそれがやや大きくなり,小豆大または扁桃大となったものである.IV型は,腸管の横軸方向の潰瘍で,輪状または帯状潰瘍と言われるものである.長径2cm以下のものをIVA型(Fig. 2),2cm以上のものをIVB型とした.V型は縦軸方向の潰瘍で,長径2cm以下のものをVA型,2cm以上のものをVB型とした.VI型は円形または類円形の潰瘍で,扁桃大以上のものである.VII型は不整形潰瘍で,扁桃大以上である.VIII型は潰瘍が互いに融合し,広範な潰瘍となったものである(Fig. 3).
潰瘍性大腸炎のMayoスコアとMatts分類(the endoscopic severity assessment of ulcerative colitis ; Mayo Score and Matts classification)
著者: 岩男泰
ページ範囲:P.745 - P.745
定義
潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis ; UC)の分類には,罹患範囲による分類,病期による分類,臨床経過による分類に加え,臨床的活動度指標として臨床的重症度分類および内視鏡的活動度分類が用いられる.内視鏡的活動度分類・指標は,患者の主観によらない客観的な重症度評価を可能にするために必要である.現在までに多くの分類,指標が作成されてきたが,Matts分類1),Baron index,Mayoスコア2),Rachmilewitz index,UCEIS(UC endoscopic index of severity)3)など,いずれも臨床試験での使用を目的として作成されたものである.初期治療法を決定するに当たっては,どれを用いてもそれほど乖離はない.一方,治療に伴う改善度を判定するためには,測定項目を増やしスケールを拡げるなど,反応性を高める工夫が必要である3).一方で,実臨床における実用性の問題を考慮する必要がある.
LST(laterally spreading tumor):顆粒型,非顆粒型〔LST granular type(LST-G), LST non-granular type(LST-NG)〕
著者: 鴫田賢次郎 , 田中信治
ページ範囲:P.746 - P.746
定義
LST(laterally spreading tumor)とは,水平側方への発育進展を特徴とする径10mm以上の表層拡大型大腸病変に対するニックネーミングである1).肉眼型分類を示す用語ではないが本邦のみならず国際的に広く使用されており,「大腸癌取扱い規約第8版」2)に多くの内視鏡画像も含めて詳細に解説されている.LSTは顆粒型(LST granular type ; LST-G)と非顆粒型(LST non-granular type ; LST-NG)に亜分類され,さらに前者は顆粒均一型(homogeneous type)(Fig. 1)と結節混在型(nodular mixed type)(Fig. 2)に,後者は平坦隆起型(flat elevated type)(Fig. 3)と偽陥凹型(pseudo-depressed type)(Fig. 4)に細分類される.鑑別には,インジゴカルミン撒布像が有用である.
--------------------
図説「胃と腸」所見用語集2017 目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.519 - P.521
執筆者 フリーアクセス
ページ範囲:P.522 - P.523
索引 フリーアクセス
ページ範囲:P.748 - P.753
基本情報
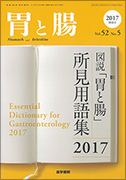
バックナンバー
59巻11号(2024年11月発行)
今月の主題 進行胃癌の診断と治療方針2024
59巻10号(2024年10月発行)
増大号 炎症性腸疾患2024
59巻9号(2024年9月発行)
今月の主題 食道運動障害の診断と治療
59巻8号(2024年8月発行)
今月の主題 臨床と病理のマリアージュ
59巻7号(2024年7月発行)
今月の主題 虚血性腸病変を整理する
59巻6号(2024年6月発行)
今月の主題 内視鏡治療後サーベイランスの現状—異時性多発病変を中心に
59巻5号(2024年5月発行)
今月の主題 胃・十二指腸神経内分泌腫瘍(NEN) up to date
59巻4号(2024年4月発行)
増大号 消化管疾患の分類2024
59巻3号(2024年3月発行)
今月の主題 上皮下発育を呈する食道病変の診断
59巻2号(2024年2月発行)
今月の主題 大腸ポリープのすべて
59巻1号(2024年1月発行)
今月の主題 自己免疫性胃炎—病期分類と画像所見
58巻12号(2023年12月発行)
今月の主題 遺伝性消化管疾患を考える
58巻11号(2023年11月発行)
今月の主題 小腸画像診断のトピックス
58巻10号(2023年10月発行)
増大号 「胃と腸」式 読影問題集2023 応用と発展—考える画像診断が身につく
58巻9号(2023年9月発行)
今月の主題 知っておくべき口腔・咽喉頭病変
58巻8号(2023年8月発行)
今月の主題 十二指腸拡大内視鏡の最新知見
58巻7号(2023年7月発行)
今月の主題 消化管リンパ増殖性疾患の診断アプローチの基本
58巻6号(2023年6月発行)
今月の主題 分類不能腸炎(IBDU)の現状と将来展望
58巻5号(2023年5月発行)
今月の主題 壁内局在からみた胃上皮下腫瘍の鑑別診断
58巻4号(2023年4月発行)
増大号 「胃と腸」式 読影問題集2023 基本と応用—考える画像診断が身につく
58巻3号(2023年3月発行)
今月の主題 食道ESD瘢痕近傍病変の診断と治療
58巻2号(2023年2月発行)
今月の主題 鋸歯状病変関連の早期大腸癌
58巻1号(2023年1月発行)
今月の主題 Non-H. pylori Helicobacter胃炎と周辺疾患
57巻13号(2022年12月発行)
今月の主題 IEEを使いこなす
57巻12号(2022年11月発行)
今月の主題 胃型形質を示す胃・十二指腸上皮性腫瘍
57巻11号(2022年10月発行)
今月の主題 食道癌診療トピックス2022
57巻10号(2022年9月発行)
今月の主題 大腸腫瘍診療の最前線
57巻9号(2022年8月発行)
今月の主題 胃癌スクリーニングの課題と将来展望
57巻8号(2022年7月発行)
今月の主題 転移性消化管腫瘍
57巻7号(2022年6月発行)
今月の主題 特殊型胃癌—組織発生と内視鏡診断
57巻6号(2022年5月発行)
今月の主題 原発性小腸癌—見えてきたその全貌
57巻5号(2022年5月発行)
増刊号 図説「胃と腸」画像診断用語集2022
57巻4号(2022年4月発行)
今月の主題 予後不良な早期消化管癌
57巻3号(2022年3月発行)
今月の主題 食道上皮内腫瘍の診断と取り扱い
57巻2号(2022年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の粘膜治癒を再考する
57巻1号(2022年1月発行)
今月の主題 H. pylori除菌後発見胃癌の診断UPDATE
56巻13号(2021年12月発行)
今月の主題 非乳頭部十二指腸腺腫・癌の診断と治療
56巻12号(2021年11月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の鑑別診断
56巻11号(2021年10月発行)
今月の主題 咽頭表在癌の内視鏡診断と治療
56巻10号(2021年9月発行)
今月の主題 胃上皮性腫瘍—組織分類・内視鏡診断の新展開
56巻9号(2021年8月発行)
今月の主題 「胃と腸」式 読影問題集—考える画像診断が身につく
56巻8号(2021年7月発行)
今月の主題 早期大腸癌内視鏡治療の新展開
56巻7号(2021年6月発行)
今月の主題 食道胃接合部腺癌の診断2021
56巻6号(2021年5月発行)
今月の主題 上部消化管非腫瘍性ポリープの内視鏡所見と病理所見
56巻5号(2021年5月発行)
増刊号 消化管診断・治療手技のすべて2021
56巻4号(2021年4月発行)
今月の主題 消化管疾患AI診断の現状
56巻3号(2021年3月発行)
今月の主題 内視鏡医も知っておくべき病理診断リファレンス—下部消化管腫瘍
56巻2号(2021年2月発行)
今月の主題 Barrett食道腺癌の内視鏡診断と治療2021
56巻1号(2021年1月発行)
今月の主題 早期胃癌内視鏡治療・適応のUPDATE
55巻13号(2020年12月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変の新展開
55巻12号(2020年11月発行)
今月の主題 高齢者早期胃癌ESDの現状と問題点
55巻11号(2020年10月発行)
今月の主題 小腸腫瘍アトラス
55巻10号(2020年9月発行)
今月の主題 食道SM扁平上皮癌治療の新展開
55巻9号(2020年8月発行)
今月の主題 一度見たら忘れられない症例
55巻8号(2020年7月発行)
今月の主題 H. pylori未感染胃の上皮性腫瘍
55巻7号(2020年6月発行)
今月の主題 薬剤関連消化管病変のトピックス
55巻6号(2020年5月発行)
今月の主題 スキルス胃癌—病態と診断・治療の最前線
55巻5号(2020年5月発行)
増刊号 消化管腫瘍の内視鏡診断2020
55巻4号(2020年4月発行)
今月の主題 内視鏡医も知っておくべき病理診断リファレンス—上部消化管腫瘍
55巻3号(2020年3月発行)
今月の主題 いま知っておきたい食道良性疾患
55巻2号(2020年2月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎関連腫瘍—診断・治療の現状と課題
55巻1号(2020年1月発行)
今月の主題 早期胃癌の範囲診断up to date
54巻13号(2019年12月発行)
今月の主題 遺伝子・免疫異常に伴う消化管病変—最新のトピックスを中心に
54巻12号(2019年11月発行)
今月の主題 上部消化管感染症—最近の話題を含めて
54巻11号(2019年10月発行)
今月の主題 大腸腫瘍の病理診断の課題と将来展望
54巻10号(2019年9月発行)
今月の主題 知っておきたい特殊な食道腫瘍・腫瘍様病変
54巻9号(2019年8月発行)
今月の主題 消化管X線造影検査のすべて—撮影手技の実際と読影のポイント
54巻8号(2019年7月発行)
今月の主題 十二指腸腺腫・癌の診断
54巻7号(2019年6月発行)
今月の主題 A型胃炎—最新の知見
54巻6号(2019年5月発行)
今月の主題 隆起型早期大腸癌の病態と診断
54巻5号(2019年5月発行)
増刊号 消化管疾患の分類2019—使い方,使われ方
54巻4号(2019年4月発行)
今月の主題 知っておきたい小腸疾患
54巻3号(2019年3月発行)
今月の主題 咽頭・食道内視鏡拡大観察の基本と最新知見
54巻2号(2019年2月発行)
今月の主題 胃・十二指腸内視鏡拡大観察の基本と最新知見
54巻1号(2019年1月発行)
今月の主題 大腸内視鏡拡大観察の基本と最新知見
53巻13号(2018年12月発行)
今月の主題 EUSによる消化管疾患の診断—現状と最新の話題
53巻12号(2018年11月発行)
今月の主題 知っておきたい十二指腸病変
53巻11号(2018年10月発行)
今月の主題 胃拡大内視鏡が変えたclinical practice
53巻10号(2018年9月発行)
今月の主題 食道表在癌の拡大内視鏡診断─食道学会分類を検証する
53巻9号(2018年8月発行)
今月の主題 消化管画像の成り立ちを知る
53巻8号(2018年7月発行)
今月の主題 対策型胃内視鏡検診の現状と問題点
53巻7号(2018年6月発行)
今月の主題 知っておきたい直腸肛門部病変
53巻6号(2018年5月発行)
今月の主題 小腸出血性疾患の診断と治療─最近の進歩
53巻5号(2018年5月発行)
増刊号 早期胃癌2018
53巻4号(2018年4月発行)
今月の主題 腸管感染症─最新の話題を含めて
53巻3号(2018年3月発行)
今月の主題 好酸球性食道炎の診断と治療
53巻2号(2018年2月発行)
今月の主題 IBDの内視鏡的粘膜治癒─評価法と臨床的意義
53巻1号(2018年1月発行)
今月の主題 胃型形質の低異型度分化型胃癌
52巻13号(2017年12月発行)
今月の主題 咽頭・頸部食道癌の診断と治療
52巻12号(2017年11月発行)
今月の主題 大腸小・微小病変に対するcold polypectomyの意義と課題
52巻11号(2017年10月発行)
今月の主題 非特異性多発性小腸潰瘍症/CEAS─遺伝子異常と類縁疾患
52巻10号(2017年9月発行)
今月の主題 胃粘膜下腫瘍の診断と治療
52巻9号(2017年8月発行)
今月の主題 大腸スクリーニングの現状と将来展望
52巻8号(2017年7月発行)
今月の主題 臨床医も知っておくべき免疫組織化学染色のすべて
52巻7号(2017年6月発行)
今月の主題 胃潰瘍は変わったか─新しい胃潰瘍学の構築を目指して
52巻6号(2017年5月発行)
今月の主題 知っておきたいまれな大腸良性疾患
52巻5号(2017年5月発行)
増刊号 図説「胃と腸」所見用語集2017
52巻4号(2017年4月発行)
今月の主題 消化管内分泌細胞腫瘍の新知見
52巻3号(2017年3月発行)
今月の主題 表在型食道胃接合部癌の治療戦略
52巻2号(2017年2月発行)
今月の主題 消化管結核の診断と治療─最近の進歩
52巻1号(2017年1月発行)
今月の主題 知っておくべき胃疾患の分類
51巻13号(2016年12月発行)
今月の主題 狭窄を来す小腸疾患の診断
51巻12号(2016年11月発行)
今月の主題 十二指腸の上皮性腫瘍
51巻11号(2016年10月発行)
今月の主題 肉芽腫を形成する消化管病変
51巻10号(2016年9月発行)
今月の主題 表在型Barrett食道癌の診断
51巻9号(2016年8月発行)
今月の主題 消化管画像プレゼンテーションの基本と実際
51巻8号(2016年7月発行)
今月の主題 消化管疾患と皮膚病変
51巻7号(2016年6月発行)
今月の主題 新しい小腸・大腸画像診断─現状と将来展望
51巻6号(2016年5月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌後発見胃癌の内視鏡的特徴
51巻5号(2016年5月発行)
増刊号 消化管拡大内視鏡診断2016
51巻4号(2016年4月発行)
今月の主題 薬剤関連消化管病変
51巻3号(2016年3月発行)
今月の主題 知っておきたいまれな大腸悪性腫瘍
51巻2号(2016年2月発行)
今月の主題 まれな食道疾患の鑑別診断
51巻1号(2016年1月発行)
今月の主題 慢性胃炎を見直す
50巻13号(2015年12月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変の取り扱い
50巻12号(2015年11月発行)
今月の主題 胃底腺型胃癌
50巻11号(2015年10月発行)
今月の主題 血管炎による消化管病変
50巻10号(2015年9月発行)
今月の主題 狭窄を来す大腸疾患─診断のプロセスを含めて
50巻9号(2015年8月発行)
今月の主題 食道胃接合部腺癌
50巻8号(2015年7月発行)
今月の主題 胃がん検診に未来はあるのか
50巻7号(2015年6月発行)
今月の主題 診断困難な炎症性腸疾患
50巻6号(2015年5月発行)
今月の主題 知っておきたいまれな胃疾患
50巻5号(2015年5月発行)
増刊号 早期消化管癌の深達度診断 2015
50巻4号(2015年4月発行)
今月の主題 早期大腸癌内視鏡治療後の中・長期経過
50巻3号(2015年3月発行)
今月の主題 胃癌範囲診断における拡大観察のピットフォール
50巻2号(2015年2月発行)
今月の主題 食道のびらん・潰瘍性病変
50巻1号(2015年1月発行)
今月の主題 消化管早期癌診断学の時代変遷─50年の歩みと展望
49巻13号(2014年12月発行)
今月の主題 胃の腺腫─診断と治療方針
49巻12号(2014年11月発行)
今月の主題 大腸LSTの診断と意義—拡大内視鏡を中心に
49巻11号(2014年10月発行)
今月の主題 胃癌ESD適応拡大病変の経過と予後
49巻10号(2014年9月発行)
今月の主題 colitic cancerの初期病変─遡及例の検討を含めて
49巻9号(2014年8月発行)
今月の主題 小腸潰瘍の鑑別診断
49巻8号(2014年7月発行)
今月の主題 表面型表層拡大型食道癌の診断と治療戦略
49巻7号(2014年6月発行)
今月の主題 大腸T1(SM)癌に対する内視鏡治療の適応拡大
49巻6号(2014年5月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori陰性胃癌
49巻5号(2014年5月発行)
増刊号 消化管悪性リンパ腫2014
49巻4号(2014年4月発行)
今月の主題 虫垂病変のすべて―非腫瘍から腫瘍まで
49巻3号(2014年3月発行)
今月の主題 消化管アミロイドーシスを見直す
49巻2号(2014年2月発行)
今月の主題 日本食道学会拡大内視鏡分類
49巻1号(2014年1月発行)
今月の主題 ESD時代の早期胃癌深達度診断
48巻13号(2013年12月発行)
今月の主題 好酸球性消化管疾患の概念と取り扱い
48巻12号(2013年11月発行)
今月の主題 虚血性腸病変
48巻11号(2013年10月発行)
今月の主題 組織混在型粘膜内胃癌の診断
48巻10号(2013年9月発行)
今月の主題 小腸の悪性腫瘍
48巻9号(2013年8月発行)
今月の主題 食道表在癌治療の最先端
48巻8号(2013年7月発行)
今月の主題 非腫瘍性大腸ポリープのすべて
48巻7号(2013年6月発行)
今月の主題 消化管内分泌細胞腫瘍の診断と治療―WHO分類との対比
48巻6号(2013年5月発行)
今月の主題 微小胃癌の診断限界に迫る
48巻5号(2013年5月発行)
特集 炎症性腸疾患 2013
48巻4号(2013年4月発行)
今月の主題 カプセル内視鏡の現状と展望
48巻3号(2013年3月発行)
今月の主題 隆起型食道癌の特徴と鑑別診断
48巻2号(2013年2月発行)
今月の主題 大腸ESDの適応と実際
48巻1号(2013年1月発行)
今月の主題 潰瘍合併早期胃癌の診断と治療
47巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 右側大腸腫瘍の臨床病理学的特徴
47巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 高齢者消化管疾患の特徴
47巻11号(2012年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌後の胃癌
47巻10号(2012年9月発行)
今月の主題 難治性Crohn病の特徴と治療戦略
47巻9号(2012年8月発行)
今月の主題 食道癌の発育進展─初期浸潤の病態と診断
47巻8号(2012年7月発行)
今月の主題 胃ポリープの意義と鑑別
47巻7号(2012年6月発行)
今月の主題 大腸憩室疾患
47巻6号(2012年5月発行)
今月の主題 経鼻内視鏡によるスクリーニング
47巻5号(2012年5月発行)
特集 図説 胃と腸用語集2012
47巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 消化管EUS診断の現状と新たな展開
47巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 咽頭・頸部食道癌の鑑別診断
47巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 改訂された胃生検Group分類の現状
47巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 腸管三次元CT診断の現状
46巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 難治性潰瘍性大腸炎─診療・治療の新たな展開
46巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 Barrett食道癌の診断
46巻11号(2011年10月発行)
今月の主題 十二指腸の腫瘍性病変
46巻10号(2011年9月発行)
今月の主題 大腸SM癌に対する内視鏡治療の適応拡大
46巻9号(2011年8月発行)
今月の主題 若年者の胃・十二指腸病変の特徴
46巻8号(2011年7月発行)
今月の主題 食道の炎症性疾患
46巻7号(2011年6月発行)
今月の主題 腸管Behçet病と単純性潰瘍─診断と治療の進歩
46巻6号(2011年5月発行)
今月の主題 胃腫瘍の拡大内視鏡診断
46巻5号(2011年5月発行)
特集 食道表在癌2011
46巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変と癌化
46巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 免疫不全状態における消化管病変
46巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 NSAID起因性小腸病変
46巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 多発胃癌─最新の知見を含めて
45巻14号(2010年12月発行)
第41巻~第45巻 総索引 2006年~2010年(平成18年~平成22年)
45巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝性消化管疾患の特徴と長期経過
45巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 特殊型胃癌の病理像と臨床的特徴
45巻11号(2010年10月発行)
今月の主題 大腸低分化腺癌の初期像とその進展
45巻10号(2010年9月発行)
今月の主題 Crohn病小腸病変に対する診断と治療の進歩
45巻9号(2010年8月発行)
今月の主題 食道表在癌の深達度診断
45巻8号(2010年7月発行)
今月の主題 直腸肛門部病変の鑑別診断─最新の知見を含めて
45巻7号(2010年6月発行)
今月の主題 低異型度分化型胃癌の診断
45巻6号(2010年5月発行)
今月の主題 側方発育型大腸腫瘍(laterally spreading tumor ; LST)─分類と意義
45巻5号(2010年4月発行)
特集 早期大腸癌2010
45巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 スキルス胃癌と鑑別を要する疾患
45巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 出血性小腸疾患─内視鏡診断・治療の最前線
45巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 中・下咽頭表在癌の診断と治療
45巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 早期胃癌のIIb進展範囲診断
44巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 collagenous colitisの現況と新知見
44巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 消化管癌の化学・放射線療法の効果判定と問題点
44巻11号(2009年10月発行)
今月の主題 食道小扁平上皮癌の診断
44巻10号(2009年9月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎の初期病変とその進展・経過
44巻9号(2009年8月発行)
今月の主題 背景粘膜からみた胃癌ハイリスクグループ
44巻8号(2009年7月発行)
今月の主題 大腸SM癌内視鏡治療の根治基準をめぐって─病理診断の問題点と予後
44巻7号(2009年6月発行)
今月の主題 食道胃接合部腺癌の診断
44巻6号(2009年5月発行)
今月の主題 小腸疾患─小病変の診断と治療の進歩
44巻5号(2009年4月発行)
今月の主題 癌や炎症と鑑別が困難な消化管悪性リンパ腫
44巻4号(2009年4月発行)
特集 早期胃癌2009
44巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 食道扁平上皮癌に対するESDの適応と実際
44巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 特発性腸間膜静脈硬化症(idiopathic mesenteric phlebosclerosis)―概念と臨床的取り扱い
44巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 未分化型胃粘膜内癌のESD―適応拡大の可能性
43巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 大腸癌の発生・発育進展
43巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 早期胃癌発育の新たな分析─内視鏡経過例の遡及的検討から
43巻11号(2008年10月発行)
今月の主題 感染性腸炎─最近の動向と知見
43巻10号(2008年9月発行)
今月の主題 早期食道癌の診断─最近の進歩
43巻9号(2008年8月発行)
今月の主題 colitic cancer/dysplasiaの早期診断─病理組織診断の問題点も含めて
43巻8号(2008年7月発行)
今月の主題 胃癌に対する内視鏡スクリーニングの現状と将来
43巻7号(2008年6月発行)
今月の主題 消化管follicular lymphoma―診断と治療戦略
43巻6号(2008年5月発行)
今月の主題 大腸の新しい画像診断
43巻5号(2008年4月発行)
今月の主題 linitis plastica型胃癌―病態と診断・治療の最前線
43巻4号(2008年4月発行)
特集 小腸疾患2008
43巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 まれな食道良性腫瘍および腫瘍様病変
43巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 消化管GIST―診断・治療の新展開
43巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 早期胃癌ESD―適応拡大を求めて
42巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 新しい治療による炎症性腸疾患(IBD)の経過―粘膜治癒を中心に
42巻12号(2007年11月発行)
今月の主題 非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)起因性消化管病変
42巻11号(2007年10月発行)
今月の主題 ESD時代における未分化型混在早期胃癌の取り扱い
42巻10号(2007年9月発行)
今月の主題 大腸腫瘍内視鏡切除後のサーベイランスに向けて
42巻9号(2007年8月発行)
今月の主題 食道表在癌内視鏡切除後の長期成績
42巻8号(2007年7月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫―除菌無効例の特徴と治療戦略
42巻7号(2007年6月発行)
今月の主題 大腸ESDの現況と将来展望
42巻6号(2007年5月発行)
今月の主題 Helicobacter pyloriと胃癌
42巻5号(2007年4月発行)
特集 消化管の拡大内視鏡観察2007
42巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患(IBD)の上部消化管病変
42巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変の発育進展と診断・取り扱い
42巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 食道扁平上皮dysplasia―診断と取り扱いをめぐって
42巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 胃分化型SM1癌の診断―垂直浸潤500μm
41巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 大腸腫瘍に対する拡大内視鏡診断の最先端
41巻12号(2006年11月発行)
今月の主題 小腸疾患診療の新たな展開
41巻11号(2006年10月発行)
今月の主題 早期胃癌に対するESDと腹腔鏡下手術の接点
41巻10号(2006年9月発行)
・sm癌の最新の診断と治療戦略
41巻9号(2006年8月発行)
今月の主題 通常内視鏡による大腸sm癌の深達度診断 垂直侵潤距離1,000μm術前診断の現状
41巻8号(2006年7月発行)
今月の主題 転移陽性胃粘膜内癌の特徴と取り扱い
41巻7号(2006年6月発行)
今月の主題 Helicobacter pyloriに起因しないとされる良性胃粘膜病変
41巻6号(2006年5月発行)
今月の主題 非定型的炎症性腸疾患―診断と経過
41巻5号(2006年4月発行)
今月の主題 陥凹性小胃癌の診断―基本から最先端まで
41巻4号(2006年4月発行)
特集 消化管内視鏡治療2006
41巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腸管悪性リンパ腫―最近の知見
41巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 食道表在癌の内視鏡診断―最近の進歩
41巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 早期胃癌に対するESDの適応の現状と今後の展望
40巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 いわゆる側方発育型大腸腫瘍の治療法を問う
40巻12号(2005年11月発行)
今月の主題 胃癌EMR後の異時性多発を考える
40巻11号(2005年10月発行)
今月の主題 小腸内視鏡検査法の進歩
40巻10号(2005年9月発行)
今月の主題 難治性潰瘍性大腸炎―診断と治療の新知見
40巻9号(2005年8月発行)
今月の主題 表在性の中・下咽頭癌
40巻8号(2005年7月発行)
今月の主題 免疫異常と消化管病変
40巻7号(2005年6月発行)
今月の主題 胃癌化学療法の進歩と課題
40巻6号(2005年5月発行)
今月の主題 Crohn病の初期病変―診断と長期経過
40巻4号(2005年4月発行)
特集 消化管の出血性疾患2005
40巻5号(2005年4月発行)
今月の主題 切開・剥離法(ESD)時代の胃癌術前診断
40巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 特殊組織型の食道癌
40巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 大腸カルチノイド腫瘍 転移例と非転移例の比較を中心に
40巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 胃癌の時代的変遷と将来展望
39巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 大腸sm癌の内視鏡治療後の長期経過
39巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 消化管の画像診断―21世紀の展開
39巻11号(2004年10月発行)
今月の主題 胃生検診断の意義 Group分類を考える
39巻10号(2004年9月発行)
今月の主題 大腸sm癌の深達度診断―垂直浸潤1,000μm
39巻9号(2004年8月発行)
今月の主題 Barrett食道癌―表在癌の境界・深達度診断
39巻8号(2004年7月発行)
今月の主題 家族性大腸腺腫症―最近の話題
39巻7号(2004年6月発行)
今月の主題 胃癌術後の残胃癌
39巻6号(2004年5月発行)
今月の主題 深達度診断を迷わせる食道表在癌―その原因と画像の特徴
39巻5号(2004年4月発行)
今月の主題 大腸腫瘍に対する拡大内視鏡観察―V型pit pattern診断の問題点
39巻4号(2004年4月発行)
特集 消化管の粘膜下腫瘍 2004
39巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫―除菌治療後の経過と予後
39巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 Crohn病経過例における新しい治療の位置づけ
39巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 最新の早期胃癌EMR―切開・剥離法
38巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 消化管への転移性腫瘍
38巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 上部消化管拡大観察の意義
38巻11号(2003年10月発行)
今月の主題 粘膜下腫瘍様の形態を示した消化管癌
38巻10号(2003年9月発行)
今月の主題 胃腺腫の診断と治療方針
38巻9号(2003年8月発行)
今月の主題 直腸肛門部病変の鑑別診断
38巻8号(2003年7月発行)
今月の主題 経過観察からみた大腸癌の発育・進展sm癌を中心に
38巻7号(2003年6月発行)
今月の主題 消化管の炎症性疾患診断におけるX線検査の有用性
38巻6号(2003年5月発行)
今月の主題 消化管腫瘍診断におけるX線検査の有用性
38巻5号(2003年4月発行)
今月の主題 胃型早期胃癌の病理学的特徴と臨床像―分化型癌を中心に
38巻4号(2003年4月発行)
特集 全身性疾患と消化管病変
38巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 食道癌と他臓器重複癌―EMR時代を迎えて
38巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 腸型Behçet病と単純性潰瘍の長期経過
38巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 胃癌―診断と治療の最先端
37巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 胃癌と鑑別を要する炎症性疾患
37巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 Ⅰp・Ⅰsp型大腸sm癌
37巻11号(2002年10月発行)
今月の主題 消化管のvirtual endoscopy
37巻10号(2002年9月発行)
今月の主題 食道sm癌の再評価―食道温存治療の可能性を求めて
37巻9号(2002年8月発行)
今月の主題 胃粘膜内癌EMRの適応拡大と限界
37巻8号(2002年7月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と腫瘍(2)潰瘍性大腸炎以外
37巻7号(2002年6月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と腫瘍(1)潰瘍性大腸炎
37巻6号(2002年5月発行)
今月の主題 十二指腸の非腫瘍性びまん性病変
37巻5号(2002年4月発行)
今月の主題 cap polyposisと粘膜脱症候群
37巻4号(2002年3月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌に伴う問題点
37巻3号(2002年2月発行)
特集 消化管感染症2002
37巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 4型大腸癌とその鑑別診断
37巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 食道m3・sm1癌の診断と遠隔成績
36巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 早期胃癌診療の実態と問題点
36巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 十二指腸の小病変
36巻11号(2001年10月発行)
今月の主題 sm massive以深に浸潤した10mm以下の大腸癌
36巻10号(2001年9月発行)
今月の主題 縮小治療のための胃癌の粘膜内浸潤範囲診断
36巻9号(2001年8月発行)
今月の主題 GIST(gastrointestinal stromal tumor)―概念と臨床的取り扱い
36巻8号(2001年7月発行)
今月の主題 多発食道癌
36巻7号(2001年6月発行)
今月の主題 小腸腫瘍―分類と画像所見
36巻6号(2001年5月発行)
今月の主題 早期大腸癌の深達度診断にEUSと拡大内視鏡は必要か
36巻5号(2001年4月発行)
今月の主題 早期の食道胃接合部癌
36巻4号(2001年3月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎診断基準の問題点
36巻3号(2001年2月発行)
特集 消化管癌の深達度診断
36巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Crohn病診断基準の問題点
36巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 表層型胃悪性リンパ腫の鑑別診断―治療法選択のために
35巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 21世紀への消化管画像診断学―歩みと展望
35巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 早期大腸癌肉眼分類―統一をめざして
35巻11号(2000年10月発行)
今月の主題 胃カルチノイド―新しい考え方
35巻10号(2000年9月発行)
今月の主題 食道アカラシア
35巻9号(2000年8月発行)
今月の主題 薬剤性腸炎―最近の話題
35巻8号(2000年7月発行)
今月の主題 多発大腸癌
35巻7号(2000年6月発行)
今月の主題 胃の“pre-linitis plastica”型癌
35巻6号(2000年5月発行)
今月の主題 腸管の血管性病変―限局性腫瘍状病変を中心に
35巻5号(2000年4月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌後の消化性潰瘍の経過―3年以上の症例を中心に
35巻4号(2000年3月発行)
今月の主題 食道癌の発育進展―初期病巣から粘膜下層癌へ
35巻3号(2000年2月発行)
特集 消化管ポリポーシス2000
35巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患における生検の役割
35巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の基本所見とピットフォール
34巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 大腸腫瘍の内視鏡診断は病理診断にどこまで近づくか
34巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 胃癌診断における生検の現状と問題点
34巻11号(1999年10月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫―Helicobacter pylori除菌後の経過
34巻10号(1999年9月発行)
今月の主題 Crohn病の長期経過―10年以上の症例を中心に
34巻9号(1999年8月発行)
今月の主題 早期胃癌のEUS診断
34巻8号(1999年7月発行)
今月の主題 逆流性食道炎―分類・診断・治療
34巻7号(1999年6月発行)
今月の主題 AIDSとATLの消化管病変
34巻6号(1999年5月発行)
今月の主題 大腸sm癌の内視鏡的切除をめぐって
34巻5号(1999年4月発行)
今月の主題 大腸腫瘍内視鏡的切除後の局所再発―腺腫・m癌を中心に
34巻4号(1999年3月発行)
今月の主題 胃型の分化型胃癌―病理診断とその特徴
34巻3号(1999年2月発行)
特集 消化管の画像診断―US,CT,MRIの役割
34巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 Barrett上皮と食道腺癌
34巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 Ⅱ型早期大腸癌肉眼分類の問題点
33巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 胃癌EMR後の遺残再発―診断と治療
33巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 胃癌EMRの完全切除の判定基準を求めて
33巻11号(1998年10月発行)
今月の主題 早期大腸癌の組織診断―諸問題は解決されたか
33巻10号(1998年9月発行)
今月の主題 腸管子宮内膜症
33巻9号(1998年8月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎―最近の話題
33巻8号(1998年7月発行)
今月の主題 胃炎―Sydney SystemとHelicobacter pylori
33巻7号(1998年6月発行)
食道癌
33巻6号(1998年5月発行)
今月の主題 鋸歯状腺腫(serrated adenoma)とその周辺
33巻5号(1998年4月発行)
今月の主題 大腸疾患の診断に注腸X線検査は必要か
33巻4号(1998年3月発行)
今月の主題 胃癌の診断にX線検査は不要か
33巻3号(1998年2月発行)
特集 消化管悪性リンパ腫1998
33巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 消化管病変の三次元画像診断―現状と展望
33巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 「胃と腸」33年間の歩みからみた早期癌
32巻13号(1997年12月発行)
との鑑別を中心に
32巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 腺領域からみた胃病変
32巻11号(1997年10月発行)
今月の主題 Is型大腸sm癌を考える
32巻10号(1997年9月発行)
今月の主題 早期食道癌―X線診断の進歩
32巻9号(1997年8月発行)
今月の主題 胃噴門部領域の病変 (2)癌以外の病変
32巻8号(1997年7月発行)
今月の主題 胃噴門部領域の病変 (1)癌
32巻7号(1997年6月発行)
今月の主題 感染性腸炎(腸結核を除く)
32巻6号(1997年5月発行)
今月の主題 早期胃癌から進行癌への進展
32巻5号(1997年4月発行)
今月の主題 粘膜下腫瘍様の食道表在癌
32巻4号(1997年3月発行)
今月の主題 大腸腺腫症―最近の知見
32巻3号(1997年2月発行)
特集 炎症性腸疾患1997
32巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 十二指腸乳頭部癌―縮小手術をめざして
32巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 胃sm癌の細分類―治療法選択の指標として
31巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 大腸腫瘍の自然史
31巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 未分化型小胃癌はなぜ少ないか
31巻11号(1996年10月発行)
今月の主題 微細表面構造からみた大腸腫瘍の診断
31巻10号(1996年9月発行)
今月の主題 内視鏡的食道粘膜切除後の経過
31巻9号(1996年8月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的粘膜切除―適応拡大をめぐる問題点
31巻8号(1996年7月発行)
今月の主題 Helicobacter Pyloriと胃リンパ腫
31巻7号(1996年6月発行)
今月の主題 遺伝性非ポリポーシス大腸癌(HNPCC)
31巻6号(1996年5月発行)
今月の主題 食道dysplasia―経過観察例の検討
31巻5号(1996年4月発行)
今月の主題 表層拡大型早期胃癌
31巻4号(1996年3月発行)
今月の主題 新しいCrohn病診断基準(案)
31巻3号(1996年2月発行)
特集 図説 形態用語の使い方・使われ方
31巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 いわゆる表層拡大型大腸腫瘍とは
31巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫
30巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 小腸画像診断の新しい展開
30巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 大腸腺腫の診断と取り扱い
30巻11号(1995年10月発行)
今月の主題 食道表在癌の発育進展―症例から学ぶ
30巻10号(1995年9月発行)
今月の主題 微小胃癌
30巻9号(1995年8月発行)
今月の主題 胃の平滑筋腫と平滑筋肉腫―新しい視点を求めて
30巻8号(1995年7月発行)
今月の主題 表層拡大型食道表在癌
30巻7号(1995年6月発行)
今月の主題 大腸の悪性リンパ腫
30巻6号(1995年5月発行)
今月の主題 粘膜下腫瘍の形態を示した胃癌
30巻5号(1995年4月発行)
今月の主題 colitic cancer―微細診断をめざして
30巻4号(1995年3月発行)
今月の主題 腸結核
30巻3号(1995年2月発行)
特集 早期食道癌1995
30巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 表面型大腸癌の発育と経過
30巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 胃癌の診断と治療―最近の動向
29巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 上部消化管病変の特徴からみた全身性疾患
29巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 大腸sm癌の細分類とその臨床
29巻11号(1994年10月発行)
今月の主題 大腸sm癌の細分類とその意義
29巻10号(1994年9月発行)
今月の主題 胃底腺領域の分化型癌
29巻9号(1994年8月発行)
今月の主題 食道のヨード不染帯
29巻8号(1994年7月発行)
今月の主題 胆管癌の画像と病理
29巻7号(1994年6月発行)
今月の主題 多発胃癌
29巻6号(1994年5月発行)
今月の主題 アフタ様病変のみのCrohn病
29巻5号(1994年4月発行)
今月の主題 大腸Crohn病―非定型例の診断を中心に
29巻4号(1994年3月発行)
今月の主題 食道粘膜癌―新しい病型分類とその診断
29巻3号(1994年2月発行)
特集 早期大腸癌1994
29巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 胃良・悪性境界病変の生検診断と治療方針
29巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 表面型大腸腫瘍―肉眼分類を考える
28巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的根治切除―適応拡大の可能性と限界を探る
28巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 消化管ポリポーシス―最近の知見
28巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 大腸癌の深達度診断
28巻10号(1993年9月発行)
今月の主題 胃悪性リンパ腫―診断の変遷
28巻9号(1993年8月発行)
今月の主題 虚血性腸病変の新しい捉え方
28巻8号(1993年7月発行)
今月の主題 大腸癌存在診断の実態―m癌を除く
28巻7号(1993年6月発行)
今月の主題 十二指腸腫瘍
28巻6号(1993年5月発行)
今月の主題 大腸腫瘍切除後の経過追跡
28巻5号(1993年4月発行)
今月の主題 腸管アフタ様病変
28巻4号(1993年3月発行)
今月の主題 難治性胃潰瘍(2)臨床経過と難治化の要因
28巻3号(1993年2月発行)
特集 早期胃癌1993
28巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内視鏡的食道粘膜切除術
28巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 胃癌は変わったか―その時代的変遷
27巻12号(1992年12月発行)
今月の主題 難治性胃潰瘍(1)治癒予測を中心に
27巻11号(1992年11月発行)
今月の主題 大腸pm癌
27巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 胃癌の深達度診断mとsmの鑑別―内視鏡的治療のために
27巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 逆流性食道炎を見直す
27巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 表面型大腸腫瘍の臨床診断の諸問題
27巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 出血を来した小腸病変の画像診断
27巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 早期大腸癌の病理診断の諸問題―小病変の診断を中心に
27巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 linitis plastica型胃癌診断の現状
27巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 大腸のいわゆる結節集簇様病変
27巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 腸型Behçet病・simple ulcerの経過
27巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 食道表在癌の深達度を読む
27巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 胃癌の自然史を追う―経過追跡症例から
26巻12号(1991年12月発行)
今月の主題 集検発見胃癌の特徴
26巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 膠原病と腸病変
26巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 胃癌の組織型分類とその臨床的意義
26巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 Ⅲ型早期胃癌の診断に迫る―潰瘍の良・悪性の鑑別
26巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 大腸sm癌の治療
26巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 大腸sm癌の診断
26巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 Crohn病の長期経過
26巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎の長期経過
26巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的切除(2)―内視鏡的根治切除の評価
26巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的切除(1)―根治を目的として
26巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 食道“dysplasia”の存在を問う
26巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 早期胃癌―診断の基本と方法
25巻12号(1990年12月発行)
今月の主題 早期胃癌類似進行癌の診断
25巻11号(1990年11月発行)
今月の主題 直腸のいわゆる粘膜脱症候群
25巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 中垂腫瘤
25巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 早期食道癌を問う
25巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 臨床経過からみた胃生検の問題点
25巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 小さな表面型(Ⅱ型)大腸上皮性腫瘍
25巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の鑑別診断(2)―大腸病変を中心に
25巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の鑑別診断(1)―小腸・回盲部病変を中心に
25巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 Barrett食道
25巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 胃癌の切除範囲をどう決めるのか
25巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 膵囊胞性疾患―動態診断の基礎と臨床
25巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 上部消化管X線検査の現状の反省と将来―検査モデルを求めて
24巻12号(1989年12月発行)
今月の主題 小さな未分化型胃癌―分化型と比較して
24巻11号(1989年11月発行)
今月の主題 いわゆる“十二指腸炎”の諸問題
24巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 分類困難な腸の炎症性疾患
24巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 胃粘膜下腫瘍の診断―現況と進歩
24巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 腸のカルチノイド
24巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 胆道疾患の非手術的治療の進歩
24巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 急性胃粘膜病変(AGML)
24巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 腸管の悪性リンパ腫(2)
24巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 胃・十二指腸出血の非手術的治療
24巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 大腸腺腫と癌(2)
24巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 大腸腺腫と癌(1)
24巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 噴門部陥凹型早期胃癌の診断
23巻12号(1988年12月発行)
今月の主題 腸管の悪性リンパ腫(1)
23巻11号(1988年11月発行)
今月の主題 食道癌の発育進展―逆追跡症例を中心に
23巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 十二指腸乳頭部癌
23巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 大腸内視鏡検査法―手技を中心として
23巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 小さな膵癌―小病変の鑑別診断をめぐって
23巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 微小胃癌診断―10年の進歩
23巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 びまん浸潤型大腸癌と転移性大腸癌
23巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍と超音波内視鏡
23巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 内視鏡的胃粘膜切除の臨床―ジャンボ・バイオプシーをめぐって
23巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化管形態診断の将来はどうあるべきか
23巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 消化管のアミロイドーシス(2)
23巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 X線・内視鏡所見と切除標本・病理所見との対比(胃)
22巻12号(1987年12月発行)
今月の主題 早期食道癌の問題点
22巻11号(1987年11月発行)
今月の主題 消化管のアミロイドーシス(1)
22巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 胃のDieulafoy潰瘍
22巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 胃底腺領域の癌―Ⅱcを中心として
22巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 陥凹型早期大腸癌
22巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 腸結核と癌
22巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 胃の腺腫とは―現状と問題点
22巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 胆囊癌の診断―発育進展を中心に
22巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 小さな大腸癌―早期診断のために
22巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 直腸・肛門部病変の新しい診かた
22巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 陥凹型早期胃癌の深達度診断
22巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 電子スコープの現況
21巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 大腸のvillous tumor
21巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 消化性潰瘍のトピックス(2)―胃粘膜防御機構を中心に
21巻10号(1986年10月発行)
受容体拮抗薬のもたらした諸問題
21巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎と大腸癌
21巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 胃癌肉眼分類の問題点―進行癌を中心として
21巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 膵の囊胞性疾患―その診断の進歩
21巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 大腸生検の問題点―炎症性疾患の経過を中心に
21巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 早期胆嚢癌―その診断の進歩
21巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 Ⅱb型早期胃癌の診断
21巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 大腸早期癌診断におけるX線と内視鏡との比較
21巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 消化管の“比較診断学”を求めて(2)
21巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 消化管の“比較診断学”を求めて(1)
20巻12号(1985年12月発行)
今月の主題 食道癌の早期診断
20巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 内視鏡的乳頭括約筋切開術の長期成績
20巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 大腸ポリペクトミー後の経過
20巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 胃癌診断におけるルーチン検査の確かさ―部位別・大きさ別の検討
20巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 大腸癌の発育・進展
20巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 小腸診断学の進歩―実際から最先端まで
20巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 慢性胃炎をどう考えるか
20巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 食道静脈瘤の硬化療法
20巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 膵・胆道の形成異常
20巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 大腸診断学の歩みと展望
20巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 胃診断学20年の歩みと展望―良性疾患を中心として
20巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 胃診断学20年の歩みと展望―早期胃癌を中心として
19巻12号(1984年12月発行)
今月の主題 消化管癌の診断におけるUS・CTの役割
19巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 膵癌の治療成績
19巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 胃生検の問題点
19巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 胃潰瘍の治癒判定
19巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 胃癌の内視鏡的治療
19巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 早期胃癌の再発死亡例をめぐって
19巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 大腸腺腫症の経過と予後
19巻5号(1984年5月発行)
受容体拮抗薬の位置づけ
19巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 肝内結石症―最近の知見をめぐって
19巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 Crohn病の経過
19巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 Panendoscopyの評価(2)
19巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 Panendoscopyの評価(1)
18巻12号(1983年12月発行)
今月の主題 Crohn病の診断
18巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 逆流性食道炎
18巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 胆囊病変をめぐる最近の知見
18巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の問題点(2)―診断の現状
18巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 大腸sm癌
18巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎―治療と経過を中心に
18巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の問題点(1)―良性病変と鑑別困難な早期癌
18巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 消化管の悪性病変と皮膚病変
18巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 急性腸炎(2)―主として感染性腸炎
18巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 症例・研究特集
18巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 急性腸炎(1)―主として抗生物質起因性大腸炎
18巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 臨床の場における上部消化管スクリーニング法―X線と内視鏡
17巻12号(1982年12月発行)
今月の主題 残胃の癌
17巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 ERCP―10年を経て―(2)技術の進歩と展開
17巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 ERCP―10年を経て―(1)診断能と限界―特に総合画像診断における位置づけ
17巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 症例・研究特集
17巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 小腸X線検査法の進歩
17巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍の病態生理
17巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 胆道系疾患の臨床(3)―早期胆道癌の診断を目指して
17巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 sm胃癌の問題点(3)―臨床と病理
17巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 胃の隆起性病変(polypoid lesion)―その形態と経過
17巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 症例・研究特集
17巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 sm胃癌の問題点(2)―陥凹型症例
17巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 sm胃癌の問題点(1)―隆起型症例
16巻12号(1981年12月発行)
今月の主題 胃のⅡb病変
16巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 胆道系疾患の臨床(2)―胆管異常を中心として
16巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 小腸腫瘍(2)
16巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 小腸腫瘍(1)
16巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 症例・研究特集
16巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 実験胃癌とヒト胃癌
16巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 胆道系疾患の臨床(1)―総胆管結石症を中心として
16巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(4)―治療と経過
16巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(3)―鑑別
16巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 虚血性腸炎の臨床と病理
16巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(2)―良性リンパ腫
16巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 早期胃癌は変貌したか
15巻12号(1980年12月発行)
今月の主題 逆追跡された胃のlinitis plastica―早期発見のために(2)
15巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 逆追跡された胃のlinitis plastica―早期発見のために(1)
15巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
15巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(1)―悪性リンパ腫
15巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 大腸憩室
15巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 消化管出血と非手術的止血
15巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 小膵癌診断への挑戦
15巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 胃のGiant Rugae
15巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 大腸の早期癌―胃早期癌と比較して
15巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 症例特集
15巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 腺境界と胃病変
15巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 胃病変の時代的変貌
14巻12号(1979年12月発行)
今月の主題 胃癌の化学療法
14巻11号(1979年11月発行)
今月の主題 急性胃病変と慢性胃潰瘍の関連をめぐって
14巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 消化管の健診を考える
14巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 症例・研究特集
14巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 微小胃癌
14巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 回盲弁近傍潰瘍(2)―Intestinal Behcetを中心に
14巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 回盲弁近傍潰瘍(1)―いわゆる“Simple Ulcer”を中心に
14巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 消化管と血管病変
14巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
14巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 X線と内視鏡との協力
14巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の反省(2)
14巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の反省(1)
13巻12号(1978年12月発行)
今月の主題 クローン病(3)―疑診例を中心に
13巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 食道・胃 境界領域癌の問題点
13巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸 併存潰瘍
13巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 腸結核(3)―疑診例を中心に
13巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 症例・研究特集
13巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 慢性膵炎
13巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍の治療の検討
13巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化管粘膜拡大観察と病態生理
13巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 クローン病(2)
13巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 クローン病(1)
13巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性胃潰瘍とその周辺
13巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 胃癌の発育経過
12巻12号(1977年12月発行)
今月の主題 腸結核(2)―大腸を主として
12巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 腸結核(1)―小腸を主として
12巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
12巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 胃癌の浸潤範囲・深達度の判定(2)
12巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 胃癌の浸潤範囲・深達度の判定(1)
12巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 残胃病変
12巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 胆道癌の診断と治療
12巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 高齢者の胃病変の特徴
12巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
12巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 直腸肛門部病変
12巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 S状結腸癌
12巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 胃癌―5年以後の再発
11巻12号(1976年12月発行)
今月の主題 放射線診断の最近の進歩
11巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 Endoscopic Surgery
11巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 胃スキルスの病理
11巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 症例・研究特集
11巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎―最近の趨勢
11巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 pm胃癌
11巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 食道・噴門境界部の病変
11巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 胃潰瘍癌の考え方
11巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 研究・症例特集
11巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 早期食道癌
11巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 小腸疾患の現況
11巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 早期胃癌肉眼分類の再検討
10巻12号(1975年12月発行)
今月の主題 全身性疾患と消化管
10巻11号(1975年11月発行)
今月の主題 胃の良・悪性境界領域病変
10巻10号(1975年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
10巻9号(1975年9月発行)
今月の主題 消化管疾患の新しい診断法
10巻8号(1975年8月発行)
今月の主題 クローン病とその周辺
10巻7号(1975年7月発行)
今月の主題 消化管の非上皮性腫瘍
10巻6号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管憩室
10巻5号(1975年5月発行)
今月の主題 消化管カルチノイド
10巻4号(1975年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
10巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 胃ポリープの癌化をめぐって
10巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 胃粘膜―(2)潰瘍,ポリープの背景として
10巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 胃粘膜―(1)早期胃癌の背景として
9巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 膵疾患の展望(2)―膵炎を中心に
9巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 膵疾患の展望(1)―膵炎を中心に
9巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
9巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 消化管の特殊なポリポージス
9巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 胃潰瘍の最近の問題点
9巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 盲腸・上行結腸の診断
9巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 胃を除く上腹部腫瘤の診断
9巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 症例・研究特集
9巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 意外な進展を示す胃癌
9巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 内視鏡的ポリペクトミー
9巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 食道・腸の生検
9巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 胃の生検
8巻12号(1973年12月発行)
今月の主題 十二指腸疾患の最新の診断
8巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 症例・研究特集
8巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 表層拡大型胃癌
8巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 胃潰瘍の良・悪性の鑑別診断
8巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 早期胃癌と線状潰瘍の合併
8巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 消化管出血の緊急診断
8巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 大腸疾患 最新の話題
8巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 胃癌の経過
8巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
8巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内視鏡的膵・胆管造影
8巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 消化管の悪性リンパ腫
8巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 急性胃病変の臨床
7巻12号(1972年12月発行)
今月の主題 腸の潰瘍性病変
7巻11号(1972年11月発行)
今月の主題 十二指腸乳頭部病変
7巻10号(1972年10月発行)
今月の主題 食道炎と食道静脈瘤
7巻9号(1972年9月発行)
今月の主題 胃集検で発見された胃潰瘍
7巻8号(1972年8月発行)
今月の主題 症例・研究特集
7巻7号(1972年7月発行)
今月の主題 若年者の消化管癌
7巻6号(1972年6月発行)
今月の主題 胃癌浸潤程度の診断
7巻5号(1972年5月発行)
今月の主題 悪性サイクル
7巻4号(1972年4月発行)
今月の主題 早期胃癌肉眼分類起草10年
7巻3号(1972年3月発行)
今月の主題 早期胃癌臨床診断の実態(診断成績の推移と問題点)
7巻2号(1972年2月発行)
今月の主題 Ⅲ型早期胃癌
7巻1号(1972年1月発行)
今月の主題 Ⅱb型早期胃癌
6巻13号(1971年12月発行)
今月の主題 Ⅱa+Ⅱc型早期胃癌
6巻12号(1971年11月発行)
今月の主題 症例・研究特集
6巻11号(1971年10月発行)
今月の主題 胃前壁病変の診断
6巻10号(1971年9月発行)
今月の主題 便秘と下痢
6巻9号(1971年8月発行)
今月の主題 幽門部(pyloric portion)の病変
6巻8号(1971年7月発行)
今月の主題 幽門部(pyloric portion)の診断
6巻7号(1971年6月発行)
今月の主題 腸上皮化生
6巻5号(1971年5月発行)
今月の主題 症例特集号
6巻6号(1971年5月発行)
特集 胃集団検診
6巻4号(1971年4月発行)
今月の主題 消化管穿孔
6巻3号(1971年3月発行)
今月の主題 早期胃癌と紛らわしい病変
6巻2号(1971年2月発行)
今月の主題 陥凹性早期胃癌
6巻1号(1971年1月発行)
今月の主題 隆起性早期胃癌
5巻13号(1970年12月発行)
今月の主題 胃潰瘍の再発・再燃
5巻12号(1970年11月発行)
今月の主題 症例・研究 特集
5巻11号(1970年10月発行)
今月の主題 大腸の早期癌―胃を除く消化器の早期癌(2)
5巻10号(1970年9月発行)
今月の主題 胃を除く消化器の早期癌(1)
5巻9号(1970年8月発行)
今月の主題 高位の胃病変
5巻8号(1970年7月発行)
今月の主題 診断された微小胃癌
5巻7号(1970年6月発行)
特集 胃生検特集
5巻6号(1970年6月発行)
今月の主題 症例・研究 特集
5巻5号(1970年5月発行)
今月の主題 早期胃癌再発例の検討
5巻4号(1970年4月発行)
今月の主題 胆のう胆道疾患診断法の最近の進歩
5巻3号(1970年3月発行)
今月の主題 胃肉腫
5巻2号(1970年2月発行)
今月の主題 線状潰瘍
5巻1号(1970年1月発行)
今月の主題 胃癌の経過
4巻12号(1969年12月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎
4巻11号(1969年11月発行)
今月の主題 十二指腸の精密診断
4巻10号(1969年10月発行)
今月の主題 早期癌とその周辺
4巻9号(1969年9月発行)
今月の主題 胃癌の5年生存率
4巻8号(1969年8月発行)
今月の主題 X線・内視鏡で良性様所見を呈した生検陽性例
4巻7号(1969年7月発行)
今月の主題 胃の変位と変形(2)
4巻6号(1969年6月発行)
今月の主題 胃の変位と変形(1)
4巻5号(1969年5月発行)
今月の主題 稀な胃病変
4巻4号(1969年4月発行)
今月の主題 小腸の検査法
4巻3号(1969年3月発行)
今月の主題 胃癌深達度の診断と経過観察
4巻2号(1969年2月発行)
今月の主題 上部消化管の出血
4巻1号(1969年1月発行)
今月の主題 大彎側の病変
3巻13号(1968年12月発行)
今月の主題 陥凹性早期胃癌の経過
3巻12号(1968年11月発行)
今月の主題 多発胃癌
3巻11号(1968年10月発行)
今月の主題 食道
3巻10号(1968年9月発行)
今月の主題 直視下診断法
3巻9号(1968年8月発行)
今月の主題 消化管の医原性疾患
3巻8号(1968年7月発行)
今月の主題 進行癌の問題点
3巻7号(1968年6月発行)
今月の主題 胃癌の発生
3巻6号(1968年6月発行)
今月の主題 前癌病変としての胃潰瘍とポリープの意義
3巻5号(1968年5月発行)
今月の主題 胃の巨大皺襞
3巻4号(1968年4月発行)
今月の主題 胃の食物輸送機能
3巻3号(1968年3月発行)
今月の主題 大腸・直腸
3巻2号(1968年2月発行)
今月の主題 胃集団検診と早期胃癌
3巻1号(1968年1月発行)
今月の主題 早期胃癌研究の焦点
2巻12号(1967年12月発行)
今月の主題 小腸
2巻11号(1967年11月発行)
今月の主題 慢性胃炎2
2巻10号(1967年10月発行)
今月の主題 慢性胃炎1
2巻9号(1967年9月発行)
今月の主題 胃の多発性潰瘍
2巻8号(1967年8月発行)
今月の主題 難治性胃潰瘍
2巻7号(1967年7月発行)
今月の主題 胃切除後の問題
2巻6号(1967年6月発行)
今月の主題 胃のびらん
2巻5号(1967年5月発行)
今月の主題 早期胃癌の鑑別診断
2巻4号(1967年4月発行)
今月の主題 胃微細病変の診断
2巻3号(1967年3月発行)
今月の主題 胃液分泌の基礎と臨床
2巻2号(1967年2月発行)
今月の主題 十二指腸潰瘍〔2〕
2巻1号(1967年1月発行)
今月の主題 十二指腸潰瘍〔1〕
