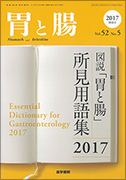文献詳細
増刊号 図説「胃と腸」所見用語集2017
画像所見〔胃〕
文献概要
定義
稜線状発赤は胃体部小彎や前庭部大彎を中心に,胃長軸方向に平行に縦走する,数条の帯状発赤である(Fig. 1〜3).発赤は胃皺襞の頂上部に一致して観察される.欧文表記はドイツ語のkammrötungであり,本来は畝に沿う発赤という語意であるが,kammを“櫛”と誤訳されたことで,櫛でこすってできたような内視鏡所見も相まって本邦では櫛状発赤と広まったようである.「消化器内視鏡用語集第3版」では櫛状発赤は稜線状発赤として改められている1).1956年にHenningが表層性胃炎の1所見として報告2)しているが,病理組織学的には細胞浸潤はみられず,発赤部における表層血管のうっ血が確認される3).一般に非萎縮粘膜の過酸・正酸例にみられることから,稜線状発赤の成因としては胃の蠕動収縮時に皺襞の尾根にうっ血が生じ,そこに接する胃酸が作用しているものと考えられる.
稜線状発赤は胃体部小彎や前庭部大彎を中心に,胃長軸方向に平行に縦走する,数条の帯状発赤である(Fig. 1〜3).発赤は胃皺襞の頂上部に一致して観察される.欧文表記はドイツ語のkammrötungであり,本来は畝に沿う発赤という語意であるが,kammを“櫛”と誤訳されたことで,櫛でこすってできたような内視鏡所見も相まって本邦では櫛状発赤と広まったようである.「消化器内視鏡用語集第3版」では櫛状発赤は稜線状発赤として改められている1).1956年にHenningが表層性胃炎の1所見として報告2)しているが,病理組織学的には細胞浸潤はみられず,発赤部における表層血管のうっ血が確認される3).一般に非萎縮粘膜の過酸・正酸例にみられることから,稜線状発赤の成因としては胃の蠕動収縮時に皺襞の尾根にうっ血が生じ,そこに接する胃酸が作用しているものと考えられる.
参考文献
1)日本消化器内視鏡学会用語委員会(編).内視鏡所見に関する用語─各論.消化器内視鏡用語集,第3版.医学書院,pp 90-91, 2011
2)Henning N. Krankheiten des Magens. In Lehrbuch der Verdauungs─krankheiten. Georg Thieme, Sttutgart, p 118, 1956
3)斎藤満.胃粘膜防御機構に関する内視鏡学的研究─胃粘膜発赤について.Gastroenterol Endosc 27:2707-2715, 1985
掲載誌情報