本号のテーマは「一度見たら忘れられない症例」である.今まで何度か序説を書かせていただいたが,正直なところこの序説を書くことに非常に苦しみ,困難を極めている.この業界にいて写真を撮ることは当たり前のことであるが,この“当たり前”を“当たり前”として説明することほど難しいものはない.
本誌は,美麗な臨床画像をもとに病理組織学的視点も加えて消化管疾患の理解を深めることを目的としている.“美麗な臨床画像”とは単に風景をパチパチ撮ったわけではない.放射線診断にかかわる大家の先生や技師の方からはお叱りを頂戴するかもしれないが,例えば一定の条件で撮像されるCT像において額縁に入れて自室に飾りたい画像があるかと言えば,“ない”のではないだろうか.しかし,筆者には自分で撮影した内視鏡画像を美しいと感じて,他の絵画のように自室に飾りたいと思うことがある.実際には家内に“気色悪い”と言われそうなので飾れないでいるのが,家長としてだらしない.
雑誌目次
胃と腸55巻9号
2020年08月発行
雑誌目次
今月の主題 一度見たら忘れられない症例
序説
一度見たら忘れられない症例—たかが“当たり前”,されど“当たり前”
著者: 山野泰穂
ページ範囲:P.1123 - P.1124
主題
腐食性食道炎に発生した胸部食道癌
著者: 三浦昭順 , 門馬久美子 , 春木茂男 , 鈴木邦士 , 山口和哉 , 塩原寛之 , 前田有紀 , 飯塚敏郎 , 堀口慎一郎 , 比島恒和
ページ範囲:P.1126 - P.1130
臨床経過
40歳代,男性.2歳時に苛性ソーダの誤飲により腐食性食道狭窄を発症.胃瘻造設術が施行された.その後,食事摂取は可能であったが,40歳代になり,胸部のつかえ感が増強したため近医を受診した.上部消化管内視鏡検査(esophagogastroduodenoscopy ; EGD)にて食道狭窄を指摘され,食道拡張術目的に当科に紹介され受診となった.
当院のEGDでは,切歯列より20〜26cmの食道粘膜は白濁し,血管が透見できず,多数の瘢痕を認めた(Fig.1a〜c).切歯列より26cmから食道狭窄が始まり,狭窄部の左壁〜後壁に1/2周程度の病変を認めた.左壁側は表面に付着物があり,一見盛り上がって見えたが,後壁側は境界が明瞭な陥凹性病変として観察され,病変は峡谷のような切り立った崖状を呈していた(Fig.1d〜f).細径scopeでの肛門側の観察では,左壁および後壁側の病変は,発赤した厚みのある病変として捉えられ,中央には深い溝状の陥凹がみられた(Fig.1g,i).しかし,NBI(narrow band imaging)近接観察では,病巣表面にB2血管らしき所見がみられ,前壁側には血管が増生するBA(brownish area)もみられた(Fig.1h).狭窄部にできた病変のため,病変が誇張されて見えている可能性も考慮し,MM-SMの表在癌と診断した.内視鏡が狭窄部を通過できないため,病変の全貌は確認できなかったが,ヨード染色にて不染を示す病変部の生検にて,扁平上皮癌と診断された(Fig.1f).
神経内分泌癌成分を伴ったBarrett食道腺癌の1例
著者: 福山知香 , 中島寛隆 , 河内洋 , 下井銘子 , 北沢尚子 , 渡海義隆 , 門馬久美子 , 榊信廣
ページ範囲:P.1131 - P.1136
臨床経過
患者:70歳代,女性.
食道X線造影検査(Fig.1):食道胃接合部の混合型ヘルニアと,下部食道の表面に大小不同の結節を伴う約30mm大の隆起性病変および,粘膜の顆粒状変化を伴う丈の低い隆起(Fig.1b,黄矢頭部)を認めた.後壁側の辺縁像は平滑で,この領域において病変の連続性はないと考えた.また,食道壁の伸展は保たれていた.以上より,混合型ヘルニアを背景とした隆起型Barrett食道腺癌と診断した.
上部消化管内視鏡検査(esophagogastroduodenoscopy ; EGD):白色光観察で食道胃接合部から口側に約60mm長の全周性の発赤粘膜を認め,LSBE(long-segment Barrett esophagus)と診断した.LSBE内の左側壁に,30mm大の丈が高く基部の狭い0-Ip型隆起を認め(病変A,Fig.2a),隆起表面は凹凸不整で白苔が付着していた.病変Aの対側には,中心部に相対的な陥凹を有する丈の低い0-I型隆起がみられ,表面は顆粒状の粘膜変化が観察された(病変B,Fig.2b).病変Aと病変Bの間には,丈の低い0-IIa型隆起が介在しており(病変C,Fig.2a),病変の口側端は扁平円柱上皮接合部(squamo columnar junction ; SCJ)と接していた.病変付近の食道壁の伸展は良好であった(Fig.2a).
ボーリング生検で診断したMALTリンパ腫成分を伴う隆起型胃びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫
著者: 赤松泰次 , 下平和久 , 宮島正行 , 中村真一郎 , 植原啓之 , 木畑穣 , 市川徹郎 , 浅野直子
ページ範囲:P.1137 - P.1140
臨床経過
患者は30歳代,男性.
上腹部の不快感が続くため,近医で上部消化管内視鏡検査(esophagogastroduodenoscopy ; EGD)を受けたところ,胃に多発した隆起性病変を指摘されて当院を受診した.家族歴や既往歴に特記事項はなかった.当院でEGDを再検したところ,前庭部,胃角部大彎,胃体部,胃穹窿部に多発する粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)様病変を散在性に認めた(Fig.1).一部の病変は表面に発赤とびらんがみられ,背景粘膜には萎縮の所見はみられなかった.細径プローブを用いた超音波内視鏡検査(endoscopic ultrasonography ; EUS)では,第2,3層に主座のある比較的均一な低エコー像を認め,第4層は保たれていた(Fig.2).以上より,悪性リンパ腫を疑った.さらに,明らかな潰瘍形成を伴わないことやEUSで病変が粘膜下層までにとどまることから低悪性度リンパ腫〔MALT(mucosa-associated lymphoid tissue)リンパ腫〕の可能性が高いと考えられた.
しかし,病変が広範囲に多発してみられ,低悪性度リンパ腫にしては内視鏡所見が“派手過ぎる”印象があった.隆起型胃MALTリンパ腫では,病変の深部に形質転化したびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(diffuse large B-cell lymphoma ; DLBCL)が存在することがあるため,胃角部大彎の病変(Fig.1b)からボーリング生検を行った.病変の表層から採取された生検組織の病理組織学的所見では,小型異型リンパ球の浸潤を認め,lymphoepithelial lesionがみられた(Fig.3).免疫組織化学染色でCD20,IRTA1(FCRL4)が陽性,BCL2が弱陽性,CD3,CD5,CD10が陰性であったことからMALTリンパ腫と診断された.一方,ボーリング生検で病変の深部から採取された生検組織の病理組織学的所見では,中型〜大型の異型リンパ球のびまん性浸潤を認め(Fig.4),Ki-67染色では表層のMALTリンパ腫の部分に比べて明らかな陽性細胞の増加が観察され(Fig.5),DLBCLと診断された.AP12-MALT1染色体転座は認めなかった.
スキルス胃癌
著者: 梅垣英次 , 宇治恵美子 , 門田修蔵 , 笹田真由 , 二ノ宮壮広 , 近石昌也 , 笹平百世 , 葉祥元 , 福嶋真弥 , 大澤元保 , 村尾高久 , 半田有紀子 , 半田修 , 松本啓志 , 塩谷昭子
ページ範囲:P.1142 - P.1145
臨床経過
患者は30歳代,女性.特に自覚症状を認めなかったが,会社検診の胃X線造影検査を受け,胃の異常を指摘されたため精査加療目的で受診となった.家族歴,既往歴に特記事項はない.また,理学的所見,血液生化学検査でも異常を認めず,血清H. pylori(Helicobacter pylori)-IgGは陰性であった.
胃X線造影検査では,背臥位充盈(Fig.1a)で胃穹窿部から胃体上部大彎に,比較的限局性の壁硬化像を認めた.また,背臥位・腹臥位二重造影像では(Fig.1b,c),胃穹窿部から胃体上部にかけて口径不同のある縦ひだに横走するひだの交錯する所見を認めた.
遺伝性びまん性胃癌
著者: 丸山保彦 , 島村隆浩 , 甲田賢治 , 安田和世 , 岩泉守哉 , 椙村春彦
ページ範囲:P.1146 - P.1149
臨床経過
患者は30歳代,男性.
健診の内視鏡検査で胃前庭部の褪色斑から生検され印環細胞癌が指摘されたため,当科に紹介され受診となった.既往歴に特記事項なく,父親がスキルス胃癌で28歳で死亡していた.血液検査では,血清H. pylori(Helicobacter pylori)抗体,便中抗原とも陰性で,腫瘍マーカーも正常範囲でPG(pepsinogen)1:65ng/ml,PG 2:12ng/ml,PG 1/2:5.4であった.
通常内視鏡検査では,胃体下部から前庭部にかけて萎縮のない背景粘膜の中に径5mm前後の褪色斑が散在していた(Fig.1).NBI(narrow band imaging)拡大内視鏡観察では,褪色斑は境界明瞭で背景の血管と比較して細く疎になり部分的に消失していた(Fig.2a,b).また,褪色斑の中には表面構造が不明瞭になり縮れたcorkscrew様の血管が観察されるものもあった(Fig.2c,d).8か所の褪色斑からそれぞれ生検を行いすべてでsigが検出された.
転移性胃癌—乳癌(浸潤性小葉癌)による胃転移
著者: 荒尾真道 , 上堂文也 , 松浦倫子 , 北村昌紀 , 藤澤文絵
ページ範囲:P.1150 - P.1153
臨床経過
患者:50歳代,女性.
主訴:嘔気,腹部膨満.
病歴:嘔気,腹部膨満が数週間続くため,近医で腹部超音波検査と腹部単純CTが撮影され,腹水を指摘された.上部消化管内視鏡検査(esophagogastroduodenoscopy ; EGD)で胃体部に粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)様の隆起と皺襞腫大を認め,ポジトロン断層法で胃,腹膜,腹水に異常集積を認めたため,進行胃癌による腹膜播種が疑われ,精査加療目的に当院を紹介され受診した.
当院で行ったEGDでは,胃穹窿部の皺襞腫大,胃体部に多発するSMT様隆起や皺襞腫大を認めた(Fig.1).多発病変であったことから,転移性胃癌が鑑別に挙がり,既往歴を確認したところ15年前に乳癌の手術歴があり,12年経った時点で経過観察が終了していた.
好酸球性胃腸炎
著者: 増永哲平 , 辻国広 , 土山寿志
ページ範囲:P.1155 - P.1157
臨床経過
[症例1] 50歳代,女性.
心窩部痛を主訴に当院を受診した.既往歴・アレルギー歴・家族歴に特記事項はなかった.常用薬はなかったが,生理痛のためにロキソプロフェンの頓服を行うことがあった.血液検査ではヘモグロビン値9.8g/dlと貧血があったが,好酸球数を含めその他に異常所見は認めず,血清H. pylori(Helicobacter pylori)IgG抗体も陰性であった.
上部消化管内視鏡検査(esophagogastroduodenoscopy ; EGD)では胃前庭部に浅い潰瘍が多発していたが(Fig.1a),他の消化管に異常はなかった.非ステロイド性抗炎症薬(nonsteroidal anti-inflammatory drugs ; NSAIDs)による消化性潰瘍を疑い,ボノプラザン20mg/dayの投薬を開始したところ,症状は速やかに改善し,1か月後のEGDで潰瘍の瘢痕化を確認した(Fig.1b).しかし,瘢痕部からの生検で高度の好酸球浸潤を認めたため(Fig.1c),好酸球性胃腸炎(eosinophilic gastroenteritis ; EGE)と確定診断した.3か月後にもフォローアップの内視鏡検査を施行したが,潰瘍の再燃は認めなかった.
先天性十二指腸膜様狭窄症
著者: 吉永繁高 , 小田一郎 , 江郷茉衣 , 阿部清一郎 , 野中哲 , 鈴木晴久 , 斎藤豊 , 永村良二
ページ範囲:P.1158 - P.1161
臨床経過
患者は40歳代,女性.検診にて十二指腸粘膜下腫瘍を指摘され脂肪腫と診断されたが,経時的に増大傾向を認めたため当院に紹介され受診となった.家族歴,既往歴に特記事項はなかった.当院初回の上部消化管内視鏡検査(esophagogastroduodenoscopy ; EGD)では,前医で指摘された粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)様隆起(Fig.1)が虚脱して舌状の形態を呈し(Fig.2a),その付着部のある十二指腸下行脚は盲端になっていた(Fig.2b).また,呼吸により隆起は前後に移動していた(Fig.2c,d).
初回のEGDから2日後に超音波内視鏡検査(endoscopic ultrasonography ; EUS)を施行したが,その際の内視鏡検査においてSMT様隆起は消失していた(Fig.3a).初回時と同様に今回も十二指腸下行脚は盲端になっていたが乳頭側に瘻孔を認め(Fig.3b),同部に内視鏡を挿入すると正常の十二指腸下行脚を認めた(Fig.3c).EUSにて20MHz超音波細径プローブを用いて十二指腸下行脚から抜去しながらscanすると,粘膜下層を挟むように粘膜が存在する,いわゆる鏡面像を呈する5層構造の膜様構造物を認めた(Fig.3d).低緊張性十二指腸X線造影検査を患者に提案したものの拒否されたため,静脈麻酔を施行したうえでアミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン液(ガストログラフイン®経口・注腸用)を用いて内視鏡下でのX線造影検査を行った.X線造影像にて十二指腸下行脚近位部に膜様,囊状の構造物を認め,乳頭側の欠損部より十二指腸下行脚への造影剤の流出を認めた(Fig.4).
広範囲粘膜脱落を呈する潰瘍性大腸炎
著者: 大川清孝 , 佐野弘治 , 宮野正人 , 山口誓子 , 倉井修
ページ範囲:P.1162 - P.1165
臨床経過
患者は40歳代,男性.
下痢が出現して徐々に増強し,発熱も出現してきたため,近医を受診し,急性腸炎と診断され入院した.感染性腸炎の疑いで抗菌薬投与と絶食にて1週間以上経過観察されていた.しかし,症状が軽快せず,腹部単純X線検査で腸管の拡張も増強してきたため,当院へ転院となった.
入院時の腹部単純X線検査では大腸および小腸の著明な拡張がみられた(Fig.1).血液検査はWBC 15,600/μl,RBC 434×104/μl,Hb 12.9g/dl,TP 4.6g/dl,Alb 1.6g/dl,CRP 24.4mg/dl,ESR 44mm/hであり,著明な炎症反応の上昇と低蛋白血症を認めた.診断目的で緊急内視鏡を施行した.S状結腸遠位側には粘膜の著明な脱落がみられ,ごくわずかの粘膜残存を島状に認め,縦列していた(Fig.2).粘膜脱落部に,筋層と思われる線維構造がみられた(Fig.2a,d).これ以上近位側への挿入は危険と考え,内視鏡を抜去した.直腸には小びらんがびまん性にみられ(Fig.3a),潰瘍性大腸炎と考えられる像であったが,一部では正常粘膜がみられた(Fig.3b).中毒性巨大結腸症を合併した重症の潰瘍性大腸炎と考えたが,このような内視鏡像の経験はなく,生検病理組織学的診断結果を待つ必要があると考え,ステロイドパルス療法を開始した.
急速な粘膜内脱分化を示した潰瘍性大腸炎関連癌の多発例
著者: 岩男泰 , 下田将之
ページ範囲:P.1166 - P.1170
臨床経過
患者は50歳代,女性.高血圧で10年前から加療中であった(カンデサルタン,アムロジピンを服薬).200X−8年,下痢,粘血便,腹痛を自覚するようになり,徐々に増強したため近医を受診.大腸内視鏡検査で全大腸炎型の潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis ; UC)と診断された.5-アミノサリチル酸製剤で症状は改善するも効果は十分でなく,経口ステロイド薬の投与を受け臨床的寛解を得た.しかし,ステロイド漸減中に再燃を認め,血球成分除去療法,免疫調整薬の投与などを受けるも軽度の活動性は持続し,軽症ではあるが慢性持続型として経過していた.
200X年に経過観察目的に大腸内視鏡検査を施行した.左側結腸のハウストラは消失し,腸管は短縮,鉛管状を呈しており,粘膜混濁,血管透見像の低下を認めた(Fig.1).S状結腸近位側には浅く広い陥凹が多発しており(Fig.2a),インジゴカルミン色素撒布で陥凹面はより明瞭となった(Fig.2b).また,辺縁には炎症性ポリープを認めた(Fig.2a,b).陥凹面は比較的平滑であったが脆弱であり,スコープの接触や送気,送水によっても出血が容易にみられた(Fig.2c,d).なお,陥凹間の介在粘膜には,一部血管透見像が観察可能であった.NBI(narrow band imaging)拡大観察では,介在粘膜の大部分におけるvessel patternは,血管径は拡張しているもののnetworkを形成しほぼ均一であった.しかし,太い異常血管やAVA(avascular area)も散見された(Fig.2e).陥凹部のsurface patternは観察困難であり,口径不同の異常血管の断片化,途絶が観察された(Fig.2f).
消化管GVHD
著者: 小村成臣 , 小山恵司 , 尾﨑隼人 , 前田晃平 , 大森崇史 , 堀口徳之 , 城代康貴 , 鎌野俊彰 , 大久保正明 , 舩坂好平 , 長坂光夫 , 中川義仁 , 柴田知行 , 大宮直木
ページ範囲:P.1171 - P.1174
臨床経過
患者は30歳代,女性.
10歳時に1型糖尿病を発症し,インスリンで加療するも慢性腎不全となり透析が導入され,30歳時に脳死膵腎同時移植が施行された.その後ステロイド,タクロリムス,ミコフェノール酸モフェチルなど内服.移植2年後に下痢が6週間持続するため当科に紹介され受診となった.大腸内視鏡検査にて,回腸末端にアフタの散在を認め(Fig.1a),盲腸には輪状傾向の幅の狭い潰瘍や瘢痕(Fig.1b),散在性に不整形びらん(Fig.1c,d)を認めた.盲腸からS状結腸にかけては血管透見消失像(Fig.1e〜g),orange peel appearanceが観察された.
生検病理組織学的所見は,盲腸から上行結腸では好酸球やリンパ球,形質細胞を主体とした高度の炎症細胞浸潤と陰窩の減少,萎縮がみられた(Fig.2a).残存する陰窩には再生性の増生がみられ(Ki-67陽性細胞増加),アポトーシスが散見された(Fig.2b).横行結腸から下行結腸では腺底部にポップコーン状のアポトーシス(γ-H2AX免疫染色陽性)がみられ,同様の高度炎症と陰窩の萎縮を認めた.Ziehl-Neelsen染色は陰性,DFS(direct fast scarlet)染色陰性,サイトメガロウイルス(cytomegalovirus ; CMV)感染陽性像はなく,病理組織学的に移植片対宿主病(graft-versus-host disease ; GVHD)に矛盾しない所見であった.以上より消化管GVHDと診断し,膵酵素製剤の補充療法を行ったところ,下痢は改善し退院となった.
Sessile serrated lesion with dysplasia(SSLD)由来pT1b粘液癌の1例
著者: 永田信二 , 鴫田賢次郎 , 金子真弓
ページ範囲:P.1175 - P.1178
臨床経過
患者は60歳代,女性.
20XX年に定期検査目的で施行した大腸内視鏡検査にて,横行結腸肝彎曲に病変を指摘された.白色光観察では径5mmの隆起性病変に連続して径5mmの扁平隆起性病変を認め,肉眼型は0-Is+IIaと診断した(Fig.1a).NBI(narrow band imaging)拡大観察では隆起部分(Is)の立ち上がりは整なsurface patternとvessel patternを呈していたが,隆起頂上は陥凹しており血管径の太い不整なvessel patternとその周囲のsurface patternは不明瞭であった(Fig.1b,c).インジゴカルミン色素撒布像では,扁平隆起部分(IIa)において粘液付着を認めた(Fig.2a,b).拡大観察では隆起頂上の陥凹は明瞭となり陥凹部分のみ腫瘍性pitを認めたが,その周囲はI〜II型pit patternを認めた(Fig.2c).
以上より鋸歯状病変に異型を伴った病変と診断し,内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection ; EMR)を施行した.
直腸肛門部にみられた悪性黒色腫の1例
著者: 十倉淳紀 , 斎藤彰一 , 安江千尋 , 井出大資 , 千野晶子 , 五十嵐正広 , 河内洋
ページ範囲:P.1179 - P.1183
臨床経過
患者は50歳代,女性.
肛門痛を主訴に近医を受診し,病変を指摘されたため当院に紹介され受診となった.既往歴に特記事項はなかった.当院の下部消化管内視鏡検査(total colonoscopy ; TCS,Fig.1)では,肛門縁から脱出する巨大な黒色腫瘤を認めた(Fig.1a〜c).また,盲腸(Fig.1d),上行結腸(Fig.1e),上部直腸(Fig.1f)にも黒色の隆起性病変や,色素沈着が散在性に認められた.さらに,上部消化管内視鏡検査(esophagogastroduodenoscopy ; EGD)(Fig.2)では,胃角部後壁(Fig.2a),胃体中部大彎(Fig.2b)にびらんを伴う黒色の色素沈着を認めた.
その他,CTにて両側鼠径リンパ節の腫大を認めた.以上より直腸肛門部原発の悪性黒色腫(anorectal malignant melanoma ; AMM)を考え,皮膚悪性黒色腫に準じたstaging(第7版AJCC皮膚メラノーマ病期分類)で,cT4bN0M1,cStage IVと診断した.肛門の疼痛,また出血のコントロール不良のため,AMMに対して経肛門的局所切除術が施行された.
小腸海綿状リンパ管腫
著者: 岡志郎 , 田中信治 , 飯尾澄夫 , 壷井章克 , 隅岡昭彦 , 茶山一彰
ページ範囲:P.1185 - P.1188
臨床経過
患者は30歳代,男性.
全身倦怠感にて前医受診し,血液検査にてHb 4.9g/dlと高度貧血を認めたため,上・下部消化管内視鏡検査,造影CTを施行したが,貧血の原因となる病変は指摘できなかった.鉄剤内服を開始し4か月後にHb 11.3g/dlまで改善した.その後に小腸精査目的で当科に紹介され受診となった.
家族歴,既往歴に特記事項はなかった.入院時現症は,身長167.6cm,体重49.4kg,血圧139/81mmHg,脈拍85/min,体温36.5℃で理学的所見に異常は認めなかった.
肛門fibroepithelial polyp
著者: 佐野村誠 , 桶本大 , 冨永真央 , 西田光志 , 沼圭次朗 , 福田斯盧恵 , 西川知宏 , 西谷仁 , 佐々木有一 , 長田憲和 , 廣瀬善信 , 中悠 , 柿本一城 , 川上研 , 中村志郎 , 樋口和秀
ページ範囲:P.1189 - P.1194
臨床経過
患者:60歳代後半,男性.
主訴:排便時の腫瘤脱出.
既往歴:20歳代後半から痔核(無治療).
現病歴:数年前から排便時に肛門から腫瘤が脱出するようになり,当科外来を受診した.
初診時現症:肛門診察において,視診では痔核,裂肛,痔瘻は認めなかった.肛門指診では6時方向(背側)に表面平滑で軟らかい腫瘤を触知し,疼痛,圧痛はなかった.また,血液生化学検査に異常所見はなかった.
早期胃癌研究会症例
NBI併用拡大観察が有用であった虫垂印環細胞癌の1例
著者: 尾石義謙 , 小林広幸 , 藤原美奈子 , 岩﨑一秀 , 瀬尾充 , 松浦隆志 , 本下潤一 , 畠山定宗
ページ範囲:P.1195 - P.1201
要旨●患者は40歳代,女性.近医にてスクリーニング目的で施行された下部消化管内視鏡検査(TCS)で盲腸に異常を認め,生検の結果虫垂癌が疑われ当院に紹介となった.TCSでは,虫垂開口部周囲はSMT様に隆起し,表面は発赤調でイクラ様の顆粒状粘膜を呈していた.NBI併用拡大観察ではI型pit様の腺管開口部周囲の窩間部が開大し,虫垂開口部近傍では顆粒の一部にirregularな血管が観察された.造影CT検査で虫垂の腫大を認めるも,壁外への浸潤や転移を疑う所見はなく,腹腔鏡下右半結腸切除術が施行され,虫垂印環細胞癌と診断された.切除標本の病理組織像との対比から,拡大観察所見は盲腸上皮直下まで進展した虫垂癌を見ていたと考えられた.
腫瘍露出し短期間に形態変化を来したGISTの1例
著者: 外山雄三 , 長浜隆司 , 宇賀治良平 , 西澤秀光 , 松村祐志 , 山本栄篤 , 浅原新吾 , 宍倉有里 , 二村聡
ページ範囲:P.1202 - P.1208
要旨●患者は30歳代,女性.めまいを主訴に当院を受診し,貧血(Hb 3.0g/dl)を認めた.EGDを施行した胃体下部前壁にbridging foldを伴う大きさ約35mmの隆起性病変を呈していた.隆起の立ち上がりは急峻であり境界明瞭,辺縁は整であった.生検にて紡錘形細胞腫瘍,特にGISTが疑われた.2か月後の内視鏡検査では,頂部に白苔を伴う深い陥凹を有する大きさ20mm程度のSMTへと形態変化を来した.切除標本では固有筋層内に紡錘形細胞から成る腫瘍性病変を認めた.c-kit弱陽性,CD34陽性,DOG1陽性,PDGFRA陽性でGISTと診断した.今回筆者らは,表層に腫瘍が露出し短期間で脱落したまれな胃GISTの1例を経験したので報告する.
今月の症例
Helicobacter pylori陰性の胃粘膜に発生した胃MALTリンパ腫の1例
著者: 萩原武 , 市原真 , 横山崇 , 高木将 , 伊藤彰洋 , 柳原志津妃 , 賀集剛賢 , 道上篤 , 乙黒雄平 , 寺門洋平 , 鈴木肇 , 小澤広 , 前田聡 , 今村哲理 , 後藤田裕子 , 村岡俊二
ページ範囲:P.1117 - P.1122
患者
70歳代,女性.
主訴
検診の精査希望.
生化学的検査所見
血清抗H. pylori(Helicobacter pylori)抗体0.4U/ml.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1115 - P.1115
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1116 - P.1116
早期胃癌研究会 症例募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.1136 - P.1136
「今月の症例」症例募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.1153 - P.1153
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1210 - P.1210
編集後記 フリーアクセス
著者: 松本主之
ページ範囲:P.1211 - P.1211
本誌は,発行当時から消化管疾患の形態診断に特化した医学誌として発展を遂げ,1990年頃までは通常X線・内視鏡所見と病理所見を詳細に対比することが基本であった.すなわち,病変の肉眼所見とX線・内視鏡所見を対比し,その結果から病理組織所見を推測することが大きなテーマであり,その背景として質の高い病理組織学的診断が必須であった.しかし,その後の画像診断法の目覚ましい進歩に伴い,特に画像強調内視鏡を中心とした詳細な観察で得られた所見と病理所見を直接比較検討することが重要な課題となっている.その結果,病理所見と寸分も乖離することのない完璧な臨床診断を目指した診断学が確立されようとしている.以上のような流れのなかで,今回は早期胃癌研究会の中堅メンバーの皆さまを中心に,実際に経験した自身はもちろん,読者も一度見たら忘れられないようなインパクトのある「忘れられない症例」の提示とともに消化管診断学に対する「熱い思い」をお示しいただくようお願いした.
本号の掲載論文を通読してみたところ,各著者が「忘れられない」とした症例では,実際の診断過程のどこかで大変苦慮したであろうことを強く感じた.事実,初回検査では鑑別疾患に挙がることのなかった疾患が最終診断であったという症例が数多く取り上げられている.また,読者として画像を拝見しても,鑑別診断が列挙できない疾患が少なくない.おそらく,著者らはその症例を経験することにより知識レベルの向上を体験し,患者に貢献できたという爽快感を得たものと思われる.次に感じたのは,画像強調内視鏡所見がそれほど取り上げられていないことである.今回提示された画像の大部分は,おそらく著者自身が撮影したものと考えてよいであろう.すなわち,私たちは初回観察時のX線・内視鏡像でインパクトのある症例に感銘を受け,症例の貴重さにのめり込むものと推測される.そして,最後に注目すべき点として症例の多彩さが挙げられる.本号の企画に際しては,著者を領域別に大別したうえで症例提示をお願いしたが,重複する疾患は全くなく,上皮性腫瘍,非上皮性腫瘍,炎症性疾患,形態異常など幅広い疾患が集積された.その要因として消化管疾患が極めて多岐に及ぶことが考えられるが,それらを「忘れられない」と感じる感受性が臨床医によって大きく異なることも影響していると思われる.その差異こそ,臨床医の能力,および経験と知識を反映したものであろう.
基本情報
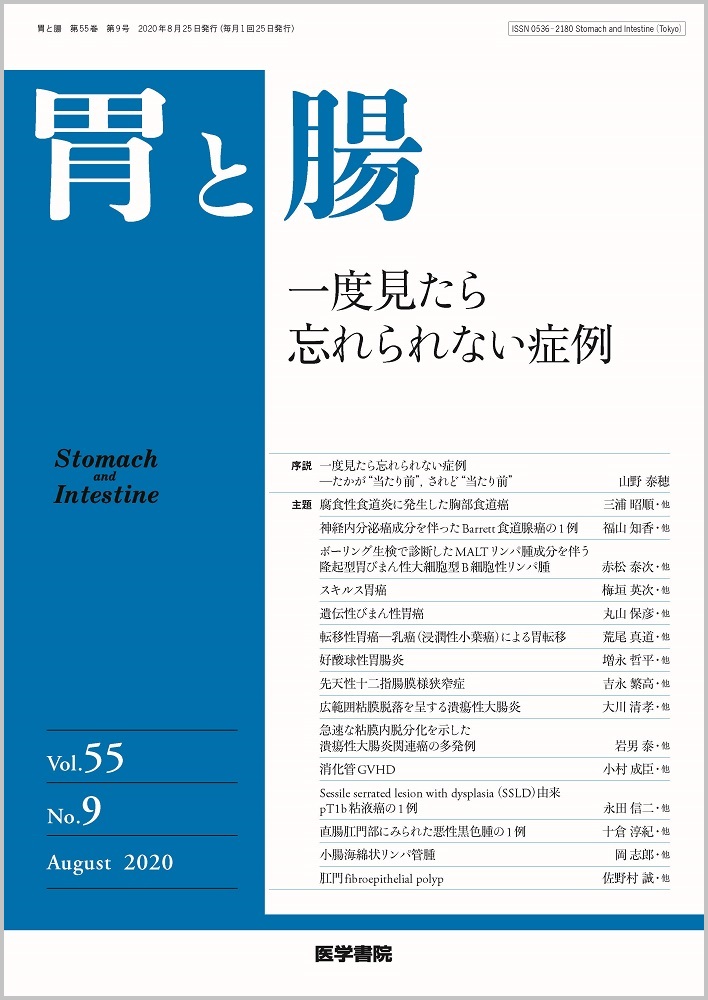
バックナンバー
59巻11号(2024年11月発行)
今月の主題 進行胃癌の診断と治療方針2024
59巻10号(2024年10月発行)
増大号 炎症性腸疾患2024
59巻9号(2024年9月発行)
今月の主題 食道運動障害の診断と治療
59巻8号(2024年8月発行)
今月の主題 臨床と病理のマリアージュ
59巻7号(2024年7月発行)
今月の主題 虚血性腸病変を整理する
59巻6号(2024年6月発行)
今月の主題 内視鏡治療後サーベイランスの現状—異時性多発病変を中心に
59巻5号(2024年5月発行)
今月の主題 胃・十二指腸神経内分泌腫瘍(NEN) up to date
59巻4号(2024年4月発行)
増大号 消化管疾患の分類2024
59巻3号(2024年3月発行)
今月の主題 上皮下発育を呈する食道病変の診断
59巻2号(2024年2月発行)
今月の主題 大腸ポリープのすべて
59巻1号(2024年1月発行)
今月の主題 自己免疫性胃炎—病期分類と画像所見
58巻12号(2023年12月発行)
今月の主題 遺伝性消化管疾患を考える
58巻11号(2023年11月発行)
今月の主題 小腸画像診断のトピックス
58巻10号(2023年10月発行)
増大号 「胃と腸」式 読影問題集2023 応用と発展—考える画像診断が身につく
58巻9号(2023年9月発行)
今月の主題 知っておくべき口腔・咽喉頭病変
58巻8号(2023年8月発行)
今月の主題 十二指腸拡大内視鏡の最新知見
58巻7号(2023年7月発行)
今月の主題 消化管リンパ増殖性疾患の診断アプローチの基本
58巻6号(2023年6月発行)
今月の主題 分類不能腸炎(IBDU)の現状と将来展望
58巻5号(2023年5月発行)
今月の主題 壁内局在からみた胃上皮下腫瘍の鑑別診断
58巻4号(2023年4月発行)
増大号 「胃と腸」式 読影問題集2023 基本と応用—考える画像診断が身につく
58巻3号(2023年3月発行)
今月の主題 食道ESD瘢痕近傍病変の診断と治療
58巻2号(2023年2月発行)
今月の主題 鋸歯状病変関連の早期大腸癌
58巻1号(2023年1月発行)
今月の主題 Non-H. pylori Helicobacter胃炎と周辺疾患
57巻13号(2022年12月発行)
今月の主題 IEEを使いこなす
57巻12号(2022年11月発行)
今月の主題 胃型形質を示す胃・十二指腸上皮性腫瘍
57巻11号(2022年10月発行)
今月の主題 食道癌診療トピックス2022
57巻10号(2022年9月発行)
今月の主題 大腸腫瘍診療の最前線
57巻9号(2022年8月発行)
今月の主題 胃癌スクリーニングの課題と将来展望
57巻8号(2022年7月発行)
今月の主題 転移性消化管腫瘍
57巻7号(2022年6月発行)
今月の主題 特殊型胃癌—組織発生と内視鏡診断
57巻6号(2022年5月発行)
今月の主題 原発性小腸癌—見えてきたその全貌
57巻5号(2022年5月発行)
増刊号 図説「胃と腸」画像診断用語集2022
57巻4号(2022年4月発行)
今月の主題 予後不良な早期消化管癌
57巻3号(2022年3月発行)
今月の主題 食道上皮内腫瘍の診断と取り扱い
57巻2号(2022年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の粘膜治癒を再考する
57巻1号(2022年1月発行)
今月の主題 H. pylori除菌後発見胃癌の診断UPDATE
56巻13号(2021年12月発行)
今月の主題 非乳頭部十二指腸腺腫・癌の診断と治療
56巻12号(2021年11月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の鑑別診断
56巻11号(2021年10月発行)
今月の主題 咽頭表在癌の内視鏡診断と治療
56巻10号(2021年9月発行)
今月の主題 胃上皮性腫瘍—組織分類・内視鏡診断の新展開
56巻9号(2021年8月発行)
今月の主題 「胃と腸」式 読影問題集—考える画像診断が身につく
56巻8号(2021年7月発行)
今月の主題 早期大腸癌内視鏡治療の新展開
56巻7号(2021年6月発行)
今月の主題 食道胃接合部腺癌の診断2021
56巻6号(2021年5月発行)
今月の主題 上部消化管非腫瘍性ポリープの内視鏡所見と病理所見
56巻5号(2021年5月発行)
増刊号 消化管診断・治療手技のすべて2021
56巻4号(2021年4月発行)
今月の主題 消化管疾患AI診断の現状
56巻3号(2021年3月発行)
今月の主題 内視鏡医も知っておくべき病理診断リファレンス—下部消化管腫瘍
56巻2号(2021年2月発行)
今月の主題 Barrett食道腺癌の内視鏡診断と治療2021
56巻1号(2021年1月発行)
今月の主題 早期胃癌内視鏡治療・適応のUPDATE
55巻13号(2020年12月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変の新展開
55巻12号(2020年11月発行)
今月の主題 高齢者早期胃癌ESDの現状と問題点
55巻11号(2020年10月発行)
今月の主題 小腸腫瘍アトラス
55巻10号(2020年9月発行)
今月の主題 食道SM扁平上皮癌治療の新展開
55巻9号(2020年8月発行)
今月の主題 一度見たら忘れられない症例
55巻8号(2020年7月発行)
今月の主題 H. pylori未感染胃の上皮性腫瘍
55巻7号(2020年6月発行)
今月の主題 薬剤関連消化管病変のトピックス
55巻6号(2020年5月発行)
今月の主題 スキルス胃癌—病態と診断・治療の最前線
55巻5号(2020年5月発行)
増刊号 消化管腫瘍の内視鏡診断2020
55巻4号(2020年4月発行)
今月の主題 内視鏡医も知っておくべき病理診断リファレンス—上部消化管腫瘍
55巻3号(2020年3月発行)
今月の主題 いま知っておきたい食道良性疾患
55巻2号(2020年2月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎関連腫瘍—診断・治療の現状と課題
55巻1号(2020年1月発行)
今月の主題 早期胃癌の範囲診断up to date
54巻13号(2019年12月発行)
今月の主題 遺伝子・免疫異常に伴う消化管病変—最新のトピックスを中心に
54巻12号(2019年11月発行)
今月の主題 上部消化管感染症—最近の話題を含めて
54巻11号(2019年10月発行)
今月の主題 大腸腫瘍の病理診断の課題と将来展望
54巻10号(2019年9月発行)
今月の主題 知っておきたい特殊な食道腫瘍・腫瘍様病変
54巻9号(2019年8月発行)
今月の主題 消化管X線造影検査のすべて—撮影手技の実際と読影のポイント
54巻8号(2019年7月発行)
今月の主題 十二指腸腺腫・癌の診断
54巻7号(2019年6月発行)
今月の主題 A型胃炎—最新の知見
54巻6号(2019年5月発行)
今月の主題 隆起型早期大腸癌の病態と診断
54巻5号(2019年5月発行)
増刊号 消化管疾患の分類2019—使い方,使われ方
54巻4号(2019年4月発行)
今月の主題 知っておきたい小腸疾患
54巻3号(2019年3月発行)
今月の主題 咽頭・食道内視鏡拡大観察の基本と最新知見
54巻2号(2019年2月発行)
今月の主題 胃・十二指腸内視鏡拡大観察の基本と最新知見
54巻1号(2019年1月発行)
今月の主題 大腸内視鏡拡大観察の基本と最新知見
53巻13号(2018年12月発行)
今月の主題 EUSによる消化管疾患の診断—現状と最新の話題
53巻12号(2018年11月発行)
今月の主題 知っておきたい十二指腸病変
53巻11号(2018年10月発行)
今月の主題 胃拡大内視鏡が変えたclinical practice
53巻10号(2018年9月発行)
今月の主題 食道表在癌の拡大内視鏡診断─食道学会分類を検証する
53巻9号(2018年8月発行)
今月の主題 消化管画像の成り立ちを知る
53巻8号(2018年7月発行)
今月の主題 対策型胃内視鏡検診の現状と問題点
53巻7号(2018年6月発行)
今月の主題 知っておきたい直腸肛門部病変
53巻6号(2018年5月発行)
今月の主題 小腸出血性疾患の診断と治療─最近の進歩
53巻5号(2018年5月発行)
増刊号 早期胃癌2018
53巻4号(2018年4月発行)
今月の主題 腸管感染症─最新の話題を含めて
53巻3号(2018年3月発行)
今月の主題 好酸球性食道炎の診断と治療
53巻2号(2018年2月発行)
今月の主題 IBDの内視鏡的粘膜治癒─評価法と臨床的意義
53巻1号(2018年1月発行)
今月の主題 胃型形質の低異型度分化型胃癌
52巻13号(2017年12月発行)
今月の主題 咽頭・頸部食道癌の診断と治療
52巻12号(2017年11月発行)
今月の主題 大腸小・微小病変に対するcold polypectomyの意義と課題
52巻11号(2017年10月発行)
今月の主題 非特異性多発性小腸潰瘍症/CEAS─遺伝子異常と類縁疾患
52巻10号(2017年9月発行)
今月の主題 胃粘膜下腫瘍の診断と治療
52巻9号(2017年8月発行)
今月の主題 大腸スクリーニングの現状と将来展望
52巻8号(2017年7月発行)
今月の主題 臨床医も知っておくべき免疫組織化学染色のすべて
52巻7号(2017年6月発行)
今月の主題 胃潰瘍は変わったか─新しい胃潰瘍学の構築を目指して
52巻6号(2017年5月発行)
今月の主題 知っておきたいまれな大腸良性疾患
52巻5号(2017年5月発行)
増刊号 図説「胃と腸」所見用語集2017
52巻4号(2017年4月発行)
今月の主題 消化管内分泌細胞腫瘍の新知見
52巻3号(2017年3月発行)
今月の主題 表在型食道胃接合部癌の治療戦略
52巻2号(2017年2月発行)
今月の主題 消化管結核の診断と治療─最近の進歩
52巻1号(2017年1月発行)
今月の主題 知っておくべき胃疾患の分類
51巻13号(2016年12月発行)
今月の主題 狭窄を来す小腸疾患の診断
51巻12号(2016年11月発行)
今月の主題 十二指腸の上皮性腫瘍
51巻11号(2016年10月発行)
今月の主題 肉芽腫を形成する消化管病変
51巻10号(2016年9月発行)
今月の主題 表在型Barrett食道癌の診断
51巻9号(2016年8月発行)
今月の主題 消化管画像プレゼンテーションの基本と実際
51巻8号(2016年7月発行)
今月の主題 消化管疾患と皮膚病変
51巻7号(2016年6月発行)
今月の主題 新しい小腸・大腸画像診断─現状と将来展望
51巻6号(2016年5月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌後発見胃癌の内視鏡的特徴
51巻5号(2016年5月発行)
増刊号 消化管拡大内視鏡診断2016
51巻4号(2016年4月発行)
今月の主題 薬剤関連消化管病変
51巻3号(2016年3月発行)
今月の主題 知っておきたいまれな大腸悪性腫瘍
51巻2号(2016年2月発行)
今月の主題 まれな食道疾患の鑑別診断
51巻1号(2016年1月発行)
今月の主題 慢性胃炎を見直す
50巻13号(2015年12月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変の取り扱い
50巻12号(2015年11月発行)
今月の主題 胃底腺型胃癌
50巻11号(2015年10月発行)
今月の主題 血管炎による消化管病変
50巻10号(2015年9月発行)
今月の主題 狭窄を来す大腸疾患─診断のプロセスを含めて
50巻9号(2015年8月発行)
今月の主題 食道胃接合部腺癌
50巻8号(2015年7月発行)
今月の主題 胃がん検診に未来はあるのか
50巻7号(2015年6月発行)
今月の主題 診断困難な炎症性腸疾患
50巻6号(2015年5月発行)
今月の主題 知っておきたいまれな胃疾患
50巻5号(2015年5月発行)
増刊号 早期消化管癌の深達度診断 2015
50巻4号(2015年4月発行)
今月の主題 早期大腸癌内視鏡治療後の中・長期経過
50巻3号(2015年3月発行)
今月の主題 胃癌範囲診断における拡大観察のピットフォール
50巻2号(2015年2月発行)
今月の主題 食道のびらん・潰瘍性病変
50巻1号(2015年1月発行)
今月の主題 消化管早期癌診断学の時代変遷─50年の歩みと展望
49巻13号(2014年12月発行)
今月の主題 胃の腺腫─診断と治療方針
49巻12号(2014年11月発行)
今月の主題 大腸LSTの診断と意義—拡大内視鏡を中心に
49巻11号(2014年10月発行)
今月の主題 胃癌ESD適応拡大病変の経過と予後
49巻10号(2014年9月発行)
今月の主題 colitic cancerの初期病変─遡及例の検討を含めて
49巻9号(2014年8月発行)
今月の主題 小腸潰瘍の鑑別診断
49巻8号(2014年7月発行)
今月の主題 表面型表層拡大型食道癌の診断と治療戦略
49巻7号(2014年6月発行)
今月の主題 大腸T1(SM)癌に対する内視鏡治療の適応拡大
49巻6号(2014年5月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori陰性胃癌
49巻5号(2014年5月発行)
増刊号 消化管悪性リンパ腫2014
49巻4号(2014年4月発行)
今月の主題 虫垂病変のすべて―非腫瘍から腫瘍まで
49巻3号(2014年3月発行)
今月の主題 消化管アミロイドーシスを見直す
49巻2号(2014年2月発行)
今月の主題 日本食道学会拡大内視鏡分類
49巻1号(2014年1月発行)
今月の主題 ESD時代の早期胃癌深達度診断
48巻13号(2013年12月発行)
今月の主題 好酸球性消化管疾患の概念と取り扱い
48巻12号(2013年11月発行)
今月の主題 虚血性腸病変
48巻11号(2013年10月発行)
今月の主題 組織混在型粘膜内胃癌の診断
48巻10号(2013年9月発行)
今月の主題 小腸の悪性腫瘍
48巻9号(2013年8月発行)
今月の主題 食道表在癌治療の最先端
48巻8号(2013年7月発行)
今月の主題 非腫瘍性大腸ポリープのすべて
48巻7号(2013年6月発行)
今月の主題 消化管内分泌細胞腫瘍の診断と治療―WHO分類との対比
48巻6号(2013年5月発行)
今月の主題 微小胃癌の診断限界に迫る
48巻5号(2013年5月発行)
特集 炎症性腸疾患 2013
48巻4号(2013年4月発行)
今月の主題 カプセル内視鏡の現状と展望
48巻3号(2013年3月発行)
今月の主題 隆起型食道癌の特徴と鑑別診断
48巻2号(2013年2月発行)
今月の主題 大腸ESDの適応と実際
48巻1号(2013年1月発行)
今月の主題 潰瘍合併早期胃癌の診断と治療
47巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 右側大腸腫瘍の臨床病理学的特徴
47巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 高齢者消化管疾患の特徴
47巻11号(2012年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌後の胃癌
47巻10号(2012年9月発行)
今月の主題 難治性Crohn病の特徴と治療戦略
47巻9号(2012年8月発行)
今月の主題 食道癌の発育進展─初期浸潤の病態と診断
47巻8号(2012年7月発行)
今月の主題 胃ポリープの意義と鑑別
47巻7号(2012年6月発行)
今月の主題 大腸憩室疾患
47巻6号(2012年5月発行)
今月の主題 経鼻内視鏡によるスクリーニング
47巻5号(2012年5月発行)
特集 図説 胃と腸用語集2012
47巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 消化管EUS診断の現状と新たな展開
47巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 咽頭・頸部食道癌の鑑別診断
47巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 改訂された胃生検Group分類の現状
47巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 腸管三次元CT診断の現状
46巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 難治性潰瘍性大腸炎─診療・治療の新たな展開
46巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 Barrett食道癌の診断
46巻11号(2011年10月発行)
今月の主題 十二指腸の腫瘍性病変
46巻10号(2011年9月発行)
今月の主題 大腸SM癌に対する内視鏡治療の適応拡大
46巻9号(2011年8月発行)
今月の主題 若年者の胃・十二指腸病変の特徴
46巻8号(2011年7月発行)
今月の主題 食道の炎症性疾患
46巻7号(2011年6月発行)
今月の主題 腸管Behçet病と単純性潰瘍─診断と治療の進歩
46巻6号(2011年5月発行)
今月の主題 胃腫瘍の拡大内視鏡診断
46巻5号(2011年5月発行)
特集 食道表在癌2011
46巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変と癌化
46巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 免疫不全状態における消化管病変
46巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 NSAID起因性小腸病変
46巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 多発胃癌─最新の知見を含めて
45巻14号(2010年12月発行)
第41巻~第45巻 総索引 2006年~2010年(平成18年~平成22年)
45巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝性消化管疾患の特徴と長期経過
45巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 特殊型胃癌の病理像と臨床的特徴
45巻11号(2010年10月発行)
今月の主題 大腸低分化腺癌の初期像とその進展
45巻10号(2010年9月発行)
今月の主題 Crohn病小腸病変に対する診断と治療の進歩
45巻9号(2010年8月発行)
今月の主題 食道表在癌の深達度診断
45巻8号(2010年7月発行)
今月の主題 直腸肛門部病変の鑑別診断─最新の知見を含めて
45巻7号(2010年6月発行)
今月の主題 低異型度分化型胃癌の診断
45巻6号(2010年5月発行)
今月の主題 側方発育型大腸腫瘍(laterally spreading tumor ; LST)─分類と意義
45巻5号(2010年4月発行)
特集 早期大腸癌2010
45巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 スキルス胃癌と鑑別を要する疾患
45巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 出血性小腸疾患─内視鏡診断・治療の最前線
45巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 中・下咽頭表在癌の診断と治療
45巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 早期胃癌のIIb進展範囲診断
44巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 collagenous colitisの現況と新知見
44巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 消化管癌の化学・放射線療法の効果判定と問題点
44巻11号(2009年10月発行)
今月の主題 食道小扁平上皮癌の診断
44巻10号(2009年9月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎の初期病変とその進展・経過
44巻9号(2009年8月発行)
今月の主題 背景粘膜からみた胃癌ハイリスクグループ
44巻8号(2009年7月発行)
今月の主題 大腸SM癌内視鏡治療の根治基準をめぐって─病理診断の問題点と予後
44巻7号(2009年6月発行)
今月の主題 食道胃接合部腺癌の診断
44巻6号(2009年5月発行)
今月の主題 小腸疾患─小病変の診断と治療の進歩
44巻5号(2009年4月発行)
今月の主題 癌や炎症と鑑別が困難な消化管悪性リンパ腫
44巻4号(2009年4月発行)
特集 早期胃癌2009
44巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 食道扁平上皮癌に対するESDの適応と実際
44巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 特発性腸間膜静脈硬化症(idiopathic mesenteric phlebosclerosis)―概念と臨床的取り扱い
44巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 未分化型胃粘膜内癌のESD―適応拡大の可能性
43巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 大腸癌の発生・発育進展
43巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 早期胃癌発育の新たな分析─内視鏡経過例の遡及的検討から
43巻11号(2008年10月発行)
今月の主題 感染性腸炎─最近の動向と知見
43巻10号(2008年9月発行)
今月の主題 早期食道癌の診断─最近の進歩
43巻9号(2008年8月発行)
今月の主題 colitic cancer/dysplasiaの早期診断─病理組織診断の問題点も含めて
43巻8号(2008年7月発行)
今月の主題 胃癌に対する内視鏡スクリーニングの現状と将来
43巻7号(2008年6月発行)
今月の主題 消化管follicular lymphoma―診断と治療戦略
43巻6号(2008年5月発行)
今月の主題 大腸の新しい画像診断
43巻5号(2008年4月発行)
今月の主題 linitis plastica型胃癌―病態と診断・治療の最前線
43巻4号(2008年4月発行)
特集 小腸疾患2008
43巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 まれな食道良性腫瘍および腫瘍様病変
43巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 消化管GIST―診断・治療の新展開
43巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 早期胃癌ESD―適応拡大を求めて
42巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 新しい治療による炎症性腸疾患(IBD)の経過―粘膜治癒を中心に
42巻12号(2007年11月発行)
今月の主題 非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)起因性消化管病変
42巻11号(2007年10月発行)
今月の主題 ESD時代における未分化型混在早期胃癌の取り扱い
42巻10号(2007年9月発行)
今月の主題 大腸腫瘍内視鏡切除後のサーベイランスに向けて
42巻9号(2007年8月発行)
今月の主題 食道表在癌内視鏡切除後の長期成績
42巻8号(2007年7月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫―除菌無効例の特徴と治療戦略
42巻7号(2007年6月発行)
今月の主題 大腸ESDの現況と将来展望
42巻6号(2007年5月発行)
今月の主題 Helicobacter pyloriと胃癌
42巻5号(2007年4月発行)
特集 消化管の拡大内視鏡観察2007
42巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患(IBD)の上部消化管病変
42巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変の発育進展と診断・取り扱い
42巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 食道扁平上皮dysplasia―診断と取り扱いをめぐって
42巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 胃分化型SM1癌の診断―垂直浸潤500μm
41巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 大腸腫瘍に対する拡大内視鏡診断の最先端
41巻12号(2006年11月発行)
今月の主題 小腸疾患診療の新たな展開
41巻11号(2006年10月発行)
今月の主題 早期胃癌に対するESDと腹腔鏡下手術の接点
41巻10号(2006年9月発行)
・sm癌の最新の診断と治療戦略
41巻9号(2006年8月発行)
今月の主題 通常内視鏡による大腸sm癌の深達度診断 垂直侵潤距離1,000μm術前診断の現状
41巻8号(2006年7月発行)
今月の主題 転移陽性胃粘膜内癌の特徴と取り扱い
41巻7号(2006年6月発行)
今月の主題 Helicobacter pyloriに起因しないとされる良性胃粘膜病変
41巻6号(2006年5月発行)
今月の主題 非定型的炎症性腸疾患―診断と経過
41巻5号(2006年4月発行)
今月の主題 陥凹性小胃癌の診断―基本から最先端まで
41巻4号(2006年4月発行)
特集 消化管内視鏡治療2006
41巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腸管悪性リンパ腫―最近の知見
41巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 食道表在癌の内視鏡診断―最近の進歩
41巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 早期胃癌に対するESDの適応の現状と今後の展望
40巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 いわゆる側方発育型大腸腫瘍の治療法を問う
40巻12号(2005年11月発行)
今月の主題 胃癌EMR後の異時性多発を考える
40巻11号(2005年10月発行)
今月の主題 小腸内視鏡検査法の進歩
40巻10号(2005年9月発行)
今月の主題 難治性潰瘍性大腸炎―診断と治療の新知見
40巻9号(2005年8月発行)
今月の主題 表在性の中・下咽頭癌
40巻8号(2005年7月発行)
今月の主題 免疫異常と消化管病変
40巻7号(2005年6月発行)
今月の主題 胃癌化学療法の進歩と課題
40巻6号(2005年5月発行)
今月の主題 Crohn病の初期病変―診断と長期経過
40巻4号(2005年4月発行)
特集 消化管の出血性疾患2005
40巻5号(2005年4月発行)
今月の主題 切開・剥離法(ESD)時代の胃癌術前診断
40巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 特殊組織型の食道癌
40巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 大腸カルチノイド腫瘍 転移例と非転移例の比較を中心に
40巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 胃癌の時代的変遷と将来展望
39巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 大腸sm癌の内視鏡治療後の長期経過
39巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 消化管の画像診断―21世紀の展開
39巻11号(2004年10月発行)
今月の主題 胃生検診断の意義 Group分類を考える
39巻10号(2004年9月発行)
今月の主題 大腸sm癌の深達度診断―垂直浸潤1,000μm
39巻9号(2004年8月発行)
今月の主題 Barrett食道癌―表在癌の境界・深達度診断
39巻8号(2004年7月発行)
今月の主題 家族性大腸腺腫症―最近の話題
39巻7号(2004年6月発行)
今月の主題 胃癌術後の残胃癌
39巻6号(2004年5月発行)
今月の主題 深達度診断を迷わせる食道表在癌―その原因と画像の特徴
39巻5号(2004年4月発行)
今月の主題 大腸腫瘍に対する拡大内視鏡観察―V型pit pattern診断の問題点
39巻4号(2004年4月発行)
特集 消化管の粘膜下腫瘍 2004
39巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫―除菌治療後の経過と予後
39巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 Crohn病経過例における新しい治療の位置づけ
39巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 最新の早期胃癌EMR―切開・剥離法
38巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 消化管への転移性腫瘍
38巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 上部消化管拡大観察の意義
38巻11号(2003年10月発行)
今月の主題 粘膜下腫瘍様の形態を示した消化管癌
38巻10号(2003年9月発行)
今月の主題 胃腺腫の診断と治療方針
38巻9号(2003年8月発行)
今月の主題 直腸肛門部病変の鑑別診断
38巻8号(2003年7月発行)
今月の主題 経過観察からみた大腸癌の発育・進展sm癌を中心に
38巻7号(2003年6月発行)
今月の主題 消化管の炎症性疾患診断におけるX線検査の有用性
38巻6号(2003年5月発行)
今月の主題 消化管腫瘍診断におけるX線検査の有用性
38巻5号(2003年4月発行)
今月の主題 胃型早期胃癌の病理学的特徴と臨床像―分化型癌を中心に
38巻4号(2003年4月発行)
特集 全身性疾患と消化管病変
38巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 食道癌と他臓器重複癌―EMR時代を迎えて
38巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 腸型Behçet病と単純性潰瘍の長期経過
38巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 胃癌―診断と治療の最先端
37巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 胃癌と鑑別を要する炎症性疾患
37巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 Ⅰp・Ⅰsp型大腸sm癌
37巻11号(2002年10月発行)
今月の主題 消化管のvirtual endoscopy
37巻10号(2002年9月発行)
今月の主題 食道sm癌の再評価―食道温存治療の可能性を求めて
37巻9号(2002年8月発行)
今月の主題 胃粘膜内癌EMRの適応拡大と限界
37巻8号(2002年7月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と腫瘍(2)潰瘍性大腸炎以外
37巻7号(2002年6月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と腫瘍(1)潰瘍性大腸炎
37巻6号(2002年5月発行)
今月の主題 十二指腸の非腫瘍性びまん性病変
37巻5号(2002年4月発行)
今月の主題 cap polyposisと粘膜脱症候群
37巻4号(2002年3月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌に伴う問題点
37巻3号(2002年2月発行)
特集 消化管感染症2002
37巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 4型大腸癌とその鑑別診断
37巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 食道m3・sm1癌の診断と遠隔成績
36巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 早期胃癌診療の実態と問題点
36巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 十二指腸の小病変
36巻11号(2001年10月発行)
今月の主題 sm massive以深に浸潤した10mm以下の大腸癌
36巻10号(2001年9月発行)
今月の主題 縮小治療のための胃癌の粘膜内浸潤範囲診断
36巻9号(2001年8月発行)
今月の主題 GIST(gastrointestinal stromal tumor)―概念と臨床的取り扱い
36巻8号(2001年7月発行)
今月の主題 多発食道癌
36巻7号(2001年6月発行)
今月の主題 小腸腫瘍―分類と画像所見
36巻6号(2001年5月発行)
今月の主題 早期大腸癌の深達度診断にEUSと拡大内視鏡は必要か
36巻5号(2001年4月発行)
今月の主題 早期の食道胃接合部癌
36巻4号(2001年3月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎診断基準の問題点
36巻3号(2001年2月発行)
特集 消化管癌の深達度診断
36巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Crohn病診断基準の問題点
36巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 表層型胃悪性リンパ腫の鑑別診断―治療法選択のために
35巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 21世紀への消化管画像診断学―歩みと展望
35巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 早期大腸癌肉眼分類―統一をめざして
35巻11号(2000年10月発行)
今月の主題 胃カルチノイド―新しい考え方
35巻10号(2000年9月発行)
今月の主題 食道アカラシア
35巻9号(2000年8月発行)
今月の主題 薬剤性腸炎―最近の話題
35巻8号(2000年7月発行)
今月の主題 多発大腸癌
35巻7号(2000年6月発行)
今月の主題 胃の“pre-linitis plastica”型癌
35巻6号(2000年5月発行)
今月の主題 腸管の血管性病変―限局性腫瘍状病変を中心に
35巻5号(2000年4月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌後の消化性潰瘍の経過―3年以上の症例を中心に
35巻4号(2000年3月発行)
今月の主題 食道癌の発育進展―初期病巣から粘膜下層癌へ
35巻3号(2000年2月発行)
特集 消化管ポリポーシス2000
35巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患における生検の役割
35巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の基本所見とピットフォール
34巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 大腸腫瘍の内視鏡診断は病理診断にどこまで近づくか
34巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 胃癌診断における生検の現状と問題点
34巻11号(1999年10月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫―Helicobacter pylori除菌後の経過
34巻10号(1999年9月発行)
今月の主題 Crohn病の長期経過―10年以上の症例を中心に
34巻9号(1999年8月発行)
今月の主題 早期胃癌のEUS診断
34巻8号(1999年7月発行)
今月の主題 逆流性食道炎―分類・診断・治療
34巻7号(1999年6月発行)
今月の主題 AIDSとATLの消化管病変
34巻6号(1999年5月発行)
今月の主題 大腸sm癌の内視鏡的切除をめぐって
34巻5号(1999年4月発行)
今月の主題 大腸腫瘍内視鏡的切除後の局所再発―腺腫・m癌を中心に
34巻4号(1999年3月発行)
今月の主題 胃型の分化型胃癌―病理診断とその特徴
34巻3号(1999年2月発行)
特集 消化管の画像診断―US,CT,MRIの役割
34巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 Barrett上皮と食道腺癌
34巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 Ⅱ型早期大腸癌肉眼分類の問題点
33巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 胃癌EMR後の遺残再発―診断と治療
33巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 胃癌EMRの完全切除の判定基準を求めて
33巻11号(1998年10月発行)
今月の主題 早期大腸癌の組織診断―諸問題は解決されたか
33巻10号(1998年9月発行)
今月の主題 腸管子宮内膜症
33巻9号(1998年8月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎―最近の話題
33巻8号(1998年7月発行)
今月の主題 胃炎―Sydney SystemとHelicobacter pylori
33巻7号(1998年6月発行)
食道癌
33巻6号(1998年5月発行)
今月の主題 鋸歯状腺腫(serrated adenoma)とその周辺
33巻5号(1998年4月発行)
今月の主題 大腸疾患の診断に注腸X線検査は必要か
33巻4号(1998年3月発行)
今月の主題 胃癌の診断にX線検査は不要か
33巻3号(1998年2月発行)
特集 消化管悪性リンパ腫1998
33巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 消化管病変の三次元画像診断―現状と展望
33巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 「胃と腸」33年間の歩みからみた早期癌
32巻13号(1997年12月発行)
との鑑別を中心に
32巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 腺領域からみた胃病変
32巻11号(1997年10月発行)
今月の主題 Is型大腸sm癌を考える
32巻10号(1997年9月発行)
今月の主題 早期食道癌―X線診断の進歩
32巻9号(1997年8月発行)
今月の主題 胃噴門部領域の病変 (2)癌以外の病変
32巻8号(1997年7月発行)
今月の主題 胃噴門部領域の病変 (1)癌
32巻7号(1997年6月発行)
今月の主題 感染性腸炎(腸結核を除く)
32巻6号(1997年5月発行)
今月の主題 早期胃癌から進行癌への進展
32巻5号(1997年4月発行)
今月の主題 粘膜下腫瘍様の食道表在癌
32巻4号(1997年3月発行)
今月の主題 大腸腺腫症―最近の知見
32巻3号(1997年2月発行)
特集 炎症性腸疾患1997
32巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 十二指腸乳頭部癌―縮小手術をめざして
32巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 胃sm癌の細分類―治療法選択の指標として
31巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 大腸腫瘍の自然史
31巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 未分化型小胃癌はなぜ少ないか
31巻11号(1996年10月発行)
今月の主題 微細表面構造からみた大腸腫瘍の診断
31巻10号(1996年9月発行)
今月の主題 内視鏡的食道粘膜切除後の経過
31巻9号(1996年8月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的粘膜切除―適応拡大をめぐる問題点
31巻8号(1996年7月発行)
今月の主題 Helicobacter Pyloriと胃リンパ腫
31巻7号(1996年6月発行)
今月の主題 遺伝性非ポリポーシス大腸癌(HNPCC)
31巻6号(1996年5月発行)
今月の主題 食道dysplasia―経過観察例の検討
31巻5号(1996年4月発行)
今月の主題 表層拡大型早期胃癌
31巻4号(1996年3月発行)
今月の主題 新しいCrohn病診断基準(案)
31巻3号(1996年2月発行)
特集 図説 形態用語の使い方・使われ方
31巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 いわゆる表層拡大型大腸腫瘍とは
31巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫
30巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 小腸画像診断の新しい展開
30巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 大腸腺腫の診断と取り扱い
30巻11号(1995年10月発行)
今月の主題 食道表在癌の発育進展―症例から学ぶ
30巻10号(1995年9月発行)
今月の主題 微小胃癌
30巻9号(1995年8月発行)
今月の主題 胃の平滑筋腫と平滑筋肉腫―新しい視点を求めて
30巻8号(1995年7月発行)
今月の主題 表層拡大型食道表在癌
30巻7号(1995年6月発行)
今月の主題 大腸の悪性リンパ腫
30巻6号(1995年5月発行)
今月の主題 粘膜下腫瘍の形態を示した胃癌
30巻5号(1995年4月発行)
今月の主題 colitic cancer―微細診断をめざして
30巻4号(1995年3月発行)
今月の主題 腸結核
30巻3号(1995年2月発行)
特集 早期食道癌1995
30巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 表面型大腸癌の発育と経過
30巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 胃癌の診断と治療―最近の動向
29巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 上部消化管病変の特徴からみた全身性疾患
29巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 大腸sm癌の細分類とその臨床
29巻11号(1994年10月発行)
今月の主題 大腸sm癌の細分類とその意義
29巻10号(1994年9月発行)
今月の主題 胃底腺領域の分化型癌
29巻9号(1994年8月発行)
今月の主題 食道のヨード不染帯
29巻8号(1994年7月発行)
今月の主題 胆管癌の画像と病理
29巻7号(1994年6月発行)
今月の主題 多発胃癌
29巻6号(1994年5月発行)
今月の主題 アフタ様病変のみのCrohn病
29巻5号(1994年4月発行)
今月の主題 大腸Crohn病―非定型例の診断を中心に
29巻4号(1994年3月発行)
今月の主題 食道粘膜癌―新しい病型分類とその診断
29巻3号(1994年2月発行)
特集 早期大腸癌1994
29巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 胃良・悪性境界病変の生検診断と治療方針
29巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 表面型大腸腫瘍―肉眼分類を考える
28巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的根治切除―適応拡大の可能性と限界を探る
28巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 消化管ポリポーシス―最近の知見
28巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 大腸癌の深達度診断
28巻10号(1993年9月発行)
今月の主題 胃悪性リンパ腫―診断の変遷
28巻9号(1993年8月発行)
今月の主題 虚血性腸病変の新しい捉え方
28巻8号(1993年7月発行)
今月の主題 大腸癌存在診断の実態―m癌を除く
28巻7号(1993年6月発行)
今月の主題 十二指腸腫瘍
28巻6号(1993年5月発行)
今月の主題 大腸腫瘍切除後の経過追跡
28巻5号(1993年4月発行)
今月の主題 腸管アフタ様病変
28巻4号(1993年3月発行)
今月の主題 難治性胃潰瘍(2)臨床経過と難治化の要因
28巻3号(1993年2月発行)
特集 早期胃癌1993
28巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内視鏡的食道粘膜切除術
28巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 胃癌は変わったか―その時代的変遷
27巻12号(1992年12月発行)
今月の主題 難治性胃潰瘍(1)治癒予測を中心に
27巻11号(1992年11月発行)
今月の主題 大腸pm癌
27巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 胃癌の深達度診断mとsmの鑑別―内視鏡的治療のために
27巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 逆流性食道炎を見直す
27巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 表面型大腸腫瘍の臨床診断の諸問題
27巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 出血を来した小腸病変の画像診断
27巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 早期大腸癌の病理診断の諸問題―小病変の診断を中心に
27巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 linitis plastica型胃癌診断の現状
27巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 大腸のいわゆる結節集簇様病変
27巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 腸型Behçet病・simple ulcerの経過
27巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 食道表在癌の深達度を読む
27巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 胃癌の自然史を追う―経過追跡症例から
26巻12号(1991年12月発行)
今月の主題 集検発見胃癌の特徴
26巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 膠原病と腸病変
26巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 胃癌の組織型分類とその臨床的意義
26巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 Ⅲ型早期胃癌の診断に迫る―潰瘍の良・悪性の鑑別
26巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 大腸sm癌の治療
26巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 大腸sm癌の診断
26巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 Crohn病の長期経過
26巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎の長期経過
26巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的切除(2)―内視鏡的根治切除の評価
26巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的切除(1)―根治を目的として
26巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 食道“dysplasia”の存在を問う
26巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 早期胃癌―診断の基本と方法
25巻12号(1990年12月発行)
今月の主題 早期胃癌類似進行癌の診断
25巻11号(1990年11月発行)
今月の主題 直腸のいわゆる粘膜脱症候群
25巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 中垂腫瘤
25巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 早期食道癌を問う
25巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 臨床経過からみた胃生検の問題点
25巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 小さな表面型(Ⅱ型)大腸上皮性腫瘍
25巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の鑑別診断(2)―大腸病変を中心に
25巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の鑑別診断(1)―小腸・回盲部病変を中心に
25巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 Barrett食道
25巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 胃癌の切除範囲をどう決めるのか
25巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 膵囊胞性疾患―動態診断の基礎と臨床
25巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 上部消化管X線検査の現状の反省と将来―検査モデルを求めて
24巻12号(1989年12月発行)
今月の主題 小さな未分化型胃癌―分化型と比較して
24巻11号(1989年11月発行)
今月の主題 いわゆる“十二指腸炎”の諸問題
24巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 分類困難な腸の炎症性疾患
24巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 胃粘膜下腫瘍の診断―現況と進歩
24巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 腸のカルチノイド
24巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 胆道疾患の非手術的治療の進歩
24巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 急性胃粘膜病変(AGML)
24巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 腸管の悪性リンパ腫(2)
24巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 胃・十二指腸出血の非手術的治療
24巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 大腸腺腫と癌(2)
24巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 大腸腺腫と癌(1)
24巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 噴門部陥凹型早期胃癌の診断
23巻12号(1988年12月発行)
今月の主題 腸管の悪性リンパ腫(1)
23巻11号(1988年11月発行)
今月の主題 食道癌の発育進展―逆追跡症例を中心に
23巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 十二指腸乳頭部癌
23巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 大腸内視鏡検査法―手技を中心として
23巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 小さな膵癌―小病変の鑑別診断をめぐって
23巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 微小胃癌診断―10年の進歩
23巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 びまん浸潤型大腸癌と転移性大腸癌
23巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍と超音波内視鏡
23巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 内視鏡的胃粘膜切除の臨床―ジャンボ・バイオプシーをめぐって
23巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化管形態診断の将来はどうあるべきか
23巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 消化管のアミロイドーシス(2)
23巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 X線・内視鏡所見と切除標本・病理所見との対比(胃)
22巻12号(1987年12月発行)
今月の主題 早期食道癌の問題点
22巻11号(1987年11月発行)
今月の主題 消化管のアミロイドーシス(1)
22巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 胃のDieulafoy潰瘍
22巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 胃底腺領域の癌―Ⅱcを中心として
22巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 陥凹型早期大腸癌
22巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 腸結核と癌
22巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 胃の腺腫とは―現状と問題点
22巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 胆囊癌の診断―発育進展を中心に
22巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 小さな大腸癌―早期診断のために
22巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 直腸・肛門部病変の新しい診かた
22巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 陥凹型早期胃癌の深達度診断
22巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 電子スコープの現況
21巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 大腸のvillous tumor
21巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 消化性潰瘍のトピックス(2)―胃粘膜防御機構を中心に
21巻10号(1986年10月発行)
受容体拮抗薬のもたらした諸問題
21巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎と大腸癌
21巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 胃癌肉眼分類の問題点―進行癌を中心として
21巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 膵の囊胞性疾患―その診断の進歩
21巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 大腸生検の問題点―炎症性疾患の経過を中心に
21巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 早期胆嚢癌―その診断の進歩
21巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 Ⅱb型早期胃癌の診断
21巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 大腸早期癌診断におけるX線と内視鏡との比較
21巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 消化管の“比較診断学”を求めて(2)
21巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 消化管の“比較診断学”を求めて(1)
20巻12号(1985年12月発行)
今月の主題 食道癌の早期診断
20巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 内視鏡的乳頭括約筋切開術の長期成績
20巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 大腸ポリペクトミー後の経過
20巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 胃癌診断におけるルーチン検査の確かさ―部位別・大きさ別の検討
20巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 大腸癌の発育・進展
20巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 小腸診断学の進歩―実際から最先端まで
20巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 慢性胃炎をどう考えるか
20巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 食道静脈瘤の硬化療法
20巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 膵・胆道の形成異常
20巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 大腸診断学の歩みと展望
20巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 胃診断学20年の歩みと展望―良性疾患を中心として
20巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 胃診断学20年の歩みと展望―早期胃癌を中心として
19巻12号(1984年12月発行)
今月の主題 消化管癌の診断におけるUS・CTの役割
19巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 膵癌の治療成績
19巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 胃生検の問題点
19巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 胃潰瘍の治癒判定
19巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 胃癌の内視鏡的治療
19巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 早期胃癌の再発死亡例をめぐって
19巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 大腸腺腫症の経過と予後
19巻5号(1984年5月発行)
受容体拮抗薬の位置づけ
19巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 肝内結石症―最近の知見をめぐって
19巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 Crohn病の経過
19巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 Panendoscopyの評価(2)
19巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 Panendoscopyの評価(1)
18巻12号(1983年12月発行)
今月の主題 Crohn病の診断
18巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 逆流性食道炎
18巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 胆囊病変をめぐる最近の知見
18巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の問題点(2)―診断の現状
18巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 大腸sm癌
18巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎―治療と経過を中心に
18巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の問題点(1)―良性病変と鑑別困難な早期癌
18巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 消化管の悪性病変と皮膚病変
18巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 急性腸炎(2)―主として感染性腸炎
18巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 症例・研究特集
18巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 急性腸炎(1)―主として抗生物質起因性大腸炎
18巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 臨床の場における上部消化管スクリーニング法―X線と内視鏡
17巻12号(1982年12月発行)
今月の主題 残胃の癌
17巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 ERCP―10年を経て―(2)技術の進歩と展開
17巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 ERCP―10年を経て―(1)診断能と限界―特に総合画像診断における位置づけ
17巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 症例・研究特集
17巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 小腸X線検査法の進歩
17巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍の病態生理
17巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 胆道系疾患の臨床(3)―早期胆道癌の診断を目指して
17巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 sm胃癌の問題点(3)―臨床と病理
17巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 胃の隆起性病変(polypoid lesion)―その形態と経過
17巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 症例・研究特集
17巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 sm胃癌の問題点(2)―陥凹型症例
17巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 sm胃癌の問題点(1)―隆起型症例
16巻12号(1981年12月発行)
今月の主題 胃のⅡb病変
16巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 胆道系疾患の臨床(2)―胆管異常を中心として
16巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 小腸腫瘍(2)
16巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 小腸腫瘍(1)
16巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 症例・研究特集
16巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 実験胃癌とヒト胃癌
16巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 胆道系疾患の臨床(1)―総胆管結石症を中心として
16巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(4)―治療と経過
16巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(3)―鑑別
16巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 虚血性腸炎の臨床と病理
16巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(2)―良性リンパ腫
16巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 早期胃癌は変貌したか
15巻12号(1980年12月発行)
今月の主題 逆追跡された胃のlinitis plastica―早期発見のために(2)
15巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 逆追跡された胃のlinitis plastica―早期発見のために(1)
15巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
15巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(1)―悪性リンパ腫
15巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 大腸憩室
15巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 消化管出血と非手術的止血
15巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 小膵癌診断への挑戦
15巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 胃のGiant Rugae
15巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 大腸の早期癌―胃早期癌と比較して
15巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 症例特集
15巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 腺境界と胃病変
15巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 胃病変の時代的変貌
14巻12号(1979年12月発行)
今月の主題 胃癌の化学療法
14巻11号(1979年11月発行)
今月の主題 急性胃病変と慢性胃潰瘍の関連をめぐって
14巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 消化管の健診を考える
14巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 症例・研究特集
14巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 微小胃癌
14巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 回盲弁近傍潰瘍(2)―Intestinal Behcetを中心に
14巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 回盲弁近傍潰瘍(1)―いわゆる“Simple Ulcer”を中心に
14巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 消化管と血管病変
14巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
14巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 X線と内視鏡との協力
14巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の反省(2)
14巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の反省(1)
13巻12号(1978年12月発行)
今月の主題 クローン病(3)―疑診例を中心に
13巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 食道・胃 境界領域癌の問題点
13巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸 併存潰瘍
13巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 腸結核(3)―疑診例を中心に
13巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 症例・研究特集
13巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 慢性膵炎
13巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍の治療の検討
13巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化管粘膜拡大観察と病態生理
13巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 クローン病(2)
13巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 クローン病(1)
13巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性胃潰瘍とその周辺
13巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 胃癌の発育経過
12巻12号(1977年12月発行)
今月の主題 腸結核(2)―大腸を主として
12巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 腸結核(1)―小腸を主として
12巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
12巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 胃癌の浸潤範囲・深達度の判定(2)
12巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 胃癌の浸潤範囲・深達度の判定(1)
12巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 残胃病変
12巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 胆道癌の診断と治療
12巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 高齢者の胃病変の特徴
12巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
12巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 直腸肛門部病変
12巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 S状結腸癌
12巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 胃癌―5年以後の再発
11巻12号(1976年12月発行)
今月の主題 放射線診断の最近の進歩
11巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 Endoscopic Surgery
11巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 胃スキルスの病理
11巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 症例・研究特集
11巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎―最近の趨勢
11巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 pm胃癌
11巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 食道・噴門境界部の病変
11巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 胃潰瘍癌の考え方
11巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 研究・症例特集
11巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 早期食道癌
11巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 小腸疾患の現況
11巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 早期胃癌肉眼分類の再検討
10巻12号(1975年12月発行)
今月の主題 全身性疾患と消化管
10巻11号(1975年11月発行)
今月の主題 胃の良・悪性境界領域病変
10巻10号(1975年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
10巻9号(1975年9月発行)
今月の主題 消化管疾患の新しい診断法
10巻8号(1975年8月発行)
今月の主題 クローン病とその周辺
10巻7号(1975年7月発行)
今月の主題 消化管の非上皮性腫瘍
10巻6号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管憩室
10巻5号(1975年5月発行)
今月の主題 消化管カルチノイド
10巻4号(1975年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
10巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 胃ポリープの癌化をめぐって
10巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 胃粘膜―(2)潰瘍,ポリープの背景として
10巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 胃粘膜―(1)早期胃癌の背景として
9巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 膵疾患の展望(2)―膵炎を中心に
9巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 膵疾患の展望(1)―膵炎を中心に
9巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
9巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 消化管の特殊なポリポージス
9巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 胃潰瘍の最近の問題点
9巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 盲腸・上行結腸の診断
9巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 胃を除く上腹部腫瘤の診断
9巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 症例・研究特集
9巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 意外な進展を示す胃癌
9巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 内視鏡的ポリペクトミー
9巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 食道・腸の生検
9巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 胃の生検
8巻12号(1973年12月発行)
今月の主題 十二指腸疾患の最新の診断
8巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 症例・研究特集
8巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 表層拡大型胃癌
8巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 胃潰瘍の良・悪性の鑑別診断
8巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 早期胃癌と線状潰瘍の合併
8巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 消化管出血の緊急診断
8巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 大腸疾患 最新の話題
8巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 胃癌の経過
8巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
8巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内視鏡的膵・胆管造影
8巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 消化管の悪性リンパ腫
8巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 急性胃病変の臨床
7巻12号(1972年12月発行)
今月の主題 腸の潰瘍性病変
7巻11号(1972年11月発行)
今月の主題 十二指腸乳頭部病変
7巻10号(1972年10月発行)
今月の主題 食道炎と食道静脈瘤
7巻9号(1972年9月発行)
今月の主題 胃集検で発見された胃潰瘍
7巻8号(1972年8月発行)
今月の主題 症例・研究特集
7巻7号(1972年7月発行)
今月の主題 若年者の消化管癌
7巻6号(1972年6月発行)
今月の主題 胃癌浸潤程度の診断
7巻5号(1972年5月発行)
今月の主題 悪性サイクル
7巻4号(1972年4月発行)
今月の主題 早期胃癌肉眼分類起草10年
7巻3号(1972年3月発行)
今月の主題 早期胃癌臨床診断の実態(診断成績の推移と問題点)
7巻2号(1972年2月発行)
今月の主題 Ⅲ型早期胃癌
7巻1号(1972年1月発行)
今月の主題 Ⅱb型早期胃癌
6巻13号(1971年12月発行)
今月の主題 Ⅱa+Ⅱc型早期胃癌
6巻12号(1971年11月発行)
今月の主題 症例・研究特集
6巻11号(1971年10月発行)
今月の主題 胃前壁病変の診断
6巻10号(1971年9月発行)
今月の主題 便秘と下痢
6巻9号(1971年8月発行)
今月の主題 幽門部(pyloric portion)の病変
6巻8号(1971年7月発行)
今月の主題 幽門部(pyloric portion)の診断
6巻7号(1971年6月発行)
今月の主題 腸上皮化生
6巻5号(1971年5月発行)
今月の主題 症例特集号
6巻6号(1971年5月発行)
特集 胃集団検診
6巻4号(1971年4月発行)
今月の主題 消化管穿孔
6巻3号(1971年3月発行)
今月の主題 早期胃癌と紛らわしい病変
6巻2号(1971年2月発行)
今月の主題 陥凹性早期胃癌
6巻1号(1971年1月発行)
今月の主題 隆起性早期胃癌
5巻13号(1970年12月発行)
今月の主題 胃潰瘍の再発・再燃
5巻12号(1970年11月発行)
今月の主題 症例・研究 特集
5巻11号(1970年10月発行)
今月の主題 大腸の早期癌―胃を除く消化器の早期癌(2)
5巻10号(1970年9月発行)
今月の主題 胃を除く消化器の早期癌(1)
5巻9号(1970年8月発行)
今月の主題 高位の胃病変
5巻8号(1970年7月発行)
今月の主題 診断された微小胃癌
5巻7号(1970年6月発行)
特集 胃生検特集
5巻6号(1970年6月発行)
今月の主題 症例・研究 特集
5巻5号(1970年5月発行)
今月の主題 早期胃癌再発例の検討
5巻4号(1970年4月発行)
今月の主題 胆のう胆道疾患診断法の最近の進歩
5巻3号(1970年3月発行)
今月の主題 胃肉腫
5巻2号(1970年2月発行)
今月の主題 線状潰瘍
5巻1号(1970年1月発行)
今月の主題 胃癌の経過
4巻12号(1969年12月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎
4巻11号(1969年11月発行)
今月の主題 十二指腸の精密診断
4巻10号(1969年10月発行)
今月の主題 早期癌とその周辺
4巻9号(1969年9月発行)
今月の主題 胃癌の5年生存率
4巻8号(1969年8月発行)
今月の主題 X線・内視鏡で良性様所見を呈した生検陽性例
4巻7号(1969年7月発行)
今月の主題 胃の変位と変形(2)
4巻6号(1969年6月発行)
今月の主題 胃の変位と変形(1)
4巻5号(1969年5月発行)
今月の主題 稀な胃病変
4巻4号(1969年4月発行)
今月の主題 小腸の検査法
4巻3号(1969年3月発行)
今月の主題 胃癌深達度の診断と経過観察
4巻2号(1969年2月発行)
今月の主題 上部消化管の出血
4巻1号(1969年1月発行)
今月の主題 大彎側の病変
3巻13号(1968年12月発行)
今月の主題 陥凹性早期胃癌の経過
3巻12号(1968年11月発行)
今月の主題 多発胃癌
3巻11号(1968年10月発行)
今月の主題 食道
3巻10号(1968年9月発行)
今月の主題 直視下診断法
3巻9号(1968年8月発行)
今月の主題 消化管の医原性疾患
3巻8号(1968年7月発行)
今月の主題 進行癌の問題点
3巻7号(1968年6月発行)
今月の主題 胃癌の発生
3巻6号(1968年6月発行)
今月の主題 前癌病変としての胃潰瘍とポリープの意義
3巻5号(1968年5月発行)
今月の主題 胃の巨大皺襞
3巻4号(1968年4月発行)
今月の主題 胃の食物輸送機能
3巻3号(1968年3月発行)
今月の主題 大腸・直腸
3巻2号(1968年2月発行)
今月の主題 胃集団検診と早期胃癌
3巻1号(1968年1月発行)
今月の主題 早期胃癌研究の焦点
2巻12号(1967年12月発行)
今月の主題 小腸
2巻11号(1967年11月発行)
今月の主題 慢性胃炎2
2巻10号(1967年10月発行)
今月の主題 慢性胃炎1
2巻9号(1967年9月発行)
今月の主題 胃の多発性潰瘍
2巻8号(1967年8月発行)
今月の主題 難治性胃潰瘍
2巻7号(1967年7月発行)
今月の主題 胃切除後の問題
2巻6号(1967年6月発行)
今月の主題 胃のびらん
2巻5号(1967年5月発行)
今月の主題 早期胃癌の鑑別診断
2巻4号(1967年4月発行)
今月の主題 胃微細病変の診断
2巻3号(1967年3月発行)
今月の主題 胃液分泌の基礎と臨床
2巻2号(1967年2月発行)
今月の主題 十二指腸潰瘍〔2〕
2巻1号(1967年1月発行)
今月の主題 十二指腸潰瘍〔1〕
