「胃と腸」誌の専門分野である消化管は口腔から肛門に至る長大な管腔であり,多彩な疾病が発生する臓器である.臨床医学においては,病歴,身体所見,検査成績を把握することが基本であるが,消化管疾患は非特異的な症状を契機に診断されることが多い.事実,消化管腫瘍の大部分は無症状のまま診断されており,これはスクリーニング検査の精度が向上したためと考えられている.このように,消化管疾患を診断するためには適切な検査法の選択と,得られた所見や生検結果を正確に分析する能力が要求される.
さらに,消化管疾患においては内視鏡を中心とした治療手技が数多く開発されてきた.中でも,粘膜下層に対する内視鏡的アプローチはこの領域の最近の話題であり,斬新な治療法が次々と開発・報告されている.したがって,新旧治療法の特徴を理解したうえで適切に選択することも消化管専門医の任務と言える.そこで,今回の増刊号は,消化管疾患の形態診断と治療について,古典的手法から最新の手技まで網羅的に取り上げ,簡潔に解説することを目的に企画された.加えて,X線・内視鏡検査所見の解析に必須である解剖学的特徴についても解説している.
雑誌目次
胃と腸56巻5号
2021年05月発行
雑誌目次
増刊号 消化管診断・治療手技のすべて2021
序文 フリーアクセス
著者: 松本主之
ページ範囲:P.527 - P.527
咽喉頭 診断
咽喉頭の解剖
著者: 船越真木子 , 武藤学
ページ範囲:P.529 - P.529
咽喉頭の解剖名を正確に認識することは,適切に病変を評価し,耳鼻咽喉科/頭頸部外科と連携をとるうえで重要である.本稿では消化器内視鏡医に必要と思われる中咽頭,下咽頭,咽頭の解剖を簡潔に解説する.
通常内視鏡(経鼻)
著者: 川田和昭
ページ範囲:P.530 - P.531
咽喉頭癌の治療では発声や嚥下といった機能を喪失する可能性が高い.しかし,表在癌の段階で内視鏡診断できれば,治療による機能損失は最小限に抑えられ,術後のQOL(quality of life)にも大きく寄与するはずである.この領域の表在癌診断は消化器内視鏡医に課された新しい使命とも言えるのではないだろうか.咽喉頭を入念に観察するためには,嘔吐反射を誘発することが少ない経鼻内視鏡が最適と考えられる.最新型経鼻内視鏡スコープの画像解像度は通常径内視鏡(経口内視鏡)のそれに匹敵すると評価されており,スクリーニングには問題のないレベルに達している.本稿では経鼻内視鏡検査時の咽喉頭観察・撮影法,そしていかに病変を拾い上げるかを解説する.
画像強調内視鏡:拾い上げ診断と鑑別診断
著者: 船越真木子 , 武藤学
ページ範囲:P.534 - P.535
NBI(narrow band imaging)やBLI(blue laser imaging),LCI(linked color imaging)に代表される画像強調内視鏡が日常診療で用いられるようになり,咽喉頭の内視鏡診断学は一変した.NBI,BLIにおいて扁平上皮癌は,“well demarcated brownish area with scattered brown dots”1)(異常血管を伴う境界明瞭な茶褐色領域)として認識され,拾い上げられることが多い.一方で,咽喉頭観察をすることによって,消化器内視鏡医にとっては馴染みの薄い咽喉頭病変に遭遇する機会が増えた.本稿では,画像強調内視鏡を用いた咽喉頭癌の鑑別診断について概説する.
治療
ESD
著者: 飯塚敏郎 , 梶原有史
ページ範囲:P.536 - P.537
本稿では,咽喉頭表在癌を発見した場合に内視鏡医が施行する内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)について解説する.基本的操作であるマーキング,切開,剝離,止血操作に関しては,消化管と同様であるため本稿では割愛する(他稿参照のこと).
ELPS
著者: 卜部祐司 , 田中信治
ページ範囲:P.538 - P.539
咽喉頭表在癌に対するELPS(endoscopic laryngopharyngeal surgery)の適応,手技の実際に関して解説する.
EMR-C
著者: 土田知宏
ページ範囲:P.540 - P.541
EMR-C(endoscopic mucosal resection with a cap-fitted panendoscope)法は,スコープ先端に装着した透明キャップ内に病変部を吸引してスネアで絞扼するという方法である1).内視鏡治療初心者でも安全に行える治療手技であることから一般に普及し,ESD(endoscopic submucosal dissection)が主流となった現在でも用いられている手技である.
食道 診断
食道の解剖
著者: 平澤大 , 赤平純一
ページ範囲:P.542 - P.542
食道の区分
食道は咽頭と胃を繋ぐ細長い直線的な管腔臓器である.食道の区分はFig.1 1)の通り,口側からCe,Ut,Mt,Lt,Aeと定められている.内視鏡的には,Phの柵状血管下端がO(輪状軟骨下縁レベル)にあたり,食道遠位側の柵状血管下端がEGJに相当する.Oは食物通過時以外は内腔が閉鎖しているので,内視鏡的に確認するにはフードをつけるなどの工夫が必要である.食道は3か所の生理的狭窄部を有し,それぞれO,大動脈ならびに左主気管支と食道の交差する部位(Mt領域内),食道裂孔部(ほぼEGJに一致)である.
食道造影:撮影法と拾い上げ診断
著者: 小田丈二 , 入口陽介 , 細井董三
ページ範囲:P.544 - P.545
撮影法
筆者ら1)は,食道表在癌の拾い上げを目的として,1995年より胃X線集団検診の場に食道癌のhigh risk groupである55歳以上の男性に対し,立位第1斜位での食道二重造影像を1枚を加えた食道・胃同時集検を行ってきた.その結果,対象をhigh risk groupに集約すれば,胃X線集団検診の場に食道検診を導入する意義は大きいと思われた1)〜3).
撮影の実際については,本稿は拾い上げ診断を目的とした撮影法の解説が目的であるため,精密X線検査ではなく,スクリーニング検査時の撮影法3)を述べることとする.対策型検診における撮影は,診療放射線技師が行うことが多い.発泡剤を服用後,立位第1斜位にし,バリウムを大口で飲んでもらい,透視観察しながら中部食道から入口部付近までをタイミングよく二重造影で撮影する.椎体の重なりなどの障害陰影や,心拍動によるブレに注意しながら,良質な二重造影を心がける.場合によっては連続撮影3)も考慮する.人間ドックなど任意型検診の場合には,上部食道や第2斜位での撮影を組み合わせることが多い.
食道造影:癌の診断および深達度診断
著者: 小野陽一郎 , 八尾建史
ページ範囲:P.546 - P.547
癌の診断
食道X線造影検査(以下,食道造影)による食道癌の診断は正面像と辺縁像から成り立つ1).すなわち,正面像では縦走ひだの変化(不明瞭化や中断,口径不同)や粘膜面の異常所見(粗糙,不整な陰影斑・透亮像など)に注目し,側面像では辺縁の所見(壁不整,伸展不良など)を参考にして病変を拾い上げる.そして,これらの所見の拡がりや程度によって病変の範囲,深達度を診断する.
食道造影は粘膜面の凹凸を描出する検査法である.ごく軽微な形態変化にとどまるT1a-EP/LPM癌は,病変境界が不明瞭であることや,粘膜面の異常所見,辺縁の所見が乏しいことが多く,食道造影による描出には限界がある.ゆえに,少量〜中等量の空気量(弱伸展像)による縦走ひだの変化を捉えることが必要である(Fig.1).
通常内視鏡:撮影法と拾い上げ診断
著者: 高木靖寛
ページ範囲:P.548 - P.549
内視鏡所見による食道の解剖
食道は食道入口部から食道胃接合部(esophagogastric junction ; EGJ)までの約25cmの管腔臓器で,生理的狭窄部が3か所ある.第1狭窄部は上部食道括約筋に相当する食道入口部で切歯列から18cm付近,第2狭窄部は大動脈弓と左主気管支による圧排部で27〜28cmに位置する(Fig.1).第3狭窄部はEGJで下部食道括約筋部に相当する.食道の上端(Fig.2)と下端には柵状血管が観察され,EGJはこの柵状血管の下端もしくは胃側からのひだの上端と定義される.
画像強調内視鏡
著者: 岩坪太郎 , 石原立
ページ範囲:P.550 - P.550
概要
NBI(narrow band imaging)やBLI(blue laser imaging)などの画像強調内視鏡(image enhancement endoscopy ; IEE)は狭帯域光によって病変の視認性を向上させ,白色光観察では拾い上げが困難な表在扁平上皮癌の検出を可能とする.NBIやBLIで観察すると,癌は茶色域(brownish area ; BA)として認識される.
BAの茶色変化の成因の一つは,癌化によりIPCL(intra-epithelial papillary capillary loop)の拡張や蛇行したType B血管が増生することである.そして,もう一つの成因が血管と血管の間の上皮の茶色化(background coloration)である.正常の扁平上皮表層は光を強く反射するため白色調に見えるが,癌部分は食道上皮がほぼ全層性に癌細胞で置換されることで,食道粘膜内に進入しヘモグロビンに吸収される光が増加し,background colorationが出現すると考えられている1).
通常内視鏡:癌の診断と鑑別診断
著者: 都宮美華 , 有馬美和子
ページ範囲:P.552 - P.553
表在型食道扁平上皮癌の通常内視鏡観察は,まず病変の拡がりと病型を診断する.病変を構成する隆起や陥凹成分の大きさ・形態,個数と配列などを把握し,空気量や観察角度も変えながら動的に観察する.本稿では表在型食道扁平上皮癌の通常観察の要点と,鑑別を要する病変との相違点について病型ごとに解説する.
色素内視鏡(ヨード/トルイジンブルー)
著者: 中村理恵子 , 大森泰
ページ範囲:P.554 - P.555
ヨード染色法
0.5〜1.0%のヨウ素/ヨウ化カリウム溶液を用いて食道粘膜(重層扁平上皮)を染色する方法である.正常食道粘膜上層と有棘細胞層内にはグリコーゲンが含まれており,撒布されたヨウ素が細胞内グリコーゲンと反応し発色する現象(ヨウ素・デンプン反応)を利用した染色法である.正常食道粘膜は茶褐色に染色されるが,癌細胞はグリコーゲンを含まないために黄白色を示す領域となる.このような黄白色領域をヨード不染帯と言う.この現象は表在型食道癌を診断する上で重要である(Fig.1a).
しかし,上皮欠損を示す食道炎などの炎症性変化,萎縮などの上皮菲薄部,異所性胃粘膜などでもヨード不染帯となり,注意が必要である(Fig.1b).上皮全層が癌細胞である病変は通常観察で淡い発赤を示すことが多く,ヨード染色では明瞭なヨード不染帯となる.染色直後は黄白色不染帯であるが,数分後に淡いピンクの色調変化が不染部に起こる.この現象をPC(pink-color)signと呼び,粘膜内癌では高頻度に認められる1)(Fig.1c).長径5mm以上・不整形の不染帯でPC sign陽性であれば癌である可能性が極めて高く,多発ヨード不染帯からの表在型食道癌拾い上げ診断に極めて有用である.
色素内視鏡(Barrett食道)
著者: 田中一平 , 平澤大
ページ範囲:P.556 - P.557
本稿ではBarrett食道癌に対するスクリーニング,精密検査に用いる色素内視鏡に関して解説する.
画像強調拡大内視鏡(癌の精査)
著者: 竹内学
ページ範囲:P.560 - P.561
食道癌に対し拡大内視鏡観察を行う主目的は深達度診断である.深達度を診断する際に通常内視鏡観察および超音波内視鏡検査(endoscopic ultrasonography ; EUS),さらに食道X線造影検査の結果も加味して判断するが,今回はNBI(narrow band imaging)拡大内視鏡での診断手法・診断のコツについて解説する.
超拡大内視鏡
著者: 郷田憲一 , 入澤篤志
ページ範囲:P.562 - P.562
超拡大内視鏡(Endocyto)は最大倍率520倍の拡大機能を有し,内視鏡施行中に生体内でHE染色を施した病理組織像に匹敵する細胞レベルの内視鏡像が得られる.その観察に際し,食道上皮の細胞核・細胞質を染色する必要があり1),焦点距離が極めて近いため,スコープの先端を食道表面に接触させて観察する.
染色液として,0.05%クリスタルバイオレット(crystal violet ; CV)と1%メチレンブルー(methylene blue ; MB)の混合液1)または1% MB単独が使用されている.しかし,海外においてCVとMBの発癌性を指摘する報告があり,CVに関しては本邦での製造が中止された.このような状況を鑑み,食道扁平上皮癌に対するEndocytoにトルイジンブルー染色を用いている施設もある2).
EUS
著者: 前田有紀
ページ範囲:P.564 - P.565
EUS機器の選択
超音波内視鏡(endoscopic ultrasonography ; EUS)は細径超音波プローブとEUS専用機に大別される(Fig.1).
細径プローブは内視鏡の鉗子孔から挿入し,病変を直視下に超音波を走査するため,小病変でも的確に描出できる.表在病変の診断には20MHzの高周波プローブが適する.高周波は分解能が良好で表層の詳細な観察に優れる一方,深部減衰が強いため,隆起性病変の深部や壁外の観察は難しい.
内視鏡と一体になっているEUS専用機は探触子が大きく,広範囲の鮮明な画像を得やすい.専用機の周波数は5〜12MHzで切り替えられ,さまざまな病変を観察できる.ただし,内視鏡と超音波の描出部位がずれるため,凹凸の乏しい小病変は部位の同定が難しい.進行癌や大きな粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT),系統的なリンパ節転移診断には専用機が適する.
治療
ESD
著者: 菊池大輔 , 布袋屋修
ページ範囲:P.566 - P.567
本稿では食道ESD(endoscopic submucosal dissection)の手技について,処置具の使用法を含めて,先端系ナイフを用いた方法について概説する.基本テクニックと知っておくと便利なテクニックに分けて概説する.
EMRC法(キャップ法)
著者: 井上晴洋
ページ範囲:P.568 - P.568
1991年当時,食道でovertubeを用いた内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection ; EMR)が行われていた1).それとは前後して,米国のStiegmann GV2)が,rubber band ligatorを用いた食道静脈瘤に対する結紮術を報告した.それを見た瞬間,筆者は消化管のEMRに使用可能であると考えた.およそ30年前(1992年)に,透明キャップを用いたEMRC(EMR with a cap-fitted panendoscope)法(キャップ法)はまず早期食道癌に施行された3)(Fig.1).その後,消化管全域に適用を拡げており4),ESDが普及した現在でも,特に食道の2cmくらいまでの病変は,短時間で治療できる.キャップ法は,その後,band ligator+snare法(duet,captivatorなど)として,広く普及した.
EEMR-tube
著者: 島田英雄 , 幕内博康
ページ範囲:P.569 - P.569
EEMR-tube法の基本手技
EEMR-tube(endoscopic esophageal mucosal resection-tube)法はMakuuchiら1)が開発したEEMR-tubeを用いる内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection ; EMR)の手技である.チューブはシリコンラバー製で,透明で軟らかく全長60cm,内径14mmで先端部は斜めになっている.スネアを通すサイドチャンネル,手元部にはチューブ内腔を気密化するバルーンが備わっている(Fig.1).
基本手技は,まずEEMR-tubeにスコープを通しておき食道内に挿入する.病巣の口側2〜3mmの位置に粘膜下注入して切除範囲を膨隆させる(Fig.2a).次に内視鏡に沿わせEEMR-tubeを進める.サイドチャンネルからスネアを挿入し病巣上に拡げ(Fig.2b),手元バルーンに空気を注入しチューブ内を気密化する.内視鏡の吸引で病巣を含む食道粘膜をチューブ内に吸引し,スネアで絞扼する(Fig.2c).チューブをわずかに引き抜き,ポリープ状に絞扼された食道粘膜を通電切離する.筆者ら2)はEEMR-tube法で一括切除が困難な病巣には,分割切除法と遺残再発防止のトリミングによる4 step法を施行している.
APC焼灼
著者: 川田研郎
ページ範囲:P.570 - P.570
APCの原理と機器
APC(argon plasma coagulation)はイオン化されたアルゴンガスの中を高周波電流が効率よく組織に流れ,組織を失活させ破壊する方法で,止血や花粉症の治療などさまざまな用途に用いられる.食道早期癌にAPCを行う際に準備するのは高周波手術装置(VIO3)とアルゴンガス,APCプローベで,APCプローベにはビームが,①直線的に伸びるaxial type(A-probe),②側方に伸びるside fire type(S-probe),③円周状に伸びるcircumferential type(C-probe)の3種類がある.経鼻内視鏡を通過する細径用のプローベも市販されている.APCには①従来から行われているforced APCに加え,②広範囲をすばやく凝固できるpulsed APC,③より浅い凝固層の形成が可能なprecise APC,の3種類のモードがある.実施の際には内視鏡の先端にフードを装着する.
RFA
著者: 岩谷勇吾
ページ範囲:P.571 - P.571
消化管に対するラジオ波焼灼術(radiofrequency ablation ; RFA)は,バイポーラシステムを用いて粘膜の一定深度(0.5〜1mm)までを焼灼する治療手技である.本邦では未導入であるが,欧米では主にBarrett食道や胃前庭部毛細血管拡張症(gastric antral vascular ectasia ; GAVE),放射線性直腸炎に用いられ,アジアでも台湾や中国を中心に食道扁平上皮の多発ヨード不染などへの使用が試みられている.本稿では欧米でのBarrett食道への使用につき解説する.
欧米に多いLSBE(long segment Barrett's esophagus)は発癌リスクが高く,内視鏡による腫瘍切除後の異時性多発が問題となる.よって,欧米ではまず腫瘍を内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection ; EMR)や内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)で切除したのちに,残存するBarrett粘膜に対しRFAやcryotherapyに代表される焼灼療法(ablative therapy)を行う.その後強力な酸分泌抑制治療を行うことで,Barrett粘膜を扁平上皮に完全に置換させることを治療の最終ゴールとしている.
PDT
著者: 渡邊崇 , 矢野友規
ページ範囲:P.572 - P.573
光線力学的療法(photodynamic therapy ; PDT)は,化学放射線療法または放射線療法後の局所遺残再発食道癌で,内視鏡的切除(EMR/ESD)が不可能,または外科的手術適応がない患者に対する治療として行われる.PDTの適応に関してはFig.1に示した通りである.本治療では,光感受性物質であるレザフィリン®投与後に病変部にレーザー光を照射することで,光化学反応を惹起し,腫瘍を壊死させる.
EVL
著者: 中村真一
ページ範囲:P.574 - P.575
内視鏡的静脈瘤結紮術(endoscopic variceal ligation ; EVL)は1988年Stiegmannらにより臨床応用された.EVLは手技が簡便で,経験や技量による差が少なく,期待度に近い治療効果が得られる.出血例に対しても有用であり,消化器内視鏡医が習得しておくべき基本手技の一つである.
EIS
著者: 小原勝敏
ページ範囲:P.576 - P.578
本稿では食道静脈瘤(esophageal varices ; EV)に対するEIS(endoscopic injection sclerotherapy)の手技のコツを中心に,EVL(endoscopic variceal ligation)との適応の住み分けについても解説する.
バルーン拡張術
著者: 卜部祐司 , 田中信治
ページ範囲:P.579 - P.579
食道狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術(endoscopic balloon dilation ; EBD)の適応,手技の方法,治療の偶発症と限界に関して解説する.
RIC
著者: 青山育雄 , 武藤学
ページ範囲:P.580 - P.580
RIC(radial incision and cutting)は,高周波ナイフを用いて狭窄部の瘢痕組織を切開・除去することによって狭窄を改善する手技である.本稿ではRICの手技の方法とそのコツ,注意点に関して解説する.
ステント留置
著者: 岡村卓真 , 野中哲
ページ範囲:P.582 - P.583
食道ステントの種類
現在,本邦で食道ステントとして臨床で使用できる製品はSEMS(self-expandable metallic stent)である.数社からさまざまな特色のある製品が出されているが,皮膜の範囲によってuncovered,partially covered,fully coveredに分類される.その他,海外で承認・市販されている製品としてはSEPS(self-expandable plastic stent),BDステント(biodegradable stent)などがある.BDステントは吸収性のあるポリジオキサノン縫合糸を用いた生体分解性ステントであり,4〜5週間で加水分解され始め,2〜3か月で完全分解される.
異物除去
著者: 五十嵐公洋
ページ範囲:P.584 - P.584
食道は生理的狭窄部位を有するため,異物による停滞を来しやすい.また,管腔が狭いためスネアや回収ネットを扱いにくいという問題もある.
鋭利な異物の場合,摘出する際に入口部や咽頭に裂傷を来すリスクがある.小さな異物の場合,先端透明フード内に鋭利な部分を収めるのみで回収できるが,有鈎義歯などのサイズの大きな異物の場合は回収が困難である.指サック1)や手袋2),コンドーム型尿カテーテル3)を内視鏡先端にスカート状に巻きつけて鋭利な部分を被覆して回収する方法が報告されており,有用と思われる.Fig.1のようにいったん胃内に落とし,ネットなどに完全に収納して除去するのも選択肢の一つである.
POEM
著者: 南ひとみ
ページ範囲:P.586 - P.587
食道アカラシアおよび類縁疾患に対するPOEM
1.POEMの適応
POEM(per-oral endoscopic myotomy)1)の適応は,主に内輪筋の異常収縮あるいは弛緩不全を主な病態とする疾患である.内輪筋を食道壁内で切開して短軸方向の狭窄や異常な収縮運動を解除することで効果が得られる.よって,食道アカラシアや遠位食道痙攣,Jackhammer食道などがPOEMのよい適応となる.
POET
著者: 佐藤千晃 , 井上晴洋
ページ範囲:P.588 - P.588
POET(per-oral endoscopic tumor resection)はPOEM(per-oral endoscopic myotomy)1)の粘膜下トンネル手技を応用した経口内視鏡的粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)摘出術である.本稿ではその手技と適応について解説する.
ARMS/ARMA
著者: 井上晴洋 , 田邊万葉 , 角一弥
ページ範囲:P.589 - P.589
ARMAとはanti-reflux mucosal ablationの略語であり,胃食道逆流症に対する逆流防止を目的とした内視鏡的粘膜焼灼術である.
内視鏡的縫縮(機械吻合によるGERDの治療)
著者: 土橋昭 , 炭山和毅
ページ範囲:P.590 - P.590
近年,内視鏡的縫合器を用いた低侵襲かつ治療効果の高い胃食道逆流症(gastroesophageal reflux disease ; GERD)の治療が報告され1)2),専用のTIF(transoral incisionless fundoplication)デバイス1)3)を用いた内視鏡治療が欧米を中心に普及しつつある.内視鏡を用いたGERDの治療の主な目標は,下部食道括約筋(lower esophageal sphincter ; LES)圧を増加させることと食道胃接合部(esophagogastric junction ; EGJ)のflap valveを再建し胃酸逆流を防ぐことにある3).
Zenker憩室に対する新しい内視鏡治療(Z-POEM)
著者: 小山恒男 , 高橋亜紀子 , ,
ページ範囲:P.591 - P.591
Zenker憩室の標準的治療法は,かつて外科的切除術であった.しかし,1995年に経口内視鏡を用いて,憩室と食道の間を切開する内視鏡的憩室形成術が報告され1)2),内視鏡治療が可能となった.しかし,この方法では,切開が不十分だと症状が改善せず,切開を長くすると穿孔を来すという欠点があった.
2016年にLiら3)が報告したZ-POEM(Zenker's peroral endoscopic myotomy)は,Zenker憩室の3cm口側で粘膜を切開し,Zenker憩室付近の粘膜下層をトンネル状に剝離して,Zenker憩室と食道内腔間の筋層を露出させ,直視下に筋層を切開する手技である.本法の開発により,穿孔の危険性がなく,十分な筋層切開が可能となった.
胃 診断
胃の解剖
著者: 赤松泰次
ページ範囲:P.592 - P.592
部位の名称
胃の各部の名称(Fig.1a)は一般に,①噴門部,②胃穹窿部,③胃体部,④胃角部,⑤前庭部の5つに区分され,さらに胃体部は口側より上部,中部,下部に細分される.また,周在を,①小彎,②大彎,③前壁,④後壁,の4つに分ける.それぞれの境界線は必ずしも厳密ではないが,病変部位を示す場合はできるだけ正確に部位と周在を記述する必要がある.病変が2つ以上の領域に跨る場合には,“胃体下部から胃角部にかけて”や“小彎やや後壁より”などと表現する.
一方,小彎と大彎をそれぞれ3等分し,部位を上部(U),中部(M),下部(L)の3つに分ける方法もある(Fig.1b).X線造影検査や内視鏡検査などで所見を記載する場合は通常前者を用いるが,「胃癌取扱い規約 第15版」1)では後者と定められている.また,同規約では食道胃接合部領域を胃食道接合部より上下各2cmと定義している(Fig.2)1).
木村・竹本分類
著者: 赤松泰次
ページ範囲:P.594 - P.595
木村・竹本分類1)は1969年に報告された内視鏡所見による胃粘膜萎縮境界の分類である(Fig.1).胃粘膜の色調,高さ(段差),血管透見像により胃底腺と幽門腺(正確には偽幽門腺化生)の境界を判定し,その境界が生検組織所見やコンゴーレッド染色像とほぼ一致することを証明している.加えて,この萎縮境界が胃体部の小彎から前後壁,さらに大彎に拡がるに従って胃酸分泌能が低下すると述べられている.したがって,この萎縮境界の分類は,内視鏡所見による胃粘膜萎縮の程度を表す指標となっている.
胃造影:撮影法
著者: 松本主之
ページ範囲:P.596 - P.597
特徴
かつては,胃癌の診断法として最初に習得すべき検査法であった.現在でもスクリーニングの検査法として胃がん検診に用いられているが,むしろ既知の胃病変の精密検査法として施行されることが多い.病変が胃前後壁とともに平面像として表現されるため,読影にコツを要する.しかし,美麗に撮影できれば,粗大病変のみならず,小病変の診断にも有用である.術者の技量が画像の質や読影に反映されるため,経験と知識を要する検査法の一つと言える.
胃造影:癌の診断と鑑別診断
著者: 入口陽介
ページ範囲:P.598 - P.599
胃X線検診における撮影法と読影法
胃X線検診では,撮影する放射線技師はスクリーニング撮影法1)の特徴を十分に理解し,撮影中にはバリウムの流れに注意を払いながら透視観察を効率的に行う.異常所見に気がついた場合には,読影補助として適切な追加撮影を行い,異常所見の有無を明確にすることが重要である.読影だけでなく撮影においても,胃上部には早期胃癌形態の進行癌の頻度が比較的高いことなどを理解し,H. pylori(Helicobacter pylori)感染状態を考慮して臨む必要がある.読影は,胃全体のバランス,辺縁像,粘膜ひだ像,粘膜像をもとに診断する.異常所見の領域性が認められるかどうかが重要であるが,胃粘膜へのバリウムの付着状態が不良であれば,病変の全体が描出されていない場合があることを念頭に置いて,拾い上げ診断を行うことも見落としを防ぐうえで大切である2).
通常内視鏡:撮影方法と拾い上げ診断
著者: 宇賀治良平 , 長浜隆司
ページ範囲:P.600 - P.601
上部消化管内視鏡検査において病変の早期発見・見落としを防ぐためには,胃全体を網羅的に盲点なく効率よく観察・撮影し,わずかな粘膜の色調変化や形態変化などを的確に拾い上げる必要がある.本稿では,早期胃癌の見つけ出しを目的としたスクリーニング法について,撮影方法,拾い上げ診断のコツについて概説する.
H. pylori感染の内視鏡診断
著者: 寺尾秀一
ページ範囲:P.602 - P.603
H. pylori未感染の内視鏡像
H. pylori(Helicobacter pylori)未感染胃では,胃粘膜全体が光沢を帯びた正色調で,胃体部で萎縮性変化(褪色・血管透見)を伴わず,多くの例で胃角付近までRAC(regular arrangement of collecting venule)が観察される(C0,Fig.1).後述するが,C1例の軽度前庭部胃炎の除菌後(既感染)との鑑別が通常観察では難しい場合もある.
A型胃炎の内視鏡診断
著者: 丸山保彦
ページ範囲:P.604 - P.605
A型胃炎は抗壁細胞抗体,抗内因子抗体による自己免疫性胃炎であり,H. pylori(Helicobacter pylori)感染によるB型胃炎とは内視鏡所見が異なる.
色素内視鏡(インジゴカルミン)
著者: 小澤俊文
ページ範囲:P.606 - P.606
色素内視鏡において,本法インジゴカルミン(indigo carmine ; IC)撒布はコントラスト法に分類される.染色法(メチレンブルー染色やクリスタルバイオレット染色)や反応法(ヨード染色やコンゴーレッド染色)と異なり,短時間で容易に再検が可能である.原理としては色素の溜まりやはじきを利用することで凹凸を強調する.これにより,①病変の形態,②病変の範囲/拡がり,③皺襞集中の有無,④萎縮の程度などが強調され視認しやすくなる(Fig.1).検査用ICは1アンプルに20mg/5ml(0.4%)含まれている.当院では0.15〜0.2%程度に希釈して使用している.症例(病変)によっては薄く,あるいは濃くする場合もある.
使用方法は,小病変であれば鉗子口から空気を含めたシリンジで5mlほど直接注入/撒布するが,広範な病変(腫瘍,炎症)では撒布チューブを用いて色素を撒く.撒布前に病変をよく洗浄し,粘液を洗い落とす必要がある(Fig.2).また,病変に直接撒布すると予期せぬ出血を来す場合があるため,重力の方向を勘案しながら対象病変上流側の健常粘膜に撒くことがコツである.
色素内視鏡(酢酸法/Congo-red法)
著者: 名和田義高
ページ範囲:P.607 - P.607
酢酸法
円柱上皮に1.5%の酢酸を撒布すると,上皮細胞の細胞質内の蛋白質が可逆的に変化し,半透明であった粘膜が白色化し光を透過しなくなる.白色化の程度は,上皮の種類によって異なり,腸上皮化生は白色化しやすく,早期胃癌などの発赤病変は,やや白色化しにくい1).また,白色化が消失するまでの時間は癌の領域で早く,組織型によっても異なる2).
白色光観察では,この色調差を利用して早期胃癌の範囲診断に利用することができる.さらにインジゴカルミンを追加撒布することで,癌部は赤,非癌部は青という良好なコントラストが得られることもある.また,酢酸とインジゴカルミンを混合したAIM(acetic acid indigo carmine mixture)法(Fig.1)や,最後に水洗を追加する方法も報告されている2).
画像強調内視鏡(NBI)
著者: 谷泰弘 , 上堂文也
ページ範囲:P.608 - P.608
NBIの原理
NBI(narrow band imaging)は画像強調観察の狭帯域光法に分類され,光学フィルタによってヘモグロビンに吸収されやすい波長415nmの青と波長540nmの緑の狭帯域光を照射することで,粘膜表層の微小血管や微細表面構造を高いコントラストで視覚化できる内視鏡である.第一世代NBIは光量が少なく,胃の遠景観察時に画像が暗くなる問題があったが第二世代NBIは,露光時間と照射光量の増加により画像が明るく,胃の遠景観察が可能となっている.
画像強調内視鏡(BLI,LCI)
著者: 土肥統
ページ範囲:P.609 - P.609
胃癌の拾い上げ
1.BLI(blue laser imaging)-bright観察
BLI像では病変部において周囲粘膜と比べ高いコントラストが得られ,BLI-brightはややコントラストが低くなるものの,明るい状態で観察できる.前向きランダム化比較試験(randomized controlled trial ; RCT)では,白色光観察よりも非拡大BLI-bright観察において胃癌発見割合が有意に高い結果となり1),除菌後発見胃癌に多い平坦・陥凹型病変には非拡大BLI-bright観察が有用である(Fig.1).
拡大内視鏡の理論と基本手技
著者: 東佑香 , 平澤俊明
ページ範囲:P.610 - P.611
拡大内視鏡では,内視鏡像を80倍まで光学拡大観察し,狭帯域光(narrow band imaging ; NBI)観察を併用することで,表面微細構造および微小血管構築像を観察することができる.胃癌の正確な診断を下し,内視鏡像と病理組織像の一対一対応を行うためには,出血がなくブレのない内視鏡像を撮影する必要がある.本稿では,胃癌診断におけるNBI併用拡大観察の基本的な理論と手技について述べる.
拡大内視鏡(胃炎の診断)
著者: 八木一芳 , 寺井崇二
ページ範囲:P.612 - P.613
慢性胃炎はH. pylori(Helicobacter pylori)起因性が大部分であるため,本稿ではH. pylori起因性慢性胃炎のNBI拡大内視鏡所見について述べる.
拡大内視鏡(癌/非癌の診断)
著者: 土山寿志 , 八尾建史
ページ範囲:P.614 - P.615
拡大内視鏡とNBI(narrow band imaging)を併用することで癌特有の微小血管構築像および表面微細構造が鮮明に描出可能となり,胃病変の癌・非癌の鑑別診断に大きく貢献する.本稿では,NBI併用拡大内視鏡(magnifying endoscopy with NBI ; M-NBI)による胃病変の鑑別診断について解説する.なお,筆者ら1)が開発した胃M-NBIの診断能を向上させるE-learning systemを公開しており(https://www.medicaltown.net/mnbi/),効率よく,かつ正しい学習のために利用していただきたい.
拡大内視鏡(癌の組織型診断)
著者: 濱本英剛
ページ範囲:P.616 - P.618
早期胃癌の診断・治療において,組織型診断は内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)で治癒に至るかどうかを判断する上で重要である.本稿は胃癌の組織型診断について既報をまとめ概説する1)2).
拡大内視鏡(癌の指標)
著者: 吉田尚弘 , 土山寿志
ページ範囲:P.620 - P.621
NBI併用拡大内視鏡検査(M-NBI)による早期胃癌の診断方法は,2016年に日本消化器内視鏡学会,日本消化器病学会,日本胃癌学会の3学会が合同で提唱した,早期胃癌の拡大内視鏡診断アルゴリズム(magnifying endoscopy simple diagnostic algorithm for early gastric cancer ; MESDA-G)が標準的となっている.
MESDA-Gを用いることで早期胃癌の診断は容易になったものの,実臨床では非癌病変(腺腫,胃炎など)との鑑別に苦慮する病変に遭遇することも珍しくない.
超拡大内視鏡(ECS)
著者: 野田啓人 , 貝瀬満 , 岩切勝彦
ページ範囲:P.622 - P.623
本稿では超拡大内視鏡(endocytoscopy ; ECS)による早期胃癌診断について解説する.
EUS
著者: 赤星和也 , 大石善丈
ページ範囲:P.624 - P.625
EUSの特徴と適応
超音波内視鏡検査(endoscopic ultrasonography ; EUS)は消化管内腔,壁内,壁外の状態を超音波断層像により詳細に観察できる断層イメージング内視鏡検査である.その主な適応は悪性腫瘍の病期診断(壁深達度およびリンパ節転移)および粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)の鑑別診断(壁外および壁内局在層診断,ルーペ像レベルの内部性状診断,腫瘍径計測)である1).
EUS-FNA(SMT診断)
著者: 肱岡範 , 吉永繁高
ページ範囲:P.626 - P.627
本稿では,胃粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)診断に対する超音波内視鏡下穿刺吸引法(endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration ; EUS-FNA)の手技の方法とコツについて解説する.
治療
ESD先端系
著者: 室井航一 , 藤城光弘
ページ範囲:P.628 - P.629
内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)に使用する高周波ナイフの種類は多岐にわたる.中でも,瘢痕や線維化を伴う病変,血管が豊富な症例などの治療困難例では,直視下に剝離操作を行う先端系ナイフが有効である.本稿では,先端系ナイフの特徴や使用方法について述べていく.
ESD絶縁体系(ITknife,ITknife2)
著者: 田邉聡 , 和田拓也
ページ範囲:P.630 - P.631
早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)が開発されて20年近くになり,その手技も確立され広く普及してきている.絶縁体系の代表であるITknife(オリンパス社製)(Fig.1a)は細川ら1),Onoら2)により開発され,2002年に世界で初めてESDの専用処置具として市販化された.ITknifeの特徴は,針状ナイフの先端にセラミックの絶縁チップを付けることにより,穿孔を防止する構造になっている.先端の絶縁チップの部分を切開面に引っ掛け,針状のブレードで粘膜,あるいは粘膜下層の組織に通電して切開・剝離を行う.特に,ITknifeの改良型であるITknife2(オリンパス社製,Fig.1b)は絶縁チップの裏に放射状のショートブレードが装着されており,従来のITknifeと比較して切開能,止血能が向上した2).そのため,他の先端系の処置具と比較して,切開・剝離速度が速いのが利点である.本稿ではITknife2を用いた胃ESDの基本手技について解説する.
ESDはさみ系
著者: 草野央 , 後藤田卓志
ページ範囲:P.632 - P.633
内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)は早期消化管腫瘍に対する内視鏡的切除法として1990年代に登場した.ESDによって大きな病変や瘢痕病変でも一括切除が得られるようになった.一方で,いまだスコープ操作や止血の難しさは課題として残されている.本稿ではデバイス自体に複雑な動きや安全機能を持たせることで,ESD手技の難易度を下げ安全性を向上させたハサミ型ナイフを用いたESDを紹介する.
ESDトラクション法
著者: 吉田将雄 , 小野裕之
ページ範囲:P.634 - P.635
ESDトラクション法は食道の病変に対する方法として考案された手技であるが,胃の病変でも応用が可能である1)2).特に胃内の重力方向と噴門の位置関係から治療困難部位とされる胃体部の大彎病変では,ESDトラクション法を行わないときと比べて治療時間を短縮することが大規模臨床試験で示されている3).本稿では,胃ESDにおけるトラクション法の手技の解説とコツなどについて言及する.
Strip Biopsy
著者: 多田正弘
ページ範囲:P.636 - P.636
概要
病変の形態,大きさ,部位に関係なく,合併症が少なく,短時間に大きな組織切除を目的に開発されたjumbo biopsyがstrip biopsyである.周知のように粘膜下層の機械的剝離,さらに病変をスネアでつかみやすいように内視鏡下に局注を行うのがこの手技の基本である.
ERHSE(EMR-HSE)
著者: 石後岡正弘 , 森園竜太郎
ページ範囲:P.637 - P.637
1982年に平尾ら1)2)により開発されたERHSE(endoscopic resection with local injection of hypertonic saline epinephrine solution,HSE局注を併用した内視鏡的粘膜切除術)の手技の方法とコツを概説する.
EDSP
著者: 竹腰隆男
ページ範囲:P.638 - P.639
内視鏡的ポリペクトミーは,広基性病変では取り残しや術後合併症を考慮し禁忌とされてきた.一方,胃腺腫内癌やポリープ癌は従前の生検診断法では確定診断が困難であった.そこで筆者らは1975年,腺腫や0-IIa型を内視鏡的切除しうるEDSP(endoscopic double snare polypectomy)を考案した.本法切除第1例は術前診断では胃腺腫であったが,切除回収標本病理診断が胃腺腫内癌であったことから意を強くして,腺腫・0-IIa型の切除例を重ねた.本法は全病巣の一括切除・回収,かつ回収切除標本の病理組織学的検索による深達度や断端・脈管の癌浸潤診断も可能である.本法での治療の結果,患者の生活の質(quality of life ; QOL)の維持が可能なことが確認されたので,外科手術に代わる治療法として1980年の第35回胃癌研究会1),1981年の第32回内視鏡関東地方会2)で報告した.
SMTの内視鏡的切除
著者: 七條智聖 , 上堂文也
ページ範囲:P.640 - P.641
胃粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)のうち,有症状のもの,病理組織学的にGIST(gastrointestinal stromal tumor)と診断されたもの,または5cmを超えるものは手術適応である1).無症状のものでも2cm以上で内視鏡や超音波内視鏡検査(endoscopic ultrasonography ; EUS),CTで悪性所見(潰瘍形成,辺縁不整,増大,壊死・出血,辺縁不整,実質不均一)を認めるものは手術適応となる.また,2cm未満でも増大傾向または悪性所見のあるもの,2〜5cmであれば悪性所見がなくても相対的手術適応となる.
現在,切除可能なGISTの治療の第一選択は外科手術であり,偽被膜を損傷することなく安全なマージンを確保し,肉眼的に切除断端陰性で切除することが求められる.GISTの外科治療において,腹腔鏡下手術は開腹手術と同等ないしはそれ以上に優れた短期成績が報告されている2).ただし,特に内腔発育型の腫瘍では胃壁の切除範囲が必要以上に大きくなり,噴門・幽門近傍の病変では解剖学的に腫瘍のみの切除が困難なため,近位側または幽門側胃切除が必要となるなどの問題点があった.
ポリペクトミー
著者: 中川昌浩 , 宮原孝治
ページ範囲:P.642 - P.642
ポリペクトミーは粘膜下に局注を行わず,金属線製の輪(スネア)に通電して,主に有茎性もしくは亜有茎性の隆起性病変を切除する治療手技である.対象となる病変のほとんどは良性であり,胃では過形成性ポリープが最も多い.胃過形成性ポリープの癌化の頻度は平均2.2(0〜9.7)%で,癌化例は15mm以上の大型ポリープで,頭部に分化型粘膜内癌が多いと報告されており1),15mm以上の過形成性ポリープはポリペクトミーの適応と考える.
術前診断では茎部を有するか否かの確認が重要であり,亜有茎性の場合にはより確実な一括完全切除のため,ポリペクトミーではなく内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection ; EMR)が選択されることもある.さらに,使用するスネアの種類・大きさの選択や出血予防処置の必要性,切除標本の回収方法などを想定しておくことが大切である.
PDT
著者: 小野裕之
ページ範囲:P.643 - P.643
胃癌に対する光線力学的治療(photodynamic therapy ; PDT)は,腫瘍特異的親和性を有するポルフィマーナトリウム(フォトフリン®)を,治療の48〜72時間前に患者に注射にて投与した後,エキシマダイレーザーを用いて波長630nmの赤色光を病変に照射し,一重項酸素(活性酸素の一種)を発生させ,腫瘍を変性壊死させる治療法である.
LECS
著者: 恩田毅 , 後藤修
ページ範囲:P.644 - P.645
腹腔鏡内視鏡合同手術(laparoscopic and endoscopic cooperative surgery ; LECS)は,本邦において考案された腹腔鏡と内視鏡を用いた局所切除手術法である.
LECSは2008年にHikiら1)により報告された.その手法の概要は,胃粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)に対し内視鏡的に全周性に粘膜切開を行った後,漿膜筋層を意図的に穿孔させて全周を内視鏡的もしくは腹腔鏡的に切除して病変を経腹壁的に回収するというものである.当初提唱されたこの手法は,現在ではclassical LECSと呼称されている.
超音波内視鏡下コイル塞栓療法
著者: 永島一憲 , 入澤篤志
ページ範囲:P.648 - P.648
近年,孤立性胃静脈瘤(isolated gastric varices ; iGV)に対して,超音波内視鏡ガイド下静脈瘤内コイル留置術(endoscopic ultrasonography-guided coil deployment ; EUS-CoD)が行われるようになった.2010年にスペインのRomeroら1)が4人のGV患者に対して施行したEUS-CoDを報告し,その後徐々に本法の研究が進んできた.さらに,コイル留置後に組織接着薬であるCA(cyanoacrylate)系薬剤や硬化剤(ethanolamine oleate ; EO)などを注入するEUS-CDS(EUS-guided coil deployment with sclerotherapy)を施行することで良好な治療成績が示されている2)3).EUS-CDSは,静脈瘤径の120〜150%径を使用してコイルが大循環に流出する可能性が低いこと,1回の穿刺でコイル留置からEOの注入まで連続して施行できることなどから,iGVに対する安全かつ効果的な内視鏡的治療法と考えられている.本稿では,EUS-CDSにおける手技の方法と,そのコツについて解説する.
止血術
著者: 皆川武慶 , 住吉徹哉 , 近藤仁
ページ範囲:P.650 - P.651
出血性胃潰瘍などの上部消化管出血は臨床の現場で遭遇する機会が多く,迅速かつ確実に処置が行われなければ出血性ショックなどの重篤な病態になりうるため,さまざまな止血法を習得しておく必要がある.本稿では本邦で一般的に行われている,①止血鉗子による凝固止血術,②クリップ止血術,③局注止血術について解説する.
焼灼術:GAVEに対するAPC焼灼治療
著者: 田邉聡 , 石戸謙次
ページ範囲:P.652 - P.652
胃前庭部毛細血管拡張症(gastric antral vascular ectasia ; GAVE)は胃前庭部を中心に血管拡張を認める病態を示し,慢性貧血,消化管出血の原因として認識されている1).GAVEは胃前庭部を中心に血管拡張が放射状に縦走するため,watermelon stomachとも呼ばれている2)(Fig.1a).一方,胃前庭部を主体にびまん性に毛細血管が拡張する病態は,びまん性胃前庭部毛細血管拡張症(diffuse antral vascular ectasia ; DAVE)として報告されている3)(Fig.2).GAVE,DAVEとも毛細血管からの出血が原因で起こる貧血を呈する消化管の出血性疾患である.両者の内視鏡所見は異なるが,病理学的には同じ範疇の疾患と考えられる.
両者とも焼灼術を中心とした内視鏡治療が有用であり,安全性,有効性の点から,アルゴンプラズマ(argon plasma coagulation ; APC)による焼灼治療が推奨される.本稿ではAPCによる焼灼治療の実際について解説する.
胃石の溶解・破砕
著者: 花畑憲洋 , 吉村徹郎
ページ範囲:P.653 - P.653
胃石の分類
胃石には主に植物性胃石と毛髪胃石があり,大半は植物性胃石で胃内容物の滞留とタンニンを多く含む食品の大量摂取により生じる.毛髪胃石は小児や精神疾患患者に多く,抜毛癖,異食症により毛髪を大量に摂取し,胃内で毛髪が複雑に絡み合い一塊となったものである.植物性胃石は溶解療法が期待できるが,毛髪胃石は一般的に溶解療法,破砕療法が困難であり手術的に除去することが多い.
異物除去
著者: 吉村大輔
ページ範囲:P.654 - P.654
胃の異物除去を要する病態
2012年4月〜2020年3月までの間に,自身で経験した上部消化管異物除去治療175例の詳細を示す(Table 1).異物の多くは管腔が狭く,生理狭窄部を有する食道に滞留する.胃に到達しえた異物は一般には摘除の必要はないが,①物理的嵌頓のリスクがある,②鋭利で物理的な消化管損傷のリスクがある,③電気化学的な消化管損傷のリスクがある(電池),④有症状のアニサキス症(アナフィラキシーを含む),⑤その他(義歯など心証を踏まえた社会的適応など),の際に治療を要する.しばしば夜間,時間外の緊急手技となるが,内視鏡医には患者本人や小児においては保護者の心理的動揺に配慮しながら真に治療を要する病態か状況判断し,安心を与える所作が求められる.
PEG(Pull法)
著者: 日下部俊朗 , 長岡康裕
ページ範囲:P.655 - P.655
Pull法の特徴
経皮内視鏡的胃瘻造設術(percutaneous endoscopic gastrostomy ; PEG)の一つであるPull法は1979年にPonskyら1)により考案された方法で(報告は1980年),Introducer原法と比較して穿刺針が細く,一期的に太いカテーテルを留置でき,カテーテル逸脱の危険も少なく,手技として安定した方法である.欠点として,造設時に咽頭などの細菌がカテーテルに付着するため,瘻孔感染の頻度が高い.これを克服するため,オーバーチューブを装着したキットも発売されている.また,一期的にボタン型の胃瘻を造設できるキットもある.
PEG(Introducer法)
著者: 倉敏郎 , 日下部俊朗
ページ範囲:P.656 - P.656
PEG造設手技の分類
PEG(percutaneous endoscopic gastrostomy)造設手技は胃瘻カテーテルが口腔内を経由して留置されるか否かでPull/Push法(経由する)とIntroducer法(経由しない)に分類される.Introducer法はさらにIntroducer原法(内部ストッパーがバルーン型)とIntroducer変法(内部ストッパーがバンパー型)に分類される1).本稿では誌面の都合により主に本邦で多く用いられているIntroducer変法(イディアルPEGキット)について解説する.
PTEG
著者: 大石英人
ページ範囲:P.657 - P.657
経皮経食道胃管挿入術(PTEG,ピーテグ)は経皮内視鏡的胃瘻造設術(percutaneous endoscopic gastrostomy ; PEG)の実施が不能もしくは困難な症例に対し考案・開発された代替法である.同術式は,非破裂型穿刺用バルーン(rupture-free balloon ; RFB)を用いた超音波下穿刺による頸部食道瘻造設術と,造設された頸部食道瘻からのX線透視下のチューブ挿入留置術を組み合わせた,簡便かつ安全で低侵襲な消化管のIVR(interventional radiology)手技である.
経鼻的にRFBを頸部食道内へ挿入し拡張させ食道内腔を確保後,体表より超音波プローブでRFBを圧迫することにより,頸部食道の前方に位置する臓器を左右に移動させ穿刺可能な経路を確保し,超音波下に頸部食道内のRFBを外筒付き穿刺針で穿刺する(Fig.1).次に,穿刺針外筒を介してガイドワイヤーをRFB内へ挿入留置し,X線透視下にガイドワイヤーの先端を食道内腔にリリース後,シース付きのダイレーターをガイドワイヤーに通し刺入部を拡張しシースを留置する.シースを介して留置チューブを食道内へ挿入し,X線透視下にチューブ先端を目的とする臓器まで誘導し留置する(Fig.2).
ステント留置(悪性狭窄の治療)
著者: 中堀昌人 , 奥薗徹
ページ範囲:P.658 - P.659
悪性腫瘍による胃・十二指腸閉塞の治療として,低侵襲で早期に経口摂取可能となる胃・十二指腸ステント留置術が普及してきている.本稿では適応,ステントの選択,手技のポイントについて概説する.
G-POEM
著者: 井上晴洋
ページ範囲:P.660 - P.660
胃における経口内視鏡的括約筋切開術(gastric per-oral endoscopic myotomy ; G-POEM)は,胃弛緩症(gastroparesis)に対する内視鏡治療である.胃の排泄遅延を伴う症例で,胃蠕動運動亢進の薬剤治療抵抗性のものが適応となる.一次性(idiopathic),二次性があり,糖尿病に関連して起こる二次性のものが多いとされる1).本邦では症例は比較的少ないのに対し,米国では多数の患者を認める.gastroparesisの診断には胃の排泄遅延の確認が必要である.バリウム透視,胃内圧検査やシンチなど種々の検査法があるが,最も簡便な診断法は,幽門輪を20mmバルーンで拡張してみて,胃膨満感などの症状が改善するかをみる方法である.一時的な改善をみたら,幽門括約筋の切開の効果が期待できると推定される.
G-POEMは,食道アカラシアに行われるPOEM(経口内視鏡的筋層切開術)を胃幽門括約筋に対して行う術式である.幽門輪から5cm手前の幽門部大彎で粘膜下局注の後2cmの粘膜切開をおく.粘膜下層に入り,固有筋層の表面に沿って粘膜下層トンネルを作製する.粘膜下トンネル内で幽門輪に到達すると,小円弧状の筋層の表面が観察される.幽門輪の2cm手前から筋層切開を開始する(Fig.1).内輪状筋切開を行う.切開された幽門括約筋は約1cm径の輪状の切離面として認識される.一方,十二指腸球部側の筋層は急に薄くなることから容易に鑑別できる.十二指腸球部側の筋層を切開する必要はない.治療後,幽門輪が弛緩し,スコープの通過が容易であることを確認する.粘膜切開部は,クリップで閉鎖する.
十二指腸 診断
十二指腸の解剖
著者: 鈴木悠悟 , 布袋屋修
ページ範囲:P.661 - P.661
十二指腸の臨床的解剖と内視鏡診療
十二指腸は胃の幽門輪から膵頭部を囲むようにCの字を描いて走行し,空腸に至るまでの長さ25cmほどの比較的短い管腔臓器である(Fig.1).球部,下行部,水平部,上行部に分けられ,内視鏡観察時に病変の位置関係の指標となるのは上十二指腸角,主乳頭,下十二指腸角である.
低緊張性十二指腸造影
著者: 森山智彦 , 鳥巣剛弘
ページ範囲:P.662 - P.663
十二指腸造影は病変の質的診断,隣接臓器との関係などを評価するために施行する.十二指腸は蠕動著明かつ皺襞が錯綜している臓器のため,情報量の多い画像を撮影するためには鎮痙薬を用いて低緊張状態にし,スムーズかつ手早く検査を行う必要がある1)〜3).本稿では低緊張性十二指腸造影の撮影法と読影手順について述べる.
通常内視鏡:癌/腺腫の診断
著者: 廣瀬崇 , 角嶋直美
ページ範囲:P.666 - P.667
本稿では表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍(superficial nonampullary duodenal epithelial tumor ; SNADET)に対する癌/腺腫の診断について,白色光観察を中心に既報や知見をもとに述べる.
画像強調内視鏡
著者: 遠藤昌樹 , 菅井有 , 松本主之
ページ範囲:P.668 - P.669
本稿では十二指腸疾患における拾い上げ,および精密検査に用いる画像強調内視鏡(image enhanced endoscopy ; IEE)について,主に上皮性腫瘍に関して解説する.
治療
ESD
著者: 矢作直久 , 佐々木基
ページ範囲:P.670 - P.671
表在型非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍(superficial non-ampullary duodenal epithelial tumor ; SNADET)に対する内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)は,他臓器のものとは難易度もリスクも全く異なるため,食道や大腸の手技に慣れているというだけで気軽にトライすべきものではない.十二指腸の場合,偶発症に対して適切な対応ができなければ致死的な状況に進展しかねないため,十分な知識と技量を備えた術者が,万全なリスクマネージメント体制のもとで行うべきである.
ESDの偶発症予防策
著者: 辻陽介 , 小池和彦
ページ範囲:P.672 - P.674
内視鏡治療の最難関とも言われる十二指腸ESD(endoscopic submucosal dissection)は,治療後の偶発症が多いことも大きな問題である.剝離後の潰瘍面が胆汁・膵液に曝露されることにより後出血・遅発性穿孔が高率に生じるとされており,これらの予防法を積極的に行う必要がある.最近はさまざまな偶発症予防策が発達してきており,限られた施設において十二指腸ESDを慎重に行い始めている状況である.本稿では十二指腸ESD後の偶発症予防策について概説する.
内視鏡的縫縮
著者: 村元喬 , 森宏仁 , 大圃研
ページ範囲:P.676 - P.677
潰瘍底縫縮の意義
表在性非乳頭部十二指腸腫瘍(superficial nonampullary duodenal epithelial tumor ; SNADET)に対する内視鏡治療では,スコープの操作性や筋層が薄いといった解剖学的な特徴から,他の臓器に対する内視鏡治療に比べて術中に生じる偶発症の頻度が高いことはもちろんのこと,切除後の潰瘍底に直接胆汁・膵液が曝露することで引き起こされる遅発性穿孔や後出血が最大の問題である1).しかしながら,術後の潰瘍底を完全に縫縮することで,遅発性の偶発症が減少することもわかっている2)3).このため,術後の潰瘍底の縫縮が必須であり,いかにして確実に潰瘍底を縫縮するかが重要である.
EMR
著者: 平澤欣吾 , 前田愼
ページ範囲:P.678 - P.678
内視鏡治療の金字塔であるESD(endoscopic submucosal dissection)の勢力圏が広がる中,現時点では,特異的な偶発症リスクから,十二指腸において簡単にESDが選択されることは,決して一般的ではない1).十二指腸ではEMR(endoscopic mucosal resection)をいかにうまく使いこなすかはいまだ重要なポイントなのである(Fig.1).
まず,上部スコープでは鉗子孔が7時前後にあるため,病変を可能な限り6時方向に位置させることは,手技全般を容易で確実にする(Fig.1a).後述するが,スコープの選択はwater jet機能と拡大観察機能がついているほうがよりよい.
UEMR
著者: 前畑忠輝 , 矢作直久
ページ範囲:P.679 - P.679
表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍(superficial non-ampullary duodenal epithelial tumor ; SNADET)に対して有効性が示唆されている1).UEMR(underwater EMR)について解説する.
Coldスネアポリペクトミー
著者: 滝沢耕平
ページ範囲:P.680 - P.680
適応
筆者は,十二指腸の10mm以下の腺腫と考えられる病変にはD-CSP(duodenal cold snare polypectomy)1)を,10mmを超える腺腫や癌を疑う病変に対してはunderwater EMRを選択することが多い.局注を用いないため,生検瘢痕を有する場合も適応外とはしていない.
LECS
著者: 吉水祥一 , 布部創也
ページ範囲:P.681 - P.681
十二指腸腫瘍に対するLECSの応用
十二指腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)は,十二指腸壁の薄さや狭い管腔内での操作を要するという問題があるため,高難度の手技である.十二指腸ESDは術中穿孔だけでなく,治療後に潰瘍底が膵液・胆汁に曝されることで起こる遅発性穿孔の発生も大きな問題であり,近年では一部の専門病院のみでの施行に限られている.一方,Hikiら1)は腹腔鏡・内視鏡合同手術(laparoscopic and endoscopic cooperative surgery ; LECS)を考案し,胃粘膜下腫瘍に対して必要最小限の切除範囲で腫瘍の完全切除が得られる術式であることを報告してきた.この術式を応用することで,十二指腸腫瘍の局所切除を必要最小限の切除範囲で済ませることができ,腹腔鏡側からの縫合により切除部を補強することで遅発性穿孔を回避しうる利点がある2).D-LECS(LECS for duodenal tumors)は,2020年度の診療報酬改定により,“腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)”として保険収載された.
小腸 診断
小腸の解剖
著者: 松田圭二 , 橋口陽二郎
ページ範囲:P.682 - P.682
小腸
小腸は本来,胃幽門輪の肛門側から始まり,回盲弁(Bauhin弁)に終わる6〜7mの中空性器官である1)2).①十二指腸,②空腸,③回腸,の3つの部門に区分される.十二指腸の解剖は別項にて述べられるため,本稿では空腸と回腸の解剖について記述する.
十二指腸は後腹壁に埋まっているが,これが腸間膜をもって腹腔内に表れるところで空腸が始まる3)(Fig.1).空腸,回腸は遊離腸間膜を有しており,可動性に富んでおり,口側40%を空腸,肛門側60%を回腸としている1).腹腔内での位置はさまざまであるが,概ね空腸は左上方,回腸は右下方に位置する2).空腸と回腸ともに上腸間膜動脈によって血液が供給されているため,上腸間膜動脈の根部が閉塞すると空腸から回腸の広い範囲で壊死に陥る.
小腸造影(充満法)
著者: 江﨑幹宏
ページ範囲:P.684 - P.685
小腸X線造影検査は,X線被曝や手技上の問題から実施される機会は減少しているが,X線検査による小腸病変の性状評価が病態把握や治療法の選択に有用と考えられるすべての疾患において適応となる.小腸X線造影検査は,撮影法の違いにより小腸自体あるいは隣接臓器に由来する小腸索の変形や病変分布の把握に主眼を置いた充満法と,送気により粘膜の微細模様を広範に描出し小病変の性状評価も可能にする二重造影法に分類される.本稿では,簡便な検査法である充満法について解説する.
カプセル内視鏡
著者: 中村哲也 , 田中孝尚 , 入澤篤志
ページ範囲:P.688 - P.689
カプセル内視鏡(capsule endoscopy ; CE)の普及と機器の発展,保険適用拡大などにより,小腸腫瘍の早期診断が当たり前になりつつある.そこで本稿では,小腸カプセル内視鏡の適応,検査方法,偶発症に加え,主な小腸腫瘍のCE画像を紹介する.
ダブルバルーン内視鏡(DBE)
著者: 矢野智則 , 山本博徳
ページ範囲:P.690 - P.691
原理と操作手順
小腸は胃と大腸の間をなす細長い臓器で,十二指腸,空腸,回腸の3つの部位から成っている.このうち空腸・回腸は腹腔内でほとんど固定されていないため,通常の内視鏡では手元の操作が手前の屈曲した腸管の伸縮に費やされてしまい,スコープ先端に伝わらない.ダブルバルーン小腸内視鏡(double-balloon enteroscopy ; DBE)では,バルーン付きオーバーチューブで手前の腸管が曲がっていても伸びないように把持できるため,手元の操作がスコープ先端まで伝わり,深部小腸でも操作性が維持される.
実際の操作手順としては,可能な限りスコープを進めたところでスコープ先端のバルーンを拡張して腸管を把持し,オーバーチューブ先端バルーンを虚脱させてオーバーチューブを進める.オーバーチューブを進めたら両方のバルーンを拡張した状態で全体を引き戻すことで,オーバーチューブ上に腸管を畳み込んで短縮し,形状を単純化できる.この一連の操作を繰り返して挿入していく.
シングルバルーン内視鏡(SBE)
著者: 辻川知之
ページ範囲:P.692 - P.693
SBEの特徴
オリンパス社製のシングルバルーン内視鏡(single balloon endoscopy ; SBE)は名称の通り,スライディングチューブ(以下,ST)先端にバルーンを有するが,スコープ先端にはバルーンを装着しない.したがって,STを挿入する際にスコープ先端が抜けない工夫として,先端を強く屈曲(傘の柄のようなステッキ状)させている.
Spiral内視鏡
著者: 大塚和朗
ページ範囲:P.694 - P.695
内視鏡の深部小腸への挿入は,通常内視鏡では困難である.Akermanら1)により,2008年に発表されたスパイラル内視鏡(spiral enteroscopy ; SE)は,内視鏡本体にらせん状のフィンのある外筒を装着し,これを助手が回転させて腸管を手繰り寄せることにより,深部挿入を可能とする.単純な操作で,高い挿入性と安定性を持っている.
MR Enterography
著者: 竹中健人 , 北詰良雄
ページ範囲:P.698 - P.699
MREの実際
近年,機器の進化により撮影時間が短くなり,蠕動を伴う小腸でも評価可能なMRE(MR enterography)が開発された.MREは下部消化管内視鏡では評価できない回腸・空腸を評価できるだけでなく,腸管壁や腸管外の情報も得ることができ,瘻孔や膿瘍などの合併症を生じるCrohn病を診療する際に,非常に有用となる.また,MREによる予後予測の指標も報告されており,臨床的寛解であるCrohn病においてMREによりその後の再燃,入院,手術が予測可能となった1).
小腸は通常,内腔は虚脱している.検査精度を高めるために,等張液で適度に腸管を拡張させた後に,MRI(magnetic resonance imaging)を行う必要がある.MRI機器は1.5T以上のスキャナーであれば十分に評価可能である.撮影シークエンスも一般的なものであり,新規の機材やソフトウエアは必要なく,検査の導入は物理的には容易である.一方,前処置が必要であるため,処置を行う場所の確保と,検査手順の理解を含めた放射線科・コメディカルの協力が必要である.
EUS
著者: 中村正直 , 藤城光弘
ページ範囲:P.700 - P.701
小腸用超音波内視鏡検査(endoscopic ultrasonography ; EUS)専用機は存在しないため,バルーン内視鏡の鉗子口を利用したミニプローブによる管腔内超音波内視鏡(SP702,富士フイルム社製)検査を行い,腫瘍の鑑別とその深達度について評価する1)2).鉗子口径は2.8mm以上確保されているが,小腸深部では走査困難な場合があり,できる限りスコープのねじれや屈曲を認めない状態での施行が望まれる.プローブの周波数は,①12MHz,②15MHz,③20MHz,の3種を状況に応じて選択する.
炎症と腫瘍の鑑別が有用な状況もあるが,多くは腫瘍の質的診断に寄与するモダリティと考える.
治療
止血術(クリップ,APC)
著者: 松田知己 , 伊藤聡司
ページ範囲:P.702 - P.702
スコープの鉗子口径が2.8mm以上あればクリッピングが可能である.腸管の屈曲が強く,治療に難渋する場合はスコープの特性を大いに利用すべきである.通常内視鏡では空気量の調節,体位変換,用手圧迫を利用するが,バルーン内視鏡に関しては,それ以外にオーバーチューブを再挿入して短縮し直す,あるいはオーバーチューブをやや抜いて,スコープを押し込むなど,スコープとオーバーチューブとの相対的位置関係を変化させることによって手技の難易度を軽減することもできる1).また,フードの装着は必須で,かつ少し長めに出しているほうがひだを押さえ込んで視野を確保できる.
止血術(薬剤局注)
著者: 岡志郎 , 田中信治
ページ範囲:P.703 - P.703
ポリドカノールは,食道静脈瘤の内視鏡治療に使用する硬化剤であるが,静脈瘤以外の消化管出血の止血にも有用である.本稿では小腸血管性病変に対するポリドカノール局注法(polidocanol injection ; PDI)の適応と手技について解説する.
止血術(IVR)
著者: 新槇剛
ページ範囲:P.704 - P.704
小腸出血の原因には,動脈性出血と静脈性出血があり,また特殊な場合として腫瘍からの出血がある.動脈性小腸出血に対するIVR(interventional radiology)による止血術の考え方には,①塞栓術による止血,②血管収縮薬による止血,の2通りがある.また,静脈性小腸出血に対するIVRによる止血には塞栓術による直接的な止血の他,静脈圧を低下させて止血を図る方法がある.
腸重積解除
著者: 矢野智則
ページ範囲:P.705 - P.705
腸重積
腸重積(invagination, intussusception)とは,腸管の一部が先進部となり,これに続く腸管内腔へ嵌入することによって起こる.部位により小腸・小腸型,結腸・結腸型,回腸・結腸型がある.
結腸・結腸型や回腸・結腸型の腸重積では,希釈した造影剤を肛門から注入する高圧浣腸を使った腸重積解除術が試みられる.小腸・小腸重積では,従来は外科的治療が選択されてきたが,ダブルバルーン内視鏡を用いた腸重積解除術も選択肢となる.
EMR,ポリペクトミー
著者: 髙梨訓博 , 勝木伸一
ページ範囲:P.706 - P.706
内視鏡の挿入
内視鏡処置全般に共通することであるが,すべての処置は病変を最も処置に適した部位に配置することから始まる.処置を見据えた小腸内視鏡検査にはballoon assisted enteroscopyが用いられるが,通常の上部・下部内視鏡に比べると,内視鏡挿入自体の難易度が高いことも多く,また術後腸管ではその難易度もさらに高度となる.詳細は小腸内視鏡挿入に関する報告1)を参照いただくこととするが,病変への到達,さらに処置に適した位置取りが第一の難関となる.
内視鏡的バルーン拡張術(EBD)
著者: 平井郁仁
ページ範囲:P.707 - P.707
本稿では,主にCrohn病(Crohn's disease ; CD)の小腸狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術(endoscopic balloon dilation ; EBD)について解説する.
RIC
著者: 諸井林太郎 , 志賀永嗣
ページ範囲:P.708 - P.708
本稿では,特に通常の大腸用内視鏡が到達できる範囲の小腸狭窄に対するRIC(radial incision and cutting)1)について解説する.大腸や小腸—大腸吻合部狭窄に対するRICについては筆者ら2)3)の過去の報告を参照されたい.
RICに際し,内視鏡はPCF-H290TI(Olympus社製),電気メスはITknife nano(Olympus社製)を使用している.高周波装置および設定は大腸内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)に準じている(当科ではERBE社のVIO300DをEndo Cut I,Effect 2〜3,Cut duration 2,Cut interval 2,Swift凝固50Wに設定している).RIC適応病変としては狭窄長2cm以下(理想はいわゆる膜様狭窄)で,屈曲部ではなく比較的直線の部位にある狭窄である.
大腸 診断
大腸の解剖
著者: 松田圭二 , 橋口陽二郎
ページ範囲:P.710 - P.711
大腸
大腸は回腸遠位端から肛門までの腸管で,成人では約1.5mの長さであり,腸の内容物から液体と塩類を吸収し,糞便を形成する1).右下腹部で虫垂を伴った盲腸で始まり,上方へ向かって右結腸曲(肝彎曲)を形成し,横行結腸を経て左季肋部に至り,脾臓直下で大腸は下方へ屈曲して左結腸曲(脾彎曲)を形成し,下行結腸となって左下腹部へ進み,S状結腸となって骨盤腔の上部へ入り,直腸として骨盤腔の後壁に沿って下行して肛門管に至る.特徴としては,小腸より内径が大きい,腹膜垂,大腸壁の縦走筋が集まって縦に走る結腸ヒモ,結腸の膨らみ(haustra),などが挙げられる.
注腸造影(総論)
著者: 小林広幸
ページ範囲:P.712 - P.713
本稿では大腸疾患のスクリーニングとして用いられる注腸X線造影検査(ルーチン検査)の手技とそのコツ,留意点について解説する.質の高い注腸X線造影検査には,術者の技量はもとより,前処置と造影剤・撮影の工夫,そして読影能力を向上(ブラッシュアップ)していくことが必要である.
注腸造影(腫瘍の診断)
著者: 大内彬弘 , 鶴田修
ページ範囲:P.714 - P.714
近年,内視鏡機器の進歩により,内視鏡検査が大腸腫瘍診断の中心となってきている.検査頻度は低下しているものの,注腸X線造影検査は病変の正確な大きさ,部位,全体像や側面像をより客観的に把握することが可能であり,内視鏡検査にはない利点を有している.早期大腸癌に対する壁深達度診断,すなわち粘膜下層深部浸潤か否かを判別することにおいては,内視鏡検査と同様に非常に有用な検査である.
大腸癌の壁深達度診断に必要なX線造影所見としては,腫瘍正面像(表面性状,大きさ),側面像(側面変形,硬化像),腫瘍周囲の所見(ひだの集中像)などが挙げられる1)(Fig.1).側面変形に関しては,その有無と程度について,①無変形,②角状変形,③弧状変形,④台形状変形の4パターンに分類され,無変形では癌は粘膜層にとどまっているか,粘膜下層にごく少量浸潤したもの,角状変形は粘膜下層への中等量の浸潤,弧状変形は粘膜下層に高度に浸潤しているか,または固有筋層に少量浸潤しているもの,そして台形状変形は固有筋層またはそれ以深に浸潤した進行癌の所見とされている2).また,粘膜下層以深浸潤癌に特異的に出現する所見として,伸展不良所見(画然とした硬化像,腫瘍周囲の透亮像,ひだの集中像)が重要である3)とも言われている.
注腸造影(炎症性疾患の診断)
著者: 池上幸治 , 蔵原晃一
ページ範囲:P.715 - P.715
炎症性疾患の診断における注腸造影の有用性
大腸における炎症性疾患の診断は内視鏡検査単独で完遂されることが多いが,狭窄合併例(Fig.1,2)や瘻孔形成例に対する内視鏡的アプローチには限界があり,これらの病変の全体像の把握や鑑別診断には注腸造影の併用が有用となる1)2).また,注腸造影は,炎症性病変の部位や分布,管腔の変形や狭窄,結腸紐や周囲臓器との関連などを大腸全域にわたって客観的に評価でき,病変部位を対応させて経時的変化を評価できるなど,内視鏡検査とは異なる特性を有し,相補的な関係にある1)〜3).
大腸内視鏡の前処置・挿入法
著者: 加藤文一朗 , 松下弘雄
ページ範囲:P.716 - P.717
大腸病変の検索方法として,内視鏡検査はゴールドスタンダードとされている.ただし,質の高い検査を行うためには,良好な前処置を行い,苦痛がなく,確実な大腸内視鏡挿入法が必須である.本稿では筆者らが施行している前処置,挿入法の実際を述べる.
通常内視鏡(炎症)
著者: 清水誠治
ページ範囲:P.720 - P.721
内視鏡の適応と前処置
腸の炎症性疾患は極めて多彩であり,症候や病歴のみで鑑別することは困難である1).診断にはさまざまな検査を組み合わせる必要があり,内視鏡検査は血便や下痢がみられる場合に実施されることが多い.特に特発性炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease ; IBD)の診断においては,内視鏡検査が必須である.便潜血陽性精査の内視鏡観察で病変が発見されることもある.
検査に際して腸管洗浄液による前処置を行うことが望ましいが,必ずしも全大腸を観察する必要はなく,前処置は排便状況,全身状態,緊急性,必要な観察範囲などを考慮して判断する.下痢が高度な場合や直腸に病変が存在する場合には前処置なしでも観察可能である.アメーバ性大腸炎では腸管洗浄液により付着している壊死物質が脱落し,診断が困難になる場合がある.病変部位や範囲を把握する目的では超音波やCTも有用である.腸管穿孔では内視鏡が禁忌であるが,中毒性巨大結腸症には前処置なしで最小限の送気にとどめれば下部大腸の観察が可能である.
色素拡大内視鏡(腫瘍)
著者: 平田大善 , 佐野寧
ページ範囲:P.722 - P.723
大腸内視鏡観察において腺管開口部はpitと呼ばれ,その形状には病変の構造異型が反映される.色素拡大内視鏡観察では,このpitの形状を詳細に観察し,pit pattern分類(Fig.1)に準じて診断を行うことが基本である.
拡大内視鏡(炎症)
著者: 松本主之
ページ範囲:P.724 - P.725
歴史
1970年代に一部の施設で拡大大腸ファイバースコープの試作機が用いられ,炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease ; IBD)の直腸病変を対象とした拡大内視鏡所見が報告された.ただし,画像解像度の問題があり,臨床応用されることはなかった.その後,大腸上皮性腫瘍の拡大観察の普及とともに,IBDの拡大内視鏡所見が改めて注目された.特に1990年代前半から中盤にはCrohn病の微小病変の拡大内視鏡所見と臨床的意義が検討された.一方,1990年代中盤以後,現在に至るまで潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis ; UC)の拡大内視鏡所見が注目され,解像度の高い内視鏡の開発に伴い,拡大所見と組織学的重症度,および臨床経過との関係が検討されてきた.
IBDの拡大観察では光学拡大鏡が用いられるが,画像強調観察法は色素法や光デジタル法など多彩である.さらに,近年ではEC(endocytoscopy)を用いた観察も可能となった.拡大観察の主な目的は組織学的重症度の推定,およびUC関連腫瘍の診断であり,今後は後者がより重要な課題となると思われる.
画像強調拡大内視鏡(NBI,BLI)(腫瘍)
著者: 田中秀典 , 田中信治
ページ範囲:P.726 - P.727
NBI(narrow band imaging)やBLI(blue laser imaging)を用いた画像強調拡大内視鏡観察では,vessel patternあるいはsurface patternを評価することで大腸腫瘍の質的診断が可能である.
vessel patternに関しては,正常粘膜や過形成性病変では微小血管は細く疎なため視認困難であるが,大腸腫瘍では血管新生の亢進,血管径の増大,血管密度の増加により茶褐色に観察され,さらに間質反応がその形状を修飾する.通常,腺腫ではvessel patternは整な網目状に観察されるが,癌では癌細胞の浸潤増殖,炎症細胞浸潤や間質反応に伴い生じる血管径の不均一性や血管走行の不整,分布の乱れが観察され,深部浸潤癌では無血管野,血管の断片化が観察される.
画像強調拡大内視鏡(LCI)(腫瘍)
著者: 吉田直久 , 井上健 , 土肥統
ページ範囲:P.728 - P.729
LCIの原理
LCI(linked color imaging)はレーザー内視鏡(LASEREO,富士フイルム社製)の410nmおよび450nmの2つの短波長のレーザー光と,それにより励起された蛍光体により病変の血管や表面構造を強調できる観察法である1).BLI(blue laser image)-brightと同じレーザー出力バランスを用いてプロセッサー内で病変部と正常部の赤色と白色を強調することで色差を増し,より明るい視野で病変の視認性を向上させる.
一方で,2020年から本邦でも使用可能となったLED(light-emitting diode)内視鏡(ELUXEO,富士フイルム社製)においては,4つのLED光として,①violet,②blue-violet,③green,④redを用いており,独自の光のバランスと出力を適切に調整するmulti-light technologyによってLCIモードが可能となる1).
Endocytoscopy
著者: 森悠一 , 工藤進英
ページ範囲:P.730 - P.731
Endocyto(超拡大内視鏡)の特徴
超拡大内視鏡(endocytoscopy ; EC)のEndocyto(CF-H290ECI,オリンパス社製)は,超高精度のoptical biopsyの実現を視野に,2018年2月に上市された次世代内視鏡であり,520倍の接触拡大観察により病変の生きた細胞を直接観察できる軟性内視鏡である.
Endocytoの使用法は極めてシンプルである.ターゲットとなる病変を見つけたら,1.0%メチレンブルーにて前染色を行い,内視鏡先端を病変に接触させ,ハンドレバーで拡大倍率を最大にするのみである.拡大内視鏡で必要とされる,微細なピント合わせは不要であり,初学者でも扱いは容易である.
confocal laser endoscopy
著者: 酒井英嗣 , 大圃研
ページ範囲:P.732 - P.733
本稿ではプローブ型共焦点レーザー内視鏡(probe-based confocal laser endoscopy ; pCLE,Cellvizio®,Mauna Kea Technologies社製)を用いた大腸腫瘍の診断に関して解説する.pCLEでは表層から約50μm程度の粘膜横断面を拡大倍率1,000倍でリアルタイムに観察可能となる.単腺管である大腸粘膜はpCLEのよい適応であり,病理組織像に匹敵する画像を得ることができる.
EUS
著者: 斉藤裕輔 , 稲場勇平 , 藤谷幹浩
ページ範囲:P.734 - P.736
近年の早期大腸癌1)および大腸粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)発見の増加と内視鏡切除術〔内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection ; EMR),内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)〕の普及により,大腸(上皮性および粘膜下)腫瘍に対する術前診断が,より重要となっている.大腸腫瘍に対する精密検査として,注腸X線造影検査,通常内視鏡検査,拡大内視鏡検査などがあるが,超音波内視鏡検査(endoscopic ultrasonography ; EUS),高周波超音波細径プローブ検査(high-frequency ultrasound probe ; HFUP)は2)これらの検査とは異なり,病変の病理割面像に近い断層像が得られ,その画像に客観性を有するという点で他にはない利点を持つ検査法である.早期大腸癌はHFUPのよい適応であり,術前にTis・T1a癌と診断して内視鏡的切除を行うか,T1b癌と診断して外科手術を行うかの鑑別に重要である.一方,大腸SMTは病変の主座が粘膜下層であり正常粘膜で覆われているため,内視鏡検査のみでは性状診断は困難であり,EUSの併用が極めて有用である.「大腸ポリープ診療ガイドライン2020」3)においても,EUSは早期大腸癌の深達度診断およびSMTの性状診断に有用であり,併用が推奨されている.
カプセル内視鏡
著者: 大宮直木
ページ範囲:P.738 - P.739
従来の大腸検査(大腸内視鏡検査,注腸X線造影検査,CTコロノグラフィ)はすべて経肛門的アプローチであったが,大腸カプセル内視鏡検査は唯一経口内服で行う大腸検査法である.
2020年12月現在,本邦で販売されている大腸カプセル内視鏡PillCamTM COLON 2(コビディエンジャパン/メドトロニック社製)は大きさ31.5×11.6mm,重さ2.9gの両端にカメラがついた2ヘッドのカプセル内視鏡(Fig.1a)である.172°(2ヘッドで全方位に近い344°)の視野角を持ち,有効視程距離は30mm,最小検出対象は0.1mm,標準駆動時間は10時間以上(最大16〜17時間)である.ポシェットに入れて携帯するデータレコーダ(DR3)にはリアルタイムモニターが付いており,現在撮像している画像を確認できる.また,DR3とカプセル内視鏡がセンサアレイを介して双方向無線通信を行うことで,カプセルからの画像から移動量を判定し,撮像速度を両カメラ合わせて毎秒4枚または毎秒35枚に変換するフレームレート調整(adaptive frame rate ; AFR)機能を有する.つまり,カプセル内視鏡が速く移動する際に撮像速度を速くし,見落としを防ぐ.ただし,まれではあるが,検査途中カプセルのバッテリー消費が激しい(例えば毎秒35枚で特定の部位を往復する場合など).つまり10時間以上バッテリーが持たないとDR3が判断すると,撮像レートが毎秒4枚に固定される.
CT Colonography
著者: 野﨑良一 , 有馬浩美
ページ範囲:P.740 - P.741
CTC(CT colonography)が大腸癌術前検査のみならず,大腸スクリーニングにおける画像診断法として注目されている.術前検査として,CTCは注腸X線造影検査(barium enema ; BE)にとって代わろうとしている.盲腸まで内視鏡で観察できない,いわゆる全大腸内視鏡検査(total colonoscopy ; TCS)不成功例に対しても,CTCは有用な検査法である.大腸スクリーニングについてみると,大腸がん検診の精密検査法として本格的導入が間近となっている1).
本稿では大腸スクリーニング,大腸癌術前検査としてのCTCについて解説する.
潰瘍性大腸炎の内視鏡的活動性評価
著者: 髙林馨 , 緒方晴彦
ページ範囲:P.742 - P.743
潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis ; UC)における内視鏡活動性スコアはこれまでに数多く報告されているが,本稿ではその中でも本邦で使用頻度の高いMES(Mayo endoscopic subscore)とUCEIS(ulcerative colitis endoscopic index of severity)について概説する.
潰瘍性大腸炎関連腫瘍(UCAN)の内視鏡診断
著者: 岩男泰
ページ範囲:P.744 - P.745
潰瘍性大腸炎関連腫瘍(ulcerative colitis-associated neoplasm ; UCAN)の初期病変の発見に必要な,サーベイランスにおける内視鏡診断の手順・方法・手技について解説する.
治療
ポリペクトミー
著者: 樫田博史
ページ範囲:P.746 - P.747
本稿では大腸ポリープをスネアに通電して切除する従来のポリペクトミー(hot snare polypectomy)に関して解説する.現在の適応は,主として有茎性ポリープである.
Coldポリペクトミー
著者: 竹内洋司 , 七條智聖
ページ範囲:P.748 - P.749
大腸内視鏡検査で発見される病変の多くは,10mm未満の小ポリープである.本稿では,それら小ポリープに対する安全な内視鏡的切除法として普及しているcold polypectomyに関し,鉗子を用いるCFP(cold forceps polypectomy)とスネアを用いるCSP(cold snare polypectomy)について解説する.
EMR
著者: 山野泰穂
ページ範囲:P.750 - P.752
EMR(endoscopic mucosal resection)は内視鏡治療の基本手技であるが,細やかな戦略を必要とする.以下,遺残再発や偶発症を極力抑制する正しい手技とコツについて解説する.
*本論文中、QRコードを読み込む,もしくはURLにアクセスいただくことで動画を再生できます(公開期限:2024年5月).
UEMR
著者: 竹内洋司 , 上堂文也
ページ範囲:P.754 - P.755
本邦では,10mm未満の小さな良性のポリープに対する安全な治療法としてCSP(cold snare polypectomy)が,20mmを超え悪性が疑われるような病変に対する一括切除割合の高い治療法として内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)が広く普及し,第一選択の治療法とされることが多い.どちらにも当てはまらないものは,従来,局注後にスネアで絞扼し切除する内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection ; EMR)が選択されることが多かったが,本稿ではそのEMRに代わる治療法として期待されるUEMR(underwater EMR)について解説する.
precutting EMR
著者: 髙田和典 , 堀田欣一
ページ範囲:P.756 - P.757
本稿では大腸腫瘍に対するprecutting EMR(endoscopic mucosal resection)の概要について解説する.
Hybrid ESD
著者: 川崎啓祐 , 鳥巣剛弘
ページ範囲:P.758 - P.759
概念
大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)は,粘膜下層に局注後,高周波ナイフを用いて病変の周囲切開と粘膜下層の剝離をする手法である.一方,hybrid ESDは周囲切開後,スネアリングが可能な程度に粘膜下層剝離を行った後にスネアを用いて病変を一括切除する手技であり,内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection ; EMR)とESDを組み合わせた手法である1).
ESD(IT-nano)
著者: 斎藤豊 , 高丸博之
ページ範囲:P.760 - P.761
手技の方法とそのコツ:ITナノ円盤なし
1.適応
大腸ESD(endoscopic submucosal dissection)は,先進医療制度から保険収載を経て日本全国で施行する施設・内視鏡医が急速に増加している1).
当院では以前から,拡大観察でV型(invasive pattern)pitを呈さない大腸腫瘍のうち,通常,内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection ; EMR)で一括切除困難な,20mm超の非顆粒型側方発育型腫瘍(LST-NG)および顆粒型LSTのうち,30mm超の結節混合型(LST-G mixed type)ならびに30mm超のIsをESDの適応とし,20mm未満の腫瘍や,30mm未満のLST-Gに対しては外来EMRで基本的に対応している.再度,入院してESDをすることは,時間的にも経済的にも患者負担となると考えるからである.特に1cm以下の直腸NET(neuroendocrine tumor)に対しては外来ESMR-L(endoscopic submucosal resection with a ligation device)あるいはEMR-C(endoscopic mucosal resection with a cap-fitted panendoscope)で対応している.
ESD(先端系)
著者: 豊永高史
ページ範囲:P.762 - P.765
先端系ナイフの特徴
大腸は内腔が狭い上に壁が薄く屈曲しているため先端系デバイスが適していると考えられている.先端系にもHookナイフ,TTナイフなど長めのナイフとFlexナイフ,Flushナイフ,B-ナイフ,Dualナイフなど短めのナイフとがある.中でもFlushナイフやDualナイフに代表されるshort needle系は長さや方向の調節が不要で,シース先端で支点を作れることから好まれる傾向にある.また,送水機能の有用性が証明され1),多くのナイフが搭載するようになっている.さらにFlexナイフ,Dualナイフ,FlushナイフBT-S,N-Sはシースを細くすることで吸引・鉗子孔挿通性能を向上させている.
ナイフの先端形状はさまざまであるが,それぞれナイフ先端でも支点を作ることができるように工夫がされて来ている.形状は,引っかかりや切れ味を重視しているか,止血能・放電性能をより重視しているか2),によって違いがある.切開性能に関してはモードの調節でいくらでも対応可能であるが,後者についてはデバイスの形・大きさに依存する.また,適度に滑りのある先端形状の応用力の高さから,筆者はFlushナイフBT-Sを主に使用している.ball tip B-knifeと相似形であるが,B-knifeは先端から放電しないことを意図しており,操作法は異なる.
ESD(scissors)
著者: 本間清明 , 小林真 , 花畑憲洋
ページ範囲:P.766 - P.767
壁が薄く内視鏡操作に制限が加わりやすい大腸では,通電時に内視鏡先端部を大きく動かす必要がなく,不用意に深部を損傷する操作につながりにくいハサミ型ナイフが有用である1).本稿では同ナイフの特徴とトンネル法を用いた操作のコツを解説する.
per-anal endoscopic myectomy
著者: 鴫田賢次郎 , 永田信二
ページ範囲:P.768 - P.769
PAEMの適応
下部直腸(Rb)腫瘍に対する外科手術において,人工肛門造設や術後の肛門機能の低下,手術自体の偶発症などの問題を考慮するとover surgeryを避けることは重要であり,内視鏡治療の適応拡大が議論されてきた.腸管の筋層は内輪筋と縦走筋の2層構造になっているが,肛門近傍のRbは縦走筋の厚みがあるため内輪筋まで切除しても全層切除にはならず,さらにRbは腹膜反転部より肛門側に位置するため腹腔内へ穿孔する危険性がない.近年,Rb腫瘍を内輪筋まで含めて内視鏡的に切除するPAEM(per-anal endoscopic myectomy)という手技をToyonagaら1)2)が報告しており,この術式は筋層のラインで切除を行うため,粘膜下層の病変であれば確実に切除断端が陰性で切除できることが期待される.当院でのPAEMの適応は,院内倫理委員会の認定を受けたうえ,①腫瘍と筋層の距離が近接しているcT1b癌,②線維化を伴ったcTis癌,③粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)など,従来の内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)ではデバイスの熱焼灼により切除断端(垂直断端)が陽性/不明となる可能性がある症例としている3).ただし,Rb前壁側の病変は解剖学的に膀胱や子宮と近く,腸管周囲の脂肪組織も少ないため,現時点では適応から除外している.
止血術(止血鉗子)
著者: 吉田直久 , 井上健
ページ範囲:P.770 - P.771
止血鉗子の種類
モノポーラ止血鉗子としてCoagrasper(FD-410LR,有効長1,650mm,開き幅5.0mm,外径2.75mm,オリンパス社製)が2004年に登場し,そして下部用の小さい開き幅のFD-411QR(有効長1,950mm,開き幅4.0mm,外径3.1mm)は2008年に,上部用のより大きな開き幅のFD-412LR(有効長1,650mm,開き幅6.5mm,外径2.75mm)が2014年に市販されている(Fig.1a,b).その特徴は把持部が鋸歯状になっており,組織を滑らずに把持することができ,回転機能により正確なピンポイントの止血が可能である.当院では開きが大きく滑りにくい上部用(FD-410LR)を大腸用として使用している.また,外径2.35mmと細く吸引機能を向上した,開き幅6.0mmの回転可能な止血鉗子としてRaicho 2(カネカ社製)がある(Fig.1c).その他,深部への凝固に配慮したバイポーラ止血鉗子としてHemoStat-Y(開き幅4.0mm or 5.8mm,有効長1,800mm,外径2.6mm,回転機能なし,ペンタックスメディカル社製)もある.
止血術(クリップ)
著者: 關谷真志 , 浦岡俊夫
ページ範囲:P.772 - P.772
クリップ止血術の適応
クリップによる止血には,出血している血管を直接把持することで止血する方法と,粘膜を把持することで圧迫止血する方法がある.前者は血管断端を認識できる憩室出血,直腸潰瘍,内視鏡的ポリープ切除後などが適応病変であり,後者は内視鏡的ポリープ切除後の非動脈性湧出性出血に適している.
止血術(留置スネア)
著者: 小林克誠
ページ範囲:P.773 - P.773
大腸憩室出血に対する内視鏡治療において,近年は結紮法の報告が増えている.留置スネア法(endoscopic detachable snare ligation ; EDSL)はバンド結紮法と異なり,出血源を同定後にその視野を維持したまま責任憩室の結紮・止血へ移行できる利点がある.本稿ではEDSLについて解説する1).
止血術(IVR)
著者: 曽根美都 , 加藤健一
ページ範囲:P.774 - P.774
適応
大腸動脈性出血に対する塞栓術の適応として,保存的治療や内視鏡的止血術で制御できない場合が挙げられる.原因疾患の多くは憩室出血で,その他に腫瘍や炎症性腸疾患がある.
ステント留置術
著者: 桑井寿雄 , 楠龍策
ページ範囲:P.776 - P.777
大腸ステント留置術の適応は,原発性および外因性の大腸悪性狭窄で,腸閉塞発症後はできるだけ早期に施行する.絶対的な禁忌は穿孔を伴う症例であるが,その他にも,①強い炎症や瘻孔を伴っている症例,②肛門縁に近い(歯状線より5cm以内)症例,③狭窄部が複数の症例,④bulkyな腫瘍で狭窄が長大かつ複雑な症例,などは適応を慎重に検討する必要がある.また,大腸ステントは常に偶発症が起こる可能性を伴うため,予防的な留置は行わない1).症例の閉塞程度の評価は大腸ステント安全手技研究会が考案したCROSS(colorectal obstruction scoring system)を用いて行う.術前減圧(bridge to surgery ; BTS)目的でCROSS score 0〜1,緩和(palliation ; PAL)目的でCROSS score 0〜2が適応の目安となる(Table 1)2).狭窄部をスコープが通過可能な症例は,基本的に適応外である.
手技は必ず透視下で施行し,CO2送気と送水システムは必須である.病変は屈曲部にあることが多いため,先端硬性部が短く細径のスコープが有用である.ステントは,BTS,PALともにuncovered typeが推奨されており,axial forceが小さくradial forceが十分で,かつデリバリーシステムが9Frのものが使いやすい.ステント長は狭窄長より両側1.5〜2cm程度長いものを選択する1).
EBD
著者: 坂本琢 , 吉永繁高
ページ範囲:P.778 - P.779
EBDの対象
EBD(endoscopic balloon dilation)は,侵襲性が比較的低く簡便な治療法であり,消化管狭窄に対する姑息的治療としての対象は広く考えられる.特に,腫瘍性病変に対する大腸癌外科治療や内視鏡治療〔主に広範囲の内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)〕,狭窄を伴う炎症性腸疾患が挙げられる.EBDの適応については,絶対的な条件は提示されていないのが現状であるが,以下のような条件が適応条件として挙げられる1)2).
内視鏡的縫縮術
著者: 吉井新二
ページ範囲:P.780 - P.781
ESD(endoscopic submucosal dissection)によって大きな大腸腫瘍の一括切除が可能となったが,後出血,遅発穿孔,PECS(post-ESD coagulation syndrome)などを含めた偶発症が一定の頻度で発生する1).その予防として切除後潰瘍の縫縮が期待されるが,ESD後の大きな切除後潰瘍の縫縮は容易ではない.筆者ら2)は,ナイロン糸とクリップで簡単に作成できる自作クリップ(Ring-clip)を考案し,それを用いてESD後の切除後潰瘍の縫縮を行っているので紹介する.
全層切除術
著者: 鈴木桂悟 , 斎藤彰一
ページ範囲:P.782 - P.783
内視鏡的全層切除(endoscopic full thickness resection ; EFTR)は上部消化管領域では腹腔鏡内視鏡合同手術(laparoscopy and endoscopy cooperative surgery ; LECS)を中心に広く行われるようになり,多くの手法が開発されてきたが,大腸ではいまだ十分に確立されてはいない.
大腸EFTRの適応となりうる症例としては“内視鏡治療困難な粘膜内病変”と“粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)”が挙げられる.前者は具体的に,①虫垂内や憩室内に進展した病変,②高度の線維化症例,③筋層牽引所見を有する隆起型腫瘍が考えられる.①は全層切除のよい適応と考えられる.②に関しては欧米では適応とされているが,本邦においてはpocket-creation methodやtraction device,water pressure methodなどの工夫により内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)で一括切除できる症例が増えており,EFTRの適応となる症例は少ない.③のような病変は深達度診断が難しく,根治切除を目的としているEFTRでは適応としづらい.
大腸憩室出血の部位同定と内視鏡的止血法(EBL)
著者: 鴫田賢次郎 , 青山大輝
ページ範囲:P.784 - P.785
大腸憩室出血の部位同定
大腸憩室出血の内視鏡診断には,SRH(stigmata of recent hemorrhage)を捉えることが必要である(Fig.1).SRHとは活動性出血,非出血性露出血管,除去によって活動性出血もしくは露出血管を伴う凝血塊付着などの所見を指す.憩室出血は間欠的な動脈出血を来すという疾患特性から,特に自然止血後に膨大な数の憩室の中から責任憩室を見つけ出すのは容易ではない.SRH同定率を上げるためには,内視鏡検査を行うタイミングや検査時の工夫,経口洗浄剤による前処置,造影CT併用など個々のケースに見合った選択をする必要がある.
神経内分泌腫瘍に対するESMR-L
著者: 山﨑嵩之 , 松田尚久
ページ範囲:P.786 - P.787
内視鏡治療の適応
大腸の神経内分泌腫瘍(neuroendocrine tumor ; NET)は,本邦では消化管NETの半数以上を占め,特に下部直腸(Rb)に好発する.
内視鏡治療は,転移のリスクが低いと判断される症例に対して適応となる.治療前に診断が可能な転移リスク因子としては,腫瘍径,深達度が挙げられ,本邦のガイドライン1)では腫瘍径1cm未満かつ深達度が粘膜下層(SM)までにとどまるものに内視鏡治療が推奨されている.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.524 - P.526
執筆者一覧(執筆順) フリーアクセス
ページ範囲:P.520 - P.522
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.790 - P.790
編集後記 フリーアクセス
著者: 田中信治
ページ範囲:P.791 - P.791
「胃と腸」の2021年の増刊号として,「消化管診断・治療手技のすべて2021」をお届けする.本誌では,1年に1回増刊号を発刊し,さまざまなテーマを取り上げてきた.昨年2020年は「消化管腫瘍の内視鏡診断2020」をテーマとして刊行した.その他にも,「消化管内視鏡治療2006」,「早期消化管癌の深達度診断2015」,「消化管拡大内視鏡診断2016」をはじめ,疾患別には,「早期大腸癌2010」,「食道表在癌2011」,「炎症性腸疾患2013」,「消化管悪性リンパ腫2014」,「早期胃癌2018」などを刊行しており,バックナンバーを取り寄せて勉強する価値のある素晴らしい増刊号が盛りだくさんである.
今回の「消化管診断・治療手技のすべて2021」は,手技に力点を置いた本誌としては比較的珍しい増刊号である.本誌は主として消化管診断学を取り扱う雑誌であるが,時に治療やサーベイランスなどを取り上げることもある.今回は,全消化管(咽喉頭,食道,胃,十二指腸,小腸,大腸)のほぼすべての診断・治療手技がその道のプロフェッショナルによって網羅的に掲載されているが,項目が非常に多いため,原則2ページでコンパクトかつ詳細にまとめていただいた.
基本情報
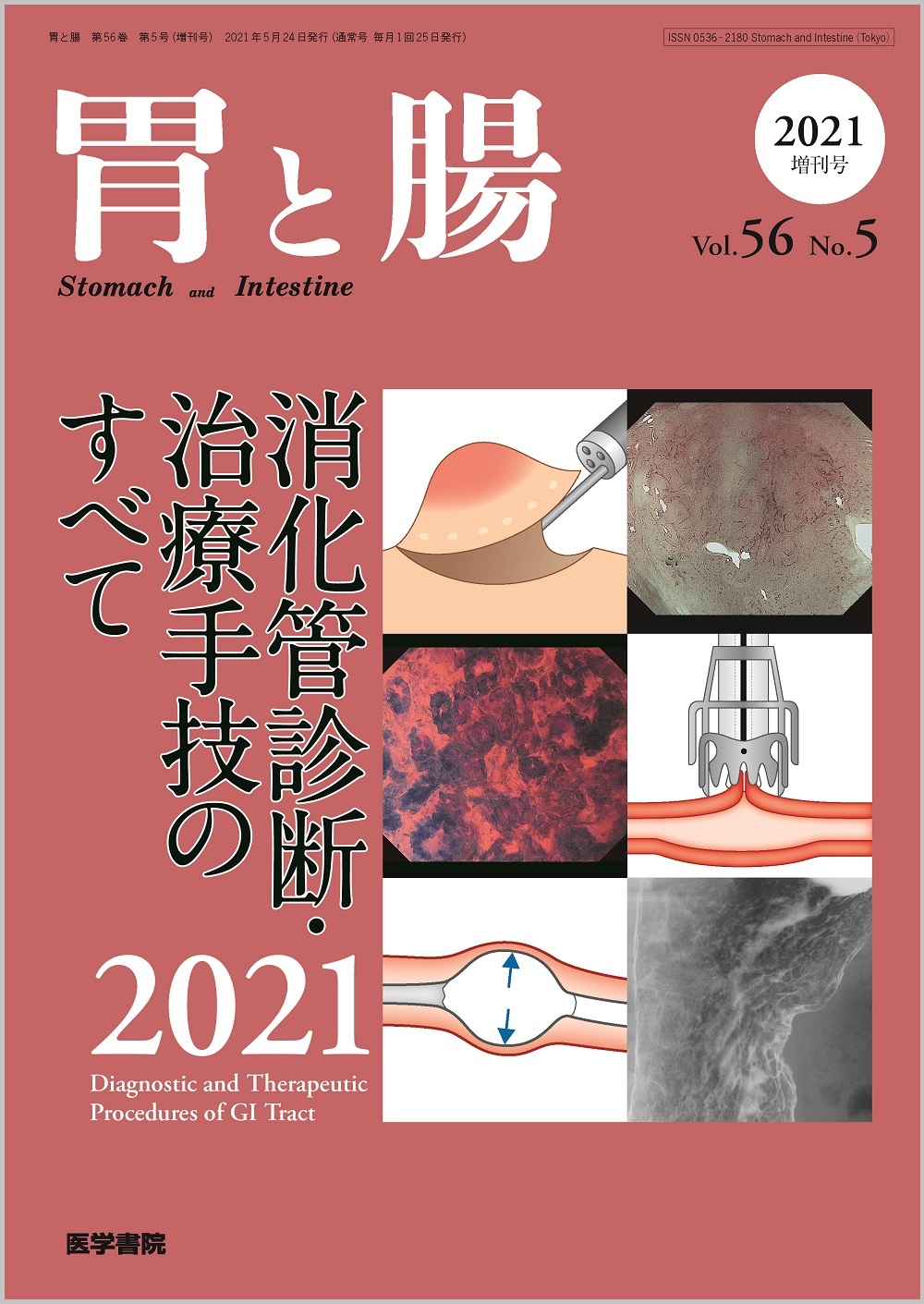
バックナンバー
59巻11号(2024年11月発行)
今月の主題 進行胃癌の診断と治療方針2024
59巻10号(2024年10月発行)
増大号 炎症性腸疾患2024
59巻9号(2024年9月発行)
今月の主題 食道運動障害の診断と治療
59巻8号(2024年8月発行)
今月の主題 臨床と病理のマリアージュ
59巻7号(2024年7月発行)
今月の主題 虚血性腸病変を整理する
59巻6号(2024年6月発行)
今月の主題 内視鏡治療後サーベイランスの現状—異時性多発病変を中心に
59巻5号(2024年5月発行)
今月の主題 胃・十二指腸神経内分泌腫瘍(NEN) up to date
59巻4号(2024年4月発行)
増大号 消化管疾患の分類2024
59巻3号(2024年3月発行)
今月の主題 上皮下発育を呈する食道病変の診断
59巻2号(2024年2月発行)
今月の主題 大腸ポリープのすべて
59巻1号(2024年1月発行)
今月の主題 自己免疫性胃炎—病期分類と画像所見
58巻12号(2023年12月発行)
今月の主題 遺伝性消化管疾患を考える
58巻11号(2023年11月発行)
今月の主題 小腸画像診断のトピックス
58巻10号(2023年10月発行)
増大号 「胃と腸」式 読影問題集2023 応用と発展—考える画像診断が身につく
58巻9号(2023年9月発行)
今月の主題 知っておくべき口腔・咽喉頭病変
58巻8号(2023年8月発行)
今月の主題 十二指腸拡大内視鏡の最新知見
58巻7号(2023年7月発行)
今月の主題 消化管リンパ増殖性疾患の診断アプローチの基本
58巻6号(2023年6月発行)
今月の主題 分類不能腸炎(IBDU)の現状と将来展望
58巻5号(2023年5月発行)
今月の主題 壁内局在からみた胃上皮下腫瘍の鑑別診断
58巻4号(2023年4月発行)
増大号 「胃と腸」式 読影問題集2023 基本と応用—考える画像診断が身につく
58巻3号(2023年3月発行)
今月の主題 食道ESD瘢痕近傍病変の診断と治療
58巻2号(2023年2月発行)
今月の主題 鋸歯状病変関連の早期大腸癌
58巻1号(2023年1月発行)
今月の主題 Non-H. pylori Helicobacter胃炎と周辺疾患
57巻13号(2022年12月発行)
今月の主題 IEEを使いこなす
57巻12号(2022年11月発行)
今月の主題 胃型形質を示す胃・十二指腸上皮性腫瘍
57巻11号(2022年10月発行)
今月の主題 食道癌診療トピックス2022
57巻10号(2022年9月発行)
今月の主題 大腸腫瘍診療の最前線
57巻9号(2022年8月発行)
今月の主題 胃癌スクリーニングの課題と将来展望
57巻8号(2022年7月発行)
今月の主題 転移性消化管腫瘍
57巻7号(2022年6月発行)
今月の主題 特殊型胃癌—組織発生と内視鏡診断
57巻6号(2022年5月発行)
今月の主題 原発性小腸癌—見えてきたその全貌
57巻5号(2022年5月発行)
増刊号 図説「胃と腸」画像診断用語集2022
57巻4号(2022年4月発行)
今月の主題 予後不良な早期消化管癌
57巻3号(2022年3月発行)
今月の主題 食道上皮内腫瘍の診断と取り扱い
57巻2号(2022年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の粘膜治癒を再考する
57巻1号(2022年1月発行)
今月の主題 H. pylori除菌後発見胃癌の診断UPDATE
56巻13号(2021年12月発行)
今月の主題 非乳頭部十二指腸腺腫・癌の診断と治療
56巻12号(2021年11月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の鑑別診断
56巻11号(2021年10月発行)
今月の主題 咽頭表在癌の内視鏡診断と治療
56巻10号(2021年9月発行)
今月の主題 胃上皮性腫瘍—組織分類・内視鏡診断の新展開
56巻9号(2021年8月発行)
今月の主題 「胃と腸」式 読影問題集—考える画像診断が身につく
56巻8号(2021年7月発行)
今月の主題 早期大腸癌内視鏡治療の新展開
56巻7号(2021年6月発行)
今月の主題 食道胃接合部腺癌の診断2021
56巻6号(2021年5月発行)
今月の主題 上部消化管非腫瘍性ポリープの内視鏡所見と病理所見
56巻5号(2021年5月発行)
増刊号 消化管診断・治療手技のすべて2021
56巻4号(2021年4月発行)
今月の主題 消化管疾患AI診断の現状
56巻3号(2021年3月発行)
今月の主題 内視鏡医も知っておくべき病理診断リファレンス—下部消化管腫瘍
56巻2号(2021年2月発行)
今月の主題 Barrett食道腺癌の内視鏡診断と治療2021
56巻1号(2021年1月発行)
今月の主題 早期胃癌内視鏡治療・適応のUPDATE
55巻13号(2020年12月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変の新展開
55巻12号(2020年11月発行)
今月の主題 高齢者早期胃癌ESDの現状と問題点
55巻11号(2020年10月発行)
今月の主題 小腸腫瘍アトラス
55巻10号(2020年9月発行)
今月の主題 食道SM扁平上皮癌治療の新展開
55巻9号(2020年8月発行)
今月の主題 一度見たら忘れられない症例
55巻8号(2020年7月発行)
今月の主題 H. pylori未感染胃の上皮性腫瘍
55巻7号(2020年6月発行)
今月の主題 薬剤関連消化管病変のトピックス
55巻6号(2020年5月発行)
今月の主題 スキルス胃癌—病態と診断・治療の最前線
55巻5号(2020年5月発行)
増刊号 消化管腫瘍の内視鏡診断2020
55巻4号(2020年4月発行)
今月の主題 内視鏡医も知っておくべき病理診断リファレンス—上部消化管腫瘍
55巻3号(2020年3月発行)
今月の主題 いま知っておきたい食道良性疾患
55巻2号(2020年2月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎関連腫瘍—診断・治療の現状と課題
55巻1号(2020年1月発行)
今月の主題 早期胃癌の範囲診断up to date
54巻13号(2019年12月発行)
今月の主題 遺伝子・免疫異常に伴う消化管病変—最新のトピックスを中心に
54巻12号(2019年11月発行)
今月の主題 上部消化管感染症—最近の話題を含めて
54巻11号(2019年10月発行)
今月の主題 大腸腫瘍の病理診断の課題と将来展望
54巻10号(2019年9月発行)
今月の主題 知っておきたい特殊な食道腫瘍・腫瘍様病変
54巻9号(2019年8月発行)
今月の主題 消化管X線造影検査のすべて—撮影手技の実際と読影のポイント
54巻8号(2019年7月発行)
今月の主題 十二指腸腺腫・癌の診断
54巻7号(2019年6月発行)
今月の主題 A型胃炎—最新の知見
54巻6号(2019年5月発行)
今月の主題 隆起型早期大腸癌の病態と診断
54巻5号(2019年5月発行)
増刊号 消化管疾患の分類2019—使い方,使われ方
54巻4号(2019年4月発行)
今月の主題 知っておきたい小腸疾患
54巻3号(2019年3月発行)
今月の主題 咽頭・食道内視鏡拡大観察の基本と最新知見
54巻2号(2019年2月発行)
今月の主題 胃・十二指腸内視鏡拡大観察の基本と最新知見
54巻1号(2019年1月発行)
今月の主題 大腸内視鏡拡大観察の基本と最新知見
53巻13号(2018年12月発行)
今月の主題 EUSによる消化管疾患の診断—現状と最新の話題
53巻12号(2018年11月発行)
今月の主題 知っておきたい十二指腸病変
53巻11号(2018年10月発行)
今月の主題 胃拡大内視鏡が変えたclinical practice
53巻10号(2018年9月発行)
今月の主題 食道表在癌の拡大内視鏡診断─食道学会分類を検証する
53巻9号(2018年8月発行)
今月の主題 消化管画像の成り立ちを知る
53巻8号(2018年7月発行)
今月の主題 対策型胃内視鏡検診の現状と問題点
53巻7号(2018年6月発行)
今月の主題 知っておきたい直腸肛門部病変
53巻6号(2018年5月発行)
今月の主題 小腸出血性疾患の診断と治療─最近の進歩
53巻5号(2018年5月発行)
増刊号 早期胃癌2018
53巻4号(2018年4月発行)
今月の主題 腸管感染症─最新の話題を含めて
53巻3号(2018年3月発行)
今月の主題 好酸球性食道炎の診断と治療
53巻2号(2018年2月発行)
今月の主題 IBDの内視鏡的粘膜治癒─評価法と臨床的意義
53巻1号(2018年1月発行)
今月の主題 胃型形質の低異型度分化型胃癌
52巻13号(2017年12月発行)
今月の主題 咽頭・頸部食道癌の診断と治療
52巻12号(2017年11月発行)
今月の主題 大腸小・微小病変に対するcold polypectomyの意義と課題
52巻11号(2017年10月発行)
今月の主題 非特異性多発性小腸潰瘍症/CEAS─遺伝子異常と類縁疾患
52巻10号(2017年9月発行)
今月の主題 胃粘膜下腫瘍の診断と治療
52巻9号(2017年8月発行)
今月の主題 大腸スクリーニングの現状と将来展望
52巻8号(2017年7月発行)
今月の主題 臨床医も知っておくべき免疫組織化学染色のすべて
52巻7号(2017年6月発行)
今月の主題 胃潰瘍は変わったか─新しい胃潰瘍学の構築を目指して
52巻6号(2017年5月発行)
今月の主題 知っておきたいまれな大腸良性疾患
52巻5号(2017年5月発行)
増刊号 図説「胃と腸」所見用語集2017
52巻4号(2017年4月発行)
今月の主題 消化管内分泌細胞腫瘍の新知見
52巻3号(2017年3月発行)
今月の主題 表在型食道胃接合部癌の治療戦略
52巻2号(2017年2月発行)
今月の主題 消化管結核の診断と治療─最近の進歩
52巻1号(2017年1月発行)
今月の主題 知っておくべき胃疾患の分類
51巻13号(2016年12月発行)
今月の主題 狭窄を来す小腸疾患の診断
51巻12号(2016年11月発行)
今月の主題 十二指腸の上皮性腫瘍
51巻11号(2016年10月発行)
今月の主題 肉芽腫を形成する消化管病変
51巻10号(2016年9月発行)
今月の主題 表在型Barrett食道癌の診断
51巻9号(2016年8月発行)
今月の主題 消化管画像プレゼンテーションの基本と実際
51巻8号(2016年7月発行)
今月の主題 消化管疾患と皮膚病変
51巻7号(2016年6月発行)
今月の主題 新しい小腸・大腸画像診断─現状と将来展望
51巻6号(2016年5月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌後発見胃癌の内視鏡的特徴
51巻5号(2016年5月発行)
増刊号 消化管拡大内視鏡診断2016
51巻4号(2016年4月発行)
今月の主題 薬剤関連消化管病変
51巻3号(2016年3月発行)
今月の主題 知っておきたいまれな大腸悪性腫瘍
51巻2号(2016年2月発行)
今月の主題 まれな食道疾患の鑑別診断
51巻1号(2016年1月発行)
今月の主題 慢性胃炎を見直す
50巻13号(2015年12月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変の取り扱い
50巻12号(2015年11月発行)
今月の主題 胃底腺型胃癌
50巻11号(2015年10月発行)
今月の主題 血管炎による消化管病変
50巻10号(2015年9月発行)
今月の主題 狭窄を来す大腸疾患─診断のプロセスを含めて
50巻9号(2015年8月発行)
今月の主題 食道胃接合部腺癌
50巻8号(2015年7月発行)
今月の主題 胃がん検診に未来はあるのか
50巻7号(2015年6月発行)
今月の主題 診断困難な炎症性腸疾患
50巻6号(2015年5月発行)
今月の主題 知っておきたいまれな胃疾患
50巻5号(2015年5月発行)
増刊号 早期消化管癌の深達度診断 2015
50巻4号(2015年4月発行)
今月の主題 早期大腸癌内視鏡治療後の中・長期経過
50巻3号(2015年3月発行)
今月の主題 胃癌範囲診断における拡大観察のピットフォール
50巻2号(2015年2月発行)
今月の主題 食道のびらん・潰瘍性病変
50巻1号(2015年1月発行)
今月の主題 消化管早期癌診断学の時代変遷─50年の歩みと展望
49巻13号(2014年12月発行)
今月の主題 胃の腺腫─診断と治療方針
49巻12号(2014年11月発行)
今月の主題 大腸LSTの診断と意義—拡大内視鏡を中心に
49巻11号(2014年10月発行)
今月の主題 胃癌ESD適応拡大病変の経過と予後
49巻10号(2014年9月発行)
今月の主題 colitic cancerの初期病変─遡及例の検討を含めて
49巻9号(2014年8月発行)
今月の主題 小腸潰瘍の鑑別診断
49巻8号(2014年7月発行)
今月の主題 表面型表層拡大型食道癌の診断と治療戦略
49巻7号(2014年6月発行)
今月の主題 大腸T1(SM)癌に対する内視鏡治療の適応拡大
49巻6号(2014年5月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori陰性胃癌
49巻5号(2014年5月発行)
増刊号 消化管悪性リンパ腫2014
49巻4号(2014年4月発行)
今月の主題 虫垂病変のすべて―非腫瘍から腫瘍まで
49巻3号(2014年3月発行)
今月の主題 消化管アミロイドーシスを見直す
49巻2号(2014年2月発行)
今月の主題 日本食道学会拡大内視鏡分類
49巻1号(2014年1月発行)
今月の主題 ESD時代の早期胃癌深達度診断
48巻13号(2013年12月発行)
今月の主題 好酸球性消化管疾患の概念と取り扱い
48巻12号(2013年11月発行)
今月の主題 虚血性腸病変
48巻11号(2013年10月発行)
今月の主題 組織混在型粘膜内胃癌の診断
48巻10号(2013年9月発行)
今月の主題 小腸の悪性腫瘍
48巻9号(2013年8月発行)
今月の主題 食道表在癌治療の最先端
48巻8号(2013年7月発行)
今月の主題 非腫瘍性大腸ポリープのすべて
48巻7号(2013年6月発行)
今月の主題 消化管内分泌細胞腫瘍の診断と治療―WHO分類との対比
48巻6号(2013年5月発行)
今月の主題 微小胃癌の診断限界に迫る
48巻5号(2013年5月発行)
特集 炎症性腸疾患 2013
48巻4号(2013年4月発行)
今月の主題 カプセル内視鏡の現状と展望
48巻3号(2013年3月発行)
今月の主題 隆起型食道癌の特徴と鑑別診断
48巻2号(2013年2月発行)
今月の主題 大腸ESDの適応と実際
48巻1号(2013年1月発行)
今月の主題 潰瘍合併早期胃癌の診断と治療
47巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 右側大腸腫瘍の臨床病理学的特徴
47巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 高齢者消化管疾患の特徴
47巻11号(2012年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌後の胃癌
47巻10号(2012年9月発行)
今月の主題 難治性Crohn病の特徴と治療戦略
47巻9号(2012年8月発行)
今月の主題 食道癌の発育進展─初期浸潤の病態と診断
47巻8号(2012年7月発行)
今月の主題 胃ポリープの意義と鑑別
47巻7号(2012年6月発行)
今月の主題 大腸憩室疾患
47巻6号(2012年5月発行)
今月の主題 経鼻内視鏡によるスクリーニング
47巻5号(2012年5月発行)
特集 図説 胃と腸用語集2012
47巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 消化管EUS診断の現状と新たな展開
47巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 咽頭・頸部食道癌の鑑別診断
47巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 改訂された胃生検Group分類の現状
47巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 腸管三次元CT診断の現状
46巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 難治性潰瘍性大腸炎─診療・治療の新たな展開
46巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 Barrett食道癌の診断
46巻11号(2011年10月発行)
今月の主題 十二指腸の腫瘍性病変
46巻10号(2011年9月発行)
今月の主題 大腸SM癌に対する内視鏡治療の適応拡大
46巻9号(2011年8月発行)
今月の主題 若年者の胃・十二指腸病変の特徴
46巻8号(2011年7月発行)
今月の主題 食道の炎症性疾患
46巻7号(2011年6月発行)
今月の主題 腸管Behçet病と単純性潰瘍─診断と治療の進歩
46巻6号(2011年5月発行)
今月の主題 胃腫瘍の拡大内視鏡診断
46巻5号(2011年5月発行)
特集 食道表在癌2011
46巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変と癌化
46巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 免疫不全状態における消化管病変
46巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 NSAID起因性小腸病変
46巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 多発胃癌─最新の知見を含めて
45巻14号(2010年12月発行)
第41巻~第45巻 総索引 2006年~2010年(平成18年~平成22年)
45巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝性消化管疾患の特徴と長期経過
45巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 特殊型胃癌の病理像と臨床的特徴
45巻11号(2010年10月発行)
今月の主題 大腸低分化腺癌の初期像とその進展
45巻10号(2010年9月発行)
今月の主題 Crohn病小腸病変に対する診断と治療の進歩
45巻9号(2010年8月発行)
今月の主題 食道表在癌の深達度診断
45巻8号(2010年7月発行)
今月の主題 直腸肛門部病変の鑑別診断─最新の知見を含めて
45巻7号(2010年6月発行)
今月の主題 低異型度分化型胃癌の診断
45巻6号(2010年5月発行)
今月の主題 側方発育型大腸腫瘍(laterally spreading tumor ; LST)─分類と意義
45巻5号(2010年4月発行)
特集 早期大腸癌2010
45巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 スキルス胃癌と鑑別を要する疾患
45巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 出血性小腸疾患─内視鏡診断・治療の最前線
45巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 中・下咽頭表在癌の診断と治療
45巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 早期胃癌のIIb進展範囲診断
44巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 collagenous colitisの現況と新知見
44巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 消化管癌の化学・放射線療法の効果判定と問題点
44巻11号(2009年10月発行)
今月の主題 食道小扁平上皮癌の診断
44巻10号(2009年9月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎の初期病変とその進展・経過
44巻9号(2009年8月発行)
今月の主題 背景粘膜からみた胃癌ハイリスクグループ
44巻8号(2009年7月発行)
今月の主題 大腸SM癌内視鏡治療の根治基準をめぐって─病理診断の問題点と予後
44巻7号(2009年6月発行)
今月の主題 食道胃接合部腺癌の診断
44巻6号(2009年5月発行)
今月の主題 小腸疾患─小病変の診断と治療の進歩
44巻5号(2009年4月発行)
今月の主題 癌や炎症と鑑別が困難な消化管悪性リンパ腫
44巻4号(2009年4月発行)
特集 早期胃癌2009
44巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 食道扁平上皮癌に対するESDの適応と実際
44巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 特発性腸間膜静脈硬化症(idiopathic mesenteric phlebosclerosis)―概念と臨床的取り扱い
44巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 未分化型胃粘膜内癌のESD―適応拡大の可能性
43巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 大腸癌の発生・発育進展
43巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 早期胃癌発育の新たな分析─内視鏡経過例の遡及的検討から
43巻11号(2008年10月発行)
今月の主題 感染性腸炎─最近の動向と知見
43巻10号(2008年9月発行)
今月の主題 早期食道癌の診断─最近の進歩
43巻9号(2008年8月発行)
今月の主題 colitic cancer/dysplasiaの早期診断─病理組織診断の問題点も含めて
43巻8号(2008年7月発行)
今月の主題 胃癌に対する内視鏡スクリーニングの現状と将来
43巻7号(2008年6月発行)
今月の主題 消化管follicular lymphoma―診断と治療戦略
43巻6号(2008年5月発行)
今月の主題 大腸の新しい画像診断
43巻5号(2008年4月発行)
今月の主題 linitis plastica型胃癌―病態と診断・治療の最前線
43巻4号(2008年4月発行)
特集 小腸疾患2008
43巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 まれな食道良性腫瘍および腫瘍様病変
43巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 消化管GIST―診断・治療の新展開
43巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 早期胃癌ESD―適応拡大を求めて
42巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 新しい治療による炎症性腸疾患(IBD)の経過―粘膜治癒を中心に
42巻12号(2007年11月発行)
今月の主題 非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)起因性消化管病変
42巻11号(2007年10月発行)
今月の主題 ESD時代における未分化型混在早期胃癌の取り扱い
42巻10号(2007年9月発行)
今月の主題 大腸腫瘍内視鏡切除後のサーベイランスに向けて
42巻9号(2007年8月発行)
今月の主題 食道表在癌内視鏡切除後の長期成績
42巻8号(2007年7月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫―除菌無効例の特徴と治療戦略
42巻7号(2007年6月発行)
今月の主題 大腸ESDの現況と将来展望
42巻6号(2007年5月発行)
今月の主題 Helicobacter pyloriと胃癌
42巻5号(2007年4月発行)
特集 消化管の拡大内視鏡観察2007
42巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患(IBD)の上部消化管病変
42巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変の発育進展と診断・取り扱い
42巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 食道扁平上皮dysplasia―診断と取り扱いをめぐって
42巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 胃分化型SM1癌の診断―垂直浸潤500μm
41巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 大腸腫瘍に対する拡大内視鏡診断の最先端
41巻12号(2006年11月発行)
今月の主題 小腸疾患診療の新たな展開
41巻11号(2006年10月発行)
今月の主題 早期胃癌に対するESDと腹腔鏡下手術の接点
41巻10号(2006年9月発行)
・sm癌の最新の診断と治療戦略
41巻9号(2006年8月発行)
今月の主題 通常内視鏡による大腸sm癌の深達度診断 垂直侵潤距離1,000μm術前診断の現状
41巻8号(2006年7月発行)
今月の主題 転移陽性胃粘膜内癌の特徴と取り扱い
41巻7号(2006年6月発行)
今月の主題 Helicobacter pyloriに起因しないとされる良性胃粘膜病変
41巻6号(2006年5月発行)
今月の主題 非定型的炎症性腸疾患―診断と経過
41巻5号(2006年4月発行)
今月の主題 陥凹性小胃癌の診断―基本から最先端まで
41巻4号(2006年4月発行)
特集 消化管内視鏡治療2006
41巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腸管悪性リンパ腫―最近の知見
41巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 食道表在癌の内視鏡診断―最近の進歩
41巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 早期胃癌に対するESDの適応の現状と今後の展望
40巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 いわゆる側方発育型大腸腫瘍の治療法を問う
40巻12号(2005年11月発行)
今月の主題 胃癌EMR後の異時性多発を考える
40巻11号(2005年10月発行)
今月の主題 小腸内視鏡検査法の進歩
40巻10号(2005年9月発行)
今月の主題 難治性潰瘍性大腸炎―診断と治療の新知見
40巻9号(2005年8月発行)
今月の主題 表在性の中・下咽頭癌
40巻8号(2005年7月発行)
今月の主題 免疫異常と消化管病変
40巻7号(2005年6月発行)
今月の主題 胃癌化学療法の進歩と課題
40巻6号(2005年5月発行)
今月の主題 Crohn病の初期病変―診断と長期経過
40巻4号(2005年4月発行)
特集 消化管の出血性疾患2005
40巻5号(2005年4月発行)
今月の主題 切開・剥離法(ESD)時代の胃癌術前診断
40巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 特殊組織型の食道癌
40巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 大腸カルチノイド腫瘍 転移例と非転移例の比較を中心に
40巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 胃癌の時代的変遷と将来展望
39巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 大腸sm癌の内視鏡治療後の長期経過
39巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 消化管の画像診断―21世紀の展開
39巻11号(2004年10月発行)
今月の主題 胃生検診断の意義 Group分類を考える
39巻10号(2004年9月発行)
今月の主題 大腸sm癌の深達度診断―垂直浸潤1,000μm
39巻9号(2004年8月発行)
今月の主題 Barrett食道癌―表在癌の境界・深達度診断
39巻8号(2004年7月発行)
今月の主題 家族性大腸腺腫症―最近の話題
39巻7号(2004年6月発行)
今月の主題 胃癌術後の残胃癌
39巻6号(2004年5月発行)
今月の主題 深達度診断を迷わせる食道表在癌―その原因と画像の特徴
39巻5号(2004年4月発行)
今月の主題 大腸腫瘍に対する拡大内視鏡観察―V型pit pattern診断の問題点
39巻4号(2004年4月発行)
特集 消化管の粘膜下腫瘍 2004
39巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫―除菌治療後の経過と予後
39巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 Crohn病経過例における新しい治療の位置づけ
39巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 最新の早期胃癌EMR―切開・剥離法
38巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 消化管への転移性腫瘍
38巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 上部消化管拡大観察の意義
38巻11号(2003年10月発行)
今月の主題 粘膜下腫瘍様の形態を示した消化管癌
38巻10号(2003年9月発行)
今月の主題 胃腺腫の診断と治療方針
38巻9号(2003年8月発行)
今月の主題 直腸肛門部病変の鑑別診断
38巻8号(2003年7月発行)
今月の主題 経過観察からみた大腸癌の発育・進展sm癌を中心に
38巻7号(2003年6月発行)
今月の主題 消化管の炎症性疾患診断におけるX線検査の有用性
38巻6号(2003年5月発行)
今月の主題 消化管腫瘍診断におけるX線検査の有用性
38巻5号(2003年4月発行)
今月の主題 胃型早期胃癌の病理学的特徴と臨床像―分化型癌を中心に
38巻4号(2003年4月発行)
特集 全身性疾患と消化管病変
38巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 食道癌と他臓器重複癌―EMR時代を迎えて
38巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 腸型Behçet病と単純性潰瘍の長期経過
38巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 胃癌―診断と治療の最先端
37巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 胃癌と鑑別を要する炎症性疾患
37巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 Ⅰp・Ⅰsp型大腸sm癌
37巻11号(2002年10月発行)
今月の主題 消化管のvirtual endoscopy
37巻10号(2002年9月発行)
今月の主題 食道sm癌の再評価―食道温存治療の可能性を求めて
37巻9号(2002年8月発行)
今月の主題 胃粘膜内癌EMRの適応拡大と限界
37巻8号(2002年7月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と腫瘍(2)潰瘍性大腸炎以外
37巻7号(2002年6月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と腫瘍(1)潰瘍性大腸炎
37巻6号(2002年5月発行)
今月の主題 十二指腸の非腫瘍性びまん性病変
37巻5号(2002年4月発行)
今月の主題 cap polyposisと粘膜脱症候群
37巻4号(2002年3月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌に伴う問題点
37巻3号(2002年2月発行)
特集 消化管感染症2002
37巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 4型大腸癌とその鑑別診断
37巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 食道m3・sm1癌の診断と遠隔成績
36巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 早期胃癌診療の実態と問題点
36巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 十二指腸の小病変
36巻11号(2001年10月発行)
今月の主題 sm massive以深に浸潤した10mm以下の大腸癌
36巻10号(2001年9月発行)
今月の主題 縮小治療のための胃癌の粘膜内浸潤範囲診断
36巻9号(2001年8月発行)
今月の主題 GIST(gastrointestinal stromal tumor)―概念と臨床的取り扱い
36巻8号(2001年7月発行)
今月の主題 多発食道癌
36巻7号(2001年6月発行)
今月の主題 小腸腫瘍―分類と画像所見
36巻6号(2001年5月発行)
今月の主題 早期大腸癌の深達度診断にEUSと拡大内視鏡は必要か
36巻5号(2001年4月発行)
今月の主題 早期の食道胃接合部癌
36巻4号(2001年3月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎診断基準の問題点
36巻3号(2001年2月発行)
特集 消化管癌の深達度診断
36巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Crohn病診断基準の問題点
36巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 表層型胃悪性リンパ腫の鑑別診断―治療法選択のために
35巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 21世紀への消化管画像診断学―歩みと展望
35巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 早期大腸癌肉眼分類―統一をめざして
35巻11号(2000年10月発行)
今月の主題 胃カルチノイド―新しい考え方
35巻10号(2000年9月発行)
今月の主題 食道アカラシア
35巻9号(2000年8月発行)
今月の主題 薬剤性腸炎―最近の話題
35巻8号(2000年7月発行)
今月の主題 多発大腸癌
35巻7号(2000年6月発行)
今月の主題 胃の“pre-linitis plastica”型癌
35巻6号(2000年5月発行)
今月の主題 腸管の血管性病変―限局性腫瘍状病変を中心に
35巻5号(2000年4月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌後の消化性潰瘍の経過―3年以上の症例を中心に
35巻4号(2000年3月発行)
今月の主題 食道癌の発育進展―初期病巣から粘膜下層癌へ
35巻3号(2000年2月発行)
特集 消化管ポリポーシス2000
35巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患における生検の役割
35巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の基本所見とピットフォール
34巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 大腸腫瘍の内視鏡診断は病理診断にどこまで近づくか
34巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 胃癌診断における生検の現状と問題点
34巻11号(1999年10月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫―Helicobacter pylori除菌後の経過
34巻10号(1999年9月発行)
今月の主題 Crohn病の長期経過―10年以上の症例を中心に
34巻9号(1999年8月発行)
今月の主題 早期胃癌のEUS診断
34巻8号(1999年7月発行)
今月の主題 逆流性食道炎―分類・診断・治療
34巻7号(1999年6月発行)
今月の主題 AIDSとATLの消化管病変
34巻6号(1999年5月発行)
今月の主題 大腸sm癌の内視鏡的切除をめぐって
34巻5号(1999年4月発行)
今月の主題 大腸腫瘍内視鏡的切除後の局所再発―腺腫・m癌を中心に
34巻4号(1999年3月発行)
今月の主題 胃型の分化型胃癌―病理診断とその特徴
34巻3号(1999年2月発行)
特集 消化管の画像診断―US,CT,MRIの役割
34巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 Barrett上皮と食道腺癌
34巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 Ⅱ型早期大腸癌肉眼分類の問題点
33巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 胃癌EMR後の遺残再発―診断と治療
33巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 胃癌EMRの完全切除の判定基準を求めて
33巻11号(1998年10月発行)
今月の主題 早期大腸癌の組織診断―諸問題は解決されたか
33巻10号(1998年9月発行)
今月の主題 腸管子宮内膜症
33巻9号(1998年8月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎―最近の話題
33巻8号(1998年7月発行)
今月の主題 胃炎―Sydney SystemとHelicobacter pylori
33巻7号(1998年6月発行)
食道癌
33巻6号(1998年5月発行)
今月の主題 鋸歯状腺腫(serrated adenoma)とその周辺
33巻5号(1998年4月発行)
今月の主題 大腸疾患の診断に注腸X線検査は必要か
33巻4号(1998年3月発行)
今月の主題 胃癌の診断にX線検査は不要か
33巻3号(1998年2月発行)
特集 消化管悪性リンパ腫1998
33巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 消化管病変の三次元画像診断―現状と展望
33巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 「胃と腸」33年間の歩みからみた早期癌
32巻13号(1997年12月発行)
との鑑別を中心に
32巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 腺領域からみた胃病変
32巻11号(1997年10月発行)
今月の主題 Is型大腸sm癌を考える
32巻10号(1997年9月発行)
今月の主題 早期食道癌―X線診断の進歩
32巻9号(1997年8月発行)
今月の主題 胃噴門部領域の病変 (2)癌以外の病変
32巻8号(1997年7月発行)
今月の主題 胃噴門部領域の病変 (1)癌
32巻7号(1997年6月発行)
今月の主題 感染性腸炎(腸結核を除く)
32巻6号(1997年5月発行)
今月の主題 早期胃癌から進行癌への進展
32巻5号(1997年4月発行)
今月の主題 粘膜下腫瘍様の食道表在癌
32巻4号(1997年3月発行)
今月の主題 大腸腺腫症―最近の知見
32巻3号(1997年2月発行)
特集 炎症性腸疾患1997
32巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 十二指腸乳頭部癌―縮小手術をめざして
32巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 胃sm癌の細分類―治療法選択の指標として
31巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 大腸腫瘍の自然史
31巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 未分化型小胃癌はなぜ少ないか
31巻11号(1996年10月発行)
今月の主題 微細表面構造からみた大腸腫瘍の診断
31巻10号(1996年9月発行)
今月の主題 内視鏡的食道粘膜切除後の経過
31巻9号(1996年8月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的粘膜切除―適応拡大をめぐる問題点
31巻8号(1996年7月発行)
今月の主題 Helicobacter Pyloriと胃リンパ腫
31巻7号(1996年6月発行)
今月の主題 遺伝性非ポリポーシス大腸癌(HNPCC)
31巻6号(1996年5月発行)
今月の主題 食道dysplasia―経過観察例の検討
31巻5号(1996年4月発行)
今月の主題 表層拡大型早期胃癌
31巻4号(1996年3月発行)
今月の主題 新しいCrohn病診断基準(案)
31巻3号(1996年2月発行)
特集 図説 形態用語の使い方・使われ方
31巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 いわゆる表層拡大型大腸腫瘍とは
31巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫
30巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 小腸画像診断の新しい展開
30巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 大腸腺腫の診断と取り扱い
30巻11号(1995年10月発行)
今月の主題 食道表在癌の発育進展―症例から学ぶ
30巻10号(1995年9月発行)
今月の主題 微小胃癌
30巻9号(1995年8月発行)
今月の主題 胃の平滑筋腫と平滑筋肉腫―新しい視点を求めて
30巻8号(1995年7月発行)
今月の主題 表層拡大型食道表在癌
30巻7号(1995年6月発行)
今月の主題 大腸の悪性リンパ腫
30巻6号(1995年5月発行)
今月の主題 粘膜下腫瘍の形態を示した胃癌
30巻5号(1995年4月発行)
今月の主題 colitic cancer―微細診断をめざして
30巻4号(1995年3月発行)
今月の主題 腸結核
30巻3号(1995年2月発行)
特集 早期食道癌1995
30巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 表面型大腸癌の発育と経過
30巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 胃癌の診断と治療―最近の動向
29巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 上部消化管病変の特徴からみた全身性疾患
29巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 大腸sm癌の細分類とその臨床
29巻11号(1994年10月発行)
今月の主題 大腸sm癌の細分類とその意義
29巻10号(1994年9月発行)
今月の主題 胃底腺領域の分化型癌
29巻9号(1994年8月発行)
今月の主題 食道のヨード不染帯
29巻8号(1994年7月発行)
今月の主題 胆管癌の画像と病理
29巻7号(1994年6月発行)
今月の主題 多発胃癌
29巻6号(1994年5月発行)
今月の主題 アフタ様病変のみのCrohn病
29巻5号(1994年4月発行)
今月の主題 大腸Crohn病―非定型例の診断を中心に
29巻4号(1994年3月発行)
今月の主題 食道粘膜癌―新しい病型分類とその診断
29巻3号(1994年2月発行)
特集 早期大腸癌1994
29巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 胃良・悪性境界病変の生検診断と治療方針
29巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 表面型大腸腫瘍―肉眼分類を考える
28巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的根治切除―適応拡大の可能性と限界を探る
28巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 消化管ポリポーシス―最近の知見
28巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 大腸癌の深達度診断
28巻10号(1993年9月発行)
今月の主題 胃悪性リンパ腫―診断の変遷
28巻9号(1993年8月発行)
今月の主題 虚血性腸病変の新しい捉え方
28巻8号(1993年7月発行)
今月の主題 大腸癌存在診断の実態―m癌を除く
28巻7号(1993年6月発行)
今月の主題 十二指腸腫瘍
28巻6号(1993年5月発行)
今月の主題 大腸腫瘍切除後の経過追跡
28巻5号(1993年4月発行)
今月の主題 腸管アフタ様病変
28巻4号(1993年3月発行)
今月の主題 難治性胃潰瘍(2)臨床経過と難治化の要因
28巻3号(1993年2月発行)
特集 早期胃癌1993
28巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内視鏡的食道粘膜切除術
28巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 胃癌は変わったか―その時代的変遷
27巻12号(1992年12月発行)
今月の主題 難治性胃潰瘍(1)治癒予測を中心に
27巻11号(1992年11月発行)
今月の主題 大腸pm癌
27巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 胃癌の深達度診断mとsmの鑑別―内視鏡的治療のために
27巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 逆流性食道炎を見直す
27巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 表面型大腸腫瘍の臨床診断の諸問題
27巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 出血を来した小腸病変の画像診断
27巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 早期大腸癌の病理診断の諸問題―小病変の診断を中心に
27巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 linitis plastica型胃癌診断の現状
27巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 大腸のいわゆる結節集簇様病変
27巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 腸型Behçet病・simple ulcerの経過
27巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 食道表在癌の深達度を読む
27巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 胃癌の自然史を追う―経過追跡症例から
26巻12号(1991年12月発行)
今月の主題 集検発見胃癌の特徴
26巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 膠原病と腸病変
26巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 胃癌の組織型分類とその臨床的意義
26巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 Ⅲ型早期胃癌の診断に迫る―潰瘍の良・悪性の鑑別
26巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 大腸sm癌の治療
26巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 大腸sm癌の診断
26巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 Crohn病の長期経過
26巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎の長期経過
26巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的切除(2)―内視鏡的根治切除の評価
26巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的切除(1)―根治を目的として
26巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 食道“dysplasia”の存在を問う
26巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 早期胃癌―診断の基本と方法
25巻12号(1990年12月発行)
今月の主題 早期胃癌類似進行癌の診断
25巻11号(1990年11月発行)
今月の主題 直腸のいわゆる粘膜脱症候群
25巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 中垂腫瘤
25巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 早期食道癌を問う
25巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 臨床経過からみた胃生検の問題点
25巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 小さな表面型(Ⅱ型)大腸上皮性腫瘍
25巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の鑑別診断(2)―大腸病変を中心に
25巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の鑑別診断(1)―小腸・回盲部病変を中心に
25巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 Barrett食道
25巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 胃癌の切除範囲をどう決めるのか
25巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 膵囊胞性疾患―動態診断の基礎と臨床
25巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 上部消化管X線検査の現状の反省と将来―検査モデルを求めて
24巻12号(1989年12月発行)
今月の主題 小さな未分化型胃癌―分化型と比較して
24巻11号(1989年11月発行)
今月の主題 いわゆる“十二指腸炎”の諸問題
24巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 分類困難な腸の炎症性疾患
24巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 胃粘膜下腫瘍の診断―現況と進歩
24巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 腸のカルチノイド
24巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 胆道疾患の非手術的治療の進歩
24巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 急性胃粘膜病変(AGML)
24巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 腸管の悪性リンパ腫(2)
24巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 胃・十二指腸出血の非手術的治療
24巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 大腸腺腫と癌(2)
24巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 大腸腺腫と癌(1)
24巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 噴門部陥凹型早期胃癌の診断
23巻12号(1988年12月発行)
今月の主題 腸管の悪性リンパ腫(1)
23巻11号(1988年11月発行)
今月の主題 食道癌の発育進展―逆追跡症例を中心に
23巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 十二指腸乳頭部癌
23巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 大腸内視鏡検査法―手技を中心として
23巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 小さな膵癌―小病変の鑑別診断をめぐって
23巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 微小胃癌診断―10年の進歩
23巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 びまん浸潤型大腸癌と転移性大腸癌
23巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍と超音波内視鏡
23巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 内視鏡的胃粘膜切除の臨床―ジャンボ・バイオプシーをめぐって
23巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化管形態診断の将来はどうあるべきか
23巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 消化管のアミロイドーシス(2)
23巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 X線・内視鏡所見と切除標本・病理所見との対比(胃)
22巻12号(1987年12月発行)
今月の主題 早期食道癌の問題点
22巻11号(1987年11月発行)
今月の主題 消化管のアミロイドーシス(1)
22巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 胃のDieulafoy潰瘍
22巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 胃底腺領域の癌―Ⅱcを中心として
22巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 陥凹型早期大腸癌
22巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 腸結核と癌
22巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 胃の腺腫とは―現状と問題点
22巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 胆囊癌の診断―発育進展を中心に
22巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 小さな大腸癌―早期診断のために
22巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 直腸・肛門部病変の新しい診かた
22巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 陥凹型早期胃癌の深達度診断
22巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 電子スコープの現況
21巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 大腸のvillous tumor
21巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 消化性潰瘍のトピックス(2)―胃粘膜防御機構を中心に
21巻10号(1986年10月発行)
受容体拮抗薬のもたらした諸問題
21巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎と大腸癌
21巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 胃癌肉眼分類の問題点―進行癌を中心として
21巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 膵の囊胞性疾患―その診断の進歩
21巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 大腸生検の問題点―炎症性疾患の経過を中心に
21巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 早期胆嚢癌―その診断の進歩
21巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 Ⅱb型早期胃癌の診断
21巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 大腸早期癌診断におけるX線と内視鏡との比較
21巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 消化管の“比較診断学”を求めて(2)
21巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 消化管の“比較診断学”を求めて(1)
20巻12号(1985年12月発行)
今月の主題 食道癌の早期診断
20巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 内視鏡的乳頭括約筋切開術の長期成績
20巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 大腸ポリペクトミー後の経過
20巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 胃癌診断におけるルーチン検査の確かさ―部位別・大きさ別の検討
20巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 大腸癌の発育・進展
20巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 小腸診断学の進歩―実際から最先端まで
20巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 慢性胃炎をどう考えるか
20巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 食道静脈瘤の硬化療法
20巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 膵・胆道の形成異常
20巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 大腸診断学の歩みと展望
20巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 胃診断学20年の歩みと展望―良性疾患を中心として
20巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 胃診断学20年の歩みと展望―早期胃癌を中心として
19巻12号(1984年12月発行)
今月の主題 消化管癌の診断におけるUS・CTの役割
19巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 膵癌の治療成績
19巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 胃生検の問題点
19巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 胃潰瘍の治癒判定
19巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 胃癌の内視鏡的治療
19巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 早期胃癌の再発死亡例をめぐって
19巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 大腸腺腫症の経過と予後
19巻5号(1984年5月発行)
受容体拮抗薬の位置づけ
19巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 肝内結石症―最近の知見をめぐって
19巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 Crohn病の経過
19巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 Panendoscopyの評価(2)
19巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 Panendoscopyの評価(1)
18巻12号(1983年12月発行)
今月の主題 Crohn病の診断
18巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 逆流性食道炎
18巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 胆囊病変をめぐる最近の知見
18巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の問題点(2)―診断の現状
18巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 大腸sm癌
18巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎―治療と経過を中心に
18巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の問題点(1)―良性病変と鑑別困難な早期癌
18巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 消化管の悪性病変と皮膚病変
18巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 急性腸炎(2)―主として感染性腸炎
18巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 症例・研究特集
18巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 急性腸炎(1)―主として抗生物質起因性大腸炎
18巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 臨床の場における上部消化管スクリーニング法―X線と内視鏡
17巻12号(1982年12月発行)
今月の主題 残胃の癌
17巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 ERCP―10年を経て―(2)技術の進歩と展開
17巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 ERCP―10年を経て―(1)診断能と限界―特に総合画像診断における位置づけ
17巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 症例・研究特集
17巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 小腸X線検査法の進歩
17巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍の病態生理
17巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 胆道系疾患の臨床(3)―早期胆道癌の診断を目指して
17巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 sm胃癌の問題点(3)―臨床と病理
17巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 胃の隆起性病変(polypoid lesion)―その形態と経過
17巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 症例・研究特集
17巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 sm胃癌の問題点(2)―陥凹型症例
17巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 sm胃癌の問題点(1)―隆起型症例
16巻12号(1981年12月発行)
今月の主題 胃のⅡb病変
16巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 胆道系疾患の臨床(2)―胆管異常を中心として
16巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 小腸腫瘍(2)
16巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 小腸腫瘍(1)
16巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 症例・研究特集
16巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 実験胃癌とヒト胃癌
16巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 胆道系疾患の臨床(1)―総胆管結石症を中心として
16巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(4)―治療と経過
16巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(3)―鑑別
16巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 虚血性腸炎の臨床と病理
16巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(2)―良性リンパ腫
16巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 早期胃癌は変貌したか
15巻12号(1980年12月発行)
今月の主題 逆追跡された胃のlinitis plastica―早期発見のために(2)
15巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 逆追跡された胃のlinitis plastica―早期発見のために(1)
15巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
15巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(1)―悪性リンパ腫
15巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 大腸憩室
15巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 消化管出血と非手術的止血
15巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 小膵癌診断への挑戦
15巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 胃のGiant Rugae
15巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 大腸の早期癌―胃早期癌と比較して
15巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 症例特集
15巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 腺境界と胃病変
15巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 胃病変の時代的変貌
14巻12号(1979年12月発行)
今月の主題 胃癌の化学療法
14巻11号(1979年11月発行)
今月の主題 急性胃病変と慢性胃潰瘍の関連をめぐって
14巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 消化管の健診を考える
14巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 症例・研究特集
14巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 微小胃癌
14巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 回盲弁近傍潰瘍(2)―Intestinal Behcetを中心に
14巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 回盲弁近傍潰瘍(1)―いわゆる“Simple Ulcer”を中心に
14巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 消化管と血管病変
14巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
14巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 X線と内視鏡との協力
14巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の反省(2)
14巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の反省(1)
13巻12号(1978年12月発行)
今月の主題 クローン病(3)―疑診例を中心に
13巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 食道・胃 境界領域癌の問題点
13巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸 併存潰瘍
13巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 腸結核(3)―疑診例を中心に
13巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 症例・研究特集
13巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 慢性膵炎
13巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍の治療の検討
13巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化管粘膜拡大観察と病態生理
13巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 クローン病(2)
13巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 クローン病(1)
13巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性胃潰瘍とその周辺
13巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 胃癌の発育経過
12巻12号(1977年12月発行)
今月の主題 腸結核(2)―大腸を主として
12巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 腸結核(1)―小腸を主として
12巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
12巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 胃癌の浸潤範囲・深達度の判定(2)
12巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 胃癌の浸潤範囲・深達度の判定(1)
12巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 残胃病変
12巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 胆道癌の診断と治療
12巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 高齢者の胃病変の特徴
12巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
12巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 直腸肛門部病変
12巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 S状結腸癌
12巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 胃癌―5年以後の再発
11巻12号(1976年12月発行)
今月の主題 放射線診断の最近の進歩
11巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 Endoscopic Surgery
11巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 胃スキルスの病理
11巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 症例・研究特集
11巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎―最近の趨勢
11巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 pm胃癌
11巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 食道・噴門境界部の病変
11巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 胃潰瘍癌の考え方
11巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 研究・症例特集
11巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 早期食道癌
11巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 小腸疾患の現況
11巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 早期胃癌肉眼分類の再検討
10巻12号(1975年12月発行)
今月の主題 全身性疾患と消化管
10巻11号(1975年11月発行)
今月の主題 胃の良・悪性境界領域病変
10巻10号(1975年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
10巻9号(1975年9月発行)
今月の主題 消化管疾患の新しい診断法
10巻8号(1975年8月発行)
今月の主題 クローン病とその周辺
10巻7号(1975年7月発行)
今月の主題 消化管の非上皮性腫瘍
10巻6号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管憩室
10巻5号(1975年5月発行)
今月の主題 消化管カルチノイド
10巻4号(1975年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
10巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 胃ポリープの癌化をめぐって
10巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 胃粘膜―(2)潰瘍,ポリープの背景として
10巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 胃粘膜―(1)早期胃癌の背景として
9巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 膵疾患の展望(2)―膵炎を中心に
9巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 膵疾患の展望(1)―膵炎を中心に
9巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
9巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 消化管の特殊なポリポージス
9巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 胃潰瘍の最近の問題点
9巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 盲腸・上行結腸の診断
9巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 胃を除く上腹部腫瘤の診断
9巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 症例・研究特集
9巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 意外な進展を示す胃癌
9巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 内視鏡的ポリペクトミー
9巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 食道・腸の生検
9巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 胃の生検
8巻12号(1973年12月発行)
今月の主題 十二指腸疾患の最新の診断
8巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 症例・研究特集
8巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 表層拡大型胃癌
8巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 胃潰瘍の良・悪性の鑑別診断
8巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 早期胃癌と線状潰瘍の合併
8巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 消化管出血の緊急診断
8巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 大腸疾患 最新の話題
8巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 胃癌の経過
8巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
8巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内視鏡的膵・胆管造影
8巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 消化管の悪性リンパ腫
8巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 急性胃病変の臨床
7巻12号(1972年12月発行)
今月の主題 腸の潰瘍性病変
7巻11号(1972年11月発行)
今月の主題 十二指腸乳頭部病変
7巻10号(1972年10月発行)
今月の主題 食道炎と食道静脈瘤
7巻9号(1972年9月発行)
今月の主題 胃集検で発見された胃潰瘍
7巻8号(1972年8月発行)
今月の主題 症例・研究特集
7巻7号(1972年7月発行)
今月の主題 若年者の消化管癌
7巻6号(1972年6月発行)
今月の主題 胃癌浸潤程度の診断
7巻5号(1972年5月発行)
今月の主題 悪性サイクル
7巻4号(1972年4月発行)
今月の主題 早期胃癌肉眼分類起草10年
7巻3号(1972年3月発行)
今月の主題 早期胃癌臨床診断の実態(診断成績の推移と問題点)
7巻2号(1972年2月発行)
今月の主題 Ⅲ型早期胃癌
7巻1号(1972年1月発行)
今月の主題 Ⅱb型早期胃癌
6巻13号(1971年12月発行)
今月の主題 Ⅱa+Ⅱc型早期胃癌
6巻12号(1971年11月発行)
今月の主題 症例・研究特集
6巻11号(1971年10月発行)
今月の主題 胃前壁病変の診断
6巻10号(1971年9月発行)
今月の主題 便秘と下痢
6巻9号(1971年8月発行)
今月の主題 幽門部(pyloric portion)の病変
6巻8号(1971年7月発行)
今月の主題 幽門部(pyloric portion)の診断
6巻7号(1971年6月発行)
今月の主題 腸上皮化生
6巻5号(1971年5月発行)
今月の主題 症例特集号
6巻6号(1971年5月発行)
特集 胃集団検診
6巻4号(1971年4月発行)
今月の主題 消化管穿孔
6巻3号(1971年3月発行)
今月の主題 早期胃癌と紛らわしい病変
6巻2号(1971年2月発行)
今月の主題 陥凹性早期胃癌
6巻1号(1971年1月発行)
今月の主題 隆起性早期胃癌
5巻13号(1970年12月発行)
今月の主題 胃潰瘍の再発・再燃
5巻12号(1970年11月発行)
今月の主題 症例・研究 特集
5巻11号(1970年10月発行)
今月の主題 大腸の早期癌―胃を除く消化器の早期癌(2)
5巻10号(1970年9月発行)
今月の主題 胃を除く消化器の早期癌(1)
5巻9号(1970年8月発行)
今月の主題 高位の胃病変
5巻8号(1970年7月発行)
今月の主題 診断された微小胃癌
5巻7号(1970年6月発行)
特集 胃生検特集
5巻6号(1970年6月発行)
今月の主題 症例・研究 特集
5巻5号(1970年5月発行)
今月の主題 早期胃癌再発例の検討
5巻4号(1970年4月発行)
今月の主題 胆のう胆道疾患診断法の最近の進歩
5巻3号(1970年3月発行)
今月の主題 胃肉腫
5巻2号(1970年2月発行)
今月の主題 線状潰瘍
5巻1号(1970年1月発行)
今月の主題 胃癌の経過
4巻12号(1969年12月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎
4巻11号(1969年11月発行)
今月の主題 十二指腸の精密診断
4巻10号(1969年10月発行)
今月の主題 早期癌とその周辺
4巻9号(1969年9月発行)
今月の主題 胃癌の5年生存率
4巻8号(1969年8月発行)
今月の主題 X線・内視鏡で良性様所見を呈した生検陽性例
4巻7号(1969年7月発行)
今月の主題 胃の変位と変形(2)
4巻6号(1969年6月発行)
今月の主題 胃の変位と変形(1)
4巻5号(1969年5月発行)
今月の主題 稀な胃病変
4巻4号(1969年4月発行)
今月の主題 小腸の検査法
4巻3号(1969年3月発行)
今月の主題 胃癌深達度の診断と経過観察
4巻2号(1969年2月発行)
今月の主題 上部消化管の出血
4巻1号(1969年1月発行)
今月の主題 大彎側の病変
3巻13号(1968年12月発行)
今月の主題 陥凹性早期胃癌の経過
3巻12号(1968年11月発行)
今月の主題 多発胃癌
3巻11号(1968年10月発行)
今月の主題 食道
3巻10号(1968年9月発行)
今月の主題 直視下診断法
3巻9号(1968年8月発行)
今月の主題 消化管の医原性疾患
3巻8号(1968年7月発行)
今月の主題 進行癌の問題点
3巻7号(1968年6月発行)
今月の主題 胃癌の発生
3巻6号(1968年6月発行)
今月の主題 前癌病変としての胃潰瘍とポリープの意義
3巻5号(1968年5月発行)
今月の主題 胃の巨大皺襞
3巻4号(1968年4月発行)
今月の主題 胃の食物輸送機能
3巻3号(1968年3月発行)
今月の主題 大腸・直腸
3巻2号(1968年2月発行)
今月の主題 胃集団検診と早期胃癌
3巻1号(1968年1月発行)
今月の主題 早期胃癌研究の焦点
2巻12号(1967年12月発行)
今月の主題 小腸
2巻11号(1967年11月発行)
今月の主題 慢性胃炎2
2巻10号(1967年10月発行)
今月の主題 慢性胃炎1
2巻9号(1967年9月発行)
今月の主題 胃の多発性潰瘍
2巻8号(1967年8月発行)
今月の主題 難治性胃潰瘍
2巻7号(1967年7月発行)
今月の主題 胃切除後の問題
2巻6号(1967年6月発行)
今月の主題 胃のびらん
2巻5号(1967年5月発行)
今月の主題 早期胃癌の鑑別診断
2巻4号(1967年4月発行)
今月の主題 胃微細病変の診断
2巻3号(1967年3月発行)
今月の主題 胃液分泌の基礎と臨床
2巻2号(1967年2月発行)
今月の主題 十二指腸潰瘍〔2〕
2巻1号(1967年1月発行)
今月の主題 十二指腸潰瘍〔1〕
