はじめに
胃癌患者の予後の改善には早期診断と早期治療が重要と考えられ,早期胃癌の発見・鑑別・ステージングに対する内視鏡診断は大きく発展してきた.現在胃癌は進行癌よりも早期癌で発見される症例のほうが多く,早期胃癌に対する画像強調観察,拡大内視鏡を用いた診断の進歩には目を見張るものがある.しかし一方で,不幸にも胃癌が進行した状態で発見される患者がいまだに多いのも実状である.進行胃癌の組織構築は早期胃癌と大きく異なるため,その診断体系は異なるはずである.それにもかかわらず進行胃癌であっても,その診断に早期胃癌と同じ診断体系(拡大画像強調観察,周囲生検による進展範囲診断など)が適用されているのを散見する.
これまで本誌では進行胃癌の診断について,3巻8号(1968年)「進行癌の問題点」,11巻10号(1976年)「胃スキルスの病理」,15巻11・12号(1980年)「逆追跡された胃のlinitis plastica—早期発見のために」,21巻8号(1986年)「胃癌肉眼分類の問題点—進行癌を中心として」,25巻12号(1990年)「早期胃癌類似進行癌の診断」,27巻5号(1992年)「linitis plastica型胃癌診断の現状」,32巻6号(1997年)「早期胃癌から進行癌への進展」,45巻4号(2010年)「スキルス胃癌と鑑別を要する疾患」,55巻6号(2020年)「スキルス胃癌—病態と診断・治療の最前線」といった主題が組まれてきたが,進行癌全体を包括的にまとめたものはなかった.早期胃癌の診断体系が大きく変化した現在において,進行胃癌の診断体系を過去との比較において改めて見直したい.
また最近では,外科手術の方法や術式(腹腔鏡切除や噴門側切除など)も変化していたり,化学療法の適応に分子マーカーが用いられるため複数の生検採取が必須となっていたりと,診断において以前とは異なるアプローチも必要となってきている.
以上のことから,本号では現在(2024年)における進行胃癌の治療方針に則って,進行胃癌の診断体系を今一度整理し直し,更新・再構築することで現在の胃癌診療の改善に役立てることを目的とした.消化管癌の正確な臨床・病理診断には形態の詳細な観察と分析が最重要であるため,①胃癌の肉眼分類の歴史と実際の適用,②最近の進行胃癌に対する病理診断の役割,③体系的なX線・内視鏡・進行度診断体系,④進行胃癌に対する現在の外科的・薬物療法による治療方針について概説をいただいた.
雑誌目次
胃と腸59巻11号
2024年11月発行
雑誌目次
今月の主題 進行胃癌の診断と治療方針2024
序説
進行胃癌の診断と治療方針2024
著者: 上堂文也
ページ範囲:P.1612 - P.1615
主題
進行胃癌肉眼分類の歴史とその適用
著者: 下田忠和 , 小関佑介 , 吉田将雄 , 会澤大介 , 寺島雅典 , 杉野隆
ページ範囲:P.1616 - P.1630
要旨●進行胃癌の肉眼分類はBorrmannによって初めてなされ,現在もその分類が基礎となっている.当時は肉眼型と組織型の関連性はなされていないが,本稿では組織型とその浸潤形式の関連性について記載した.また当時からスキルスと肉眼分類の関係について多くの議論がなされてきたが,本稿ではそのスキルスに焦点を当ててその問題点を記載した.スキルスは本来硬い癌との意味であるが,歴史的には軟らかい癌も含まれていた時期があり,その多くは幽門部全周性に拡がった癌の一部と考えられていた.また4型胃癌の中でlinitis plasticaと記載されてきた癌の特徴についても歴史的観点からの変遷について述べた.
進行胃癌に対する病理診断・バイオマーカー検査
著者: 桑田健
ページ範囲:P.1631 - P.1643
要旨●進行胃癌に対する分子標的治療薬適応判定に必要な4つのバイオマーカーが存在する.いずれも患者の治療方針決定に直結する情報であり,日本胃癌学会は「切除不能進行・再発胃癌バイオマーカー検査の手引き」において,一次治療前にすべてのバイオマーカー検査の実施を推奨している.胃癌の病理診断に関わるすべての病理医は,これらバイオマーカー検査の意味を理解し,適切なタイミングで検査を実施できる体制を整える必要がある.あわせて,バイオマーカー検査で求められる病理組織検体の品質について,検体採取に関わる診療科を含めた施設内での情報共有も重要である.
進行胃癌のX線診断体系update
著者: 依光展和 , 園田隆賀 , 吉永繁高 , 岸大輔 , 霧生信明 , 神谷綾子 , 山里哲郎 , 冨野泰弘 , 水谷勝 , 石橋雄次 , 小田丈二 , 山村彰彦 , 入口陽介
ページ範囲:P.1644 - P.1654
要旨●かつて国民病と言われた胃癌に対し,胃X線検査は検診として死亡率減少効果を示し,診断学を発展させた.近年,画像強調内視鏡を用いた拡大内視鏡診断が発展し,粘膜表層の微細構造から胃癌を正確に診断することが可能となった.しかし胃癌には,粘膜層に存在せず,粘膜下層以深を浸潤する病変が少なからず存在する.胃X線検査では,粘膜下腫瘍様隆起,粘膜ひだ所見,変形などの所見から,粘膜下層以深の胃癌の浸潤範囲を診断することが可能であり,撮影前に描出すべき所見を熟考し,撮影手順を検討することが重要である.内視鏡検査と胃X線検査を組み合わせ,それぞれの長所を生かすことにより,正確な診断から適切な治療を選択することができる.
進行胃癌の内視鏡診断体系update
著者: 吉田将雄 , 下田忠和 , 杉野隆 , 坂東悦郎 , 小野裕之
ページ範囲:P.1655 - P.1662
要旨●胃癌の診療は時代の変遷とともに大きく変化したが,日常診療で進行胃癌に遭遇する機会は多い.進行胃癌の鑑別診断や深達度診断は,病変の肉眼形態に応じて異なってくる.また,範囲診断は術式決定に直結するため,正確な先進部の評価が求められるが,進行癌の側方進展パターンを理解することによって系統的な内視鏡診断が可能になる.一方,生検検体の大半は粘膜部分しか採取されておらず,生検に依存した範囲診断には限界があることを理解すべきである.実際には,内視鏡診断や生検診断では正確な評価が困難な場合もあり,胃X線造影検査などの他のモダリティや術中迅速断端評価を用いるなど柔軟な姿勢が求められる.
進行胃癌の進行度診断体系update
著者: 鶴丸大介 , 西牟田雄祐 , 南條勝哉 , 石神康生
ページ範囲:P.1663 - P.1672
要旨●胃癌の進行度診断は,壁深達度(T),リンパ節転移(N),その他の転移(M)を基準とする.「胃癌取扱い規約 第15版」では,胃癌の進行度は臨床分類と病理学的分類に分けられ,原発巣の進行度はT2とT3およびT4aとT4b,リンパ節転移はN0とN1〜3を鑑別する.いずれの診断も造影CTによる画像診断が基本となる.特に胃を拡張した状態で撮像する3次元CT(CT gastrography)は診断精度が高く有用である.また増強パターンにより病理組織学的診断を類推することができる.MRIは,肝転移の補助的診断として有用である.FDG-PETは,胃癌の進行度診断における貢献度は低い.
進行胃癌の治療方針update—外科医の立場から
著者: 木下敬弘
ページ範囲:P.1673 - P.1678
要旨●局所進行胃癌に対しては手術先行+術後補助化学療法が日本の標準治療であるが,高度リンパ節転移症例では術前化学療法が選択される.限局型では30mm,浸潤型では50mmの肉眼的マージンを保ち,D2郭清を伴う幽門側胃切除か胃全摘を行う.食道胃接合部癌では噴門側胃切除を選択する場合が多いが,手術アプローチを決定する際に,食道側と胃側の浸潤距離の術前評価が重要となる.大彎浸潤を来した胃上部進行胃癌では脾門郭清が必要となる.幽門側胃切除に関しては,進行胃癌であっても腹腔鏡下手術が標準治療とされている.切除可能境界胃癌では化学療法後の手術を前提とした集学的治療を行う.切除不能胃癌に対しては化学療法が第一選択であるが,ダウンステージしR0切除が可能と判断された場合,コンバージョン手術を行う場合もある.
進行胃癌の治療方針update—腫瘍内科医の立場から:進行胃癌に対する化学療法—バイオマーカーと効果判定方法も含めて
著者: 太田高志 , 岩本剛幸 , 井上貴功 , 須田貴広 , 野﨑泰俊 , 水本塁 , 有本雄貴 , 山口真二郎 , 伊藤善基 , 吉村道子 , 萩原秀紀 , 林紀夫
ページ範囲:P.1679 - P.1687
要旨●進行胃癌に対する化学療法は,免疫チェックポイント阻害薬を含めた分子標的薬剤の開発とともに予後の改善が得られるようになった.現在,胃癌には4つのバイオマーカーがあり,最適な治療レジメン選択のためには治療開始前にすべてのバイオマーカーを測定することが望ましい.生検検体を用いてバイオマーカーを測定する場合は,内視鏡医は胃癌の不均一性や肉眼型にも注意して検査を行う必要がある.化学療法の効果判定はCTを用いることで客観的な判断が可能となるが,原発巣や腹膜播種などの非標的病変の評価については,内視鏡検査や臨床症状も判断材料とすることで,より適切な評価を行うことができる.
主題症例
術前の壁深達度診断が困難であった胃粘液癌の1例
著者: 松田恵伍 , 金光高雄 , 八尾建史 , 平瀬崇之 , 小野陽一郎 , 田邉寛 , 今村健太郎 , 宮岡正喜 , 二村聡 , 久部高司
ページ範囲:P.1689 - P.1694
要旨●患者は70歳代,女性.心窩部不快感を主訴に当科でEGDを施行された.白色光通常内視鏡観察で,胃体中部大彎に30mm大の口側に深い陥凹を伴う発赤調の隆起性病変を認めた.インジゴカルミン色素撒布後観察にて,口側の陥凹内部に凹凸を認め,陥凹辺縁に棘状の不整な伸びだしが観察された.一方,病変肛門側の立ち上がりはなだらかで,表面は非腫瘍粘膜に被覆された上皮下病変様の形態を呈していた.壁強伸展下観察で,口側の陥凹に収束する数条のひだ集中を認め,わずかに台状挙上を呈していたため,低確信度で台状挙上所見陽性と判定した.一方で肛門側の上皮下病変様隆起部は送気により伸展良好であった.NBI併用拡大観察で,陥凹と周囲粘膜との間に明瞭なDLを認め,陥凹内部はirregular MV pattern plus irregular MS pattern with a DLと判定し,vessel plus surface classification systemより癌と診断可能であった.病変の壁深達度の精査目的にEUSを行い,陥凹部で第3層に低エコー域を,上皮下病変様隆起部では第3層に高エコーと低エコーの混在するモザイクパターンを呈していた.以上の内視鏡所見より,粘膜下層以深へ浸潤する早期胃癌と診断し,当院外科にて腹腔鏡補助下幽門側胃切除術を施行された.切除標本では口側の陥凹は腫瘍腺管が密に増殖しており,高分化〜中分化管状腺癌を粘膜内〜固有筋層にかけて認めた.一方,肛門側の上皮下病変様隆起部には低分化腺癌および著明な粘液結節が存在し,最深部は漿膜外まで浸潤していた.術前の壁深達度診断と実際の病理組織診断に乖離を認め,壁深達度診断が困難な1例であった.
ESDで診断した噴門部進行胃癌の1例
著者: 田邊元太郎 , 上堂文也 , 北村正紀
ページ範囲:P.1695 - P.1699
要旨●70歳代,男性.嚥下困難を主訴に前医を受診し,EGDで食道アカラシアが疑われ他院に紹介された.他院では噴門部胃癌の可能性を指摘された.EGDを再検し,噴門部病変から生検したがGroup 1であった.EUS-FNAの病理組織学的検査では腺管を認めるが,異型に乏しく癌と診断されなかった.粘膜切開生検はGroup 2で確定診断できず,当院へ紹介され受診となった.当院EGDでは,噴門部前壁に凹凸不整な発赤粘膜,壁の硬化像を認め,4型進行癌が疑われた.診断的なESDで管状腺癌と診断され,腹腔鏡下噴門側胃切除術を実施した.4型,70×70mm,tub1,pT4a(SE),INFc,Ly0,V1c,pCY1,pPM1,pDM0,Stage IVであった.
術前に早期胃癌と診断したが漿膜下層浸潤を有する進行胃癌であった1例
著者: 上田駿介 , 吉田将雄 , 下田忠和 , 小野裕之
ページ範囲:P.1700 - P.1705
要旨●患者は60歳代,女性.貧血を主訴に潰瘍を伴う未分化型癌の診断で当院を受診した.EGDで胃体中部後壁に陥凹性病変を認め,早期胃癌,0-IIc型,cT1b2(SM)N0M0と診断し,幽門側胃切除+D2郭清を行った.病理組織学的には粘膜内に低分化腺癌と印環細胞癌が増殖し,粘膜下層以深では高度の線維性間質を背景に癌細胞が漿膜まで散在性に浸潤していた.脈管侵襲陽性で進行胃癌(por2>sig),pT4a(SE)Ly1V1N0と最終診断された.本症例は早期癌類似進行胃癌であり,術前の深達度診断が難しかった.術前内視鏡検査でT1b2〜MPと診断された陥凹性病変において,早期胃癌であれば深読み,進行胃癌であれば浅読みの是正にEUSが適していると報告があり,EUSを考慮する必要があった症例と言える.
早期胃癌研究会症例
完全型腸上皮化生を背景に発生しWOSを伴う胃底腺粘膜型腺癌の1例
著者: 竹内学 , 小林雄司 , 高綱将史 , 加藤卓 , 味岡洋一
ページ範囲:P.1707 - P.1716
要旨●患者は70歳代,男性.胃体下部小彎前壁に12mm大の発赤調で立ち上がり急峻な隆起性病変を認めた.NBI拡大観察で隆起部はWOSを伴う大小不同で小型な顆粒状・乳頭状構造を呈し,背景粘膜は絨毛状構造を呈しWGA類似の白色調変化が散見された.EMRによる一括切除を行い,病理組織学的に背景粘膜はMUC2,CD10陽性の完全型腸上皮化生,隆起部表層は主にMUC5AC陽性で腺窩上皮類似異型腺管,上皮下では不規則に分岐拡張するpepsinogen IやMUC6陽性主体の胃底腺類似異型腺管を認め,胃底腺粘膜型腺癌と診断した.また,WOSとWGA類似部分はともにadipophilin陽性の脂肪滴であり,WOSでは上皮内,WGAでは上皮下間質に存在しNBI拡大観察の血管所見を反映していた.胃底腺粘膜型腺癌の多くは萎縮のない胃底腺に発生することが多いが,本病変は背景粘膜が完全型腸上皮化生であった点,胃上皮性腫瘍にWOSを認める場合は腸型形質が多いが本病変では胃型形質であった点が貴重であると考えた.
0-IIc型の通常型早期胃癌との鑑別が困難であった胃底腺粘膜型腺癌の1例
著者: 鈴木信之 , 赤澤陽一 , 上山浩也 , 上村泰子 , 山本桃子 , 岩野知世 , 内田涼太 , 宇都宮尚典 , 阿部大樹 , 沖翔太朗 , 池田厚 , 竹田努 , 上田久美子 , 北條麻理子 , 八尾隆史 , 永原章仁
ページ範囲:P.1717 - P.1726
要旨●60歳代,男性.H. pylori除菌後の定期の上部消化管内視鏡検査(EGD)で,萎縮粘膜を背景に胃体中部小彎に10mm大の境界明瞭な発赤調陥凹性病変を認め,軽度の上皮下腫瘍様隆起を伴っていた.0-IIc型の通常型早期胃癌の診断でESDを施行した.病理組織学的には,腫瘍の深層は胃底腺へ分化を示す腫瘍を認め,浅層では腺窩上皮へ分化を示す腫瘍で構成され,それぞれの層構造が保たれていたことから,胃底腺粘膜型腺癌(Ueyama・Yao分類のType 1)と診断された.辺縁部の一部は非腫瘍性上皮に被覆されていた.既感染胃粘膜を背景とした境界明瞭な発赤陥凹型の早期胃癌は,胃底腺粘膜型腺癌との鑑別が困難な症例が存在することがあるため注意が必要である.
追悼
追悼 小池盛雄先生
著者: 河内洋
ページ範囲:P.1727 - P.1728
2023年12月26日,小池盛雄先生がご逝去されました.享年83歳でした.僭越ながら弟子を自覚する者の一人として,謹んで哀悼の意を捧げます.
小池盛雄先生と私との邂逅は,私が東京医科歯科大学医学部医学科6年生であった1997年の夏でした.当時,中村恭一教授(故人)が主宰されていた病理学教室に入局することがすでに決まっていた私は,中村教授がリーダーを務めておられたJICAによる中南米病理医を対象とする研修コースの講師陣が集まる懇親会に参加する機会を得,偶然,小池先生の隣に座りご挨拶をしました.大きな声と笑顔,快活な語り口,鮮やかな白髪が印象的で,同門の大先輩であること,東京都立駒込病院病理科の部長であることを伺い,そして,「病理をやるなら駒込に来たらいいよ,俺が中村さんに頼んでおくから!」と初対面の私におっしゃってくださり,私はその場で小池先生に病理を教わりたいと強く思いました.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1609 - P.1609
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1610 - P.1610
バックナンバー・定期購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1608 - P.1608
「今月の症例」症例募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.1643 - P.1643
早期胃癌研究会 症例募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.1654 - P.1654
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1730 - P.1730
編集後記 フリーアクセス
著者: 長浜隆司
ページ範囲:P.1731 - P.1731
早期胃癌の治療の多くは内視鏡治療で行われるが,詳細な局所の診断を行い診断と治療を同じモダリティで行う早期胃癌とは異なり,進行胃癌では組織構築や治療法の違いがあるため,早期胃癌とは別のアプローチが必要となってきている.このような中,本号は,進行胃癌の診断と治療方針をいまいちど整理・更新・再構築することで現在の進行胃癌診療の改善に役立てたいとの思いから企画された.
序説で上堂は早期胃癌との組織構築や内視鏡診断の相違から進行胃癌の診断体系を改めて考え直す必要性を概説した.
奥付 フリーアクセス
ページ範囲:P.1732 - P.1732
基本情報
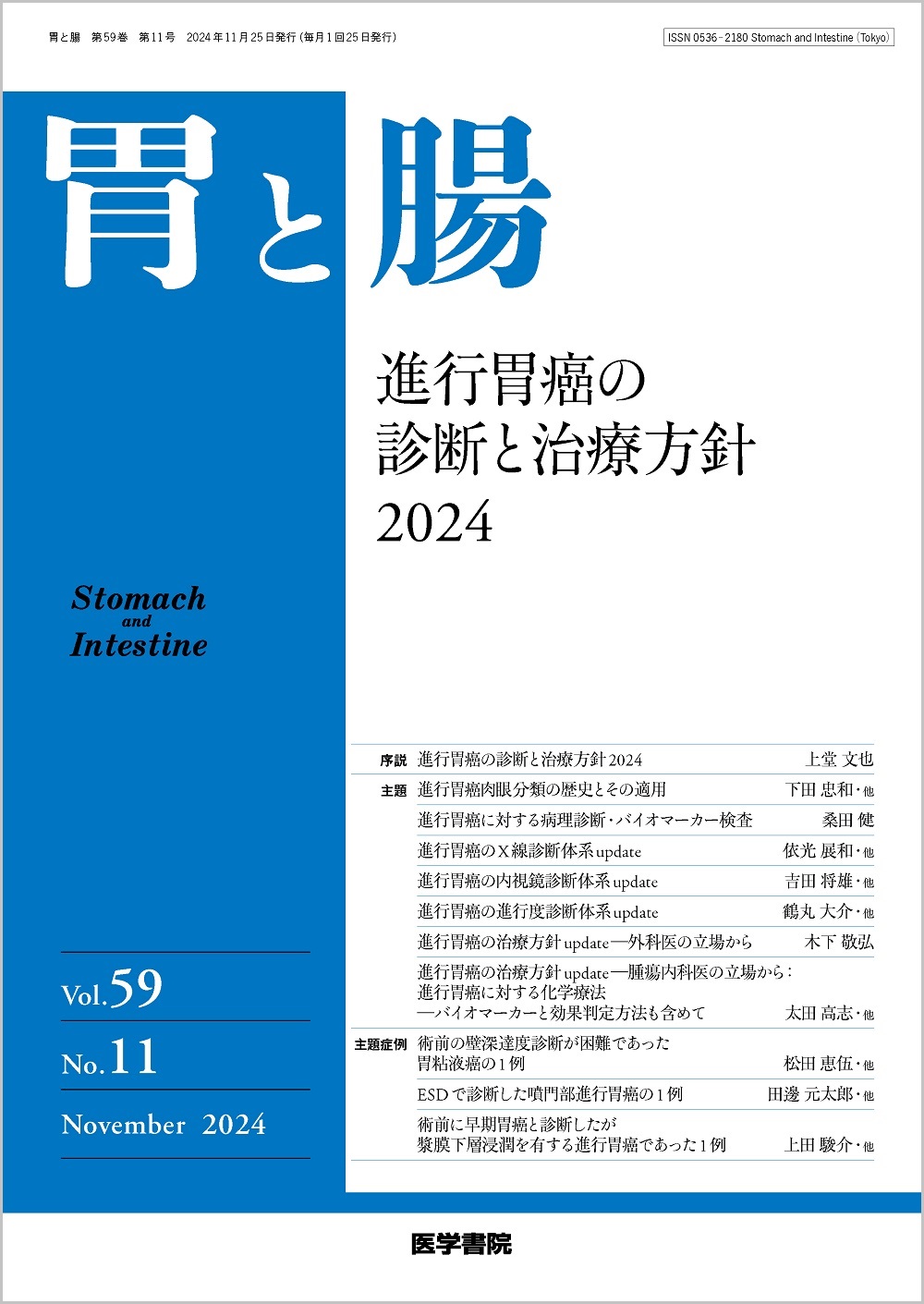
バックナンバー
59巻11号(2024年11月発行)
今月の主題 進行胃癌の診断と治療方針2024
59巻10号(2024年10月発行)
増大号 炎症性腸疾患2024
59巻9号(2024年9月発行)
今月の主題 食道運動障害の診断と治療
59巻8号(2024年8月発行)
今月の主題 臨床と病理のマリアージュ
59巻7号(2024年7月発行)
今月の主題 虚血性腸病変を整理する
59巻6号(2024年6月発行)
今月の主題 内視鏡治療後サーベイランスの現状—異時性多発病変を中心に
59巻5号(2024年5月発行)
今月の主題 胃・十二指腸神経内分泌腫瘍(NEN) up to date
59巻4号(2024年4月発行)
増大号 消化管疾患の分類2024
59巻3号(2024年3月発行)
今月の主題 上皮下発育を呈する食道病変の診断
59巻2号(2024年2月発行)
今月の主題 大腸ポリープのすべて
59巻1号(2024年1月発行)
今月の主題 自己免疫性胃炎—病期分類と画像所見
58巻12号(2023年12月発行)
今月の主題 遺伝性消化管疾患を考える
58巻11号(2023年11月発行)
今月の主題 小腸画像診断のトピックス
58巻10号(2023年10月発行)
増大号 「胃と腸」式 読影問題集2023 応用と発展—考える画像診断が身につく
58巻9号(2023年9月発行)
今月の主題 知っておくべき口腔・咽喉頭病変
58巻8号(2023年8月発行)
今月の主題 十二指腸拡大内視鏡の最新知見
58巻7号(2023年7月発行)
今月の主題 消化管リンパ増殖性疾患の診断アプローチの基本
58巻6号(2023年6月発行)
今月の主題 分類不能腸炎(IBDU)の現状と将来展望
58巻5号(2023年5月発行)
今月の主題 壁内局在からみた胃上皮下腫瘍の鑑別診断
58巻4号(2023年4月発行)
増大号 「胃と腸」式 読影問題集2023 基本と応用—考える画像診断が身につく
58巻3号(2023年3月発行)
今月の主題 食道ESD瘢痕近傍病変の診断と治療
58巻2号(2023年2月発行)
今月の主題 鋸歯状病変関連の早期大腸癌
58巻1号(2023年1月発行)
今月の主題 Non-H. pylori Helicobacter胃炎と周辺疾患
57巻13号(2022年12月発行)
今月の主題 IEEを使いこなす
57巻12号(2022年11月発行)
今月の主題 胃型形質を示す胃・十二指腸上皮性腫瘍
57巻11号(2022年10月発行)
今月の主題 食道癌診療トピックス2022
57巻10号(2022年9月発行)
今月の主題 大腸腫瘍診療の最前線
57巻9号(2022年8月発行)
今月の主題 胃癌スクリーニングの課題と将来展望
57巻8号(2022年7月発行)
今月の主題 転移性消化管腫瘍
57巻7号(2022年6月発行)
今月の主題 特殊型胃癌—組織発生と内視鏡診断
57巻6号(2022年5月発行)
今月の主題 原発性小腸癌—見えてきたその全貌
57巻5号(2022年5月発行)
増刊号 図説「胃と腸」画像診断用語集2022
57巻4号(2022年4月発行)
今月の主題 予後不良な早期消化管癌
57巻3号(2022年3月発行)
今月の主題 食道上皮内腫瘍の診断と取り扱い
57巻2号(2022年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の粘膜治癒を再考する
57巻1号(2022年1月発行)
今月の主題 H. pylori除菌後発見胃癌の診断UPDATE
56巻13号(2021年12月発行)
今月の主題 非乳頭部十二指腸腺腫・癌の診断と治療
56巻12号(2021年11月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の鑑別診断
56巻11号(2021年10月発行)
今月の主題 咽頭表在癌の内視鏡診断と治療
56巻10号(2021年9月発行)
今月の主題 胃上皮性腫瘍—組織分類・内視鏡診断の新展開
56巻9号(2021年8月発行)
今月の主題 「胃と腸」式 読影問題集—考える画像診断が身につく
56巻8号(2021年7月発行)
今月の主題 早期大腸癌内視鏡治療の新展開
56巻7号(2021年6月発行)
今月の主題 食道胃接合部腺癌の診断2021
56巻6号(2021年5月発行)
今月の主題 上部消化管非腫瘍性ポリープの内視鏡所見と病理所見
56巻5号(2021年5月発行)
増刊号 消化管診断・治療手技のすべて2021
56巻4号(2021年4月発行)
今月の主題 消化管疾患AI診断の現状
56巻3号(2021年3月発行)
今月の主題 内視鏡医も知っておくべき病理診断リファレンス—下部消化管腫瘍
56巻2号(2021年2月発行)
今月の主題 Barrett食道腺癌の内視鏡診断と治療2021
56巻1号(2021年1月発行)
今月の主題 早期胃癌内視鏡治療・適応のUPDATE
55巻13号(2020年12月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変の新展開
55巻12号(2020年11月発行)
今月の主題 高齢者早期胃癌ESDの現状と問題点
55巻11号(2020年10月発行)
今月の主題 小腸腫瘍アトラス
55巻10号(2020年9月発行)
今月の主題 食道SM扁平上皮癌治療の新展開
55巻9号(2020年8月発行)
今月の主題 一度見たら忘れられない症例
55巻8号(2020年7月発行)
今月の主題 H. pylori未感染胃の上皮性腫瘍
55巻7号(2020年6月発行)
今月の主題 薬剤関連消化管病変のトピックス
55巻6号(2020年5月発行)
今月の主題 スキルス胃癌—病態と診断・治療の最前線
55巻5号(2020年5月発行)
増刊号 消化管腫瘍の内視鏡診断2020
55巻4号(2020年4月発行)
今月の主題 内視鏡医も知っておくべき病理診断リファレンス—上部消化管腫瘍
55巻3号(2020年3月発行)
今月の主題 いま知っておきたい食道良性疾患
55巻2号(2020年2月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎関連腫瘍—診断・治療の現状と課題
55巻1号(2020年1月発行)
今月の主題 早期胃癌の範囲診断up to date
54巻13号(2019年12月発行)
今月の主題 遺伝子・免疫異常に伴う消化管病変—最新のトピックスを中心に
54巻12号(2019年11月発行)
今月の主題 上部消化管感染症—最近の話題を含めて
54巻11号(2019年10月発行)
今月の主題 大腸腫瘍の病理診断の課題と将来展望
54巻10号(2019年9月発行)
今月の主題 知っておきたい特殊な食道腫瘍・腫瘍様病変
54巻9号(2019年8月発行)
今月の主題 消化管X線造影検査のすべて—撮影手技の実際と読影のポイント
54巻8号(2019年7月発行)
今月の主題 十二指腸腺腫・癌の診断
54巻7号(2019年6月発行)
今月の主題 A型胃炎—最新の知見
54巻6号(2019年5月発行)
今月の主題 隆起型早期大腸癌の病態と診断
54巻5号(2019年5月発行)
増刊号 消化管疾患の分類2019—使い方,使われ方
54巻4号(2019年4月発行)
今月の主題 知っておきたい小腸疾患
54巻3号(2019年3月発行)
今月の主題 咽頭・食道内視鏡拡大観察の基本と最新知見
54巻2号(2019年2月発行)
今月の主題 胃・十二指腸内視鏡拡大観察の基本と最新知見
54巻1号(2019年1月発行)
今月の主題 大腸内視鏡拡大観察の基本と最新知見
53巻13号(2018年12月発行)
今月の主題 EUSによる消化管疾患の診断—現状と最新の話題
53巻12号(2018年11月発行)
今月の主題 知っておきたい十二指腸病変
53巻11号(2018年10月発行)
今月の主題 胃拡大内視鏡が変えたclinical practice
53巻10号(2018年9月発行)
今月の主題 食道表在癌の拡大内視鏡診断─食道学会分類を検証する
53巻9号(2018年8月発行)
今月の主題 消化管画像の成り立ちを知る
53巻8号(2018年7月発行)
今月の主題 対策型胃内視鏡検診の現状と問題点
53巻7号(2018年6月発行)
今月の主題 知っておきたい直腸肛門部病変
53巻6号(2018年5月発行)
今月の主題 小腸出血性疾患の診断と治療─最近の進歩
53巻5号(2018年5月発行)
増刊号 早期胃癌2018
53巻4号(2018年4月発行)
今月の主題 腸管感染症─最新の話題を含めて
53巻3号(2018年3月発行)
今月の主題 好酸球性食道炎の診断と治療
53巻2号(2018年2月発行)
今月の主題 IBDの内視鏡的粘膜治癒─評価法と臨床的意義
53巻1号(2018年1月発行)
今月の主題 胃型形質の低異型度分化型胃癌
52巻13号(2017年12月発行)
今月の主題 咽頭・頸部食道癌の診断と治療
52巻12号(2017年11月発行)
今月の主題 大腸小・微小病変に対するcold polypectomyの意義と課題
52巻11号(2017年10月発行)
今月の主題 非特異性多発性小腸潰瘍症/CEAS─遺伝子異常と類縁疾患
52巻10号(2017年9月発行)
今月の主題 胃粘膜下腫瘍の診断と治療
52巻9号(2017年8月発行)
今月の主題 大腸スクリーニングの現状と将来展望
52巻8号(2017年7月発行)
今月の主題 臨床医も知っておくべき免疫組織化学染色のすべて
52巻7号(2017年6月発行)
今月の主題 胃潰瘍は変わったか─新しい胃潰瘍学の構築を目指して
52巻6号(2017年5月発行)
今月の主題 知っておきたいまれな大腸良性疾患
52巻5号(2017年5月発行)
増刊号 図説「胃と腸」所見用語集2017
52巻4号(2017年4月発行)
今月の主題 消化管内分泌細胞腫瘍の新知見
52巻3号(2017年3月発行)
今月の主題 表在型食道胃接合部癌の治療戦略
52巻2号(2017年2月発行)
今月の主題 消化管結核の診断と治療─最近の進歩
52巻1号(2017年1月発行)
今月の主題 知っておくべき胃疾患の分類
51巻13号(2016年12月発行)
今月の主題 狭窄を来す小腸疾患の診断
51巻12号(2016年11月発行)
今月の主題 十二指腸の上皮性腫瘍
51巻11号(2016年10月発行)
今月の主題 肉芽腫を形成する消化管病変
51巻10号(2016年9月発行)
今月の主題 表在型Barrett食道癌の診断
51巻9号(2016年8月発行)
今月の主題 消化管画像プレゼンテーションの基本と実際
51巻8号(2016年7月発行)
今月の主題 消化管疾患と皮膚病変
51巻7号(2016年6月発行)
今月の主題 新しい小腸・大腸画像診断─現状と将来展望
51巻6号(2016年5月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌後発見胃癌の内視鏡的特徴
51巻5号(2016年5月発行)
増刊号 消化管拡大内視鏡診断2016
51巻4号(2016年4月発行)
今月の主題 薬剤関連消化管病変
51巻3号(2016年3月発行)
今月の主題 知っておきたいまれな大腸悪性腫瘍
51巻2号(2016年2月発行)
今月の主題 まれな食道疾患の鑑別診断
51巻1号(2016年1月発行)
今月の主題 慢性胃炎を見直す
50巻13号(2015年12月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変の取り扱い
50巻12号(2015年11月発行)
今月の主題 胃底腺型胃癌
50巻11号(2015年10月発行)
今月の主題 血管炎による消化管病変
50巻10号(2015年9月発行)
今月の主題 狭窄を来す大腸疾患─診断のプロセスを含めて
50巻9号(2015年8月発行)
今月の主題 食道胃接合部腺癌
50巻8号(2015年7月発行)
今月の主題 胃がん検診に未来はあるのか
50巻7号(2015年6月発行)
今月の主題 診断困難な炎症性腸疾患
50巻6号(2015年5月発行)
今月の主題 知っておきたいまれな胃疾患
50巻5号(2015年5月発行)
増刊号 早期消化管癌の深達度診断 2015
50巻4号(2015年4月発行)
今月の主題 早期大腸癌内視鏡治療後の中・長期経過
50巻3号(2015年3月発行)
今月の主題 胃癌範囲診断における拡大観察のピットフォール
50巻2号(2015年2月発行)
今月の主題 食道のびらん・潰瘍性病変
50巻1号(2015年1月発行)
今月の主題 消化管早期癌診断学の時代変遷─50年の歩みと展望
49巻13号(2014年12月発行)
今月の主題 胃の腺腫─診断と治療方針
49巻12号(2014年11月発行)
今月の主題 大腸LSTの診断と意義—拡大内視鏡を中心に
49巻11号(2014年10月発行)
今月の主題 胃癌ESD適応拡大病変の経過と予後
49巻10号(2014年9月発行)
今月の主題 colitic cancerの初期病変─遡及例の検討を含めて
49巻9号(2014年8月発行)
今月の主題 小腸潰瘍の鑑別診断
49巻8号(2014年7月発行)
今月の主題 表面型表層拡大型食道癌の診断と治療戦略
49巻7号(2014年6月発行)
今月の主題 大腸T1(SM)癌に対する内視鏡治療の適応拡大
49巻6号(2014年5月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori陰性胃癌
49巻5号(2014年5月発行)
増刊号 消化管悪性リンパ腫2014
49巻4号(2014年4月発行)
今月の主題 虫垂病変のすべて―非腫瘍から腫瘍まで
49巻3号(2014年3月発行)
今月の主題 消化管アミロイドーシスを見直す
49巻2号(2014年2月発行)
今月の主題 日本食道学会拡大内視鏡分類
49巻1号(2014年1月発行)
今月の主題 ESD時代の早期胃癌深達度診断
48巻13号(2013年12月発行)
今月の主題 好酸球性消化管疾患の概念と取り扱い
48巻12号(2013年11月発行)
今月の主題 虚血性腸病変
48巻11号(2013年10月発行)
今月の主題 組織混在型粘膜内胃癌の診断
48巻10号(2013年9月発行)
今月の主題 小腸の悪性腫瘍
48巻9号(2013年8月発行)
今月の主題 食道表在癌治療の最先端
48巻8号(2013年7月発行)
今月の主題 非腫瘍性大腸ポリープのすべて
48巻7号(2013年6月発行)
今月の主題 消化管内分泌細胞腫瘍の診断と治療―WHO分類との対比
48巻6号(2013年5月発行)
今月の主題 微小胃癌の診断限界に迫る
48巻5号(2013年5月発行)
特集 炎症性腸疾患 2013
48巻4号(2013年4月発行)
今月の主題 カプセル内視鏡の現状と展望
48巻3号(2013年3月発行)
今月の主題 隆起型食道癌の特徴と鑑別診断
48巻2号(2013年2月発行)
今月の主題 大腸ESDの適応と実際
48巻1号(2013年1月発行)
今月の主題 潰瘍合併早期胃癌の診断と治療
47巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 右側大腸腫瘍の臨床病理学的特徴
47巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 高齢者消化管疾患の特徴
47巻11号(2012年10月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌後の胃癌
47巻10号(2012年9月発行)
今月の主題 難治性Crohn病の特徴と治療戦略
47巻9号(2012年8月発行)
今月の主題 食道癌の発育進展─初期浸潤の病態と診断
47巻8号(2012年7月発行)
今月の主題 胃ポリープの意義と鑑別
47巻7号(2012年6月発行)
今月の主題 大腸憩室疾患
47巻6号(2012年5月発行)
今月の主題 経鼻内視鏡によるスクリーニング
47巻5号(2012年5月発行)
特集 図説 胃と腸用語集2012
47巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 消化管EUS診断の現状と新たな展開
47巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 咽頭・頸部食道癌の鑑別診断
47巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 改訂された胃生検Group分類の現状
47巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 腸管三次元CT診断の現状
46巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 難治性潰瘍性大腸炎─診療・治療の新たな展開
46巻12号(2011年11月発行)
今月の主題 Barrett食道癌の診断
46巻11号(2011年10月発行)
今月の主題 十二指腸の腫瘍性病変
46巻10号(2011年9月発行)
今月の主題 大腸SM癌に対する内視鏡治療の適応拡大
46巻9号(2011年8月発行)
今月の主題 若年者の胃・十二指腸病変の特徴
46巻8号(2011年7月発行)
今月の主題 食道の炎症性疾患
46巻7号(2011年6月発行)
今月の主題 腸管Behçet病と単純性潰瘍─診断と治療の進歩
46巻6号(2011年5月発行)
今月の主題 胃腫瘍の拡大内視鏡診断
46巻5号(2011年5月発行)
特集 食道表在癌2011
46巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変と癌化
46巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 免疫不全状態における消化管病変
46巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 NSAID起因性小腸病変
46巻1号(2011年1月発行)
今月の主題 多発胃癌─最新の知見を含めて
45巻14号(2010年12月発行)
第41巻~第45巻 総索引 2006年~2010年(平成18年~平成22年)
45巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝性消化管疾患の特徴と長期経過
45巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 特殊型胃癌の病理像と臨床的特徴
45巻11号(2010年10月発行)
今月の主題 大腸低分化腺癌の初期像とその進展
45巻10号(2010年9月発行)
今月の主題 Crohn病小腸病変に対する診断と治療の進歩
45巻9号(2010年8月発行)
今月の主題 食道表在癌の深達度診断
45巻8号(2010年7月発行)
今月の主題 直腸肛門部病変の鑑別診断─最新の知見を含めて
45巻7号(2010年6月発行)
今月の主題 低異型度分化型胃癌の診断
45巻6号(2010年5月発行)
今月の主題 側方発育型大腸腫瘍(laterally spreading tumor ; LST)─分類と意義
45巻5号(2010年4月発行)
特集 早期大腸癌2010
45巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 スキルス胃癌と鑑別を要する疾患
45巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 出血性小腸疾患─内視鏡診断・治療の最前線
45巻2号(2010年2月発行)
今月の主題 中・下咽頭表在癌の診断と治療
45巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 早期胃癌のIIb進展範囲診断
44巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 collagenous colitisの現況と新知見
44巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 消化管癌の化学・放射線療法の効果判定と問題点
44巻11号(2009年10月発行)
今月の主題 食道小扁平上皮癌の診断
44巻10号(2009年9月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎の初期病変とその進展・経過
44巻9号(2009年8月発行)
今月の主題 背景粘膜からみた胃癌ハイリスクグループ
44巻8号(2009年7月発行)
今月の主題 大腸SM癌内視鏡治療の根治基準をめぐって─病理診断の問題点と予後
44巻7号(2009年6月発行)
今月の主題 食道胃接合部腺癌の診断
44巻6号(2009年5月発行)
今月の主題 小腸疾患─小病変の診断と治療の進歩
44巻5号(2009年4月発行)
今月の主題 癌や炎症と鑑別が困難な消化管悪性リンパ腫
44巻4号(2009年4月発行)
特集 早期胃癌2009
44巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 食道扁平上皮癌に対するESDの適応と実際
44巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 特発性腸間膜静脈硬化症(idiopathic mesenteric phlebosclerosis)―概念と臨床的取り扱い
44巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 未分化型胃粘膜内癌のESD―適応拡大の可能性
43巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 大腸癌の発生・発育進展
43巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 早期胃癌発育の新たな分析─内視鏡経過例の遡及的検討から
43巻11号(2008年10月発行)
今月の主題 感染性腸炎─最近の動向と知見
43巻10号(2008年9月発行)
今月の主題 早期食道癌の診断─最近の進歩
43巻9号(2008年8月発行)
今月の主題 colitic cancer/dysplasiaの早期診断─病理組織診断の問題点も含めて
43巻8号(2008年7月発行)
今月の主題 胃癌に対する内視鏡スクリーニングの現状と将来
43巻7号(2008年6月発行)
今月の主題 消化管follicular lymphoma―診断と治療戦略
43巻6号(2008年5月発行)
今月の主題 大腸の新しい画像診断
43巻5号(2008年4月発行)
今月の主題 linitis plastica型胃癌―病態と診断・治療の最前線
43巻4号(2008年4月発行)
特集 小腸疾患2008
43巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 まれな食道良性腫瘍および腫瘍様病変
43巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 消化管GIST―診断・治療の新展開
43巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 早期胃癌ESD―適応拡大を求めて
42巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 新しい治療による炎症性腸疾患(IBD)の経過―粘膜治癒を中心に
42巻12号(2007年11月発行)
今月の主題 非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)起因性消化管病変
42巻11号(2007年10月発行)
今月の主題 ESD時代における未分化型混在早期胃癌の取り扱い
42巻10号(2007年9月発行)
今月の主題 大腸腫瘍内視鏡切除後のサーベイランスに向けて
42巻9号(2007年8月発行)
今月の主題 食道表在癌内視鏡切除後の長期成績
42巻8号(2007年7月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫―除菌無効例の特徴と治療戦略
42巻7号(2007年6月発行)
今月の主題 大腸ESDの現況と将来展望
42巻6号(2007年5月発行)
今月の主題 Helicobacter pyloriと胃癌
42巻5号(2007年4月発行)
特集 消化管の拡大内視鏡観察2007
42巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患(IBD)の上部消化管病変
42巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 大腸鋸歯状病変の発育進展と診断・取り扱い
42巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 食道扁平上皮dysplasia―診断と取り扱いをめぐって
42巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 胃分化型SM1癌の診断―垂直浸潤500μm
41巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 大腸腫瘍に対する拡大内視鏡診断の最先端
41巻12号(2006年11月発行)
今月の主題 小腸疾患診療の新たな展開
41巻11号(2006年10月発行)
今月の主題 早期胃癌に対するESDと腹腔鏡下手術の接点
41巻10号(2006年9月発行)
・sm癌の最新の診断と治療戦略
41巻9号(2006年8月発行)
今月の主題 通常内視鏡による大腸sm癌の深達度診断 垂直侵潤距離1,000μm術前診断の現状
41巻8号(2006年7月発行)
今月の主題 転移陽性胃粘膜内癌の特徴と取り扱い
41巻7号(2006年6月発行)
今月の主題 Helicobacter pyloriに起因しないとされる良性胃粘膜病変
41巻6号(2006年5月発行)
今月の主題 非定型的炎症性腸疾患―診断と経過
41巻5号(2006年4月発行)
今月の主題 陥凹性小胃癌の診断―基本から最先端まで
41巻4号(2006年4月発行)
特集 消化管内視鏡治療2006
41巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 腸管悪性リンパ腫―最近の知見
41巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 食道表在癌の内視鏡診断―最近の進歩
41巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 早期胃癌に対するESDの適応の現状と今後の展望
40巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 いわゆる側方発育型大腸腫瘍の治療法を問う
40巻12号(2005年11月発行)
今月の主題 胃癌EMR後の異時性多発を考える
40巻11号(2005年10月発行)
今月の主題 小腸内視鏡検査法の進歩
40巻10号(2005年9月発行)
今月の主題 難治性潰瘍性大腸炎―診断と治療の新知見
40巻9号(2005年8月発行)
今月の主題 表在性の中・下咽頭癌
40巻8号(2005年7月発行)
今月の主題 免疫異常と消化管病変
40巻7号(2005年6月発行)
今月の主題 胃癌化学療法の進歩と課題
40巻6号(2005年5月発行)
今月の主題 Crohn病の初期病変―診断と長期経過
40巻4号(2005年4月発行)
特集 消化管の出血性疾患2005
40巻5号(2005年4月発行)
今月の主題 切開・剥離法(ESD)時代の胃癌術前診断
40巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 特殊組織型の食道癌
40巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 大腸カルチノイド腫瘍 転移例と非転移例の比較を中心に
40巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 胃癌の時代的変遷と将来展望
39巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 大腸sm癌の内視鏡治療後の長期経過
39巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 消化管の画像診断―21世紀の展開
39巻11号(2004年10月発行)
今月の主題 胃生検診断の意義 Group分類を考える
39巻10号(2004年9月発行)
今月の主題 大腸sm癌の深達度診断―垂直浸潤1,000μm
39巻9号(2004年8月発行)
今月の主題 Barrett食道癌―表在癌の境界・深達度診断
39巻8号(2004年7月発行)
今月の主題 家族性大腸腺腫症―最近の話題
39巻7号(2004年6月発行)
今月の主題 胃癌術後の残胃癌
39巻6号(2004年5月発行)
今月の主題 深達度診断を迷わせる食道表在癌―その原因と画像の特徴
39巻5号(2004年4月発行)
今月の主題 大腸腫瘍に対する拡大内視鏡観察―V型pit pattern診断の問題点
39巻4号(2004年4月発行)
特集 消化管の粘膜下腫瘍 2004
39巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫―除菌治療後の経過と予後
39巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 Crohn病経過例における新しい治療の位置づけ
39巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 最新の早期胃癌EMR―切開・剥離法
38巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 消化管への転移性腫瘍
38巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 上部消化管拡大観察の意義
38巻11号(2003年10月発行)
今月の主題 粘膜下腫瘍様の形態を示した消化管癌
38巻10号(2003年9月発行)
今月の主題 胃腺腫の診断と治療方針
38巻9号(2003年8月発行)
今月の主題 直腸肛門部病変の鑑別診断
38巻8号(2003年7月発行)
今月の主題 経過観察からみた大腸癌の発育・進展sm癌を中心に
38巻7号(2003年6月発行)
今月の主題 消化管の炎症性疾患診断におけるX線検査の有用性
38巻6号(2003年5月発行)
今月の主題 消化管腫瘍診断におけるX線検査の有用性
38巻5号(2003年4月発行)
今月の主題 胃型早期胃癌の病理学的特徴と臨床像―分化型癌を中心に
38巻4号(2003年4月発行)
特集 全身性疾患と消化管病変
38巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 食道癌と他臓器重複癌―EMR時代を迎えて
38巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 腸型Behçet病と単純性潰瘍の長期経過
38巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 胃癌―診断と治療の最先端
37巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 胃癌と鑑別を要する炎症性疾患
37巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 Ⅰp・Ⅰsp型大腸sm癌
37巻11号(2002年10月発行)
今月の主題 消化管のvirtual endoscopy
37巻10号(2002年9月発行)
今月の主題 食道sm癌の再評価―食道温存治療の可能性を求めて
37巻9号(2002年8月発行)
今月の主題 胃粘膜内癌EMRの適応拡大と限界
37巻8号(2002年7月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と腫瘍(2)潰瘍性大腸炎以外
37巻7号(2002年6月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患と腫瘍(1)潰瘍性大腸炎
37巻6号(2002年5月発行)
今月の主題 十二指腸の非腫瘍性びまん性病変
37巻5号(2002年4月発行)
今月の主題 cap polyposisと粘膜脱症候群
37巻4号(2002年3月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌に伴う問題点
37巻3号(2002年2月発行)
特集 消化管感染症2002
37巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 4型大腸癌とその鑑別診断
37巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 食道m3・sm1癌の診断と遠隔成績
36巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 早期胃癌診療の実態と問題点
36巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 十二指腸の小病変
36巻11号(2001年10月発行)
今月の主題 sm massive以深に浸潤した10mm以下の大腸癌
36巻10号(2001年9月発行)
今月の主題 縮小治療のための胃癌の粘膜内浸潤範囲診断
36巻9号(2001年8月発行)
今月の主題 GIST(gastrointestinal stromal tumor)―概念と臨床的取り扱い
36巻8号(2001年7月発行)
今月の主題 多発食道癌
36巻7号(2001年6月発行)
今月の主題 小腸腫瘍―分類と画像所見
36巻6号(2001年5月発行)
今月の主題 早期大腸癌の深達度診断にEUSと拡大内視鏡は必要か
36巻5号(2001年4月発行)
今月の主題 早期の食道胃接合部癌
36巻4号(2001年3月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎診断基準の問題点
36巻3号(2001年2月発行)
特集 消化管癌の深達度診断
36巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 Crohn病診断基準の問題点
36巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 表層型胃悪性リンパ腫の鑑別診断―治療法選択のために
35巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 21世紀への消化管画像診断学―歩みと展望
35巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 早期大腸癌肉眼分類―統一をめざして
35巻11号(2000年10月発行)
今月の主題 胃カルチノイド―新しい考え方
35巻10号(2000年9月発行)
今月の主題 食道アカラシア
35巻9号(2000年8月発行)
今月の主題 薬剤性腸炎―最近の話題
35巻8号(2000年7月発行)
今月の主題 多発大腸癌
35巻7号(2000年6月発行)
今月の主題 胃の“pre-linitis plastica”型癌
35巻6号(2000年5月発行)
今月の主題 腸管の血管性病変―限局性腫瘍状病変を中心に
35巻5号(2000年4月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori除菌後の消化性潰瘍の経過―3年以上の症例を中心に
35巻4号(2000年3月発行)
今月の主題 食道癌の発育進展―初期病巣から粘膜下層癌へ
35巻3号(2000年2月発行)
特集 消化管ポリポーシス2000
35巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患における生検の役割
35巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の基本所見とピットフォール
34巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 大腸腫瘍の内視鏡診断は病理診断にどこまで近づくか
34巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 胃癌診断における生検の現状と問題点
34巻11号(1999年10月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫―Helicobacter pylori除菌後の経過
34巻10号(1999年9月発行)
今月の主題 Crohn病の長期経過―10年以上の症例を中心に
34巻9号(1999年8月発行)
今月の主題 早期胃癌のEUS診断
34巻8号(1999年7月発行)
今月の主題 逆流性食道炎―分類・診断・治療
34巻7号(1999年6月発行)
今月の主題 AIDSとATLの消化管病変
34巻6号(1999年5月発行)
今月の主題 大腸sm癌の内視鏡的切除をめぐって
34巻5号(1999年4月発行)
今月の主題 大腸腫瘍内視鏡的切除後の局所再発―腺腫・m癌を中心に
34巻4号(1999年3月発行)
今月の主題 胃型の分化型胃癌―病理診断とその特徴
34巻3号(1999年2月発行)
特集 消化管の画像診断―US,CT,MRIの役割
34巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 Barrett上皮と食道腺癌
34巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 Ⅱ型早期大腸癌肉眼分類の問題点
33巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 胃癌EMR後の遺残再発―診断と治療
33巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 胃癌EMRの完全切除の判定基準を求めて
33巻11号(1998年10月発行)
今月の主題 早期大腸癌の組織診断―諸問題は解決されたか
33巻10号(1998年9月発行)
今月の主題 腸管子宮内膜症
33巻9号(1998年8月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎―最近の話題
33巻8号(1998年7月発行)
今月の主題 胃炎―Sydney SystemとHelicobacter pylori
33巻7号(1998年6月発行)
食道癌
33巻6号(1998年5月発行)
今月の主題 鋸歯状腺腫(serrated adenoma)とその周辺
33巻5号(1998年4月発行)
今月の主題 大腸疾患の診断に注腸X線検査は必要か
33巻4号(1998年3月発行)
今月の主題 胃癌の診断にX線検査は不要か
33巻3号(1998年2月発行)
特集 消化管悪性リンパ腫1998
33巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 消化管病変の三次元画像診断―現状と展望
33巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 「胃と腸」33年間の歩みからみた早期癌
32巻13号(1997年12月発行)
との鑑別を中心に
32巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 腺領域からみた胃病変
32巻11号(1997年10月発行)
今月の主題 Is型大腸sm癌を考える
32巻10号(1997年9月発行)
今月の主題 早期食道癌―X線診断の進歩
32巻9号(1997年8月発行)
今月の主題 胃噴門部領域の病変 (2)癌以外の病変
32巻8号(1997年7月発行)
今月の主題 胃噴門部領域の病変 (1)癌
32巻7号(1997年6月発行)
今月の主題 感染性腸炎(腸結核を除く)
32巻6号(1997年5月発行)
今月の主題 早期胃癌から進行癌への進展
32巻5号(1997年4月発行)
今月の主題 粘膜下腫瘍様の食道表在癌
32巻4号(1997年3月発行)
今月の主題 大腸腺腫症―最近の知見
32巻3号(1997年2月発行)
特集 炎症性腸疾患1997
32巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 十二指腸乳頭部癌―縮小手術をめざして
32巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 胃sm癌の細分類―治療法選択の指標として
31巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 大腸腫瘍の自然史
31巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 未分化型小胃癌はなぜ少ないか
31巻11号(1996年10月発行)
今月の主題 微細表面構造からみた大腸腫瘍の診断
31巻10号(1996年9月発行)
今月の主題 内視鏡的食道粘膜切除後の経過
31巻9号(1996年8月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的粘膜切除―適応拡大をめぐる問題点
31巻8号(1996年7月発行)
今月の主題 Helicobacter Pyloriと胃リンパ腫
31巻7号(1996年6月発行)
今月の主題 遺伝性非ポリポーシス大腸癌(HNPCC)
31巻6号(1996年5月発行)
今月の主題 食道dysplasia―経過観察例の検討
31巻5号(1996年4月発行)
今月の主題 表層拡大型早期胃癌
31巻4号(1996年3月発行)
今月の主題 新しいCrohn病診断基準(案)
31巻3号(1996年2月発行)
特集 図説 形態用語の使い方・使われ方
31巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 いわゆる表層拡大型大腸腫瘍とは
31巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 胃MALTリンパ腫
30巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 小腸画像診断の新しい展開
30巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 大腸腺腫の診断と取り扱い
30巻11号(1995年10月発行)
今月の主題 食道表在癌の発育進展―症例から学ぶ
30巻10号(1995年9月発行)
今月の主題 微小胃癌
30巻9号(1995年8月発行)
今月の主題 胃の平滑筋腫と平滑筋肉腫―新しい視点を求めて
30巻8号(1995年7月発行)
今月の主題 表層拡大型食道表在癌
30巻7号(1995年6月発行)
今月の主題 大腸の悪性リンパ腫
30巻6号(1995年5月発行)
今月の主題 粘膜下腫瘍の形態を示した胃癌
30巻5号(1995年4月発行)
今月の主題 colitic cancer―微細診断をめざして
30巻4号(1995年3月発行)
今月の主題 腸結核
30巻3号(1995年2月発行)
特集 早期食道癌1995
30巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 表面型大腸癌の発育と経過
30巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 胃癌の診断と治療―最近の動向
29巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 上部消化管病変の特徴からみた全身性疾患
29巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 大腸sm癌の細分類とその臨床
29巻11号(1994年10月発行)
今月の主題 大腸sm癌の細分類とその意義
29巻10号(1994年9月発行)
今月の主題 胃底腺領域の分化型癌
29巻9号(1994年8月発行)
今月の主題 食道のヨード不染帯
29巻8号(1994年7月発行)
今月の主題 胆管癌の画像と病理
29巻7号(1994年6月発行)
今月の主題 多発胃癌
29巻6号(1994年5月発行)
今月の主題 アフタ様病変のみのCrohn病
29巻5号(1994年4月発行)
今月の主題 大腸Crohn病―非定型例の診断を中心に
29巻4号(1994年3月発行)
今月の主題 食道粘膜癌―新しい病型分類とその診断
29巻3号(1994年2月発行)
特集 早期大腸癌1994
29巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 胃良・悪性境界病変の生検診断と治療方針
29巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 表面型大腸腫瘍―肉眼分類を考える
28巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的根治切除―適応拡大の可能性と限界を探る
28巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 消化管ポリポーシス―最近の知見
28巻11号(1993年10月発行)
今月の主題 大腸癌の深達度診断
28巻10号(1993年9月発行)
今月の主題 胃悪性リンパ腫―診断の変遷
28巻9号(1993年8月発行)
今月の主題 虚血性腸病変の新しい捉え方
28巻8号(1993年7月発行)
今月の主題 大腸癌存在診断の実態―m癌を除く
28巻7号(1993年6月発行)
今月の主題 十二指腸腫瘍
28巻6号(1993年5月発行)
今月の主題 大腸腫瘍切除後の経過追跡
28巻5号(1993年4月発行)
今月の主題 腸管アフタ様病変
28巻4号(1993年3月発行)
今月の主題 難治性胃潰瘍(2)臨床経過と難治化の要因
28巻3号(1993年2月発行)
特集 早期胃癌1993
28巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 内視鏡的食道粘膜切除術
28巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 胃癌は変わったか―その時代的変遷
27巻12号(1992年12月発行)
今月の主題 難治性胃潰瘍(1)治癒予測を中心に
27巻11号(1992年11月発行)
今月の主題 大腸pm癌
27巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 胃癌の深達度診断mとsmの鑑別―内視鏡的治療のために
27巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 逆流性食道炎を見直す
27巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 表面型大腸腫瘍の臨床診断の諸問題
27巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 出血を来した小腸病変の画像診断
27巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 早期大腸癌の病理診断の諸問題―小病変の診断を中心に
27巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 linitis plastica型胃癌診断の現状
27巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 大腸のいわゆる結節集簇様病変
27巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 腸型Behçet病・simple ulcerの経過
27巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 食道表在癌の深達度を読む
27巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 胃癌の自然史を追う―経過追跡症例から
26巻12号(1991年12月発行)
今月の主題 集検発見胃癌の特徴
26巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 膠原病と腸病変
26巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 胃癌の組織型分類とその臨床的意義
26巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 Ⅲ型早期胃癌の診断に迫る―潰瘍の良・悪性の鑑別
26巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 大腸sm癌の治療
26巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 大腸sm癌の診断
26巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 Crohn病の長期経過
26巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎の長期経過
26巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的切除(2)―内視鏡的根治切除の評価
26巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 早期胃癌の内視鏡的切除(1)―根治を目的として
26巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 食道“dysplasia”の存在を問う
26巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 早期胃癌―診断の基本と方法
25巻12号(1990年12月発行)
今月の主題 早期胃癌類似進行癌の診断
25巻11号(1990年11月発行)
今月の主題 直腸のいわゆる粘膜脱症候群
25巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 中垂腫瘤
25巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 早期食道癌を問う
25巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 臨床経過からみた胃生検の問題点
25巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 小さな表面型(Ⅱ型)大腸上皮性腫瘍
25巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の鑑別診断(2)―大腸病変を中心に
25巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 炎症性腸疾患の鑑別診断(1)―小腸・回盲部病変を中心に
25巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 Barrett食道
25巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 胃癌の切除範囲をどう決めるのか
25巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 膵囊胞性疾患―動態診断の基礎と臨床
25巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 上部消化管X線検査の現状の反省と将来―検査モデルを求めて
24巻12号(1989年12月発行)
今月の主題 小さな未分化型胃癌―分化型と比較して
24巻11号(1989年11月発行)
今月の主題 いわゆる“十二指腸炎”の諸問題
24巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 分類困難な腸の炎症性疾患
24巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 胃粘膜下腫瘍の診断―現況と進歩
24巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 腸のカルチノイド
24巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 胆道疾患の非手術的治療の進歩
24巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 急性胃粘膜病変(AGML)
24巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 腸管の悪性リンパ腫(2)
24巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 胃・十二指腸出血の非手術的治療
24巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 大腸腺腫と癌(2)
24巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 大腸腺腫と癌(1)
24巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 噴門部陥凹型早期胃癌の診断
23巻12号(1988年12月発行)
今月の主題 腸管の悪性リンパ腫(1)
23巻11号(1988年11月発行)
今月の主題 食道癌の発育進展―逆追跡症例を中心に
23巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 十二指腸乳頭部癌
23巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 大腸内視鏡検査法―手技を中心として
23巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 小さな膵癌―小病変の鑑別診断をめぐって
23巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 微小胃癌診断―10年の進歩
23巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 びまん浸潤型大腸癌と転移性大腸癌
23巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍と超音波内視鏡
23巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 内視鏡的胃粘膜切除の臨床―ジャンボ・バイオプシーをめぐって
23巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 消化管形態診断の将来はどうあるべきか
23巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 消化管のアミロイドーシス(2)
23巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 X線・内視鏡所見と切除標本・病理所見との対比(胃)
22巻12号(1987年12月発行)
今月の主題 早期食道癌の問題点
22巻11号(1987年11月発行)
今月の主題 消化管のアミロイドーシス(1)
22巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 胃のDieulafoy潰瘍
22巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 胃底腺領域の癌―Ⅱcを中心として
22巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 陥凹型早期大腸癌
22巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 腸結核と癌
22巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 胃の腺腫とは―現状と問題点
22巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 胆囊癌の診断―発育進展を中心に
22巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 小さな大腸癌―早期診断のために
22巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 直腸・肛門部病変の新しい診かた
22巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 陥凹型早期胃癌の深達度診断
22巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 電子スコープの現況
21巻12号(1986年12月発行)
今月の主題 大腸のvillous tumor
21巻11号(1986年11月発行)
今月の主題 消化性潰瘍のトピックス(2)―胃粘膜防御機構を中心に
21巻10号(1986年10月発行)
受容体拮抗薬のもたらした諸問題
21巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎と大腸癌
21巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 胃癌肉眼分類の問題点―進行癌を中心として
21巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 膵の囊胞性疾患―その診断の進歩
21巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 大腸生検の問題点―炎症性疾患の経過を中心に
21巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 早期胆嚢癌―その診断の進歩
21巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 Ⅱb型早期胃癌の診断
21巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 大腸早期癌診断におけるX線と内視鏡との比較
21巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 消化管の“比較診断学”を求めて(2)
21巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 消化管の“比較診断学”を求めて(1)
20巻12号(1985年12月発行)
今月の主題 食道癌の早期診断
20巻11号(1985年11月発行)
今月の主題 内視鏡的乳頭括約筋切開術の長期成績
20巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 大腸ポリペクトミー後の経過
20巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 胃癌診断におけるルーチン検査の確かさ―部位別・大きさ別の検討
20巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 大腸癌の発育・進展
20巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 小腸診断学の進歩―実際から最先端まで
20巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 慢性胃炎をどう考えるか
20巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 食道静脈瘤の硬化療法
20巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 膵・胆道の形成異常
20巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 大腸診断学の歩みと展望
20巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 胃診断学20年の歩みと展望―良性疾患を中心として
20巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 胃診断学20年の歩みと展望―早期胃癌を中心として
19巻12号(1984年12月発行)
今月の主題 消化管癌の診断におけるUS・CTの役割
19巻11号(1984年11月発行)
今月の主題 膵癌の治療成績
19巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 胃生検の問題点
19巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 胃潰瘍の治癒判定
19巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 胃癌の内視鏡的治療
19巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 早期胃癌の再発死亡例をめぐって
19巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 大腸腺腫症の経過と予後
19巻5号(1984年5月発行)
受容体拮抗薬の位置づけ
19巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 肝内結石症―最近の知見をめぐって
19巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 Crohn病の経過
19巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 Panendoscopyの評価(2)
19巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 Panendoscopyの評価(1)
18巻12号(1983年12月発行)
今月の主題 Crohn病の診断
18巻11号(1983年11月発行)
今月の主題 逆流性食道炎
18巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 胆囊病変をめぐる最近の知見
18巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の問題点(2)―診断の現状
18巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 大腸sm癌
18巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎―治療と経過を中心に
18巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の問題点(1)―良性病変と鑑別困難な早期癌
18巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 消化管の悪性病変と皮膚病変
18巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 急性腸炎(2)―主として感染性腸炎
18巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 症例・研究特集
18巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 急性腸炎(1)―主として抗生物質起因性大腸炎
18巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 臨床の場における上部消化管スクリーニング法―X線と内視鏡
17巻12号(1982年12月発行)
今月の主題 残胃の癌
17巻11号(1982年11月発行)
今月の主題 ERCP―10年を経て―(2)技術の進歩と展開
17巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 ERCP―10年を経て―(1)診断能と限界―特に総合画像診断における位置づけ
17巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 症例・研究特集
17巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 小腸X線検査法の進歩
17巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍の病態生理
17巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 胆道系疾患の臨床(3)―早期胆道癌の診断を目指して
17巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 sm胃癌の問題点(3)―臨床と病理
17巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 胃の隆起性病変(polypoid lesion)―その形態と経過
17巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 症例・研究特集
17巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 sm胃癌の問題点(2)―陥凹型症例
17巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 sm胃癌の問題点(1)―隆起型症例
16巻12号(1981年12月発行)
今月の主題 胃のⅡb病変
16巻11号(1981年11月発行)
今月の主題 胆道系疾患の臨床(2)―胆管異常を中心として
16巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 小腸腫瘍(2)
16巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 小腸腫瘍(1)
16巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 症例・研究特集
16巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 実験胃癌とヒト胃癌
16巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 胆道系疾患の臨床(1)―総胆管結石症を中心として
16巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(4)―治療と経過
16巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(3)―鑑別
16巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 虚血性腸炎の臨床と病理
16巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(2)―良性リンパ腫
16巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 早期胃癌は変貌したか
15巻12号(1980年12月発行)
今月の主題 逆追跡された胃のlinitis plastica―早期発見のために(2)
15巻11号(1980年11月発行)
今月の主題 逆追跡された胃のlinitis plastica―早期発見のために(1)
15巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
15巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 胃リンパ腫(1)―悪性リンパ腫
15巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 大腸憩室
15巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 消化管出血と非手術的止血
15巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 小膵癌診断への挑戦
15巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 胃のGiant Rugae
15巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 大腸の早期癌―胃早期癌と比較して
15巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 症例特集
15巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 腺境界と胃病変
15巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 胃病変の時代的変貌
14巻12号(1979年12月発行)
今月の主題 胃癌の化学療法
14巻11号(1979年11月発行)
今月の主題 急性胃病変と慢性胃潰瘍の関連をめぐって
14巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 消化管の健診を考える
14巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 症例・研究特集
14巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 微小胃癌
14巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 回盲弁近傍潰瘍(2)―Intestinal Behcetを中心に
14巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 回盲弁近傍潰瘍(1)―いわゆる“Simple Ulcer”を中心に
14巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 消化管と血管病変
14巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
14巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 X線と内視鏡との協力
14巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の反省(2)
14巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 早期胃癌診断の反省(1)
13巻12号(1978年12月発行)
今月の主題 クローン病(3)―疑診例を中心に
13巻11号(1978年11月発行)
今月の主題 食道・胃 境界領域癌の問題点
13巻10号(1978年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸 併存潰瘍
13巻9号(1978年9月発行)
今月の主題 腸結核(3)―疑診例を中心に
13巻8号(1978年8月発行)
今月の主題 症例・研究特集
13巻7号(1978年7月発行)
今月の主題 慢性膵炎
13巻6号(1978年6月発行)
今月の主題 胃・十二指腸潰瘍の治療の検討
13巻5号(1978年5月発行)
今月の主題 消化管粘膜拡大観察と病態生理
13巻4号(1978年4月発行)
今月の主題 クローン病(2)
13巻3号(1978年3月発行)
今月の主題 クローン病(1)
13巻2号(1978年2月発行)
今月の主題 急性胃潰瘍とその周辺
13巻1号(1978年1月発行)
今月の主題 胃癌の発育経過
12巻12号(1977年12月発行)
今月の主題 腸結核(2)―大腸を主として
12巻11号(1977年11月発行)
今月の主題 腸結核(1)―小腸を主として
12巻10号(1977年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
12巻9号(1977年9月発行)
今月の主題 胃癌の浸潤範囲・深達度の判定(2)
12巻8号(1977年8月発行)
今月の主題 胃癌の浸潤範囲・深達度の判定(1)
12巻7号(1977年7月発行)
今月の主題 残胃病変
12巻6号(1977年6月発行)
今月の主題 胆道癌の診断と治療
12巻5号(1977年5月発行)
今月の主題 高齢者の胃病変の特徴
12巻4号(1977年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
12巻3号(1977年3月発行)
今月の主題 直腸肛門部病変
12巻2号(1977年2月発行)
今月の主題 S状結腸癌
12巻1号(1977年1月発行)
今月の主題 胃癌―5年以後の再発
11巻12号(1976年12月発行)
今月の主題 放射線診断の最近の進歩
11巻11号(1976年11月発行)
今月の主題 Endoscopic Surgery
11巻10号(1976年10月発行)
今月の主題 胃スキルスの病理
11巻9号(1976年9月発行)
今月の主題 症例・研究特集
11巻8号(1976年8月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎―最近の趨勢
11巻7号(1976年7月発行)
今月の主題 pm胃癌
11巻6号(1976年6月発行)
今月の主題 食道・噴門境界部の病変
11巻5号(1976年5月発行)
今月の主題 胃潰瘍癌の考え方
11巻4号(1976年4月発行)
今月の主題 研究・症例特集
11巻3号(1976年3月発行)
今月の主題 早期食道癌
11巻2号(1976年2月発行)
今月の主題 小腸疾患の現況
11巻1号(1976年1月発行)
今月の主題 早期胃癌肉眼分類の再検討
10巻12号(1975年12月発行)
今月の主題 全身性疾患と消化管
10巻11号(1975年11月発行)
今月の主題 胃の良・悪性境界領域病変
10巻10号(1975年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
10巻9号(1975年9月発行)
今月の主題 消化管疾患の新しい診断法
10巻8号(1975年8月発行)
今月の主題 クローン病とその周辺
10巻7号(1975年7月発行)
今月の主題 消化管の非上皮性腫瘍
10巻6号(1975年6月発行)
今月の主題 消化管憩室
10巻5号(1975年5月発行)
今月の主題 消化管カルチノイド
10巻4号(1975年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
10巻3号(1975年3月発行)
今月の主題 胃ポリープの癌化をめぐって
10巻2号(1975年2月発行)
今月の主題 胃粘膜―(2)潰瘍,ポリープの背景として
10巻1号(1975年1月発行)
今月の主題 胃粘膜―(1)早期胃癌の背景として
9巻12号(1974年12月発行)
今月の主題 膵疾患の展望(2)―膵炎を中心に
9巻11号(1974年11月発行)
今月の主題 膵疾患の展望(1)―膵炎を中心に
9巻10号(1974年10月発行)
今月の主題 症例・研究特集
9巻9号(1974年9月発行)
今月の主題 消化管の特殊なポリポージス
9巻8号(1974年8月発行)
今月の主題 胃潰瘍の最近の問題点
9巻7号(1974年7月発行)
今月の主題 盲腸・上行結腸の診断
9巻6号(1974年6月発行)
今月の主題 胃を除く上腹部腫瘤の診断
9巻5号(1974年5月発行)
今月の主題 症例・研究特集
9巻4号(1974年4月発行)
今月の主題 意外な進展を示す胃癌
9巻3号(1974年3月発行)
今月の主題 内視鏡的ポリペクトミー
9巻2号(1974年2月発行)
今月の主題 食道・腸の生検
9巻1号(1974年1月発行)
今月の主題 胃の生検
8巻12号(1973年12月発行)
今月の主題 十二指腸疾患の最新の診断
8巻11号(1973年11月発行)
今月の主題 症例・研究特集
8巻10号(1973年10月発行)
今月の主題 表層拡大型胃癌
8巻9号(1973年9月発行)
今月の主題 胃潰瘍の良・悪性の鑑別診断
8巻8号(1973年8月発行)
今月の主題 早期胃癌と線状潰瘍の合併
8巻7号(1973年7月発行)
今月の主題 消化管出血の緊急診断
8巻6号(1973年6月発行)
今月の主題 大腸疾患 最新の話題
8巻5号(1973年5月発行)
今月の主題 胃癌の経過
8巻4号(1973年4月発行)
今月の主題 症例・研究特集
8巻3号(1973年3月発行)
今月の主題 内視鏡的膵・胆管造影
8巻2号(1973年2月発行)
今月の主題 消化管の悪性リンパ腫
8巻1号(1973年1月発行)
今月の主題 急性胃病変の臨床
7巻12号(1972年12月発行)
今月の主題 腸の潰瘍性病変
7巻11号(1972年11月発行)
今月の主題 十二指腸乳頭部病変
7巻10号(1972年10月発行)
今月の主題 食道炎と食道静脈瘤
7巻9号(1972年9月発行)
今月の主題 胃集検で発見された胃潰瘍
7巻8号(1972年8月発行)
今月の主題 症例・研究特集
7巻7号(1972年7月発行)
今月の主題 若年者の消化管癌
7巻6号(1972年6月発行)
今月の主題 胃癌浸潤程度の診断
7巻5号(1972年5月発行)
今月の主題 悪性サイクル
7巻4号(1972年4月発行)
今月の主題 早期胃癌肉眼分類起草10年
7巻3号(1972年3月発行)
今月の主題 早期胃癌臨床診断の実態(診断成績の推移と問題点)
7巻2号(1972年2月発行)
今月の主題 Ⅲ型早期胃癌
7巻1号(1972年1月発行)
今月の主題 Ⅱb型早期胃癌
6巻13号(1971年12月発行)
今月の主題 Ⅱa+Ⅱc型早期胃癌
6巻12号(1971年11月発行)
今月の主題 症例・研究特集
6巻11号(1971年10月発行)
今月の主題 胃前壁病変の診断
6巻10号(1971年9月発行)
今月の主題 便秘と下痢
6巻9号(1971年8月発行)
今月の主題 幽門部(pyloric portion)の病変
6巻8号(1971年7月発行)
今月の主題 幽門部(pyloric portion)の診断
6巻7号(1971年6月発行)
今月の主題 腸上皮化生
6巻5号(1971年5月発行)
今月の主題 症例特集号
6巻6号(1971年5月発行)
特集 胃集団検診
6巻4号(1971年4月発行)
今月の主題 消化管穿孔
6巻3号(1971年3月発行)
今月の主題 早期胃癌と紛らわしい病変
6巻2号(1971年2月発行)
今月の主題 陥凹性早期胃癌
6巻1号(1971年1月発行)
今月の主題 隆起性早期胃癌
5巻13号(1970年12月発行)
今月の主題 胃潰瘍の再発・再燃
5巻12号(1970年11月発行)
今月の主題 症例・研究 特集
5巻11号(1970年10月発行)
今月の主題 大腸の早期癌―胃を除く消化器の早期癌(2)
5巻10号(1970年9月発行)
今月の主題 胃を除く消化器の早期癌(1)
5巻9号(1970年8月発行)
今月の主題 高位の胃病変
5巻8号(1970年7月発行)
今月の主題 診断された微小胃癌
5巻7号(1970年6月発行)
特集 胃生検特集
5巻6号(1970年6月発行)
今月の主題 症例・研究 特集
5巻5号(1970年5月発行)
今月の主題 早期胃癌再発例の検討
5巻4号(1970年4月発行)
今月の主題 胆のう胆道疾患診断法の最近の進歩
5巻3号(1970年3月発行)
今月の主題 胃肉腫
5巻2号(1970年2月発行)
今月の主題 線状潰瘍
5巻1号(1970年1月発行)
今月の主題 胃癌の経過
4巻12号(1969年12月発行)
今月の主題 潰瘍性大腸炎
4巻11号(1969年11月発行)
今月の主題 十二指腸の精密診断
4巻10号(1969年10月発行)
今月の主題 早期癌とその周辺
4巻9号(1969年9月発行)
今月の主題 胃癌の5年生存率
4巻8号(1969年8月発行)
今月の主題 X線・内視鏡で良性様所見を呈した生検陽性例
4巻7号(1969年7月発行)
今月の主題 胃の変位と変形(2)
4巻6号(1969年6月発行)
今月の主題 胃の変位と変形(1)
4巻5号(1969年5月発行)
今月の主題 稀な胃病変
4巻4号(1969年4月発行)
今月の主題 小腸の検査法
4巻3号(1969年3月発行)
今月の主題 胃癌深達度の診断と経過観察
4巻2号(1969年2月発行)
今月の主題 上部消化管の出血
4巻1号(1969年1月発行)
今月の主題 大彎側の病変
3巻13号(1968年12月発行)
今月の主題 陥凹性早期胃癌の経過
3巻12号(1968年11月発行)
今月の主題 多発胃癌
3巻11号(1968年10月発行)
今月の主題 食道
3巻10号(1968年9月発行)
今月の主題 直視下診断法
3巻9号(1968年8月発行)
今月の主題 消化管の医原性疾患
3巻8号(1968年7月発行)
今月の主題 進行癌の問題点
3巻7号(1968年6月発行)
今月の主題 胃癌の発生
3巻6号(1968年6月発行)
今月の主題 前癌病変としての胃潰瘍とポリープの意義
3巻5号(1968年5月発行)
今月の主題 胃の巨大皺襞
3巻4号(1968年4月発行)
今月の主題 胃の食物輸送機能
3巻3号(1968年3月発行)
今月の主題 大腸・直腸
3巻2号(1968年2月発行)
今月の主題 胃集団検診と早期胃癌
3巻1号(1968年1月発行)
今月の主題 早期胃癌研究の焦点
2巻12号(1967年12月発行)
今月の主題 小腸
2巻11号(1967年11月発行)
今月の主題 慢性胃炎2
2巻10号(1967年10月発行)
今月の主題 慢性胃炎1
2巻9号(1967年9月発行)
今月の主題 胃の多発性潰瘍
2巻8号(1967年8月発行)
今月の主題 難治性胃潰瘍
2巻7号(1967年7月発行)
今月の主題 胃切除後の問題
2巻6号(1967年6月発行)
今月の主題 胃のびらん
2巻5号(1967年5月発行)
今月の主題 早期胃癌の鑑別診断
2巻4号(1967年4月発行)
今月の主題 胃微細病変の診断
2巻3号(1967年3月発行)
今月の主題 胃液分泌の基礎と臨床
2巻2号(1967年2月発行)
今月の主題 十二指腸潰瘍〔2〕
2巻1号(1967年1月発行)
今月の主題 十二指腸潰瘍〔1〕
