ダメージ・コントロール(damage control)とは,物理的な攻撃・衝撃を受けた際に被害を最小限におさえるためにとる対策のことであり,元々は軍事的概念で敵の攻撃などによって艦艇が損傷を被った際,その被害が広がらないように施される事後の処置のことである.現在では自動車分野,医療分野,格闘技などのスポーツでも使用されている.医療分野では重度外傷において侵襲の大きい根治的手術の侵襲が加わると,致死的になりかねない場合に,呼吸と循環に関わる損傷の治療を最優先し,それ以外の部分は全身状態がよくなってから二期的に手術を行うdamage control surgery(DCS)としての概念である.
整形外科分野では,骨盤骨折や多発外傷において一期的に根治的固定を行わず,創外固定などを用いて骨折部を安定化させ,全身状態の回復を待って根治的固定を行うdamage control orthopaedics(DCO)の概念が普及している.また関節周囲骨折などで局所の軟部組織に重大な損傷がある場合,創外固定により骨折部を安定させ,軟部組織の回復を待って最終内固定を行うlocal damage controlが行われている.
雑誌目次
臨床整形外科56巻2号
2021年02月発行
雑誌目次
特集 ダメージ・コントロールとしての創外固定
緒言 フリーアクセス
著者: 澤口毅
ページ範囲:P.120 - P.120
整形外科ダメージ・コントロールの背景と意義
著者: 宮本俊之
ページ範囲:P.121 - P.125
医療の進歩とともに多発外傷患者の蘇生法は向上し,整形外科医は筋・骨格系外傷に対する速やかな根治治療を求められる時代となった.本稿では整形外科ダメージ・コントロール(damage control orthopedics;DCO)が行われ始めた歴史的な背景と意義,そして最前線の治療と本邦の現状を簡潔に述べたい.
上腕・肘関節骨折へのダメージ・コントロールとしての創外固定
著者: 松村福広
ページ範囲:P.127 - P.133
上肢骨折に対する真のダメージ・コントロールとして一時的創外固定を行うことは,下肢骨折に比べて稀である.しかしその目的は下肢骨折と同様に,全身状態または局所軟部組織状態の改善にある.上腕骨骨折や肘関節(脱臼)骨折に対するダメージ・コントロールとして一時的創外固定が適応となるのは,多発外傷に伴った開放骨折がほとんどであり,稀ではあるが重度の軟部組織損傷,汚染が強い開放骨折,外固定では骨折や関節の適合が不良な症例が当てはまる.そして安全に創外固定を行うためには,上肢の解剖に精通しておく必要がある.
前腕・手関節骨折におけるダメージ・コントロールとしての創外固定
著者: 重本顕史
ページ範囲:P.135 - P.140
前腕・手関節骨折において,ダメージ・コントロールとしての一時的創外固定の利用は,下肢骨折ほど標準化していない.しかし重症多発外傷に対するdamage control orthopaedics(DCO)を目的として,また軟部組織の状態などにより一期的内固定が困難な場合に二期的内固定を行うまでの待機ならびに軟部組織安定化を目的として,前腕・手関節骨折においても有効な手段である.本稿では,主に橈骨遠位端骨折に関するダメージ・コントロールとしての創外固定に関し,手技および合併症を含め概説する.
骨盤創外固定法—基本と適応
著者: 前川尚宜
ページ範囲:P.141 - P.146
近年では重症骨盤骨折においても,damage control resuscitation(DCR)とdamage control surgery(DCS),damage control orthopedics(DCO)を包括したdamage control strategyに基づいた戦略的治療により,その治療成績は向上してきている.DCSの中で骨盤創外固定法は,骨盤外傷診療において止血を得るためのツールであり,重要な役割を担っている.適応として不安定型骨盤骨折が挙げられているが,各骨折に対する適切なピン挿入方法を十分に理解しておくことが重要であり,装着タイミングなど各施設において適切な戦略を考えておく必要がある.
大腿骨骨折におけるダメージ・コントロールとしての創外固定
著者: 伊藤雅之
ページ範囲:P.147 - P.154
多発外傷における大腿骨骨折は体幹に近い長管骨で起こるため,全身管理の面からも早期内固定が勧められてきたが,手術によるセカンドヒットから全身状態の悪化や死亡例も認める.適応を見極めてダメージ・コントロール整形外科を行う必要があるが,最終固定までを見据えた手術計画と遂行が大切であり,施設の総合力が必要である.骨幹部骨折が主軸となるが,近位部骨折,遠位部骨折についても,それぞれ症例を提示しながら解説する.
脛骨近位部および骨幹部骨折に対するダメージ・コントロールとしての創外固定
著者: 依光正則
ページ範囲:P.155 - P.160
高エネルギー外傷によって生じた脛骨近位部骨折では,軟部組織に重大な損傷を生じている可能性が高い.多くの症例では最終内固定のために大きな展開が必要となることから,軟部組織損傷を過少に評価せず,腫脹および水疱形成を退縮させるために創外固定を用いた局所のダメージ・コントロールが必要となる.脛骨骨幹部骨折は最も開放骨折を生じやすい長管骨骨折であり,重度の開放骨折では軟部組織合併症の低減と感染の予防目的に初期治療として創外固定が必要となる.
足関節骨折に対するダメージ・コントロールとしての創外固定
著者: 松井健太郎
ページ範囲:P.161 - P.170
足関節周囲骨折に対するダメージ・コントロールとしての創外固定は,多発外傷など全身状態不良の場合に行ういわゆるダメージ・コントロールのみならず,軟部組織状態の改善を待つ場合や骨折整復位を保持する場合など,ローカルダメージ・コントロールを目的とする適応がある.二期的内固定術につなげるため,ピン挿入位置,クランプ配置などで注意を要する点がある.
“Floating” Elbow/Kneeに対するLimb Damage Control
著者: 二村謙太郎
ページ範囲:P.171 - P.176
Floating elbowもfloating kneeもfloating segment(FS)により患肢が非常に不安定な状態となる.両者とも開放骨折やそれに伴う軟部組織損傷,神経血管損傷など局所ダメージ・コントロールの観点から創外固定(external fixator:EF)が有用である.特にfloating kneeにおいては深部静脈血栓症やそれに伴う肺塞栓症,急性肺障害など全身的観点でも創外固定は必須の手段である.創外固定の固定力を高めるためにはFSにもハーフピンを挿入することになるが,神経血管束の走行には細心の注意を払う必要がある.
視座
コミュニケーションは足りていますか?
著者: 門野夕峰
ページ範囲:P.119 - P.119
2020年12月新型コロナウイルス感染症の第3波が押し寄せて,連日2,000名を超える新規感染者が報告されています.海外からはワクチンが認可され接種との話が届いていますが,安全なワクチンが日本に届くにはもう少し時間がかかるかもしれません.会食は少人数でと言われ,他人と会話する機会が少なくなったことかと思います.大学では講義はWeb配信が行われ,学生と会話することが難しくなっています.
さて話が変わりますが,安全で安心できる医療を提供するためには,適切なコミュニケーションが重要であることは周知の事実だと思います.医師同士や看護師,セラピストとの会話,患者家族への手術説明と同意取得,さまざまな場面でコミュニケーションが取られています.これらのコミュニケーションでエラーを生じると何らかのインシデントにつながる可能性が高くなります.ノンテクニカルスキルを向上させるためにTeam STEPPS(Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety)を行いましょうと,医療安全業界からは号令がかかりますが,どうも現場までは届かないようです.そもそも現在では他人とのコミュニケーションは電子化され,肉声での会話がなくても情報を伝えることができます.採血,画像診断,処方,処置など医師は時間内に電子カルテに指示入力すれば,看護師が情報を拾って実施してくれます.一言も発することなく仕事が進んでいくので,あたかもコミュニケーションが取れているように勘違いしてしまいます.この流れでは,実行されて結果が見えてはじめて指示が伝わったと確認できることになっています.急な指示変更などでは,看護師による自主的な情報の拾い上げは行われず,指示は伝わりません.「指示を変更したから確認しておいて」との一言があるかないかで,大きな違いが生まれます.紙カルテ時代に研修した自分は当たり前のことと思っていましたが,周りでは「電子カルテに入力したのに何でやってないんだ!」「時間を守ってないからでしょう!」「こっちは忙しんだから時間内にできないだろ!」「そんなきつい口調で…パワハラです!」なんて言葉が飛び交っているような….
Lecture
整形外科医の働き方改革—2024年4月に向けての基礎知識
著者: 三上容司
ページ範囲:P.179 - P.185
過重労働の改善は,政府の進める働き方改革の重要な柱である.そのために2024年4月から医師に対して時間外労働時間の罰則付き上限規制が適用される.時間外労働の上限時間は,年間960時間または年間1,860時間が見込まれている.2019〜2020年に実施された日本整形外科学会会員に対するアンケート調査によれば,多くの整形外科医の時間外労働時間がこの上限基準を超えており,現状のままでは多くの整形外科医が違法状態のまま2024年4月を迎えてしまう.整形外科医は,残された期間でタスクシフト/シェアの推進,特定看護師・診療看護師の活用,男女共同参画運動の推進などに取り組む必要がある.
境界領域/知っておきたい
日本におけるCadaver Surgical Training(CST)の現状と課題—外科系全般
著者: 八木沼洋行
ページ範囲:P.186 - P.189
はじめに
より安全で高度な医療を国民に提供するため,日本国内でも合法的に遺体を用いた手術手技研修が行えるようにしてほしいという声の高まりを受けて,2012年(平成24年)に日本外科学会と日本解剖学会が連名で「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン」(以下,ガイドライン)を策定し公開した1).これを契機に本邦における献体遺体を用いた臨床手技研修(cadaver surgical training:CST)の実施大学数,研修数とも,年々増加している.しかし一方,さまざまな課題によってCSTの実施に至っていない大学も多い.
筆者は解剖学会側委員としてガイドライン策定に関わり,公表後は所属する大学内の各種組織の立ち上げや献体登録者からの同意書の再取得などCSTの実施に至る実務を経験している.また,日本外科学会CST推進委員会委員として,各大学から提出されたCST実施報告書の審査やガイドラインの改訂にも関わってきた.本稿では,それらの経験も踏まえて,日本におけるCSTの現状と課題について解説し,その解決の方策について考察する.
連載 いまさら聞けない英語論文の書き方・30
データ取り扱いの基礎(2) エラーバー
著者: 堀内圭輔 , 千葉一裕
ページ範囲:P.190 - P.194
前回の「n」に引き続き,今回はエラーバーを取り上げます.エラーバーを利用することは論文のグラフを作成するうえで基本的なことですが,必ずしも適切になされていないのではないでしょうか.統計学の用語は可能な限り避けたいところですが,正確性を期するため,今回はやむなくいくつか解説を用意しました.読まなくとも本質はご理解いただけるかと思いますが,必要に応じてご参照ください.
Debate・2
指尖部切断—再接着術 vs. 皮弁形成術
著者: 林洸太 , 服部泰典 , 林悠太 , 四宮陸雄
ページ範囲:P.195 - P.198
症例:33歳女性
受傷機転:電動カッターを用いて作業中に誤って,カッターの刃に左母指と示指の先端部が接触し受傷した.受傷直後に当院を受診した(受傷から30分後).
既往歴:うつ病(内服あり)
臨床経験
人工股関節全置換術における杖歩行自立時の股関節筋力と術式の関連性—前外側および後側方アプローチに差異はあるか
著者: 湖東聡 , 池田崇 , 渡邉実 , 中西亮介
ページ範囲:P.199 - P.202
背景:人工股関節全置換術(THA)の術式により術後早期の筋力回復は異なるため,術後杖歩行自立時の股関節筋力を術式(前側方進入:ALSと後側方進入:PL)ごとに調査した.
対象と方法:初回片側THAを施行した22例22関節.術式による杖歩行自立日数,杖歩行自立時における術式ごとの筋力において比較検討した.
結果:杖歩行自立日数はALS群で有意に短かった.股関節筋力は術側外旋筋のみALSで有意に高値であった.
まとめ:股関節の深層筋である外旋筋群のみ差がみられたことから,杖歩行自立の早期獲得には,外旋筋群の回復が重要であると考えられる.
症例報告
手術待機中に完全骨折に至った非定型大腿骨不全骨折の2例
著者: 藤原達司 , 松村宣政 , 大浦圭一郎 , 野村幸嗣 , 西井孝
ページ範囲:P.203 - P.207
緒言:手術待機中に完全骨折に至った非定型大腿骨転子下骨折の2例を経験したので報告する.
症例:症例は47歳と52歳女性.非定型大腿骨転子下不全骨折と診断され,手術適応とした.しかしその後,手術待機中に完全骨折となり,術後経過は難渋した.
考察:cortical lucencyを認めない2例であったが,前駆症状発現から完全骨折まで,過去の報告と比較すると短期間であった.いったん完全骨折となれば難治化する傾向にある,特に転子下での非定型大腿骨不全骨折に対しては,cortical lucencyがなくとも可及的早期に手術治療を検討すべきと考える.
書評
手に映る脳,脳を宿す手—手の脳科学16章 フリーアクセス
著者: 平田仁
ページ範囲:P.208 - P.208
本書の主役である「手」のことを深く理解する人はどれほどいるだろうか? 手はとても身近な器官であり,ほぼ全ての所作にかかわり,営みのあらゆる場面を支え,そして,「第2の目」と称されるように貴重な情報収集源ともなっている.人々は「手の価値」を問われれば異口同音に「大切」と即答するだろうが,その際羅列される根拠の大半が「手」からすれば実に過小で心外なものであろう.この状況は「空気」,「水」,「伴侶」,など,あまりにも身近であるが故にことさらに考えることを忘れがちなものに共通する.「脳」は異なるもの,まれなものへの分析が大好きだが,当たり前のものへの敬意は総じて足りない.「あって当然」であり,「居ることが当たり前」なものは失って始めて真の価値に気付かれ,深い洞察の対象となるのである.
本書の原題は『The Hand and the Brain:From Lucy's Thumb to the Thought-Controlled Robotic Hand』と随分潤いを欠くものである.これに対する邦文タイトル『手に映る脳,脳を宿す手』はとても神秘的で,読者の好奇心をくすぐるものとなっている.タイトルは本の顔であり究極の要約であるが,原書と訳書でこれほどにタイトルのテイストが異なる背景には砂川融先生をはじめとする本書の翻訳にかかわった全ての人の読者へのある種の込められた思いがあるのだろう.
医療者のための成功するメンタリングガイド フリーアクセス
著者: 志水太郎
ページ範囲:P.209 - P.209
まず,本書評を書かせていただくにあたって触れるべきこと.それは何をかくそう,評者(私)の最強メンターは本書の監訳者,徳田安春先生であるということである.徳田先生はどのようなメンターであったか? それを語るには,本書で個人的に最重要章と感じる,Chapter 3をお読みいただきたい.同章の骨格となるポイント,すなわち「メンターでなく,メンティー自身の成長に有益なタスクを与えよ」「動き続けよ」「難しい対話に備えよ」「いつでもつながれるようにする」(詳細は本書をお読みください)などは,まさに往年の徳田(メンター)—志水(メンティー)の関係そのものを言語化したものである.徳田先生と出会ったのは2005年11月,東京都立墨東病院での徳田先生の講演で,自分はそのシャープかつ俯瞰的な指導に魅了され,徳田先生の行く先々に追随し,オンライン・オフライン問わず,バスの中で,飛行機の隣で,新幹線の往復で,フレッシュひたちの中で,貴重な教えをスポンジのように学んだ.宝物のような時間だった.それは自分が米国に滞在した中でも後も継続したのである.「ジャーナルではレビューとエディトリアルを毎週フォローしてください」「私が診ます,といえば丸く収まるのです」「スピードと集中がカギです」など枚挙にいとまがないが,全てメンティーの自分がメンターとして拡散すべき“グレート・アントニオ”徳田の教えである.
いきなりChapter 3にフォーカスしたが,ここで本書の構成を紹介したい.本書は全10chapterからなり,メンターへ(Chapter 1-3),メンティーへ(Chapter 4-7),そしてメンター&メンティーへ(Chapter 8-10),という3部構成に分けられている(さらに巻末に約50ページにわたるメンタリングの参考文献の数々の紹介もうれしい).とはいえ,メンターはメンティーの章を,またメンティーはメンターの章を読むことで,相手の立場をおもんぱかることができる.その結果,全ての読者は本書の全ページから重要な学びを得られるだろう.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P. - P.
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.117 - P.117
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.211 - P.211
あとがき フリーアクセス
著者: 酒井昭典
ページ範囲:P.214 - P.214
2021年がスタートして一息ついたところですが,いかがお過ごしでしょうか.昨年はCOVID-19に振り回された1年でした.昨年の学習から今年はもう少し賢明に対応し,安全で有効なワクチンを武器に最終的にはCOVID-19を鎮静化させたいものです.COVID-19後の整形外科医の働き方や学会などのイベントのあり方についても,それ以前より改善されるよう取り組んでいきたいものです.また,東京オリンピック・パラリンピック競技大会が無事に開催されることを願っています.
本号の特集は「ダメージコントロールとしての創外固定」です.2018年,一時的創外固定骨折治療術(K046-3 34,000点)が保険収載されたことで,開放骨折,関節内骨折もしくは粉砕骨折または骨盤骨折における骨折観血的手術に当たって一時的に創外固定器を用いて骨折治療を行う機会が増えてきました.今や,一時的に創外固定を行い,患者を不要なリスクに曝すことなく,全身状態の改善や局所における軟部組織の腫脹改善を待って最終的な内固定を行うこと(damage control orthopedics:DCO)は,世界的な標準治療になっています.各著者には,上肢,下肢,骨盤の骨折に対してDCOの適応や実際の治療プロトコールについて実例を挙げながら述べていただきました.早期の固定が外傷治療の基本とされたearly total careからDCOへ,そしてdamage control resuscitationの状態下でのearly appropriate careへと,外傷医療は着実に進化を遂げています.
基本情報
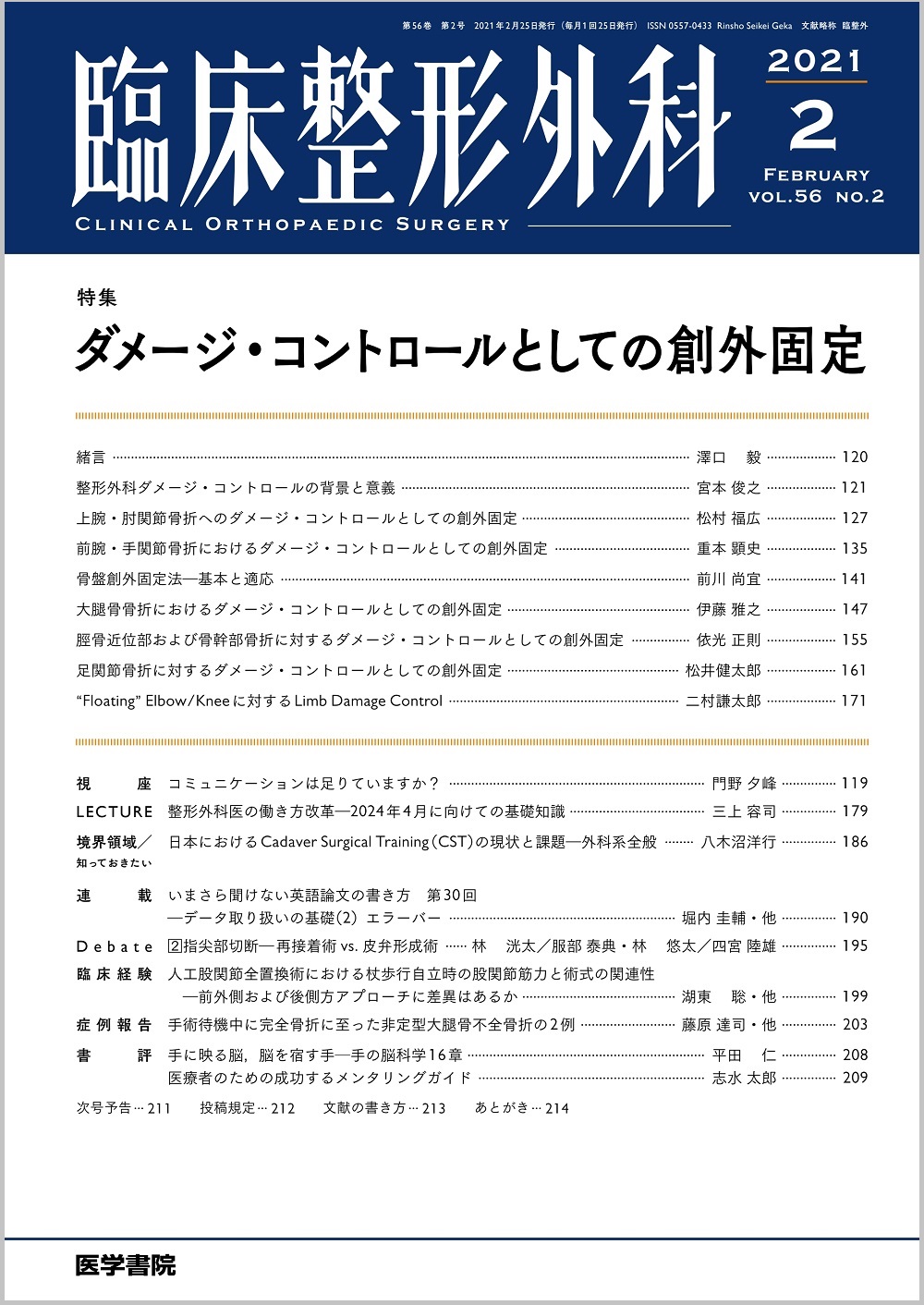
バックナンバー
59巻12号(2024年12月発行)
特集 初療対応からきれいな指再建まで 指尖部切断に対する治療
59巻10号(2024年10月発行)
特集 整形外科医のための臨床研究の進め方—立案から実施まで
59巻9号(2024年9月発行)
特集 変形性関節症に対するBiologics
59巻8号(2024年8月発行)
特集 脊損患者への投与が始まった脊髄再生医療—脊髄損傷患者に希望が見えるか
59巻7号(2024年7月発行)
特集 大規模レジストリーによる整形外科リアルワールドエビデンス構築
59巻6号(2024年6月発行)
特集 TKAにおける最新Topics
59巻5号(2024年5月発行)
増大号特集 絶対! 整形外科外傷学
59巻4号(2024年4月発行)
特集 脊椎関節炎SpAを理解する—疾患概念・診断基準・最新治療
59巻3号(2024年3月発行)
特集 知ってると知らないでは大違い 実践! 踵部痛の診断と治療
59巻2号(2024年2月発行)
特集 ここまで来た! 胸郭出口症候群の診断と治療
59巻1号(2024年1月発行)
特集 はじめたい人と極めたい人のための 超音波ガイド下インターベンション
58巻12号(2023年12月発行)
特集 がん時代の整形外科必携! 骨転移診療アップデート
58巻11号(2023年11月発行)
特集 外傷性頚部症候群—診療の最前線
58巻10号(2023年10月発行)
特集 腱板断裂の治療戦略
58巻9号(2023年9月発行)
特集 脊椎内視鏡下手術の進化・深化
58巻8号(2023年8月発行)
特集 小児の上肢をいかに診るか—よくわかる,先天性障害・外傷の診察と治療の進め方
58巻7号(2023年7月発行)
特集 股関節鏡手術のエビデンス—治療成績の現状
58巻6号(2023年6月発行)
特集 FRIの診断と治療—骨折手術後感染の疑問に答える
58巻5号(2023年5月発行)
増大号特集 できる整形外科医になる! 臨床力UP,整形外科診療のコツとエッセンス
58巻4号(2023年4月発行)
特集 疲労骨折からアスリートを守る—今,おさえておきたい“RED-S”
58巻3号(2023年3月発行)
特集 二次骨折予防に向けた治療管理
58巻2号(2023年2月発行)
特集 外反母趾診療ガイドライン改訂 外反母趾治療のトレンドを知る
58巻1号(2023年1月発行)
特集 医師の働き方改革 総チェック
57巻12号(2022年12月発行)
特集 大腿骨近位部骨折—最新トレンドとエキスパートの治療法
57巻11号(2022年11月発行)
特集 腰椎椎間板ヘルニアのCutting Edge
57巻10号(2022年10月発行)
特集 整形外科領域における人工知能の応用
57巻9号(2022年9月発行)
特集 わかる! 骨盤骨折(骨盤輪損傷) 診断+治療+エビデンスのUpdate
57巻8号(2022年8月発行)
特集 整形外科ロボット支援手術
57巻7号(2022年7月発行)
特集 整形外科医×関節リウマチ診療 今後の関わり方を考える
57巻6号(2022年6月発行)
特集 高齢者足部・足関節疾患 外来診療のコツとトピックス
57巻5号(2022年5月発行)
増大号特集 もう悩まない こどもと思春期の整形外科診療
57巻4号(2022年4月発行)
特集 骨軟部組織感染症Update
57巻3号(2022年3月発行)
特集 診断・治療に難渋したPeriprosthetic Joint Infectionへの対応
57巻2号(2022年2月発行)
特集 ロコモティブシンドローム臨床判断値に基づいた整形外科診療
57巻1号(2022年1月発行)
特集 知っておきたい足関節周囲骨折の新展開
56巻12号(2021年12月発行)
特集 整形外科手術に活かす! 創傷治療最新ストラテジー
56巻11号(2021年11月発行)
特集 末梢神経の再建2021
56巻10号(2021年10月発行)
特集 脊椎転移の治療 最前線
56巻9号(2021年9月発行)
特集 膝周囲骨切り術を成功に導く基礎知識
56巻8号(2021年8月発行)
特集 外来で役立つ 足部・足関節の超音波診療
56巻7号(2021年7月発行)
特集 手外科と労災
56巻6号(2021年6月発行)
特集 ACL再断裂に対する治療戦略
56巻5号(2021年5月発行)
増大号特集 整形外科 外来・当直 エマージェンシーマニュアル
56巻4号(2021年4月発行)
特集 成人脊柱変形 手術手技の考えかた・選びかた
56巻3号(2021年3月発行)
特集 骨折に対する積極的保存療法
56巻2号(2021年2月発行)
特集 ダメージ・コントロールとしての創外固定
56巻1号(2021年1月発行)
特集 パラスポーツ・メディシン入門
55巻12号(2020年12月発行)
特集 女性アスリートの運動器障害—悩みに答える
55巻11号(2020年11月発行)
特集 足部・足関節の画像解析—画像から病態を探る
55巻10号(2020年10月発行)
55巻9号(2020年9月発行)
特集 インプラント周囲骨折の治療戦略—THA・TKA・骨折後のプレート・髄内釘
55巻8号(2020年8月発行)
特集 整形外科×人工知能
55巻7号(2020年7月発行)
特集 脊椎手術—前方か後方か?
55巻6号(2020年6月発行)
特集 各種骨盤骨切り術とそのメリット
55巻5号(2020年5月発行)
増大号特集 臨床整形超音波学—エコー新時代、到来。
55巻4号(2020年4月発行)
特集 人工関節周囲感染の現状と展望 国際コンセンサスを踏まえて
55巻3号(2020年3月発行)
特集 頚椎を含めたグローバルアライメント
55巻2号(2020年2月発行)
特集 整形外科の職業被曝
55巻1号(2020年1月発行)
特集 新しい概念 “軟骨下脆弱性骨折”からみえてきたこと
54巻12号(2019年12月発行)
誌上シンポジウム 患者の満足度を高める関節リウマチ手術
54巻11号(2019年11月発行)
誌上シンポジウム 腰椎前方アプローチ—その光と影
54巻10号(2019年10月発行)
誌上シンポジウム がん診療×整形外科「がんロコモ」
54巻9号(2019年9月発行)
誌上シンポジウム 肩腱板断裂 画像診断の進歩
54巻8号(2019年8月発行)
誌上シンポジウム 整形外科治療の費用対効果
54巻7号(2019年7月発行)
誌上シンポジウム 骨軟部腫瘍の薬物治療アップデート
54巻6号(2019年6月発行)
誌上シンポジウム 変形性膝関節症における関節温存手術
54巻5号(2019年5月発行)
誌上シンポジウム 整形外科を牽引する女性医師たち—男女共同参画
54巻4号(2019年4月発行)
誌上シンポジウム 超高齢社会における脊椎手術
54巻3号(2019年3月発行)
誌上シンポジウム サルコペニアと整形外科
54巻2号(2019年2月発行)
誌上シンポジウム 足部・足関節疾患と外傷に対する保存療法 Evidence-Based Conservative Treatment
54巻1号(2019年1月発行)
誌上シンポジウム 小児の脊柱変形と脊椎疾患—診断・治療の急所
53巻12号(2018年12月発行)
誌上シンポジウム 外傷における人工骨の臨床
53巻11号(2018年11月発行)
誌上シンポジウム 椎間板研究の最前線
53巻10号(2018年10月発行)
誌上シンポジウム 原発巣別転移性骨腫瘍の治療戦略
53巻9号(2018年9月発行)
誌上シンポジウム 外反母趾の成績不良例から学ぶ
53巻8号(2018年8月発行)
誌上シンポジウム 椎弓形成術 アップデート
53巻7号(2018年7月発行)
誌上シンポジウム 膝前十字靱帯のバイオメカニクス
53巻6号(2018年6月発行)
誌上シンポジウム 変形性足関節症のフロントライン
53巻5号(2018年5月発行)
誌上シンポジウム 外傷後・術後骨髄炎の治療
53巻4号(2018年4月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症性脊椎骨折の治療 Cutting Edge
53巻3号(2018年3月発行)
誌上シンポジウム THAの低侵襲性と大腿骨ステム選択
53巻2号(2018年2月発行)
誌上シンポジウム 骨関節外科への3Dプリンティングの応用
53巻1号(2018年1月発行)
誌上シンポジウム 脂肪幹細胞と運動器再生
52巻12号(2017年12月発行)
誌上シンポジウム 慢性腰痛のサイエンス
52巻11号(2017年11月発行)
52巻10号(2017年10月発行)
52巻9号(2017年9月発行)
誌上シンポジウム パーキンソン病と疼痛
52巻8号(2017年8月発行)
誌上シンポジウム 創外固定でどこまでできるか?
52巻7号(2017年7月発行)
誌上シンポジウム 認知症の痛み
52巻6号(2017年6月発行)
52巻5号(2017年5月発行)
誌上シンポジウム 成人脊柱変形の目指すポイント PI-LL≦10°,PT<20°はすべての年齢層に当てはまるのか
52巻4号(2017年4月発行)
52巻3号(2017年3月発行)
誌上シンポジウム 股関節疾患の保存的治療とリハビリテーション
52巻2号(2017年2月発行)
誌上シンポジウム リバース型人工肩関節手術でわかったこと
52巻1号(2017年1月発行)
誌上シンポジウム 胸椎OPLL手術の最前線
51巻12号(2016年12月発行)
51巻11号(2016年11月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症診療—整形外科からの発信
51巻10号(2016年10月発行)
誌上シンポジウム 高気圧酸素治療の現状と可能性
51巻9号(2016年9月発行)
誌上シンポジウム THAのアプローチ
51巻8号(2016年8月発行)
誌上シンポジウム 脊椎診療ガイドライン—特徴と導入効果
51巻7号(2016年7月発行)
誌上シンポジウム 脊椎腫瘍 最近の話題
51巻6号(2016年6月発行)
51巻5号(2016年5月発行)
誌上シンポジウム 整形外科と慢性腎不全
51巻4号(2016年4月発行)
誌上シンポジウム THA後感染の予防・診断・治療の最前線
51巻3号(2016年3月発行)
誌上シンポジウム 半月変性断裂に対する治療
51巻2号(2016年2月発行)
誌上シンポジウム MISの功罪
51巻1号(2016年1月発行)
50巻12号(2015年12月発行)
特集 世界にインパクトを与えた日本の整形外科
50巻11号(2015年11月発行)
誌上シンポジウム 成人脊柱変形へのアプローチ
50巻10号(2015年10月発行)
誌上シンポジウム 人工骨移植の現状と展望
50巻9号(2015年9月発行)
誌上シンポジウム Life is Motion—整形外科医が知りたい筋肉の科学
50巻8号(2015年8月発行)
誌上シンポジウム 反復性肩関節脱臼後のスポーツ復帰
50巻7号(2015年7月発行)
50巻6号(2015年6月発行)
50巻5号(2015年5月発行)
誌上シンポジウム 股関節鏡の現状と可能性
50巻4号(2015年4月発行)
誌上シンポジウム 難治性テニス肘はこうみる
50巻3号(2015年3月発行)
誌上シンポジウム 骨軟部腫瘍における画像評価最前線
50巻2号(2015年2月発行)
誌上シンポジウム 関節リウマチ—生物学的製剤使用で変化したこと
50巻1号(2015年1月発行)
49巻12号(2014年12月発行)
49巻11号(2014年11月発行)
誌上シンポジウム 運動器画像診断の進歩
49巻10号(2014年10月発行)
誌上シンポジウム 検診からわかる整形外科疾患
49巻9号(2014年9月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症に対する治療戦略
49巻8号(2014年8月発行)
49巻7号(2014年7月発行)
49巻6号(2014年6月発行)
誌上シンポジウム MIS人工膝関節置換術の現状と展望
49巻5号(2014年5月発行)
49巻4号(2014年4月発行)
誌上シンポジウム 整形外科外傷治療の進歩
49巻3号(2014年3月発行)
誌上シンポジウム 良性腫瘍に対する最新の治療戦略
49巻2号(2014年2月発行)
49巻1号(2014年1月発行)
誌上シンポジウム 下肢壊疽の最新治療
48巻12号(2013年12月発行)
誌上シンポジウム 慢性疼痛と原因療法―どこまで追究が可能か
48巻11号(2013年11月発行)
48巻10号(2013年10月発行)
誌上シンポジウム 低出力超音波パルス(LIPUS)による骨折治療―基礎と臨床における最近の話題
48巻9号(2013年9月発行)
48巻8号(2013年8月発行)
48巻7号(2013年7月発行)
誌上シンポジウム 転移性骨腫瘍―治療の進歩
48巻6号(2013年6月発行)
48巻5号(2013年5月発行)
48巻4号(2013年4月発行)
誌上シンポジウム 腰椎変性側弯症の手術―現状と課題
48巻3号(2013年3月発行)
誌上シンポジウム 創外固定の将来展望
48巻2号(2013年2月発行)
誌上シンポジウム 高齢者の腱板断裂
48巻1号(2013年1月発行)
47巻12号(2012年12月発行)
誌上シンポジウム 高位脛骨骨切り術の適応と限界
47巻11号(2012年11月発行)
誌上シンポジウム 橈骨遠位端骨折の治療
47巻10号(2012年10月発行)
誌上シンポジウム 内視鏡診断・治療の最前線
47巻9号(2012年9月発行)
誌上シンポジウム 脊椎脊髄手術の医療安全
47巻8号(2012年8月発行)
誌上シンポジウム 難治性足部スポーツ傷害の治療
47巻7号(2012年7月発行)
47巻6号(2012年6月発行)
誌上シンポジウム 難治性良性腫瘍の治療
47巻5号(2012年5月発行)
誌上シンポジウム 重度後縦靱帯骨化症に対する術式選択と合併症
47巻4号(2012年4月発行)
誌上シンポジウム 壮年期変形性股関節症の診断と関節温存療法
47巻3号(2012年3月発行)
誌上シンポジウム 大震災と整形外科医
47巻2号(2012年2月発行)
47巻1号(2012年1月発行)
誌上シンポジウム 整形外科領域における蛍光イメージング
46巻12号(2011年12月発行)
46巻11号(2011年11月発行)
46巻10号(2011年10月発行)
46巻9号(2011年9月発行)
誌上シンポジウム 生物学的製剤が与えた関節リウマチの病態・治療の変化
46巻8号(2011年8月発行)
46巻7号(2011年7月発行)
46巻6号(2011年6月発行)
誌上シンポジウム 腰部脊柱管狭窄[症]に対する手術戦略
46巻5号(2011年5月発行)
46巻4号(2011年4月発行)
誌上シンポジウム 運動器の慢性疼痛に対する薬物療法の新展開
46巻3号(2011年3月発行)
46巻2号(2011年2月発行)
46巻1号(2011年1月発行)
45巻12号(2010年12月発行)
誌上シンポジウム 小児の肩関節疾患
45巻11号(2010年11月発行)
45巻10号(2010年10月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症診断・治療の新展開
45巻9号(2010年9月発行)
誌上シンポジウム 軟骨再生―基礎と臨床
45巻8号(2010年8月発行)
誌上シンポジウム 四肢のしびれ感
45巻7号(2010年7月発行)
45巻6号(2010年6月発行)
誌上シンポジウム 整形外科領域における抗菌薬の使い方
45巻5号(2010年5月発行)
誌上シンポジウム 整形外科医の未来像―多様化したニーズへの対応
45巻4号(2010年4月発行)
45巻3号(2010年3月発行)
誌上シンポジウム 軟部腫瘍の診断と治療
45巻2号(2010年2月発行)
誌上シンポジウム 肩腱板不全断裂
45巻1号(2010年1月発行)
誌上シンポジウム 慢性腰痛症の保存的治療
44巻12号(2009年12月発行)
44巻11号(2009年11月発行)
44巻10号(2009年10月発行)
誌上シンポジウム 整形外科術後感染の実態と予防対策
44巻9号(2009年9月発行)
誌上シンポジウム 高齢者骨折と転倒予防
44巻8号(2009年8月発行)
誌上シンポジウム 創傷処置に関する最近の進歩
44巻7号(2009年7月発行)
44巻6号(2009年6月発行)
44巻5号(2009年5月発行)
誌上シンポジウム プレート骨接合術―従来型かLCPか
44巻4号(2009年4月発行)
44巻3号(2009年3月発行)
44巻2号(2009年2月発行)
誌上シンポジウム 膝骨壊死の病態と治療
44巻1号(2009年1月発行)
誌上シンポジウム 整形外科における人工骨移植の現状と展望
43巻12号(2008年12月発行)
43巻11号(2008年11月発行)
誌上シンポジウム 外傷性肩関節脱臼
43巻10号(2008年10月発行)
誌上シンポジウム 発育期大腿骨頭の壊死性病変への対応
43巻9号(2008年9月発行)
43巻8号(2008年8月発行)
誌上シンポジウム 腰椎変性側弯の治療選択
43巻7号(2008年7月発行)
誌上シンポジウム 人工股関節術後の骨折の治療
43巻6号(2008年6月発行)
誌上シンポジウム 胸椎後縦靱帯骨化症の治療―最近の進歩
43巻5号(2008年5月発行)
誌上シンポジウム 手・肘関節鏡手術の現況と展望
43巻4号(2008年4月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症性脊椎骨折の病態
43巻3号(2008年3月発行)
誌上シンポジウム 変形性手関節症の治療
43巻2号(2008年2月発行)
誌上シンポジウム 整形外科手術におけるコンピュータナビゲーション支援
43巻1号(2008年1月発行)
誌上シンポジウム 高齢者(80歳以上)に対する人工膝関節置換術
42巻12号(2007年12月発行)
42巻11号(2007年11月発行)
42巻10号(2007年10月発行)
誌上シンポジウム 外傷性頚部症候群―最近の進歩
42巻9号(2007年9月発行)
誌上シンポジウム 骨折治療の最新知見―小侵襲骨接合術とNavigation system
42巻8号(2007年8月発行)
42巻7号(2007年7月発行)
誌上シンポジウム 人工股関節手術における骨セメント使用時の工夫と問題点
42巻6号(2007年6月発行)
誌上シンポジウム 整形外科疾患における痛みの研究
42巻5号(2007年5月発行)
誌上シンポジウム 肩こりの病態と治療
42巻4号(2007年4月発行)
誌上シンポジウム 関節軟骨とヒアルロン酸
42巻3号(2007年3月発行)
誌上シンポジウム 腰椎椎間板ヘルニア治療の最前線
42巻2号(2007年2月発行)
42巻1号(2007年1月発行)
誌上シンポジウム 変形性膝関節症―最近の進歩
41巻12号(2006年12月発行)
誌上シンポジウム 肘不安定症の病態と治療
41巻11号(2006年11月発行)
41巻10号(2006年10月発行)
41巻9号(2006年9月発行)
41巻8号(2006年8月発行)
誌上シンポジウム 腰部脊柱管狭窄症―最近の進歩
41巻7号(2006年7月発行)
誌上シンポジウム 運動器リハビリテーションの効果
41巻6号(2006年6月発行)
41巻5号(2006年5月発行)
41巻4号(2006年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学 最近の進歩 2006(第34回日本脊椎脊髄病学会より)
41巻3号(2006年3月発行)
41巻2号(2006年2月発行)
誌上シンポジウム de Quervain病の治療
41巻1号(2006年1月発行)
40巻12号(2005年12月発行)
40巻11号(2005年11月発行)
誌上シンポジウム 整形外科疾患における骨代謝マーカーの応用
40巻10号(2005年10月発行)
誌上シンポジウム 関節鏡を用いた腱板断裂の治療
40巻9号(2005年9月発行)
特別シンポジウム どうする日本の医療
40巻8号(2005年8月発行)
誌上シンポジウム 整形外科におけるリスクマネジメント
40巻7号(2005年7月発行)
40巻6号(2005年6月発行)
誌上シンポジウム 脊柱短縮術
40巻5号(2005年5月発行)
40巻4号(2005年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学 最近の進歩 2005(第33回日本脊椎脊髄病学会より)
40巻3号(2005年3月発行)
40巻2号(2005年2月発行)
誌上シンポジウム 前腕回旋障害の病態と治療
40巻1号(2005年1月発行)
39巻12号(2004年12月発行)
誌上シンポジウム 小児大腿骨頚部骨折の治療法とその成績
39巻11号(2004年11月発行)
39巻10号(2004年10月発行)
誌上シンポジウム 関節リウマチ頚椎病変の病態・治療・予後
39巻9号(2004年9月発行)
39巻8号(2004年8月発行)
誌上シンポジウム 診療ガイドラインの方向性―臨床に役立つガイドラインとは
39巻7号(2004年7月発行)
39巻6号(2004年6月発行)
39巻5号(2004年5月発行)
シンポジウム 手指の関節外骨折
39巻4号(2004年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学 最近の進歩 2004(第32回日本脊椎脊髄病学会より)
39巻3号(2004年3月発行)
39巻2号(2004年2月発行)
39巻1号(2004年1月発行)
シンポジウム 外傷に対するプライマリケア―保存療法を中心に
38巻12号(2003年12月発行)
38巻11号(2003年11月発行)
シンポジウム RSDを含む頑固なneuropathic painの病態と治療
38巻10号(2003年10月発行)
シンポジウム 整形外科医療におけるリスクマネジメント
38巻9号(2003年9月発行)
シンポジウム 全人工肩関節置換術の成績
38巻8号(2003年8月発行)
シンポジウム 難治性骨折の治療
38巻7号(2003年7月発行)
38巻6号(2003年6月発行)
シンポジウム 脊椎転移癌に対する治療法の選択
38巻5号(2003年5月発行)
シンポジウム 外傷に伴う呼吸器合併症の予防と治療
38巻4号(2003年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学最近の進歩 2003(第31回日本脊椎脊髄病学会より)
38巻3号(2003年3月発行)
シンポジウム 腰椎変性すべり症の治療
38巻2号(2003年2月発行)
シンポジウム 膝複合靱帯損傷に対する保存療法および観血的治療の選択
38巻1号(2003年1月発行)
37巻12号(2002年12月発行)
37巻11号(2002年11月発行)
シンポジウム 手術支援ロボティックシステム
37巻10号(2002年10月発行)
37巻9号(2002年9月発行)
シンポジウム 橈骨遠位端骨折の保存的治療のこつと限界
37巻8号(2002年8月発行)
37巻7号(2002年7月発行)
37巻6号(2002年6月発行)
シンポジウム スポーツ肩障害の病態と治療
37巻5号(2002年5月発行)
シンポジウム 縮小手術への挑戦―縮小手術はどこまで可能か
37巻4号(2002年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学最近の進歩(第30回日本脊椎脊髄病学会より)
37巻3号(2002年3月発行)
37巻2号(2002年2月発行)
37巻1号(2002年1月発行)
シンポジウム 足関節捻挫後遺障害の病態と治療
36巻12号(2001年12月発行)
シンポジウム 手根部骨壊死疾患の病態と治療
36巻11号(2001年11月発行)
シンポジウム 頚肩腕症候群と肩こり―疾患概念とその病態
36巻10号(2001年10月発行)
シンポジウム 下肢長管骨骨折に対するminimally invasive surgery
36巻9号(2001年9月発行)
36巻8号(2001年8月発行)
36巻7号(2001年7月発行)
36巻6号(2001年6月発行)
シンポジウム 膝複合靭帯損傷の診断と治療
36巻5号(2001年5月発行)
36巻4号(2001年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進歩―主題とパネル演題を中心に(第29回日本脊椎外科学会より)
36巻3号(2001年3月発行)
36巻2号(2001年2月発行)
シンポジウム 舟状骨偽関節に対する治療
36巻1号(2001年1月発行)
35巻13号(2000年12月発行)
シンポジウム 21世記の整形外科移植医療~その基礎から臨床応用に向けて
35巻12号(2000年11月発行)
35巻11号(2000年10月発行)
シンポジウム スポーツによる肘関節障害の診断・治療
35巻10号(2000年9月発行)
35巻9号(2000年8月発行)
35巻8号(2000年7月発行)
35巻7号(2000年6月発行)
35巻6号(2000年5月発行)
35巻5号(2000年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進歩―長期予後からみた問題点を中心として―(第28回日本脊椎外科学会より)
35巻4号(2000年3月発行)
35巻3号(2000年2月発行)
シンポジウム 変形性膝関節症の病態からみた治療法の選択
35巻2号(2000年2月発行)
35巻1号(2000年1月発行)
34巻12号(1999年12月発行)
シンポジウム 脊椎内視鏡手術―最近の進歩
34巻11号(1999年11月発行)
シンポジウム 日本における新しい人工股関節の開発
34巻10号(1999年10月発行)
34巻9号(1999年9月発行)
34巻8号(1999年8月発行)
34巻7号(1999年7月発行)
34巻6号(1999年6月発行)
シンポジウム 整形外科と運動療法
34巻5号(1999年5月発行)
34巻4号(1999年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進捗―脊椎骨切り術と脊椎再建を中心として―(第27回日本脊椎外科学会より)
34巻3号(1999年3月発行)
シンポジウム オステオポローシスの評価と治療方針
34巻2号(1999年2月発行)
シンポジウム 日本における新しい人工膝関節の開発
34巻1号(1999年1月発行)
33巻12号(1998年12月発行)
33巻11号(1998年11月発行)
33巻10号(1998年10月発行)
33巻9号(1998年9月発行)
33巻8号(1998年8月発行)
シンポジウム 骨組織に対する力学的負荷とその制御―日常臨床に生かす視点から
33巻7号(1998年7月発行)
33巻6号(1998年6月発行)
33巻5号(1998年5月発行)
33巻4号(1998年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進歩―OPLLを中心として―(第26回日本脊椎外科学会より)
33巻3号(1998年3月発行)
シンポジウム 大きな骨欠損に対する各種治療法の利害得失
33巻2号(1998年2月発行)
シンポジウム 人工股関節置換術の再手術における私の工夫
33巻1号(1998年1月発行)
32巻12号(1997年12月発行)
32巻11号(1997年11月発行)
シンポジウム 腰椎変性疾患に対するspinal instrumentation―適応と問題点―
32巻10号(1997年10月発行)
32巻9号(1997年9月発行)
32巻8号(1997年8月発行)
32巻7号(1997年7月発行)
32巻6号(1997年6月発行)
32巻5号(1997年5月発行)
32巻4号(1997年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進歩(第25回日本脊椎外科学会より)
32巻3号(1997年3月発行)
32巻2号(1997年2月発行)
シンポジウム 脊柱側弯症に対する最近の手術療法
32巻1号(1997年1月発行)
シンポジウム 骨肉腫の診断と治療のトピックス
31巻12号(1996年12月発行)
31巻11号(1996年11月発行)
31巻10号(1996年10月発行)
31巻9号(1996年9月発行)
31巻8号(1996年8月発行)
31巻7号(1996年7月発行)
31巻6号(1996年6月発行)
31巻5号(1996年5月発行)
31巻4号(1996年4月発行)
特集 脊椎外傷の最近の進歩(上位頚椎を除く)(第24回日本脊椎外科学会より)
31巻3号(1996年3月発行)
31巻2号(1996年2月発行)
31巻1号(1996年1月発行)
シンポジウム 腰椎変性すべり症の手術
30巻12号(1995年12月発行)
30巻11号(1995年11月発行)
30巻10号(1995年10月発行)
30巻9号(1995年9月発行)
30巻8号(1995年8月発行)
30巻7号(1995年7月発行)
シンポジウム 原発性脊椎悪性腫瘍の治療
30巻6号(1995年6月発行)
30巻5号(1995年5月発行)
30巻4号(1995年4月発行)
特集 上位頚椎疾患―その病態と治療(第23回日本脊椎外科学会より)
30巻3号(1995年3月発行)
シンポジウム 膝関節のUnicompartmental Arthroplasty
30巻2号(1995年2月発行)
シンポジウム 機能的電気刺激(FES)の理論と実際
30巻1号(1995年1月発行)
シンポジウム 長期成績からみたBipolar型人工股関節の適応の再検討
29巻12号(1994年12月発行)
29巻11号(1994年11月発行)
29巻10号(1994年10月発行)
29巻9号(1994年9月発行)
29巻8号(1994年8月発行)
29巻7号(1994年7月発行)
シンポジウム 慢性関節リウマチ頚椎病変
29巻6号(1994年6月発行)
シンポジウム 変性腰部脊柱管狭窄症の手術的治療と長期成績
29巻5号(1994年5月発行)
29巻4号(1994年4月発行)
特集 椎間板―基礎と臨床(第22回日本脊椎外科学会より)
29巻3号(1994年3月発行)
29巻2号(1994年2月発行)
シンポジウム 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)をめぐって
29巻1号(1994年1月発行)
シンポジウム 関節スポーツ外傷の診断と治療―最近の進歩
28巻12号(1993年12月発行)
28巻11号(1993年11月発行)
28巻10号(1993年10月発行)
28巻9号(1993年9月発行)
28巻8号(1993年8月発行)
28巻7号(1993年7月発行)
28巻6号(1993年6月発行)
28巻5号(1993年5月発行)
28巻4号(1993年4月発行)
特集 痛みをとらえる(第21回日本脊椎外科学会より)
28巻3号(1993年3月発行)
シンポジウム 癌性疼痛に対する各種治療法の適応と限界
28巻2号(1993年2月発行)
28巻1号(1993年1月発行)
シンポジウム 外反母趾の治療
27巻12号(1992年12月発行)
27巻11号(1992年11月発行)
シンポジウム 膝十字靱帯再建における素材の選択
27巻10号(1992年10月発行)
27巻9号(1992年9月発行)
27巻8号(1992年8月発行)
27巻7号(1992年7月発行)
27巻6号(1992年6月発行)
27巻5号(1992年5月発行)
シンポジウム ペルテス病の長期予後
27巻4号(1992年4月発行)
特集 主題・腰部脊柱管狭窄症/パネルI・脊椎転移性腫瘍の手術的治療/パネルII・脊椎脊髄MRI診断(第20回日本脊椎外科学会より)
27巻3号(1992年3月発行)
シンポジウム 頸部脊柱管拡大術の長期成績
27巻2号(1992年2月発行)
27巻1号(1992年1月発行)
26巻12号(1991年12月発行)
26巻11号(1991年11月発行)
26巻10号(1991年10月発行)
シンポジウム 脊髄損傷の神経病理とMRI画像
26巻9号(1991年9月発行)
26巻8号(1991年8月発行)
26巻7号(1991年7月発行)
26巻6号(1991年6月発行)
シンポジウム 悪性骨軟部腫瘍への挑戦
26巻5号(1991年5月発行)
シンポジウム 先天性股関節脱臼に対する牽引療法―その方法と後療法を具体的に
26巻4号(1991年4月発行)
特集 主題I:Spinal Dysraphism/主題II:Pedicular Screwing(第19回日本脊椎外科学会より)
26巻3号(1991年3月発行)
26巻2号(1991年2月発行)
シンポジウム 先天性股関節脱臼に対する治療法の限界と展望
26巻1号(1991年1月発行)
25巻12号(1990年12月発行)
25巻11号(1990年11月発行)
25巻10号(1990年10月発行)
25巻9号(1990年9月発行)
シンポジウム 機能的電気刺激(FES)の基礎と臨床
25巻8号(1990年8月発行)
25巻7号(1990年7月発行)
25巻6号(1990年6月発行)
25巻5号(1990年5月発行)
25巻4号(1990年4月発行)
特集 不安定腰椎(第18回日本脊椎外科研究会より)
25巻3号(1990年3月発行)
シンポジウム 予防処置導入後の乳児先天股脱
25巻2号(1990年2月発行)
25巻1号(1990年1月発行)
シンポジウム 全人工股関節置換術―セメント使用と非使用:その得失―
24巻12号(1989年12月発行)
24巻11号(1989年11月発行)
24巻10号(1989年10月発行)
24巻9号(1989年9月発行)
24巻8号(1989年8月発行)
24巻7号(1989年7月発行)
24巻6号(1989年6月発行)
24巻5号(1989年5月発行)
シンポジウム Rb法の限界
24巻4号(1989年4月発行)
特集 不安定頸椎—基礎と臨床—(第17回日本脊髄外科研究会より)
24巻3号(1989年3月発行)
24巻2号(1989年2月発行)
24巻1号(1989年1月発行)
シンポジウム 広範囲腱板断裂の再建
23巻12号(1988年12月発行)
23巻11号(1988年11月発行)
23巻10号(1988年10月発行)
シンポジウム 大腿骨頭壊死症の最近の進歩
23巻9号(1988年9月発行)
シンポジウム 変形性股関節症に対するBipolar型人工骨頭の臨床応用
23巻8号(1988年8月発行)
23巻7号(1988年7月発行)
23巻6号(1988年6月発行)
23巻5号(1988年5月発行)
23巻4号(1988年4月発行)
特集 脊柱管内靱帯骨化の病態と治療(第16回日本脊椎外科研究会より)
23巻3号(1988年3月発行)
23巻2号(1988年2月発行)
シンポジウム 日本におけるスポーツ整形外科の現状と将来
23巻1号(1988年1月発行)
22巻12号(1987年12月発行)
22巻11号(1987年11月発行)
22巻10号(1987年10月発行)
シンポジウム 骨肉腫の患肢温存療法
22巻9号(1987年9月発行)
22巻8号(1987年8月発行)
シンポジウム 椎間板注入療法の基礎
22巻7号(1987年7月発行)
シンポジウム 多発骨傷
22巻6号(1987年6月発行)
22巻5号(1987年5月発行)
シンポジウム 人工膝関節の長期成績
22巻4号(1987年4月発行)
特集 腰仙部根症状の発症機序—基礎と臨床—(第15回日本脊椎外科研究会より)
22巻3号(1987年3月発行)
シンポジウム 骨悪性線維性組織球腫
22巻2号(1987年2月発行)
シンポジウム 陳旧性肘関節周囲骨折の治療
22巻1号(1987年1月発行)
シンポジウム 陳旧性膝関節重度靱帯損傷の治療
21巻12号(1986年12月発行)
シンポジウム セメントレス人工股関節
21巻11号(1986年11月発行)
シンポジウム Bioactive Ceramics研究における最近の進歩
21巻10号(1986年10月発行)
シンポジウム 骨軟骨移植の進歩
21巻9号(1986年9月発行)
21巻8号(1986年8月発行)
21巻7号(1986年7月発行)
シンポジウム 頸椎多数回手術例の検討
21巻6号(1986年6月発行)
21巻5号(1986年5月発行)
21巻4号(1986年4月発行)
特集 脊椎・脊髄外科診断学の進歩(第14回日本脊椎外科研究会より)
21巻3号(1986年3月発行)
21巻2号(1986年2月発行)
21巻1号(1986年1月発行)
シンポジウム 骨盤臼蓋の発育
20巻12号(1985年12月発行)
20巻11号(1985年11月発行)
シンポジウム 骨肉腫の化学療法
20巻10号(1985年10月発行)
20巻9号(1985年9月発行)
20巻8号(1985年8月発行)
20巻7号(1985年7月発行)
シンポジウム 骨巨細胞腫の診断と治療
20巻6号(1985年6月発行)
20巻5号(1985年5月発行)
シンポジウム 人工股関節再置換術の問題点
20巻4号(1985年4月発行)
特集 Spinal Instrumentation(第13回脊椎外科研究会より)
20巻3号(1985年3月発行)
20巻2号(1985年2月発行)
20巻1号(1985年1月発行)
19巻12号(1984年12月発行)
19巻11号(1984年11月発行)
19巻10号(1984年10月発行)
19巻9号(1984年9月発行)
19巻8号(1984年8月発行)
19巻7号(1984年7月発行)
19巻6号(1984年6月発行)
特集 小児股関節(第22回先天股脱研究会より)
19巻5号(1984年5月発行)
19巻4号(1984年4月発行)
特集 頸部脊椎症(第12回脊椎外科研究会より)
19巻3号(1984年3月発行)
19巻2号(1984年2月発行)
19巻1号(1984年1月発行)
シンポジウム 関節鏡視下手術
18巻13号(1983年12月発行)
シンポジウム 電気刺激による骨形成
18巻12号(1983年11月発行)
18巻11号(1983年10月発行)
シンポジウム 四肢軟部腫瘍
18巻10号(1983年9月発行)
18巻9号(1983年8月発行)
シンポジウム 悪性軟部腫瘍の病理診断をめぐって
18巻8号(1983年7月発行)
18巻7号(1983年7月発行)
18巻6号(1983年6月発行)
シンポジウム 先天股脱初期整復後の側方化
18巻5号(1983年5月発行)
18巻4号(1983年4月発行)
特集 上位頸椎部の諸問題
18巻3号(1983年3月発行)
18巻2号(1983年2月発行)
18巻1号(1983年1月発行)
17巻12号(1982年12月発行)
17巻11号(1982年11月発行)
シンポジウム 人工股関節再手術例の検討
17巻10号(1982年10月発行)
17巻9号(1982年9月発行)
17巻8号(1982年8月発行)
17巻7号(1982年7月発行)
17巻6号(1982年6月発行)
17巻5号(1982年5月発行)
17巻4号(1982年4月発行)
特集 脊椎分離症・辷り症
17巻3号(1982年3月発行)
17巻2号(1982年2月発行)
17巻1号(1982年1月発行)
16巻12号(1981年12月発行)
シンポジウム 動揺性肩関節
16巻11号(1981年11月発行)
シンポジウム 特発性大腿骨頭壊死
16巻10号(1981年10月発行)
16巻9号(1981年9月発行)
シンポジウム 義肢装具をめぐる諸問題
16巻8号(1981年8月発行)
シンポジウム 脱臼ペルテスとペルテス病
16巻7号(1981年7月発行)
16巻6号(1981年6月発行)
シンポジウム 腰部脊柱管狭窄—ことにdegenerative stenosisの診断と治療
16巻5号(1981年5月発行)
16巻4号(1981年4月発行)
特集 Multiply operated back
16巻3号(1981年3月発行)
シンポジウムII Riemenbügel法不成功例の原因と対策
16巻2号(1981年2月発行)
シンポジウム 人工股関節置換術—この10年の結果をふりかえって
16巻1号(1981年1月発行)
シンポジウム 胸椎部脊椎管狭窄症の病態と治療
15巻12号(1980年12月発行)
15巻11号(1980年11月発行)
15巻10号(1980年10月発行)
15巻9号(1980年9月発行)
15巻8号(1980年8月発行)
15巻7号(1980年7月発行)
15巻6号(1980年6月発行)
15巻5号(1980年5月発行)
シンポジウム 先天股脱の予防
15巻4号(1980年4月発行)
シンポジウム CTと整形外科
15巻3号(1980年3月発行)
特集 脊椎腫瘍(第8回脊椎外科研究会より)
15巻2号(1980年2月発行)
15巻1号(1980年1月発行)
14巻12号(1979年12月発行)
14巻11号(1979年11月発行)
14巻10号(1979年10月発行)
14巻9号(1979年9月発行)
シンポジウム 最近の抗リウマチ剤の動向
14巻8号(1979年8月発行)
14巻7号(1979年7月発行)
シンポジウム 五十肩の治療
14巻6号(1979年6月発行)
14巻5号(1979年5月発行)
14巻4号(1979年4月発行)
特集 脊椎外傷—早期の病態・診断・治療—(第7回脊椎外科研究会より)
14巻3号(1979年3月発行)
14巻2号(1979年2月発行)
14巻1号(1979年1月発行)
13巻12号(1978年12月発行)
13巻11号(1978年11月発行)
13巻10号(1978年10月発行)
13巻9号(1978年9月発行)
13巻8号(1978年8月発行)
13巻7号(1978年7月発行)
13巻6号(1978年6月発行)
13巻5号(1978年5月発行)
13巻4号(1978年4月発行)
特集 脊椎の炎症性疾患
13巻3号(1978年3月発行)
13巻2号(1978年2月発行)
13巻1号(1978年1月発行)
12巻12号(1977年12月発行)
12巻11号(1977年11月発行)
12巻10号(1977年10月発行)
12巻9号(1977年9月発行)
12巻8号(1977年8月発行)
12巻7号(1977年7月発行)
12巻6号(1977年6月発行)
12巻5号(1977年5月発行)
12巻4号(1977年4月発行)
特集 胸椎部ミエロパチー
12巻3号(1977年3月発行)
12巻2号(1977年2月発行)
12巻1号(1977年1月発行)
11巻12号(1976年12月発行)
11巻11号(1976年11月発行)
11巻10号(1976年10月発行)
11巻9号(1976年9月発行)
11巻8号(1976年8月発行)
特集 腰部脊柱管狭窄の諸問題
11巻7号(1976年7月発行)
11巻6号(1976年6月発行)
11巻5号(1976年5月発行)
11巻4号(1976年4月発行)
11巻3号(1976年3月発行)
11巻2号(1976年2月発行)
シンポジウム Silicone rod
11巻1号(1976年1月発行)
10巻12号(1975年12月発行)
特集II Myelopathy・Radiculopathy
10巻11号(1975年11月発行)
シンポジウム 頸部脊椎症性ミエロパチー
10巻10号(1975年10月発行)
シンポジウム 関節軟骨の病態
10巻9号(1975年9月発行)
10巻8号(1975年8月発行)
10巻7号(1975年7月発行)
シンポジウム 慢性関節リウマチの前足部変形に対する治療
10巻6号(1975年6月発行)
10巻5号(1975年5月発行)
10巻4号(1975年4月発行)
10巻3号(1975年3月発行)
10巻2号(1975年2月発行)
10巻1号(1975年1月発行)
9巻12号(1974年12月発行)
9巻11号(1974年11月発行)
特集 脊椎外科(第1回脊椎外科研究会より)
9巻10号(1974年10月発行)
9巻9号(1974年9月発行)
9巻8号(1974年8月発行)
9巻7号(1974年7月発行)
シンポジウム 変形性股関節症の手術療法
9巻6号(1974年6月発行)
9巻5号(1974年5月発行)
9巻4号(1974年4月発行)
9巻3号(1974年3月発行)
9巻2号(1974年2月発行)
9巻1号(1974年1月発行)
8巻12号(1973年12月発行)
8巻11号(1973年11月発行)
8巻10号(1973年10月発行)
シンポジウム 移植皮膚の生態
8巻9号(1973年9月発行)
8巻8号(1973年8月発行)
8巻7号(1973年7月発行)
8巻6号(1973年6月発行)
8巻5号(1973年5月発行)
シンポジウム 顔面外傷
8巻4号(1973年4月発行)
8巻3号(1973年3月発行)
8巻2号(1973年2月発行)
シンポジウム 乳幼児先天股脱の手術療法
8巻1号(1973年1月発行)
7巻12号(1972年12月発行)
7巻11号(1972年11月発行)
7巻10号(1972年10月発行)
シンポジウム 膝の人工関節
7巻9号(1972年9月発行)
7巻8号(1972年8月発行)
7巻7号(1972年7月発行)
7巻6号(1972年6月発行)
7巻5号(1972年5月発行)
7巻4号(1972年4月発行)
7巻3号(1972年3月発行)
7巻2号(1972年2月発行)
7巻1号(1972年1月発行)
6巻12号(1971年12月発行)
6巻11号(1971年11月発行)
6巻10号(1971年10月発行)
6巻9号(1971年9月発行)
6巻8号(1971年8月発行)
6巻7号(1971年7月発行)
シンポジウム 四肢末梢血管障害
6巻6号(1971年6月発行)
6巻5号(1971年5月発行)
6巻4号(1971年4月発行)
6巻3号(1971年3月発行)
6巻2号(1971年2月発行)
6巻1号(1971年1月発行)
5巻12号(1970年12月発行)
5巻11号(1970年11月発行)
5巻10号(1970年10月発行)
5巻9号(1970年9月発行)
5巻8号(1970年8月発行)
5巻7号(1970年7月発行)
5巻6号(1970年6月発行)
5巻5号(1970年5月発行)
5巻4号(1970年4月発行)
5巻3号(1970年3月発行)
5巻2号(1970年2月発行)
5巻1号(1970年1月発行)
4巻12号(1969年12月発行)
4巻11号(1969年11月発行)
4巻10号(1969年10月発行)
4巻9号(1969年9月発行)
4巻8号(1969年8月発行)
シンポジウム 腰部椎間板症
4巻7号(1969年7月発行)
4巻6号(1969年6月発行)
4巻5号(1969年5月発行)
4巻4号(1969年4月発行)
4巻3号(1969年3月発行)
4巻2号(1969年2月発行)
4巻1号(1969年1月発行)
3巻12号(1968年12月発行)
3巻11号(1968年11月発行)
シンポジウム 股関節形成術
3巻10号(1968年10月発行)
シンポジウム 日本の義肢問題
3巻9号(1968年9月発行)
シンポジウム 内反足
3巻8号(1968年8月発行)
シンポジウム 腕神経叢損傷
3巻7号(1968年7月発行)
3巻6号(1968年6月発行)
3巻5号(1968年5月発行)
シンポジウム 脊髄損傷患者に対する早期脊椎固定術の適応と成績
3巻4号(1968年4月発行)
シンポジウム いわゆる鞭打ち損傷
3巻3号(1968年3月発行)
3巻2号(1968年2月発行)
3巻1号(1968年1月発行)
2巻12号(1967年12月発行)
2巻11号(1967年11月発行)
2巻10号(1967年10月発行)
2巻9号(1967年9月発行)
2巻8号(1967年8月発行)
シンポジウム 脳性麻痺
2巻7号(1967年7月発行)
2巻6号(1967年6月発行)
シンポジウム 腰痛
2巻5号(1967年5月発行)
シンポジウム 骨肉腫の治療および予後
2巻4号(1967年4月発行)
シンポジウム 関節リウマチの治療
2巻3号(1967年3月発行)
シンポジウム 先天性股関節脱臼 私の治療法
2巻2号(1967年2月発行)
シンポジウム 先天性筋性斜頸 私の治療法
2巻1号(1967年1月発行)
シンポジウム 脊髄損傷
