骨軟部組織感染症に含まれる病態は多種多様であり,術後合併症はこれら感染症との闘いと言っても過言ではない.この企画を担当するにあたって心掛けたことは,若手医師から経験のある医師すべての方に対して,骨軟部組織感染症の歴史的変遷から最新の治療までの知識を一度に理解できるように構成することである.現在,本分野の第一線で活躍中の先生に趣旨を説明したところ,ご多忙中にもかかわらず執筆をご快諾いただいた.以下,概説する(敬称略).
雑誌目次
臨床整形外科57巻4号
2022年04月発行
雑誌目次
特集 骨軟部組織感染症Update
骨軟部組織感染症治療の歴史的変遷—Overview
著者: 高原俊介
ページ範囲:P.339 - P.343
人類と骨軟部組織感染症の闘いの歴史は古く,古代エジプト時代から資料が残されている.死亡率が高く,死と直面する病態であったことが容易に想像されるが,当時から既に軟部組織被覆の重要性が示されていた.以降,長きにわたり骨軟部組織感染症の治療に大きな変革は起こっていなかったが,1940年代の抗菌薬の登場により,骨軟部組織感染症は死に直面する病態から脱却することとなる.以降,手術手技の向上,全身抗菌薬投与レジメンのbrush up,局所抗菌薬療法の発展により,感染症の高い鎮静化率,高い機能予後の獲得が可能な時代となってきている.
抗菌薬の使用方法—各種ガイドラインからみた骨軟部組織感染症の抗菌薬治療
著者: 山田浩司
ページ範囲:P.345 - P.351
抗菌薬の適正使用で最も重要なのが,“原因菌の同定”である.抗菌薬治療の基本はβラクタム系抗菌薬である.そのため,まずセフェム系とペニシリン系抗菌薬についてその基本を理解しておく必要がある.その他に,抗MRSA薬の特徴についても熟知している必要がある.抗菌薬のバイオアベイラビリティや組織移行性の問題も重要である.
整形外科感染症における黄色ブドウ球菌感染とバイオフィルムのUpdate
著者: 崔賢民 , 稲葉裕
ページ範囲:P.353 - P.359
整形外科感染症は,整形外科疾患の中でも診断・治療に難渋することが多い疾患である.黄色ブドウ球菌は最も頻度の高い整形外科感染症であり,黄色ブドウ球菌を用いた研究により,原因菌による皮質骨内侵入や宿主細胞内寄生,ヒト細胞に特異的な毒素の産生,免疫細胞や抗菌薬から細菌を保護する特殊な環境の形成が,診断・治療における難治化に関係していることが明らかとなってきた.黄色ブドウ球菌は強い接着因子を持つ菌であり,ほとんどの黄色ブドウ球菌感染でバイオフィルムが発症に関与している.バイオフィルムは段階的に成熟し,成熟したバイオフィルムは菌の拡散や毒素の産生により骨破壊や炎症を惹起する.特にバイオフィルムの成熟と感染の発症には,クオラムセンシングと呼ばれる細菌同士のシグナル伝達が重要な役割を持ち,整形外科感染症の難治化と大きく関係している.近年の整形外科感染の病態やバイオフィルム形成メカニズムに関する知見の進歩を知ることは,整形外科感染症の診断および治療の成績の向上に重要であると考える.
骨軟部組織感染症に対する高気圧酸素治療とオゾンナノバブル水による閉鎖式局所持続洗浄療法
著者: 川嶌眞之 , 田村裕昭 , 永芳郁文 , 川嶌眞人
ページ範囲:P.361 - P.372
高気圧酸素治療(HBO)には骨軟部組織感染症に対しても多様な効果が報告されており,われわれは化膿性骨髄炎や化膿性関節炎,インプラント周囲感染症,軟部組織感染症などに対する治療において活用している.急性期の症例では抗菌薬の投与やHBOなどによる保存的治療にて感染が鎮静化することもあるが,慢性化した難治症例では外科的治療を必要とすることも多く,このような症例に対してわれわれは病巣搔爬や閉鎖式局所持続洗浄療法を行っている.また近年は創処置や持続洗浄療法の洗浄液にオゾンナノバブル水(NBW3)を使用する試みを行っている.
重症開放骨折における深部感染の治療戦略
著者: 長谷川真之
ページ範囲:P.373 - P.379
重症開放骨折の治療は深部感染との戦いである.受傷時に過不足のないデブリドマンを行い,1週間以内に骨接合と軟部組織再建を実践するorthoplastic approachが原則である.しかしながら,理想的な治療を滞りなく施行しても深部感染は起こり得る.そのため,プラスアルファで,再建後の追加デブリドマンや皮弁下洗浄,死腔内の滲出液や血腫の貯留を予防すること,そして症例に応じて高濃度抗菌薬局所投与(High CALI)を適応することが決め手となる.
持続局所抗菌薬灌流(CLAP)療法の過去,現在と今後の発展性
著者: 圓尾明弘
ページ範囲:P.381 - P.387
抗菌薬の局所投与の歴史は古く,1960年代にはsuction irrigationとして高流量・低濃度で持続的に洗浄する治療法が報告されていた.時代の変遷とともに低流量・高濃度の抗菌薬を移行させるcontinuous local antibiotics perfusion(CLAP)という治療概念に変わっていった.局所投与には起炎菌にかかわらず,濃度依存性のゲンタマイシンを1,200μg/mLとして2mL/hで投与することで,耐性菌を誘導することなく耐性菌も制圧できる利点がある.この濃度はバイオフィルムを制圧する濃度にも匹敵するので,CLAPを開放骨折の感染予防,骨接合後や人工関節後の感染の治療などに応用している.
“難治性”骨軟部組織感染症治療のパラダイムシフト—CLAP時代では感染症との戦い方はどう変わるか?
著者: 姫野大輔
ページ範囲:P.389 - P.395
CLAP時代が到来し,これまで“難治性”とされてきた感染症の治療も大きく変わろうとしている.本稿ではまずこれまでの“難治性”の要因を掘り下げる.そして世界初のCLAP論文となった症例を交え,CLAPで“難治性”感染症治療をどのように必然的に治すことができるかを肌で感じていただく.治療の必然性に欠かせないキーワードは「“難治性”の要因を1つひとつ解決する」+「細菌がいる範囲にCLAPを行う」である.本稿を熟読した翌朝にはどんよりとした感染症治療に明るい光が差す,そんなCLAP時代への旅に出かけたい.
上肢・手部領域の難治性骨軟部組織感染症に対する持続局所抗菌薬灌流療法
著者: 佐藤直人 , 善家雄吉 , 濱田大志 , 安藤恒平 , 真弓俊彦 , 酒井昭典
ページ範囲:P.397 - P.403
上肢・手部領域の動物咬傷後や化膿性腱鞘炎などに代表される本領域の感染症は,①解剖学的に複雑である,②深部まで到達しやすい,③受診が遅れやすい,などの点より治療が難渋しやすい.また,上肢は下肢に比較して支持性よりも巧緻運動が求められるため,治療が長期間に及ぶことで,組織浮腫・瘢痕化により,容易に関節拘縮などの機能障害を残してしまう.当院では,基礎疾患を有する,あるいは受診の遅れなどにより発症から時間が経過したようないわゆる難治性の骨軟部組織感染症に対して,洗浄,デブリドマンに加えて持続局所抗菌薬灌流(CLAP)療法を併用し,可動域訓練を行いつつ感染制御を行うことで,機能障害を最小限に留める努力をしている.本稿では,上肢・手部領域の難治性感染症に対するCLAP療法の実際を症例提示し紹介する.
胸腰椎化膿性脊椎炎に対し経皮的椎弓根スクリューを併用した前後方固定術の手術成績—罹患椎体へのスクリュー挿入の試み
著者: 馬場秀夫 , 山田周太 , 今井智恵子 , 三溝和貴 , 貞松毅大 , 小西宏昭
ページ範囲:P.405 - P.411
胸腰椎化膿性脊椎炎に対し,自家腸骨を使用した前方搔爬固定に後方に経皮的椎弓根スクリュー(PPS)を併用した前後方固定術を行った37例の手術成績について検討した.CTでscrew挿入部に椎体破壊がなく挿入が可能な場合,PPSを挿入した.菌の検出は椎間板穿刺,血液培養が陰性で手術採取部位陽性が7例(19%)であった.罹患椎体へのscrew挿入数は全screw 185本中101本,挿入率54.6%であった.CRPが1未満まで改善した期間は6〜62日(平均20日)だった.その多くが4週までで1未満になっており,6週を超える症例は2例のみで感染は全例治癒した.
壊死性軟部組織感染症の温故知新
著者: 安藤恒平
ページ範囲:P.413 - P.418
2021年現在言われている壊死性軟部組織感染症(NSTI)は,古くから認知されており,ともすれば紀元前2,500年頃に作成されたヒエログリフの中に記述された48症例目なども含まれるかもしれない.20世紀初頭までは外傷性に由来することが多かったものの,昨今では疾患的に,または医療的に免疫抑制状態にある方々が多いこと,また,肝機能障害の方々を丁寧に治療・観察していく中で,本疾患を見出すようになってきている.本稿では,NSTIの歴史的な記述や,今に至るまでの先人の苦難と成功を紐解き,現在行われようとしているCLAP治療までの変遷を紹介する.
視座
医学部入試について思う
著者: 高橋謙治
ページ範囲:P.332 - P.333
医学部入試は近年やや落ち着いてきたものの,かなりの難関であることに変わりはないらしい.都市部では小学生から厳しい勉強をして中学受験し,中高一貫校で勉強を怠らず塾にも通わないと合格はかなわないという.結果として毎年同じ進学校からの生徒が多くなる.日本の研究論文の質・量が国際的に低迷する中で,経歴においても偏差値においても均質な学生を集めて特徴のない教育をしていては,もはや国際的に通用する才能は輩出できないのではないかという危惧がある.もっと多様な学生に入学させるべきか,今までどおり入試時点での成績優秀者をとるべきか,入試改革の議論が行われ始めている.地域医療貢献を希望する人,国際的な研究を目指す人,医療行政に興味がある人,いろいろな若者に入学してほしいと個人的には思う.
大学入試とは言うまでもなく入学に際して大学が求める要件や力をクリアしているかどうかを見極める試験である.大学が求める要件は「アドミッションポリシー」に示される.個別試験と共用試験の配点割合,推薦枠,前期後期どちらも試験が受けられた時代など母校の歴史的な試験制度の変遷を調べても,どのような入試が「アドミッションポリシー」に合う生徒を選別するのに適切か見当がつかない.
論述
大腿骨近位部骨折における受傷後48時間以内の手術は合併症を低下させる
著者: 喜多晃司 , 海野宏至 , 渡邉健斗 , 佐藤昌良 , 森本政司 , 湏藤啓広
ページ範囲:P.419 - P.426
目的:大腿骨近位部骨折は手術までの待機期間が合併症と死亡率のリスク増加に関与すると報告されている.術後合併症の発生率を評価し,早期手術の重要性について検討した.対象と方法:当院で手術を行った187例を対象とし,受傷後48時間以内に手術を行った症例と48時間以上経過してから手術を行った症例に分け,術後合併症などを評価した.結果:合併症は,早期群は2.3%,待機群は27.1%であり,待機群で有意に高い結果となり,入院中死亡は待機群1.39%で認め,早期群で認めなかった.まとめ:受傷後48時間以内の手術は術後合併症の発生率を低下させる.
変形性膝関節症患者に対する足関節捻挫用サポーター付き足底挿板装着によるウォーキング運動の効果
著者: 戸田佳孝 , 増田研一
ページ範囲:P.427 - P.431
変形性膝関節症(膝OA)に対し,足関節弾性固定付き外側楔状足底挿板(外側楔状)をウォーキング訓練での疼痛を減少させる目的で使用した.76例の膝OA患者を無作為に外側楔状装着群と平坦な中敷きを装着する対照群に分類し,1日平均歩数を2,000歩増加するように指導した.結果,1日平均歩数の変化は,外側楔状装着群(2,174±823歩増加)が対照群(1,251±914歩増加)に比べて有意に増加した(p<0.0001).膝OAに対する外側楔状はウォーキング訓練の有効な補助具であると考察した.
Lecture
鑑定人となる場合に留意すべき事項
著者: 宗像雄
ページ範囲:P.435 - P.437
本稿の目的と問題意識
本稿は,医師が裁判所の依頼を受けて鑑定人となる場合に留意すべき事項について,若干の提言を試みるものである.
裁判所は,事件について審理をするうえで必要がある場合に,鑑定を命じる.医師による鑑定は,医療(過誤)事件はもちろん,交通事故その他の人的被害が問題となる事件の審理において,広く用いられる.裁判所は,鑑定人がした鑑定の結果を踏まえたうえで,事件について判決を下す.鑑定の結果は,判決において,被害者に支払われる賠償金の有無ないし範囲に重要な影響を及ぼす.それゆえ,訴訟の当事者,中でも被害者は,これに大きな関心を抱いている.
臨床経験
肩手術中のSPIDER Limb Positionerのグリップ形状と術後手指症状の関係(前向き研究)
著者: 新宮恵 , 大石隆太 , 宇野智洋 , 結城一声 , 村成幸
ページ範囲:P.439 - P.443
背景:SPIDERのグリップ(グリップ)の新品と再滅菌による形状の違いが,術後の手指症状発症に影響を及ぼしていると考え検討した.対象と方法:再滅菌により細くなったグリップを使用した再滅菌群24例と新品を使用した新品群23例を前向きに手指症状について調査した.結果:術直後は28例(59.6%)に手指症状がみられ,腫脹自覚症例は術後3〜4日目で中指より手掌で厚くなっていた.再滅菌群,新品群両群で手指の自覚症状,手指の浮腫の計測値に差はなかった.まとめ:グリップ再滅菌使用による,術直後の手指症状発症への影響はみられなかった.
症例報告
腰椎に発症したびまん型腱滑膜巨細胞腫の1例
著者: 田中宏毅 , 竹内宏仁 , 藤田諒 , 大嶋茂樹 , 安保裕之 , 藤谷正紀 , 織田格
ページ範囲:P.445 - P.449
72歳女性,半年前から続く腰痛と右大腿前面痛を主訴に来院した.単純X線画像とCT画像では右L4/5椎間関節に骨破壊がみられ,単純MRI画像では同部位を中心にT1低〜等信号,T2低信号の脊柱管内外から椎間孔内に及ぶ分葉状腫瘤と関節水腫を認めた.右L4/5椎間関節全切除および経椎間孔的椎体間固定術を施行した後,びまん型腱滑膜巨細胞腫(D-TGCT)と診断した.術後痛みは改善した.腰椎発生のD-TGCTは変性疾患や他の脊椎腫瘍との鑑別が難しいことがある.稀な疾患ではあるが特徴を知り,念頭に置いて診療に当たる必要がある.
書評
Critical Thinking脊椎外科 第2版 フリーアクセス
著者: 松本守雄
ページ範囲:P.433 - P.433
脊椎外科を専門としている私も,若い頃には先輩医師に“レーゲルどおりにするように”と指導され,何の疑いもなくいわれるとおりに診療を行っていた.たとえば,椎間板ヘルニアに対するLove法術後に2週間のベッド上安静を行うなど,今から思えばどのような根拠があってそのようなことを行っていたのか,不思議でもある.脊椎外科領域にはこのように根拠が曖昧な常識が数多くある(あるいはかつてあった)が,そこに鋭く切り込んで行ったのが星地亜都司先生による“Critical Thinking脊椎外科”である.
私事で恐縮だが,著者の星地先生は私の高校の2年先輩であり,当時から人に厳しく,自分にはもっと厳しい方であり,求道者然とした方であった.そのような星地先生が執筆された本書の初版は脊椎外科の本質を鋭く捉えており,私も含めて数多くの読者が目から鱗の感銘を受けたが,このたび13年の年月を経て待望の第2版が出版された.本書では,脊椎脊髄の解剖学,病態学,診断学に始まり,一般的な疾患から稀少なものまで,さまざまな脊椎疾患に対する手術の実際のこつ,合併症への対処,さらには英文投稿や統計学の重要性など,脊椎外科領域のあらゆる項目が網羅されている.脊椎外科における星地先生ご自身の豊富な経験とともに失敗談も包み隠さず披露されており,通常ならやり過ごされる事象についても深い洞察でその原因と解決策を見いだそうとされており,文章は哲学的ですらある.さらに,13年の間に新たに臨床の場に導入された手術手技や,椎弓形成術の項目に代表されるように星地先生ご自身が加えられた工夫などについてもご加筆され,内容も非常にup-to-dateなものになっている.
これで解決! みんなの臨床研究・論文作成 フリーアクセス
著者: 家研也
ページ範囲:P.438 - P.438
臨床研究や論文執筆に取り組む上で,避けて通れない「壁」がある.この壁はさまざまな場面で,姿かたちを変えて繰り返し出没してわれわれの心を折ろうとする.私自身,研究に取り組み始めた当初から,数えきれない壁を経験した.研究テーマ探し,文献検索,研究計画書作成,データ収集,統計解析,論文の書き方,投稿先探し,rejectに心が折れる経験,意地悪な査読の対処,そもそも忙しくて研究が進まない! など,多岐にわたる.思い返すと,それらの場面で壁を乗り越える手助けを常に誰かがしてくれた.それは指導医・メンターに限らず,仲間,後輩,時に書籍であったりもした.このように,初心者が臨床研究を論文化するまでは手取り足取りの指導が必要な場面だらけである.
本書は臨床医でありながら50編近くの原著論文を筆頭著者として世に送り出し,さらに多くの後輩の研究を指導してきた辻本哲郎先生による,気持ちがいいまでの「実践の書」である.臨床研究デザインや統計解析,論文作成に関する本は多数存在するが,本書の特徴を端的に表すと「身近で面倒見の良い先輩」である.研究初心者がつまずく壁一つひとつについて,具体的にステップを示してくれる.特にコラムが秀逸で,臨床研究の現場のリアルがそこにある.臨床現場の一隅で隙間時間に取り組む研究の場で,面倒見の良い先輩が失敗談やコツを共有し,曖昧だった概念の理解を助け,次に何をしたら良いか具体的に示してくれる,そんな頼れる先輩を常に座右に置いておけるような一冊である.
小児と成人のための超音波ガイド下区域麻酔図解マニュアル フリーアクセス
著者: 鈴木昭広
ページ範囲:P.453 - P.453
『小児と成人のための超音波ガイド下区域麻酔図解マニュアル』.書籍のタイトル自体で,「小児」が「成人」より大きく書かれていることがまずユニークだ.平置きで「映える」こと請け合いである.麻酔科領域において,確かに小児の鎮痛は長いことおざなりにされてきた.そもそも暴れて泣き叫ぶ小児に,区域麻酔など危なくてできやしない.術中もおとなしくしているはずもない.手術の大小にかかわらず,何か必要があればすぐに全身麻酔.大人なら併用するはずの硬膜外麻酔もなく,戦う武器はせいぜい仙骨ブロックのみ.起きた患児は,創は痛いわ足は動かないわでパニック状態.手術をした後もやっぱり手がつけられない.「母親が1番の薬だよ」と全ては母親に丸投げ…….私自身,恥ずかしながらこういうプラクティスを繰り返し,古くからの悪習を後輩に伝える悪い先輩だったことだろう.しかし,前職の東京慈恵会医大で小児麻酔への考えを改めさせられた.JPOPS(Jikei Post-Operative acute Pain Service)という術後疼痛管理チームが術後痛のプロトコールを決め,小児でも胸部や腰部の硬膜外を実施し,区域麻酔の補助のあるなしにかかわらず,薬をタイトレーションして覚醒させ,抜管後にスヤスヤと過ごすわが子を母親がそばの椅子に座って見守る風景が当たり前の術場回復室(PACU:post-anesthesia care unit).もし子供が泣いていようものなら「なんで泣いてんだ!?」とU主任教授が怒り心頭でやってくる.それ以来,小児事例が当たると,わが子の麻酔と思って他のスタッフと同じような穏やかな目覚めを提供できないかを考えるようになった.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.334 - P.335
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.336 - P.336
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.450 - P.450
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.451 - P.452
あとがき フリーアクセス
著者: 酒井昭典
ページ範囲:P.456 - P.456
古代エジプト時代あるいはそれ以前の太古から今日に至るまで,人類は骨軟部組織感染症と闘い続けてきました.長らくは致死の病として,四肢の切断を余儀なくされてきましたが,抗菌薬の登場によって死を回避することが可能となりました.新規抗菌薬の開発とともに,創洗浄,ブラッシング,デブリドマン,創外固定などの手術手技の工夫により治療成績が向上してきました.さらに,近年,持続局所抗菌薬灌流(CLAP)が難治性の骨軟部組織感染症に対する治療においてパラダイムシフトを起こしました.善家雄吉先生にご企画いただいた本号の特集「骨軟部組織感染症Update」では,感染症と治療法の歴史的変遷・温故知新,抗菌薬の使い方,四肢および脊椎における具体的な治療戦略が記載されています.過去の辛酸をなめた経験とともに最新の医療技術に関する情報がたくさん盛り込まれています.本号の特集を通して,感染による運動機能損失を最小限に抑えつつ,感染を制御できる時代が到来することを願っています.
Lectureでは,鑑定人となる場合に留意すべき事項を宗像 雄先生から教えていただきました.私も裁判所から依頼され医療訴訟の鑑定人になったことがありますが,鑑定事項に対する返答の内容はもとよりその文章の枝葉末節にも相当な神経を使い,労力を費やした苦い経験があります.カルテの記載内容や検査データだけでの判断には限界があることを痛感しました.私が鑑定を担当した訴訟案件はその後,和解に至ったとのことで,裁判所から感謝されたことは幸いでした.鑑定を引き受けるにはそれ相応の強い覚悟が必要であることを再認識いたしました.
基本情報
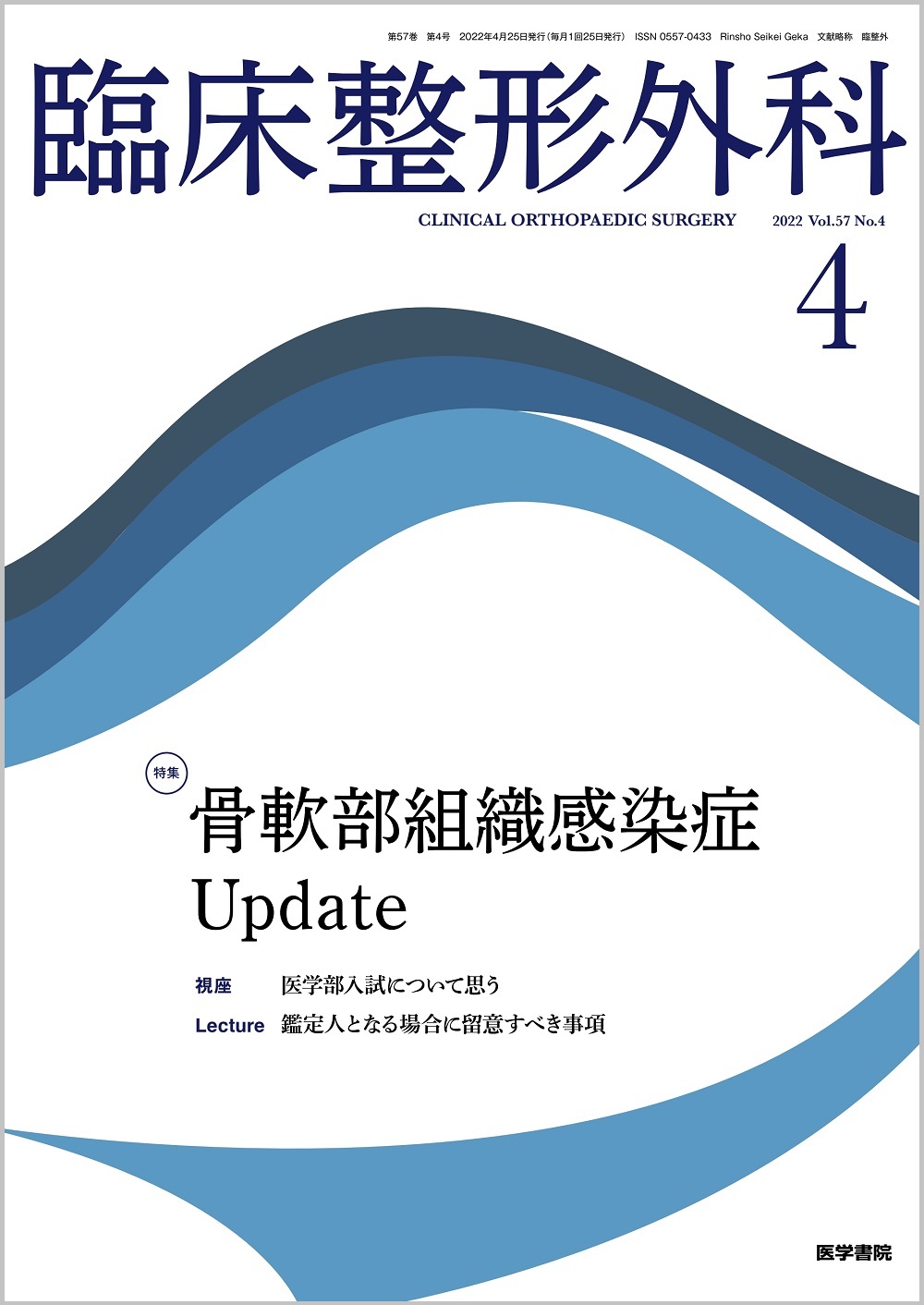
バックナンバー
59巻12号(2024年12月発行)
特集 初療対応からきれいな指再建まで 指尖部切断に対する治療
59巻10号(2024年10月発行)
特集 整形外科医のための臨床研究の進め方—立案から実施まで
59巻9号(2024年9月発行)
特集 変形性関節症に対するBiologics
59巻8号(2024年8月発行)
特集 脊損患者への投与が始まった脊髄再生医療—脊髄損傷患者に希望が見えるか
59巻7号(2024年7月発行)
特集 大規模レジストリーによる整形外科リアルワールドエビデンス構築
59巻6号(2024年6月発行)
特集 TKAにおける最新Topics
59巻5号(2024年5月発行)
増大号特集 絶対! 整形外科外傷学
59巻4号(2024年4月発行)
特集 脊椎関節炎SpAを理解する—疾患概念・診断基準・最新治療
59巻3号(2024年3月発行)
特集 知ってると知らないでは大違い 実践! 踵部痛の診断と治療
59巻2号(2024年2月発行)
特集 ここまで来た! 胸郭出口症候群の診断と治療
59巻1号(2024年1月発行)
特集 はじめたい人と極めたい人のための 超音波ガイド下インターベンション
58巻12号(2023年12月発行)
特集 がん時代の整形外科必携! 骨転移診療アップデート
58巻11号(2023年11月発行)
特集 外傷性頚部症候群—診療の最前線
58巻10号(2023年10月発行)
特集 腱板断裂の治療戦略
58巻9号(2023年9月発行)
特集 脊椎内視鏡下手術の進化・深化
58巻8号(2023年8月発行)
特集 小児の上肢をいかに診るか—よくわかる,先天性障害・外傷の診察と治療の進め方
58巻7号(2023年7月発行)
特集 股関節鏡手術のエビデンス—治療成績の現状
58巻6号(2023年6月発行)
特集 FRIの診断と治療—骨折手術後感染の疑問に答える
58巻5号(2023年5月発行)
増大号特集 できる整形外科医になる! 臨床力UP,整形外科診療のコツとエッセンス
58巻4号(2023年4月発行)
特集 疲労骨折からアスリートを守る—今,おさえておきたい“RED-S”
58巻3号(2023年3月発行)
特集 二次骨折予防に向けた治療管理
58巻2号(2023年2月発行)
特集 外反母趾診療ガイドライン改訂 外反母趾治療のトレンドを知る
58巻1号(2023年1月発行)
特集 医師の働き方改革 総チェック
57巻12号(2022年12月発行)
特集 大腿骨近位部骨折—最新トレンドとエキスパートの治療法
57巻11号(2022年11月発行)
特集 腰椎椎間板ヘルニアのCutting Edge
57巻10号(2022年10月発行)
特集 整形外科領域における人工知能の応用
57巻9号(2022年9月発行)
特集 わかる! 骨盤骨折(骨盤輪損傷) 診断+治療+エビデンスのUpdate
57巻8号(2022年8月発行)
特集 整形外科ロボット支援手術
57巻7号(2022年7月発行)
特集 整形外科医×関節リウマチ診療 今後の関わり方を考える
57巻6号(2022年6月発行)
特集 高齢者足部・足関節疾患 外来診療のコツとトピックス
57巻5号(2022年5月発行)
増大号特集 もう悩まない こどもと思春期の整形外科診療
57巻4号(2022年4月発行)
特集 骨軟部組織感染症Update
57巻3号(2022年3月発行)
特集 診断・治療に難渋したPeriprosthetic Joint Infectionへの対応
57巻2号(2022年2月発行)
特集 ロコモティブシンドローム臨床判断値に基づいた整形外科診療
57巻1号(2022年1月発行)
特集 知っておきたい足関節周囲骨折の新展開
56巻12号(2021年12月発行)
特集 整形外科手術に活かす! 創傷治療最新ストラテジー
56巻11号(2021年11月発行)
特集 末梢神経の再建2021
56巻10号(2021年10月発行)
特集 脊椎転移の治療 最前線
56巻9号(2021年9月発行)
特集 膝周囲骨切り術を成功に導く基礎知識
56巻8号(2021年8月発行)
特集 外来で役立つ 足部・足関節の超音波診療
56巻7号(2021年7月発行)
特集 手外科と労災
56巻6号(2021年6月発行)
特集 ACL再断裂に対する治療戦略
56巻5号(2021年5月発行)
増大号特集 整形外科 外来・当直 エマージェンシーマニュアル
56巻4号(2021年4月発行)
特集 成人脊柱変形 手術手技の考えかた・選びかた
56巻3号(2021年3月発行)
特集 骨折に対する積極的保存療法
56巻2号(2021年2月発行)
特集 ダメージ・コントロールとしての創外固定
56巻1号(2021年1月発行)
特集 パラスポーツ・メディシン入門
55巻12号(2020年12月発行)
特集 女性アスリートの運動器障害—悩みに答える
55巻11号(2020年11月発行)
特集 足部・足関節の画像解析—画像から病態を探る
55巻10号(2020年10月発行)
55巻9号(2020年9月発行)
特集 インプラント周囲骨折の治療戦略—THA・TKA・骨折後のプレート・髄内釘
55巻8号(2020年8月発行)
特集 整形外科×人工知能
55巻7号(2020年7月発行)
特集 脊椎手術—前方か後方か?
55巻6号(2020年6月発行)
特集 各種骨盤骨切り術とそのメリット
55巻5号(2020年5月発行)
増大号特集 臨床整形超音波学—エコー新時代、到来。
55巻4号(2020年4月発行)
特集 人工関節周囲感染の現状と展望 国際コンセンサスを踏まえて
55巻3号(2020年3月発行)
特集 頚椎を含めたグローバルアライメント
55巻2号(2020年2月発行)
特集 整形外科の職業被曝
55巻1号(2020年1月発行)
特集 新しい概念 “軟骨下脆弱性骨折”からみえてきたこと
54巻12号(2019年12月発行)
誌上シンポジウム 患者の満足度を高める関節リウマチ手術
54巻11号(2019年11月発行)
誌上シンポジウム 腰椎前方アプローチ—その光と影
54巻10号(2019年10月発行)
誌上シンポジウム がん診療×整形外科「がんロコモ」
54巻9号(2019年9月発行)
誌上シンポジウム 肩腱板断裂 画像診断の進歩
54巻8号(2019年8月発行)
誌上シンポジウム 整形外科治療の費用対効果
54巻7号(2019年7月発行)
誌上シンポジウム 骨軟部腫瘍の薬物治療アップデート
54巻6号(2019年6月発行)
誌上シンポジウム 変形性膝関節症における関節温存手術
54巻5号(2019年5月発行)
誌上シンポジウム 整形外科を牽引する女性医師たち—男女共同参画
54巻4号(2019年4月発行)
誌上シンポジウム 超高齢社会における脊椎手術
54巻3号(2019年3月発行)
誌上シンポジウム サルコペニアと整形外科
54巻2号(2019年2月発行)
誌上シンポジウム 足部・足関節疾患と外傷に対する保存療法 Evidence-Based Conservative Treatment
54巻1号(2019年1月発行)
誌上シンポジウム 小児の脊柱変形と脊椎疾患—診断・治療の急所
53巻12号(2018年12月発行)
誌上シンポジウム 外傷における人工骨の臨床
53巻11号(2018年11月発行)
誌上シンポジウム 椎間板研究の最前線
53巻10号(2018年10月発行)
誌上シンポジウム 原発巣別転移性骨腫瘍の治療戦略
53巻9号(2018年9月発行)
誌上シンポジウム 外反母趾の成績不良例から学ぶ
53巻8号(2018年8月発行)
誌上シンポジウム 椎弓形成術 アップデート
53巻7号(2018年7月発行)
誌上シンポジウム 膝前十字靱帯のバイオメカニクス
53巻6号(2018年6月発行)
誌上シンポジウム 変形性足関節症のフロントライン
53巻5号(2018年5月発行)
誌上シンポジウム 外傷後・術後骨髄炎の治療
53巻4号(2018年4月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症性脊椎骨折の治療 Cutting Edge
53巻3号(2018年3月発行)
誌上シンポジウム THAの低侵襲性と大腿骨ステム選択
53巻2号(2018年2月発行)
誌上シンポジウム 骨関節外科への3Dプリンティングの応用
53巻1号(2018年1月発行)
誌上シンポジウム 脂肪幹細胞と運動器再生
52巻12号(2017年12月発行)
誌上シンポジウム 慢性腰痛のサイエンス
52巻11号(2017年11月発行)
52巻10号(2017年10月発行)
52巻9号(2017年9月発行)
誌上シンポジウム パーキンソン病と疼痛
52巻8号(2017年8月発行)
誌上シンポジウム 創外固定でどこまでできるか?
52巻7号(2017年7月発行)
誌上シンポジウム 認知症の痛み
52巻6号(2017年6月発行)
52巻5号(2017年5月発行)
誌上シンポジウム 成人脊柱変形の目指すポイント PI-LL≦10°,PT<20°はすべての年齢層に当てはまるのか
52巻4号(2017年4月発行)
52巻3号(2017年3月発行)
誌上シンポジウム 股関節疾患の保存的治療とリハビリテーション
52巻2号(2017年2月発行)
誌上シンポジウム リバース型人工肩関節手術でわかったこと
52巻1号(2017年1月発行)
誌上シンポジウム 胸椎OPLL手術の最前線
51巻12号(2016年12月発行)
51巻11号(2016年11月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症診療—整形外科からの発信
51巻10号(2016年10月発行)
誌上シンポジウム 高気圧酸素治療の現状と可能性
51巻9号(2016年9月発行)
誌上シンポジウム THAのアプローチ
51巻8号(2016年8月発行)
誌上シンポジウム 脊椎診療ガイドライン—特徴と導入効果
51巻7号(2016年7月発行)
誌上シンポジウム 脊椎腫瘍 最近の話題
51巻6号(2016年6月発行)
51巻5号(2016年5月発行)
誌上シンポジウム 整形外科と慢性腎不全
51巻4号(2016年4月発行)
誌上シンポジウム THA後感染の予防・診断・治療の最前線
51巻3号(2016年3月発行)
誌上シンポジウム 半月変性断裂に対する治療
51巻2号(2016年2月発行)
誌上シンポジウム MISの功罪
51巻1号(2016年1月発行)
50巻12号(2015年12月発行)
特集 世界にインパクトを与えた日本の整形外科
50巻11号(2015年11月発行)
誌上シンポジウム 成人脊柱変形へのアプローチ
50巻10号(2015年10月発行)
誌上シンポジウム 人工骨移植の現状と展望
50巻9号(2015年9月発行)
誌上シンポジウム Life is Motion—整形外科医が知りたい筋肉の科学
50巻8号(2015年8月発行)
誌上シンポジウム 反復性肩関節脱臼後のスポーツ復帰
50巻7号(2015年7月発行)
50巻6号(2015年6月発行)
50巻5号(2015年5月発行)
誌上シンポジウム 股関節鏡の現状と可能性
50巻4号(2015年4月発行)
誌上シンポジウム 難治性テニス肘はこうみる
50巻3号(2015年3月発行)
誌上シンポジウム 骨軟部腫瘍における画像評価最前線
50巻2号(2015年2月発行)
誌上シンポジウム 関節リウマチ—生物学的製剤使用で変化したこと
50巻1号(2015年1月発行)
49巻12号(2014年12月発行)
49巻11号(2014年11月発行)
誌上シンポジウム 運動器画像診断の進歩
49巻10号(2014年10月発行)
誌上シンポジウム 検診からわかる整形外科疾患
49巻9号(2014年9月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症に対する治療戦略
49巻8号(2014年8月発行)
49巻7号(2014年7月発行)
49巻6号(2014年6月発行)
誌上シンポジウム MIS人工膝関節置換術の現状と展望
49巻5号(2014年5月発行)
49巻4号(2014年4月発行)
誌上シンポジウム 整形外科外傷治療の進歩
49巻3号(2014年3月発行)
誌上シンポジウム 良性腫瘍に対する最新の治療戦略
49巻2号(2014年2月発行)
49巻1号(2014年1月発行)
誌上シンポジウム 下肢壊疽の最新治療
48巻12号(2013年12月発行)
誌上シンポジウム 慢性疼痛と原因療法―どこまで追究が可能か
48巻11号(2013年11月発行)
48巻10号(2013年10月発行)
誌上シンポジウム 低出力超音波パルス(LIPUS)による骨折治療―基礎と臨床における最近の話題
48巻9号(2013年9月発行)
48巻8号(2013年8月発行)
48巻7号(2013年7月発行)
誌上シンポジウム 転移性骨腫瘍―治療の進歩
48巻6号(2013年6月発行)
48巻5号(2013年5月発行)
48巻4号(2013年4月発行)
誌上シンポジウム 腰椎変性側弯症の手術―現状と課題
48巻3号(2013年3月発行)
誌上シンポジウム 創外固定の将来展望
48巻2号(2013年2月発行)
誌上シンポジウム 高齢者の腱板断裂
48巻1号(2013年1月発行)
47巻12号(2012年12月発行)
誌上シンポジウム 高位脛骨骨切り術の適応と限界
47巻11号(2012年11月発行)
誌上シンポジウム 橈骨遠位端骨折の治療
47巻10号(2012年10月発行)
誌上シンポジウム 内視鏡診断・治療の最前線
47巻9号(2012年9月発行)
誌上シンポジウム 脊椎脊髄手術の医療安全
47巻8号(2012年8月発行)
誌上シンポジウム 難治性足部スポーツ傷害の治療
47巻7号(2012年7月発行)
47巻6号(2012年6月発行)
誌上シンポジウム 難治性良性腫瘍の治療
47巻5号(2012年5月発行)
誌上シンポジウム 重度後縦靱帯骨化症に対する術式選択と合併症
47巻4号(2012年4月発行)
誌上シンポジウム 壮年期変形性股関節症の診断と関節温存療法
47巻3号(2012年3月発行)
誌上シンポジウム 大震災と整形外科医
47巻2号(2012年2月発行)
47巻1号(2012年1月発行)
誌上シンポジウム 整形外科領域における蛍光イメージング
46巻12号(2011年12月発行)
46巻11号(2011年11月発行)
46巻10号(2011年10月発行)
46巻9号(2011年9月発行)
誌上シンポジウム 生物学的製剤が与えた関節リウマチの病態・治療の変化
46巻8号(2011年8月発行)
46巻7号(2011年7月発行)
46巻6号(2011年6月発行)
誌上シンポジウム 腰部脊柱管狭窄[症]に対する手術戦略
46巻5号(2011年5月発行)
46巻4号(2011年4月発行)
誌上シンポジウム 運動器の慢性疼痛に対する薬物療法の新展開
46巻3号(2011年3月発行)
46巻2号(2011年2月発行)
46巻1号(2011年1月発行)
45巻12号(2010年12月発行)
誌上シンポジウム 小児の肩関節疾患
45巻11号(2010年11月発行)
45巻10号(2010年10月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症診断・治療の新展開
45巻9号(2010年9月発行)
誌上シンポジウム 軟骨再生―基礎と臨床
45巻8号(2010年8月発行)
誌上シンポジウム 四肢のしびれ感
45巻7号(2010年7月発行)
45巻6号(2010年6月発行)
誌上シンポジウム 整形外科領域における抗菌薬の使い方
45巻5号(2010年5月発行)
誌上シンポジウム 整形外科医の未来像―多様化したニーズへの対応
45巻4号(2010年4月発行)
45巻3号(2010年3月発行)
誌上シンポジウム 軟部腫瘍の診断と治療
45巻2号(2010年2月発行)
誌上シンポジウム 肩腱板不全断裂
45巻1号(2010年1月発行)
誌上シンポジウム 慢性腰痛症の保存的治療
44巻12号(2009年12月発行)
44巻11号(2009年11月発行)
44巻10号(2009年10月発行)
誌上シンポジウム 整形外科術後感染の実態と予防対策
44巻9号(2009年9月発行)
誌上シンポジウム 高齢者骨折と転倒予防
44巻8号(2009年8月発行)
誌上シンポジウム 創傷処置に関する最近の進歩
44巻7号(2009年7月発行)
44巻6号(2009年6月発行)
44巻5号(2009年5月発行)
誌上シンポジウム プレート骨接合術―従来型かLCPか
44巻4号(2009年4月発行)
44巻3号(2009年3月発行)
44巻2号(2009年2月発行)
誌上シンポジウム 膝骨壊死の病態と治療
44巻1号(2009年1月発行)
誌上シンポジウム 整形外科における人工骨移植の現状と展望
43巻12号(2008年12月発行)
43巻11号(2008年11月発行)
誌上シンポジウム 外傷性肩関節脱臼
43巻10号(2008年10月発行)
誌上シンポジウム 発育期大腿骨頭の壊死性病変への対応
43巻9号(2008年9月発行)
43巻8号(2008年8月発行)
誌上シンポジウム 腰椎変性側弯の治療選択
43巻7号(2008年7月発行)
誌上シンポジウム 人工股関節術後の骨折の治療
43巻6号(2008年6月発行)
誌上シンポジウム 胸椎後縦靱帯骨化症の治療―最近の進歩
43巻5号(2008年5月発行)
誌上シンポジウム 手・肘関節鏡手術の現況と展望
43巻4号(2008年4月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症性脊椎骨折の病態
43巻3号(2008年3月発行)
誌上シンポジウム 変形性手関節症の治療
43巻2号(2008年2月発行)
誌上シンポジウム 整形外科手術におけるコンピュータナビゲーション支援
43巻1号(2008年1月発行)
誌上シンポジウム 高齢者(80歳以上)に対する人工膝関節置換術
42巻12号(2007年12月発行)
42巻11号(2007年11月発行)
42巻10号(2007年10月発行)
誌上シンポジウム 外傷性頚部症候群―最近の進歩
42巻9号(2007年9月発行)
誌上シンポジウム 骨折治療の最新知見―小侵襲骨接合術とNavigation system
42巻8号(2007年8月発行)
42巻7号(2007年7月発行)
誌上シンポジウム 人工股関節手術における骨セメント使用時の工夫と問題点
42巻6号(2007年6月発行)
誌上シンポジウム 整形外科疾患における痛みの研究
42巻5号(2007年5月発行)
誌上シンポジウム 肩こりの病態と治療
42巻4号(2007年4月発行)
誌上シンポジウム 関節軟骨とヒアルロン酸
42巻3号(2007年3月発行)
誌上シンポジウム 腰椎椎間板ヘルニア治療の最前線
42巻2号(2007年2月発行)
42巻1号(2007年1月発行)
誌上シンポジウム 変形性膝関節症―最近の進歩
41巻12号(2006年12月発行)
誌上シンポジウム 肘不安定症の病態と治療
41巻11号(2006年11月発行)
41巻10号(2006年10月発行)
41巻9号(2006年9月発行)
41巻8号(2006年8月発行)
誌上シンポジウム 腰部脊柱管狭窄症―最近の進歩
41巻7号(2006年7月発行)
誌上シンポジウム 運動器リハビリテーションの効果
41巻6号(2006年6月発行)
41巻5号(2006年5月発行)
41巻4号(2006年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学 最近の進歩 2006(第34回日本脊椎脊髄病学会より)
41巻3号(2006年3月発行)
41巻2号(2006年2月発行)
誌上シンポジウム de Quervain病の治療
41巻1号(2006年1月発行)
40巻12号(2005年12月発行)
40巻11号(2005年11月発行)
誌上シンポジウム 整形外科疾患における骨代謝マーカーの応用
40巻10号(2005年10月発行)
誌上シンポジウム 関節鏡を用いた腱板断裂の治療
40巻9号(2005年9月発行)
特別シンポジウム どうする日本の医療
40巻8号(2005年8月発行)
誌上シンポジウム 整形外科におけるリスクマネジメント
40巻7号(2005年7月発行)
40巻6号(2005年6月発行)
誌上シンポジウム 脊柱短縮術
40巻5号(2005年5月発行)
40巻4号(2005年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学 最近の進歩 2005(第33回日本脊椎脊髄病学会より)
40巻3号(2005年3月発行)
40巻2号(2005年2月発行)
誌上シンポジウム 前腕回旋障害の病態と治療
40巻1号(2005年1月発行)
39巻12号(2004年12月発行)
誌上シンポジウム 小児大腿骨頚部骨折の治療法とその成績
39巻11号(2004年11月発行)
39巻10号(2004年10月発行)
誌上シンポジウム 関節リウマチ頚椎病変の病態・治療・予後
39巻9号(2004年9月発行)
39巻8号(2004年8月発行)
誌上シンポジウム 診療ガイドラインの方向性―臨床に役立つガイドラインとは
39巻7号(2004年7月発行)
39巻6号(2004年6月発行)
39巻5号(2004年5月発行)
シンポジウム 手指の関節外骨折
39巻4号(2004年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学 最近の進歩 2004(第32回日本脊椎脊髄病学会より)
39巻3号(2004年3月発行)
39巻2号(2004年2月発行)
39巻1号(2004年1月発行)
シンポジウム 外傷に対するプライマリケア―保存療法を中心に
38巻12号(2003年12月発行)
38巻11号(2003年11月発行)
シンポジウム RSDを含む頑固なneuropathic painの病態と治療
38巻10号(2003年10月発行)
シンポジウム 整形外科医療におけるリスクマネジメント
38巻9号(2003年9月発行)
シンポジウム 全人工肩関節置換術の成績
38巻8号(2003年8月発行)
シンポジウム 難治性骨折の治療
38巻7号(2003年7月発行)
38巻6号(2003年6月発行)
シンポジウム 脊椎転移癌に対する治療法の選択
38巻5号(2003年5月発行)
シンポジウム 外傷に伴う呼吸器合併症の予防と治療
38巻4号(2003年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学最近の進歩 2003(第31回日本脊椎脊髄病学会より)
38巻3号(2003年3月発行)
シンポジウム 腰椎変性すべり症の治療
38巻2号(2003年2月発行)
シンポジウム 膝複合靱帯損傷に対する保存療法および観血的治療の選択
38巻1号(2003年1月発行)
37巻12号(2002年12月発行)
37巻11号(2002年11月発行)
シンポジウム 手術支援ロボティックシステム
37巻10号(2002年10月発行)
37巻9号(2002年9月発行)
シンポジウム 橈骨遠位端骨折の保存的治療のこつと限界
37巻8号(2002年8月発行)
37巻7号(2002年7月発行)
37巻6号(2002年6月発行)
シンポジウム スポーツ肩障害の病態と治療
37巻5号(2002年5月発行)
シンポジウム 縮小手術への挑戦―縮小手術はどこまで可能か
37巻4号(2002年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学最近の進歩(第30回日本脊椎脊髄病学会より)
37巻3号(2002年3月発行)
37巻2号(2002年2月発行)
37巻1号(2002年1月発行)
シンポジウム 足関節捻挫後遺障害の病態と治療
36巻12号(2001年12月発行)
シンポジウム 手根部骨壊死疾患の病態と治療
36巻11号(2001年11月発行)
シンポジウム 頚肩腕症候群と肩こり―疾患概念とその病態
36巻10号(2001年10月発行)
シンポジウム 下肢長管骨骨折に対するminimally invasive surgery
36巻9号(2001年9月発行)
36巻8号(2001年8月発行)
36巻7号(2001年7月発行)
36巻6号(2001年6月発行)
シンポジウム 膝複合靭帯損傷の診断と治療
36巻5号(2001年5月発行)
36巻4号(2001年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進歩―主題とパネル演題を中心に(第29回日本脊椎外科学会より)
36巻3号(2001年3月発行)
36巻2号(2001年2月発行)
シンポジウム 舟状骨偽関節に対する治療
36巻1号(2001年1月発行)
35巻13号(2000年12月発行)
シンポジウム 21世記の整形外科移植医療~その基礎から臨床応用に向けて
35巻12号(2000年11月発行)
35巻11号(2000年10月発行)
シンポジウム スポーツによる肘関節障害の診断・治療
35巻10号(2000年9月発行)
35巻9号(2000年8月発行)
35巻8号(2000年7月発行)
35巻7号(2000年6月発行)
35巻6号(2000年5月発行)
35巻5号(2000年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進歩―長期予後からみた問題点を中心として―(第28回日本脊椎外科学会より)
35巻4号(2000年3月発行)
35巻3号(2000年2月発行)
シンポジウム 変形性膝関節症の病態からみた治療法の選択
35巻2号(2000年2月発行)
35巻1号(2000年1月発行)
34巻12号(1999年12月発行)
シンポジウム 脊椎内視鏡手術―最近の進歩
34巻11号(1999年11月発行)
シンポジウム 日本における新しい人工股関節の開発
34巻10号(1999年10月発行)
34巻9号(1999年9月発行)
34巻8号(1999年8月発行)
34巻7号(1999年7月発行)
34巻6号(1999年6月発行)
シンポジウム 整形外科と運動療法
34巻5号(1999年5月発行)
34巻4号(1999年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進捗―脊椎骨切り術と脊椎再建を中心として―(第27回日本脊椎外科学会より)
34巻3号(1999年3月発行)
シンポジウム オステオポローシスの評価と治療方針
34巻2号(1999年2月発行)
シンポジウム 日本における新しい人工膝関節の開発
34巻1号(1999年1月発行)
33巻12号(1998年12月発行)
33巻11号(1998年11月発行)
33巻10号(1998年10月発行)
33巻9号(1998年9月発行)
33巻8号(1998年8月発行)
シンポジウム 骨組織に対する力学的負荷とその制御―日常臨床に生かす視点から
33巻7号(1998年7月発行)
33巻6号(1998年6月発行)
33巻5号(1998年5月発行)
33巻4号(1998年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進歩―OPLLを中心として―(第26回日本脊椎外科学会より)
33巻3号(1998年3月発行)
シンポジウム 大きな骨欠損に対する各種治療法の利害得失
33巻2号(1998年2月発行)
シンポジウム 人工股関節置換術の再手術における私の工夫
33巻1号(1998年1月発行)
32巻12号(1997年12月発行)
32巻11号(1997年11月発行)
シンポジウム 腰椎変性疾患に対するspinal instrumentation―適応と問題点―
32巻10号(1997年10月発行)
32巻9号(1997年9月発行)
32巻8号(1997年8月発行)
32巻7号(1997年7月発行)
32巻6号(1997年6月発行)
32巻5号(1997年5月発行)
32巻4号(1997年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進歩(第25回日本脊椎外科学会より)
32巻3号(1997年3月発行)
32巻2号(1997年2月発行)
シンポジウム 脊柱側弯症に対する最近の手術療法
32巻1号(1997年1月発行)
シンポジウム 骨肉腫の診断と治療のトピックス
31巻12号(1996年12月発行)
31巻11号(1996年11月発行)
31巻10号(1996年10月発行)
31巻9号(1996年9月発行)
31巻8号(1996年8月発行)
31巻7号(1996年7月発行)
31巻6号(1996年6月発行)
31巻5号(1996年5月発行)
31巻4号(1996年4月発行)
特集 脊椎外傷の最近の進歩(上位頚椎を除く)(第24回日本脊椎外科学会より)
31巻3号(1996年3月発行)
31巻2号(1996年2月発行)
31巻1号(1996年1月発行)
シンポジウム 腰椎変性すべり症の手術
30巻12号(1995年12月発行)
30巻11号(1995年11月発行)
30巻10号(1995年10月発行)
30巻9号(1995年9月発行)
30巻8号(1995年8月発行)
30巻7号(1995年7月発行)
シンポジウム 原発性脊椎悪性腫瘍の治療
30巻6号(1995年6月発行)
30巻5号(1995年5月発行)
30巻4号(1995年4月発行)
特集 上位頚椎疾患―その病態と治療(第23回日本脊椎外科学会より)
30巻3号(1995年3月発行)
シンポジウム 膝関節のUnicompartmental Arthroplasty
30巻2号(1995年2月発行)
シンポジウム 機能的電気刺激(FES)の理論と実際
30巻1号(1995年1月発行)
シンポジウム 長期成績からみたBipolar型人工股関節の適応の再検討
29巻12号(1994年12月発行)
29巻11号(1994年11月発行)
29巻10号(1994年10月発行)
29巻9号(1994年9月発行)
29巻8号(1994年8月発行)
29巻7号(1994年7月発行)
シンポジウム 慢性関節リウマチ頚椎病変
29巻6号(1994年6月発行)
シンポジウム 変性腰部脊柱管狭窄症の手術的治療と長期成績
29巻5号(1994年5月発行)
29巻4号(1994年4月発行)
特集 椎間板―基礎と臨床(第22回日本脊椎外科学会より)
29巻3号(1994年3月発行)
29巻2号(1994年2月発行)
シンポジウム 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)をめぐって
29巻1号(1994年1月発行)
シンポジウム 関節スポーツ外傷の診断と治療―最近の進歩
28巻12号(1993年12月発行)
28巻11号(1993年11月発行)
28巻10号(1993年10月発行)
28巻9号(1993年9月発行)
28巻8号(1993年8月発行)
28巻7号(1993年7月発行)
28巻6号(1993年6月発行)
28巻5号(1993年5月発行)
28巻4号(1993年4月発行)
特集 痛みをとらえる(第21回日本脊椎外科学会より)
28巻3号(1993年3月発行)
シンポジウム 癌性疼痛に対する各種治療法の適応と限界
28巻2号(1993年2月発行)
28巻1号(1993年1月発行)
シンポジウム 外反母趾の治療
27巻12号(1992年12月発行)
27巻11号(1992年11月発行)
シンポジウム 膝十字靱帯再建における素材の選択
27巻10号(1992年10月発行)
27巻9号(1992年9月発行)
27巻8号(1992年8月発行)
27巻7号(1992年7月発行)
27巻6号(1992年6月発行)
27巻5号(1992年5月発行)
シンポジウム ペルテス病の長期予後
27巻4号(1992年4月発行)
特集 主題・腰部脊柱管狭窄症/パネルI・脊椎転移性腫瘍の手術的治療/パネルII・脊椎脊髄MRI診断(第20回日本脊椎外科学会より)
27巻3号(1992年3月発行)
シンポジウム 頸部脊柱管拡大術の長期成績
27巻2号(1992年2月発行)
27巻1号(1992年1月発行)
26巻12号(1991年12月発行)
26巻11号(1991年11月発行)
26巻10号(1991年10月発行)
シンポジウム 脊髄損傷の神経病理とMRI画像
26巻9号(1991年9月発行)
26巻8号(1991年8月発行)
26巻7号(1991年7月発行)
26巻6号(1991年6月発行)
シンポジウム 悪性骨軟部腫瘍への挑戦
26巻5号(1991年5月発行)
シンポジウム 先天性股関節脱臼に対する牽引療法―その方法と後療法を具体的に
26巻4号(1991年4月発行)
特集 主題I:Spinal Dysraphism/主題II:Pedicular Screwing(第19回日本脊椎外科学会より)
26巻3号(1991年3月発行)
26巻2号(1991年2月発行)
シンポジウム 先天性股関節脱臼に対する治療法の限界と展望
26巻1号(1991年1月発行)
25巻12号(1990年12月発行)
25巻11号(1990年11月発行)
25巻10号(1990年10月発行)
25巻9号(1990年9月発行)
シンポジウム 機能的電気刺激(FES)の基礎と臨床
25巻8号(1990年8月発行)
25巻7号(1990年7月発行)
25巻6号(1990年6月発行)
25巻5号(1990年5月発行)
25巻4号(1990年4月発行)
特集 不安定腰椎(第18回日本脊椎外科研究会より)
25巻3号(1990年3月発行)
シンポジウム 予防処置導入後の乳児先天股脱
25巻2号(1990年2月発行)
25巻1号(1990年1月発行)
シンポジウム 全人工股関節置換術―セメント使用と非使用:その得失―
24巻12号(1989年12月発行)
24巻11号(1989年11月発行)
24巻10号(1989年10月発行)
24巻9号(1989年9月発行)
24巻8号(1989年8月発行)
24巻7号(1989年7月発行)
24巻6号(1989年6月発行)
24巻5号(1989年5月発行)
シンポジウム Rb法の限界
24巻4号(1989年4月発行)
特集 不安定頸椎—基礎と臨床—(第17回日本脊髄外科研究会より)
24巻3号(1989年3月発行)
24巻2号(1989年2月発行)
24巻1号(1989年1月発行)
シンポジウム 広範囲腱板断裂の再建
23巻12号(1988年12月発行)
23巻11号(1988年11月発行)
23巻10号(1988年10月発行)
シンポジウム 大腿骨頭壊死症の最近の進歩
23巻9号(1988年9月発行)
シンポジウム 変形性股関節症に対するBipolar型人工骨頭の臨床応用
23巻8号(1988年8月発行)
23巻7号(1988年7月発行)
23巻6号(1988年6月発行)
23巻5号(1988年5月発行)
23巻4号(1988年4月発行)
特集 脊柱管内靱帯骨化の病態と治療(第16回日本脊椎外科研究会より)
23巻3号(1988年3月発行)
23巻2号(1988年2月発行)
シンポジウム 日本におけるスポーツ整形外科の現状と将来
23巻1号(1988年1月発行)
22巻12号(1987年12月発行)
22巻11号(1987年11月発行)
22巻10号(1987年10月発行)
シンポジウム 骨肉腫の患肢温存療法
22巻9号(1987年9月発行)
22巻8号(1987年8月発行)
シンポジウム 椎間板注入療法の基礎
22巻7号(1987年7月発行)
シンポジウム 多発骨傷
22巻6号(1987年6月発行)
22巻5号(1987年5月発行)
シンポジウム 人工膝関節の長期成績
22巻4号(1987年4月発行)
特集 腰仙部根症状の発症機序—基礎と臨床—(第15回日本脊椎外科研究会より)
22巻3号(1987年3月発行)
シンポジウム 骨悪性線維性組織球腫
22巻2号(1987年2月発行)
シンポジウム 陳旧性肘関節周囲骨折の治療
22巻1号(1987年1月発行)
シンポジウム 陳旧性膝関節重度靱帯損傷の治療
21巻12号(1986年12月発行)
シンポジウム セメントレス人工股関節
21巻11号(1986年11月発行)
シンポジウム Bioactive Ceramics研究における最近の進歩
21巻10号(1986年10月発行)
シンポジウム 骨軟骨移植の進歩
21巻9号(1986年9月発行)
21巻8号(1986年8月発行)
21巻7号(1986年7月発行)
シンポジウム 頸椎多数回手術例の検討
21巻6号(1986年6月発行)
21巻5号(1986年5月発行)
21巻4号(1986年4月発行)
特集 脊椎・脊髄外科診断学の進歩(第14回日本脊椎外科研究会より)
21巻3号(1986年3月発行)
21巻2号(1986年2月発行)
21巻1号(1986年1月発行)
シンポジウム 骨盤臼蓋の発育
20巻12号(1985年12月発行)
20巻11号(1985年11月発行)
シンポジウム 骨肉腫の化学療法
20巻10号(1985年10月発行)
20巻9号(1985年9月発行)
20巻8号(1985年8月発行)
20巻7号(1985年7月発行)
シンポジウム 骨巨細胞腫の診断と治療
20巻6号(1985年6月発行)
20巻5号(1985年5月発行)
シンポジウム 人工股関節再置換術の問題点
20巻4号(1985年4月発行)
特集 Spinal Instrumentation(第13回脊椎外科研究会より)
20巻3号(1985年3月発行)
20巻2号(1985年2月発行)
20巻1号(1985年1月発行)
19巻12号(1984年12月発行)
19巻11号(1984年11月発行)
19巻10号(1984年10月発行)
19巻9号(1984年9月発行)
19巻8号(1984年8月発行)
19巻7号(1984年7月発行)
19巻6号(1984年6月発行)
特集 小児股関節(第22回先天股脱研究会より)
19巻5号(1984年5月発行)
19巻4号(1984年4月発行)
特集 頸部脊椎症(第12回脊椎外科研究会より)
19巻3号(1984年3月発行)
19巻2号(1984年2月発行)
19巻1号(1984年1月発行)
シンポジウム 関節鏡視下手術
18巻13号(1983年12月発行)
シンポジウム 電気刺激による骨形成
18巻12号(1983年11月発行)
18巻11号(1983年10月発行)
シンポジウム 四肢軟部腫瘍
18巻10号(1983年9月発行)
18巻9号(1983年8月発行)
シンポジウム 悪性軟部腫瘍の病理診断をめぐって
18巻8号(1983年7月発行)
18巻7号(1983年7月発行)
18巻6号(1983年6月発行)
シンポジウム 先天股脱初期整復後の側方化
18巻5号(1983年5月発行)
18巻4号(1983年4月発行)
特集 上位頸椎部の諸問題
18巻3号(1983年3月発行)
18巻2号(1983年2月発行)
18巻1号(1983年1月発行)
17巻12号(1982年12月発行)
17巻11号(1982年11月発行)
シンポジウム 人工股関節再手術例の検討
17巻10号(1982年10月発行)
17巻9号(1982年9月発行)
17巻8号(1982年8月発行)
17巻7号(1982年7月発行)
17巻6号(1982年6月発行)
17巻5号(1982年5月発行)
17巻4号(1982年4月発行)
特集 脊椎分離症・辷り症
17巻3号(1982年3月発行)
17巻2号(1982年2月発行)
17巻1号(1982年1月発行)
16巻12号(1981年12月発行)
シンポジウム 動揺性肩関節
16巻11号(1981年11月発行)
シンポジウム 特発性大腿骨頭壊死
16巻10号(1981年10月発行)
16巻9号(1981年9月発行)
シンポジウム 義肢装具をめぐる諸問題
16巻8号(1981年8月発行)
シンポジウム 脱臼ペルテスとペルテス病
16巻7号(1981年7月発行)
16巻6号(1981年6月発行)
シンポジウム 腰部脊柱管狭窄—ことにdegenerative stenosisの診断と治療
16巻5号(1981年5月発行)
16巻4号(1981年4月発行)
特集 Multiply operated back
16巻3号(1981年3月発行)
シンポジウムII Riemenbügel法不成功例の原因と対策
16巻2号(1981年2月発行)
シンポジウム 人工股関節置換術—この10年の結果をふりかえって
16巻1号(1981年1月発行)
シンポジウム 胸椎部脊椎管狭窄症の病態と治療
15巻12号(1980年12月発行)
15巻11号(1980年11月発行)
15巻10号(1980年10月発行)
15巻9号(1980年9月発行)
15巻8号(1980年8月発行)
15巻7号(1980年7月発行)
15巻6号(1980年6月発行)
15巻5号(1980年5月発行)
シンポジウム 先天股脱の予防
15巻4号(1980年4月発行)
シンポジウム CTと整形外科
15巻3号(1980年3月発行)
特集 脊椎腫瘍(第8回脊椎外科研究会より)
15巻2号(1980年2月発行)
15巻1号(1980年1月発行)
14巻12号(1979年12月発行)
14巻11号(1979年11月発行)
14巻10号(1979年10月発行)
14巻9号(1979年9月発行)
シンポジウム 最近の抗リウマチ剤の動向
14巻8号(1979年8月発行)
14巻7号(1979年7月発行)
シンポジウム 五十肩の治療
14巻6号(1979年6月発行)
14巻5号(1979年5月発行)
14巻4号(1979年4月発行)
特集 脊椎外傷—早期の病態・診断・治療—(第7回脊椎外科研究会より)
14巻3号(1979年3月発行)
14巻2号(1979年2月発行)
14巻1号(1979年1月発行)
13巻12号(1978年12月発行)
13巻11号(1978年11月発行)
13巻10号(1978年10月発行)
13巻9号(1978年9月発行)
13巻8号(1978年8月発行)
13巻7号(1978年7月発行)
13巻6号(1978年6月発行)
13巻5号(1978年5月発行)
13巻4号(1978年4月発行)
特集 脊椎の炎症性疾患
13巻3号(1978年3月発行)
13巻2号(1978年2月発行)
13巻1号(1978年1月発行)
12巻12号(1977年12月発行)
12巻11号(1977年11月発行)
12巻10号(1977年10月発行)
12巻9号(1977年9月発行)
12巻8号(1977年8月発行)
12巻7号(1977年7月発行)
12巻6号(1977年6月発行)
12巻5号(1977年5月発行)
12巻4号(1977年4月発行)
特集 胸椎部ミエロパチー
12巻3号(1977年3月発行)
12巻2号(1977年2月発行)
12巻1号(1977年1月発行)
11巻12号(1976年12月発行)
11巻11号(1976年11月発行)
11巻10号(1976年10月発行)
11巻9号(1976年9月発行)
11巻8号(1976年8月発行)
特集 腰部脊柱管狭窄の諸問題
11巻7号(1976年7月発行)
11巻6号(1976年6月発行)
11巻5号(1976年5月発行)
11巻4号(1976年4月発行)
11巻3号(1976年3月発行)
11巻2号(1976年2月発行)
シンポジウム Silicone rod
11巻1号(1976年1月発行)
10巻12号(1975年12月発行)
特集II Myelopathy・Radiculopathy
10巻11号(1975年11月発行)
シンポジウム 頸部脊椎症性ミエロパチー
10巻10号(1975年10月発行)
シンポジウム 関節軟骨の病態
10巻9号(1975年9月発行)
10巻8号(1975年8月発行)
10巻7号(1975年7月発行)
シンポジウム 慢性関節リウマチの前足部変形に対する治療
10巻6号(1975年6月発行)
10巻5号(1975年5月発行)
10巻4号(1975年4月発行)
10巻3号(1975年3月発行)
10巻2号(1975年2月発行)
10巻1号(1975年1月発行)
9巻12号(1974年12月発行)
9巻11号(1974年11月発行)
特集 脊椎外科(第1回脊椎外科研究会より)
9巻10号(1974年10月発行)
9巻9号(1974年9月発行)
9巻8号(1974年8月発行)
9巻7号(1974年7月発行)
シンポジウム 変形性股関節症の手術療法
9巻6号(1974年6月発行)
9巻5号(1974年5月発行)
9巻4号(1974年4月発行)
9巻3号(1974年3月発行)
9巻2号(1974年2月発行)
9巻1号(1974年1月発行)
8巻12号(1973年12月発行)
8巻11号(1973年11月発行)
8巻10号(1973年10月発行)
シンポジウム 移植皮膚の生態
8巻9号(1973年9月発行)
8巻8号(1973年8月発行)
8巻7号(1973年7月発行)
8巻6号(1973年6月発行)
8巻5号(1973年5月発行)
シンポジウム 顔面外傷
8巻4号(1973年4月発行)
8巻3号(1973年3月発行)
8巻2号(1973年2月発行)
シンポジウム 乳幼児先天股脱の手術療法
8巻1号(1973年1月発行)
7巻12号(1972年12月発行)
7巻11号(1972年11月発行)
7巻10号(1972年10月発行)
シンポジウム 膝の人工関節
7巻9号(1972年9月発行)
7巻8号(1972年8月発行)
7巻7号(1972年7月発行)
7巻6号(1972年6月発行)
7巻5号(1972年5月発行)
7巻4号(1972年4月発行)
7巻3号(1972年3月発行)
7巻2号(1972年2月発行)
7巻1号(1972年1月発行)
6巻12号(1971年12月発行)
6巻11号(1971年11月発行)
6巻10号(1971年10月発行)
6巻9号(1971年9月発行)
6巻8号(1971年8月発行)
6巻7号(1971年7月発行)
シンポジウム 四肢末梢血管障害
6巻6号(1971年6月発行)
6巻5号(1971年5月発行)
6巻4号(1971年4月発行)
6巻3号(1971年3月発行)
6巻2号(1971年2月発行)
6巻1号(1971年1月発行)
5巻12号(1970年12月発行)
5巻11号(1970年11月発行)
5巻10号(1970年10月発行)
5巻9号(1970年9月発行)
5巻8号(1970年8月発行)
5巻7号(1970年7月発行)
5巻6号(1970年6月発行)
5巻5号(1970年5月発行)
5巻4号(1970年4月発行)
5巻3号(1970年3月発行)
5巻2号(1970年2月発行)
5巻1号(1970年1月発行)
4巻12号(1969年12月発行)
4巻11号(1969年11月発行)
4巻10号(1969年10月発行)
4巻9号(1969年9月発行)
4巻8号(1969年8月発行)
シンポジウム 腰部椎間板症
4巻7号(1969年7月発行)
4巻6号(1969年6月発行)
4巻5号(1969年5月発行)
4巻4号(1969年4月発行)
4巻3号(1969年3月発行)
4巻2号(1969年2月発行)
4巻1号(1969年1月発行)
3巻12号(1968年12月発行)
3巻11号(1968年11月発行)
シンポジウム 股関節形成術
3巻10号(1968年10月発行)
シンポジウム 日本の義肢問題
3巻9号(1968年9月発行)
シンポジウム 内反足
3巻8号(1968年8月発行)
シンポジウム 腕神経叢損傷
3巻7号(1968年7月発行)
3巻6号(1968年6月発行)
3巻5号(1968年5月発行)
シンポジウム 脊髄損傷患者に対する早期脊椎固定術の適応と成績
3巻4号(1968年4月発行)
シンポジウム いわゆる鞭打ち損傷
3巻3号(1968年3月発行)
3巻2号(1968年2月発行)
3巻1号(1968年1月発行)
2巻12号(1967年12月発行)
2巻11号(1967年11月発行)
2巻10号(1967年10月発行)
2巻9号(1967年9月発行)
2巻8号(1967年8月発行)
シンポジウム 脳性麻痺
2巻7号(1967年7月発行)
2巻6号(1967年6月発行)
シンポジウム 腰痛
2巻5号(1967年5月発行)
シンポジウム 骨肉腫の治療および予後
2巻4号(1967年4月発行)
シンポジウム 関節リウマチの治療
2巻3号(1967年3月発行)
シンポジウム 先天性股関節脱臼 私の治療法
2巻2号(1967年2月発行)
シンポジウム 先天性筋性斜頸 私の治療法
2巻1号(1967年1月発行)
シンポジウム 脊髄損傷
