整形外科外傷学は数ある整形外科のサブスペシャリティーの中で,最も基礎的な分野でありながら,奥深く難しい分野でもあります.今回,その整形外科外傷学の魅力を多くの方々にお伝えしたく本企画を考案しました.執筆陣は,現在本分野の第一線で活躍されている先生方に打診いたしましたところ,皆さん売れっ子であちこち引っ張りだこであるにもかかわらず,快く引き受けてくださり,期待以上に素晴らしい原稿を仕上げていただきました.この場を借りて改めて感謝申し上げます.
本特集を企画するにあたり特に意識したことは,巷に多くの良書がある中でも興味を持って本書を手に取っていただけるような構成と内容にすることでした.まず冒頭の座談会では,整形外傷教育の普及や啓発活動を実践するために設立した任意団体「JOIN TRAUMA」の初期メンバー4名に集まっていただき,これまでの活動の振り返りと今後の10年について存分に語り合っていただきました.以後の構成は,1人の外傷整形外科医が日常臨床で遭遇するさまざまな状況を再現すべく,7つの場面に分けて項目を仕立てました.
雑誌目次
臨床整形外科59巻5号
2024年05月発行
雑誌目次
増大号特集 絶対! 整形外科外傷学
緒言 フリーアクセス
著者: 善家雄吉
ページ範囲:P.443 - P.443
座談会
JOIN TRAUMA設立から10年—整形外科外傷学のために,仲間と走ってきた. フリーアクセス
著者: 善家雄吉 , 松井健太郎 , 依光正則 , 二村謙太郎 , 北田真平
ページ範囲:P.448 - P.454
善家 任意団体として活動を続けてきましたJOIN TRAUMA(Japanese Orthopaedic INstitute for INnovation and renovation in TRAUMA)は設立から10年がたちました.今回の特集号が外傷に携わる若い読者を対象にした企画ということで,このJOIN TRAUMAの今までの10年を振り返り,そして今後の10年につなげていく,そんな趣旨で初期メンバーであるみなさんに話していただきたいと思います.
まず,設立時の代表である松井健太郎先生.初期の頃の話を聞かせていただけますか.
1章 整形医局(自習室)
ビジュアルにわかる骨癒合の基礎—バイオロジーとバイオメカニクス
著者: 新倉隆宏
ページ範囲:P.456 - P.463
Point!
●骨癒合(骨折治癒)の基礎を理解することは,臨床において必ず役に立つ.
●骨癒合の基礎を理解するにはバイオメカニクス(物理学的な観点)とバイオロジー(生物学的な観点),両方の観点が必要である.
●骨折治癒に関わる骨化形態には2種類ある.膜性骨化と軟骨内骨化(内軟骨性骨化)である.
●骨折治癒過程は,炎症,膜性骨化,軟骨形成,軟骨内骨化,リモデリングが段階的に,しかもそれぞれがオーバーラップしながら,絶妙なハーモニーを奏でつつ進行する.
●骨折治癒,すなわち骨癒合には2つのタイプがある.一次性骨癒合(直接的骨癒合)と二次性骨癒合(間接的骨癒合)である.
作図だけではない術前計画
著者: 前原孝 , 金子倫也 , 宇津朋生 , 近藤秀則
ページ範囲:P.464 - P.474
Point!
●「術前計画」には「作図」以外にも多くの要素が含まれている.
●「作図」は手術の理想的な完成形を頭の中に構築する作業であり,そこに至るまでの道筋を逆算しながら万全の準備をして手術に臨む必要がある.
●「術前計画」と術後の「振り返り」を繰り返すことによって,手術手技の精度やトラブル回避能力を向上させることができる.
—手術に必要なサージカルアプローチエッセンス—肩関節
著者: 最上敦彦 , 永井洋輔 , 松本匡洋
ページ範囲:P.475 - P.486
Point!
●上腕骨骨幹部骨折の髄内釘固定において,腱板を切開せずに腱板疎部(rotator interval:RI)から順行性に髄内釘を挿入する「RIアプローチ」は肩関節機能障害を来しにくい.
●上腕骨骨幹部骨折における橈骨神経確認に「上腕前外側アプローチ」は有用である.
●近年増加傾向にある肩甲骨骨折の手術加療において,これまでの「Judetアプローチ」に比べて「Brodskyアプローチ」は低侵襲・高汎用性のアプローチといえる.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
—手術に必要なサージカルアプローチエッセンス—肘関節
著者: 今谷潤也
ページ範囲:P.487 - P.494
Point!
●肘関節の支持機構としては,骨構造と軟部構造に二分され,これらはお互いに関連し合って機能している.
●神経・血管構造は複雑で,骨および関節に近接して存在している.
●肘関節の解剖学的特徴や位置関係を熟知することにより的確な病態把握や手術適応の決定,さらには適切な手術アプローチ法を選択でき,安全で低侵襲性な手術が可能となる.
●肘関節手術で用いられる主要な手術アプローチ,すなわち前方,外側,内側,後方アプローチの特徴や適応などについて詳述した.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
—手術に必要なサージカルアプローチエッセンス—手関節
著者: 安部幸雄
ページ範囲:P.495 - P.501
Point!
手関節には多数の腱,神経,血管が存在し,その展開には複雑な解剖構造を頭に入れておくことが重要である.アプローチごとのポイントは以下のとおりである.
●掌側アプローチ:①神経,血管,腱に注意,②橈骨遠位端骨折(DRF)に対しては橈側手根屈筋腱(FCR)と橈骨動脈の間から展開,③掌側月状骨窩(VLF)骨片へは皮切を尺側遠位に延長する.
●背側アプローチ:①背側正中切開,②橈骨,尺骨神経背側枝に注意,③伸筋支帯は閉創時の再建を見越しての切離が必要,④手関節内へはdorsal ligament-sparing capsular incisionあるいはwindow approachにて進入する.
●尺側アプローチ:①尺骨神経背側枝は尺骨遠位端より平均6〜7cm中枢で尺骨神経より分岐して,尺側手根屈筋腱(FCU)の深層尺側を走行する.そして尺骨遠位端より約1cm遠位で背側へ横切る.②尺骨遠位骨幹部尺側縁はinternervous planeである.
●関節鏡アプローチ:鏡視には適切な位置へのポータル作成が重要である.ポータルのほとんどが背側ポータルであり,作成にあたっては伸筋腱コンパートメントの理解が必須である.
橈骨手根関節(RCJ)では伸筋腱コンパートメントの3-4,4-5あるいは6R,手根中央関節(MCJ)ではこれらの約1cm遠位にポータルを作成する.遠位橈尺関節(DURJ)の鏡視には4-5ポータルの約1cm中枢の橈骨尺側切痕と尺骨頭の間に作成する.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
—手術に必要なサージカルアプローチエッセンス—骨盤・寛骨臼
著者: 普久原朝海
ページ範囲:P.502 - P.512
Point!
●骨盤輪骨折に対する創外固定法はNIIGATAがお勧め
●腸骨稜の展開は覆いかぶさる腹斜筋の展開方法がキモ
●PSIS周囲の展開は皮切をPSIS直上に置かないことが創部離開を防ぐコツ
●寛骨臼骨折の手術は必ずエキスパートがかかわることが重要
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
—手術に必要なサージカルアプローチエッセンス—股関節
著者: 神田章男
ページ範囲:P.513 - P.518
Point!
●Direct lateral approachは外側広筋から中殿筋・小殿筋まで縦の連続性を保ちつつ,筋線維方向に鈍的に剥離することが重要である.
●Direct anterior approachは関節包靱帯の修復がさらなる脱臼率低下のために有用となる.
●Direct anterior approachは特殊牽引台または一般牽引台を使用することにより手技が容易になる.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
—手術に必要なサージカルアプローチエッセンス—膝関節
著者: 依光正則
ページ範囲:P.519 - P.525
Point!
●大腿骨遠位部骨折では,関節内の骨折に対して発生部位に応じて最も適したアプローチを選択し,関節外の骨折は閉鎖的整復と外側プレート固定が可能である.
●脛骨近位部骨折では,外側関節面の圧潰が最も多く存在することから前外側アプローチに習熟することが必須である.
●両顆の骨折を伴う骨折では,関節面の整復に必要なアプローチと骨幹端部を有効に支持するプレートの設置に必要なアプローチを組み合わせて選択する.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
—手術に必要なサージカルアプローチエッセンス—足関節
著者: 松井健太郎
ページ範囲:P.526 - P.534
Point!
●足関節には360°アプローチが可能である.
●ピロン骨折において,どのアプローチを選択するか,どのように組み合わせるかの判断が肝となる.
●各アプローチの利点・欠点をすべてふまえたうえで手術法を決定する.
●軟部組織状態を評価し,手術時期を決定し,術中の皮膚の取り扱いには細心の注意を要する.
2章 整形外来
骨折診断のピットフォール
著者: 佐藤直人 , 善家雄吉 , 酒井昭典
ページ範囲:P.536 - P.541
Point!
●骨折の見逃しには,①そもそも疑うことができなかった場合と,②所見はあったが画像的に診断に至らなかった場合の2パターンがある.
●まずは見逃しやすい骨折があるということを認識しておく必要がある.
●骨折治療は,その初期治療が以後の転帰に及ぼす影響が大きい.
●そのため,日常診療で比較的遭遇しやすい肩関節・手関節・腰背部・股関節・足関節周囲の愁訴に対して,見逃しやすい骨折の具体例を筆者の経験を踏まえて解説する.
超音波を用いた新時代の外傷診療の現状と展望
著者: 宮武和馬 , 草場洋平 , 都竹伸哉 , 稲葉裕
ページ範囲:P.542 - P.548
Point!
●外傷診断にこそエコーは有用である.
●神経損傷を疑う際は必ず損傷部位をエコーで確認する.
●術後疼痛管理は持続カテーテル留置が有用である.
●術後遺残疼痛治療の選択肢に,ハイドロリリースがある.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
外来で対応可能な小手術のコツとピットフォール
著者: 大茂壽久
ページ範囲:P.549 - P.553
Point!
●安心・安全・確実な周術期管理は,術後成績と同等に外来手術において重要である.
●局所麻酔薬中毒(LAST)の症状と予防法,治療法について熟知しておく.
●小径関節鏡と周辺機器を用いることで,TFCC(triangular fibrocartilage complex)小窩部断裂手術は,低侵襲,短時間で修復可能である.
炭酸ガス経皮吸収療法による外傷後フォロー
著者: 戸羽直樹 , 飯山俊成
ページ範囲:P.554 - P.558
Point!
●炭酸ガス経皮吸収療法(以下,CO2療法)は,炭酸ガスの血管拡張作用・血流増加作用・Bohr効果による組織への酸素供給効果が原理と推察される治療法である.
●線維化が生じる要因として慢性炎症,感染,虚血,低酸素などが挙げられる.
●外傷後に生じる拘縮,いわゆる線維化を少しでも防止する目的で,組織への酸素供給効果が考えられるCO2療法を臨床応用してきた.
Fix and Treat!—外傷病院から始める二次性骨折予防
著者: 脇貴洋
ページ範囲:P.559 - P.566
Point!
●脆弱性骨折は病的骨折であり,bone health optimization(骨の健康の最適化)が必要である.
●脆弱性骨折にはAO法に基づいた適切な骨接合と,術直後からの骨粗鬆症治療が重要である(fix and treat).
●若手整形外科医が二次性骨折予防に関わりやすい環境の整備が指導医に求められる.
●骨粗鬆症治療が継続されるために,家族への骨粗鬆症治療の必要性の十分な説明と,初回再診外来のフォロー率向上が重要である.
骨折保存治療の極意を伝える
著者: 高畑智嗣
ページ範囲:P.567 - P.574
Point!
●保存療法の成績は,自分の経験の範囲内ではなく,成書を読んで確認したい.本稿ではその一部を紹介した.
●保存療法では骨折部が安定する外固定が必要.安定すると関節運動しても痛みが軽いので,筋力低下と関節拘縮を防止することになる.
●一般にシーネは弱すぎることが多いので,スプリント材を2枚重ねにするか2枚で患肢をはさんで強くすること.キャストは厚すぎることが多いので,素早く薄く巻いて速やかにモールディングする.
●本稿では保存療法に有用な外固定を解説し,一部は作成法を動画で示した.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
3章 手術室
手術室における塵埃SSIの予防
著者: 小関弘展
ページ範囲:P.576 - P.581
Point!
●手術部位感染(SSI)はしばしば重症化し,極めて難治性となる.
●空気中の浮遊微粒子が担体となって媒介する塵埃感染は,重大な感染経路の1つである.
●肉眼では見えないものの,手術室内動作や歩行によって多くの塵埃が飛散する.
●整形外科医だけでなく手術に携わるすべてのスタッフは,塵埃感染のリスクに対する意識を高め,注意を怠らないことが重要である.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
手術準備—医師と看護師のコミュニケーション
著者: 花林昭裕
ページ範囲:P.582 - P.583
Point!
●手術をトラブルなく円滑に進行させるためには,医師と看護師が良好なコミュニケーションを保つことが重要
●コミュニケーションを保つ方法として,術前に医師が作成した術前計画に基づいて術前にミーティングをすることが非常に重要
●術前ミーティングを行うことにより,術前には手術室には必要な手術台,インプラント,手術器械が準備され,予定された手順通りに手術が進行することが期待される.
手術室における術前準備と計画
著者: 藤原照美
ページ範囲:P.584 - P.586
Point!
●術前計画は手術を担当する器械出しと外回り看護師だけでなく,術前準備を行う看護師にも必要な情報である.
●術前準備には骨折手術の手技を理解するだけではなく,手術全体をマネジメントする能力も必要である.
●術前準備から術前計画を共有し,使用する器械を明らかにすることは安全な手術の提供につながる.
整形外科で扱う器材とその使い方
著者: 柴田陽子
ページ範囲:P.587 - P.590
Point!
●整形外科手術で扱う基本的な器材の種類について理解する.
●手術中の器材の使用方法について理解する.
●スムーズな器械出しをするためには,看護師が医師に望むことと医師が看護師に望むことを互いに理解する.
インプラントを準備して実践してみよう
著者: 土井武
ページ範囲:P.591 - P.592
「術前の段取りができるようになると手術も上手になる」と研修医に指導をしている.整形外傷に限らないが手術を完遂するためにはさまざまな関係者の手を煩わすことになる.特に開放骨折など時間に制約がある緊急手術では手術スタッフ・麻酔科への連絡,インプラントの確認・手配,患者家族への説明などをほぼ同時に行う段取りができないといけない.
インプラントを準備して実践するために,執刀医が気をつけるべき点をまとめてみた.
—インプラントを準備して実践してみよう—プレート固定
著者: 三好伸明
ページ範囲:P.593 - P.597
Point!
●プレート固定術を安全に,かつスムーズに進行させるためには,必要な専用器械や基本的器械,医療材料を術前に手術室看護師に細かく伝達することが重要である.
●適切な手術体位を選択することに加え,看護師と共同して体位を整える必要がある.
●手術台やテーブル,執刀医の立ち位置,透視装置,モニターの位置関係を術前に協議しておくことが重要である.
●正しいインプラントを清潔に出すには,外回り看護師やメーカー担当者とのコミュニケーションエラーへの対策や感染対策を講じる必要がある.
—インプラントを準備して実践してみよう—髄内釘手術をスムーズに進行するためのコツ
著者: 酒井こころ
ページ範囲:P.598 - P.601
Point!
●すべての症例に対して術前計画を立て,その内容を術前に手術室看護師に共有する.
●医師と手術室看護師がお互いに声をかけながら器械の受け渡しを行うことで,安全に手術を進行できる.
●ともに手術に臨む手術室看護師に対しての信頼を持つと同時に,安全確認を怠らない(特にインプラントの取り扱い,各スクリューに対するドリル径,ドライバーの種類など).
●自施設で所有している整復器械の種類や保管場所を把握する.
—インプラントを準備して実践してみよう—創外固定
著者: 赤松大志
ページ範囲:P.602 - P.606
Point!
●創外固定の利点と適応を理解する.
●創外固定の基本的な構造,種類を理解する.
●創外固定の固定強度を増すための要素を理解する.
●創外固定に使用する器械の特徴と注意点を理解する.
4章 整形病棟
当院で行っている皮弁術後の回診時の観察項目
著者: 濱口隼人 , 山岡秀司
ページ範囲:P.608 - P.611
Point!
●皮弁術後の合併症として,皮弁内の血流障害が最も注意すべき点であり,当院での観察項目を述べる.
●tcPCO2(経皮二酸化炭素分圧)モニターは,当院で最も重要視している皮弁モニタリングであり,皮弁の動脈系と静脈系の両方の異常を早期に検出することができる.
●術後は皮弁のみならず,皮弁採取部の観察も重要である.
整形外科回診に必要な器材・物品
著者: 池田晶彦 , 西田匡宏
ページ範囲:P.612 - P.616
Point!
●前日の処置などを記した回診板と,必要十分な器材の事前準備
●感染症例は最後に回診
●外科医とのコミュニケーションが重要
CLAP(持続局所抗菌薬灌流)療法における病棟管理の実際
著者: 圓尾明弘 , 津山愛里 , 吉本香代子
ページ範囲:P.617 - P.621
Point!
●チューブやピンがつながって手術室から帰室したときに,正しく回路が接続されているか?をまずは確認する.
●次に手術中に確立した灌流を維持するため,経過中閉塞しないようにフラッシュやミルキングを励行する.
●排液の性状や回収率を計測し,治療効果が得られているか? 副作用が起きてないか? を観察する.異常かなと思えば,医師への迅速な報告で未然にトラブルを回避できることもある.
イリザロフ創外固定術後の病棟管理の実際
著者: 朝倉愛子 , 三田基樹
ページ範囲:P.622 - P.626
Point!
●イリザロフ創外固定術後のケアのポイントは,ピンサイト感染の予防に努めることである.そのためには,連日ピンサイトを観察し洗浄することが重要である.
●患者がイメージしやすいよう,入院後早期よりピンサイトケアについての患者指導を行い,退院後のセルフケア獲得につなげている.不安が増強しないよう,精神的支援も行う必要がある.
●日常生活での注意点には周囲の破損の予防や衣類の工夫がある.在宅での生活に向け,患者が創外固定器を装着していても安全に生活できるよう支援することが重要である.
5章 リハビリテーション室
上腕骨近位端骨折—骨接合術後の術後リハビリテーション
著者: 寺田忠司
ページ範囲:P.628 - P.632
Point!
●肩関節の他動関節可動域(ROM)訓練は,術翌日からfull rangeで行う.
●内外旋他動ROM訓練は,2nd positionでのみ術翌日から許可される.
●自動ROM訓練は,術後3週間までは屈曲および外転は90°までに制限される.
●術後3週から自動ROM訓練は制限なく,full rangeで許可される.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
上腕骨遠位端関節内骨折—外傷術後療法とリハビリテーションの実際
著者: 渡久知かおり , 仲宗根素子
ページ範囲:P.633 - P.637
Point!
●受傷機転や初期治療の内容について理解し,拘縮要因や合併症のリスクに留意して,患者個々に合った治療計画を立案する.
●骨癒合後は拘縮を防ぐために積極的な可動域訓練を行い,患者の日常生活や職業に応じた目標を設定する.
●機能的かつ安全な術後リハビリテーションを実施するために,主治医とリハビリテーション専門職とが密に連携をとりながら進めていく必要がある.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
橈骨遠位端関節内骨折術後のリハビリテーションの実際
著者: 松澤翔太 , 森谷浩治
ページ範囲:P.638 - P.643
Point!
●術後外固定期間における非固定関節の運動は,橈骨遠位端骨折術後のリハビリテーションの中で最も重要な訓練の1つであり,同時に実施される浮腫の管理やその対処法についても理解する.
●術後訓練の開始時期や経過に応じた後療法の変化過程を知る.手関節と前腕のリハビリテーションの方法および訓練前期(外固定除去後)と訓練後期におけるリハビリテーションの違いを認識する.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
切断指再接着後のリハビリテーション
著者: 越後歩 , 辻英樹
ページ範囲:P.644 - P.650
Point!
●機能的な再接着指は十分な安定性,知覚,関節可動域を有する.このうち安定性と知覚は手術によるところが大きいが,関節可動域は積極的なリハビリテーションによってのみ獲得できる.
●再接着指のリハビリテーションは術後5〜10日を目安に,血行安定後に開始する.Early protective motionを用いて,関節可動域と腱滑走を維持する.
●どのzoneでも伸筋腱の機能維持に注意をはらう.PIP・DIP関節の伸展ラグを防ぐため,伸展ダイナミックスプリントを活用する.
●再接着指に機能障害が残存しても,useful handを獲得することができる.再接着部位より近位の関節機能や非損傷指の機能を維持することが重要である.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
大腿骨近位部骨折の術後リハビリテーション
著者: 小村英明 , 村岡辰彦
ページ範囲:P.651 - P.655
Point!
●理学療法士は,手術加療の効果を活かし,患者の状態に応じたリハビリテーションを実施しなくてはならない.
●合併症予防など術後を見据えた術前リハビリテーションの有用性を理解し,多職種が協力して取り組むことが望ましい.
●術後はできる限り受傷前の生活に戻ることを目標とすべきだが,患者の状態を適切に評価したうえで判断していくことが大事である.
●術後早期は,患部への過負荷や疼痛誘発を回避し,治癒を阻害することなく動作能力の改善を図っていくことが重要である.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
脛骨プラトー骨折後の術後療法とリハビリテーション
著者: 藤田慎矢 , 田中創 , 徳永真巳
ページ範囲:P.656 - P.661
Point!
●脛骨プラトー骨折後のリハビリテーションでは,受傷機転や手術記録,合併症の有無,術後プロトコル,禁忌事項の確認が必要である.
●術後早期よりアイシングや下肢挙上位の保持,下肢の運動により炎症症状と急性痛の軽減を図るとともに,深部静脈血栓症の予防に努める.
●医師の指示の下,脛骨大腿関節や膝蓋大腿関節の可動域運動をできるだけ早期に開始する.また,症例自身にも可動域運動の必要性を説明し積極的に実施していただく.加えて術後の安静度に応じて筋力増強運動を実施する.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
足関節周囲骨折後のリハビリテーション
著者: 山下正太郎
ページ範囲:P.662 - P.668
Point!
●足関節周囲骨折に対する骨接合術は軟部組織の状態を考慮して行われる.リハビリテーションは,①術前,②術後免荷・固定期,③術後免荷・固定解除期,④荷重期に分けられ,術前から開始することが多い.
●①,②では骨折部の転位増悪や軟部組織の腫脹増強によるコンパートメント症候群,創部治癒遷延などを引き起こさないように注意を図りながら早期にADLを拡大し全身の廃用予防や足関節〜足趾の機能障害予防を目指す介入を行う.
●③,④では免荷・固定により生じた足関節〜足趾の可動域制限や筋力低下などの機能障害を速やかに改善し,早期に受傷前と同等のADL獲得を目指す介入を行う.
●各期に応じたリハビリテーションの内容や注意点を具体的に挙げる.
脆弱性骨盤骨折症例の歩行を中心とした移動能力の経過と阻害要因
著者: 荒木心太 , 師岡祐輔 , 大林茂 , 上田泰久
ページ範囲:P.669 - P.678
Point!
●脆弱性骨盤骨折は高齢の症例が多く,受傷前からの低活動や管理を要する既往歴,併存疾患,合併症に配慮する必要がある.
●術後に全荷重が可能となった症例は,walkerなど歩行補助具を用いた歩行を早期から開始できる.
●歩行開始の阻害要因として,免荷や入院前からの歩行障害,せん妄あるいは認知機能障害がある.
●歩行獲得への主な阻害要因は逃避性跛行であり,早期からの運動や活動にはwalkerなど歩行補助具を使用した歩行が推奨される.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
6章 学会会場
高齢者開放骨折の問題点
著者: 小暮敦史 , 野坂光司 , 二村謙太郎 , 濱田大志
ページ範囲:P.680 - P.687
はじめに
現在,日本の65歳以上人口の割合は約29%であり,世界でも有数の超高齢社会である1).総人口が減りつつあるなかで,65歳以上の高齢者人口は2045年頃までは増加を続けると推計されている1).高齢者の皮膚は脆弱なため,低エネルギーでも容易に開放骨折に至る.そのため,高齢者の開放骨折に遭遇する機会が増えており,今後も増えることが予想される.膝周囲や下腿・足関節付近の開放骨折では,皮膚・軟部組織が脆弱で破綻しやすく,Gustilo Type IIIA以下と予想した開放骨折がIIIBになったり2),骨が脆弱で早期荷重が困難だったりと,治療に悩むことが多い.2023年に筆者らでオンラインシンポジウムを開催し,論点を明らかにして討論を行ったので,整理して提示する.
Olecranon Fracture-Dislocation—分類の再確認・難治症例へのアプローチ
著者: 佐藤俊介 , 楢﨑慎二 , 松井裕帝 , 対比地加奈子 , 土橋皓展
ページ範囲:P.688 - P.699
はじめに
Olecranon fracture-dislocation(OFD)は,complex elbow instabilityを来す外傷の1つである.本疾患は,これまで「transolecranon fracture-dislocation」や「posterior Monteggia fracture」などとも呼称され,脱臼形態や近位橈尺関節(proximal radio-ulnar joint:PRUJ)の損傷の有無,合併する靱帯損傷など,治療に対して考慮すべき点が多岐にわたり,適切な診断と治療戦略が必要とされる.脱臼方向とPRUJ損傷の有無から,MI分類1)が提唱され,OFDの診断と治療にアプローチしやすくなったが,それでも考慮すべき点が多々見受けられる.
本シンポジウムの目的は,複雑多岐にわたるOFDに対し,分類から見直し,難治症例へのさらなる適切なアプローチを検討することである.
それはCharcot骨折だったのでは?
著者: 野坂光司 , 岡田祥明 , 佐藤俊介 , 髙野祐護 , 杉田淳 , 市橋雅大
ページ範囲:P.700 - P.710
はじめに
2005年にビスホスホネート製剤の長期使用が骨代謝回転の過剰な抑制を生じ得ることが報告されてから,非定型大腿骨骨折(atypical femur fracture:AFF)の疾患概念が生まれ,骨粗鬆症治療(ビスホスホネート製剤)にはあまり関心がなかった外傷医も,今では,骨折患者さんがビスホスホネート製剤を飲んでいないかチェックするまでに急速に浸透した.Charcot関連骨折も,今後,AFFと同様の経過で浸透していくことが予想される.
糖尿病や梅毒の急激な増加により,Charcot関連の難治骨折が急増している1,2)中,本誌上シンポジウムにおいては,各シンポジストの,今後増加していくCharcot関節関連骨折啓発への願いが込められている.すべて教育的な症例であり,症例1は慎重に加療するも難渋したCharcot足関節骨折,症例2は1年経過して判明したCharcot関節の開放性ピロン骨折,症例3はCharcot足でこそ有用な高度足部変形に対するMATILDA法3)の応用,症例4は神経梅毒により脛骨高原骨折,足部Charcot関節症,大腿骨頚部骨折が生じた1例,症例5はCharcot関節に生じたピロン骨折に対して順行性Nailで距腿関節固定を行った1例である.
大腿骨近位部骨折の早期手術
著者: 井上三四郎 , 宮本俊之 , 上野宜功 , 福田文雄
ページ範囲:P.711 - P.715
緒言
本増大号の企画者と本稿筆頭著者の2人は,第145回西日本整形・災害外科学会学術集会のシンポジウムの座長となり,大腿骨近位部骨折に対する早期手術について議論した1).その中で話し合われた2つの演題を参考にして,「誌上シンポジウム4:大腿骨近位部骨折の早期手術」を開催する.
7章 外傷教育
オンライン教育の現状とこれから
著者: 土田芳彦
ページ範囲:P.718 - P.722
●オンライン教育の始まり
筆者がオンラインを使用してセミナーを始めたのは,今から10年以上前の2012年の4月のことであった.なぜ,そのようなことを始めたのか? 今となっては思い出すことはできないが,当時の開催挨拶文には以下のように書かれていた.
カタバーを用いた手外科&血管マイクロ・外傷整形手術教育
著者: 善家雄吉
ページ範囲:P.723 - P.729
はじめに
運動器外科において,肉眼解剖は非常に重要な役割を占めているが,従来,本邦にて解剖実習体を用いた外科手術手技向上研修(サージカルトレーニング)を行うことは,法的解釈の問題もあり,一般的には実践されてこなかった.しかしながら,その実践に対するガイドライン1)が作成されて以降,本邦でも条件が整えば,実施することが可能になった.当大学においても,2014年度より解剖学教室の協力により,外科系教室連合で実際に献体を用いたサージカルトレーニングや研究を行っており,その環境も徐々に整備されつつある.当整形外科学教室では,これまで計22回のサージカルトレーニングを施行してきた.うち,手外科・外傷分野は8回開催(表1)した実績があり,同分野のプログラムを中心に詳述する.
*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年5月末まで)。
海外留学のススメ—若手に送るメッセージ
四十路ボンバイエ—KAZUの挑戦
著者: 宇田川和彦
ページ範囲:P.730 - P.732
●はじめに
Good day!!!! 皆さんはじめまして.現在オーストラリアにあるプリンセスアレキサンドラ病院で整形外傷フェローで働いている宇田川和彦(KAZU)と申します.私の働いている病院は,クイーンズランド州にある1,038床の三次病院(tertiary hospital)です.年間5,000人以上の外傷患者の入院治療を行い,そのうち重症外傷患者は500人以上の外傷病院です.
私は,当院の重症外傷患者を専門に治療する外傷チームと整形外科チーム両方のフェローとして働いており,重症外傷患者の整形外傷のマネジメント,下肢外傷患者の手術,および外来加療をメインで行っております.
EnglandにおけるObserver Fellowship
著者: 筒井完明
ページ範囲:P.733 - P.735
●本稿を読んでくださっている皆様へ
私と横並びで留学に関して執筆している宇田川和彦先生,林洸太先生よりは一番皆さんが手の届きそうな留学は,私が今回行ってきたobserver fellowshipだと思います.3カ月と短い期間ではありましたが,自分の価値観や臨床に大きな影響を与えました.この経験が皆様の参考に少しでもなれば幸いです.
マイクロサージャリー臨床留学のススメ
著者: 林洸太
ページ範囲:P.736 - P.738
私は,四肢骨折治療,手外科,マイクロサージャリーの技術を駆使した重度四肢外傷の再建,および腕神経叢損傷を中心とした末梢神経損傷の再建を専門としている.主に,マイクロサージャリー全般と腕神経叢損傷の再建を学ぶために,台湾のDepartment of Plastic and Reconstructive Surgery, Chang Gung Memorial Hospital(長庚紀念病院,CGMH)のLinkou(林口)branchに2022年7月〜2023年6月の1年間留学した.CGMH, Linkouはベッド数が3,000〜3,500以上,手術室が約100ある巨大病院で,遊離皮弁を用いた再建手術(頭頸部,乳房,神経,外傷)が1カ月に約100件と症例数が非常に多く,世界中からinternational fellowを毎年8〜9人受け入れている1-3).それに加えて海外からの見学者も常時受け入れており,非常に国際色豊かである.
International fellowの構成は,形成外科トップのFu-Chan Wei教授のfellowが8人と,神経チームのDavid Chuang教授のnerve fellowが1人であった.前者は頭頚部,乳房,神経,外傷の各チームをローテーションするが,後者は基本的に1年間神経チームのもとで研修する.私はclinical nerve fellowとして留学した(図1).
column
整形外科外傷治療と最先端技術の交差点
著者: 渡部欣忍
ページ範囲:P.463 - P.463
21世紀の技術革新の流れの中で,人工知能(artificial intelligence:AI),仮想現実(virtual reality:VR),ロボット工学が医療の領域でも融合すると考えていました.これらの技術が,当初の想定を超越するような洗練されたツールとなりつつあることに驚きます.AIはエキスパート・システムの延長として,膨大な知識の貯蔵庫だと考えていました.しかし,大規模言語モデル(large language models:LLM)の例を挙げるまでもなく,機械学習とディープ・ラーニングの進化によって,AIは実現不可能と考えられていた領域へと突き進み,さらに汎用人工知能(artificial general intelligence:AGI)へと発展しています.同様に,VRの軌跡は拡張現実(augmented reality:AR)から複合現実(mixed reality:MR)へと変化し,現実世界と仮想世界の境界を融合させました.人の手の代替としてのロボットの力は,20世紀に既に証明されています.
AI,VR,ロボット工学の融合は必然であり,今後10年ほどで医療やヘルスケアに驚異的な変革をもたらすことになるでしょう.人工関節手術においては,術前計画から実際の手術まで,AIとロボットの融合による治療は既に外科医の知的能力と手術テクニックをはるかに凌駕してしまいました.対象物を固定できれば,ロボット手術の正確性は揺るぎないものです.この流れは,脊椎外科手術にも及び,人工関節手術と同様にロボット手術が主流になるのは明らかです.また,全世界の電子カルテ情報が統合されれば,蓄積されたリアルワールドのエビデンスに基づいた治療法をAIから指示されるようになり,診療ガイドラインなどは陳腐な遺物になってしまうかもしれません.
勉強と経験と,そして.
著者: 石橋恭之
ページ範囲:P.501 - P.501
私が研修医時代,外傷は若手の担当でした.その状況は今もあまり変わらないと思います.当時は外傷を中心とした教科書はなく,もちろん,外傷専門を標榜する病院など存在しません.われわれは英語で書かれたCampbell's Operative Orthopaedicsや初版(?)のAO Principles of Fracture Managementなどを読んで治療にあたっていました.もちろん,系統的に整形外科外傷学を学んだわけではありませんので,今思えばレベルの低い治療を患者さんに施してきたのだろうと反省しきりです.
指を再接着しても関節拘縮が残り,邪魔なので切断してくださいと患者さんに言われたこともありました.下肢骨折後では,術後のちょっとしたアライメント不良のため,十数年後には変形性膝関節症が生じた症例も経験しました.
これからの技能習得に思いを馳せる
著者: 野田知之
ページ範囲:P.574 - P.574
医師にも時間外労働の上限規制が適用されるいわゆる「働き方改革」がいよいよ2024年4月から施行されます.労務管理の適正化やタスクシフトの推進などが期待される一方で,自己研鑽の定義や取り扱い,非常勤派遣医師の減少の懸念など多くの未解決な問題を抱えたうえでのスタートとなりそうです.緊急対応や緊急手術を余儀なくされるわれわれ整形外傷医の「働き方」も大きく影響を受けそうで,十分な人員で業務効率化を図った施設でないと立ち行かなくなる可能性も容易に想像されます.
さて一方で,重度の関節内骨折や開放骨折,骨盤・寛骨臼骨折など複雑な整形外傷の治療においては高度な専門知識と手術手技が必要とされ,その習得は決して一朝一夕には成し得ません.「働き方改革」と「高度な技能習得」,これら相反する事象をいかにして効率的に両立させるか,ということが今後ますます重要になってきます.ブラック労働このうえない自身の若い頃を美化するつもりは毛頭ありませんが,圧倒的な数の症例を否応なく経験し,その後の糧とすることができていったのは,凡庸な自身にとって貴重なことでした.昔も今も時代や環境がどうであれ,トップ(あるいはボトム)クラスの人の振る舞いや伸び方には大きな差はないと考えますが,かたや大多数を占める中間層の成長は環境やシステムに大きく左右されます.そういう意味ではこれを機に,これらの人を叱責する,あるいは発表や論文作成などを命じることが憚られるシステムになっていくことも懸念されます.
整形外科と形成外科と働き方改革
著者: 櫻庭実
ページ範囲:P.590 - P.590
重度四肢外傷の治療における最も治療に手数の必要な病態として,広範な皮膚軟部組織欠損や末梢の血流途絶を伴う場合が挙げられる.血流が途絶している場合は迅速に血行再建術が必要であるし,広範な皮膚軟部組織欠損では7日以内程度の準緊急に組織移植による再建術が必要である.いずれの場合もマイクロサージャリーの技術が必要で,かつ手術に長時間を要する場合も多い.このような技術を持つのは整形外科医または形成外科医以外には考えられない.
一方で,医師の過労死問題に端を発した働き方改革が2024年4月から本格的に始動する.前述のような長時間緊急手術などを行い深夜まで労働した場合は,翌日休む,あるいは9時間の勤務間インターバルをとることが求められる.これを額面通りに実施すると,代替えの医師がいない限り翌日の予定手術を延期・中止するなどの必要に迫られることは明白である.
その背部痛,整形外科医で助けられますか?
著者: 湏藤啓広
ページ範囲:P.597 - P.597
今から約20年ほど前でしょうか.私がとある病院で当直をしていたときのことです.高齢の女性が「卓球をしていたら背中が痛くなった」という主訴のもと,普通に徒歩で夜間の外来に来られました.背中を拝見したところ特記すべき他覚的所見はなく,胸椎のX線撮影を行いましたが,こちらも異常所見はなし.筋肉痛かもしれませんねと言いながら,傍脊柱筋にワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液を局注し,診察終了.
その後,院内のトイレで意識消失発作を来し,心肺停止状態.診察室にて心臓マッサージ,挿管,昇圧剤投与等の処置を数時間行うも全く回復する徴候なく,そのまま帰らぬ人となりました.駆けつけた家族からは注射の副作用じゃないかと問い詰められたり,罵声を浴びせられたり…….
外傷学に関する研修会参加の勧め
著者: 帖佐悦男
ページ範囲:P.616 - P.616
最近では,外傷学を学ぶセミナーとして,日本骨折治療学会をはじめ多くの研修会が開催され,若手医師にとり大変有意義です.私が医師になった当時,地方の一般病院に勤務すると地域の人々が受診できる病院も限られていました.その多くの外傷の患者さんの治療に遭遇し,午前は外来,午後は毎日手術という生活を余儀なくされ,数少ない先輩からの指導や「骨折の治療」テキストに頼っていました.その当時は大腿骨近位部骨折の骨接合術にはscrew,enderネイル,CHS(compression hip screw)やDHS(dynamic hip screw)を,長管骨骨幹部骨折にはKüntscherネイルやプレート(dynamic compression plate:DCP)を用い,プレート固定の場合は骨膜を剥離し,ジグソーパズルを合わせるように解剖学的整復(レントゲン美人)を主眼に置いて治療を行っていました.
私にとり外傷学の転機になったのは,スイスに留学し,骨盤骨折を中心とした多くの外傷症例を経験できたことや,ダボスでのAO(Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen)コースに参加する機会を得たことでした.AOのベーシックコースでは,骨折や骨折手術に関する基本的な知識やAO骨折理論に基づいたスクリューやプレートなどの使用方法を学び,アドバンスドコースでは,骨折治療における応用的な概念・手技などを学び,治療の選択肢を広げることができるようになりました.当時はありませんでしたが,現在はスペシャルティコースやマスターコースなども整備されています.
外傷教育の重要性
著者: 尾﨑敏文
ページ範囲:P.637 - P.637
整形外科専攻医や初期研修医を含めた若手医師にとって,外傷は整形外科で最も接することが多い分野といえます.外傷救急医療では70%程度の症例に整形外科が関与していると思います.骨折手術は,整形外科領域で最も多い手術の1つで,整形外科手術の基本といえます.骨折に対する考え方や手術手技は年々変化し,進歩していますので,整形外科医の骨折治療に関する知識のアップデートはとても重要と考えられます.若手医師に対する系統だった教育だけでなく,指導医に対する知識や手技のアップデートの重要性,さらには,重度四肢外傷や骨盤骨折などの治療に従事する高度な専門医の育成の重要性も感じております.
私は毎年骨折治療に関係する学会に参加させていただいていますが,参加者に若手医師が非常に多く活気があること,そして年々増えている演題数を拝見すると骨折治療に対する若手医師の関心度がよくわかります.岡山大学整形外科では外傷教育を重視しており,1954年の開講以来,常に外傷班とその外傷チーフを教室スタッフに配属してきました.また,私自身も2015年にはAOベーシックコースに参加し,知識のアップデートも行ってきました.
最悪の事態を想定しておけば,最悪なことは起こらない
著者: 酒井昭典
ページ範囲:P.661 - P.661
手術において最悪の事態を想定し,悲観的に準備しておけば,最悪なことは起こらないものです.手術までに心がけるべきことは,どこまでも悲観的に準備をすることです.順調にいかなかった場合にどうするかを前もって決めておくことです.そうすれば,不測の事態が起きても,すべては想定内となり,何が起ころうとも落ち着いて対処することができます.
身近な例を1つ挙げれば,裂離骨折で小さな骨片をスクリューで内固定しようとして,骨片を割ってしまった場合です.割れるかもしれないことを事前に想定し,割れたときはtension band wiringで固定する,あるいは,骨接合を諦めて軟部組織をsuture anchorで固定する,あるいは,骨粗鬆症で骨質が悪くanchorが骨から引き抜けてしまったときはpull-out wireで固定するなど,次善の策を考え,フローチャートを描いて,固定材料をすぐ出せるように準備しておけば,すべてのイベントは想定内です.焦ることなく,手順よく手術ができます.
外傷を解く
著者: 鳥谷部荘八
ページ範囲:P.687 - P.687
外傷には時間制限があります.
そこには変性疾患,腫瘍,麻痺,先天異常などにはない緊迫感があります.待ったなしの外傷は,まさに何があるかわからない.予想だにしない状況に陥ることも稀ではありません.そこに外傷の怖さ,面白さ,醍醐味があると言ってもいい.外傷好きの医師はそこにヒリヒリし,うまく切り抜け解決することで達成感,いやエクスタシーすら感じます.重度四肢外傷,多発外傷などは1つとして同じ損傷はなく,無限のバリエーション(問題)があります.それをどうやって1つひとつクリアしてゆくのか……?
働き方改革と整形外傷専門医
著者: 井口浩一
ページ範囲:P.715 - P.715
大腿骨近位部骨折に対する受傷から48時間以内の手術が,わが国でも行われるようになってきた.Early appropriate careと呼ばれる戦略では,骨盤,大腿骨,寛骨臼,脊椎の骨折に対し,受傷から36時間以内に最終的な骨接合術を行うことを推奨している.開放骨折だけでなく,閉鎖骨折でも緊急手術や準緊急手術を行うべきだとのプレッシャーがかかる時代に突入した.手術のタイミングを手術室や医療者の都合で遅くすることで,患者に不利益をもたらすのであれば根絶するべきであろう.
一方,働き方改革で時間外の手術を行える病院が減る可能性が危惧される.そうなると,整形外傷の手術を行える病院は減少するのではないだろうか.整形外傷患者の集約化が今後進行する可能性が高まっている.わが国には外傷センターの認定制度は存在しない.しかし整形外傷患者の集約化を目指している病院は,他の病院との違いを明確にするために外傷センターを名乗るようになってきた.
若手整形外科医へ贈るVSOP
著者: 西良浩一
ページ範囲:P.716 - P.716
一流の整形外科医になるための心構えがVSOPです.若い20代は我武者羅(がむしゃら)でがんばりvitalityで乗り切る.いわゆるgeneralist修得の時代です.私はこの時期,徳島県の鳴門病院でプライマリケア,外傷学などを研鑽しました.
Specialtyの30代は,専門領域を決めてその道を極める年代です.私は31歳のとき,現在の専門である脊椎スポーツ医学と脊椎脊髄病を選択しました.最初の仕事はアイオワ大学脊椎センター留学でした.発育期分離症がすべるメカニズムを解明することがテーマでした.帰国後,粉骨砕身で教科書を読み,それを完璧に実践できるように励みました.教科書をしっかりと読む年代なのです.専門性を持ち10年過ぎれば,おのずとoriginalityを要求される年齢となります.教科書を読む人間から,教科書を書く人間に飛躍する時期です.それがoriginalityの40代なのです.教科書を書く人間になってください.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.444 - P.447
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.740 - P.740
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.741 - P.741
あとがき フリーアクセス
著者: 黒田良祐
ページ範囲:P.744 - P.744
今年の3月は異常な寒さでした.気象庁によれば7年ぶりに「寒い3月」で,その影響もあり今年の桜の開花は過去10年で最も遅かったそうです.読者の皆さんは今年も綺麗な桜を楽しまれたでしょうか?
さて,2024年度が始まり,新専攻医が新しい職場で勤務し始めています.今年度の専攻医の採用総数は過去最多で,なかでも整形外科医は最多の増加(93人増)です.外傷学は整形外科医にとって必須の習得分野であり,本号が多くの新人整形外科医に読まれることを期待しています.
基本情報
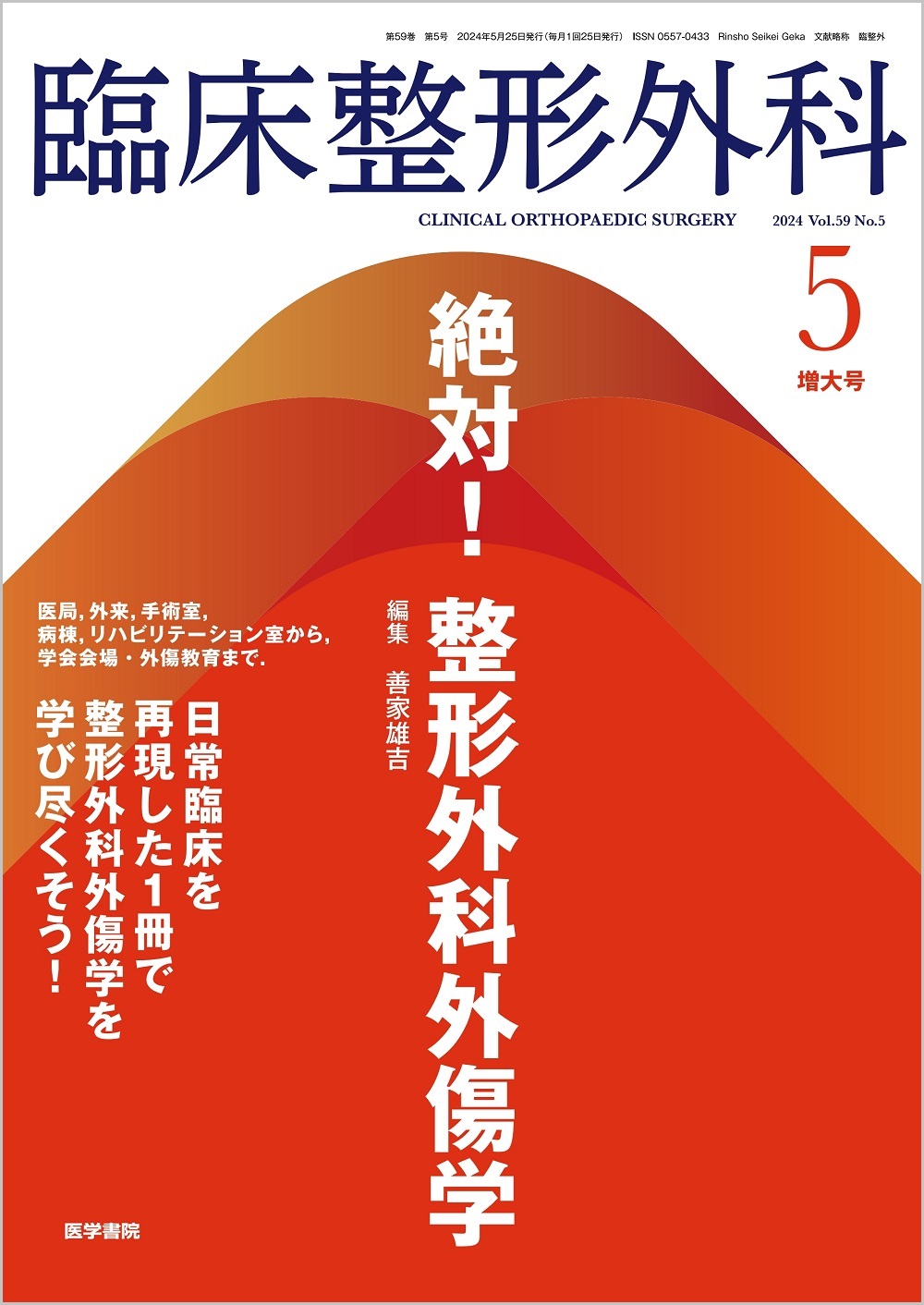
バックナンバー
59巻12号(2024年12月発行)
特集 初療対応からきれいな指再建まで 指尖部切断に対する治療
59巻10号(2024年10月発行)
特集 整形外科医のための臨床研究の進め方—立案から実施まで
59巻9号(2024年9月発行)
特集 変形性関節症に対するBiologics
59巻8号(2024年8月発行)
特集 脊損患者への投与が始まった脊髄再生医療—脊髄損傷患者に希望が見えるか
59巻7号(2024年7月発行)
特集 大規模レジストリーによる整形外科リアルワールドエビデンス構築
59巻6号(2024年6月発行)
特集 TKAにおける最新Topics
59巻5号(2024年5月発行)
増大号特集 絶対! 整形外科外傷学
59巻4号(2024年4月発行)
特集 脊椎関節炎SpAを理解する—疾患概念・診断基準・最新治療
59巻3号(2024年3月発行)
特集 知ってると知らないでは大違い 実践! 踵部痛の診断と治療
59巻2号(2024年2月発行)
特集 ここまで来た! 胸郭出口症候群の診断と治療
59巻1号(2024年1月発行)
特集 はじめたい人と極めたい人のための 超音波ガイド下インターベンション
58巻12号(2023年12月発行)
特集 がん時代の整形外科必携! 骨転移診療アップデート
58巻11号(2023年11月発行)
特集 外傷性頚部症候群—診療の最前線
58巻10号(2023年10月発行)
特集 腱板断裂の治療戦略
58巻9号(2023年9月発行)
特集 脊椎内視鏡下手術の進化・深化
58巻8号(2023年8月発行)
特集 小児の上肢をいかに診るか—よくわかる,先天性障害・外傷の診察と治療の進め方
58巻7号(2023年7月発行)
特集 股関節鏡手術のエビデンス—治療成績の現状
58巻6号(2023年6月発行)
特集 FRIの診断と治療—骨折手術後感染の疑問に答える
58巻5号(2023年5月発行)
増大号特集 できる整形外科医になる! 臨床力UP,整形外科診療のコツとエッセンス
58巻4号(2023年4月発行)
特集 疲労骨折からアスリートを守る—今,おさえておきたい“RED-S”
58巻3号(2023年3月発行)
特集 二次骨折予防に向けた治療管理
58巻2号(2023年2月発行)
特集 外反母趾診療ガイドライン改訂 外反母趾治療のトレンドを知る
58巻1号(2023年1月発行)
特集 医師の働き方改革 総チェック
57巻12号(2022年12月発行)
特集 大腿骨近位部骨折—最新トレンドとエキスパートの治療法
57巻11号(2022年11月発行)
特集 腰椎椎間板ヘルニアのCutting Edge
57巻10号(2022年10月発行)
特集 整形外科領域における人工知能の応用
57巻9号(2022年9月発行)
特集 わかる! 骨盤骨折(骨盤輪損傷) 診断+治療+エビデンスのUpdate
57巻8号(2022年8月発行)
特集 整形外科ロボット支援手術
57巻7号(2022年7月発行)
特集 整形外科医×関節リウマチ診療 今後の関わり方を考える
57巻6号(2022年6月発行)
特集 高齢者足部・足関節疾患 外来診療のコツとトピックス
57巻5号(2022年5月発行)
増大号特集 もう悩まない こどもと思春期の整形外科診療
57巻4号(2022年4月発行)
特集 骨軟部組織感染症Update
57巻3号(2022年3月発行)
特集 診断・治療に難渋したPeriprosthetic Joint Infectionへの対応
57巻2号(2022年2月発行)
特集 ロコモティブシンドローム臨床判断値に基づいた整形外科診療
57巻1号(2022年1月発行)
特集 知っておきたい足関節周囲骨折の新展開
56巻12号(2021年12月発行)
特集 整形外科手術に活かす! 創傷治療最新ストラテジー
56巻11号(2021年11月発行)
特集 末梢神経の再建2021
56巻10号(2021年10月発行)
特集 脊椎転移の治療 最前線
56巻9号(2021年9月発行)
特集 膝周囲骨切り術を成功に導く基礎知識
56巻8号(2021年8月発行)
特集 外来で役立つ 足部・足関節の超音波診療
56巻7号(2021年7月発行)
特集 手外科と労災
56巻6号(2021年6月発行)
特集 ACL再断裂に対する治療戦略
56巻5号(2021年5月発行)
増大号特集 整形外科 外来・当直 エマージェンシーマニュアル
56巻4号(2021年4月発行)
特集 成人脊柱変形 手術手技の考えかた・選びかた
56巻3号(2021年3月発行)
特集 骨折に対する積極的保存療法
56巻2号(2021年2月発行)
特集 ダメージ・コントロールとしての創外固定
56巻1号(2021年1月発行)
特集 パラスポーツ・メディシン入門
55巻12号(2020年12月発行)
特集 女性アスリートの運動器障害—悩みに答える
55巻11号(2020年11月発行)
特集 足部・足関節の画像解析—画像から病態を探る
55巻10号(2020年10月発行)
55巻9号(2020年9月発行)
特集 インプラント周囲骨折の治療戦略—THA・TKA・骨折後のプレート・髄内釘
55巻8号(2020年8月発行)
特集 整形外科×人工知能
55巻7号(2020年7月発行)
特集 脊椎手術—前方か後方か?
55巻6号(2020年6月発行)
特集 各種骨盤骨切り術とそのメリット
55巻5号(2020年5月発行)
増大号特集 臨床整形超音波学—エコー新時代、到来。
55巻4号(2020年4月発行)
特集 人工関節周囲感染の現状と展望 国際コンセンサスを踏まえて
55巻3号(2020年3月発行)
特集 頚椎を含めたグローバルアライメント
55巻2号(2020年2月発行)
特集 整形外科の職業被曝
55巻1号(2020年1月発行)
特集 新しい概念 “軟骨下脆弱性骨折”からみえてきたこと
54巻12号(2019年12月発行)
誌上シンポジウム 患者の満足度を高める関節リウマチ手術
54巻11号(2019年11月発行)
誌上シンポジウム 腰椎前方アプローチ—その光と影
54巻10号(2019年10月発行)
誌上シンポジウム がん診療×整形外科「がんロコモ」
54巻9号(2019年9月発行)
誌上シンポジウム 肩腱板断裂 画像診断の進歩
54巻8号(2019年8月発行)
誌上シンポジウム 整形外科治療の費用対効果
54巻7号(2019年7月発行)
誌上シンポジウム 骨軟部腫瘍の薬物治療アップデート
54巻6号(2019年6月発行)
誌上シンポジウム 変形性膝関節症における関節温存手術
54巻5号(2019年5月発行)
誌上シンポジウム 整形外科を牽引する女性医師たち—男女共同参画
54巻4号(2019年4月発行)
誌上シンポジウム 超高齢社会における脊椎手術
54巻3号(2019年3月発行)
誌上シンポジウム サルコペニアと整形外科
54巻2号(2019年2月発行)
誌上シンポジウム 足部・足関節疾患と外傷に対する保存療法 Evidence-Based Conservative Treatment
54巻1号(2019年1月発行)
誌上シンポジウム 小児の脊柱変形と脊椎疾患—診断・治療の急所
53巻12号(2018年12月発行)
誌上シンポジウム 外傷における人工骨の臨床
53巻11号(2018年11月発行)
誌上シンポジウム 椎間板研究の最前線
53巻10号(2018年10月発行)
誌上シンポジウム 原発巣別転移性骨腫瘍の治療戦略
53巻9号(2018年9月発行)
誌上シンポジウム 外反母趾の成績不良例から学ぶ
53巻8号(2018年8月発行)
誌上シンポジウム 椎弓形成術 アップデート
53巻7号(2018年7月発行)
誌上シンポジウム 膝前十字靱帯のバイオメカニクス
53巻6号(2018年6月発行)
誌上シンポジウム 変形性足関節症のフロントライン
53巻5号(2018年5月発行)
誌上シンポジウム 外傷後・術後骨髄炎の治療
53巻4号(2018年4月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症性脊椎骨折の治療 Cutting Edge
53巻3号(2018年3月発行)
誌上シンポジウム THAの低侵襲性と大腿骨ステム選択
53巻2号(2018年2月発行)
誌上シンポジウム 骨関節外科への3Dプリンティングの応用
53巻1号(2018年1月発行)
誌上シンポジウム 脂肪幹細胞と運動器再生
52巻12号(2017年12月発行)
誌上シンポジウム 慢性腰痛のサイエンス
52巻11号(2017年11月発行)
52巻10号(2017年10月発行)
52巻9号(2017年9月発行)
誌上シンポジウム パーキンソン病と疼痛
52巻8号(2017年8月発行)
誌上シンポジウム 創外固定でどこまでできるか?
52巻7号(2017年7月発行)
誌上シンポジウム 認知症の痛み
52巻6号(2017年6月発行)
52巻5号(2017年5月発行)
誌上シンポジウム 成人脊柱変形の目指すポイント PI-LL≦10°,PT<20°はすべての年齢層に当てはまるのか
52巻4号(2017年4月発行)
52巻3号(2017年3月発行)
誌上シンポジウム 股関節疾患の保存的治療とリハビリテーション
52巻2号(2017年2月発行)
誌上シンポジウム リバース型人工肩関節手術でわかったこと
52巻1号(2017年1月発行)
誌上シンポジウム 胸椎OPLL手術の最前線
51巻12号(2016年12月発行)
51巻11号(2016年11月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症診療—整形外科からの発信
51巻10号(2016年10月発行)
誌上シンポジウム 高気圧酸素治療の現状と可能性
51巻9号(2016年9月発行)
誌上シンポジウム THAのアプローチ
51巻8号(2016年8月発行)
誌上シンポジウム 脊椎診療ガイドライン—特徴と導入効果
51巻7号(2016年7月発行)
誌上シンポジウム 脊椎腫瘍 最近の話題
51巻6号(2016年6月発行)
51巻5号(2016年5月発行)
誌上シンポジウム 整形外科と慢性腎不全
51巻4号(2016年4月発行)
誌上シンポジウム THA後感染の予防・診断・治療の最前線
51巻3号(2016年3月発行)
誌上シンポジウム 半月変性断裂に対する治療
51巻2号(2016年2月発行)
誌上シンポジウム MISの功罪
51巻1号(2016年1月発行)
50巻12号(2015年12月発行)
特集 世界にインパクトを与えた日本の整形外科
50巻11号(2015年11月発行)
誌上シンポジウム 成人脊柱変形へのアプローチ
50巻10号(2015年10月発行)
誌上シンポジウム 人工骨移植の現状と展望
50巻9号(2015年9月発行)
誌上シンポジウム Life is Motion—整形外科医が知りたい筋肉の科学
50巻8号(2015年8月発行)
誌上シンポジウム 反復性肩関節脱臼後のスポーツ復帰
50巻7号(2015年7月発行)
50巻6号(2015年6月発行)
50巻5号(2015年5月発行)
誌上シンポジウム 股関節鏡の現状と可能性
50巻4号(2015年4月発行)
誌上シンポジウム 難治性テニス肘はこうみる
50巻3号(2015年3月発行)
誌上シンポジウム 骨軟部腫瘍における画像評価最前線
50巻2号(2015年2月発行)
誌上シンポジウム 関節リウマチ—生物学的製剤使用で変化したこと
50巻1号(2015年1月発行)
49巻12号(2014年12月発行)
49巻11号(2014年11月発行)
誌上シンポジウム 運動器画像診断の進歩
49巻10号(2014年10月発行)
誌上シンポジウム 検診からわかる整形外科疾患
49巻9号(2014年9月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症に対する治療戦略
49巻8号(2014年8月発行)
49巻7号(2014年7月発行)
49巻6号(2014年6月発行)
誌上シンポジウム MIS人工膝関節置換術の現状と展望
49巻5号(2014年5月発行)
49巻4号(2014年4月発行)
誌上シンポジウム 整形外科外傷治療の進歩
49巻3号(2014年3月発行)
誌上シンポジウム 良性腫瘍に対する最新の治療戦略
49巻2号(2014年2月発行)
49巻1号(2014年1月発行)
誌上シンポジウム 下肢壊疽の最新治療
48巻12号(2013年12月発行)
誌上シンポジウム 慢性疼痛と原因療法―どこまで追究が可能か
48巻11号(2013年11月発行)
48巻10号(2013年10月発行)
誌上シンポジウム 低出力超音波パルス(LIPUS)による骨折治療―基礎と臨床における最近の話題
48巻9号(2013年9月発行)
48巻8号(2013年8月発行)
48巻7号(2013年7月発行)
誌上シンポジウム 転移性骨腫瘍―治療の進歩
48巻6号(2013年6月発行)
48巻5号(2013年5月発行)
48巻4号(2013年4月発行)
誌上シンポジウム 腰椎変性側弯症の手術―現状と課題
48巻3号(2013年3月発行)
誌上シンポジウム 創外固定の将来展望
48巻2号(2013年2月発行)
誌上シンポジウム 高齢者の腱板断裂
48巻1号(2013年1月発行)
47巻12号(2012年12月発行)
誌上シンポジウム 高位脛骨骨切り術の適応と限界
47巻11号(2012年11月発行)
誌上シンポジウム 橈骨遠位端骨折の治療
47巻10号(2012年10月発行)
誌上シンポジウム 内視鏡診断・治療の最前線
47巻9号(2012年9月発行)
誌上シンポジウム 脊椎脊髄手術の医療安全
47巻8号(2012年8月発行)
誌上シンポジウム 難治性足部スポーツ傷害の治療
47巻7号(2012年7月発行)
47巻6号(2012年6月発行)
誌上シンポジウム 難治性良性腫瘍の治療
47巻5号(2012年5月発行)
誌上シンポジウム 重度後縦靱帯骨化症に対する術式選択と合併症
47巻4号(2012年4月発行)
誌上シンポジウム 壮年期変形性股関節症の診断と関節温存療法
47巻3号(2012年3月発行)
誌上シンポジウム 大震災と整形外科医
47巻2号(2012年2月発行)
47巻1号(2012年1月発行)
誌上シンポジウム 整形外科領域における蛍光イメージング
46巻12号(2011年12月発行)
46巻11号(2011年11月発行)
46巻10号(2011年10月発行)
46巻9号(2011年9月発行)
誌上シンポジウム 生物学的製剤が与えた関節リウマチの病態・治療の変化
46巻8号(2011年8月発行)
46巻7号(2011年7月発行)
46巻6号(2011年6月発行)
誌上シンポジウム 腰部脊柱管狭窄[症]に対する手術戦略
46巻5号(2011年5月発行)
46巻4号(2011年4月発行)
誌上シンポジウム 運動器の慢性疼痛に対する薬物療法の新展開
46巻3号(2011年3月発行)
46巻2号(2011年2月発行)
46巻1号(2011年1月発行)
45巻12号(2010年12月発行)
誌上シンポジウム 小児の肩関節疾患
45巻11号(2010年11月発行)
45巻10号(2010年10月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症診断・治療の新展開
45巻9号(2010年9月発行)
誌上シンポジウム 軟骨再生―基礎と臨床
45巻8号(2010年8月発行)
誌上シンポジウム 四肢のしびれ感
45巻7号(2010年7月発行)
45巻6号(2010年6月発行)
誌上シンポジウム 整形外科領域における抗菌薬の使い方
45巻5号(2010年5月発行)
誌上シンポジウム 整形外科医の未来像―多様化したニーズへの対応
45巻4号(2010年4月発行)
45巻3号(2010年3月発行)
誌上シンポジウム 軟部腫瘍の診断と治療
45巻2号(2010年2月発行)
誌上シンポジウム 肩腱板不全断裂
45巻1号(2010年1月発行)
誌上シンポジウム 慢性腰痛症の保存的治療
44巻12号(2009年12月発行)
44巻11号(2009年11月発行)
44巻10号(2009年10月発行)
誌上シンポジウム 整形外科術後感染の実態と予防対策
44巻9号(2009年9月発行)
誌上シンポジウム 高齢者骨折と転倒予防
44巻8号(2009年8月発行)
誌上シンポジウム 創傷処置に関する最近の進歩
44巻7号(2009年7月発行)
44巻6号(2009年6月発行)
44巻5号(2009年5月発行)
誌上シンポジウム プレート骨接合術―従来型かLCPか
44巻4号(2009年4月発行)
44巻3号(2009年3月発行)
44巻2号(2009年2月発行)
誌上シンポジウム 膝骨壊死の病態と治療
44巻1号(2009年1月発行)
誌上シンポジウム 整形外科における人工骨移植の現状と展望
43巻12号(2008年12月発行)
43巻11号(2008年11月発行)
誌上シンポジウム 外傷性肩関節脱臼
43巻10号(2008年10月発行)
誌上シンポジウム 発育期大腿骨頭の壊死性病変への対応
43巻9号(2008年9月発行)
43巻8号(2008年8月発行)
誌上シンポジウム 腰椎変性側弯の治療選択
43巻7号(2008年7月発行)
誌上シンポジウム 人工股関節術後の骨折の治療
43巻6号(2008年6月発行)
誌上シンポジウム 胸椎後縦靱帯骨化症の治療―最近の進歩
43巻5号(2008年5月発行)
誌上シンポジウム 手・肘関節鏡手術の現況と展望
43巻4号(2008年4月発行)
誌上シンポジウム 骨粗鬆症性脊椎骨折の病態
43巻3号(2008年3月発行)
誌上シンポジウム 変形性手関節症の治療
43巻2号(2008年2月発行)
誌上シンポジウム 整形外科手術におけるコンピュータナビゲーション支援
43巻1号(2008年1月発行)
誌上シンポジウム 高齢者(80歳以上)に対する人工膝関節置換術
42巻12号(2007年12月発行)
42巻11号(2007年11月発行)
42巻10号(2007年10月発行)
誌上シンポジウム 外傷性頚部症候群―最近の進歩
42巻9号(2007年9月発行)
誌上シンポジウム 骨折治療の最新知見―小侵襲骨接合術とNavigation system
42巻8号(2007年8月発行)
42巻7号(2007年7月発行)
誌上シンポジウム 人工股関節手術における骨セメント使用時の工夫と問題点
42巻6号(2007年6月発行)
誌上シンポジウム 整形外科疾患における痛みの研究
42巻5号(2007年5月発行)
誌上シンポジウム 肩こりの病態と治療
42巻4号(2007年4月発行)
誌上シンポジウム 関節軟骨とヒアルロン酸
42巻3号(2007年3月発行)
誌上シンポジウム 腰椎椎間板ヘルニア治療の最前線
42巻2号(2007年2月発行)
42巻1号(2007年1月発行)
誌上シンポジウム 変形性膝関節症―最近の進歩
41巻12号(2006年12月発行)
誌上シンポジウム 肘不安定症の病態と治療
41巻11号(2006年11月発行)
41巻10号(2006年10月発行)
41巻9号(2006年9月発行)
41巻8号(2006年8月発行)
誌上シンポジウム 腰部脊柱管狭窄症―最近の進歩
41巻7号(2006年7月発行)
誌上シンポジウム 運動器リハビリテーションの効果
41巻6号(2006年6月発行)
41巻5号(2006年5月発行)
41巻4号(2006年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学 最近の進歩 2006(第34回日本脊椎脊髄病学会より)
41巻3号(2006年3月発行)
41巻2号(2006年2月発行)
誌上シンポジウム de Quervain病の治療
41巻1号(2006年1月発行)
40巻12号(2005年12月発行)
40巻11号(2005年11月発行)
誌上シンポジウム 整形外科疾患における骨代謝マーカーの応用
40巻10号(2005年10月発行)
誌上シンポジウム 関節鏡を用いた腱板断裂の治療
40巻9号(2005年9月発行)
特別シンポジウム どうする日本の医療
40巻8号(2005年8月発行)
誌上シンポジウム 整形外科におけるリスクマネジメント
40巻7号(2005年7月発行)
40巻6号(2005年6月発行)
誌上シンポジウム 脊柱短縮術
40巻5号(2005年5月発行)
40巻4号(2005年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学 最近の進歩 2005(第33回日本脊椎脊髄病学会より)
40巻3号(2005年3月発行)
40巻2号(2005年2月発行)
誌上シンポジウム 前腕回旋障害の病態と治療
40巻1号(2005年1月発行)
39巻12号(2004年12月発行)
誌上シンポジウム 小児大腿骨頚部骨折の治療法とその成績
39巻11号(2004年11月発行)
39巻10号(2004年10月発行)
誌上シンポジウム 関節リウマチ頚椎病変の病態・治療・予後
39巻9号(2004年9月発行)
39巻8号(2004年8月発行)
誌上シンポジウム 診療ガイドラインの方向性―臨床に役立つガイドラインとは
39巻7号(2004年7月発行)
39巻6号(2004年6月発行)
39巻5号(2004年5月発行)
シンポジウム 手指の関節外骨折
39巻4号(2004年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学 最近の進歩 2004(第32回日本脊椎脊髄病学会より)
39巻3号(2004年3月発行)
39巻2号(2004年2月発行)
39巻1号(2004年1月発行)
シンポジウム 外傷に対するプライマリケア―保存療法を中心に
38巻12号(2003年12月発行)
38巻11号(2003年11月発行)
シンポジウム RSDを含む頑固なneuropathic painの病態と治療
38巻10号(2003年10月発行)
シンポジウム 整形外科医療におけるリスクマネジメント
38巻9号(2003年9月発行)
シンポジウム 全人工肩関節置換術の成績
38巻8号(2003年8月発行)
シンポジウム 難治性骨折の治療
38巻7号(2003年7月発行)
38巻6号(2003年6月発行)
シンポジウム 脊椎転移癌に対する治療法の選択
38巻5号(2003年5月発行)
シンポジウム 外傷に伴う呼吸器合併症の予防と治療
38巻4号(2003年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学最近の進歩 2003(第31回日本脊椎脊髄病学会より)
38巻3号(2003年3月発行)
シンポジウム 腰椎変性すべり症の治療
38巻2号(2003年2月発行)
シンポジウム 膝複合靱帯損傷に対する保存療法および観血的治療の選択
38巻1号(2003年1月発行)
37巻12号(2002年12月発行)
37巻11号(2002年11月発行)
シンポジウム 手術支援ロボティックシステム
37巻10号(2002年10月発行)
37巻9号(2002年9月発行)
シンポジウム 橈骨遠位端骨折の保存的治療のこつと限界
37巻8号(2002年8月発行)
37巻7号(2002年7月発行)
37巻6号(2002年6月発行)
シンポジウム スポーツ肩障害の病態と治療
37巻5号(2002年5月発行)
シンポジウム 縮小手術への挑戦―縮小手術はどこまで可能か
37巻4号(2002年4月発行)
特集 脊椎脊髄病学最近の進歩(第30回日本脊椎脊髄病学会より)
37巻3号(2002年3月発行)
37巻2号(2002年2月発行)
37巻1号(2002年1月発行)
シンポジウム 足関節捻挫後遺障害の病態と治療
36巻12号(2001年12月発行)
シンポジウム 手根部骨壊死疾患の病態と治療
36巻11号(2001年11月発行)
シンポジウム 頚肩腕症候群と肩こり―疾患概念とその病態
36巻10号(2001年10月発行)
シンポジウム 下肢長管骨骨折に対するminimally invasive surgery
36巻9号(2001年9月発行)
36巻8号(2001年8月発行)
36巻7号(2001年7月発行)
36巻6号(2001年6月発行)
シンポジウム 膝複合靭帯損傷の診断と治療
36巻5号(2001年5月発行)
36巻4号(2001年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進歩―主題とパネル演題を中心に(第29回日本脊椎外科学会より)
36巻3号(2001年3月発行)
36巻2号(2001年2月発行)
シンポジウム 舟状骨偽関節に対する治療
36巻1号(2001年1月発行)
35巻13号(2000年12月発行)
シンポジウム 21世記の整形外科移植医療~その基礎から臨床応用に向けて
35巻12号(2000年11月発行)
35巻11号(2000年10月発行)
シンポジウム スポーツによる肘関節障害の診断・治療
35巻10号(2000年9月発行)
35巻9号(2000年8月発行)
35巻8号(2000年7月発行)
35巻7号(2000年6月発行)
35巻6号(2000年5月発行)
35巻5号(2000年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進歩―長期予後からみた問題点を中心として―(第28回日本脊椎外科学会より)
35巻4号(2000年3月発行)
35巻3号(2000年2月発行)
シンポジウム 変形性膝関節症の病態からみた治療法の選択
35巻2号(2000年2月発行)
35巻1号(2000年1月発行)
34巻12号(1999年12月発行)
シンポジウム 脊椎内視鏡手術―最近の進歩
34巻11号(1999年11月発行)
シンポジウム 日本における新しい人工股関節の開発
34巻10号(1999年10月発行)
34巻9号(1999年9月発行)
34巻8号(1999年8月発行)
34巻7号(1999年7月発行)
34巻6号(1999年6月発行)
シンポジウム 整形外科と運動療法
34巻5号(1999年5月発行)
34巻4号(1999年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進捗―脊椎骨切り術と脊椎再建を中心として―(第27回日本脊椎外科学会より)
34巻3号(1999年3月発行)
シンポジウム オステオポローシスの評価と治療方針
34巻2号(1999年2月発行)
シンポジウム 日本における新しい人工膝関節の開発
34巻1号(1999年1月発行)
33巻12号(1998年12月発行)
33巻11号(1998年11月発行)
33巻10号(1998年10月発行)
33巻9号(1998年9月発行)
33巻8号(1998年8月発行)
シンポジウム 骨組織に対する力学的負荷とその制御―日常臨床に生かす視点から
33巻7号(1998年7月発行)
33巻6号(1998年6月発行)
33巻5号(1998年5月発行)
33巻4号(1998年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進歩―OPLLを中心として―(第26回日本脊椎外科学会より)
33巻3号(1998年3月発行)
シンポジウム 大きな骨欠損に対する各種治療法の利害得失
33巻2号(1998年2月発行)
シンポジウム 人工股関節置換術の再手術における私の工夫
33巻1号(1998年1月発行)
32巻12号(1997年12月発行)
32巻11号(1997年11月発行)
シンポジウム 腰椎変性疾患に対するspinal instrumentation―適応と問題点―
32巻10号(1997年10月発行)
32巻9号(1997年9月発行)
32巻8号(1997年8月発行)
32巻7号(1997年7月発行)
32巻6号(1997年6月発行)
32巻5号(1997年5月発行)
32巻4号(1997年4月発行)
特集 脊椎外科最近の進歩(第25回日本脊椎外科学会より)
32巻3号(1997年3月発行)
32巻2号(1997年2月発行)
シンポジウム 脊柱側弯症に対する最近の手術療法
32巻1号(1997年1月発行)
シンポジウム 骨肉腫の診断と治療のトピックス
31巻12号(1996年12月発行)
31巻11号(1996年11月発行)
31巻10号(1996年10月発行)
31巻9号(1996年9月発行)
31巻8号(1996年8月発行)
31巻7号(1996年7月発行)
31巻6号(1996年6月発行)
31巻5号(1996年5月発行)
31巻4号(1996年4月発行)
特集 脊椎外傷の最近の進歩(上位頚椎を除く)(第24回日本脊椎外科学会より)
31巻3号(1996年3月発行)
31巻2号(1996年2月発行)
31巻1号(1996年1月発行)
シンポジウム 腰椎変性すべり症の手術
30巻12号(1995年12月発行)
30巻11号(1995年11月発行)
30巻10号(1995年10月発行)
30巻9号(1995年9月発行)
30巻8号(1995年8月発行)
30巻7号(1995年7月発行)
シンポジウム 原発性脊椎悪性腫瘍の治療
30巻6号(1995年6月発行)
30巻5号(1995年5月発行)
30巻4号(1995年4月発行)
特集 上位頚椎疾患―その病態と治療(第23回日本脊椎外科学会より)
30巻3号(1995年3月発行)
シンポジウム 膝関節のUnicompartmental Arthroplasty
30巻2号(1995年2月発行)
シンポジウム 機能的電気刺激(FES)の理論と実際
30巻1号(1995年1月発行)
シンポジウム 長期成績からみたBipolar型人工股関節の適応の再検討
29巻12号(1994年12月発行)
29巻11号(1994年11月発行)
29巻10号(1994年10月発行)
29巻9号(1994年9月発行)
29巻8号(1994年8月発行)
29巻7号(1994年7月発行)
シンポジウム 慢性関節リウマチ頚椎病変
29巻6号(1994年6月発行)
シンポジウム 変性腰部脊柱管狭窄症の手術的治療と長期成績
29巻5号(1994年5月発行)
29巻4号(1994年4月発行)
特集 椎間板―基礎と臨床(第22回日本脊椎外科学会より)
29巻3号(1994年3月発行)
29巻2号(1994年2月発行)
シンポジウム 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)をめぐって
29巻1号(1994年1月発行)
シンポジウム 関節スポーツ外傷の診断と治療―最近の進歩
28巻12号(1993年12月発行)
28巻11号(1993年11月発行)
28巻10号(1993年10月発行)
28巻9号(1993年9月発行)
28巻8号(1993年8月発行)
28巻7号(1993年7月発行)
28巻6号(1993年6月発行)
28巻5号(1993年5月発行)
28巻4号(1993年4月発行)
特集 痛みをとらえる(第21回日本脊椎外科学会より)
28巻3号(1993年3月発行)
シンポジウム 癌性疼痛に対する各種治療法の適応と限界
28巻2号(1993年2月発行)
28巻1号(1993年1月発行)
シンポジウム 外反母趾の治療
27巻12号(1992年12月発行)
27巻11号(1992年11月発行)
シンポジウム 膝十字靱帯再建における素材の選択
27巻10号(1992年10月発行)
27巻9号(1992年9月発行)
27巻8号(1992年8月発行)
27巻7号(1992年7月発行)
27巻6号(1992年6月発行)
27巻5号(1992年5月発行)
シンポジウム ペルテス病の長期予後
27巻4号(1992年4月発行)
特集 主題・腰部脊柱管狭窄症/パネルI・脊椎転移性腫瘍の手術的治療/パネルII・脊椎脊髄MRI診断(第20回日本脊椎外科学会より)
27巻3号(1992年3月発行)
シンポジウム 頸部脊柱管拡大術の長期成績
27巻2号(1992年2月発行)
27巻1号(1992年1月発行)
26巻12号(1991年12月発行)
26巻11号(1991年11月発行)
26巻10号(1991年10月発行)
シンポジウム 脊髄損傷の神経病理とMRI画像
26巻9号(1991年9月発行)
26巻8号(1991年8月発行)
26巻7号(1991年7月発行)
26巻6号(1991年6月発行)
シンポジウム 悪性骨軟部腫瘍への挑戦
26巻5号(1991年5月発行)
シンポジウム 先天性股関節脱臼に対する牽引療法―その方法と後療法を具体的に
26巻4号(1991年4月発行)
特集 主題I:Spinal Dysraphism/主題II:Pedicular Screwing(第19回日本脊椎外科学会より)
26巻3号(1991年3月発行)
26巻2号(1991年2月発行)
シンポジウム 先天性股関節脱臼に対する治療法の限界と展望
26巻1号(1991年1月発行)
25巻12号(1990年12月発行)
25巻11号(1990年11月発行)
25巻10号(1990年10月発行)
25巻9号(1990年9月発行)
シンポジウム 機能的電気刺激(FES)の基礎と臨床
25巻8号(1990年8月発行)
25巻7号(1990年7月発行)
25巻6号(1990年6月発行)
25巻5号(1990年5月発行)
25巻4号(1990年4月発行)
特集 不安定腰椎(第18回日本脊椎外科研究会より)
25巻3号(1990年3月発行)
シンポジウム 予防処置導入後の乳児先天股脱
25巻2号(1990年2月発行)
25巻1号(1990年1月発行)
シンポジウム 全人工股関節置換術―セメント使用と非使用:その得失―
24巻12号(1989年12月発行)
24巻11号(1989年11月発行)
24巻10号(1989年10月発行)
24巻9号(1989年9月発行)
24巻8号(1989年8月発行)
24巻7号(1989年7月発行)
24巻6号(1989年6月発行)
24巻5号(1989年5月発行)
シンポジウム Rb法の限界
24巻4号(1989年4月発行)
特集 不安定頸椎—基礎と臨床—(第17回日本脊髄外科研究会より)
24巻3号(1989年3月発行)
24巻2号(1989年2月発行)
24巻1号(1989年1月発行)
シンポジウム 広範囲腱板断裂の再建
23巻12号(1988年12月発行)
23巻11号(1988年11月発行)
23巻10号(1988年10月発行)
シンポジウム 大腿骨頭壊死症の最近の進歩
23巻9号(1988年9月発行)
シンポジウム 変形性股関節症に対するBipolar型人工骨頭の臨床応用
23巻8号(1988年8月発行)
23巻7号(1988年7月発行)
23巻6号(1988年6月発行)
23巻5号(1988年5月発行)
23巻4号(1988年4月発行)
特集 脊柱管内靱帯骨化の病態と治療(第16回日本脊椎外科研究会より)
23巻3号(1988年3月発行)
23巻2号(1988年2月発行)
シンポジウム 日本におけるスポーツ整形外科の現状と将来
23巻1号(1988年1月発行)
22巻12号(1987年12月発行)
22巻11号(1987年11月発行)
22巻10号(1987年10月発行)
シンポジウム 骨肉腫の患肢温存療法
22巻9号(1987年9月発行)
22巻8号(1987年8月発行)
シンポジウム 椎間板注入療法の基礎
22巻7号(1987年7月発行)
シンポジウム 多発骨傷
22巻6号(1987年6月発行)
22巻5号(1987年5月発行)
シンポジウム 人工膝関節の長期成績
22巻4号(1987年4月発行)
特集 腰仙部根症状の発症機序—基礎と臨床—(第15回日本脊椎外科研究会より)
22巻3号(1987年3月発行)
シンポジウム 骨悪性線維性組織球腫
22巻2号(1987年2月発行)
シンポジウム 陳旧性肘関節周囲骨折の治療
22巻1号(1987年1月発行)
シンポジウム 陳旧性膝関節重度靱帯損傷の治療
21巻12号(1986年12月発行)
シンポジウム セメントレス人工股関節
21巻11号(1986年11月発行)
シンポジウム Bioactive Ceramics研究における最近の進歩
21巻10号(1986年10月発行)
シンポジウム 骨軟骨移植の進歩
21巻9号(1986年9月発行)
21巻8号(1986年8月発行)
21巻7号(1986年7月発行)
シンポジウム 頸椎多数回手術例の検討
21巻6号(1986年6月発行)
21巻5号(1986年5月発行)
21巻4号(1986年4月発行)
特集 脊椎・脊髄外科診断学の進歩(第14回日本脊椎外科研究会より)
21巻3号(1986年3月発行)
21巻2号(1986年2月発行)
21巻1号(1986年1月発行)
シンポジウム 骨盤臼蓋の発育
20巻12号(1985年12月発行)
20巻11号(1985年11月発行)
シンポジウム 骨肉腫の化学療法
20巻10号(1985年10月発行)
20巻9号(1985年9月発行)
20巻8号(1985年8月発行)
20巻7号(1985年7月発行)
シンポジウム 骨巨細胞腫の診断と治療
20巻6号(1985年6月発行)
20巻5号(1985年5月発行)
シンポジウム 人工股関節再置換術の問題点
20巻4号(1985年4月発行)
特集 Spinal Instrumentation(第13回脊椎外科研究会より)
20巻3号(1985年3月発行)
20巻2号(1985年2月発行)
20巻1号(1985年1月発行)
19巻12号(1984年12月発行)
19巻11号(1984年11月発行)
19巻10号(1984年10月発行)
19巻9号(1984年9月発行)
19巻8号(1984年8月発行)
19巻7号(1984年7月発行)
19巻6号(1984年6月発行)
特集 小児股関節(第22回先天股脱研究会より)
19巻5号(1984年5月発行)
19巻4号(1984年4月発行)
特集 頸部脊椎症(第12回脊椎外科研究会より)
19巻3号(1984年3月発行)
19巻2号(1984年2月発行)
19巻1号(1984年1月発行)
シンポジウム 関節鏡視下手術
18巻13号(1983年12月発行)
シンポジウム 電気刺激による骨形成
18巻12号(1983年11月発行)
18巻11号(1983年10月発行)
シンポジウム 四肢軟部腫瘍
18巻10号(1983年9月発行)
18巻9号(1983年8月発行)
シンポジウム 悪性軟部腫瘍の病理診断をめぐって
18巻8号(1983年7月発行)
18巻7号(1983年7月発行)
18巻6号(1983年6月発行)
シンポジウム 先天股脱初期整復後の側方化
18巻5号(1983年5月発行)
18巻4号(1983年4月発行)
特集 上位頸椎部の諸問題
18巻3号(1983年3月発行)
18巻2号(1983年2月発行)
18巻1号(1983年1月発行)
17巻12号(1982年12月発行)
17巻11号(1982年11月発行)
シンポジウム 人工股関節再手術例の検討
17巻10号(1982年10月発行)
17巻9号(1982年9月発行)
17巻8号(1982年8月発行)
17巻7号(1982年7月発行)
17巻6号(1982年6月発行)
17巻5号(1982年5月発行)
17巻4号(1982年4月発行)
特集 脊椎分離症・辷り症
17巻3号(1982年3月発行)
17巻2号(1982年2月発行)
17巻1号(1982年1月発行)
16巻12号(1981年12月発行)
シンポジウム 動揺性肩関節
16巻11号(1981年11月発行)
シンポジウム 特発性大腿骨頭壊死
16巻10号(1981年10月発行)
16巻9号(1981年9月発行)
シンポジウム 義肢装具をめぐる諸問題
16巻8号(1981年8月発行)
シンポジウム 脱臼ペルテスとペルテス病
16巻7号(1981年7月発行)
16巻6号(1981年6月発行)
シンポジウム 腰部脊柱管狭窄—ことにdegenerative stenosisの診断と治療
16巻5号(1981年5月発行)
16巻4号(1981年4月発行)
特集 Multiply operated back
16巻3号(1981年3月発行)
シンポジウムII Riemenbügel法不成功例の原因と対策
16巻2号(1981年2月発行)
シンポジウム 人工股関節置換術—この10年の結果をふりかえって
16巻1号(1981年1月発行)
シンポジウム 胸椎部脊椎管狭窄症の病態と治療
15巻12号(1980年12月発行)
15巻11号(1980年11月発行)
15巻10号(1980年10月発行)
15巻9号(1980年9月発行)
15巻8号(1980年8月発行)
15巻7号(1980年7月発行)
15巻6号(1980年6月発行)
15巻5号(1980年5月発行)
シンポジウム 先天股脱の予防
15巻4号(1980年4月発行)
シンポジウム CTと整形外科
15巻3号(1980年3月発行)
特集 脊椎腫瘍(第8回脊椎外科研究会より)
15巻2号(1980年2月発行)
15巻1号(1980年1月発行)
14巻12号(1979年12月発行)
14巻11号(1979年11月発行)
14巻10号(1979年10月発行)
14巻9号(1979年9月発行)
シンポジウム 最近の抗リウマチ剤の動向
14巻8号(1979年8月発行)
14巻7号(1979年7月発行)
シンポジウム 五十肩の治療
14巻6号(1979年6月発行)
14巻5号(1979年5月発行)
14巻4号(1979年4月発行)
特集 脊椎外傷—早期の病態・診断・治療—(第7回脊椎外科研究会より)
14巻3号(1979年3月発行)
14巻2号(1979年2月発行)
14巻1号(1979年1月発行)
13巻12号(1978年12月発行)
13巻11号(1978年11月発行)
13巻10号(1978年10月発行)
13巻9号(1978年9月発行)
13巻8号(1978年8月発行)
13巻7号(1978年7月発行)
13巻6号(1978年6月発行)
13巻5号(1978年5月発行)
13巻4号(1978年4月発行)
特集 脊椎の炎症性疾患
13巻3号(1978年3月発行)
13巻2号(1978年2月発行)
13巻1号(1978年1月発行)
12巻12号(1977年12月発行)
12巻11号(1977年11月発行)
12巻10号(1977年10月発行)
12巻9号(1977年9月発行)
12巻8号(1977年8月発行)
12巻7号(1977年7月発行)
12巻6号(1977年6月発行)
12巻5号(1977年5月発行)
12巻4号(1977年4月発行)
特集 胸椎部ミエロパチー
12巻3号(1977年3月発行)
12巻2号(1977年2月発行)
12巻1号(1977年1月発行)
11巻12号(1976年12月発行)
11巻11号(1976年11月発行)
11巻10号(1976年10月発行)
11巻9号(1976年9月発行)
11巻8号(1976年8月発行)
特集 腰部脊柱管狭窄の諸問題
11巻7号(1976年7月発行)
11巻6号(1976年6月発行)
11巻5号(1976年5月発行)
11巻4号(1976年4月発行)
11巻3号(1976年3月発行)
11巻2号(1976年2月発行)
シンポジウム Silicone rod
11巻1号(1976年1月発行)
10巻12号(1975年12月発行)
特集II Myelopathy・Radiculopathy
10巻11号(1975年11月発行)
シンポジウム 頸部脊椎症性ミエロパチー
10巻10号(1975年10月発行)
シンポジウム 関節軟骨の病態
10巻9号(1975年9月発行)
10巻8号(1975年8月発行)
10巻7号(1975年7月発行)
シンポジウム 慢性関節リウマチの前足部変形に対する治療
10巻6号(1975年6月発行)
10巻5号(1975年5月発行)
10巻4号(1975年4月発行)
10巻3号(1975年3月発行)
10巻2号(1975年2月発行)
10巻1号(1975年1月発行)
9巻12号(1974年12月発行)
9巻11号(1974年11月発行)
特集 脊椎外科(第1回脊椎外科研究会より)
9巻10号(1974年10月発行)
9巻9号(1974年9月発行)
9巻8号(1974年8月発行)
9巻7号(1974年7月発行)
シンポジウム 変形性股関節症の手術療法
9巻6号(1974年6月発行)
9巻5号(1974年5月発行)
9巻4号(1974年4月発行)
9巻3号(1974年3月発行)
9巻2号(1974年2月発行)
9巻1号(1974年1月発行)
8巻12号(1973年12月発行)
8巻11号(1973年11月発行)
8巻10号(1973年10月発行)
シンポジウム 移植皮膚の生態
8巻9号(1973年9月発行)
8巻8号(1973年8月発行)
8巻7号(1973年7月発行)
8巻6号(1973年6月発行)
8巻5号(1973年5月発行)
シンポジウム 顔面外傷
8巻4号(1973年4月発行)
8巻3号(1973年3月発行)
8巻2号(1973年2月発行)
シンポジウム 乳幼児先天股脱の手術療法
8巻1号(1973年1月発行)
7巻12号(1972年12月発行)
7巻11号(1972年11月発行)
7巻10号(1972年10月発行)
シンポジウム 膝の人工関節
7巻9号(1972年9月発行)
7巻8号(1972年8月発行)
7巻7号(1972年7月発行)
7巻6号(1972年6月発行)
7巻5号(1972年5月発行)
7巻4号(1972年4月発行)
7巻3号(1972年3月発行)
7巻2号(1972年2月発行)
7巻1号(1972年1月発行)
6巻12号(1971年12月発行)
6巻11号(1971年11月発行)
6巻10号(1971年10月発行)
6巻9号(1971年9月発行)
6巻8号(1971年8月発行)
6巻7号(1971年7月発行)
シンポジウム 四肢末梢血管障害
6巻6号(1971年6月発行)
6巻5号(1971年5月発行)
6巻4号(1971年4月発行)
6巻3号(1971年3月発行)
6巻2号(1971年2月発行)
6巻1号(1971年1月発行)
5巻12号(1970年12月発行)
5巻11号(1970年11月発行)
5巻10号(1970年10月発行)
5巻9号(1970年9月発行)
5巻8号(1970年8月発行)
5巻7号(1970年7月発行)
5巻6号(1970年6月発行)
5巻5号(1970年5月発行)
5巻4号(1970年4月発行)
5巻3号(1970年3月発行)
5巻2号(1970年2月発行)
5巻1号(1970年1月発行)
4巻12号(1969年12月発行)
4巻11号(1969年11月発行)
4巻10号(1969年10月発行)
4巻9号(1969年9月発行)
4巻8号(1969年8月発行)
シンポジウム 腰部椎間板症
4巻7号(1969年7月発行)
4巻6号(1969年6月発行)
4巻5号(1969年5月発行)
4巻4号(1969年4月発行)
4巻3号(1969年3月発行)
4巻2号(1969年2月発行)
4巻1号(1969年1月発行)
3巻12号(1968年12月発行)
3巻11号(1968年11月発行)
シンポジウム 股関節形成術
3巻10号(1968年10月発行)
シンポジウム 日本の義肢問題
3巻9号(1968年9月発行)
シンポジウム 内反足
3巻8号(1968年8月発行)
シンポジウム 腕神経叢損傷
3巻7号(1968年7月発行)
3巻6号(1968年6月発行)
3巻5号(1968年5月発行)
シンポジウム 脊髄損傷患者に対する早期脊椎固定術の適応と成績
3巻4号(1968年4月発行)
シンポジウム いわゆる鞭打ち損傷
3巻3号(1968年3月発行)
3巻2号(1968年2月発行)
3巻1号(1968年1月発行)
2巻12号(1967年12月発行)
2巻11号(1967年11月発行)
2巻10号(1967年10月発行)
2巻9号(1967年9月発行)
2巻8号(1967年8月発行)
シンポジウム 脳性麻痺
2巻7号(1967年7月発行)
2巻6号(1967年6月発行)
シンポジウム 腰痛
2巻5号(1967年5月発行)
シンポジウム 骨肉腫の治療および予後
2巻4号(1967年4月発行)
シンポジウム 関節リウマチの治療
2巻3号(1967年3月発行)
シンポジウム 先天性股関節脱臼 私の治療法
2巻2号(1967年2月発行)
シンポジウム 先天性筋性斜頸 私の治療法
2巻1号(1967年1月発行)
シンポジウム 脊髄損傷
