アレルギー性鼻炎に代表される即時型アレルギー反応がIgE抗体によることが解明されたのは1967年のことである。石坂公成,照子両先生の「レアギン活性担体としてのIgE抗体」の業績は燦然として輝いている。この後約40年間,臨床アレルギー学の進歩は基礎科学としての免疫学と不即不離の関係にあった。病態について新しい知見が報告されるごとに,臨床のターゲットは細胞面では抗体産生細胞,肥満細胞,好酸球,Tリンパ球へと移動している。また,化学伝達物質についてもヒスタミン,ロイコトリエンやプロスタグランジンへと拡大されている。しかしこれらの傾向も決して一定ではない。新技術の導入によって抗体産生やT細胞を標的としたワクチン療法が開発途上であるし,第3世代の抗ヒスタミン薬についての合意形成も進んでいる。研究のハイライトは螺旋を描きながら上昇し,治療に反映されつつあるが,根治の目途はまだ見えていない。
一方で,感染症や癌と異なり,アレルギー疾患は基本的に「生活の質」を損う病気であり,診断や治療に患者の主観が反映されることが多い。また,アレルギー疾患増加のメカニズムも十分に解明されたわけではない。診療面では耳鼻咽喉科や眼科専門医が必ずしも臨床アレルギー学に精通しているとは限らない。逆もまたしかりである。専門性と専門科横断的病態をもつアレルギー研究の並立はなかなか難しいものであるが,アレルギー疾患が表現される標的器官としての上気道は主に耳鼻咽喉科医が担当する分野である。加えてアレルギー疾患と言っても,本特集で取り上げたアレルギー性鼻炎のⅠ型以外にⅢ型やⅣ型によるものもある。上気道ではこれら他のアレルギー機序による疾患も忘れてはならない。また,この分野の臨床研究が国際化しており,強くエビデンスが求められていることも強調しておかねばならない。
雑誌目次
耳鼻咽喉科・頭頸部外科76巻5号
2004年04月発行
雑誌目次
特集 上気道アレルギーを診る
序 フリーアクセス
著者: 竹中洋
ページ範囲:P.5 - P.5
1.鼻アレルギーの臨床像
1)アレルギー性鼻炎の症状と重症度,QOL
著者: 大久保公裕
ページ範囲:P.7 - P.13
I.症状の成り立ち
1.鼻粘膜のアレルギー反応
アレルギー性鼻炎は鼻粘膜局所のアレルギー反応であり,マスト細胞上のIgEが仲介する抗原抗体反応の結果,鼻炎症状が発現する。鼻粘膜には少なくとも2種類のマスト細胞があり,粘膜型(Tタイプ),結合組織型(TCタイプ)と呼ばれている。Okudaら1)の報告で,粘液上皮層にある粘膜型マスト細胞がアレルギー反応に重要であることが確認され,抗原と結合しメディエーターを放出している。アレルギー性鼻炎の特徴である発作性のくしゃみはこの放出されたメディエーターの中のヒスタミンが三叉神経知覚枝終末を刺激し,くしゃみ中枢を介して生じる。この反射が軸索反射を誘発し,粘膜腺が刺激され鼻汁過多が生じる。メディエーターが血管系のそれぞれの受容体に働くと鼻閉が生じる2)。これらのくしゃみ,鼻汁,鼻閉がアレルギー性鼻炎の3大症状であり,患者の重症度とquality of life(QOL)を規定する。
長年,通年性アレルギー性鼻炎があると,鼻粘膜は上皮細胞の杯細胞の増加,繊毛の変化,上皮層の増殖,粘膜腺組織の増加などの変化が生じ,種々の細胞浸潤が慢性的に認められるようになる。これら変化が生じると,可逆性であるアレルギー反応といえども非可逆性の鼻粘膜腫脹が出現する。これら全ての変化が鼻粘膜でのアレルギー性炎症であり,軽症のものから非可逆性の難治性のものまである。非可逆性の粘膜変化は,スギ花粉症などの季節性アレルギー反応では生じにくいものである。
2)小児アレルギー性鼻炎の特徴
著者: 工藤典代
ページ範囲:P.15 - P.18
I.はじめに
近年ますます増加傾向にあるアレルギー性鼻炎は,幼小児においても例外ではなく,低年齢児にも及んでいる。器官の発達や成長時期である小児期のアレルギー性鼻炎は,成人のアレルギー性鼻炎とは症状も病態も異なるように思われる。15歳以下を小児とした場合,特に就学前後で大きく様相が異なる。10歳以降の小児は成人とほぼ同様の傾向であるが,乳幼児期や就学前後の児のアレルギー性鼻炎は成人とは異なった面がある。
本稿では特に,乳幼児から就学前後の小児に重点を置き臨床像を述べる。
2.鼻アレルギーの臨床検査
鼻アレルギーの検査には何が必要か
著者: 竹内万彦
ページ範囲:P.19 - P.28
I.はじめに
鼻アレルギーの診断に必要な臨床検査については,鼻アレルギー診療ガイドライン1)の中で詳述され,わが国の事情に即した具体的な記載になっている。一方,2001年に発表されたAllergic Rhinitis and its Impact on Asthma(ARIA)Workshop Report2)の中で述べられている臨床検査についての記述は,網羅的であり,エビデンスを重視している。
本稿では,この両者と他の文献を参考に,筆者の考えも交えて鼻アレルギーの臨床検査について概説したい。
3.鼻アレルギーと類縁疾患
鑑別と治療
著者: 櫻井大樹 , 岡本美孝
ページ範囲:P.30 - P.37
I.はじめに
アレルギー性鼻炎は鼻粘膜のⅠ型アレルギー性疾患で,発作性反復性のくしゃみ,水様性鼻漏,鼻閉を3主徴とする疾患と定義される。鼻アレルギー診療ガイドラインでは,アレルギー性鼻炎は過敏性非感染性鼻炎に分類され(表1)1),この過敏性非感染性鼻炎の分類の中にはアレルギー性鼻炎以外に,いくつかの非アレルギー性鼻炎が分類されている。これには血管運動性鼻炎(vasomotor rhinitis)および好酸球増多性鼻炎(eosinophilic rhinitis,non-allergic eosinophilia syndrome)が含まれる。これらは,アレルギー性鼻炎の3主徴であるくしゃみ,水様性鼻漏,鼻閉のうちいくつかの症状を複合してもっているため複合型に分類され,臨床的にはアレルギー性鼻炎との鑑別が必要となる。
アレルギー性鼻炎の診断には問診,鼻鏡検査,鼻汁好酸球検査を行い,過敏症であるか過敏症でないか,またアレルギー性か非アレルギー性かを判断する必要がある。さらに,原因抗原を特定するために皮膚テスト,血清特異的IgE抗体定量,誘発テストを行い治療方針を決定していく必要がある(図1)1)。特異抗原を同定するための検査が陰性であり,かつ鼻汁好酸球検査で有意な好酸球の増加が認められれば,好酸球増多性鼻炎と診断される。鼻汁好酸球検査が陰性であれば,血管運動性鼻炎と診断されることになる(表2)1)。しかし,抗原が同定できない場合であってもアレルギー性鼻炎を安易に除外するのではなく,臨床症状などから総合的に判断し診断していくことが必要である。
4.鼻アレルギーの治療
3)鼻アレルギーの新しい治療の可能性
著者: 岡野光博
ページ範囲:P.91 - P.98
I.はじめに
鼻アレルギーの治療は,①抗原の除去・回避,②薬物療法,③免疫療法,④手術療法などに分けられる。そのうち現時点で治癒または長期寛解を期待できる唯一の治療法は特異的免疫療法(減感作療法)である。しかし,効果発現が遅い点や稀にアナフィラキシーなどの重篤な副反応を生じることから,一般の普及に至っていないのが現状である。一方,鼻アレルギーの感作および発症機序が明らかとなり,根治のために制御すべき因子が明らかになりつつある(図1)。さらに近年,免疫寛容(tolerance)のメカニズムに関する研究が進んできている。
本稿では,古典的な特異的免疫療法に代わり得る,より即効性でかつ安全性が高く新しい根治療法となり得る治療法を紹介し,その臨床応用の可能性および考えられる問題点について概説する。
1)保存的治療―適応と薬剤の選択
(1)薬物治療(全身)
著者: 川内秀之
ページ範囲:P.39 - P.44
I.はじめに
通年性アレルギー性鼻炎,花粉症の治療に関しては,鼻アレルギー診療ガイドライン(以下,ガイドライン)が2002年に改訂され,コンセンサスが得られつつある(表1)。
治療法において抗原除去と回避が基本となることは当然であるが,アレルギー性鼻炎治療薬を用いた薬物療法の役割は非常に大きく,これは通年性アレルギー性鼻炎,季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)いずれにおいても同様である。2002年に原田らが中心となって行った中国地区の耳鼻咽喉科医,内科医およそ600名を対象としたアンケート調査の結果では,特に第2世代抗ヒスタミン薬を第1選択としていることが明らかにされた。しかし一方で,特に鼻閉では遅発相を念頭におき,ロイコトリエン受容体拮抗薬,トロンボキサンA2受容体拮抗薬もその役割と地位を築きつつある(表2)。客観的なデータからみても,鼻腔通気度を改善する薬剤として評価されている。
(2)薬物療法(局所)
著者: 馬場廣太郎
ページ範囲:P.47 - P.58
I.はじめに
アレルギー性鼻炎に対する薬物療法の投与経路は,経口および経鼻投与が少数の例外を除く全てと考えてよい。ケミカルメディエーター遊離抑制薬や受容体拮抗薬は内服薬が主体で,局所用剤は鼻用ステロイド薬の占める割合が高い。かつて点鼻薬といえば血管収縮薬と考えられていたが,1967年インタール(R)の開発以来,アレルギーに起因する鼻症状を抑制する薬剤の経鼻投与という方法が拓かれたのである。その後副作用の軽減や高濃度の薬剤を局所に直接作用させることが可能なこの方法によって,局所ステロイド薬が生まれ,第2世代抗ヒスタミン薬にも点鼻薬が開発されるに至った。最も,抗ヒスタミン薬の点鼻用剤は市販薬であるOTCが先行しており,第1世代抗ヒスタミン薬と血管収縮薬の合剤が多数発売されている。
処方薬の局所用剤は,ケミカルメディエーター遊離抑制薬(インタール(R),ソルファ(R)),第2世代抗ヒスタミン薬(ザジテン(R),リボスチン(R)),局所ステロイド薬(プロピオン酸ベクロメタゾン,フルニソリド,プロピオン酸フルチカゾン)および点鼻用血管収縮薬(5薬剤)がある。なお,抗コリン薬の点鼻用剤は製造が中止された。
(3)免疫療法
著者: 大橋淑宏
ページ範囲:P.59 - P.66
I.はじめに
アレルギー性鼻炎に対する治療は抗原からの回避以外に,1)薬物療法,2)免疫療法(特異的減感作療法),3)手術療法などがある。いずれの治療法にも一長一短がある。アレルギー性鼻炎患者を治療する際には,どの治療法が各患者に最適であるかを医師が判断することも重要であるが,最終的には各治療法の概要や長所,短所などの情報を医師がわかりやすく呈示し,患者本人が治療法を選択すべきである。
2)外科的治療―適応と術式
(1)レーザーによる治療
著者: 池田勝久 , 関眞規子
ページ範囲:P.67 - P.69
I.はじめに
鼻アレルギーの治療では,抗ヒスタミン剤,ロイコトルエン拮抗剤,トロンボキサンA2拮抗剤,局所的ステロイド剤を中心とした薬物療法や,特異的免疫療法が主体をなしてきた。しかしながら,これらの様々な保存治療に対し抵抗を示す症例も少なくない。近年,患者の精神的・肉体的な侵襲の軽減,時間的・経済的な制約の軽減などの目的に対して,外来で行えるday surgeryが耳鼻咽喉・頭頸部外科領域においても実践されてきている。保存的治療によっても症状の改善されない鼻アレルギー患者に対して行っているレーザー治療の短期と長期の予後について解説する。
(2)ハーモニックスカルペルによる治療
著者: 太田伸男
ページ範囲:P.71 - P.75
I.はじめに
アレルギー性鼻炎に対する治療は,①セルフケア,②薬物療法,③手術療法,④減感作療法に分けられる。抗原回避が基本であるが,症状を抑制しQOLを向上させるためには薬物療法が必要となることが多い。しかし,近年開発され臨床応用された新薬にも抵抗性の場合や時間的経済的な負担の問題から,患者の希望によって薬物療法に代わり手術療法が選択されることも多くなっている。アレルギー性鼻炎に対する外科的治療としては下鼻甲介粘膜に対する切除術,電気凝固術,化学焼灼術,凍結手術,レーザー手術などが行われている。
今回われわれは,従来外科用の凝固切開器具として汎用されていたにハーモニックスカルペル(R)を用いて通年性アレルギー性鼻炎症例の下鼻甲介粘膜の処理方法について紹介するとともに,他の外科的療法との多面的な比較を行ったのでその結果について報告する。
(3)薬物による焼灼
著者: 八尾和雄
ページ範囲:P.77 - P.84
I.はじめに
鼻アレルギーは現代病といわれ,症例数が増えたことで社会問題にまで発展しつつある。しかし治療に関しては,発症のメカニズムがかなり解明されてきているにもかかわらず十分に満足のいく治療法がない。最近の治療指針である鼻アレルギー診療ガイドライン(2002年版)によれば,アレルギー性鼻炎の手術治療は重症度分類における重症と診断した症例に適応があり,抗アレルギー剤内服治療が優先としている印象がある。この手術療法は目的別に3種類に分類される。第1は鼻粘膜縮小と変調を目的とした手術で,電気凝固,凍結手術,レーザー手術法,80w/v%トリクロール酢酸塗布が含まれている。第2は鼻腔通気度の改善を目的とした鼻腔整復術で,粘膜下下甲介骨切除術,下甲介粘膜切除術,鼻中隔矯正術,高橋式鼻内整形術,下甲介粘膜広範切除術,鼻茸切除術で,第3は鼻漏の改善を目的としたvidian神経切断術が示されている。いずれも優れた治療法であるにもかかわらず,第1の方法を除いて入院対処が必要となることが多い。また第1の方法において,たとえday surgeryの方法であっても高額な設備を必要とする方法を含んでいる。社会的,経済的負担が多いことが,重症例に適応とした原因のように思う。もしも負担の条件がなく,臨床成績が比較的良好であるなら,手術治療はアレルギー性鼻炎の治療手段として第1選択と考える。
われわれは,1986年からトリクロール酢酸の80w/v%濃度溶液(以下,TCA)を十分な表面麻酔後に,両側下甲介に綿棒で塗布する下甲介化学剤手術(以下,TCA手術)をアレルギー性鼻炎の第1治療選択法として行ってきた1,2)。内服治療が,内科は当然としてあらゆる科で安易に行われている現状に対して,TCA手術は耳鼻咽喉科独自のday surgeryとしての方法であり,安全で副作用がなく3),保険適用があり,臨床成績は良好である。
(4)鼻腔形態矯正術と後鼻神経手術
著者: 竹野幸夫 , 小川知幸 , 石野岳志 , 夜陣紘治
ページ範囲:P.85 - P.89
I.はじめに
気管支喘息やアトピー性皮膚炎などの他のアトピー疾患と比較した場合,鼻アレルギーの臨床的特徴として挙げられるのは,1)局所の抗原抗体反応により惹起された肥満細胞の活性化などによるⅠ型アレルギー反応が主体である,2)アレルギーの原因となる特異的抗原が同定可能な場合が多い,3)鼻腔内でアレルギー反応が生じる場所がほぼきまっている=下鼻甲介,といった点である。この中で鼻アレルギーに対する手術療法はいうまでもなく,上記の3)の特色に着目して,アレルギー炎症の反応の場である下鼻甲介を手術的に処理する方法である。この期待される効果としては,1)鼻腔の形態異常を矯正するとともに,アレルギー反応の領域を縮小させ(下鼻甲介切除など),鼻腔の通気性を改善させる,2)粘膜表層のアレルギー反応の場を変性させ(CO2レーザー焼灼など),抗原抗体反応から連鎖的に生じる慢性のアレルギー炎症を生じにくくする,3)アレルギー反応を増幅する神経ネットワークを処理し(後鼻神経手術など),鼻アレルギーに伴う鼻過敏症状を軽減するなどの点が挙げられる。また,患者に対する手術侵襲の程度により,外来手術として施行可能なものと,入院して全身麻酔下に施行されるもの,とに分類可能である。前者の代表が炭酸ガスレーザーによる下鼻甲介表面粘膜焼灼術であり,後者の代表が後鼻神経手術(+粘膜下下鼻甲介切除術)といえる。いずれにしてもその手術適応の判断は,鼻アレルギーかどうかと,その重症度に関するしっかりとした診断が重要である。
5.鼻アレルギーと副鼻腔炎
1)アレルギー性副鼻腔炎の発症機序と確定診断へのアプローチ
著者: 黒野祐一
ページ範囲:P.99 - P.105
I.はじめに
アレルギー性鼻炎患者の副鼻腔単純X線撮影を行うと,上顎洞あるいは篩骨洞に高頻度に何らかの陰影が認められること,そして慢性副鼻腔炎患者の多くがアレルギー性鼻炎を合併していることから,アレルギー性鼻炎と副鼻腔の病態に何らかの関連性があると考えられる。また,1960年代からアレルギー性鼻炎が急増する一方で,慢性副鼻腔炎はこれと逆比例するように年々減少し,かつ軽症化の傾向にあり,かつてのように膿性の鼻漏を常時多量に認める典型的な慢性副鼻腔炎症例はほとんどみられなくなってきた1)。こうした背景により,アレルギー性鼻炎を合併した慢性副鼻腔炎では,副鼻腔の病態に感染よりもむしろⅠ型アレルギーが関与していると考えられ,アレルギー性副鼻腔炎という概念が提唱された2)。しかし,本疾患の定義は未だ確立しておらず,本疾患の診断はもちろん,その発症機序についても統一した見解が得られているとはいい難い。
そこで本稿では,アレルギー性副鼻腔炎の概念を整理し,その発症機序を様々な角度から検証し,診断に至るまでのアプローチについて考察してみたい。
2)アスピリン喘息の診断と管理
著者: 荻野敏 , 瀬尾律
ページ範囲:P.107 - P.111
I.はじめに
アスピリン(アセチルサリチル酸)は,100年ほど前から優れた鎮痛解熱作用のため広く使われてきた。反対に広く使われるため,多くの副作用が報告されている。その1つにアスピリン過敏症(アスピリン不耐症)がある。アスピリンによる過敏症にはいくつかのタイプがあるが,代表的なものとして,合併する症状からいわゆるアスピリン喘息(aspirin-induced asthma:AIA)とアスピリン蕁麻疹に分けることができる。
このうち,アレルギー性鼻炎との鑑別も必要であり,副鼻腔炎,鼻茸の合併が高頻度に認められることから,耳鼻咽喉科と密接に関係しているのがAIAである。AIAは日常診療において稀な疾患ではなく,対応,管理を誤ると極めて重大な結果をもたらすこともあり得る。
3)アレルギー性真菌性副鼻腔炎の特徴
著者: 鈴木元彦 , 中村善久 , 大野伸晃
ページ範囲:P.113 - P.118
I.はじめに
副鼻腔真菌症は,①acute or fulminant invasive fungal sinusitis,②chronic or indolent invasive fungal sinusitis,③mycetoma,④allergic fungal sinusitis(アレルギー性真菌性副鼻腔炎)に分類される。アレルギー性真菌性副鼻腔炎は最近新しく分類された疾患で,副鼻腔組織に著明な好酸球浸潤を認め(図1),真菌に対するアレルギー炎症がその病態と考えられている。病理組織学的特徴としてはallergic bronchopulmonaryAspergillosis(アレルギー性気管支肺アスペルギルス症)に非常に類似している。1976年,Safirstein1)は鼻内ポリープ,痂皮形成を認め副鼻腔内においてAspergilusを検出したアレルギー性気管支肺アスペルギルス症と類似した症例を初めて報告した。また1981年Millarら2)は,Aspergillus fumigatusに対する即時型反応を示し,またA. fumigatusによる慢性副鼻腔炎を引き起こした症例をallergicAspergillosisof the paranasal sinusesとして報告した。さらに1983年,Katzensteinら3)は副鼻腔内に好酸球,Charcot-Leyden結晶,真菌の菌糸を含むムチン(allergic mucin)が存在する副鼻腔炎を報告し,アレルギー性アスペルギルス副鼻腔炎(allergic Aspergillus sinusitis)と命名した。しかし,その後,これらの副鼻腔炎はアスペルギルス以外の真菌でも生じることが報告され,アレルギー性真菌性副鼻腔炎(allergic fungal sinusitis)と呼ばれるようになった4)。以後,アレルギー性真菌性副鼻腔炎については数多くの報告がされているが,いまだに不明なことが多い。
6.鼻アレルギーといびき症
鼻アレルギーがいびき,睡眠時無呼吸の病態に及ぼす影響
著者: 宮崎総一郎 , 内田亮
ページ範囲:P.119 - P.122
I.はじめに
鼻アレルギーによる鼻呼吸障害があると,日中は意識的に口呼吸で代償するが,睡眠時には意識的な代償がなされず,狭窄した鼻で呼吸しようとするためにいびきや睡眠時無呼吸の原因となる。成人では鼻呼吸が制限されても,ある程度口を通じて呼吸することが可能であるが,小児では解剖学的理由から,鼻呼吸障害は重症のいびきや睡眠時無呼吸を引き起こす。
7.鼻アレルギーと喘息
1)鼻アレルギーが小児喘息に及ぼす影響
著者: 小田嶋博
ページ範囲:P.125 - P.131
I.はじめに
小児の気管支喘息(以下,喘息と略)患者の多くは鼻アレルギーを合併している。母親の中には,鼻が悪くなってきたと思ったら喘息発作になったというものも多い。この両者が関連していることは,臨床的経験からは想像に難くない。しかし,花粉症の原因としてのスギ花粉が喘息の発作に関連するか否かについては必ずしも明らかではない。
本稿では,両者の関連について,われわれの経験と文献的考察を加えて述べてみたい。
2)鼻アレルギーが成人喘息に及ぼす影響
著者: 辻文生 , 東田有智
ページ範囲:P.133 - P.140
I.はじめに
アレルギー疾患は現代病といわれ,近年わが国のみならず,世界的にも増加の傾向にある。上気道のアレルギー疾患であるアレルギー性鼻炎と下気道のアレルギー疾患である気管支喘息(以下,喘息と略)においてもその例外ではない。それぞれの疾患は,主に耳鼻咽喉科そして内科と異なる科が扱う疾患であり,しかも標的気管も異なるため独立した疾患と捉えられ,独自に研究や開発が進められ,治療法が確立されてきた。しかし,最近10年間にそれぞれの科の枠を超え,その両者の密接な関連性は疫学的研究や臨床所見により明らかにされ,同時に免疫学的研究や治療に対する反応性などによって裏づけられるようになってきた。そこで,アレルギー性鼻炎と喘息の関係において“one airway,one disease(1つの気道,1つの疾患)”という新しい概念が提唱されるようになった。つまり,アレルギー性鼻炎と喘息は,同じ気道の炎症に特徴づけられる疾患であり,上気道の変化は,下気道に影響を及ぼす可能性があるという概念を示したものであるが,まだまだ確立されたものではなく賛否両論がある。
本稿では,アレルギー性鼻炎と喘息における疫学的関係,臨床研究,病態生理そして治療法などの種々の側面から過去の知見を紹介し,アレルギー性鼻炎が成人喘息に及ぼす影響について述べる。
8.口腔アレルギー症候群(OAS)
口腔アレルギー症候群の診断と治療
著者: 安部裕介 , 原渕保明
ページ範囲:P.141 - P.147
I.はじめに
口腔アレルギー症候群(oral allergy syndrome:OAS)は,1987年にAmlotら1)によって,原因となる特定の食物を摂取することによって生じる口腔,咽頭粘膜のIgE抗体を介したⅠ型アレルギー反応による一連の症状を呈する症候群として提唱された。食物摂取後15分以内に口唇や口腔粘膜の腫脹,かゆみ,ヒリヒリ感などで発症する。口腔咽頭症状のみならず,ときには喘鳴,喉頭浮腫などの喉頭症状,蕁麻疹や血管浮腫などの皮膚症状,腹痛,下痢などの消化器症状,さらに喘息発作やアナフィラキシーショックなどが出現する(表1)。そば,卵などの食物アレルギーによって生じる口腔症状も広い意味でOASに含まれるが,本症の最も重要な特徴は花粉症患者に高頻度に発症し,その原因食物の多くは果実であることである。特にシラカンバ花粉症患者における発症率は欧米では70%2~4)と極めて高い。花粉症以外にはラテックスアレルギー患者にもlatex-fruits syndrome5)として,約50%に発症することがいわれている。
9.喉頭アレルギー
喉頭アレルギーの診断基準
著者: 内藤健晴
ページ範囲:P.148 - P.151
I.はじめに
アレルギー性鼻炎と喘息は代表的な気道アレルギー疾患であり,最近ではone airway one diseaseの概念から,それぞれ隔絶した疾患と考えるのではなく,一気道アレルギー疾患として捉える国際的な趨勢にある。呼吸器という1つの臓器とみなす観点からすると,鼻と下気道の中間に位置する咽頭,喉頭,気管においてもアレルギーは標的臓器として成立し得ることになる。しかし,アレルギー性鼻炎や喘息のようにそれほど一般的なアレルギー性気道疾患とならないのはなぜであろうか。気道の中でバイパスのない喉頭や気管で鼻や末梢気道のように顕著なアレルギーが起きてしまうようでは容易に窒息をきたし,速やかに生命危機に陥ってしまう。こうした点から考えると,生体発生上これらの臓器は本来アレルギー反応が起きにくい臓器なのではないかと想定される。それゆえ,従来,喉頭アレルギーという診断名はあまり馴染みの深いものではなく,アレルギーに関する成書の中でもあまり目にすることはなかったものと思われる。
しかし,最近では,臨床的にスギ花粉症患者の多くが眼・鼻症状のほかに咽喉頭症状を訴えることが注目されたり,咽喉頭異常感症患者の中にアレルギーの関与を疑わせる症例がいくらか存在したり,慢性咳嗽患者にアトピー素因を有する者が多いことなどから,臨床的にノドにおいても慢性に経過するアレルギーがあるのではないかと多くの実地医家は疑い始め,その研究がされるようになった。肺に明らかな病変がなく慢性の咳嗽をきたす疾患として喉頭アレルギーが挙げられるが,そのほかにも鑑別すべき類似疾患が数多く存在する。
本稿では,喉頭アレルギーの鑑別疾患とその診断について,筆者らが行ってきた研究を中心に最近の知見を述べることにする。
10.好酸球性中耳炎
好酸球性中耳炎の病態と治療
著者: 飯野ゆき子
ページ範囲:P.155 - P.160
I.はじめに
近年,気管支喘息に合併した難治性の滲出性中耳炎,あるいは慢性中耳炎が注目を集めている。これらの症例では,感染がない場合極めて粘稠な中耳貯留液を有し,これまでの滲出性中耳炎や慢性中耳炎の治療に抵抗を示す。この中耳貯留液や中耳粘膜には多数の好酸球の浸潤をみることから,Tomiokaら1)はこの中耳炎を好酸球性中耳炎として報告した。この中耳炎の存在が明らかになるにつれ報告も相次ぎ,2003年には東北大学耳鼻咽喉科小林俊光教授が班長となり,好酸球性中耳炎の研究班が組織され,日本全国の基幹病院における好酸球性中耳炎の疫学調査が施行された。その結果,好酸球性中耳炎はそれほど稀な疾患ではないことが判明している。
本稿では好酸球性中耳炎の自験例やこれまでの報告に加え,われわれの研究結果をもとにその病態,さらに治療に関して述べてみたい。
11.化学物質過敏症
化学物質過敏症の臨床像
著者: 荒木倫利
ページ範囲:P.161 - P.166
I.はじめに
最近,特に室内での化学物質曝露に対して体調の不良を訴える人々の報告が増え社会問題となっており,原因の解明が求められている。
環境中の微量な化学物質の曝露により様々な健康障害を生じる可能性は以前から指摘されており,米国では本態性多種化学物質過敏状態(multiple chemical sensitivity:以下,MCSと略)として検討されてきた。日本では「化学物質過敏症」の名称で広く知られつつあるが,病態について不明であり,十分に科学的に把握されているわけではない。MCS,化学物質過敏症は,原因として種々の化学物質が想定され,多臓器にわたる他覚的所見の乏しい自覚症状を呈する状態であり,概念,病態,診断,治療について多くの議論がなされているが,いまだ一定の見解は得られていない。
12.臨床医に必要なアレルギーの基礎的知識 1)気道のⅠ型アレルギー反応の特徴
(1)浸潤細胞とサイトカイン
著者: 藤枝重治
ページ範囲:P.167 - P.176
I.はじめに
Ⅰ型免疫反応は,肥満細胞上にあるIgEに抗原が結合することにより放出されたヒスタミンが引き起こし,その代表がアレルギー性鼻炎とされている。アレルギー性鼻炎の発症機序はT細胞,B細胞はもちろん,肥満細胞,好酸球,好塩基球など多くの細胞とサイトカインが複雑にネットワークを形成していることによる。
本稿ではその中で,T細胞とB細胞に焦点を絞って述べる。
T細胞とB細胞によって行われる主たることは,IgE抗体産生であるが,1)抗体を産生するB細胞の分化・増殖,2)細胞の活性化・記憶,3)Th2細胞への分化,Th1・Th2バランスの3点が重要である。これまでに常識とされていることはもちろん説明するが,できる限り最新の内容を記載する。
(2)化学伝達物質:ヒスタミン
著者: 久保伸夫
ページ範囲:P.177 - P.181
I.はじめに
ヒスタミンはヒスタミンH1受容体(以下,H1)を介してアレルギー疾患やアナフィラキシーショックの発症に関与するが,生理的にも体内に広く分布する分子量111の生体活性アミンであり,重要な生理機能を果たしている。末梢ではヒスタミンH2受容体(以下,H2)を介し胃酸分泌に大きく関与し,一方,生理的免疫応答にも関与している。中枢にはヒスタミン作動神経が存在し,覚醒,睡眠,学習,認知,食欲など精神情動に関与する重要な神経伝達物質である。過去30年間ヒスタミン研究の中心は日本であった。
末梢でのヒスタミン産生細胞は,組織中の肥満細胞,末梢血中好塩基球,胃粘膜のECL細胞(enterochromaffin-like cell)などが知られているが,これらの細胞ではヒスタミンは細胞内顆粒に貯蔵され,IgE-IgE受容体を介する刺激に応じて脱顆粒し細胞外に開口放出される。放出されたヒスタミンは効果器細胞のヒスタミン受容体に結合してメッセージを伝える。現在4種類のヒスタミン受容体が同定されている。いずれも7回膜貫通型GTPタンパク共役型受容体であり,1型アレルギーに関与するH1,胃酸分泌に関与するH2,中枢ヒスタミン作動神経系のオートレセプターであるヒスタミンH3受容体(以下,H3),最近クローニングされまだ機能はわかっていないが,血球に広く分布しリンパ球や好酸球での役割が注目されているヒスタミンH4受容体(以下,H4)である。
(3)化学伝達物質:ロイコトリエン
著者: 白崎英明 , 氷見徹夫
ページ範囲:P.183 - P.188
I.はじめに
ロイコトリエンはアラキドン酸カスケードにおいて,リポキシゲナーゼにより産生される一連の代謝物であるが,LTC4,LTD4およびLTE4のシステイニルロイコトリエン(CysLT)が気道アレルギー疾患に関与していると考えられている。上気道においては,鼻アレルギー患者抗原誘発後の鼻汁中にCysLTが検出され1),CysLT受容体拮抗剤が鼻アレルギー患者の特に鼻閉に対し優れた有効性が認められることより2~4),CysLTは鼻アレルギーを含め気道のアレルギー炎症性疾患に重要な役割を演じていると考えられている。
本稿では鼻アレルギーにおけるロイコトリエン,特にLTD4およびその受容体であるCysLT1受容体の関与について,これまでの報告を整理し,その推定される役割および機能につき概説する。
(4)好酸球性炎症とアレルギー
著者: 増山敬祐
ページ範囲:P.189 - P.197
I.アレルギーと好酸球
アレルギー性炎症における細胞反応の1つの特徴は,炎症局所における選択的な好酸球の浸潤である(図1)。この好酸球の組織浸潤は,抗原誘発後に起こる遅発相の反応において顕著に認められる(図2)1)。しかも,活性化好酸球が多数を占めており,遅発反応の惹起に関与している主要な細胞の1つである。また,ヒトにおける遷延化したアレルギー性炎症では,長期にわたる抗原誘発の結果,即時相と遅発相の反応が繰り返され,好酸球を中心とする慢性炎症像が形成される。
近年の研究により,アレルギー性炎症の形成にはいわゆるTh2タイプのサイトカインが深く関与していることが明らかにされた。1つにはアレルギーの誘導相において,例えばスギ花粉(Cry j I)やカバノキ花粉(Bet v I)に対し特異的に反応するヒトT細胞クローンはTh2クローンであることが報告されている2,3)。Th2クローンはIL-4を優位に産生しIFN-γはほとんど産生せずに,Ⅰ型アレルギーの特徴であるIgE抗体産生を誘導する。さらに,Th2タイプのサイトカインはアレルギーの効果相においても発現することが知られている。Durhamら4)は花粉非飛散期にチモシー花粉症患者の鼻内抗原誘発を行い,鼻粘膜遅発相に発現されたサイトカインのmRNAを観察した。彼らの報告によると,抗原誘発ではコントロール誘発に比べてIL-4,IL-5(Th2タイプサイトカイン)のmRNAの発現が有意に高値を示し,IL-2,IFN-γ(Th1タイプサイトカイン)のmRNAの発現はコントロール誘発と有意差はなかった(図3)。つまり,抗原誘発によりアレルギー性炎症局所の遅発相においてTh2タイプの反応が誘導されるのである。さらに,活性化好酸球とTh2タイプサイトカイン発現との間には有意の正の相関が認められ,アレルギー効果相における好酸球の活性化にも関わっている(図4)。
2)疫学
(1)スギ花粉症の疫学
著者: 今井透 , 本田靖
ページ範囲:P.199 - P.205
I.はじめに
疫学とは,「明確に規定された人間集団の中で出現する健康関連のいろいろな事柄の頻度と分布およびそれらに影響を与える要因を明らかにして,健康関連の諸問題に対する有効な対策樹立に役立てるための科学」と定義されている1)。スギ花粉症に関しては,疫学調査でわかっていることはまだまだ限界がある。これまで多くの花粉症疫学調査が行われてきたが,有病率の全国比較が最近報告されたばかりである2,3)。さらに花粉症対策は,現在十分に満足される対策法が樹立されているとはいえない。特に治療期間が長くかかること,長期にわたって症状で悩みQOLが低下すること,十分な効果が得られる場合でも医療費がかかることが挙げられる4)。このような国民的な問題を解決していくためには,花粉症の発症機序や誘因となる様々な環境因子がどの程度関与しているかを判断することが必要である。多くの環境問題の解決には国を挙げての対処が必要であろうが,そのためには客観的な疫学的調査結果の集積が望まれる。
スギ花粉症の疫学に関しての総説が,これまでにいくつかまとめられている5~7)。特に,厚生労働省の補助を受けてガイドラインの中にまとめられたものは多くの論文をEBM的に検討しており,さらに膨大な資料がCD-ROMとして付録に付けられている8)。今回は2つの全国調査の結果とメタアナリシスを紹介する。次にわれわれが参加する機会を得た科学技術庁(現文部科学省)と東京都の調査を紹介し,電子疫学調査の可能性を示したい。
(2)学校検診と鼻アレルギー
著者: 出島健司
ページ範囲:P.207 - P.211
I.はじめに
小児期における耳鼻咽喉科疾患のうち,罹患率が高く,主要な疾患として鼻疾患と扁桃疾患を挙げることができる。鼻疾患の中では,鼻アレルギーと慢性副鼻腔炎が重要で,それぞれの疾患有病率は時代の変遷とともに変化してきた。このような疾患構造の変化といった歴史は,日常小児鼻疾患を診療するうえで臨床医として当然理解を深めておく必要がある。
本稿では,学校検診のデータを中心にそれ以外の疫学データも加味して,小児鼻疾患の変遷と現時点での疾患の有病率について,過去の報告からreviewする。
(3)寄生虫とアレルギー
著者: 遠藤朝彦 , 今井透 , 渡辺直煕 , 名和行文 , 本田靖 , 新田裕史
ページ範囲:P.213 - P.220
I.はじめに
耳鼻咽喉科臨床の現場でアレルギー疾患患者の増加がいわれて久しい。今日では,耳鼻咽喉科の多くの施設で外来患者の第1位を占めるといわれている。つい30~40年前,「日本にはアレルギー性鼻炎や花粉症患者は少ない」といわれていたことを考えると隔世の感がある。しかし,われわれの診療圏では,現在もアレルギー性鼻炎や花粉症が増え続けているかというと,かなり以前から微増ないし横ばい状態にあり,急激な増加傾向はみられていない。つまり,少なくとも当地では,過去のある時点において発症者数が急増したことを意味している。事実,東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科(以下,慈恵医大耳鼻科と略)の疫学調査によれば,「昭和40年代から50年代にかけてアレルギー性鼻炎や花粉症が急増した」との調査結果がある1)。では,なぜそれ以前はアレルギー性鼻炎や花粉症が少なかったのか,なぜある時点で急増したのか,その後なぜ増加傾向が鈍化したのか。その理由は今日でも明確にされておらず,素因のほかに大気汚染,住環境,栄養,気候など種々取りざたされている。
その理由の1つに寄生虫感染の問題がある。
われわれは,文部科学省の科学技術振興調整費による「スギ花粉症克服に向けた総合研究」において,研究の一環としてスギ花粉症と寄生虫の問題を取り上げ,既にその一部を報告した2)。本稿では,その後の調査結果を加え,若干の知見も得られたので報告する。
3)アレルゲン
(1)日本の花粉アレルゲン―植物学的分類に従って―
著者: 宇佐神篤 , 柘植昭宏 , 杉本昌利 , 岩城勝 , 高木恭子
ページ範囲:P.221 - P.234
I.はじめに
1930年代に渡米中に“枯草熱”に罹患した例の症例報告があった。その後30数年を経て,わが国の花粉症第1号としてブタクサ花粉症の報告がなされた。爾来これまでに症例報告を伴う花粉抗原は,筆者の調べでは61種にのぼる。
本稿では,植物学的分類に従って,その特徴を略述し,浜松市における自験の空中花粉調査成績を記した。また,IgE抗体測定可能な抗原については,測定の際の抗原のコード番号と抗原名を記し,臨床の要に供した。
(2)ダニアレルゲンと室内環境
著者: 安枝浩
ページ範囲:P.235 - P.242
I.室内環境アレルゲンとしてのダニ
アレルギー疾患は環境的要因と遺伝的要因の相互作用によって発症する。アレルギー疾患の発症にかかわる環境的要因の中で最も重要なものは,環境中のアレルゲンへの曝露とそれに伴う感作である。近年,アレルギー疾患は飛躍的に増加しているが,それには現代の都市化された社会におけるヒトの生活様式の変化や,住宅構造の変化によってもたらされた室内環境アレルゲンの増加というものが密接に関わっている。特に問題となる室内環境アレルゲンとして,ダニ,ネコやイヌなどのペット,ゴキブリなどがあり,わが国を初めとする温暖,湿潤な気候の地域においては,室内塵中に生息するチリダニ科ヒョウヒダニ属の2種類のダニ,ヤケヒョウヒダニ(Dermatophagoides pteronyssinus)とコナヒョウヒダニ(D. farinae)が最重要の室内環境アレルゲンとなる1)。室内塵への曝露がアレルギー疾患の原因になるということは200年以上も前から知られていたが,その室内塵アレルゲンの本態がヒョウヒダニであるということは,1960年代の後半にわが国のMiyamotoら2),オランダのVoorhorstら3)によって明らかにされた。
ダニとは分類学的には節足動物門,クモ型綱,ダニ目に属する8本足の生物で,地球上に3万種以上が生息していると考えられている。これらの中で室内環境アレルゲンとして問題になるダニは,チリダニ科のダニとコナダニ科,ニクダニ科のダニである。チリダニ科のダニは別名室内塵ダニ(house dust mites)といわれている。一方,コナダニ科,ニクダニ科のダニは穀物などの貯蔵庫で大量発生することから貯蔵庫ダニ(storage mites)と呼ばれている。コナダニ科,ニクダニ科のダニは,中南米などの熱帯,亜熱帯地方におけるネッタイタマニクダニ(Blomia tropicalis)のように,地域によっては室内環境アレルゲンとしてチリダニ科のダニ以上に重要になることもある。しかし,わが国ではコナダニ科,ニクダニ科のダニに対するIgE抗体の陽性率,抗体価はともにヒョウヒダニに比べるとはるかに低く(表1),わが国の一般家庭においては,コナダニ科,ニクダニ科のダニによるアレルギーが問題になることはほとんどない。すなわち,アレルゲンとしてはチリダニ科の2種類のヒョウヒダニだけを考えればよいということになる。
基本情報
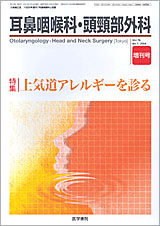
バックナンバー
96巻13号(2024年12月発行)
特集 内視鏡下鼻副鼻腔手術—基本とコツで上手くなる
96巻12号(2024年11月発行)
特集 必携! 救急対応・手技マニュアル
96巻11号(2024年10月発行)
特集 頭頸部がん薬物療法—プロに学ぶ最善の選択
96巻10号(2024年9月発行)
特集 伝えたい レジェンドによる耳科診療の極意
96巻9号(2024年8月発行)
特集 嗅覚診療最前線
96巻8号(2024年7月発行)
特集 必携! 唾液腺診療 虎の巻
96巻7号(2024年6月発行)
特集 他科はこう診る! 耳鼻咽喉科・頭頸部外科の症候
96巻6号(2024年5月発行)
特集 上手にやろう 外来処置と小手術
96巻5号(2024年4月発行)
増刊号 ランドマークはこれだ! 局所解剖アトラス〔特別付録Web動画〕
96巻4号(2024年4月発行)
特集 頭頸部がん診療のControversy
96巻3号(2024年3月発行)
特集 顔面神経麻痺—治癒への10の鍵
96巻2号(2024年2月発行)
特集 実践! 花粉症治療マニュアル2024
96巻1号(2024年1月発行)
特集 伝音難聴を克服する 一歩進んだ診断と手術・人工聴覚器の適応の見極め
95巻13号(2023年12月発行)
特集 めざせ! 一歩進んだ周術期管理
95巻12号(2023年11月発行)
特集 嚥下障害の手術を極める! プロに学ぶコツとトラブルシューティング〔特別付録Web動画〕
95巻11号(2023年10月発行)
特集 必見! エキスパートの頸部郭清術〔特別付録Web動画〕
95巻10号(2023年9月発行)
特集 達人にきく! 厄介なめまいへの対応法
95巻9号(2023年8月発行)
特集 小児の耳鼻咽喉・頭頸部手術—保護者への説明のコツから術中・術後の注意点まで〔特別付録Web動画〕
95巻8号(2023年7月発行)
特集 真菌症—知っておきたい診療のポイント
95巻7号(2023年6月発行)
特集 最新版 見てわかる! 喉頭・咽頭に対する経口手術〔特別付録Web動画〕
95巻6号(2023年5月発行)
特集 神経の扱い方をマスターする—術中の確実な温存と再建
95巻5号(2023年4月発行)
増刊号 豊富な処方例でポイント解説! 耳鼻咽喉科・頭頸部外科処方マニュアル
95巻4号(2023年4月発行)
特集 睡眠時無呼吸症候群の診療エッセンシャル
95巻3号(2023年3月発行)
特集 内視鏡所見カラーアトラス—見極めポイントはここだ!
95巻2号(2023年2月発行)
特集 アレルギー疾患を広く深く診る
95巻1号(2023年1月発行)
特集 どこまで読める? MRI典型所見アトラス
94巻13号(2022年12月発行)
特集 見逃すな!緊急手術症例—いつ・どのように手術適応を見極めるか
94巻12号(2022年11月発行)
特集 この1冊でわかる遺伝学的検査—基礎知識と臨床応用
94巻11号(2022年10月発行)
特集 ここが変わった! 頭頸部癌診療ガイドライン2022
94巻10号(2022年9月発行)
特集 真珠腫まるわかり! あなたの疑問にお答えします
94巻9号(2022年8月発行)
特集 帰しちゃいけない! 外来診療のピットフォール
94巻8号(2022年7月発行)
特集 ウイルス感染症に強くなる!—予防・診断・治療のポイント
94巻7号(2022年6月発行)
特集 この1冊ですべてがわかる 頭頸部がんの支持療法と緩和ケア
94巻6号(2022年5月発行)
特集 外来診療のテクニック—匠に学ぶプロのコツ
94巻5号(2022年4月発行)
増刊号 結果の読み方がよくわかる! 耳鼻咽喉科検査ガイド
94巻4号(2022年4月発行)
特集 CT典型所見アトラス—まずはここを診る!
94巻3号(2022年3月発行)
特集 中耳・側頭骨手術のスキルアップ—耳科手術指導医をめざして!〔特別付録Web動画〕
94巻2号(2022年2月発行)
特集 鼻副鼻腔・頭蓋底手術のスキルアップ—鼻科手術指導医をめざして!〔特別付録Web動画〕
94巻1号(2022年1月発行)
特集 新たに薬事承認・保険収載された薬剤・医療資材・治療法ガイド
93巻13号(2021年12月発行)
特集 頭頸部の再建をマスターする!〔特別付録Web動画〕
93巻12号(2021年11月発行)
特集 必読!メニエール病の新分類とその周辺疾患
93巻11号(2021年10月発行)
特集 手術道具・材料はこう使う!—プロに学ぶ基本とコツ〔特別付録Web動画〕
93巻10号(2021年9月発行)
特集 知っておきたい 効果的なリハビリテーション〔特別付録Web動画〕
93巻9号(2021年8月発行)
特集 副腎皮質ステロイド—どこに注意し,どう使う?
93巻8号(2021年7月発行)
特集 小児難聴を究める!
93巻7号(2021年6月発行)
特集 必見!頭頸部がんのあたらしい治療
93巻6号(2021年5月発行)
特集 遠隔医療の“いま”と“これから”〔特別付録Web動画〕
93巻5号(2021年4月発行)
増刊号 術前画像と術中解剖—カンファレンスで突っ込まれないための知識〔特別付録Web動画〕
93巻4号(2021年4月発行)
特集 あたらしい聴覚・平衡機能検査の見方と臨床応用
93巻3号(2021年3月発行)
特集 カラーアトラス 基本から学ぶ病理組織の見方
93巻2号(2021年2月発行)
特集 新型コロナウイルス感染症—備え,守り,治す
93巻1号(2021年1月発行)
特集 好酸球性副鼻腔炎up-to-date—病態解明と最適な治療をめざして
92巻13号(2020年12月発行)
特集 カラー術中写真でよくわかる 達人による頭頸部がん拡大切除
92巻12号(2020年11月発行)
特集 漢方医学入門—耳鼻咽喉科で漢方薬を使いこなす
92巻11号(2020年10月発行)
特集 Voiceを診る—音声障害を知ろう!〔特別付録Web動画〕
92巻10号(2020年9月発行)
特集 今さら聞けない自己免疫疾患の基礎知識
92巻9号(2020年8月発行)
特集 唾液腺腫瘍の診療最前線
92巻8号(2020年7月発行)
特集 エキスパートに学ぶ手術記録の描き方
92巻7号(2020年6月発行)
特集 耳鼻咽喉科領域の外傷を診る!—初期対応から根治療法まで
92巻6号(2020年5月発行)
特集 高齢者のめまいを治す
92巻5号(2020年4月発行)
増刊号 フローチャートと検査一覧で ひと目でわかる耳鼻咽喉科診療
92巻4号(2020年4月発行)
特集 耳鼻咽喉科医が知っておくべきワクチン医療
92巻3号(2020年3月発行)
特集 頸部エコーを使いこなす—描出のコツと所見の読み方〔特別付録web動画〕
92巻2号(2020年2月発行)
特集 カラーアトラス 口腔・咽頭粘膜疾患—目で見て覚える鑑別ポイント
92巻1号(2020年1月発行)
特集 補聴器と人工聴覚器の最前線2020
91巻13号(2019年12月発行)
特集 舌がん・口腔がん治療の最前線〔特別付録web動画〕
91巻12号(2019年11月発行)
特集 診療で役に立つ味覚・嗅覚障害の知識
91巻11号(2019年10月発行)
特集 進化する経外耳道的内視鏡下耳科手術(TEES)—エキスパートに学ぶスタンダードな手術手技〔特別付録web動画〕
91巻10号(2019年9月発行)
特集 嚥下障害を診る!—プロに学ぶ実践スキル
91巻9号(2019年8月発行)
特集 内視鏡下鼻副鼻腔手術—エキスパートに学ぶスタンダードな手術手技(特別付録web動画)
91巻8号(2019年7月発行)
特集 耳管診療の手引き—基本から最新治療まで
91巻7号(2019年6月発行)
特集 甲状腺腫瘍の診療最前線
91巻6号(2019年5月発行)
特集 細菌感染に立ち向かう—抗菌薬使用の新常識
91巻5号(2019年4月発行)
増刊号 救急・当直マニュアル—いざというときの対応法
91巻4号(2019年4月発行)
特集 初診時に必要十分な 問診・検査オーダー虎の巻
91巻3号(2019年3月発行)
特集 一側性難聴の現状とその対応
91巻2号(2019年2月発行)
特集 ここまできた! 頭頸部希少癌の治療戦略
91巻1号(2019年1月発行)
特集 役に立つ! アレルギー診療の最新情報
90巻13号(2018年12月発行)
特集 扁桃診療最前線—扁桃を取り巻く諸問題
90巻12号(2018年11月発行)
特集 見逃してはならない耳鼻咽喉科疾患—こんな症例には要注意!
90巻11号(2018年10月発行)
特集 今さら聞けないかぜ診療のABC
90巻10号(2018年9月発行)
特集 どこが変わった頭頸部癌診療ガイドライン
90巻9号(2018年8月発行)
特集 知っておきたい顎顔面形成外科の知識
90巻8号(2018年7月発行)
特集 知っておきたい遺伝学的検査と遺伝外来ABC
90巻7号(2018年6月発行)
特集 知っておきたい麻酔の知識
90巻6号(2018年5月発行)
特集 目からウロコ 内視鏡時代の臨床解剖
90巻5号(2018年4月発行)
増刊号 患者・家族への説明ガイド—正しく伝え,納得を引き出し,判断を促すために
90巻4号(2018年4月発行)
特集 基本診察・処置・手術のABC
90巻3号(2018年3月発行)
特集 頭頸部癌に対する薬物療法—最新情報
90巻2号(2018年2月発行)
特集② 知っておきたい眼科疾患の知識
90巻1号(2018年1月発行)
特集 こんなときどうする? 術中・術後のトラブル対応
89巻13号(2017年12月発行)
特集 どこが変わった頭頸部がんTNM分類
89巻12号(2017年11月発行)
特集 知っておきたい難治性副鼻腔疾患の診療
89巻11号(2017年10月発行)
特集② 知っておきたい耳鼻咽喉科の在宅医療
89巻10号(2017年9月発行)
特集 レーザー治療の最前線—コツとピットフォール
89巻9号(2017年8月発行)
特集 自宅でできるリハビリテーションのレシピ
89巻8号(2017年7月発行)
特集 ここが知りたい! 高齢化時代の頭頸部がん診療
89巻7号(2017年6月発行)
特集 耳鼻咽喉科で診る睡眠障害
89巻6号(2017年5月発行)
特集 抗菌薬を使いこなす
89巻5号(2017年4月発行)
増刊号 臨床力UP! 耳鼻咽喉科検査マニュアル
89巻4号(2017年4月発行)
特集 内視鏡手術の上達ポイント
89巻3号(2017年3月発行)
特集 女性と耳鼻咽喉科—診療のポイント
89巻2号(2017年2月発行)
特集 こどもの上手な診かた
89巻1号(2017年1月発行)
特集 めまい診療のNew Trend
88巻13号(2016年12月発行)
特集 聴神経腫瘍診療のNew Concept
88巻12号(2016年11月発行)
特集 外来に必須! 外用薬の上手な使い方
88巻11号(2016年10月発行)
特集 頸部郭清術のNew Concept
88巻10号(2016年9月発行)
特集 外リンパ瘻診療の新しい展開
88巻9号(2016年8月発行)
特集 頸部腫瘤を見極める
88巻8号(2016年7月発行)
特集 もう困らない! 異物摘出マニュアル
88巻7号(2016年6月発行)
特集 顔面神経麻痺—新たな展開
88巻6号(2016年5月発行)
特集 いまさら聞けない聴覚検査のABC
88巻5号(2016年4月発行)
増刊号 耳鼻咽喉科処方マニュアル
88巻4号(2016年4月発行)
特集 嚥下障害の完全マスター
88巻3号(2016年3月発行)
特集 新しい指定難病制度を理解する
88巻2号(2016年2月発行)
特集② がん免疫療法のブレイクスルー—免疫チェックポイント阻害薬
88巻1号(2016年1月発行)
特集 小児の中耳炎を究める
87巻13号(2015年12月発行)
特集 漢方薬を使いこなす
87巻12号(2015年11月発行)
特集 これだけは知っておこう—鼻出血への対応法
87巻11号(2015年10月発行)
特集 心へのアプローチ—心療耳鼻咽喉科外来
87巻10号(2015年9月発行)
特集 長引く咳を診る
87巻9号(2015年8月発行)
特集② 今また結核を見直す
87巻8号(2015年7月発行)
特集② 味と味覚障害の最前線
87巻7号(2015年6月発行)
特集 All about頭頸部再建—多彩な皮弁を使いこなす!
87巻6号(2015年5月発行)
特集 注意すべき真菌症診療の落とし穴
87巻5号(2015年4月発行)
増刊号 こんなときの対応法がわかる 耳鼻咽喉科手術ガイド
87巻4号(2015年4月発行)
特集 最新の補聴器診療—補聴器による聴覚リハビリテーション
87巻3号(2015年3月発行)
特集 痛みの鑑別診断
87巻2号(2015年2月発行)
特集 膿瘍—マネジメントとピットフォール
87巻1号(2015年1月発行)
特集 新しい治療機器
86巻13号(2014年12月発行)
特集 口腔粘膜の難治疾患への対応法
86巻12号(2014年11月発行)
特集② 創管理の最前線—知っておきたい形成外科の知識
86巻11号(2014年10月発行)
特集 インフルエンザ
86巻10号(2014年9月発行)
特集 咽頭癌・頸部食道癌の治療戦略Update
86巻9号(2014年8月発行)
特集 前庭機能検査の新展開
86巻8号(2014年7月発行)
特集② 緩和医療・支持療法を知る
86巻7号(2014年6月発行)
特集 鼻副鼻腔内視鏡手術Update
86巻6号(2014年5月発行)
特集② 歯科口腔外科の話題
86巻5号(2014年4月発行)
増刊号 画像診断パーフェクトガイド―読影のポイントとピットフォール
86巻4号(2014年4月発行)
特集 音声外科Update
86巻3号(2014年3月発行)
特集② 知っておきたい血液内科の知識―専門医の診方・治し方
86巻2号(2014年2月発行)
特集 小児難聴Update
86巻1号(2014年1月発行)
特集 耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の最新トピックス
85巻13号(2013年12月発行)
特集 耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域疾患の最新疫学
85巻12号(2013年11月発行)
特集② 耳鼻咽喉科領域のジェネリック医薬品とサプリメント
85巻11号(2013年10月発行)
特集 帰してはいけない耳鼻咽喉科外来患者
85巻10号(2013年9月発行)
特集② 知っておきたい消化器疾患の知識―専門医の診方・治し方
85巻9号(2013年8月発行)
特集 局所副腎皮質ステロイドの正しい使い方
85巻8号(2013年7月発行)
特集② 知っておきたい呼吸器疾患―専門医の診方・治し方
85巻7号(2013年6月発行)
特集 分子標的薬時代の耳鼻咽喉科診療―処方するとき,服用患者を診るときのポイント
85巻6号(2013年5月発行)
特集② 知っておきたい神経内科の知識―専門医の診方・治し方
85巻5号(2013年4月発行)
特集 急患・急変対応マニュアル―そのとき必要な処置と処方
85巻4号(2013年4月発行)
特集 身につけたいリハビリテーションの最新スキル
85巻3号(2013年3月発行)
特集② コーンビームCT活用法
85巻2号(2013年2月発行)
特集 ここまでできる外来手術
85巻1号(2013年1月発行)
特集 花粉症の治療―新たな展開
84巻13号(2012年12月発行)
特集 メニエール病Update
84巻12号(2012年11月発行)
特集② 知っておきたい小児科の知識―専門医の診方・治し方
84巻11号(2012年10月発行)
特集 扁桃とアデノイドUpdate
84巻10号(2012年9月発行)
特集② 知っておきたい眼科の知識―専門医の診方・治し方
84巻9号(2012年8月発行)
特集 HPV・EBVと頭頸部腫瘍
84巻8号(2012年7月発行)
特集 耳鼻咽喉科領域のアンチエイジング
84巻7号(2012年6月発行)
特集 診療ガイドラインのエッセンスとその活用法
84巻6号(2012年5月発行)
特集 耳鼻咽喉科手術におけるナビゲーションとモニタリング
84巻5号(2012年4月発行)
特集 最新の診療NAVI―日常診療必携
84巻4号(2012年4月発行)
特集 最新の漢方診療
84巻3号(2012年3月発行)
特集 知っておきたい精神神経科の知識―専門医の診方・治し方
84巻2号(2012年2月発行)
特集 ワクチン
84巻1号(2012年1月発行)
特集 日常診療で遭遇するトラブルへの対応
83巻13号(2011年12月発行)
特集 治りにくい症状への対応
83巻12号(2011年11月発行)
特集 知っておきたい皮膚科の知識―専門医の診方・治し方
83巻11号(2011年10月発行)
特集 こんなときどうする?―鼻科手術編
83巻10号(2011年9月発行)
特集 これを読めばPETがわかる
83巻9号(2011年8月発行)
特集 こんなときどうする?―耳科手術編
83巻8号(2011年7月発行)
特集 知っておきたい唾液腺疾患
83巻7号(2011年6月発行)
特集 こんなときどうする?―頭頸部外科編
83巻6号(2011年5月発行)
特集 最新技術―補聴器と人工中耳・人工内耳
83巻5号(2011年4月発行)
特集 耳鼻咽喉科感染症の完全マスター
83巻4号(2011年4月発行)
特集 特殊疾患への対応
83巻3号(2011年3月発行)
特集 耳鼻咽喉科専門研修をはじめる医師へ―疼痛への対応
83巻2号(2011年2月発行)
特集 診療所における工夫―私はこうしている
83巻1号(2011年1月発行)
特集 めまい―最新のトピックス
82巻13号(2010年12月発行)
特集 耳鼻咽喉科における心因性疾患とその対応
82巻12号(2010年11月発行)
特集 耳鼻咽喉科専門研修をはじめる医師へ―書類作成と留意点
82巻11号(2010年10月発行)
特集 表在癌の新しい対応
82巻10号(2010年9月発行)
特集 好酸球関連の病変
82巻9号(2010年8月発行)
82巻8号(2010年7月発行)
82巻7号(2010年6月発行)
特集 耳鼻咽喉科領域と感染症
82巻6号(2010年5月発行)
特集 耳鼻咽喉科領域の術後機能評価
82巻5号(2010年4月発行)
特集 耳鼻咽喉科・頭頸部外科の検査マニュアル―方法・結果とその解釈
82巻4号(2010年4月発行)
82巻3号(2010年3月発行)
特集 診療ガイドライン・診療の手引き概要
82巻2号(2010年2月発行)
82巻1号(2010年1月発行)
特集 急性感音難聴の取り扱い
81巻13号(2009年12月発行)
特集 耳鼻咽喉科専門研修をはじめる医師へ―知っておきたい臨床解剖
81巻12号(2009年11月発行)
特集 耳鼻咽喉科専門研修をはじめる医師へ―外来手技とインシデント・アクシデント
81巻11号(2009年10月発行)
特集 聴覚障害を生じる薬物
81巻10号(2009年9月発行)
特集 放射線治療における有害事象
81巻9号(2009年8月発行)
81巻8号(2009年7月発行)
81巻7号(2009年6月発行)
特集 最近の頭頸部癌治療
81巻6号(2009年5月発行)
特集 リスクマネジメント
81巻5号(2009年4月発行)
特集 頭頸部再建外科―日常臨床から理論まで
81巻4号(2009年4月発行)
特集 耳鼻咽喉科とチーム医療の実践(3)
81巻3号(2009年3月発行)
特集 診療所で必要な救急処置
81巻2号(2009年2月発行)
81巻1号(2009年1月発行)
特集 耳鼻咽喉科とチーム医療の実践(2)糖尿病合併者のステロイド療法
80巻13号(2008年12月発行)
特集 聴神経腫瘍の治療:症例呈示と治療原則
80巻12号(2008年11月発行)
特集 耳鼻咽喉科とチーム医療の実践(1)小児難聴児への対応
80巻11号(2008年10月発行)
80巻10号(2008年9月発行)
特集 耳鼻咽喉科専門研修をはじめる医師へ―疾患とその処方例
80巻9号(2008年8月発行)
80巻8号(2008年7月発行)
特集 嚥下障害手術のコツ
80巻7号(2008年6月発行)
80巻6号(2008年5月発行)
80巻5号(2008年4月発行)
特集 オフィスサージャリー・ショートステイサージャリー
80巻4号(2008年4月発行)
特集 女性と耳鼻咽喉科疾患
80巻3号(2008年3月発行)
80巻2号(2008年2月発行)
80巻1号(2008年1月発行)
特集 耳鼻咽喉科専門研修をはじめる医師へ―症例報告発表・論文執筆のコツ,注意点
79巻13号(2007年12月発行)
特集 耳鼻咽喉科専門研修をはじめる医師へ―外来処置,手術のコツ,注意点
79巻12号(2007年11月発行)
79巻11号(2007年10月発行)
特集 地域医療との共生―術後処置の依頼と紹介
79巻10号(2007年9月発行)
79巻9号(2007年8月発行)
特集 耳鼻咽喉科関連の資格等の取得について
79巻8号(2007年7月発行)
79巻7号(2007年6月発行)
特集 新生児聴覚検診の役割
79巻6号(2007年5月発行)
79巻5号(2007年4月発行)
特集 耳鼻咽喉科・頭頸部外科のリハビリテーション―症例を中心に
79巻4号(2007年4月発行)
特集 耳鼻咽喉科領域の真菌感染の治療
79巻3号(2007年3月発行)
79巻2号(2007年2月発行)
特集 抗菌薬のファースト・チョイス
79巻1号(2007年1月発行)
特集 頭頸部領域の温度外傷・化学的腐食の取り扱い
78巻13号(2006年12月発行)
特集 耳鼻咽喉科専門研修をはじめる医師へ―手術手技とコツ
78巻12号(2006年11月発行)
78巻11号(2006年10月発行)
特集 スポーツと耳鼻咽喉科疾患
78巻10号(2006年9月発行)
78巻9号(2006年8月発行)
特集 耳鼻咽喉科疾患と高齢者(65歳以上)への対応
78巻8号(2006年7月発行)
78巻7号(2006年6月発行)
特集 知っておきたい耳鼻咽喉科疾患の病理
78巻6号(2006年5月発行)
78巻5号(2006年4月発行)
78巻4号(2006年4月発行)
特集 甲状腺疾患の診断と治療
78巻3号(2006年3月発行)
特集 突発性難聴の今
78巻2号(2006年2月発行)
特集 耳鼻咽喉科領域の疼痛
78巻1号(2006年1月発行)
特集 耳鼻咽喉科とウイルス
77巻13号(2005年12月発行)
77巻12号(2005年11月発行)
特集 耳管機能検査
77巻11号(2005年10月発行)
特集 副鼻腔炎
77巻10号(2005年9月発行)
特集 嗄声の診断と治療
77巻9号(2005年8月発行)
77巻8号(2005年7月発行)
特集 頸部リンパ節腫脹
77巻7号(2005年6月発行)
特集 補聴器に関する最近の変化
77巻6号(2005年5月発行)
特集 囊胞性疾患
77巻5号(2005年4月発行)
特集 聴力改善手術
77巻4号(2005年4月発行)
特集 耳鼻咽喉科領域の異物とその摘出法
77巻3号(2005年3月発行)
特集 味覚・嗅覚障害
77巻2号(2005年2月発行)
77巻1号(2005年1月発行)
特集 顔面神経麻痺
76巻13号(2004年12月発行)
特集 耳鼻咽喉科・頭頸部外科の癌化学療法レジメン
76巻12号(2004年11月発行)
76巻11号(2004年10月発行)
76巻10号(2004年9月発行)
特集 頭頸部癌の治療指針―私たちはこうしている―
76巻9号(2004年8月発行)
特集 頭頸部癌の治療指針―私たちはこうしている―
76巻8号(2004年7月発行)
特集 頭頸部癌の治療指針―私たちはこうしている―
76巻7号(2004年6月発行)
特集 頭頸部癌の治療指針―私たちはこうしている―
76巻6号(2004年5月発行)
特集 頭頸部癌の治療指針―私たちはこうしている―
76巻5号(2004年4月発行)
特集 上気道アレルギーを診る
76巻4号(2004年4月発行)
特集 画像・動画の保存とプレゼンテーション
76巻3号(2004年3月発行)
特集 好酸球性中耳炎
76巻2号(2004年2月発行)
特集 人工聴覚手術の現況
76巻1号(2004年1月発行)
75巻13号(2003年12月発行)
特集 電子カルテの現在と将来
75巻12号(2003年11月発行)
75巻11号(2003年10月発行)
特集 耳鼻咽喉科・頭頸部外科におけるナビゲーション手術
75巻10号(2003年9月発行)
75巻9号(2003年8月発行)
特集 いびきの治療
75巻8号(2003年7月発行)
特集 耳鼻咽喉科領域の皮膚・粘膜疾患
75巻7号(2003年6月発行)
75巻6号(2003年5月発行)
75巻5号(2003年4月発行)
特集 耳鼻咽喉科・頭頸部外科の機能検査―何がどこまでわかるか―
75巻4号(2003年4月発行)
75巻3号(2003年3月発行)
75巻2号(2003年2月発行)
特集 薬物による聴覚障害
75巻1号(2003年1月発行)
74巻13号(2002年12月発行)
特集 身体障害者福祉法と耳鼻咽喉科
74巻12号(2002年11月発行)
特集 急性感音難聴
74巻11号(2002年10月発行)
特集 小児の人工内耳
74巻10号(2002年9月発行)
74巻9号(2002年8月発行)
特集 難治性副鼻腔炎の治療
74巻8号(2002年7月発行)
74巻7号(2002年6月発行)
74巻6号(2002年5月発行)
特集 私のクリニック
74巻5号(2002年4月発行)
特集 耳鼻咽喉科・頭頸部外科における手術の危険度
74巻4号(2002年4月発行)
74巻3号(2002年3月発行)
74巻2号(2002年2月発行)
トピックス めまいの治療
74巻1号(2002年1月発行)
トピックス 院内感染の現況とその取り扱い
73巻13号(2001年12月発行)
73巻12号(2001年11月発行)
トピックス 心身医学と耳鼻咽喉科
73巻11号(2001年10月発行)
73巻10号(2001年9月発行)
トピックス 嚥下障害
73巻9号(2001年8月発行)
73巻8号(2001年7月発行)
73巻7号(2001年6月発行)
73巻6号(2001年5月発行)
トピックス 耳鼻咽喉科・頭頸部外科と遺伝子解析
73巻5号(2001年4月発行)
特集 耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の新しい器械,器具
73巻4号(2001年4月発行)
トピックス クリニカルパスとその周辺
73巻3号(2001年3月発行)
73巻2号(2001年2月発行)
トピックス 今話題の花粉症
73巻1号(2001年1月発行)
72巻13号(2000年12月発行)
72巻12号(2000年11月発行)
トピックス 補聴器とその適合
72巻11号(2000年10月発行)
トピックス 耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域のレーザー治療—その適応と成績
72巻10号(2000年9月発行)
72巻9号(2000年8月発行)
72巻8号(2000年7月発行)
72巻7号(2000年6月発行)
72巻6号(2000年5月発行)
72巻5号(2000年4月発行)
特集 全身疾患と耳鼻咽喉科
72巻4号(2000年4月発行)
72巻3号(2000年3月発行)
トピックス 結核と耳鼻咽喉科
72巻2号(2000年2月発行)
72巻1号(2000年1月発行)
トピックス 耳鼻咽喉科と奇形
71巻13号(1999年12月発行)
71巻12号(1999年11月発行)
トピックス ことばの障害と耳鼻咽喉科
71巻11号(1999年10月発行)
71巻10号(1999年9月発行)
トピックス めまい—私の考え方
71巻9号(1999年8月発行)
71巻8号(1999年7月発行)
71巻7号(1999年6月発行)
71巻6号(1999年5月発行)
71巻5号(1999年4月発行)
特集 再建外科
71巻4号(1999年4月発行)
71巻3号(1999年3月発行)
71巻2号(1999年2月発行)
71巻1号(1999年1月発行)
70巻13号(1998年12月発行)
70巻12号(1998年11月発行)
トピックス 頭頸部癌—私の治療方針と成績(その3)
70巻11号(1998年10月発行)
70巻10号(1998年9月発行)
トピックス 頭頸部癌—私の治療方針と成績(その2)
70巻9号(1998年8月発行)
70巻8号(1998年7月発行)
トピックス 頭頸部癌—私の治療方針と成績(その1)
70巻7号(1998年6月発行)
70巻6号(1998年5月発行)
トピックス ベル麻痺の診断と治療—最近の知見
70巻5号(1998年4月発行)
特集 高齢者の耳鼻咽喉科・頭頸部疾患—治療とリハビリのてびき
70巻4号(1998年4月発行)
70巻3号(1998年3月発行)
70巻2号(1998年2月発行)
70巻1号(1998年1月発行)
69巻13号(1997年12月発行)
69巻12号(1997年11月発行)
トピックス 頭頸部領域の乳頭腫—その基礎と臨床
69巻11号(1997年10月発行)
69巻10号(1997年9月発行)
トピックス 鼻アレルギーの診断と治療—最近の知見
69巻9号(1997年8月発行)
69巻8号(1997年7月発行)
69巻7号(1997年6月発行)
69巻6号(1997年5月発行)
特集 外傷と耳鼻咽喉科
69巻5号(1997年5月発行)
69巻4号(1997年4月発行)
69巻3号(1997年3月発行)
69巻2号(1997年2月発行)
トピックス 口腔疾患の診断と治療
69巻1号(1997年1月発行)
68巻13号(1996年12月発行)
68巻12号(1996年11月発行)
68巻11号(1996年10月発行)
特集 耳鼻咽喉科・頭頸部外科手術マニュアル—私の方法
68巻10号(1996年10月発行)
68巻9号(1996年9月発行)
68巻8号(1996年8月発行)
トピックス 聴神経腫瘍
68巻7号(1996年7月発行)
68巻6号(1996年6月発行)
68巻5号(1996年5月発行)
68巻4号(1996年4月発行)
68巻3号(1996年3月発行)
68巻2号(1996年2月発行)
68巻1号(1996年1月発行)
67巻13号(1995年12月発行)
67巻11号(1995年11月発行)
特集 耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の画像診断
67巻12号(1995年11月発行)
67巻10号(1995年10月発行)
トピックス ウェゲナー肉芽腫症の診断と治療
67巻9号(1995年9月発行)
67巻8号(1995年8月発行)
67巻7号(1995年7月発行)
トピックス 下咽頭・頸部食道癌の治療とその成績
67巻6号(1995年6月発行)
67巻5号(1995年5月発行)
67巻4号(1995年4月発行)
67巻3号(1995年3月発行)
トピックス 日帰り手術
67巻2号(1995年2月発行)
67巻1号(1995年1月発行)
トピックス 耳鼻咽喉・頭頸部領域のスポーツ外傷
66巻13号(1994年12月発行)
66巻12号(1994年11月発行)
トピックス メディカルフォトテクニック
66巻11号(1994年10月発行)
特集 耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域 腫脹の診断
66巻10号(1994年10月発行)
66巻9号(1994年9月発行)
トピックス 耳鼻咽喉科領域の真菌症—診断と治療
66巻8号(1994年8月発行)
66巻7号(1994年7月発行)
66巻6号(1994年6月発行)
トピックス 耳管機能とその評価
66巻5号(1994年5月発行)
66巻4号(1994年4月発行)
66巻3号(1994年3月発行)
トピックス 頭頸部領域の悪性リンパ腫
66巻2号(1994年2月発行)
66巻1号(1994年1月発行)
65巻13号(1993年12月発行)
65巻12号(1993年11月発行)
65巻11号(1993年10月発行)
特集 耳鼻咽喉科の機能検査マニュアル
65巻10号(1993年10月発行)
65巻9号(1993年9月発行)
65巻8号(1993年8月発行)
65巻7号(1993年7月発行)
トピックス 耳鼻咽喉科とリハビリテーション
65巻6号(1993年6月発行)
65巻5号(1993年5月発行)
65巻4号(1993年4月発行)
65巻3号(1993年3月発行)
トピックス 耳鼻咽喉頭頸部領域の自己免疫疾患—最近の知見
65巻2号(1993年2月発行)
65巻1号(1993年1月発行)
トピックス 環境と耳鼻咽喉科
64巻13号(1992年12月発行)
トピックス メニエール病の診断と治療
64巻12号(1992年11月発行)
64巻10号(1992年10月発行)
トピックス 内視鏡による診療・最近の進歩
64巻11号(1992年10月発行)
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 症候群事典
64巻9号(1992年9月発行)
64巻8号(1992年8月発行)
トピックス 耳小骨連鎖再建術
64巻7号(1992年7月発行)
64巻6号(1992年6月発行)
64巻5号(1992年5月発行)
トピックス 補聴器の処方
64巻4号(1992年4月発行)
トピックス 頸部腫瘤の穿刺吸引細胞診
64巻3号(1992年3月発行)
64巻2号(1992年2月発行)
64巻1号(1992年1月発行)
トピックス 副鼻腔のエアロゾル療法
63巻13号(1991年12月発行)
63巻12号(1991年11月発行)
トピックス 耳鼻咽喉科領域の異物とその除去法
63巻11号(1991年11月発行)
特集 外来診療マニュアル—私はこうしている
63巻10号(1991年10月発行)
63巻9号(1991年9月発行)
63巻8号(1991年8月発行)
トピックス 舌癌の治療
63巻7号(1991年7月発行)
63巻6号(1991年6月発行)
トピックス 耳鼻咽喉科医のための甲状腺疾患
63巻5号(1991年5月発行)
63巻4号(1991年4月発行)
63巻3号(1991年3月発行)
トピックス 高齢者と耳鼻咽喉科・愁訴と対応
63巻2号(1991年2月発行)
63巻1号(1991年1月発行)
62巻13号(1990年12月発行)
トピックス 鼻茸
62巻12号(1990年11月発行)
トピックス 聴力改善手術
62巻11号(1990年10月発行)
トピックス 心因性難聴
62巻10号(1990年10月発行)
症例特集 頭頸部腫瘍
62巻9号(1990年9月発行)
トピックス 嗅覚障害
62巻8号(1990年8月発行)
トピックス 小児副鼻腔炎
62巻7号(1990年7月発行)
トピックス 顔面神経麻痺
62巻6号(1990年6月発行)
トピックス 人工中耳・人工内耳
62巻5号(1990年5月発行)
トピックス 嚥下障害
62巻4号(1990年4月発行)
トピックス ダニとアレルギー
62巻3号(1990年3月発行)
トピックス 頭頸部癌に対する制癌剤の選択
62巻2号(1990年2月発行)
トピックス 音声外科
62巻1号(1990年1月発行)
トピックス 耳音響放射
