理学療法においてウィメンズヘルス領域,小児領域とそれぞれ発展を遂げるなか,子どもが健やかに産まれ育つ社会をめざすには,各領域をそれぞれ独立した分野ではなく一連の流れとした理学療法の展開を考えていく時期にあると考える.今回,各フェーズにおける現状や課題を把握できるよう,それぞれ先駆的に,他職種とも連携を図りながら取り組みを行ってきた方々にご解説いただいた.多職種連携や地域の実情を踏まえながら子どもと母をつなぎ支え,子どもが健やかに産まれ育つ社会へ理学療法がどのように寄与できるか考えるきっかけにされたい.
雑誌目次
理学療法ジャーナル58巻12号
2024年12月発行
雑誌目次
特集 “子ども”と“母”をつなぎ支える理学療法
—エディトリアル—健やかなる“子ども”と“母”をつなぎ支える理学療法
著者: 沖原優子
ページ範囲:P.1316 - P.1319
はじめに
現代社会において,子どもが“健やか”に産まれ育つためには,妊娠期から出産後,そして成長期に至るまでのすべての段階で包括的な支援が必要である.特に,子どもと母を中心とした家族の健康を支える理学療法の役割は大変重要であり,その専門的なアプローチが求められている.理学療法士は,母と子の健全な発達を促進し,家族全体の福祉向上に寄与するため,こども家庭庁や子育て世代包括支援センターと協力し,地域社会と連携しながらその役割を果たしていく必要がある.小児領域の理学療法,母を支えるウィメンズヘルス領域の理学療法のどちらもさらなる発展を遂げる今,双方をつなぎ,子どもが健やかに産まれ育てることを支える一連の流れとする理学療法として考える機会に本特集がなることを願う.
“子ども”に関する制度と理学療法
著者: 小塚直樹 , 宮城島沙織 , 鎌塚香央里
ページ範囲:P.1320 - P.1326
Point
●子どもと母に関する法と制度は,いくつかの省庁によって規定されてきたが,2023年4月1日に発足したこども家庭庁によって一元化され,以降の子育て環境が整うことが期待される
●小児理学療法に携わる者は,対象となる家族,とりわけ母親の子育てや介護の苦労を十分理解したうえで,家族全体の心身の健康を見守る役割を担い,よき相談相手として寄り添う姿勢が大切である
●子育て世代の理学療法士の就労は,さまざまな社会資源の効果的な活用が肝要であるが,一方で母親に負担が偏らない家族や職場の理解も重要となる
将来の母を支える理学療法—妊娠・産褥期へのかかわり
著者: 春本千保子 , 森憲一
ページ範囲:P.1327 - P.1334
Point
●産前産後における腰痛発症率は約7割に及ぶ.家事や育児のみならず,日常生活に支障を来すケースも少なくない
●妊娠期に共通する身体変化を理解し,姿勢や動作の問題に対する個別の評価と治療が重要である
●わが国では妊娠期マイナートラブルに対する理学療法はいまだ保険適用外である.理学療法士は医師と連携を図り,介入結果を蓄積することが不可欠である
産後の母を支える理学療法
著者: 佐々木聡子
ページ範囲:P.1335 - P.1343
Point
●産後は,身体的変化に伴うさまざまな症状を生じやすい.身体面のみならず精神面へも影響があり,両者は密接にかかわっている
●分娩後,産科での心身状況を共有し,必要に応じた多職種による訪問支援は,母の心身状態の改善を導く一助となっている.多職種での多方面からのかかわりが望まれる
●実際の生活の場(自宅)での母体ケアや育児動作指導は,母にとって理解しやすく習慣化が得られやすい
新生児を支える理学療法
著者: 齋藤悟子
ページ範囲:P.1344 - P.1350
Point
●新生児集中治療室(neonatal intensive care unit:NICU)は子どもと母・父が初めて出会う場である
●子どもの理学療法では養育者も対象者となる
●生まれた子どもの成長発達に合わせて,母のウィメンズヘルス領域と,小児領域の理学療法を切れ目なく一連の流れとして提供するにあたって,それぞれの施設の特性などを知り,垣根を越えて情報を共有することが,理学療法のなかで広義のチーム医療といえる
地域の子どもを支える理学療法
著者: 井上和広
ページ範囲:P.1351 - P.1357
Point
●小児理学療法の対象や重症度,年齢層は幅広く,日常的にかかわる職種や支援場所も,多種多様となってきている
●障害をもつ子どもたちの支援には家族支援と地域連携が重要な位置づけとなる
●家族支援にはfamily-centered careの概念が重要であり,特にライフサイクルに応じたさまざまな情報提供が求められている
助産師の立場から理学療法士に求めるもの—妊産婦と子どもの継続ケア
著者: 山本英子
ページ範囲:P.1358 - P.1364
Point
●妊産婦は,妊娠・出産に伴い身体や社会的役割が大きく変化し,不安やストレスを高めやすい状態にあるため妊娠期からの継続ケア,メンタルヘルス支援が重要である
●専門性を活かした視点で対象者(妊産婦と子ども)を多角的・包括的に捉える
●互いの専門性の理解と尊重のもと,対象者とともにチームで課題・目標を共有し統合されたケアを実践・継続していく
Close-up 理学療法と公衆衛生
公衆衛生に関する理学療法のあるべき姿
著者: 木村朗
ページ範囲:P.1366 - P.1373
はじめに
本邦では,多くの理学療法士が専門職として,けがや病気で体の動きが悪くなった人たちを助けるうえで重要な役割を果たしている.しかし筆者は,理学療法士ができることはそれだけではなく,実はもっと多いと考えている.最近では,理学療法士が「みんなの健康」を守る活動,つまり地域の人々が健康でいるための取り組みにもかかわるべきだという声がこれまで以上に高まっている.
公衆衛生に理学療法士がかかわるために
著者: 小池孝康
ページ範囲:P.1374 - P.1379
はじめに
理学療法士及び作業療法士法に規定される本邦の“理学療法”は,身体に障害のある者に対して医師の指示のもとに行う診療の補助行為であり,医療施設を主体に行う「医学的リハビリテーション」として位置づけられる1,2).一方,国民全体の健康増進,予防施策を強く推進する近年の政策のもと,理学療法士の活動の場は医療施設にとどまらず,地域社会へと拡大している.
このような背景のなか,公衆衛生活動に深くかかわる理学療法士は今後さらに増加することが予想され,従来の理学療法の提供の形である「直接・対個人」に対し,公衆衛生分野では「間接・対集団」へのアプローチが求められる.したがって,理学療法士は法で定める“理学療法”の視点を踏まえつつも,それとは異なる視点や方略を備え,公衆衛生に伴う課題を理解する必要がある.
本稿では,理学療法士が公衆衛生分野でさらなる貢献ができるよう,具体的な役割や業務,アプローチを整理したうえで,公衆衛生に理学療法士がかかわるための課題と展望について概説する.
連載 とびら
大事なことはみーんな患者さんに教わった
著者: 小山田香
ページ範囲:P.1311 - P.1311
理学療法士として働きはじめた35年前,当時サービス残業は当たり前,遅くまで仕事がずれ込んで,記録をこなしつつ夕食が終わるのを待ってから残りの病棟業務に出かけることも多かった.
筋萎縮性側索硬化症の50歳台女性を担当したのは確かまだ1年目.300床クラスの総合病院で神経内科は主な標榜科でもあり,通例となっていた2〜3週間のリハビリテーション目的を兼ねた入院に病棟スタッフは慣れっこらしく,院内に何台もない3モーターのベッドが早々に用意されていた.新米の私は,初めてみる疾患の患者を前に教科書を慌てて繰り直し,学生実習の手順をなぞるのが精一杯だった.
視覚ベースの動作分析・評価・第8回
歩行—歩行観察の結果から膝関節および胸郭機能の改善を図り,歩行時の膝関節痛軽減が得られた症例
著者: 森口晃一
ページ範囲:P.1307 - P.1309
症例紹介
60歳台女性.右変形性膝関節症(Kellgren-Laurence分類Ⅲ).
数年前から正座不可,右膝関節の可動域制限を感じていた.約3か月前から15分以上の歩行で疼痛が出現するようになり,症状が強くなってきたため来院.歩行時の最大の疼痛の程度はNumerical Rating Scale(NRS)で5,右膝関節の可動域は屈曲137°,伸展−20°.
*本論文中,動画マークのある箇所につきましては,関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年12月31日).
運動療法に活かすための神経生理(学)・第6回【最終回】
ADLを改善するために筋緊張異常をどう制御するか?
著者: 後藤淳
ページ範囲:P.1381 - P.1384
筋緊張とは
筋緊張とは,神経生理学的に支配されている筋に,持続的に不随意に生じている筋の一定の緊張のことである1,2).簡単に言えば,骨格筋の硬度や弾力,つまり骨格筋の張り具合いである.筋緊張は,生体の姿勢保持や体温調節に関与し,また,運動あるいは姿勢保持の際に活動する骨格筋の準備状態に重要である.なお,神経学的検査における筋緊張とは,安静背臥位での随意的な活動のない状態における筋緊張3)を示す.
筋緊張の制御は,主に上位運動ニューロン(脊髄〜脳)により行われており,また,固有受容器制御で代表される伸張反射,前庭反射や緊張性頸反射・立ち直り反射などの姿勢反射は,筋緊張の神経生理機構に大きく関与する.
今月の深めたい理学療法周辺用語・第12回【最終回】
ヘルスリテラシー
著者: 中山和弘
ページ範囲:P.1385 - P.1387
ヘルスリテラシーの定義と日本の状況
ヘルスリテラシーとは,健康情報を入手し,理解し,評価し,意思決定するというプロセスを踏むための4つの力である1).意思決定とは2つ以上の選択肢から1つを選ぶことであり,そもそも選択肢がなければ行えない.理学療法においては,主に治療の選択肢に焦点が当たることになる.
ヘルスリテラシーの測定では,一人ひとりの力のみならず,例えそれがなくても意思決定できるような支援が得られる環境にあるかにも注目されている.欧州8か国の調査では,ヘルスリテラシーに困難がある人は約半数を占めたが2),日本でもその割合は約85%と高くなっていた3).さらにアジアの6つの国・地域でも測定され4),平均点(50点満点)を比較すると日本の値はどの国・地域よりも低い状況にあった.
理学療法士のための「money」講座・第12回【最終回】
協会費2万円は無駄なのか—お金よりも大事なもの,自己投資の還元
著者: 細川智也
ページ範囲:P.1389 - P.1392
はじめに
いよいよ,本連載も最終回を迎えることとなりました.1年間にわたり,さまざまな視点からお金について解説してきましたが,最も重要なのは,お金は単なるツールであり,お金の真の価値は「どう活用するか」にかかっているということです.最終回の内容は,「理学療法士協会の年会費は無駄なのか」という辛辣な問いから自己投資の重要性,後半は人生のゴール設定にまで及びます.ぜひ最後までお読みください.
臨床実習サブノート 「どれくらい運動させていいかわからない」をどう克服するか・第9回
—神経・筋疾患—パーキンソン病患者に対する歩行練習
著者: 中山恭秀
ページ範囲:P.1393 - P.1397
パーキンソン病(Parkinson disease:PD)による歩行障害は,特異的姿勢変化の影響を受ける歩容とすくみ足です.医学的情報や機能評価,能力評価をもとに理学療法による改善を検討します.特異的姿勢変化とは,PDの4大徴候である筋固縮症状,無動症状による姿勢の変化です.そして,すくみ足はフローズンゲイト(frozen gait)であり,日常生活における動作困難や転倒,不活動に関与します.臨床の流れをイメージして,それぞれを捉えてみましょう.
My Current Favorite・32
理学療法×産業保健
著者: 松垣竜太郎
ページ範囲:P.1380 - P.1380
現在の関心事は?
現在の私の関心事は「産業保健における理学療法士の役割」です.多くの理学療法士にとって産業保健はまだなじみの薄い分野かもしれません.産業保健とは,働く人々の健康や安全,生産性の向上に寄与する活動を指します.
私のターニングポイント・第59回
ちょっとネガティブなターニングポイント
著者: 東海林淳一
ページ範囲:P.1400 - P.1400
今の職場に就職して27年.転職を考えたり進む方向を大きく変えたりするような大きなターニングポイントは特にないのですが,強いて挙げるなら母の死かなと思います.
理学療法士をめざす前は大学の工学部で勉強していたのですが,部活の友人の影響で医療に興味をもち,医療系の研究をしている研究室に所属し大学院進学も考えました.しかし,臨床の場で働きたいという思いが強くなりこの道を選びました.もともとは終末期の医療に関心があったのですが,学生時代の教官の影響もあり急性期のリハビリテーションに興味をもち今の職場に就職しました.
症例報告
全身の動脈硬化性疾患から経年的帰結として心不全に至り,運動耐容能向上に難渋した1例
著者: 五月女宗史
ページ範囲:P.1401 - P.1406
要旨 動脈硬化は全身的および経時的変化をもたらす疾患であり,全身の重要臓器と関連した合併症をもたらす.今回,冠動脈および下肢血管の閉塞を繰り返し,左下肢閉塞性動脈硬化症に血行再建術を施行した術後理学療法と,その1年3か月後に心不全にて再入院となり理学療法を行った経験を得た.下肢血行再建術後の理学療法では,下肢血行動態および下肢運動機能は改善したが,虚血を有する低心機能が露呈した.運動療法および患者教育を行い自宅退院となったが,アドヒアランスが低下していたため,経年的帰結として心不全となり再入院となった.理学療法を再開しADLは改善したが,運動耐容能の低下を認め,心血管系だけでなく骨格筋系と呼吸器系の重度機能低下が考えられた.重度の動脈硬化に起因する心血管疾患患者の場合,全身の臓器で経時的に病態が進行することを踏まえ,患者の状況を考慮した包括的な理学療法が重要であると考えた.
紹介
多機関からなる大学附属病院の連携を通じた職場内教育体制の創出
著者: 藤田吾郎 , 中村高良 , 樋口謙次 , 高橋仁 , 中山恭秀
ページ範囲:P.1407 - P.1410
はじめに
医療環境は,少子高齢化の進展,医療技術の高度化により急速に変化している.こうした社会情勢に適応する人材の育成は医療機関の重要課題である.理学療法分野においては,2022年に新生涯学習制度が始まるなど,卒後教育の見直しが図られている.その流れを受け,昨今は日本理学療法士協会の広報や関連書誌でも先進的な施設の職場内教育が紹介されている.しかし,その多くは単施設の取り組みがモデルとなっている.そこで本稿では,東京慈恵会医科大学(以下,本学)で推進している多機関連携を活かした職場内教育の一部を紹介する.
学会印象記
—第36回大阪府理学療法学術大会—高め合うワークとライフの実現をめざして
著者: 後藤祐貴
ページ範囲:P.1365 - P.1365
育児休業中の大会長による学会
「ワーク・ライフ・インテグレーション」というテーマのもと,第36回大阪府理学療法学術大会が開催されました.増田先生は本学術大会初の女性大会長であることに加え,準備期間中に妊娠・出産を経て,大会当日も育児休業をとるなかで大会長という任を執られました.育児と仕事の両立,またその支援は日本中でも関心の高いトピックであります.理学療法関連学会において,近年では子育て世代の学びを応援するため,子連れでの参加や同伴者(配偶者・ご両親など)の参加,託児所の開設などが行われています.当日は増田先生も子連れで参加され,まさにワーク・ライフ・インテグレーションを体現されておりました.
—第10回日本呼吸理学療法学会学術大会—呼吸理学療法の新たな展開
著者: 村川勇一
ページ範囲:P.1398 - P.1398
第10回日本呼吸理学療法学会学術大会が瀬崎学大会長(済生会新潟県央基幹病院)のもと,2024年9月7日(土),8日(日)に朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターで開催されました.本学術大会は会場およびwebのハイブリッド形式にて開催され,参加者900名以上と大盛況でした.
本学術大会では,「呼吸理学療法の新たな展開—The first step toward the next decade」をテーマに掲げ,学会シンポジウム,教育講演,一般演題,協賛セミナーといった多くのプログラムが行われました.一般演題においても90演題と全国から多くの演題が集まり,当日には各会場にて活発なディスカッションが行われていました.
臨床のコツ・私の裏ワザ
頸部痛・肩こりが再発しやすい症例の評価・介入のコツ
著者: 上田泰久
ページ範囲:P.1412 - P.1413
頸部痛・肩こりが再発しやすい症例の座位バランス
頸部痛・肩こりは,日本人の労働生産性低下の最大の要因である1).頸部痛・肩こりを有する症例では,後頸部にある軟部組織の滑走不全を認めることが多い.この滑走不全を有する症例に対し,後頸部の軟部組織の滑走を促すと,即時的に症状を緩和させることができる2).
しかし症状を緩和させても,再発する症例も散見する.頸部痛・肩こりが再発しやすい症例の座位バランスの特徴として,体幹の立ち直り反応が出現しにくく,頸部の立ち直り反応で代償し,後頸部の過剰な筋活動を認めることが多い(図1).このような症例では,特に上部体幹(第7〜9胸椎にある上半身質量中心から頸胸移行部まで)の可動域制限を呈しているため,胸郭を含めた上部体幹の可動域について評価・介入することが重要である.
書評
—荒木 秀明(著)—「非特異的腰痛の運動療法[Web動画付] 第2版—病態をフローチャートで鑑別できる」 フリーアクセス
著者: 葉清規
ページ範囲:P.1399 - P.1399
著者の荒木秀明先生は,腰痛に対する臨床と研究に取り組まれる理学療法士として,私が尊敬する先生のお一人です.
腰痛に対する理学療法の方法論は数多く紹介されていますが,医療技術として,理学療法はエビデンスに基づいて行われるものであり,エビデンスの臨床応用として,evidence-based practice(利用可能な最良のエビデンス・医療者の専門性・患者の価値観を統合し,最善の医療を行う)という概念が重要となります.エビデンスとは臨床研究です.研究には,研究を実践する立場と,研究結果を解釈(活用)する立場があります.荒木先生はご自身の臨床データを,国際腰痛学会・国際骨盤痛学会や日本腰痛学会で学会発表されるなど研究を実践しています.しかし,それだけではなく,先生の真骨頂は,臨床疑問の解決に結びつく数多くの先行研究の成果を理解して臨床応用する,「研究結果を解釈する立場」を高いレベルで行われているところにあります.『非特異的腰痛の運動療法 第2版』には,そのエッセンスが盛り込まれています.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1312 - P.1313
雑誌年間購読料改定のお知らせ フリーアクセス
ページ範囲:P.1319 - P.1319
動画配信のお知らせ フリーアクセス
ページ範囲:P.1334 - P.1334
「作業療法ジャーナル」のお知らせ フリーアクセス
ページ範囲:P.1364 - P.1364
お知らせ 第23回日本PNF学会学術集会と演題募集のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1373 - P.1373
第36回「理学療法ジャーナル賞」のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1410 - P.1410
バックナンバー・次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1416 - P.1417
編集後記 フリーアクセス
著者: 細田里南
ページ範囲:P.1418 - P.1418
2024年の締めとなる第58巻第12号をお届けします.
本号は「“子ども”と“母”をつなぎ支える理学療法」を特集としております.われわれの誰もが母から生まれた存在であり,家族や社会に支えられ成長して今ここに居ます.それら成長の糧となるバトンをつなぐ存在の一人として,理学療法士が活躍できることを誇りに思います.これまで身体障害をもつ“子ども”中心に展開されてきた歴史的背景のある理学療法ですが,過去・現在・未来においても,対象の中心であった“子ども”のそばには“母”なる存在があり,その存在を無視して理学療法を展開していくことはできないのではないでしょうか.“子ども”と“母”をつなぐために論じる視点として,さまざまな法と施策に始まり,妊娠・出産にかかわる母体そのものや地域連携を含む“子ども”と“母”へのそれぞれの理学療法の変遷について具体的に紹介されています.さらに,働く女性が母親となった際の働き方に関する課題についても提言されており,ワーキングマザーとして日々奮闘している方々,またそれを支えている方々にも,どのような支援体制が必要かについてもあらためて考える機会になったのではないかと考えます.
読者の声募集 フリーアクセス
ページ範囲:P. - P.
理学療法ジャーナル 第58巻 総目次 フリーアクセス
ページ範囲:P. - P.
基本情報
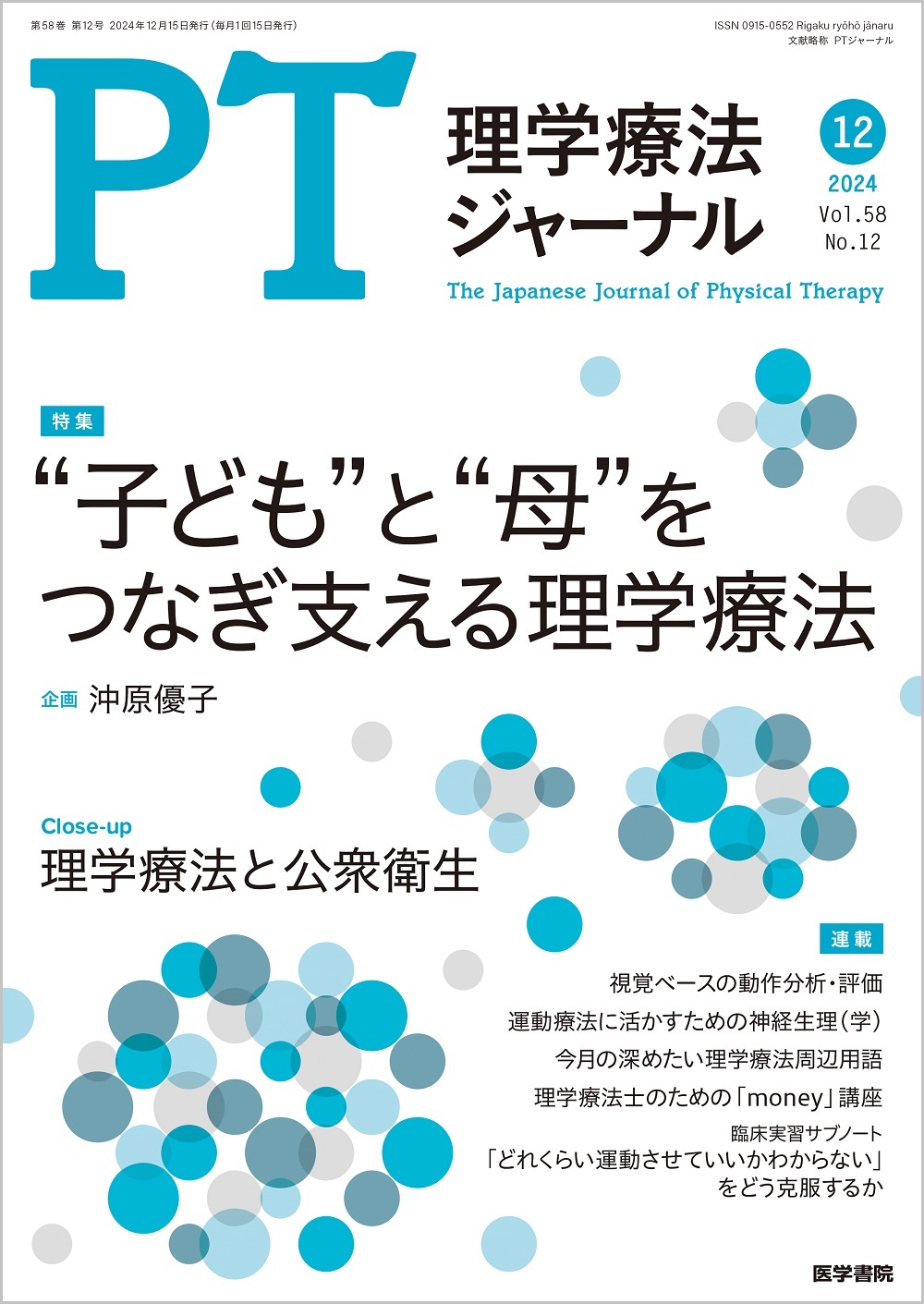
バックナンバー
58巻12号(2024年12月発行)
特集 “子ども”と“母”をつなぎ支える理学療法
58巻11号(2024年11月発行)
特集 Multimorbidity and Multiple Disabilities(MMD)—多疾患重複時代がやってきた!
58巻10号(2024年10月発行)
特集 小脳update—運動と認知
58巻9号(2024年9月発行)
特集 最適な非対称性動作を考える
58巻8号(2024年8月発行)
特集 全身持久力トレーニング
58巻7号(2024年7月発行)
特集 視覚障害を併存する対象者の理学療法を考える
58巻6号(2024年6月発行)
特集 足病—あしを救って機能も救うために
58巻5号(2024年5月発行)
特集 “行為”の回復のための理学療法
58巻4号(2024年4月発行)
特集 DXが理学療法にもたらす未来
58巻3号(2024年3月発行)
特集 骨盤底機能障害と運動器障害の連関
58巻2号(2024年2月発行)
特集 総合理学療法
58巻1号(2024年1月発行)
特集 Physical Activity
57巻12号(2023年12月発行)
特集 疾病・介護予防のための運動療法
57巻11号(2023年11月発行)
特集 ヴィジョン—見えるものと見えないもの
57巻10号(2023年10月発行)
特集 ACP—個人の人生史を尊重し受け入れる
57巻9号(2023年9月発行)
特集 運動器理学療法をどう捉えるか—統合的戦略で自らの思考の枠を乗り越える
57巻8号(2023年8月発行)
特集 睡眠と理学療法の深い関係
57巻7号(2023年7月発行)
特集 腎臓リハビリテーション
57巻6号(2023年6月発行)
特集 脳卒中の予後予測と目標設定
57巻5号(2023年5月発行)
特集 関節間トレードオフ
57巻4号(2023年4月発行)
特集 理学療法の2040年
57巻3号(2023年3月発行)
特集 システムとしての姿勢制御—メカニズムの解明から臨床応用まで
57巻2号(2023年2月発行)
特集 嚥下機能に着目した理学療法
57巻1号(2023年1月発行)
特集 多様化する急性期理学療法
56巻12号(2022年12月発行)
特集 脊椎圧迫骨折に対する理学療法の工夫
56巻11号(2022年11月発行)
特集 回復期リハビリテーション病棟 これからの役割と戦略
56巻10号(2022年10月発行)
特集 子どもの成長・発達を支える理学療法
56巻9号(2022年9月発行)
特集 運動イメージ—科学的根拠に基づく臨床実践をめざして
56巻8号(2022年8月発行)
特集 住まいとくらし—理学療法士の環境づくり
56巻7号(2022年7月発行)
特集 人工関節置換術後の理学療法
56巻6号(2022年6月発行)
特集 医療現場におけるサルコペニア・フレイル
56巻5号(2022年5月発行)
特集 動作分析と臨床のマッチング
56巻4号(2022年4月発行)
特集 臨床に活かすニューロリハビリテーション
56巻3号(2022年3月発行)
特集 筋—理学療法士の視点から捉える
56巻2号(2022年2月発行)
特集 進歩する低侵襲手術に応じた理学療法—治療プログラム,目標設定,リスク管理
56巻1号(2022年1月発行)
特集 機能解剖と理学療法
55巻12号(2021年12月発行)
特集 大腿骨近位部骨折 up to date
55巻11号(2021年11月発行)
特集 パーキンソン病の最新知見と効果的な理学療法
55巻10号(2021年10月発行)
特集 タッチ—触れることと触れられること
55巻9号(2021年9月発行)
特集 チーム医療におけるコラボレーション
55巻8号(2021年8月発行)
特集 がん治療のリアル
55巻7号(2021年7月発行)
特集 移動—理学療法からみた学際的探求
55巻6号(2021年6月発行)
特集 Inner & Intrinsic Muscles—筋による関節の安定化,姿勢調整機能を探る
55巻5号(2021年5月発行)
特集 目標に基づく理学療法のための臨床推論—症状・疾患別の実際
55巻4号(2021年4月発行)
特集 皮神経滑走と運動療法の新知見
55巻3号(2021年3月発行)
特集 重症化予防
55巻2号(2021年2月発行)
特集 関節可動域評価のABC—治療計画につなぐ応用的解釈まで
55巻1号(2021年1月発行)
特集 高齢者の膝関節の痛み
54巻12号(2020年12月発行)
特集 歩行PART 2 運動器疾患と歩行指導
54巻11号(2020年11月発行)
特集 歩行PART 1 脳神経疾患と歩行
54巻10号(2020年10月発行)
特集 疼痛に対する最新の理学療法—治療効果を最大化するための理論と実践
54巻9号(2020年9月発行)
特集 軟部組織に着目した理学療法の最前線
54巻8号(2020年8月発行)
特集 パフォーマンス向上のための筋力トレーニング
54巻7号(2020年7月発行)
特集 脊椎・脊髄疾患の多彩な症状と理学療法
54巻6号(2020年6月発行)
特集 Pusher現象の謎 「傾き」への挑戦—臨床像と治療アプローチ
54巻5号(2020年5月発行)
特集 投球障害を捉える—動作,機能解剖,エコーの活用,予防に対する理学療法士の英知
54巻4号(2020年4月発行)
特集 症例から考える脳幹病変へのアプローチ
54巻3号(2020年3月発行)
特集 地域における予防の効果—理学療法の可能性
54巻2号(2020年2月発行)
特集 薬と運動療法
54巻1号(2020年1月発行)
特集 急性期理学療法の今—育成・働き方・連携・エビデンス
53巻12号(2019年12月発行)
特集 装具の臨床
53巻11号(2019年11月発行)
特集 今と将来を見据えた小児整形外科理学療法
53巻10号(2019年10月発行)
特集 これからの理学療法—2025年以降の姿を見据えて
53巻9号(2019年9月発行)
特集 栄養を学ぶ—学際と実際
53巻8号(2019年8月発行)
特集 IADL—生活をもっと科学的に
53巻7号(2019年7月発行)
特集 脳卒中患者の上肢に対する理学療法up to date
53巻6号(2019年6月発行)
特集 上肢運動器疾患—若年者と中高年者の特徴
53巻5号(2019年5月発行)
特集 全体像を把握する
53巻4号(2019年4月発行)
特集 理学療法士がめざす安心と安全
53巻3号(2019年3月発行)
特集 こころの問題と理学療法
53巻2号(2019年2月発行)
特集 変形性股関節症とメカニカルストレス
53巻1号(2019年1月発行)
特集 高齢者の転倒と予防
52巻12号(2018年12月発行)
特集 退院支援—理学療法士はその先が見えているか
52巻11号(2018年11月発行)
特集 生涯学習—卒前教育との連動と発展性
52巻10号(2018年10月発行)
特集 オリンピック・パラリンピック—世界と向き合うために
52巻9号(2018年9月発行)
特集 バランス再考
52巻8号(2018年8月発行)
特集 ジェネラリストとスペシャリスト
52巻7号(2018年7月発行)
特集 疼痛管理
52巻6号(2018年6月発行)
特集 地域に広がる心臓リハビリテーション
52巻5号(2018年5月発行)
特集 視床出血と理学療法
52巻4号(2018年4月発行)
特集 変形性膝関節症に対する最新の保存療法
52巻3号(2018年3月発行)
特集 理学療法における動作のアセスメント
52巻2号(2018年2月発行)
特集 低栄養/摂食嚥下機能障害と理学療法
52巻1号(2018年1月発行)
特集 筋力低下と理学療法
51巻12号(2017年12月発行)
特集 エキスパートが語る小児理学療法
51巻11号(2017年11月発行)
特集 多分野に広がる理学療法
51巻10号(2017年10月発行)
特集 半側空間無視
51巻9号(2017年9月発行)
特集 ACL損傷と動作
51巻8号(2017年8月発行)
特集 理学療法と臓器連関
51巻7号(2017年7月発行)
特集 理学療法のプロフェッショナルをめざして
51巻6号(2017年6月発行)
特集 理学療法士のはたらき方
51巻5号(2017年5月発行)
特集 歩行の安全性
51巻4号(2017年4月発行)
特集 理学療法と下肢装具
51巻3号(2017年3月発行)
特集 通院・通所における理学療法を再考する
51巻2号(2017年2月発行)
特集 現任研修—求められる臨床技能の習得
51巻1号(2017年1月発行)
特集 多職種で取り組むがん診療と理学療法
50巻12号(2016年12月発行)
特集 地域包括ケア病棟
50巻11号(2016年11月発行)
特集 臨床に役立つ臨床推論の実際
50巻10号(2016年10月発行)
特集 生活支援につなぐ小児理学療法
50巻9号(2016年9月発行)
特集 重症下肢虚血と理学療法
50巻8号(2016年8月発行)
特集 社会の要請に応える理学療法教育
50巻7号(2016年7月発行)
特集 被殻出血と理学療法
50巻6号(2016年6月発行)
特集 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて
50巻5号(2016年5月発行)
特集 運動器疾患—エキスパートはこうみる
50巻4号(2016年4月発行)
特集 理学療法からみた「予防」の取り組みと効果
50巻3号(2016年3月発行)
特集 TENS
50巻2号(2016年2月発行)
特集 最新の糖尿病治療と運動療法
50巻1号(2016年1月発行)
特集3 理学療法の50年に寄せて
49巻12号(2015年12月発行)
特集 理学療法士界における継往開来
49巻11号(2015年11月発行)
特集 地域包括ケアシステムと小児理学療法
49巻10号(2015年10月発行)
特集 歩行支援機器による歩行up to date
49巻9号(2015年9月発行)
特集 脳機能回復と理学療法
49巻8号(2015年8月発行)
特集 地域包括ケアシステムの構築に向けて
49巻7号(2015年7月発行)
特集 慢性期の理学療法—目標設定と治療・介入効果
49巻6号(2015年6月発行)
特集 急性期からの理学療法
49巻5号(2015年5月発行)
特集 頭頸部および肩凝りに対する理学療法
49巻4号(2015年4月発行)
特集 世界の理学療法—激動のAsia Western Pacific地区の現状と今後
49巻3号(2015年3月発行)
特集 大規模災害の支援・防災活動—大震災からの学び
49巻2号(2015年2月発行)
特集 障害者権利条約の実現と理学療法
49巻1号(2015年1月発行)
特集 姿勢と歩行—理学療法士の診るべきこと
48巻12号(2014年12月発行)
特集 認知行動療法
48巻11号(2014年11月発行)
特集 脊椎・脊髄疾患と理学療法
48巻10号(2014年10月発行)
特集 安全管理
48巻9号(2014年9月発行)
特集 脳卒中片麻痺患者の体性感覚障害と理学療法
48巻8号(2014年8月発行)
特集 慢性腎臓病と理学療法
48巻7号(2014年7月発行)
特集 股関節の運動機能と評価方法
48巻6号(2014年6月発行)
特集 臨床実習教育の実態と展望
48巻5号(2014年5月発行)
特集 老年症候群と理学療法
48巻4号(2014年4月発行)
特集 理学療法実践に役立つコミュニケーション技術
48巻3号(2014年3月発行)
特集 地域における理学療法のパラダイムシフト
48巻2号(2014年2月発行)
特集 発達障害児の理学療法と生活指導
48巻1号(2014年1月発行)
特集 バランスupdate―実用的な動作・活動の獲得のために
47巻12号(2013年12月発行)
特集 神経筋疾患の治療と理学療法
47巻11号(2013年11月発行)
特集 呼吸理学療法の進歩
47巻10号(2013年10月発行)
特集 ウィメンズ・ヘルスと理学療法士のかかわり
47巻9号(2013年9月発行)
特集 在宅理学療法の可能性を探る
47巻8号(2013年8月発行)
特集 物理療法の再興
47巻7号(2013年7月発行)
特集 頸肩腕障害と理学療法
47巻6号(2013年6月発行)
特集 脳卒中理学療法のシームレス化にむけて
47巻5号(2013年5月発行)
特集 医療系教育における臨床実習の現状と展望
47巻4号(2013年4月発行)
特集 予防と理学療法
47巻3号(2013年3月発行)
特集 関節リウマチの最新治療と理学療法
47巻2号(2013年2月発行)
特集 心理・精神領域の理学療法
47巻1号(2013年1月発行)
特集 脳のシステム障害と理学療法
46巻12号(2012年12月発行)
特集 高齢下肢切断の理学療法
46巻11号(2012年11月発行)
特集 はたらく理学療法士の動機づけ
46巻10号(2012年10月発行)
特集 地域包括ケアシステムと訪問理学療法
46巻9号(2012年9月発行)
特集 心疾患に対する理学療法の新たな展開
46巻8号(2012年8月発行)
特集 外来理学療法
46巻7号(2012年7月発行)
特集 スポーツと理学療法
46巻6号(2012年6月発行)
特集 脳卒中理学療法のクリニカルリーズニング
46巻5号(2012年5月発行)
特集 理学療法士のキャリアデザイン
46巻4号(2012年4月発行)
特集 理学療法技能の評価と学習支援
46巻3号(2012年3月発行)
特集 東日本大震災と理学療法
46巻2号(2012年2月発行)
特集 慢性疼痛への包括的アプローチ
46巻1号(2012年1月発行)
特集 運動学習と理学療法
45巻12号(2011年12月発行)
特集 下肢機能再建と理学療法
45巻11号(2011年11月発行)
特集 チーム医療における理学療法士の役割
45巻10号(2011年10月発行)
特集 認知症と理学療法
45巻9号(2011年9月発行)
特集 足部・足関節の機能と理学療法
45巻8号(2011年8月発行)
特集 糖尿病の理学療法
45巻7号(2011年7月発行)
特集 神経生理学的アプローチの転換
45巻6号(2011年6月発行)
特集 小児理学療法の新たなる展開
45巻5号(2011年5月発行)
特集 がん患者のリハビリテーションと理学療法
45巻4号(2011年4月発行)
特集 ロコモティブシンドローム
45巻3号(2011年3月発行)
特集 脳卒中片麻痺患者の装具と運動療法
45巻2号(2011年2月発行)
特集 通所サービスにおける理学療法
45巻1号(2011年1月発行)
特集 自立支援
44巻12号(2010年12月発行)
特集 股関節疾患の理学療法―update
44巻11号(2010年11月発行)
特集 症例検討―脳血管障害患者を多側面から診る
44巻10号(2010年10月発行)
特集 身体障害者スポーツと理学療法の関わり
44巻9号(2010年9月発行)
特集 画像を活かした脳損傷のケーススタディ
44巻8号(2010年8月発行)
特集 徒手理学療法
44巻7号(2010年7月発行)
特集 在宅理学療法の実践
44巻6号(2010年6月発行)
特集 呼吸機能障害とチーム医療
44巻5号(2010年5月発行)
特集 新人教育
44巻4号(2010年4月発行)
特集 筋力増強―update
44巻3号(2010年3月発行)
特集 病期別理学療法モデル
44巻2号(2010年2月発行)
特集 脳卒中のゴール設定
44巻1号(2010年1月発行)
特集 これからの理学療法
43巻12号(2009年12月発行)
特集 連携教育
43巻11号(2009年11月発行)
特集 地域の高齢者に対する理学療法士の視点
43巻10号(2009年10月発行)
特集 老化による身体機能低下と理学療法
43巻9号(2009年9月発行)
特集 膝関節疾患の理学療法
43巻8号(2009年8月発行)
特集 ICFと理学療法
43巻7号(2009年7月発行)
特集 筋再生と理学療法
43巻6号(2009年6月発行)
特集 パーキンソン病の理学療法最前線
43巻5号(2009年5月発行)
特集 小児の地域理学療法
43巻4号(2009年4月発行)
特集 理学療法士による起業
43巻3号(2009年3月発行)
特集 不全型脊髄損傷の病態と理学療法
43巻2号(2009年2月発行)
特集 クリニカルリーズニング
43巻1号(2009年1月発行)
特集 大量養成時代に求められる教育
42巻12号(2008年12月発行)
特集 ニューロリハビリテーションと理学療法
42巻11号(2008年11月発行)
特集 がん治療における理学療法の可能性と課題
42巻10号(2008年10月発行)
特集 骨関節疾患の理学療法とバイオメカニクス
42巻9号(2008年9月発行)
特集 褥瘡の予防と治療―理学療法の役割
42巻8号(2008年8月発行)
特集 介護保険下の理学療法
42巻7号(2008年7月発行)
特集 ヘルスプロモーションと理学療法
42巻6号(2008年6月発行)
特集 Stroke Unitと理学療法
42巻5号(2008年5月発行)
特集 アジアの理学療法
42巻4号(2008年4月発行)
特集 認知運動療法の臨床アプローチと効果
42巻3号(2008年3月発行)
特集 WCPT
42巻2号(2008年2月発行)
特集 痛みの病態生理と理学療法
42巻1号(2008年1月発行)
特集 地域リハビリテーションにおける理学療法
41巻12号(2007年12月発行)
特集 大腿骨―整形外科的治療と理学療法
41巻11号(2007年11月発行)
特集 メタボリックシンドロームと理学療法
41巻10号(2007年10月発行)
特集 外来・通所理学療法
41巻9号(2007年9月発行)
特集 理学療法士の卒後教育
41巻8号(2007年8月発行)
特集 病棟理学療法の視点と実践
41巻7号(2007年7月発行)
特集 脳性麻痺児の理学療法
41巻6号(2007年6月発行)
特集 NST(nutrition support team)と理学療法
41巻5号(2007年5月発行)
特集 実践理学療法のエビデンス
41巻4号(2007年4月発行)
特集 慢性期脳卒中者の理学療法
41巻3号(2007年3月発行)
特集 臨床実習の具体的展開
41巻2号(2007年2月発行)
特集 「腰痛症」の要因と理学療法
41巻1号(2007年1月発行)
特集 高齢者の運動療法の効果と限界
40巻12号(2006年12月発行)
特集 末梢循環障害と理学療法
40巻13号(2006年12月発行)
特集 理学療法の展望2006
40巻11号(2006年11月発行)
特集 緩和ケアとしての理学療法
40巻10号(2006年10月発行)
特集 理学療法における運動療法と装具療法の融合
40巻9号(2006年9月発行)
特集 理学療法と連携
40巻8号(2006年8月発行)
特集 歩行練習
40巻7号(2006年7月発行)
特集 認知症へのアプローチ
40巻6号(2006年6月発行)
特集 アスリートのための理学療法
40巻5号(2006年5月発行)
特集 創傷治癒と理学療法
40巻4号(2006年4月発行)
特集 脳卒中治療ガイドラインと理学療法
40巻3号(2006年3月発行)
特集 腰部・下肢関節疾患の理学療法―姿勢・動作の臨床的視点
40巻2号(2006年2月発行)
特集 物理療法の有効性とリスク管理
40巻1号(2006年1月発行)
特集 臨床実習教育
39巻12号(2005年12月発行)
特集 ボディイメージ
39巻11号(2005年11月発行)
特集 精神障害者の理学療法
39巻10号(2005年10月発行)
特集 急性期に必要な薬物療法と理学療法
39巻9号(2005年9月発行)
特集 心臓外科治療の進歩と理学療法
39巻8号(2005年8月発行)
特集 脳卒中の理学療法を再考する
39巻7号(2005年7月発行)
特集 介護予防動向―理学療法士はどうかかわるのか
39巻6号(2005年6月発行)
特集 介護老人保健施設における理学療法の課題
39巻5号(2005年5月発行)
特集 回復期リハビリテーション病棟における理学療法
39巻4号(2005年4月発行)
特集 脳性麻痺
39巻3号(2005年3月発行)
特集 脳科学からみた理学療法の可能性と限界
39巻2号(2005年2月発行)
特集 実践能力を高めるカリキュラム
39巻1号(2005年1月発行)
特集 高齢者骨折の外科的治療と理学療法
38巻12号(2004年12月発行)
特集 理学療法士の国際協力
38巻11号(2004年11月発行)
特集 認知運動療法の適応と限界
38巻10号(2004年10月発行)
特集 診療報酬
38巻9号(2004年9月発行)
特集 運動療法の基礎
38巻8号(2004年8月発行)
特集 移動動作(分析・介入・介助者への指導)
38巻7号(2004年7月発行)
特集 生活機能向上のための理学療法
38巻6号(2004年6月発行)
特集 ヘルスプロモーション
38巻5号(2004年5月発行)
特集 理学療法モデル
38巻4号(2004年4月発行)
特集 脳血管障害による摂食・嚥下障害の理学療法
38巻3号(2004年3月発行)
特集 物理療法の鎮痛作用
38巻2号(2004年2月発行)
特集 難病の理学療法
38巻1号(2004年1月発行)
特集 整形外科疾患に対する徒手的運動療法
37巻12号(2003年12月発行)
特集 「注意」の障害に対する理学療法
37巻11号(2003年11月発行)
特集 介護保険対応の理学療法
37巻10号(2003年10月発行)
特集 身体と環境
37巻9号(2003年9月発行)
特集 早期理学療法
37巻8号(2003年8月発行)
特集 脳卒中の理学療法の展開
37巻7号(2003年7月発行)
特集 物理療法の効果
37巻6号(2003年6月発行)
特集 “活動”水準を高める理学療法士の専門性
37巻5号(2003年5月発行)
特集 こどもの理学療法
37巻4号(2003年4月発行)
特集 理学療法教育施設の自己点検・評価
37巻3号(2003年3月発行)
特集 医療保険・介護保険と理学療法
37巻2号(2003年2月発行)
特集 整形外科疾患のクリティカルパス
37巻1号(2003年1月発行)
特集 脳卒中片麻痺患者の歩行
36巻12号(2002年12月発行)
特集 運動障害がある場合の内部障害への対応
36巻11号(2002年11月発行)
特集 超高齢者の骨・関節疾患の理学療法
36巻10号(2002年10月発行)
特集 医療事故管理
36巻9号(2002年9月発行)
特集 新しい下肢装具
36巻8号(2002年8月発行)
特集 ファシリテーションは今
36巻7号(2002年7月発行)
特集 理学療法専門職の管理・運営とリーダーシップ
36巻6号(2002年6月発行)
特集 低出生体重児の理学療法
36巻5号(2002年5月発行)
特集 高齢者の転倒
36巻4号(2002年4月発行)
特集 バランス障害と理学療法
36巻3号(2002年3月発行)
特集 介護保険制度下のリハビリテーション
36巻2号(2002年2月発行)
特集 理学療法に関わる整形外科の最新知見
36巻1号(2002年1月発行)
特集 臨床現場にいかす障害構造・障害分類
35巻13号(2001年12月発行)
総目次・著者索引 第21巻~第35巻 1987年(昭和62)年~2001(平成13)年
35巻12号(2001年12月発行)
特集 理学療法の効果判定
35巻11号(2001年11月発行)
特集 症例報告
35巻10号(2001年10月発行)
特集 リスクマネジメント
35巻9号(2001年9月発行)
特集 自営理学療法士の活動
35巻8号(2001年8月発行)
特集 病棟理学療法
35巻7号(2001年7月発行)
特集 脊髄損傷―新しい下肢装具の活用
35巻6号(2001年6月発行)
特集 筋力再検討
35巻5号(2001年5月発行)
特集 EBP in Physical Therapy
35巻4号(2001年4月発行)
特集 理学療法におけるパラダイム転換
35巻3号(2001年3月発行)
特集 回復期リハビリテーション病棟
35巻2号(2001年2月発行)
特集 公的介護保険
35巻1号(2001年1月発行)
特集 整形外科疾患に対する外来運動療法
34巻12号(2000年12月発行)
特集 21世紀の理学療法教育
34巻11号(2000年11月発行)
特集 脳卒中のバランス障害
34巻10号(2000年10月発行)
特集 悪性腫瘍治療の進歩と理学療法
34巻9号(2000年9月発行)
特集 早期理学療法―そのリスクと効果
34巻8号(2000年8月発行)
特集 訪問リハビリテーションの実際
34巻7号(2000年7月発行)
特集 福祉機器の適用基準
34巻6号(2000年6月発行)
特集 精神疾患をもつ患者の理学療法
34巻5号(2000年5月発行)
特集 認知と理学療法
34巻4号(2000年4月発行)
特集 義足―新しい技術と適応
34巻3号(2000年3月発行)
特集 臨床実習の課題と展望
34巻2号(2000年2月発行)
特集 ICUにおける理学療法
34巻1号(2000年1月発行)
特集 理学療法士のアイデンティティー
33巻12号(1999年12月発行)
特集 予後予測
33巻11号(1999年11月発行)
特集 関連領域―代謝疾患と理学療法
33巻10号(1999年10月発行)
特集 小児理学療法の動向
33巻9号(1999年9月発行)
特集 脳科学の進歩と理学療法
33巻8号(1999年8月発行)
特集 中高年者のスポーツ障害
33巻7号(1999年7月発行)
特集 進行性疾患―QOL向上への取り組み
33巻6号(1999年6月発行)
特集 最新・理学療法関連機器
33巻5号(1999年5月発行)
特集 学際的分野での理学療法士の研究活動
33巻4号(1999年4月発行)
特集 嚥下障害/熱傷
33巻3号(1999年3月発行)
特集 上肢帯機能障害と理学療法
33巻2号(1999年2月発行)
特集 最新・バイオフィードバック療法
33巻1号(1999年1月発行)
特集 脳卒中患者の体力
32巻12号(1998年12月発行)
特集 物理療法 今と昔
32巻11号(1998年11月発行)
特集 インフォームド・コンセント
32巻10号(1998年10月発行)
特集 産業理学療法
32巻9号(1998年9月発行)
特集 救急医療と理学療法
32巻8号(1998年8月発行)
特集 認知障害
32巻7号(1998年7月発行)
特集 臨床実習の課題と工夫
32巻6号(1998年6月発行)
特集 身体障害者スポーツ
32巻5号(1998年5月発行)
特集 ケアマネジメント
32巻4号(1998年4月発行)
特集 動作分析
32巻3号(1998年3月発行)
特集 転倒と骨折
32巻2号(1998年2月発行)
特集 合併障害をもつ片麻痺者の理学療法
32巻1号(1998年1月発行)
特集 Welcome to the 13th WCPT Congress
31巻12号(1997年12月発行)
特集 プラトー?
31巻11号(1997年11月発行)
特集 難病と理学療法
31巻10号(1997年10月発行)
特集 ひとり職場の運営
31巻9号(1997年9月発行)
特集 家屋改造とフォローアップ
31巻8号(1997年8月発行)
特集 急性期の理学療法
31巻7号(1997年7月発行)
特集 関連領域―腎障害と運動療法
31巻6号(1997年6月発行)
特集 小児の理学療法
31巻5号(1997年5月発行)
特集 杖・歩行補助具
31巻4号(1997年4月発行)
特集 脳卒中理学療法の効果
31巻3号(1997年3月発行)
特集 チームワーク
31巻2号(1997年2月発行)
特集 4年制大学における理学療法教育
31巻1号(1997年1月発行)
特集 整形外科系運動療法の新展開
30巻13号(1996年12月発行)
総索引・総目次 理学療法と作業療法 第21巻~第22巻(1987年~1988年)/理学療法ジャーナル 第23巻~第30巻(1989年~1996年)
30巻12号(1996年12月発行)
特集 理学療法の展望
30巻11号(1996年11月発行)
特集 特別養護老人ホームにおける理学療法
30巻10号(1996年10月発行)
特集 退院前指導とそのフォローアップ
30巻9号(1996年9月発行)
特集 高次脳機能障害をもつ患者の理学療法
30巻8号(1996年8月発行)
特集 理学療法における基礎研究
30巻7号(1996年7月発行)
特集 地域リハと病院リハの連携―理学療法士の役割
30巻6号(1996年6月発行)
特集 高齢者と運動
30巻5号(1996年5月発行)
特集 姿勢調節
30巻4号(1996年4月発行)
特集 脳卒中における実用歩行訓練
30巻3号(1996年3月発行)
特集 スポーツ外傷
30巻2号(1996年2月発行)
特集 高齢脊髄損傷
30巻1号(1996年1月発行)
Kinetics
29巻12号(1995年12月発行)
特集 廃用症候群と理学療法
29巻11号(1995年11月発行)
特集 病棟訓練
29巻10号(1995年10月発行)
特集 運動コントロールと運動学習
29巻9号(1995年9月発行)
特集 カンファレンスの在り方
29巻8号(1995年8月発行)
特集 骨・関節疾患のバイオメカニクスと理学療法
29巻7号(1995年7月発行)
特集 関連領域―頭頸部の障害とリハビリテーション
29巻6号(1995年6月発行)
特集 運動発達障害;新生児からのアプローチ
29巻5号(1995年5月発行)
特集 外来理学療法の再検討
29巻4号(1995年4月発行)
特集 脳卒中片麻痺に対する理学療法;15年の変遷
29巻3号(1995年3月発行)
特集 疼痛
29巻2号(1995年2月発行)
特集 Duchenne型筋ジストロフィー
29巻1号(1995年1月発行)
特集 世界は今
28巻12号(1994年12月発行)
特集 脳外傷
28巻11号(1994年11月発行)
特集 Ⅱ.ハンドセラピー
28巻10号(1994年10月発行)
特集 脊髄損傷者の社会参加とQOLの向上
28巻9号(1994年9月発行)
特集 生活関連動作
28巻8号(1994年8月発行)
特集 高齢の整形外科的疾患患者に対する理学療法
28巻7号(1994年7月発行)
特集 臨床実習教育
28巻6号(1994年6月発行)
特集 障害予防
28巻5号(1994年5月発行)
特集 治療を目的とした装具と運動療法
28巻4号(1994年4月発行)
特集 嚥下障害
28巻3号(1994年3月発行)
特集 理学療法業務の見直し
28巻2号(1994年2月発行)
特集 脳卒中リハビリテーションプログラムの各段階に応じた理学療法
28巻1号(1994年1月発行)
特集 理学療法研究の取り組み
27巻12号(1993年12月発行)
特集 脳性麻痺児の生活指導
27巻11号(1993年11月発行)
特集 健康増進と理学療法
27巻10号(1993年10月発行)
特集 呼吸機能障害の理学療法
27巻9号(1993年9月発行)
特集 高次脳機能の最近の話題
27巻8号(1993年8月発行)
特集 整形外科疾患と理学療法
27巻7号(1993年7月発行)
特集 精神障害と理学療法
27巻6号(1993年6月発行)
特集 小児の理学療法
27巻5号(1993年5月発行)
特集 教育
27巻4号(1993年4月発行)
特集 脊髄損傷
27巻3号(1993年3月発行)
特集 障害者と生活指導
27巻2号(1993年2月発行)
特集 脳卒中における廃用・過用・誤用と理学療法
27巻1号(1993年1月発行)
特集 患者の人権
26巻12号(1992年12月発行)
特集 終末期ケアと理学療法
26巻11号(1992年11月発行)
特集 ADLとQOL
26巻10号(1992年10月発行)
特集 中高年脳性麻痺者の問題点
26巻9号(1992年9月発行)
特集 福祉機器
26巻8号(1992年8月発行)
特集 老人保健施設の理学療法
26巻7号(1992年7月発行)
特集 ゴール設定
26巻6号(1992年6月発行)
特集 整形外科
26巻5号(1992年5月発行)
特集Ⅱ 骨粗鬆症をめぐって
26巻4号(1992年4月発行)
特集 高齢者のスポーツおよびレクリエーション
26巻3号(1992年3月発行)
特集 隣接領域における理学療法教育
26巻2号(1992年2月発行)
特集 内部疾患と理学療法
26巻1号(1992年1月発行)
特集 脳卒中
25巻12号(1991年12月発行)
特集 地域・在宅の理学療法
25巻11号(1991年11月発行)
特集Ⅱ ホームプログラム
25巻10号(1991年10月発行)
特集 理学療法処方をめぐって
25巻9号(1991年9月発行)
特集 痴呆と理学療法
25巻8号(1991年8月発行)
特集 重度障害児の理学療法
25巻7号(1991年7月発行)
特集 Ⅱ.糖尿病と理学療法
25巻6号(1991年6月発行)
特集 日常生活動作(ADL)
25巻5号(1991年5月発行)
特集 整形外科疾患の理学療法
25巻4号(1991年4月発行)
特集 卒後教育
25巻3号(1991年3月発行)
特集 運動療法
25巻2号(1991年2月発行)
特集 体幹機能
25巻1号(1991年1月発行)
特集 脳卒中;回復期以降の理学療法を中心に
24巻12号(1990年12月発行)
特集 いす
24巻11号(1990年11月発行)
特集 整形外科;スポーツ傷害を中心に
24巻10号(1990年10月発行)
特集 地域リハビリテーションにおけるグループ訓練
24巻9号(1990年9月発行)
特集 診療報酬
24巻8号(1990年8月発行)
特集 ハイリスク・体力消耗状態
24巻7号(1990年7月発行)
特集 起居動作
24巻6号(1990年6月発行)
特集 脳性麻痺児の発達過程と理学療法
24巻5号(1990年5月発行)
特集 急性期の理学療法
24巻4号(1990年4月発行)
特集 老人保健施設の理学療法
24巻3号(1990年3月発行)
特集 苦労した症例報告集
24巻2号(1990年2月発行)
特集 履物
24巻1号(1990年1月発行)
特集 脳血管障害
23巻12号(1989年12月発行)
特集 整形外科
23巻11号(1989年11月発行)
特集 筋力増強
23巻10号(1989年10月発行)
特集 下肢切断の理学療法
23巻9号(1989年9月発行)
特集 筋萎縮性疾患
23巻8号(1989年8月発行)
特集 医療事故
23巻7号(1989年7月発行)
特集 脳性麻痺の理学療法と手術および装具療法
23巻6号(1989年6月発行)
特集 通所・訪問リハビリテーションの技術
23巻5号(1989年5月発行)
特集 先天性疾患
23巻4号(1989年4月発行)
特集 拘縮
23巻3号(1989年3月発行)
特集 卒後教育(含新人教育)
23巻2号(1989年2月発行)
特集 不全四肢麻痺;高齢者を中心に
23巻1号(1989年1月発行)
特集 理学療法の展望
