特集の意図
細胞構築をもとに脳を区分けし,番号を振った。なんとシンプルなコンセプトだろう。しかし,それから100年余り,脳研究の端々にそのコンセプトの影響は色濃く残る。単純なものは生き続ける。「各領野における研究の最前線をわかりやすくまとめる」—この増大特集のコンセプトも極めてシンプルなものとした。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩69巻4号
2017年04月発行
雑誌目次
増大特集 ブロードマン領野の現在地
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.298 - P.299
ブロードマンの脳地図をめぐって
著者: 河村満
ページ範囲:P.301 - P.312
ブロードマンの脳地図は非常に有名であるが,それが掲載された1909年出版のモノグラフ自体は意外に読まれていない。また,1909年のモノグラフに掲載された脳地図のほかにも1910年,1914年に出版された脳地図があり,この2つの脳地図には詳細には1909年のものとは異なった点がある。また,動物では1〜52野までがきちんと示されているが,ヒトでは欠番(12〜16野,48〜51野)がある。これらについて詳細を述べた。さらに,ブロードマンの人と業績についてレヴューした。
タッチの階層仮説
著者: 岩村𠮷晃
ページ範囲:P.313 - P.325
ブロードマンの細胞構築学的区分,3,1,2野に関連して,これと同時代の研究者の細胞構築学区分とを照合した。3つの領野の形態学的特徴について,Mountcastleによるサルでの顕微鏡観察の記述を紹介した。われわれが行ったサルの3,1,2野の体性感覚刺激に応答する単一ニューロン活動記録実験の結果を,情報処理の階層仮説に基づいて説明した。近年における主としてヒトでの脳画像による研究の成果について述べた。
動作制御機能の中枢
著者: 中山義久 , 星英司
ページ範囲:P.327 - P.337
一次運動野はブロードマン4野,前頭葉の最後部に位置しており,運動指令を脳幹や脊髄に出力している。ブロードマン4野の前方には6野があり,複数の高次運動野が同定されている。外側面には運動前野が位置し,感覚情報に基づいた動作の企画や実行に関与する。内側面には補足運動野があり,内的情報に基づく動作の企画や実行に関与する。4野と6野は,動作のアイデアを具体的な運動に変換する中枢であると考えられる。
脳と外界のインタラクション
著者: 泰羅雅登
ページ範囲:P.339 - P.345
ブロードマン領野5野,7野は頭頂葉にある体性感覚と視覚の連合野である。ブロードマンの脳地図ではヒトとサルで7野の位置が異なっている。ヒトでは7野が頭頂間溝の上方の上頭頂小葉にあるが,サルでは下方の下頭頂小葉にある。他の脳地図では上頭頂小葉,下頭頂小葉はヒトとサルで同じように領域区分がなされている。したがって,ブロードマンの分類による5野,7野の機能の議論は難しい。
注意,学習,社会性機能
著者: 渡邊正孝
ページ範囲:P.347 - P.354
ブロードマンは細胞構築に基づきサルとヒトの前頭連合野内に8,9野を割り当てたが,のちの詳しい分析からPetridesらは9/46野を加えた修正版の前頭連合野脳地図を提案した。8野外側部は条件性弁別学習に,8野内の最後部にある前頭眼野は,視覚的注意や眼球運動の制御に関係している。9野外側部,9/46野は実行機能を支えるのに重要な働きをしている。8,9野内側部は心の理論や社会性に関係している。
前向きな行動を支える10野,意味処理のハブの役割を担う38野
著者: 梅田聡
ページ範囲:P.355 - P.365
ブロードマン10野および38野の持つ構造的特徴と機能的役割について概観する。両領域ともに,これまでに取り上げられた研究は数多く,神経心理学研究,脳機能画像研究,精神疾患研究,神経疾患研究,脳神経外科研究など多岐に及ぶ。これら2つの領域は極めて高次な機能的役割を担っているのが現状であり,その解明は極めて難解である。本稿では,それぞれの領域について,いくつかの認知的側面からこれまでの研究を概観し,複雑な機能の解明に有効な研究の方向性を示唆することを目的とする。
情動,記憶,共感
著者: 上田敬太 , 藤本岳 , 生方志浦 , 村井俊哉
ページ範囲:P.367 - P.374
ブロードマン領野11野は眼窩前頭皮質を,46野は背外側前頭前皮質を構成する主な脳領域であり,それぞれ情動や価値の処理過程,作動記憶を含めた認知的処理過程に大きく関与している。47野についてはその役割は複雑である。他者の発話内容に対する共感といった情動的側面を持つ一方で,46野と比較し自動的な,意思の介在しない運動の処理に関与し,さらに左の47野は言語の統語的処理に強く関連している。
味覚,社会性,そして時間認知と12野
著者: 河村満
ページ範囲:P.375 - P.381
ブロードマン領野12野は,11野とともに,前頭眼窩野に属する。前頭側頭葉変性症の味覚障害は,12/47野(両側)と関連するというVBM(voxel-based morphometry)データがある。またわれわれの検討では,パーキンソン病の意思決定機能障害とVBMでの萎縮部位(両側)が相関し,社会的認知機能とも関連することが明らかであった。さらに,時間順序の認識など時間認知機能との関連が指摘でき,この後さらに研究が進む可能性がある。
内受容感覚に基づく行動の制御
著者: 大平英樹
ページ範囲:P.383 - P.395
シルヴィウス裂の内奥に位置する島皮質(ブロードマン領野13,14,15,16野)は,知覚,言語,認知,感情,運動など,多様な精神機能に関連することが知られている。中でも,島皮質は身体の生理的状態を表象する内受容感覚がつくられる場所であり,それにより身体の状態を適切に制御し,ひいては多くの精神機能をも制御する機能が実現されている。近年,そうした島皮質の機能を説明する共通原理として,前部島における内的モデルによる予測の形成と,予測と感覚信号を比較し予測誤差を計算し,その予測誤差を最小化することで心身の統合的な適応を図ろうとするメカニズムが提唱されている。本論では,そうした島皮質の機能原理について記述するとともに,それが行動を選択する意思決定にも影響を与えている可能性について論考する。
ヒトの視覚野の区分と症候
著者: 河内十郎
ページ範囲:P.397 - P.410
ヒトの17,18,19野は,後頭葉に位置する視覚皮質で,それぞれ固有の視野局在区分を持つ。特に19野は,対側視野の半分あるいは全体を表現する多数の領野と,機能的に異なるいくつかの領野に区分されており,さらに細胞構築学的に異なる9個の領野が区別されている。多数が明らかにされている後頭葉の線維結合の起始部・終止部の詳細は明らかではない。後頭葉の損傷によりさまざまなタイプの視野欠損,幻視,視覚性失認などが起こる。
ウェルニッケ野周辺の機能
著者: 加我君孝 , 南修司郎
ページ範囲:P.411 - P.416
ブロードマンの22,21,20野は側頭葉にあり,上・中・下側頭回とほぼ同一であると考えられる。髄鞘化や細胞構築により領野として命称されたもので,側頭連合野として分類される。機能は聴覚と音声・言語,視覚と関連していると報告されているがこの部位の臨床報告は少ない。
悲しみと痛みと認知の中枢
著者: 仁井田りち , 三村將
ページ範囲:P.417 - P.426
後部帯状回(23野)はデフォルトモードネットワーク(DMN)のハブであり,アルツハイマー病において早期に解剖学的結合が低下する部位である。前部帯状回(24野)はDMN,ワーキングメモリ,顕著性ネットワークなどのネットワークとつながりがあり,それらのネットワークの相互の調整の役割を果たす。前部帯状回の吻側に位置する膝下部前帯状回はうつ病との関連が強く示唆されている部位である。
辺縁葉皮質と空間認知・エピソード記憶形成
著者: 小林靖
ページ範囲:P.427 - P.437
ブロードマンは辺縁葉の範囲のうち,海馬の周辺に27,28,34,35,36野を,脳梁の周辺に23,24,25,26,29,30,31,32,33野を区別した。24,25,32,33野は帯状回前部,23,26,29,30,31野は帯状回後部を占める。25,32野と24野前下部は情動反応に深く関わる。29,30野は23,31野,前頭前野背外側部,27,28,35,36野と密に連絡し,空間認知,ワーキングメモリ処理,エピソード記憶形成の間を仲立ちする。
記憶と認知の接する場所
著者: 永福智志
ページ範囲:P.439 - P.451
海馬傍回と紡錘状回に存在するブロードマン領野27,28,36,37野について,概念を再確認したのち,機能に関する最新情報を,主に最近のヒトでの機能的脳イメージングの知見に基づき,まとめた。これらの研究は動物実験での知見を基礎としているものが多いため,ヒトと動物間の脳部位の対応関係についても考察を加えた。特に,37野の機能については,36野の機能と併せて,顔認知における機能的役割に焦点を絞った。
海馬研究の最前線
著者: 岡田桜 , 青木勇樹 , 佐々木拓哉 , 池谷裕二
ページ範囲:P.453 - P.460
内側側頭葉に位置する海馬体の機能は,スライス標本や成体動物を用いた研究が盛んに行われてきた。最近では,多チャンネル計測用電極の開発や機械工作技術の向上により,海馬の神経細胞群が機能的にも構造的にもさらに多様な性質を有することが示されている。本論では特に,海馬回路によるパターン情報処理,目的指向型行動の表象,正負の価値の表象,について近年の研究動向を述べる。
ヒトの頭頂連合野と高次機能
著者: 櫻井靖久
ページ範囲:P.461 - P.469
角回(ブロードマン39野)と縁上回(40野)の神経解剖と機能について述べた。角回,縁上回とも頭頂葉の下部を構成する。角回からの連合線維は上縦束Ⅱ/弓状束を経て背外側前頭前野に,縁上回からの線維は上縦束Ⅲ/弓状束を経て腹外側前頭前野に達する。角回の損傷で漢字の失書(語彙性失書)と軽度の失名辞が出現する。縁上回の損傷で仮名の失書(音韻性失書)と仮名の失読(音韻性失読)を生ずる。ゲルストマン症候群(手指失認,左右識別障害,失書,失算)と言語性短期記憶障害は,角回,縁上回のいずれが損傷されても出現する。いわゆる“角回性失読失書”の失読は,角回後方の中後頭回の損傷で出現する。角回・縁上回病変による失読の特徴は,単語読みにおける仮名文字の転置のエラーで,継時的な音韻処理の破綻を示している。
聴覚機能マップ
著者: 藤本蒼 , 小村豊
ページ範囲:P.471 - P.478
ブロードマン領野41,42野は,上側頭回に位置し,聴覚皮質としてみなされている。聴覚機能の基本は周波数分析だが,ヒト聴覚皮質における周波数地図については,最近,マカクザル聴覚皮質の入出力に関する知見と照合するまで一定しなかった。聴覚皮質は,条件づけ学習,人工内耳手術後などで可塑性を示し,音声知覚や音楽鑑賞や統合失調症における幻聴などは,視床や前頭葉や辺縁系などの他領域との連関によって説明できる。
ブローカ野における文法処理
著者: 山田亜虎 , 酒井邦嘉
ページ範囲:P.479 - P.487
ブロードマン領野44,45野はブローカ野として知られるが,真の機能的役割はいまだに明らかでない。近年のイメージング技術の発展により,ブローカ野の構造と機能が詳細に明らかになってきた。特に言語機能については,運動性のものに限らず,文法処理の中枢として働くという十分な証拠が蓄積されている。本総説では,ブローカ野の文法中枢としての役割を概観し,言語以外の機能への関与についても触れる。
症例報告
低ナトリウム血症を誘因として非痙攣性てんかん重積状態をきたした高齢女性の1例
著者: 倉内麗徳 , 矢坂正弘 , 徳永敬介 , 齊藤正樹 , 下濱俊 , 岡田靖
ページ範囲:P.489 - P.492
症例は67歳女性で,意識障害を主訴に当院に入院した。心因性多飲により血清ナトリウムが115mEq/Lと著明に低下していた。脳波検査では全般性に5Hzの徐波が出現し,ジアゼパムの静注により徐波は著明に改善し,意識障害が回復したことから非痙攣性てんかん重積状態(NCSE)と判断した。レベチラセタム1,000mg/日の内服を追加し,低ナトリウム血症の補正を行った後に中止したが,再発はみられなかった。低ナトリウム血症を誘因としたNCSEの報告は少なく,早期の診断治療で良好な転帰を得たので報告する。
学会印象記
Neuroscience 2016—The 46th Annual Meeting of the Society for Neuroscience(2016年11月12〜16日,サンディエゴ)
著者: 川合隆嗣
ページ範囲:P.493 - P.495
2016年11月12〜16日に米国のサンディエゴで開催された北米神経科学大会(Neuroscience 2016)に参加しました。この大会は,神経科学分野では世界最大規模を誇る学会である北米神経科学学会(Society for Neuroscience)の第46回目の年次大会です。私は今回でかれこれ4度目の参加になるのですが,毎年会場の広さと参加している研究者の数に驚かされます。今年は日本を含む世界80以上の国から30,000人以上が参加したそうです。同じく2016年に横浜で開催された第39回日本神経科学大会の参加者が3,000人強だったそうですから,いかに大きな大会であるか想像していただけるかと思います。
さて,今回の開催地サンディエゴは全米屈指のリゾート地として知られています。場所は米国西海岸,カリフォルニア州の南端にあります。玄関口のサンディエゴ国際空港へは成田空港から直行便で行くことができます。サンディエゴは流石にリゾート地というだけあって,非常に快適に滞在できました。まず気候がとても温暖でした。日本から出発するとき,私が住んでいる茨城県つくば市は寒かったので厚着のまま飛行機に乗り込んだのですが,サンディエゴに着いたら半袖でも問題ありませんでした。11月でしたが,日中は暑いくらいです。驚いたことに,プールや海で泳いでいる方もいました。ただ,暑いとは言っても,日本でしばしば経験するような例のじめ〜っとした感じは一切ないため不快感はありません。夜も長袖で十分で,とにかく過ごしやすいのが印象的でした。
--------------------
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.300 - P.300
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.325 - P.325
お知らせ 第31回 日本ニューロモデュレーション学会 フリーアクセス
ページ範囲:P.416 - P.416
お知らせ 第56・57回 筋病理セミナー フリーアクセス
ページ範囲:P.438 - P.438
お知らせ 第28回 日本末梢神経学会学術集会 フリーアクセス
ページ範囲:P.452 - P.452
書評 ブランドと脳のパズル—脳科学をマーケティングにどう活かすか フリーアクセス
著者: 的場匡亮
ページ範囲:P.488 - P.488
本書が対象としているのは,消費者の脳です。マーケティングとは,人びとが価値を感じるものを生み出し,伝達し,届けていくための活動のことで,近年,神経科学を基盤とした手法(EEG,MEG,fMRIなど)を活用することにより,消費者やその行動を理解しようという試みが活発に行われるようになりました。
これをニューロマーケティングと呼んでいて,本書はこの分野の基本的な考え方から今後の展望まで丁寧かつ冷静に論じています。
今月の表紙 フリーアクセス
著者: 河村満 , 岡本保 , 菊池雷太
ページ範囲:P.496 - P.497
今月の表紙の写真は,サルペトリエール病院のアンテルヌであったソリエ(Paul Sollier;1861-1933)ら1)の論文からのものです。この論文で,ソリエはドイツの精神科医カールバウム(Karl Ludwig Kahlbaum;1828-1899)が1874年に提示した2)カタトニアの疾患概念について,自験例をもって批判しています。
筆者も含め多くの神経内科医にとってカタトニアは,遠くの親戚のような存在ではないでしょうか。その理由として,長い間精神医学の中で取り扱われてきたこと,その一方でカタレプシーなどの神経学的な姿勢異常を示すことが挙げられると思います。
「読者からの手紙」募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.499 - P.499
あとがき/読者アンケート用紙 フリーアクセス
著者: 酒井邦嘉
ページ範囲:P.500 - P.500
天文観測は「月に始まり,月に終わる」といわれる。月は最も身近な天体であると同時に,最も奥深い天体でもあるのだ。楕円軌道や潮汐力など,天文に関するさまざまな現象が月に集約されているといっても過言ではない。さらに月の影響は,生体のバイオリズムから暦(旧暦)といった慣習にまで幅広くみられる。「月はみているときにしか存在しないのか」と問うて,量子力学の解釈を批判したのはアインシュタインであった。
月の満ち欠けの周期(朔望月)は,平均で約29.530589日であるが,実際には約29.3日から29.8日の間を1年ほどかけて変動する。しかも月の楕円軌道の向きが回転するため,朔望月の変動の幅は約9年周期で半分以下にまで変わっていく。新月が月齢ゼロと決められているが,こうした月の複雑な運動のため,満月(月と太陽の黄道上の角度が180°となるとき)は月齢15日とは限らない。自分の腕時計に付いていたムーンフェイズ(月相)がなかなか実際と合わないので調べてみたところ,そうした理由があったのだった。
基本情報
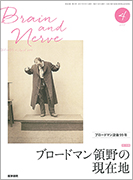
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
